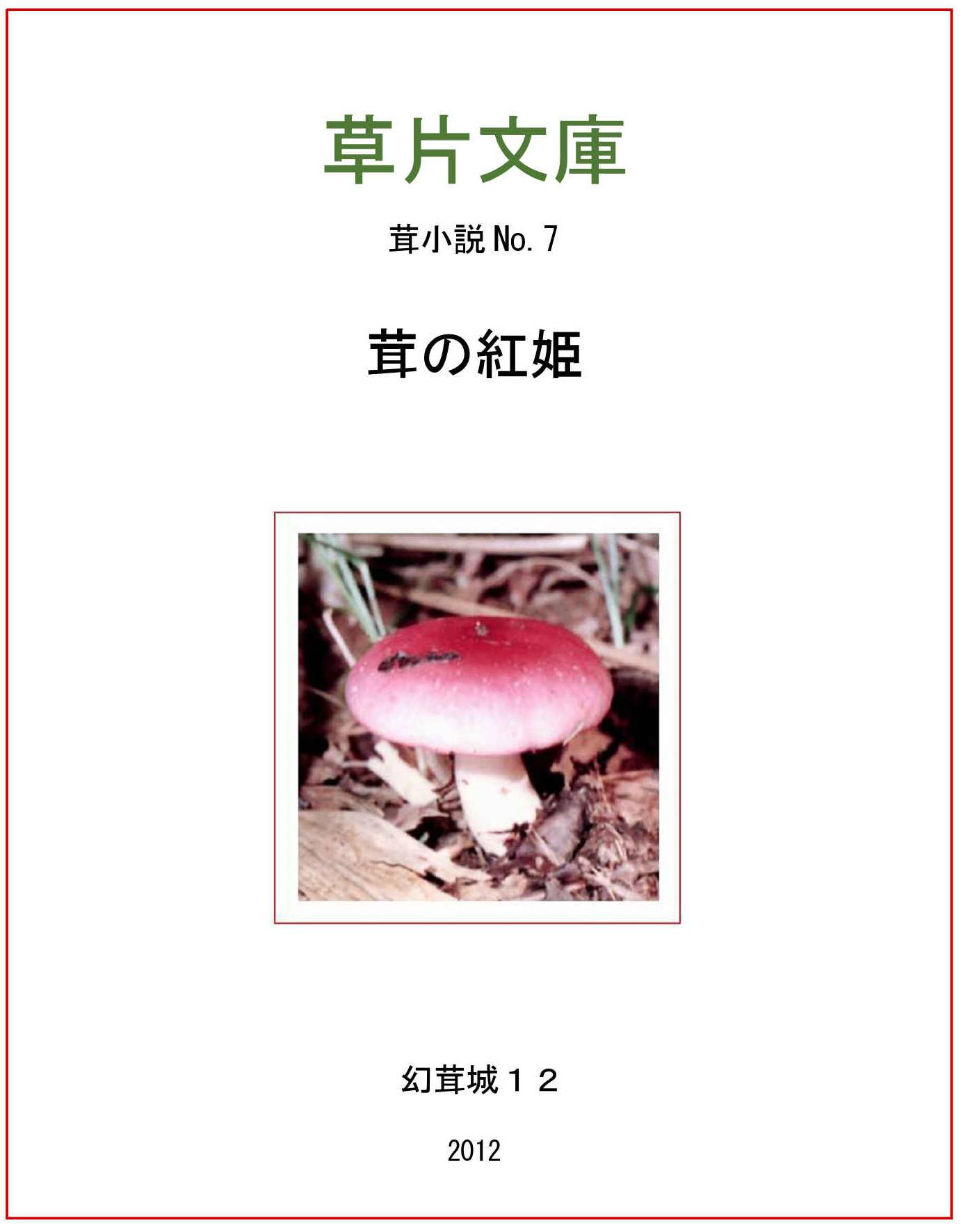
茸の紅姫ー幻茸城12
「姫さま、どちらへいらっしゃいますのか、殿から外へ出さぬよう、言いつかっておりまする」
七左衛門は、六十年に及ぶ生涯の中で、このように難しい仕事を仰せつかったのは初めてであった。
瓜城の殿から七つになった姫子の教育係を言いつかったのは一年前である。
紅姫が七歳になるにあたって、姫に城を与え、男の子と同じ教育を受けさせるということで、七左衛門にその役割の白羽の矢が立ったのである。
七左衛門はその昔、今の瓜城の殿の教育係であった。まだ七左衛門が独り者のとき、先輩のような立場で、若い頃の殿と長い間を過ごした。
おっとりとした七左衛門とは正反対の早急で生意気だった殿が、日本の三本指に入る有名な殿様になったのは彼のお陰と言われている。彼としては、ただ正直に殿と向き合っていたに過ぎなかったのだが。
そんな彼に殿の娘の教育役が回ってきたわけである。
紅姫はそれは頭の良い娘ではあったが、殿の若いときとそっくりで、自分のやりたいことは必ずといってよいほどやり遂げた。それも早急にである。いうなれば我ままである。
その姫がこの城に来て一年経った今、城の外に興味を持ち始めたのである。姫は周りの者をそそのかして城を出ようとしたことが何度もある。勝手に外に出て、何かがあったら七左衛門にとって大変なことである。
紅姫は七左衛門の顔を見て片目をつむった。
「七爺、お外はいろいろなものがあるとききまする、蝦釣りがしたい」
「なんと、蝦釣りですかな、それならば、お城の中でもできますぞ、明日しましょうな」
「今日したいのう」
七左衛門はしどろもどろで答えた
「紅姫さま、今日は蝦が寝ております」
「なぜじゃ」
「満月の日は寝ているのだそうです」
「そうかえ、それじゃ、明日には必ずな」
「はいはい、姫さま」
それからが大変であった、明日までに、蝦を百匹用意して、池に入れよと、下知を出した。
下々の暮らしを知らない侍が、いきなり、蝦百匹に一両という法外な値で買い取ることを村に通達した。
紅姫のいる城の周りも、殿の国から連れてきた村人や、年貢のほとんどないことを聞きつけた農民により人家が増え、かなりの賑わいを見せている。
通達を出して一時もならぬというのに、笊(ざる)に一杯の蝦を持った子どもたちが城の通用門の前に並んだ。
これには困った。七左衛門は赤いのではなければだめだと係りの者に伝え、たまたま、赤っぽい蝦を持ってきた子どものものだけを買い上げた。買ってもらえなかった蝦子供たちは門の前に捨ててしまった。お陰で通用門の周りは蝦だらけである。
村では城の誰かが病気で、薬にするのではないかと噂が飛び交ったことは確かである。蝦の体の中の小さな石は蝦石といわれ万能薬といわれる。
こうして蝦は池に放された。
さて、この後がある。どのように蝦を釣ったらよいのかわからない侍たちは、教えるものに百文出すと触れたところ、これまた子どもたちが並んでしまった。
それはどうっていうことはなく、蛙で釣れるということが分かった。
ただ、とある侍の息子が言ったことには、干し烏賊でいとも容易(たやす)く釣れるとのこと、姫さまにはこの方が良いということで、干し烏賊に白羽の矢が当たった。干し烏賊は海が遠いこの地にとって珍味である。
「姫さま、干し烏賊で、蝦が釣れますぞ」
池の前で、七左衛門は細竹の先の糸に干し烏賊をつるして紅姫に渡した。
「七爺、これで蝦を釣るの」
「はい、姫さま、これでよく釣れるそうでございますよ」
「蝦は烏賊(いか)の干したのが好きなの」
「そうでしょうな、よく食いつくそうですぞ、姫さま」
「池に烏賊はいないのではないの、爺」
「ええ、ええ」
「では、どうして、蝦は烏賊が好きなの」
紅姫のこんな質問はいつものことである。
そこは七左衛門の得意とするところである。
「海にはいろいろな蝦がいましてな、小さいのや大きいのや、姫さまもお食べになるでしょう」
「伊勢海老はきらい、あんなごちごちしたのいや」
「でもおいしゅうございましょう」
「かわいい海老がいい」
「はあ、はあ、それで、海の海老が川の蝦に烏賊は旨いものだと教えたそうでございます」
「海の海老がどこで川の蝦に教えるの」
「小さな川は大きな川となって海に繋がるのですぞ、そこは海の海老と川の蝦がいろいろ話をするところなのですぞ」
「嘘ばっかり、七爺、私ももう八つ、お話を作るのはおやめ」
「ははは、そうですな、ともかく、釣りましょうぞ」
紅姫も大きくなったものである。七左衛門は頭をかいて、自分の蝦釣りの竹竿を池にむかって突きだした。
つるした干し烏賊が睡蓮の間に沈んでいくと、あっという間に強い引きがあった。
「お、きましたぞ、姫さま」
七左衛門は、子どもたちに教わったように、そうっと竹竿を持ち上げた。
烏賊の足に赤い蝦が挟みついていた。
「ほら、捕まりましたぞ、姫さま」
桶の中に蝦を放すと、紅姫が覗き込んだ。
「あまりかわいくない、透き通った蝦がいい」
「透き通った蝦がいるかどうかわかりませんが、姫さま、ともかく一度おためしください」
七左衛門は紅姫に釣りをうながした。
紅姫は烏賊の足を池に放り込んだ。
と、すぐに引きが来たようで、紅姫が重そうに竹竿を持ち上げた。
「お、大物ですな」
七左衛門が機嫌をとった。
上がってきたものを見た紅姫は、
「なんじゃ、こりゃ」
と言ったのである。
鴉賊に食いついていて、手足をばやばやさせている大きな蛙が、みっともない格好で釣られてきた。
七左衛門は紅姫から竹竿をとると、
「蛙のやつ意地汚い」
蛙を捕まえて、足元に放り投げた。
紅姫はぷすっとした顔をして、蛙の頭を引っぱたくと、ぎゅうっと足をつかんで池の中に放り投げた。
「姫さま、もう一度」
新しい烏賊のついた竹を姫に渡した。
紅姫は烏賊を睡蓮の葉の間に沈めた。
すると、またもやすぐに引きがきた。
竹がしなっている。
「お、今度こそ蝦ですぞ」
紅姫が竿をそうっと持ち上げると、睡蓮の間から鴉賊の足に喰いついた蝦蟇(がま)蛙が顔を出した。
「また、このおばか」
姫はそれしか言わず、竿を上げた。そして大きな声で笑い出した。
糸の先の干し烏賊に食いついた蝦蟇蛙がおとなしく持ち上げられたが、だらんと垂れた蛙の両の足に、蝦が二匹挟みついて上がってきたのである。
「ははは、さすが、姫さま」
七左衛門は、蝦を蛙から離すと桶に入れた。
「爺、蛙をちょうだい」
七左衛門が蛙を紅姫の前におくと、姫はいきなり、七左衛門の腰につけていた短い刀を引き抜いて、蛙の頭をはねた。
驚いたのは七左衛門である。
「姫さまなにをなさいます」
あわてて姫から刀を奪いとると鞘に納めた。
「怪我をなされたら、爺は切腹でございます」
「爺、すまなかったな、蛙はこうするのじゃ」
姫は手際よく頭を刎ねた蛙の皮をむき、竿の先の糸にくくりつけると、池に放り込んだ。とたんに、蛙の足に三匹もの蝦がくっついてきた。
「蝦つりには蛙がよいようじゃな」
紅姫は、そう言うと、もう飽きたと、庭からあがってしまった。
次の日のことである。
「爺、鼠釣りがしたい」
「姫さま、鼠は釣れませぬ」
「でもしたい」
そのような難題は何回も経験している。
七左衛門は誰か良い考えがないか周りに聞いた。
一人の供の者が、「鼠を捕まえて水の中に泳がし、それに鈎(かぎ)針(ばり)で釣り上げればよのでは」と、申し出た。
「それは良い考えじゃ、すぐに準備せい」
ということで、鼠がたくさん捕まえられ、樽の中の水の中に泳がされた。
「おお、ちと可哀想じゃが、仕方あるまい」
七左衛門は水の中でおぼれまいと必死に泳いでいる鼠を見てつぶやいたが、紅姫はおかまいなし。
「面白い、早く釣り竿をおよこし」
供の者に言いつけた。
釣り竿を受け取った姫は、太い鈎針のついた先を水に沈め、いっきに引揚げた。
その先には鈎針に腹を刺された黒鼠がもがいていた。
「ほれ、釣れた、そやつを、水の中に沈めよ」
紅姫は釣れた鼠を別の樽の中でおぼれ死にさせ、
「運が悪いと思え」
と、また釣り竿を鼠が泳いでいる中に沈め持ち上げた。
「面白いのう」
紅姫は数十匹の赤鼠や黒鼠を釣り上げておぼれさせ、
「もう飽いた」
そういい残して、部屋に入ってしまった。
「七左衛門さま、残った鼠はいかにいたしましょうか」
供の者が聞くと、七左衛門も、
「そちらにまかせる」
やはりそう言って、自分の部屋に戻ってしまった。
結局、鼠はすべておぼれ死んだのである。
ある日の朝のことである。
「紅姫さまがいらっしゃらなくなりました」
奥の女中の冬があまりあわてた様子もなく、七左衛門の部屋にやってきた。
七左衛門は城内の屋敷の一室で寝起きをしている。
「いつからじゃ」
昨夜は私どもも姫さまがお部屋にお入りになり、お休みになったのを知っております。その後、私どもみな隣室におりました。そこを通らねば、外に出ることはできませぬ」
紅姫には冬、夏、秋、春という四人の女中がついている。四人は七左衛門が選んだ紅姫付きのお女中たちである。
「窓から出たのであろう」
「窓が開きますと、音が鳴るようにしてありまする、音も鳴らず、開けた様子もございませぬ」
女中たちの後について姫の部屋に入った七左衛門は、竹格子のある丸窓を見た。開けると音が鳴るように鈴がついている。音を立てずに開けたにしても竹格子を壊さねば外に出ることはできない。
「なぜ、鈴などをつけたのじゃ」
「姫さまが夜中にごそごそなにやらなさっているような音が聞こえました。襖(ふすま)を開けると、姫さまはお休みになっておられたのです。中には何も怪しきものはおりませんでした、それが続きましたものですから、万一のことがあるといけませぬので、鈴をおつけしたのでございます」
「うむ、それはよかったな、だがなにをなさっておられたのじゃろうな」
七左衛門が首をかしげていると、女中の中で一番若い夏がおずおずと言った。
「申し上げます、姫さまのお部屋の中で、一度、姫さまに赤い粉を飲むようにと言われたことがございます」
「なんと、赤い粉とな、それは何じゃ」
「わかりませぬ。からだによい薬で、気持の良くなるもの、とかおっしゃっておりました。薬の包みを開くと、真っ赤な粉が少しございました。姫さまはそれを私に飲むようにと、水と一緒におよこしになりました」
「それはいつごろじゃ」
「半月ほど前のことでございます」
「鼠釣りのすぐ後のことじゃな、あれから姫は外に出たいと言わなくなったが、なにかたくらんでおったのじゃな、それで、薬を飲んだらどうなったのじゃ」
「はい、それはとても気持ちがよくなりまして、ふわふわ部屋の中を飛んでいるようでございました」
「ほう、それでどうなった」
「からだもぽかぽかと暖かくなり、目の前にきれいな殿御が現れました」
「それでどうした」
それから私は、何もわからなくなり、ただただ気持ちがよくなり、幸せでした。それで、気がつきましたら、姫さまの前で、着物をすべて脱ぎ捨てて寝ておりました」
「姫はどうしておったのじゃ」
「姫さまは目覚めた私に、着物を掛けてくだされて、どんな気持ちだったかお聞きになりましたので、正直に申し上げました」
「それでどうした」
「はい、このことは誰にも言わぬように、言ったらお前が私の目の前でどんなことをしたのか言いますぞ、そうしたらここにはおれなくなりますから、いいねと、おっしゃいました」
「ふむ、何をしたのだ、お前は」
「わかりませぬ、ただ、気持ちがよかっただけでございます。まるで、雲の間に浮かんでいるように」
「その薬はどこから手に入れたのじゃろう、誰か知らぬか」
みな首を横に振った。
しかし、春が思い出したように言った。
「そういえば、いつぞやの夜、寝ずの番で、襖の外におりましたところ、なにやら音がしますので、襖をちょいと開けて見ました。姫さまの部屋の窓が少し開いており、赤い鼠が姫さまの部屋から外に飛び出していきました。その後、姫さまのご様子を見ましたが、何事も無くお休みでした。鼠はよく見かけますので、とくと気にも留めずおりました次第でございます」
「鼠か、ふむ、何かありそうだが、鼠が薬を持ってくるわけはあるまいが」
夏が言った。
「姫さまは自分で飲む前に私でお試しになったのではないでしょうか」
「そうかもしれんな、それで、ご自分でも飲まれたのかもしれぬ、じゃが、姿が見えなくなったのと関係があるかのう」
「わかりませぬ」
「そうじゃ、殿にはまだ言っておらぬのか」
「先ほど、向こうの城に使いを出しましてございます。すぐに、殿さまから返事がきて、どうせ、あの姫のこと、城の中で何かしているのであろう、城は広い,空腹になれば戻ってくる、と申されました、それに、すべて爺にまかした、とも書いてありました」
「そうじゃな、あの姫さまのことだ、お前たちがたぶらかされたのであろう、ともかく、城の中を探すことじゃな」
「はい、すぐ庭は探しましたが、おられないようでございます」
「どれ、わしも庭を探してみるか、冬は部屋で姫を待っていておくれ、いつひょっこり帰ってくるかわからんからな」
七左衛門は三人の女中たちを伴って庭に出た。池の辺には色とりどりの茸がたくさん生えている。
「今年は茸が多いのう」
「はい、お城の庭にはたくさんの茸が生えております」
秋が答えた。
「食える茸はないようじゃな」
「朽ちた木に木耳(きくらげ)がたくさん生えておりました」
「そうか」
「昨晩、酢味噌にいたしまして、城の者たちは大変美味しくいただきました、七左衛門さまにもお持ちしたはずでございます」
「おお、そうじゃった、旨かったな、食べたあと、酒も飲まなかったのに眠くなって、よく寝たわい」
「はい、私どももいただきまして、よく寝ることができました」
そこで七左衛門ははっと気がついた。
「なんだ、お前たちもよく寝てしまったのではないか」
女中たちもはっとした。
「そういえば、姫さまは、酢味噌はいやじゃとおっしゃいまして、召し上がりませんでした」
春が思い出した。
「それじゃ、あの木耳は、食すと眠くなるものかもしれぬ、お前たちがぐっすり寝ているすきに、姫は外に出たのじゃ」
「そうかもしれませぬ」
女中たちが相槌をうった。
「それは大変じゃ、何をしておる、こうしておれぬ、城の外にでも出られてしまうと大事じゃ、我々も外に姫を探しに行かねばならぬ、ほら、お前たちも用意せい、それに供のものを何人かよこすように言うてくれ」
しばらくして、七左衛門と三人の女中、それに城を守る男たち数人が、城外に姫を探しに出た。
塀を乗り越えれば外に出ることはできるが、城は小高い丘の上である、そこから下に降りるのは時間がかかる。
城から降りると、周りは草の生えた平地である。木も生えていたが、すべて切り倒されている。そのほうが櫓(やぐら)からは見通しが良く、侵入者を見つけやすい。
しかしこう長(た)けのある草が覆ってしまっては人の動きはわかりにくい。
姫がここまでくると、城の上からでは見つけられないであろう。
城下の町はこの草原を抜けさえすればすぐである。
城から降りた七左衛門は女中たちに言った。
「ずいぶんと、茸が生えておる」
草に混じって傘のような大きな白い茸がいたるところで生えていた。
「唐傘のような茸じゃな」
「はい、その通りでございます。唐傘茸と申します」
女中の秋が答えた。
「秋は茸のことをよく知っておるの」
「はい、山奥の茸の里で育ちましてございます」
「そうか、秋は城の奥の生活にはなれたかの」
秋は城勤めを始めてまだ半年である。七左衛門のお気に入りでもある。
秋は姫ばかりではなく、七左衛門の身の回りにもよく気を配ってくれる。
「はい、姫さまにはよくして頂いております」
夏と春も頷いて、春が、
「秋は姫さまの良い遊び相手でございます」
と言った
「そうなのか」
「お座敷では、秋とばかり遊んでいらっしゃいます」
「ほお、どんな遊びをするのかな」
「双六や、吹き矢でございます」
「双六はわかるが、吹き矢とは面白いのう」
夏が、
「襖の竜の目を狙ったり、牡丹の花の芯をねらったり、穴だらけでございます」
と、ぐちった。
「はは、それは、姫さまらしい遊びじゃな、殿に見つかるとお叱りであろうな、あれは殿が絵師に描かせた気に入ったものであろう」
「いいえ、殿がみえたとき一緒になさっておられました」
「よう似ておるよのう」
「ほんに」
七左衛門と三人の女中、それにお供のものたちは、草原(くさはら)を横切ろうと歩いていくが、なかなか抜け出ることができない。
「不思議じゃな、草の丈がだんだん高くなっていく、なぜ草原を抜けることができないんじゃ、おや、大きな唐傘茸じゃな、わしの眼の高さほどもあろう」
背の高い唐傘茸が七左衛門の目の前に現れた。傘は七左衛門の頭より大きいほどである。
「あれ、ほんに大きな唐傘茸が、いたるところに生えている、草も丈が高いこと」
「わしらが小さくなったような気持ちになるわい」
夏が唐傘茸に手を伸ばした。触れたとたん、傘からふわーっと赤い煙が立ちのぼって、漂ってきた。
夏の着ていた白い着物が薄赤くなった。
「この唐傘茸は赤い胞子を持っておる」
七左衛門が少しむせた。
夏が着物についた赤い胞子を見た。
「この胞子は私が姫さまから飲まされた赤い薬にそっくりでございます」
「なんと、そうなのか」
七左衛門は赤い胞子をますます吸い込んで咳き込んだ。
「からだが、すーっとしてきたぞ」
「はい、私もでございます」
春が裾を気にしながらふらふらとからだを揺らし始めた。
「この、楽しさ、姫さまから飲まされたときと同じでございます、赤い薬はこの唐傘茸の胞子のようでございます」
夏がそう言いながら、着物の襟元(えりもと)をはだけた。
「周りの茸がどんどん大きくなってくるのう」
七左衛門は唐傘茸を見上げながら言った。
「ほんに、周りの草も大きくなりまする」
夏と春が周りを見回した。
「おや、供の男どもはどうしなすったのか、居りませぬが」
春の声で七左衛門が振り向くと、三人の伴の男はおらず、三匹の黒い大きな鼠が見上げている。
夏が着物を脱ぎ始めた。
「からだがふわふわしてまいりました、いつぞやの時のようです」
春は唐傘茸を折り取ると、手にもって踊り始めた。唐傘茸から赤い胞子があたり一面にばら撒かれた。
ほんわかとしてきた七左衛門は大きな唐傘茸の下で足を投げ出し、茸の幹に寄りかかった。
七左衛門が思い出したように言った。
「秋、秋がおらん」
七左衛門の前に秋が立った。
「ここにおりまする」
そう言い終わらないうちに、秋は真っ赤な大きな鼠になった。
「あ、あのとき姫様の部屋にいた赤鼠」
唐傘茸を持って踊っていた春が鼠を見た。
「ほほほ、そうじゃ、私が秋じゃ、七左衛門殿、城に住む赤鼠じゃ」
夏が白い肌をさらして、赤い鼠の前で横になった。
「夏、お前は何になりたいかえ」
赤鼠の秋がたずねた。
「アー、気持ちがいい、風が私をなぜいく、いつまでもこうしていたい」
「そうか、お前は風が好きか、それなら薄にしてさしあげよう」
赤い鼠が尾を振ると、夏のからだはスーッと細い薄の穂になり、風に吹かれて、ふわふわと揺れている。
「お春さん、お前さまは何になりたいかえ」
唐傘茸を持って踊っていた春は、
「こうして、いつまでも、踊っていたいのよ」
「それじゃ、薄の周りを踊る風におなり」
薄の穂が踊る風に吹かれて、ふわりふわりと揺れている。
「夏と春はいつまでも揺れておいで、七左衛門殿は何になりたいかえ」
茸に寄りかかっていた七左衛門は赤鼠の秋の声に気が付いて、
「紅姫さまを探さなければ」と立ち上がろうとした。
だが、腰は地面に根を生やしたように重く、動くことができなかった。
「紅姫に会いたいかえ」
赤鼠が聞いた。
「もちろんじゃ、紅姫さまは無事なのだろうか」
「紅姫さまは草原の切り株のところで、おとなしゅうにされております、七左衛門さまをお連れしましょうか」
七左衛門は頷いた。
「ほら、連れていっておやり」
三匹の黒鼠が、七左衛門を背に乗せた。
「行きまするぞ」
赤鼠と七左衛門をかついだ黒鼠たちは、唐傘茸の間を歩いて、切り株のあるところに出た。
「あれが紅姫さまよ」
赤鼠の言ったほうを七左衛門が見た。
切り株の脇に大きな真っ赤な茸が生えている。
「ほほ、紅姫さまは赤いおべべを着て、お外に出たいと駄々をこねられました、これこのように紅天狗茸じゃ、赤いべべきて、天狗になってらっしゃる」
「おおあれが紅姫さまか、おいたわしや、草片(くさびら)なんぞになってしまわれて」
七左衛門は赤い茸に声をかけた。
赤い茸が揺れた。
「さー、七左衛門殿、何を望まれる」
「腹を切らねば、殿に申し訳がたたぬ、お守りすることができなかった」
「ほほほ、まだそのようなことを、この城周りでは、そんなぶっそうなことはさせませんぞ」
「それじゃ、紅姫さまの傍でいつまでもお守りいたしたい」
「おお、そうじゃ、それがよい、姫さまと一緒に虫の音でも聞いておらっしゃれ」
赤い鼠が尾っぽを一振りすると、七左衛門は赤い茸の脇にある切り株に引っ付いた茶色の茸になった。
「ほれ、七左衛門殿、お前さまは、月夜茸じゃ。夜になると緑色に光りまする、紅姫を照らすのじゃ、満足でござろう。姫も喜ばれよ、草の中の真っ暗闇は怖いものよ、鼠だけではないぞ、虫たちも茸は好物じゃ、近寄って齧るやもしれぬ」
切り株の月夜茸がちぎれそうにねじくれた。
「ほほ、そんなに心配なされますな、安心しなされ、七左衛門殿。姫さまも七左衛門殿も私たち鼠とよくお遊びになられましたなあ、大層よくしてくだされた、せめてものお返しじゃ、紅天狗茸も、月夜茸も猛毒じゃ、鼠とて食いはせぬ、あはははは」
そう言い終わると、赤い鼠は黒い鼠とともに消えていった。
薄が風にたなびいている。
茸の紅姫ー幻茸城12
私家版第一茸小説集「幻茸城、2016、302p、一粒書房」所収
茸写真:著者 長野県蓼科 1968-8-15


