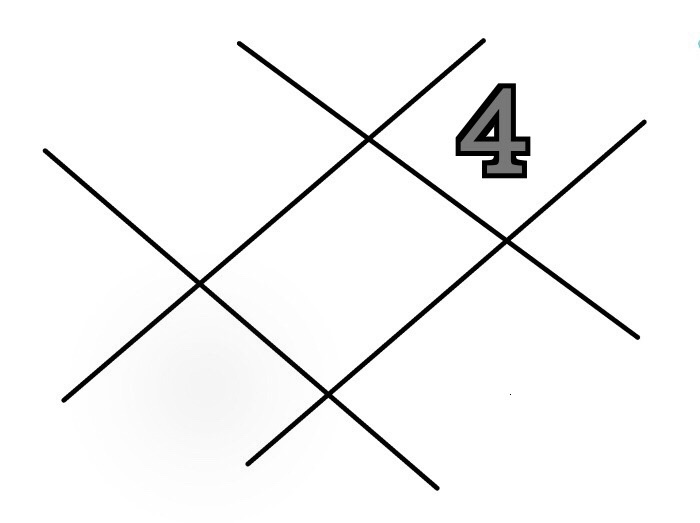
平行感覚【4】
4.生命帰還
人間は夢を見る。様々なタイプの夢を見る。覚えている人もいれば、忘れてしまう人もいる。
僕はこの頃、よく思う。その夢に出てきた人物たちはどこから生まれどこへ消えて行くのか。化学的証明なんか要らない。だって、皆、誰にだって真実程の恐怖はないだろう。科学よりも何よりも、もし解明できるなら夢より生命について、是非、知りたいものだ。この上なく絶望を込めて、八重さんと違い僕にはあらゆる恐怖は持ち合わせていないんでね。
「何してるの?」
その日は、仲間たちと別れて早々に自宅へ帰るために、駅のホームで電車を待っていた。まだ、昼過ぎぐらいのためか人通りは少なかった。僕は幾度も通過する電車を眺めていた。もちろん、僕が乗るべき電車も停車し通過していった。僕は乗るべき電車が幾度もあったのに乗らなかった。
それはまばらな人々の電車の出入りに混じって、彼女を見つけたからだ。黄色い線の外側に立ち、通過する電車を眺めてるというより、彼女の視界に『電車』というものはなかったんだろうと思う。 僕が声をかけた時も、表情を一つも変えず、疑問の声を告げたからだ。
「何のこと?」
「そこは危ないよ。八重さん」
「あなた。どうしてここにいるの?」
「僕は電車を待っていたんだよ。ここは駅でしょう」
「駅?」
八重さんは僕の言葉に、改めて人のいる場所を確認し、疲れきった表情になる。
「そう。そうだったんだ」
「何してたの?」
「見えないの?」
「え?」
「ほら、あの光」
彼女が指すのは痛いほどの晴天の青空。彼女は何を見て追いかけていたのだろう。僕はそれとなく聞いてみた。
八重さんは明らかに話したくなさそうだった。しばしの沈黙の後、電線に止まっていた一羽の鳥が鳴きもせずに飛び立った。
八重さんは何かに驚き、線路の中に落ちそうになった。僕は咄嗟に彼女の腕をつかんだ。八重さんは落ちはしなかったものの、すぐに自分の腕をつかんでいた僕の手を振り払った。
まるで、余計なことをと言わんばかりの態度だ。そんなに悪いことを僕はしたのかは知らない。ただ、彼女にかける言葉は一つ。
「危なかったね。気を付けなよ」
「そうね」
そっけない彼女の言葉。また沈黙が続く。
そして、何通過目かの僕が乗る電車が止まった。
「八重さん。来て」
僕は強引に彼女を電車に引き入れた。彼女の拒絶感はすごいものだった。僕が彼女の肩を押しただけで、極度の震えが一瞬ふれただけの僕にまで伝わってきた。顔面は蒼白し、声には出さないものの、助けの悲鳴を上げているみたいだった。
きっと、瞳さんに向けてだ。僕は素知らぬ顔で空いてる席に座った。電車の中も空いていたから、誰も八重さんの異変に気付かないだろう。すると、震えたままの彼女が僕を見てはっきりと言った。
「私は人が怖いけど、あなたはもっと怖い。あなたの平坦な態度と興味本位な好奇心。それは私が一番、恐れているものに近いから」
僕はそれに答えた。きっと今まで誰にも見せなかった表情で、八重さんに対してだけ。
「それは光栄だね」
三つぐらい駅を越したすぐの所に僕の住んでいるオンボロアパートがある。無理矢理、八重さんを連れて部屋の中へ入った。
入った途端、八重さんは目の前の恐怖に逃げることもできなかったようだ。ま、逃げたくても不可能だっただろう。ドアはなくなっていた。というより、八恵さんが見たものは部屋なんて生温いものじゃない。そこは暗闇しかなかった。
「初めて、お見せするよ。僕たちの本当の部屋」
僕は八重さんの次から次へと出てくる反応を楽しんだ。様々な恐怖とやらを。
八重さんの震えは、もはや彼女を立ち上がらせることもできない程に、打ち崩れた。
「ね? 何を見てたの? 何を追いかけていたのさ」
僕は面白がって、さっきと同じ質問をした。八重さんは何かブツブツと呟いている。人の名前を呼んでいるみたいだった。きっと瞳さんの名前を呼び続けているのだ。
哀れな人。僕は腹の底から笑った。
「応えなよ。ここにいて、拒否権は使えないよ。幾ら、逃げたって あなたを守る。お菓子の城も瞳さんもいない」
「一体、何なのよ」
脅える声。僕を直視し、何度も訴える。
「どうして、私に付きまとうのよ!」
「言わなかった? 話がしたいだけだって、なのにあなたがいつまでもお菓子の城から出ようとしないから、やっと出たと思ったら、声を聞かせてくれないから、ここに連れてきたのさ。ここなら、瞳さんも来ない。仲間たちもまだ帰ってこない。いや、あいつ等は気付いてないからここにはこれない」
八重さんは急に静止した。震えもなく、やがて落ち着いた表情で僕を見返す。
「…キミは見えなかった? ううん。最初から見えていたの?」
何を言い出すかと思えば、さっきの質問の返答のようだ。まるで別人のように八重さんは静かな静かにか細い声で続ける。
「本当に青空だった? そこは青だった?」
砂漠のように乾いた表情でスッと立ち上がり、まるでお芝居を見ているような気分になる。
「人間は、ううん、私は何故に私となったのか。時々、無性に誰かに聞きたくなるの。青空の向こうに答えがあるのなら。それともあなたが知ってるの?」
「僕は知らない。僕が何故に僕となったのか。でもこれだけはわかってるよ」
「何?」
八重さんは目を細めた。僕は彼女に近付くとちょうど首筋にあたる喉仏を目がけて、両腕を伸ばした。ゆっくりと、彼女の首を絞める素振りを見せる。もちろん、力は入れてない。
「八恵さんは奇跡を信じる?」
「信じない」
「即答だね。僕の思った通り、この空間を見て何だと思った?」
「…同時に答える?」
彼女は何かを悟ったらしい。それとも、そう望んだのかはわからないが、僕は彼女の提案に同意した。
『真実』
言った途端、僕は力を込め彼女の首を絞めた。八恵さんは抵抗しない。死にたがっているとか、そういう分類に値しないことぐらいわかっていた。わかっていたからこそ、僕は逆上した。
「あなたは贅沢な人だよ! 何をそんなに脅えて、世の中という時間というものから姿を消そうとするのさ!」
僕は叫んだ。怒鳴った。僕は生きててこんな気持ちになったのは初めてだ。その嬉しさと彼女に対しての深い憎しみは消えることはない。決して、彼女が悪いわけではない。そんなこと誰に言われなくてもわかっている。だけど、僕が込み上げてきた怒りの場所は、どこに返せば良いのかはわからない。何も、何もわからない。
「一つの感覚が失われただけのあなたは、それに捕らわれたままだ。僕なら、僕なら、その感覚は持ち合わせている。だから! あなたが持っていて、僕らにはないただ一つの感覚をくれよっ。じゃないと、僕は気付いてしまった僕はっ」
と、僕はハッとなった。八重さんの目から涙がこぼれ落ち、首を絞めていた僕の手に伝う。僕は狂気の叫び声をあげ、八重さんから離れた。
これは何? 違う。この、この感覚は。目の前の八重さんは、どんな表情をしてるのか。こんな時でも僕は興味を湧いた錯覚をする。だけど。
「うわぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ」
平行感覚【4】

