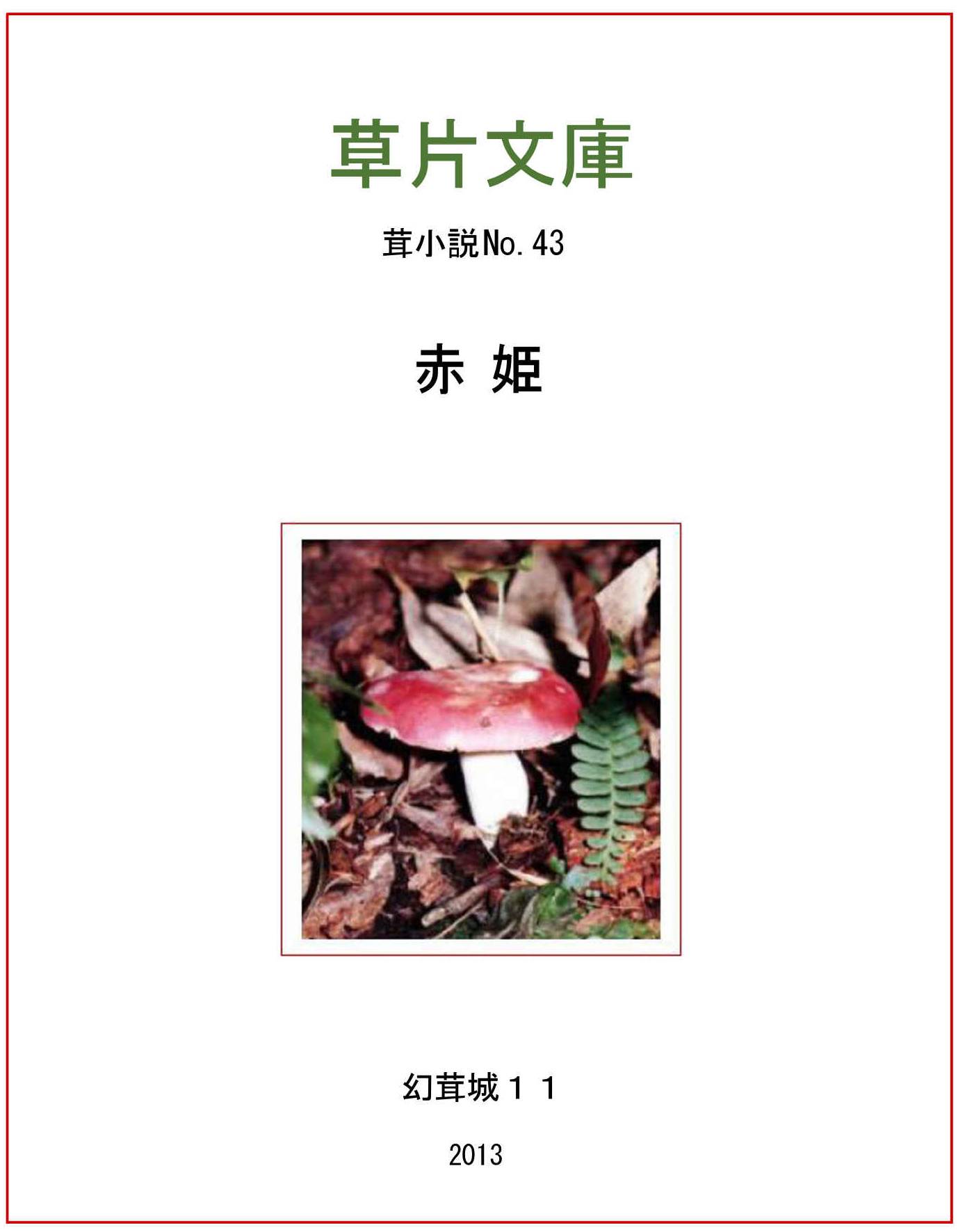
赤姫 - 幻茸城11
幻茸城天守閣の屋根裏である。
「赤姫さま、大変なことになっております」
赤鼠の姫に大黒鼠の爺が言った。
誇り茸を食し、大人になった赤鼠の姫は赤姫と呼ばれている。
「あい、わかっています、猫たちをおとなしくさせなければなりません」
幻茸城に猫が放たれた。
「あの猫たちは餌をもらっておりません、鼠を探し回っています、たくさんの仲間たちが喰われてしまいました、赤姫さまにはそろそろ城から逃げていただかなければなりません」
「爺、赤大山椒魚様のところに行ってまいります、良い考えをお教えくださるかもしれませぬ」
「じゃが、ここから出ると、猫が襲ってきます」
「大丈夫じゃ、女郎蜘蛛の姉さんと、鬼蜘蛛の兄さんにたのんで、蝙蝠の兄さんたちを呼んでもらいます」
蝙蝠の背に乗って、闇岳の半裂穴の闇の宮殿にすむ闇の大王、赤大山椒魚のところにいったことがある。
「おお、それがいい、姫さまは良い家来を持ったものですの」
「爺や、蜘蛛の夫婦や蝙蝠の兄さんたちは家来ではありません。私を助けてくれる大事なお友達です」
「そうですな、いいお友達を持ちましたな」
「はい」
その夜、女郎蜘蛛が鬼蜘蛛を伴って、天守閣の屋根裏にやってきた。
「姫さん、騒々しい奴らが城にやってきましたな」
「そうなの、仲間がだいぶ食べられてしまいました。女郎蜘蛛の姉さんと、鬼蜘蛛の兄さんに、赤山椒魚さまのところに連れてってもらおうと思うの」
「それじゃ、黒蝙蝠を呼ぶかい」
「はい、お願いいたします」
鬼蜘蛛が触覚を振るわせると、すぐさまに黒蝙蝠がやってきた。
「姫さん、久しぶりだな」
「はい、黒蝙蝠の兄さんもお元気そう、お城が大変なんです、赤大山椒魚様のところに連れていってくれませんか」
「ああ、城に猫が送り込まれたと聞いている。たくさんの猫を相手にするのは大変なことだ」
「わしらも行くから、お願いしやすよ」
「おやすいごようさ、仲間を呼ぶから待ってくれ」
すぐに二匹の黒蝙蝠が入って来た。
「さー、お姫さんたちお乗りなさい」
三匹の黒蝙蝠たちが飛びたつ準備をした。
「はい、お願いします」
赤姫と蜘蛛たちは黒蝙蝠の背に乗った。
窓から外にでると、その日もまた新月、星の輝く夜である。城の中からは猫の鳴き声が聞こえてくる。早くしないと仲間達が食われてしまう。
赤姫が心配しているのを、黒蝙蝠たちも感じ取っていたのであろう。まっしぐらに闇岳に向かい、あっという間に着いたのである。
「早い」と赤姫が驚いた。
「一刻も早いほうがいいと思いやして」。
黒蝙蝠たちは鼻の頭にたくさんの汗をかいている。
「ありがとう」
そこへ白蝙蝠が現れた。「おー待っておりました、どうぞこちらへ」
赤姫たちは白蝙蝠につれられて闇の宮殿へ入った。
宮殿の執務室では赤大山椒魚の闇の大王が机を前にしてぼーっとしている。
「おお、待ってましたぞ、赤姫殿、ずいぶん大きくなられましたな」
赤大山椒魚は立ち上がると、にこにこと赤姫のそばによってきた。
「お久しぶりです、赤大山椒魚さま、大王さまは私が来るのをお分かりになっていらしたのですか」
「ああ、人間が猫を放したということは聞いておる、猫一匹なら、どうってことないが、たくさんの猫をいっぺんに退治するのは大変じゃろう」
「はい、難しゅうございます、それでご相談にまいりました」
「そうだな、じゃが、いいことを教えてやろう、猫は木天蓼(またたび)という植物の実に狂うのじゃ、それを食すと、陶酔の境地になる。そうなった隙に、髭を全部切り取るのだ。猫は穴の中に入っていけなくなる」
「でも赤大山椒魚様、また生えてくるのではないでしょうか」
「その通りじゃ、しかし、生えてくるまでは時間がかかる、少し生えてきたら、また、木天蓼を与えて髭を切り取るのじゃ、三回それをすると、猫は動きたくなくなるのじゃ」
「それは良い考えです、木天蓼はどこにあるのでしょう」
「隣の山の中腹にたくさん生えておる、すぐ見つかる。草蜉蝣(くさかげろう)が案内してくれるぞ、草蜉蝣も木天蓼が好きなのじゃ、こちらに来るよう申し付けてある」
「赤大山椒魚様、まもなく草蜉蝣が到着します」
白蝙蝠が伝えにきた。
ほんの一時もすると、大きな鷲(わし)ほどもある草蜉蝣が入ってきた。
「おお、草蜉蝣の妖怪がきた、百十年も生きておる」
草蜉蝣が、赤大山椒魚の前に舞い降りた。
「まいりました」
「おお、ご苦労、ここにおるのが赤姫だ」
「あ、この方が赤姫殿か、いずれあやかしの頭領になられると聞いております、わたしが草蜉蝣でござります」
「赤にございます、よろしくお願いします」
「木天蓼の虫の付いた実をたくさん欲しいのだが、案内してくれぬか」
赤大山椒魚が頼むと、
「おやすいご用です、付いて来てくだされ」
そう言って草蜉蝣は空中に浮き上がった。
赤姫は蜘蛛たちと黒蝙蝠の背に乗った。
「闇の大王様、ありがとうございました」
「赤姫殿、木天蓼だけではだめかも知れぬが、姫の賢き考えで猫を退治なされい」
赤大山椒魚は手を振った。
赤姫と蜘蛛たちを乗せた黒蝙蝠たちは草蜉蝣のあとをめがけて急降下した。
赤姫はぞくっと鳥肌を立てた。まるで鷲が獲物を狙うようだ。
草蜉蝣は大きな木天蓼が絡まっている大木の枝に止まった。
「これは五百年の木天蓼でございます、とても匂いが強く、私はもうすでに目がくらくらしております、猫のやつらだって同じでございます」
木天蓼の蔓(つる)には大きな虫瘤の実がたくさん生っている。
「どうやって運ぶかね、おまえさん」
女郎蜘蛛は大きな蔓を見上げた。
「鬼蜻蜒(おにやんま)のやつらに手伝ってもらおう」
「そりゃいい考えだよ」
「それじゃ、おいらたちが呼んでやる」
黒蝙蝠が耳に聞こえぬ声を使って鬼蜻蜒に連絡した。
「すぐ来るそうだ、一族そろってな」
「私は、そろそろ、戻らせてもらいます、木天蓼の匂いで立っているのも一苦労です。赤姫さま、頑張って猫を退治してくださいよ」
草蜉蝣はすーっと夜空に浮いた。
「ありがとう」、赤姫は手を振った。
「さあ、それじゃ、これから、猫の退治に行きます」
「だが、闇の大王の言うには、髭を切らなければならないが、どうやるね、姫さま」
鬼蜘蛛がたずねた。
「別の方法で退治しましょう。それならば髭を切らずとも大丈夫です。鬼蜻蜒のみなさんに手伝ってもらいます」
そこに、何十匹もの鬼蜻蜒が舞い降りた。
「こんにちは、赤姫さま大きくなったね、すっかり大人だ」
「ありがとう、みなさん、お願いします」
「おお、なんでもやりますよ」
「この木天蓼の実を咥(くわ)えてお城に飛んでください」
「おやすいご用だ」
「そして、お城にいる猫をおびき寄せて、外に連れ出してください」
「そりゃかまわないが、城の中に入るのは大変だな、猫を外に追い出してくださらんかな。そうすれば、どこにでも猫を連れて行きますぜ」
赤姫は少し考えて言った。
「はい、やりましょう、猫が城から外にでるようにします。外に出てきた猫を海まで連れて行って、そこで木天蓼の実をやってください」
「それはいい、猫たちゃ、もう戻ってこれないだろうな」
「あい」
「いい考えた、さすが赤姫さまだ」
女郎蜘蛛と鬼蜘蛛が頷いた。
「しかし、どうやって、猫を城の外に追い出したらいいのかね」
「私に考えがあります、鬼蜻蜒さん、私たちは先に城に帰って、猫を追い出す支度をします、鬼蜻蜒さんたちは木天蓼の実を咥えて城の周りを飛んで、匂いを撒いていてください」
「おいきた、わかった、まかしといてくださいよ、赤姫さん」
鬼蜻蛉は木天蓼の実をついばみ始めた。
「私たちは先に」
赤姫と蜘蛛は黒蝙蝠に乗って城に戻った。
「黒蝙蝠の兄さんたちありがとう」
「なんか手伝うことはないかい」
「ありがとうございます。これで十分です、あとは鬼蜻蜒さんに頼みます」
「そうかい、でも、なんかこのまま帰るのもつまらない、お城の天辺で見物させてもらいますよ、もし手助けが必要なら呼んでくださいよ」
黒蝙蝠は天守閣の屋根の上に陣取った。
もう鬼蜻蜒が数匹やってきて、木天蓼の匂いを撒き始めた。
「あっしらも上にいまさあ、手助けはいつでもしますで」
鬼蜘蛛と女郎蜘蛛も天守閣の屋根に登った。
屋根裏に戻った赤姫は爺にことの次第を報告した。
「それで、どうやって、猫を外に追い出そうといいますのじゃ」
爺が心配そうに聞いた。
赤姫は自分の巣のところから五つの水晶の玉を転がしてきた。
「爺、この水晶の玉を一斉にお城の部屋に放り投げてくれまいか」
「そりゃ、造作もないこと、黒鼠の兵にさせますぞ」
爺が黒鼠を呼んだ。
「この水晶を、私の合図で、それぞれの部屋に投げ入れてください」
「仰せの通り」
黒鼠たちは二匹で一つの水晶の玉を持つと、それぞれの階に運んだ。
部屋では猫たちがうろうろしている。
黒鼠たちが配置に着くと、赤姫が尾で床を叩いて合図をした。
黒鼠たちが一斉に水晶の玉を投げ入れると、水晶から月の光がほとばしり出た。
それは部屋の中を日の光よりも強く照らし出し、慌てふためいた猫たちがめくらめっぽう外に向かって飛び出していった。
階段を使って外に走り出る猫や、屋根を落ちるようにして庭に飛び降りる猫、大騒ぎになった。
「姫さま、あの水晶はなぜ光をだしたのでございましょう」
爺はびっくりした。
「七色井守の持っていた力を教わっていたのです。水晶に月の光を閉じ込め、いっぺんに解放する術を学びました」
「そりゃすごい」
猫たちは庭に出ると、頭がくらっとした。
木天蓼の匂いに気が付いたのである。
鬼蜻蜒たちはうろうろしていた猫たちの頭上を飛んだ。
猫たちの目の色が赤くなり、頭すれすれに飛んでくる鬼蜻蜒のあとを追いかけた。
鬼蜻蜒は城から出ると、低空飛行で海に向かった。
この強力な木天蓼は、猫たちをどんどん走らせた。
「女郎蜘蛛の姉さん、鬼蜘蛛の兄さん、黒蝙蝠のお兄さんたち、もう一度助けてください」
赤姫が天守閣の屋根で見物していた蜘蛛と蝙蝠に声をかけた。
「ほい、もちろん」
声を上げて嬉しそうに黒蝙蝠は蜘蛛たちを乗せて飛んできた。
「爺、私は鬼蜻蜒のあとを途中までついて行きます。それから、閻魔様に会いに行きます」
「なにをしに閻魔様のところに行くのですかな」
「この城を守るには、猫を追い払うだけでは足りません、それを閻魔さまに教わるのです」
「気を付けて行ってくださいよ、わしは城の後片付けをしておきます」
赤姫は黒蝙蝠に乗った。
「たのみましたよー」
みんなが乗った黒蝙蝠は鬼蜻蜒たちのあとを追った。
猫たちは赤い目をらんらんと輝かせて、鬼蜻蜒を追いかけていく。
赤鼠を乗せた黒蝙蝠は途中で向きを変え、一番近い地獄の入り口に向かった。
関東の箱根という場所にも地獄の入口があった。
蒸気が上がり硫黄の匂いが充満している。
「こんな近くにも地獄の入口があったのね」
黒蝙蝠たちは硫黄で黄色くなった岩の隙間の前に着陸した。
赤姫たちは黒蝙蝠の背中からおりた。
待っていたかのように入口が開き、閻魔鴉の親分と娘が現れた。
「赤鼠の姫さま、大人になられましたな、久ぶりでございます。閻魔様は赤姫様が来るのをご存知で、この地獄の入り口でお待ちしろと仰せでした」
「閻魔鴉の親分さん、久しぶりです、よろしゅうお願いします」
閻魔鴉のお嬢さんが前にすすみでた。
「おかげで元気になり、今では父の手伝いをしております」
「今度は私が助けていただく番になりました。よろしくお願いします」
赤姫が頭を下げた。
「もう、なんなりと、どうぞこちらに、閻魔様がお待ち兼ねです」
「おれたちゃこのまま待っているからよ」
鬼蜘蛛が言った。
「あい、すぐ戻ります」
赤姫は閻魔鴉の案内で地獄の中に入って行った。
閻魔様の部屋についた。
閻魔様は前のようにニコニコと赤姫のそばに来た。
「おお、大きくなったな、赤姫、今日の用事はよくわかっている」
「ご無沙汰しております」
「挨拶はいいから、さー、こっちにおいで」
閻魔様が赤姫を案内したのは真っ青な洞窟だった。
「きれいな青」
「そうじゃろう、ほら見てごらん」
閻魔様が指さした先には、真っ青な茸がニョッキリ生えていた。
「幻茸城、お前たちにとって鬼火城の茸じゃ」
「幻茸城が本当の名前なのですね、その茸がどうしてここに」
「幻茸城に何かがあったときに、この茸を使うのじゃ。今がそのときだろう」
「どうやって使うのですか」
「赤姫、これを食すのだ」
「え」
「食べるのじゃ」
「どうなりまするのですか」
「いったん死ぬ、それで赤姫のからだだけ八百年が一瞬にして過ぎ去り、しばらくたつと、息を吹き返す」
「はい」
「そうなったときには、姫は妖術を使う鼠になるのだ」
「妖術を使えるようになるのですか」
「そうじゃ、念じれば、相手は茸になる」
「それは恐ろしい」
「そうじゃ、すごい武器を手にすることになる。じゃが、赤姫は立派な妖怪の頭領となるので、使い方を間違えることはあるまい」
「自信がありません」
「大丈夫じゃ」
閻魔さまは青い茸をとると、赤姫に差し出した。
「さー一族を守るのじゃ、食べなさい」
「ここで食べるのですか」
「そうじゃ」
「はい」
赤姫は青い茸を一気に齧った。
「あ、く、苦しい」
そのとたん、赤姫の顔が白くなり、痙攣すると床に倒れてしまった。
「死んだか」
閻魔様が一言言った。
そこへ、あまりにも帰りが遅く心配した鬼蜘蛛と女郎蜘蛛が入ってきた。
赤姫の様子を見た女郎蜘蛛は倒れている赤姫の脇に駆け寄った。
「赤姫が息をしていない」
女郎蜘蛛は青くなって赤姫を揺すった。それを見た鬼蜘蛛が、
「赤姫さまを殺したのか、やい、閻魔」
閻魔様の胸ぐらをつかんだ。しかし、閻魔鴉に取り押さえられてしまった。
「早まるんじゃない、閻魔様がそのようなことをするわけはないぞ」
閻魔鴉は鬼蜘蛛を羽交い絞めにした。
「ああ、よいよい、赤姫を気遣ってのこと、鬼蜘蛛よ、それに女郎蜘蛛、お主たちは良く今まで赤姫を育ててくれた。礼を言う」
閻魔鴉が鬼蜘蛛を放した。
「でもよ、赤姫さまが死んじまったじゃないか」
鬼蜘蛛の目に涙が浮かんだ。
「おお、死んではいない。いや、死んだが、すぐ生き返る」
すると、見る間に赤姫の顔が赤くなり、ぴくりと鼻を動かした。
「赤姫さま」
女郎蜘蛛が赤姫を抱えた。
「うーん」とうなって赤姫が立ち上がる。
その目は赤く爛々と光り、ふさふさした毛は真っ赤に燃える火の色になった。
「赤姫さま」
「大丈夫じゃ」
赤姫の声は低く地獄に響き、蜘蛛たちは恐怖すら感じた。
「どうしたんだ、姫さまは」
鬼蜘蛛と女郎蜘蛛は顔を見合わせた。
「女郎蜘蛛の姉さん、鬼蜘蛛の兄さん、もう大丈夫、ありがとう」
赤姫のからだの色が火の色から茜色に変わった。
元の赤姫さまの優しい声に戻った。しかし、その目は赤く光ったままである。
「私のからだは元のままですが、もう前の赤ではないようです、私の、この頭の中が真っ赤に煮えたぎっています。それを誰かに向けると、どうなるやら、自分でも怖いほどなのです」
閻魔様がそれに答えた。
「赤姫よ、そなたが怒ると、その相手は、姫の赤いマグマによって、茸に変わってしまうのだ」
「はい、怒ることは差し控えます」
「怒る時は怒りなされ、だが、それはめったにあることではないだろうがのう」
「あい」
その返事を聞いて、蜘蛛たちはほっとしたのである。元の姫さまに戻っている。赤姫様が子どものときの返事だ。
「城に戻る、閻魔様ありがとうございました」
赤姫と蜘蛛たちは黒蝙蝠たちの背に乗った。
「これから、赤姫があやかしの世界を率いていくのじゃ」
閻魔様はまたもとのニコニコ顔にもどった。
「私どもも、いつでもはせ参じまする、何かあったらお呼びください」
閻魔鴉とその娘は飛び立った赤姫に声をかけた。
黒蝙蝠に乗った赤姫は城に戻った。
城は閑散としている。
天守閣の屋根裏に戻った赤姫を見て爺はびっくりした。
「赤姫さま、もう姫様ではありませぬな、赤の女王様でございますな」
「何を言う、爺、私は赤姫のままです。でも、妖怪の仲間入りをさせていただきました、爺に近づいたのです」
「とんでもございません、誰が何を言ったか知りませんが、まだ爺は妖怪にはなっておりません、赤姫、姫はもう死ぬことはありませんが爺は死にまする」
姫はちょっとびっくりした。爺は妖怪だと思っていたからだ。赤山椒魚様が爺は妖怪に近いと言っていた。
「赤姫さま、猫は全くいなくなりました。城の中は安全でございます、ただ、どのような人間が入ってくるのか分かりません」
「その時は、また考えましょう」
「赤姫さまがいらっしゃればもう何も怖くありません」
「爺、そのようなことはない、これからも爺が頼りです」
「はいはい、赤姫さま、だが、もう早く寝なさいとは申しません」
「それは嬉しい、遊びまわるぞ」
「怪我はされますな、妖怪でも怪我をすると痛いものです」
「はい、気を付けます」
「やれやれ、これで、わしの役目も終わりましたな」
「まだまだじゃ、頼むぞ」
「ははあ、爺は女郎蜘蛛にもらった酒を飲んで寝るとしますか」
大黒鼠は笑いながら自分の巣に引揚げた。
それを見ていた女郎蜘蛛と鬼蜘蛛、黒蝙蝠たち、それに戻っていた鬼蜻蜒たちが、あまりの姫の変わりように、びっくりして帰るのも忘れていた。
それに気がついた赤姫はみなに言った。
「すまぬ、忘れていました。今日は、みなさんのおかげで猫を追い払うことができ、それに、私はあやかしの世界にはいりました。大人になったのでお酒を飲んでみたい。さあ、いっしょに、爺の部屋に行きましょう」
鬼火城、または幻茸城と呼ばれる城の天守閣、その屋根裏の片隅で、そこに巣食う生き物たちの酒宴が開かれていた。
赤姫の周りには黒鼠の兵隊、女郎蜘蛛に鬼蜘蛛、黒蝙蝠たちに鬼蜻蜒の面々が集まり、酒を酌み交わしている。
白座頭虫も駆けつけた。
大黒鼠の爺はもういびきをかいている。
水晶の発する月明かりの下で、あやかしの赤姫が真っ赤に燃えている。
これを機に、この幻茸城は人とあやかしの戦の場となるのである。
赤姫 - 幻茸城11
私家版第一茸小説集「幻茸城、2016、302p、一粒書房」所収
茸写真:著者 秋田県湯沢市 1977-8-12


