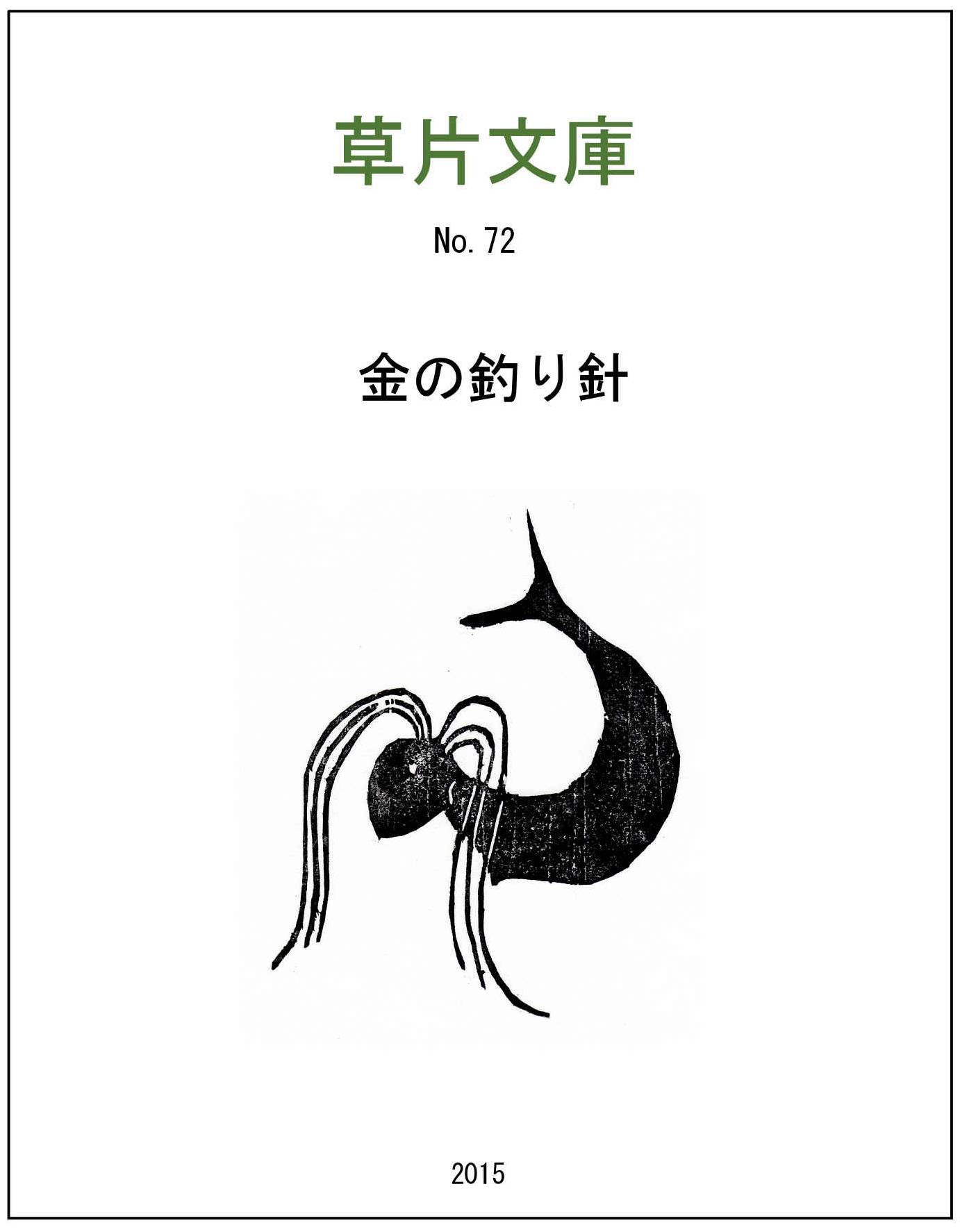
金の釣り針
その昔、金の細工で栄えた金沢の町の出来事である。
大店の主人たちがつくっている遊びの会があった。金箔屋、海産物問屋、医師、反物屋、金物屋の主人たちの集まりで、金ではなく銀の会と称して、月一度、怪談話をもちよったり、変わった物を食べたり、裏の遊びをしたり、時に野天湯に入りに行ったりしていた。
金箔屋の主人、嘉平はなかなかの読書家で、どこでどのように仕入れてくるのか、変わった本をみつけ、その内容を面白可笑しく話したり、よその国の本を持ってきて、その国の生活などを紹介した。海産物問屋の九朗は自慢の集めた南蛮の貝殻などをもちより、珍しい話とともにみなに見せたり、巧妙な貝細工を施した仕掛け箱をもってきたりした。町医者の幸庵は全国から奇妙な薬を取り寄せ、みなに振舞った。薬を口に含むと、酸っぱい物がすべて甘くなるようなもの、精力が異様に高くなる薬、女にその気にさせる薬、頭が気持ちよくなる薬、銀の会の者たちも面白い体験を経験した。反物屋の七衛門は西洋の服という物を取り寄せ、芸者等に着せて踊らせたり、男どもの目を楽しませた。今で言うミニスカートなどのようである。その当時、それを女性にはかせたとなると、異様な興奮があったに違いがない。そして金物屋の三次は刀剣を集めているだけではなく、武器を幅広く扱っていたことから、西洋の鉄砲類をもっていた。皆で浜に集まって、三次がもってきた小さな鉄砲、今で言うピストルで木の標的に穴を開けたりして遊んでもいた。
このメンバーのよいところは、決して家業をおろそかにせず、家族は大事にするという。暗黙の了解のようなものがある。みなの性格上そうなったのかもしれない。
銀の会はそのようなグループである。それそれが若旦那の時代からもう四十年も続いているので、面白い遊びもほとんどしてしまった感がある。
旦那たちもそろって六十を越え、何か刺激的な遊びはないかという思いは皆同じのようである。
彼らが好んでいたのは釣りである。銀の会として集まり釣りをよくしたが、一人で行くこともあれば、家族を連れていったりして、それぞれも楽しんでいる。
「今日は海が和いでいるし、夜釣りをしようじゃないか」
中でも一番年上の九朗が声をかけると、必ず皆が参加する。
寒くなってからでも、厚着をして夜釣りの舟を仕立てる。ちょっと贅沢な大型の舟で、面倒を見てくれる男衆と、舟の上で酒の用意をしてくれる女衆が乗っている。船頭は釣りのことをよく知っている男たちである。
「今日は夫婦岩あたりかね」
「へえ、金色岩あたりもいいかもしれねえです」船頭が答える。
やがて、釣り場につくと、五人は船の中の好きな場所で竿をおろす。それぞれのところに酒が運ばれ、ちびりちびりやりながら世間話をして待っていると、まず九朗の竿に引きがきた。
「お、きましたな」いつものように慎重に竿を上げていく。
「かなりの大きさだ」、海面に現れたのは平目だった。
「なかなかのものですな」嘉平が声をかける。
男衆の一人が平目を針からはずすと、まな板の上で刺身にする。それが各人の脇に置かれ、つまみながら竿の番をする。
「お、きましたぞ」幸庵が竿をあげた。
「大きな鯖ですな」三次があがった魚を見る。
女衆が、とりあげ、すぐさま煮付け、味噌をつけ、皆に配る。
今度は七衛門と嘉平が鯛を釣り上げた。それは刺身になった。
「今日はなかなか旨い物が上がるな」
「ほんとうに」
「いつもこのようなら良いがなあ」
七衛門がつぶやいた。このように金をかけて舟をだしても、ぼうずのときもあるからだ。そのようなときは、舟に持ち込んでおいた物を食べながら余興を考える。船に乗る男衆、女衆には芸達者な者を選んである。その者たちに、踊り、鳴物をさせるのである。
めいめいが何尾かの魚を釣り上げると、車座になって酒宴となった。
「旨い魚を釣るのもよいものだが、何か変わった物を釣り上げたいものですな」
九朗は商売柄、多くの海の物を見てきている。実際に漁師たちの舟にも乗ったりして、あがる魚介類をみて、干したら売れそうな物を選んだりしている。そのようなときに、奇妙な魚を見ることもある。こんな提案をした。
「どうでしょうな、皆で、釣り上げる魚を決めて、釣り針を工夫し、上手く釣り上げた者に、みながごちそうをするなんて趣向はいかがでしょうな」
「そりゃ、面白いかもしれませんな、変わった魚がいいですな、なかなか釣り上げることができない魚もいい」
最初に興味を持ったのは医師の幸庵である。
「海の深いところにすんでいる珍しい魚を釣るのはいかがでしょうかな、私のところに、魚の図譜があるが、面白い形をしたのがたくさんおりますぞ」
嘉平が提案した。
「そりゃあ面白いが、長い糸はなんとかなるにしても、かなり沖にでなければ、そのような場所はありますまい」
「そうですな、大きな舟を貸し切るのは、かなりの金を必要としますな、それに見合うような面白い物がいますかな」
「花魁という魚がいるそうな、一体どんな格好をしているのやら、会ってみたいね」
七衛門が呟いた。舟にも乗ったことのある九朗が言う。
「そりゃあ、竜宮の使いという長く大きな魚だ、海の深いところにいる、ほんのたまに、網に掛かることがあるそうだが、きわめて稀なことで、私も見たことはない。紅くて長くのびた鰭のようなものが華やかなので、漁師たちは花魁と呼んでいるようですよ」
「深海にまで糸を垂らすのは大変なことですな」
「だけど、網にかかるというなら、たまには海の上のほうに上がってくるということだろうから、釣れないことはないだろう」
「わしは、鯨のように大きな烏賊がいるというのを聞いたことがありますが、そんなもんもよろしかろう」
「大王烏賊といいまして、それは大きなものだそうですぞ、旨いかどうかはわからないようだがな」
幸庵や七衛門も知っていた。
「どちらをねらいましょうや」
「どうだろうね、どちらも大きいもので、釣り上げるのは大変だ、どちらか好きな方でいいんじゃないか」
「そうですね、だがそれがかかるまで、何年かかるかわからない、いつもの釣りもしながらやりましょう、竿を二本用意してな」
「それはいい、いつもの魚を釣りながら、大物釣りもする」
「大物の釣りの仕掛けはめいめいが考えると言うことで楽しみますかな」
ということで、釣り舟の楽しみに余興的な釣りが加わった。
しかし、誰もそれが旨くいくとは思っていない。ともかく新しいことをしてみたいのである。
嘉平の家に五人が集まって、深い海の魚の図譜を見た。
竜宮の使いは一丈から四丈、一丈は三メートルである。重さは重いものだと五十貫をこすという。一貫は四キロ弱である。網でしか獲れないようである。食べ物はアミなどの小さい生き物とある。大王烏賊にいたっては四丈、重さはわからないほど重く、魚や烏賊を食べているという。
「こりゃあ、花魁を釣る餌を作るのは難しいのう、大王烏賊の方が易しいわい」
「そうじゃが、よい針を作って、引っ掛ければよいだろう」
「それにしてもでかい」
「どうだろう、子供の竜宮の使いや大王烏賊でもよいということではいかがだろうか」
「それが現実的でしょうな」
小さいものでもよいから珍しい魚と烏賊を釣ろうじゃないかということになった。
花魁と大王烏賊の図を嘉平が模写し、大きさや食べる物を書いた書付をそれぞれにに配った。
「もうだいぶ寒くなった、銀の会の船遊びは次の月の早めにいたしましょう」
「それまでに、釣り針を工夫いたしますか」
「ちょっと凝ったのでも造りましょうや」
「あたしゃ、自分じゃあ無理だ、釣り針作りの名人に相談しますよ」
反物屋の七衛門は細かいことはしない。
「儂も誰か探して頼むとしよう」
海産物問屋の九朗も手先は器用ではない。嘉平、幸庵、三次の商売は細かいことができないとやってはいけないこともあり、三人は自分で造ると言って嘉平の家を辞した。
次の月の舟遊びの日である。海の上に昇ったばかりの太陽の光がきらきらとまぶしい。釣りにはもってこいの日である。この時期にしては暖かい。今日は一日中舟の上にいることになる。
五人の隠居衆が船着き場に思い思いの出立ちで集まった。手には巾着袋を吊るしている。後ろには二本の竿をもった男衆がついている。
「みなさんいきましょう」
舟の中で車座になると、五人は巾着袋の中から釣り針を取り出した。
三次の針は以外と細いものである。
「これは、ただの鉄ではないんですよ、南蛮渡来の強い鉄でつくってあります。小さいが、かなり重い魚でも大丈夫ですな、それだけではないのです、匂う鉄です、魚の匂いがしますよ」
「どれ、みせてくださいますか」
幸庵が受け取ると、匂いをかいだ。薬の臭いをかぎ分けるのにはなれている。鼻がよく利く。
「たしかに、普通の人にはわからないだろうが、臭う」
「どうだろう、私の釣り針は匂いではなく光るものじゃが」」
海産物問屋の九朗は、富山の漁師に造ってもらった釣り針を皆の前に出した。きらきらと光った、頑丈そうな針である。
「富山で花魁をあげた漁師をみつけましてな、その漁師に釣り針を作る男を紹介してもらい、作ったものです」
「それは、よい人をみつけましたな、それでその漁師は、花魁はどんな魚だと言っておりましたかな」
「赤で銀色の鱗をもった長い魚で、あれは魚を食ったりはしないので、餌じゃつれないといってまして、はっきりはわからないが、きらきらと光るものを飲み込むかも知れないということでしたな」
「ほーなるほど、私が造ってもらったのも九朗さんと同じように、大王烏賊を見た漁師に作ってもらったのです。その漁師は自分で釣り針を作る男で、その大王烏賊を釣りたいと思って、それようの釣り針を作り、試したことがあるそうです」
七衛門が取り出したのは、赤っぽい烏賊の形の細工が付いた針であった。
「漁師は海に浮いていた大王烏賊を舟に引き上げ、腹を割いたところ、中から赤っぽい烏賊がでてきたということで、大王烏賊の好物は烏賊だろうと言っておった」
「共食いですな、だが、上手くいくかもしれないですな」
そう言って、幸庵は漆で黒く塗った針を取り出した。針の根本に印籠のような物がついている。
「これはな、細い鉄の管で造った釣り針で、この中に匂う薬と、しびれさせる薬が仕込んである。竜宮の使い、大王烏賊どちらでもいいが、これに食いつけば、しびれ薬が流れて、魚たちは動きが弱くなる。すなわち、釣り上げ易いということです」
「さすが、幸庵先生ですな」
「私は、これしかなくてですな」
嘉平は金色に光るきれいな釣り針を取り出した。
「ほほう、さすが、喜平さんは金で造られましたな」
「はは、これしか私には作れませんな、ただ、この金は普通の金ではありません」
「謂われがありそうですな」
「竜宮城の屋根の金の瓦の一部だというものです」
「どうされたのかな」
金の釣り針まわして、みな手に取ってみた。形や重さは取り立てて珍しいものではないが、手に取ると、何か刺さってくるような怖さがある。
「海からあがった物なのです」
「だが、なぜそれが竜宮の物とわかりましたのじゃ」
「ご存知の方もあろうが何百年も前のこと、大地震が起きて、このあたりに津波が押し寄せました、そのとき、沖の方に浮かび上がったのが、華麗な建物だそうです、赤や青に彩られ、屋根は金色に光ってまぶしかったという、まさに竜宮城そのもので、町の中に流れてきたのですが、津波が引くときにあっと言う間に沖に消えていったそうです。津波が退くと、一枚の壊れた金の瓦が落ちていということで、その様子が書かれた文献があります、曾祖父が金の瓦を手に入れまして、いつかそれで金箔を造るつもりだったのでしょう、それを私が釣り針にしてしまいました」
「そりゃあ、豪勢だ、竜宮の使いにとっては魅力ですな」
話の後、めいめい長く強い糸に針を付け、船の中の釣り場に座った。糸は金沢の漁師にたのみ、特別強い物を造ったものである。百寸と、けた外れに長く、錘は二百匁と重いものである。糸は五人とも同じ物を使っている。
「まあ、なにが釣れるかわからんが楽しみですな」
いつもと違いかなり沖での釣りである。
こうして、五人の隠居たちは工夫した針をつけた深海竿と、いつもの竿を船縁(ふなべり)から伸ばし、糸を垂れた。
しばらくはぼんやり見ている他ないであろう。寄ってくる海鳥を眩しく見ていると、それぞれいつもの竿に手応えがあり、引き上げた。あがってきた多くは顔なじみの魚であるが、釣り場が沖だからであろう、知らない魚も混じる。
深海竿はというと、一時たってもまったく当たりがなかった。
昼時になり、五人は女人衆が用意した御膳を囲んでいる。
「なかなか掛かりませんな」
「まあ、そりゃあしかたがないでしょう」
「想像で造った針ですからな」
などと話しているところに、「旦那さま、引いております」と、七衛門の男衆の声がした。
七衛門はあわてて箸をおき、船縁に戻った。深海竿をみると、確かにヒクヒクと波間の浮きが動いている。
他の旦那衆も七衛門の周りに集まった。七衛門が竿を持ち上げると手応えがある。流し糸なので、手で糸をたぐりよせる。「なかなかの大物ですぞ」七衛門は嬉しそうに糸を引いた。かなりの時がかかったが、赤っぽい物が海面に現れた。しかし竜宮の使いや大王烏賊ではなさそうである。
舟の上に引き上げられたのは、大きな真っ赤な蛸のような生き物であった。
「蛸なのだろうか、ちと気味が悪い」
七衛門のがっかりした声に、嘉平が「いやいや、なかなか面白い物をお釣りになった、それは深海に住む蛸の仲間、図譜にありましたぞ」
「それでなんと申すのかな、この蛸は」
「図譜を持ってきております」
嘉平が図譜をめくると、確かに似た蛸の絵がある。赤っぽく、八本の足の間に膜があり、蛸らしくない。
「蝙蝠蛸とありますな」
「ほー、七衛門どのが珍しい物を釣り上げた第一号でございますな」
幸庵が絵筆をとると、さっとその蛸の絵を描いた。日付と七衛門の名前を記した。
「相変わらず、幸庵さんは絵がお上手だ、儂も何か引き上げて描いてもらいたいものですな」
絵をのぞきこんで三次が羨ましそうに見た。
「この蛸を食らいましょうぞ」
七衛門が女人衆に言ったが、気味悪がっている。三次が「あたしがしましょう」と、西洋の刃物をとりだすと、まだぐにょぐにょ動いている蛸を切り裂いた。
三次は七衛門に切り身を渡した。
「すみませんな、それでは、最初に毒味を」
七衛門は皿の醤油に蛸の切り身を付けると口に運んだ。
「おお、いけますぞ」
その声を聞いて、三次は蝙蝠蛸を細かく刻んだ。
「なかなか旨いものですな」
「昼時によい物が釣れたものです」
こうして昼も終わり、それから一時ほど経ったとき、九朗の深海竿に引きがきた。
「さすがに、職人さんに作ってもらった釣り針は掛かりがよいですな」
時間をかけて九朗が糸をたぐり寄せると、上がってきたのはきらきら光るきれいな水母だった。緑色の光を絶え間なく放っている。
「こりゃまた、きれいな水母で」
「でも、竜宮の使いじゃなけりゃ」
九朗が捨てようとすると、嘉平が止めた。
「いや、幸庵さんに絵を描いてもらおうじゃありませんか、それに、酢の物にでもすれば旨いかも知れない、あたしが名前を調べましょう」
嘉平が図譜を調べて「そりゃあ、やっぱり深い海にいる櫛水母というものらしい」
「そいじゃ、あたしが、もう一度切り刻んでみますかな」
幸庵が絵にし終わると、三次が西洋包丁を取り出して櫛水母を切り刻んだ。女人衆が塩と砂糖を入れた三杯酢を運んでくると、水母の切り身を浸した。
九朗がまず食べてみた。
「こりゃ、なかなかなもの、お酒ですな」
「ほー、それじゃ、燗をつけておくれ」
七衛門の声で女人衆が酒を暖め始めた。
皆の箸が酢水母に伸びた。そこへ、「なにかが引っかかったようです」と幸庵の男衆が深海竿を押さえている。
旦那たちは男衆に竿をまかせてしまっている。気儘なもので、旦那衆は気が向くと竿の前に座る。
幸庵が代わって竿をもつと、
「こりゃ、生きものではないわい、なにか引っかかったんじゃ」
糸をたぐり寄せると、紅い海藻が絡みついてきた。
「石花菜(せっかさい)だな」
「天草でございますな」
「つまらんものが、掛かったわい」
「これも酒のつまにいたしましょう」
糸をすべてたぐり寄せると、山ほどの天草が舟の上に積みあがった。
「こりゃまた、真っ赤できれいですな」
嘉平が天草を持ち上げたところ、親指ほどの白い蟹がぞろぞろと天草の間から出てきた。
「これは不思議な蟹でございますな」
嘉平は白い蟹をつまみあげた。
「なかなかきれいな蟹ですよ、幸庵さん」
どれ、と幸庵も蟹を摘み上げる。
「確かに、沢蟹の白い奴ですな、川にいるのが海にいるとは珍しい蟹かも知れない」
嘉平が蟹の図譜を開くと、湯の花蟹とある。
「この蟹も深い海の蟹で、なんと、熱い湯が好きと書いてありますぞ」
「ほー、深いところに沈んだ天草に蟹が潜り込んだまま海の中を漂い始め、幸庵さんの針に掛かって、持ち上げられたのでしょうな」
幸庵は女人衆を呼んだ。
「誰か、器をもっておいで、蟹を捕まえて集めておくれ」
さらに、言った。
「沢蟹はあげると旨い、この蟹も油で揚げておくれ」
「また、酒のつまみですな、それにしても深海釣りは面白い」
五人衆は深海水母の酢の物、揚げた深海蟹を摘みながら酒を飲んだ。
「あたしたちのは何もかかりませんな」
嘉平と三次が話していると、三次の深海竿に引きがきた。
「とうとう、きましたな」
三次の針にはその辺にいる当たり前の鯛がかかっていた。
「ほーつまらない、ただの鯛だ」
「まあまあ、三次さん、ずいぶん立派な鯛ではないですか、刺身にしていただきましょうよ」
「たしかに、あたしが釣った鯛では一番大きいようだ、それで満足しなければなりませんな」
そういいながら三次がまた酒の場に座った。
「残るはあたしだけだ、竜宮の金の瓦の御利益はなさそうですな」
嘉平が溜息をついた。
「いやいや、まだ誰も竜宮の使いや、大王烏賊を釣っておりませんぞ、金の釣り針はこれからですぞ」
七衛門が嘉平をなぐさめる。
それから一時が過ぎた、それでも嘉平の金の釣り針には何も掛からなかった。その間に、蝙蝠蛸がもう一回、三次の烏賊の疑似餌に掛かった。
「どうも私の金の釣り針には魚が寄りつかないようですな」
「まだまだわかりませんぞ、すごい物が釣れるかも知れません、釣りは気長な楽しみ」
「そうでしたな、あせってしまい、みっともないことで」
嘉平は頭をかく。
また一時、夕暮れが間近になってくる。
そのとき、嘉平の深海竿がしなった。
「旦那様、掛かっております」
嘉平があわてて竿を持ち上げると、ぴくっと生きた物がかかった様子。
嘉平はゆっくりと糸をたぐり寄せる、かなり重く、男衆にも手伝ってもらう。
「何でございましょうね、旦那様」
男衆は釣りにはなれている者たちである。嘉平にもなにが掛かったかわからないが、男衆にもわからないようだ。
海の上に釣り上げられた物が顔を出した。赤っぽい物が浮かび上がってくる。
男衆が叫んだ
「あ、ありゃ、花魁、いや恵比寿様じゃありやせんか」
「え」
嘉平もそれを見る。その声でみんなが集まってくる。
「あー、えらいもんを釣り上げましたな」
七衛門が声を上げた。波の上に浮いた物は、紅い着物を着た女の土左衛門だった。
「だが、確かに生きていると思ったのだがな」
嘉平は手の感触を確かめるようにつぶやくと、
「旦那様、わたしも確かにそう思いました」と男衆も頷く。
「死んだばかりか、それなら生き返るかも知れぬ、早く上げねば」
幸庵が男衆に手をかすように指図をする。
舟の上に上げられた女は色の白い都の顔をしている。女の手はしっかりと金の釣り針の糸を掴んでいた。
「死んだばかりだ」
幸庵はすぐさま女の襟元をはだけ、自分の両手を組み胸を押した。白い形のよい乳房が揺れる。幸庵が女人衆に女の手足をさするように指示する。
しばらく押し続けると、水を口から吹きだし、顔に赤みが差してきた。幸庵は女を横にし、背中をたたく。
こうして、女は息を吹き返した。
女人衆に女の介抱を頼み、舟を岸に向かわせた。
「金の釣り針は女を釣り上げるのですな」
「ほんとに面白い」
女は幸庵の療養所に運ばれ、温浴と投薬で、口が利けるようになった。それで顛末が明らかになった。
沖をいく大名の船から落ち、浮かんだまま金沢の岸に近づいたのだが、力つきて沈んでしまったとのことである。ところが、海の中で金色にきらりと光る物が目に入り、手を伸ばして掴んだところ、釣り上げられたということであった。
その女はとある大名の奥にいる女で、後にその大名から大いなる感謝と、金子が五人に与えられた。
五人はその金子の半分はそれぞれの店の働いている者たちに配り、半分は船遊びに使うことにした。
銀の会の舟遊びはますます盛んになった。もうかなり寒いのに、五人は天気がよいと、毎日のように釣りに出て、深海竿を使った。竜宮の使いや大王烏賊こそあがらなかったが、珍しい魚や生きものが釣れることが分かり、それだけでも面白い、それにいつかは大物を釣り上げることができるだろうと期待したからでもある。
「深い海には面白い魚がいるものですなあ」
「なにが釣れるかわからんのも良いものですわ」
「それにしても、嘉平さん、金の釣り針はすごいですな、女子(おなご)を釣り上げなすった」
「冷やかしちゃいやですよ、雑魚でもいいから掛かってほしいものです」
沖にでると必ず誰かの深海竿に何かが掛かった。大王烏賊ではないが、かなり大きな烏賊も釣れたし、かわった海老が釣られてきたこともあった。いろいろな形や色の水母がかかり、味を楽しませるだけではなく、目も楽しませた。
その日も、真っ赤な水母が九朗の竿で釣り上げられたが、その味も今までの水母と違い、旨いものであった。名前はわからなかった。
さて、帰ろうかと言うとき、嘉平の竿がしなった。
「おや、嘉平さんに当たりですよ、きっとまた、土左衛門かもしれませんぞ」
三次がちゃちゃをとばす。
「いやですよ」
と言いながらも、やっと引きがきた嘉平は嬉しそうだ。
糸をたぐっていくと、明らかに生きた魚である。しかも人のように重くない。
「今度は必ず魚ですよ」
嘉平がそう言ったとき、海の上に現れたのは若い女の顔である。
「あー、また」
見ていた周りの者が驚きの声を上げた。もっとも驚いたのは嘉平である。急いで糸をたぐり寄せると、女の目が瞬きをしながら船縁に近寄ってくる。糸がピンと張ると、女の手が海の上に上げられた。そこで糸が切れた。
女は手をあげたまま舟の脇にきた。手には糸のついた金の釣り針を持っている。
「誰か、綱梯子をもってこい」
七衛門の声で、男衆が梯子を舟にかけた。すると、女は上半身を海の上に現すと、梯子を手で上った。
どったという音とともに、舟の中に落ち込むと、女はみんなを見た。
旦那たちも、男衆女衆も目は女に釘付けである。
女は上半身裸で、腰より下は緑の鱗に包まれている魚だった。尾鰭がぱたんぱたんと動いている。大人の女性より少し小さいが、熟れた身体つきをしている。
嘉平がうなった。
「人魚だ」
幸庵は絵筆をとり、ささっと人魚の画を描いた。
皆どうしてよいかわからずにいると、人魚が口を利いた。
「この、釣り針はどうしたのじゃ」
嘉平は進み出て、自分が作ったと言った。
「そうか、仔細を聞きたいのう」
そこで、九朗が女衆に酒と刺身の用意をするように言った。その上で、人魚に言った。
「よく来られましたな、ちょっと酒などを一緒にいかがなもんかと思います、そなたさんのお国のことなどお聞きしたいがいかがでしょう」
さすがに九朗である、落ち着きを取り戻していた。
人魚はそれを聞くとうなずいた。
「ほら、席をはやく」
みんなは、舟の座敷に移動した。人魚もいっしょについてきた。
人魚のまわりに五人が座った。めいめいの前にお膳が用意された。
「人魚様はどちらからいらしたのですかな」
九朗が口火をきった。
「竜宮城だが、ご存じであろう」
「はい、竜宮城は知っておりますが、人魚の方々がいるとは思っておりませんでした、乙姫様と魚たちと聞いております」
「乙姫様は人魚族の長じゃ」
「それで、あなた様は、どういうご身分で」
「私は竜宮城を守る役目、今日見回りをしていると、竜宮城の金の瓦で作った釣り針が降りてきた、それで捕えてここに来たのじゃ、この釣り針の金はどうしたのだ」
嘉平が、釣り針の金のいわれを説明した。
「そうか、竜宮城は海底にあるのではなく、浮いているのじゃ、深い海にいることもあれば、上の方に上がってくることもある。その昔のこと、ちょっと上の方にいるときに、津波に遭い、陸に流されたとき、屋根が何やらとぶつかり、瓦の一部を落としてしまった。して、釣り針を作った残りの金はどうしたのじゃ」
「すべて、釣り針にいたしました」
「何本あるのじゃ」
「八本にございます、無くなったときの予備として今もっております」
「見せてくれぬか」
嘉平は巾着から七本の釣り針を出した。
「返してもらってよいな、これで、欠けた瓦を直すことができる」
「ははあ、もちろんでございます」
嘉平は釣り針を差し出した。
「礼を申します」
そう言って人魚は帰ろうとします。
「どうぞ、一献」
七衛門が酒を人魚の前にある杯についだ。
「酒か、私は酒は飲んでいけないことになっている、竜宮の中の乙姫様が執り行う酒宴でも飲むことはない、警護の役割があるからじゃ」
「ここは舟の上、かまわぬではありませんか」
「私も酒は好きではあるが、確かに舟の上、海の中とは違いますね」
瓜実顔の人魚は微笑んだ。
猪口を手にすると、一気に飲んだ。
「よい酒です」
鯛の刺身が運ばれてきた。人魚はそれには箸をつけなかった。
幸庵がまた酒をついだ。人魚はすぐ飲んだ。かなり好きそうである。
「これ、誰か、この人魚様にお酌をしてくれ、我々もいただく」
女人衆の一人がお酌をした。五人の衆は酒盛りを始めた。
白い人魚の顔に赤みが差してきた。きれいな肌もうっすらと赤くなっている。人魚が酒を飲むたびに、大きくはないがかわいらしい形の乳房が揺れる。
「人魚様はいくつになられますのかな」
「わたしはまだ六十、やっと大人になったところ」
「いくつまで生きますのかな」
「死にはしない」
「おおすばらしい、それで、子供はどのように作るのですかな」
「大人になった人魚は、卵を産壷に産み落とすのじゃ、通りかかった雄の魚たちが精をかけていくと、いつかは子供ができる」
それを聞いて、みなほーっと感嘆した。
隣に座っていた三次がいきなり人魚の尾鰭に触った。ちょっと酔っている。
人魚は驚いて、尾を反対側に回した。
「どうぞ、刺身を召し上がってくだされ、飲んでばかりでは体にさわる」
医師の幸庵は心配した。
「ほほ、大丈夫じゃ、酒が旨い、魚は食わぬ」
「あ、そうですな」
刺身を食うということは、自分の下半身を喰らうことになる。
人魚の酒の強いことには驚いた。五人衆はちびちびとやっていてだいぶ酔いが回ってきた。人魚はかわらず勢いよく酒を飲む。
男衆が七衛門に耳打ちをした。酒がなくなりそうだということであった。
「人魚様、もってきた酒が、もうほとんどございません、いかがでしょう、また、別の日に私どもの用意した宴においでになりませんでしょうか」
「酒はうまい、言ったように乙姫様にだめだと言われています、もし、その掟を破れば、私はただの鯛にされてしまいます、あなた方に食われちまう」
「お酒はもう召し上がっております。内緒に致しますから、今度は酒をたくさん積んできたとき、是非ごいっしょに」
「ありがたいことだが、次はない、今ここにいるのは本当に偶然のこと、この瓦の金がなければ舟の上に上がることはない、これが知れたら大変じゃ」
「それじゃ、これが人魚さんの見納めか」
三次はだいぶ酒がまわっている。五人の中で一番若いが、酒は一番弱い。
「おいしいお酒だった、馳走になった、嘉平殿、竜宮の金には感謝している」
人魚が伸び上がって動こうとしたとき、三次の手が人魚の左側の乳に伸び、むんずと掴んだ。
人魚は驚いて、飛び上がった。人魚の目が釣りあがった。
顔が真っ赤になり、おちょぼ口だと見えた口が大きく裂け、牙が外に飛び出した。
「乙姫様しか触れぬ、お主、覚悟せよ」
そう言うと、三次の顔に噛み付いた。鼻が削りとられた。あっと言う間に喉笛を噛み切られた。
人魚はつぎつぎに隠居たちにの顔に噛み付き、その五人の喉を噛み切ると、死体を食べてしまった。あっと言う間の出来事である。
男衆女人衆は呆気にとられ、逃げだそうとすると、人魚はすべての人間を捕まえ、噛み付き食べてしまった。
舟の上は真っ白な骨が何体も横たわっている。
人魚は骨まできれいにしゃぶったのである。
人魚が海に飛び込んだ。ざぶんという音と共に大きなしぶきが白骨死体にかかった。
やがて海が静まると、舟は漂いだした。
半年後のことである。
行方不明であった釣り船が金沢の浜に打ち上げられた。潮の異変で遠くに流されてしまった舟が、潮の向きが変わって浜に戻ってきた、と金沢の町の人は考えた。
人々は舟の中に行方知れずになった五人の隠居と、付き人たちの骨をみつけた。そばに幸庵が描いたと思われる絵がぼろぼろになって落ちている。女の顔と魚の尾が描かれているが何が描かれていたのか分からなかった。船の中を見回った隠居たちの家族は、みな楽しんだ挙句の事故だったのだろうと思った。
ただ一人、幸庵の跡を継いでいた息子が、死んだ人たちの頭蓋骨の顔面部分が欠けているのに不審を覚えた。何かに齧られた跡のように見えたからだ。しかし、それもすぐに彼の脳裏から消えていった。
金の釣り針
私家版 金幻想譚「金箔虫 2019 一粒書房」所収
木版画:著者


