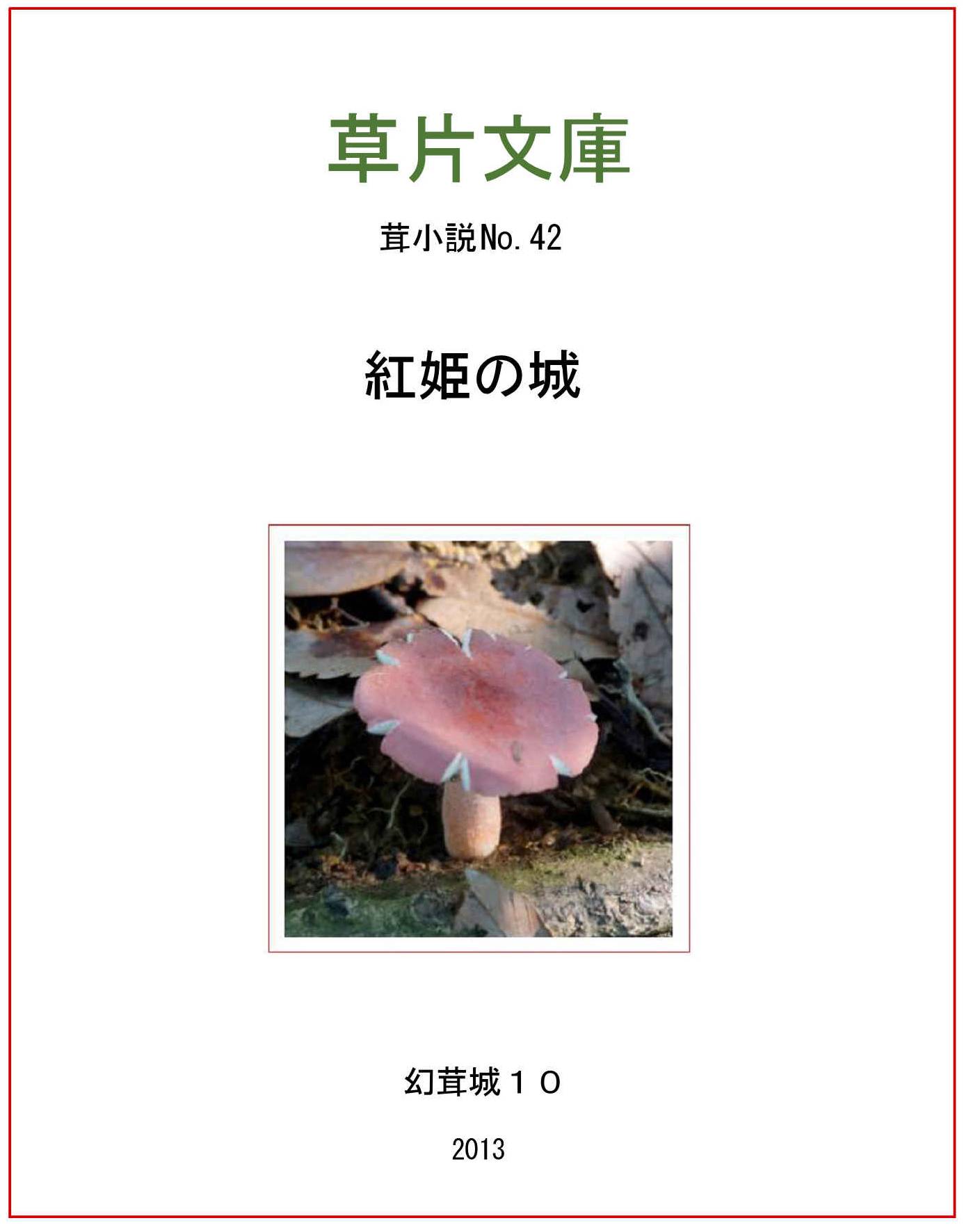
紅姫の城 - 幻茸城10
瓜城の紅姫が六つになったときである。
この国に大地震が起きた。天地がひっくり返るように揺れ、大雨が十日間続いたのである。
瓜城から、遠くに見えるいくつかの山が爆発し、その地区の城はことごとくマグマに呑まれてしまった。
瓜城の周りでも、地面は陥没し、あるところは隆起した。
このような大きな大地の変りように比べ、不思議と変わりが無かったのは浅黄川の流れである。
瓜城そのものも天守閣の一部が壊れ、石垣はかなりの部分が崩れた。助かったことは火の手が上がらなかったことだろう。
地震が起きたのは、真夏のことで、しかも、最初の地震は昼過ぎの、村の者たちは暑さしのぎに、涼しい場所を求め、昼寝などをしていた時刻であった。
百姓たちの家の大半は使い物にならなくなったが、そこは元々粗末なものであったこともあり、建て直すのに時間はかからなかった。
城もいそぎ修復をはじめた。その間、城内に姫の仮住まいを建てた。ところが姫は気に入らなかった。
瓜の殿様は姫の後に子供を授からなかったこともあり、ことのほか紅姫を大事にしている。
「姫にいい屋敷がないものか」
瓜の殿様は家老に言った。
「どこの城も、これと思しき屋敷もことごとく壊れております。半年ほど時間をいただければ、この城も完全に元に戻ると思いまする」
「うむ。わしもそう言っておるのだが、姫は気に入らぬようなのだ」
「頭の良い姫君のこと、よくわかっていらっしゃると思いますが」
「うむ、そうなのだが、なぜか、城が欲しいという」
「なにか、別のお考えをお持ちなのかもしれませぬ」
「なんじゃ」
「ご自分が一人でお住みになりたいのではないのでしょうか」
「うむ、わしといると窮屈なのか」
「いや、殿と言うより、我々と言った方がよいかもしれません、好みの強いお姫様です」
「うむ、一人暮らしをさせてやってもよいが城がない」
「一つ、全く壊れていない城がございます」
「なに、わしは知らんぞ、この地震で壊れないような丈夫な城があったのか」
「はい、幻茸城でございます」
「あの城はどうした」
「あの一帯の平野が一斉に盛り上がり、今では高い台地になってございます。遠くからもあの城が見えるようになったということでございます」
「だれか見たのか」
「はい、密偵をあの地においておきましてございます」
「わしも行ってみたい」
次の日、瓜の殿様は家来数十人引き連れて幻茸城を見に行った。
浅黄川は変わりなくきれいな水をたたえ、静かに流れている。
上流に向かって進むと、そのあたりも様子ががらりと変わってしまっている。茜ヶ原にいくまでの山はすべて崩れ平野となり、城の一角だけが、そそり立ち、浅黄川べりからよく見えた。
「おお、すごい城になった、あそこに登るのは大変か」
「いえ、もうすでに道ができております」
「誰が造ったのだ」
「おそらく、幻茸城の者たちだと思います」
「いったい、どんな奴らなのだ、気味の悪いものだ」
「はい、いつぞやの戦は、まったくの負け戦でございました」
「相手の顔さえ見ることができなかったな」
「はい」
だが瓜城の殿はがんと言った。
「どのような妖怪が住んでいようが、この城は姫のためにもらうとする、このあたりの土は肥えておる。よい作物もとれるであろう、姫が住むようになったら、多くの百姓や商人をこの地に住まわせ、この地を富ませるのだ。そうだ、金細工の職人を抱えて、この地できれいな物を作らせようぞ」
「さすが殿様です、今のうちから、瓜の城に金細工職人と、京都の女子(おなご)を姫様につけてはよいかと存じます」
「それはよい考えじゃ、すぐ手配してくれ」
「はい、京都に人を走らせます」
「その前に、この城をとらねばならぬ」
「はい、今、偵察に五人ほどやっております。まもなく戻ってくると思います」
そこに偵察に行った者たちが戻ってきた。
一人のりりしい男をつれてきていた。
その男は髷を結っておらず、ざんばら頭で、茶色の着物の着流しである。素足に高下駄をつっかけている。戦の格好ではない。顔は彫りが深く太い眉が異国の匂いを感じさせる。
「これ、そこの男、殿の前である、膝をつき頭を下げよ」
警護の武者が男に言った。
男は微動だにせず、たたずんだまま、瓜の殿と目が合うとお辞儀をした。
五人の武者は殿の前で膝をついた。
「この方は、幻茸城の主、幻茸殿でございます」
瓜の殿はちょっとびっくりした様子だったが、そこは多くの城を自分の物にしてきた賢者である。
「おお、あの城のご城主でござるか、お会いしたかった」
瓜の殿は椅子から立ち上がるとお辞儀をして、前に椅子を持ってくるように部下に命じた。
「私もお会いしたいと思っておりました」
挨拶すると、幻茸城の主人は優雅に椅子に腰を下ろした。
「瓜のご城主がみえていると、配下のものが申しまして、私ども、前々よりお願いがあり、ちょうどよい時と、こうして瓜殿の手の者の方に案内いただいた所存でございます」
「おおそれは、わざわざかたじけない、それにしても、ここに来ると決めたのは昨日のこと、よくおわかりになった、さすがに幻茸の一族ですな」
「いや、燕が話してくれました」
「燕とな」
「われわれ、動物の言葉がわかりまする」
「それは、奇異なこと、それでは、我々の話は筒抜けということになりますな」
「そういうことでございます。異国のことなど鳥に聞けばなんでもわかりまする」
「それはすごい」
「すべて我々の言うことが伝わっているとすると、わしが、幻茸城を欲しがっていることもお見通しと言うことでござるな、隠すことができないわけだ」
「その通りでございます、武将ならそう考えるのが当たり前でござる」
「うむ、して、その用とはなんでござるか」
「あの城をもらっていただけぬかと思いましてな」
瓜の殿はさすがにびっくりした。
「くださるというのか」
「その通りでございます」
「もし、お言葉どおりとすると、あなた方はどこに行きなさるのか」
「われわれ幻茸一族、八十八名は、とある島に移りまする」
「しかし、あまりにも不思議な」
「ご不審に思われるのはもっともなこと、だが、そこにおられる五名の部下の方にはお見せしました」
「お主らなにを見て参った」
偵察に行った一人の武将が答えた。
「はい、きれいな城の中にはどなたもいらっしゃらず、空のようでございます」
「もう、我々一族は、その島に移動しておりまする。地震の直後でございます」
「それで、見返りはなにを所望かな」
「名前を残すこと、城を戦の場にしないとお約束いただきたい」
「それは約束いたそう、わしの娘の城にしたい」
「はい、それはよろしゅうございます、城はきれいにしてお渡しいたします」
「して、いついただけますのかな」
「半年お待ちください。まだ片付いていないものもございます」
「半年とな」
「暮れには、必ずお渡しいたす」
「それはありがたい、新しい年明けにふさわしい」
「それでは、これで、お会いするのも最後、お元気で」
「なに、最後とな」
「暮れには門を開けておきまする、どうぞご自由にお入りくだされ、私はそのときにはおりませぬ」
「幻茸どの、それでは、これをお取りくだされ」
瓜の殿は腰の小刀をはずすと幻茸に差し出した。
「それは、大事にされている刀と聞き及びます、そのような物いただけませぬ。我々、刀を持つことはございません、もし、いただけますのなら、お持ちの扇子をいただけませんでしょうか、それも珍しきもの、我々島の暮らしには扇子のほうがありがたいのでございます」
「おお、そうであったか、では、この扇子を差し上げよう、扇子と城を交換したと、末代まで有名になることよ」
「ははは、その通りでございます、では」
幻茸城の主は、すっと立ち上がると、扇子を持って、ぶらり、ぶらりと、城に戻っていった。
「なんと不思議な男よ、それに、もう城が手に入った、なにか物足りぬが、夢ではないな」
「はい、確かに、夢ではございません」
瓜の一行は瓜城に戻り、幻茸城が半年後に瓜一族の物になったことを皆に伝え、祝った。
「良いことづくめでございますな、殿」
「ああ、幸先の良いことよ」
「紅姫様も喜ばれることでございましょう」
「半年の間に姫を教育せねば」
「はい、京から女子どもがもうすぐまいります」
「うむ、作法、着るもの、飾るものは京でよいが、紅姫はただの女子に育てとうはない。男にも勝る強い女に育てるのじゃ」
「もう、殿に似てお元気でございます」
「そうじゃな、そうだ、七左衛門はどうしておる」
「城下で、隠居暮らしをしております。奥様は亡くなられ、お一人暮らしだそうでございます」
「そうか、七爺なら姫の教育役にもってこいではないか」
「はい、殿を育てたお方でございます、しかし、お年を召しておられますから、少しむずかしいかもしれません」
「いや、大丈夫じゃ、あの爺は、なかなかの好き物でな、おそらく、今でも若い女の一人や二人、かこっておろうぞ」
「そうでございますか」
「うむ、きっとそうじゃ」
その日の夕刻、七左衛門が城にやってきた。
「殿、おかわりなく」
「おお、七爺、爺もかわりなさそうじゃの」
「はい、元気に老後を楽しんでおります」
「じつは頼みがある。幻茸城を手に入れた」
「聞き及んでおります、おめでとうございます」
「じつはあの城を、爺に預けたい」
「なんと、私ごときが大将になるのは無理でございます。もう、戦などできませぬ」
「いや、あの城をもらうとき、あの城では戦はせぬと約束させられた。紅にやろうと思う。そのお守を爺に頼もうと思うのじゃ」
「な、なんと、あのお元気な紅姫様を私が教育するなど、とても出来そうもございません」
「はは、紅の利かん気は皆知っておるとみえるの」
「いや、そのような」
「どうじゃ、紅の身の回りにおく女子は、七爺に選んでもらってもよいぞ」
「いや、その」
「女子としてのしつけは京から何人か呼ぶが、身の回りの世話と、強い女に育てるには、ほかの女子が必要であろう、のう、七爺の好みの女ならば、紅も強くなろう、これは命令である」
「ははあ」七左衛門はひれ伏した。
「たのむぞ、半年後じゃ、城内に、爺の屋敷を建ててしんぜようぞ」
「ありがたいことでございます。それでは、私の命のつきるまで、紅姫様をお育ていたします」
「幻茸城主はきれいにしておくと言ってはおるが、やはり手入れは必要であろう。それに、爺の屋敷を建てたり、敷地の中に池を造ってやろうと思っている」
そばで聞いていたお付きの者が言った。
「お話中でございますが、あの城の中にはすでに、きれいな池が造られております」
「おお、そうか、なかなか風流な御仁だったのだな」
「はい、私も忍びの一人でございました故、城の中を見せていただきました。きれいな装飾も施され、なかなか、みごとでございました」
「ほー、そうか、すると、爺の屋敷を作ればよいのであるな」
「それも、ございます」
「なに」
「ご家来集の屋敷も整ってございます」
「天守閣しかないと思っておったが、それは助かるな、では、鼠を退治するだけで良さそうだ」
「はい鼠を退治いたします、猫を放ち、しばらくおいておけば鼠は居なくなります」
「そうだな、それでは、暮れの引き渡しの日には猫を集めて連れていくように」
「わかりましてございます」
瓜の殿様は紅姫の部屋に入った。
「城が手に入ったぞ」
「父上、私のお城がもらえるのですか」
「そうじゃ、紅、来年の正月にはおまえが幻茸城の主となるのだぞ」
「うれしうございます」
「きれいな城だ、しかも大きく立派だ、庭には池があり、草花もきれいに咲くそうだぞ」
「薙刀を振るところもございますか」
「もちろんだ」
「早く行きたい」
「そうじゃろう、鼠退治をしたらおまえの城だ」
「はい」
「扇子一つと取り替えたのじゃ、すごいであろう」
「なんと、父上のお持ちの扇子がお城と同じとはすごいことです」
「それで、京都から女子を呼んでおまえにつけるぞ、いろいろ教わりなさい、それに七左衛門もお前につける」
「え。あの七爺ですか、うれしい」
「あの爺が好きか」
「はい、お父上を育てたのでごさいましょう、きっと私も強くなります」
「そうじゃな」
その年も暮れ、約束の晦日になった。
「殿、忍びの者より、門が開かれ、幻茸殿が一人で旅立たれたことを聞きましてございます」
「そうか、それでは、城の中を検分しておけ、猫を放て」
「かしこまりました」
こうして、幻茸城には猫が数十匹放された。
城の内部はきれいになっており、改めて掃除をする必要がなかった。ただ、天守の一室の床の間に、真っ黒な茸が生えており、とろうとするのだが、全く動かすことができず、そのままになっていた。庭は見事なつくりになっており、四季折々に咲く花が植えられていたのだが、草花の陰で、色とりどりの茸が生えるようになることを、城に入った瓜の姫たちは知ることになるのである。
紅姫のための調度が京都から取り寄せられ、瓜城とは異なった趣の城となった。
「どうじゃ、紅」
「はい、楽しみです」
「幻茸城の名前を紅城としようと思うがどうだ」
「うれしうございます。だが、名前を変えないという約束とお聞きしましたが」
「心配はいらん、誰がどのような名前で呼ぼうがかまわぬ、幻茸殿は小さな島に渡った、もうここには戻ってこまい」
瓜城の殿は幻茸が鳥のことばを聞き分けることを忘れている。
紅姫は幻茸城に入る準備を始めた。
紅姫の城 - 幻茸城10
私家版第一茸小説集「幻茸城、2016、302p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2015-7-12


