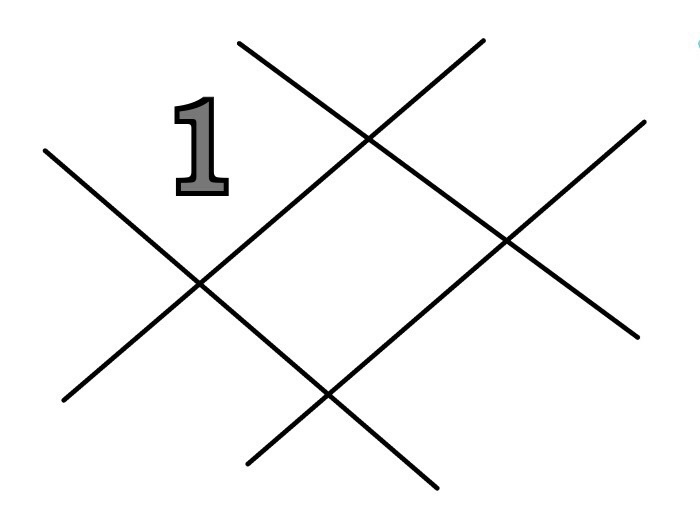
平行感覚【1】
1.散り花
僕たちは生きていく上で何も不安はない。いつものように仲間と語り合い。悲しいことも嬉しいことも一定以上に感知しない。
八重さんは違う。一定でも感知することを恐れた。そんな異様な様子に僕が問いかけると、『心臓が動く自信がないから』と答えた。
要するに人との関わり合いは、八重さんにとって生死に関わる問題なのだと思う。僕はそれに否定はしない。そんな権利は誰も持ち合わせていないだろう。生きている僕等は自分自身以外に口出しするような、そんな大それた人間ではないからだ。
生き方が人それぞれなら、人の感じ方もまた自由であり事実に違いないのだから。
「待った? ごめんね。皆が離してくれなくて」
僕はあの日以来、よく八重さんと瞳さんの喫茶店で待ち合わせするようになった。
初めは警戒する八重さんも瞳さんの喫茶店だったらと承諾してくれた。要するに見張り付きなわけだ。
僕は別にそう言うことに深く考えたりしない。ただ、八重さんと話がしたいだけだった。それには仲間たちが邪魔だった。別に邪険にしているわけではない。ただ、八重さんと話すにはこれはベストに近い選択だった。
「来なくても良かったのに」
八重さんは喫茶店の奥のテーブルに着いていた。一応、気を利かせてくれたらしい。と、言うより僕がどんな話をするか、場合によっては瞳さんに聞かれたくないことでもあるのだろうか。
僕が彼女に向かい合って座ると、緊張してるのだろうか? 八重さんは震えながら置いてあったコーヒーを口にするが、手元が震えているのを僕は見逃さなかった。
「僕が怖いの?」
「皆、怖い。私の視界に入るもの全てが」
彼女はコーヒーをテーブルに置くと、険しい表情を見せた。
僕はそんな彼女を尻目に、水を持ってきた瞳さんに八重さんと同じものを注文したが、コップを乱暴に僕の前に置き、軽蔑した眼差しを残したままカウンターへと戻っていった。
店内はカウンター合わして、十数人ぐらい入れる狭い店で、お客は僕たちしかいない。
「えらい嫌われようだな」
僕は周辺に零れた水を、テーブルに備えてあった布きんで拭いた。
「話は何なの?」
「今、してるじゃない」
「えっ」
「これが会話でしょう?」
困惑したまま八重さんは席を立った。僕は無理に会話を続けた。
「僕は佐々木…」
「知ってる。咲さんのお友達、この前、逢ったでしょう」
「僕はあなたと話がしたかったんだ。理由はないけど、とっても重要だと思うんだよ」
八重さんは軽く、ため息を着いた。僕はもっとも人間らしい感情をその時、初めて見た気がする。
「何に重要があるの?」
「あなたが今、いきり立っていることとか。皆といる時は決して見せなかったじゃない。これって重要でしょう?」
「何のために?」
「僕とあなたが出会った証拠として」
何故、そんなことを口走ったのかは僕にもわからない。八重さんはその後カウンターへと去り、僕は瞳さんに追い出された。
一つ、わかったことは、と言うより薄々感じていた。初めて出会った時から、彼女を知ったり、見たり、もちろん話を交わすことは、彼女を崩していく。まるで枯れかけた一輪の花にそっと触れる度、花びらが一枚一枚と落ちて逝くように…そして、茎だけが残る。
『私は咲いてました』と言う。きっと、彼女はもう茎の存在なのかもしれない。
あの時、瞳さんのマンションで見た生気のない虚ろな表情はまさに『私は生きていた』に繋がる。
まるで、この喫茶店は彼女にとってお城のようだ。そこだけは誰も彼女を苦しませない。一体、瞳さんは八重さんを何から守ろうとしているんだろう? 僕はふっと青く続く空を見上げた。ゆっくりと雲は流れる。
まさかね。僕は仕方なく、仲間たちの所へ戻った。そこには仁王立ちした咲ちゃんがいたのは言うまでもない。
平行感覚【1】

