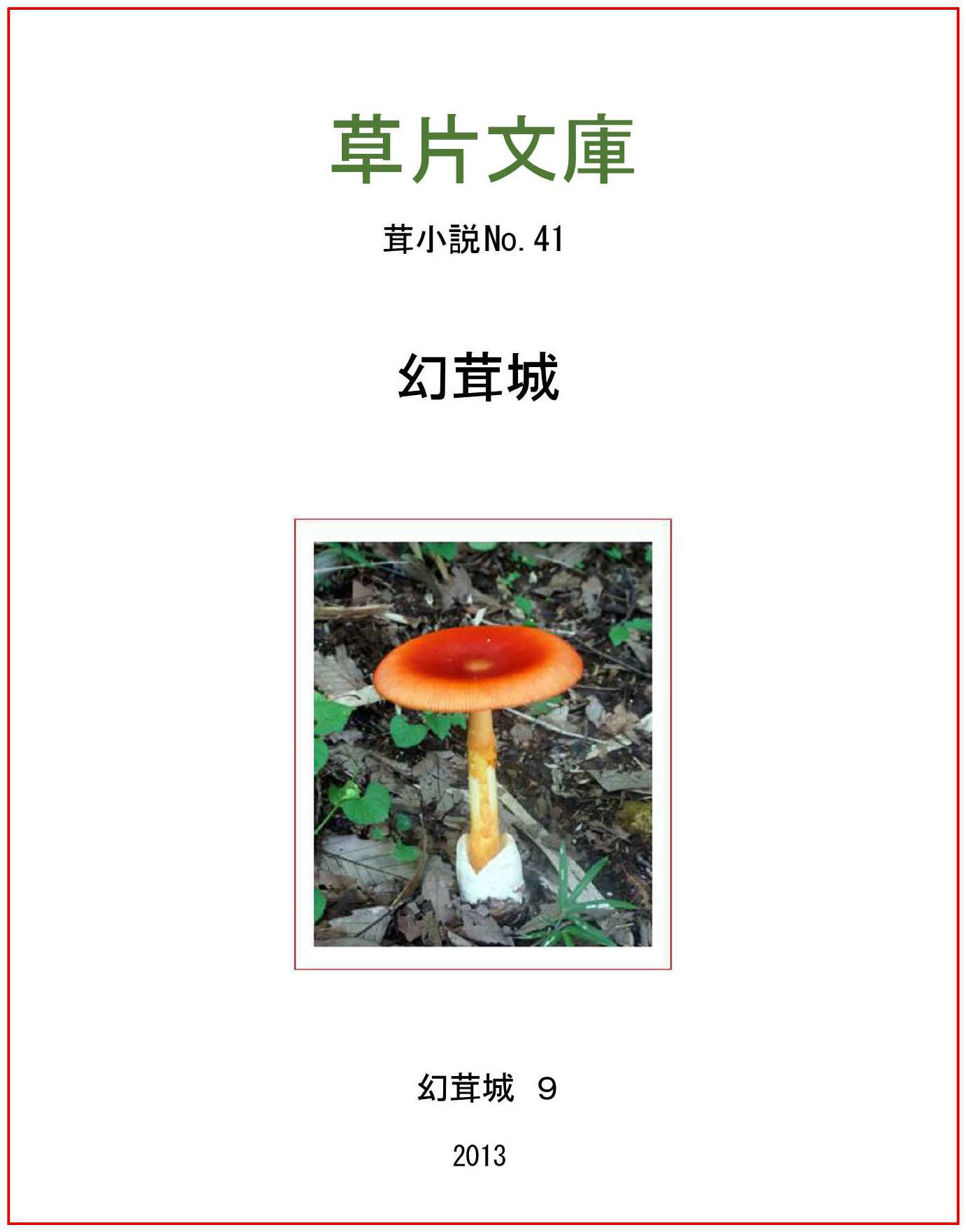
幻茸城 - 幻茸城9
「殿、お生まれになりました」
「もう、産声が聞こえておる、うろたえるな」
「殿、姫様でございます」
「そうか、男がよかった」
「一姫二太郎でございます」
瓜城(うりじょう)は明るい出来事で湧いていた。生まれた子供が男の子ではなかったにせよ、いつも乱暴な殿様も周りに当たり散らすようなことはしない。
浅黄川(あさぎがわ)の辺にある瓜城は頑丈な石垣に守られた大きな城である。栄華を誇る瓜城の侍たちは戦に負けたことがなく、天下一と自分たちを鼓舞するのである。
城の周りの百姓たちも、乱暴な瓜の一族に支配されてはいるが、生活は安心している。年貢にしても決して高いわけではない。瓜の侍たちはこぞって強者で、百姓の年貢に頼っておらず、遠くの城さえも攻め落とし、一族が繁栄していった。
治める地が広がると、その土地に元々あった技術を保護し高め、新たに瓜の領土となった地そのものも潤っていった。
その村に良い鉄の出る山と刀鍛冶がいれば、さらによい刀を作るように努力させ、それを他の国に売りさばき、良い土があり、陶工がいれば、さらに綺麗な器を作らせ、全国に売りさばいた。
それは瓜城や一族の城だけではなく、その地域をも豊かなものにしていった。
このように瓜城の城主は武勇だけではなく治政にも長けていた。
しかし瓜の殿様には一つだけ村人から忌み嫌われていることがあった。
戦では残忍なことをした。
逆らうものをことごとく殺し、攻め落とした城の一族は赤ん坊一人たりとも生かしておかなかったのである。
戦を勝利すると、切り放った相手方の首を槍先に吊るしての凱旋である。
その後、石垣の上に首が並べられ、城では酒宴が七日も続いた。
朝になると、無惨にもカラスに突つかれた首が、崩れた顔を浅黄川に向けて剥けているのであった。
人々はその首が白く骨になるのを見せつけられるのである。
しかし、今日は違った。さらされ白い骨になった首は、浅黄川に捨てられ水に流れていった。
その後には、陶器に植えられた牡丹の花が並べられた。
お姫様がお生まれになったと、城下にあっという間に伝わった。
「姫子なら殿も少しは落ち着くだろう」
人々はしばらく戦のない静かな暮らしになるだろうと思い、安堵の気持ちになっていた。
ところが、全く違った。
たしかに七日の間は穏やかな城であった。
お七夜が明けた次の日、城から狼煙(のろし)が上がった。
戦の準備を知らせるものであった。
百姓も駆り出された。ただ強制ではなかった。雇われるのである。
死ぬことも覚悟しなければならないが、多くの金子をもらうことができた。
死ぬと家族にその倍の金子が与えられた。
その仕組みから、腕っ節の強い男はみな志願したがった。
その上、今まで瓜が負けたことのないことは志願者を増やした。
希望者が多い場合には今まで戦に参加したことのない者が選ばれた。
こうして、百姓の間にも戦の仕方が浸透し、瓜の一族をますます強くしていった。
しかし、戦が終わると、三、四人の死者は出る。老人女子どもたちは、戦の間は重苦しい気持ちになるのは当たり前である。
「父ちゃん、今度はいかないべ」
子供たちは父親に問う。
「ああ、だが、その次はいくぞ」
勝ち戦の味を知っている父親にとって、戦の厳しさもあるが、いつもの生活とは違うものもあることを知っている。
勝ち戦は負けた地のお女子(なご)を弄ぶ。百姓の男たちは命をかけたことの代償と楽しんだのである。
瓜の侍は決してそういうことをしなかった。殿様のお達しがそういうことをすることを禁止していた。それは家で待つ侍の妻の不安を少しながら和らげる効果があった。
瓜城の殿は人あしらいにも長けていたのである。
「殿、今度はどこの城を攻めるおつもりで、もうこのあたりには目ぼしい城はございませぬが」
「もちろんじゃ、今回は大した戦にならんであろう。浅黄川の上流にある幻茸城(げんじじょう)じゃ」
「あの、気味の悪い城でございますか」
「そうじゃ」
「あの城の主がどんな者か知るものがおりません。一説には病を持った一族の城ともいいます。うつる病やもしれず、誰一人としてあの城に近づこうといたしませぬ」
家老の七左衛門が説明をすると、後ろから若い男が、
「殿、あそこに住むのは獣が化けた者とも言われております。接すると祟りなぞがあるとも言われます」
「なにをたわけたことを、ただの噂にすぎぬ」
「あの、亥和城(いのわじょう)の亥和殿が攻めたことがあったと聞きます。攻め込んだ次の日、早々に逃げてきたということでございます」
亥和の一族は瓜の一族に勝るとも劣らない勇敢な武者がそろっていた。
幻茸城はその一族が攻め落とすことができなかったばかりか、一日で戻ってきてしまった。その亥和城は瓜に攻められ落城し、今では瓜の一族により支配されている。
「あれは、亥和殿が急な病にかかったので戻ったと聞くぞ」
「いえ、表向きのことにございます、本当はかなりの負傷者が出て、戻らざるをえなかったと聞いております」
「そんなに強いならやりがいがあろう」
「殿なら必ず攻め落とすこと信じておりますが、損失は大きいものと覚悟は必至と存じます」
「それでは、いつもより多くの兵を集めよ。娘の生まれた祝いじゃ、いつもの倍の金子をとらせよ」
集兵の触れが出ると、あっと言う間に必要な兵が集まった。
出陣の夜会がもようされ、次の日、朝早くに幻茸城に向かった。
途中で亥和城の一党が加わり、いつもより膨大な数になった。
「あのような小さな城、このように大勢でなくとも大丈夫であろうに」
「きっと、お姫様誕生のお祝いだろう」
武者たちは口々にそう噂した。
幻茸城は浅黄川の上流から山道を一里ほど歩いたところにある。
山道を抜けると突然目の前に開ける茜ヶ原と呼ばれる平野の外れに出る。田と畑がちらほらとあるだけでほとんどが野っぱらで、家はちらほらしか見ることができない。
その平野をぐるりと囲んだ山際の道を進んでいくと黒塗りの城が見えてくる。城は平野の真ん中にあった。
変わった城である。真っ黒に塗られた大きな天守閣がぽつんとたっている。ただ、敷地は広く、石垣に囲まれ、作りは頑丈である。
山を抜けたところでいきなり目の前に広がる茜ヶ原、その先に見える黒い城、武者たちは、ぞくっと体が震えた。武者震いなのか、何かの予感なのかはわからなかった。
瓜の武者たちは不思議に思った。
人がいない。
戦を知って家に引きこもっているのか、逃げたのか。
「すすむのだ」
瓜の殿様の声に武者たちは力強く歩いていく。
石垣の下に来ると、城の広さと大きさに驚きの声さえあがった。それでも、殿の合図で火矢を石垣の中に放った。高い石垣に囲まれた城は、下から矢を射っても届くわけがなく、火は敷地の中に消えていくだけであった。
それにしても迎え撃ってこない。
大将たちは首をかしげた。
「この城に人は居るのか」
殿は家来たちを見回した。
「居るはずでございます」
「うむ、攻めるにも、どこに居るのかわからぬではやたらに動けまい」
「今、忍びを放っております」
というところに若い武者が戻ってきた。
「石垣の上に登って参りました。屋敷の中には背の高い草が生え、とても人の住まうようには見えませんでした」
「空城と申すのか」
「かと思いまする」
「それで、どこから城に入れるのか」
「山よりの方に門がございます、そこが開いております」
「なんと開いていると」
「はい、門が開けてあるのでございます」
「罠ではなかろうな」
「天守閣の入口も開いております」
「そうか、今度は中に入って偵察してこい、誰もいないようならもらうだけだ」
「わかりましてございます」
何人かの忍びの者が城の中に入った。
蜘蛛の巣こそ張ってはいなかったが、真っ黒な茸が部屋のあちこちに生えており、人っ子一人居なかった。
忍びたちが一つの部屋に入った時、いい匂いがしてきた。
部屋の台の上に、暖かな湯気の立つ茸汁が、たくさんの椀にいれられ置いてあった。
「これはおかしくないか」
「うむ、おかしい」
と言いながらも、一人の忍びが椀に手を伸ばした。
「味見をしてみる」
「気をつけろよ」
椀を持ち上げ汁を口に含んだ。
すぐに吐き出すと、
「特におかしな味はしないようだ、口のしびれもない、とても旨い味がして、吐き出すのはもったいない感じがした」
「どれ、わしも」
もう一人が口に入れ少し飲んだ。
「これは旨い」
偵察に入った残りの者たちも集まってきた。
「そんなに旨いか」
「うん、旨い」
皆が汁を口にした。あまりの旨さに時を忘れた。
やがて、目の前に酒を持った美しい女子があらわれ酒宴になった。
外で待つ者たちは忍びたちが戻らないのにしびれを切らした。
瓜の殿が「もう一度、誰か城を調べてこい」と怒鳴った。
また、忍びが放たれた。
忍びの者たちは天守閣を下から探っていった。
五層の天守閣の一番上に上がると、膳がたくさん用意されており、旨そうな獅子の肉と茸の煮付けが盛りつけられていた。酒まで用意されている。
部屋中、不思議な香が満ちている。
忍びの一人が匂いに誘われ、箸をとって肉と茸を口に入れた。
「変な味はしない。毒など入っておらん、これは旨い」
忍びたちは、腹が減っていたこともあり、何かにとり憑かれたかのように、肉と茸を口に押しこんだ。
そこに、きれいな娘たちが新たな料理と酒を持ってきた。
外では大将たちがまたも帰らぬ忍びたちを待っていた。
「遅い」
瓜の殿様のいら立った声が聞こえる。
「捕まっているのではないでしょうか」
武将が殿に言ったそのときである。
瓜の軍隊の周りに、黒いものが忍びよってきた。
一人の兵士がそれに気づき、大きな声を上げた。
「敵だ」
その声で、皆が総立ちになり、背後から忍んできた黒い陰に槍を向け、剣を向け、矢を射った。
そのようなものはなにも役に立たず、たくさんの黒い陰はゆっくりと瓜の殿様のほうに向かってきた。
そのとき、天守閣の一番上から何かが放り投げられた。
皆が天守閣を見上げた。
それは、瓜の武将たちの目の前に、どさっと落ちた。
城に偵察に出た十数名の忍びたちであった。
偵察たちは大将の前でぐちゃっとつぶれ、首が折れ頭が破裂した。
「ひけー」
大将は軍隊に声を上げた。
気味が悪くなった軍隊は一目散に幻茸城から撤退したのであった。
このようにして、瓜の殿様は初めての敗北を味わった。
それに不思議なことがあった。
瓜城に帰り着き、労を労おうと、部下を庭に集めた殿は、偵察にやった十数人の忍びたち全員が混じっているのに気が付いた。
「お前たちは、死んだのではないのか」
「いえ、我々は、城の中には何もおらず、安心だということを伝えに戻ったとたん、殿におかれましては、ひけー、と声を上げられたのでございます」
「わしの目の前にお前たちが天守閣から落ちてきたのだぞ」
「いえ、われわれは、門より出て、殿の前にまいりました」
「ふむ、幻覚を見たのか、妖術かもしれん」
そこは賢明な瓜の殿であった。すなおに、自分が妖術にかかったことを認めたのである。それから、また七日間、憑き物おとしの宴を催したのである。
こうして、紅姫が生まれた年は暮れていった。
幻茸城 - 幻茸城9
私家版第一茸小説集「幻茸城、2016、302p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2015-7-11


