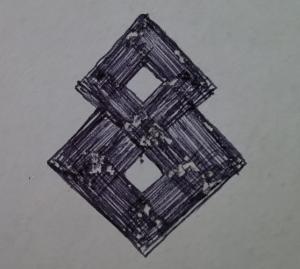官能小説作法試論
タイトル
官能小説作法試論;ポルノグラフィーとしての小説に向き合う個人の感触
(森下巻々)
まえがき
いま、二〇二〇年の、二月四日になったところです。
長編を執筆しなければならないなあ、と思っているところです。
前から思ってはいますが、もういいかげんにといった感じを覚えているのです。
ぼくが今までに執筆できたもので長めのものは、実のところ中編と言えるでないかと考えています。
純文学であれば長編とも呼べる場合があるかも知れない、と思うのですけれど、官能小説は、文庫本になっているものを考えると、枚数が多いです。フツー、書き下ろしで中編は無いのではないかと思われます。
どこか編集部に送る場合、やはり相当な枚数で仕上げて送ったほうがよさそうだと考えるようになりました。
しかしながら、ぼくには、どうしても振り切ることのできない拘りがあります。
新たな官能小説作品の執筆に取り掛かる前に、その拘りについて、官能小説作法について、整理してみようというのが、この文書です。
編集部に送ることを考えている割には、逆のことを言うようですが、ぼくの考えていることを実行したままでいたら、書籍化は無理かも知れないとも感じています。
なぜなら、或る官能小説新人賞の編集部コメント(一般に向けて公開されているもの)などで、ぼくの考えていることとは異なる方法を見かけることがあるからです。
いや、整理してみる前から、そんなこと言ってもしようがないですね。
とにかく、官能小説作法について考えてみます。
特に、視点についてです。
視点
まず、この文書の中では、視点という言葉はどういう意味を持ち得るかを考えてみます。
視点とは、ビデオカメラの位置、とぼくは考えます。
ぼくは、ぼくの場合の読書体験を思い出すことでしか、実感を得られない訳ですが、小説をよんでいるとき、朧気ながら映像をあたまの内に組み立てています。そのときの映像をビデオカメラが捉えたものと考え、そのビデオカメラの位置を視点と考えたいです。
小説をよんでいるときに生成されるイメージを、思い起こしてみると、登場人物が見ているとされているもののイメージ、登場人物たちを俯瞰で見るイメージ、文章を追うたび、そのときどきで変化しているように思われます。
同じ文章をよんでも、読者によってビデオカメラの位置は違うだろうとも思います。
誰かが面と向かって話しているのを想像してみると、或る読者は、その話している登場人物の口元にクローズアップしてイメージしているかも知れないし、或る読者は、結構距離をとって上半身全体をイメージしているかも知れないとも思います。
因みに、ぼくの読書時のイメージがどの程度の明瞭さか、解像度かと言えば、とても低い気がします。登場人物の顔を実在の人物のようにはしっかり思い浮かべられていないです。しかし、可愛らしい感じであれば、その可愛らしい感じを捉えることはできているという感じです。例えば、現実世界で親しい人と話しているときには、親しい雰囲気が発生し、それを自らも感じますね。そういう感じで、可愛らしい感じをよみ受け取ることができている気がします。
さて、視点とはビデオカメラの位置である、と書きましたが、この文書で念頭にあるのは官能小説です。
官能小説では登場人物の性的な行為の描写が物語の中心の場所に必ずあります。
読者が、その行為にどれだけ没入することができるのかという意味で、視点について考えることは極めて重要な気がします。
ポルノグラフィーにおいて、性行為は、受け手からどのように見られているのでしょうか。
受け手
映像作品では、ビデオカメラの位置は明確です。各読者が文章をよみとって、それぞれに映像をあたまにうかべているのではなく、実際に画面に映されているのですから。
画面に林檎が映っているとします。ということは、林檎の手前にビデオカメラがあったことになると考えられます。誰が見ても、そう考えるでしょう。
そこで、いま言ったような意味で分かりやすい、映像作品で、受けての側に立って考えてみたいと思います。
ポルノグラフィーとしての映像作品、性行為を撮影したものを見る場合、受けてである視聴者は、どのような位置にいるのでしょうか。
実際に撮影された現場からは、時間と空間が離れています。
モデルが二人だとして、その二人は、フツーには他者です。自分自身が映っている場合は、いま問題にしません。
女性を好きな男性が男女の行為を見るとして、その行為する男性は他者であり、その他者の性行為を見て、昂奮するということになります。
しかし、この他者が実感としても、他者なのかは微妙なところです。
モデルの男性に自らを重ね合わせて見ているかも知れないからです。
女性の胸を揉んでいるとき、視聴者である自身が揉んでいるような見方をしているのではないでしょうか。
<主観映像>という言葉を見かけることがあります。視聴者の視線とビデオカメラの視線が重なるように撮影された作品があるのです。これなどは、でき得る限り自らを重ねられるように考えられています。
<主観映像>のような作品が数多くリリースされていることを思えば、受けてである視聴者に、登場人物と自らを重ねたい慾望をもった人が一定数いることが想像できます。
いや、ぼく自身がそうなのですが……。
ぼく自身がそうなので、これを小説で実現するには、どの人称が向いているかと考えることになります。
人称
フツー、人称は一人称、二人称、三人称と分けられていると思います。
二人称は、本当に稀だと思いますし、いまのところぼくには難しいので外に置いておきます。官能小説を二人称で執筆した場合、新しい可能性が生まれる予感もしますけれど。
登場人物と、小説をよんでいる自分自身とを重ねたい慾望のある、ぼくとしては一人称と三人称、どちらがよいのでしょうか。
ぼくは、三人称で書くことのほうがフツーです。
一人称のほうが、主語が<僕>とかであって、向いていると考える人もいるでしょうか。
ぼくの場合は、そうは感じません。
主語を<僕>にした場合、その登場人物が、受け手であるぼくに話しかけてくるような感じになると思います。<そうされて、僕は気持ちいい>なんて、報告されると、距離ができます。
名前を主語とする三人称のほうが、むしろ感情移入しやすいです。
いつの間にか、その名前の登場人物になったつもりで、よんでいると思います。
それから、また映像作品の話になって恐縮ですが、女性どうしの性行為を描いた作品をぼくは見たことがあって、その場合も、どちらかの女性になったつもりの時間があったように思います。
また女性の自慰行為を描いた作品の場合は、どうかと考えると、これも自身を重ねているように思われます。第一に、ビデオカメラの視点にです。第二に、その女性にです。
女性しか映っていなくても、ぼくの場合は、ビデオカメラとという形で自身を重ねていることに思い至りました。
改めて、一人称と三人称を比べた場合、やはり、三人称をぼくは取りたくなります。
一人称が生きる場合があるとすれば、ぼくが思いつくのは、女性の視点で読者であるぼくに語りかけてくる方法のものです。<そうされて、私は気持ちいい>のように。
登場人物の<感情の代弁>、これも重要な問題ですね。
感情の代弁
三人称では、各登場人物の感情を書こうと思えば、書けます。
これは、三人称のなかでも、いわゆる<神の視点>で描かれている場合ですね。
<Aには快感だった。Bにとっても快感だった>という風に。
しかし、ぼくは、これが肌に合わないのです。
ぼくは、登場人物に自分自身を重ねるようなよみかたをします。だから、Aに寄り添っていたら、Aが快感だったことは自然と受け取れるのですが、Bが快感だったことがAに分かるのは不自然と感じてしまいます。<Aには快感だった。また、表情を見る限りはBにとっても快感だったようである>なら、自然に受け取れます。
ぼくは、どうしても、ひとりの登場人物に寄り添うような形の文章を好んでしまいます。
Aの感情が書かれて、今度はBの感情が書かれてと、ころころ変わるものは、どうも好みではありません。
Aに寄り添った文章は、それで固めて、Bに寄り添った文章は、それで固めて、と書く方法もある訳ですが、性行為ではないところで切り替わるならまだしも、男女の性行為を描いている中でも切り替わるとすると、たのしみが薄れてしまうのです。
それから、或る登場人物だけに寄り添って執筆していくにしても、それが男性か女性かということがありますね。
男女のカップルを描く場合、ぼくはやはり男性に寄り添って書かれたもののほうが、よみやすいです。
女性に寄り添って書かれた作品で、いいなあと感じるものもありますが、たぶん、かなりうまく書かれていないと難しい気がします。よんでいるときには、女性と自分を重ねつつ、相手の男性の身にもなってみる、という感じになると思います。自分が女性になったつもりで昂奮する、ということもあるでしょうけれど。
<感情の代弁>について書きましたが、<身体の代弁>という側面もあると思うのです。
身体の代弁
仮に、<身体の代弁>と書いてみました。
これは、どういうことかと言うと、ぼくが登場人物のひとり(主人公?)に寄り添って、執筆していることからくる身体の描き方です。
いつから、それが気になるようになったかは思い出せないのですが、特別な場合でない限り、<右手で〇〇した>とは書いてません。
どう書くかというと、<利き手で〇〇した>です。
自分の官能小説をよむであろう人に、左利きの人も右利きの人もいるだろうことを考えると、そのほうが自然と描写に入り込めるのではと考えるようになったのです。
それでは、更に<知識の代弁>についても触れます。
知識の代弁
ぼくが、いま<知識の代弁>と書いたのは、次のようなことです。
これも、登場人物自身になった気分で執筆することからくる拘りです。
登場人物が林檎を見たとします。<そこには、○○があった>と書いたとして、○○が、ただ<林檎>ならかまわないのですが、〇〇が、種類の名前だった場合、その登場人物に林檎の種類についての知識がないと、おかしいと思うのです。
官能小説をよんでいて気になるのは、ファッション(例えば、衣服・アクセサリーの名前など)の言葉が地の文にある場合などです。
その男性主人公が、そんなの知っている訳ないだろう、という気になってしまいます、ぼくは。
もしかしたら、こういうよみかたは、おかしいのかも知れません。繰り返すことにします。もしかしたら、こういうよみかたは、おかしいのかも知れません。
しかし、ぼくは気になるから、Gパンと言ったり、デニムと言ったりくらいは気にかけています。
登場人物に寄り添う形の三人称にするだけでなく、その登場人物の設定・個性をふまえた執筆ができればと思っています。
あとがき
まえがきにも書きましたが、ぼくが拘っていることを実行すると、書籍化にはずっと至れないかもしれないとも思います。
しかしながら、どうしても(官能小説において)三人称で、登場人物みんなの感情を描くことの良さが、よく分からないのですよねえ……。
最後まで、よんでくださって嬉しいです。有難うございました。
官能小説作法試論