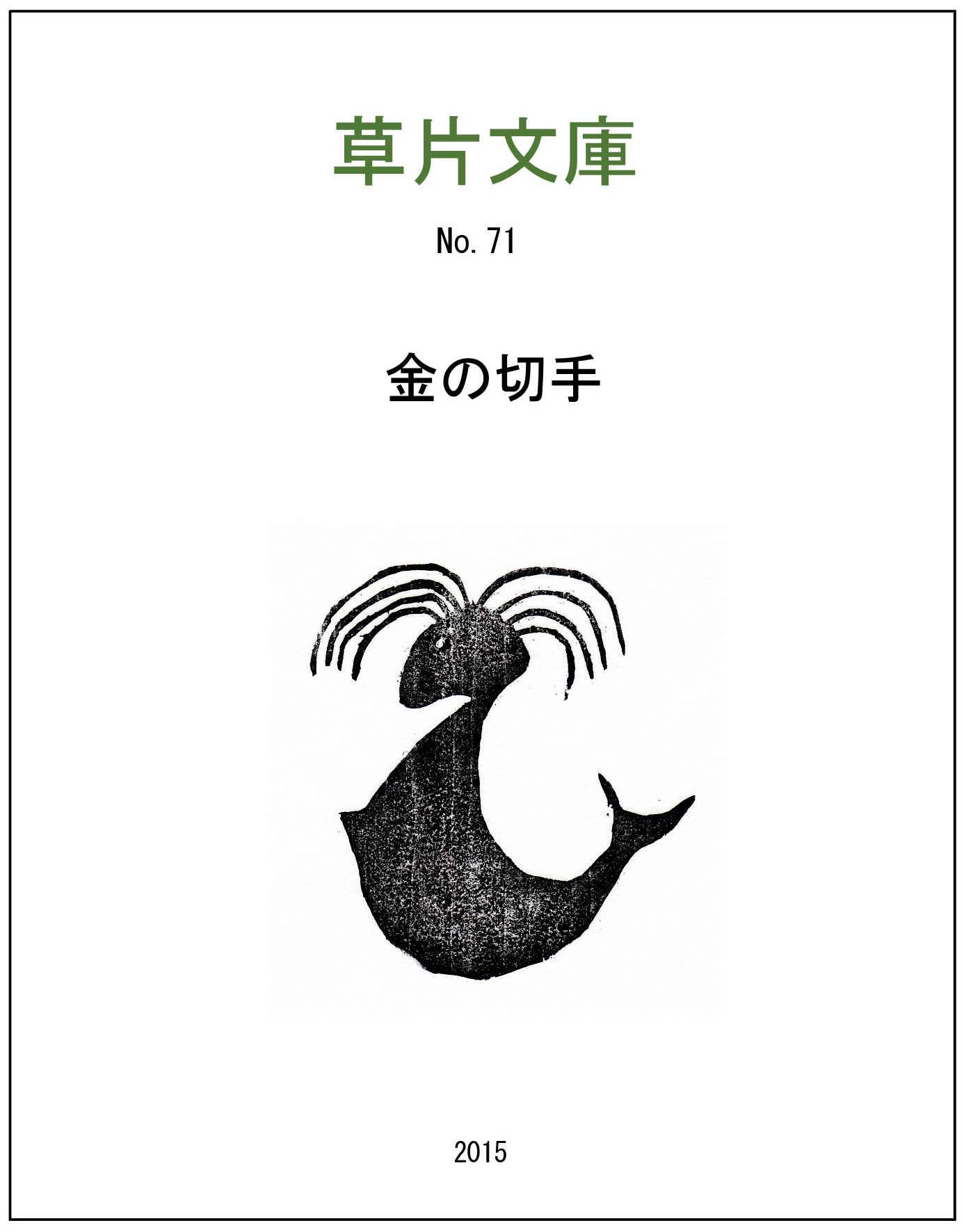
金の切手
金の切手を貼ったら、どこに届くのか。
少年は封筒に金の切手を貼って、ポストにいれた。
宛先が書いてない。誰が考えても郵便局から少年に手紙が戻ると考える。
郵便局の脇の裏道で、切手を売っている爺さんがいた。少年は近寄って台の上を見た。金色に光っている切手が大きなセロファンの袋に入れられている。82円の切手である。きれいだなと少年は欲しくなった。ポケットに百円入っている。
「ぼうや、これはね、金の切手だよ、純金のね」
少年は去年まで切手を集めていた。でもやめちゃった。
見本の金色の切手は、きらきら輝いていて、今まで見たことのないものだった。
ポケットの百円玉に手が触れた。なかなか決断できないでいた。そこにどこかの小母さんがきて、台の上をちらっと見ると言った。
「ほんとに金なの、こんなの手紙に貼ったらどこにいっちゃうかわからないわね」
「どうです、一枚」
売っている爺さんが、見本を差し出すと、小母さんは、
「純金なら、82円じゃ買えないでしょ」、と疑いの目で見た。
「特別です」
「ニッケルなんじゃないの」
「本物ですよ」
「ふーん」
小母さんは全く信用しない様子で立ち去った。
お爺さんはやな顔一つしないで、
「またおいでください」、と見送った。
少年はその切手が本物の金でできている、その瞬間信じた。爺さんの目が金色に輝いたように見えたからだ。
「ください」
少年は駆け寄った。
「ぼうや、ありがとさんね」
爺さんは金の切手を小さなセロファンの袋に入れると、手渡してくれた。
「はい」
少年はポケットから百円を出して爺さんに渡した。
爺さんはその百円を受け取ると、少年を見た。
「なあ、ぼおや、信用してくれたから、この百円はいらないよ、切手はあげよう」
百円玉を少年の手に押しつけた。
「え、ありがと」
少年はちょっとびっくりして爺さんを見た。爺さんの目がまた金色に光った。
「その切手を貼って出すと、手紙に書いてあることが本当になるのだよ」
少年は信じた。
こっくりうなずいた。
家に帰り自分の部屋にはいると、勉強机の上に袋から出した金の切手をおいた。
竜の絵が描いてあった。
今何がほしいのだろう、何がしたいのだろう、少年は、今は何もないなと思いながら、塾に行く支度をした。
塾から帰ってくると、母親が食事の支度をしながら、「どの中学にする」ときいてきた。少年は母親が薦める電車に乗って通う私立中学より、歩いていける山の麓にある市立中学の方がよかった。
「近くのにしたい」
そう言ったのだが結論はわかっていた。私立中学に行かされるに決まっているのだから。
「願書届いたわよ」
ほら、もう決めているのに、一応どうすると聞くのだ。いつものことだ。おやじは何も言わない。母親には少年の好きなようにさせなさいと言っている。だから母親は一応、自分にどうする、と聞くのだ。だけど、そのときすでに決まっている。どうでもよいが、と少年は思っていた。
黒猫の「真っ暗」が戸を勝手にこじ開けて少年の部屋に入ってきた。ひょいと机の上に飛び乗ると、金の切手を見ている少年の顔にからだを押し付けた。
「まっくら、じゃまだよ」
少年は椅子の上であぐらをかいて黒猫を膝の上にのせた。猫の名は少年がつけた。少年が拾ってきた猫でもある。昨年の暮れ、塾の帰り、もう暗くなっていて、街頭のない大きな塀の家の前を通ったら、本当に真っ暗闇になった。そのとき金色の目がきらりと光り、そばに寄ってきたのだ。それがこの黒猫だった。擦りついてきた黒猫を少年は抱き上げた。そのまま家に持って帰り、飼ってもらうことにした。それで真っ暗という名前にしたのだが、飼ってもらうまでが大変だった。母親が動物に興味がなく、家が汚れるのを嫌ったからだ。父親が仕事から帰ってきて、やっと許しがでた。
黒猫は金色の目を少年の方に向けた。
「これは、金の切手なんだよ」
少年は猫に話しかける。
「手紙を書いて、この切手を貼ってポストに入れると、書いてあることがほんとになるんだって」
真っ暗と呼ばれた黒猫は勝手に身繕いをはじめた。黒猫に話が通じたのかどうかわからない。猫と話ができるといいのにと少年は思った。少年には兄弟がいない。話し相手がほしいと思っていたのである。
次の日、学校から帰ると、少年は猫と話をしている様子を手紙に書いて、金の切手を貼った。それをもって郵便局の前のポストにだしにいった。ポストに入れ、郵便局の脇を見ると、まだあの爺さんが金の切手を売っていた。爺さんが少年に話しかけた。
「ぼおや、もう願いを書いてだしたのかい」
「うん、猫と話がしたいんだ」
「へー、面白いお願いだね、たいていは、美味しいものが食べたいとか、頭をよくして欲しいとか書くのだけどね」
それを聞いて、少年はそうか、そうすればよかったかなと思った。
「今までで一番面白い手紙を書いたから、ご褒美に、もう一枚、金の切手をあげよう」
お爺さんはセロファンの袋に金の切手を入れて少年に渡した。
少年はびっくりして「ありがとう」と受け取った。
家に帰ると、少年は金の切手を机の引き出しの中に入れた。頭がよくなっても仕方がない、お腹が空けば何でも美味しい。それより、宛先を書かなかったけど届くのかなと心配になった。金の切手を貼ると、行くところが決まっているのかも知れない。そうか、住所が間違っていたりすると戻ってくる。もし行き先が分からなければ金の切手の手紙は戻ってくるだろう。そうしたら金の切手を剥がしてしまっておこうと思った。
そう思って三日が過ぎた。手紙は戻ってこない。
いったいどこにとどいたのだろう。
算数の勉強をしていると、真っ暗が戸を前足で開けて入ってきた。
「算数やってるのか」
誰かが少年に話しかけた。少年が振り向くと、真っ暗が金色の目を少年に向けて、口をもぐもぐさせていた。
「教えてやろうか」
猫がしゃべった。手紙が届いたのだ。
少年は頷いた。算数は苦手だ。
「どうやったら算数、わかるようになるのかな」
「難しくないと思えばいいんだよ、まず、もう一度九九を暗唱してごらん」
少年は九九を言った。
「ほら、全部言えるじゃないか、それだけ知ってればいいんだよ、あとは、タスヒクワルカケを記号の通りにやればいい」
そう言われて、問題集をみると、ぱっとひらめいた。一つ問題を解くと、次の問題も解けた。そうやって問題を見ていくと、すぐに答えに行き着いた。
「まっくらは学校や塾の先生より教えるの上手だね」
「俺たちは学校には行かないけれど、寝ている間に夢が教えてくれるのだよ」
「それはいいな、だから猫はよく寝ているのだね」
「そんなとこだ」
少年は塾にいくのが楽しくなった。それに、真っ暗は塾に行く途中のどこに猫がいるか教えてくれた。早く家を出て、猫とおしゃべりをするのも嬉しい。
塾は歩いて二十分ほどのところにある。駅の反対側なので、小学校とは違う方向だ。郵便局や市役所の集まったところを通り越して、お店の並んだ通りを抜けると、駅の広場にでる。駅の中を通り、反対側の住宅地の一角に塾のはいっている三階建てのビルがある。下がコンビニエントストアーになっているので、お腹の空いたときには便利だ。
猫はいろいろな所にいる。まず、大通りにでる手前の、赤い屋根の家の門柱の上でぼーっとしている虎猫である。
少年は虎猫の尾っぽを握った。猫が振り向いた。
「尾っぽ触るなよ、こそばゆいじゃないか」
「そうなんだ、尾っぽがピコピコしてかわいいから触ったんだよ」
「勝手に動いちまうんだよ、そういやあ、俺たちの言葉がわかるのは、あの爺さんの金の切手のせいなのかい」
「うん、うちのまっくらと話がしたかったのさ」
「ああ、あの黒のうちの子なんだ」
「うん」
「あの黒はこのあたりじゃ、大統領だ」
「なんで、大統領なの」
「みんなで選挙したんだ、このあたりの大統領は誰にしようってね、そうしたら、あんたの所の黒さ、あいつは大事なところで良いことを言うからね」
「そうなんだ」
「ところで、小学校で辞める先生がいるって言う噂だよ」
「たまにいるから不思議はないよ」
「いや、あんたの先生辞めちゃうよ」
「どうして」
「なんでも、あんたらから集めたお金を使って、洋服買っちゃったんだって」
「いつもきれいな洋服着ているよ」
「給料、みんな洋服に使っちゃうんだって、それでも足りなかったようだよ」
「それで、僕たちが払ったお金どうなるの、工作の材料費なんかでしょう」
「それがね、それだけではないんだって、給食代や本の代金をまとめる役目でね、小学校のあんたらの学年の銀行の通帳をもっていたのだって」
「悪いことをしたんだね」
「そうだよ」
少年はそんな話を聞いてから塾に行った。次の日、小学校に行くと、その女の先生はこなかった。代わりに副教頭先生がきて、勉強を見てくれた。家に帰るとお母さんが、担任の女の先生が急病になって学校を辞めると言った。大人はみんな本当のことは言わないんだな。
大通りの床屋の店の前で身繕いをしている三毛猫はこんなことを言った。
「ぼおや、きょうね、デパートの屋上にね、空飛ぶ円盤がくる」
「どこから」
「銀河系のはずれからだよ」
「何しにくるの」
「地球の観光さ、私が案内をする役目だよ」
「どんな宇宙人なの」
「猫に似ているんだ」
「猫が宇宙人」
「形が似ているだけだよ、人間よりずっと頭がいいんだよ、でもね、前に来たときに、九九ってすごいって言ってたよ」
「会ってみたいな」
「夜中だからね、無理だね、あんたはちゃんと寝なければいけないよ」
「うん」
「だけど、何か欲しいものがあるかい、持って来てもらうよ」
「よく消える消しゴム」
「どうして消しゴムが欲しいんだい」
「国語が苦手なんだ、文章を書くとき何度も書き直すんだ。漢字も間違えるしね、きれいに消して書き直したい」
「そりゃ偉いね、聞いてみるよ」
そうしたら、二日後、真っ暗が三毛から頼まれたと、黄色い消しゴムをもってきた。
「何でも消せて、減らない消しゴムだよ」
それで、少年は間違えても怖くなくなった。
塾に行くとき、郵便局の前を通って、金の切手を売っているお爺さんがいるかどうか見た。もういなかった。もらった金の切手を貼った手紙が、どこに行ったのか聞きたかったけど、できないな。
郵便局の斜め前にケーキ屋さんがあって、その店にいつも真っ白な猫がいる。少年はケーキ屋さんのところに行って白い猫に聞いた。
「金の切手を売っているお爺さん知っている」
「知っているわよ」
「いつ売りにくるの」
「決まってないのよ」
「金の切手のこと知っている」
「少しはね」
白い猫は髭を洗った。
「どんな人が買うのかな」
「買うのは子供たちよ、大人にも売っているけど、買いたいという大人はいないわね、欲しいというのは少年ばかり」
「女の子には売らないの」
「女の子があの爺さんを見つけて、欲しいと言ったときには売ってあげてるわよ」
「女の子は切手を欲しがらないからね」
「でもね、郵便局の裏にいる婆さんもね80円の金の切手を売っていてね、それじゃたりないから、2円の花びらでできた切手も一緒に売っているの、手紙は82円だからね、それは女の子がよく買っているわよ」
「みんな願い事をするんだね」
「本当はね、誰でも子供の頃に必ず金の切手を貼って、願い事をするものなのよ」
「お父さんもお母さんも金の切手を買って、願い事を書いて出したのかな」
「必ずどこかで金の切手を買ってるのよ」
「どんなお願いをするのかな」
「それはね、個人の秘密だから、知っていても教えることができないわ」
「猫と話ができるようにお願いした子はいるのかな」
「あんただけよ」
「それで僕にもう一枚金の切手をくれたんだ」
それを聞いて、白猫はかなり驚いた。
「普通は、一人一枚なんだけどね、それは初めてね、使い方を間違わないようにね」
「間違えたらどうなるのかな」
「それはわからないわ、ともかく本当に使いたいときに使いなさいね」
少年は頷くと
「あの切手を貼ってポストに入れると、どこに行くのか知っているの」
一番知りたいことを聞いた。
「知らないなあ」
白猫は首を横に振った。
「そう、どうもありがとう、またね」
白猫もバイバイをした。少年は塾に行った。
塾の帰り道、駅を過ぎて、自分の家に戻る大通りに出たところで、三匹の猫に会った。
「腹が減った、どこかに食い物はないかね」
野良猫たちである。少年は後先を考えないで、「家においでよ」と声をかけた。
斑と黒虎と茶色の猫は大喜びで少年の後をついていった。
「ただいま、猫がお腹空いたと言うから連れてきた」
少年は正直に母親に言った。
母親は夕食の支度を終えたところだった。
「なに、それ、猫が言うわけはないでしょう」
そういえばお母さんは僕が猫と話せるのを知らないのだ。
「猫たちは餌をやって」
「なに言ってるの、猫たちに、でしょ、言葉はきちんと使いなさい」
確かにお母さんの言う通りだ。
「猫たちは餌を食べたいって」
少年の後に付いてきた三匹の猫が「おじゃまします」と言った。お母さんにはにゃーと聞こえた。
お母さんはびっくりして、猫たちを見た。
「入ってくるな、汚れる」
お母さんの顔は鬼みたいになった。その剣幕に猫たちは縮みあがった。
お母さんは大声で「出ていけー」とそばにあったしゃもじを振り上げて、三匹の猫の頭を叩こうとした。
三匹の猫は、「ありゃー、逃げろ」、あわてて玄関のほうに走っていった。玄関の戸は閉まっている。母親はドタドタと追いかけていくと、しゃもじを振りあげながら、裸足のまま玄関に飛び降り、鍵をはずした。
三匹の猫は大慌てで外に飛び出していった。
お母さんはそのまま台所に戻ってきた。
「だめでしょ、野良猫なんかを家に上げたら、蚤が落ちたらどうするの」
少年は怒られた。
「猫に約束したのに」
「なにを」
「ご飯があるって」
「野良猫にやるためにご飯炊いたんじゃないよ」
母親は大いにむくれた。
真っ暗が少年の部屋から欠伸をしながら出てきた。
「野良猫を連れてきたのかい」
少年はうなずいた。
「かわいそうに、腹が減ってたろうに」
真っ暗も野良猫だったのを少年が拾ってきたのだ。そのときはお父さんが良いと言ってくれたので、飼うことができた。
「猫たちにご飯あるっていっちゃった、怒ってるだろうな」
「大丈夫、町であったら言っておくよ」
少年はうなずいたが、猫に悪いと思い手紙を書いた。
お母さんが猫たちに餌をやってくれますように、と書いた。つもりだった。
次の日、手紙の入った封筒に金の切手を貼ってポストにいれた。
二日後、塾から家に帰って台所に行くと、食事の用意をしていたお母さんが振り向いた。
その瞬間だった。お母さんがぱっと消えた。
お母さんの立っていたところに真っ黒な溝鼠(どぶねずみ)がいた。
少年はびっくりした。
「お母さん、どこにいったの」
少年は鼠がでてきたので、どこかに逃げたのだと思った。
少年はのろのろしているネズミを捕まえると玄関から外にだした。お母さんに見つかると叩かれて、もしかすると死んじゃうかもしれない。しかし、外に出たネズミは逃げようとしなかった。
外にはちょうど真っ暗が三匹の野良猫を引き連れて家に戻ってくるところだった。
「お、餌をくれたぞ、生きた鼠だ」
三匹の野良猫は少年が外に出した鼠を見た。
鼠は猫に気がついて、震え上がると、あわてて少年の方に戻ってきて、家の中に逃げ込もうとした。
少年は急いで玄関の戸を閉めた。
鼠は大慌てで、家の脇を走って逃げて行く。
「道に逃げたぞ、追いかけろ」三匹の猫たちは後を追った。
「ぼおや、ありがとよ」
猫たちはそう言って走っていった。
少年は玄関の中に入った。少年は三匹の猫に餌をあげることができた気になって、ちょっとよかったと思った。
真っ暗が戻ってきて少年にたずねた。
「あの鼠どうしたんだい」
「台所に出てきたんだ、お母さんがびっくりしてどこかに消えちゃった」
「おかしいな、このあたりにはもう鼠はいないけどな」
真っ黒は「ちょっと、三毛猫に会ってくる」
そう言うと、また外に出て行ってしまった。
いくら待っても、お母さんは消えたまま戻ってこなかった。
真っ暗が家に帰ってきた。
少年に言った。
「手紙の書き方を間違えたんだね」
少年には意味が分からなかった。
「金の切手を貼った手紙は銀河系のはずれの星に届くのだよ、猫のような宇宙人が住んでいるんだ、そこの金の切手の係の人が地球にきてね、三毛猫に言ったそうだよ」
「なんて」
「あの少年は、数学は出来るようになったが、国語をもっとしっかり勉強しなければいけないとね」
真っ暗は続けた。
「あんたの手紙には、お母さんが猫たちに餌をやってくれますように、ではなくて、お母さんが猫たちの餌になってくれますようにと書いてあったそうだよ」
「え、そんなに間違っちゃったの、それじゃ、お母さんは食べられちゃったかな」
「そりゃね、野良猫の斑は頭を、黒虎は前半分を、茶色は後半分を食べちゃったよ」
「お腹壊さないといいね」
少年は笑った。
「国語も教えてくれる」
真っ暗に頼んだ。
「ああ、いいよ、日本語を間違えると大変なことになることが分かったろう」
「うん、これからは気をつけるよ」
少年は自分の部屋で、国語を教わりながら、お父さんが帰ってくるのを待つことにした。
金の切手
私家版 金幻想譚「金箔虫 2019 一粒書房」所収
木版画:著者


