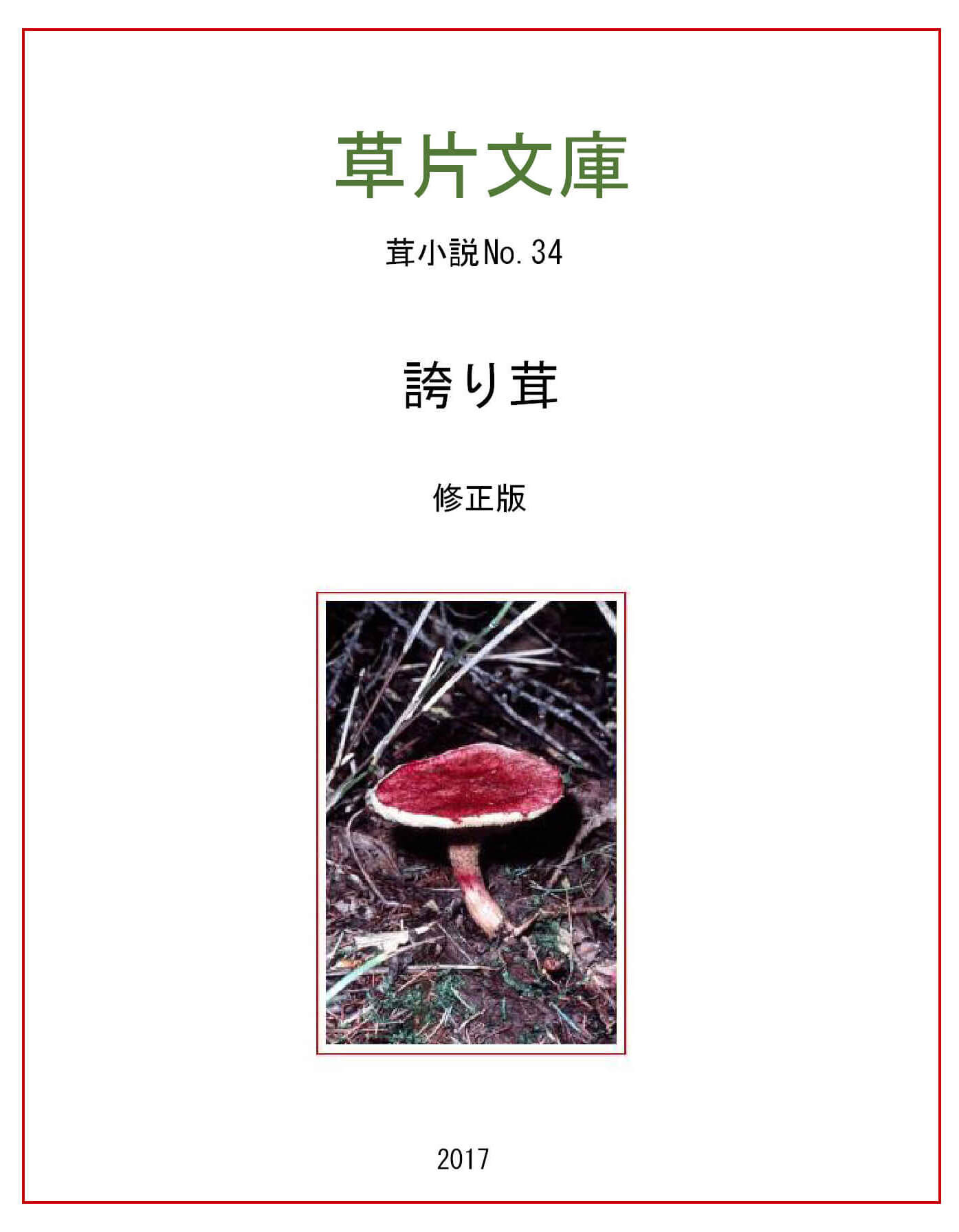
幻茸城8-誇り茸
鼠と茸のファンタジー 連載中です
城の天守閣の屋根裏に住む赤鼠の姫様が巣から起きてきた。大黒鼠の爺やがやってきた。
「おお、姫様お目覚めですな、今日は、良い天気でござますぞ、久しく行っていない、お池に行きましょうかな」
「爺、今日はよい、もう、お池などと言わぬでいいぞ、池でいい」
「そうですかな、では何をいたしましょうかな」
「爺、今日は外には出ぬ」
「はあ」
「爺は大黒様の所で何をやっていたのですか」
「闇の大王が何か言いましたかな」
「いや、何も聞いてはいないが、大黒様のところにいたと申されていた」
「爺は大黒様の元で、お使いをしておりました」
「なんのお使いをしていたの」
「大黒様の言伝(ことづて)を、人間に届けておったのです」
「どんな言伝であったのです」
「どこそこを掘ると、小判が出てくるとか、そのようなことを、大黒様がおっしゃった人間に伝えておったのです」
「どうしてそんなことをしたの」
「大黒様は、良いことをした人間にいろいろと振る舞われたのですよ」
「ふーん」
「その頃、爺はまだ若く、この白い毛も、もっと白くあったのですがな」
「爺は鼠なのに、なぜ白いのであろうなあ」
「本当は黒鼠にございますが、天のいたずらか、真っ白に生まれてしまったのでございます」
「爺が子どもの頃はどうであった。私のように我ままでしたか」
「いや、姫様は我ままではありませぬぞ、聞き分けのよい姫様じゃ、爺の若い頃は弱虫でな、真っ白だったせいもあって、仲間に何かと苛められましたな、色が白いと、人間にも見つかりやすいこともありましてな、人のいないところで、遊んでおりました」
「どのようなところで遊んだのです」
「人のこない藪の中や、洞窟や、山の頂上や、そののようなところで、いろいろな生き物たちと会いましたな。そこでだんだんと分かってきたことは、人より動物のほうが怖いということですな。人は害を与えさえしなければ、放っておいてくれますのじゃ」
「なぜですか」
「人は忙しい、自分に関係のないことはかまわぬのです、それに、鼠は機敏で人には捕まえることができません、しかし、人が鼠の天敵を連れてきますと怖いことになります」
「鼠の天敵とはなんじゃ」
「鼠を食べたい奴らはたくさんおりますが、なにしろ鼠は旨いそうですからな、腹の空いた猫や梟は容赦なく襲ってきますからな」
「猫や梟は城の中にはいませんね」
「この城は人がおりませんからな、人は鼠を食わせるために猫を飼います。姫様はまだ猫を知りませんな」
「はい、見てみたい」
「猫と梟の仲間たちは、夜でも目が見え、鼠と同じで機敏なのですじゃ。爺は大きくなってからは人の住む家の天井裏や縁の下におりました」
「それで、なぜ、大黒様のところにいったのじゃ」
「そのころは大黒様が直接、人間のところに行って、いろいろな物を授けておったのですじゃ。良いことをした人の寝ている枕元に宝の隠してある地図をおいたりしておられました。
姫様のいる鬼火城は、そのむかし月城と呼ばれておりましてな、月が天に昇ると、遠くからでもきれいに輝いて見える城だったのですぞ。
城主は住民たちに慕われていたとても良いお殿様で、大黒様はたくさん実のなる稲の穂をお与えになったのじゃ。
城の廊下に落ちている稲穂を拾ったお殿様は、家来衆に城内の田圃にそれを撒くように言いましてな。それが育ったとき、あまりの穂の多さに驚いたのです。その種を農民たちに分け与え、この村はますます裕福になりました」
「それで、爺はどうして大黒様につかえたのじゃ」
「爺はそのとき大変腹が減っていたのですが、廊下においてあった稲穂を食べるようなことをしなかったのです、それに気がついた大黒様が私を館におつれになり、おいしい米を鱈腹食べさせてくださいました、それから、大黒様のお使いを務めるようになったのですじゃ」
「だが、この城に今は誰も住んでいない」
「はい、姫様、それは大昔の話し、この城はそれから多くの戦に巻き込まれ、何人もの城主が入れ替わり、長い長い物語があるのです」
「爺、この城の中をあないしてはくれまいか、いつも外に遊びに行くので、城の中をよく見ていない」
「おお、そうですな、姫様が興味を持たれたときが一番、城の中を歩いてみましょうな、この天守閣は五階建てですので、我々の住処はその上の六階ということになりますな」
「外に出るには階段の脇を駆け下りるので、部屋の中に入ることはなかったが、すぐ下の部屋だけは、遊びに行ったことがあります。広い広いところで、何もなかった」
「ほかの所も同じですぞ、塵がたまっているだけで」
「でも見てみたい」
「それじゃあ、姫、行きますかな」
赤鼠の姫と白鼠の爺は天守閣の天井の隅にある穴から下に降りた。
板の間には埃が高く積もっている。
朽ちた行灯が倒れてこぼれた油もすでに乾きただの染みになっていた。
赤鼠が板の間の埃の中を歩いて行くと、大きな蜘蛛が現れた。
爺が蜘蛛に「赤鼠の姫様だ、そそうのないように」と言うと、
巣を作らない大きな蜘蛛は、
「爺さん、あんたはよく見るが、この娘は初めてだな」
と、赤鼠を見た。
「来たことはあります」
「そうか、ここはわしが取り仕切っておる。何かあったら声をかけるように」
巣を張らない大きな蜘蛛はするすると壁を上って天井の脇にぺたっと張り付いた。
「あい、よろしくお願いします。女郎蜘蛛の姉さんと、鬼蜘蛛の兄さんと、今度一緒に参ります」
「おお、あの夫婦を知ってるのか、わしも、よう知っとる」
「いろいろなところに連れて行ってくれます」
「そうか、そりゃ楽しかろう、あの夫婦は顔が広いからな」
「あい」
「この蜘蛛は足高蜘蛛といって、こんなに図体が大きいのに、すばしっこくって、誰よりも足の速い蜘蛛ですぞ」
爺が言った。
「頼もしいのですねえ」
「ああ、この中にいる限りはわしが皆を守る」
「よろしゅうお願いします」
赤鼠と爺はもう一つ下の階に下りた。
埃のたまったその部屋では、二匹が歩くたびに、赤鼠と白鼠の足跡がぽつぽつとついていく。
床には曲がった刀や、血が茶色にこびりついた布がビリビリに裂けて、転がっていた。
「姫、ここは、月城に最後に住んでいた殿様が切腹され、幼い子どもたちも道連れにされた場所にございます」
「どうして、そんなによい殿様が切腹しなければならないのですか」
「だまされたのです」
「こ城の主は、自分たちの命をささげて、村人たちを助けようとしました」
「何が起きたのです」
「この城を攻めてきた敵はとても強く、城を守りきれませんでした。城を空け渡せば村人の命は助けると、敵の大将が言ったのです」
「それで、ここのお殿様は、家族も一緒に死んだのですね」
「はい」
「それで、村人たちは助かったのですね、それはすごい、私にできるかどうかわかりません」
「姫様、よくお聞きください、結局、村人たちも一人残らず殺されてしまいました」
「それでは、その殿様の死は無駄になってしまったのですね、かわいそう」
「そうなのです、もし、姫が殿様だったらどうしますかな」
「分かりません、その時は、どうしたでしょう」
赤鼠の姫にはまだ、難しい問題だった。
「爺にも難しいことです、みなの頭になると難しいことを決めなければなりません」
「それで、この城は敵のものになってしまったのですね」
「そうですじゃ、しかし、そのような無分別な者達がそのまま生き延びることができるわけがありません」
「どうしたのです」
「遠くにすむ、もっと強い武将が、この城を取って有頂天になっていた荒くれたちを、攻めて、一晩にして根こそぎ殺してしまいました」
「だけど、この城には誰も住んでいません」
「村人たちも死に絶えていることから、その武将はこの城を捨てたのです」
「この城の部屋には、血が至る所にこびりついていたのですが、動物達、虫達、風が、少しづつ、きれいにしてここまでにしたのです」
「この部屋にはお殿様と、奥方様、子供達の遺体があったのですか」
「はい」
「でも、いまはありませんね」
「はい、下の部屋には、武者達の死骸が折り重なっていました」
「だれが片付けたのですか」
「はい、人の死体に生えて骨にしてしまう茸でした。葬り茸と呼ばれています。
「その茸は人の死体につくのですか」
「はい、戦で死んだ人につくのです」
「そして、部屋にはたくさんのが骨が転がっていました、そのころ、姫のお父上がこの城に赤鼠を連れて入ってきたのです、片腕だった鬼火が骨を灰にしました」
「そうだったのですか、そして、わたしが生まれてすぐに病がはやり、父上母上をはじめ、みな死んでしまったのですね」
「赤鼠に悪い病でしてな、闇の大王に頼まれ、お父上たちを助けるよう、爺たちがここにきたのですじゃ、爺にとっても懐かしい城でございました」
「この灰の中には人々の灰も混じっているのですね、いつか弔わねば」
「この城がこれからどのようになるかわかりませんのじゃ。どこぞの大将がこのあたりに町を造ろうと思うかもしれませんしな、その時、この城はまた動き出しますのじゃ」
「でも、こんなに荒れた城に誰が入りますか」
「この城は、元は大変にしっかりと造られた有名な城、きっと誰かが利用するでしょうな、その時のことを我々は考えておかなければなりません」
「そうじゃな」
姫達は下の階に降りていった。どこも同じようであった。
赤鼠の姫は庭に出て天守閣を見上げた。
「我々はずいぶん高い所に住んでいるのですね」
「はい、姫様」
そこに、鬼蜘蛛と女郎蜘蛛が来た。
「お姫さんたち、何してるんです」
「お城の中を爺に見せてもらいました」
「ちょっと、怖い話を入り口の松の木から聞かされましてね」
女郎蜘蛛の話を鬼蜘蛛が引きついだ。
「あっしが、松の木に巣をかけて獲物を待っていると、松のやつが言ったんでさ、林の中の木が噂してたことだそうで、隣の国の殿様が、鬼火城をその殿様のお姫さんのために綺麗にするという話ですぜ」
「なんじゃと、あの乱暴な殿様か」爺が身を乗り出した。
「爺さんは知ってるのかい、強い力のある武将で、乱暴だがけっして村人には悪くないそうだよ、だけど我ままで、周りの国に攻め入って、乱暴を働いているようだ。だから周りの国はいつも戦の準備をしているということだ」
「知っておる、それでどうしてこの城をそのお姫様の住まいにするのじゃ」
「なんでも、この地はあまり重要ではなく、安心なので、ここで姫様を育てるということだ」
「となると、大勢の侍がここに住むことになるのであろうな」
「うん、そうなる、それに、村人も増える」
「だが、その侍達がどのように振る舞うかが気になるところだ」
「そうだな」
赤鼠の姫様が言った。
「まず、私たちが見つからないようにしましょう」
「さすが、姫様、その通りで、昼間に遊びに出るのは難しくなりますぞ」
「夜の方が面白そうじゃ」
「強い姫様になってきた、末頼もしいや」
「それじゃ、今日、真夜中にまた散歩に行きましょう」
「あい、迎えに来てください」
「爺も一緒に行きますぞ」
「侍たちが入ってくるのだから、爺はその準備をしてくだされ」
「はは、姫様は本当に賢い、爺もじゃまになってきましたな、天守閣の屋根裏をみつからないように工夫しますでな、鬼蜘蛛と女郎蜘蛛よ、無理するでないぞ、頼んだぞ」
「あいよ、爺さん、美味しいお酒は用意しとくよ」
「それじゃ、姉さん、兄さん、夜にはよろしくお願いします」
「面白いところに行きましょうね」
蜘蛛たちは松の木に登って行った。
夜も更け、かなり遅くなってからである、鬼蜘蛛が天井裏の窓に顔を出した。
近頃、赤鼠の姫は夜になってもなかなか眠りにつけなくなっていた。爺は大人になってきた証と言っていたが、姫は今日もまだ部屋の隅で蜘蛛たちが来るのを首を長くして待っていたのである。
「お姫様、迎えに来たよ、今日は、蜻蜒や蝙蝠は来ないから、夜中の庭を歩いて、行くことにするよ、夜歩くのも面白いよ」
「あい」
窓から蜘蛛の糸の梯子が下まで垂れ下がっていた。
「この梯子を伝わって、下に降りることができるかね、姫様」
赤鼠の姫様は下のほうを見た。お城のお庭の植木が小さく見える、目がくらくらとする。
「怖い」
「ああ、姫様正直だ。今に慣れますよ。今日は綱でおろしてあげましょうや。鬼蜘蛛は尻からするすると糸を出すと後ろ足でたぐっていき、袋を作った。
「さあ、お嬢さん、袋の中にどうぞ」
「あい」
姫が袋に入ると、鬼蜘蛛は糸をあやつり、ゆるゆると、天守閣から地面におろした。
「赤鼠の姫様ご到着」
下で待っていた女郎蜘蛛が声をあげた。
「あい、着きましたか」
赤鼠は袋から顔を出した。そこへ、鬼蜘蛛は、糸を伝ってするすると降りてきた。
その身軽さに「すごーい」と姫様は見上げるとため息をついた。
「さー、いこう」
「どこへ行くのですか」
姫様が聞くと、鬼蜘蛛は、
「地蔵に会いに行く」と言った。
「地蔵さんは、道のいろいろなところにあります」
女郎蜘蛛が説明する。
姫様は道の角にある地蔵を思い出した。
「お城から出てすぐのところにあるお地蔵さんですか」
「そうだねーあれも地蔵だが、本物に会いに行こうね」
「どこにいるの」
「土の中と言っておこうかね」
「じゃあ、閻魔様と同じ」
「違うのさ」
「土の中じゃないの」
「閻魔様も本当は土の中じゃないのさ、世の中、いろいろな世界があるのさ、お城の中も二階、三階とあるじゃないか、閻魔様のいる世界、闇の大王のいる世界、菩薩のいる世界、我々の世界それはお城の部屋のように同時にある世界なのだよ。でもみんな繋がっていてね、出入りができるってわけだ」
「世の中はお城の部屋のようになっているのね」
赤鼠のお嬢さんは驚いた。しかし、まだよくはわかってはいない。
「どこで繋がっているの」
「地獄には地獄の入り口があったでしょ、地蔵のいる世界はその入り口があるのさ」
「地蔵の入口はどこにあるの」
「さー、これから行って見なきゃわかんないね、入り口がいつも変わっちまうんだ」
「どうやって探すの」
「あっちらの仲間が案内してくれると言っていたので、そいつらに乗っていくんでさ」
鬼蜘蛛の言う仲間って誰だろうと、赤鼠の姫が考えていると、女郎蜘蛛が、
「座頭虫さね」と言った
「あ、知ってる、庭で小さな茸を背中に乗っけていたことがある、あんなに細い足で私たちを乗せることができるのかしら」
「そいつがね、とてつもなく大きいな座頭虫がいるんでさあ」
「座頭虫の妖怪かしら」
そう言っているところに、真っ白な猫ほどもある座頭虫が三匹歩いて来た。
「よー、ここだ」
「おー、鬼蜘蛛の兄いか、女郎蜘蛛の姉さんも」
「ほら、赤鼠のお姫さんだ」
「あー、かわいい姫様じゃないか、ほら、背中にお乗んなさい」
白座頭虫の大将が足を折ってからだを低くした。
「うれしいな」
赤鼠のお姫様は喜んだ。
「どうしてだい」
白座頭虫が胴体を持ち上げながら聞いた。
「ちいちゃいとき、お庭でかわいい茸を二つ乗せた座頭虫さんを見たことがあるの、いいなーって、乗ってみたいなーと思ってたの」
「そりゃあ、庭にいる赤座頭虫じゃないか」
「そう、赤かった」
「あいつは、子煩悩で、ちっちゃなものが大好きなんだ、いいやつらだよ」
女郎蜘蛛も鬼蜘蛛も白座頭虫に乗った。
「さて、でかけよう、」
白座頭虫は暗い城の庭を大股でゆるりゆるりと歩く。
足が長いから、あっという間に池の脇に来て、塀から外に出ると、石垣を器用に下に降りていった。
降りたところは野原だ。ときどき、青い光がぼーっと燃える。
「あれはな、燐の燃える光だ」
「あい、一度見たことがあります、おどろの庭で」
「姫様は物覚えがいいや、その通り、野原のいろいろなところで死んだ動物たちが埋まっているんだよ、人も埋まっているかもしれない、その死体から燐が出るのさ」
草が多い繁った中を歩いて行くと道に出た。大昔、侍たちが戦のために歩いた道である。
三匹の白座頭虫はゆっくり歩いて行く。
空には星が無数に瞬いている。座頭虫の背中から、いきなり赤鼠の姫が座頭虫に尋ねた。
「どれが目」
座頭虫は立ち止まると長い足の一本を折り曲げて自分の目の所を示した。三匹ともそうした。
「その点が目なの、かわいい」
赤鼠のお嬢さんは微笑んだ。
「かわいいとさ」と、
笑いながら白座頭虫は再び歩き出した。
鬼蜘蛛の兄さんが言った。
「座頭っていやあ、目の見えない者のことだが、白座頭虫の旦那たちは、その小さな目で、真っ暗闇でも、何でも見えちまうんだ」
「すごい」
しばらく歩いて行くと、道の角に小さな社があり、中にお地蔵さんが立っている。
「古い地蔵だ、このあたりで、地蔵の世界の入り口を作ってもらおう」
「入口を作ってもらうの」
「そうだよ、地蔵口を開けてもらうのさ」
「誰に」
「地蔵狸さ」
「狸が門番なの」
「ただの狸じゃなくてね、入口の鍵を持っている妖怪狸さ、地蔵狸というんだ、いつもは草の中で寝ころんで、昼でも夜でも空を見ている、流れる雲が好きなんだ」
「雲の形からお話作りを楽しんでいるんだ」
白座頭虫は六本の足を集めて一本にすると、しゅーっと伸ばした。赤鼠の姫様のからだがすーっと上に上がった。
「あ、こんなに高くなる」
姫様は上のほうから周りを見渡した。
「ほら、向こうの草の中をごらん」
星の光に照らされて、丈の高い草原の中に、丘が飛び出している。
「あ、動いている」
茶色の丘が膨らんだり縮んだりしている。
「あれは地蔵狸の腹さ」
「どこにでもいるの」
「地蔵のあるところなら、どこかで空を見ているはずさ」
「あの狸さんに地蔵の入口を作ってもらうのね」
「機嫌が良ければすぐに作ってくれるし、悪いと一日待たなければならない」
大きな丘がむっくりと起き上がった。
山のような大きな狸が立ち上がった。まるでお城だ。
座頭虫の上から赤鼠の姫様が見上げるほどだ。
大きな狸が首をこちらに回すと、座頭虫たちを見た。
「来たね」
狸はにこにこして姫様の上に顔を出した。
「赤鼠の姫様、これから鍵を開けるからね」
機嫌はいいようだ。首にかけていた鍵をはずすと、草原の上に小さな扉が現れた。
地蔵狸は鍵を差し込んだ。
かちゃ、という音とともに、戸が開くと、穴からふーっと冷たい空気が赤鼠の姫様たちの頭上に流れてきた。
「さあ、どうぞ」
「来るのが分かってたのかね」
鬼蜘蛛が地蔵狸に尋ねた。
「すぐ分かったさ、昼間、雲の形を見ていると、誰が来て、誰が地蔵さんのところに行くか、よくわかる」
「ふーん、それで、赤鼠のお嬢さんが見えたのかい」
「ああ、雲の形が座頭虫になり、その上に当たったお日様の光が赤鼠の顔になった」
「雲から未来が分かっちまうとはすごいこった」
「地蔵狸さん、ありがとうございます」赤鼠が挨拶した。
「ともかく、中にお入りよ」
ぽっかりとあいた穴はかなり高いところにある。しかも小さい。
「小さな穴だけど、入れるかしら」
赤鼠の姫様は心配になった。
「まかしとけ」、白座頭虫たちは、足を縮めて背を低くすると、
「赤鼠の姫さん、蜘蛛の旦那達も、一端降りてくれないか」と言った。
赤鼠の姫たちが草原に降りると、白座頭虫たちの一本の足が赤鼠と蜘蛛をつかまえた。白座頭虫は五本足を伸びして背を高くすると、皆をつかまえている足を穴の入口近くに伸ばし、シューっと赤鼠を放り投げた。みごとに赤鼠は穴の中に入った。
「蜘蛛たちもおいき」
女郎蜘蛛と鬼蜘蛛も放り投げられた。穴の中に入った。
「白座頭は目がいいね、うまいもんだ」女郎蜘蛛が鬼蜘蛛に言った。
赤鼠が穴から顔をだした。
「城座頭のお兄さんたち、お上手、ありがとう」
「俺たちは、外で待っているよ、地蔵狸が退屈なんだとよ、一緒に遊ぶさ」
穴の奥は真っ暗で何も見えない。
「どうやっていけば地蔵さんに会えるの」
赤鼠の姫が地蔵狸に聞いた。
「そこに地蔵さんの使いはいないのかい、また地蔵茸を探しに行ってるな」
「なあに、それ」
「地蔵の世界に生える茸さ、まあ、地蔵の世界の土の中に生える茸といったところさ、それが、旨いのだ、熟したやつは酒になってる」
女郎蜘蛛が鬼蜘蛛を見た。
「お前さん、吸いたいだろう」
「うん、旨そうだ」
「なかなかな、他にはない味なんだよ、たまにもらって食べるけど、酒になっているので一日寝てしまうんだ」
地蔵狸は舌なめずりをしている。
そこへ穴の奥から地蔵の使いがあわてて走ってきた。
「待ったか、すまぬな、なかなか茸が見つからぬ」
地蔵の使いは角を生やした真っ赤な鬼だった。
「あ、鬼さん」
「ほんとだ、地獄じゃないのになぜ鬼がいるんだ」
「あたしゃ、鬼に会ってみたかったよ」
女郎蜘蛛の姉さんは憧れの鬼に始めて出会って、目を輝かせている。
赤鬼は笑いながら赤鼠と蜘蛛たちを見た。
「おれたちゃ、もともと、地蔵様に仕えておる、地獄にゃ鬼はいらないんだ」
「鬼さんは何をしてるの」
赤鼠の姫は鬼の角が可愛いと思っている。
「地蔵の世界に来たものどもを懲らしめるのだよ」
「地獄とどう違うの」
「地獄に行くのは死んだ人間、地蔵様の世界にくるのは死んだ動物たちだ。動物の本能を忘れたやつらは地蔵様の世界に来る、そこでその動物たちに本能について教えるのだ。それを懲らしめるという」
「地獄は見て来ました、でも、人だって動物でしょう、なぜ分かれているのかしら」
「おお、姫様は賢い、地獄で見てこられたであろう、地獄にいった人間は何もすることがない、それが人間への懲らしめだ。だが、動物は何もすることがないと喜んでしまう。動物を懲らしめるには他の方法が必要だ、地蔵の世界は地蔵獄とも言う」
「地蔵獄に来た動物たちは何をしなければならないのかしら」
「動物に悪いことを教えるのだよ」
「悪いことを教えるのは悪いことのような気がするけど」
「動物も人も悪いことを知らないで生まれてくる。大きくなっていくなかで悪いことを覚える。悪いことができないと動物は滅びてしまう」
「悪いこととはどんなことかしら」
「地蔵獄に行ってみなさい、そうすればわかる。悪いことができないと動物は死ぬ。それで死んだ動物たちは、この地蔵獄に来て、お地蔵様に悪いことを教わって、無の世界に行く。無の世界から新たな生命が作り出されるとき、動物は新しい生命として生まれ変わり、そのとき、悪いことを知った生き物になる」
「むずかしい」
「お地蔵様の話を聞くがいい」
赤鬼は三匹を引き連れて穴の奥に入っていった。
赤鬼が奥の扉を開けた。
「あとは一本道だ、景色を楽しみながら歩いていくといい。出口は向こうにいる鬼が教えてくれるだろう」
「ありがとうございます」
赤鼠の姫様は礼を言った。
地蔵獄に入ると、空には雲一つない青空がひろがり、遠くには雪がかむった山々の頂がくっきり見えた。
まっすぐに延びている道の脇は花畑で、果てしなく広がっている。咲き乱れている花はさまざまで、身近にある花もあるが、初めて見る花がかなり混じっている。
「きれいなお花」
「ほんとだね、これだけたくさんあると、きれいだね、ところが、よく見てごらんな、ほら、これは蒲公英(たんぽぽ)だよ、これは薊(あざみ)、これは罌(け)栗(し)、季節なんかありゃしない。みんないっぺんに咲いているんだね、それに、見たこともないようなものがあるね」
「きっとよその国の花ではないかしら、すべての世の中の花が集められているのね」
三匹がゆるゆると道を歩いて行くと、一匹の猫が後ろから追いついて来た。
赤鼠の姫は「きゃ、なに」と言って、鬼蜘蛛の後ろに隠れた。
「お嬢さん、心配いりやせん、おお、そうか、猫を始めて見なすったか。だが、この猫は地蔵獄にきた猫、というこたあ、もう死んだ奴でさあ」
茶虎の猫は髭を震わせて姫を見た。
「鼠と蜘蛛のみなさん、このままいけば、お地蔵さまに会えるのでしゅなあ」
「あっちらも、初めてだし、そう言われたから歩いているんだが、お前さん、どうしてここに来たんだい」
「おいらは腹が減って、腹が減って、死んじまったんだ、ここに来たら、腹が減った感じがしないのはとても幸せだな」
「そんなもんかね」
「どうして食わなかったんだい」
「だってよう、鼠を捕まえたら、その子供たちがめんこい目でおいらを見たじゃないか、だから、親鼠を放してやって、子供たちを尾っぽで遊ばせてやったのさ、それで、腹が減って、鶏が座っていたから、襲いかかったら、お腹の下から黄色いひよこが三匹ぴよぴよと出てきて、おいらを見るから、親鳥を放しちまった。もう腹が減って、そいで、人の家に入ってカツオブシを失敬したら、そこの子供に追いかけられて、カツオブシを落としたあげく、水をかけられて、びしょびしょになって、腹減って神社の境内で寝ていたら、風邪まで引いて動けなくなって死んだんだ」
「なんか情けないね、それで地蔵獄にきたのか、赤鼠の姫様、こいつは心配いりません」
「す、すいません」
鬼蜘蛛が道にはいつくばって謝った。
「最初はそこの猫、ここに来なさい」
「なぜ死んだ」
「腹が減って、風邪を引きました」
「なぜ、鼠を、鳥を喰わなかったのだ」
「かわいかったからです」
「そんな人間のようなことを言うでない、動物として間違っている。猫は鼠を食ってあたりまえ、鳥を食って当たり前なのだ」
「はい」
「心を入れ替えなさい」
「はい」
「つぎ、ほら、雀蜂、なぜここに来た」
雀蜂は三匹に話したことを菩薩に言った。
「はは、おまえは人間ではない。本能を忘れた人間は餓えて死のうとどうしようと悪いことではないが、動物が本能に従って生きないのは悪だ。だからここにきたのだぞ。鬼たちにしごかれ、心を入れ替えるのだ。人でいう心と、動物でいう心は違うものじゃ、動物は人の心を持ってはいかんのだ」
「はい」
雀蜂は素直に返事をした。
「さて、そこの三匹、おまえたちは、死んでここに来たのではない、私に会いたくて来たのでろう」
「はい、お地蔵さまが大好きでしたから、お地蔵様の世界を見てみたいと思っておりました」
赤鼠の姫様が答えた。
「誰でも入れるわけではない、誰に連れて来てもらったのじゃ」
「白座頭虫でございます」
「あやつらは動物ではない、妖怪のなかまじゃ、座頭虫が百年生きると白座頭虫になる」
「おまえたちの周りには、あやかしの仲間がいるようじゃ」
「あやかしの仲間とはどのようなものでございましょう」
「おまえを育てているのは誰じゃ」
「大黒鼠の爺でございます」
「大黒のところにいた白鼠か」
「はい」
「そうか、あやつは、五百年生きている白鼠じゃ、もう妖怪の域に達しておる。おまえもいずれは、そうなるのであろう。地蔵獄の中をよく見て学んでいきなさい、そこの蜘蛛たちもな」
「でも、なぜ爺は妖怪ではないのでしょうか。百年生きれば妖怪になると聞いております」赤鼠の姫様が質した。
「虫は百年、獣は八百年で妖怪じゃ」
菩薩さんは、そう言うと奥に入ろうとした。そのとき振り返って、
「地蔵獄の茸を与える。誇り茸じゃ、青鬼、たのんだぞ」と言った。
青鬼は「はいかしこまりました」と一礼した。
「ありがとうございます」
赤鼠の姫は何に効く茸か聞こうと思ったときにはすでに奥に入ってしまった。
「さて、ご一同、大切なお客として地蔵獄を案内しまする」
「青鬼さんよ、いってえ、どうしておいらたちは客になったんで」
「菩薩様のお考えだ、地蔵獄の茸を与えられる者は大事なお客様だ、俺が知っている限り、八百年前にこの菩薩獄にきた大山椒魚だけだ、今、闇の大王になっている」
「会いました。鬼蜻蜒がつれていってくれました」
「そうか、あの山椒魚がいないと、闇夜は魑魅魍魎の世界になってしまうのだ」
「大変な力をお持ちなのですね」
「そうだ、さて、案内しよう」
青鬼が地蔵獄の真ん中に一本ある道を歩き出した。
しばらく歩くと、道沿いの罌栗の花の咲く畑で青鬼が立ち止まった。
罌粟の花の中では、真っ白い背の高い鬼が、花の中をのぞき込んで何か言っている。
赤鼠と蜘蛛たちがそばによると、一緒に入った雀蜂が罌粟の花の中にいる毛虫を捕まえようとして、躊躇している。
毛虫がつぶらな目から涙を流して助けてくれと言っている。
「ほら、雀蜂、喰え」
白鬼が指図をした。
雀蜂は毛虫に噛み付いた。
「きゃあああ」
毛虫が悲鳴を上げると、雀蜂は毛虫を罌粟の花の中に落としてしまった。
白鬼は毛虫を抓(つま)むとつぶしてしまった。
「おまえが食べないなら、わしがつぶして殺す」
雀蜂の母親はうなだれた。
「わしにつぶされた毛虫はただの無になった、もしおまえが食べれば、おまえの中で生き続けることができる」
白鬼はとくとくと、菩薩の教えを雀蜂に言うのであった。
「いつも私たちがやってることじゃないか」
女郎蜘蛛は首を傾げた。
「それができない動物がいるのだ、そいつらが地蔵獄に来て、根性をたたき直される。動物は食べて、生きて、相手を倒して、子供を作って、一生を終えるのだ。そこに悪はない、生き物の本能は悪ではない」
「はい、よくわかります」赤鼠の姫は頷いた。
今度は、稲が生えている田圃があった。そこに猫がいた。
そこでも白鬼が猫に言っていた。
「稲の中にいる畑鼠をとって喰え」
猫はなかなかとろうとしなかったが、やっと一匹捕まえると頭からボリボリ食べた。
「そうだ、それでいい、旨いだろう」
猫は頷いた。
「だんだんなれるだろう、猫は鼠を喰うんだよ」
猫は赤鼠を見て涎を垂らした。
「猫、お嬢さんをそんな目で見るのではない、喰っていいのとだめなのがある」
女郎蜘蛛が注意した。猫はすぐにうなだれた。
「うん、ごめん」
「喰えただけでもいい、次は女郎蜘蛛の言ったように大人になるのだ」
青鬼は笑いながらが言った。
「しかたないわね」
赤鼠のお嬢さんは猫を見た。
猫は下を向いたままだった。
「まだ、だめみたい」
赤鼠の姫が笑った。
「やさしい猫さん」
青鬼は歩きだした。道はどこまでも続いている。
いつまで歩くのかわからないが、花畑の所々で、いろいろな動物が白い鬼にしかられながら、動物として生きることを教えてもらっている。
青鬼は池の畔にきた。
「この池は底なし池だ」
三匹がのぞくと、ザリガニ(ざりがに)が蛙を挟むところだった。
白鬼が「ほらいまだ」と声をかけているが、なかなか上手くいかない。
白鬼はザリガニを「なにやってる」としかった。
ザリガニは御(お)玉(たま)杓子(じゃくし)を捕まえた。
「よし、喰っちまえ」
白鬼が声をかけると、ザリガニは御玉杓子を口に持ってきた。ところが、御玉杓子が目から涙を流すと、離してしまった。
「ねえ、青鬼さん、もし地蔵獄で直らなかったら、どうなるの」
「いつまでもここにいるのさ、地獄だからね」
「でも、優しい動物って、新しい動物になったためじゃないかしら」
「ほー、難しいことが分かる鼠だな」
「無理に直すことないんじゃないのかしら、人間に生まれ変わればいいのよ」
「それは、正しいな、賢い姫さまだな」
と、突然、池の中から菩薩さんが、ぼちゃっと、顔を出した。
「聞いておった、その通りじゃ、たしかに賢い、この地蔵獄の本当の役割は、動物として出直すことのできない動物を選んで、新たな動物として生まれ変わる世界に送るのも一つの役割なのだ、人間が滅びたあとに、人の代わりになる動物を育てるためにな、そなたは、頼もしい、あやかしの頭領に相応しい、赤姫になり動物をまとめよ」
菩薩が水面に浮かぶと、出てきた穴が水の中の石の隋道となった。
「この隧道の途中に誇り茸が生えておる、採るがよい、明日の朝に食べなさい、それはそなたの体に底知れぬ力を付けるであろう。生き物としての力と誇りがわき出るのだ、自分ではそれを感じることはないであろうが、必要なときにその力が発揮されるであろう」
「ありがとうございます」
赤鼠はお礼を言った。
菩薩は鬼蜘蛛と女郎蜘蛛の方を向いた。
「そちたちには支え茸を与える、隧道の途中に生えておる白い茸を採っていきなさい、姫をはじめ動物たちの大きな支えになるであろう、その茸の養分を吸いなさい」
「へい、ありがとうございます」
「また会おうぞ」
菩薩は音も立てずに水の中に沈んで消えていった。
青鬼は先に立って隧道の中に入った。
「ありがたいお言葉をいただいたね、ついておいで、隧道を通って帰ることにしよう、出口まで送るから」
「ありがとう、青鬼さん、お聞きしたいことが一つあるの」
「なんだい」
「気の弱い動物に食べられていた虫や蛙たちはどうなるの」
「あれは幻覚だ、菩薩様が作り出している、本物ではない」
赤鼠の姫と蜘蛛たちは大きく頷いて納得した。
石でできている隋道の中は薄明かりが射している。
しばらくいくと、石壁から真っ赤な茸が生えていた。
「あれが、誇り茸だ、採っていきなさい」
赤鼠の姫は青鬼に言われて赤い茸を採ると大事に抱えた。
それからしばらくいくと、白い茸が二つ生えていた。
「ほら、支え茸だ」
二匹の蜘蛛は白い茸を抱えた。
だいぶ歩くと、出口が見えてきた。青鬼が扉の鍵を開けた。
星の光が射し込んできた。
「お世話になりました、青鬼さん」
「それでは元気でな、またおいで」
と三匹が外に出ると、青鬼が扉を閉めた。
外では赤鬼が待っていた。
「帰ってきたな、地蔵獄はどうであった」
「動物だけでなく、この世ににとって大切なところだということが分かりました」
「そうであろう、ほら、これが菩薩茸だ、二つ採っておいた、一つはみやげ、一つは地蔵狸にな、旨い酒の茸だよ」
「ありがとう、爺が喜びます」
空に浮かんだ地蔵極の穴から、三匹は白座頭虫の上に飛び降りた。
「さようなら、赤鬼さん」
「またおいで」
と赤鬼が手を振った。
地蔵狸が空中の入口に鍵を掛けると、穴はすーっと消えた。
「ありがとう、地蔵狸さん、これ菩薩茸、赤鬼さんから」
「お、嬉しいね、赤鬼はいいやつだ、それじゃ、またな」と地蔵狸も草原の中に消えていった。
三匹は白座頭虫に乗って、城に帰った。
白座頭虫から降りた赤鼠は細いが頑丈な座頭虫の足を撫でた。
「白座頭虫さん、ありがとう、またお世話になると思います、そのときはよろしくお願いします」
「赤鼠の姫さん、ますます賢くなったね、何かあったら言ってくれよな、助けにくるから」
と白座頭虫は帰っていった。
蜘蛛たちと分かれて天守閣の屋根裏に戻った姫は茸を爺に手渡した。
「爺、菩薩茸をいただいたのよ、お酒の茸だから爺にあげる」
「おー、ご無事で、これすばらしい土産を、ありがたきしあわせ」
「地蔵様は菩薩様でした。その菩薩様が、爺に菩薩茸をくださいました。私には、この誇り茸をくださいました」
赤鼠の姫様は赤い茸を爺に見せた。
「なんと、誇り茸を、その茸は闇の大王の大赤山椒魚以外、誰もいただいておりませんぞ、菩薩様も姫様があやかしの頭領にふさわしいとお思いになったのでございましょう。この茸は明日の朝食に用意させまする」
「赤姫になりなさいと言われました」
「そうですな、大人になった暁には赤姫様じゃ、まだまだじゃ、もう寝てくだされ」
「はい、おやすみなさい」
赤鼠の姫は床に入った。もう夜が明けようとしている。大人の鼠が寝る時間になっていた。
「幻茸城」(第一茸小説)2016年発行(一粒書房)所収
(短編を一つの物語に編纂)
幻茸城8-誇り茸


