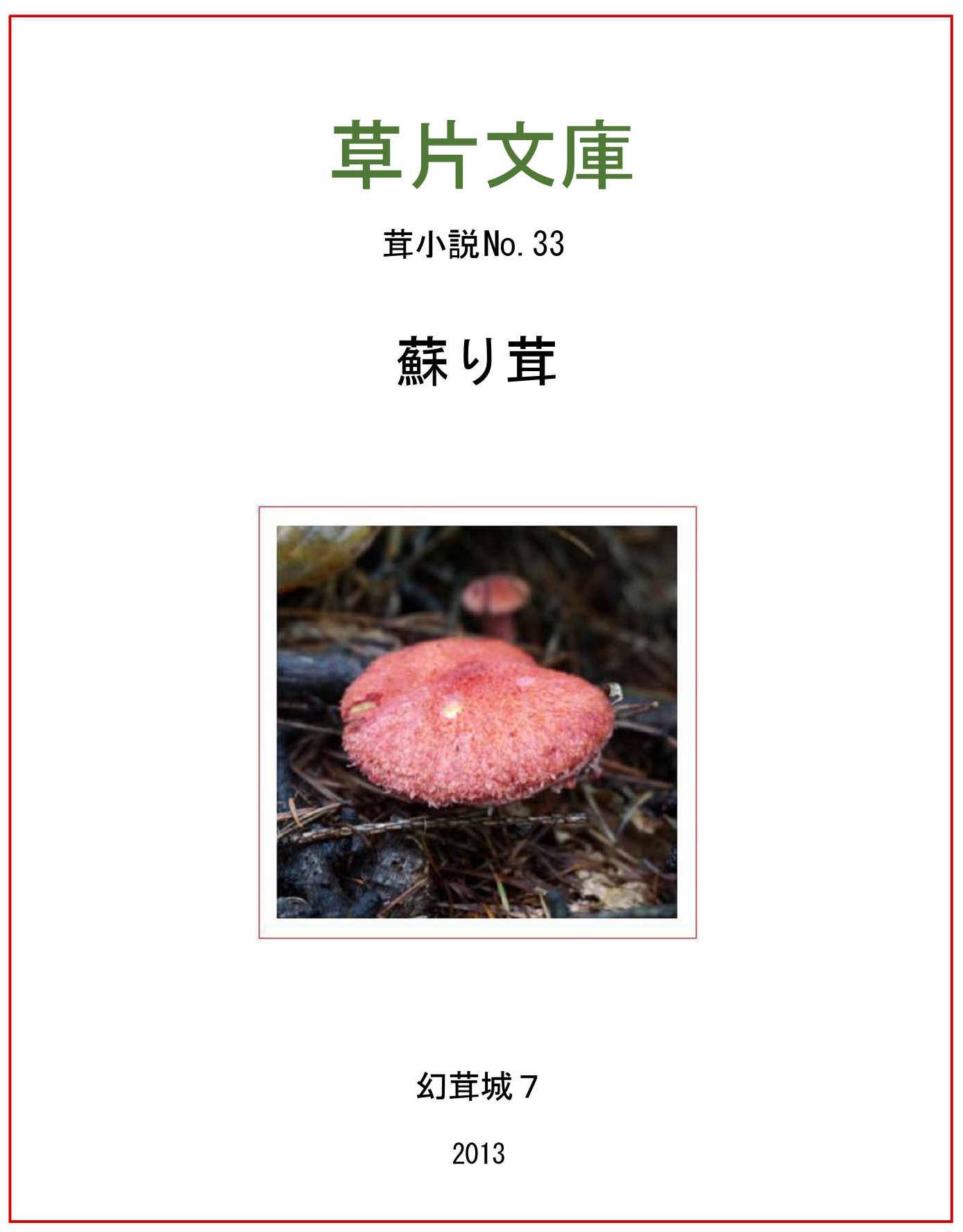
蘇り茸ー幻茸城7
城に住む赤鼠の姫がどこぞに遊びに行けないかと天守閣から外を見ている。
窓からひょいと女郎蜘蛛の姉さんが顔を出した。
「姫さん、どうです、今日は、東のはずれの山に行ってみませんかね」
「あい、嬉しい、爺に言ってきます」
「ああ、それがいいよ、女郎蜘蛛が迎えにきたと言っておくれな、それから、これを持っていってくださいな」
女郎蜘蛛は瓢箪に入った酒を姫に渡した。
「あい、爺も喜びます、最近は年を取ったせいか、昔のようにお池にお弁当持っていくこともしません」
「はは、あの爺さんは年取ってみえるが、妖怪に近い鼠さね」
「え、妖怪」
「いや、最近知ったのさ、赤大山椒魚が言ってたじゃないか、大黒さんのそばにいた偉い鼠だよ。妖怪ではないけどね、私らのことは前からわかっていたくせに、しらばっくれていたのさ」
「そうなの」
「それにね、すごいらしいよ」
「なにが」
「子だくさん、いろいろなところに、子供がいるのさ」
「それじゃ、奥さんもたくさんいるの」
「はは、そういうことになるね」
「それを渡して、地獄巡りをして来ると言っておやりな」
「あい」
赤鼠の姫は瓢箪をもって爺の部屋に行った。
まもなく姫が爺を連れて戻ってきた。
「女郎蜘蛛、酒はありがたく頂戴した。姫様をたのんだぞ」
いつもとは違った物の言い様に女郎蜘蛛は目を丸くした。
赤鼠の姫様もびっくり顔だ。
「はい、大黒鼠様」
「爺さんでいいよ」
「へ、お見通しで、爺さん」
「遠慮のない蜘蛛だ、お前さん、いくつになった」
「女子(おなご)に年を聞くなんて、野暮ですよ」
「なに言っとる」
「まだ、八十九歳で」
それを聞いて赤鼠の姫様はまたびっくり。
「まあ、姫様をたのんだよ」
「はいよ、爺さん、地獄巡りをしてくるよ」
「このあいだは闇の大王、今日は地獄の閻魔か」
「爺、夕刻までには戻ります」
「姫様、よく見ておいでなさい」
「あい」
「そうじゃ、姫様、もし、鬼火が必要になったら、鬼火よ来ておくれと念じてくだされ、そうすると、すぐ姫のもとにまいります」
「あい、聞いています、では行ってきます」
「危ないことはしないでくだされよ、姫様」
爺は頷きながら自分の部屋に戻って行った。
「あの爺さん、早く部屋で酒を飲みたいのさ」
女郎蜘蛛が陰口を叩くと、聞こえたと見えて、爺やの大きなくしゃみが聞こえた。
そこへ鬼蜻蜒(おにやんま)が飛んできた。
「久しぶりだな、お嬢さん」
「あ、鬼蜻蜒の兄さん」
赤鼠の姫は袋を首にくくりつけると鬼蜻蜒の上に乗った。
「その袋はなんだい、姫様」
女郎蜘蛛が不思議そうに袋を見た。
「井守の黒焼きの霊薬、それに醍醐」
「それは準備がいい、姫様もすこしゃ大人になったね」
「今日は、地獄に行くんだとな」
もう一匹の鬼蜻蜒が飛んできた。
「女郎蜘蛛の姉さんは、こっちだ」
「すまないねえ」
女郎蜘蛛も鬼蜻蜒の上に乗った。
二匹の鬼蜻蜒が飛び上がると、どこからともなくたくさんの鬼蜻蜒たちが現れ、二匹の後を飛び始めた。
「今日も豪勢だね、みんなおでましかい」
「ああ、あの連中も地獄巡りしてみたいとよ」
「鬼蜻蜒のみなさんも物好きだねえ」
「退屈してんのさ」
「そうだね、このあたりにゃ遊ぶ相手が少ないからね」
「鬼火城はもう朽ちるだけだろうかね」
「そりゃあ、わからないさ、人間の世界はね、このあたりに興味のある侍が、城に住み始めるかもしれないじゃないか」
「そうなりゃ、面しれえね、いろんなことが起きる」
「赤鼠の一族にゃあぶないけどね」
「さて、どの地獄に行くかね」
「どこでもいいが、任せていいかい」
「もちろんさあ、それなら北の果ての地獄だ」
鬼蜻蜒が急上昇した。青空高く高く舞いあがる。
山が下の方に見えるようになってきた。お城が小さくなる。
「鬼蜻蜒の兄い、ずいぶん高くあがるね」
「今日は遠出だ」
「どこにあるんだい」
「この国の北の果て、青森だ」
鬼蜻蜒はどんどん空の上にあがった。
「青森というとこはな、冬になると雪で覆われる。そこに、地獄がある。いろいろなところに地獄あるが、青森の地獄には閻魔が住む、でっかい地獄だ」
「青森というのはそんなに大きな森なのかい」
「森じゃあない、日本の北の果ての海に突き出た地のことだ、その海を渡ると北海道という大きな島だ、寒い島だ」
「冗談およしよ、遠いんだろ、何年もかかるんだろう」
「人間が歩いて何ヶ月もかかるところだ」
「そんなに遠くじゃ、行けっこないじゃないか」
「鬼蜻蜒の力をお見せしようじゃないか」
鬼蜻蜒の集団は、ぐんぐんと空の上に上っていった。
「すごい、お山があんなに小さく見える、お城がもう見えない」
赤鼠のお嬢さんが目を丸くする。
「さて、お二人さん、しっかりつかまっていてくれよ、目を瞑ったほうがよいかもしれんな」
鬼蜻蜒は急上昇すると、日本の北の果てまで吹いている、早い早い空気の流れにのった。
あまりの早さで、地上を見ても何も見えない。
「これはな、蜻蜒(やんま)気流と呼ばれていてな、俺たちしか知らない空気の流れなのだよ」
鬼蜻蜒の兄さんが説明してくれた。
「こりゃすごいやね、いい経験だねえ」
女郎蜘蛛の姉さんは、お尻から一本の糸を出した。
「うわー」姉さんは叫んで、鬼蜻蜒にかじりついた。
糸が気流に引っ張られ、姉さんが落ちそうになったのだ。
糸がぷつんと音をたてて切れて飛んでいった。
「おー助かった」
「女郎蜘蛛の姉さん、糸だしちゃ危ないよ」
「ああ、恐ろしかったよ、もうしないよ」
赤鼠のお嬢さんは目を瞑っている。
一時も経っただろうか、鬼蜻蜒たちは蜻蜒気流から外れると、ふんわりと宙に浮かんだ。
「すごかった」
女郎蜘蛛と赤鼠は周りを見た。
風が冷たい。
「もう、北の果てかい」
女郎蜘蛛が聞くと、鬼蜻蜒は頷いてゆっくり降下した。
遠くに煙の上がっている禿げた山が見えてきた。
「ほら、あれが地獄の山だ」
近づくと、黄色い岩肌のあちこちから蒸気が上がっている。
「すごい匂い」
「これはな、硫黄という物質の匂いなんだ」
鬼蜻蛉が説明をする。
「硫黄ってなあに」
「黄色い石の仲間でな、火山の奥のほうで作られるんだ」
「火山てなあに」
「火を吹く山のことだよ、火山の地下では土も石もみんな溶けて、真っ赤に焼けて燃えている、時々それが山のてっぺんから噴き出すのさ、そのときゃあ大変だ、空一面に真っ黒な煙が上がり、熱くなった石が降ってくるし、ひどい時には溶けた石がどろどろと流れ出るのさ」
「火山の地下が地獄なの」
「いや、それが地獄ではない」
「地獄はどこ」
「地獄の山に入口がある、その中だ、地獄は死んだ者が行くところ。我々は簡単には入れない。悪いことをして死ぬと地獄に落とされ、責められる」
「痛いの」
「頭の奥が苦しくなる」
「地獄には行きたくないわ」
「そうだねえ、でもあたしゃ地獄おちだよ、いろいろ悪いことをしているからね」
「でも、私にはいいことをしている、合わせると何も無くなって、地獄には行かなくていい」
「ありがとよ、お嬢さんはいいこというね、頭がいいね」
「ほんとだな、女郎蜘蛛の姉さんは、いずれこのお姫さまに助けられるぞ」
「そうだね」
そう言っているうちに、硫黄の匂いが強くなってきた。
「降りるぞ」
鬼蜻蜒の大将の合図で、一斉に鬼蜻蜒たちが地獄の岩の上に降り立った。
辺り一面、鬼蜻蜒だらけだ。
そこへ、どこからか一羽の鴉が飛んできた。あわてている。
「おい、この地獄の山に誰の許しを得て入ってきた」
「地獄の山にくるのに、許しがいるとは知りやせんでした」
鬼蜻蜒の大将が頭を下げた。
「すぐ立ち去れ」
「せっかく、遠くからきたので、ちょっくら見せてはいただけませんかねえ、あたしからもお願いしますよ」
女郎蜘蛛が鴉に声をかけた。
「蜘蛛など口出しするな」
女郎蜘蛛の姉さんはカチンときた。
「なんだい、えばって、いったい誰に許しをこえっていうのさ」
「閻魔鴉の親分さんに、貢ぎ物が必要だ」
「おーあからさまに、賄賂かい、地獄の頭領は閻魔だろう」
「我々閻魔鴉が入り口を守っている」
「馬鹿おいいでないよ、そんなことしてると、閻魔様にしかられるから」
「つべこべ言わずに、よこせ」
「なにが欲しいのさ」
「地獄茸を採ってこい」
「なんだいそれは」
「この地獄の山のどこかには、かならず地獄茸が生えている、それを採ってくれば地獄に入れてやる」
「ふーん、どうして自分たちで採らないのさね」
「我々閻魔鴉は捜しに捜した、だがいまだにみつからない」
「そのようなものをすぐに捜せるわけないではないか」」
「それがなければ入れてやることはできない」
「その茸は何の役に立つのさ」
「それを煮立てて死体に振りかければ生き返る」
「ふーん、怖い茸だね」
「それで、誰にかけるのさ」
閻魔鴉は、ちょっと言いよどんだ。
「閻魔鴉の親分のお嬢様にふりかける。いまご病気で、明日にも死ぬ、そうしたら、閻魔茸をふりかけて生き返らせる」
「そりゃ、可哀想だけど、こんな頼み方はないだろう」
閻魔鴉は横を向いて俯いた。
「ともかく、地獄茸を採ってくれれば、地獄巡りをさせてやる」
「もし、茸がなかったらどうするね」
「帰ってもらう」
「地獄をよく知っているあんたらが捜してないものが、来たばっかりの私らにみつけることができるわけはないだろう、赤鼠の姫さんをつれて、遠くはるばる来たのだから、入れておくれな」
女郎蜘蛛の姉さんがつめよった。
赤鼠の姫様がまえにでた。
「その茸を使わなくても元気にしてあげましょう」
「どういうことだ」
閻魔鴉の使いは赤鼠を見た。
「私が直してさしあげます」
女郎蜘蛛と鬼蜻蜒たちも驚いて姫様を見た。
「私にはその力があります」
赤鼠の姫の顔は自信に満ちていた。
「ほんとうか、その通りなら、もちろん、地獄の案内は任せてもらおう、閻魔鴉の親分も喜ばれる」
「それじゃあ、お嬢さんのところに案内してください」
「かしこまってござる」
うってかわった閻魔鴉の使いが翼を広げ、岩山に恭しくお辞儀をした。
そのとたん、硫黄がかぶって黄色くなっている大きな岩が動いた。
真っ黒な地獄の入り口がずーんと開いた。
入口の奥は、もっと黒い、真っ暗闇である。
こうして、閻魔鴉を先頭に、赤鼠の姫と女郎蜘蛛、それに鬼蜻蜒の集団は地獄の穴に入って行った。
閻魔鴉の目が赤く光り、洞窟を照らした。
洞窟の壁からごつごつと岩が飛び出している。その明かりが無いと岩にぶつかって怪我をする。
地獄の入り口から少し進むと脇道があり、奥の丸い岩の前に閻魔鴉が立っていた。そこが閻魔鴉の館のようだ。
案内をしてきた閻魔鴉は門番の閻魔鴉に事の次第を話した。
門番の閻魔鴉はうなずき、丸い石が半分にわれ、左右に開き、閻魔鴉の住まいの中が見渡せた。
広い部屋の中に閻魔鴉たちが集まり、奥の部屋を見つめている。
案内の閻魔鴉の後についていくと、奥の部屋の中に案内され、そこでは一羽の大きな閻魔鴉がうなだれて、寝台の脇にたたずんでいる。
寝台の上では、痩せた閻魔鴉が横たわり目を瞑っている。息をしているのかしているのかいないのか、まったく動かない。
赤鼠の姫たちが案内の閻魔鴉についていくと、大きな閻魔鴉が振り向いた。
「その者たちはなんじゃ」
「親分さん、お嬢さんを助けることができるという、赤鼠と女郎蜘蛛でございます、鬼蜻蜒たちがつれてきました」
「なに、娘を助けることができるというのか、地獄茸をとったのか」
「いえ、地獄茸はありません、病に効く薬をもっているということです」
「娘を助けてくれるとな」
「あい、お助けしましょう」
赤鼠の姫様が言った。
「ほんとうだな、もし、もし助けてくれたら、何でもする、頼む」
親分鴉が頭を下げた。周りで見ている閻魔鴉も頭を下げた。
赤鼠の姫さんが声をあげた。
「みなさんはお嬢さんの周りから離れてください」
赤鼠の姫の声がいつもと違い力がある。
閻魔鴉や鬼蜻蜒たちは壁際に寄った。
女郎蜘蛛が心配そうに「手伝うことはないのかい」と赤鼠に声をかけた。
「お願いしたいことがあります」
赤鼠の姫が女郎蜘蛛に手招きをして、声を上げた。
「鬼火、出ておいで」
姫の声で鬼火がふわっと宙に現れ、病気の鴉を照らし出した。
赤鼠の姫が閻魔鴉の娘に声をかけた。
その声で、横たわっていた痩せこけた鴉の娘の目がうっすらと開いた。
赤鼠の姫は皮袋を取り出し女郎蜘蛛に手渡した。
「この薬をお嬢さんに飲ませてくださいな」
地獄の闇の大王、赤大山椒にもらった、七色井守の黒焼き霊薬だ。
「口の中に入れればいいのかい」
「はい、その前に、この粉薬をクモの糸で包んでください」
「そりゃたやすいが、どうしてだい」
「お腹の中でゆっくりと薬が効きます、そのほうが効果があります」
女郎蜘蛛は糸で袋をつくり粉薬をいれた。
「さあ、お嬢さん、口をあけて薬を飲んでくださいな」
姫が閻魔鴉のお嬢さんに声をかける娘は小さな口をやっとあけた。
女郎蜘蛛が糸で包んだ薬を口の中に押し込んだ。
「鬼火、体を温めておくれ」
鬼火は宙からふわりふわりと降りてきて、病気の鴉を包みこんだ。
ほどなくすると、閻魔鴉のお嬢さんの胸が大きく膨らみ、大きな息を吐き出した。
「おお、娘が息を」
離れて見ていた閻魔鴉の親分が近づこうとしたが、赤鼠の姫は押しとどめた。
「もう少しです、おまちください」
そういわれ、ほんのひと時がすぎると、息を吹き返した閻魔鴉のお嬢さんの目をぱっちりと開いた。
「さー、もう大丈夫です」
赤鼠の姫が閻魔鴉の親分に声をかけた。
閻魔鴉の親分が寝台に駆け寄った。
娘鴉は閻魔鴉の親分を見た。
「お父様、とても良い気分です」
「おお、娘が口をきいた、奇跡だ、早く死んでしまった母親と同じ病気になり、もうあきらめておった」
「この醍醐を少しずつ食べてください、そうするとからだに力がつき、元に戻るでしょう」
赤鼠の姫様は持ってきた醍醐を閻魔鴉の親分に手渡した。
「これはかたじけない、なにからなにまで、このお礼は何でもして差し上げますぞ」
「地獄を見せてください」
「容易(たやす)いごようじゃ、地獄の中を案内させよう、お前様はいったいどなたじゃ、このようなことをできる者がこの世にいるとは思うておらなかった」
「これは、鬼火城の赤鼠のお姫様ですよ」
女郎蜘蛛が閻魔鴉の親分に説明する。
「おー、聞いたことがある、赤鼠一族のことは、もしわしらが役に立つことがあったらいつでも馳せ参じよう」
「ありがとうございます」
「それでは地獄を案内させよう、本当の地獄じゃ、日本のいろいろなところに入り口があるが、この地獄の入り口はもっとも閻魔様に近いところなのだ、出雲の国にある入り口より近いのだよ、北海道の登別の地獄、秋田、九州の地獄といろいろある、そこでは閻魔鴉の一族が入口を守っておる。
赤鼠の姫にはいつでもそこを通れるような手形をお渡ししよう」
「あい、ありがとうございます、私の仲間にもお願いできませぬでしょうか」
「よいとも」
閻魔鴉の親分のお嬢さんが起きあがった。
「ありがとうございました」
赤鼠の姫様に向かって頭を下げた。
「元気になられましたら、鬼火城にお遊びにおいでください」
「はい」
「さて、地獄を案内させますぞ」
そこに地獄茸を要求した閻魔鴉の使いがきた。
「先ほどはすまぬことを言ってしまいました」
「慣れてないと思ったよ、あんな脅しじゃ、だれも貢ぎ物なんかよこさないよ」
女郎蜘蛛の姉さんが笑う。
「初めてでござる」
「そんなことだろうと思った」
閻魔鴉の親分が頭を下げた。
「こやつは忠義者でござる、許してやってはくれまいか」
「もういいさね、お嬢さんが元気になったお祝いさね」
「それでは、私たちは地獄を見てまいります」
姫様は閻魔鴉の親分に挨拶をした。
閻魔鴉の親分と娘は深々とお辞儀をした。
「このご恩は一生忘れませぬ」
閻魔鴉の使いは道を引き返した。みんなも一緒についていく。
「地獄の中をしっかり案内いたしまする」
「頼むよ、また東の国の高尾山まで帰らなきゃならないんだ」
「ずいぶん遠いところから来たものだな」
「この鬼蜻蜒の兄さんの一族がすごくてね、空の上の上の方の気流に乗ってあっというまさ」
「ほー、そりゃすごい、鴉も使えるのかね」
「後で、乗り方を教えやしょう、ちょっと狭いが、乗っちまえばだいじょうぶ」
「そりゃありがたい、さて、こちらです」
赤鼠と女郎蜘蛛、それにたくさんの蜻蜒たちは地獄の扉の前に立った。
門番は鬼ではなかった。真っ白な閻魔鴉がいて岩の扉を開けた。
「おやま、簡単に入れちまうんだ」
女郎蜘蛛は驚いた。
案内の閻魔鴉は頷いた。
「入るのはいいが、案内人がいないと出ることができない、だから死にたい者は入れるが、地獄の中で死ぬまで生きていくのはつらいぞ。わざわざ地獄に来たい奴もいまい。これから中を覗くとその意味がわかる」
女郎蜘蛛はつぶやいた。
「焦熱地獄、針山地獄、飢餓地獄、熱地獄、楽しみだねえ」
地獄の中に入ると岩だらけの世界が目の前に開けた。
どこまでも続く地平線、一面の岩の世界。大きな岩と岩の間は底知れぬ深い谷。女郎蜘蛛たちが思っていた火がめらめらと燃えている地獄とはだいぶ違う。
案内の閻魔鴉が言った。
「鬼蜻蜒の大将、またこの二人を乗せてくれまいか」
「まかしとけ」
赤鼠の姫様と女郎蜘蛛は鬼蜻蜒の背に乗った。
閻魔鴉の合図で宙に舞った鬼蜻蜒たちは眼下の岩の世界に向かって飛んだ。
降りて行くと、岩また岩の上で何万もの人間が、ぼーっと立って宙を見上げている。死んで地獄に来た者たちだ。
「あの人間たちは何をしてるのでしょう」
赤鼠の姫は不思議そうな顔をした。
「ここへ来た人間は何もすることがない、日がな一日ああしているしかない」
「それは恐ろしいことです」
「だから、地獄なのだ」
「そうだね、あたしゃ何もやることがなくなったらおっちんじまうよ、退屈でね」
「人間は特にそうなのだ、ここは本当の地獄なのだ。地獄の釜ゆでなんて人間の作ったこと、何もすることがないところ、眠ることができないところ、それが地獄だ」
「ほんとうだねえ、ところで、人間ばかりじゃないか、私ら動物がいないね」
案内の閻魔鴉が説明をした。
「地獄だ、天国だなんて、人のためだけにある。我々動物は、煉獄と菩薩地獄だけだよ」
「でも、あんたは、人の地獄にいるじゃないか」
「閻魔様を手伝うのが我々の使命だからな」
「鬼ってやつもいないんだね」
女郎蜘蛛は鬼に興味があるようだ。
「ああ、鬼は人間の地獄にいるものではない」
「何処にいるんだい」
「知らぬ、俺もまだ会ったことがない」
「突っ立っている人間を見ていてもしょうがないね、ぐるーっと回ったら帰ろう」
女郎蜘蛛はため息をついた。
「あい」
赤鼠の姫様も相づちを打つ。
ほんの一時も地獄にいる必要はなかった。
「あの人間はいつまでああしているんだい」
女郎蜘蛛が尋ねると、閻魔鴉は「本人たちがいい人になるまでだ」と答えた。
「いい人って」
「地獄にやってきた人間は、もっと良いところに住みたいとか、もっと良いものが欲しいとか、欲を持った者たちだ」
「でも、誰でも欲があるし、欲があるから進歩するのではないかしら」
「さすが姫様、その通りだ、だから人間は死ぬとみんな地獄に来る、しかし、自分がいた世界が一番いいと悟ったものは地獄から出ていく、平和な欲しかもっていなかった人間はすぐそれに気付くものだ、欲もなくなり他人に悪さができなくなる人間がいい人なのだ」
「なるほどね、あたしゃ欲しかないよ」
「正直なのもいい人だ」
「私、閻魔様に会いたい」
赤鼠の姫様が思い出したように言った。
「あたしゃ会いたくもないが、姫様は閻魔様に会ってどうするの」
「閻魔様は人間のことをよくお知りでしょう、きっとそれだけではなくて、動物たちのことも知っているに違いないわ、いろいろお知恵をお持ちのことと思います」
閻魔鴉が赤鼠の姫様に念をおした。
「ほんとに閻魔に会いたいのかね、閻魔が喜ぶな、閻魔に会いたいなんてやつはいないからな」
「ええ、会いたい」
閻魔鴉は閻魔と呼び捨てにした。
女郎蜘蛛は「閻魔様と言わないと怒られないのかい」と心配した。
「そんな細かいことにとらわれないのが閻魔だよ」
閻魔鴉は言った。
「どんなやつなんだろう」
女郎蜘蛛もちょっぴり会ってみたくなった。
「それじゃ、ついてきてくれ」
閻魔鴉は地獄の底の人々の上を滑るように飛ぶと、大きな岩山に開いている大きな穴の一つに入っていった。そのあとを赤鼠と女郎蜘蛛を乗せた鬼蜻蛉たちが続く。
穴に入ると、閻魔鴉の目が赤く光り、あたりを照らし出した。
奥深い穴の先に着陸すると、大きな扉があった。閻魔鴉が大きな声を出した。
「閻魔様、お客人にございます」
扉がぎーっという音と共に開くと、部屋の中では白髪の小さな老人が笑窪を寄せて待っていた。
女郎蜘蛛の姉さんは目を丸くした。なにせ想像していた、とても大きな、怖い顔の閻魔とは余りにもかけ離れていたのだ。
「来たね、赤鼠の姫さん」
人懐っこそうな老人は、赤鼠たちのところにやって来た。
「あい、閻魔様」
「地獄はどうだい」
「あい、いろいろな色が渦巻いています」
「おー、よく見えるね、その通りだよ、それは欲望が地獄に堕ちた者たちのからだから離れて出てくるのだよ。早くそれがでてしまうと、あのものたちは本当の天国に行くのだよ、私はそれを見ているだけなのさ」
「あい、大変なお仕事です」
「おお、賢いな」
「俺たちが知っている地獄は誰が創ったのだろう」
鬼蜻蜒の大将がつぶやいた。
「そりゃあ、宗教を創った奴だろう、地獄に堕ちると大変だから良いことをしなさい、悪いことをしないようにしなさいってね、教えるためさ」
女郎蜘蛛の姉さんが言った。
「その通りじゃ、そこの蜘蛛のお女中は良くわかってるな」
閻魔様はニコニコして女郎蜘蛛を褒(ほ)めた。
女郎蜘蛛は閻魔が好きになったようだ。
「閻魔様は褒めるのがおじょうずです」
姫様が言うと、閻魔様がうなった。
「うーん、賢いどころではないな、赤鼠の姫は」
「さすが閻魔様です、人間を改心させるには、良いところを褒めて、自信を持たせるのが大事だと思います」
「その通りじゃ、先に立ち、まわりをまとめる者は、みなのそれぞれの良いところを認め、力を発揮してもらわにゃならん、それには、その者たちに自信を与えなされ」
「はい、大事なことを閻魔様から教わりました」
「赤姫になって、地の上の世界を良いものにしなされよ、わしはたまに地上に行くから、また会うこともあるだろうね、そのときには姫は大きくなって、あやかしの頭領になっていることだろう」
閻魔様が真っ黒な茸を懐から取り出した。
「これが、地獄茸じゃ、お前にやろう、大きくなったら使うことがあるだろう、よく考えて使うことだよ、この茸を漬けておいた汁を飲ますと、死んだ者が生き返るのじゃ、蘇(よみがえ)りの茸とも呼んでいる」
閻魔鴉たちもさがすことができなかった茸である。
「はい、ありがとうございます」
姫様は茸を受け取った。
「これからもいろいろお教えいただきとうございます」
「いつでもおいで」
「はい、閻魔鴉の親分さんから自由に入れる手形をいただきました」
赤鼠の姫と女郎蜘蛛は鬼蜻蛉の背に乗った。
鬼蜻蜒はすーっと舞い上がった。
「元気でな」
閻魔様が手を振った。
「ありがとうございました」
赤鼠の姫も手を振った。
閻魔鴉に案内されて、鬼蜻蛉たちは地獄の出口に向かった。
出口につながる洞窟に入ると、閻魔鴉の親分が元気になった娘と一緒に待っていた。
閻魔鴉の親分が赤鼠の姫に言った。
「どうでしたな、地獄は」
「怖いところです」
「そうだな、だが、ああやっているうちに、気持ちがきれいになって、人として回復すれば消滅することができる」
「え、天国に行くのではないの」
「そうなだよ、消滅し無になる、そこが本当の天国だ」
「でも、生き返るのでしょう」
「姫は賢い、いつの日かわからないが、またその時に、その者にふさわしい生を受け継ぐことにもなろう、だが前の生のことは覚えておらん」
「あい、わかりました」
閻魔鴉の娘が赤鼠に言った。
「こんなに元気になりました。お友達になれると嬉しい」
「あい、わたしも嬉しい」
赤鼠の姫も頷いた。
「それでは、姫様帰りましょう、閻魔鴉の親分さん、ありがとうね」
女郎蜘蛛が姫に鬼蜻蜒の背にのるよう促した。
閻魔鴉の親分と娘が手を振った。
赤鼠と女郎蜘蛛をのせて、鬼蜻蜒は一気に洞穴から抜けて外に出ると、上空にのぼり、蜻蜒気流に乗った。
帰りもあっと言うまであった。
「地獄ってなあ、やなものだねえ」
女郎蜘蛛は思い出しながら言った。
「はい、でも人間は可哀想です、死ぬとかならず地獄に行きます」
「そうだね、姫様、でも生き物はみな欲がある、あって、あたりまえ、ほとんどの人間は他人に悪さをするほどの欲はもっていないものさ、だから、地獄は素通りするだけの人が多いんだよ、安心していいよ」
「あい」
「姫様、この旅で、大人になったね、でもね、あたしゃ、鬼ってやつに会ってみたかったんだよね」
女郎蜘蛛が言った。
城につくと、赤鼠の姫様は鬼蜻蛉と女郎蜘蛛に頭を下げた。
「ありがとうございました」
「やだねーかしこまっちゃ、またいっしょに遊んでくださいな」
「そうだなー、もっともっと遊ばなきゃ」
鬼蜻蛉も相槌をうつ。
「あい、また、遊びに行きたい」
「それじゃよくお眠りなさい、姫様」
鬼蜻蜒たちは帰って行った。
赤鼠は天井裏の自分の寝床にいく前に、大黒鼠の部屋をのぞいた。爺は鼻提灯を出していびきをかいていた。
赤鼠の姫は、寝床に入ったのだが、地獄の人間たちのあの、ぼーっとなった顔を思い出し、身震いをした。
なかなか眠りにつくことができず、とうとう夜が明けてしまった。
蘇り茸ー幻茸城7
私家版第一茸小説集「幻茸城、2016、302p、一粒書房」所収
茸写真:著者 長野県富士見町 2015-9-25


