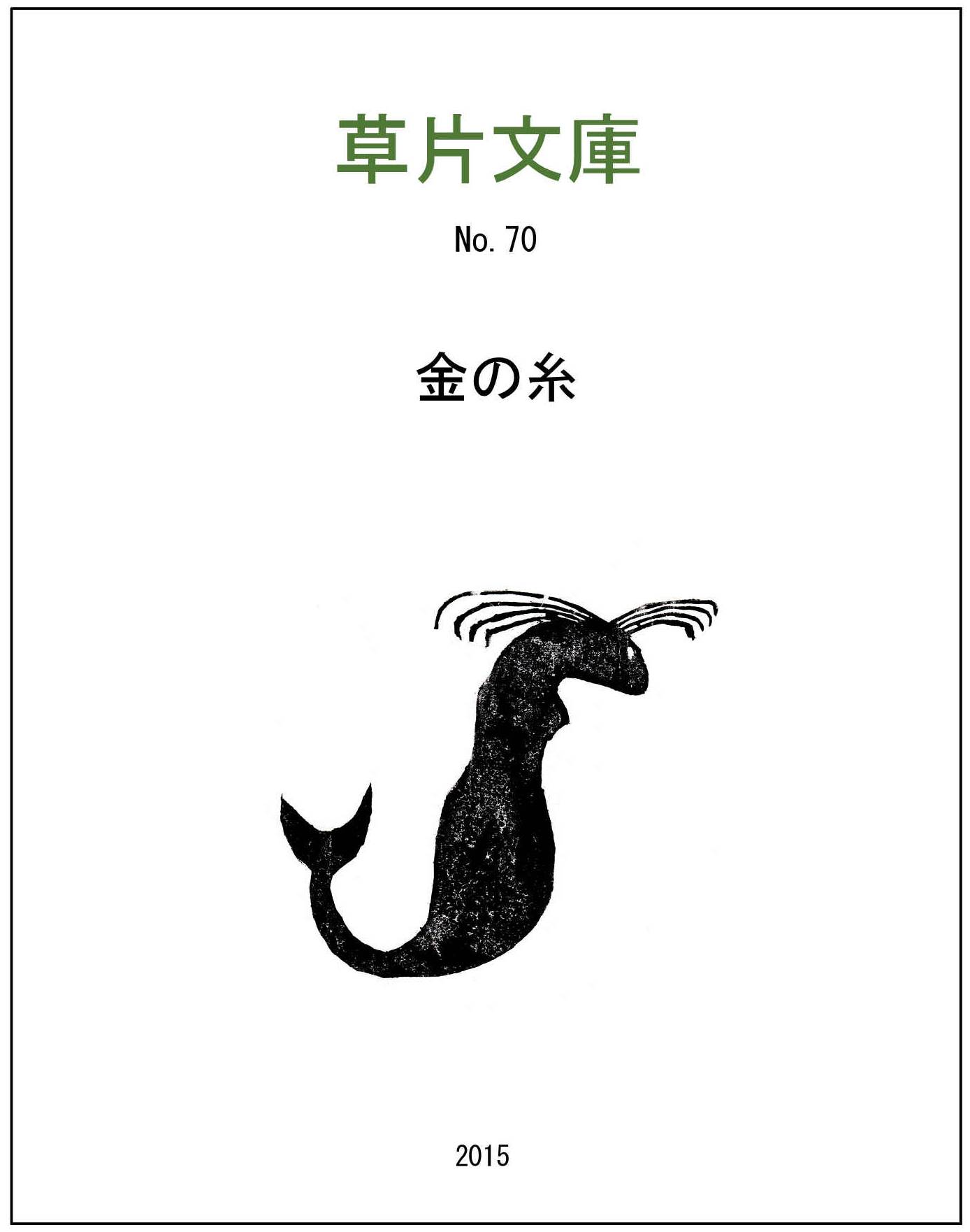
金の糸
これは現代の怪談である。
地方の都市の政治家が主人公で、地方の政治家というとその場所の昔からの権力者であることが多いが、この話でもある面ではあてはまる。その男は市議であると同時に町の主要な場所に点々と土地をもち、駅前の一等地のほとんどは彼のものである。
名前を赤根章造、ホテルや不動産屋を経営している。代々の資産家である。しかし決して強突く張りではなく、あたりの権力者とは全くといって違う。周りに対して聞き分けも良く、どうしてもいろいろなイベントにかり出された。それがやむなく市議へ立候補させられ、市民は彼をトップに選び当選したという経緯がある。本来なら市長にというのを断り続け、それなら市議へということでそうなった。赤根の推挙により選ばれた今の市長は赤根を尊敬し、大事な場面で頼りにしていた。
六十、すなわち還暦になった赤根の誕生祝いのときである。市長、市議はもちろん、県のお偉方が勢ぞろいし、彼の業績をたたえ、健勝を祝った。今まで病気一つしたことのない赤根は満面の笑みを浮かべて、胸に赤い花を付け、ホテルのホールの主賓席に腰掛けていた。隣には三十年近く連れ添った妻の光子が黒っぽいスーツを着て腰掛け、隣の二人の子供たちに話しかけている。光子は章造とは十も離れており、五十になろうとしているのに三十そこそこに見える。
息子の春樹と娘の夏子はまだ独身で地方公務員である。春樹は市役所に勤めており、夏子は市立中学の事務員で、まじめに仕事をしていた。章造は二人の子供をとても大事にしており、家族は至って平凡な暮しをしている。資産家にありがちな、浪費家で派手な妻であったり、放蕩息子であったり、男の出入りの激しい娘であったりすることはない。父親を尊敬し、犬猫をかわいがって、単純と言っていいほどの日々を送っている。
赤根章造自身が贅沢を望んでおらず、遅く帰ってきても光子の手料理で一杯飲んで、朝は規則正しく社長をつとめる地元のホテルに顔を出し、その隣にある、やはり自分が経営する不動産会社の一室に入る。
ホテルと不動産会社の実質的な経営者は章造が抜擢した若い実業家である。本人たちにすべてを任せ、何かをせっつくようなことをせず、必要なときに章造のコネと資産で彼らの仕事をサポートしていた。章造は卓越した頭脳力を持ち合わせているのではないが、人を見る目と、人に接することのうまさ、物事の流れの全体をつかむことのできる頭をもっており、しかもそれが表に出ない。
ホテルと不動産屋の社長室のデスクには、どちらも自分が座ることはほとんどなく、専務である若い実業家に使わせており、知らない人は彼らが社長だと思っている。自分は大きな取引の場面で、必要なときだけデスクの前に座り、社長として応対をするということをしていた。
そのようなことで、彼自身には自分の自由になる時間が有り余るほどあり、通常の人であればゴルフや旅行など、遊びにふけるところであろうが、彼はその時間を市の発展になるボランティアの活動に使っていた。
そこでいろいろ頼まれることも多く、ちょっとしたことでも、一生懸命になる彼の性格は、幅広く市民から信頼を得ていたのである。
彼の本当の意味での執務室は、三階建ての不動産屋ビルにある資料室と呼ばれるところにある。そこには彼の趣味の本が置いてある。彼は迷信に興味を持っており、日本全国の迷信が解説されている本や資料を集めているのである。もちろんのこと、自分の郷土の歴史の資料も市の図書館より充実しているほどだった。
章造自信は迷信を信じるか信じないかは興味がなく、迷信がどうして生じたか知りたいと思い、それが人間の何から出てくるものか自分なりに理解しようとした。かなりの本を読破した結果だろう、人の気持ちが読めるようになり、本人はそのつもりはなくとも、心理学を知らない間に身につけてきたといってよいのかもしれない。
還暦の祝いが始まった。
司会から赤根章造の紹介があり、市長の挨拶が終わった。
そのとき、後ろから若い男が飛び出した。そいつは壇上から降りようとする市長めがけて突進してきた。手にはシャンデリアの灯りにキラリと反射するものを持っている。市長が避けようとして、章造の方に逃げた。そこを暴漢が襲いかかる、刃物が振りおろされ、市長の左腕が切られ、市長は右手で刃物を振り払った。刃物は宙を飛び、章造の方に飛んできた。
あっと言って、章造は手で払いのけたが、刃が左手首にあたり、血が吹き出した。あわててハンカチを当てたが、白いハンカチが見る間に赤く染まっていく。
その場に居合わせた市立病院の院長がすぐに市長と章造の応急措置をした。
暴漢はやはり出席していた警察署の署長と数人の刑事に取り押さえられた。後でわかったことは、その男は市の福祉施設で働いていたが、休みがちなため解雇され、その恨みで市長を狙ったようである。
章造は救急車で病院に運ばれた。命に関わるようなものではないが、意外と傷は深く、縫わなければならなくなった。手首の動脈が切れていたのである。
手術台にあがるとき、章造は背広のポケットから名刺入れを取り出すと、中から小さなビニール袋に入ったものを引きずりだした。
「これを使ってくれないかね」
医師に差し出すとそう言った。
「なんでしょう」
「糸ですよ、この糸で縫ってくれませんかな」
医師は手にしたものを見た。
「何の糸です」
「体にいいという糸です、消毒されて密封されていますから、そのまま使えます」
章造が説明するのだが、医師は首をひねった。
「しかし、溶ける糸でないと後が大変なので困るのですが」
「抜かなくてかまわぬのです、後生ですから、これでお願いします。これでなければ縫わないで結構です」
医師は明らかに困っているようである。
「どうですかな、私が一筆書きます、何があっても先生に責任がいかないようにしますから」
そこまで町の著名人に言われると、医師も頷かなければならなくなった。
「筋肉と血管のところはこの糸で縫いますが、皮膚はこちらのものを使うということなら、引き受けます」
「ありがたい、それで結構です、先生には迷惑をかけません」
そういうことで、左手首の手術はその糸で行われた。
章造がこだわった糸は金でできていた。どうして章造が金の糸にこだわったか、どうして持っていたか、説明がいるだろう。
それは章造が持っている一冊の本である。金沢でその昔に書かれたもので、書いたのは金沢の町の医師のようである。
金糸命と題された本で、明治の初め頃に印刷された洋装本である。その当時としては珍しいものである。今で言うハードカバーの本で、表紙はアールヌーボー調の真っ赤な心臓に金の糸が絡まったようなデザインで、斬新なものである。
それには金の糸にまつわる話が書かれていた。その当時、日本ではまだ行われていない西洋式の手術のことであった。
金沢の金箔師の女房に乳のしこりができ、長崎から帰ってきたばかりの医師の見立てでは悪いもので、取り除かなければ死に至ると言われた。
医師の家には金箔師の張った襖がある。その出来はみごとなもので、なにかと頼まれることがあり、昔から懇意にしていたことから、女房のことを相談したのである。
医師は手術の費用は実費のみでよいという提案をした。長崎から帰ってきて日も浅く、良い結果を出せば、それが巷に知られ、後々、その治療所の名前も知れることになると踏んだのかもしれない。
その金箔師、白泉の女房、おさんは自分の身体に傷を付けるなどということは考えられず、まして乳房がなくなるということは女として恥ずべきものであり、死んだ方がましとまで手術を拒否した。一方、白泉は仏像に金箔を張る仕事をしていることもあり、仏のご加護を深く信じていた。金箔の斬新な使い方を考えている男で、新しいことへの理解もあり、長崎帰りの医師の西欧の医術を信じてもいた。
医師は早ければ早いほど直りは良いと言い、白泉の妻に手術をすすめた。白泉はなかなか首を縦に振らない女房のおさんを説得するのに大変であったが、一冊の代々伝わる本をおさんにみせた。金の働きの本である。その本には貴重な金が、金としての価値がある以外に、人の身体にとって良い働きをするということが書かれていた。
「どうだ、おさん、金は身体の中にはいるととてもよいそうだ、儂が乳の中に入れる金を作るので、それを入れてもらえば乳の膨らみも前のまま、しかも身体によいのだ、手術を受けたらよい」
おさんは金を身体に入れるというところに興味をもった。しかも乳の大きさはかわらないという。
「だけど、あんた、金を乳に入れたら重くて垂れちまわないのだろうか」
「それは儂が考えてやる。重くない金をつくればよいのだろう」
そう言われ、おさんは手術を承諾したのである。
医師にそのことを伝えると、医師は白泉に言った。
「金の糸をつくりなさい、それを、悪い出来物をとった後に入れてあげよう、そうすれば、重くなく形もそのままであるようにできる」
今考えると乱暴のような話であるが、金は身体を害さないこともあり、理にかなっていないわけではない。
それから白泉は純金を糸のように伸ばす技術を開発した。金は薄い箔に伸ばすことができる。ということは糸にすることもさして難しいことはないだろうと、試行錯誤をして、何とか細い糸にすることに成功したのである。
おさんは手術を受け、乳の皮膚の中のしこりを取り除いてもらい、そのあとに金の糸を丸めたものを入れたのである。はじめは触らぬように言われたが、日が経つにつれ、皮膚の切断部もくっつき、触れてみると少しばかり柔らかだが、それでもしっかりとした膨らみができた。
その医師は金の糸を使うことで町の中で有名になり、士族や金のある商人から病を治すことを依頼され繁盛したとある。
それから金の糸は身体の中に入ると、病気を吸い取り、外に出すという迷信が生まれたということが書かれている。町の者たちは、白泉の作った金の糸を買い求め、それを、着物の一部に縫い合わせたり、袋に入れて持ち歩いたりして、病気のお守りとして使ったそうである。
白泉の金の糸の作り方もその本に書かれていた。
章造は今まで病気をしたことがなく、医者や手術に縁がなかったが、金というところに興味をひかれ、金沢の金箔屋に連絡して金の糸を作らせ、箱に入れて床の間においておいた。もちろん、その一部は袋に入れて財布やらにいれて持ち歩いていたのである。
そういうことで赤根章造はとばっちりで左手を十針も縫う怪我をしたお陰で、金の糸が体の中に入った。
迷信を信じることはなかった章造であるが、金が身体によいことは、金歯がはやることから、科学的にも本当だろうと考えたのである。
その後も、赤根章造は集まりや会議に顔を出し、それなりの意義のある提案をすることから、ますます彼の評判は高まっていった。
その日も二つの会合に顔を出す予定があった。一つは午後一時から市立病院の建て増しの相談会であった。彼の資金が当てにされていたばかりではなく、彼はときとして、皆が思いもつかないようなことに気づくことがあり、運営などにも大事な人間として頼りにされていた。その後、観光開発の会合が夕方あった。市でも何か目玉を考え出し、観光客を呼び込もうということで行なわれる大事な集まりであった。それは章造の仕事にとっても大きな意味がある。
その時、病院建設の会合が長引き、次の会合に遅刻しそうになった。章造は隣の市との境にある温泉宿に向かって車を走らせていた。彼はいくら急いでいてもあわてた運転をしたことがない。そのときも遅いくらいの法定速度内で走っていたのであるが、自分がいくら注意していても事故は起こる。赤信号を無視した若者の車が彼の車の真横から突っ込んできた。相当なスピードでぶつかったため、章造の車はほとんど二つに折れるように壊れた。しかし、内蔵が破裂状態で、かなりの出血をしていても、奇跡的にも、彼の意識ははっきりしていた。病院に運ばれた章造は、救急車内で救急隊員に家族と連絡させ、金の糸を持ってこさせた。それを使って体の中の手術をさせたのである。
彼はそれさえ使えば、死ぬことはないと信じ、そうさせたのである。
奇跡がおきた。半年後にはまたいつもの生活に戻っていた。彼の内蔵の至る所に、金の糸が縫い込まれた。それは赤根章造にとって非常に好ましいもので、金の糸が彼に幸運を呼び込んだ強く信じることになったのである。彼はわざとでも金の糸を腹の中にいれたいほどの気持ちだった。
彼の市議としての働きもめざましいもので、新たな特産品を開発することを提案し、さらに、新たな温泉を掘ることを進めていた。特産品はビールと猪の肉で作ったソーセージである。温泉とビールと猪ソーセージを組み合わせ売り出そうと計画を練った。ひなびた温泉は日本の至る所にあり、新たにそういった温泉場を造ってもなかなか競争に入り込めないだろう。それよりも若い人に受けるような、温泉と地ビールレストランを組み合わせたものにしようと考えたわけである。猪に至っては増えすぎて、農作物を荒らして困っていたこともあり一石二鳥である。猪のソーセージをイノセージと名付けた。
二年後には計画通りに、市のはずれの山の中腹に温泉を掘り、イノセージもビールも量産体制になるという目覚しい発展を遂げた。
市の経営する温泉施設として、年寄りだけではなく若者にも受けるような、煉瓦づくりの初期ロマネスク様式のホテルを建て、ビール工場やビヤホール、猪ソーセージ工場も同じ敷地内で同様の煉瓦づくりの建物にした。その一体化が、林に囲まれたヨーロッパ風、しかも古風な雰囲気をかもしだし、旅の本にも載るようになった。
温泉施設の経営は赤根章造のホテル経営の知識が生かされているばかりではなく、何人ものスタッフを送り込んでおり、実質的に経営をまかせられているようなものであった。
「赤根社長、明日のイノテルの五周年記念のスピーチよろしくお願いします」
秘書の箕輪雪が資料室にやってきた。
「うん、わかっている」
市の温泉施設をイノテルと名付けたのも章造であった。ビヤホールはイノホール、ビール名もイノビールである。
「明日、私がお送りします」
「そうしてくれ」
自動車事故に遭ってから、章造は自分では運転をしなくなった。タクシーを使うか、会社の車で誰かに送ってもらう。
その日は快晴で、市民はビールジョッキ一杯とイノセージ一皿無料ということで、朝早くからイノテルに集まっていた。温泉のただ券も各家庭に配られていた。
式典は十時からである。会場はビールが振る舞われる野外ステージである。
イノテルのある市の広大な敷地内にある木に囲まれた広場には、芝生が植えられて、大人数の集会が出来る。そこになかなか良くできたステージが建てられた。まだ機能していないが、ジャズのフェスティバルなどが市の若手によって企画されている。今回の五周年記念はこのステージの開設祝いも兼ねている。ステージに名前が付けられていないので、これから募集するという。きっと、イノステージあたりに落ち着くのだろう。
セレモニーが終わり次第、ビールパーティーが始まるという算段になっている。
章造も時間通りに会場に着いた。ステージの前の広場にはいつもと変わらぬメンバーが集まっている。彼が入っていくと市長が近寄ってきた。
「イノテルは大成功です。一重に赤根さんのおかげです。そのことを祝辞のときに言うつもりです」
「いや、お恥ずかしい、私の名前などださんでください」
そう返事をしたときである。赤根は目の前が真っ暗になった。
市長はあっと言って、倒れた赤根に近寄った。
「大変だ、誰か救急車を呼んでくれ」
市長の声に、職員があわてて携帯で警察に連絡した。
しばらくして、赤根章造は私立病院のICUで眼を開けた。
「あ、お父さん、眼を覚ましましたわ」
家内の声である。
医師が彼をのぞき込んだ。
「良かった、回復の見込みはあります」
章造は声をだそうとした。
「何が起きたのです」
と言いたかったのだが、きちんとした言葉にならない。だがそれでも妻の光子には理解ができた。章造があわてて早口でものを言うときと同じような調子だったからだ。
「新聞社が飛ばしたドローンが落ちたのですよ」
ローカルテレビがステージでの模様を空の上から撮ろうと飛ばしたドローンが、操縦不能に陥って、彼の頭に落ちてまともに当たってしまったのだ。かなり大仕掛けなドローンで、重さがかなりある。またもや偶然の出来事であった。
章造は光子の言うことにうなずいた。
脳外科の医師が章造に話しかけた。
「脳の中に出血があります。それを取り除けばほとんど問題はなくなります」
章造はそれに対してもうなずいた。
医師は章造が聞く能力や判断する能力には支障をきたしていないと判断した。
「先生、金の糸を脳の中に入れることはできないでしょうか」
章造が小さな声で言った。町にきたばかりの医師には意味がわからなかった。光子が何を言っているのかわからないと言う顔をしている医師にあらためて伝えた。
「金の糸というのは何でしょう」
医師が不思議な顔をしているので、今まで彼が受けた手術のことを光子が説明した。
「しかし、脳の中に異物を入れれば、障害物になってしまう可能性があります、それはできません」
章造はそれに対してもうなずき、言った。
「脳膜を縫うときに使ってください」
章造は脳のことを勉強していたらしい、どのようなかたちでも頭蓋骨の中に入れれば、金の糸が脳の働きをよくしてくれるものと信じていた。
医師はしばらく考えていたが、「院長と相談して決めさせていただきます」
と答えて出ていった。
当然のこと、市立病院の院長は章造のことをよく知っている。従って、脳外科の医師に彼の希望を叶えさせてくれるように言った。
「脳の表面の出血は穴をあけて吸い出すだけでいいのですが、ちょっと奥にも出血を認めますので、開頭します。最後に脳膜をその糸で縫いましょう、ただ糸は残りますので、それがどのような影響を及ぼすか私には自信がありません」
「大丈夫だよ、私の方から家族に了解を取っておく、赤根さんは金の糸に強い気持ちを持っていて、そうしてあげないと、彼はがっかりし過ぎて逆に病気になるかも知れないほどなのですよ」
「そうですか、院長がそうおっしゃるなら、金の糸を使います、明日手術をします」
「それじゃ頼むね、金の糸は家族の人に持ってくるように言っておくから」
そういうことで、彼の頭蓋骨の中にも金の糸が縫い込まれたのである。脳外科の医師は熱心に章造の治療に当たり、リハビリに効果のある方法を助言してくれた。東京出身の脳外科の医師は新しいリハビリの仕方や、看病の仕方をよく知っており、光子にも丁寧に教えた。
その甲斐もあって、章造はまもなく退院し、前にもまして明晰な判断を下すようになり、市をはじめ、自分の事業がますます発展していった。章造は脳外の医師に感謝し、それからも家庭医のように、家族の健康の相談役として付き合うようになった。
それから三年、その年に大変なことが起きた。娘の夏子が勤め帰りに誘拐され、身代金が要求されたのである。
五千万の要求に彼は応じるつもりで金を用意した。最初に秘書の雪に打ち明けて相談したのである。家族に相談すればパニックになるに違いないが、秘書ならばこの程度の額ならば扱いになれていたし、いつも落ち着いて振る舞ってくれている娘だったのでそうしたのである。雪は警察に届けない方がよいのではと言った。金さえ渡せばすぐに戻るだろうと言った。
本人もそう判断して警察には届けなかった。そこが失敗したところであった。
金の受け渡しの指示がきた。秘書に金を持たせた。車で市の端を流れる川にかかる橋の袂に持って来いという要求は、章造には納得できるもので、任せてくださいという秘書を全面的に信用した。
しかし結果は無惨なものであった。秘書ともどもその金はなくなり、ほとんど人のいかない荒れ寺の本堂で夏子の遺体が見つかった。
なかなか戻ってこない秘書を心配して、彼は警察に届けたのである。赤根の娘ということで大捜査が行われ、遺体の発見に至ったわけである。警察の調べでは、犯行は秘書も関係し、おそらく秘書の内縁の夫が犯人だろうということになった。二人とも行方をくらましたからだ。
それからはなんとしてでも犯人を捕まえると、賞金をかけた。それでもなかなか犯人は捕まらなかった。
気落ちした章造は市議もやめ、社長の座を息子に譲り、自分は家にこもるようになった。不動産屋の資料室にあった本をすべて自宅の二階に運び込み、その部屋でいつもなにやら調べものをしていた。
夕食は息子の春樹と光子ととったが、そのあとにすぐ寝てしまい。夜中に起きて、二階の部屋でにこもっていた。
そこでしていることを見たら家族は仰天しただろう。彼はアルコールと脱脂綿、それに縫い針を一本机の上に用意すると、机の上に針灸の本を広げ、読みながら、自分の体に金の糸を入れていたのである。
右手の手首をアルコールで消毒すると、針もアルコールに湿し皮膚に刺す。血がちょっとでるが、それをアルコール綿でふき取り、ルーペを頼りに金の糸を小さな穴に通すのである。入るところまで突き刺し、そこで切る。それを、手足、胴の皮膚の下、腹は皮下を貫き筋より奥の腹腔まで入れた。始めは臍から腹の中に入れたのだが、臍が膿んだのでそれはやめた。そのようにしていたる所に金の糸を差し込んだ。
毎夜毎夜、体の中に金の糸を通し二年ほど経った。
娘を殺した犯人は見つからず、懸賞金を倍にしたりしたが効果はない。警察は外国に逃げたのだろうと、アジア諸国やハワイにも手配をした。
そのようなさなか、章造が急死するという出来事が起きた。誰もが不思議に思ったのだが、診断は心身消耗下での心臓発作ということだった。七六だった。
その町で一番古い寺が章造の家の菩提寺である。彼自身は無神論者ではあるが、代々葬られている寺には多大な寄進をし、供養もしきたりに則って、端折ることなく行っていた。最晶寺という浄土宗の寺であるが、住職はできた人物で、坊主ではあるが宗教から離れて、付き合いの多い人間であった。章造とはとても馬があった。
章造は常々和尚に葬式は簡素なものがいいと言っていたこともあり、藩元和尚は通夜の次の日に章造の身近の者だけに声をかけ、心のこもった葬儀を寺の本堂で行った。そのような章造の気持ちを家族はよく知っていたのですべてを和尚にまかせていた。
しかし市からの強い要望で、異例のことではあるが、三日後に、市のイノホールで、大層なお別れの会が開かれ、そこからの出棺ということになった。妻の光子は涙ながらに亡くなった亭主の人徳と優しさを語った。
セレモニーの終了後、霊柩車と数台のタクシーに乗ったのは内輪の者だけであった。妻の光子、息子の春樹、章造の兄弟、妻の兄弟と両親、家庭医である脳外科の医師であった。
多くの関係者の見守る中、車は市の火葬場に向かった。
その日は他に葬儀がなかったようで、程なく章造の棺が火葬炉に入れられることになった。簡略化して行うとはいえ、さすがに和尚は時間を取らないからと自ら申し出、棺を前にして心のこもった読経を行った。
炉に入れられて三十分、遺骨を拾うことになった。
炉から出され、ステンレスの台の上に乗せられたとき、係りの老人が、眼を大きく見開いて、「こりゃあ」とつぶやいて動きをとめた。
近くで待っていた者たちだれもが係りの老人を見た。
なかなか台を動かそうとしない老人の元に、和尚が近寄りのぞき込んで、びっくりしたような顔で皆の方を見た。
「かまわんでしょう」
和尚の声がして、老人はステンレスの台を押して、家族の元に寄せた。
「ご遺族のみなさま、お骨をお拾いいただきたいのですが、拾いづらいかもしれません」
老人は礼をただすと、箸を何組か用意した。
皆が近寄ってのぞき込んだ。
誰からとなく「なぜ」という声がもれた。
赤根章造の骨は立派なものであった。頭蓋骨も大きく、手足の骨もしっかりしたものである。
それはいいのだが、寝ている骨を、天井の明かりを反射してきらきら光る糸が章造の形をして繭のように覆っている。金の糸の網だ。
「なぜ、金が溶けないでいたのだろう」
脳外科の医師が目を見張っている。
「なみあむだぶつ」
和尚が手を合わせた。
「箸で金の糸をほぐし、そこからお骨を拾いなされ」
係りの老人が困っているのを見て和尚が言った。
「奥様どうぞ」
と老人が声をかけたが、光子は「春樹、先にやってちょうだい」と長男に箸を渡した。
光子は戸惑っているようにも見え、気味悪そうにも見えた。
春樹は素直に箸をとると、絡んでいる金の糸を少し広げ、箸をいれ、二の腕の骨をはさむと骨壷に入れた。
光子も同じように箸をとると金の糸の隙間に差し込んだ。
そのとき、きらりと光が走ると、金の糸の絡み合った繭が、章造のからだの形をして上半身を持ち上げ、宙を飛んで光子のからだに絡みついた。
「あー」という声を出し、光子は絡みついた金の糸をほぐそうと手をあてた。だが、金の糸は光子からだを、顔を、首を絞めていく。
脳外科の医師が、光子のからだに絡みついた糸を解こうと糸を引っ張った。
すると、金の糸は光子のからだから離れ、章造の格好になると、脳外科の医師に絡みついた。
光子はいき絶え絶えになって床に転がっている。
あっという間の出来事である。今度は医師が苦しさに悶え始めた。
春樹が声をあげた。
「おやじなのか、なぜなのだ」
その声で金の糸は医師から離れたと思うと、また光子のからだに絡み付き、宙に浮き上がった。
章造を焼いた隣の炉の蓋が開いた。
宙に舞っていた金の糸に絡まれた光子のからだが、すーっと焼却炉の中に飛び込んでいった。
炉の蓋がしまると、赤いランプがついた。
部屋の電気が消え、真っ暗になった。
炉の中が燃焼し始め、光子の大声が一度聞こえ、すぐに静かになった。
「なんとかしろ」春樹が叫んだ。係りの老人が扉に走ったが開かなかった。皆が戸を押した。係りの老人は電話機をとりあげた。音はしなかった。
燃焼の赤いランプだけがちらちらと光っているだけであった。
三十分もしただろう、いきなり部屋の明かりがつき、燃焼炉の扉が開き、骨が飛び出してきた。
光子の骨のまわりに、章造の形をした、金の糸でできた繭が覆っていた。
和尚の読経の声が聞こえる。
見守る人たちは動こうとしない。
章造の形をした金糸の繭は上体を起こし、やがて立ち上がった。
歩き始めると、顔を春樹の方に向けた。眼があるわけではないが、春樹を見ていた。
章造の形をした金の繭が歩き始めた。
「おやじ、どこにいくんだ」
金の糸でできた章造の頭は前を向き、扉を開けると外に出ていった。
誰一人その場を動こうとしなかった。
入口の扉が閉まった。
誰がこのような出来事を信じることができるのだろうか。参列者の顔はみな青ざめていた。
二体の骨が台の上に乗っている。
誰もが途方に暮れていた。
和尚がみなの気持ちを汲んで言った。
「春樹どの、みなさま、二人の骨をその骨壺にいれてくだされ」
係りの老人が骨を砕き、周りの者たちが二人の骨を一つの骨壺にいれた。
「章造さんは光子さんに惚れて惚れて、嫁にきてもらえるとなったときのあの嬉しそうな顔を覚えておるわ、いっしょにあちらにいきたかったのだろうなあ」
和尚の声は優しかった。しかし春樹は違う思いをもっていた。おやじは怒っている。それでなきゃ、お袋のからだにあんなにきつく絡みつくことなどしないし、むしろ長生きを願うだろう。それにあの医者を死にそうになるまで締め付けるなんて、おやじはそんなことをする人ではない。
「そこのご老人、今日は大変であったと思いますが、これも仏様のご意思の出来事、いつものように、報告をして、すべて胸の中にしまわれますように」
そう言われた係りの老人はうなずき、骨壺をいつものように箱に入れ、用意を済ました。
「春樹殿、これから、儂とちと話をしてくださらんか、ご親族のみなさま、あす、春樹殿が、光子さんが行方知れずになったことを警察に届けます」
周りの者たちは大きく頷いた。
親族に挨拶をすませた春樹は藩元和尚とともに最晶寺に行った。
「春樹さん、驚くことが起きましたな、私には説明はできません、お父上は、夏子さんのことで何か感じていらっしゃったのだろう、時が解決してくれるとは思うが、春樹さんには章造さんの意志をついでこの町をよりよいものにしてくだされ、光子さんのこともわしには何一つ説明が付きません、章造さんが光子さんに何を感じていたのか、詮索をすれば春樹さんも不幸になる」
春樹はうなずいた。ただ姉の死に母が関わっていたということはないだろうと思う。母と姉はとても仲が良かった。父の死が突然すぎた。それが不思議だ。そこに母が関係しているのだろうか。あの医師はどうだろう。
黙っている春樹に和尚が頷いた。
「いろいろなことが考えられるでしょう、先も申したように時が解決してくれます。ご自分を失わないように、しっかりと生きていってくだされ」
こんどは、「はい」と和尚の眼を見ながら春樹が頷いた。
それから二年後、シンガポールで金の糸が首に巻かれて死亡している日本人の男女のことがテレビで報道されていた。
脳外科の医師は薬物管理の手落ちで市立病院を追われ東京に戻った。
それらが終わったとき、春樹は父の突然の死に思いを馳せた。
やがて春樹は章造の跡を継いで市議になった。ホテルと不動産屋は今までのように昔の専務にまかせ、章造の残した迷信に関する本を読んでいた。しかし、章造とは違って、春樹は小説を書こうとしている。
金の糸
私家版 金幻想譚「金箔虫 2019 一粒書房」所収
木版画:著者


