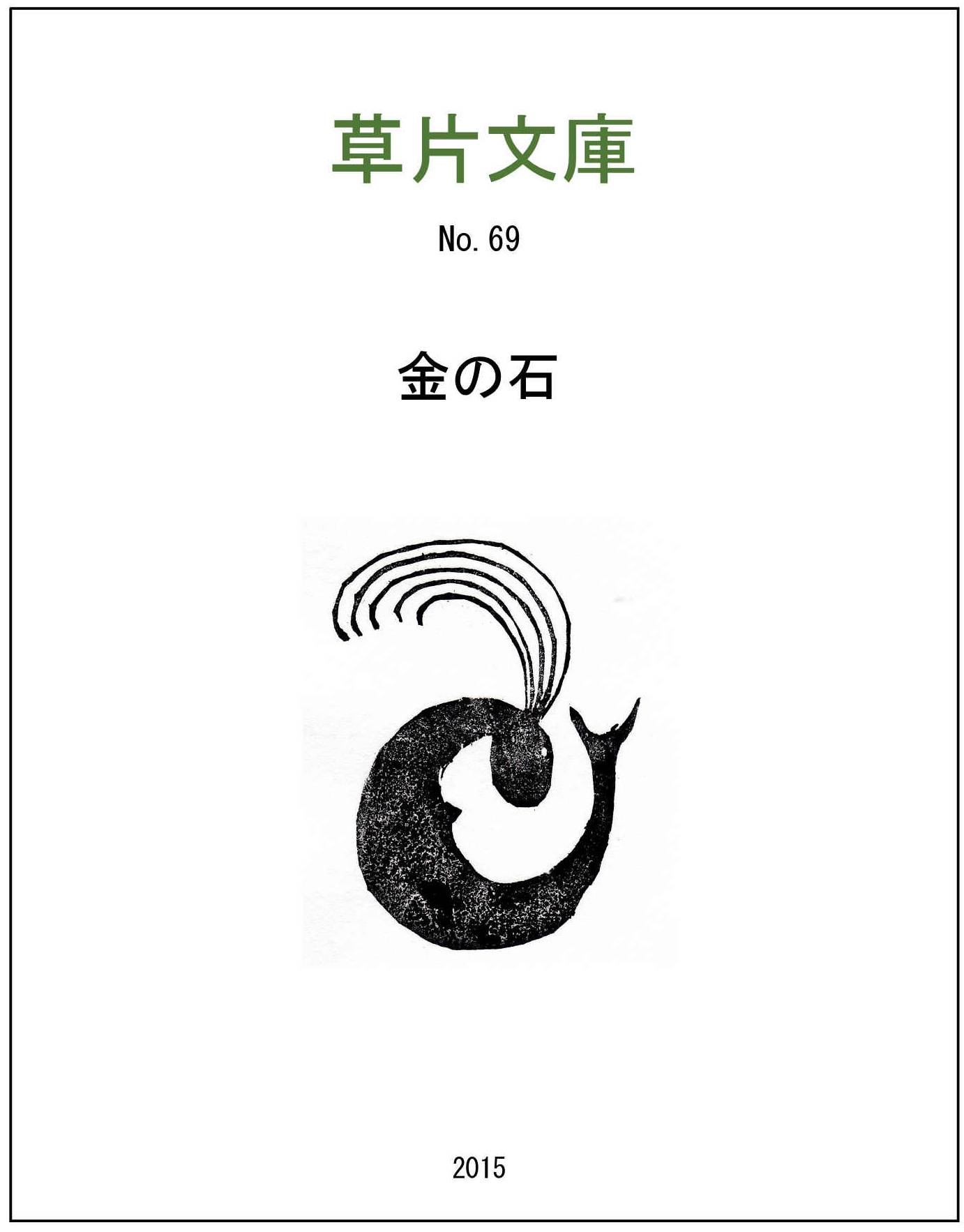
金の石
金沢山科の百姓の倅、三助は名前の通り三男で、五人兄弟の末っ子である。十一になったとき、町中の食料問屋、山八の丁稚になった。魚の乾物や干した山菜類、それに、味噌、豆腐なども扱っている店で、三助は店の掃除、便所掃除はもちろん、飯炊きの手伝い、荷物の仕分け、あらゆることをさせられた。ただ、まじめによく働いたことから、旦那さんやおかみさんだけではなく、周りの奉公人からいじめられることもなく、一年経つと、一日だが家に帰ることも許された。スルメを五枚もって家に帰ってきた三助はおっとうやおっかあ、兄弟から英雄視されて気持ちのいい一日を過ごし、大根を土産に店に戻ってきた。そのようなこともあって、ますます三助は一生懸命に働いた。三助は小さい時分はからだが弱く、両親はもとより、兄弟たちがかばってくれ、自分たちは我慢して、白い米の粥を食べさせてくれたこともある。三助は十をすぎると、からだも普通の子と変わりなく丈夫になり、一生をかけて親や兄弟に恩返しをしようと考えていた。
三助が十三になった時である。三助はなかなか呑み込みも早く、からだも立派になって力がついたこともあり、店から浜の漁師のところに手伝いにやらされた。働いていた山八は魚の乾物を作る手伝いを漁師の元締に送り出していたのである。いまでいう出向である。ただ、通うのにかなりの時間がかかり、朝早い浜の仕事のためには、暗いうちに店を出なければならない。
その時期、鯖の醤油浸けを作る手伝いを求められ、三助が行かされたのである。
包丁など使ったことのない三助はまず鯖を開くことから教わった。それも難なくこなし、開いた鯖を魚醤油につけて干すことを、ほどなく身につけた。
便利な小僧だということで、山八の旦那も漁師仲間も三助をたよりにするようになった。
水揚げされた鯖はすぐにさばく必要がある。若いのに三助の手際の良さは、他の者と比べると一段上である。
その日、「今日はほれ、こんな鯖がとれた」
漁師頭の五平が数匹の鯖を三助のところにもってきた。他の鯖と違い、色が黄色っぽく、開いた口には太い歯が生えていた。
「すごい歯だ」
「ああ、色も他の鯖と違うでな、だが、旨いかどうかわからん、三助、たまりに漬けて干してくれ、あまり旨くないようなら、店に出すのはやめて俺たちで片付けちまおうと思ってな」
「はい、親方、作ってみます」
三助は早速、その鯖の腹に出刃を入れた。
内臓を引き出したときである。血に染まった臓物の中にきらりと光ったものがある。どうも硬いもののようだ。
光ったものを刃先でまな板の脇によけ、二枚に開くと、次の魚にとりかかった。
腹を裂くと、また臓物に混じって金色のものがあった。三助はよく見てみたいと思ったが、とりあえず魚を処理した。こうして五匹の鯖をさばいたのであるが、すべての鯖の内蔵に光るものがあった。
臓物を桶に捨てる際に、光るものを拾って海水で洗ってみた。金色の石である。三助はまさかそれが金だとは思わなかった。
金色の石は内蔵にまみれていたためもあるが光は鈍いものであった。
三助は洗った金色の石を記念にと紙に包んで懐にいれ、いつもの鯖をさばきはじめた。他の鯖の内蔵にはそのようなものは入っていなかった。
すべての鯖を手早くたまり醤油につけ、魚を干す台に並べてその日の仕事は終わった。その足で山八にもどり、いつもの仕事をこなし、やっと昼になる。
手足を洗うときにもう一度金色の石を水で洗い改めて見た。
五つとも大きさは小指の先ほどで、形はほぼ同じ八角形をしている。光具合も同じである。まさか鯖が腹の中で石を作り出しているのではないだろうに、すべて同じに見える。雑巾の上に載せ、水分をとると自分の手ぬぐいにくるんだ。
「三助、何しているんだ」
番頭さんの呼ぶ声が聞こえた。
「今行きます、魚の匂いをおとしております」
「あー、そうか、今日は魚さばきだったのだな、ご苦労さん」
台所に行くと、皆、自分の席に座っていた。
「すみません、遅くなりました」
「いや、まだ遅れたわけではありません、大丈夫ですよ、魚をさばくのが上手くなったと、五平さんが言っていました」
この店は主人だけではなく、番頭さんも、兄さんたちも、女子衆もいい人ばかりである。みな貧しい農家の出で、三助とにたりよったりの境遇で育ってきた者たちである。
「さーいただきますよ」
台所の食事では、番頭さんが一番上である。番頭さんの合図で食事が始まる。旦那さん一家は別の部屋で食事をする。
食事の最中で話題になるのが、やはり食べることである。どこの何々が美味い、とか、あそこの甘いものは砂糖が足りないとか、奉公人が何かのついでに、目上からご馳走になったりしたことから、話題が盛り上がる。いずれ自分の金でそういうものを食したいというのが皆の願いである。
三助の楽しみはちょっと違った。旨いものを知り、食べられることは嬉しいが、店などをもてなくとも、行商人になって、自分で売る物を選び、そんなに儲けなくても良いから、生活の出来る金を得るということをしてみたかった。両親を楽にしてやりたいという思いがその根底にあった。
三助は今日の鯖のことを思い出していた。漁師の親方は初めて見る鯖で美味いかどうかわからないと言っていた。確かに少し黄みがかっていて感じが違ったが、形や大きさは今までの物と違いはない。明日になれば味はわかる。どこでとれたものか聞いてみよう。
あの金色の石は何だろう、たいしたものではないだろうが、そう思いつつも、三助は幸運をつかんだような気持ちになっていた。
「三助、何考えてんだ」
隣に座っている同じ年に入った丁稚の平太がのぞき込んだ。
「うん、さばいた魚のことだよ、鯖なんだけど、親方も今までとはちょっと違うんで、味を心配していたんだ」
「そんなことか」
平太は三助と違った特技がある。お客さんに対する対応がとても上手くて、誰にでも好かれる。三助もそれが出来ないと言うわけではないが、ちょっとぎこちない。
平太は金沢で生まれた三助とは違い、かなり遠くの出である。能登の海の方だ。地元に戻り山八のような食料問屋をやりたいと思っている。
皆それぞれに良いところがあり、番頭さんはそれをよく知っていて、皆に適した役を割り振っている。
次の朝、三助はいつものように、朝まだ暗いうちに店をでると浜にやってきた。干されている鯖の様子を見る。出来は悪くなさそうである。五匹の鯖も他の鯖と同じような色具合だ。どのみち今回、この五匹は売り物にしない。彼は一匹の肉をそのまま少し摘んでみた。これは焼いたらとても旨いものになる。脂がのっていて、今までに無いほど上等な、醤油一夜干しの鯖である。
頭が来たら報告しよう。彼は作業小屋に入っていった。
朝の漁にでた船が戻る前に五平がやってきた。今日は船に乗らなかったようだ。
「親方、あの鯖、とてもいいものです」
「そうか、摘んでみたか」
「すみません、心配だったので」
「いや、かまわん、ちょっと持ってきてくれ」
三助は自分が摘んだ一匹を親方もところに持っていった。五平は浜の焚き火のところに持っていくと、少しばかりあぶり豪快にかじって、「これは旨い」と叫んだ。
「親方、それはどこで獲れたのですか」
「ああ、あれは、箕(み)の岩の近くだったな、昨日はいつものところでも沢山獲れたのだが、なぜか、箕の岩の東側で船を止めて竿をおろしてみたのだよ」
「あそこは、何も獲れないところと言われているのではないですか」
「そうなんだ、確かにいつもは獲れない、今回だって、獲れたといっても半時でたった五匹だったからな、だが、これはかなり美味いな、今度獲れたら、醤油干しを作って、城にでも献上するか」
「まかしてください、うまい干し鯖を作ります」
「そのときには三助に頼むさ」
今回作った干し鯖は、親方が懇意の町方に届けたようである。
それからしばらくはその黄身がかった鯖はあがらなかった。
寒い冬が終わりを告げ、四月に入ってからである。ちょうど三助が十五になって二日ほど経った日のこと、いつものように朝早く浜の漁師小屋に行くと、少し早く戻った船から黄色い鯖があがったと、親方が桶をもってきた。二つの桶にあの黄色い鯖が入っていた。
「さばいてくれや」
三助はさっそく、黄色い鯖をさばき始めた。去年のときと同じように、臓物を取り出すと、固い石がでてきた。大きさも金色に光るのも同じだった。十二匹の鯖を開きにしたが、すべての魚にその金色の石が入っていた。
三助はその石を洗うと、手ぬぐいにくるんだ。
「親方、今度の鯖の一夜干しを、二匹いつか払いますので、いただけませんだろうか」
「どうするんだ」
「店のご主人と奥さんに、おらが作ったこの美味い魚を食べてもらいたいと思いまして」
「そうか、金はええ、儂から主人へのみやげじゃ」
いい親方だった。
そのようなことで、次の日に三助は店で売るいつもの干し鯖と、主人への土産をもって、店にもどった。
「なに、親方が、この鯖を土産にとか」
「はい、黄色い鯖で、めったにとれるものではなく、とても旨い干し魚です」
「そうか、夕餉にいただくことにしよう」
「私がさばいたものです」
「それは、楽しみだな」
「幾つになったのかな、三助は」
「はい、さきおととい、十五になりました」
「武士なら元服だ、よく働いていたから、二日も暇をやろう、親の元に顔を出しておいで、しばらく帰っておらんだろう」
「ありがとうございます」
三助は干物の端切れを持って、家に帰り、父親と母親にいろいろと報告した。
「三助、ようやってくれとるの」
父親も母親も三助がいっぱしの男になっていくのを好ましげにみるのであった。
店に戻ると、三助にはもっと嬉しいことが待ち受けていた。
主人に呼ばれ、初めてと言って良いが、主人の部屋に来るように言われた。きれいな畳の間で、床の間には見たこともないような美しい箱が置いてあり、墨で描かれた絵の掛け軸が掛かっている。
これが金沢の有名な塗りの箱と有名な絵師の絵であることなど三助にはわからなかった。
「どうだ、三助、おまえも大人の仲間入りだが、うちでの仕事は面白いか」
「はい、皆よくしてくれますし、商いについてもだんだんわかってきました」
「そうだろう、それで、おまえさんは行く先何をしたいのだい」
「はい、このお店の物などを、遠くの町などに売り歩きたいと思っております」
「店番よりも、外にでるのが好きか」
「はい、魚をさばくのも嫌いではありません」
「そろそろ、今年から給金を出してやろうと思う」
これには三助は嬉しいより驚いた。普通の店の奉公人は給金などもらうことはない。せいぜい、盆暮れにちょっともらう程度である。山八の主人の考えなのであろう。
「それでな、五平さんとも話したのだが、おまえが浜の手伝いをずーっとしてくれるなら、あそこの魚の干物はうちですべて扱わせてくれるということだ。これは大変な儲けになります。このあたりの他の店にうちからすべて卸すことになるのだからな。それで、三助には干物作りの手伝いと、それを他の店に卸す仕事を任せたいが、どうだ、何なら売り歩いてもいい」
三助はそれ以上の望みはないというほどのやりたいことであった。
「ありがとうございます、がんばります」
畳に頭をすり付けるようにして、主人に礼を言った。
「一つお願いがございます。浜とこのお店の間あたりの家にすまわせていただけませんでしょうか。そうしますと浜にいくにもお店にも来るにも手間がかからず、沢山働けます」
「おおそうか、通いということだな、では家を世話してやろう、いずれは嫁もとらなければならないだろう、精一杯働いておくれ」
こうして、三助は小さいながら借家に住まうことになった。
平太が三助を捕まえて言った。
「おまえも、ご主人によばれたが、良い話だったか」
「うん、干物をすべて任せられた」
「そりゃあよかった、俺は店の売り子になった、給金もくれるぞ」
「俺もだ、それに通いになる」
「いいご主人だな」
三助も平太もこの年からいっぱしの働き手になった。
頭の回る三助は鯖の醤油干しに等級をつけた。黄色い鯖の開きを、金鯖と名付け、熨斗(のし)をつけた。肉厚の鯖は厚鯖、普通の鯖は幸鯖、形が崩れて普通なら売らないような物は重さで統一し、福鯖として、町の小店におろし、さらに、そのような店がないところや、貧乏長屋などにも、旗を立てて売った。魚の分け方は鯖だけではなく、他の魚にも等級を振り、金鯖、金鯵、金烏賊などは、武家での買い上げが急増し、金鯖の三助と呼ばれるようになった。一方で、貧乏長屋では福鯖の三助さんと慕われるようになった。
三助は黄色い鯖があがると必ず鯖の内蔵から金の石を取り出し、布袋に貯めていた。それがもう三袋になる。三助はお守り代わりに一粒だけ小さな袋に入れ、首から吊していた。
ある時、いつも金鯖を購入してくれる細工師の家で、その袋を落としたことがあった。細工師は紫金とよばれる漆塗りの職人であるが、裏の顔は金箔師であった。そのころ、江戸から金箔を張ることは禁止されていたのである。だが好事家はどこにでもいて、金箔張りの飾り物を紫金に作らせていた。
落したことに気づいた三助は、次の日、干し魚を配達する途中に紫金の家に寄って小袋が落ちていなかったか尋ねた。紫金の妻が落ちていたと言い、珍しく紫金本人がその小さな袋を持って三助の前に現れた。
本人とは今まで話したことがない。
「あんたさん、これをどこで手に入れなさった」
「へえ、浜の小石の間に落ちてやした」
そう嘘を言った。
「ほう、なんだか知ってるのか」
「へえ、ようわかりませんが」
「これは金だ、しかも、佐渡の金より、もっと質がよい」
「金だとは知りませんでした。そうならいいなとは思いまして、お守り代わりに首に吊るしておりました」
「海の中にはこの金のでる場所があるのかもしれないが、何か聞いたことはないか」
そう言いながら、紫金は袋を三助に返した。
「いえ、漁師からはそのようなことは聞いたことがありません」
「良い物を拾ったな、小さい物だから大してならんが、お守りには良いだろう」
「これで、いくらほどになるものでしょうか」
「そうだな、簪の小さな飾りにでもなるだろうから、米五合ほどだ」
かなり値打ちがありそうである。三助のもっている金の塊をすべてあわせると相当になるだろう。
「ありがとうございました、これは昨朝つくった金鯖でございます、お礼においてまいります」
「そりゃ、すまんな、山八の、魚はみな旨い」
紫金はそういうと奥に入った。
それを聞いてから、黄色の鯖をさばくのが楽しみになった。魚の内蔵からでた金の石は次第に増えていった。
山八は魚の干物が有名になるにつれ、他の物もよく売れ、金沢の町でかなり知られるようになった。そのころ三助は十九になっていた。
ある日、行商から帰ると、主人に呼ばれた。
「三助、今日、紫金師匠が見えてな、おまえに会わせたい人があるそうな、明日、師匠のところに寄っていきなさい」
「紫金師匠がわざわざ来たのですか」
あの偏屈そうな師匠がわざわざ店に来るなどというのは大層な出来事である。何事なのか想像もつかなかった。あの金のことだろうか。三助はちょっと不安でもあった。
「師匠が金鯖を気に入ってくれてのう、三助のおかげじゃ」
「はい、ありがたいことと思っております。明日必ず寄ります」
次の日、三助は気になって最初に紫金の家に行った。
「あら、三助さん、早くによってくれたのね、おまえさん、みえましたよ」
紫金のおかみさんは、にこにこして奥に声をかけた。
奥の方から、「上がってもらえ」と言う声がした。
「どうぞ、主人が呼んでますから」
紫金の家に上がるなどということがあるとは思っていなかった。
おかみさんに案内されると、紫金の家は外見とは違い、武家屋敷のように広かった。通された部屋は紫金の仕事部屋のようで、作りかけの金張りのものが置いてある。
「来てくれたか、すまんな」
紫金は板の間であぐらをかいて、三助に座るようにすすめた。
「茶をもってきてくれ」
「実はな、三助さん、懇意にしている紙屋、紙久の主人が話してくれたことなのだが、探しているものがあってな、それがあんたさんが持っている金のようなので、来てもらったのだよ」
三助はやはり、と思って、ちょっと躊躇をした。それを察した紫金は「大丈夫だ、紙久の主人にはあんたのことまだ言っていない」と言った。
「こういう話なのだよ。紙久の主人は船釣りが好きで、よく海に出かけるそうだ。ほんの一月ほど前に、釣りをしていたところ、急に雨風がひどくなり、乗っていた舟がひっくり返ったそうだ。船頭ともども荒れた海に放り出され、紙久の主人は必死に浮かんでいようとしたが、大きなうねりに飲み込まれ海の中に引きずり込まれちまったそうだ。ところが、もうおしまいだと思ったときに、目の前に棒が突き出され、必死に掴んだそうだ。すると、ぐっと力強く引き上げられ、一艘の舟に助け上げられたということだ。小柄な船頭が魯を突き出しててくれたお陰で助かった。船頭は風雨の中を上手く舟をあやつり、船着き場まで戻ることができたということなのだ。
命の恩人の船頭を紙久の主人は家につれて帰り、風呂を勧め、酒をだしたそうだ」
内風呂がある家など数えるほどしかないだろう。
「その船頭が風呂から上がり、用意された着物を着て、酒の席に入ってきたときには、紙久の主人はびっくり仰天したと言っておったよ。
船頭の頭から長い黒髪が後ろに垂れていたんだ。女だったのだ。色は黒いが整った顔の、かなりの美女だったそうだ。主人は食事をもてなし。お礼の金を出したところ、それは受け取らず、頼みを聞いて欲しいとのことを言われた。
女は親から形見にもらった小さな金の塊を探していたんだ。もしそれを持っているか、知っている人がいたら教えて欲しいとのことだった。それで主人は見つけたら連絡するので、女船頭に家を教えてくれと言ったところ、いつも、日が昇る頃と、沈む頃には、その舟着き場にやって来るということしか言わなかったそうだ」
「のう、三助さん、女船頭はあんたさんと同じように袋に金の塊を入れ、首から下げていたようだが、気がつかぬ間に紐が切れて、海に落ちてしまったということだ、あんたの金は海で拾ったということで、話のつじつまがあうような気がする、紙問屋の主人に会ってくれまいか」
紙久の主人は紫金に御法度の金箔物を作らせていた。女船頭を招いた部屋には、金の魚拓が飾ってあり、それを見たので女船頭がそのような話をしたのだろうというということである。金の魚拓とは、これも紫金が考え出したことだが、墨でとった魚拓を、金箔で写し取り、墨の魚拓と寸分違わない金でできた魚拓を作り出すのである。墨の濃淡は、貼る金箔の枚数を変え光方をかえる、それで、濃淡を表すとのことである。
三助は女船頭が探しているものと自分が持っているものは違うものだと思った。自分は沢山の金の石をもっている。その女船頭はたった一つの物である。しかし、紫金の頼みごとであるし、会ってみることにした。
数日後、会いたいという連絡があり、紙久に三助が訪ねていった。
「いや、よく来てくれましたな、ちょっと上がって話をきいてくれまいか」
紙久の主人はわざわざ店先まで出てきて、三助を部屋に案内した。
紙久の主人の話は紫金が話した通りだった。
その金の塊を見せて欲しい、と言われ、三助は首に掛けていた袋を開き中の物を渡した。
指に挟み主人は隈なく見ていたが、眼を輝かせた。
「この金は、間違いなく、佐渡島や日本の普通の金とは違う、貴重なものだ」
この主人も金に相当詳しいようである。
「どうだろう、これをわしに売ってはもらえんだろうか」
三助は畳に頭をつけて首を横に振った。
「私にとって、幸運の守り神、それだけはお許しください。ただ、この金の石をその女船頭にお見せいただき、もし、それをそうだと言われましたときには、ご主人様とその女船頭の方と一緒にお話させていただきたく存じます」
「そうだな、これがそうだとは決まったことではない、それでは、これを借りて女船頭にみせる、それはよいでしょうな」
「はい」
「そうなったら、三助さんに引き合わせようじゃないか」
「ありがとうございます」
三助は袋ごと主人に手渡した。
その次の日だった。紙久の主人から使いが来て、残念ながら違う物だったが、話をもう一度したいとのことだった。
仕事を終え、夕方、三助は前日に続き紙久の家に行った。
「三助さん、あの女船頭に会うことができました。本当のことを言うと、違って良かったと思っておるのですよ、もう一度あの女船頭に会ってみとうなってな、こんな年になって恥ずかしいが、何とも魅力のある女でな」
「なんと、ご主人様は気持ちの若いことでございます」
「いや、もうそのような年ではないが、女が船頭で生きているのは大変なこと、命の恩人でもあるし、何とか助けになってやりたいと思ったのでな」
紙久の主人は情が深いとみえる。
「しかし、この金は、本当に珍しい、もし、譲る気になったときにはわしが高く買いたい、是非声をかけて欲しいものだ」
「かしこまりました」
「女船頭が誰のものか聞いたので、おまえさんのことを言いました。わしの見立てと同じくに、珍しい金だと申しておったな」
「ありがとうございます」
「それで、いろいろ迷惑をかけた、これは私からのお礼だ」
主人は三助の金の石と幾ばくかの包みを三助の前に差し出した。
「わたしは、そのようなものは受け取れません、今後も金鯖をよろしくお願いいたします」と三助は謝礼金を押し返した。
「よくできた奉公人だ、山八さんは羨ましい、うちにも毎日魚を運んでくださいよ」
三助にまた大きなお得意さんができた。山八の主人も大層喜んだ。
その日、仕事を終え、自分の住まいに帰り、袋に貯めた金の石を見た。どれも同じような形をしているのは不思議である。いくつあるかわからないが、紫金がいうほどのものなら、家がいくつも建つほどになる。しかしこれをどうしたらよいのか三助にはわからなかった。
いつものように夕飯を終え、寝支度を整えていると、戸をたたく者がいる。秋も深まり、日の沈むのが早くなった今頃、あまり出歩く者もいないのだがと思い戸を開けた。
立っていたのは青色の手ぬぐいでほっかむりをした色の浅黒い女だった。顔を見ると、目元のはっきりした、鼻筋の通った整った顔をしている。きりっとした眉。意志が強そうである。この女が紙久の言っていた女船頭であることはすぐにわかった。確かに町の女にはない清らかさがある。町のこびる女たちに飽きた紙久の主人があこがれるのがわかる気がする。と三助は思った。
女が三助を見て頭を下げた。
「こんな夜分に突然に訪れ申し訳ありません、緋(ひ)藻(も)と申します。紙久のご主人が三助さんに話した船頭でございます。あの金塊は私が探していたものでございます。ご主人には母からもらったものと申しましたが、それはいつわりでございます。とある理由からあの金を探しておりました、それをお話したくてまいりました」
三助は緋藻に上がるようにうながした。
横座りになった緋藻はいきなりこう言った。
「私は黒鯛にございます」
三助は耳を疑って、聞き返した。
「今、なんとおっしゃったんで」
「黒鯛でございます」
「黒鯛と言えば、魚の一つだが、どのようなことをおっしゃっているのだかわかりませんが」
「本当に黒鯛でございます」
三助には意味がわからなかった。
「ご不審に思われるのは当たり前でございます。その上で、三助さんの金の石が私どもにとって、とても大切なものであることをお話しさせていただきます」
その後、緋藻は信じられないようなことを話した。
「この、金沢の海の奥に、魚神様がすんでいらっしゃいます。魚神様は海の泰平には欠かせないお方でございます。人知れず何万年ものあいだ、海の生き物たちの様子をみてこられました。海の異変が起こる前兆を早くにお知りになり、海の生き物に伝えてくださるのです」
「魚神というと、私が子供の頃、親に話を聞いた、上半身が人で下半身が魚というそういう生き物ですか」
「それは、人魚でございましょう、魚神さまは人魚ではございません。魚の形をしておりますが、五感だけでなく、時の感覚が鱗すべてに備わって、海の中ばかりではなく、日、月、風、あらゆるところからくるものを感じとることができるのです。ただ、海の中でしか生きることができません。海の底の奥に魚神様の住む世界があり、私はそこで魚神様を守る役割をしている黒鯛でございます」
三助には黒鯛の言っていることを理解することがまだ出来なかった。あまりにも不思議すぎる話である。
「黒鯛と申しましても、人に姿を変えることのできる黒鯛でございます。私どもも、魚神様がお生まれになった時、一緒に生れた魚でございます。魚神様を守るため、このように人の姿になって陸に上がります、海の世界に人の世界の話を伝えるのも我々の役目でございます」
三助は押し黙ったままであった。信じろと言う方が無理である。
「魚神様は全世界で八百人おられます。金沢の海にお一人、駿河の海にお一人いらっしゃいます。日本にはあと三人、土佐と長崎、それに蝦夷の海でございます。魚神様が未来を予知するためには、金に囲まれてなければなりません。魚神様がお住まいになっている海の底の洞窟には、金で出来た部屋がございます。その部屋に入られ、未来を予見するのでございます。その金は人のもつ金とは異なり、海金という金でございます。魚神様はその金の光を浴びてお力を発揮されるのです。海金の光が弱まれば、魚神様の力が衰えるのでございます」
海の中の金の部屋とは竜宮上のようなものかと三助は思った。
「それが、私の持つあの金ですか」
「はい、今年になりまして、どこからか、鬼鯖の大群が現れ、魚神様が海の中にお出かけになったところを見計らって洞窟に入り込み、海金を齧りとってしまいました。魚神様の金の部屋の海金が半分ほどなくなってしまったのです。海金は金藻と言う藻が作りだしますが、年にほんの一匁です。それを使って魚神様の金の岩屋の壁に張るのですが、とても足りなくて、魚神様の未来を見通す力が弱くなっておいでです。
ある時、私は一匹の鬼鯖を見つけ捕まえて殺しました。すると、腹から海金の塊を見つけたのです。鬼鯖の腹の中で齧りとられた金が石のように塊になるのを知ったのです。鬼鯖はときとして人の網に掛かり食べられます。鬼鯖が人に捕まり、海金が人に見つかれば騒ぎになります。きっと人の世界に行けば探せると思い、船頭となり探していたのでございます」
「どのようにして魚が人になれるのか、あまりにも不思議で信じるのは難しいが」
「私どもは顔を海の上に出せば人間に、人間になっているときに足を海に入れれば黒鯛にもどります、いずれごらんになっていただきましょう」
三助は考えた、あれだけの金があれば、両親兄弟に楽な暮らしをさせられる。
「三助さん、どのくらい海金をお持ちでしょうか。もしお返しいただけたら、何でもいたします」
「今までさばいた金鯖から取り出して、何袋にもなっています」
緋藻は眼を輝かせた。
「どうしたら返していただけますか」
「元々、拾ったようなものなので返さないわけはないが、あれだけの金があったら、両親兄弟に楽がさせられると思っておりました」
「もし、三助さんのご両親、ご兄弟に楽な生活ができるようにして差し上げれば返してくださいますか」
三助はうなずいた。
「ありがとうございます、では私を嫁にしてくださいまし、三助さんが漁師になっていただければ、毎日でも豊漁にして差し上げます」
三助は布袋を三つ緋藻に渡した。
「こんなにも沢山の海金をお集めになったのですね、これだけあれば、ほとんどの壁を直すことができます。ありがとうございます。これで魚神様のからだがもとにもどります」
緋藻は立ち上がると、三つの袋を持ち上げた。
「私はこれを持って、すぐに海に戻ります。一緒にきてください。これをとどけて、金箔雀鯛に渡してまいります。その魚は金藻が作った金塊を箔にして岩屋の壁を金でおおいます」
魚にも金箔師がいるのだなと、三助は金沢の海の世界が少しばかり見たくなった。
その夜、三助は緋藻につれられ海に来た。舟に乗ると緋藻は櫓を上手にこいで沖にでた。
「では、少しの間ここでお待ちください、必ずもどります」
緋藻は着物をするりとぬぐと、金の石の入った袋を手にもち、足を海に入れた。
その瞬間、あっと言う間に緋藻は大きな黒い鯛に変わり、袋をくわえて海の中に消えていった。
あまりの奇妙な出来事に、呆然としていた三助は四半時ほど待った。
波を見ていると、暗い海の中からいきなり黒い鯛が顔を出した。その瞬間、黒い鯛は緋藻にかわり、泳いできて手を舟縁にかけた。三助があわて舟の上に引き上げると、きれいな乳房を持った熟れた女が目の前に立った。
その場で二人は睦み合った。三助には初めての女であった。
こうして緋藻は三助の家に住むようになった。
三助は山八の主人のもとに緋藻をつれていった。主人はびっくりすると同時に、大いに喜んで、祝言の宴を整えてくれた。
その場に、紫金や紙久の主人も呼んだ。
紙久の主人は三助の妻が女船頭であることを知って驚き、大いに喜んでくれた。
山八の主人の許しを得、五平親方と相談の上、緋藻と一緒に漁にでることになった。ただし一本釣りである。ところが珍しい立派な鯛や、平目を毎日のように釣りあげ、やがて、金沢一の漁師になり、親方の跡を継いで、そのあたりの頭領になった。
こうして、三助は両親、兄弟に家を建てることができた。
二人には子供が八人もできた。子どもたちは元気に育ち、男の子はいっぱしの商人、漁師となり、女の子はみなそろって美人に育った。それぞれが良い家庭をつくり、たくさんの孫に囲まれる身となった。
ただ、不思議なことに、緋藻は自分の子どもたちの姉妹と間違われるほど若々しいままであった。
齢、八十になった三助は、若い頃と全く変わらない緋藻に言った。
「おまえは、あの時と全くかわらない、わしが死んだら、また海にもどるのだろうな」
緋藻はときどき海に入って、黒鯛になると、魚神様のいる海の底に行ってくる。
「三助さん、あなたが死んだとき、あなたを黒鯛に変えて、一緒に魚神様のところで暮らしたいと考えております」
「そのようなことができるのか」
「魚神様にお願いしてございます。魚神様も三助さんには感謝していらっしゃいます、黒鯛に変えてくださると言ってくださいました」
それを聞いて、三助は死んでも次の世界があることを知った。
こうして金の岩屋に住む魚神様に会えることを楽しみに、三助は八十八で静かに死んだ。緋藻は三助の遺体を舟にのせ、沖にでて海に投げ入れた。
しばらくすると、三助の骸を口にくわえた真っ赤な大魚が海の上に躍りでて、胸鰭で三助の骸(むくろ)をたたいた。
その瞬間、三助は大きな黒鯛になり、船べりに泳ぎ着いた。緋藻も海に足をいれ、黒鯛になった。
二匹の黒鯛は真っ赤な魚神の後を追って、ゆったりと海の底に潜っていった。
やがて、魚神が海の底の洞窟に入っていくと、二匹の黒鯛は入口で舞い踊り、洞窟脇に繁っている金藻に向かって、卵と精子を一斉に放ったのである。
金の石
私家版 金幻想譚「金箔虫 2019 一粒書房」所収
木版画:著者


