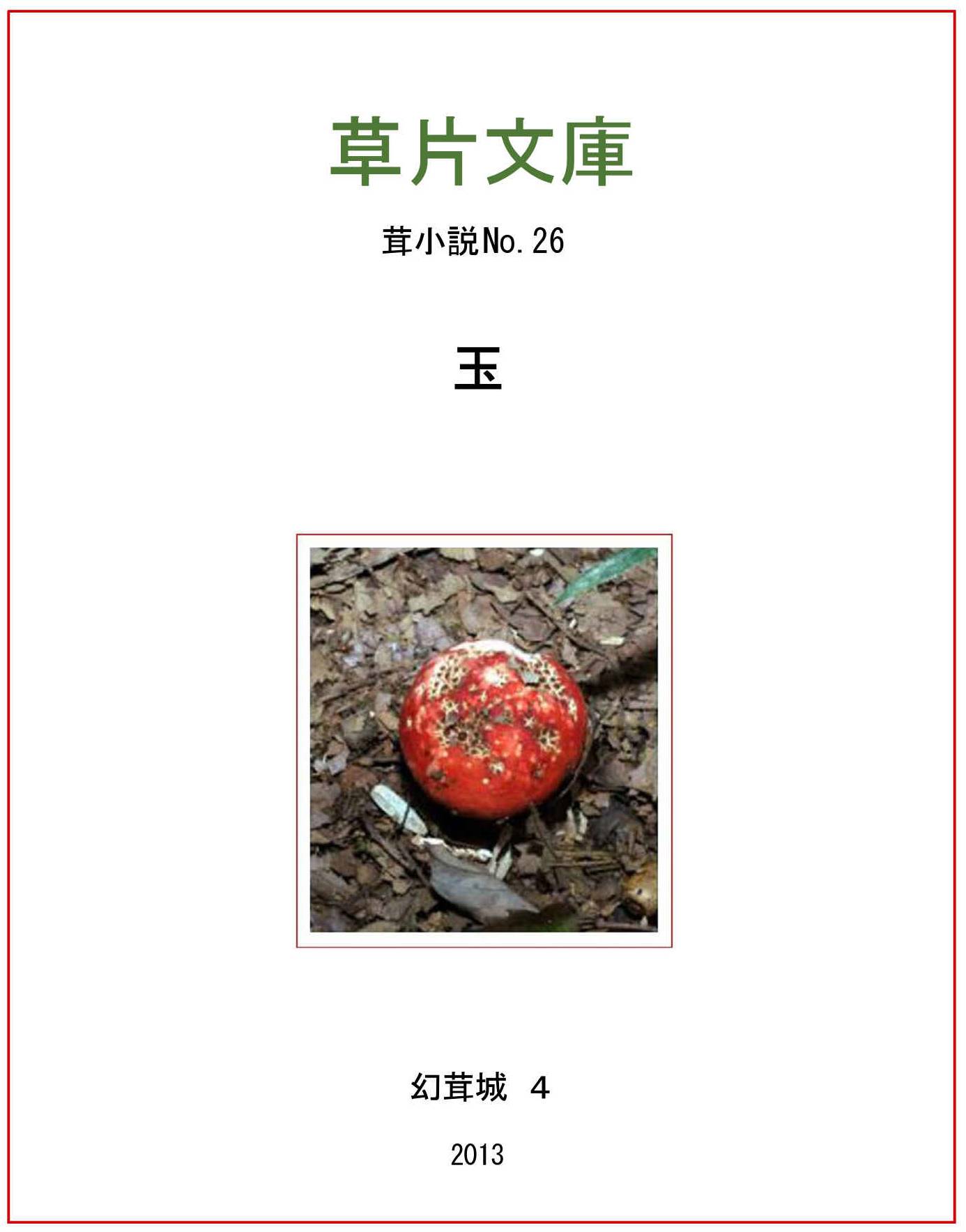
玉 - 幻茸城4
赤鼠の姫様が池の畔で糸蜻蛉の舞いを見ている。
池の水は青く透き通り、底からぽこぽこと水が湧き出ている。
「綺麗」
水面を糸蜻蛉がすれすれに飛ぶ様が水面に映り、水の上を糸蜻蛉たちが泳いでいるように見える。
何十匹もの糸蜻蛉たちがすーっと水面から離れて、空に上っていくと、玉になり、池の反対側に漂って行った。
残された池の水面は鏡のように青い空を映している。
赤鼠の姫様の髭を春のそよ風がゆらした。
「あ、風」
そのとき、青い空を映していた水面から青い水玉がいくつもいくつも飛び出して、岸辺にあがってきた。
水玉は赤鼠の姫様の周りにころころと転がった。
池の岸に生えている色とりどりの茸の間をぬって青い水玉は転がっていく。
赤い茸にぶつかった。パシャッと音を残し、青い水飛沫となって水玉は消えた。
「あれはなんでしょ、でも綺麗」
赤鼠の姫様は喜んだ。
そこへ忘れ物を取りに城に戻っていた大黒鼠の爺やが帰って来た。
「姫、台所に忘れてきた醍醐を取ってまいりましたぞ」
「じい、ありがとう、食べましょう」
「はい、姫さま、それにしても、この水玉はどうしましたぞ」
「池の面から転がり出てまいった」
「おお、そうでありましたか、なにも悪さをしなさそうですな」
「綺麗でした」
赤鼠の姫は茸の間に転がっている水の玉を見た。
「爺、お酒もある、飲んでよいぞ」
「また、女郎蜘蛛の悪巧みですな」
女郎蜘蛛が造った蜘蛛酒だ。
「大丈夫じゃ、あの女郎蜘蛛の姉さんは私に色々なことを教えてくれるのじゃ」
「心配ですけどのう」
「お酒はいりませぬか」
「いや、姫、それは旨いもの、いただきますぞ」
大黒鼠の爺は醍醐をかじって酒を飲んだ。
しばらくすると、ころりと横になり、いびきをかきはじめた。
女郎蜘蛛が大きな蝙蝠を連れてやってきた。
「おや、鬼蜘蛛さんは」
「今日は野暮用でこれないんで、こ奴を連れてまいりました」
蝙蝠は翼を広げ、頭を下げた。
「お初でござんす」
「今日はちょっと怖いところに案内しますが、よござんすか」
女郎蜘蛛の姉さんは赤鼠の姫に向かってちょいとばかり微笑んだ。赤鼠の姫は女郎蜘蛛や鬼蜘蛛にいろいろなところに連れてってもらっている。
「あい」
「大黒鼠の爺さんは、明日の朝まで寝てますよ、今日の酒は強いからね」
爺は髭をたらし、唐傘茸の下でだらしなく伸びている。
「ほら、お姫さん、蝙蝠の背中にお乗んなさい、あたしも乗るからね」
赤鼠のお姫様は地面に伏せている蝙蝠の背中の上によじ登った。
女郎蜘蛛も姫の後に乗った。
「それじゃ、出やすから」
蝙蝠はふわりと宙に浮かぶと、音もなく上空へ飛び立った。
上へ上へと舞って行くと、お城の方に向かった。
お城の屋根の瓦はずれ落ち、壁にはひびが入っている。薄汚れていて、とても酷いものである。
「こんなに壊れてるの」
赤鼠の姫様は自分の棲んでいる城の様子をはじめて知ったようだ。
「ほほ、そうよ、このお城は昔、昔のものなの」
「でも、お侍がたくさん住んでいるし、怖いこともしているのに」
「そう、侍が戦で切り取った首をさらして、酒を飲んでいるわね、でも、それがなにか今日わかるのよ」
「あい」
蝙蝠は一端、天守閣の屋根の上に降りた。
「逢魔が時を過ぎないと」
蝙蝠がつぶやいた。夕暮れまでにはまだ時間がある。
「そうだね、あいつら暗くならなきゃ出てこないね」
女郎蜘蛛も頷いた。
赤鼠の姫様が周りを眺めると、屋根の上には女郎蜘蛛の巣がたくさんあった。巣の真ん中で、女郎蜘蛛たちは思い思いの格好で餌を待っている。
一匹の女郎蜘蛛が蝙蝠の一行に気が付いた。
「おや、姉さん、蝙蝠の兄さんにくっついてどこへ」
「ちょっと、おどろのお庭にいくんさね」
「あんな庭に、なんぞ用などあるのかい」
「この赤鼠のお嬢さんに見せるのさ」
「赤鼠も一緒だったかね、きっと怖くて逃げ出すさ」
「さあ、どうかね、このお嬢さん、赤鼠の姫さんさ、このお城のね」
「ああ、そうだったのかね、そいじゃわちきらも挨拶せにゃあ」
女郎蜘蛛たちは巣から離れると、黒と黄色のからだをくねらせ、一斉に蝙蝠のところによって来た。赤鼠の姫様に向かって一斉に声をかける。
「よろしぃうに」
「あい、こちらもよろしくお願いします」
赤鼠の姫様も頭を下げた。
「まだ、かわいいね。悪いことを教えるんじゃないよ、姉さん」
「お前たちまでそんなことを、ちょっと世の中を見せてやるのさね、いずれお城の主だからね」
「そいじゃ怖いものの前に、ちょっと綺麗なものを見せてあげようじゃないか」
女郎蜘蛛たちはお尻を一斉に空に向けた。
蜘蛛たちが吐き出した糸は微風にたなびき、青い空に向かって一斉に上っていく。
赤鼠の姫様は糸がゆらゆらと揺れて上っていく様に目を見張った。
糸は上へ上へとどこまでも上がっていく。
一匹の女郎蜘蛛が「さあ」と声をかけた。
すると、糸の先が丸まって、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の空気の玉を捕まえた。その瞬間、女郎蜘蛛たちは糸をたぐり寄せ始めた。
天守閣の周りに、色とりどりの空気がふわふわと浮いた。
「きれい、きれい」
赤鼠の姫は手をたたいた。
「お日様にはこの色たちが一緒になっているんですよ、虹の玉よ」
「ニュートンの色だ」
蝙蝠が付け加えた。
「なに、それ」
女郎蜘蛛は蝙蝠に尋ねた。
「いや、なに、どうでもいい」
「時々、蝙蝠のあんさんは変なことをお言いだね」
赤鼠の姫は不思議に思った。
「お日様の色は赤だけじゃないのね」
「そうです。紫も青も」
「ふーん」
女郎蜘蛛たちは蜘蛛の糸を一斉に切った。
天空一面に色々な色の空気の玉がゆらりゆらりと上って行くと、青い空の中で破裂して混じりあい、青い空に溶け込んでいく。
「そろそろ夕暮れ、夕日が落ちるのを、天守閣の上で見ましょうね」
女郎蜘蛛の姉さんに促され蝙蝠が飛び上がった。
赤鼠の姫は女郎蜘蛛たちに手をふった。
「きれいな虹の玉をありがとう」
「姫さん、大きくなっても、わちらを食わんでくださいよ」
女郎蜘蛛たちは自分の巣に戻っていく。
蝙蝠は天守閣の壊れたしゃちほこの上におりた。
遠くの山間に夕日が揺らめく。
日が落ち始めた。
山全体が橙色に輝きはじめた。だがそれは一瞬のことだった。
暗くなり始めた山のほうから、黒いものがたくさん飛んできた。
蝙蝠の仲間たちだ。
一匹が天守閣の上にいる大きな蝙蝠と姫様たちを見つけて降りてきた。
「兄(あに)さんなにしてるね」
「このお嬢さんたちのお供だよ」
「どこにいくのかい」
「おどろの庭だ」
「おや、おや、ものずきだねえ」
「ままよ、いい経験だぜ」
「そうだよな、それじゃ、楽しんできなせい、その前に、みなでちょっくら綺麗なものをお見せしやしょう」
数え切れないほどの蝙蝠が天守の屋根に降り立った。お城の屋根の上が蝙蝠で埋もれて真っ黒だ。
蝙蝠たちは屋根の上で翼を広げて天を見た。
「黒玉よ、降りて参れ」
蝙蝠たちが声をそろえて叫ぶと、薄暗くなった上空から、黒い玉が次から次へと、ふわふわ、ふわふわと飛んできた。黒玉は空でひしめき合いながら、ほとんど山の陰になった太陽の光を下から受けて、橙色に輝いている。
「きれい、さっきのは虹の玉、今度のは夕闇の玉、すてき、みんな玉でできているのね」
赤鼠の姫様は池から飛び出してきた水の玉のことも思い出していた。
蝙蝠たちは大きな蝙蝠に挨拶をした。
「それじゃ兄さん、おいらたちは、町のほうに遊びに行ってきやす」
「ありがとう」
赤鼠の姫様が手を振った。
蝙蝠たちは薄暗い空に一斉に飛び上がり、空一面の黒い玉を蹴散らして飛んでいった。その勢いで、黒玉がいきなりヒュー、ヒューと城の庭の上空を飛び交い始めた。勢い良く互いにぶつかると、破裂して小さな橙色に輝く玉になった。
空いっぱいに、黒玉と橙色の玉がぶつかって増え。逢魔時色になった。
逢魔時だ。それもやがて消え、星が輝きだした。
「今日は新月、月がない夜だ」
蝙蝠がつぶやいた。
「月はどこに隠れたの」
「はは、機嫌が悪くてね、顔を出さないんだ」
「こら、蝙蝠、そんないい加減なことを言うと、このお嬢さんはみんな信じちまうじゃないか」
女郎蜘蛛がしかめっ面をした。
「おう、そうか、お月さんは、地面が隠してしまうんだ」
「蝙蝠の兄さん、博識だね、だけどたしかにそれじゃお嬢さんにわかんないやね、月の機嫌が悪い方がいいかもしれないね」
女郎蜘蛛は笑った。赤鼠のお嬢さんには難しかったようだ。
大蝙蝠は赤鼠と女郎蜘蛛を乗せて天守の屋根を飛び立った。
空を飛んでいれば星の明かりで明るいが、地面に降りれば暗闇が続く。
蝙蝠は草が生い茂った丘の麓に降りたった。
荊(いばら)がはびこり、至る所に石が埋もれている。うらぶれた場所である。
「ここがおどろの庭だよ」。
「あの石はなあに」
「あの石はねえ、自然な石だけどね、墓石なんだ」
「墓石ってなあに」
赤鼠のお嬢さんが明るい声でたずねた。
「死んだ者を埋めてその上に載せる石のことさね、人間のすることさ」
「どうして載せるの、重くてかわいそう」
「死んだものがまた地上に出てきて悪さをしないようにするのさ」
「石がないと死んだものは生き返るの」
「生き返る事はねえが、死んだまま動き出すことがあるのさ、それは悪さをするのだよ」
そう蝙蝠が説明を加えた。姫様には理解できなかったようだ。
蝙蝠は草むらから飛び上がると、大きな墓石の上に降りたった。石の上面が平になっており、周りが見渡せる。
「ここでいいだろう」
蝙蝠の声で、女郎蜘蛛と赤鼠は蝙蝠の背から降りた。三匹は石の上で並んだ。
女郎蜘蛛がちょっと怖い顔になって言った。
「さあ、お嬢さん、これから起こることをよおく見ておくのだよ」
「あい」
赤鼠が返事をした時、おどろの庭一面にある無数の石がぐらぐらと揺らぎだした。あたりに漂うなま暖かい風が腐臭を運んでくる。
「いやな匂い」
赤鼠の鼻は敏感だ。
「死人の匂いさね」
女郎蜘蛛もこの匂いはきらいだった。
揺れる石の脇から、蒼白く光る玉が飛び出した。また玉である。
蒼白い玉はおどろの庭一面に駆けまわった。
赤鼠の乗っている石の周りにも玉は光ながらころころと転がりまわった。
一つの玉がぴょんと飛びあがると、赤鼠の鼻の脇を通り過ぎた。
ぷーんと生臭い匂いが鼻をついた。
「冷たい」
赤鼠は横を向いた。
「この玉は燐だ、蒼白く燃えているんだ」
蝙蝠が言った。
「燐てなに」
赤鼠のお嬢さんが聞いた。
「死んだ人間から出る魂さ」
女郎蜘蛛は飛んできた燐をよけた。
「夜出てきて、また骨に戻る」
そのとき、いくつもの石がめくり上がりひっくり返った。
その下には人間の死骸が横たわっていた。青い燐はぽっと赤く光るとその死骸に入っていく。
周りに橙色の火がぽっぽっと舞い始めた。
死骸から一本の黒い茸がにょっきりと生えた。それは大きくなると、鎧甲をかぶった武者になった。
そこここのめくれた石の下にあった死骸に次々と黒い茸が生えていく。
茸はむくむくと膨らんで武者になった。
武者は剣を抜くと、やたらめたらと周りの武者に切りつけた。一人が相手の首を切った。首を切ると大きな声をあげた。あちこちで同じように相手の首を切った武者たちが声を上げた。
蒼白い玉は、荊に火をつけた。ぼうぼうと燃えると鬼火になった。
首を抱えた武者たちは意気揚々と鬼火を従えて城に向かい始めた。
「怖い」
赤鼠のお姫様の顔が青くなった。
頭の上ではまた蒼白い玉が光り飛び交った。
まだそのままだった墓石が持ち上がると、燐は赤く燃え、死骸を呼び起こし、黒い茸を生やした。
黒い茸は次々と武者になり、他の武者の首を切った。
首を持った武者たちは一列になって、城に向かって歩き始めた。
何回も何回も新たな墓石がめくりあがり、戦がくり返された。
「古い石は大昔の戦で死んだ侍の墓石なのさ」
「でも、石があっても死んだ人が出てくるのね」
赤鼠の姫さまは不思議そうだ。
「そうなんですよ、姫様大事なことに気付きましたね、いくら墓石を置いても、怨念が強いと、こういうことが起きるのですよ、安らかに死んでいない証拠です」
「安らかに死ねないとこうなるの」
「そうですよ」
「だから、人間たちは安らかに死ねるように祈るのです」
「ふーん、でもどうしてお城に行くのかしら」
「みんな死ぬ前はお城に住んでいた者たちなのよ、まだお城にいたいのね」
「どうだい、あっちらも、城に戻ろうぜ」
蝙蝠が声をかけた。
「ああ、そうしようね」
赤鼠の姫と女郎蜘蛛の姉さんはまた蝙蝠の背中に乗り闇の空に舞った。
空の上のほうから見ると、蒼白く光る玉に導かれ、鬼火に照らされて、死骸から生えた黒い茸から変化(へんげ)した武者たちは列をなし、首を持って城の中へと入っていく。
先回りして、赤鼠と女郎蜘蛛を乗せた蝙蝠は庭が見渡せる屋根の上に降りたった。
武者たちが城に入ってきた。武者たちは討ち取った首を石垣の上に並べ、屋敷の庭に陣取った。
何処からともなく、酒を持った小坊主が武者たちに酒を振舞った。
武者たちは,杯をぐっと傾けると、旨そうに酒を飲んだ。
一人の武者が酒を晒した首にかけた。
並べられた首からはメラメラと炎が立ちのぼり、首から真っ黒な茸がにょきにょきと顔を出した。
酒盛りは一晩中続いた。
うっすらと夜が明け始めた。武者たちは、庭の隅々で色とりどりの茸になり、その茸も赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の空気の玉となって空の中に溶け込んでいった。
石垣の上の黒い茸の生えた首は黒い玉となって空中に消えていった。
酒を配っていた小坊主は蒼白く光る玉となり消えた。
そこに朝の空気が吹き込んできた。
「みんな空気が作っていたのね」
「姫さんかしこい、そうだねえ」
あの騒がしかった酒盛りがいきなり消滅し、静かな城の庭に戻った。
「さて、帰るとするか」
蝙蝠は赤鼠のお姫様と女郎蜘蛛を背に乗せて、少し明るくなり始めた池の畔に戻ってきた。
大黒鼠の爺はまるまっている。
「ほら、爺さんはまだ寝ている」
「それじゃ、あっちらは帰るとしよう」
「あい、面白かったけど、怖いことでもありました」
赤鼠の姫は二匹に礼を言った。
女郎蜘蛛が最後につぶやいた。
「あの城に住んでいる侍たちは、もう命のないものたちなのよ、夜だけああやって大騒ぎするのだねえ、昔を思い出してね」
「え、城に侍たちは住んでいないの」
「そうよ、誰もいないよ。もうこの城に何百年も生きた人はいないのさ、亡霊が生きている人のようにこの城に出入りしてるのさ」
「でも、この醍醐はお城の人に持ってきたものと聞いています」
「なに、爺さんの作り話さね、商人の店に忍び込んで盗んだもの、姫様に心配させまいとした作り話ですよ」
赤鼠のお姫様はため息をついた。
爺やが目を覚ました。辺りをきょろきょろ見回すと、赤鼠の姫様が見ているのに気が付いた。
「そろそろ、日が落ちます、城に帰らねば」
「爺、しっかりして頂戴、これから日が昇るのよ」
爺やは女郎蜘蛛と蝙蝠に気が付いた。
「おや、蝙蝠と女郎蜘蛛か、何をしにきている」
「ほほほ、爺やさん、ちっとも何もしておりません、それじゃお嬢さんまた行きましょうね」
「あい、ありがとう」
女郎蜘蛛は蝙蝠に乗り天守閣の屋根に帰って行った。
大黒鼠の爺やは赤鼠の姫をせかして城に戻って行く。
明るくなり始めた池の上では糸蜻蛉の踊りが始まろうとしている。
玉 - 幻茸城4
私家版第一茸小説集「幻茸城、2016、302p、一粒書房」所収
茸写真:著者 秋田県湯沢市 1974-8-1


