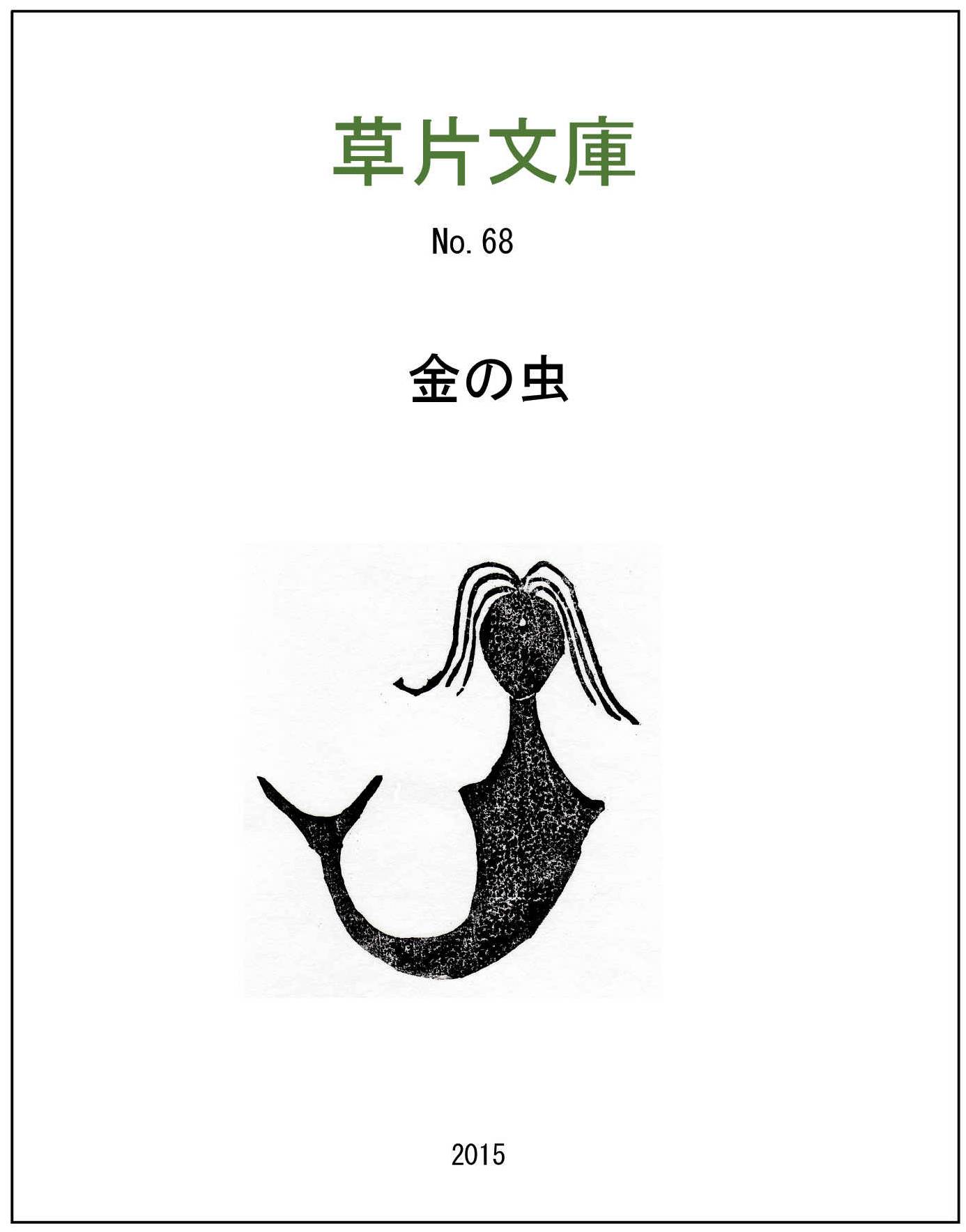
金の虫
金沢では金箔を作る所がたくさんあるように思われるかもしれないが、今の世、古来の製法でつくる店はほとんどない。
東町のはずれにある巣川金箔では、昔ながらの手作業で金を薄くのばし、箔にすると和紙の間に挟み込み、それをたたいて延ばす作業が行われていた。力の入れ様と、万遍なく叩くという、二つの具合で金箔の出来が違ってしまう。
金箔を延ばす作業を始めて五年目になる篠田卓は、いつものように作業場の畳に座り、機械で0.003ミリほどに延ばした金箔、澄と呼ばれているが、それを箔打紙の間に挟み込んだ。住み込みの卓は金箔づくり店の主人、巣川美助に教わっている。最近はいくつかの行程を一人でやらせてもらえるようになってきた。
澄の挟まった箔打紙を重ね、束ね、それを機械の打ち出す棒を万遍なく当たるように手で移動させる。それを繰り返すと、箔打紙の中で、金箔がさらにその三十分の一の厚さになる。すなわち0.0001ミリである。
箔打紙の間から薄くなった金箔を取り出し、形を整えるため、竹串を金箔の下に差し込み持ち上げる。別の和紙の上に移し、フッと息を吹きかける。息を吐き出す要領はむずかしい。うまく息がかかると、金箔がすーっと和紙の上で広がり、しわがなくなる。その上に型を乗せ、切り取り、回りを吹き落とす。そのようにして作られた金箔の挟まった紙の束は引き出しの中にしまわれていく。卓はまだ金箔を薄く伸ばすことはできない。
親方の家には、江戸時代から作られた金箔が、箔打紙に挟んだ状態で保存されている。貴重な資料である。
卓は東京にある文学系大学の美学を卒業し、その後は金沢の大学の大学院で日本の工芸職人に焦点をあて研究をした。修士課程のテーマとして、日本における金の芸術における職人の役割をとりあげた。金の薄く延ばしても破れにくい性質、金色に輝く性質、それに貴重性から、特殊な一部の支配階級の趣味の中で発達してきたことに着目し、職人の保護、その発展についてまとめあげた。その過程で、金沢の金箔屋を調査しているとき、中でも古い店の一つである巣川金箔製作所に歴史的な書物がたくさん残されていることを知り、足繁く通うようになった。
修士号をとった後は、ヨーロッパの大学の博士課程にいき、視野を外国の金と芸術にまで広げようと考えたのだが、外国に行く前に、もっと日本の金の技術を知る必要があると思い、しばらく金箔を作る店に奉公することにした。そこで巣川の店に弟子入りを頼み込んだのである。
率直な気持ちを巣川の主人、美助に伝えると、断られると思っていたのに反して、快諾してくれた。現在、卓を含め三人の弟子がいる。前からいる二人は高校を出てすぐに始めた十五年と二十年のベテランで、本当の職人肌の人たちである。親方もその二人がいればよいと思っていたのだろう。だが、卓と話している中で、卓の理論や歴史の知識が二人によい影響をもつと考えたようだ。それに、卓がこの技術を文章にして、世界に広めてくれるだろうという気持ちもあったようだ、かなり柔軟な頭の持ち主である。
自分の時間があると、卓は金沢の町の古い金箔細工や、歴史ある美術品を見て歩き、巣川の古文書を調べたりしていた。巣川にはずいぶん古い金箔技術の指導書があった。まだ目を通していないものが沢山ある。
ある夜のことである。遅くまで作業をした卓が、二階の自分の部屋にもどり、電灯を点けると、障子の隅がほんの一瞬きらっと光った。金の光である。卓は目を近づけてみた。金箔のちぎれたものが、衣服についてきてしまったりすると、親方に勘当されてしまう。
作業中は少しでも無駄にならぬよう、細心の注意を払って金箔を扱う。ちぎれた部分があると、必ず拾って、容器に貯めておかなければならない。金は貴重である。
目を凝らして探したが、それらしきものはみつからなかった。光ったのは金箔ではなかったのかもしれない。その日はそのまま床に入った。
ところが、その日から連日、仕事から自分の部屋に戻ると、必ず障子の桟のところがキラリと光った。
目を近づけてみるのだが、目に入るのはゴミぐらいのものである。
そのようなことが続き、一週間もたったころだろうか、真夜中に卓はふっと目を覚ました。いつも朝まで熟睡する卓は、どうしたことかと、布団から身を起こした。ふっと障子の桟の上を見ると、小さな光が細い列をなして動いている。暗い中でなにがうごいているのか、布団からでて障子に寄ったが、すでに光の列は消滅していた。気のせいかと布団に入りなおすと、すぐに眠気が襲って来た。
目の錯覚でないことが明らかになったのは、光の行列が始まって、一月ほどしてからである。
その日は、金箔に関する古い文献をもって自分の部屋に戻った。電灯を点けると、いつものように障子の桟の上に光がちらついている。その時は、近づかないようにして、息をこらして見ていると、いつもと違って、光が列をなしておらず、小さく点滅しながら、まばらに前に進んでいた。
そのとき、一つの光がきらりと強く瞬くと、はらりと畳の上に落ちた。針の頭先ほどの小さなものであるにも関わらず、金色の強い輝きをしている。他の光はぱっと消えてしまったが、畳に落ちた光は消えずにきらきらしている。しかも、畳の上から障子に上ろうとしているようである。
卓はそばによった。目にはいったのは金色に光っているダニのような小さな虫である。金箔を拾うときの先のとがったピンセットをもってきて、その金色の虫をつまみ上げ、座り机のペン皿にのせた。白い皿の上で金色のダニは歩こうとするのだがすべって前に進まない。
拡大鏡をもってくると目を近づけた。
まさに六本の足をばたばたさせた金のダニである。
この一月もの間、卓の部屋の桟の上で金のダニが行列をなしていたことになる。いったいどこから湧いてきたのだろう。行列はどこに行くつもりだったのだろう。
とらえた一匹の金のダニを小さな薬瓶に入れた。瓶の底をきらきらと歩き回っていたが、やがておとなしくすみで丸まった。電灯の光にかざすと、きらりと光った。
そのうち誰かに虫の名前を教えてもらおう。瓶を机の脇に置いた。
卓は机の前に座りなおすと、作業場からもってきた古い文書を開いた。今日、巣川の棚を整理していて、他の指南書とは異なった趣の本を見つけたのである。江戸時代のもののようで、書かれた文字を読み解くのは、修士で励んだこともあり、さほど難しくはない。
赤茶色になって今にも崩れそうな文書(もんじょ)の表紙には、「加賀の闇の金箔貼り」と書かれている。
彼は金沢の金箔の歴史を思い出していた。徳川家康の頃、地方で金箔を作るのは許されなかった。加賀も例外ではない、それでも金沢が金箔の産地となったのは、加賀の殿様が裏で技術を温存させたからである。そのような背景があることから、卓はこの本を、加賀で秘密に行われた金箔作りの話しだろうと思ったのである。
ところが読み解いていくと、そうではなく、薄くのばした金の箔を加賀の裏の世界ではこのように使っていた、という話であった。金箔をつくるのも極秘の作業である。金箔を貼ったものは表には出せない。それだからなおさら、外に言うのもはばかられるような使い方がされたのかもしれない。金満家の野放図な道楽である。
読んでいくうちに、唖然とするような、耽美的というより、奇怪な使われ方をしたということに、卓は驚いた。
あまり厚くないその冊子を読み終えるのに時間はかからなかった。ここにその話の概要をまとめてみよう。
最初の物語は、まだ加賀でも金箔をつくることが許されていた時代の話であった。
一、金箔葬
加賀の国に住まう伊造は若いのに腕の立つ金箔貼りで、自分で箔屋を営んでいた。遠くは江戸からも金箔を貼る依頼がきた。そのようなことから、伊造はよく江戸まで出かけていった。
江戸のとある大名屋敷の襖の修理に呼ばれた時のことである。もともと金箔を配した絵柄があったのであるが、古くなり、かなりの部分がはがれ落ちてしまっている。それを元のような艶やかな色に戻す仕事である。
かなり手間がかかり、一つの部屋の襖を仕上げるのに一月はかかる。伊造は中間の部屋に仮住まいをして、仕事に精をだした。
遊びもせず黙々と働く伊造に、中間の一人、平助が遊郭に行こうと声をかけた。伊造は首を横に振ったが、平助はそれでは旨いものを食いにいこうと、伊造に誘いかけた。伊造は食べることは嫌いではない。加賀の国には旨いものがたくさんあるが、江戸には江戸の旨いものがあると聞く。それまで中間部屋で慎ましい食事をしていた伊造の気持が動いた。
「どんなとこにいくんかね」
「鰻なんかどうだい」
伊造は加賀の安くて旨い海の魚を食べつけている。しかし、鰻は食ったことがない。あまり旨くないという話だったのと、あの蛇の様に長いぬるぬるした鰻は見るのもおぞましいものだった。
「きみわるいから、いやだね」
「伊造さんよ、鰻の面なんぞ見なくていいんだ、江戸の蒲焼きを食ってみねえ、そりゃあうめえさ」
伊造は江戸のみやげ話にいいかもしれないと思い、仕事が終わったときに連れていってくれと平助に頼んだ。
こうして、鰻の店にやってくると、ずいぶん沢山の人が鰻を食いに来ていた。なるほどと、伊造はちょっと期待した。
席に腰掛け、平助が酒と鰻を頼んだ。
色の白いかわいらしい娘が酒を運んできた。
「お咲ちゃん、ありがとよ」
平助のなじみの店のようである。
「平助さん、今日はおかみさんと一緒じゃないのね」
「ああ、加賀からきた伊造さんに江戸の旨いもの食わせるためここに連れてきたってわけさ」
「ありがとう、伊造さんは何しにきたの」
婦女子と話すなどあまりしたことの無い伊造はすぐに返事ができなかった。代りに平助が答えた。
「この人はな、加賀一の金箔貼りだ」
「すごいのね、どうぞ」
言葉の出ない伊造に咲が酒をついだ。
伊造はだまってお辞儀をしながら酒を受けた。
「ごゆっくりね」
咲はにこにこしながら奥に入っていった。伊造の目はその娘の後ろ姿を追った。
「お咲ちゃんはな、ここの三番目の娘でな、気だてはいいし、俺が独り者なら、嫁さんにしてえよ、伊造さん、加賀にいるかみさんを思い出してんだろう、一月も空けちゃなあ」
「いや、あたしは、独り身で」
「弟子もいると聞くが、それで独り身じゃたいへんだろう」
咲が蒲焼をもってきた。伊造は咲のかわいらしい顔に見とれていた。
「今日の鰻いいものだって、お父っつぁんが言ってた」
皿に乗ってでてきた鰻は脂がのってじゅうじゅういっている。
伊造は初めてみる蒲焼きにおそるおそる箸をつける。匂いはとても食欲をそそるものである。一口蒲焼を口にした伊造は驚いた。旨い。
「どうでえ、うめえだろ」
平助が伊造の様子から笑いながら声をかけた。
伊造はこっくりとうなずいて、いっきに蒲焼を食ってしまった。
「もう一つどうでえ、ゆっくり食いなよ」
平助が蒲焼の追加を頼んだ。
お咲がまた運んできた。
伊造はぼーっとなってお咲を見た。
「伊造さん、蒲焼気に入ったみたいね」
それから、伊造は帰るまでの残りの十日間、毎日蒲焼を食いにいった。
何回か付き合わされた平助に、伊造のお咲への気持が分からないわけはなかった。お咲の様子もまんざらではなかろうとふんだ平助は伊造にはっぱをかけた。
「どうでえ、お咲にほれたんなら親父に話してやろうか」
伊造はもじもじしているが、ちょっと首を縦に振ったように見えた。
平助は鰻屋に入ってお咲に話してみると、その気がないわけではないようだ。そこで、平助は伊造をお咲の父親のところに連れて行った。
平助に背中を押されて、伊造は咲の父親に話をした。
加賀という寒い遠い国に嫁にやることに渋っていた咲の父親も、伊造の誠実さと、金箔師としての腕の良さを認め、咲がよいというならということで、許されることとなった。このようにして、伊造は咲を嫁にし、加賀に帰ったのである。
伊造は傍の者が見ていてもうらやましくなるほど咲を大事にし、咲も伊造によくつくした。五年ほどその幸せが続いたが、その年、悪性のはやり病が猛威をふるい、咲もそれに罹ってしまったのである。伊造は寝ずの看病をし、大枚をはたいて医者を呼び、江戸まで南蛮渡来の薬を買いに行ったが、咲はとうとう逝ってしまったのである。
亡くなったその夜、咲の亡骸が寝かされている部屋に、遅くまで明かりがついていた。部屋の中では伊造がなにやらしている。弟子が障子を少し開けてみると、伊造が死んだ咲に話しかけている。あんなに大事にしていたおかみさんに死なれ、師匠はさぞ気落ちしているだろう、弟子はそう思いながら障子を閉め、自分の部屋に戻ったということである。
明くる朝、弟子は葬式の準備のため、おかみさんが安置されている部屋に入ると、師匠が布団の脇にすわり、じーっとおかみさんの遺体に見入っている。
弟子は、「おはようございます」、と声をかけると、伊造が振り向いた。目には隈ができ、浅黒い疲れた顔をしている。ああ、これは眠らずにおかみさんと別れを告げていたのだなと思っていると、師匠が絞り出すように口を開いた。
「見ておくれ、きれいだろう」
布団の上が、明るく光っている。
弟子が見て驚いた。
掛けてあった布がはがされ、敷き布団の上にのっていたのは、金箔で覆われたおかみさんの亡骸だった。髪の毛の先から、足の爪まで、すべて金箔がきれいに貼られている。
弟子は絞り出すように「きれいです、おきれいです」とやっと声がでたということであった。
遺体はそのまま、墓地に葬られたということである。
その話が裏の世界に広く伝わり、遺体に金を貼る金箔葬が、闇の葬儀屋によって行われるようになったということである。
加賀に金箔葬というのがあったことを示す唯一の記述である。
二、金の酒
二つ目は遊郭での金箔を使った遊びの極致に関する記載であった。これが極致なものかは意見のわかれるところであるが、一つの極致ではあるに違いがない。
商売がとても他の者にはかなわないほど上手にして、一代にして裕福な富を築いた呉服問屋の主人、井筒茂平の話である。
茂平は人当りもよく、奉公人たちには大変慕われていたが、なぜか嫁をとろうとしなかった。特に茂平の顔の造作が悪いとか、悪い病気をもっているといった、体に起因することではない。女に興味がないのかというと、むしろ嫌いじゃなく、一月のうち必ず七日ほど家をあけ、遊郭にこもってしまう。いつもいく女郎屋は決まっており、かなりの金を使って帰ってくる。
それと小さな加賀の漆塗の黒い桐の箱を遊郭から持って帰るのを常とした。いくつもの箱が茂平自身の部屋の床の間にある飾り棚に並べてあった。ところが、誰もその中のものを見たことがなかったのである。
その茂平が五十七で他界した。突然のことであった。元気よく黒い箱を持って、その日も女郎屋から帰ってきた。旨そうにいつもの好物をたっぷり食べて、床に入った。次の朝、笑うような顔で息絶えていたのである。ぽっくり病だと医者は言った。
四十になってからほとんどのことを一番番頭の京介にまかせていた。亡くなった後も縁者がいないこともあり、遺言通り京介が井筒屋を継いだ。
茂平の定宿(じょうやど)、女をあげる店であった篠原の主人の話が書かれている。
茂平は店にあがると、必ず前とは違った女を指名した。指名された女はそれから一週間、茂平の言うことを守らなければならない。要求は少しばかり苦痛を伴うことであった。と言っても、女のからだを傷つけるようなことではない。
指名された女はその間、全くものを食べることが許されず、酒と水しか口に入れさせてもらえない。ただ、茂平は女に驚くほどの大枚を与えたので、指名されるのを楽しみにしている女たちがたくさんいた。
なにをされたか選ばれた女は口止めをされ、もし口外すると、もう店には来ないと言われた。そのようなことから、女たちは茂兵との一週間を自分から話そうとはしなかった。店の主人も口止めをされており、最も大事な客が来なくなると大変になることから、女たちを厳しく仕切っていたのである。
茂平は同じ女を二度とは指名しなかったのであるが、二度指名された女が一人だけいた。お園である、お園は色が白く、豊満な肉付きのよい女である。太っているのである。それでは茂平にとって太っていればよいのかというと、それも違うようで、同じ様な体格の女が何人かいたが、一度しか指名されていない。
茂平が生きているうちは、井筒屋の者は彼の遊びについて誰も知らなかった。しかし、亡くなった後、跡継ぎの京介に請われて、篠原の主人が茂平の遊びを話したのである。
茂平は篠原にあがると、まず女を指名するのだが、必ず酒は強いのかと尋ねたそうである。お園が指名されたときも同じで、お園は無類の酒好きであったので、それはもう大きく頷いた。
部屋に入ると、茂平は帯を解かせ、園の体をくまなく触ってみる。また着物を着せ、こう言うのである。
「園、いいか、これから七日間、酒と水しか飲むでない、それと、小便はいいが、明後日から最後の前の日まで便をしてはいかん、最後の日までがまんしなさい、できるか」
園がうなずくと、さらに茂平は言い聞かせた。
「どのようなことをされたか、他言すると、もうわしは来ぬ、それだけではなく、この店を潰す」
店がなくなると女たちは路頭に迷い、もっと割の悪い、いやな相手を押しつけられる店にいくしかない。そこで園ばかりではなく、他の女たちも堅く口を閉ざすことになる。
そして、茂平は二十両という大枚を、園の前に置く。
「これは、ここの払いとは別で、園おまえのものだ、篠原の主人は知っていることだから、遠慮することはない」
こうして、茂平の前には料理と酒が運ばれる。しかし、園の前には酒だけである。
園は茂平に酌をし、茂平も園に酌をする。
「よいか、これからは、酌をせずともよい、いや酌はするな、それと、わしが酌をしたときには必ず飲め」
その後、茂平はゆっくりと自分の料理をつつくのだが、園への酌は早くなっていく。
「そんなに早く注がれますと、あっという間に眠とうなってしまいます」
園はそういいながらも、かなりの量の酒を飲む。
とうとう、園はだらしなく、その場で崩れてしまう。茂平は園を布団に引きずっていくと、着物を脱がせ、思う存分もてあそぶ。そのうち園が気づき、茂平に反応する。激しいやりとりの後、茂平も園も寝てしまう。
夜中に目を覚ました茂平は園を起こし、風呂に一緒にはいると、また、酒の用意をさせ、何度となく酌み交わす。
こうして、また男と女の行為をして、朝を迎える。
朝になり、厠からもどると、茂平が園に訪ねた。
「どうだ、通じはあったか」
「はい」
園はなぜそのようなことを聞くのかという顔で茂平を見る。
「それはよい、これからは、小便はよいが、通じはだめだからな」
園もその覚悟はできている。
茂平の前には朝食の用意がされるが、園の前には酒が運ばれてきた。
「さあ、これから五日の間、酒と水だけだからな、がまんするのだよ」
そういいながら、茂平は持ち物の中から革袋をとりだし、中のものを人差し指と親指で摘むと、園のぐい飲みに入れた。何回か繰り返し、そこに酒を注ぐ。
園が中を見ると、かなりの量の金の粉が沈んでいる。
「手に持って、ちょっとかき回し、ぐいと飲みなさい」
園は言われたとおり、ぐい飲みを持つと、指を入れちょっと回すと一気に飲んだ。
「おお、よい飲みっぷりだ、今日からその調子で飲むのだよ」
茂平はまた金粉をいれ酒を注ぐ。酒はどんどん運ばれてくる。
「飲むのは苦しくないか」
「はい、薬を飲む様な気持ちでございます」
「そうか」
そうして、園の肌が真っ赤になり、寝てしまう。そのままにしておき、また、起きたときに酒の用意をする。こうして金の酒を一日中飲まされ、夜は何度も茂平に思う存分あそばれるという毎日である。このお園という女、男を誘う雰囲気がとてもよいとみえて、茂平は一日に何度も床に入ったのである。
園は食べ物を口にしていないが、酒を飲んでいれば元気で、たくさん飲むと寝てしまう体質から、飲んだ酒を戻すようなことない。
こうして、最後の七日目になる。
朝、茂平が園にお丸をわたした。
「してよいぞ、ただし、これにだ」
園は、「あれ、恥ずかしい」
と顔を赤くしたところは、酒を飲んだときとかわりのない顔。
「屏風の陰でよい、ただし、終わったら、なにもせず、こちらへおいで」
茂平に言われて、おなかが苦しくなってきたこともあり、屏風の陰でしゃがんだ。
あっというまに園は終えると立ち上がった。
「どうだ」
茂平がのぞくと、そこには金がとぐろをまいていた。
「でかした、だれのものより、よいできだ、園、ちょっとまっていてくれ」
茂平はそれに手水場で水をかけもどってきた。
「ほれ、園がひったものは立派な金運だ」
茂平は持ってきた加賀塗りの箱にそれを収め、園と書いた紙をいれた。
茂平は園をつれ朝湯に入り、一緒に、特別に用意させた朝餉を食べると、また、十両を渡し、おまえは特別だ、また声をかけるからな」
と言って篠原を後にした。こうして、持ち帰ったその箱は茂平の床の間に置かれたのである。
その話をきいた京介は、茂平の集めた金運を納得したのであった。
そのような遊びをする達者ものは、茂平が死んだ後でもう現れることもなかった。しかし、その話が伝わると、金粉の入った酒を真似る者がでてきて、それが加賀の名物、金粉入りの酒となったのである。
三、金箔踊り
三番目の話は悲惨な話である。
加賀の陶芸家の話であった。加賀梲(うだつ)という男は、裏の陶器を作るので好事家にはよく知られていた。何分にも九谷など加賀の焼き物とは趣が全くといって異なり、彼の作るものは西欧のものによく似ていた。人を模るのだが、肌の色、目の色、髪の黒すべてが、実物とかわりのないもので、しかも、女人の裸体の陶器であった。おそらく、ほとんどの加賀の住人はそれを見たことがないであろう。
大商人の中でも、そのような世界に明るい者や武将の中の好事家が、周りに知られぬよう、梲に陶器を焼かせていた。
それを作るとき、梲は女を拐かしてきて、遊んだ上にモデルにする。いろいろなポーズをとらせ、絵に写し、それをもとに土をこねる。作品ができるまで女を家に帰すことはない。しかし、終わった後は、それなりの金子を女に渡すことから、今までお上に知られるようなことはなかった。
ところが、その女が連れてこられたときは、梲の目の色が変わった。加賀の町はずれに住む金箔を作る職人の娘であった。美人ではないが、体全体の形が整い、日本人離れした胸の膨らみと、西欧の女性に匹敵する大きな尻をもつ。彼は西欧の女人の絵を見せてもらったときに覚えた高揚を感じていた。梲はそのような女が好みであったのであろう。しかし、今までそのような女に出会う機会はなかった。
その女の名前はお金(かね)と言った。父親の金箔師がつけた名である。父親の無経(むけい)と呼ばれている男は、金箔作りに関しては相当な腕前を持っていたのであるが、遊び癖がひどく、家の中は火の車であった。そのなかで、口入れ屋に女郎に売られるより、安全で金になると言われたお金は、梲のモデルを引き受けたのである。
梲が到着したお金に、すぐ絵のモデルになるように言った。
一糸まとわぬお金は、たいそう立派なからだをしていた。色も白く、赤い乳首が、それこそ西欧の絵にでてくる女であった。
布団の上に寝かされたお金に梲が指示を与えた。
「背をそらせ、両足を開いて足をたてよ」
あられもない姿をさらさなければならないお金は、屈辱感を味わった。
だが梲は半紙に次から次へ絵を描き、姿勢を指図した。
その日、梲がお金をよとぎの相手にしたのだが、梲はお金が考えもしない格好をさせた。
こうして一月、毎日休むことなくお金はモデルと梲の夜の相手をした。
あるとき、お金はいったん家に帰りたいことを梲に伝えた。
「お金、家に帰りゃあ、もうここに戻ってこねえだろう、そうはさせねえ」
「家に金子を渡さなければなりません」
「そりゃあ、終わってる、口入れ屋からおまえのおとっつぁんにすでに渡してあるんだ、おめえは一年ここで働くのよ」
そう言われてしまうと、お金も従わざるをえない。
それからまた毎日毎日、梲の家からでることもなく、モデルと女郎まがいのことをさせられていた。
半年ほど経ったある日、いつものように梲がお金に床の上で横になるように言った。お金が裸のまま上向きになると、梲が部屋の外に声をかけた。
「用意はできた、やってくれ」
その声で入ってきたのは若い男だった。
お金は身を堅くして、その男を見た。どこかで見たことがある。
「久しぶりだねえ、お金さん」
お金はまじまじとその男を見た。
「半造さん」
「そうよ、お金さん、師匠は相変わらず飲んだくれて、おまえさんの稼いだ金などもうほとんどないって話だぜ、あと半年して家に戻っても、また奉公にでなきゃなんねえぜ」
半造はもう三年ほど前になるが、お金の父親、無経に師事していた男である。父親の技量に惚れて弟子になったのだが、父親があまりかまうことなく、半造は一年で辞めた。
「半造さんはどうしていなすったの」
「あっしは、三品(みしな)の旦那のところで修行をして、今は一人で金箔を貼っております」
「悪いことをしたね」
「お金さんがあやまるこたあねえ、お金さんも苦労するね、梲の旦那は厳しいだろう」
「はい、疲れました」
梲はそれを聞いても顔色一つ変えない。
「梲の旦那は、もっと稼がせてやってもいいとおっしゃっているんだ」
「なにをするのです」
梲が言葉を引き継いだ。
「なに、おまえのからだを、見せてやれば金になる」
「誰に見せるのですか」
「それは言えねえ、だが決して乱暴はしねえ、夜は相手をしなければならねえが」
「それじゃ、女郎と同じ」
「いや、ちがう、わしがおまえの体の絵をかいて、そのままの焼き物を作る、おまえはその焼き物の持ち主になるお方と寝るんだよ、一回だけだ、それに一回ごとにお前に五両直接払ってやる、半年後にはその金をもって、家にもどればよい」
「だけど、ただそれだけで、なぜ半造さんが」
「お前は頭も良く回る、そうだ、いつもとは違う、お前の体に金を貼り、わしが絵を描いて、後で金色の焼き物つくる。お前は一晩そのまま焼き物を頼まれた殿御と床を一緒にするのだ」
「それで、半蔵さんが私に金を貼るのですか」
「そうだ」
お金は半年もの間、梲に仕込まれたこともあり、また女郎屋に行くよりもいいだろうと判断したに違いない、こっくりとうなずいた。
半造は礼儀正しく一礼すると、お金の体に金箔を貼り始めた。首から、胸、乳、腹、足、股間と貼り、横を向かすと脇に貼った。反対脇も貼り、うつ伏せになったお金の背中と尻に貼った。
お金の首より下は見事に金色の体になった。
梲はそれを見ながら、紙にその様子を描き留めていった。
「お金さん、体を起こして立ってみてくんねえ」
お金は言われるとおりに、半造の前で立った。
梲はそれを見て目を見張った。金色の女の体は奇妙な色香が漂っていた。
「動いてくれねえか」
お金が動くと、半造は金箔が切れたところがないか調べた。
「いいようだ、そこに寝て、股を開いてくれねえか」
半造は股の間に金箔を継ぎ足した。
「あのとき切れちまわないようにな」
お金は恥ずかしさを押し殺すように無表情であった。
「それじゃお嬢さん、座ってくれますか、顔に貼らせていただきます」
そのとき、お金が口を開いた。
「半造さん、お嬢さんはやめてください。お金です」
半造はなにも言わずにうなずいた。
半造は体に貼ったものより小さい金箔を額のところから貼り始めた。指で直接金箔をとり、お金の顔に貼り付けていく。丁寧に丁寧に、瞼の回りに金箔を貼り、目の下、鼻、唇、耳、顔の全面が金に覆われた。
「お金さん、笑ってくれませんか」
お金は作り笑いをした。両頬のところの金箔が少し切れた。
「お金さんは大きな笑窪がよるんだね」
そう言うとお金は本当に笑った。
半造は笑窪のところを修正し、「もう一度笑ってくんねえ」と言った。
今度は問題なく金箔に覆われた笑窪ができた。
「半造さんと言ってくれませんか」
意味も分からずお金は「半造さん」というと、今度は梲師匠と言ってくれと言われ、そう言った。
「話しても、唇の金は大丈夫のようだ」
半造は自分からうなずいた。
残りの首周りに金を貼り、最後の仕上げをする。金色になったが、お金の顔である。ここまで、およそ半日かかった。
梲が声をかけた。
「お金、立ち上がってそのあたりを歩き回れ」
お金は言われたとおりに、梲と半造の間で歩いた。
「大丈夫のようだ、半造よくやってくれた、これなら、殿も喜ぶと思う」
「どこの殿様で」
そう半造がいうと、梲の顔がこの上もなく怖いものになった。
「聞くでない、半造には金を貼ってもらうこともあり、遊びのためと話したが、どこの誰の遊びかは聞いてはならぬ、それだけの大枚をわたすではないか」
「へえ、すみません、他言はしません」
「また、このようなことを頼まれたら、半造にまわすからな」
「ありがとうございます、それじゃああっしはこれで、お金さん、体には気をつけなすってください」
「ありがとう」
金色になったお金が返事をした。
半造が帰った後、お金はいろいろな姿勢をとらされ、梲はそれを絵にした。
「これから、飯を運んでくる、うまいものだ、腹一杯食って、よく寝るのだ、夜中に、駕籠が迎えにくる、後はついたところで、殿の望まれるようにするのだぞ、それに、決して、その殿の顔を見てはいかん、殿は頭巾をかぶったままお遊びなさる、いいな」
お金はうなずいた。
その夜、駕籠が迎えにきて、お金も頭巾をかぶせられ、どこかの屋敷につれていかれた。
そこでは、一人の恰幅のよい頭巾をかぶった侍が酒を飲んでいた。お金はその前に引きだされた。
「きたか、頭巾と着物をとれ」
お金が着物を脱ぐと、その男は言った。
「金の女だな、面白い、酌をせい」
お金はその男の隣に横座りになり酒をついた。
「よい顔をしている」
男は手をお金の頬に当て、そのまま体中にはわせた。
「人肌になった金の感触は悪いものではない、暖かな金だ」
男はお金の乳房を乱暴にもみしだいた。それでも、金が剥がれることはなかった。半造の腕はたいしたものである。
「どうだ、金を貼られた気分は、言うてみろ」
「少し息苦しく思います」
「そうか」
男は立ち上がると、お金を床につれていき、金色の唇を吸った。
「金の味はあまり良いものではないな、むしろ見るものかもしれん」
男はお金のからだをまさぐり、交わり精を放った。
お金の顔が絶頂を迎えると金色に光った。
「これはよい、よい顔じゃ」
男はまたお金をくみしだいた。そのとき、お金の手が無意識のうちに男の頭巾をつかんだ。その拍子に頭巾がめくれ男の顔が現れた。
今をときめくとある侍だった。加賀では誰でも知っている。
「見たな」
あわてて頭巾をかぶった男がお金に問いつめた。
お金は首を横に振った。
男はその後なにも言わずに何度もお金を弄んだ。
明け方、まだ暗いうちにお金は再び駕籠に乗せられ、梲の家にもどった。
「お金、ごくろうだった、疲れたであろう、これを飲み寝るがよい、疲れに効く薬だ」
お金は用意されていた湯呑みの薬を飲んだ。
「甘くて旨いであろう、体力が回復する」
お金は、うなずいてあたえられた部屋にいき床に入った。疲れていたこともあり、すぐに寝付いてしまった。
しかし、朝遅くになってもお金は起きてこなかった。
梲はお金の部屋にはいると、着物をはぎ、お金のからだに貼った金箔をはがした。
お金は息をしていなかった。
「悪く思うなよ、お金、殿の顔を見てしまったのが運の尽きよ、殿から薬を飲ませるよう言われたのだ」
梲は返事をしないお金に向かって独り言のように言った。
お金の遺体は、病死と言うことで、親元に帰され、働いた金は父親に届けられた。それが唯一、梲の良心だったのだろう。
お金の死を不審に思ったのは半造だった。半造はそのことを無経に告げた。無経はその後、遊ぶことをやめ、金箔作りに精進し、半造と共に箔屋を起こしたということである。
その話が伝わると、女が体に金を貼り、踊ってみせる金箔踊りが、加賀の裏の世界で行われるようになったということである。
本にはそのようなことがいくつか書かれていた。
篠田卓がその本を読み終わった次の日である。師匠の美助が作業場で大声を上げた。
「なんだ、これは、金箔がこんなになっている」
美助が古い金箔をしまってある重厚なタンスの引き出しを開け、中のものを見て驚いている。
「師匠、どうしたのです」
「これを見てくれ、江戸の時代に先祖が作った金箔だ、それに一面の穴だ」
和紙の間に挟んである金箔が針でつつかれたように一様に穴が開いている。
「虫が付くっていうことがあるのでしょうか」
「金を食らう虫などおらん、なにがおきたのだろうか」
何十枚も重なっている和紙の間の金箔すべてがそうなっていた。江戸時代のものだけである。明治に作られたり、大正、昭和初期のものは無事であった。
卓が虫眼鏡を持ってきてのぞくと、驚いたことに、その穴はただの穴ではなく、虫の形をしていた。
「なんでしょう、これは」
美助もこれには声がでなかった。人間の仕業ではない。そのとき卓が部屋の障子を這っていた金の虫のことを思い出した。
「師匠、ちょっとお話があります、私の部屋にきていただけませんでしょうか」
美助はいぶかしげに卓を見た。卓の困惑した顔は初めて見るものであった。
美助が部屋に行くと、卓はきちんと整理されている机の上の小さな薬瓶をとると、虫眼鏡とともに美助にわたした。
美助が瓶の底にある金色の粒を虫眼鏡で見て驚いた。死んだ金色の虫である。
「これは、あの金箔の穴と同じ形をしているじゃないか、どうしたんだ」
卓はこの一月、毎日のように障子の桟にこの虫が行列をなしていたことを話した。
「信じられんことだ、ともかく金箔から金の虫がでてくることなどあるわけがないが、といって、あの金箔に一様にこの虫の形の穴など開けることは人の手ではできない」
「あの金の虫はどこからきたのか不思議でした。まさか、あの金箔の中から出てきたとは不思議です、それにどこに歩いていったのでしょう」
「一階から二階に上がり、屋根伝いで外に出たとしか思えん」
師匠は卓にこの不思議な出来事は誰にも言わないようにと言った。
そのようなことがあった次の日、金沢の町で一人の著名な陶工の娘が死んだ。喘息による病死とされていたが、ある新聞には怪死と見出しが付けられていた。二十歳になる娘は体中に金粉がまぶされ、喉の奥まで金の粉がついていたという。窒息死の可能性も書かれていた。
卓は「加賀の闇の金箔貼り」の本を持って師匠のところにいった。
「師匠、この本は読まれましたか」
「いや、卓君、わしゃそういう素養がなくて読めない、何か大事なことが書いてあるのかな」
卓は内容の一部を美助に聞かせた。
「ほう、そんなことをやっていたのだな、最後の話の無経という金箔貼りは儂の先祖だよ、遊び人だったという話だからな」
「それで、師匠、昨日、あの有名な焼き物の先生の娘さんが金粉にまぶされて死んでいたのはご存じですよね」
「ああ、あの記事が本当なら、奇妙なことだ」
「その焼き物の先生は梲という人と関係がありませんか」
師匠はそれを聞くと、「あっ」と声を上げた。
「あそこ、あの陶芸家の先祖は、金を使った洋風焼き物を考えた者だと聞いている、まさか、うちにあった金箔からでた虫が、お金の仇討ちのために、あそこの娘を殺したというのか」
卓は師匠の言葉に返事ができなかった。
昔の職人たちの執念というものが、今の芸術を生み出している。自分はそのような執念をもてるだろうか、卓は自問していた。
金の虫
私家版 金幻想譚「金箔虫 2019 一粒書房」所収
木版画:著者


