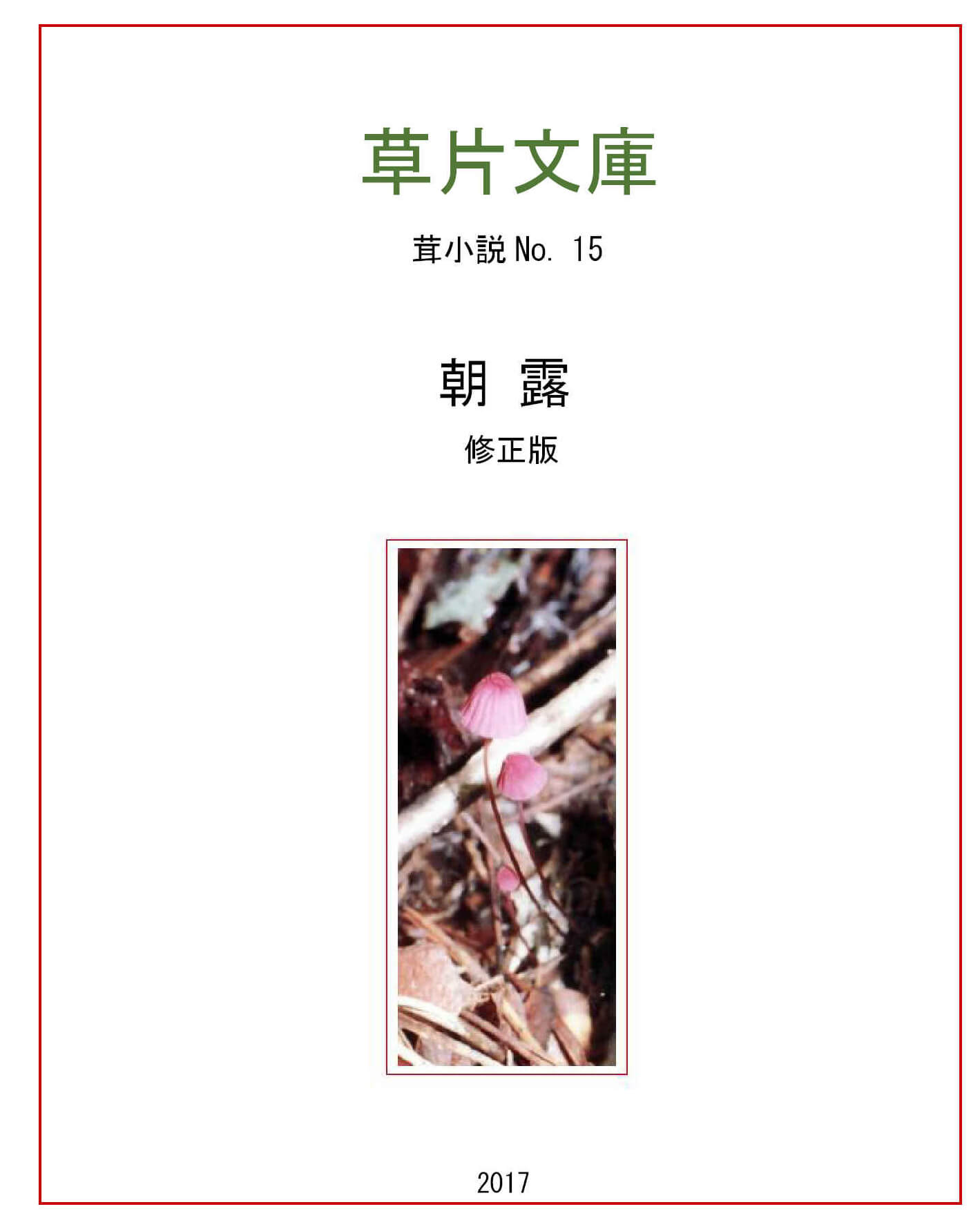
幻茸城2-朝露
茸と鼠のファンタジー「幻茸城」の第二序章です。
朝靄の中、古びた城の庭先で、小さな赤い茸が二つ、霜柱の花を愛でている。
霜柱の葉からきらきら光る露が、ピンク色の針金落葉茸の傘の上に落ちた。
雫は玉になって、傘の縁に垂れ下がった。朝日が当たって、水晶の様に輝いた。
小さいほうの赤い茸が霜柱の露に気がついた。
「ほら、きれい、きれい、乳(ちち)姫のようやわ」
赤い茸は隣の少し大きな赤い茸に言った。
乳姫は笑いながら、「玉姫はなんでもきれいというのね」と答えた。
露が緋色のチャワンタケの中に落ちると、珠になって中をくるりとひと回りした。
玉姫が喜んだ。
「玉姫のように元気な朝露ですこと」
乳姫が笑った。
茂みをつくっていた霜柱の葉から一斉に朝露が落葉の上に落ちた。
朝露は蟻の通り道に集まると、二人の姫の前に流れてきた。
乳姫と玉姫はかがむと赤い傘を流れに浸した。
「おー冷たくて気持ちのよいこと」
「ほんに」
二人の姫は露を傘の襞に吸い込んだ。
「この露は甘いなあ」
「ほんにほんに」
赤い茸たちは寄りかかって、露の朝餉(あさげ)を楽しんでいる。
「おや、蜘蛛のお兄さんが来る」
赤い茸の脇に折れそうな細い足を大儀そうに動かして、座頭虫がやって来た。
「朝露のごはんかね、かわゆいのう」
座頭虫は、二つの赤い茸の傘に足を乗せた。
乳姫と玉姫は傘を寄せ合って笑った。
「兄さん、今日は何処へ」
「ちと、やぶようで」
「連れてってはくれまいなあ」
「ふーむ、わしゃ、この足だからなあ、二人は無理じゃなあ」
二つの小さな赤い茸は、残念そうに首を垂れた。
座頭虫の兄さんは二つの茸が大好きだ。
「よっしゃ、弟を呼ぶとするさ」
座頭虫は長い足を踏ん張ってからだを上に下にと動かした。それは周りの空気を震わせる。仲間に『来てくれよ』の合図だ。
朝露が一滴生まれるほんのちょっとの間に、座頭虫の弟がやって来た。
「あら、久しぶり」
小さな赤い茸は、座頭虫の弟に挨拶をした。
座頭虫の弟は恥ずかしげに、「おはよう」とだけ言った。
「この子達を、庭の外れの、池の辺(ほとり)に連れていってやろう」
座頭虫たちは赤い小さな茸を、枯葉の間から持ち上げてお互いの背中に乗せた。
乳姫と玉姫は初めて高いところから庭を見た。
二匹の座頭虫はゆっくらゆっくら歩いていく。
赤い茸たちも上下に揺れる。
「おお、目が回る」
乳姫が弟の座頭虫の背ではしゃいでいる玉姫に声をかけた。
「玉姫、枯葉の上を見てくださいな、団子虫の子どもが、ほれ、丸まって駄々をこねている」
玉姫が下を見ると、団子虫の子どもたちが、お母さんに叱られて丸まっている。
「どうしたの」
玉姫が座頭虫の上から声をかけた。
団子虫のお母さんが見上げて驚いた。
「おや、赤い茸のお姫様たち、蜘蛛の背中に乗っかっておでかけかね」
「そうなの、池の辺に行きますの」
二匹の座頭虫は団子虫の前でからだを低くした。
「お楽しみね、あたしゃ、ほとほと、この子たちに手を焼いてね」
「どうしましたの」
「いえねえ、この子たちが、あの寒(かん)葵(あおい)の若葉を食っちまったのさね、茎に登って、葉っぱをなめて、みんなだめにしちまった」
「食べちゃったの」
「そうなんですよ、今、しっかり叱ったの、あの寒葵の花は団子虫の病に良く効く大事なものなのよ」
「でも、来年にはまた、葉が出ますでしょう」
「ええ、でも、花が咲かなくなっちまったかもしれないでしょう、だから叱ったの」
丸まった団子虫の子どもたちが、そうっと顔を出して、へへへと笑って、また丸まると、コロコロと、転がって逃げていく。
「あ、あの子たちは、しょうがない」
母親の団子虫は、たくさんの足を一生懸命動かして追いかける。だけど、転がるほうが早い。母親も丸くなると、「こらーまてー」ごろごろと、追いかけていった。
二つの茸は声を上げて笑った。
「さて、お姫さんたち、いくぞ」
「あい」
座頭虫はからだを持ち上げると、また歩き出した。
「落ち葉の庭を上から見るのははじめて、ほら、あそこに、カタツムリの赤ちゃんが歩いている」
「ほんに、ゆっくりね」
透明の殻を背にしょって小さな小さなカタツムリが、湿って地面に張り付いている赤茶色の柿の葉の縁を歩いている。
カタツムリの子どもが、キセル貝のおじいさんに「おはよう」と言っている。
乳姫が座頭虫の上から、
「ちゃんとご挨拶ができるの、えらいのね」
と声をかけた。
カタツムリの子どもは透きとおった小さな目をきょろきょろさせて、声の主を探した。
「どこにいるの」
キセル貝のじいさんが、「ほれ、上をごらん」と教えている。
カタツムリの子どもの目が上に向いた。
「あー、赤い茸の姫様だ、おはようございます」
「おはよー、キセル貝のおじいさんもおはよう」
二つの赤い茸は声を合わせて言った。
キセル貝のじいさんもカタツムリと同じように角を出して、
「ああ、おはよう」
と声をかけた。
「どこいくの」
カタツムリの子どもが聞いた。
「池の辺に行くの」
「いいなあ、僕も乗りたいな」
座頭虫は、
「いいとも、こんど乗せてやるよ」
と返事をして、長い長い足を前にだした。
茸の姫たちは手を振った。
池の水際にはガマの穂綿がたくさん生えている。
殿様蛙が水面から半分顔を出して大きな眼で見ている。
「ここで降ろしてくださいな」
玉姫が言うと、座頭虫がからだを地面につけた。
乳姫も降りて、仲良く岸辺の石の脇に並んだ。
「姫さんたち、おれは、用事に行くけど、帰りにまた乗せていってやろう、弟はまた呼ぶから」
「あい、ありがとう、お願いしますわ」
赤い二つの茸は、座頭虫に礼を言った。
座頭虫の兄は池の周りを回って、石塀の穴から外に出た。
弟はもと来た道を戻って行った。
「お池って、こんなに広いのね、ほら、水(あめ)馬(んぼ)が」
水馬が、すーっと、ガマの穂綿の周りの水面を滑っていく。
「どうやって水に浮いているのかしら」
それを聞いた、殿様蛙が、水からからだを持ち上げた。
「手足の裏に毛が生えているのさ」と言った。
乳姫が蛙にたずねた。
「毛があると水に浮くの」
「そうは簡単にはいかないが、あいつらはそれをうまく使っている」
そこへ水馬がやってきた。
「ほい、赤い茸じゃないか、水の上を散歩してみるかい」
そう言って、前足をあげてみせた。そこに毛がたくさん生えていた。
「うれしー、行きましょう、乳姫」
「でも、どうやって」
「背中にお乗り」
水馬は座頭虫より小さいくらいだからとても無理であろうと乳姫は思った。
「小さいけど大丈夫さ、友を呼ぶよ」
「それじゃ、水馬の兄さんお願いします」
乳姫がそういうと、水馬は前足を水面に打ちつけた。
それを合図に、もう一匹の水馬がやって来た。
二匹の水馬は羽を広げて空中に舞うと、茸の姫様のところに飛んできた。
「あれえ、飛ぶこともできるのねえ、うらやましいわ」
赤い茸が背に乗ると、水馬は空を飛んで、池の真ん中に下りた。
そのまま、すーっと水面を滑走しはじめる。
「気持がいいわあ」赤い茸は喜んだ。
水馬が通ると浮き草が揺れて、蓮の葉の上で居眠りをしていた小さな蛙が眼をあけた。
「あ、茸が泳いでいる」
寝ぼけ眼をこすっている。
「ほー水馬で遊覧かい」
蛙はそう言うと、また寝てしまった。
「風の気持ちの良いこと」
茸の姫たちは、見るものすべてが初めてで有頂天だ。今まで会ったことのない生き物たちがたくさんいる。
そんなとき、いきなり、水の中から、大きな生き物が顔を出した。おかげで水馬がひっくり返って、茸の姫様たちが空に舞まった。
「あれえええ、たすけて」
茸の姫様たちは水の中に落っこちた。
しかし、赤い茸たちは沈まない。ぷかぷか池の上で浮いている。
「おやあ、こんなところに、茸がいるぞ」
大きな生き物は、鮒の子どもたちだった。
鮒の子は赤い茸を見つけると、そばによってきた。
「なんで、こんなところに茸がいるんだ」
鮒の子は茸の姫様を口でつついた。
「こそばゆい」
茸の姫様はくすぐったくって縮み上がった。
一匹の鮒の子が乳姫を突き上げて、水の上から空に飛ばした。
「きゃー」
赤い茸が空に舞い、水に落ちる瞬間に、別の鮒の子が空に突き飛ばした。
玉姫が空に飛ばされた、もう一匹がそれを受けてまた空に飛ばした。
「茸の玉突きだー」
鮒の子どもたちは茸の姫様たちを空に飛ばして大喜び。
「あれえー」
茸の姫様は空中から池を見た。
東のほうで赤白まだらの大きな魚が泳いでいる。あれが鯉だろう。きれいだなあと思っていると、水面に近づき、また、ポーンと空に舞った。
その時、池に落ちることなく、二つの茸は空に浮かんだままになった。
「あれ、どうしたのかしら、玉姫ええ」
「乳姫さまああ」
茸の姫様たちは、いつの間にか秋(あき)茜(あかね)の背中に乗っていた。
「茸の姫様、今度は空を散歩したらいかが」
茸を乗せた秋茜はスイーっと池の上を飛んだ。
水面から鮒の子どもたちが鰭を振っている。
「ばいばい」
赤い茸たちも傘を振った。
「ありがとう、蜻蛉の兄さんたち」
「どうかね、城の外に出てみようじゃないか」
「嬉しいー」
秋茜は塀の上を越えて、城から離れると、林の中にある神社の境内に向かった。
神社の屋根が日に映えて輝いている。
「すてきー」
神社に巣くっている鬼蜘蛛が、秋茜たちに気がついた。
「おーい、茸を何処に運ぶんじゃい」
「散歩じゃあ、鬼蜘蛛のおっさんよ、茸は食わんよな」
「いやさ、どんな味だろうと思ってな」
「意地汚いこった」
蜻蛉は大きな蜘蛛の巣をよけて、急降下すると、野菊の葉の上に止まった。
乳姫が社の礎の脇で動くものを見た。
「あ、座頭虫のお兄さんのよう」
玉姫もうなずいた。
「ほんに、こんなところで」
秋茜は「知り合いかい」とたずねた。
「ええ」
「そいじゃ、あそこで降ろそうか」
「あい、お願いします」
秋茜は紫色の野菊から飛び上がると、すいーっと、社の脇に急降下した。
二つの茸を下ろすと、「それじゃ」と舞い上がった。
「ありがとう、蜻蛉の兄さん」
茸たちは礼を言った。
びっくりしている座頭虫に、茸たちは池での出来事を話した。
「ほう、そりゃあ、面白かっただろう」
座頭虫の兄さんは笑顔を茸たちに向けた。
「そろそろ、帰ろうと思っていたところだ、ちょうどいい」
そこへ、小さな座頭虫がわさわさと、よってきた。赤い茸はちょっとびっくり。
座頭虫の兄さんは恥ずかしそうに言った。、
「俺の、子どもたちだ」
座頭虫の子どもたちは赤い茸たちに「こんちわー」と声をそろえた。
「あれえ、兄さんの子ども、こんなにたくさん、こんにちわー」
乳姫と玉姫は驚いてますます赤くなった。
「これは、かみさん」
白い大きな座頭虫が現れた。
「あれえ、はじめてお目にかかります」
茸たちはお辞儀をした。
座頭虫は「庭の茸の姫様たちだよ」と白い座頭虫に言った。
座頭虫のお嫁さんは、つぶらな目を赤い茸たちにむけてお辞儀をした。
「今日から、お城の庭に住まわせてもらいますで、ほんによろしゅう」
「茸の姫様、俺とかみさんに乗りな、帰ろう」
赤い茸は、座頭虫夫婦の背中に乗ると、ゆっくりゆっくりと、城の庭に向かった。
座頭虫の子どもたちはぞろぞろと後をついてくる。
石垣を登って、石塀の穴をくぐると、池の脇に来た。
池の中から、蛙や水馬や鮒の子たちが手を振った。
「お帰り」
庭に入ると座頭虫から茸たちが降りた。
二つの茸は傘をちょっぴり広げた。
「ありがとう」
こうして、いつもの庭石の脇に乳姫と玉姫が戻った。
あくる朝、霜柱の葉から露が落葉に落ちるのを見て、
「きれい、今日もとてもきれい、乳姫様」
「きれいね、玉姫」
いつものように、二つの茸は朝露に傘を浸して顔を洗った。
蟻の道にできた朝露の小さな流れに、座頭虫の子どもたちが集まった。
露で顔を洗うと赤い茸に挨拶をした。、
「茸の姫様、おはよう」
「お父さんとお母さんはどこに行ったの」
乳姫が聞くと、一番大きな子どもが答えた。
「今日は、お城の座頭虫にご挨拶に行きました」
「お留守番ね」
「はい、茸の姫様にお庭のことを教わりなさいって言われました」
「あれ、玉姫どうしましょう」
「ほんに、私たちが教えることなど何もないのにねえ」
「茸の姫様は歌が上手だから教わりなさいって言われました」
「あら、座頭虫の兄さんはきっと、私たちの傘の音(ね)のことを言っているのね」
「やってみて」
座頭虫の子どもたちが二つの赤い小さな茸を見た。
茸の姫様は茸の傘を震わせて、小さな小さな音(おと)だったけれど、コロコロと鈴を転がすよう。茸の音は庭の草草の間をただよって、お城の庭に広がった。
座頭虫の子どもたちは、音に合わせて小さくからだを揺すった。
「あ、父ちゃん、母ちゃんだ」
お城の脇から城にすむ座頭虫たちを連れて、子どもの親が庭にやって来た。
「姫様、いい音だね」
座頭虫たちは子どもの後ろで耳を澄ました。
赤い小さな茸の姫様は、懸命に傘を震わせた。
城に住む女郎蜘蛛や鬼蜘蛛たちもやって来た。
赤鼠の子どもも遠くから聞いている。
茸の姫様たちの傘から赤い煙が立ち上った。胞子だ。
胞子は虫たちの回りを包むようにして漂い、暖かい匂いを撒き散らした。
やがて、小さな赤い茸の姫様たちはもっともっと小さくなって、庭石の脇で消えていった。
しばらくの間、動かずにいた座頭虫たちは、
「さよなら、姫様、来年も出ておいで」
そう言うと朝の食事に出かけていった。
「幻茸城」(第一茸小説)2016年発行(一粒書房)所収
(短編を一つの物語に編纂)
幻茸城2-朝露


