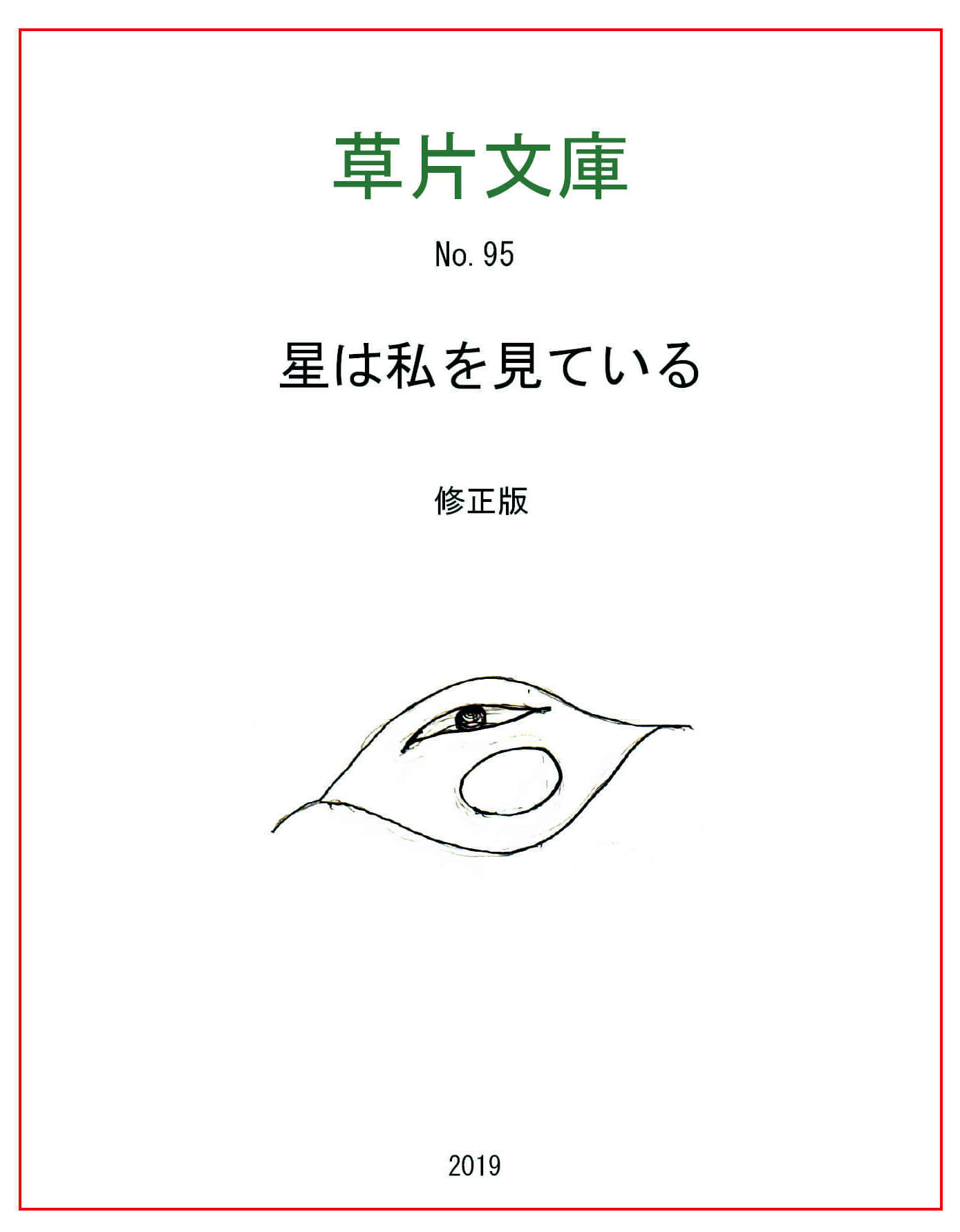
星は私を見ている
星幻想SFです 縦書きでお読みください。
太陽の光を浴びるとからだがしゃんとする。
月の光を浴びると精神が澄んでくる。
それでは無数にある星の光はどんな働きを持つのだ。からだのどこにどのように効くのか、星星の一つ一つによって違うのか。北極星は頭のてっぺん、アルファケンタウリは前頭葉か。
からだには8兆の細胞があるという。星の数はいくつだ。銀河系の中の恒星といわれる星だって2000億あるという。きっと星の数と人の細胞の数は同じじゃないか。
みんな晴れた日に夜空を見上げて、こんなに星が見えると感嘆の声を上げる。
なにがきれいだ。誰もあの星の目的を知らない。
あそこに棲んでいる奴のことを知らない。
雨の日はともかく、曇りの日でさえ、ちょっとの隙間があれば、のぞいているんだ。あの限りなくある星から、俺を、あんたをのぞいているのだ。
家なんてそんなものがあっても意味がない。あの何億光年も向こうから見ている目にとっちゃ意味がない。素っ裸の俺たちを見ているのである。
すっぱだっかっていやらしい。
そんなんじゃない、脳の中を裸にするんだ。それがどういうことかわかるか、とっても怖いことなんだ。
今まで人間は何人死んだのであろう。誰か計算した人がいるだろうか。生まれてきた人は必ず死ぬ、同じ日に死ぬとすると、毎日生まれた数だけ死んでいく。要するに人が一体いままで地球の上に何人いて、どのくらい土に返っていったかだ。
どこへ行くか知っているかい。
冥土にいく、地獄にいく、極楽にいく、そんなもの生きている人が作ったものだ。
本当はね、星にいくんだよ、死ぬと星をつくってそこに行くんだ。死んだおやじやお袋は何億光年の向こうの星の一つに主人としてとっついているんだ。それで、地球を見ている。
星は保死なんだ。
星を見上げたとき、あいつが見てら、と笑っているんだよ。
奴らにとって、それしか楽しみがないのだよ。
俺が死んだら、星になんかいきたくない。
星がのぞいている証拠があるかって、あるさ、昨日だって、雲の合間から、小さな光が、俺のおでこに射していた。俺には見えた。だが、どの星だかわからない。だから、誰がのぞいていたのか知らない。だが、俺の脳を覗いていたことは確かだ。
昨日、酒を飲んで、家に帰ってきて、寝台に倒れ込んだとき、天井から、キラリと、俺のおでこに光があたった。俺の脳の中を覗いているんだ。
そいつらはみんな死人だ。
え、ほかの星に生き物はいないのかって聞くのかい。
いないんだ。死んだ生き物は星を作るんだ。だから作ったそいつしかいない。宇宙で唯一地球に生きた生き物がいる、犬や猫だって、しねば自分の星にいく。星っていうのは地球の生命の死んだあとの生活の場なのさ。
137億年前に宇宙ができて、46億年前に地球ができて、35臆年前に細菌ができる、それが遺伝子を増やす装置、いわゆる生き物の始まりであって、細菌の個体の死が始まる、とすると、そこから星が生まれることになる。
矛盾じゃないか。
それは俺たちの宇宙の物理の法則でしかない、生命ができて、やっと星の存在も意識される、生命がいない時期は、地球もほかの星も、宇宙も他の法則の中で存在していたんだ。生命がその存在を意識したときから、地球は46億年前にできたことになったんだ。
じゃあ、細菌が地球を意識したのか。
もちろん、細菌の意識は、人の意識とは違う。大脳新皮質で生じる意識と、化学反応だけで生じる意識は同じはずはない、しかし細菌の身体中の化学反応は地球を意識している。
それはいいとしても、細菌が他の星を意識できるか。
生きているときは出来なくても、死ぬとつくった星に行くからそこから星を意識をしはじめ、地球を見ている。
細菌も死ぬと一つの星になるとすると膨大な数の星が存在しなければならない。
そうさ、星はいくらでもできる。作る場所が足りなくなったるとその場所、宇宙は広がっていく。宇宙は膨張する。生命体と星は繋がっているんだ。
だけどなぜ、地球を見ているんだ。
それによって、我々の宇宙の物理の法則が存在し得るからだ、死んだ生命体は星の主人になることで、生きていたこの宇宙を守ろうとしているんだ。
それで、なぜ地球が守れるんだ。
星は瞬くことで、死んだら星にくるんだよと人に教えてるんだ。
だけど誰一人として人間はそんなことを知らないじゃないか。知っているのはあんただけだ。
確かに誰もそんなこと言わないな。
星が見ているのはあんただけなんだ。
そんなことはないだろ、数え切れないほどの星がなぜ俺だけみる必要があるんだ。
あんたがこの世の法則に必要だからだ。
おかしいじゃないか
星の光が当たったらあんたは死なない。
どういうことだ。
死んで星にこられては困るからだ。
俺が行くと星はどうなるのだ
あんたがやってきた星は消滅して、それが他の星に連鎖を起こす。星が消滅する。なにもなくなる。
そうしたらどうなる
無だ
しかしこの世が現実にある。無から有が生まれたなら、無というものは無でなく有というものがあることになる。矛盾しかない。星はいつも自分を照らしている、俺が死ぬのを待っている。
そんなことはない
いや、待っている、それは無になるのを望んでいるからだ。ところで俺は誰と話をしてるんだ。
あんたのおでこを照らしてる奴だ。
星の光か。
そうだ、よく死んだら星に行くことに気がついたな。
星の光がおでこに当たったときからだ。
死んだ地球の生き物は星に瞬きをはじめさせるが、そこにはいない。
じゃあ、星から死人が地球を見ているのじゃないのか。
ああ、星そのものがあんただけを見ているんだ、さっき言ったろう、あんたが死んだらこまるからだ。
どうして
無になるからだ
なぜ無になったら困るんだ
無から有になったか、すなわちこの世ができたか誰も知らない。地球の生命がそれを解決する生き物になったときまで、無になっては困る。
それでなぜ星が俺を見ているんだ。
前も言ったが、あんたが死んで星ができてその星に行くと、その星が溶けて、やがてすべての星がなくなり、無になる、星の瞬きはあんたを照らして、無限に生きていてもらわねばならないのだよ、ギルガメッシュ、あんたしかこの世がなぜできたか解明できないからだ。
星は私を見ている


