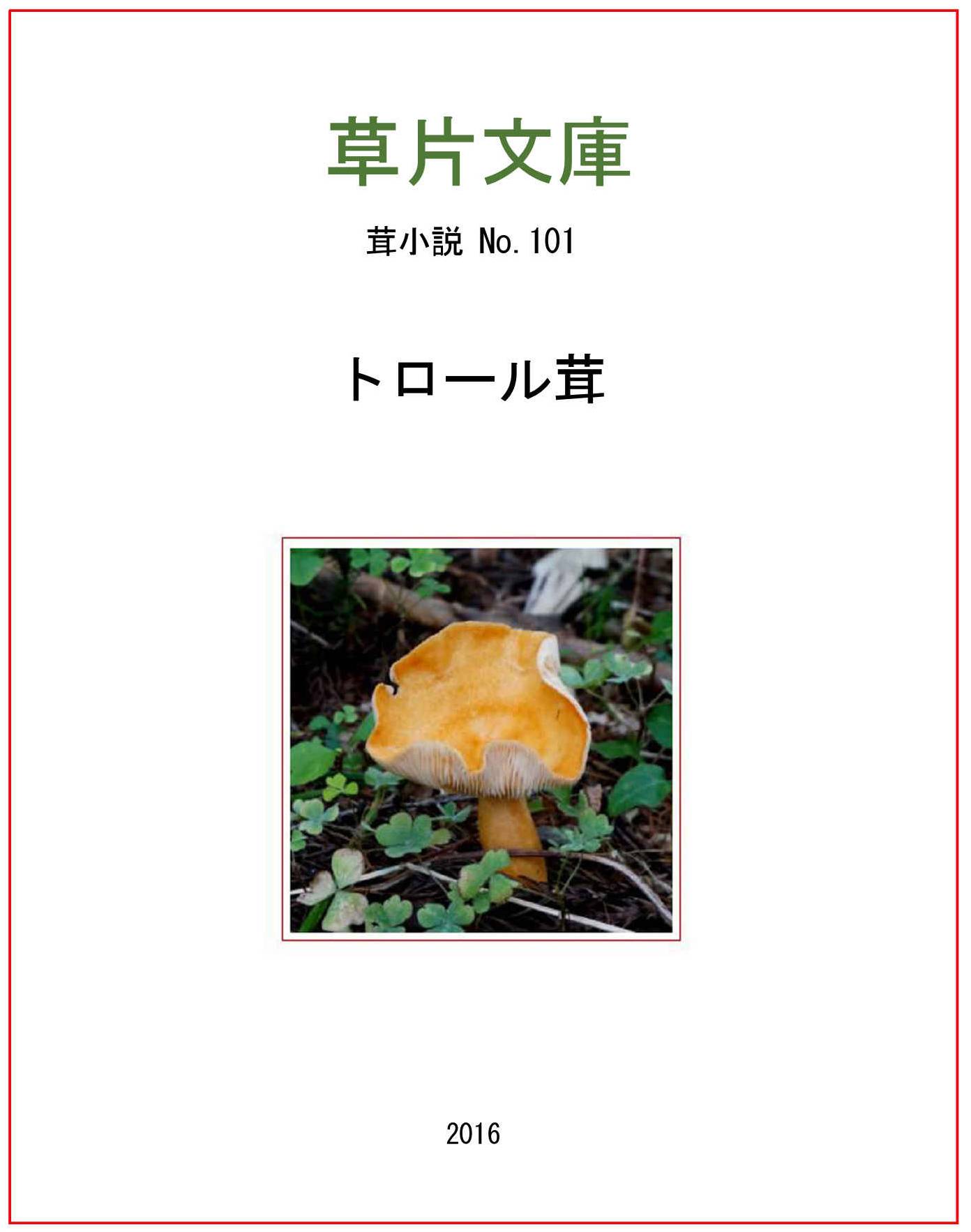
トロール茸
ノールウェーのガイランゲルを訪れた時のことである。
有名なガイランゲルフィヨルドの奥にある名勝地で、大手旅行業者の北欧四カ国ツアーの目玉といっていいところだ。
宿泊することになったホテルの窓からは雄大なフィヨルドを見渡すことができた。
ホテル前には小さな滝もあり、それに沿って海に向かって降りていく小路がある。
夕食後、外灯の点いているその道をぶらぶらと下っていくと、木陰から猫ほどの大きさのものが私の前に飛び出してきた。薄暗がりでなんだかわからず、ちょっと飛び上がってしまった。逃げなければいけないかと来た道を引き返そうとすると、その生きものは、思わぬ速さで私の前にまわって立塞がった。
四足動物ではなかった。少し離れたところにある街灯の弱い光がその生きものの顔を照らし出した。
トロール、私の頭の中にはその言葉が浮かんできた。
オスロから電車とバスを乗り継いでここにくるまでに、食事をしたところ、土産物屋などいたるところで、様々な形をした妖精、トロールの人形が売られていた。伝説のただの人形かと思っていたのだが、いま目の前にいる。
目の前のトロールは背丈が私の腰までしかなく、皺くちゃの老人であった。彼は尖った鼻を私のほうに突き出して見上げた。
「だんなさん、これ」
彼は両手で抱えあげ、紫色の茸を突き出した。
私はノールウェー語ができないが、なぜか彼の言葉が分かった。
日本語で「それはなに」と聞き返すと、彼は「紫茸」と答えた。どうして私に差し出すのか分からず、ただ見ていると、さらに「あげる」と言った。
「どうして」
「あんたさんの胸が痛んでるからさ」
昨日から確かに空咳がでる。
「どうして分かったんです」
「あんたの足音さ、路をすすんでいく時、ほらそこの苔を踏んだだろ」
トロールは私の足元に生えている、紫がかった苔を指差した。日本の苔とは違い、土にへばりついていて植物らしくない。
「その苔は踏んだ人間のからだのコンディションが分かるんじゃよ、わしらに連絡をしてくる、それでわしがこの茸をもってきた」
彼の言っていることはなぜか信じられた。
「タック」
唯一知っているノールウェー語でありがとうと言い、紫茸を受け取った。
「これを食べるといいのかな」
「ああ、いろんな病に利くよ、少しずつ食べて、病気が治ったら、とっとくといい、いつか役に立つよ」
「ホテルに帰ったら食べよう」
「いや今じゃなくて、あんたさんの国に帰ってからな」
「だけど、なぜ親切にしてくれるのです」
「わしらは人間を助けるためにいるんでさ」
彼はそう言うと、ポッと消えてしまった。というより、風のような速さで木の間に走っていく後姿がちらりと見えた。
手元には紫色の茸が残されている。それはトロールが今しがた目の前にいたことの証である。もっといろいろな話をしておくべきだったと思ったが遅かった。
私は下には降りず、そのままホテルに引き返した。
ホテルに入ると、ロビーにいたホテルマンが愛想よく私に挨拶をし、左手に持っている紫色の茸をみて、「珍しい茸をとりましたね」と英語で声をかけた。
「珍しいのですか」私も英語で答えた。
「はい、見たことがない」
「毒でしょうか」
「さあ、でもきれいですね」
そう言って、彼はカウンターの中に入って行った。トロールにもらったとは言えなかった。
私は部屋に戻って、スーツケースの中に紫色の茸をしまった。
ツアーは全部で十六人、夫婦での参加が四組、三人家族が一組、残りは私のように一人旅である。私はもう七十になろうとする年金生活者である。ただ、年に一度このようなツアーに参加して英気を養っている。六十で退職し、いろいろなツアーに参加したが、今回のように和気あいあいと楽しめるのは始めてである。いつも誰かが病気になったり、文句を言ったり、ちょっとしたことだが、気にかかることがあったりして、どこか不完全だったが、今回のツアーはそういうことがない。
朝食の会場で、一組の夫婦がサラダをつつきながら話している。
「この国はトロールの国ね」
「うん、ノールウェーはトロールのほうが多くすんでいるんじゃないかね」
「そうね、もし土産物屋のトロールが動き出したら、ノールウェー人より多くなるわね」
「夜になると動き出しているさ」
「それじゃ、ノールウェーのトロールは森に住んでいるのじゃなくて、土産物屋にすんでいるのね」
「そういうことになるな」
「ははははは、ほほほほほ」
他愛ない会話であるが、トロールがいるおかげでこういう平和な会話ができる。
こうして、他のフィヨルドを見たり氷河を見たりして帰国した。
「北欧の旅はどうだった」
古くからの友人が家に来てくれた。家内を亡くして私は独り身である。
「トロールに会ったよ」
「妖精か、よかったかい」
「とても感じのいい爺さんだった」
私は買ってきたトロールの人形を見せた。
「一つ目なのか」
「いや、会った爺さんの目は二つあった、顔が一番似ているのを選んだら、一つ目のトロール人形になっちまった」
「あんたも若いね、トロールに会えるなんて」
「やっぱり信じてないんだな」
「おいおい、ほんとに信じているんか」
「いやいや、まあ、そんなとこだ」
それから、ノールウェーの自然、フィンランドのヘルシンキ、スウェーデンのストックホルム、デンマークのコペンハーゲンの比較話をして、出前の寿司を二人でつまんだ。旅から帰ってきて、やはり寿司が食べたくなり、一緒に食べてくれと、彼を呼んだのである。
「むこうはビール、うまかったよ、だけど高いね」
「みんなデンマーク製だろう」
「スウェーデンのもあったよ」
友人は何度もヨーロッパ旅行をしている。そういう仕事をしていたからだ。北欧のこともよく知っていて、今回のツアーを勧めてくれたのは彼である。彼はヨーロッパの主要な国の言葉を話せるのでツアーではなく一人旅が出来るが、私は仕事柄、せいぜい英語の片言である。
「俺も北欧には何度か行ったけど、まだトロールには会ってないな、そのトロールとは話をしたのかい」
「うん、茸をくれたんだ、俺の胸に悪いところがあるので食えってさ」
私は萎びた紫色の茸を彼に見せた。
「どうしてくれたんだ」
「俺が歩いたところの苔が俺の体の状態を感知して、トロールに言ったそうだよ」
「それは面白い話しだね」
「トロールは人間のためにいるんだと言ってたな」
「それで、調子は悪いのかい」
「いや、とくにね、空咳は出るけど、昔からだからね」
「見てもらったほうがいいんじゃないか」
「そのうちいくさ」
「俺はこの間行ったら、前立腺肥大だそうだ」
「男ならみんななるだろう、俺もその気があるって言われている」
「前がん状態だそうだ、様子見だよ」
「この茸食べてみるかい」
「いや、いいよ、医者に任せてある、心配していないよ、いざとなりゃとっちまえばいいんだそうだ」
それから、しばらくして、空咳が少し多くなり、坂道を登るとちょっと息切れがした。それでかかりつけの医者に寄った。久しぶりである。医師は喉を覗き込み、
「喉はよさそうだけどレントゲン撮っとこうか」と私をレントゲン室を指差した。
医者はできあがった画像を見ながら、
「ちょっと気になるな、大学病院紹介するから、行ってみてください」
とまじめに言った。この医者はいつもなんとなくちゃらんぽらんなのだが、見るところは見ていると信じている。その医者が冗談なしに言ったということはちょっと気になる。
「なんですか」
「いえね、これが、肺炎でなければいいんだけど」と、白くもやっとした部分を指差した。
こうしてその医者の出身大学の付属病院にかかることになった。
MRI検査をし、結局、細胞検査をした結果、癌らしいもが左の肺にあるということになった。
その若い医師は無表情で、
「早いほうがいい、とりましょう、一週間後に入院してもらいますから、手術の日はその後きめましょう」と言った。
「悪いんですね」
「大丈夫です、転移していないし、まだ早いし、取り易いところだから、取ってしまえば長生きしますよ」
これも味気なく言った。ただ、こういう風にさっぱり言われたほうが良いのかもしれない。
「癌は怖い病気じゃなくなりましたからね」
念を押された。
家に帰って、妹に電話をして、一週間後に入院することを連絡した。妹は大学病院の近くに夫と二人暮しをしている。二人の子どもは巣立っていていない。
「癌はこわくないわよ、そのうち入院の手伝いに行くわ、今日の夕飯、茸の煮しめよ、兄貴は茸すきでしょ、行くときにはつくっていくね」
その言葉で、トロールがくれた紫色の茸を思い出した。しなびていたが、記念にとってある。トロールが言っていたように、少しずつ食べてみようか。
その日から、三食ごとに、薬を飲むような感覚で、しぼんだ紫色の茸を削って食べた。おまじないのようなものである。味など分からない。
そして入院したのである。
「これから三日、検査と手術の準備をします」
医者は再度精密検査を私に施した。そこで驚嘆のというか、首をかしげた。
「癌がない」
医者は、検査室のチーフに電話をかけまくった。血液検査でも癌のマーカーに反応がなく、MRIの検査でも画像には影がなく、さらに細胞検査でも癌は見つからなかった。
「最初の検査のミスか、何らかの原因で癌がなくなったようです、入院の必要はありません、申し訳ありません」
私にはその原因が良くわかっていた。あれが効いたのだ。紫茸。それまでの費用は言われるままに払った。しきりに医師は恐縮していたが、彼にもお礼をもって行った。
「精神的なものが癌を減衰させることがあります、よほど信念がおありなのでしょう、これからの学問分野に精神神経免疫学という分野があります、端的に言うと、病は気からということの科学的分析学というのでしょうか」
と難しいことを言っていた。
私は棚に置いてあった一つ目のトロール人形に「ありがとう」と声をかけた。
私は残っていた茸を友人にあげようと思った。だが友人はそれを断った。
「俺はいいよ、まだ癌になっていないし、とっちまえば直るって言われていたから」
さらに、「あんたは、精神的に強いね」と医者と同じような感想を言った。
次の年、今度は一人でノールウェーのガイリンゲルをおとづれた。もう一度あのトロールに会いたかったからだ。お礼を言いたい。旅行業者を通して、同じホテルを予約した。
ホテルからでて、私は滝の脇の道をくだっていった。紫色の苔があった。ぎゅっと踏む気にならず、ゆっくりと足をのせた。
黒い影が現れた。目の前にはあのトロールがいた。
「よく来たね、茸が効いたんだな、あんたさん」
「お礼が言いたくて、きました」
「俺たちの使命だからな、お礼なんていいよ、人を助けると、俺たちそれだけ幸せになれるんでね」
「ノールウェーの人たちはみな助けられているのですね、羨ましい」
「いや、それが、我々を見ることのできる人だけしか助けられないのさ、大人のほとんどは我々の存在を信じてないからね」
「あの茸を探そうと思うのですが」
「それは無理だよ、我々しか採ることのできない茸だから」
「また、調子が悪くなったらもらいに来ていいですか」
「一人に一つしか渡せないんだ、だが、あんたさん、まだ残りがあるだろう、死ぬ前にあれを食べると楽に死ねるよ」
「それは嬉しい、トロールのいるノールウェーが羨ましい」
私はもう一度羨ましいといった。そうしたら、トロールが意外なことを言った。
「いや、ほら、あんたさんのところにもいるよ、わしらの仲間が」
「どこに」
「北海道にさ、蕗の好きなやつらでね」
そう言ってトロールはふっと消えてしまった。
「ありがとう」
そうだった、コロボックルだ、日本のトロールだ。日本に帰ったら北海道の旅に出よう。
ガイランゲルから帰国し、家に帰ると、残っている萎びた紫色の茸を仏壇の下の引き出しにしまった。
トロール茸
私家版 第九茸小説集「茸異聞、2021、一粒書房」所収
茸写真:著者:長野県北安曇郡白馬村 2016-9-12


