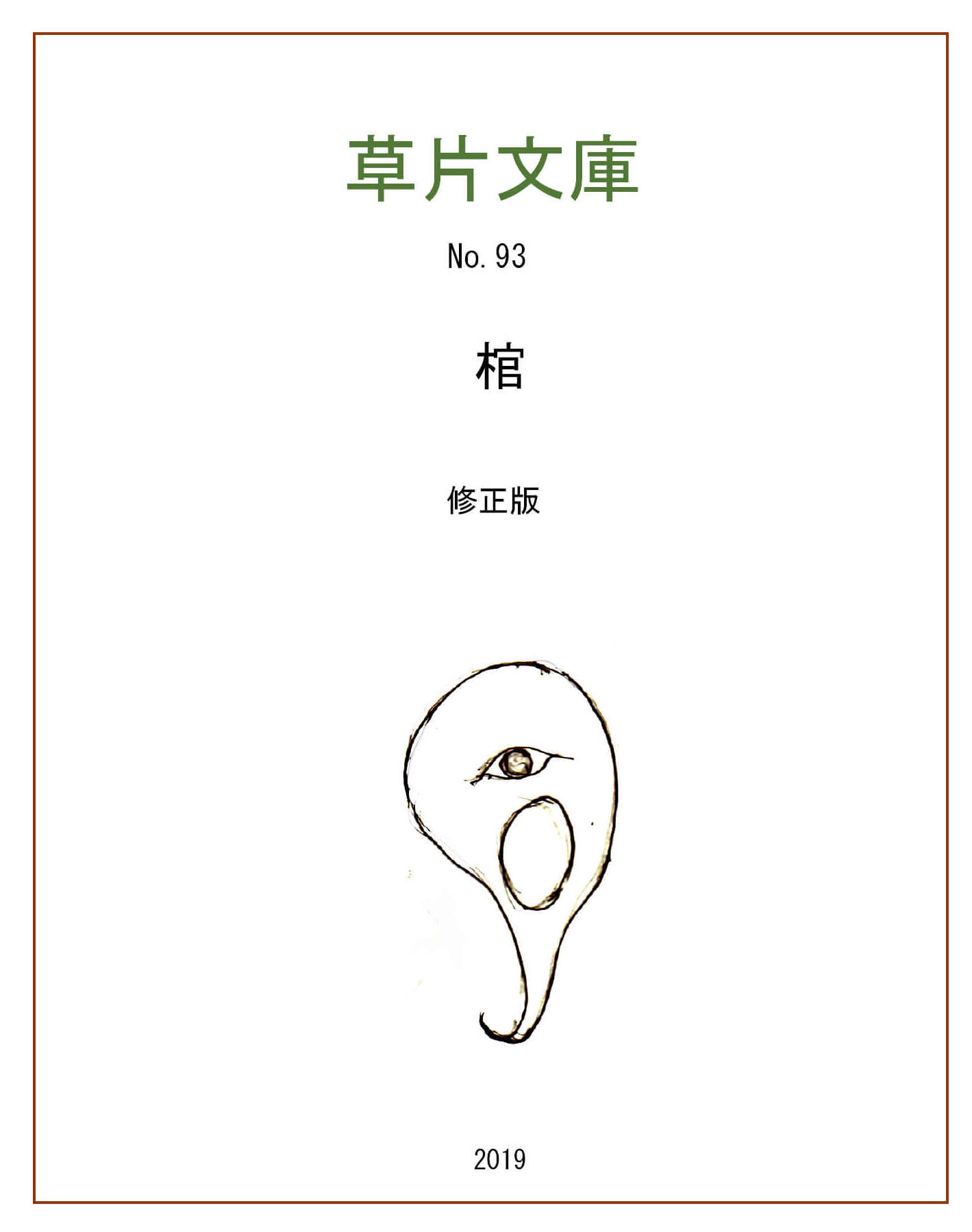
棺
奇妙な味のSF小説です。縦書きでお読みください。
昨日、一瞬のうちに未来が見えなくなった。人間というのは長い間変わらない環境に囲まれていると、ちょっと遠い未来の予測が無意識のうちにできるが、突然未来が変る大きな出来事に出くわすと、全く思考が停止するものだ。30年連れ添って、当たり前のように隣のベッドで寝ていた人がいなくなると、ほんの一日先の未来も予測できなくなり、黒い闇、黒い穴としか認識できない。今の私だ。
主人が脳動脈瘤破裂で帰らぬ人となった。退職したばかりなのに。
なにもできなくなった、子供のいない私を支えてくれたのは主人の妹だった。葬式のことも手につけられないでいるところを、彼女がすべてを取り仕切ってくれた。
病院の霊安室に駆けつけてくれた彼女は、
「葬儀社はどうする」とまず聞いた。
義理の妹は化粧品の会社を立ち上げ、今では年商一億の売り上げを誇っている。私もその会社のアドバイザーとして給料をもらっていた。まだ独り者である。
「今も病院の人に聞かれたのだけど、そんなこと考えてもいなかったので、主人の妹がきてから決めますと言ったところなの」
「そうね、兄貴がこんなにあっけなく逝くとは思わなかったものね、知り合いにちょっと変な奴だけど、葬儀社やっているのがいるからそいつでいいかしら」
「おまかせします」
「それじゃすぐ連絡する」
彼女はスマホを取り出した。
「すぐに車を回してくれるそうよ、遺体は葬儀社の安置室にはいることになる、その後はそれから相談しますって」
「なんて言う葬儀社」
「懐古社」
「病院にそう言ってきます」
私は病院の係りの人に伝えて、それまでに今までの支払いをすますことにした。
「私は廊下で待っているからね」
妹は霊安室前の廊下にある椅子に腰掛けるとスマホを再び取り出した。会社の誰かに指示をしているのだろう。彼女の頭のめぐりの速さで会社がもっている、と主人も言っていた。「あいつは宇宙人だよ」とも言っていたことを思い出した。
会計ですべてをすまして帰ると、もう葬儀社の人がきていた。黒い背広を着たひょろんとした頭のはげた男性が妹と話をしている。
「あ、彼が懐古社の社長、私の同級生よ」
大学のだろうか高校のだろうか、わからないがともかくよろしくとお願いした。
彼は甲高い声で、「お妹さんにはお世話になっています」と挨拶をした。
世話って何だろう、妹は葬儀社の紹介もやっているのだろうか。
「バンで来ていますので、お二人ともお乗りになりますか」
私も妹もうなずいた。
「懐古社はどこにあるのですか」
まだ場所も聞いていなかった。妹が答えた。
「青山よ」
住んでいるマンションから遠くない。病院からも近い。
私は遺体と一緒に後部に腰掛けた。妹は助手席に乗った。
懐古社にはすぐ着いた。青山通りに面した十五階建ての瀟洒なビルである。
車は地下駐車場に吸い込まれた。
「ここの地下二階に懐古社があります」
彼は乗ったまま車用らしい大きなエレベータの中に車を滑り込ませた。どうも車そのものにリモコンが組み込まれているようだ。エレベータに入ると運転手は運転パネルのどこかに指を当てて扉を閉めた。妹はと見るとスマホの画面を見ている。なんだかこの場所に慣れているようだ。
地下二階と言われたが、5分までは行かないと思うが、ずいぶん時間がかかった。かなり深い地下である。
車ごとエレベータから滑り出ると、前の広いエントランスに、二人の女性が待っていた。
我々が車からでると、女性が「これから安置室の方にご主人をお連れします」
と主人の乗った移動ベッドを引き出して引っ張っていく。
我々がついていくと、そこもかなり広い部屋で、棺がたくさん置かれていた。
係りの女性がいきなり「どの棺にします」と聞くので戸惑っていると、「失礼しました、まだお話ししていなかったようですね、葬儀の方法によって棺が異なります、と言ってもみな桧でできていて、内側は変わりがありません、葬儀方法を決めていただければ棺も費用も決まります」と改めて説明してくれた。
「どのような葬儀があるのでしょうか」
「星葬、月葬、深葬、鳥葬、魚葬、です、後は懐古的な葬儀で土葬と火葬があります」
星や月は今はやりの宇宙葬というものなのだろうか。
「星葬は星のかなたへ、月は月のあばたに着陸よ」
妹が私の考えを見透かしたように説明してくれた。
「深葬は海の底、深海に沈めます、骨を撒くのではありません、魚葬はごらんのように棺にスリットがあり海に沈めて魚に食べてもらいます」と係りの女性が言った。
鳥葬など私は聞いた事がない。棺に鳥の絵が描かれている。私がその棺を見ていると、妹が「昔はアンデスなどで、山の頂に死体を置いて鳥に食べさしたのよ」と説明してくれた「昔の映画、世界残酷物語にでてきたわ」とも言った。
なんだか恐ろしい葬儀だ。
星葬や月葬などロケットを使うとすると相当な金持ちでなければ無理だろう。先ほどから価格のことは教えてくれていない。どうも金持ちしか使わない葬儀社のようだ。心配になってきた。
「一番安いのでいいわ、主人はいつも葬式に金をかけるなと言っていたから」
それは嘘ではない、主人は死に対してとてもストイックだった。葬式なんていらん、黒服など着るなといっていた。だから普通の火葬でよかった。
「兄貴はそういう性格よね」
妹がフォローしてくれた。
「はいわかりました、それでは星葬にいたします」
聞き間違いかと思った、星に飛ばすなどいくらかかるのかわからない。
「それは、でも、宇宙に飛ばすのでは、とてもかかるのではないでしょうか」
私はあわてた。係りの女性は笑顔になって、
「いえ、星葬は一番お安い葬儀です、月葬は月に棺をおいてきます、深葬は海の海溝に静かに沈めなければなりません、鳥葬はそれなりの山に運ばなければなりません、魚葬も海に持っていきます。土葬は場所をとります、火葬は火葬場でやってもらいますが、いずれにしろ、棺は買い取ってもらわなければなりません、星葬は棺代がいりませんし、この場で星葬の棺に入っていただくだけですので、運ぶ手間もいりません、それで一番安いのです」
言っていることがよくわからなかったが「おいくらですか」
と聞いたところ、十万円ですとずいぶん安いことをいった。私は驚いて「お願いします」と言ってしまった。妹を見ると頷いている。しかし、どのような葬儀が行われるのか私は全く想像できなかった。
「いつ行いましょうか、友引だとか、大安とかこだわられますか」
「いえ、それはありません」
私は一人っ子で両親はもういない。子供もできなかった。主人の兄弟は妹一人でもう両親もいない。親戚筋で呼ぶ人は見あたらない。友人と会社関係だけだ。
「主人は葬式は家族だけがいいねと言っていたので、私たち二人だけだわ」
「それもいいね、兄貴の会社や友達関係は連絡先教えてよ、葬儀が終わったら、私の方からあなたの名前で手紙の用意をしてあげる」
「なにもかもすみません」
「こういうとき、喪主はなにもしないものよ、参列者に挨拶するぐらい」
本当に助かる。
「それでは、星葬でお願いします、葬式はしませんし、おそらく参列は私たち二人です」
と言ったとき、主人の特殊な友達のことを思いだした。
「すみません、ちょっと一人お呼びしたい方を思い出しました。北海道の方なので来るかどうかわかりませんが、連絡してみます。それからでいいですか」
「はい、棺に入れるまで霊安室でお預かりします、電話で連絡ください」
そう言うことで、とりあえず、マンションに帰ることにした。妹も一緒にくることになった。
タクシーでマンションに戻ると、主人の手帳からその友人の名前を見つけだした。私は結婚式のときに会っただけであるが、主人はインターネットができてからはかなりの頻度でやりとりをしていたようである。たまにあいつが新しい星を見つけたようだよと言っていた。中学のときの同級生で確か長身のおとなしそうな男性で、宇宙の研究者だと思った。北海道の大学でまだ星を眺めているはずである。
主人の携帯を開いたら彼の名前があった。
電話をかけるとすぐでた。甲高い声である。主人が死んだことを言うと、ちょっとの間があって、あんな元気な男がどうしてときいた。脳動脈破裂のことを言うと悔やみの言葉と、葬式のことを聞いてきたので、妹と二人だけの家族葬であることを伝えた。しかし、彼は声を落として、是非出席させてほしいと言うので、都合のいい日をきいた。
「その人知ってるわよ、子供の頃うちによく遊びに来たし、兄貴も彼の家に遊びに行っていた。ちょっと離れていたけど、よく行き来していたわね、おかしいのよ、そのころ彼のほうが運動が上手で、兄が数学が得意だったのよ、子供のころ教えっこしていた、大人になったら逆になっていたのよ、性格がずいぶん違ったから仲が良かったのね」
私は懐古社に電話をして、彼の都合のよい日を言うと、夜の八時はどうかと聞くので同意した。彼にも連絡すると、その日に来るということになった。
少し落ち着いたら星葬とは何をするのだろうと改めて疑問がわいてきた。
「ねえ、星葬ってなにをするのかしら」
義理の妹に聞くと「きっと姉さんが思っているようなものじゃないと思う」
「あの葬儀やさん、どうして知ったの」
「私のパートナー」
どういう意味だろう、主人と私は三歳違いだから、彼女は私と同じ年である。今まで、結婚相手だとか、恋人の話は聞いたことはない。
「葬儀社の仕事もしているの」
「いや、パートナーよ、仲間といってもいいかな」
どこで会ったのかまでは聞けなかった。
葬儀の日である。七時につくと、主人の妹はもう来ていた。
「遅くなりました」
「まだ一時間あるわよ、彼はまだ来てないわよ」
予定では間に合うはずである。
主人はまだ白い布に覆われてベッドの上にいた。
隣に白木の棺がおかれていた。何の変哲もない棺である。
係りの女性が「もう一人の方がいらしたら始めます」とお茶と和菓子を持って、言いに来た。
彼は八時調度にやってきた。
私の所にきて「遅くなりました、このたびは」までしか言わなかった。話すのは得意じゃなさそうである。研究に没頭して社会になじめない人である。
「久しぶりです、今日は遠くからありがとうございます、主人に会ってください」
そう言うと彼は俯いたまま「いや、お顔は見ないで帰ります」と言った。
私にはよく意味は分からなかった。北海道からわざわざきたのは顔を見るためでないのだろうか」
妹はうなずいて「そばにいてやってください」と言っている。
「前に会ったのは彼が出張で北海道に来たときですから、十年前です、そのとき彼はジンギスカンにかぶりついていました。うらやましいほど元気で、仕事も順調のようでした。その顔を頭の中にずーっと残しておきます。今の彼の顔を見てしまうと、それが壊れてなくなるようで」
私は想像力が欠如しているのだろう。彼の言う通りかもしれない。
「よろしいでしょうか」
妹がパートナーと言った懐古社の社長である男性が言いにきた。
私がハイとうなずくと、係りの女性が二人きて白木の棺のふたを開け、ベッドに寝ていた主人を覆っている布をとって中に抱え入れた。
主人の友人はちょっと離れたところから見ている。
私と妹は棺の周りに立った。白い布に包まれて主人の顔は生きているようにすっきりしている、寝ているだけのような錯覚に陥る。口の周りに触れてみると、髭ががさがさと指に触れる。死んでからも髭は生える。そう聞いたことがあっても涙が出てくる。生きているようだ。この人も会社のために一生懸命がんばって、やっと自分の時間がもてたのに。
髭に触っていてもきりがない。私は後ろにさがった。
「蓋を閉めます」
女性が蓋をのせた。ただそれだけだった。花もなにも入れなかったのは私が何もいわなかったからかと悔やんでいると、妹が「これからなのよ、一時間かかるわね」
どのようになるのか知っているようであった。
主人の友人は蓋が閉められると棺に近寄って、棺の周りを不思議そうに歩き回った。
「棺をこれからどうするのかしら」
火葬にするわけではなく、土葬でもない、とすると、主人はどうなるのか想像がつかない。私は聞いた。
女性が椅子をもってきて棺の周りにおいた。
妹のパートナーという社長がそばによって来た。
「これからご主人様は旅をなされます」そう言った。
死は冥土への旅である、その意味で言ったのだろうか。星葬であるからには宇宙に旅たつということなのだろうか。そんなことを考えていると、主人の友人の声が思いを遮った。
「オゾンの匂いだ、なんでしょう」
黙っていた主人の友人は棺の周りをゆっくり歩いている。
「これから星葬がはじまります」
係りの女性が彼の言葉を遮るように言った。
「火葬はしないそうですが、ご遺体はどうなるのでしょう」
主人の友人はなんだか腑に落ちない様子で私を見た。私も同じ状態だ。棺はただ石の台の上に乗っているだけのように見える。係りの女性は彼の質問には答えなかった。
「はじめます」
係りの女性が棺桶の蓋にあった赤いボタンのような物を押した。棺そのものに仕掛けがあるのだろう。
だが、音がするわけでもなく見ている限りでは何も起きない。
「これから一時間あります、周りの椅子におかけください、飲み物をお持ちします」
ワゴンにワインが何本か用意された。
「姉さんはお酒だめだったわね、アルコールのないものもあるわよ、ここのワインはおいしいのよ、先生はどうです」
主人の友人を先生と呼んでいる。
社長が二人のグラスにワインを注いだ。私にはレモンスカッシュを開けてくれた。
「先生私を覚えていますか」
ワインを片手に妹は主人の友人に声をかけた。
「彼の妹さんですよね、もちろんです、あのころまるで宵の明星のようでしたね」
科学者らしからぬ表現だと私は不思議に思った。
「この学者さんは、中学の頃から星マニアで、みんなにあだなをつけていたのよ、兄は北極星、私は宵の明星、金星ね、理由はわからないけど」
「まだ子供でしたからね、お兄さんは僕の行き先を示してくれる北極星のような存在だったかな、彼は数学が得意だったからこつを教わったのが今につながっているんです」
「私はなぜ金星だったのかしら」
「単純にきれいだったからかな」
「あら、そうだったの嬉しいな」
「また、オゾンの匂いがする、奇妙ですね」
科学者はまだオゾンの匂いが気になっているようだ。私にはわからないが人が焼ける匂いよりはいいだろう。
「もうそろそろ終わりですね」彼は腕時計をみた。
確かにあと十分ほどで一時間になる。そこに、係りの女性が妹のパートナーに声をかけた。
「社長ちょっとこちらにきてください」
呼ばれて別室に行った葬儀社社長は戻ってくると我々に向かって言った。
「申し訳ありません、棺の状態がちょっと悪くて、終わるまで30分ほど伸びます」
「どうしたの」妹が聞いた。
「特殊な嵐が起きまして、まだ星葬が始まっておりません、嵐はすぐ収まると思います」
火葬場でも火葬炉の具合が悪くて、棺を入れ替えたりしていることがある。同じような状態なのだろうか。
それから二十分経った。
係りの女性がきて、
「終わったはずですので、棺の蓋をはずします」
主人は骨になっているのだろうか。
私と妹は棺の脇に立った。友人もそばにきた。
女性が蓋をあけた。
一匹の死んだ魚が棺の床にのびている。
「なんだこれは」
主人の友人が目を丸くした。私はちょっと卒倒しそうになった。まるで手品のようだ。主人の遺体が死んだ魚になった。
「なにやってるのあんたは」
妹が葬儀社の社長に怒鳴っている。
「すみません」女性はあわてて、棺の蓋を閉めると、また赤いボタンを押した。
社長が頭を下げた。
「今まで、このような故障はありませんでした、宇宙が荒れているようですみません」
どういうことなのだろうか。
「それにしても、なんで彼が魚になったんだ」
私が聞きたいことを友達が聞いてくれた。
「いいから説明しちゃいなさいよ」
妹が社長に言っている。
「いいんですか」
「いいわよ、しょうがないでしょう」
「星葬は人間を原始に帰し、その後星の奥に送り込むのです」
この説明でもわからなかった。
「原始に帰すということは、どういうこと」
「進化を逆転させて、生命の大元の分子に戻すことです」
「それは遺伝子、DNAに戻すということですか」
そのようなことができるわけはない。
「棺の中の宇宙の状態が悪く、途中の魚の状態でした、後十分もすると、星葬は終わると思います」
「それで、私の主人はどこに行くのです」
「ブラックホールに吸い込まれて反対側に行きます」
「それならブラックホール葬にしたほうがはっきりするじゃない」
妹が言った。
友人は星と聞いて興味をもったが、やはり眉唾に感じたようだ。
「そんな技術があるとは思えないが」
「そろそろ終わりです」
係りの女性が棺の脇に立った。
彼女が蓋を開けると、棺の中は黒い渦が巻いていて、白い物が真ん中をひらひらと飛んでいった。ふっと、主人の働いていたときの白いワイシャツの後ろ姿が見えた気がした。
「申し訳ありませんでした。まだ最後のところでした、しかし、これで星葬が終わりました、ご主人様は向こうにいかれました」
妹の声である。妹もよく知っているようだ。
葬儀社の社長も首を傾げている。
そのとき、棺の中の黒い渦が広がってくると、棺の外まで吹き出てきて、真ん中から、大きな物が飛び出し、どたっと床の上に落ちた。
黒い渦はすーっと棺の中に消えると、棺の中にはなにもなくなった。
「やっちまった」
「どうするの、違法行為なのがばれちゃうでしょう」
社長はうなだれた。
床には細い手と足を持った人間が上向けで横たわっていた。大きな頭には目玉が五つもあった。
私は妹にしがみついた。
妹を見た。
妹は五つの目玉で私を見た。
「ごめん、私たち、ブラックホールの向こう側の生き物なの、地球でちょっと商売しようと思ったのよ、二つ目をもつDNAが欲しかった、むこうで高く売れるのよ、宇宙法では違反よ、機械の調子が狂って、向こうで兄貴の遺体を待っていた仲間がブラックホールに吸い込まれここに放り出されてしまったのよ」
そう言い終わったとき、棺から真っ黒い生き物が四人出てくると、葬儀社の社長と二人の女性、それに妹に網をかぶせて動けないようにした。
真っ黒の生き物は五つ目を私に向けて、
「すまなかった、我々がブラックホールの反対側に戻ったら、ご主人の遺体は元に戻すので、改めて葬式をしてください、ここに費用をおいておきます」
そう言った。
黒い五つ目の生き物は、日本のお札の束を棺の脇に並べた。
「ごめんね、妹さんは昔になくなっていたのよ、私が化けていたの、さよなら」
妹の形をして五つ目の彼女が言った。
五つ目の生き物は棺の底に湧いてきた黒い渦の中に妹達を連れて入っていく。
「失礼しました」
最後の五つ目が、部屋に飛び出してきた五つ目の死体をかつぐと、礼儀正しく挨拶をして黒い渦に頭を入れた。
黙って見ていた友達の友人がそこに飛び込んだ。彼はこう叫んだ。
「ブラックホールの向こうに連れてってくれ」
それっきり消えてしまった。
ぼーっとしていると、棺の中が白っぽくなった。
白い布に包まれて主人の遺体がそこにあった。髭がもう少し伸びているようだ。
触ってみた。生きているみたい。
これから自分で葬儀社を探さなければならない。私はあの生き物がおいていったお札の束を見た。いくらあるのだろうか。こんな量のお札を見たことがないので想像することすらできない。
もしかすると宇宙葬ができそうだ。それもいいかもしれない。
棺


