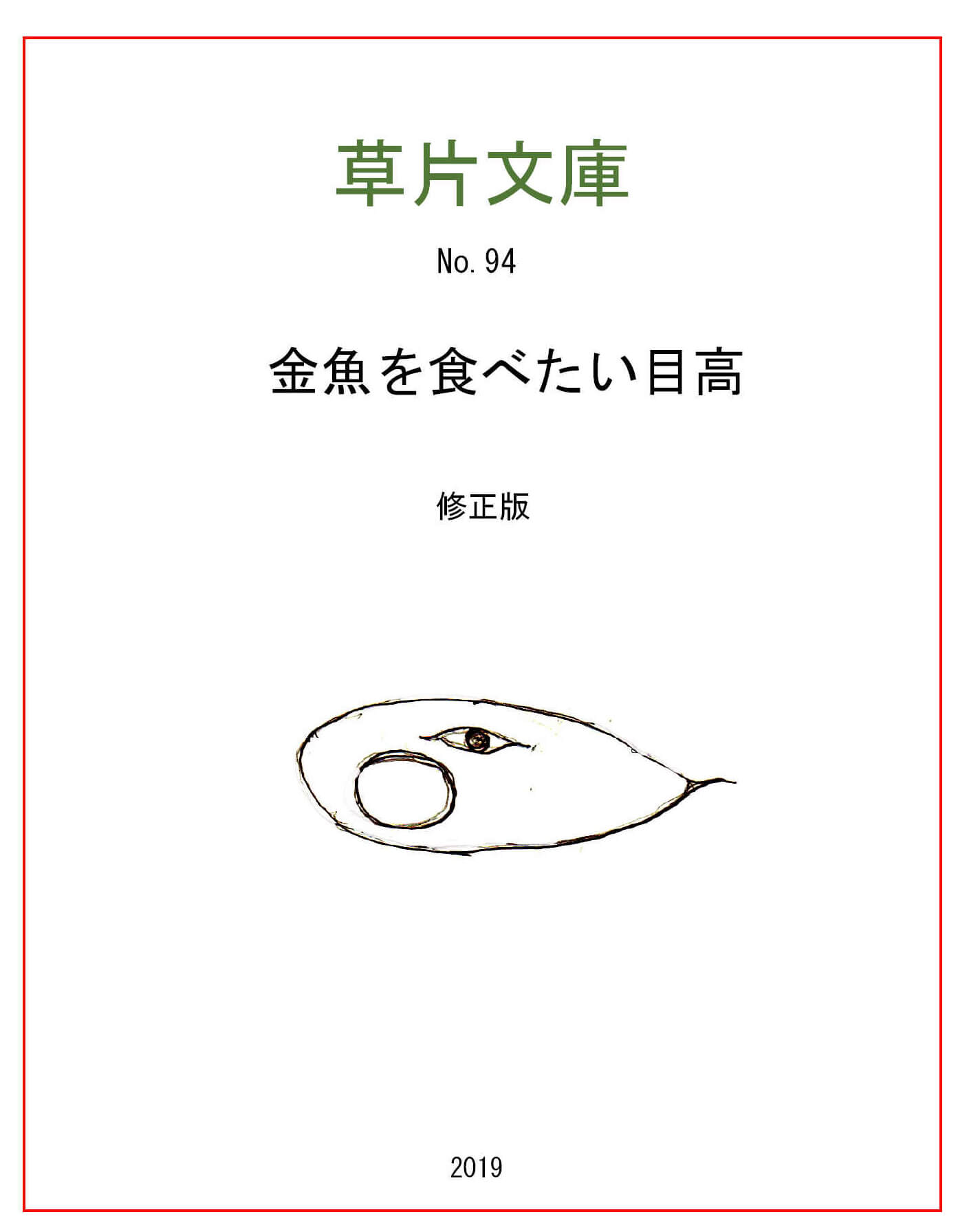
金魚を食べたい目高
幻想ホラーコミカル小説です。
目高がな、金魚が食べたくてな、小川から田圃の水の中に泳いでいったんだ。金魚というのは赤くて人間が好きなものだと聞いたからだそうだ。
その目高の好きな物といえばミジンコだったのだ。特に玉ミジンコが好きだった。何しろうまい。からだにいい。その目高は好きということは食べることだと思っていたんだ。それで、群の中で小川の流れに逆らって泳いでいたら、女の子が金魚大好きというのが聞こえた。ミジンコよりおいしいものがあるの、と不思議に思ったわけだ。それで、その目高は金魚が食べたくなったんだ。おまけに女の子はあの家のお池にいる真っ赤な出目金が一番好きと言っておったんだ。目高はもう我慢ができなくなって、小川で一緒に泳いでいた仲間に「出目金を食べてくる」と言って、群からはずれたわけだ。
田圃から小川にでていた泥鰌に「庭のお池に行くにはどうしたらいいの」って聞いた。
「田圃を横切って反対側の山際の用水路に入って登っていくと庄屋さんの庭の池に繋がる水路があるから、そこに入ると庭にいくよ、ただそこからが大変だ、まず水を貯める場所があって、そこから炊事場の中に入る水路と、庭の池に行く水路に分かれる。もし炊事場の方に行くと、茶碗や皿、鍋を洗うところにはいる、その水はまた用水路に戻されるから、庭からおっぽり出されることになる」
そう泥鰌は親切に教えてくれた。
目高は田圃に入った。稲の間にはミジンコがたくさんいて、とてもいい思いをしながら泳いでいった。田圃ってタニシやマツモ虫や結構にぎやかなところだった。三つほど田圃をくぐり抜け水路にたどり着いた。水路の流れは小川より急である。
さてどっちに行けばいいか。わからないけど目高は水路を上りたくなった。みずに逆らうのが好きだからだ。
どんどん行くと山の中を流れる小さな川になった。どうも反対の方向にきてしまったようだ。
目高は泳ぐのをやめた。
水の流れに身を任せると、勢いよく流れていき、さっきの田圃の出口を通り越した。しばらく行くと山際の方に分かれていく流れが見えた。目高は鰭を一生懸命動かして流れの反対側に行くと、幅が狭いが石が積まれてできている水路に身を踊らせた。そのまま流れに乗っていくと、水の流れは緩くなり、石づくりの貯水槽のような所になった。そこから小さな流れが二つある。きっと泥鰌が言っていた、炊事場に行く水路と庭の池に行く水路に違いない。しかしほとんど同じ大きさでどっちにいったらいいわからなかった。
炊事場に行くとまた庭からでて外の水路に入ってしまう。そうなるとまた田圃にはいって、戻ってこなければならないだろう。
目高は水の上を見上げると苔が覆っているのが見えた。そこに緑色の蜘蛛が歩いている。
「池の方に行くにはどっちに入ったらいいの」
蜘蛛は「俺にゃわからんよ、何せこんなに小さいんでもっと高い木に登ることのできるやつに聞きなよ」と行っちまった。
そこにイトトンボがやってきた。いいところにきたもんだ。尾っぽをちょっちょっと水面につけようとして、目高に気がつくと、尾っぽを持ち上げた。
目高はトンボがなにやっているのか知らなかった。
「炊事場に行く水路はどっちだか教えて」
イトトンボはほっとして、あっちだよと目高に教えた。
親切なトンボだと思って、礼を言うと目高はそっちの水路に入ってしまった。効き方を間違えたのだ。池に行く水路を聞くべきだった。それか炊事場と違う方の水路を選ぶべきだったのだ。
イトトンボは卵を生もうとしていたのだ。しかし、目高に食われると思ってやめたのだ。それで上の空で返答をしたわけだ。だけどイトトンボは間違っていない。考えなきゃいけなかったのは目高である
目高は炊事場に向かって泳いでいった。もちろん途中で気がついたのだが、ちょっと逆走するには疲れていたのだ。
やってきたところに大根が水の底に寝ていた。人間が大根を洗うため流れに沈めておいたのだ。そこに、白くにごった水が広がってきた。目高の目玉に白い水をもろにかぶってしまった。米を研いだ後の水だった。ご飯粒が浮いてきた。器を洗った後の水だ。
あわてて、目高は逃げた。一生懸命に尾鰭を動かしたのでだいぶ疲れたけど、ともかくまた水の流れに戻った。水路にはいったようだ。流れに逆らって上っていけばまた庄屋さんの庭に行く水路があるにちがいない。
目高は一生懸命鰭を動かした。ともかく金魚が食べたいんだ。
あまりにも水の流れが速かったので、もとのところにいくのに朝までがんばらなければならなかった。次の日になってしまったわけである。それでもまた庭に行く水路に入れて、貯水槽にたどりついた
白い丸いものが貯水槽の壁の藻の所についていた。目高はずいぶんおなかが空いていたので、つついてみた。なかなかうまかった。それがイトトンボの卵だとは知らなかった。
今度は入る水路を間違えなかった。
水の流れに任せていくと、チャボンと落ちた所は睡蓮が茂っているなかなかゆったりしたところだ。ここがきっと池なのだろう。
さて目高は金魚を食べたいのだが、どのようなものか知らない。赤いことは確かである。目高のイメージではミジンコを真っ赤にしたようなものだった。
と言うことは睡蓮の葉っぱのあたりにいるのではないか。目高は睡蓮の葉っぱの裏をのぞいていった。ミジンコがいたりはするが、金魚はみつからなかった。
大きな口だ。吸い込まれるといけないので慌てて脇に寄った。
魚は目高に言った。
「おめえ、何柄こんなとこにいるんだ、目高は小川で泳いでな」
自分のことを目高だと知っているこいつは何だろう。でぶった目高の妖怪みたいだ
「おじさん誰」
「俺を知らねえのか、鮒だ」
聞いたことがなかった。目高の妖怪ではなかった。
「金魚食べたいの」
「へ、今なんて言った、金魚を食うのかい」
「うん赤い出目金」
「出目子を食うんか」
「どうしてだい」
「人間の女の子が好きなんだって」
鮒は笑い出した。そして、大きな声で呼んだ」
「おーい、出目子」
すると、真っ赤で大きなデブの魚が下の方から浮かんできて、目高を弾き飛ばした。目高はなんとか睡蓮の葉っぱにぶつかって止まった。
「鮒のおじさん、呼んだ」
金魚は大きく飛び出した目で目高を見ながら甲高い声をだした。目高はその目玉より小さかった。
鮒はまだ笑っている。
「そこの目高が、出目子を食いたいんだと」
出目子はそれを聞くと、大きく口を開けた。
目高は吸い込まれないように蓮の葉っぱの陰にかくれた。
出目子の口がよってきた。目高がいっぺんに五匹入っちまいそうだ。
めだかはもっとびっくりして目を飛び出させた。
「早くしてちょうだい」
鮒はまた笑った。
「出目子なにしてるんだい」
「この子、歯糞を食べてくれるんでしょ」
どうも出目金は歯の掃除をしてもらうつもりだった。いつも出目子は金魚の子供に歯をつつかせていたんだ。
「いやな、この目高の坊主が赤い金魚を食べたいって言ってきてな、特に赤い出目金だとさ」
「あたしを食べたいの、目高のぼおや」
目高は怖くて震えていた。金魚ってこんなに大きいんだ。
目高は首を横に振った。飛び出た目玉がますます横に飛び出した。
「人間の女の子が赤い出目金が好きと言うのを聞いて、食うもんだと思ったんだとよ」
鮒のおじさんが言った。
「あらかわゆいこと、目高のぼおや、お父さんとお母さんは好きかい」
「見たことがないからわからない」
「そうね、どうやったら説明できるかしら、鮒のおじさんは黒っぽい、あたしは赤い、わかるでしょ」
目高はうなずいた。
「赤と黒とどっちが好き」
「赤の方がいい、きれいだから」
「そういうとき赤が好きって言うでしょ、でも赤は食べないでしょ」
目高はそれを聞いて、好きというのは食べるものばかりではないことを知った。
「ところで目高のぼおやは小川と池とどっちがいいの」
小川には仲間がいて、仲間と泳いでいたほうがいいと思って「小川」、そう言った。
「小川が好きなのね、この池には私よりもっともっと大きな魚がいるからね、食べられないうちに小川に帰りなさい」
出目金の出目子が池から用水路にいく水路を教えてくれた。やっと落ち着いた目高は、「ありがと」と言って、田圃の脇の水路に戻った。田圃を横切って、やっと小川にもどった。
小川では兄弟仲間が何列かになって泳いでいた。目高は仲間の中に入っていった。
「ただいま」
すると仲間が「出目金を食べると目が出るんだ」
と池に行ってきた目高に言った。
まだ目が飛び出たままだったんだ。
目高がなにも答えなかったものだから、仲間がさらに聞いた。
「うまかったかい」
目高はそれにも応えなかったら、仲間たちは「きっとうまいものに違いない」とそろって、田圃にはいって行ってしまった。
目高は小川で一人になってしまった。
一方、池に目高がぞろぞろ入ってきたものだから、出目金や鮒はたいそう驚いた。
出目子が目高のそばによると、目高は大勢だったものだから、みんなして出目子をつつき始めた。
「きゃあくすぐったい」
出目子が身をよじった。
その声を聞いた池のほとりにいたトノサマガエルが一斉に池にとびこんだ。見ると仲のいい出目子が目高につつかれている。
トノサマガエルはみな出目子が大好きだ。
「たすけてやるぞ」
トノサマガエルたちは一斉に目高を丸飲みにしてしまった。
とうとうその目高はひとりぼっちになってしまったのである。
しばらくの間、目高は一匹で小川を泳いでいて大人になった。
ある日人間の女の子が二人でこんな話をしていた。
「赤い出目金死んじゃったよ」
目高は出目子がなつかしく思い出された。池に行った仲間はどうなったのだろう。もう一度池に行ってみよう。
目高は間違わずに池に行った。
ぽちゃんと池に入った目高に向かって、睡蓮の葉っぱの影から、たくさんの赤い目高が泳いで来た。
「黒い出目金のこどもなの」
赤い目高の一匹が目高のそばによってきて聞いた。
「僕は目高だよ、赤い目高ってはじめてだよ」
「私たちは出目金よ」
赤い目高だと思ったのは、出目子の子供たちだった。
それでも仲良くなって、一緒に池で過ごすことになった。
赤い出目金の子供たちは出目子にだんだん似て来た。
やがて、大きくなった赤い出目金の一匹が、目高に向かって
「目高はちいちゃいままなのね、食べたくなっちゃう」
と言った。
目高ははて、好きということと食べたいということは違うと出目子に教えてもらったけど、どのように返事していいいかわからなかった。それで、とりあえず「うん」と言ったんだ。その赤い出目金は大きな口を開けた。あのときに歯糞を食べてもらいたいと出目子が口を開けたことを思い出し、目高はその出目金の口の中に頭を突っ込んだ。
赤い出目金はいいのかしらと思いながらもがぶっと目高の頭を食ってしまった。
金魚を食べたい目高


