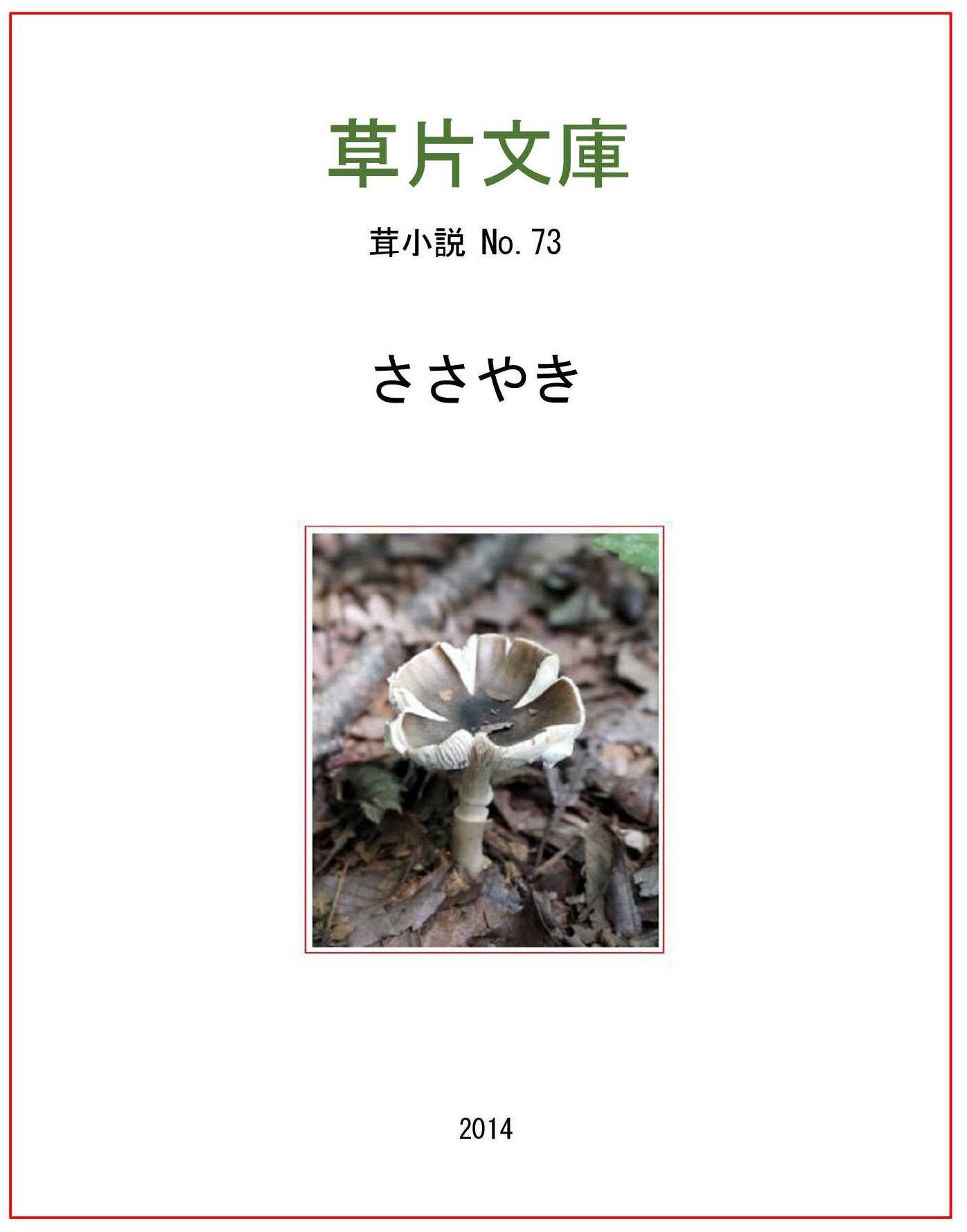
ささやき
「この茸を食うてみなされ」
老人が真っ白な茸を私に手渡してくれた。
「生で食べるのですか」
「ああ、毒じゃないから大丈夫だよ」
パリの東駅から乗ったモーツアルト号のコンパートメントの中のことである。
私はパリで用事を済ませ、ハンガリーのケレチ駅に向かっていた。乗り合わせたフランス人の老人が、茸を私に差し出したのである。
老人の持つ皮袋の中にいくつもの白い茸がみえる。
私はその場でかじった。ずいぶん甘い。
「甘い茸ですね、それに、ジューシーだ、まるで果物のようです」
「そうじゃろう、この茸は私の農園で作っているものじゃ、果物のようでもあるが、それよりもっと楽しい働きがあるのだよ、しばらくたつと、耳元で天使のささやきが聞こえるようになる」
「それは楽しいですね」
そのとき、老人の言ったことは、気分が良くなることのたとえだと思い、私は笑って食べ終わった。
その後、私は日本の松茸など、日本は茸国であることを話し、老人はフランスの玉子茸やモレーユの自慢をしたり、茸の話の花を咲かせた。
老人はストラスブルグにつくと、旅を楽しんでねと降りていった。名前を聞くのを忘れてしまった。
私はハンガリーでの仕事を無事に終え日本に帰国した。
成田からリムジンで京王線の調布につき、駅前のマンションに戻った。旅のパッケージをほどいて、風呂を沸かし、冷蔵庫からビールを取り出した。
ぐっと飲んだ。日本のビールもうまい。一息ついた。
テレビをつけると、一週間留守をしていた間に、二件の女児が消えた事件があったようだ、自宅から近くのコンビや友達の家にいくほんのちょっとの間にいなくなっている。東京のはずれと大阪での出来事なので二つの事件に関連性はなさそうだが、最近、変質的な人間が増えてきている。
風呂に入り、もう一缶ビールを空けると、ベッドに入った。明日はいつものように、会社にでなければならない。旅は慣れているので、ほとんど時差ボケはないのでその心配は要らない。すぐ眠りについた。
明け方夢を見た。自分は林の下草の中にいる。シダや草類が頭の高さである。ということは自分が小人になっているわけである。脇を足の長い蜘蛛のたぐいがゆったり歩いている。座頭虫だ。山の林の中でみかける小さな虫なのだが、自分の頭ほどの大きさがある。
歩いていくと赤い茸が生えていた。自分よりはるかに背が高く大きい。近づくといきなり、茎の根本にドアがあらわれ戸が開いた。おとぎの国か。
人が出てきた。その人は私の半分ほどの大きさである。
「やあ、元気かい」
その人は私に声をかけた。よく見ると、パリからの列車の中で茸をくれた老人の顔をしている。
私がなんと返事をしたか覚えていないが、その小人の老人の後ろから、ふっくらして色の白いかわいい女性が出てきた。
老人は私に「わしの孫の、マノンじゃよ、これから、あんたにいろいろささやくから、よく聞きなされよ」
と言った。老人が言い終わると、二人ともその茸の中に入っていった。
そこで目が覚めた。そのあとも、緑色のワンピースを着た、マノンさんとやらの姿が目の前に残っていた。
朝風呂に入り、いつものようにトーストとハムで食事を終え、何杯めかの紅茶を飲んでいるときであった。
耳がほかほかと暖かくなった。なんだと周りを見たがなにもない。すると日本語で、
「おはよう、シオン」とささやき声が聞こえた。
テレビの中の声かと、画面を見たが、男のアナウンサーが野球の結果を解説しているだけである。
「シオン」
また声が聞こえた。私の名は市(し)温(おん)菊(きく)馬(ま)という。
今度は、
「キクマ、今日は新宿には行かないでね」
ささやき声が私にうったえた。
夢にでてきたマノンと呼ばれていた女性の声に違いないと思った。やはり旅の疲れか、まわりを見てしまう。幻聴の類だろう。夢であの老人の言ったことが頭にこびりついてしまったようだ。ささやきだ。
そうこうすると家を出る時間になり、用意をして外にでた。パリとブタペシュトの結果をチームに報告しなければならない。
渋谷にある会社には新宿から山の手で通っている。井の頭線で渋谷にでることもできるし、その方が安いが、新宿によることも多いのでそちらの定期を購入している。
ところが、その日は、いつもの時間の特急に乗って、調布からしばらく行ったところで、いきなり明大前で井の頭線に乗り換えようと思い立った。そう思う理由はあった。ゆったりしたヨーロッパからから帰ると、新宿のあの喧噪が何となく煩わしく思えるからだ。いつもそのような気分になる。
明大前で混んだ渋谷行きの快速をやり過ごし、各駅停車で座っていくことにした。
会社についてオフィスの入口を開けると、中は閑散としている。おかしなこともあるものだ。私は腕時計をみた。もうすぐ九時半になろうとしている。会社は九時半からであり、いつも九時にはスタッフすべてがそろっている。どうしたことか。
自分のデスクに座るとPCを立ちあげ、インターネットからニュースを開いた。
新宿で爆弾騒ぎ、と太字のタイトルが目に入ってきた。これで誰もいない理由がわかった。電車が止っているのだ。詳しい情報を知らなければと、オフィスのテレビをつけた。
テレビには新宿の南口出口から黒い煙が吹き出している様子が映し出されている。山手線のホームにおかれていたバックが爆発し、電車を待っていた客数人がけがをしたらしい。爆発の時間はいつも私がいるころである。
その様子を見ていると、耳元で、「よかったわ」と誰かがささやいた。
つい振り向いてしまう。だれもいやしない。
夢の女性がささやいた記憶がもどってきた。新宿には行くなといっていたような気がする。偶然だろう。昔からこのような無意識の勘がよいほうだった。今回もそんなことだろうと思ったのだが、あまりにもささやきがクリアーだ。
そこで、オフィスのドアがあいた。スタッフが出勤してきた。
「おはようございます、市温さん、はやいですね、事故にあわなかったようでよかったです」
「うん、今日は井の頭線まわりできたんだ」
「いい勘してますね、よかったです、おかえりなさい、どうでした」
最初に入ってきたのは後輩の山(やま)床(とこ)古粒(こりゅう)である。彼は東南アジアの、特にタイの担当である。
「ハンガリーは古い都で魅力的だ。人もとてもいいし、食べ物もうまい、歩きやすくていいよ、ヨーロッパで一番古い電気で走る地下鉄っていうのがあったよ」
「それで、売れそうですか」
「けっこういいかもしれないね、あそこは市民が芸術品にずい分興味をもっている。自宅に気に入った作品をかけているようだよ」
私の会社は若い画家や彫刻家の作品を外国に売り込む会社である。東南アジアでは、金持ちあいてだが、ヨーロッパではそれなりの作品も結構売れる。最近の若手のマンガの原画は、どの国も若い人が目の色を変えてとびつく。
「ところで、新宿の爆破はテロなのかな」
「まだわからないみたいで、しばらく電車は動かないでしょうね、僕は近くなので、地下鉄で来たんですよ、それでぎゅうぎゅう、おくれました」
「地下鉄は動いているの」
「新宿を通らないのは動いてます、新宿に乗り入れているものは止まっているようですよ」
「ほかの連中はなかなか来れないのだろうね」
「いや、来れないわけはない、うまくさぼっているのでしょう」
と言っているところに、ぞろぞろと女性陣が入ってきた。
「だいじょうぶだったのか」
「はーい、みんなで、タクシーできました」
ピンクのハイヒールを履いた雪落(せつらく)白花(はくか)が元気よく答えた。
「そんなにみんな近くにすんでいたっけ」
「へへ、昨日はみんなで銀座のホテルで宿泊、食事とエステを楽しんで、今日はゆっくりとでてきました」
「いいな、若くて」
「部長はどのようにきたのですか」
「井の頭線だ」
「あ、そうか」
私は部長といっても、まだ三十二歳、平均年齢が二十八歳という若い会社である。しかし、五十人を超す社員がいる。社長は八十一になる若(わか)根(ね)兎(と)草(ぐさ)という老人で、昔は絵を描いていた不動産持ちである。兎草はある年になったとき、若い画家を育てることに情熱を注ぎ始め、この会社を興した。気に入った若い女性の画家の卵がいて、そのおかげでこの会社ができたいう人もいた。社長のもと、営業部長である私と、画家発掘担当係長の熊谷蘭がいる。あとは一律平社員という構成で、みんな伸び伸びと働いている。私は昔、彫刻家を志したことがあるが、作る物がまじめすぎるといわれ、自分でもそう思い挫折した。やはり破天荒でないと面白いものはつくれない。
その日はハンガリーがマーケットとして有望なことと、以外とシュールかかったものも売れる可能性があることを報告し、若手の作品として誰がいいか、選定グループを構成し、依託して終わった。
夕方には爆弾犯人もつかまり、電車も正常までにいかないが、問題なく家に帰ることができた。
その夜のことである。
寝入っているところ、耳元で誰かがささやいた。
「今日は助かったでしょう、あなたの会社の女の子たち、みんなかわいいわね、私の国にほしいのよ」
目の前にマノンちゃんがほほえんでいた。茸からおじいさんがでてきた。
「やあ、どうかね、マノンのささやきは役に立つだろう、あんたを守ってくれるし、どうだい、たまにはここに遊びにおいで」
「だが、どうやったら、いけるのです」
私は夢の中で答えている。
「マノンのささやきに答えればいいのだよ」
「ここに来たいと言えばいいのですか」
「いや、来たいと言われても、すぐにいいよとはなかなか言えないのだよ」
「どうしてです」
「そのときのこちらの状況でね、あんたに来てほしい状態でないとそれはできないのだよ」
「両方が望まなければだめと言うことですね」
「まあ、それに近いかな、時間をかけて、お互いを知り合わないとね」
「そうですね」
「どうかね、今日は私どもがお招きするよ、一時、遊んでいかないかね」
「いいんですか」
「最初の時は、夢のようじゃっただろうが、今回は、本当にこの地に来てもらうよ」
「いきます」
と私は言っていた。そのとたん、私は、林の下草の中にいた。最初の夢の時と同じではない。大きなシダが私の頭に触れると、その匂いや髪の毛にふれた感触は夢とは全く違う。いつもの生活の中である。
「いらっしゃい」
マノンの白いふっくらとした手が私の手をとって白い茸の中にさそった。
茸の中は一つの部屋になっている。柔らかな白い腰掛けと、テーブルがあった。子供の頃のおとぎの国である。
老人が地下からあがってきた。
「きましたな、わしの部屋は地下で、孫のマノンは二階にすんでいます」
マノンが色とりどりの茸を籠に入れて持ってきてテーブルの上においた。
「どうぞ、いろいろな味がしますし、楽しめます」
マノンが籠の中から赤い茸をとって、老人と私の皿に載せてくれた。
ホークもナイフも置いていないので、ヨーロッパで老人とであった電車の中でしたように赤い茸を手にとってかじった。
「いや、こうやって」
マノンが笑いながら、赤い茸の皮をむくと指で折って口に入れた。
私もまねをして皮をむき、口に入れると、香ばしい匂いと、酒の香りが口中に広がった。口の中で溶けて、ごくんと飲むと、とろりとした酒である。
「酒茸でな、うまいだろう」
私はうなずいた。老人に言われるまでもなく旨い。
「成長しながら茎の中が発酵して酒になる、飲むのと食べるのを一緒にできる不思議な茸でな」
マノンが黒い茸を皿に移した。皮をむこうとすると、マノンが、
「これは、こうやって食べるの」
かわいらしい口でかじった。
私もまねしてかじると、これがステーキそのものの味だった。
「これは、牛に生える茸でな、牛は筋肉が弱るが、茸を刈り取ると、また元気になる、牛の体が培養土のようなものだな」
「牛が気の毒だな」
私が感想を漏らすと、老人は首を横に振った。
「ところが、そんなことはなくて、牛はこの茸が生えているときは、とても気持ちがいいのだよ」
「どうしてですか」
「筋肉のエキスも吸い取るが、茸の成分が牛の頭の中に巣くっている不安という奴を取り除くのだよ、野生の生き物はいつもびくびくしとる、それがなくなるのだよ」
「そうなのですね」
それは野生の動物にとって幸せである。しかし、人間のドラッグと同じような効果ではないかと疑ってしまう。
老人はそれを察したように説明した。
「牛は決して癖にはならないのだよ、茸が生えなくなったからといって、苛立ったり凶暴になったりしない」
次に皿に取り分けられた茸は白色のまん丸な茸であった。マノンは皿の上の茸の上を指で突っついた。茸から赤い煙が立ちのぼり、それを鼻から吸い込んでいる。マノンの顔がピンク色になった。
「吸ってみてください」
マノンのかわいらしい顔が僕をみている。僕も指で突っついて赤い煙を出し、吸い込んだ。
そのとたん、頭がすーっとして、からだが浮いた感じになり、妙に緊張してきた。
「茸は幻覚を引き起こすものが多いのじゃが、これもその一つ、だが、体や脳には全く害は及ぼさないから安心しなさい」
老人の声が遠くで聞こえる。
「私の部屋に行きましょう」
マノンの声も聞こえた。私たちは連れ添って二階に行った。そのあと男と女の交わりがあり、身体にしびれたような快感が残っていた。その状態がどうしようもなく長く続いき、裸のまま、茸の部屋の天井を見つめていたのだが、いつの間にか寝てしまった。
目を覚ますと、朝になっていた。
その日、会社のオフィスに入っていくと、女の子たちが一斉に私をみた。
「シオンさん、いい匂い、お安くない香水ね」
雪落白花がまじまじと私を見た。
「ただ者じゃないわね、どこのお嬢様、お相手は」
胡桃(くるみ)緑(ろ)実(み)が興味しんしんに私を見ている。
確かに、何か香るようであるが、自分からでているとは思っていなかった。道理で、電車の中で周りの人たちが無遠慮に私を見るわけである。
「昨日は、ぐっすりとよく寝たよ、自分のベッドで一人でね」
そう言ったのだが、すぐに、
「それじゃ、その香りはなあに」
とのリアクションがあった。
「きっと、電車の中での移り香じゃないかな」
そういいながら、夢の中のマノンとのことを思い出していた。
「でも、この香りどこの香水なのかな、知らない香りね」
化粧にとても興味をもっている楠木(くすのき)朱(あけ)野(の)が誰にともなく言った。
「ほんとね、こんな香水があったらほしいな」
という声も聞こえた。
その日、帰宅してからのことである。
炊飯器の予約スイッチを押し忘れていて、ごはんが炊けるのをテレビをみながら待っていた。
耳元でマノンのささやきが聞こえた。
「高尾山にいきなさいね」
テレビでは旅の番組をやっている。山形の銀山温泉である。だが、高尾山が気になってきた。京王線の終点の一つであり、何度も行ったが、ここのところご無沙汰である。山頂のビアホールは眺めがよく気持ちがいい。最近は観光客が多く、登るのに込み合っているらしい。
新宿を気をつけるように言われたときは、事件がおき、ある意味では命拾いをしたのかもしれない。今回のささやきの意味を考えていたらなかなか寝付けなくなり、ベッドからでて、グレンフィディックを一杯ひっかけた。
そこでまたマノンがささやいた。
「女の子たちつれてきて」
ショットグラスでもう一杯飲んだ。
その夜はそれでなんとか眠りについた。
次の日、会社ではみんなでハイキングをいく相談をしていた。
「シオンさん、来週の土曜日、山にいこうということになったのよ、いきます」
「独り身だから、空いているよ、つきあうよ」
夕食代をせびろうっていうのだろう。いつも余計に払わされる。
「そろそろ、ビールもおいしいよね」
連休が始まる手前である。気候もいい、たしかにハイキングは気持ちがいいだろう。そのとき、フットささやきが思い出された。
「高尾山、どうだろう」、つい口を挟んでしまった。
それを聞くと、みんなが驚いた顔をして、「さっすがあ」と大きな声をあげた。
「おおげさだな、京王線に住んでいるからだよ」
「いいえ、誰も高尾山って思い出さなかったんだもん、あんなに近くで人気のあるところなのにね、三ツ星ですよ」
山(やま)高蘭(たからん)が言った
「なにその三ツ星って」
「あれ、シオンさん知らないの、ミッシュランの三ツ星、都会から近くて、自然の多い、とてもいい場所だから、ミッシュランが三ツ星をつけたのよ、それはたいしたものよ」
「あそこで、ビールが飲めるでしょう」
「いいなあ、そこにしよう」
それで高尾山に行くことになった。今の時期なら少しはすいているだろう。
「社長さんはだめみたい、でもたんまり寄付してもらおう」
「熊谷さんは北海道、山床君はタイに行くんだって」
「え、それじゃ、男はおれだけか」
「そうよ、たっくさん荷物をお願いします」
「もう三十五だよ」
「シオンさん、三十五はまだ青年の部類ですよ」
「大志なんて抱いていない」
「そんなもん抱かなくても、荷物を抱いてください」
土曜日には、私の部署の女の子七人が高尾山に行くことになった。
彼女たちがきゃあきゃあ言いながら、京王線の高尾山口駅をでてきた。朝十時である。元気なものだ。私は一本前の特急で到着し、駅前広場で待っていた。
「おはよう」
声をかけると、彼女たちが自分の周りをかこんだ。
「シオンさんはやいわねえ」
『調布に住んでいるから近いんだよ』
「ねえ、頂上に行くの」
山高が低い声でつぶやいた。きゃあきゃあ言っていたのとは違ったトーンである。
この女性の声がこういうトーンのときは、めんどくさとか大変とかいう意味である。
私はこう言った。
「登り口はいくつかあるけど、どれも二時間はかかるな、もっとかかるかな」
「えー、そんなに歩くの」
「ウオーキングシューズをはいているじゃないか」
「これ、山を歩くためじゃないの、草の露に濡れないようにだけ」
「なんだ」
「ケーブルカーか、リフトがあるよ」
「それがいいじゃん」
全員一致できまった。何のためのハイキングなのだろう。
「それで、どっちにする」
「好きなほうにしたらいいじゃん」
ということで二手に分かれた。
心の底では「よかった」と思っていた。必ず登れなくなるのがでる、そうなると、おんぶをしないまでも付き添い役だ。
私はケーブルカーに乗った、二人の女子が一緒だった。山高と雪落である。二人とも三十ちかい二十代だ。わが社ではベテランのほうに入る。リフトに乗ったのは五人、二十代半ばの連中、胡桃、楠木、志乃分(しのぶ)穂(ほ)野子(のこ)、浅海(あさみ)麻(あさ)、実(み)桑(くわ)紅(べに)である。
ケーブルカーを待つ人が多く、我々は上の駅までリフトの連中より十五分も後に付いた。
展望台の前で待っていた五人が一斉に、「頂上に行くの」と声を上げた。
「行かないでどうするの」
「ほら、ここから遠くまで見ることができるよ、これで十分ね、あとビール」
新宿副都心のビルも見ることができる。すばらしい眺めではある。しかし、飲むことしか考えていないんだから、この子達はと思いつつも、彼女たちに言った。
「まだ十一時にもなっていないんだぜ、登って、景色を眺めて、それからここに降りてきて、ビールっていうのが一番うまいよ」
「そうかー、そうしよう」
というわけで、ぞろぞろと登り始めた。ヨーロッパ系の人たちや、中国人らしいカップルなどに追い越されながら、ぶらぶらとというより、だらだら歩いた。
野草園、たこ杉の前を通り、女坂を登って神社の手前までくると、浅海が「なにあれ」、と神社の脇の旗を指さした。
竿に白い布がくくられて、はためいている。
「ねえ、茸とビールって書いてない」
実桑が近寄って行った。
「そう書いてあるよ」とみんなを呼んだ。
神社の脇に行くと、耳元で、「つれてきたわね」とマノンの声が聞こえた。
奥まったところに屋台がでている。茸とビールと書いてある。
「ビール飲ましてくれるよ」
志乃分がおいでおいでをした。みんなその気になっているようだ。もうビールかと思いながらいくと、いい匂いが漂ってきた。茸に醤油をつけて焼いている。ビールのジョッキも用意されている。
「食べよー」、彼女たちは大はしゃぎ、屋台の前にたむろした。
屋台をのぞくと、鉢巻をしたおじいさんが茸を焼いていた。
屋台の中では女の子がジョッキにビールを注いでいる。うしろ姿は背が高く日本人ばなれした娘だ。ジョッキに満たされていくビールは少し色が濃い。
先に着いた連中はビールを渡され、焼けた茸をもらった者もいる。
「ねー、このビール、フランスのだって」
紙皿の上の茸を箸で摘みながら、浅海が私を見た。
「おいしいのよ、この茸も、フランスのだって」
われわれもたのんだ、茸を焼いていた老人が顔を上げた。
どきっとした。あの老人だ。
ねじり鉢巻をした老人は、日本語で、
「らっしゃい、あと三人前でいいね」と私に言った。
「はい、おねがいします」どきどきしながら返答すると、
「この茸は特別に育てたうまい茸だよ」
老人は我々三人のために茸を焼き始めた。
ビールを注いでいる女の子が、一杯になったビールジョッキを持ってこちらを振り向いた。
マノンじゃないか、と声をだしそうになった。
いやマノンに似ている。娘は山高に、「どうぞ」とジョッキを渡した。
「すごい美人」
山高が声を出した。マノンは恥ずかしそうに、後ろを向いて、新しいジョッキをビールの注ぎ口に置いた。
かぐわしい甘い香りがただよった。
「あ、こないだ、市温さんからただよった香水の匂い」
浅海が声を上げた。その声でマノンが振り返った。
老人が顔を上げた。
「すいませんな、孫にはつけるなと言ってるのですが、この茸焼きの香りにはあいませんな」
「いえ、とてもいい匂いですね、どこの香水なのですか」
雪落が聞いた。
マノンは答えず、老人が答えた。
「これは、茸の一種からとったエキスで、市販の香水ではないのですよ、娘が自分で作ります」
「え、でも、この間、この人がその匂いをさせていました」
彼女は私を指差した。
「ほー、京王線に住んでますから、孫が電車の中で一緒だったのではないですかな」
老人が言った。
「いい匂い、ほしいなあ、そんな香水」
老人は、
「家に行けばありますで、お譲りしますよ」
そう言ってエプロンのポケットから、欲しそうにしていた三人に名詞を渡した。
「茸の店もやってます、くるときは電話ください」
老人は言いながら、焼いている茸をひっくり返した。
「おいしい、もう頂上に行かないでいいよ、ここで、たっぷり食べよう」
女の子たちは、全くその気になっていた。楽しむために来ているのだから、いいか、と思ったが、座るところもない。
老人が、どこからか丸椅子をと丸いテーブルを出してきた。
「うっれしいー」
みんなは焼き茸とジョッキをもって、テーブルの周りに腰掛けた。
私は老人とマノンに、もっと焼いてくれとたのんだ。
これで今日のハイキングは打ち止めだろう。少しばかり肩の荷がおりたようだ。
老人が焼いた茸を大きな紙皿に乗せてもってきた。
「こりゃ違う茸でね、うまいよ」
マノンがビールを持ってきて私を見てほほえんだ。
「きれいな人ね、日本人じゃないみたい、あのおじいさんも、端臭い顔よね」
山高が気にしている。
「うん、そうだね、二世さんかね」
「果物の茸を召し上がらんかね、サービスですよ」
老人が白い茸を山盛りもってきた。
「このまま、かじってくだされ」
ハンガリーに向かう電車の中で食べたものだ。
私はその茸をとって、かじった。じゅうと汁が滲みだし、果物の香りがただよった。あのときの味だ、なつかしい。
「おいしい、茸」
「なんていうのかしら、珍しいわね」
みんな手を伸ばして、白い茸をほうばった。
だれもが満足をして、いつの間にか、それぞれ家に帰りついていた。
その夜、ベッドに入ると、すぐに眠りに落ち、マノンがこっちにこないかと耳元で囁いた。
わたしがうなずくと、林の下草の中に生えているマノンのすんでいる茸の二階にいた。マノンが私に寄りかかってきた。こうして朝目覚めるまでマノンと一緒にいた。
気持ちのよい目覚めであった。天気がよく、すばらしい日曜日であった。
それから一月後、志乃分、浅海、がいきなり会社を辞めた。みなそれぞれ目的があるようである。元気のよい現代っ子である。もっと気に入った職場を見つけたのであろう。それからしばらくして実桑もやめていった。音楽のほうを勉強したいということだった。我々のところのような芸術に関わる業界は、社員の入れ替わりが激しい。入社する若い子達は自分で何かしているか、何かをしたいタイプが多い。さらに芸術家に触れると、自分でもやってみたくなるようだ。
すでに新しい子がはいり、山高と雪落について、若手芸術家の作品掘り出しと、売るところ捜しの方法を学んでいる。
とうとうその年も終った。
新たな年の二日のことである。ベッドに入ると初夢を見た。
マノンの茸の中にいた。一階の居間で自分に向かって老人が頭を下げた。
「いい子たちをつれてきてもらって、ありがたいことです、しばらく、おいしい茸をつくれます、日本の女性はとても癖がなくよい茸がとれます」
私が首を傾げていると、マノンが手招きをした。
「案内しましょう、あの子たちもあなたを覚えているでしょう」
マノンは茸の香水を漂わせながら手招きをした。
マノンの家を出て、羊歯の下をしばらく歩くと、赤い茸がたくさん生えているところに来た
マノンは「ここよ」と、一つの茸の扉を開けると中に入った。
部屋のベッドの上では、志乃分が横たわっていた。
私を認めると、「あら、市温さん、お久しぶり」と上半身を起こした。
一糸まとわぬ彼女のきれいな身体から白い茸がたくさん生えていた。
言葉も出ず、私がびっくりしていると、マノンが何事もないように言った。
「茸の苗床になってるのよ、とてもおいしい茸がとれるの」
私は声が出なかった。
志乃分はうなずきながら、きれいな足を伸ばした。
「毎日が幸せ、おいしいものを食べ、したいことは全部夢がかなえてくれる」
「日本には帰りたくないのかい」
やっと声がでた。志乃分は首を横に振った。
「死ぬまでここにいるわ」
「両親は心配していないのかい」
「夢の中で話をしている。私が幸せなことを知っているからいいの」
私は何かやりきれない思いになった。
次に案内してくれた茸には浅海がいた。彼女は揺り椅子に腰掛けて、テレビを見ていた。
私に気がついて声をかけてきた。
「あら、市温さん、マノンさんと知り合いだったのね、それで高尾山に私たちを連れていってくださったのね」
浅海ははちきれんほどの肉体に真っ赤な茸をたくさんはやしていた。
「いやこうなるとは、全く知らなかったんだよ」
「私は、連れて行ってもらってよかったと思っているの、こんなすてきなところで、気持ちよく暮らせるのなんて幸せよ」
「茸が生えていていやじゃないのかい」
「この茸が生えるとき、気持ちのいいこと、男じゃああいう風に気持ちよくさせてくれないわ、大きくなると、マノンさんがとっていくの、そうすると、また生えるの、そのときは一日中、頭の中は快楽で一杯よ」
「退屈しないのかい」
「散歩してもいいし、ほら、このテレビ、世界中の番組を見ることができるのよ」
「そう」
何かやりきれない気持ちだ。
「また来てね、市温さんには何もしてあげられないけど、マノンさんがいるのでしょう」
浅海は大きな乳房を揺らした。
「うーん」
次の茸には実桑がいた。
細身の裸身から、黄色い小さな茸が一面に生えている。
実桑はピアノに向かって指を動かしていた。
聴いたことのない曲であるが、とても気持ちの安らぐメロディーである。
実桑が私たちに気がついて立ち上がった。
「あ、市温さん、やっぱりマノンが相手だったのね、あの香水の匂い」
「いや、そんな」
私が返事にこまっていると、実桑は笑った。
「いいのよ、私はすてきな一生をもらったのよ、ここでは自由、しかも自分の能力が思う存分発揮できるわ、今の曲どうでした」
「とても気持ちがよくなった」
「私が作ったの、これエストニアではやっているのよ」
「すてきだね」
「私、本当にこの世界大好き、茸が生えるたびに気持ちがよくなって、新しい曲が作れるの、つくった曲はこうしてどこかの国でヒットしたり、しないまでも誰かが好きで口ずさんでくれていたり、やりがいがあるわ」
「それはよかったな」
「今度、市温さんとマノンのお二人に曲をつくっておくわね」
「ありがとう、楽しみにしている」
実桑はふたたびピアノにむかって指を動かし始めた。
「それじゃ」
私とマノンは外にでた。
帰り道、マノンが言った。
「また、かわいい子つれてきてね、ああいうふうに幸せになるのよ」
「高尾山で食べた茸も女の子に生えたものなのかな」
「ええ、あれは、フランスの女の子、元気に絵を描いているわ」
私は聞いた。
「彼女たちから茸が生えなくなったらどうなるの」
マノンは答えた。
「骨になるのよ」
ささやき
私家版 第九茸小説集「茸異聞、2021、一粒書房」所収
茸写真:著者: 東京都日野市南平 2016-9-6


