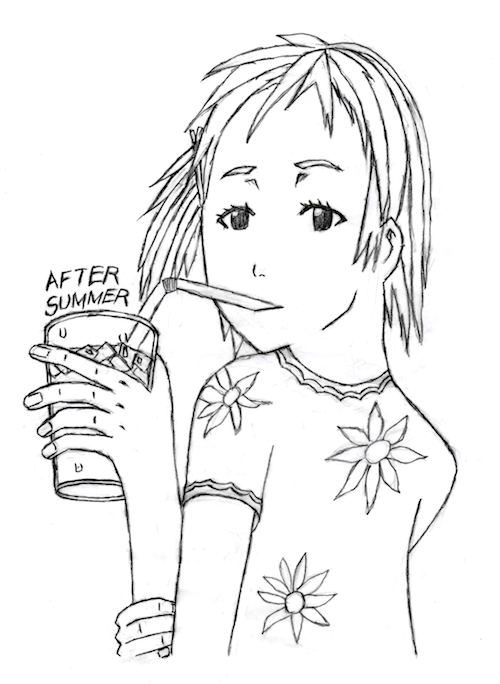
夏の終わりに
「どうしてなんだろう、こんなに急に一緒に買い物しようなんて。」
綾佳は太陽が照りつけるアスファルトの陸橋の上を歩いていた。空気は少しばかり涼しくなってきていたが、それでも太陽の光は肌を焼くように照らしつけていた。全く暑い。ツクツクボウシの鳴き声が、もうこの夏も終わりにさしかかっていることを、それと知らせていた。橋の下をバイクが爆音を立てながら走っていく。今日は友達の可奈に一緒に買い物に来ないかと誘われたので、こんな暑い中を綾佳は歩いていた。
綾佳は女子高生。「花の」とでも言えればいいものだが、今年の夏は到底そんな感じではなかった。
夏の初め頃に急に母親が死んだ。原因は脳出血。風呂に入っているときに出血を起こし、家族がなかなか出てこないことを不思議に思って風呂の扉を開けたときには、もう意識がなくなっていた。そして病院で死亡が確認された。その風呂の扉を開けたのは、綾佳だった。
あまりに急なことで、綾佳は母親の死を受け入れられず、葬式の時でさえ涙は出てこなかった。ただ、もっと早く気づいていればという後悔の念だけが綾佳の頭に何度もよぎった。淡々と後片付けをする綾佳のことを、周りは冷徹な娘だと思ったかもしれない。しかしある日、母親が昔旅行の時に買ってきたマグカップを見て、緊張の糸が切れたのか、綾佳は人知れず大粒の涙を流した。父親のほうも母親の死以来、どうも元気がない。
そんな日々からもしばらく経ち、綾佳は母親の死を何とか受け止められるようになってきていたが、今度は綾佳の心は何とも鈍い気分に包まれるようになっていた。可奈に買い物に誘われたのは、そんな時だった。気乗りはしなかったが、断るのも悪い気がしたし、かかってきた電話では明るい可奈の声に押されて、しかも電話はすぐ切れてしまったので断る暇もなかった。かけ直して断りの電話を入れるのもめんどくさくて、ついに今日買い物に行くことになってしまったというわけだ。
電話の時に言われたとおり、可奈は店の建物の影になっている入り口で待っていた。そして無言で挨拶を交わすと、まず綾佳のほうが声を掛けた。
「暑くなかった?」
可奈が首を振る。
「大丈夫、私は暑さより冷房の寒い方が苦手なの。アヤのほうこそ、暑くなかった?」
「夏は暑くてあたりまえ、もう慣れちゃった。」
綾佳のその言葉を聞いて頬を綻ばせると、
「さ、早く行こ。」
可奈は綾佳の腕をつかんで引っ張り、自動ドアを通って建物の中に誘導した。冷房の冷気が肌に触れる。
ショッピングモールの中は騒然とした明るい雰囲気に包まれていた。放送のBGMに人のしゃべり声、レジのキーを叩くような音、それら全てがガヤガヤとした雰囲気を醸し出していた。客の明るい様子を見て、綾佳は無意識のうちにため息をすると、可奈は戸惑った顔をした。しかし一転明るい顔に戻ると、可奈は綾佳の腕をまた引っ張った。
「うわー私ここ来たの初めてなんだー。」
可奈が吹き抜けの上を向いて大きな声を上げる。綾佳も見上げてみてその広さに驚いた。広大な空間に、たくさんの人が動いているのが見える。
「うわー!」
そして可奈は綾佳の方を向くと言った。
「今日はいろいろ買えそうだね!」
二人はその新装開店の巨大ショッピングモールの中を何時間もかけて歩き回った。まずCDショップで最新盤を確認して、試聴用の機械で試聴した後(可奈は他の客のことも考えずに12曲連続再生した)、本屋に入り新刊として棚に並んでいた有名人のエッセー本を読んだ。100円ショップでは可奈は小さなマスコット付きの携帯ストラップを買った。綾佳は、特別何か買うつもりがあったわけでもなかったが、思いついてお守りを一つ買った。父親にあげるつもりなのだ。そしてその後は洋服屋に入り、服を見て回って、可奈に言われて秋物の服をいくらかかった(「うん、似合うよ!」)。買い物の後はいろいろな店を回って貯めた福引き券を使って、回転福引きをすることにした。可奈はたわしが当たったが、綾佳は意図せずテレビゲーム機を当ててしまった(「アヤ、すごーい!」と可奈が言った)。乗り気でなかったはずの綾佳も、いつの間にか買い物を楽しんでいた。
「私、なんか甘いものが食べたくなっちゃった。あのソフトクリーム屋さんに入っていいかな。」
テレビゲーム機の箱の入った紙袋を手に提げながら、綾佳がはじめて自分から提案すると、
「うん、ちょうど私もそう思ってたところ。」
可奈は快諾した。そして二人はソフトクリーム屋のカウンターでいろいろと迷った後、結局綾佳はマンゴー味のソフトクリーム、可奈はグレープ味のソフトクリームにした。
二人で木で出来た一枚板のイスに腰をおろしてソフトクリームを舐めはじめると、綾佳はずっと疑問に思っていたことを言ってみた。
「ずっと疑問なんだけど、今日何でわたしなんかを買い物に誘ったの?」
可奈は少しの間無言でいると、その質問には答えずに綾佳のほうを見て、こう聞いた。
「アヤ、今日は、楽しい?」
綾佳はこの質問を不思議に思った。しかし、答えた。
「うん、楽しいよ」
「そう、ならよかった。」
可奈が微笑む。
「どうして?」
綾佳はまたキョトンとして聞いた。
「ちょっと前、先生から聞いたの。アヤのお母さんが亡くなられたんでしょ?」
「え?……うん、だけど」
「私たち、友達でしょ? 何かつらいことがあったら、話してくれていいんだよ。——私になんかに何が出来るかはわからないけど。」
そして間をおくと、可奈は急にうつむいて真面目な目になって言った。
「中学生の時だけど、私のお母さんが死んだの。交通事故で。」
綾佳と可奈は高校に入ってから友達になった。綾佳はまだ可奈の昔の話はあまり聞いたことはない。別段聞かなければいけない理由などなかったし、学校で何気ないことをしゃべっている限りそのような必要もなかった。だから、その話は初耳だった。確かに綾佳は可奈の母親を見たことがなかったが、そのような過去があるなど気づきもしなかった。
可奈の母親は可奈が中学生のとき死んだ。死因は交通事故。ひき逃げだった。買い物帰りに横断歩道を渡っていた可奈の母親を、信号無視の車が轢いたのだ。後続の車にまで轢かれた遺体はズタズタで、警察も尽力はしたが、事件の時に雨が降っていたこともあって証拠が集まらず、結局犯人は捕まらなかった。そしてそれ以来可奈は涙に明け暮れる日々を送った。父親は可奈のことを精一杯支えてくれたが、それでもたとえば授業参観の時に母親がこないと、その理由を思い出して暗い気分にならないことはなかった。
可奈はいっぺんに、そして淡々とそれらの話を言い終えると、こう言った。
「だからさ、アヤの気持ちよくわかるの。——あ、ごめんね、私になんかにアヤの気持ちわかるなんてそんなことないよね。うん。——でもさ、何となく……何となく、そんな気持ちがするんだ。」
綾佳は驚いてその話を聞いていたが、気づくと、
「そんな、交通事故のほうがひどいよ。わたしより大変な体験だよ」
慌てて言った。
「でもさ——」
可奈は顔を上げて話を続けた。
「でも父さんが言ってた。車を運転していた人を恨むなら、あの時雨が降っていたことを恨みなさい。そして、何かを恨む気持ちは誰かを守りたいというやさしさの裏あわせだから、どっちの気持ちも大切にしなさいって。」
「……そうだったんだ。」
可奈はソフトクリームのコーンの包み紙をゴミ箱に捨てると、立ち上がった。そして急に明るい顔になって振り返ると、綾佳に張りのある声で呼び掛けた。
「さあ、アヤ。花火大会が始まるよ! これを見逃したら今年の夏が終わらないんだから。早く行こうよ。場所取りしなきゃ! じゃないと立って見なきゃいけないよ。どこか座って観れる場所をさがそ。」
「うん、……うん!」
綾佳も包み紙をゴミ箱に捨てる。そして立ち上がった。
「じゃ、行こう」
デパートの出口のドアを通りすぎる時に、綾佳は可奈に声を掛けた。
「可奈……今日は——そして、いつもありがとね」
すると少しの間、可奈は驚いた顔をしたが、
無言で大きく頷いて満面の笑顔を返した。
そして夏の終わりを名残惜しむように、二人は花火を見物した。外の空気は、もう涼しかった。それは、夏の終わりだった。
綾佳は空に舞い散る花火を見て、心の中でこう呟いた。
(お母さん。私、可奈と友達でほんとに、ほんとに良かった。だってこんなに励ましてもらえる事なんてそう無いよね。そうでしょ、お母さん?)
母親の笑顔が花火をバックに浮かぶ。そして可奈のほうを見ると、視線に気づいた可奈がこちらに笑顔を返すのが花火の光に照らされて見えるのだった。
夏の終わりに
(2008.8.26)


