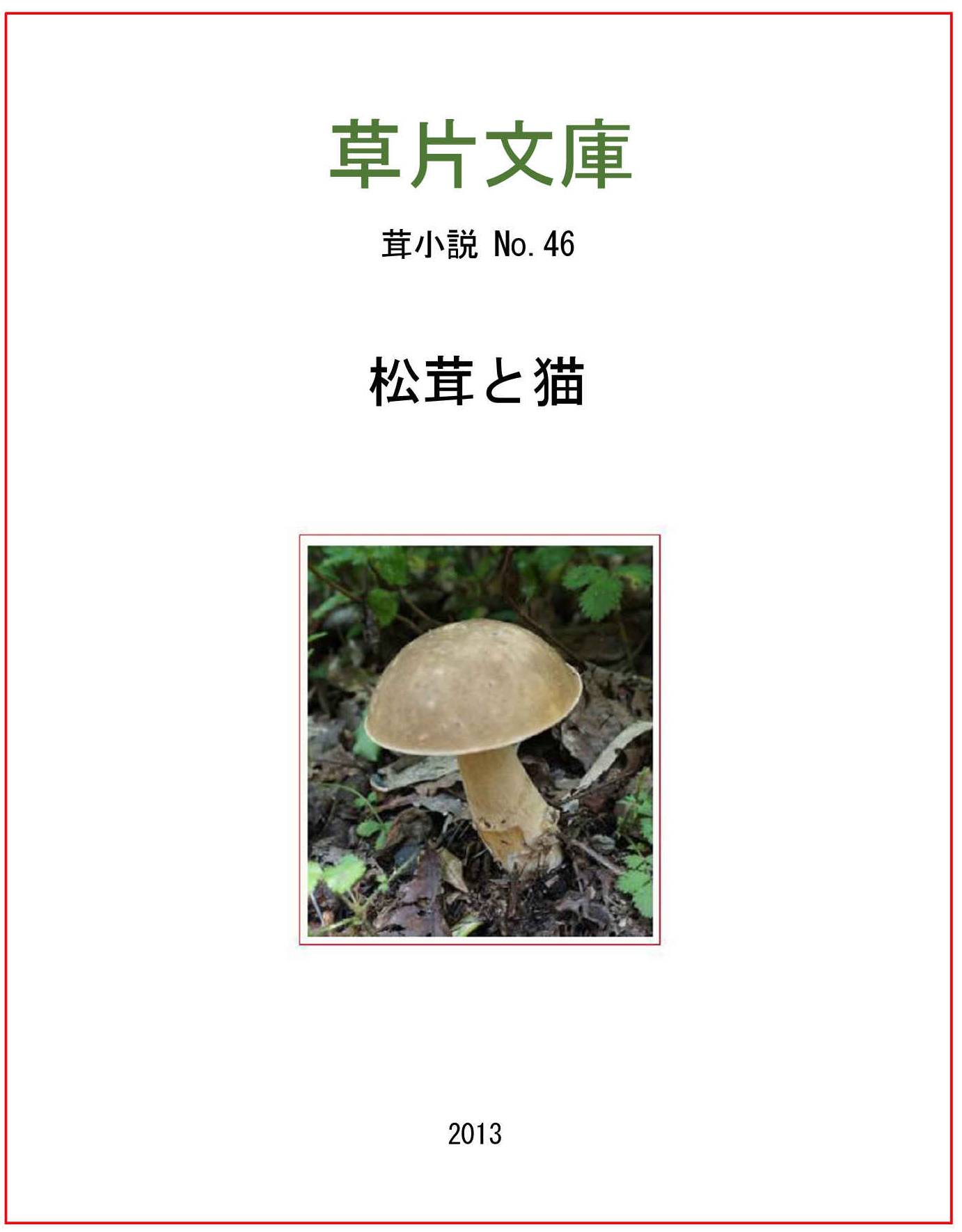
松茸と猫
もらった松茸を一本、庭の練炭コンロの上で焼いているときである。
「あちい」
という声が聞こえた。誰もいないはずである。空耳だろうか。
「あちい」
また聞こえた。網の上の松茸が身をよじった。松茸の言い香りが漂ってきた。
いきなり松茸が飛び上がった。松茸のやつ栓を開けておいた一升瓶を押し倒し、こぼれでる日本酒に頭を浸した。
「熱かったじゃないか」
明らかに松茸がしゃべっている。
「なら、土瓶蒸しの方がよかったか」
ちょっとひねくれた反応をしてしまった。
「湯加減がよけりゃな」
松茸の答えも大したものである。
「何で松茸がしゃべるんだ」
「なんで、木偶(でく)の坊が俺たちを食おうってんだ」
「なんだ、木偶の坊ってのは」
なんだか喧嘩の雰囲気である。
「茸から見りゃ、人間、特にお前は木偶の坊だ、虫や鼠や蛇やいろいろいるが、みんな六感をもっている、人間だけだぞ六感が薄くなっちまったのは、だから宇宙に反応できずに突っ立っている木偶の坊だ」
やけに理論的である、負けそうだ。
そこで、松茸の調子が変わってきた。
「おい、木偶、俺を生えていたところに返せ」
松茸が赤くなって叫んでいる。
「酔っぱらったのか」
「安い酒を喰らってやがら」
たちの悪い茸だ。
「どこでとっ捕まったんだ」
「京都の山奥だ」
「注意してないから、木偶に採られるんだ」
「おれたちゃ、顔出すと後は動けない運命だ、この運命には逆らえん」
「俺の友達が初めて採った松茸だと言ってあんたをくれたんだ、そいつは、百二十キロのでぶで、ゆったりとしていて、とても松茸など見つけることができないおっとりものだ、そいつに採られるんだから、よほどアホだ」
「俺様は松茸の中でも最も上等の種族だ、匂いが強いんだぞ、お前のだちは食いしん坊で、何でも食っちまうんだろう、きっと匂ったんだ」
松茸の言うとおり、あいつは食いしん坊で、食べ物しか目がない。しかも山など登らない奴が、社長のお供で仕方なく山に入ったんだ。社長や取り巻きはそれなりの松茸を採ることができたが、あいつはこの一本だ、それを俺にくれたのは、俺から借金しているからだ。本当はその場でこの茸を食っちまいたいくらいだったろう。
松茸が続けた。
「ずぼしだろう、ほら、電話をかけて友達に採った場所を聞けよ」
私は携帯をとった、だが、なんて電話しよう。ともかく電話した。
「おう、あの松茸食ったか」とあいつから声をかけてきた。よほど食いたかったんだろう。
「ああ、旨かった、それで、どこで採ったんだ」
「うーんと、社長の車に乗せられて行ったんでよくわからない」
「そうか、しょうがないな、また採ったら一緒に食おう」
そんなやりとりで、電話を切った。
「どこで採ったかやっこさん覚えていない」
「愚鈍だ」
「いや、あいつは切れる。必要なときにはすごいアイデアを出す。余計なことを考えないだけだ、あいつは大きな会社の課長だぞ、俺はまだ平だ」
「へん、すべてに気が回らない奴は、愚鈍だ、木偶の愚鈍だ、木偶(でく)鈍(どん)、うん、この言葉が言い、おまえの友人は木偶鈍だ、テポドンに似てなくもない、あのミサイルも愚鈍だ」
「おしゃべりが過ぎると、匂いがなくなるぞ」
私がそういうと、よほど匂いが大切なようで大人しくなった。
「帰る場所がわからなきゃ、おまえの家の居候だ」
松茸はそういって、我が家に入っていった。
「汚ったねえな、もっと整理しろ」
「うるさい奴だ、塩水に漬けてちょんぎっちまうから」
と言ったら、部屋の中を、床も、天井も、壁もなく走り回った。目が回る。
「ほら、捕まえてみい」
とうとう電灯の笠の上に立って、私を見下ろした。
「わかったよ、おまえの場所を作ってやるから、静かにしろ」
升に日本酒を並々と入れてやった。
「お、いいね、気がきくじゃないか、それがありゃ、大人しくしていてやらあ」
そう言って、升の酒の中に体をしずめて、
「いい、湯だな、あ、ははん」などと歌いだした。
松茸というのはこんなにおしゃべりなんだろうか。
「おい、俺はここにつかってりゃ満足だ、勝手に好きなことをやっていいぞ」
「当たり前だろ、俺のうちだ」
そこに外飼い猫の大山椒魚が帰ってきた。頭がでかく、太っていて、尾っぽがあまり長くない。上から見るとまさに大山椒魚なので、その名前を付けた。でも長くて呼びづらいので、結局、サンショ、サンショ、と呼んでいる。どっしりとしていて、たくさん飯を食う。後はどこぞへ遊びに行って、夕方家に帰ってくる。
サンショは私の顔を見ると、餌のおねだり声を上げた。
それを聞いた松茸は升酒の中で立ち上がると、
「オオ、久しぶりだ」
と大声を上げた。
サンショは松茸を見ると、
「お、茸ちゃんじゃないか、何でこんなとこにいる」
小さな目を大きくした。
「へへ、いろいろ訳があってね、もう少しでこいつに食われるところだった」
「そりゃ、あぶなかった、木偶の坊だからな」
大山椒魚まで私のことを木偶の坊だとぬかした。
私の方を見て、ほへという顔をした。本当のことを言っちまったという顔である。
まったく、松茸や猫になめられている。
「まあ、ゆっくり逗留していけや、きれいなところじゃないけど」
猫の奴、飼ってもらっていることも忘れて、いけしゃあしゃあと、外飼い主の前で、と思っていると、
「先生、すいませんな、つい地がでちまってね」
とサンショが私を見た。私は大学の教師をしている。独身。
私はむっとして、食いそびれた茸をどうしようかと考えていると、
「そいじゃ、しばらくいさせてもらおうかな」
松茸は枡の縁に腰を下ろした。
私はいつか捕まえて食ってやろうと思って、
「どうぞ、いつまでも」と言ってやった。
「この猫とも久しぶりに語らいたいし、ありがたい」
「どこで知り合ったんだい」
「こいつが子猫の頃さ、おれは、東京高尾山の赤松に生えた松茸の胞子だった、その赤松のふもとに、子猫が三匹捨てられてね、その一匹がこいつさね、ほかの猫はみゃあみゃあないて煩かったが、こいつだけは、生きることを考えてたね、食えるものはみんな食っていた、生命力の強い奴で、ほかの二匹は飢えて死んじまったが、こいつは生き延びて、とうとう、俺がくっついている松茸、すなわち親を食っちまった。俺は、そのとき傘の襞から離れ、飛び出すと、こいつの毛の中に入り込んだのだ。それからの付合いだ」
猫の大山椒魚が引き継いだ。
「助かったね、この茸ちゃんのおかげで、俺の毛の中から、風の流れを読んで、食べ物のあるところを教えてくれてね、それで最初の飼い主に拾われることになったんだ、命の恩人だ、だけど、台風のある日、外に出たら、胞子のこいつが風にとられて飛んでいっちまった。命の恩人が飛んで行っちまったんだぜ、さみしかったし悲しかったな、こうして会えるとは思わなんだ」
「ほー、奇遇だな、それで、サンショはなぜ俺の家にきたんだ」
「飼い主のばあさんには大事にされて幸せだったが、死んじまってね、身よりのないばあさんで、俺は追い出されたのさ、そして放浪の旅にでて、このあたりにすんでいるんだ」
「そのあと、飼い主はみつからなかったのか」
「うんにゃ、あんたのところで飯を食う数が一番多いが、ほら、一つ下の通りあの美人、三味線のお師匠さんにもかわいがられているんだ、紹介してやろうか」
「お世話にゃならん」
「ふん、もてず独身」
「口の悪い奴だ」
「それで、松茸はそれからどうした」
「台風に巻き上げられたのはいいんだが、変な台風が来たことがあったろう昔に、関東に上陸して日本海に抜けたのはいいが日本海を南下して、鳥取のあたりでまた上陸して関西でいきなり消滅したやつが」
「たしかにあった、もう十年ほども前だろう」
「そうだよ、そいで、俺は京都の山に不時着し、赤松の元で菌糸をのばして、十年たってやっと俺様が出てきたのだ」
「ほー。辻褄があうな」
「やっと出てきたら、あのデブの木偶の坊に見つかっちまった、運が悪い、というか、しかし、こうやってこの猫に会えたんだから運がいいのかもな」
ということで、松茸の奴、毎日日本酒の升の中で歌を歌ってのんびりしてやがった。大山椒魚も我が家からでなくなり、松茸と今までのことを話していたのである。
私が仕事から帰ると、食えない松茸のいい匂いだけがする。部屋に入ると、二人してなにやらひそひそと話している。
「おい、なにたくらんでいるんだ」
「おまえさんに、嫁さんを世話してやろうってんだ」
「だから、よけいなお世話だって言っているだろう」
「貧乏ったらしい生活から足洗えよ」
「よーおし、料理上手できれい好きな嫁さんをもらって、茸料理でもしてもらうか、猫の毛の嫌いな奥さんだと、大山椒魚は入ってこれなくなる」
「へん、探してみろ」
一番苦手なことを突っつきやがる。
「居候なら、居候らしくしろ」としかると、
「へい」としおらしく二人でしゃべりはじめる。
そんな暮らしが一月ほど続いたある日、大学から帰ると、松茸の匂いが強くして、部屋の中がもやっている。
「なんだこれは」と部屋を見ると、大山椒魚が、床の上に横たわっている松茸を見て涙を流している。松茸から胞子が空気中に吐き出されている。煙っているのはそのせいだ。
「おい、木偶の坊、松茸の奴寿命だって言っていきなり倒れると胞子をまき散らし始めたんだ、それでな、
『こんなに楽しい茸生活を送れたのは幸せだ、あいつに感謝いていると言ってくれ』だとよ、さらにな『焼いて食ってくれ』ってさ、土葬より火葬のほうがいいな、なんて言いながらさ」
「そりゃ、悲しいことだな」
「食ってやれよ」
大山椒魚が涙して頼むので、練炭コンロに炭をいれ火を起こして、網の上に松茸を載せ焼いた。一緒にいたせいで、どうも食欲はわかない。其れでも焼けてくると、いい匂いが漂ってきた。
醤油を持ってくると、
「おい、半分食え」と松茸を裂いて、大山椒魚にやった。
複雑な気持ちだが、おいしい松茸だった。
「こいつ、俺が子供の時に食った親のように旨いや、あんときゃ、腹が減って死にそうだから旨かったのかと思ったけど、そうじゃねえ、本当に上等な奴だったんだ」
大山椒魚は涙ながらに松茸を食べた。
「旨かった、ありがとよ、木偶の坊の旦那」
大山椒魚は猫穴からそう言って出ていった。
と思ったら、戻ってきて、猫穴から、
「あいつたくさん胞子をだしていきやがった、きっと近くの松の木にゃ、子どもがたくさん生えるぜ、食ってやんなよ」
そう言った。
それっきり大山椒魚は家に戻ってこなかった。
友達を食った大山椒魚の複雑な気持ちは私には分からない。
そりゃ、人間は木偶の坊だからな、といわれそうだ。
松茸と猫
私家版 第九茸小説集「茸異聞、2021、一粒書房」所収
茸写真:著者: 長野県北安曇郡白馬村 2016-9-12


