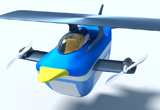コトノハコダマ奇譚
第一話 影仁 ――ヒナタヒロ――
―― 刺さり続けた小さな棘 第一話 ―――――
――その日も大森瑞葉はいつものように、家族と一緒に夕食を食べて、しばらくテレビを見てから二階にある自分の部屋に戻ってきて。真っ暗な部屋の中で、ケータイの着信ランプがチカチカと点滅しているのを見て、内心では期待に胸を膨らませながらも落ち着いて、まずは部屋の電気をつける。
そのままベッドの上に寝転がって、枕元の台の上に置かれたケータイを手に取って。メールの着信履歴を見て、期待した相手じゃないことに少し落胆をして。
でも珍しい相手だよね、何だろうとメールを開いた瑞葉は、その内容に思わずアリエネーなんてこぼしつつ、「ごめんなさい」と打ち込んで送信をする。
……いやあ、頑張って書いたんだと思うけどさ。でも、大して仲が良いわけでもないのにメールで告白してくるとかさ、ダメダメだよね。全く、コーコーセーはこれだからなんて思いながら、携帯電話を待ち受けに戻して充電スタンドの上に置いて。まあ、自分も同じ高校で、しかも同級生だから偉そうなことは言えないんだけど。
まあ、その気があるっぽいのは薄々感づいてたし、私もフリーってことになってるけどさ。でも悪いね、実はもう相手がいるんだよねと、心の中で呟いて。
……ま、もうちょっとレベルが高かったら考えてあげても良かったかも、だけど。でも、こんなメールを送ってくるようじゃねと、そんなことを思いながら、ここ最近なかなか会えないでいる「彼」のことを思い出す。
自分よりも十以上も年上の、出会い系サイトで知り合った「彼」。何度か会っている内にお金のことも「まあいっか」なんて思うようになってしまった、表向きはとてもそんなことをするようには見えないような、優しくて家庭的な若いパパとして振舞っている人の姿を。
――大森瑞葉は気付かない。単に背徳的な遊びに興じているだけだと思いながら、自分が既に、深く昏い何かに足を踏み入れていることを。
―――――――――――――――――――――――
いつもの小説投稿サイトにいつもの時間。推敲を終えて記念すべき第一話を投稿した影仁は、あとは結果を待つだけと、パソコンデスクから目と鼻の先にあるキッチンにまで足を運び。流しの横に置いたコンビニ袋から夕食に買っておいたのり弁を取り出して、レンジに入れて。
温めている間に、一緒に買ってきてあったサラダとペットボトルのお茶をパソコンデスクに並べて。最後に、「準備完了」なんて言いながら、チンした弁当をパソコンデスクの中央、空けておいたスペースに置いて。
飾り気のない事務的な机の上に所せましと並べられたいかにもな夕食に、影仁は思う。――うーん、見事なまでに「男の一人暮らし」だなぁ、と。
――影仁は知らない。「男の一人暮らし」が生み出す異世界を。
そもそも男という生き物は、掃除洗濯を毎日きっちりとこなせるようにできていない。掃除は足の踏み場がなくなってからすれば良いと思っているし、ゴミはたまってから出せばいい、洗濯は週に一度まとめてやるものだと、そう信じて疑わない生き物で、仕事が忙しかったり遊びに誘われたりするだけで、あっさりと先延ばしにしてしまうのだ。
彼らは知らない。異世界はいつも、目の届かない場所で、ひっそりと育つということを。そして、すくすくと元気に育った異世界を目のあたりにして、ようやく悟るのだ。
――これが男の一人暮らしか!、と。
そんな世の中の真理も、普段からマメに掃除洗濯をこなす影仁には無縁な話で。狭い中、常に整理整頓を欠かさず小ぎれいな状態に保たれた影仁の部屋は、むしろ自信を持って客を呼べる部類の部屋だろう。
だが、そんなこの世の異世界のことを知らない影仁は、この部屋を見て「そのうち何とかしないとな」なんて少しピントがずれたことを思いながら、毎日を過ごしていたのだ。
そんな、狭いながらも手入れの行き届いた、機能的にまとめられた部屋の片隅で。お手軽でお値打ちな夕食を平らげて後片付けまで済ませた影仁は、再びパソコンデスクに座って、パソコンの電源ボタンを押す。
しばらくして、パソコンが省電力から復帰したのを確認して。慣れた手つきでマウスを動かして。いつものようにブラウザを立ち上げて、小説投稿サイト、SNSの順に開いた影仁は、早速SNSの方にメッセージが届いているのを確認ををする。
「昭和な現代物! それものっけから不穏ワードが! ヒナタっち、いつからそんなそんなキャラに!」
いつもの相手からいつものように届いた、気安い言葉。その言葉に軽く笑いながら、影仁はキーボードの上に手を置いて。このお得意さまになんて返事をしようかと考え始める。
コトノハコダマ。影仁がヒナタヒロという名前で小説家サイトに投稿を始めた頃からの読者で、生まれて初めて書いた自分の小説に「どこか透明で、だけど強く響くような言葉で紡がれた物語ですね」という、むしろ自分の書いた小説よりも心に残るんじゃないかというような詩的な感想を残してくれた人。
その後もずっと自分の小説を読んでくれていて。気が付いたらお互いにSNSで気軽に言葉を交わすようになっていて。
……とはいえ、互いにプライベートには立ち入るわけでもなく。あくまでも作者と読者という距離感を保ちながらも、他愛もないことを話し合ったり、時に忌憚のない意見を交換しあったりして交流を深めていった相手。
――そんな、互いに顔も年齢も知らないような関係でありながら。コトノハコダマという人は影仁にとってとても大切な、ただのいち読者と割り切ることの難しい相手でもあった。
そんな彼女からのメッセージに影仁は、頭の中に浮かんだ返事を素早く打ち込んで、返信をする。
「読んで頂いてありがとうございます。……って、そこまでレトロじゃないから」
「え~! でも、このケータイって、アレでしょ? 昔懐かしの折りたたみケータイ!」
「昭和は1980年代まで。ケータイが普及したのは1990年代。ケータイ文化は平成の文化です」
「相変わらず調べてるよね~」
次から次へと、まるでチャットのようにメッセージを送りあいながら。普段と変わらない相手の様子に、影仁はそっと安堵する。コトノハに指摘されるまでもなく、影仁は今回の話が、今まで自分が書いてきた小説と違う方向性の話になることをはっきりと自覚していたのだから。
別に僕はコトノハさんのために小説を書いているわけではないけれど。それでも、彼女は大切な読者の一人だから、できることなら読んでほしいし楽しんでほしいよねと、そんなことを思いながら彼女とやり取りをして。他の人からの感想に目を通して、返事をして。そろそろ次の話の準備をするかなと、書き溜めておいた次の話を読み返し始める。
――まったく、何度読み返しても手直ししないといけないところが出てくるのは何とかならないかなと、そんなことを思いながら。
◇
その夜、影仁は夢を見る。それは、ねばりつくような空気の感触と、表現しがたいような重苦しさと生々しさに溢れた夢で。その夢の中で影仁は、何か文字の羅列を見ては空っぽの胃の中を吐き出して。遠くから聞こえてくる心地よい言葉に癒されて。そしてまた、文字の羅列を見て、吐き出して。
文字の羅列から目を背ければ苦しむことはない、そう理解しながらも覗き込んで、限界まで文字を追って。吐き出して、癒されては覗き込んで。
――そんなことを夢の中で、目が覚めるまで繰り返した。
第二話 惰性
―― 刺さり続けた小さな棘 第五話 ―――――
――サイテー。
門人に最後に会ったのはもう一月も前。こちらからの電話には出ない、メールは放置。っていうか、この前見たら削除してたし。そうね、家族がいるからね。ウンウン、私だって子供じゃない、言われなくたってわかるわよ、その位。
――バッカじゃないの! そういうことじゃないでしょ! じゃあどうすれば良いって!? 私に聞くな!、そんなこと!!
確かにこの前、そう言ってやったよね。なんか宥められてウヤムヤにされて、都合の良いように扱われて帰ってきたけどさ。
……いつからさ、こんな風になっちゃったのかな、私たち。
初めは違ったよね。そりゃあ人目は避けてたけどさ、二人で食事もしたし、買い物にだって行った。並んで歩いてさ、おんなじものを見て、笑ってさ。そりゃさ、そんなのがいつまでも続かないなんてわかってたけど。でも、だからって、これは無いんじゃない?
それでもきっと、次にメールが来たら、きっと……
……ホント、バッカじゃないかなと、今まで何度も思ってきたことを思い出して。感情を乱されて。ああもう、考えても仕方がないと、ケータイを閉じて、布団にもぐる。
――そうしてまた、今までと変わらない今日が終わり。今までと変わらない明日が始まる。
―――――――――――――――――――――――
「……うわぁ」
「援交の果ての不倫なんて、こんなもんでしょ」
「……ねぇ、ヒナタっち、ホントにキャラ変わった?」
続く第二話、第三話を投稿して。コトノハさんから返ってきた反応に、影仁はどこかすましたような言葉を返しながら、以前彼女から聞いたことを思い出す。
――そういえばコトノハさん、「感情が前に出た」作品が苦手なんだっけ、と。
あれは確か、面白い投稿小説を紹介しあっていたときのことだろうか。いくつかお勧めの小説をコトノハさんに紹介したときに、「悪くないと思うんだけど読めない」みたいな反応をされたことがあって。
……確か、「作品に込められた感情にあてられて、気分が悪くなる」なんて言ってたっけと、そんなことを思い出す。
パソコンの画面に表示された「キャラ変わった?」という言葉の返事を考えながら、影仁は思う。確かに、今のこの場面を好き好んで書いているかと言われれば違うだろうし、そういった意味では多分自分らしくないのかなと。
そう思って、一度は「書きたいものを書くためには、今のこの場面は書かなくてはいけないから」と返事を入力して。その文章を読み返して送信ボタンを押す前に、ふと思いなおして、文章を打ち直す。
「今のこの場面も含めて、書きたいものだから」
――打ち直した文章を見て。うん、やっぱりこっちだなと納得をして、頷いて。
今書いている場面が、この先に必要になるから書いていたとしても。それでもやっぱり、今の場面だって、嫌々書いているわけではないのだから、言い訳のようなことを言うのは違うと、そんなことを思いながら、影仁は送信ボタンを押して、入力したメッセージを相手に送信した。
◇
そんなことを思いながらも、影仁は今までと同じように更新を続けて。更新後、素早くいつものように感想をくれるコトノハに感謝をしながら、その言葉のやり取りを楽しむ。
「卒業して、就職してもそのままかぁ。『愛してるなんて言葉、歯が浮きすぎてアホらしい』って瑞葉ちゃん、わかってるのならなんとかしよ? ――無理かなぁ」
その日もいつものように更新をして。少しだけ間を置いてからコトノハから届いたメッセージに影仁は、「しょうがないんじゃないかな、瑞葉の性格だと、そこで割り切るのは難しいと思うよ」と、少しぼかした返事をする。
実際のところ、瑞葉を動かしているのは執筆している影仁自身で。そう考えるとこの返事もかなり白々しいと、彼自身思わないでもないのだが。
それでも、彼は瑞葉がそんな性格をしていないと本気で思っていて。そのことをわかっていたのだろう、影仁のメッセージにコトノハも「だよね~」という気軽な返事を返してくる。
「やっぱりコトノハさんもそう思うよね。うん、いつもありがとうございます」
「いやいや、こっちこそ楽しませてもらってるよ。じゃ、また~」
最後にそんな言葉を交わして。影仁はその日のやりとりを終えた。
◇
――またあの夢か。
次の日の朝、目が覚めた影仁は、つい先ほどまで見ていた夢を思い起こす。以前も見た、文字の羅列を覗き込んでは苦しんで、癒されては覗き込むのを繰り返す、あの夢。それはまるで命を削るような行いで。
――それでも、どれだけ苦しくても、その行いを当たり前のように繰り返すことに、心のどこかに引っ掛かりを感じていた。
◇
「せっかくのコンパも断っちゃって。瑞葉っち、閉じこもってくなぁ。ほら、その『遊くん?』、軽そうだけど実は良い人だよ?」
再び最新話を投稿して。いつものようにコトノハから届いたメッセージを見て、影仁はパソコンモニタの前で、困ったような表情を浮かべる。
……えっと。確かに今回登場させた横櫛遊之助というキャラは、「実は良い奴」なんだけど。とりあえず今は名前を出しただけで、性格なんてわかりっこないはずなんだけどなぁと、そう思った影仁は、少し言葉を選びながら、どうして遊之助が良い人だと思ったのか、コトノハに尋ねてみて……
「う~ん、ヒナタっちの性格? だってこのままじゃ、瑞葉っちがあんまりじゃない? バカな女が深入りして不幸になるだけの話をヒナタっちが書くはずないかなぁって。で、チャラそうなキャラが出てきたから、ヒナタっちなら『実は良い人だった』って逆をついてくるかなって」
コトノハから返ってきた言葉に、影仁は軽く頭を抱える。……うん、まあ、非公開メッセージだし、別にネタバレしても良いんだけど。うん、でもやっぱり返す言葉が思いつかないよなぁ。
「……そういう見方をされては困りますな、お客さま」
「大丈夫! ヒナタっちのこと、信じてるから!」
影仁は悩んだ末に、結局ぼかした返事をして。即座に返ってきたコトノハの返事を見て脱力する。
――ああ、もうこれ、ネタバレしたようなもんだよな!、と。
◇
再び見た夢に、影仁は気付く。
――ああ、そうだ。あの「文字の羅列」は、命を削ってでも追いたいんだ、と。
◇
その日も影仁は、いつものように小説サイトに投稿して。いつものようにコトノハと、少しバカ交じりのやり取りをして。ふと、以前コトノハの言っていたことが何故か気になって。思い切って彼女に聞いてみる。
「そういえば。以前、『感情にあてられて気分が悪くなる』なんて言ってたけど、大丈夫? 今回の話、正直、あんまり綺麗な話じゃないと思うんだけど」
質問を入力して、送信ボタンを押して。入力中のメッセージが送信済みに置き換わったのを見た影仁は、なぜこんなことを聞こうと思ったのか、遅まきながらに気付く。
――ああ、そうだ。あの夢のことが気になっているんだ、と。
この連載を始めてから見るようになった夢。あの夢は、今にして思えばいつも最新話を投稿した日の夜に見ていたと、そんな引っかかりを覚えていて。
……だけど、画面の向こうにいるコトノハは、影仁のそんな漠然とした不安とはまた違ったことを思ったのだろう。いつもよりも少しだけ間をおいてから、影仁に対し、ためらいがちな口調でメッセージを送ってくる。
「そうだね。正直ちょっと読んでいてきつい時もあるんだけど。……ただ、ヒナタっち、これ、少し言いにくいんだけどね」
コトノハから送られてきた、その先が気になるメッセージを見て、影仁は少し息を飲んで。ほんの少しだけ間をおいてからコトノハから送られてきた「はっきり言ってこの話、ヒナタっちが思っているほどドロドロしてないと思うよ」という言葉に虚を突かれたのだろう、影仁は一瞬だけ動きを止めて。そのあと、大きなため息をつく。
「普通、こういう話を書くと、こう、もっとドロっとした感情が込められててもおかしくないと思うんだけど。これがそんな話だったら、悪いけど私、例えヒナタっちの書いた作品でも読めないよ。
ヒナタっちはね、こういう話を書いても、なんというか。瑞葉っちもね、ホントにダメなんだけど、それでもどこか一途なんだよね。どこか憎めないんだよ。うん、やっぱりちょっと珍しいと思う。もしもドロドロした話を書きたくてこの話になったのなら、はっきり言ってヒナタっちは向いていないと思う。
――大丈夫、これはこれで味があるから。それにヒナタっちは『けがれなき作家』って、ちゃんとわかってたから!」
最初はためらいがちだったのに、途中から筆が乗ったのかストレートな物言いになって、最後はノリノリになったコトノハの返信を見て、影仁は軽く脱力をして。……それでも、引っ掛かっていた嫌な気分は晴れたのだろう、やや軽い口調で返信をする。
「お褒めに預かり光栄です。――実はそうじゃないかとうすうす感じておりました」
「やっぱり~(笑)、気付かない訳ないよね~(笑)」
即座に帰ってきたコトノハの返信を見て、影仁は思う。
――まあ、コトノハさんは好意的に見てくれてるけど。けどこれって、良いことなのか、悪いことなのか、どっちなんだろう、と。
◇
そうして、コトノハとのやりとりを終えた影仁は、一つのテキストファイルを開く。――今までコツコツと書きためてきた、来週公開する予定の話が書かれたテキストファイルを。
今もまだ書き途中の、この物語のターニングポイントともいえる話をまずは一読して。カーソルを移動して、手を止めて、打ち込む文章を考え始める。
―― 影仁は思う。この話だけはしっかりと、「自分が表現したいと望んだ感情」を込めなくてはいけないと。
そして影仁は、この場面、この状況に直面した瑞葉が抱くであろう「感情」を思い描き、思い浮かべ、思い出す。
それはきっと、嫉妬だったのだろう。怒りだったのだろう。好きな人がいて、その人には好きな人がいて、その好きな人は鈍感で。その時が来るまで、みんな仲がよくて。あれはきっと、どうにもできなかった話で。どうにかできる奴は何も気付かなかった、そんな話で。
あの時はわからなかったけど。あの時に抱いた感情こそが、影仁が表現したかったもので。今はその感情がどんな感情だったのか、影仁は理解していて。
ただ、趣味で小説を書くために必要という、たったそれだけの理由で。影仁は、過去に一度だけ友人に対して抱いたその感情を思い出そうとしていた。
――「殺意」という感情を作品に込める、ただそれだけのために。
◇
――その日の夜、影仁はまた、あの夢を見た。
第三話 殺意
―― 刺さり続けた小さな棘 第十二話 ――――
――それは、ある晴れた日の出来事。
気が付けば、就職してからそろそろ三ヵ月くらいが経とうとしていたある日の夜。高校時代に仲のよかった友人の上野優菜が引っ越しをするから、手伝いがてらみんなで押しかけないかなんてメールが来て。どうやら彼女、就職先での新人研修が終わって配属先も決まったから、その近くのアパートを借りて一人暮らしを始めるみたい。正直、その話を聞いたときは、いままでずっと新人研修だったの、なんて思ったんだけど。だってもう、入社してから半年よ、半年。新人研修なんて普通、一二週間じゃないの。
……そう思ったんだけど。えっと、他の友人たちに聞いたら、意外とまちまちで。私と同じように一二週間の子もいれば数か月とかいう子も結構いて。結構会社によって違うんだと、久しぶりにみんなで笑いあって。
そんなわけで、優菜の引っ越しの手伝いと、あとちょっとしたお祝いをしようなんて話が持ち上がって。週末に高校時代の友人四人で、駅から少し離れた所にある2DKの部屋にお邪魔する。
「へぇ~、意外と良い部屋じゃん?」
「ちょっと狭くない?」
「……この部屋に会社のお金で住めるのはズルい」
「別にワンルームでも良かったんだけどね」
部屋の中にみんなでぞろぞろと入りこんで、当の優菜も交えて好き放題なことを言いながら、まずは部屋の中でくつろいで。じゃあとっとと片付けて宴会だなんて言いながら、部屋の片隅に積まれた段ボールと戦い始めて。意外とあっさり片付いて。
夕飯を食べに出て、お酒とツマミを買って部屋に戻って。カンパイして。気がついたらみんなで雑魚寝してて。
「ありがとー」
「いやぁ、むしろ邪魔しちゃってない?」
「全然! 助かったよ」
そうして次の日の朝、飲み会の後片付けをしてから、彼女の部屋をおいとまして。バイバイ、さよならと、みんなで彼女に声をかけて。うん、久しぶりに高校時代の友人たちとの楽しい時間だったね。
――その帰り道。
「じゃ、私こっちだから」
彼女の部屋から少し歩いた先の、信号のある交差点で。今まで一緒に歩いてきた友人たちに、そう声をかける。
「あれ? 瑞葉、駅こっちだよ?」
「ううん、こっちの駅の方が楽だから」
「……おお、ハイテク」
来た駅と違うところに帰ろうとする私に声をかけてきた友人に、あらかじめケータイで出しておいた地図を見せて。来た時に使った駅でも帰れるけど、ちょっと遠回りになるからと説明する。うん、一回街中にまで出て乗り換える形になっちゃうからね、できれば避けたいよねと。
「そういえば瑞葉っち、携帯変えたんだっけ?」
「あれ? 就職したら普通、変えない?」
「……瑞葉、たまにオタクが入るよね」
別れ際、信号待ちの間にそんなことを話し合って。……うん、ちょっと聞き捨てならないよね、オタクってどういうことって聞いたら、普通は就職したくらいでケータイは変えない、就職直後にメアドが変わったの瑞葉だけ、なんて言われて。一斉に頷かれて。えー、だって、高校の時のケータイなんてオモチャじゃんなんて、そんなことをワイワイと言い合ってから、みんなと別れて。
一人で少し歩いてから、やっぱりみんなと一緒に帰れば良かったかななんて思ったけど、後の祭りで。ケータイの見にくい地図を見ながら、頑張って、目的の駅までたどり着こうとして。
一本中に入った小さな道から、聞き覚えのある声を聞いた気がして、足を止めて。少しだけ悩んでから、そちらの方に足を向ける。
――それは、ある晴れた日の出来事。瑞葉はその日、いままでずっと会ってきた人の、表の顔に初めて出会う。
それは、今まで会ってきた彼と同じ顔で。その顔には、今まで彼に会ってきた自分には得られなかった、あたたかで幸せに満ちた表情を浮かべていた。
―――――――――――――――――――――――
書きあがった文章を読んで、違和感を感じたところを修正して。もう一度読み直しては修正する。そんな地道な作業を黙々と繰り返していた影仁は、ようやくある程度満足したのだろう、修正した文章をファイルに保存してから軽く背伸びをして。少し暖かいものを飲もうと席を立って。
――やがて、笛吹きケトルのピーという音が、小さなワンルームの部屋の中に鳴り響く。
ガス台の前でお湯が沸くのを待っていた影仁は、素早く火を止めて、あらかじめ準備してあった急須にお湯を入れて。そのまますぐに、少し大きめの湯飲みにお茶を注いで。多分貧乏症なのだろう、もう一回、急須にお湯を継ぎ足してからお盆に乗せて、パソコンデスクまで運ぶ。
そうして、再び椅子に座った影仁は、自分の入れたほうじ茶をずずずと飲み込んで。これぞ男の一人暮らしだねぇなんて思いながら、張りつめていた気を解きほぐして。
――そうして、休憩を終えた影仁は、再び筆を執る。ただ黙々と、今書いている文章が物語となって産声を上げる、その時まで。
―――――――――――――――――――――――
瑞葉が足を向けた先、そこは静かな住宅街の一角で。小さな敷地に建てられたありふれた一軒家の玄関の前で、つい今ほど出てきたであろう一つの家族の姿を、彼女は交差点の反対側から、ぼんやりと見続ける。
――それは、どこにでもある、なんてことはない家族の風景で。
初めて見る家の前であの人は、元気そうに歩きまわる子供に話しかけて。その子供も、じっとしていられないとばかりに玄関の前を行ったり来たりしながら、父親の言葉に耳を傾け。
――もう少しでママも出てくるからおとなしくしてなさい、はーい、そんなありふれた会話に、瑞葉の心は凍てついて。
やがて、再び玄関の扉が空いて。先ほどの子供よりも少し年上の女の子と、その女の子と手をつないだ「ママ」が出てきて。おまたせ!、おそーい!、こら、わがまま言わないのと明るく言い合う言葉が、耳から身体の中に入ってくる。
そんな幸せそうな会話に、でもその幸せは、まるで目の前に壁があるかのようにはじかれて。立ち止まって、身動きすることも忘れて。やがて、たまたまこちらの方を見たであろう門人が、私の方に気が付いたのだろう、とっさに目を反らして。その映像が、久しぶりに見るアノヒトのそんな態度が、私の心をどこかに吸い寄せる。
――ははは、ははははは。瑞葉の心が軋んで嗤う。
こっちを見ない門人の方に顔を向けて、身体を向けて。一歩、前に進んで。バッグのひもを固く握りしめて。もう一歩、前に進んで。門人の方を見て。アノヒトの方だけを見て。近づいてくる車の音も、こちらを指さして何かを叫ぼうとする子供の姿も気にも留めず、ただアノヒトだけを見て。このヒトは、このヒトはと、さらに一歩、前に進む。「……ない」と叫ぶ声は見えない何かに弾かれて。吸い寄せられるように、さらに一歩、前に進んで。はははは、はははと心が嗤い続けて、塗りつぶされて、コ……
――吸い寄せられるように歩く瑞葉と、その視線の先の一家団欒とを分け隔てた住宅街の小さな交差点で。日常と非日常をかき消すような甲高い音を立てながら、一台の軽自動車が瑞葉の目前にまで迫って。彼女の少し前で、かろうじて停止する。
窓ごしにこちらを見て、こちらに怪我がないことを見てとったのだろう、運転席の女性が少し甲高い声で「危ないわね、気を付けなさいよ!」と叫んで、走り去って。その様子をぼんやりと眺めて。
遠ざかる車が見えなくなって、全身から力が抜けて。その場にかがみこんで。「……じょうぶ?」そんな子供の声がすぐ目の前から聞こえてきて。すぐ目の前に女の子がかがみこんで、心配そうにこちらを見ているのに気が付いて。「大丈夫、ごめんなさい」そう返事をして立ち上がって。もう一人の子供と、女の人もこちらに駆け寄ってくるのを見て。
「お怪我はありませんか?」
「はい、大丈夫です。ご心配をかけてごめんなさい」
その声はとても優しくて。それでも。きっとアノヒトの前でこの人と言葉を交わしたらいつかおかしくなってしまうと、すぐにその場を立ち去る決意をする。今も目をそらして玄関の前に立ち尽くすことしかできないようなヒトなんかほっとけば良い、私の居場所はここに無い。だから早く、少しでも早くこの場から立ち去らなくてはいけない。
――アノヒトなんかどうでもいい。だけど、あの人たちをこれ以上見てはいけない。これ以上見たら戻れなくなる。悲鳴を上げた私の心がそう叫んでた。
―――――――――――――――――――――――
影仁はキーボードを叩いて、筆を走らせる。文を紡いで、読み返して、消して、削って、書き加えて。タタタと音を立てながら、一つの感情を文字にしていく。それは、最初は影仁の「考えた」文章で。やがてそれは、影仁が「抱いた」感情が込められた文章になっていって。いつしかその文章は、まるで影仁の心の中に住む瑞葉の感情を代弁するようになっていって。
――筆を走らせて、見直して。影仁は自分の書いた文章に、確かな何かを感じ始めていた。
―――――――――――――――――――――――
閑静な住宅街を、その景色をゆがませながら、瑞葉は一人歩く。深呼吸しては先ほどのことを思い出して。涙を拭いては、あの人のそむけた視線を思い出して。
どうすればいいかなんてわかり切っていた。そんなこと、昔からわかってた。それなのにどうすればいいかわからない。昔からずっとそうだったと、同じことをグルグルと考え続けて。それでも……
――もうダメだ。もうこれ以上はダメだ。そんな考えだけが、繰り返し頭をよぎる。
あの時、私はアノヒトの姿を見て、何を考えた。あの時、あの人たちのことを見て、何を考えた。わかっている。あの時、ずっと目を背け続けたアノヒトに、何も期待することなんて無いことは。何より私は、確かにあの時、門人に――を抱いたのだから。
ああ、うん、そうだ。あの時、何かを考える余裕なんてなかったけど、あれは確かに、そういう感情だった。
――あんなのはもう嫌だ。こんなのはもうたくさんだ。……なのに、どうして同じことを考えるのか。もうダメなのに。なのにいつまでも、いつまでも。
……それでも。自分の中の何か、自分を縛り付けていたものがちぎれ散ったことを、瑞葉は心の片隅で、確かに感じ取っていた。
―――――――――――――――――――――――
そうして、影仁は何度も繰り返し推敲をして、少しずつ、その「何か」を文章に込めていって。最後の最後まで推敲してから、いつものように投稿をして。食事をとって、風呂に入って、一息ついて。
――いつものように、小説投稿サイトやSNSを巡回して。そのどちらにもコトノハの感想が書きこまれていないことを確認した影仁は、そのことをほんの少しだけ残念に思いながら。まあでも、今日の話は感想を書きにくいよねなんて思いながら、いくつか書き込まれた感想に返事をしていった。
◇
――その日、影仁は夢を見る。
それは、今までに何度も見た夢で。
その夢の中は、今までに何度も味わってきた生々しさで。
――今までとは違う、突き刺すような痛みに、影仁は声なき悲鳴を上げる。
今までとは違う、鋭い感情にその身をさらされながら。
それでも、魅入られたように文字の羅列を追い続ける。
それはきっと、あの人を見て抱いた殺意で。
それはきっと、あの子を見て逃げ出して、抱かずに済んだ殺意の欠片で。
軋んだ嗤い声が癒しの音を消し去って、感情が身体に突き刺さる。
血を吐き、赤く染まり、色を無くし。
黒く染まった世界に一人、嗤いも癒しも、全ての音が遠ざかり。
文字の羅列も、軋んだ嗤いも癒しの音もなくなって。
苦しさも、刺さった痛みも読みたいという心もどこかに消え去って。
――何もない世界で、全てが去って無になった夢の中を、影仁はゆらゆらと漂い続けた。
◇
次の日の昼過ぎ、いつもよりも遥かに遅い時間に目を覚ました影仁は、まあ今にして思うとあの最新話、書き上げるのにちょっと無理してたかなと、そんなことを思いつつ、いつものようにパソコンに電源を入れて。SNSの方に届いていたコトノハからのメッセージを見て、ほんの少しだけホッとする。
今回の連載を始めてから見るようになった不吉な夢。今までは非科学的でバカバカしいと自分に言い聞かせていたけど、昨夜に見た夢はさすがに思うところがあって。それだけに、コトノハからのメッセージが、いつも以上に心に響いて。まるで彼女から直接ありがとうと言われたような、そんな気になりながら、影仁はキーボードの上に手を置いて、メッセージの返信を入力し始める。
――コトノハから届いた、「こんな表現を使っていいのかわかりませんが。面白かったです」と短く書かれたメッセージに対する返信を。
第四話 安堵
―― 刺さり続けた小さな棘 第十三話 ――――
あれから幾日かが過ぎて。
あの時のことは、自分でもびっくりするくらいに尾をひいて。その日は一日中、何もできなくて。次の日の月曜日、ほとんど眠れないまま、寝不足なのを無視して無理やり会社に行って。今にして思えば色々とおかしかったのだろう、先輩から心配されたりもして。……大丈夫ですって答えたけど、信じてない顔だったなぁ、あれ。
――まあ、そんなことを考える余裕ができたのも、その日の仕事も終わって家に帰って、まともに睡眠をとったあとだけど。
さすがにね、いつまでも周りに心配させる訳にはいかないし、第一、詳しく聞かれたら困るのは自分だから。そう無理やりに切り替えて、カラ元気を総動員して、とにかく仕事に集中して。……仕事に逃げる人の心理ってこういうことかと納得している内に週末になって。
――そんな金曜の昼休みに、近くの喫茶店に一人で入って日替わりランチを注文して。うん、今週はちょっとたるんでたな、来週からはちゃんとしなきゃなんて思いながら、暇つぶしに何となく取ってきた週刊誌を半ページほど読み進めたところで、相席いいかななんて、久しく聞いてなかった横櫛の、少しなれなれしい声が耳に入る。
「――あっちの席、空いてるけど」
空席が目立つのにわざわざ相席を求めてきた横櫛を思わずジト目で見てから、さらりとそう返事をして。それを聞いた彼は、少し大げさに「あっちの席」に視線を送ったあと、なるほどと手を叩いて、がっくしと肩を落とす。
――そのどこかひょうきんな態度に、思わず吹き出しそうになるのをぐっとこらえて。まあ好きにすればと口にして。
そんな素っ気なかったはずの私の声に横櫛は、嬉しそうな表情を浮かべながら対面に座って、注文を取りに来たおばちゃんにナポリタンスパゲッティを注文する。
……そんな横櫛の様子を、週刊誌に目を落としながらこっそり様子をうかがってた私は、あれ?、こいつこんなにも表情豊かだっけなんて疑問に思ったところで、その彼に話しかけられる。
「瑞っちさー、どっか遊びにでも行かない?」
その声を聞いて、そういえばコイツ、今週にはいってからずっと声をかけてこなかったわねと、そんなことに今更のように気がついて。でもまあいっかといつものように受け流そうとして、その言葉にささやかな引っかかりを覚える。
「……『遊び』って、何?」
いつものコイツなら、大抵が「飲みに行こう」か「ご飯でも食べに行こう」のどちらかだった気がするんだけどと、新しく出てきた誘いのパターンに少し新鮮さを覚えて聞いてみて。
「いやあ、だって瑞っち、飲みに誘っても食事に誘っても断るし。なら、他のことなら良いのかな~、なんて思ってさ」
横櫛から返ってきた返事を聞いて、その前向きさと何てことはない理由にため息を一つつく。
……とはいえ、まあ、そんなことはわかってたことだけど。
なにせコイツは、飲みに誘われた時に「そうね、たまには何人かで飲むのも悪くないかもね」なんて返事をされてもめげずにそのまま「わかった!」なんて返事をして、気がつけば参加者六人の小飲み会を実現させてしまったという、そんな前歴の持ち主なのだから。……あれ、軽い悪戯のつもりだったんだけどなぁ。なのにそこまでされて、おかげで変に罪悪感を感じて少し飲み過ぎてしまったのは今でもちょっと忘れられない。
――ただ、その時に気付いたのだけど。とにかくコイツは、何ていうかこう、見た目よりもいい加減じゃないというか。いや、チャラいんだけど。現に今も誘ってきてるし。絶対これ、私だけじゃないと思うし。
だけど何ていうのかな、無理に踏み込んでこないというか。そういえば一度も連絡先とか聞かれたことないし。うん、よくわかんない奴だななんて実は最近、思い始めてたりもして。
……そんな訳で。コイツはまあそんな奴だとわかっていたんだけど。それでも少し、コイツがどんな「遊び」に誘ってくるのか、少し興味を覚えて。試しに聞いてみる。
「……具体的には?」
「映画なんかどう? ほら、今イギリスを舞台にした映画がやってるじゃん。世界中なベストセラーを映画化したとかいう奴。あれなんかいいんじゃない?」
私の質問に即答する横櫛を見て、ああコイツは最初から映画に誘うつもりだったんだなと直感して。なら最初から映画に誘えよと、そんなことを思いながら、なんだろう、たまには付き合ってあげてもいいかな、なんて気になって。
「たまにはいいわね……って、ちょっと待って? いつ観に行くつもりよ」
珍しく、というか初めて横櫛の誘いに乗ろうとして。ふとつまらないことが気にかかる。そういえば久しく映画なんて見に行ってなかったけど、映画を見るって時間もかかるし。会社帰りに見に行くものじゃないよねなんて、そんなことを考えて始めて……
「いつって、定時ダッシュでいけばよくね? 駅前の映画館、六時過ぎから上映してたはずだから、十分間に合うでしょ」
……確かにたまにはいいかも、なんて思ったけど、だからといって、いきなり休日にコイツと二人きりで、なんて思ったところで。横櫛の、少し戸惑ったような返事を聞いて。あれ?、普通、映画館に行ったら何本も映画を見るんじゃないのなんて、言い訳めいたことを考え始めて。
――そうね。確かに何本も映画を見るなんて一言もいってないわよねと、心の中で両手を上げて、降参して。
「……そうね。たまにはそんなのも良いかもね」
――何となく断りにくくなって、コイツの誘いを受けながら。しかしコイツ、やっぱり最初からそのつもりだったよね、何せ時間まで調べてあったのだから。うん、やっぱりコイツはチャラいに違いないねと、なんだかよくわからないことを、まるで負け惜しみのように心の中でつぶやいた。
―――――――――――――――――――――――
「負け惜しみが意味不明です(笑)」
影仁は、前もって準備してあった最新話を、いつものように投稿して。いつものように雑事をすませて戻ってきた影仁は、コトノハからSNSに届いたメッセージに目を通す。
「うん、まあ、そこはあれかな? ペースを乱されたから、何かこう、心の中で毒づきたかったみたいな?」
「なるほど。それにしても瑞葉の映画館に対する勘違いはどこから」
しっかりと最後のオチに食いついてきたことに影仁は少し満足をしながら、メッセージに返信をして。さらに仕込んでおいたツッコミポイントに食いついてきたのを見て、前もってブックマークしておいたまとめサイトを見ながら影仁は、どう返信をしようか考えながら、文章を打ち始める。
「そうだね、作品は平成だけど、瑞葉の価値観はけっこう昭和なんだろうね。日本でレイトショーが一般的になり始めたのは1990年代。それまでは、よほど特別な映画でもない限り、夜中に映画を上映するなんてなかったみたいだよ。
――これは推測だけど。映画館っていうのは、昔は一日がかりで遊ぶ場所だったんじゃないかな。同時上映とか普通にやってたみたいだし」
少し長めの返事を打ち込んだ影仁は、最後に少しだけ、自分の推測を付け加えてから、メッセージを送信する。
「同時上映って、短い映画と長い映画を組み合わせて上映するやつですよね。今もやってません?」
「そうじゃなくて。昔は二本以上の『長い』映画を連続して上映してたみたいなんだ」
「……時間、かかりません?」
「もちろん。昼食を食べて映画館に行って、映画館から出た頃にはもう日が沈んでた、みたいなこともあったみたいだね」
返信で帰ってきた、いかにも「今の人風」な答えに影仁は、自分もまとめサイトやブログから得たニワカ知識で返信をして。そんなやり取りをしていると、いかにもコトノハらしいと感じるような、そんなメッセージが彼の元に届く。
「……なるほど。きっと瑞葉っちは門人と一度映画館に行ったんだね。そこでその『同時上映』の洗礼を浴びた。で、誰とも遊びに行かなくなって、取り残されてしまったと。どうですかな、この推理」
このメッセージを見て影仁は、心のどこかで抱いていたほんのひとかけらの不安が氷解するのを感じながら。それでもいつもと同じように返信をする。
「そうですね。あと少し付け足すのなら、瑞葉と門人が逢引していた時というのは人目をはばかっていた訳で。そうすると自然、知り合いの行きそうな場所は避けますね。――つまり、近くの映画館は避けて郊外の映画館に行っていたと」
「ふむふむ、つまり『同時上映』がまだ残っているような田舎に行った訳ですな。……そして、門人の性格を考えるに、一日をほとんど映画館で過ごすようなデートをしたと。何せ、安く済む上にずっと映画館の中ならバレにくいと一石二鳥ですからな」
「うん、ご名答。そんな感じですね」
いかにもコトノハらしい文章に影仁は、少しだけ懐かしい気分を覚えながら、言葉を交換しあって。そろそろ潮時だと感じたのだろう、コトノハから締めくくるようなメッセージが送られてくる。
「とりあえず、瑞葉が少し立ち直ってホッとしたよ」
そのメッセージを見て影仁は、自分もホッとしたと、心の中でそう返事をする。
――画面の向こうにいるのは間違いなくコトノハさんだと、そんな実感と共に。
第五話 節目
「……遊くん、意外と慎重だねぇ。瑞葉っちも、未だに『横櫛』なんて呼び方だし」
いつものように最新話を投稿して。ちょくちょく休日に遊びにいくようになりながら互いにそれ以上踏み込もうとせず、そのまま数か月が経過するという展開に、コトノハから少し含みのあるようなメッセージを受け取って。
その文章に目を通した影仁は、いや、これは作品のことを言いたい訳じゃなさそうだなと、そんな雰囲気を感じ取って……
「そういえばヒナタっち、恋愛物も苦手なんだっけ」
「……ガンバリマス」
「うむ。精進してくれたまえ」
その予想を裏付けるようなメッセージに、影仁はやっぱりなんて思いながらも返事をして。まったくこれだからコトノハさんはと軽く苦笑をしながら、やり取りを終える。
うん、今日はもういいかなとパソコンの電源を切った影仁は、それでも普段の習慣なのだろう、お茶を淹れに台所へと足を向けて。そうだな、今日は少し気分を変えようとハーブティーのティーバッグを取り出して。急須に入れてお湯を注いで、ひっくり返した砂時計の砂が落ちるまで待ち始める。
いつものように、少しずれていることにも気付かないまま「男の一人暮らし」なんてことを頭に浮かべた影仁は、何故だろう、もしかするとこれは男の一人暮らしとは言わないかもしれないなんて疑問を、ふと感じて。どうして急にそんな疑問を感じたのか、僅かに首を傾げる。
――まるで、そんなのは男の一人暮らしじゃないよと、誰かにツッコミをいれられたみたいだな、と。
ほんの少しの間だけ、影仁はそんなことを頭に浮かべて。だが、そんな突拍子もない考えも、砂時計の砂が落ちる頃には全て忘れて、いつものように、湯飲みにお茶を注いでいた。
◇
「おお! これは某テーマパークを思わせるような、超王道なエレクトリカル行進!」
「いや、定番かなと」
最新話を投稿して。まるでどこかから声が聞こえてくるような、いかにもコトノハらしいメッセージを見た影仁は、すました返事を返しながら、こっそりと安堵のため息をつく。
――影仁は生まれてこのかた二十年以上、その超有名なテーマパークでデートをしたこともなかったし、どうしてデートをするのにそんな待ち時間ばかりが印象に残るような場所を選ぶのかピンと来ていない、そんな人だ。
実のところ、これは影仁がどうという話ではなくて。ただ、たまたま彼が今まで出会ってきた女性で、その超有名なテーマパークにはまっている人がいなかったと、ただそれだけの話なのだが。
……なら、なぜ影仁はそんな場所をわざわざ小説の舞台に選んだのかという話になるのだが。困ったことにその巨大テーマパークには、とある客層を狙い撃ちしているとしか思えないようなあざとい演出も色々となされていて。
――つまり、そのテーマパークは現実世界に存在する施設なのに、これでもかと言う位に非現実感を作り出していて、しかもご丁寧に程よいムードまで演出してくれているという、創作者にとってとても使い勝手の良い施設なのだ。
もっとも……
「そうだね。そして、それでも進展しない二人の仲! ……ねえ、ヒナタっち。せっかく舞台を整えたんだから、少し位、ご都合で話を進めても良かったと思うよ?」
「……モウシワケナイ」
――創作者にとって使い勝手が良い施設だからといって、全ての創作者が必ずしも使いこなせるとも限らないのだが。
コトノハからのメッセージを見た影仁は、やっぱり言われたな、なんて思いつつも、返す言葉もないままに返信をして。
……実のところ、書いた本人としても、これだけおぜん立てをしたのになぜこの二人の仲が進展させることができかったのか、不思議に感じてもいるのだが。
それでもやっぱり、キャラがそう動いてくれなかったとかは言い訳にすぎなくて。単に恋愛話が苦手なだけだろうと、影仁自身がそう感じていた。
◇
さらに話が進んで。未だにただの友人である遊之助が、とうとう瑞葉と距離を詰めるために色々と動き出して。そんな最新話をみたコトノハのはしゃいだメッセージが影仁に届く。
「お~、遊くん、頑張ってる! これはアレだ、ヒナタっちも頑張ったよね。 ――まったく、遊び人みたいな名前を付けておいて、奥手にも程があるよ!」
そのメッセージを見て、影仁はいかにもコトノハさんらしいと笑いながら、うん、ちゃんと形になっていたようで良かったと胸をなでおろして。そのまま彼女とのやり取りを終えた影仁は、テキストファイルを開いて最新話の執筆を再開する。
作中時間はさらに進んで、そろそろ十一月も終わりの頃。街中にクリスマスツリーが出始めて、色とりどりの光が踊る、そんな季節の話になっていた。
◇
「……何故に十二月十七日をチョイスした」
最新話を投稿したあと、いつものように受信したメッセージに目を通した影仁は、なぜだろう、まるでコトノハさんの呆れたような声を聞いたような気になりながら、どこか言い訳めいた返信をする。
「いや、十二月二十四日はちとあざといかな、なんて思いまして……」
「むしろお約束だよ! そこに意外性なんていらないよ!」
「……ゴメンナサイ」
その返信の内容に思う所があったのか、ほとんど間を置かずにコトノハからさらにメッセージが届いて。そのあまりの速さに影仁は、即座に謝りを入れる。
そうしてしばらくして。もしかして今回のやりとりはあれで終わりだろうかなんてことを影仁が考え始めたところで、コトノハからのメッセージが届く。
「……でも瑞葉、まだちょっと、なにか引っ掛かってる感じがするよね。もしかして引きずってる?」
そのメッセージを見て影仁は、ちゃんと通じていたと密かに嬉しく思いながら。それでも、物語のテーマに関することだからあまり詳しく書けないなと少し悩んで。やがて影仁は、言葉を選びながらも、それでも思う所は正直に返信をする。
「きっと、そういったところも瑞葉の魅力なんだと思います」
そうして、相手からの反応を待っていた影仁は、程なくしてコトノハから返ってきたメッセージを見て、一つ頷く。
――そうだね。うん、私もそう思う。そう短く書かれた文章に影仁は、残りの話も頑張って書かないとなと励まされながら。
◇
「ほのぼのしたクリスマスだったでゴザル」
「……何故に『ゴザル』?」
いつものようにコトノハから送られてきたメッセージを見て影仁は、めずらしくボケてきたななんて思いながら、相手に即座にツッコミを送り返して。
「まあ、たまにはこんな恋愛物もあっていいんじゃないかなぁ」
気を取り直したようにコトノハから送られてきたメッセージを見て、影仁はこっそりと思う。
――実はヒューマンドラマのつもりで書いていたんだけど、そのことは黙っていよう。うん、そうしようと。
◇
――そうして影仁は更新を続けていって。やがて、物語は終盤の見せ場を迎える。
瑞葉と遊之助が付き合い始めたことが周りに知れ渡って。時を同じくして、瑞葉は人伝てで、優菜が恋人と同棲を始めたことを聞く。
……その相手はかつて瑞葉にメールで告白してきた相手、品川真直で。その懐かしい名前に瑞葉はほんの少しだけ複雑な気分になりながら、優菜に会う機会も無いままに時間が過ぎて。
やがて年があけて、高校時代の知人たちのあいだで、「同窓会をしないか」なんていう話が持ち上がって。出席すると返事をして。やがて、その同窓会の日がやってくる。
――高校時代の友人と楽しく騒いで飲んでいた瑞葉に優菜は、タイミングを見て声をかけて。店の外に出た二人は、周りに人がいないことを確認してから、話を始める。
それは、いままで瑞葉も知らなかった、真直がいままでずっと心の中にしまい込んでいたことで……
◇
―― 刺さり続けた小さな棘 第二十一話 ―――
「そういえば瑞葉、高校の頃、真直と『ちょっとしたこと』があったんだっけ?」
「……メールを一回、やり取りしただけだけど」
優菜にそう話しかけられて、少し気まずいななんて思いながら。それでもまあ、彼と付き合い始めて同棲までしてるんだったらまあ、知られてもおかしくないはずで。
……だから優菜は、私と彼がどんなメールをやり取りしたか知った上で聞いてるよねと、そう思いながら返事をしたんだけど。
――優菜から返ってきた返事は、私の想像を超えていて。
「実はね、そのメール、っていうか、ああ、もう、――実はあのとき、あいつに告っちゃえって焚きつけたの、私なの!」
周りを気にして、声を抑えながら。それでもどこか「えい」って叫ぶように話す優菜の声を聞いて、その内容に少しポカンとして。彼女の話を聞いて、初めて彼が私にあのメールを送ってきたときの経緯を知る。
――彼はどこかで私とアノヒトとが並んで歩いているところを見たことがあったみたいで。そのことで彼が悩んでいたことを。
わたしたちがまだ高校生だった頃、優菜は彼が何か悩んでいるのに気が付いて。からかうつもりで「女とか」みたいなことを言ったら、それがドンピシャ。聞いてしまった以上はしょうがない、話を聞こうかみたいな流れになったんだけど。
――彼は、私のこともアノヒトのことも一切話しをせずに。ただ「好きな人が、誰かと密かに付き合ってるみたいだ」って、それだけを口にしたみたい。
「いやね、確かにきっかけは私だけどさ。それだけしか言ってくれないんじゃさ、こっちも何も言えないよね」
それでも優菜は、「相手がいるんだったら引くしかないんじゃない?」と彼に答えたんだけど。彼はそれでは納得できなかったみたいで。で、そんなにもウジウジする位なら、いっそはっきり振られた方がいいと、そんなつもりで彼にこう言ったらしい。
――そんなに納得できないんなら、いっそ告って振られてこいと。
「だって、相手も付き合ってることを隠してるって話だったし。なら知らないふりして告白したって大したことにはならないかな~って思って。そりゃあ百パーセント振られると思ったけど、あいつにとってはその方が良いのかなって」
優菜の話に聞き入りながら、心のどこかで納得をして。そりゃそうだ、いきなりあんなメールをもらって喜ぶ人なんてまずいない、そんなことは誰にだってわかることなんだから。
……そう思いながらも、同時にふと思う。
――もしあの時、私があのメールに違う返事を出していたら今頃どうなっていただろうか、と。
そうすれば、私はアノヒトやその家族にあんな感情を抱くこともなかったし、遊之助と付き合うこともなかったかもしれない。優菜も彼とつきあい始めることもなかったのだろう。あのたった一通のメールで、色んな事が変わったんだなと、そんなことを考えて。
「その相手が瑞葉のことって知ったのはつい最近のことなんだけど。……けどあいつ、『なんで』瑞葉が誰かと付き合ってるのを隠してたのかは、今だに言おうとしないのよね」
少し怒ったような優菜の言葉に、ほんの少しだけホッとして。同時に、少しだけクスリと笑う。だって、優菜のこの怒り方、全然本気じゃなくて。むしろ彼のことをしょうがないなぁなんて思っているような感じの怒り方だったから。
きっと優菜は彼のことを信頼していて。彼が話さないのには理由があることをちゃんと理解もしていて。
……少しだけ、ほんの少しだけ、優菜のことが羨ましいな、なんて思いながら。
――最後に一つだけ、何でそのことを私に話そうと思ったのか、聞こうとしたんだけど……
「――何で……」
「そりゃあ、最近の瑞葉は何か、らしくない気がするからね。もしかして関係あるのかななんて思って。大丈夫! 私はちょっと口が軽いかもしれないけど、あいつは口が堅いからね。絶対誰にも言わないと断言できるよ」
その質問を遮るように、優菜にそう言われて。ああ、きっと今の私は、久しぶりにあった友人にわかるぐらいにはっきりと、あの時のことを引きずっているんだなんて気が付いて。
そんな私を見て優菜は、もしかしたら何かのきっかけになるかもしれないと、たったそれだけのためにこんな話をしてくれたんだと気が付いて。
一つだけ。今はまだ無理だけどいつかきっとと、そう心に決める。
優菜がどう思おうと、私のことで彼に隠し事をさせてはいけない。だから、いつかきっと、私に何があったのか、優菜にだけは話をしよう、と。
―――――――――――――――――――――――
影仁はいつものように書き上げて、推敲をして、投稿をして。コトノハや他の読者と感想のやり取りをして。その反応に手ごたえを感じながら、いつものようにテキストファイルを開いて、物語の続きを綴っていく。
――その物語も、あとは最終話を残すばかりとなっていた。
◇
「うん、ちゃんとした感想はまた後日書き込むとして。とりあえず完結おめでとう! 面白かったよ!」
「うん、その一言だけで十分だけどね。ありがとうございます」
そうして影仁は、書き上げた最終話を投稿して。万感の思いに浸りながら、読者からのお祝いを兼ねた感想に一つずつ返信をして。最後に、SNSの方に届いていたコトノハからのメッセージに返信をする。
そうして、全てをやり終えて。今一度達成感に浸りながら、影仁は思う。この物語を書くにあたって、読む人に伝えようと文章に込めた想いがあって。果たしてその想いは伝わったのだろうかと。
――それが伝わっているのか、気にならないと言えば嘘になる。それでも影仁は思うのだ。伝えたいことを作品に込めて公開した以上、それは聞いてはいけないことだと。それはきっと、作品の価値を損ねる行為なのだろうと。
そんなことを考えていた影仁に、少しだけ遅れて、コトノハからメッセージが届く。
「過去に何かがあったからって幸せになっちゃいけないなんてことは無いと私も思うし、良い話だったと思うよ。――瑞葉に刺さった棘は傷跡を残して、きっと痛みは残ると思うけど、それでもね。世の中にはどうしようもないことだってあるし、人間なんだからいろんな感情もある。
どんなことがあったとしても、感情を揺さぶられてもね。それでも、いろんな人のいろんな感情に向き合いながら生きていく方が人間らしくて良いと、私は思うな」
それはまるで、影仁の心の中を読んだかのようなメッセージで。その言葉を見ながら影仁は、改めてこの作品を書いて良かったと、そんなことを感じながら、来週からはどうしようかなんてことを考え始めて。
うん、せっかく時間が出来たのだから、どこか日帰りで旅行にでも行って見聞を広げてみようか、そうだ、一度書店に行ってガイドブックを買ってこようと、そんなことを影仁は考え始める。
――まるで、そうした方が良いと誰かに声をかけられたかのように。
第六話 儚 ――コトノハコダマ――
「新幹線を使えば一、二時間か。日帰りでも、思ったよりもいろんな場所に行けそうだな」
一つの物語を完結させて。その余韻にひたりながら日帰りで旅行にでも行こうかなんて思いついた影仁は、インターネットでいくつか調べ事をして。日帰りでも思いのほか遠くまで行けそうだと結論付けた彼は、よし、京都に行こうと決意をして。翌日、会社帰りに書店に立ち寄って、ガイドブックを購入して帰宅する。
そのままベッドに寝転がって、買ってきたガイドブックをパラパラとめくって。西本願寺と東本願寺ってホントに目と鼻の先にあるな、こんな近くで意地を張りあってたのか、いい迷惑だなとか、やっぱり五重塔は欠かせないよなとか、そんなことを思いながら、ページの端に折り目を付ける。
――そうして、ガイドブックを眺めながら久しぶりにのんびりとした一週間を過ごした影仁は、週末、早起きをして朝一番の新幹線に乗って。今日は一日、京都を満喫しようという決意を胸に、京都駅を出て、まずは最初の目的地、駅を出てすぐそこにある東寺に向かって歩き出した。
◇
「えっと、今はここだから……」
東寺と西本願寺を見て回って。スマホの地図を見ながら、これじゃあまるで時間に追われたバスツアーだなと少しだけ後悔しながら、とりあえず次の東本願寺は見ておこうと足を向ける。
ガイドブックを見ていると良さそうな場所はたくさんあって、いろんなところに行きたくなるものだけどと、東本願寺に向かいながら考える。思うに、京都駅周辺というのはその中でも別格なんだろうなと。
――実に多くの名所旧跡が駅周辺に密集している、京都駅というのはそういう場所なのだ。
地図だけ見ていると、行けるような気になるのだ。現に、東寺、西本願寺、東本願寺、三十三間堂、智積院と、立ち止まりさえしなければ歩いて回ることできる距離にこれだけのお寺が建っているのだから。
……もっとも、立ち止まらずに歩いて回ることに意味があるとも思えないけど。
これでも抑えたつもりなんだけどな、いや、手始めにお寺を五つってどう考えても間違ってるだろと、そう自分にツッコミを入れて。沢山の場所に行っても時間に追われて見てません覚えてませんじゃ意味ないだろうと。うん、やっぱりどこかで駅に戻って計画を立て直さないとと、そんなことを考えている間に東本願寺に到着して。とりあえずここはのんびりと見て、その後に考えますかと、びっくりするほど迫力のある門をくぐって、敷地の中に入っていった。
◇
そうして、東本願寺を十分に堪能して。うん、やっぱり観光は時間に追われちゃいけない、そんなことを考えながら、一度京都駅にまで戻ってきて。どこか喫茶店でもあると良いけどなんて思いながら周りを見渡していると、どうしてだろう、こちらを見ている一人の人が目に入る。
その人は多分、まだ中学生か高校生くらいの年齢だろうか。どこか幼さと大人っぽさが同居しているような年頃で。
――どうしてか、彼と話をしなくてはいけないような、そんな気がして。
なんでそんなことを考えたのだろうかわからずに首を傾げていると、その人の方から話しかけられて……
「すいません。少し変なことを聞きますが。もしかして『ヒナタヒロ』さんですか?」
見知らぬ人から自分のハンドルネームで呼ばれて。きっとこの人は、コトノハさんの代わりに画面の向こうでやりとりをしていた人だと、そう直感して。
――違う、直感じゃない、彼女にそう語りかけられたんだと、そんな突拍子もないことを確信する。
日引告さんと自己紹介したその人は、コトノハコダマという名前で活動していた日引儚さんの弟さんで。もう一月以上も前に亡くなった儚さんに代わって、コトノハコダマとしてメッセージを送り続けてくれた人だった。
◇
「姉は、言葉に乗った感情を力として受け止めてしまう、そんな不思議な体質の人でした」
一度でいいから儚さんの部屋を見てあげてほしい、そんなことを告さんにお願いされて。京都駅から電車で三十分の場所にあるという実家にまで案内してもらうことになって。そこに着くまでの間、告さんから儚さんの話を聞く。
――それは、とても不思議な話で。
儚さんは、聞いた言葉に強い影響を受けてしまう人で。攻撃的な言葉を聞くとまるで殴られたようなあざができたり、泣き言や愚痴を聞くと体調を崩してしまうこともある、そんな常識では考えられないような体質を抱えていたみたい。
ただ、影響を受けるのはマイナスの影響だけじゃなくて。例えば癒されるような言葉を聞けば身体も癒されるし、幸せそうな言葉を聞けば傷もなおったりする、そんな不思議な体質の人だったらしい。
そんな、常識的に考えればあり得ないような話を聞きながら。以前、更新をする度に見ていた夢を思い出していた。
――文字の羅列を覗き込んでは苦しんで、心地よい言葉に癒されては覗き込むのを繰り返してた、あの夢を。
◇
やがて到着した家は、どこにでもありそうな一軒家で。自分を見て訝しげな表情を浮かべたご両親に「ヒナタと言います。コトノハさんとはインターネットでよく話をしていました」と自己紹介をする。
告さんも説明してくれて、ようやく納得してくれたのだろう。家の中に上げてもらって。仏壇の前で、線香をあげて、手を合わせて。そっとお祈りをしてから、二階にあるという彼女の部屋にお邪魔をした。
◇
そこは、フローリングの床に、白い壁の、どこか寂しさを感じる部屋で。部屋の隅には木製のベッドと棚。白い小さな机の上には、閉じられたままのノートパソコンがちょこんと置かれ。
そんな何気ない部屋の風景にどこか違和感を感じて。もう一度、部屋の中を見渡して。普通、人の住む部屋に当たり前にあるはずのものが無いことに気が付いて。首を傾げながら、告さんに聞いてみる。
「……この部屋、窓はないんですか?」
そんな何気ない質問に対して。告さんから返ってきたのは、儚さんがその体質のために背負うことになった、過酷な現実だった。
「窓を無くして、その変わりに防音を強化しています。――姉は外の、『言葉に満ちた世界』世界では生きていけない、そんな人でしたから」
告さんは言う。自分の姉は、道端で怒鳴っている人がいるだけでまるで誰かに殴られたようなあざができるし、誰かが電話で謝ってるのを聞くだけで体調を崩す。そんな人にとって、外から聞こえてくる音は暴力以外の何物でもなかった、と。
「だから、姉は部屋の中で、外からの音も遮断して、この部屋に閉じこもって生きるしかなかったんです」
そう言う告さんの声には、姉にたいする様々な想いが入り混じっていた。
◇
儚さんが言葉に込められた感情に対して敏感になったのは、成長してからのことで。小学生の頃は何事もなく過ごしていたのが、中学生になると少しずつ「言葉の力」に影響されるようになっていって。高校生の半ばで通学するのも厳しくなって。
やがて高校に行くことも出来なくなった彼女は、高校を中退して。外に出ることもできずにこの部屋で一人、好きな癒しの曲をかけっぱなしにして。そんな彼女に残されたのは、この家に住む家族という、ほんの小さな世界だけで。窓もないこの部屋で彼女は一人、外との接点をインターネットに求めながら、毎日を過ごすことになる。
声だとどうすることもできないけど、文章なら。読むペースを落とせば影響を少なくできるし、癒されるような歌を聴きながらなら、負の感情が込められた文章でも読み進めることができる。なにより、体調を崩したのなら、そこで読むのを止めればいい。
「文章なら、たとえ変な文章を見て倒れることになっても、周りに流れている歌が癒してくれると、そう僕たちは思っていたんです。だって、たとえ姉の体質でも、ゆっくりと時間をかけて身体を癒しながら読み進めれば、どんな文章だって読めるんですから」
ああ、そうだ。ゆっくり落ち着いて読めば、儚さんは今も元気でいたんだと、あのとき見た夢のことを思い出す。どれだけ身体を貫かれても読むのを止めようとしなかった夢の中の自分のことを。
――いや、僕の話に夢中になって、命をなげうってまで読み進めてしまった儚さんのことを。
あの時の感情を思い出す。身体を突き刺すような痛みに、それでも魅入られたように文字の羅列を追い続けたあの時の儚さんが抱いていた想い。
「きっと、ヒナタさんの書かれた小説は、瑞葉さんは、姉にとっては憧れだったんです」
告さんの言葉に頷いて。あの時の儚さんの感情を思い出して、どうしようもなく泣きたくなる。
――瑞葉の抱いていた感情は、儚さんにとって、二度と抱くことができない感情で。その感情にあのときの儚さんは共感していたのだから。きっと告さんの言う通り、あの殺意という感情に儚さんは、憧れすら抱いていたのだから。
どれだけ綺麗な剣と魔法の世界だって、儚さんにとってはきっとどうでも良い世界で。人と人とが殺し合う作品に出会ったとしても、儚さんは命を削ってまで読もうとは思わなかっただろう。
ただ、描かれていたのは現実の世界で。そこに描かれていたのは、ありふれた人の感情で。そんな普通の世界の出来事が、儚さんにはなにより魅力的で。
――そこに書かれた瑞葉と言う人が、どうしようもなくバカで、一途で、感情豊かで人間らしくて情が深くて魅力的だったから。そんな感情をいだくことを許されていない彼女は瑞葉に憧れて。
だから儚さんは、ゆっくりと「文章から目を離して身体が癒えるのを待つ」なんていい加減な読み方をすることができなくて。没頭して、命を落としてまで、僕の話を読み続けることになったんだ。
◇
「姉はきっと、ヒナタさんに自分のことで悲しんでほしくないと思います」
話を終えて。告さんにそう言われて。ああ、なんとなくだけど告さんの気持ちがわかる気がして。告さんはずっと儚さんの声を聞き続けて。儚さんの願い通りに自分にメッセージを送ってきて。それはきっと、告さんは姉の願いを叶えたいと思ったからで。
――だからきっと、今日自分がここにいるのも、告さんが自分に悲しまないでほしいと言っているのも、きっと儚さんがそう願ったことなんだと、そんなことを感じて。
「今日は突然声をかけてごめんなさい。姉のことを悼んでくれてありがとうございます」
別れ際の告さんの挨拶はきっと本心なのだろう。きっといい弟さんなんだろうなと、そんなことを心の中で、そっと思った。
◇
「それじゃあ、お邪魔しました」
そう言って、彼女の家からおいとまをして。最寄りの駅から京都行きの電車に乗って。うん、京都観光はまた今度にして、今日はもう家に帰ろうかなと、そう考えたところで。
――なんでだろう、そんなことは気にしなくていいし、一緒に見て回りたいなと、そんなことをふと思って。
そうだねと一人で頷いて。よし、そうと決まれば時間いっぱいまで楽しもうと、そんなことを思いながら、持ち歩いていたガイドブックを開いて、次はどこに行こうか、ゆっくりと考え始めた。
第七話 祝い
――また、ベタな展開ですね。ヒナタさんが書くと結構新鮮です。
半年ほど前、姉が亡くなったときから見始めることになった小説投稿サイトで。告は、その時に知り合ったヒナタヒロというユーザーの書いた小説を読んで、いつものようにメッセージで感想を送る。
姉が亡くなったあの日、確かに姉はいなくなったけど。だけど告は、まだあの部屋に姉が住んでいるような気がしていたし、葬儀が終わったあと、姉のパソコンを使ってヒナタさんにメッセージを送るたびに、確かに自分は姉の代わりにメッセージを入力していると、告はそう感じていた。
――あの日、ヒナタさんを家に招き入れて、姉の部屋で姉の話をした、その時までは。
あの時から、それまで確かに感じていた姉の気配が消えて。今では、こうしてヒナタさんとメッセージをやり取りするときに、ほんの少しだけ感じるだけになって。
――もしも、もしもの話だけど。
この先ずっと、姉の声を聞く人がいたとして。その人が、今みたいにメッセージを交換するときだけじゃなくて、ずっとその声を聞き続けているのだとしたら。
そしてその人が、姉のことをとても大切に思っていて、ずっと忘れずにいてくれる人だとしたら。何より、その人が姉の大好きな言葉を紡ぐ人だったら。きっとその人の言葉は、姉にとっては永遠の祝福で。姉もきっとその人のことを祝福してくれるのかなと、そんなことを告は考える。
きっとあの人には、姉の声が聞こえているのだろう。ほんの少し物語を考えるだけで、ほんの数文字、キーボードを入力するだけで、たったそれだけで、姉の声が聞こえるのだろう。
だけど、姉に望まれる言葉を紡ぎ続けるその人にとって、その祝福は本当に祝福なのだろうか。いかにも姉が好みそうな、あの人が苦手だったはずの物語を見て、そんなことを思う。
――この祝福は、きっと、ずっと続いていく。
コトノハコダマ奇譚
本作品は、「小説家になろう」にも掲載しています。
小説家になろう:https://ncode.syosetu.com/n8311fu/