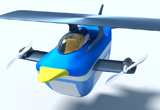故郷の小さな神社の境内、篝火の前、昔なじみの「友達」と。
年も明けて日も過ぎた、一月も半ばを迎えたある日のこと。普段は人気のない小さな神社も、その日は、役目を終えたお神札や正月飾りを燃やして宿った神さまを天に帰す、そんな神事が執り行われるためだろう、境内で甘酒が無料で振舞われ、それなりの賑わいを見せる。
使い終わった正月飾りを紙袋に入れて、神社に足を運んだ柑渚は、そこに見知った顔を見つけ、ほんの少しだけためらいを覚え、足を止める。
(あっちゃぁ、「青」じゃん。そっかぁ、帰ってたのかぁ)
足を止めた柑渚の視線の先には、高校の頃からの昔なじみである「難波 青嗣」が、紙袋を手に、境内の中央で焚かれた篝火の前で、燃え上がる炎をじっと見つめるように立っていた。
◇
地元の高校を卒業して、地方都市に本社を置く、程よい大きさの商社に就職した柑渚。家を出て、会社が借り上げたアパートに引っ越した彼女は、片道二時間という微妙な距離のせいだろうか、いつでも帰れるからと帰省するのを先延ばしにし、結局、七年もの間、ほとんど帰ることなく日々を過ごす。
そんな柑渚が、去年の年の瀬に、誰にも相談しないまま会社を辞めて。突然、実家に帰ってくると言い出した彼女を、祖父母や両親は何も言わず、暖かく迎え入れる。
そんな家族の暖かさに感謝しながらも、彼女は、久しぶりの実家に、どこか居心地の悪さを感じていた。
(……別に、邪険にされてる訳じゃないんだけどなぁ)
祖父母も両親も、昔と同じように接してくれている、そのことは柑渚にも十分に伝わってくる。だから、変わったのは自分の方で。それは、高校生から大人になったとかではなくて。きっと、故郷を顧みずに過ごしてきたことで、どこかがズレてしまったのかなぁと、そんなことを彼女は、心の片隅で考えながら。
――久しぶりの故郷や実家にいまいち馴染めないまま。それでも、柑渚は生まれ故郷で、都市の喧騒から離れて、静かな毎日を過ごしていた。
◇
(なんでこいつ、こんなところにいるのかなぁ)
正月を締めくくる神事を迎えた境内で。まだ一月とはいえ、正月休みはとっくの昔に終わっているはずなのにと、柑渚は、自分と同じように故郷を離れ、遠く東京で生活しているはずの「青」の顔を見る。
(まあ、毎年送られてくる年賀状が無かったら、わかんなかったよね)
毎年律儀に送られてくる年賀状。そこに写った写真を見て、うっわぁ、こいつら、変わってねぇなんて思ったものだけど。まあ、でも、こうやって見ると結構変わってる気がする。少しだけ精悍になった? 少なくとも、バカっぽさは無くなったねと、そこまで考えて、ふと気付く。
(あれ? マフラーは?)
高校の頃から、冬になると毎日のように首に巻いていたマフラー。もはや青のトレードマークと言ってもいいそのマフラーが無いことに違和感を感じて、柑渚は軽く首を傾げる。これだけ寒い日なのにあのマフラーをしていないなんて青らしくないなぁ、そんなことを思いながらも、彼の元へと歩み寄ろうとした、その時。
――青が、手にしていた紙袋を、篝火の中へと放り投げる。
篝火の中で炎を上げる紙袋。燃え崩れるその紙袋からちらりと覗かせたその中身に、柑渚は歩き出そうとした足を止め、再び立ち止まる。
――青が大切にしていたマフラーが。篝火の中で、紙袋に入れられたまま、ぱちぱちと音を立てて、燃えていた。
◇
初めてそのマフラーを見たのは、高校の頃だった。「海」からもらったと、マフラーを首に巻いた青が、自慢気に、嬉しそうに話していたことを思い出す。
どんな表情をしてたのか、もう思い出せない。それでも、そのことだけは、今でも忘れられない。
――篝火が炎を上げる。マフラーが炎に焼かれ、赤い炎を上げ、篝火の炎とまじりあう。
高校を卒業して、家を出て。
あの二人にも会わなくなって。
仕事に、日々の生活に追われ。
生まれ故郷のことも忘れ。
加速した時間の中で、繰り返しの毎日を過ごし。
青から毎年送られてくる年賀状。
そこに写るマフラーに心をざわつかせ。
――炎が瞬く。マフラーが赤い炎をちらつかせ。光と熱を踊らせて、込められた想いを空に還す。
ある年に、青の住所が東京に変わり。
あくる年、海の住所も変わり。
一通の年賀状に二人の写真、差出人は連名で。
その頃には、あの二人のことは遠い世界のお話で。
昔馴染みというか細い縁が、年賀状の形をとって残ってる、たったそれだけ。
おーおー元気にくっついとるのぉなんて思いながら、同居を始めた会社のセンパイくんに年賀状を見せて、高校時代の友人だよと話をして。苗字が変わるのはあっちが先かなぁなんてことを、こっそりと考えたこともあったっけ。
――懐かしく、どこか落ち着かない生まれ故郷。何度も足を運んだ神社の風景。役目を終えたお神札が、正月飾りが燃え上がり、宿した神が空へ帰る。
センパイくんと気まずくなって。
職場にも居づらくなって。
新しくアパートを借りて、センパイくんと別々に住んで。
それでも職場の空気はそのままで。
別にあの会社に執着もなかったし、センパイくんもね、別に嫌いなわけじゃない。かみ合わなくて、同じ場所にいると居心地が悪い、だから、私の方から話を切り出して出て行った、ただそれだけ。
結局は、七年間お世話になった会社も辞めて、次の職も決まらずに、一度実家に帰ろうと決心して。
空っぽになった心が、ほっと一息つきたがっていることに、ようやく気付く。
――空っぽの心に、炎が揺れる。遠い昔の思い出が、炎となって、空に帰る。それはきっと、青がずっと抱えていた想い。
なのに、どうしてだろう。
あのマフラーが燃えるたびに。
ずっと昔、どこかに置いてきたはずの気持ちが。
空っぽの心に、形を変えて、入り込む。
それはきっと、もう過ぎてしまった何かで。
それはきっと、たった今終わった何かで。
――意味もわからないままに、瞳に涙が誘われる。
自分が涙目になりかけたことに気が付いて、とっさに「アカン、青に気付かれたらマジアカン」なんて心の中でツッコミを入れて。深呼吸をして、心を落ち着けて。何事もなかったかのように、青に声をかける。
――あっれぇ、青じゃん、久っさしぶりー、と。
◇
「げっ、『柑』じゃん、マジかよー」
大げさに驚きながら声を上げる青。その声を聞いた柑渚は、こいつ、中身は変わってねぇな、そう確信しながらも、親しげに話しかける。
「帰省中? どうですかな、東京暮らしは」
「どうもこうもねえよ、都市部なんてどこも似たようなもんだろ」
そんな、他愛のない話をして。
「はぁ!?、帰ってきた!? カレシは!?」
会社を辞めて帰ってきたって言ったらひどく驚いて。
「彼氏? ああ、あのセンパイくん? あれ、違うから」
「どこがだよ! 大体、お前さぁ、自分のカレシ位、名前で呼べよ! そんなんだから出戻って……っ、痛ぇ」
青のやつ、出戻りなんて失礼なことを言いかけたから、思いっきりぶん殴ってあげて。そんなんだからとか言いかけた青をもう一発ぶん殴る。
そのあと、境内で配っていた甘酒をもらって。そうそう、こいつ、妹が今年成人だからって、わざわざ東京から戻ってきたんだって。いやぁ、凄くね? そう思ったんだけど、「当たり前だろ、家族なんだから」とか言われて。そんな世間話で盛り上がって。甘酒お代わりして。家から持ってきた正月飾りを篝火にくべて。
「温いのぉ、ホカホカじゃあ」
「……じいさまか。……っ!」
篝火に手をかざしながらこぼした台詞に、青の無神経な一言。無言で後頭部を殴ってさしあげる。
しばらくして、綺麗な衣装を身にまとった神主さまが登場して。篝火の前で、小声でモゴモゴと「りん・びょう・とう・じゃ・かい・じん・れつ・ぜん・ぎょう」と呟きながら両手を動かすのを眺めて。イマイチだなぁ、照れちゃうあたりが田舎だなぁ、衣装が泣いてるぞと二人で笑いあって。
「じゃあ、また今度な!」
「今度っていつだよ! 十年後かよ!」
そんなことを言い合って、その場はお開き。おお、寒い寒いなんて言いながら、家路につく。今頃、海はどこで何をしているのかねぇ、きっとあの子も変わんないだろうなぁと、そんなことを考えながら。懐かしい、昔から変わらない道を。少しだけ軽くなった足取りで。故郷に帰ってきたことを、しみじみと実感しながら。
――それは日常の、当たり前の風景で。久しぶりに柑渚は、そんな当たり前の日常に溶け込んでいた。
故郷の小さな神社の境内、篝火の前、昔なじみの「友達」と。
本作品は、「小説家になろう」からの転載です。
https://ncode.syosetu.com/n6346ff/