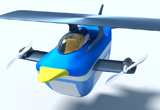血まみれジーニャの酒場へようこそ
1.国境の街グロウ・ゴラッド
帝国の端、国境線に接した街、グロウ・ゴラッド。その街の外れにある、小さな、料理店を兼ねた酒場に入ったビーツァとシエレイは、ウエイトレスであろう若い女性の、心底嫌そうな声に迎えられる。
「客? 面倒だわ」
メイド服を意識したであろう、黒を基調とした制服を身にまとった、気の強そうな顔立ちをしたウエイトレス。そのウエイトレスの、あまりに店員らしくない物言いに、ビーツァは思わず吹き出しそうになる。だが、ビーツァよりも一歩先に店に入ったシエレイは、ビーツァほど心にゆとりが持てなかったのだろう、やや不機嫌そうな表情を覗かせる。
「今なら丁度窓際の席が空いてるわ。眺めだけは一番良い席よ」
そんなことを言いながら、案内をするそぶりさえ見せないその店員の言葉に、ビーツァはその「窓際の席」の方へと視線を向け。ガラス越しに国境の河を一望するその席を見て、なるほどなと、先ほどのウエイトレスの言葉に納得する。
――氷の形をした暴虐な冬精が絶え間なく流れていく国境の河、グラニーツァリカ。普段はあえて誰も近づこうとしない寒々としたこの大河も、温かく安全な室内から眺めることができるのであれば、確かに一つの景色だろうと。
◇
帝国にとっての辺境の地は、帝都を守るためにある。それは、帝国に住む人間が等しく抱く、一つの事実だろう。
帝国の中心に位置した、華やかかりし帝王の都。極寒の地に位置する帝国の中にありながら、地中深くから吸い上げた大地の力で転換炉を稼働させ、大気から冬精を抜き取って国境の河グラニーツァリカに捨てることで冬を消し去った、人口的な常春の地。
そこは、高層ビルが立ち並び、どこまでも広い基幹道路が隅々まで張り巡らされた、世界でも有数の近代的な都市であると同時に、武装を規制されながらそこに不安を感じさせない程の、世界でも有数の治安の良さを誇る都市でもあり。――そして、「帝国臣民」として認められた者の中のさらにごく一部、ほんの一握りの成功者しか住むことができない、選ばれた者のための理想郷でもある。
そこに住むことの叶わない大半の臣民は、帝都周辺の程よく雑然とした大都市で、追われるような日常を送りながら、たまに入る「帝都」の様子を自慢げに話し合い……
――そんな帝国の当たり前の風景も、高くそびえ立つ「壁」の外に出ると、一変する。
過去の戦争によって帝国に組み入れられた、かつては他国だった場所。今も、帝国の中にありながら帝国の一部とみなされていない、捨て置かれたままの土地。そこに住む民は「帝国臣民」として扱われず、帝国の法も、魔法の保護も及ぶことはない。
鉄道すら止まらない、国境線近くの街。そこは、他国の侵略を受けた時に、足止めのように蹂躙されることだけを期待された、誰からも見放された無法地帯。帝都を守るための、破壊されることを前提とした人の楯。
――それは、帝都に住む人間にとっては傲慢で、辺境の地に住む者にとってはこの上なく過酷な、ただの事実だった。
◇
「――なるほど。確かに良い眺めだ」
不機嫌そうにウエイトレスに示された席に歩を進めたシエレイは、その風景に感心したのだろう、手にした外套を近くの衣掛けに掛けながら、素直に関心し、……だが、完全に機嫌を直した訳ではないのだろう、席に着いたとたんに、ウエイトレスへの批判を口にする。
「しかし、あれが客を出迎える態度か。程度が知れる」
「なにせここは『血まみれジーニャ』なんて名前の店だからな。血まみれになったウエイトレスが出てこなかっただけマシなんだろうさ」
「どんな屋号を付けたところで、店員が悪態をついていい理由にはならんだろう」
シエレイの、ある意味もっともな意見に、少し茶化した答えを返すビーツァ。ここはお高くとまった店じゃない、あの位で目くじらを立てるもんじゃないし、第一、見た目は悪くない。いいじゃねえか、かわいいんだからと、そんな軽薄そうなことを言いたげなビーツァの態度にシエレイは、そんな話で盛り上がるつもりもないとでもいうように、ダメなものはダメだろうと遠慮のない口調で言い放ち……
――席のすぐ隣でカツンと響いた靴音に気付いたシエレイは、当のウエイトレスが注文を取りに来たことに、遅まきながら気付く。
「残念ね。私の態度を決めるのは客じゃない、ボスよ。だから、客がどれだけ偉そうなことを言っても、全部タワゴトね。注文は?」
音もなく席まで注文を取りに来ながら、気付かせるためにわざと靴音を立てたであろうウエイトレスの子憎たらしい態度に、この相手はこちらの「心の狭い」態度を楽しんでいることに気付いたシエレイは、素早く品書きに目を走らせる。だが、めぼしい品がなかったのだろう、シエレイは、一瞬だけ悩んだ後、諦めたようにウエイトレスに質問をする。
「……蒸留酒はあるか?」
「ゴルディクライヌならね」
「じゃあ、そいつをグラスで」
ゴルディクライヌ、香草の風味が特徴的な、この街でのみ製造されている蒸留酒。その名前を聞いて、シエレイは軽く落胆しながらも、その酒を注文しようとして……
「――いや、瓶でくれ」
ビーツァの、二人で飲むには少し無謀な注文に、シエレイは一瞬だけ言葉を無くし。思わず出かけた言葉をかろうじて飲み込む。
その様子を見ていたウエイトレスは、「了解」と短く返事をして、席から離れ。すぐに、特徴のない、ありふれた瓶に入った酒とグラスを持って席へと戻り、静かにテーブルの上に置いて、無言のまま立ち去る。
そうして二人は、グラスに酒を注ぐ。シエレイはグラスの底に少しだけ、ビーツァはグラス一杯に。そうして、互いが自分のグラスを軽く持ち上げて……
「「乾杯」」
軽くグラスを合わせた後、それぞれが自分の酒を口にする。
「半年ぶりか? 確か『でかいヤマ』とか言っていたっけか? ――どうだ、掘り当てたか?」
「……ああ、とりあえず『掘り当てた』んだろうな。と言っても、儲けはまだだけどな。上手く行けば、今までに無い儲けが待ってるはずだ。――危ない橋を渡れば、だけどな」
両者が手にした酒で軽く口の中を潤して。久しく会っていなかったからか、どこか話題を探るように、昔なじみに話しかけるビーツァ。――その質問にシエレイは、含みを持たせた返事を返し。
その「含み」を聞いたビーツァは、軽く口角を持ち上げると、単刀直入に聞き返す。
「いいねぇ、景気が良くて。――で、だ。わざわざ俺を呼んだってことは、その『危ない橋』ってのは、荒事なんだろ? 殺しか? それとも用心棒か? まあ、どんな内容でもいいさ。いつもの『友達価格』で請け負うぜ」
――それは、どの組織にも属さないまま、時に互いを「お得意さま」としてここまで生きてきた「交易屋」と「殺し名」、嗅覚に優れた二人の会話だった。
2.ビーツァとシエレイ
ビーツァとシエレイ。共に十代半ばの、周りからは半人前にすら見られないような年齢で出会った彼らは、共に「クスリ」で両親を亡くすという共通した過去を抱えていたからだろうか、自然と信頼しあうようになり。やがて、相手が非凡な「何か」を持っていることに気付く。
――儲けの嗅覚を持つシエレイと、暴力の嗅覚を持つビーツァ。
壁の外には、公権力が及ばない。そんな場所は、時に、そこに住む者の想いに満ちて、渦を巻く。それは、平和な都市に住む者が想像するような安定を望む想いもあれば、商業都市に住む者が想像するような欲望に満ちた想いもある。権力、名声、富貴、時にはつまらない自己顕示欲まで、人の数だけ想いがあり、それが時に溢れ出て、人を飲み込む激流の元となり。――そして、どんな想いも、一たび激流となってしまえば、血と命を飲み込んでいく。
平和を求めて、無法の種を排除する。欲望を満たすために、人から奪う。どんな感情も、血を流すのには十分で。――そして、血を流すのは弱い者だと、相場が決まっている。
そんな世界で、寄る辺を無くした二人が、相手の嗅覚を頼りにするのは自然の成り行きだったのだろう。
シエレイにとってビーツァは、商取引が暴力によって壊され奪われるのを防いでくれる唯一無二の相棒だったし、ビーツァにとってのシエレイは、結局暴力の世界で生きるしかない自分に比較的真っ当な仕事を与えてくれる、またとない相棒だった。
やがて、二人がそれぞれの分野で、力をつけ、名を上げていき。互いに人脈を築き上げ、唯一無二の相棒で無くなった今も、数多の苦難を乗り越えて育んできた信頼と友情はそのままの形であり続けていた。
――この日、二人がこの酒場に入る、その時までは。
◇
「……ああ、そうだな。確かにその『危ない橋』は、お前の領分だ」
乾杯の後、「仕事なら友達価格で請け負う」と言ったビーツァにシエレイは、少し歯切れの悪い、どこかはぐらかすような返事をし、グラスに少しだけ入れた蒸留酒に口をつける。その様子を見たビーツァは、シエレイの、答えになっていない答えに軽く肩をすくめながら、自らのグラスを手にする。
片方はちびちびと。もう片方はごくごくと。会話の途切れた空気を嫌うように、互いに話しかける言葉を探りながら、ほのかに薄茶色に揺れる酒を、二人は無言で飲み進め……
――やがて、外の風景にその言葉を見出したのだろう、シエレイがビーツァに話しかける。
「……この河の向こうには何があるんだろうな」
「さあな。この街とは違う街があるんだろうさ」
帝国と隣国とを分かつ国境の河。極寒の地に流れる氷の河は、ただ渡るだけで命を危険にさらす、いわば、帝都の反対側にあるもう一つの壁。
帝国の中央と辺境を分かつ文字通りの「壁」と、氷塊が絶え間なく流れる、国境の河の形をした「壁」。二つの壁に囲まれた街の住民は、この街から出ることすら叶わない。だが、そんな事実も、この街に住む多くの住民にとってはどうでもいいことだった。――ほんの一握り、壁の向こうに行き来することを生業とするような者たちを除けば。
この街が「他の街と比べて」どれだけ過酷でも、街に住む人間にとっては、この街が世界の全てなのだから。
「お前、帝都に住むつもりはないか?」
――そう、「交易屋」シエレイのような、壁の向こうを知るほんの一握りの者たちを除けば。
◇
「ここに、お前の分の『臣民契約書』がある。こいつがあれば、俺たちは『壁の向こうの住民』、帝国臣民になれる。――こんなクソッタレな街で、ただ生きるために命のやりとりをする必要も無くなるんだ」
シエレイは、懐から封筒を取り出すと、その中から一枚の書類を取り出す。――帝国臣民契約書。帝国臣民、壁の中の住民にとっては出生届と同時に役所に提出する、ごくありふれた書類。だが、帝国臣民にも他国民にもなれない壁の外の人間にとっては、壁の内側で生まれ変わるという夢を叶えることを可能にする、千金の価値がある書類。
その書類を机の上に広げ、同じく懐から取り出した万年筆をその上に置いて。シエレイはビーツァに向けて、説得するように話しかける。
「ただ生きていくだけなのに、荒事がついて回るのは間違ってる。少なくとも、お前は『自分の都合で』誰かと命を取り合ったことは無いはずだ。――なら、『命のやりとりの無い、普通の暮らし』だってできるだろう? そんな未来が、こいつにサインをするだけで手に入る。悪い話じゃないだろう?」
そんなシエレイの話を、ビーツァは、どこか苦笑しながら耳を傾け。少しだけ考えた後に、シエレイに向かって問いかける。
「そいつは、今すぐに決断しないといけないことか?」
「――ああ。こいつは明後日までに『帝都』の役所に提出しないと無効になっちまう。今晩中にはここを出て明日の朝までに『壁』を超えないと、間に合わない」
シエレイの、どこか焦りを感じるような答えを聞いて。ふと、そんな未来も良いかもしれないなと、そんなことをビーツァは思う。この街から出て、壁を越えて、帝国臣民になる。それも、周辺都市に居を構えるのではなく、帝都の住民として、だ。
――きっとシエレイは、自分を誘う、たったそれだけのために、「危ない橋」と知りながらこの街に戻ってきたのだと、そうビーツァは確信をする。
ビーツァは、そんなシエレイの行動が、自分に向けた友誼から出たものだということを確信しながら……
「――返事をする前に一つ聞きたいが」
それでも、どうしても一つだけ、これだけははっきりさせなくてはと、店に入る前からそう思っていたことを確認する。
「最近、この街に出回り始めた新種の『ケムリ』、あれはお前が広めたモノなのか?」
――それは、自分たちの生に影を落とした「クスリ」という代物に、なぜお前は手を出したのかという、抑えきれない非難の響きが混じった、そんな問いかけだった。
3.血まみれジーニャ
「こんな面倒な日に来られてもね。迷惑よ」
店に入ってきた客に向けて、歓迎の言葉の代わりに、そんな憎まれ口を叩くウエイトレス。だが、そんなことはいつものことなのだろう。新しく入ってきた客も、ウエイトレスの、普通ではありえない接客の言葉に笑いながら、からかうように言葉を返す。
「ジーニャちゃんさぁ、それは無いんじゃない? こっちはお得意さまなんだ、愛想笑いの一つくらいあっても良いと思うんだけどなぁ」
「うるさいわね。今は『外の客』が来てるのよ。そのうえ愛想笑いだなんて、やってられないわ」
馴染みの客であろう男の、茶化しながらも常識的な言葉に、ウエイトレス――ジーニャ――は、相変わらずのふざけた返事を返し。その、どこまでも仕事を嫌がる発言に、馴染みの客は面白がりながら、店の奥、カウンターの向こうで寡黙に働き続ける体格の良い料理人に、気楽そうに声をかける。
「マスター! この姉さんさあ、給仕には絶対向いてないって」
「フン。そう言ってもな、うちのボスはこいつのことを気に入ってるからな。どうしようもねぇよ」
「……この店、絶対に何か間違ってるって。そのボスって人にも伝えといて」
そんな、じゃれ合いのようなやりとりを終わらせて、ジーニャにアゴで指された席に着く馴染みの客。そうして一仕事を終わらせたジーニャは、さて、あの特等席の客はどうなったかなと、窓際の特等席へと聞き耳を立て……
――そこで、今まさに「ケムリ」についての糾弾が始まったことを知ったジーニャは、自分の獲物を取りに、カウンターの奥へと姿を消した。
◇
ビーツァの「街で出回っている『ケムリ』の出所はお前か」という問いかけに、シエレイは少しだけ考える素振りを見せて。やがて、溜息を一つついた後、シエレイはビーツァの問いに答えを返す。
「……俺たちはこの先、帝都で生きていくんだ。そんなことを悩む必要もなくなるさ」
そんなはぐらかすようなことを、どこか諦めの入ったような口調で答えるシエレイ。――そんなシエレイに、ビーツァははっきりと、自分の意思を伝える。
「確かに、この街を出ていけば関係ないのだろうな。だが、この街の誰かをクスリ漬けにしてまで帝都に住みたいかと言われれば、答えはノーだ。――俺がそう答えることぐらい、わかってただろう?」
「――ああ、そうだな。わかりきってたな」
その言葉を聞いて、シエレイは何かを悟ったのだろう。全てを諦めたかのように、背もたれに体重を預けて天井を見上げ。やがて、何かを決意したかのように、口を開く。
「確かにここ最近、街で出回っていた『ケムリ』は、俺の仕事だ。そうしなければ、『臣民契約書』を手に入れることなんて出来なかったからな。――これでいいか?」
その言葉は、この終幕も想像のうちの一つだったという落ち着きと覚悟と、それでも、目の前の相手を騙すことだけはしないという決意の響きがこもった言葉で……
「――そう。なら貴方、自分がこの先どうなるのか、わかってるわよね」
その決意は、旧式の自動小銃を持ったウエイトレス――ジーニャ――にその銃口を押し当てられることになっても、揺るぐことはなかった。
◇
国境の街グロウ・ゴラッドを治めるアティーツ一家は、どんなクスリも認めない。関わった人間は、売人、情報屋、仲介者、利用者、誰であろうと、全てを裁く。
それを承知で新種の「ケムリ」を売り捌いたシエレイは、銃を突きつけてきたジーニャに、短く答える。
「――ああ、当然だ」
「何か言いたい?」
いかにも旧式といった風情を醸し出す自動小銃を突き付けられながら、顔色一つ変えずに答えるシエレイ。そんな彼に、ジーニャは表情を変えないまま、最後に言い残すことは無いか、言葉短かに問いかける。
そんなジーニャの言葉に、少しだけ考えを巡らせ。やがて何を言うのか決めたのだろう、シエレイは口を開く。
「そうだな。……俺はこの『ゴルディクライヌ』という酒が嫌いだ」
その、最後を飾るのにふさわしいと思えないような言葉に、何を言い出したのかと首をひねるジーニャ。そんなジーニャに構うことなく、シエレイは言葉を続ける。
「乱暴に蒸留した酒を癖の強い香りでごまかす。まるで、そこらへんに転がっている暴力の恐怖を酒でごまかして生きている、この街の住民そのものじゃないか。――ああ、俺はそんな、この街にふさわしいこの安酒が、本当に嫌いだ」
その言葉を聞いたジーニャは、なるほどと軽く納得したかのような顔をする。――ああ、この男は、最後の言葉にカッコつけたタワゴトを吐くタイプかと。そんな言葉を残したところで、意味もなければ恰好が付く訳でもないわねと、そんなことをちらりと思いながらも表情には出さず、もう一度、言葉短かに問いかけ……
「それだけ?」
「ああ」
これ以上の言葉が無いと確認したジーニャは、その手の愛銃の引き金を引く。
ズィマー・ジレーザ。もはや旧式となった、秒間に数発しか発射できない、骨董品と言ってもいいような突撃銃。その銃口から飛び出した弾丸が、シエレイの頭部を一撃で吹き飛ばし。さらにその亡骸を吹き飛ばしながら、なおも弾丸を吐き出そうと、遊底を大きくスライドさせる。
◇
ジーニャが手にした自動小銃が、ズドンズドンと、銃弾を目まぐるしく吐き出し続け、重い銃撃が、立て続けにシエレイの亡骸を襲う。
吹き飛ばされた亡骸は、銃弾に抉られながら、飛び散り舞い落ちる硝子の破片の中を踊るように、国境の河に向けて、その身を躍らせて。――まるでその亡骸が来るのを待ち構えていたかのように、流れゆく河に浮かぶ氷塊の形をした冬精が、その顎を大きく開け。大河にたどり着いた亡骸を一飲みにする。
――その、一人の人間が血と命をまき散らしながら消えていく様を、ビーツァは、酒の入ったグラスを片手に、黙って見つめていた。
◇
やがて、静かになった店で、ビーツァは独り、グラスの中に残った酒を一気にあおり。傍らのウエイトレスへと話しかける。
「……勘定を」
「今日は奢りだって、ウチのボスからのお達し」
「――そうか」
短い言葉のやり取り。その「奢り」の理由に思い当ったのだろう、ビーツァは一瞬だけ言葉に詰まった後、何事もなかったかのように返事をする。
「もう一つ、ボスからの伝言。行くところが無いならウチで働けって」
「……考えておく」
もう一つの、こちらも予想もしていなかったようなジーニャの言葉に、先送りの返事をして。ビーツァは、中身がなみなみと入った酒瓶を乱暴につかみ、席を立つ。短時間の間に少し飲み過ぎたのだろうか、ふらつきそうになりながら、店の外に出て……
――今日は面倒を起こしてくれた「外の客」がこの世界から出ていった、記念すべき日だ! ここにいる全員、ウチのボスからの奢りだ! 好きなだけ飲めや!
閉じた酒場の扉の向こうから聞こえてきた料理人の叫びを背に、ビーツァはだれもいない自分の部屋に帰るために、薄暗い夜の道を一人、歩き出した。
◇
「クソッタレが」
ビーツァは、友の血に濡れたまま、頼りない街灯の明かりに照らされた道を、一人歩く。話に聞く帝都の街灯は、路地裏まで余すところなく煌々と照らされ、その真昼のような明るさは、夜空から星空までも消し去ってしまうという。歩きながら安酒をグビリとあおったビーツァは、そんな話をシエレイと交わしていたことを思い出したのだろうか、再び瓶に口をつけ、中の酒をゴクリゴクリと飲み下す。
――クスリに関わった交易屋は、二度とこの街に戻ってこれない。それは、交易屋にとっては、常識だ。
有能な商人は例外なく交易屋となって、壁の向こうで仕入れをする。何故なら、価値のある商品は全て、壁の向こうからもたらされるからだ。――だが、壁の内側の人間は、壁の外の住民のことを、人の形をした動物程度にしか認識していない。
壁の向こうの帝国臣民は、交易屋に対して平然と不利な取引を持ち掛け、隙あらば騙し、時に暴力で奪い去る。――それらに適切に対処できて、初めて「交易屋」を名乗ることができるのだ。
無能な商人は、交易屋を名乗ることすらできない。だが、有能な者は、それらの不利を押しのけて、壁の向こうに取引先を確保し、――さらなる才覚があれば、帝都にまでたどり着いて、「帝国臣民」となることすら、不可能ではない。
――壁の外側を「金づる」とする覚悟さえあれば。
だが、壁の外側には組織がある。組織は、自らのシマを荒らす存在は、決して許さない。たとえ相手が「帝国」だとしても、彼らは一歩も引かずに戦う。ましてや、交易屋上がりの帝国臣民相手に、躊躇することなど無いし、いつまでも出し抜けるような甘い組織は存在しない。
――故に、故郷を売った「交易屋」は、何れ消えるのだ。
「クソッタレが」
ビーツァは再び呟く。そこには、ありえない選択をした友と、その友を無慈悲に殺したこの街と、――そして、この街で生きるためにその友を売った自分自身に向けた言葉で。
ビーツァは思う。自分も、心のどこかで、この街を出たいと考えてたのだ。そして、シエレイはそのことに気付いていたのだ、と。
――もし自分が、初めからこの街を出ないと決意していれば、シエレイもこの街に戻ってくることはなかったのだろうか。そんな、ありもしない過去を後悔しながら、ビーツァは独り、夜の街を歩く。
◇
明るい世界に憧れ、努力の末にそこにたどり着いた男がいて。明るい世界に憧れ、自らの手を血に染めながら、それでも、生まれ育った場所を憎めなかった男がいて。そんな二人がたまたま隣り合うように生まれ、違いに信じあい、道を違え。たったそれだけのことで、人が死んだ。
――これはそんな、人の命がどこまでも軽い、このクソッタレな街にお似合いな話だった。
4.酒場「血まみれジーニャ」へようこそ
次の日の朝早く。料理店も兼ねた酒場「血まみれジーニャ」の、開店前の店の中で。店を任されている料理人が従業員に一人の新人を紹介するという、普段にはない「儀式」が執り行われていた。
「今日からこの酒場で働くことになった『人消しビーツァ』君だ」
「――よろしく頼む」
……正直なところ、相手は、同業者の中では有名人だし、多分自分のことも知られてるだろう。紹介する必要はあるのだろうかと、そんな風に思っていたビーツァは、いきなり「殺し名」で紹介されたことに苦笑しながら、目の前の、もう一人の従業員に挨拶をする。
――「血まみれジーニャ」。業界では、仕事のたびに必要以上に血を撒き散らすことで有名な殺し名。この街に君臨する組織、アティーツ一家の誇る腕利きだ。
「ふうん。ホントに来たんだ。――なんか、私とは合わない気もするけど、ヨロシク」
ジーニャの言葉にビーツァは再び苦笑する。辺り一面に血の雨を降らすような派手な仕事をするジーニャと自分は、確かに相性が悪いかもしれない。――何せ自分の殺し名は、その標的が生きていたという痕跡を「まるで生まれてこなかったかのように」綺麗にこの世の中から消すことでついた名前なのだから。
そう思いながらも、とりあえずはまあ、来てもいない殺しの仕事よりも、毎日の平和な仕事だろうと、目の前の相手に挨拶を返す。
「ああ、よろしくな」
そんなビーツァの、なんの変哲もない挨拶に、ジーニャはニヤリと笑う。まるで、自分のことを知りながら自然体で接してくる名の通った「殺し名」に、次は実力を見せてもらわないとねと、そう言いたげに。
そんな、どこか肉食獣めいた笑い方を見て、ビーツァは思う。――物騒だけど、見た目は悪くない。まあいいんじゃね? かわいいんだから、と。
この日からビーツァは、この街を仕切るアティーツ一家の一員として、この店の調理人やジーニャと共に、表と裏、両方の「仕事」に当たることになる。それは、ビーツァにとって初めての、シエレイとは違う「仲間」で。
――それは同時に、ビーツァがこの街を「故郷」と定め、骨を埋める覚悟を持って生きていく、その第一歩でもあった。
血まみれジーニャの酒場へようこそ
本作品は、「小説家になろう」からの転載です。
https://ncode.syosetu.com/n3376fk/