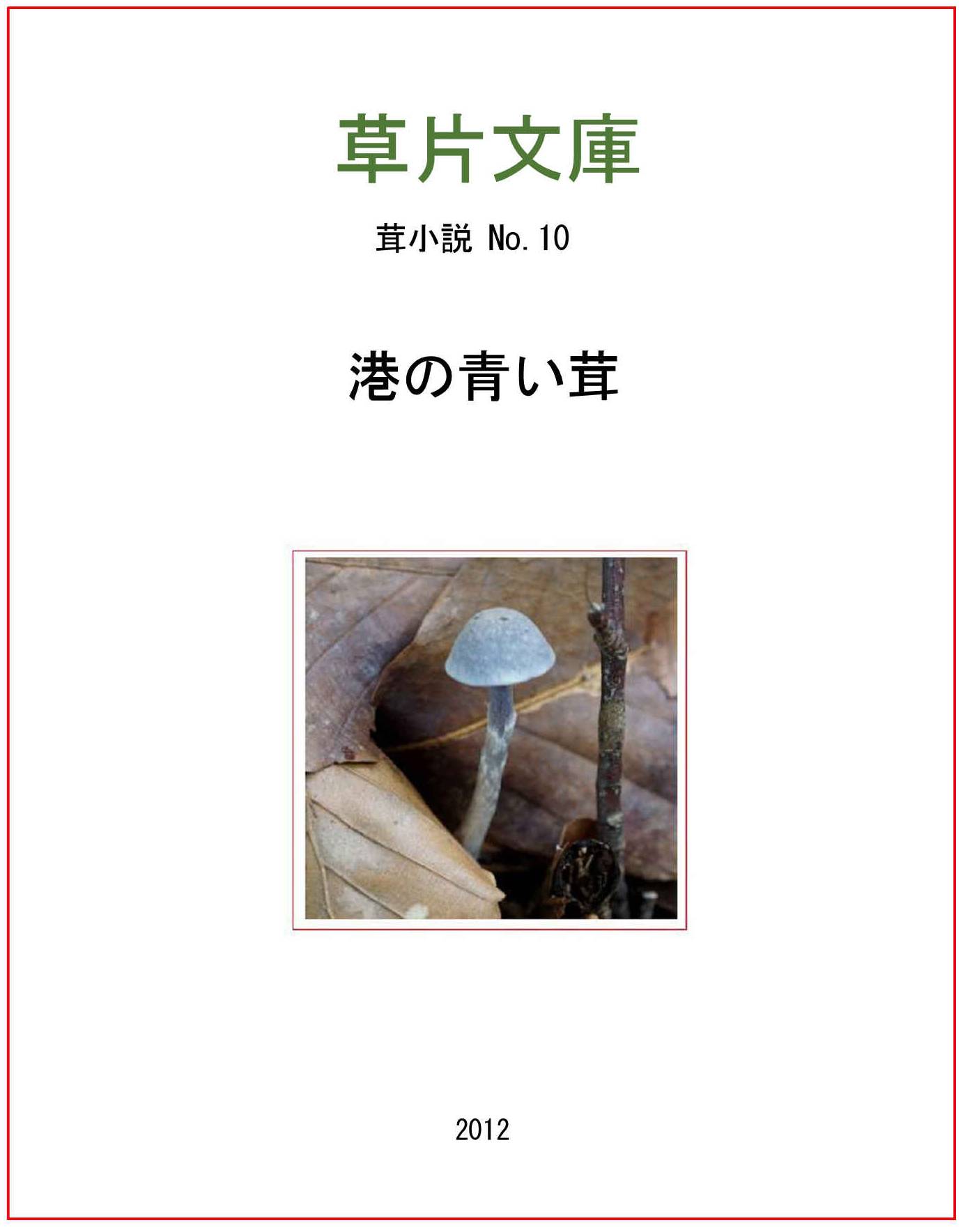
港の青い茸
門司港のホテルに着いた。すでに十時を回っている。手続きを済ませて部屋にはいった。真っ白の家具に統一されたシンプルな気持ちのよい部屋である。窓から、対岸の下関の明かりがまぶしいほどに輝いて見える。灯のともった大きな船や小さな船が一時も途切れることはなく、忙しそうに動いている。有名な関門海峡である。
スーツからジーンズに着替えると、窓の張り出しの上に角瓶をだした。旅行のときは一本抱えて持ち歩くことにしている。備え付けのグラスに少しばかり注ぐと、きゅっとあおった.旅の疲れが少しほぐれる。
海を見たくなった。
ホテルの外にでた。岸には何艘もの小さな船が停留している。
歩いていくと、一艘の真っ白な小さな漁船が眼にはいった。船の上ではたくさんの鴎(かもめ)が群がっている。この時間に鳥がいること事態おかしいが、もっと奇妙なことに、全く鳴き声をあげていない。群がっている鴎はぎゃあぎゃあと鳴きちらし、うるさいのが常である。音もなく甲板を歩き回り、飛び回っている様子は、音を消したテレビの中のシーンのようである。
船に積んであるものに群がっているようだ。それぞれ何か咥えると、飛び立ち、船の上を旋回している。
私が立ち止まって見ていると、頭上に一羽飛んできた。その鴎は口に咥えているものを私の目の前に落とした。
それは私の足下にコロンと転がった。
街灯の光が真っ青な傘を持った茸を照らし出した。マリンブルーのきれいな青である。柄の部分は白く、このような茸は見たことがない。
船の上に目をやると、甲板に積み上げられているのはその茸のようである。鴎は茸を咥えると、次から次と船の上のほうに舞い上がり、今度は降りていく。
しばらく見ていると、船の上を舞っている鴎が一斉に私を見た。
私に気がついた鴎たちは、音もなく頭上に飛んでくると、青い茸を私に向かって落としはじめた。
頭上から青い茸が降ってくる。しかし一つとして私に当たることはなく、足下にころがった。
ふっと見上げると、頭上は無数の鴎でうずまり、夜空が全く見えない。
あっと、思った瞬間、鴎が一斉に口を開けた。青い茸が私の頭めがけて落ちてくる。
茸は頭に当たることはなかったが、コロコロと転がり、私の周りに積み上げられ、とうとう、私の頭の上にも茸がのっかってきた。
やっと恐怖感が襲ってきた。逃げなければと思ったとき、すでに私は青い茸の中に埋もれていた。
あわてて青い茸をかき分けると、茸の山から顔をだすことができた。
鴎たちは船の上にもどり、声を上げることなく、茸を咥え、空に舞い上がっていく、
一羽が茸の山から顔をだした私に気づいた。ふたたび鴎たちが船から私めがけて飛んできた。口には青い茸が咥えられている。頭上で一斉に口を開けた。笑っているように見える。今度は青い茸たちが頭にぽこぽこあたった。
鴎がどんどん飛んできて、青い茸を頭上に降り注いだ。
私はとうとう青い茸に埋もれてしまった。
むかし、冬山を登っているときに雪崩に遭遇したことがある。あっと言う間に雪の中に飲み込まれてしまった。埋もれてしまった時は、息をする空間も少なく、苦し紛れに頭上の雪をかき分けると、幸いにして頭上の雪は多くは無く、外にはい出ることができた。
そのときと比べると、ごろごろとした茸は隙間があり、息苦しさは感じなかった。
しかし、次第に茸の匂いで息苦しくなってきた。先ほどと同じように、手でかき分けると茸の山がくずれた。
どうやら顔を出すことができた。船の上を見ると鴎はもういなかった。
甲板に積み上げられていた茸はなくなっているようである。かわりに漁港の岸に積み上げられている。
這いでようと足を踏ん張ると、足下の茸がぞろぞろと動き始めた。足下をすくわれ横倒しになった。もがいていると、私は上に押し上げられ、空を見上げるかっこうで茸にかつがれたまま動き出した。
星空がきれいだ。
青い茸はごろごろと動きながら私を運んでいく。
私の泊まっているホテルの前にやってくると、玄関からなだれこみ、ぞろぞろ石段を上った。入口のドアが開き、茸に担がれて中に入った。フロントの前を通り、エレベータの前で止まった。フロント係りは椅子に座って舟をこいでいる。
エレベータが開いた。茸たちは私を支えたままなだれ込んだ。
エレベータの中は茸と私でギュウギュウになり、それでも扉が閉まった。
九階についた。エレベータの扉が開いた。
茸たちは私を乗せたまま勇んで飛び出した。そのまま私はいつのまにか部屋の中にいた。
茸たちは私をベッドの上に放り投げた。乱暴なやつらだ。
青い茸はピョコピョコと私の部屋の中を飛び跳ねた。一つがテレビをつけた。テレビのチャンネルが勝手に回ると、古いアメリカの歌手が歌っていた。
ブルーベエルベットーーー
青い茸たちは椅子の上にのぼったり、私のベッドの上にあがったりおりたり、歌にあわせてからだを揺らしている。
歌が終わると、チャンネルが回って、料理の番組になった。
茸たちが画面に釘付けになった。茸に目があるわけではないが、一斉に頭を画面に向けて動かなくなったので、私にはそう見えた。画面では松茸の土瓶蒸しをつくっていた。熱い出汁の中で、丸ごとの茸がゆったりとゆれている。
青い茸たちは、風呂場に殺到した。
湯船に熱いお湯が満たされると、茸たちが飛び込んだ。青い茸たちは湯の中でプカプカ浮かんで、しばらくすると湯からでてタオルの上で転がった。
すべての茸たちが湯からでると、ベッドの上や床の上に転がって、私にテレビのチャンネルを変えるように要求した。言葉をしゃべるわけではないが、そう言っていることがわかった。さっきは自分で変えていたのだからそうやればいいのにと思っていると、一つの茸が私の鼻の頭に飛んできた。
痛いったらありゃしない、しぶしぶベッドから起きるとテレビのリモコンをとって、チャンネルを変えた。
旅のチャンネルでイギリスの小さな島を紹介していた。寒い地方のその島では、小さいにも関わらず、たくさんの有名なウイスキー蒸留所があり、スモーキーなウイスキーを世界に送り出している。
青い茸はそのウイスキーを飲ませろと言った。そんなウイスキーはないが、日本のウイスキーなら持っていると、窓の脇に載せておいたサントリーの角瓶を指差した。
茸たちはそれでよいからコップにつげといった。ガラスのコップをテーブルの上に載せ、ウイスキーを三分の一ほどいれた。ところが、なみなみとつげと茸が命令した。コップいっぱいにすると、風呂に入ってだらけていた茸たちが、とび起きて、コップの前に列をなした。
一つがコップの前でお辞儀をした。コップのウイスキーに傘を浸したのである。ウイスキーに頭を浸した茸は、頭を上げると、よろよろと床の上をさまよい始めた。
酔っぱらったわけである。頭をちょっとウイスキーに浸すと茸たちはすぐに酔っぱらって、部屋の中をよろよろとさまよった。コップからウイスキーがなくなるともっと注げと要求された。ウイスキーを足してやると、茸たちはきちんと並んで、一つずつ頭をウイスキーに浸し、酔っぱらうのである。
私はそこで初めて、茸の数というものを調べてみた。十個の茸がどのくらいあるかとみると、ざっと五十はくだらない。ということは、五百個ほどの青い茸が、私の部屋で風呂に入り、ウイスキーを飲み、酔っぱらっているのである。青い頭を持った五百の茸の頭が、部屋の中でゆらゆらと揺れている。それを見ていた私も催眠術にかかったように目がぼやけてきた。
ベッドの脇の時計をみると、もう三時を回っている。テレビはお休み前のスローなテンポの音楽を流している。
茸たちが床の上に転がっている。私の頭に色々な音が聞こえてきた。それが茸たちのいびきであることに気づくのに少し時間がかかった。
青い茸たちは気持良さそうに、いびきをかいている。
私もぼーっとしていると、窓をたたく音がする。
対岸、下関の明かりが瞬いている。見ると、鴎が窓ガラスを突ついていた。
私はベッドから降りると、茸を踏まないように窓に近づき開けてやった。
鴎は私を見ると微笑みながら部屋に入ってきて青い茸をくわえた、そうして夜空に向かって飛んでいった。次から次へと鴎たちが入ってきて、ベッドや床の上で寝ている茸を咥えた。
そうやって、鴎たちは青い茸を咥えて夜の門司港に消えていった。最後の鴎が茸を遊ばせてもらった礼を言ったような気がする。
窓が閉まり、私も眠くなってベッドの中にはいった。ベッドの下でことりと音がした。身を乗り出して下を見ると、青い茸が一つベッドの下から顔をだした。私を見るとベッドの上に飛び乗ってきた。
「どうした、忘れられちまったのか」
と声をかけると、茸は頭を横に振って、布団の中にはいると、脇で寝てしまった。
枕も半分取られた。
私も青い茸を横目に見ながらそのまま眠りに落ちた。
明くる朝、窓からの日の光で目が覚めた。気持ちのよい目覚めであった。ふと、気がつくと、真っ白だった私のホテルの部屋は青一色に染まっていた。鮮やかな気持ちのいい青空の中にいる気分でベッドから降りた。隣で寝ていた青い茸はいなかった。
空になった角瓶に朝の光があたってきらきらと輝いていた。
港の青い茸
私家版 第九茸小説集「茸異聞、2021、一粒書房」所収
茸写真:著者: 秋田県湯沢市小安 2017-9-16


