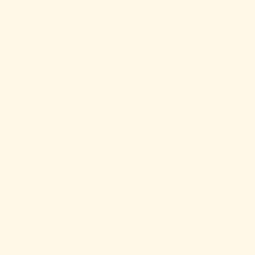冬の姿と重なる天使たちの踊り
夜が明ける。冬が来る。誰も見たことの無い閑静な冬が。小鳥たちは静かに眠っている。豪勢なベッドと、温かく光るオレンジ色のランプ。明日食べられるパン。大きな灯台。静かに眠っている小鳥たち。うっすらと春が顔を見せるが、誰かの遺志がそれを外界へと追いやる。全ては季節の流動だ、主よ。ある朝のこと、私が外に出掛けると天使たちが手を繋いで踊っていたが、あれが冬ではないのだとしたら、ついには私がおかしくなってしまったのだろうか。雪山に取り残された私はこう告げる「少年の頃、ひどく味の悪いジャムを舐めては飢えを凌いでいたが、今は太陽の光さえも美味と思える」。いや、むしろ太陽の光こそが宝石の果実なのだ。私は誰と話しているのだろうか。答えはあの暖炉の中にあるはずだ。火が弾けてコウモリが宙を舞う。暗い箱の中を影の虫が這い回る。夜に出回る水性新聞を飲む。私はあの天使の正体を確かめずにはいられないだろう。きっと明日には天からの日差しに熱せられて、あの天使を壁へと打ち付けるための釘を持って、幾ばくかの食べ物と金貨、聖なる書のコピーペーパー、私の想いを埋めた人形を持って、私はあの天使の羽根の美しさにメスを入れる。熱い涙を天使の小さな手に擦り込んで、それから天使の額に私の名前を彫るのだ。しかしそこで私はあることに気付くだろう。即ち、私に名前などないということを。
冬の姿と重なる天使たちの踊り