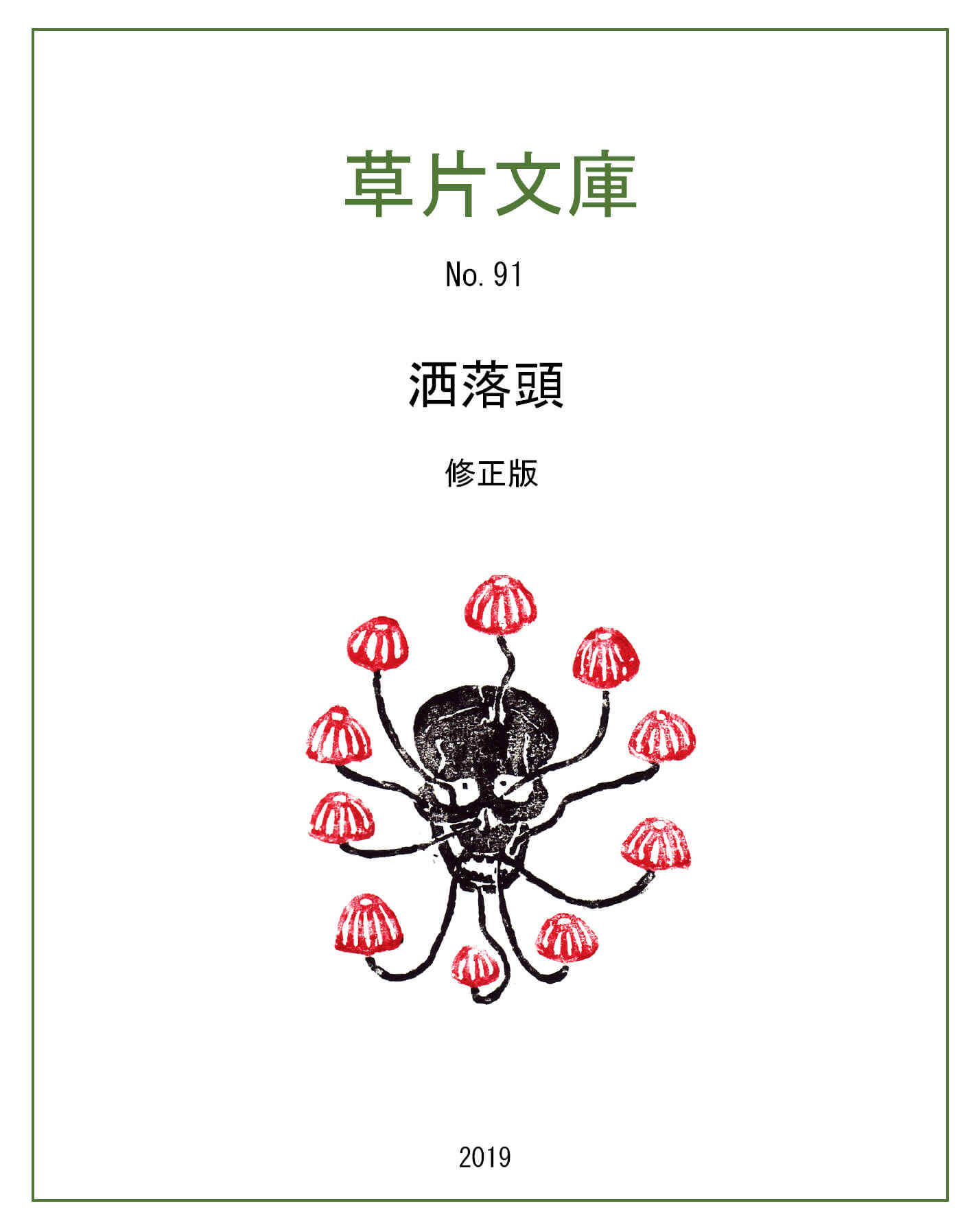
洒落頭(しゃれこうべ)
はじめての探偵小説です。殺人事件のない探偵小説です。ちょっと長い話です。ここで、掲載を一月ほどおやすみさせていただきます。
洒落頭(しゃれこうべ)
目次
洒落頭 プロローグ
探偵の二人の助手
お岩さんと外骨の墓
ミステリーサークル
紫式部と小野小町の墓
再会
北京原人
二人の依頼人
捜索の終了
新たな出発 エピローグ
主要登場人物
探偵 :詐貸美漬(さがしみつけ) 男 1970生
探偵助手 :逢手野霧(あいてのむ) 女 1978生
探偵助手 :吉都可也(きっとかなり) 男 1980生
依頼人 :跡出馬盛(あとでまもる) 男 生誕年不詳
詐貸の初恋の人:夢久愛子(むくあいこ) 筆名:塔晶子 1970生
愛子の亭主 :水良佐里雄(みずらさりお)北京骨商社員 1965生
愛子の父 :夢久多助(むくたすけ) 掘削機製作会社社長 1940生
愛子の祖父 :夢久 十(むくとう) 製薬会社北京骨商創業者 1890生
愛子の叔父 :夢久哉有(むくかなう) 製薬会社北京骨商再興者 1922生
水良佐里雄の父:水良 今(みずらこん) 北京骨商社長、薬学博士 1938生
洒落頭 プロローグ
「髑髏」は音読みで「どくろ」、訓読みで「しゃれこうべ」、「髑」も「髏」もどちらもしゃれこうべと読む。曝(晒)された頭骨のことで「されこうべ」からきている。
髑髏には沢山の穴、孔がある。目の穴、鼻の穴、耳の穴、それに小さな孔から中にある脳から出た神経が顔やからだに行く。底にある大きな孔からは脊髄がでる。
髑髏は大きな口を開け歯を剥き出してカタカタと音を立てて笑いかける。余計なものをそぎとった美だ。蒸気機関車は蒸気を通す管を備え魅力のある形になった。髑髏もまさに人間が誇るべき機能美の極致だ。洒落たカルシウムの硬い塊である。
野晒しという落語がある。野晒しも髑髏のことだ。釣りに行った男が川で曝された頭骨を釣り上げ、供養のために酒をちょいと垂らす。すると夜な夜な頭骨の持ち主の美女が幽霊となって出て来て酌をする。それを聞いた友人も真似をするが、出てきたのは男の幽霊だったと言う話である。
ここに紹介するのは、ちょいと逆で、失われた北京原人の頭骨によって釣りだされた探偵の物語であり、でてきたのはとある収集癖一家の驚きの顛末である。
探偵の二人の助手
西巣鴨にある庚申塚(こうしんづか)探偵事務所は知る人ぞ知る有能な探偵事務所で、盗難にあったものや、失われたものを確実に見つけ出す。
庚申塚という名がついているので、庚申塚に近いかというとそうでもなく、新庚申塚駅で荒川線を降り、白山通りを横切って、お岩通りをしばらく行き、妙行寺方面に曲がり、荒川線を横切ってすぐのところの小さな岩本ビルの二階にある。妙行寺はお岩さんの墓があることで知られており、訪れる人も多い。
庚申塚探偵事務所の所長、詐(さ)貸(がし)美(み)漬(つけ)は、五年前に事務所を開いた時、名前をお岩探偵事務所にしようかと思ったが、やはりそれでは客が来ないだろうと、庚申塚探偵事務所にしたのである。
詐貸一人で始めた事務所ではあるが、先月から二人の助手を雇っている。一人は大学を出て劇団に所属していたのだが全く目がでず、途方にくれていたところを詐貸が拾ったのである。
ひょんなことからその劇団の公演を見る機会があった。その時詐貸の目に留まった男がいる。彼は枯れ木の格好をして、劇が始まった時から終りまでずーっと突っ立っていたのである。詐貸は我慢強さと目の動きが面白くて覚えていた。枯れ木の男は絶えず眼を動かし観客の動きを見回していた。劇が終わるとポケットから取り出した眼鏡をかけた。蟷螂のように顎のとがった逆三角形の顔をしていた。
そんなことは忘れていたのだが、ある日詐貸が事務所に行くためにお岩通りを歩いていると、その男が妙行寺はどこかと聞いて来た。とっさに蟷螂を思い出し、公演を見たことを言うと、今度お岩さんの劇で通行人の役をやるので墓に詣でるために来たという。話をきくと名前を吉(きっ)都(と)可也(かなり)といって、都内の大学の生物学の大学院を出たのだが、演劇をやりたくて劇団に入ったという。ところがいい役はやらせてもらえないという。アルバイトで生計を立てていたが、そろそろ役者になることには見切りをつけ、定職を探そうと思っていると言った。それで調度人手が欲しいと思っていたところなので探偵助手に誘ったのである。
もう一人の助手は新庚申塚駅の一つ手前である庚申塚駅から出てきて、調度通りかかった詐貸に庚申塚の場所を尋ねた女性である。その時詐貸は昼を食べるために行きつけの蕎麦屋に行くところだった。地蔵通りを大正大学の方向に少し歩いたところにある蕎麦屋ひさごである。ひさごは手打ち蕎麦を一日70食分しか作らず、蕎麦は全国に委託した十三の蕎麦農家から直接買い付けている。天麩羅にするための山菜なども山奥から自分で採ってくるという凝った主人で、本当の蕎麦を食べさせる。通の間ではよく知られている。
庚申塚を詐貸に尋ねた彼女はさらに庚申塚探偵事務所を知っているかと聞いてきた。どうも助手公募をどこかで見てきたらしい。そのまま事務所に戻るのも面倒である。名刺をだして一緒に蕎麦屋に誘った。
彼女は驚いたことに蕎麦を二皿ぺろりと食べた。ただ珍しいことに蕎麦屋の主人は愛想が良かった。この主人、気に入らない客は店に入れないし、たとえ蕎麦を出してもほとんどしゃべらない。彼女が蕎麦に直接山葵をつけるのをちらっと見ていたので、食べっぷりもだが味の分かる女だと思ったのだろう。ここの主人がそう思うくらいなら雇わなければならない。そういうことで彼女が助手になった。色白の丸ぽちゃでどっしりとしている。図書館に勤めていたのであるがもっと動く仕事をしようと考えていたところだったそうだ。名前は逢手(あいて)野(の)霧(む)という。
最初の日、二人には出勤する時間を指定してあったので、前後して事務所に入ってきた。まず吉都でちょっと遅れて逢手である。ほぼ時間通りでこれならば大丈夫そうだ。二人にはそれぞれ机を与えた。
その日、二人を紹介して雇った理由を説明した。
「最近、一つの仕事を引き受けた。自分一人で出来るかどうかわからないので一端は断ったのだが、三度も電話があった、今まで行方不明の子供の捜索や紛失物の捜索、結婚相手や取引先相手の素性の捜索、配偶者の浮気、すべて一人でやれるものばかりだったんだ。この探偵事務所は俺一人でいいと思っていた。しかし今度引き受けたことは歴史も絡んでくるし、外国も絡んでくる仕事で,とても自分一人じゃ無理なんで二人をお願いした」
「それで、何を探すんです」
最初に口をひらいたのは逢手だ。でんと落ち着いているが結構せっかちのようだ。頭が回るのかもしれない。
「北京原人の頭の骨を探し出す」
それを聞いた二人は何も反応しなかった。北京原人を知らないのだろうか。
「考古学ですか」
「いや、人類学よ」
吉都と逢手はもう二人であたりまえのようにしゃべっている。北京原人をよく知っているようだ。むしろ詐貸のほうが知識が少ない。
「ある人からの依頼なんだ。かなりの額を提示されてね、必要なら人件費も出すというので、引き受けてしまった。北京原人の頭骨なんて全く興味なかったので、これから調べていかなければならない」
「北京原人の骨ならば研究している人は沢山いるのではないですか、人類学者や進化の研究者、それに歴史学者もいますよ」
「そういう人とはかかわらない方がいいと依頼人は言っているんだ」
「どうしてです」
「研究者は自分の考えを持っていて、それに引きずられると探す方向性が狭まるから、素人の観点で探したほうがいいと言っている。俺のやり方でやってくれということだ」
探し物は必ず見つけるというのがこの探偵事務所のうたい文句だ。
「いつまでに探す必要があるのですか」
「期限は言われていない」
「それじゃ、見つからなければずーっと雇ってもらえるというわけですか」
なんという言い草だ。
「まあ、皆さんが役に立てば」
そう言ったら。逢手野霧はゆったりした丸い顔を楕円にしてうつむくと、
「骨探しですか、骨が折れますよ」などと笑っている。さらに、
「髑髏の好きな人は結構いますね、まだ行ったことないけど、尼崎にシャレコーベミュージアムっていうのがありますよ。関西医大脳神経科の先生が作ったものですよ」
と顔をあげた。結構物知りのようだ。
「髑髏博物館なんて物好きな人もいるんだね」
「アステカ文明に水晶で作った頭蓋骨があって、クリスタルスカルって英語で言うものだから、なんとなく格好良くて頭蓋骨を集める人増えたんじゃないかしら。ほら、映画にもなったでしょう、インディージョーンズの最後の作品、クリスタルスカルの魔宮」
詐貸もそれは知っていた。
「暴走族のお兄ちゃんなんて、髑髏の旗をたてて、髑髏のキーホルダーちゃらちゃらつけて喜んでるじゃない」
野霧はまくし立てた。
「僕も知ってる」
吉都の眼鏡の奥の眼が輝いて身を乗り出した。獲物に飛び掛る前の蟷螂に似ている。
「頭骨は体の中の骨と違う出来方をするんですよ、ほとんどの骨は軟骨がまずできて、その場所に骨が作られるんだけど、頭骨は軟骨が出来ないでいきなり骨が作られるんです、なぜ子供のちいちゃな頭の骨が脳の成長にしたがって、外に大きくなっていくかわかりますか」
そんなの分かるわけはない、詐貸も逢手も首を横に振った。
「最初は袋状の物が骨になって、外側に新しい骨が出来て、内側の古い骨は吸収されるんです、それを繰り返すと中が広がる」
「でもどこかで止まるんでしょ」
逢手がそう言うと吉都がうなずいた。
「そうですね、そうしないと頭でっかちになっちゃう」
「私の頭なかなか止まらなかったんだ、あはははは」
これが二人の最初に探偵事務所に顔を出した時の会話である。
詐貸は仕事を引き受けた時、北京原人のことを知らなければと、まずインターネットを開いた。そこにはこんなことが書いてあった。
太平洋戦争が始まる前、北京のはずれに位置する周口店の洞窟からカナダ人研究者が原人の骨を発見し、北京原人、シナントロプスーペキネシスと名付けた。およそ55から30万年前のものとされている。ところが発見された骨は戦時中に行方不明になっている。
このような基本的な内容はインターネット上のどの説明もほぼ一致している。北京原人に関する専門書も調べた。それは山ほどあった。とてもそれを読み解くようなことはできない。それで助手を雇おうと思ったところもある。
詐貸は何か読んでみようと思い、色々ある本の中から小説を選んだ。小説でも少しは史実にのっとっているものである。
選んだ本は「五十万年前の死角」という伴野朗の探偵小説で、1976年に江戸川乱歩賞を受賞している。北京原人の骨が戦時中に紛失したその事件を歴史と絡ませたサスペンスである。そういったものを読んだ方が面白みが湧いてきて、北京原人の骨に対するイメージを作りやすい。などと理屈をつけているが、彼は大のミステリー好きで、特に乱歩賞受賞作はよく読んでいる。しかしその本は読んだことがなかった。ミステリー好きが探偵という職業を選ばせたのかもしれない。
北京原人の骨の紛失は、発見が戦争直前であったことが不運だったようだ。日中戦争の発端とも考えられている蘆溝橋事件が起きたところは周口店の近くである。その後太平洋戦争が起き、周口店で採取された骨は日本に略奪されることを避けるため、北京から離れた河北省の秦皇島より船でアメリカに輸送されるはずだった。しかしその船が日本軍に撃沈され行方知れずとなっている。
そんなことを二人に話したら逢手が、
「私もその本読みました。読み応えのある面白い推理小説でした、その本も骨はアメリカにいってない、という設定でしたが、今回依頼されてきた人もそう思っているわけですか」
「そうなんだ、その人は電話でこんなことを言っていたよ」
詐貸に依頼をしてきた人は、その骨が日本に渡ってきているという。北京原人の骨を含む化石骨など大事な資料が入っていた箱の一つを、泰皇島から船に積む前に人足の一人が女のところに持ち込んでいた。秦皇島は風光明媚のところで保養所でもあり、中国軍の幹部が良く訪れていた。木箱に入っているのを武器だと思った人足は密かに隠し、いずれ中国軍に渡して報奨にでもありつこうと思ったらしい。ところが女の家でその箱を開けてみるとただの骨であって、きっと戦死した者の遺骨だと勘違いした男はその家の地下室に隠した。
戦争が終わりになると、日本は敗戦しロシアとアメリカの二大強国が出現した。中国も独立して大きな国になろうとしていた。復興した日本は戦後遺骨の収集に力を注ぎ中国も協力をした。
そのような中で、遺骨の収集に来た日本人の一人に、人足の家の地下室にあった骨を、秦皇島に戦時中住んでいた亡くなった日本人のものだろうと思った子供か孫が、渡したのである。親から日本人からという言葉を聞いていたからだという。おそらく日本人から守るということを、ただ日本人からという形で記憶に残ってしまったのだと思われる。もらった遺骨収集団は箱に秦皇島と表書きして日本に持って帰ってきたということである。
それに気が付いた依頼人がその骨を捜したのだが、いつの間にか保存されていた場所から紛失していた。それでそれを捜すように詐貸に依頼したわけである。
「保管されていた所はどこなんですか」
「戦没者の遺骨管理は厚生省の管轄で、霞ヶ関の合同庁舎に収められている。一体一体調査がおこなわれ、どうしてもわからず、引取り人がいない場合には、千鳥が縁にある戦没者墓苑に葬られるということだ」
「箱が紛失したのは墓苑に葬られる前だったのですね」
「そうらしいよ、その北京原人の入った箱は依頼人がそれを知った時にはまだ調査の手が入っていなかったそうだ。調査されていれば北京原人の骨かということで新聞を賑わしたことだろうな。ところがその依頼人が尋ねて行った時にはなかったのだから、調査される前に紛失していたことになるね、他にも北京原人の骨を探していた人物がいたのかもしれないよ」
「詐貸先生はすでに合同庁舎は調べられたのですか」
「うん調べた」
戦没者の骨がしまわれているのは厚生省合同庁舎五号館である。お骨のしまってある部屋は霊安室と呼ばれている。
「秦皇島と書かれている木箱に入った遺骨を捜しているということで照会をしたんだ。昔親族がそこで亡くなったので骨を捜していると言ってね、そうしたら、北京から持ち帰った泰皇島と書かれた箱があるという記録が見つかったと連絡があり、それで出向いていったよ。
ずい分親切に案内してくれてね、まだ調査をしてない遺骨の置いてある部屋に古い箱があって、泰皇島と毛筆で書かれた黄色くなった紙が貼られていた。
案内してくれた係官が開けてくれたのだけど、古びた新聞紙しか入っていなかった。新聞紙は確かにその当時の中国のものだった。
依頼人は箱そのものがなくなっていたと言っていたが、俺が言った時には見つかった。これも不思議なことだと思ったよ」
その時の様子を詐貸は二人に話した。
箱の中に何もなかったのを見て係官は首をひねった。
詐貸は係官に「誰か盗んだのですね」と尋ねた。
「いや、帳簿ではまだ調査もしていない状態ですので、そういうことはないと思います」
「遺骨じゃなくて、塵のようなものが入っていて、捨てられたということはありませんか」
「そうだとすると帳簿にはそのことが記載されているはずですし、箱ごと捨てると思います」
「誰でもここに入れるのですか」
「いや、部屋には鍵がかかっています。ただ、建物には入れないことはないでしょうけど、遺骨を盗むような人はいないでしょう、周りの遺骨は荒らされた様子がありません、それにこの場所はあまり知られていない、何処にどのような遺骨があるか分かりませんよ」
という返答であった。
「その係官は親切にもこの件を調べて連絡してくれることになった。だいぶ経ってからだけど電話がきてね、かなり昔に一度この箱の件で身内かもしれないと見に来た人がいたが、その時は箱そのものが見つからなかったということが記録されていたそうだ。身内というのはきっと依頼人だろう、その係官が言うには箱はその時もあったのだと思うが、案内した人間が違う部屋に間違って案内して、箱がなくなっていると思ったのではないか、と言っていた」
「だけど、もしそれが本当に北京原人の骨ならば、盗んだのがいるわけですから、ミステリーらしくなってきましたね」
逢手が興味を持ち始めたようだ。
「どうして、箱だけ残したのかしら」
「気がつかれないようにじゃないかな」
「確かにそうだな、その箱に北京原人の骨が入っていたと仮定して、もう少し合同庁舎に探りをいれようや、吉都君たのもうかな、交通費や昼食代は出せるから、十分に動いてほしいんだ」
彼はうなずいた。
一方、北京原人の詳細な資料が必要である。これは図書館に勤めていた逢手に向いている仕事だろう。
「逢手君は北京原人の資料と頭骨のクリアーな写真があれば手に入れてくれないかな、見つけても本物かどうか判定できなきゃしょうがないしね」
「はい、任せてください、そういうことは得意です」
彼女は腕まくりをしてもう外に出る準備をしている。
「いや、今日じゃなくて、明日からでいいよ、専門書も最低限のものは買ってくれよ、費用はあるから」
そういうことで、吉都が合同庁舎から消えた北京原人の行方を追い、逢手は北京原人の資料集めを始めることになった。
次の日から、調査費用を現金で渡すと、二人とも驚いて飛び出して行った。領収書は要らないと言ったからだ。
二人は探偵事務所を出たり入ったりするようになった。大きな進展があると三人で意見交換をした。
逢手は科学博物館の研究者と会って北京原人について調べてきたり、本屋から詐貸には理解できないような専門書を取り寄せたりしている。中国の本を読んでいるのを見た詐貸はびっくりして、「中国語が出来るの」と聞くと、逢手は「ちょっとだけですけど、あと英語とハンガリー語」と笑った。いったいこの娘は何者だろう。
三人が顔を合わせたときに逢手が北京原人の講義をしてくれた。
「1920年代に周口店で掘り出された北京原人の骨は十数体あるんですよ、完全な頭蓋骨も数個あったようですけど、ミステリーの材料にもなるように戦争の混乱により紛失しているんです、その前に研究者が骨についてはかなり詳しい調査をしているのですが、現在完全な頭蓋骨はありません。ということは調査を依頼してきた人の言うように、北京原人の骨が何かに混じって存在していることは否定できないようです、写真もあります、全部ファイルしておきます」
話し終えた野霧はアイスクリームを食べはじめた。
「依頼人はなぜ北京原人の頭骨を探しているのですか、研究のためというわけではなさそうですね」
「俺もきいたんだが、欲しいんだただそれだけだよ、としか言わないんだ」
「歴史好きか単なる骸骨集めなのか」
詐貸にも依頼人の目的ははっきりつかめていない。
吉都も遺骨の霊安室のことを色々聞いてきた。
「最近あの部屋は掃除のとき意外は開けておらず、誰かが侵入した形跡もないということですよ、掃除は年に一度ほど業者が一斉に入っているということです。毎日掃除をするような場所ではないですね」
「まあそうだな、とすると、あの部屋に清掃会社の人が入ったということだね」
「そうです、清掃に入った人を知ろうと思って、掃除の会社を当たりました。会社はすぐ分かりましたので行ってみました。かなり大手の会社なのですが、さらに下請けに出しています。合同庁舎を担当している下請け会社にも行ってみました。
下町の小さな会社でした。卒業研究で清掃会社について調べている学生だと言って、仕組みを聞いてきました。親会社から一月の予定が入り、それぞれの日に何人必要か分かると、前もって労働者を確保する場合もあるし、日雇いをその日に探すこともあるということでした。
担当した主任者は下請け会社の社員で、実際に働く人はその日限りの人もいます。暮れの一斉掃除の日にその部屋を掃除した人間を特定するのはとても難しいと思います。
記録を見せてもらいました。掃除に行った人間の数と主任の名前はしっかりと書かれていましたし、働いた人の苗字だけはありました。しかし誰がどの部屋を掃除したということまでは記録にありません」
「ということは、逆に誰でもうまく雇ってもらえれば、骨のあった部屋に入れたということだね」
「はい、その通りです」
やはり、清掃員になって北京原人の骨を盗んだ人間がいるのだろうか。
詐貸はそのような状況を依頼人の跡出馬盛に報告した。
お岩さんと外骨の墓
そのような時に、向にある妙行寺のお岩さんの墓碑が動かされたという、奇妙な事件が起きた。
「先生、さっき妙行寺に行ったら、墓守の爺さんが面白いことを言っていました。お岩さんの墓を誰かがいじったようです」
吉都は昼休みに縁のある妙行寺に時々散歩に行く。気分転換のつもりらしい。今日は事務所に出る前に寄ってきたようだ。
「何でお岩さんの墓を動かすのだろうね、祟りが怖いと思わないのかね」
「そうですね、一週間ほど前の朝、墓守さんがいつものように掃除をしていたら、お岩さんの墓がいつもと違って見えたそうです、それでそばに行って見ると、ほんの少しだが、石段の上の塔がずれていたそうです」
お岩さんの墓の石段の上には小さい五輪塔が建っている。
「しかし、他はどうにもなっていなかったので、墓守の老人は反対側にある新しい田宮家の墓を調べたのですが、やはり墓石を動かしたような跡があったということです。何の目的だろうかねと、私に尋ねたのです」
お岩さんは田宮家の娘で実在の人物である。あの四谷怪談で有名な伊右衛門は婿として田宮家にはいった。
「どうして墓守の老人は君にそんなことを言ったのだろう」
「以前話をしたときに、そこの探偵事務所に勤めていると言ったことがあるからだと思います」
「あ、そうか、それでお岩さんと田宮家以外の墓はどうだった」
「どうもなっていなかったということです」
「それで寺ではどうしたの」
「道の道路の工事をしていたので、その振動だったのではないかということになったようです、確かにマンホールのところで下水か何かの工事をしていました。その後何も起きていないので、どこにも報告しなかったと言っていました」
「まさか、お岩さんの墓を掘ろうとしたのではないだろうね」
「ええ、僕もそう思ってちょっと調べました。あのお寺はその昔四谷界隈にあったのですが、明治42年にここに移ったそうです、お岩さんが亡くなったとされるのが1636年の3月29日です。その頃は土葬だった考えられますが、それらの骨を巣鴨に移したかどうか分かりませんでした。立派なお寺ですから、きちんと移したのだろうと思いますが、もともと墓に骨が無い可能性もあります」
「ちょっと気になるけどね」
吉都が話し終えたところに電話が鳴った。
詐貸が受話器をとると依頼主である。東京の染井霊園に墓のある宮武外骨の骨が盗まれたらしいので調べてみてくれというものだった。どうしてかと詐貸が尋ねると、がいこつだからね、と訳の分からない返事だった。別に費用を出すから頼むといわれて断ることも無いと詐貸は引き受けた。
染井霊園は都の霊園で庚申塚探偵事務所から歩いていける。巣鴨から西巣鴨の方に白山通りを歩いて十数分ほどのところにある。
「染井霊園で事件だよ」
電話を受けた詐貸はデスクでPCを眺めながらアイスクリームを食べていた逢手に声をかけた。
「あら、何が起きたのです、殺人ですか」
どうも逢手は探偵小説の読みすぎのようだ。
「いや、墓から骨が持ち去られたらしいということだ」
「あそこは有名人がたくさん眠っていますから誰の墓でしょうね、高村光雲、光太郎、知恵子、作家だと二葉亭四迷、歌の水原秋桜子、岡倉天心、水戸徳川家の墓もありますね、どなたです」
「よく知ってるね」
「ええ、図書館で働いている時に、東京都の墓地についてはいろいろ調べたことがあるんです」
「今逢手君があげた人の墓じゃないよ」
「あれ、他に誰でしょう、政治家ですか」
「いや、宮武外骨」
「ああそういえば、宮武外骨の墓がありましたね、あの人自分の墓は作らないって言ってた人なんですけどね」
「そうなの、僕は始めて聞く人なので知らないんだ」
どうもそういった知識が弱い。
「おかしな人ですよ、反政治家の新聞をだしていた反骨のジャーナリストです、何度か捕まっているでしょう」
「何で捕まったの」
「新聞をだして政府をおちょくってましたから侮辱罪、滑稽新聞ていうんですよ」
確かに名前からして面白そうだ。
「宮武のことを知るにはどの本を読んだらいいだろう」
「赤瀬川源平の学術小説―外骨という人がいた、でしょう」
「変なタイトルだな、それじゃ、その本、買ってきて」
「あたし持ってますよ、明日持ってきましょうか」
「うん、今日は一緒に染井霊園に行ってくれる」
逢手が頷いた。それを聞いた吉都も行きたそうな顔をした。
「吉都はもう少し清掃会社を調べてくれる」
「はい」吉都はしょうがないかとザックを背負うと出て行った。
逢手野霧は笑窪を寄せて巨体を持ち上げた。外に出られるのが嬉しいのだ。
染井霊園に歩いていく途中で逢手が聞いた。
「先生、依頼主は染井霊園ですか」
「いや、北京原人の依頼主だ」
「どうしてでしょうね、北京原人はいいとしても、宮武外骨の骨を捜そうとするのは分かりません」
「依頼主が言うには、同じがいこつだからなんて冗談を言っていたけど、よく聞いたら同じ犯人の可能性もあると思ったようだ、北京原人の捜索が滞っているので、何とかヒントにならないかと考えたのだろう、なかなかいいところをついているのかもしれないな」
「でも不思議な依頼主ですね、どこから外骨の墓が荒らされたことを聞いたのでしょうね」
「それは尋ねなかったな」
聞いておくべきだったかもしれない。
染井霊園のあたりにはソメイヨシノがたくさん植わっている。春先はみごとである。
霊園の管理室で「宮武外骨の墓はどこでしょう」と詐貸が尋ねると、管理人のおじさんは「イ3号21側、ここですよ」と墓の地図を示した。
「墓はどうなってますか」という問いに、
「たまに宮武さんの信奉者がみえて、きれいになっていますよ」と詐貸が考えていたこととは違う答が返ってきた。骨が盗まれたのなら掘り返したりされているはずだから、なぜ訪ねてきたか聞くだろう。
詐貸は不思議そうな顔をして管理人に何か言おうとした逢手を制して、
「ありがとうございます、行ってみます」とお辞儀をして管理室を出た。
「どうしたんです、骨のことは聞かないのですか」
「うん、どうも管理人は知らないようだよ、何かあるね、まず行ってみよう」
そこは竹の柵に囲まれたあまり広くない墓地で、宮武外骨の墓とあった。墓石は面白い形にそがれた石である。
「盗まれた様子はありませんね、依頼された方は勘違いされたのではないですか」
確かに逢手の言う通り墓石は動かされた跡がない。腕を組んで墓石を見ていた詐貸がふと自分の足もとを見た。自分の立っているところだけが土の様子が違う。最近埋められたような感じである。足跡もいくつかある。
「逢手君、足元の土をみてごらん」
「ええ」きょろきょろと見回していた逢手にもわかったようである。
「ここ掘ったんですか、穴が小さくありませんか、これでは手が入る程度ですよ、盗めたにしても時間がかかったでしょう」と大きな声を出した。
「たしかにね、これでは盗めないかもね、霊園の人は気が付かないほどだものね、とするとなぜ依頼主は外骨の骨が盗まれたことを知ったのだろうか」
「先生、霊園に聞いてみたらどうでしょう」
「いや、止めておこう、警察に聞かれたりすると、依頼人の名前を言うはめになる、依頼人は他人に名前を絶対に言わないようにとのことだ」
「吉都君がお岩さんのお墓のある近くでマンホール工事していたって言ってましたね、お岩さんの骨はマンホールから掘っていって盗まれているのかもしれませんけど、ここは他から掘るところはありませんね」
詐貸はうなずいた。
「依頼人には染井霊園に行ったけど外骨の墓はなんともなかったと言っておく、ただ墓の前の土の状態がおかしかったと言うよ」
次の日逢手が持ってきてくれた「学術小説―外骨という人がいた!」を読んだ。フランス文学専門の出版社である白水社から1985年に出ている。
確かに面白い、書き方がうまいせいもあるが、ともかく外骨の一生そのものが面白いわけである。宮武外骨は本名亀四郎で反骨の編集者、ジャーナリストである。自分の本名に入っている亀は外が骨ということで、外骨という名で文を書いていたが、それを気に入って改名し本名にしてしまったという。とぼねとも読ませたらしい。
滑稽新聞という、えも言われぬ奇妙な新聞を発行していて、政府の要人をおちょくり、何度も発売禁止になり、数度侮辱罪で逮捕されたが、それでも最後には東京大学に教員として勤め、彼の集めた膨大な明治大正の新聞資料が明治文庫に所蔵されている。東大も実に寛大だ、というより外骨の類をみない能力なのだろう。
「面白いね、この本」
「外骨さんが面白いのよね、私、ふと思ったの、この人、墓に反対していて自分の死体を売りに出し、医者の教育のための骨格標本にして欲しいと思っていたということなの。それなのに墓に入ったのはどうしかしら」
逢手が言ったことで詐貸ははっとした。
「逢手君、墓にはもともと外骨の骨はなかった可能性が考えられるね」
「先生、それは彼の骨はどこかに骨格標本としてあったということですか」
「うん、それが盗まれたのかもしれないな」
「依頼人の人は墓を捜せといったのですか」
「いや、宮武外骨の骨が盗まれた、墓は染井霊園にあると言っただけだ、それで染井霊園の墓の骨が盗まれたと思ったんだ、知識の無い俺の早とちりかもしれない」
「でもなぜ依頼人はそんな言い方をしたんでしょう」
「どうしてかな、電話で確認してみるよ、それにお岩さんの件も何か知っているか、ちょっと鎌を掛けてみよう」
詐貸はすぐに電話をかけた。彼は依頼主とたびたび相槌を打ちながらかなり長い間話をしていた。
受話器をおいた詐貸は浮かない顔を逢手に向けた。
「まずお岩さんの墓の件は何も知らないと言っていた、どうして宮武外骨の骨が盗まれたと思ったのかと聞いたら、電話の向こうで笑って、『さすがですね』と言うんだ、それから『ある私立医大の解剖学教室で骨格標本の頭の骨だけ盗まれたのを私のかかりつけの医者から聞きましてね、その医者は前々からその標本が宮武外骨ではないかという噂があることを教えてくれました。盗んだ人はもしかすると外骨に傾倒する人で、骨を霊園に戻すべきだと考えている可能性を思いましてね、それで詐貸さんに頼んだというわけです、詐貸さんが染井霊園の外骨の墓の前が掘られているかもしれないとおっしゃったんで、もしかすると骨が戻っているかもしれませんね』ということだったよ」
「それじゃ、あの掘った跡は骨を戻すためのものだったわけですか、しかし北京原人の骨の捜索とは関係がありませんね」
「そうなんだ、別に費用を出すとまで言っているのだから、何かあるのだろうけど、そこは何も言わないね」
「我々のことを試しているのか遊んでいるのと違うでしょうね、もしかすると依頼人の目的は北京原人の骨を探すだけではないのかもしれない」
逢手の推測は正しいかもしれない。
「うーん、何か隠しているような気がする」
「お金を払ってくださっているのなら、いいんじゃないですか、何でも調べますよ」
逢手野霧はまたアイスクリームを食べている。
「依頼人は何をしている人なのですか、教えてくださいよ、他には言いませんから」
「資産家であるらしい、代々中国の薬を扱っていて、今では漢方がはやっているが、その火付け役のような薬会社をやっていたようだ」
「過去形なのですか、もうやっていないわけですね」
「そうなんだ、資産を食い潰しているのだろうが、この調査に君たちの給料の費用の他に、前金として一千万もってきた。信じられないだろう」
逢手もその金額を聞いてアイスクリームを舐める舌を引っ込めた。
そこへ吉都が出勤して来た。
「遅くなりました」
特に何時に出勤しろと言ってないが、一応十時始まりである。いろいろ走り回っているが何も出てこないので、彼もどうやら嫌気が差してきたようだ。浮かない顔をしている。
「清掃会社の帳簿なんていい加減ですね、原簿を見せてもらったんですけど、結局どこの誰が働いているのかほとんど分かりません、あんなにいい加減だから文科省の入札を勝ち取ることができるのですね」
「どういうこと、可也ちゃん」
逢手は吉都のことを可也ちゃんと呼ぶ。
「人を安く雇っているってこと、まともな給料じゃなくても働く人はいますからね、だから安く落札できるんだ」
「でもそういうの、役人にばれたら入札できなくなるでしょう」
「そこは、袖の下でも渡しているんじゃないのですか」
詐貸は二人の会話を聞いていてふと思った。
「いや、袖の下などより、もっと上のほうで何かが働いているのかも知れないな」
「僕もそう思って、下請けの会社組織そのものを調べたんです」
可也もなかなか先を読める。
「なにかでてきたの」
吉都はうなずいた。
「あの会社は三年前に作られた個人会社で、二年前から合同庁舎を担当しています。奇妙なことに、大した仕事を受注していないのに、つぶれないで何とかやっているんです」
「本当に清掃会社かね」
「清掃をやらせていることは事実です」
「社長という人は誰なの」
逢手がお菓子を食べようとしていた手を止めた。
「鈴木という人です、その人に会うことができました、自分も清掃会社を作ってみたいので、色々な清掃会社の社長に会って苦労話を聞いている、鈴木さんはどのようなことに苦労されましたかと尋ねました」
「ほう、それでどんなことを話してくれたの」
「それがおかしなことに、その鈴木という社長が言うには、自分は雇われ社長で、名前だけだよ、と言って笑っていました。儲けは無いから清掃会社なんてやめたほうがいいよって言ってました。そんな話をしている時、『社長、あとでまもるさんから電話です受話器とってください』と事務の女性が鈴木さんに声をかけました。鈴木さんはちょっと失礼と近くの電話の受話器をとるとなにやら話をしていて、終わると出資者からの電話でね、その人のお陰で会社ももってますよ、などと言っていました」
それを聞いた詐貸は棒立ちになった。
「吉都、何て言った、あとでまもる、と言ったのか」
「ええ、先生知ってますか」
「依頼主と同じな名前だ、漢字はどう書くの」
一瞬みなだまってしまった。
「話で聞いただけでどう書くかわかりません」
「珍しい名前だから、同じ可能性は高いね」
「依頼人はいくつぐらいの人です」
「俺も会っていないのではっきりは分からないが若くは無い、爺さん声だ。いきなり電話依頼してきた。金をだすから頼むということだった、危ないことをやっている人では困ると思い、一端は断ったのだが、何度か話をして、北京原人を探すということで危険なことではないのですと言っていた。趣味が高じて是非探したいということだった、代理人にお金をもたせて契約するからということで引き受けた、それでみなを雇うことにしたというわけなんだ」
「代理人ってどのような人だったのです」
「品のいい年のいった女性だったよ、風呂敷のなかに一千万円はいっていた」
「名刺とかそういうものを置いては行かなかったのですか」
「うん、無いね、一千万の受け取りがいるかといったら、契約書に書いてあれば、いらないと言ったけど受領書だけは渡した、あとで問題になるといけないから」
「受け取りがいらないとは奇妙ですね、それにその清掃会社の出資者だとしたら、自分でも直接北京原人を探そうとしようとしていたのでしょうか、それで箱の中に何もないことを知って、誰かが盗んだと思って先生に依頼したとか」
「それだと、わざわざ清掃会社を使う必要が無いのじゃないかな、俺みたいに遺族の顔をして探すこともできる」
「そうですね」
「依頼人の跡出馬盛さんはどこに住んでいるのですか」
「福岡の八女だと思ったな、ただよく東京に出てきていてホテルに滞在することがあるので東京はだいたい分かりますと言っていた」
「ずい分遠くですね、そんな人が東京の小さな個人会社にお金を出しているとしたらやはりなにか目的がありますね」
「依頼人のことも調べなければならないな」
「それにしても、依頼人はどうして先生の事務所を選んだのでしょう」
逢手はなかなか鋭い。詐貸はうかつにもそれを考えてみたことがなかった。
「探すのがうまいか、俺に金がなかったからかな」
「お金がなかったということだけではないと思います。それにお金がないということを調べたとしたら、もっと詳しく調べたと思います」
確かにその通りである。
「その清掃会社と同じでこの事務所をのっとろうとしたのですね、個人でやっている小さなところ」
逢手ははっきりと物を言う。俺より洞察力がありそうだとちょっと舌をまいた。
「まあ、のっとられてはいないが、いや同じようなものかな」
「先生、それでも骨のことを知らない先生を選んだのはどうしてでしょうね」
詐貸は笑って答えた。
「これでも探し物は得意でね、今まで頼まれたことは百パーセント解決してきたんだ、ややこしいものもあったけどなんとかなったよ」
「あれ、ごめんなさい」
逢手は笑い顔になった。
「ただ、俺の顔は狭くてね、普通の探偵なら広くてねというところだろうけど、そうしないと探偵は成り立たないからね、俺は自分で考えて一人でやってきたというところが他の探偵事務所と違うだろうね、警察なんてほとんど行ったことはないし、知り合いはいないね、いや大学の同級生で警察に勤めたのはいるけど、全くコンタクトとったことはないよ、そういった孤独の探偵事務所はあまりないかもしれないな」
「どこの大学です」
詐貸が答えると逢手は、
「やっぱり、そこになにかありそう」と言った。
「どうして」
「あの大学は卒業生はたくさんいるし、左翼も右翼も、俳優もホームレスも、いろんな人が活躍している、メディアなんてあの大学の卒業生が良くも悪くもしてるみたい、きっと依頼人も先生の大学時代を知っている人よ」
まさかとは思うが。
「先生サークルは何に入っていたんです」
「ミステリーだよ」
「やっぱり、私もミステリー」
「どこの大学、まさか同じじゃないよね」。
雇った時、彼女から履歴書はもらったが、職歴しか気にせず、学歴を見落としている。興味がないせいもあった。
「東大」
詐貸も吉都もぎょっとなって目をむき出した
ちょっと間があって詐貸が逢手を見た。肉まんより可愛くずーっと怖く見えてきた。
「それでどこからか誰かが俺を見ていたというわけかい」
「学生部、またはサークルの部長の知り合い、部長さんはどんな人だったのです」
「文学部の女性の先生だったな」
「きっと魅力的な人だったんでしょ」
「ちょっと日本人離れはしていたけどね、俺はあまり好きな顔じゃなかったな、ほとんど話をしたことがないよ、俺は法学部だったからな、彼女は文学部でアメリカ文学の教授だ、ほらアメリカのテレビドラマシリーズにボーンズってのあるだろ、その主人公にちょっと似ていたな」
「ああ、あの女優さん、ずけずけ物を言う形質人類学者、自分が一番と言っている人ね、あの顔シャレコウベに似ているわ」
「うーん、確かに頭蓋骨に似てなくもないけど、それとこれとは違うね」
「すみません、頭蓋骨探しなのでつい」
吉都も笑い出した。
「でも、逢手さんが言ったこと、調べてみる価値ありませんか、そのうち僕がやりますよ」
吉都が興味を持ったようだ。勝手にさせとこう。
その日昼の休憩から戻った吉都が「大変です先生」と事務所に入ってきた。
「お岩さんの墓が崩れました」
また妙行寺に行っていたようだ。
「どういうこと」
逢手が顔を上げて吉都を見た。
「寺の前に、お岩さんのお墓はしばらく工事のため見ることができません、と張り紙があったので、墓守の爺さんを探したら、お岩さんの墓のところで石屋の作業を見ていたんです。どうしたのか聞いたら、お岩さんの墓が傾いて倒れてしまったということです」
「原因はお岩さんの呪いじゃあないでしょうね」
逢手が興味津々である。
「それが、墓守の爺さんもそんなことを言うので、そんなことはないでしょうと僕も言ったのです」
「それでどうだったの」
「墓の下が穴になって陥没した可能性があるようです、それで、お岩さんの死体、いや骨が抜け出したのではないかと爺さんは怖がっていました」
「それ穴が掘られたんじゃないの、マンホールの工事やってたじゃない」
逢手は良く覚えている。
「とすると、お岩さんの骨を盗んだやつがいるかもしれないな」
吉都も気が付いたようで神妙な顔になった。
「宮武外骨の骨、それにお岩さんの骨、北京原人の骨、どんな繋がりがあるのだろう、だけど北京原人の依頼が来て以来、急にこのようなことが起こり始めた」
一瞬三人はだまったままになった。
「骨を集めている、ボーンコレクターっていう映画があったけど、あれは殺人鬼だけど、このボーンコレクターは有名人の亡くなった方の骨を集めているわ」
逢手が言った。
「まだ結論は早いが、その可能性もある、しかし有名人の骨を集めているとすると、北京原人はちょっと範疇からずれるな」
詐貸が言うと,逢手は「第四の犯行を待ちましょう」と、ミステリー好きらしい結論をだした。殺人じゃないから平気な顔で言える台詞である。
もう一つの謎があった。依頼人のことである。詐貸は依頼人に会いたいと思う。大きな進展でもあれば直接会いたいと言えるが、今の状態では言えない。ただ清掃会社の件を持ち出して会う手もあるだろう。
ミステリーサークル
吉都は詐貸の卒業した大学に入り込んで、色々聞き込んできた。可也は調査がなかなかうまい、演劇をやっていただけあって、成りすますのが上手のようだ。事務所でその結果を読み上げた。
「詐貸先生は大学2年の時に司法試験に合格」
それを聞いた逢手が「ひゃあ」と言った。
「だけど、大学は中退」
また「ひゃあ」と言った。
「その原因はミステリーサークルにあり」
それを聞いていた詐貸は「まるで俺の素行調査じゃないか」と顔をしかめた。
「そうです、先生の素行が解決の要かもしれません」
「それからどうなったの、続けて、可也ちゃん」
逢手が先を言えと吉都を見る。肉饅が少し皺の少ない餡饅になる。
「先生がミステリーサークルの彼女、Aさんとしておきます、に振られる、彼女は大学をやめてしまう、それでやけを起して酒びたり、それで先生も大学をやめた、しかし資格はとったのに弁護士や検事さん、裁判官にはならず、バーテンのアルバイトをする傍ら探偵事務所を開く、そこまでは正しいでしょうか」
詐貸は苦笑しながら頷いた。少し前までバーでシェーカーを降りながら探偵をやっていた。
「さて、その先生を振った彼女Aさんを見張っていたのは、文学部米文学の西条やそみ教授、ミステリーサークルの部長」
「そんなこと良く調べたな、誰に聞いたたんだ」
「先生に聞いても教えてくれなかったでしょう、今のサークルの学生に話をきいて、OB,OGをたよりながら、Aさんの友人にたどりついたわけです。その友人Bさんに電話で話を聞きました」
確かにAにはBという友達がいた。
「それで教授が俺を見張っていたってなんなんだ、俺も知らなかったよ」
「Aさんはある血筋の大事なお嬢さんだったようですね、あのAさんには親の決めた婿がいたのです、詐貸先生のことを報告して欲しいと、西条やそみ教授が大学の理事の一人から頼まれたのです」
「ほう、それは誰から聞いたの」
「やっぱりBさんです、Aさんから相談をされていたということです、Aさんが先生になびきそうになったとき、Aさんは大学を辞めさせられました。先生の動きは西条先生に監視されていたのです」
「あら、詐貸先生、振られたのじゃなかったのね、早とちりで大学辞めて損をしたじゃない」
詐貸は逢手を睨みつけてやった。
「まだあるんです、西条やそみ教授は理事のその人と結婚をして、アメリカの大学で研究をされています」
「あの教授はその頃四十ちょっと前で子供がいたのじゃないかな」
「はい、家庭を捨ててその理事と一緒になりました、理事も家庭を捨てて教授と一緒になったのです」
「だけど、まだ依頼人にたどり着かないわね」
逢手はチョコレートを食べ始めた。
「理事は誰かから相当のお金をもらったようです、それでいつも西条教授を高級レストランに誘い、Aさんの監視を頼み報告を受けていたと思われます。西条教授に金を払っていたのがAさんの親族のようで、先生のことも逐一Aさんの親族に伝わっていたと思われます。何しろ学生で司法試験合格ですからね、Aさんがもっていかれるのかと気が気じゃなかったでしょうね、先生残念でした」
吉都のやつ軽く言いやがってと、詐貸はやっぱり睨み付けた。
「Aさんの親族と今回の依頼主とつながりがあるかもしれませんね」
「それで、彼女の親族について調べたのかい」
「今回はそこまで時間がありませんでした。これから調べます」
「彼女はどうしてる」
「あら、先生まだ惚れてるの」
まったく、逢手はうるさい。
「親族については彼女に聞けば早いだろう」
「ついでに、元の鞘に収まろうということ」
このどてかぼちゃ、にやにやしている。
「Aさんとは私がコンタクトとるわ、女性の方がいいでしょう、先生、写真あるでしょ、先生がいきなりAさんと会うと何が起こるかわからないわ、依頼人が先生のこと監視していてよ」
言っていることが正しいから困ったもんだ。
「明日持ってくる、サークル活動の時の写真があると思う」
詐貸はしぶしぶ言った。
「あら、Aさんすごい美人、先生もなかなか格好良かったじゃん、髪長くしていて、眼がちょっと小さいけどアランドロン系ね」
もってきた写真を見た逢手が大声を上げた。
アランドロン系ってのはなんなんだ。アンドロイドみたいだ。今も格好良く生きているつもりだ。
彼女がそんなお嬢さんだとは全く知らなかった。その頃、父親はある会社に勤めているサラリーマンだと言っていた。
「名前はなんとおっしゃるんです」
「夢(む)久(く)愛子さん、夢に久しいでむく」
詐貸ではなく吉都が答えた。
「夢野久作を縮めたような苗字、珍しいですね」
確かにあまりないだろう。
「依頼人の苗字と違いまね、依頼人は跡出馬盛と言う人でしょう」
「うん」
「それじゃ、私、愛子さんに直接会ってみます」
「これ、夢久愛子さんの住所、当時のままです」
「可也君、なかなかの探偵じゃない、これだけ分かればすぐすむわ、先生行っていいですか」
「ああ、よろしく頼む」
逢手はからだに似合わず、電話もかけずに、あっというまに支度をして出て行ってしまった。きっとどこかでアイスクリームでも食べながら電話するのだろう。
「それにしてもよく調べたね」
詐貸は吉都に言うと、吉都は笑いながら、
「先生も逢手さんも気がつきませんでしたね、逢手さんは愛子さんに会うでしょう、それで驚くと思いますよ」
なんだろう。詐貸は吉都の持って回った言い方に不思議な顔をした。
「夢久愛子さんのその当時の住所と言ったでしょう、そのままなんです。結婚した愛子さんは元の姓に戻っているんです」
これには詐貸もさすがに驚いた。
「別れたんだ、彼女」
「はい、先生、結婚は五年で解消です」
しかし詐貸は浮かない顔をした。
「きっと、詳しいことは逢手さんが報告してくれますよ、僕は夢久さんと跡出さんの関係を調べます」
「そうだな、ただ、跡出を調べだすのは大変だろうと思うよ、きっと表には出てきていない人だと思う、表に出ている総理大臣より、その後ろにもっと力がある人がたくさんいるものだ」
「そうでしょうね」
あくる日、逢手は急用ができたので休ませて欲しいと言ってきた。その次の日の朝、事務所に入ってくると逢手が「昨日は急に休んですみません、母が白内障の手術を受けに行ったものですから」と昨日来なかったことを説明した。
「逢手君はお母さんと住んでいるの」
逢手は京王線の笹塚からかよっている。
「はい、父は亡くなって、姉は北海道にいますので、私が一緒に住んでいます。白内障の手術は一日入院の予定だったのが、日帰りになるという連絡がはいって、やっぱり付き添いが必要で、昨日は面倒みていました」
「そうだったのか言ってくれればいいのに、もういいの」
「もう、とても良く見えるようになっちゃったって、アイスクリーム食べています、今まで病気一つしない人です」
親子そろってアイスクリームだ。
「そう、それなら良かった、それで、愛子との話どうだった」
「おととい、あれから電話をしたら、会って下さることになって、午後にお宅にお邪魔しました、愛子さん驚いたことに、ご主人とは離婚されていました」
「うん、吉都君にきいたよ」
「あら、可也ちゃん知っていて言わなかったわね」
「いや、ごめん、言う前に逢手さん事務所を飛び出しちゃったから、でも夢久愛子さんて言ったでしょ」
「あら、そうだったわね、そこで気付くべきだったか、ミステリーサークル出身者としては落第だな、愛子さんの離婚前の名前は水(みず)良(ら)でした、ご主人だった人は水良佐里(さり)雄(お)さんです」
「どこの人なのだろうね」
「そこのところはまだ聞きませんでしたけど、おそらく夢久家のある富山だと思います。幼馴染のような感じでした。ともかく愛子さんは快くいろいろ話をしてくださいました」
「会う目的は何て言ったんだい」
「詐貸探偵事務所の調査員とはっきり言いました、それで先生が依頼されたことと愛子さんと関係があるかもしれないと思いうかがったと言いました。すると、あら大学の時の詐貸君かしら、とおっしゃったのでそうだと言いましたら、お元気かしらとおっしゃったので、現状をお話ししました」
「それで、跡出馬盛と名前を出したの」
「いいえ、それは言いませんでした。北京原人の頭骨を捜しているとは言いましたそうしたら、あら北京原人、面白いわね、でもなんで私と関係あるのかしら、もしかすると祖父が北京にいたからかな、とおっしゃいました」
「今彼女はなにしてるの」
詐貸はやはり気になるようだ。
「今は翻訳の仕事をなさっています、ペンネームは塔晶子、まだ三冊しか出していませんが、みな北欧のミステリーです、私も大学時代、ミステリーサークルに入っていたと言ったら、話が弾んでかなり長く探偵本のお話をしました、愛子さんの訳された本買ってきました」
野霧が単行本を三冊机の上に置いた。
彼女は翻訳ものをきらっていたのだが、どうしたのだろう。ペンネームは分かりすぎるほど分かる。塔晶夫からつけたのだろう。塔晶夫は日本の探偵小説界の三大奇書、虚無への供物の著者であり、後に名を中井英夫として幻想小説をたくさん書いている。彼女は中井の信奉者であった。
「翻訳だけでやっていけるのかな」
「お忘れですか、億万長者のお嬢さんですよ、お父様もお金はあったようだけど、そのお兄さんの夢久哉(かな)有(う)は富山で薬会社をやっていて億万長者です、しかもその父親、愛子さんのおじいさん夢久十(とう)も北京で薬の商売をやっていて大もうけした方です。」
「北京とつながりがあるし、関係がありそうだな」
「北京原人の骨を削って、薬にして儲けたというわけじゃないですよね」
逢手が面白いところをついてきた。
「どうだろうね、ミイラや一角獣の角のようなことはしないだろう」
ミイラも一角獣の角もみな中国では薬にしたようである。
「そういえば、依頼主の跡出馬盛も漢方で大儲けした人だと先生がおっしゃってましたね」
吉都が詐貸に聞いた。
「うん、夢久哉有と跡出馬盛の関係が分かると何かが見えるかもしれないね」
「愛子さんのお父さん、夢久多助は、収集家で根付を集めていたようですね、象牙や骨でできていたのが好きだったみたい、お父さんの血筋には収集癖があって、おじいさんは世界中の貝、特に宝貝を集めていたそうです、だけどおじいさんはそのコレクションを海外の人にオークションで売ってしまったそうです、なんでも相当な価値のものだったらしい、ということは、お父さんのお兄さんの夢久哉有も何か集めていたのか聞きました。何かを集めていたということは知っているけど、愛子さんには何を集めているのか言ってくれなかったということです、愛子さんの父親も兄が何を集めているか知らなかったようだと言っていました」
「それはなんだろうね、北京原人の骨が関係してくるのかな、とすれば、依頼人と夢久家とかなりつながりがありそうだよね、とすると愛子も関係があるかもしれない」
「そうですね、私の勘ではやっぱり愛子さんとはコンタクトとって、もっと話を聞いたほうがいいと思います、夢久家はものを集める癖をお持ちのようですね、依頼人もやっぱり収集癖があるのではないですか」
「そうだね、また会ってみてよ」
「僕のほうは跡出馬盛を調べてみたけど、何も出てきませんでした、先生にお聞きした電話番号は闇の電話取次業のものでした。そこにかけると、受付嬢からあるところに電話がつながる、それが本当の依頼人の電話番号ということになります。依頼人に電話をすると、必ず電話取次業の電話番号を介して相手の電話にかかるような仕組みです」
「たしかにそういうのがあるね」
「それで、漢方薬を作っていたもうなくなっている古い会社を調べたら、ずい分ありました。夢久十の会社もありました。しかし、跡出馬盛はでてきませんでした」
「夢久十の会社は何ていうの」
詐貸が聞くと逢手が答えた。
「北京骨商」
「何で知ってるの」
「愛子さんがちょっと言っていました、叔父の夢久哉有の作った新しい会社も同じ名前の北京骨商です、今もあります、愛子さんのお父さんは兄の哉有さんとはずい分年が離れていて、十八も違っていたんですって、愛子さんのお父さんは、哉有さんの会社には入らず、兄がだしてくれた元手で会社を起し、それも当たって世界的なものになったそうです。愛子さんのお父さんも叔父さんの夢久哉有さんももうお亡くなりになり、いないそうです」
「そう亡くなっているの、哉有さんの北京骨商は誰かが社長になっているわけだね」
「そこまではお聞きしませんでした、調べれば分かると思います」
そこで、逢手がはっとしたように椅子から立ち上がった。
「いけない、私忘れていた。また愛子さんに会ってきます」
「どうしたんだい」
「愛子さんのご主人のことです、なぜ愛子さんは親の決めた許婚がいたのでしょうか、どうしてそのお婿さんじゃなければいけなかったんでしょうか」
「北京原人の骨とは関係ないね、あまり重要なことじゃないよ」
「なぜ離婚されたのかも聞く機会がなかったからこれから聞いてきます」
「そんなことはいいじゃないか、それよりも、叔父さんの作った新しい北京骨商について聞いたほうがいいんじゃないか、やっぱり漢方系なんだろう、今の社長のこととか、跡出と関係があるかもしれない」
「そうですね、吉都君、一緒に愛子さんのとこへ行ってくれる、二人だと聞き漏らすことも少なくなるから」
吉都も立ち上がった。
まさかこの事件が自分の身にかかわることになってくるとは思わなかった。詐貸も「たのむよ」と言ったのだがすぐに二人を呼び止めた。
「あわてないで、まず電話してからいけよ、それにおととい行ったばかりじゃないか」
逢手が戻ってきて自分の携帯で愛子の家に電話をした。
「そうですか、お帰りになったら、また連絡します」
逢手はそう言って電話を切った。いないようだ。
「先生、愛子さんのお母さんが電話に出ました。愛子さんはヨーロッパに昨日でたそうです、なんでもノールウェーの作家に会いに行くそうです」
「この間、その話はしなかったのかい」
「はい、愛子さんの予定のことは全く聞きませんでしたし、何もおっしゃらなかったので」
「いつ帰ってくるの」
「一週間後です」
「それならその後に行ったらいいじゃない、彼女に聞かなくても旦那だった人の名前も分かっているのだし、調べることもできるよ、なんなら、直接別れた旦那と会うこともできるよ」
「そうですね、そうします」
二人はデスクワークに戻った。
「前のご主人の勤め先や、仕事についてはこれから調べます」
「僕は跡出馬盛についてもっと探ってみます」
明くる日、詐貸がデスクで朝刊を読んでいると電話がかかって来た。跡出馬盛からである。たまにだが進展状況を聞いてくる。愛子の件はまだ伏せておいた方がいいだろう、むしろ跡出から本人について何か聞きだすほうがよいだろう
「今日はずい分早いですね、すみません私のほうは全くといって進展がなくて、あの清掃会社についても調べています。跡出さんのほうでなにか分かったことでもあるのでしょうか」
「いや、なにもないんだけどね、新聞を読んでいたら墓のことがあったから、詐貸さんのことを思い出して電話したんですよ」
「ご自宅からですか」
「ああ、そうだけどね、北京原人も外骨も骨を捜すのは骨が折れるね、誰かから北京原人のことなどの問い合わせはありませんでしたか」
本当に暇なようだ。駄洒落を飛ばしている。どこかで聞いたせりふだ。
「いいえありません、なかなか進まなくてすいません」
「いいですよ、ゆっくりやってください、詐貸さんならならきっと見つけますよ」
「もうお仕事をなさっているのですか」
「いや自宅でのんびりしてますよ、もう引退していますから」
清掃会社への出資は本人の指図なのだろうか。
「ところで、新聞はなにをとっています」
どうしてそのようなことを聞くのだろう
「朝日、読売、日経、産経です」
「どれもつまらん新聞でしょう、と言っても今私が見ているのも同じですけどね、内容はテレビニュースの後追いばかりでね、それで私はテレビに出ない三面記事の小さな報告記事を面白がっているというわけですよ」
「そうですか」
何を言いたいのだろうか。確かに小さなちょっとした記事からヒントをもらうことがある。わざわざ言うには新聞を見ろということかも知れない。
「事務所にはみなさんもう出勤ですか」
「ええ、一人は調べに出ていますけど」
「いやすみませんお邪魔しましたな、北京原人よろしくお願いしますよ」
跡出が電話を切りそうになったので言った。
「実は遺骨のしまわれている総合庁舎の掃除のことでちょっと進展がありました。小さな下請けの会社ですが、そこの出資者が漢字はわかりませんが、あとでまもるという人でした」
それを聞いていた跡出の声が一瞬途絶えた。
「え、私と同じ名前の者が関係しているんですか」
それで電話は切れた。自分はそのことを知らないといった様子であった。違うあとでまもるなのだろうか。
その日、調べから戻った可也が八女の住所に跡出馬盛はいないと報告してきた。
紫式部と小野小町の墓
詐貸は跡出が言った新聞の社会面を見た。すると目に止まった記事がある。
紫式部の墓が荒らされたというものであった。荒らされたといっても墓石が傷ついたり倒されたりしたのではなく、墓石に紫色のペンキで落書きされたというものであった。紫式部の墓は京都の北大路通りのある会社の敷地にある。その昔、その辺りは貴族の墓地であったようである。
気になった詐貸は逢手に紫式部のことを聞いた。やっぱり詐貸の苦手な領域である。
「紫式部は藤原の偉い人の娘ですよ、平安時代です、でもなぜ紫色のペンキで塗ったりしたのでしょうね」
「誰がどんな目的でやったかわかっていないのだけど、ちょっと気になったから」
逢手はPCをのぞいて詐貸に言った。
「紫式部は970年ごろに生まれて1031年ごろ死んだことになっていますね、はっきりしていないようです」
「源氏物語ぐらいしか頭に浮かばないけど、野霧君は読んだ」
「ミステリーの好きな人が、あんなの読まないでしょう、でもなんとなくは知ってますけどね、私は興味もっていませんでした、あたしには縁がないし」
つれない反応である。
「源氏物語が気に入らないからペンキ塗ったりしたのかな」
「どうでしょう」そういいながら逢手はPCを操作して何かを見つけた。
「紫式部の墓の近くに小野篁(たかむら)の墓がありますよ」
「それなに」
「歌を読む人だったけど、閻魔大王を補佐していた人です、それで私知っているんです、何人もの地獄に行った偉い人を甦らせているのです」
彼女は怪奇ものも好きなようだ。
「もっと面白いことがかいてありますよ、源氏物語は色物でもあるでしょう、そういう話はその当時ご法度だったようですね、だから紫式部は死んだら地獄に行ったと思われていたのじゃないかって」
「ほんとかね、平安時代でしょ、貴族の間じゃ通い婚なんて当たり前だったんじゃないかな、そんな時になぜ源氏物語はだめなんだろう」
「どうなんでしょうね、女が書いたからかも知れませんよ、その頃から男はセクハラやってたんだ」
確かにそうかも知れない。
「だけど、その小野のなんとかは紫式部のなんだったの」
「あ、いや、小野篁が活躍したのは式部より二世紀ほど前で、平安時代の初めの頃です、違う時期の人です」
「とすると、小野篁が幽霊になって紫式部を諫(いさ)めにでてきた」
「先生、なかなか小説家の資質ありますよ、源氏物語のファンが、紫式部が地獄にいるのじゃかわいそうなので、小野篁の墓を近くに持ってきて、地獄から救い出してもらおうとしたという、謂れがあるようですよ」
なんとまあわざとらしい説明だろうか。
「そんな勝手な解釈があるんだね、ファンの心理かね」
「当時巷では源氏物語にファンが沢山いたのですね」
「現代ではなんで墓を紫色にするやつが出てきたのだろう」
「今では源氏物語を読まないのは日本文学をないがしろにするやつだと思われるくらい人気がありますよ、もし気に入らなかったら倒したり壊したりするでしょう、わざわざ紫色のペンキを用意したのだから、むしろ信奉者が墓を紫にしたかったのかもしれませんね」
なるほど詐貸は頷いた。
詐貸と逢手が話をしている長い間、電話を掛け続けていた吉都が受話機を置いて面白いことを言った。
「今、その記事を書いた新聞社に電話して、書いた記者を教えてもらったんです、それで直接話ができたんですが、その記者の話では、紫式部の墓は墓石一面にペンキが塗られていただけではなく、掘ったような跡があったそうなんです、草が剥がされていた程度だったので、そのことは書かなかったということです」
「なにそれ、なんだかお岩さんの墓のときのようじゃない」
何かあるという予感が頭をよぎった。
「だがな、紫式部の頭の骨を掘り出そうというなら、何もペンキなど塗って目立つようなことをしなくてもいいよな」
「そうですね、本当に紫式部の墓を発くために掘ったのだかわかりませんね」
「だけど、跡出さんがわざわざ先生のところに電話してきて、新聞を見るように仕向けたなんて、なにかありませんか」
「そうだな、何かヒントがあるかもしれないな、愛子が帰ってくるまで時間があるし、京都でも行くか」
「誰が行くんですか」
「三人で行くんだよ、ちょっと骨休めも兼ねてかな」
それを聞いた逢手と吉都は大喜びである。
「一泊ですか」
「うーん、状況によるよな、何か出てきたら、もっと長くなるかもしれんよ」
「長くなりますように」逢手が手を組んでアーメンをした。なんだ。
「いつ行きます」
「明日」
「わ」
京都駅にはお昼に着いた。ずい分混雑している。修学旅行シーズンである。
「お昼はなに食べます」
「逢手君はまずエネルギー補給だね」
「あたりまえですよ」
「鰊そばでも食べるか」
「そうですね、昼からははも鍋なんてわけにはいきませんから」
「はもは夏だよ、今だったらそろそろまっ茸か」
「先生、そんな高いもの食べさせてもらえるんですか」
「おいおい、めいめいの出張費の中から出すならいいよ」
「それじゃ止めです、まず鰊そばにします」
ということで三人で駅の蕎麦屋に入った。
「紫式部の頃はどんな埋葬をしたのかな」
「平安時代は一般の人は土葬だったでしょうけど、偉い人は火葬だったといわれているから、紫式部もそうだったんじゃないかしら」
「とすると、骨は残っていないのじゃないか」
「いや、火葬だったにしても当時は焼き方がやわだったでしょうから、頭骨あたりは残っていたかもしれません」
逢手はそういうことをよく知っている。
蕎麦はなかなかさっぱりしていて旨い。そのあと烏丸線に乗り北大路で降りた。三人なのでそこからタクシーに乗った。タクシーの運ちゃんは紫式部の墓を知っていた。
「あそこは墓場じゃないからね、ノーベル賞の会社の土地なんだよ」
ノーベル賞の会社というのは島津製作所のことである。
「本社は鹿児島なんでしょう」
逢手が聞くと、運転手はハンドルを握りながら首を横に振った。
「違うね、これから行くとこが本社だよ、京都出身の島津さんが作った会社だよ、だけど薩摩の島津から理由は知らんが名前をもらったという話だよ」
雑学がこれで増えた。
「それじゃ、紫式部の墓は島津製作所に断って入ってくのかな」
「いや大丈夫、墓は通りから自由に入れるよ」
タクシーはその入口に止まった。
降りると確かに紫式部墓所という石碑が目に入った。白塀に囲まれている。
「ここにほら小野篁墓とあるわ」
逢手が石碑と反対側の塀の脇に立っている石柱を指差した。
小刻みな石段をあがっていくと確かに紫式部の墓があった。
「ここは誰が管理しているのかしら」
可也がその声でさっとスマートフォンを取り出し調べ始めた。
「紫式部顕彰会の人や近所の人がきれいにしていると書いてあります」
「なるほど公的なところが管理していないんだな、とするとちょっと手薄だな」
紫式部の墓石はそんなに大きなものではない、墓石は磨いたような跡がある。きっとペンキを落としたのだろう。
「掘り返された跡などないよ」
墓の奥に塚があり石塔が乗っている。
「あっちにいってみよう」
吉都が塚の周りを回って指差した。
「墓石じゃなくて、ここが問題ですね」
塚の裏手のところに掘られたような丸い跡がある。径にして五十センチほど苔がはがれている。後ろは島津製作所との境のフェンスである。
「ペンキを塗ったのと同じやつがやったんだろうか」
「掘ったにしては剥げているところが小さいですよ」
「そういう機械があるかも知れないよ」
「それにしても本当に中に紫式部の骨が埋めてあるのかな」
「紫式部の墓は栃木の方にもあるという話ですから、ここが本物とは限りませんね」
「紫色のペンキと塚を掘ったような跡との関係がわかりませんね」
「ペンキを塗って、塚が掘られていることを誰かに知らせたかったみたいね」
「俺たちに知らせるためかもしれない」
跡出は我々に墓を調べさせようとしたのか、思いついて電話しただけなのか。
その夜、松茸定食を食べながらことの成り行きを話し合った。
「北京原人から始まって、宮武外骨、お岩さん、そしてここの紫式部、だけど本当に何かが盗まれたのか分からない状態で犯人を追っているわけだ」
「確かにそうですね、我々は思い込みで勝手に動いているようですね」
「だけど、お岩さんは偶然としても、後は依頼人から聞いたことで、なにかありそうだけどね」
「共通点があるとすると墓場と有名な人、それに骨ですか」
「そうだな、しかし見つけなければいけないのは北京原人の骨だ、それも本当に日本にあるのかどうか分からない骨をね、それにしても、跡出はどうしてそんなにヒントを与えるような振る舞いをするのだろうね」
「もしそのつもりがあるとすると、我々を動かして楽しんでいるようですね」
「そうなんだ」
「それじゃ、次は何を言ってくるか考えてみましょうか、外骨の滑稽、お岩の恨み、紫式部の愛欲の次はなにか」
また逢手が面白いまとめ方をした。
「笑う、怒る、性欲」
吉都がもっと端的にまとめた。
「それは人間の脳にそなわっている感情でもあり本能でもあるよな」
「生きることと子供を作ること、動物のからだと脳はそのためにできている」
「動物は笑うのかな」
「嬉しい、気持ちがいいという動物としての感覚はあるでしょうけど、表情筋のある人間のような顔の笑いは無いと思います。笑いは人間に特有だと僕は思いますね」
「怒るのは動物でもあるね」
「ありますけど人間のとは違うわ、怒っているのではなくて、相手を遠ざけたり、相手から家族を守ったりする行動だから、攻撃行動というのでしょう、だから怒るというのはやはり人間特有じゃないかしら」
詐貸は自分でも動物をよく知らないなと思った。二人はよく知っている。
「食欲や性欲は人間の本能から出た欲求で、脳が感じているんです、それが行動を引き起こすベースになるってわけですね」
吉都が生物学出身であることを思い出した。なんだか難しい議論になって来た。
「それで、元に戻そう、墓が荒らされた知名人を逢手君が滑稽、恨み、愛欲とまとめたからそうなったんだが、源氏物語は愛欲だが紫式部を小説家ととらえると、みな文筆業、言葉ということにならないか」
「先生はさすがです、そうすると、言葉は人間特有の物になります、その代表のような著名人ということですか」
「だからと言って、次に誰の墓がいたずらされるか分からないね」
「京都、人間、島津製作所をつなげてみましょうか」
逢手が何かひらめいたようだ。
「島津製作所のノーベル賞のほかに、京都では最近、山中先生がノーベル生理学賞を受賞しています」
「だけど、それがどのように北京原人につながるんだい」
吉都の顔が輝いた。
「犬山の霊長類研究所だ」
「それが、どうしたの、あそこは名古屋でしょう」
「京都大学の霊長類研究所もあるところです」
「それで」
「人間の祖先、北京原人と進化、中山先生のステム細胞を使った生殖医療、子どもを残していくということがキーワードになります」
「すごい推理だね、いつか霊長類研究所を調べてみる必要がでるかもしれないね」
「京都霊長類研究所の隣に日本モンキーセンターもありますよ」
「面白いゲームだった、明日一端事務所に戻ろう、行くのなら頭を冷やしてから、犬山に行ったほうがいいね」
「あーあ、一泊になっちゃった」
ということで京都は松茸定食で終わった。
次の朝、依頼人に電話をした。
「京都に行って紫式部の墓を見てきました」
「わざわざ行ったのですか、なにかみつかりましたか」
跡出はあまり興味がないようである。
「塗られたペンキははがしてありました」
「電話をすればよかったですね、行くと思っていませんでした。実は京都の知り合いに電話をしたのですよ、紫式部の墓のことを聞いたら、もう犯人は捕まっているそうです、紫式部にあこがれている作家の卵でした。若い女の子です、紫色に塗った墓と一緒に自撮りをしたかったようです、いつか自分の本に使いたかったということですよ、ペンキを落す費用を出させて放免したようです」
「早とちりですみません」
「いい骨休めになったでしょう、たまにはいいことです、京都は私も好きでしてね」
そんな話で終わった。みなにもそれを伝えると、逢手は、
「だけどまだちょっとひっかかります」
と首を傾げた。
愛子が帰ってくるまであと四日ほどである。野霧は愛子の主人だった水良佐里雄のことを調べた。住んでいたのは都内だが、本籍は富山になっていた。佐里雄の勤め先は北京骨商であることが分かった。
さらに愛子は佐里雄とは別れたわけではなかった。本人は海難事故で死亡ということになっていた。実家に戻っている時に富山の海で会社の船から落ち、遺体が見つからなかったことから、一年後に失踪宣言されたという。それが五年前のことである。
富山の夢久哉有が会社員だった水良を愛子に婿として決めたのかもしれない。もちろん愛子の父も母も同意の上だろう。しかもどうしても婿にさせたいなにかがあったものと思われる。とすればミステリーサークルで俺の監視を頼んでいたのは夢久家の誰かということになる。詐貸はそう推理した。
「それで、その水良佐里雄は会社でどんな仕事をしていたんだって」
「それが、すごいですよ東京に住んでいながら、200万円の給料です、肩書きはアドバイザー」
「重役扱いだな、きっと有能だったんだろうな、だから愛子の許婚にしたんだな」
「それだけでしょうか」
「ところで、彼の年はいくつだったの」
「失踪宣言を受けたのが三十五ですから、亡くなったのは三十四、愛子さんとは五歳ほど離れています」
「哉有は亡くなっているね、それで今の社長はわかったの」
「佐里雄のお父さん、水良今という人です、年商数億の薬の会社です、なんでも魚の骨の成分から抽出した骨粗しょう症によく効く薬だそうで、海外でよく売れているようです、日本では一切宣伝をしていません、一般には知られていない会社です」
「やっぱり愛子が小さい頃から知った人だったんだな」
「そう思います。佐里雄は一人っ子です」
「それで旦那は何の船に乗っていて落ちたの」
「それが魚を獲る船に載っていたのだそうです。漁船ですね、乗組員は八人、それに混じって魚の網を引いていたようです」。
「アドバイザーが会社の船の仕事をしていたってわけか」
「不思議ですけど、そういう性格の人だったのかもしれません」
確かに上に立つ人でもみんなと働いてコミュニケーションをとろうとする人はたくさんいる。もしかすると、より高率な魚の捕獲方法を考えたり、効率的な働き方を考えてアドバイスする役割だったかもしれない。
「話は変るけど、愛子と旦那との仲についてはなにも聞いていないの」
「ええ、戻られたら聞きます」
その日の夕刊であった。また墓のことが出ていた。小野小町の墓が荒らされたというものである。秋田魁という地方新聞である。朝日新聞にはのっていない。どうして知ったかというと、これは吉都の推理からである。吉都は紫式部の源氏物語が美男の話なら、今度はその頃の美女そのものではないかと考えたのである。美女達をインターネットの検索にかけていたら、引っかかってきたのである。
「小野小町の墓はいろいろなところにあるよ」
「墓が荒らされたのは秋田の湯沢市にある小野町です」
「行ったことはないが、古くからの町のようだ、稲庭うどんや温泉で知られている」
「城下町です、お酒の大きな本舗などもありますよ」
野霧は酒はあまり飲まないのにそういう情報はよく知っている。
「吉都君、いくかい」
「はい、行ってきます」
大喜びである。逢手も行きたそうだが、もう少し愛子にかかわることを調べてもらわなければならない。
吉都は秋田新幹線に乗って湯沢に行った。大曲で奥羽本線に乗り換えなければならない。東京から四時間もかかる。かなり遠い。
逢手には北京骨商について調べを進めてもらった。
「国立図書館で富山の薬について調べてきました、富山の古くから代々続く薬問屋、夢久漢方の次男夢久十が、北京に夢久漢方の支店をだし、そちらに移りました。富山の薬を向こうで売って儲けると同時に、中国の漢方薬を日本に輸出して夢久漢方で売って大もうけしました。さらに夢久漢方で覚えた骨の製薬法のノウハウを中国で新たな薬の開発に生かして、あの辺りでとれる化石骨や恐竜の角などから、より効く薬を作りだしていたようです。それで名前も北京骨商として大々的にやっていました。中国では向こうの町や村に多大なお金を落とし、日本村を作るような発想ではなく、中国に溶け込むうまい商売をしていたようです。それで戦争が始まる前に日本に帰ってきたらしいのですが、北京骨商の日本人たちは惜しまれながら引揚げてきたということです。その時点でその北京骨商はなくなりました。日本に戻ると、兄がなくなっていたこともあって、夢久漢方の主人になっていたのですが、すぐに哉有にまかせています」
さすがに逢手である。
「夢久十は日本に帰ってきてから改めて結婚をし、愛子さんのお父さんが生まれました」
「だから十八も離れていたわけだ、ということは夢久哉有は中国でできた子供ということかな」
「はい、そのようです、母親の名前は分かりませんでした、戸籍には夢久十が日本に戻ってから再婚した年の離れた日本人の奥さんしか書いてありませんでした、嫡男は哉有、次男は愛子のお父さん、多助です」
「今の北京骨商は再興されたものだね」
「そうです、夢久哉有が若い頃、夢久十の指導があったのでしょうけど、夢久漢方を基盤にして改めて富山で起したようです」
「夢久哉有はいくつで亡くなったの」
「八十一で五年前になくなっています。佐里雄が海で事故にあった四年後です」
「俺が探偵になった頃だな」
「ちょうどそうですね」
「哉有はかなりのコレクターで、何を集めていたのかは知らないと愛子が言っていたということだが、何だろうね」
「それは分かりませんが、どこかにあるのかもしれませんね」
「水良今のことはわかったかな」
「よくわからないところがあります、夢久哉有が北京骨商を愛子さんのお父さんにゆだねずに、水良を社長にした理由がこの事件に関わるかもしれませんね」
その通りである。
「今度は水良今のことをたのむよ」
逢手はなかなか頼もしい。
「北京骨商で重要な役割をしていた人に違いないと思います、明日調べます」
次の日の夕方、逢手が調査から帰って来た。
「水良今の生まれは富山、本籍が夢久哉有と同じです。ただ住所がそうなっているというだけで姻戚関係は読み取れません。両親の名前も書いてありません。何らかの理由で新しい戸籍を作ったのだと思います。戦後の時期はそんなこともたくさんあったのではないでしょうか。現在の住所はその近くです」
「それじゃ、おそらく夢久哉有が水良今を育てたような関係かもしれないな」
「そうですね、それでその息子を愛子さんの許婚にして、愛子さんに会社を戻そうと考えたのかもしれませんね、愛子さんのお父さんも同意していたのでしょうから、お父さんも佐里雄氏の事をよく知っていたと思いますね」
「もしかすると水良今と愛子さんのお父さんは同じくらいの年なのじゃないかな」
「そうです、佐里雄氏の父親だし、水良今のことは愛子さんもよくご存知でしょう」
「愛子が帰ってくれば話が聞けるな」
「はい」
「夢久哉有に子どもはいないの」
「結婚していません」
「そのコレクションや財産は誰が引き継いだのだろう」
「おそらくコレクションと供にどこかにあるのだと思いますが分かりません、少なくとも夢久哉有が亡くなってから、愛子さんの家が遺産をもらったということは調べた限りでは出て来ませんでした」
「それで、愛子のお父さんの会社は何の会社」
「それが器械メーカーです」
「薬とはぜんぜん違う方面なんだな」
「世界で知られているようです、小型の掘削機」
「なんなのその掘削機って」
「穴を掘る機械ですよ、日本は巨大なトンネルを掘る掘削機で最も進んでいるでしょう、愛子さんのお父さんの会社は人が一人または二人通れる位の大きさの穴をすぐ掘ってしまう機械を造っています、最近、電線を上水道やガス管などと一緒に地下に埋める方向にいってますね、共同溝です、それを掘るのにとても便利で、あたっているそうです」
「彼女のお父さんも亡くなったんだよね」
「夢久哉有の二年後に亡くなっています、だから比較的若くしてなくなっているわけです。七十にいっていません、確か六十六ぐらいです」
「会社は誰がやってるの」
「専務だった人に社長を委譲していて、愛子さんのお母さんが筆頭株主となっているようです」
「お父さんの根付のコレクションはどうなったんだろう」
「おそらくお母さんが管理されていると思います」
「愛子の家にあるのだね」
「そう思います」
吉都が戻って来た。
「湯沢の小野町に小野小町の墓があってそばには母親の墓などもありました」
「稲庭うどん食べた」
「はい、天然舞茸がたっぷり入ったやつ」
「いいなー」
野霧はやはり食べることである。
「それでどうだった」
「墓石の下のところに掘られた跡があるそうですが、何がとられたとか、墓石が傷ついたということはなかったようです」
「あまり事件性がないのかな」
「地元の人は気にしていませんでした、ただ、秋田魁新聞の記者の実家が近くにあったので、その記者が母親に言われて書いたようです」
「収穫なしか」
「湯沢まで東京から4時間、往復八時間、時間をもてあましてスマホをいじるしかなくて、小野小町のことを調べまくりました」
「それでなにかでてきたの」
「墓はいろんなところにあります、だから湯沢のものが本当のものかどうかも分かりません、ただ、そこにいたことがあるようで、かなり関係のある場所であることは確かです」
「美人に会えたの」
「はあ、美人のおばあちゃんばっかりに会いました、ともかく今の若い人は小野小町と言ってもぴんとこないようで、最初若い人に小町の墓を聞いたのですが分かりませんでした。それよりも逢手先輩がとても興味持つようなことを知りました、ネットを見ていたら小野小町は小野篁の息子の娘です」
「えー、孫なの、とすると小野小町は紫式部と同年代なのね」
「いや、式部のほうが後で、活躍していた時期はかぶっていないようですけど、どちらも文才があった女性ですね」
「清少納言と小野小町が張り合っていたのは知ってるけど」
「そうなんですか、ともかく小野小町は篁の血を引いていたので、もしかすると妖しい能力をもっていたかもしれませんね」
色々な関係が分かってきたが、北京原人には結びつかない話ばかりである。
「ともかく、今までの墓の事件では骨が盗まれたり無くなったりという訴えはないね、北京原人に戻らなければな」
「そうですね、関係ないんですが、ナポレオンの頭の骨の小咄知ってますか」
「うん、古物市場でナポレオンの骨を売っていて、ずい分小さい骨なので、うそ言うんじゃないと誰かが言ったら、売り手が子供のころの骨だと言った話だろ」
「ええ、ヨーロッパじゃ骨はもう魂の抜けたもので、物として考えています、それで美術品のように飾ったり、祖先の頭骨を自宅に置いておくという習慣を持つところもあったようですね」
「そうだね、古い西洋の絵には机の上に骸骨が書かれているのが多いね」
「死んで残せるのはカルシウムだけだ」
吉都は生物学のかたまりだ。
「だけど、頭の骨を集める人がいても、カルシウムを集める人はいないわ、あの形が重要、それに、そこにはその骸骨の一生がまとわりついているので、集める人が出てくるかもしれないわね」
「自然が作り出した形の冴えたるものかもしれんな、人間にとって顔はその人そのものだよ、中には脳もある、目もある、鼻も、耳も骸骨を取り囲んでその人をつくっている」
「先生、その表現はいいですね」
「本当に墓は荒らされているのだろうか」
「もしそうだとしても、跡出馬盛は関係ないね、わざわざ我々に墓荒らしを教えたりはしないと思うよ」
「そうですね」
「わからないな、さあー昼にしようや」
野霧は買ってきた包みを広げた。吉都はいつも行く定食屋に向かった。詐貸は久しぶりに西巣鴨の蕎麦屋、ひさごに行くことにした。
戸を開けると主人がにこにこして話しかけてきた。
「おや、詐貸さん久しぶりだね、忙しかったんですか」
「ちょっとばかり飛び回ってました」
「探偵って仕事、想像つかないね」
「いや、骨折り損のくたびれもうけばっかりですよ」
「大きな仕事のようですな」
「探偵始めて初めての大きな仕事には違いないけど、なかなか埒が明かなくてね」
「今日はなににします、蕎麦は山形ですよ」
「野菜天にして」
「ところで、一週間ほど前かな、小柄な爺さんが来ましてね、詐貸探偵事務所ってどうなのって言ってましたよ、それでね、きっと大きな依頼がいったんじゃないかと思ったんですがね」
「いや、この依頼はもう半年も前のことだから、違うな」
「はい、どうぞ、この塩がいいかな」
親父が塩の入った小壷をこちらに寄せた。
天麩羅を塩で食べ、食べ終わった頃、蕎麦をうでてくれる。
「変に気取った人じゃなかったけど、着てるものや持っている物にこだわりがあるようだったな」
一体誰なのだろう。とんと思いつかない。北京原人関係者だったらわざわざ事務所のことを聞いたりしないだろう。
「これから依頼がいくのかもしれませんよ」
「そうだといいんだけど」
蕎麦はともかくうまかった。
事務所に戻ると吉都がもう帰っていて、逢手と話をしている。
「あ、先生お帰りなさい、可也君が面白いことを聞いてきましたよ」
「なに」
「妙行寺に行ったら、墓守のじいさんにお岩さんの墓がきれいになったといわれたので見てきたんです、元の様に立て直されていて、むしろ立派になっていました。それはいいのですが、お岩さんの墓を建て直す費用は田村家ではなく、寄付をしてくれた人がいたとのことでした、それで誰か教えて欲しいといったところ、水良という人だったそうです。珍しい名前なので覚えていたそうです」
「え、そりゃまた、あの佐里雄の水良なのだろうかね」
「そのようです」
それを聞いた詐貸は何を思ったか、机の上の電話をとった。いつもは携帯なのに珍しいと二人が見ていると、手帳を出して電話をかけた。
野霧と可也が顔を見合わせていると、「それはどなたでしょう」と言う声が聞こえ、「ああそうですか、その方はどこの方ですか」と電話の相手に聞いている。頷きながら、手帖に何かを書き入れながら「ありがとうございます」と電話をおいた。
「誰に電話をいれたんです」
「京都のね紫式部顕彰会、吉都君がいい情報を持ってきたものだから、もしやも知れないと思ってね」
「それで何を聞いたのです」
「紫式部の顕彰会の資金についてね、そしたら会員の中に大口の寄付をする人たちが何人かいてね、もちろん会社もいくつか含まれるけど、その中でも熱心に寄付してくれる個人の名前を聞いたんだよ」
「誰でした」
「中に水良今がいた、富山のね」
二人は大げさなほどに驚いた。
「荒らされた墓と水良今が結びつきましたね、もしかすると小野小町にも関係あるかもしれない、僕が電話してみましょう、墓や母親の塚を管理している小野村の人の電話番聞いてきましたから」
吉都がスマホで電話をした。
頷いている。
「やっぱり、水良が寄付をしています」
「わー、つながってきた、でも北京原人とはちっともつながらないですね」
「そうだね、どうしても愛子に聞くしかないか、愛子は君たちに任せようと思ったのだけど、俺も一緒に会ってみるか」
詐貸は覚悟を決めたようである。
再会
「先生、愛子さんが帰国されました、いつでもお会いしますということです」
朝詐貸が事務所に行くと、逢手がお菓子を食べながら報告した。
「ぜんざい最中じゃないか」
詐貸が逢手の食べている菓子の名前をいいあてた。
「さすが先生」
早稲田の和菓子屋、いなほの銘菓である。粒餡の中に牛皮の入っている味のいい最中である。その店はそれだけしか作っておらず、昔は皇室御用達であった。
「それでいつ愛子のところに行こうか」
「明日どうでしょうかという向こうからのお申し出です」
「わかった、君たちも一緒に行ってくれるよね」
「はい、聞きたいことを整理しておきます」
「場所は田園都市線の九品仏だよね」
「ええ、いまは大井町線ですけど」
「ああ、そうか、どうもあの辺りの線がわかりにくくてね」
「大学時代に愛子さんのおうちに行ったことはないんですか」
「うん」
「おとなしかったんですね」
詐貸は苦笑いをした。
次の日、九品仏の駅から歩いて十分ほどのところにある愛子の家に行った。住宅街の奥まったところに彼女の家はあった。昭和初期に建てられたと思われる和洋折衷の建物で、おそらく名のある設計者のものであろう。
門柱のドアホンを押すと、「はーい、今あけます」となつかしい声が聞こえた。愛子である。おそらく詐貸の顔が室内のモニターには映し出されているだろう。
玄関の扉が開いて、白いブラウスに紺のGパンをはいた愛子がでてくると、門の鍵を外した。姿は昔と変っていない。
「詐貸君、久しぶりね、男っぷりが上がったみたいね」
昔はこんな言い方はしなかったが、ずい分自信に満ちた感じの女性になった。
「今日は帰ってこられたばかりですみません」
「あら、いやだ硬くなってる、ねえ結婚してないの」
いきなりそんなことを聞かれて面食らっていると、後ろから逢手が
「ええ、先生はずーっと独身を通されています」と答えた。
「あーら、まあ、入ってくださいな」と愛子は笑いながら彼らを家の中に招いた。
何で笑うんだ。と詐貸はちょっとくさっていた。
普通の家の倍ほどの広さのある黒光りした板張りの廊下を通って、彼女の書斎と思われる部屋に通された。二十畳ほどの広さの片側に使い込んだ立派な書斎机があり、その後ろの壁面は天井まで本棚になっている。
真ん中にはこれも古くから使われたていたと思しき大きなテーブルが置かれ、十客の椅子が囲んでいた。
「お座りになって」愛子の声で、我々はそのテーブルの席に着いた。
「逢手さんとは一度お話しましたわね、ミステリーの話面白かったわ、それで今日は本物の探偵の先生じきじきのお出ましということで楽しみにしていたのよ、北京原人について私は何も知らないわよ、他に知りたいことがあればなんでも話すわよ、ちょっと時差ぼけがあるけど」
「いや、ずい分変りましたね」
「年取ったものね」
「いや、翻訳をしていると聞いて、ちょっと驚いただけ、昔翻訳物はいやだといっていたから」
「うん、自分でミステリー書きたかったけど、アイデアがでてこないの、幸い外国語は好きだったので、結局翻訳をすることにしたんです、でもありきたりのじゃなくて、ちょっと幻想的なのがいいと思っていたら、ノールウェーの作家にであって、それを訳しているのよ、ノールウェーにはトロールがたくさんいる幻想の国だから」
それならば分かる気がする。
「ご主人がお亡くなりなったとは知りませんでした、なんと言っていいか」
詐貸は本当に言葉に詰まった。愛子は、
「驚いたし、寂しくなったし、だけど五年前のこと」
明るい声で笑った。内心は分からないが大人の女性になった。
「愛子さんのお爺さんの会社、北京骨商について知っていることを教えていただけないかと思ってきたのです」
「ああ、夢久十のことね、私も父や叔父の夢久哉有に聞いただけでおそらくお調べになったことぐらいしか知らないわ、中国の周口店付近で北京骨商をひらいたのよ、探している北京原人とつながるのかしら」
「それはわかりません、戦争がはじまりそうなとき、おじいさんはその会社をたたんで、そこで働いていた日本人は、みな引き上げてきたわけですね」
「そのようね、詐貸君が探している北京原人の骨が失われたのはその後だわね、おじいさんとはあまり関係ないと思うけど」
「そうですね、ただ一緒に引揚げてきた方たちが関係していないとも限らない」
「たしかにそうね」
「働いていた日本人についてはご存知ありませんか」
「古い写真があるから、それをたどれば分かるかもしれないわね」
「哉有さんが北京骨商を再興させましたよね、哉有さんが亡くなった後、愛子さんのお父さんが継がないで、水良今さんが継いだのはなぜでしょう、そのお子さんが愛子さんのご主人でしたよね」
「そうよ、水良今叔父は今の北京骨商の研究の中心だった人、哉有叔父の右腕だったのよ、私の父は自分の仕事が順調だったこともあって、今叔父にまかせたの」
そこまでは推測と大体あっていた。だが水良今のことを叔父と呼んでいる。
「水良今さんと親戚関係」
「いえ、遺伝子のつながりは無いわ、父と一緒に育ったので、父の兄弟のように私には思えるの、だから叔父さんっていつも言っていた」
「どこの生まれの方なんですか」
「富山よ」
「写真があったら見せていただけますか、それとご主人の写真」
愛子は笑いながら「いいわよ、主人は詐貸君ほど格好は良くないけど」と、本棚の片隅からアルバムをもって来た。
映っていたのは愛子の父親と並んだ水良今だった。父親は愛子と似ているところがあったが、水良今は背の高い細面の紳士である。
「これが亭主だった人」
愛子と写っている水良佐里雄は背はどちらかというと低くて、目の上の骨が飛び出し、四角張った顔をしている。父親の今とは全く似ていない。愛子もそれは知っていたのだろう。
「主人は彼の父親とは似ていなかったわね、早く亡くなった母親と似ていたのよ」「水良今さんは息子さんがなくなって跡継ぎがいなくなって大変ですね」
「そうね、だけど水良の叔父さんは元気だからまだ跡継ぎのことまで考えていないでしょう、内の主人も後を継ごうとは思っていなかったと思うわ」
詐貸は頷いた。
「愛子さんのお父さんは根付を集めていらしたと聞きました、どうなさったのです」
「そこにあるわよ、ここは昔父の部屋だったの」
愛子が一方の壁にある大きなガラス戸を指差した。
「見ていいですか」
詐貸はその飾り棚を見て驚いた。ただの根付ではない。すべて象牙で出来たシャレコウベの根付だ。何百もありそうだ。やっぱり頭骨だ。
「すごいでしょ、象牙だけではないの、水晶もあるし、木でできたものもあるの、それは箱に入れてしまってあるわ」
詐貸は棚の上のほうにある根付に眼をやった。作家の名前がふってある。いろいろな作家の頭骨の根付である。
「作家の頭骨があるけど、どうやって作ったのだろう」
「きっと、父が作家の写真を見せて、それから想像して作ってもらったんだと思うわ、私は全く興味がなかったので、詳しくは聞かなかった」
「紫式部や小野小町の頭骨はありますか」
「多分探せばあるんじゃないかな、父は古典を読んでいたから」
愛子は根付には興味がなさそうだ。背の高い吉都は棚の上のほうに飾られている物もじっくりと眺めている。
詐貸は席に戻ると愛子に聞いた。
「これは誰が作ったの」
「色々なところに頼んでいたようだけど、奈良の職人だと思うわよ、鹿の角の細工をしていた人を知っていたの」
「愛子さんのお父さんはどうして頭骨にこだわったのかな」
「夢久漢方は骨を強くする薬を作っていたし、哉有叔父の会社には魚の骨の標本や、動物の頭骨の標本があったからかしらね、骨に囲まれていたから、それに髑髏は男の子が興味を持つものでもあるでしょう」
「確かに、気味の悪さもあるし、恐れもあって、逆に強い興味を持つかもしれないよね」
「哉有さんが集めていたものもやっぱり骨に関係がありそうだね」
「そうかもしれないけど、私全く知らないの」
「亡くなってから水良さんが保管されているのではないのではないのですか」
「うーん、聞いたことがないな」
愛子は本当に知らないようである。
「水良さんは紫式部に興味があるのですかね、それにお岩さんなんかも」
「え、変なことを聞くわね、どうでしょうね、水良の叔父さんは魚の研究者で集める趣味は無かったけど、日本の古い文学や歴史の本はよく読んでいたわね、父は水良の叔父さんに影響されて日本の古典文学を読むようになったと言っているのを聞いたことがあるわ」
「水良さんが社長になってどうですか、なにか変ったりしました」
「変ったか変らないかは分からないけど会社は順調よ、むしろ伸びているみたい、あの叔父は誠実な人で、さっきも言ったように哉有叔父の会社を継いでもらったのは父の希望でもあったわ、父が二つの会社をマネージしても良かったわけだけど、父は水良は頭がきれる、あんなにすごいのはいないとよく言っていたのよ」
荒らされたお岩や紫式部の墓に水良が何らかの関わりをもっていることは愛子には言っていない。
「詐貸君、依頼人のことを知らないって言ってなかった」
「そうなんだ、きっと依頼人の素性が明らかになると何かが見えてくるんじゃないかと思っているんだ」
「依頼人を知らない捜索なんて傍から見ると奇妙だわ、それに危ない感じがする」
愛子の言うとおり普通では考えられない。
「俺の勘で依頼人は危ない人ではないと思ったことと、実は北京原人のことを全く知らないで引き受けちまったもんで、あとでとんでもなく探すのは難しいことがわかったということなんだ」
「依頼人という人はどうして北京原人探しているのかしらね、夢久家とそんなに関係があるのかしら」
「いや、全く分からない、実は暗礁に乗り上げていて、依頼人がなぜ僕に依頼したのか知りたいと思ったら、逢手が僕の経歴に関係ありと探りを入れて、吉都がミステリーサークルから調べ上げて、愛子さんが出てきてしまったんだ、そうしたら北京と骨というキーワードと愛子さんの夢久家が当てはまるということになって、こうなってしまった。関係なかったら申し訳ない」
「いいのよ、面白い、確かにミステリーが書けそう、それに私が絡んできたらもっと面白いわね」
「愛子さんは僕が探偵になっていたのを知っていたの」
「いや、知らなかったのよ、逢手さんがインタヴビューにきたとき、詐貸探偵事務所だとおっしゃったんで、もしかと思って聞いたら当たったわ」
「愛子さん、ミステリーサークルの部長だったアメリカ文学の教授覚えているかな」
「覚えているわよ、西条やそみ先生、私文学部だもの、西条先生が哉有おじに詐貸君のことを報告していたのを調べたのね」
「そうなんだ、この吉都が有(う)袋(たい)類子さんから聞き出したんだ、君も類子さんに話していたんだね」
「うん、相談していた」
「西条先生が僕のことをその理事に報告していたことをどうして知ったの」
「あるとき、両親に今付き合っている人は止めなさいって、佐里雄を悲しますことはできません、って言われたの、それで親にどうして詐貸君のことを知ったのか聞いたら、大学の理事の人が西条先生から聞いたって言ったわ、ちょっといやだった」
「その理事の人とはどんな関係があったの」
「私が大学受かったことを富山の叔父達に報告しに行ったとき、その人が富山の家に顔をだして、叔父が紹介してくれた。
2年後期のゼミ選びの時に西条先生の研究室も回ったわ、そのときその理事が先生の部屋から出てきてばったり会ったの、西条先生に直接聞いたら、あの先生はっきりものを言う人でしょう、それは悪くは無いわね、それで話してくれたわ、ちょっとあやまっていたわ」
「そうだったのか、あの理事と西条先生が結婚して、アメリカで研究を続けているのは知っているの」
彼女は頷いた。
「西条先生は自分の研究をしたかったのよ、理事の人お金持ちだから研究費もらっていたのでしょう」
「理事の人も家庭を捨てて結婚したということだけど」
「そうじゃなくて、奥さんを若くしてなくしていたから、子供はもう独立していたし独り身のようなものだったのよ」
そのあたりの色々な謎が解けてきた。
「あの頃、愛子さんに婚約者がいたんだね」
「いや、正式に婚約者というわけではなかったんだけど、私子供のころから富山に遊びに行ってたの、佐里雄ちゃんとよく遊んだわ、親切にしてくれていいお兄ちゃんだった、親や叔父達も将来は結婚させるつもりだったのはわかっていたし、大学に入ってからは、佐里雄ちゃんもそのつもりになっていた。私も嫌じゃなかったから大学出たら結婚するって親にも言ったりしていたのよ、だけど詐貸君と会ったでしょ」
愛子が詐貸を見た。詐貸はちょっとあわててしまった。
「あ、まあ、そのことはそれで分かったけど」
逢手が笑っている。
「私、いろいろあって、佐里雄さんと結婚することを決心した時に、大学辞めようと思ったの、だってそうでしょう」
愛子がまた詐貸を見た。詐貸は目をそらせた。
親に大学を止めさせられたのではないようだ。
「それで類子に相談した。類子は家をすてて詐貸君を選ぶべきと、私は軽蔑されちゃったわ、類子はオーストラリアから留学していた男の子と付き合っていたけど、卒業したらすぐに彼を追いかけてオーストラリアに行ってしまった。私とは正反対ね、それ以来連絡してはいないわ」
吉都がそれに答えた。
「類子さんは実家にいらっしゃいました。実は電話をかけたらお出になって、その話を聞かせていただきました」
「どうして実家にいたのかしら」
「お父様が無くなって葬式に帰ってきているとおっしゃってました。愛子さんには会いたいとおっしゃってました。もうオーストラリアにお戻りになっています。愛子さんの電話を教えてしまいましたので、そのうち連絡があると思います」
「それは嬉しいな、類子のオーストラリアの電話分かるの」
「いえ聞きませんでした、日本の実家なら分かります、お母様がいらっしゃいます」
「後で教えてくださいな、私電話してみる」
「はい」
「でも、よくB子が西条先生のことを話してくれたわね」
「ええ、ちょっと言いにくいんですが」と吉都は詐貸を見た。
「いいよ、言ってごらんよ、どうせいい加減なことを言って、しゃべってもらったんだろ」
吉都がなんとなく恥ずかしそうに続けた。
「僕が精神科の医者で、患者に詐貸という人がいて、長い間欝にかかっている。どうも彼の過去の失恋が原因のようで、相手の夢久愛子さんに許婚がいたことを知らなかったことが要因じゃないかと思うので、その辺のことを知っていたら教えて欲しい。彼を助けるためにお話し願えませんかと言いました」
「あれー」
愛子はちょっと笑をこらえているようだったが、詐貸はブーっと顔を膨らませて赤くなっている。野霧なんか口を押さえて笑っている。
「すみません」
吉都は縮こまっている。
「詐貸君、いい助手をおもちね」
愛子の言葉で吉都はちょっとほっとしたようだ。
「まあ、吉都は演劇をやってたから、そういうのが得意なんだ」
「あら、そうなの、ほんとなら面白いと思ったわ」
どういうことなんだ、やっぱり愛子はずい分変った。詐貸は話を変えた。
「依頼人は漢方を扱う会社に関っていたようで資産家のようなんだ、ぽんと一千万もってきて骨の捜索を依頼されたんで、夢久家が漢方問屋だったこともあって、愛子さんに話を聞くことは意味があると思ったんだ。まだ分からないけど何か関係がありそうだな、愛子さんは全く想像がつきませんか」
「確かに夢久家とよく似た境遇の人のようね、だけど依頼人の名前も分からないのじゃ、想像しようがないわね、黙っているから教えて、知っていたら言うから」
詐貸は決心したようだ。
「依頼人は跡出馬盛という人」
「知らない人だな」
愛子は顔色一つかえなかった。本当に知らないようだ。
「外部にしゃべらないでください」
「もちろん黙っているわ、でも面白そうな話しね、また話を聞かせて」
「夢久家に関わりがあるとなったらご協力願います」
「ええ、よろこんで、当分海外には行かないから、いついらしてもいいわよ、しばらく時差ぼけだけど、逢手さんミステリーの話をまたしましょうよ」
逢手は嬉しそうにうなずいた。
詐貸たちは彼女の家を出た。
「お母さんはいなかったね」
詐貸が逢手に聞いた。
「前の時はいらっしゃいました、確かに今日はお留守のようでしたね、先生、愛子さんも言っていたけど、なんで依頼人は自分のことを隠しているのでしょう、先生に会うとまずいことあるのじゃないですか」
「そうだな、しかし顔見知りではないよ、声でもそういうのわかるだろう」
「そうですね」
「あの、僕ちょっと寄り道をしてから事務所に行きたいのですが」
吉都はそう言って渋谷で山の手線のホームに行った。詐貸と逢手は地下鉄の半蔵門線に乗り換えた。
「依頼契約にはどのような人がきたのですか」
「かなり年を年をとった品のいい女性だったな、現金一千万を持ってきて、契約書に印を押していったな」
事務所に戻ると、野霧が契約した時の書類を見せてくれという。それを見ると野霧はやっぱりという顔をした。
「全くその女性の自筆がありませんね、ここに書かれているのは、先生の字ですね」
野霧は詐貸の字をもう知っていた。たいしたものだ。
「その女性から指がリュウマチで字がうまく書けないので、書いてくれと言われててね、一千万の現金を目の前にしていたものだから、言われる通りにやっちまった、判子も俺がついてやった、確かにその書類には手がかりがほとんどない、珍しい名前だから、判子屋を探すことは可能だがな」
「やっぱり跡出馬盛は先生に顔を見られらたらまずいと思って、代理人に届けさせたのですね、一千万の大金をたくすのですから、代理人の人は跡出さんによほど信頼されている人です、きっと身内じゃないですか」
詐貸はうなずいた。
夕方事務所が閉まる間際、吉都が事務所に帰って来た。
「どこ行ってきたの」野霧が不思議そうに聞いた。
吉都が何も言わずにどこかに行くのは何かに気付いた時だ。
「大学図書館」
「なに調べてきたの」
「マリリン・モンローとアルベルト・アインシュタイン」
「おっもしろい取り合わせ」野霧が笑っている。
「先生、この本マリリン・モンローのことよく書かれていますよ」
図書館で目を通したらとてもいい本だと思ったので、大学界隈の古本屋で見つけてきたという。岩波新書の「マリリンモンロー」という本で、著者は亀井駿介である。
詐貸にはなんだか分からない。
「本当はジョー・ディマジオ、アーサー・ミラー、JFケネディーも調べたかったのですけど、時間がありませんでした」
「どうしてその人たちを調べたの」
「先生、愛子さんの家の根付を見て驚きました、先生もご覧になったでしょう紫式部も小野小町もお岩ももちろん外骨もありました。もしかするとあの根付は本物の骨を見て作られたのじゃないかと思ったんです、僕が一番上の棚を見て回ったら、外国の有名人の髑髏がありました。その中にマリリンモンローもアインシュタインもありました」
「可也ちゃん、その人たちの頭骨根付も本物を見て作ったというわけ」
「はい、マリリン・モンローだけではなく、旦那だったミラーやディマジオ、浮気をしたケネディーの頭骨の根付もありました、もしかするとそれらの頭の骨は盗まれているんじゃないでしょうか」
「ちょっと飛躍しすぎているんじゃないのかい」
「そうよ、アインシュタインは亡くなった後、散骨されていますよ、頭の骨も粉になっていると思うんだけどな」
野霧は物知りだ。吉都も引き下がらない。
「アインシュタインの脳を持ち出した解剖医がいます、脳を標本にして、調べてもらうために専門家に送りつけていて、アインシュタインの脳の空間認知などの部位が普通の人より大きいこともテレビでやっていました。その解剖医は頭骨も抜き取っている可能性もあります。あの偉大な人の頭ですから脳ばかりではなく頭の骨も調べたくなりませんか、解剖医の名前はハーヴィーです、それを探しだし盗んだ人もいるかもしれない」
「すごい推理だけど、そうすると、愛子の父親の知り合いにはその髑髏を持っている人がいるということになる。それを見て職人があの根付を作ったわけだね、夢久家の誰か、一番可能性のあるのは哉有っていうわけか」
「先生のおっしゃる通りとすると、愛子さんのお父さんも哉有の集めていた物を知っているということになりますね」
「髑髏を盗んだかどうかは別にして、この依頼に夢久家が絡んでいる可能性はありそうだな」
「そうです、ですから愛子さんとはまだまだ話し合わなければなりません」
詐貸は頷いた。
「跡出は墓荒らしを誰かがやっていることを知って、頭骨を集めている人間のいることに気づき、その人間が北京原人の骨を持っていると思っているのかもしれないね」
「たしかにそうですね」
詐貸の推理に二人は頷いた。だがかなり想像の上の想像である。
その後二人は水良今が社長をする北京骨商を詳しく調べてきた。
北京骨商の事務所は富山市の市役所の近くのオフィスビルに入っている。富山湾の有磯海岸沿いに会社の大きな敷地があり、本社屋、薬を作る工場や研究所がある。そこに続く砂浜に会社の漁船が何艘か繋ぎ止めてある。それは湾内の近場の魚を獲るためのものである。佐里雄が海に落ちたときに乗っていた船なのであろう。大型船ももっていて、近くの港に停泊させている。外洋での調査、場合によっては外国にも行く。ずい分手広くやっている大きな会社である。
「水良今は富山の事務所よりいつも工場内にいるようです。電話で問い合わせた受付の女性が、社長は研究所にいて研究の指導をしていると言ってました」
「住まいはどこなのだろう」
「自宅は富山の街中で亡くなる前は夢久哉有の邸宅でした、今は会社の所有物になっています。しかし、自宅はたまにしか帰らず水良は工場の敷地内の社宅で寝泊りしているようです」
「よく調べたね、哉有のコレクションは富山の邸宅にあるわけは無いよね」
「そうですね、そうなら愛子さんたちも目にしていると思います
愛子に話を聞くことができたのはそれから一週間後だった。また愛子の家に訪ねて行った。
「今日は元気よ、さすがにこの間はぼけていたわ」
愛子は白いブラウスに水色のロングドレスで玄関に現われた。居間に通されると、ずい分部屋の様子が変っていた。根付の入っていたガラスの棚はすべてなくなっていた。そこには新たに木製のどっしとした棚が置かれていて、たくさんの人形が飾られていた。どれも不思議な顔をした人形たちである。一つ目や三つ頭の者もいる。びっくりしている詐貸たちに愛子が得意そうに言った。
「ノールウェーのベルゲンにいったら、トロールがいたるところにいるのよ、それでみんな買っちゃった、あちらから送ったのが届いたのよ」
やっぱり愛子にもコレクターの血が流れている。
「かわいい」
逢手は嬉しそうだ。こういうキャラが好きなようだ。
「逢手さんダブっているのを一つあげるわよ、一つ目のトロール同じものを三人も買ってきちゃったから」
お手伝いさんらしき人が珈琲をもってきた。
「今日は水良叔父のことで来たのでしょう」
「うん義理のお父さんのこともだけど、ご主人やお祖父さんのこともね、色々とお聞きしたい」
「水良の叔父さん、お父さんとはなかなか呼べなかったわ、この前も言ったけど小さい時から叔父さん叔父さんて言っていたから」
「ご主人、海に出て行方不明だそうですね」
「そうなの、水良叔父から電話を受けたときは驚いたどころではないわ、佐里雄さんは泳ぎはうまくて、よく遠泳大会にでたりしていた」
「それなのに、船から落ちたのか」
「ええ水良叔父はそう言ったわ、捜索しているのだけど見つからないって、私もすぐに富山に行って一月向こうにいたわ、でも見つからなかったの、それで一年後、水良叔父の勧めで失踪届けを出して、一応離婚したことになっているの」
「水良さんが離婚を勧めたんだ」
「ええ、愛子はまだ若いって言って」
「水良さんは愛子さんのお父さんと同じくらいだね」
「そうなの、水良叔父のお父さんは夢久十の片腕だった人、一緒に中国で働いていて富山に帰国したあと、やはり日本で結婚して生んだ子供なの、だけど両親がそのころはやっていた結核や伝染病で相次いで亡くなったの、それでお祖父さまと哉有叔父が一緒になって私の父と供に育てた人よ、大きくなってからは哉有叔父の北京骨商の研究を一手に荷っていたわ」
やっぱりそうだった。
「周口店でおじいさんが活躍していたころのことを詳しくおしえてくれないかな」
「ええ、祖父からも叔父からもよく聞かされたわ、おじいさんは富山でも代々続く薬屋、夢久漢方という店だったけど、その次男でかなりの発明家だったそうよ、1920年代後半に中国に渡ったの、まだ三十歳くらいのときね、豊富な資金を親が出してくれて北京で薬屋をおこしたそうよ。
周口店は北京から50キロほどのところでしょ、寒暖の差は激しいけど古い遺跡があるのでよく遊びに行っていたそうなの、そうしたら大きな歯を拾ったそうよ、恐竜の歯だったのよ、それを削って薬として売ったら大もうけ。
北京原人の見つかった山は竜骨山って言うでしょ、恐竜の骨が出るのね、さらに恐竜の骨などをとってきて、長寿の薬にしたわけ、その中に人の歯があったの、でも自分の歯の形とはちょっと違うなと思っていたそうよ。北京原人のものだったのでしょうきっとね、それから竜骨山をくまなく歩いたようよ、まだ外国の研究者が北京原人の歯を見つける前よ」
「それでおじいさんは沢山の人を使って大きな店にしたわけだ、働いていた人たちは日本から呼んだのだね、その中に水良今氏の父親がいたわけだ」
「そう、まだ若かったけど、その人は帝大の薬学を出た人のようね、おじいさんもそうなの、きっと後輩だったのでしょう」
「終戦後は大変だっただろうな」
「いえそうでもなかったのよ、終戦間際にはまだ二十歳くらいだった哉有叔父がおじいさんの助けで新しい北京骨商を興して薬を作っていたので、軍に供給するので収入も安定していたし、魚の骨を使って薬を作るようになっていたので魚介類など食べるものは心配なかったようよ」
「どうして中国から引揚げたのだろう」
「1937年日中戦争が始まる前の年、大戦が終わる八年前に戻ってきたの、今だから言えるけど、おじいさんは日本が負けると思ったようよ、それで早く帰ったほうがいいと思ったのね、中国で働いていた人に北京骨商の建物や持っていたものをみんな分けてしまって、とても喜ばれて中国を離れたということよ、日本からきた人は一緒に帰ってきて、叔父の新たな会社で働いたわけ。
帰ってくるときは陸路でロシアのウラジオストックにいき、そこから船で戻ったということよ、それが一番近い道だったのかしらね。
北京骨商には大きな冷蔵庫があったんだって、電気もろくに引かれていない時代にね、アメリカ製の電気冷凍庫で何かが保存されていたということよ、ウラジオストックまで氷で冷やす大きな冷蔵庫で保存されていたものを運んで、それも船に積んで日本に戻ったというから、よほど大事なものだったわけ、後は日本のお金を沢山持って帰ってきということだわ、それを元手に、祖父の実家の薬屋を基礎にして、哉有叔父と一緒に新たな北京骨商を興したってわけ」
愛子の説明で会社設立までの詳しい歴史はよく分かった。
「依頼人の跡出という人は夢久家のことを知っているのじゃないかと思うふしがあって、そのへんを知りたいと思ってね」
「そうなのね、ということはやはり跡出馬盛という人物が分かると、解決が早くなるわけね、探す依頼人を探すというのは探偵小説にもないんじゃないかな」
「そうかもしれませんね、でも探偵小説は出尽くした観があるから、きっとそんなのもあるのではないですか」
逢手が口をはさんだ。
「そうね」
「哉有さんのコレクションが何か知りたいな、愛子さんは興味ないの」
「今は少しあるわね、昔哉有叔父には何度か尋ねたけど一切教えてくれなかった」
「哉有氏に聞いたとき、どのような返事をもらったの」
「いつか、分かる時があるだろうけど、俺が死んでからだな、相当勘のいいやつじゃなければ見つけることは出来ないだろうよと言っていたわ」
「どこにおいてあるかとか、どんなものとかと聞いたことあるの」
「もちろんあるわよ、遠くじゃないよとか、世界中のコレクターの中で俺が一番だとか、日本じゃ集める人はいないだろうとか言っていたわ」
「それじゃ、富山のどこかにあるわけか、それに日本人はあまり興味を持たないもの、または嫌がるもの、やっぱり骨かな」
「確かに日本では骨は気持ちの悪いものと思うかもしれないけど、西洋では魂の抜けた骨はただのオブジェね、コレクターのことは知らないけど」
「お爺さまは貝のコレクションをなさっていたけど、骨には興味をお持ちではなかったのかしら」
野霧が愛子に聞いた。
「なんと言ったらいいのかしら、哉有叔父と一緒に化石動物の骨はもっていたわよ、富山の家にはおいてあったわ」
「貝のコレクションは中国にいる時に始めたのでしょう」
「そうらしいわね、でも本格的になったのは日本に帰ってきてからのようよ」
「どうして売ってしまったのです」
「おじいさんからは直接聞いていないけど、父の話ではおじいさんが七十半ばにもう飽きたと言ってオークションにかけたということらしいわ、それですごいお金になったようよ、特に宝貝のコレクションがすごかったみたい、自然の貝だけではなくて、宝貝って昔は首飾りにしたり、お金の代わりに使われたりしたでしょ、そういうものまで集めたのよ」
「コレクターってほとんどの人は集めたものを死ぬまで持っていたいものだと思うけどね、もしやめるとすると新たに何かを集め始めたときなんだよね」
詐貸はそういう話を今まで何人かの知人から聞いている。本を集めていた人が本を全部売ってレコードを集め始めたり、車を集めていた人がすべて売ってオートバイにかえたりしている。集めるという性格を止めることはできないようだ。
「祖父の気が変わってほかのものを集め始めたということ」
「うん、それを哉有氏が受け継いでいたのではないかと想像したんだ」
「そうかもね」
「水良氏に哉有さんやおじいさんのコレクションのことなどを直接聞きたいな」
「それは大丈夫だと思うけど」
「一度話してみたいけど、その場を作ってくれるかな」
「いいわよ」
ということで、水良今氏と会う段取りをつけてもらうことにしてその日は話を終りにした。
「今日もお母様いらっしゃらなかったわね」
九品仏の駅に着いた時逢手がぽつんと言った。
北京原人
水良はいつでも会ってくれると愛子に言ってきた。北京骨商は電車で行くと富山から氷見線の越中国分駅だそうだ。
詐貸は愛子を誘って一緒に行くことにした。
東京から富山まで北陸新幹線かがやきに乗ると二時間十分で着いてしまう。詐貸たちは十時に東京駅に集まった。
「私、北陸新幹線はじめて」
逢手と吉都が最初に乗り込んで前後で二人ずつ腰掛けた。電車が動き出すと逢手は早速袋から菓子を引っ張り出して隣の吉都にも手渡している。詐貸は隣の愛子に富山の地図を見せた。
「愛子さんは富山に住んでいたことはないの」
「ええ、父親が東京に出てきてからできた子供だから、だけど私は小さいころからよく遊びに行ったわ、東京なんかよりもずーっと楽しいもの、いい海水浴場もあるわよ」
「越中国分に工場があるということは、哉有さんは富山から通っていたの」
「そうね、富山市内の家から自分で車を運転していた、今は水良の叔父の自宅になっているわ、戦前に建てられた家で十祖父が買ったものよ、哉有叔父もそこで暮らしていたの」
「水良氏も一緒に住んでいたのかな」
「子供の頃はそうだったらしいけど、高校を出て大学にいくようになってからは独立してアパートにいたみたい、大学を卒業してからは工場の敷地にある研究所に住んでいたわ」
「相当研究熱心だったんだね」
「薬学を出たのだけど、魚の発生、特に骨の発生の勉強をしていたわ、それも製薬につながる大事な研究だったみたい」
「奥さんはどんな人だったの」
「北京骨商の従業員だった人のようね、私が富山に帰っていたときは何くれとなく面倒をみてくれたわ、小柄な感じのいい人だった。大きな目の堀の深い顔、口数の少ない人だったわ、ちょっと佐里雄と似ていた、三十代で亡くなったのよ」
「ご主人だった佐里雄さんも早く亡くなってしまわれましたね」
愛子はちょっと頷いた。
富山に着いた。
「ここから、あいの風富山鉄道で高岡に行って、そこで氷見線に乗り換えて、越中国分駅で降りたら車でちょっといくの」
「長たらしい名前の電車だね」
「この辺りは春になると沖から風が吹いてきて、それが豊漁や幸福を運ぶ風だといわれているの、古くからあいの風って言われているのよ」
「ずい分洒落た名前なんですね、愛子さんの名前もそれからとったのですか」
野霧はいつも面白いことに気付く。
「そうみたいよ、父親がつけたの」
「だいぶかかるのかな」
「四十分ぐらいで着くわよ」
越中国分駅からはタクシーでワンメーターだった。工場の入口の守衛さんが愛子を認めてふかぶかとお辞儀をした。愛子はここにもよく来ていたのだろう。
「お嬢さま、社長が家でお待ちです」
そう言って守衛室の脇で止まっていた小型の自動車の扉を開けた。工場は相当広いとみえ、電気自動車が利用されている。運転手も愛子に挨拶をしてすぐに走らせた。敷地内にいくつもの建物が並んでいるのが窓越しに見えた。
工場の一番外れの高台に水良今の社宅はあった。車が上がっていくと、広く海が見渡せた。眺望のいいところである。
玄関先に電気自動車が着くと、すでに茶色の作業服を着た背の高い紳士が立って待っていた。水良氏のようだ。愛子が手を振って車から出た。
詐貸たちも後についた。
「おじさま」
愛子が声を掛けた。
「おお来なすった、久しぶりだね、探偵さんたちも一緒だね」
「ええ、お昼まだなのお腹空いちゃった」
いい年をしてずい分甘えている。
「作らせておいたよ」
水良氏は詐貸のほうに向かって笑顔で挨拶をした。端正な顔をしている。
「よく来られました、始めまして水良です、私もお会いしたいと思っておりました。愛子から話は聞いています、北京原人の頭骨を探しておられるとか、北京原人とは関わりがないわけではありませんが、紛失した頭骨については何も知りません、我々の会社のことでしたらなんでもお聞きください」
感じの良い紳士である。
「どうぞ、昼の用意をしておきましたから、食べながら話をしましょう」
ホテルのように広い客間に入ると逢手の眼がかがやいた。吉都も嬉しそうだ。
大きなテーブルに、刺身や寿司がならんでいる。
水良と愛子が並んで座ったので詐貸たちは反対側に腰掛けた。
「愛子がお世話になっています、詐貸さん、私の予想していた通りの人ですね、これからもよろしくお願いします」
どういう意味だろう。詐貸が浮かない顔をしていたのだろう。水良氏は続けた。
「昔、愛子がどうしても結婚したい相手がいるときかされた時には、愛子の父親も哉有も困りました、愛子には私の息子と結婚することが決まっていたようなものでしたから、大学に入る前までは愛子もそのつもりだったのですよ、我々も大学の理事などに様子を聞いたところ、学生時代に司法試験に通った秀才、いや天才だとか、一端は我々もあきらめようと思ったのですが、息子の佐里雄が愛子にあることを打ち明け、愛子も悩んだ挙句に佐里雄の気持ちを受け入れてくれたのです、そのことについてはまた詳しくお話しすることになるでしょう、まずお食事をなさってください」
水良の言うことに詐貸はちょっと困惑していた。昔のこととは思いつつもまだもやもやとしていたからだ、それがはっきりするのは嬉しい。
「美味しい寿司だわ、でも何の魚か分からない」
野霧が箸を動かし感嘆の声をあげる。
「そうでしょう、内の養殖所で作り出した魚です、まだ世の中にはだしていません」
「遺伝子操作ですか」
吉都が尋ねた。
「いや、遺伝子操作をやるには許可が必要だし、とても消費者には受け入れられないでしょう、古典的な方法で改良を加えた魚です」
「どういうことですか」
「同種のものは交配できるのはご存知でしょう、豹とライオンの雑種、レオポンができた、我々の研究所では魚で色々試みてきました。マサバとクロマグロの交雑を行ない子供ができました。鯖の大きさの魚で、中トロ並みの脂ののりの赤みをもち、味がとてもいい、我々はサバグロと呼んでます、体長3メートルで重さ400キロのマグロより50センチの鯖を養殖するほうが楽でしょう」
確かである。
「売るつもりですか」
「いずれ許可が下り、大量に養殖可能になったらそうしたいですね、今はまだ、北京骨商の従業員の間で食べているだけです。今はこの魚の遺伝子調査をしているところです」
「刺身もとっても美味しいわ」
野霧は嬉しそうに口に運んでいる。
「その貝や烏賊もみなそうやって作り出したものです」
食後のお茶がでた。詐貸は夢久家のことを話すつもりだったが、水良氏が北京骨商の中を見せたいと言った。
「夢久家のことを知っていただくためにも工場の中で行われていることを見ていただいたほうがいいでしょう」
水良は立ち上がった。
「私も工場の中のことあまり知らないわ」
愛子が後をついて部屋を出た。
「獲ってきた魚貝類を分類し出荷する建物と養殖場、一部を薬にする工場があります、それに、生命系の研究施設があります」
詐貸たちは玄関で待っていた二台の電気自動車に乗った。
魚を判別する建物の中は大きな魚市場のようであった。その漁猟長という人に会った。「いらっしゃいませ」と、漁師のイメージとちょっと違う静かな物言いの、小柄な毛深い男である。併設されている養殖場の建物は広く、三階には水族館のように小型のガラスの飼育ケースが並んでいて、孵化してちょっと育った小魚が泳いでいる。二階三階と大きな生簀がしつらえてあって、名前の知らない魚が泳ぎまわっていた。
薬の工場に連れて行かれた。建物の中は近代的な設備が整っており、廊下の大きな窓から見ると、マスクをした白衣の人たちが大きな機械についているメータをにらみながらなにやら操作をしていた。
にこにこと日焼けをした、人の良さそうな白衣を着た女性がやってきた。
「工場長です」
「よくいらっしゃいました、ここでは骨粗相症に聞く新薬を開発しています」と言って、その作用機序を説明してくれたが、どのように体の中で働くのか詐貸にはよくわからなかった。吉都にまかせておこう。
それらを見た後、生命研究所の入口についた。これまた大きな建物である。
研究所の二階に上がるとやはり白衣を着た人たちが忙しそうに動いている。培養室とか手術室とか書かれていると病院にきたような感じだ。
「ここでは動物や細胞を使って薬にしたものの作用を調べています」
水良社長みずから説明してくれた。
二人の白衣を着た男性が研究所長室と書かれた部屋からでてきた。一人はマスクをした背が高い老人で、もう一人は若くて背が低い。しかしどちらも研究者らしい端正な顔つきをしている。
水良が背の高い方を研究所長の壱岐さん、低い方を副所長の綿貫さんと紹介した。
研究所長が愛子に声をかけた。
「お嬢さま、久しぶりです」
「え、お会いしたことがあるのですか」
「ええ、まだ、小学校に入る前だったですか、お母様に手を引かれて、もちろん覚えていらっしゃらないでしょうね」
「こちら詐貸さん、探偵さん」
「壱岐長石です、お世話になります」
所長が詐貸に深々と頭を下げた。誰かの声に似ていると思った。
副所長が「私がご案内します、持ち物はこれに入れてください、こちらでおあずかりします」と籠を差し出した。
逢手と愛子はバックを入れた。
「どうぞこちらです」
副所長が籠を水良にわたすと、行く方向を指差した。
「私もちゃんと見たことがないの、よろしくお願いします、行きましょう」
愛子が詐貸たちを促した。
「愛子、僕は所長と話があるから、あとで詐貸さんたちと会議室の方に来てくれるかな」と水良は所長室に入ろうとして立ち止まり振り返った。
「詐貸さんにはすべてを見せてください」
副所長に念を押すように言った。
「五階もですか」
それを聞いた副所長の綿貫は驚いたような顔をした。
「うん、そうしてください」
所長も言った。
詐貸たちは副所長の後についていった。
「この建物は五階までです、一階は事務所と製品のチェックの場所、二階、三階は開発、四階、五階は先端研究センター、詐貸さんには四階と五階を見ていただきます」
副所長はエレベータで四階に我々を案内した。詐貸はおやっと思った。ほかの二人も気がついたようである。五階があるのにエレベーターは四階までであった。
エレベーターホールに降りたつと目の前にドアがあって、詐貸たちはその中に入るように促された。部屋の中は紫色の光に満たされ天井から風が吹いてくる。
「ここは消毒室です、無菌の風が頭の上からでてきています、次の部屋に帽子とーオーバーオールの服がありますのでそれをつけてください」
詐貸たちは用意されたものをはき、マスクをかけ、スリッパに履き替えるとその部屋から出た。
広いエントランスになっていて建物の中を見渡せる。大きな廊下が建物の真ん中にまっすぐに通っており両側に室がある。一番端の室が小さく見えるほど大きな研究棟である。
詐貸たちは廊下の窓から部屋中を覗いていった。部屋の入口は二重扉になっていてる。中では白衣を着た人たちが作業をしている。
副所長がそれぞれの部屋を説明した。遺伝子の調整室、細胞に遺伝子を入れる室、細胞を貯蔵する室、細胞を培養する室、細胞を卵細胞と精子に発達させる部屋、卵子と精子の保存室、しかし詐貸にはイメージが湧かなかった。逢手と吉都はうなずきながら覗いていく。
「発生実験ですね、すごい施設です」
「私には何も分からないわ」
愛子も言った。
「次は五階にまいります、第二エレベーターでしか行くことができません、こちらです」
副所長は詐貸たちを五階に降りたときに入った着替え室に案内し、彼らは再び殺菌室を通ってエレベーター室にでた。
「五階にはご自分の服のままで結構です」
四階まで上がってきたエレベーターの隣に5階に行くエレベーターがあった。その前には見慣れない器械が置いてある。
副所長はその機械に顔を近づけ、五本の指を手の形をした凹みにあてがった。
ゆっくりとエレベーターが開いた。エレベータの内部には良くわからない機械類がついていて赤や緑の光が点滅している。天井には監視用のカメラがある。きっとすべて記録されているのだろう。
詐貸たちが乗り込むと副所長がボタンを押してエレベータが上昇する。四階と五階の間だけを行き来するエレベーターである。すぐに五階についた。
「みなさんもこれに手をかざしてください」
副所長はエレベータの出口脇に設置されている手形のところを指差した。まず愛子が手をのせた。扉が開いたので愛子が降りる後を詐貸がついていこうとすると、副所長が押し留めた。愛子が降りるとすっと異常な速さでエレベータが閉まった。
「どうぞ詐貸さん手をかざしてください」
副所長の言うように手をかざすとまた扉が開いた。こうして愛子と三人が降り、副所長が最後に出て来た。
「ずい分厳重ね」
愛子も驚いている。
「私の顔が無いとエレベータは動きません、手だけでは開きません」
「ではどうして私たちの手をチェックしたの」
「帰るとき何人出たかチェックします」
詐貸は大変なものを見ることになるような予感がした。
「社長と所長がすべてお見せするようにと言われましたので、これから見ていただきますが、おそらく見ただけでは分からないと思いますのでご説明いたします」
エントランスに出ると、四階と同じように大きな廊下の突き当たりに室があり両側に研究室が見える。しかし四階とは違いそれぞれの部屋に窓は無く中の様子がわからなかった。エントランスに近い室は分娩室と書かれている。診察室と書いてある部屋もある。それ以外の部屋には番号が振ってある。突き当たりの部屋だけに窓があり中を覗くことができた。
中を見ると、子供が三人いる。三人の女性が付き添っている。
「保育所ですか」
しかし働いている人の子供を預ける場所がこんなところにあるわけはない。とすると中にいるのは特殊な子供たちなんだろう。
「そのようなものです、中に入っていただきます」
「白衣着なくていいのかしら」
「大丈夫です、衛生管理はしていますが、普通の部屋です」
みんな頷いた。
中はかなり広い。入口で靴を脱いでジュータンが敷き詰められたところにあがると、三歳くらいの子供がこちらを見た。いたって普通の子どもの顔をしている。
「今日は」
愛子が挨拶をすると子ども達がにこにこして近寄ってきた。
「はい」
女の子が持っていた絵本を愛子に渡そうとした。
「あらかわいい」
一人の女性が気がついて「はい、向こうで読んであげるね」とその子をソファーの方に連れて行った、
「こんにちはお嬢さま」
年配の女性が出てきて愛子に挨拶をした。
「あら、私のこと知っているの」
「先ほど所長から、こちらにいらっしゃることの連絡がありました。写真も一緒にありましたので、皆様のことも知っております。どうぞご覧ください」
ずい分大変な防御システムになっているようだ。
「誰の子供なの」
愛子も興味をそそられているようだ。
副所長がそれに答えた。
「この子達はみな北京原人です」
それを聞いてみんな声が出なかった。
「どの子も元気にすくすく育っています」
一人の男の子が走り出した。ちょっとヨチヨチしている。
「北京原人の子供って、どういうことです」
「あとで社長がお話しすると思います」
詐貸は子供たちをじっくりと眺めた。
「僕には普通の子と違いが分からないけど」
男の子が二人で取っ組み合いをしている。
「そうでしょう、外見ではわかりません、能力も変りません、ただ体質は違います、それは検査をしなければ分からないでしょう、まず寿命が違います、今の日本人の半分です」
子供たちはおやつの時間になったらしく、子供用のテーブルに集まった。女性からお菓子をもらうと椅子に腰掛けてお行儀良く食べている。
「あれが北京原人の子供なの」
野霧が不思議そうな顔をしている。
「どうぞこちらへ」
年配の女性が愛子たちを別の部屋に案内した。それぞれの子どもの寝室やいくつかの広い教室、遊戯室があった。それを見たあと、階段を上がって屋上にでた。そこには庭園あり、プールあり、走る場所があり、普通の小学校より格段の施設を備えたものであった。
「大きくなったらどうするの」
愛子の質問に副所長はうなずいた。
「もう少し大きくなったら研究所から出して遊ばしたりもします、様子を見て小学校に入れるような能力があるのならそのまま行かせます、もし問題がありそうなら、ここで教育をします。基本的には普通の子どもと同じ生活をさせるつもりです」
「もう言葉を話しているのね」
「はい、言葉は全く問題ありません」
「北京原人の子供がいるということは北京原人の親もいるわけですね」
詐貸が質問すると、吉都が、
「いや、遺伝子さえ手に入れば可能ですよ」
と言った。
副所長は首を横に振った。
「よくお分かりのようですね、だけど遺伝子操作により作りだされた子どもではありません、この子どもたちについても社長がお話しすると思います、これから会議室の方にご案内します」
こうして、何がなんだか分からないうちに五階からでて二階の会議室に向かった。
会議室というより、書斎のような雰囲気の、作り付けの本棚に囲まれた空間である。一枚板でつくられているテーブルが部屋の真ん中に置かれており、水良がすでに腰掛けていた。
「お待ちしていましたよ、いかがでした、北京原人の頭の骨の行方は私どもには分かりませんが、北京原人の子供がいたのにはびっくりされたでしょう」
「北京原人の子供だと言われても、ぴんときませんが」
「そりゃあそうですね、詳しくお話しましょう、壱岐さんは用事で出ていますので綿貫さんと供にお話しします」
水良が話し始めた。
「夢久十が北京骨商で冷凍にした大事なものを北京からウラジオストック経由で日本に持って帰ったことを愛子がお話ししたでしょう、北京から東京までは冷凍は出来なかったのですが、氷を変えながら極力低い温度のもとで持って帰ったものです」
詐貸はうなずいた。
「それは北京原人の死体だったのですよ、信じられないほど新鮮で、死んだばかりのようなからだだったのです。夢久十と私の父が周口店に行って薬の材料にする化石骨や角を探している時に、とある山の中腹に洞窟があるのを見つけました。二人で中に入ってみると、凍りつくように寒く、広くはなかったのですが奥はどこまであるか分からないほど長いものでした。後日改めて装備をもって入っていくと、ずい分曲がりくねった洞窟で、あちこちに枝道がありました。何回も行って調べていたところ、一つの洞窟の奥に池があって、その底に人が沈んでいたのです。池の底の水は凍る寸前の冷たいもので、しかも水に酸素成分が少なく、それだけではなく泉の特殊な成分が人のからだを保存するように働いたのでしょう、夢久十は死体を泉の水ごと凍らせ北京骨商で保存していました、日本に運ぶときは泉の水も出来るだけ運び、場所場所で凍らせてその氷を使って冷やし運びました。それを持って帰った夢久十は富山の実家の薬屋の冷凍庫に保存しました。
その北京原人は女性でした。公表は出来ませんが、すべて写真を撮ってあります。貴重な資料です、もし発表したら、あまりにも不思議なことですので大きな噂になってこの会社もおかしくなるでしょう、だから発表する予定はありません、ここに写真のファイルがあります、ご覧ください、そのころはまだ白黒写真です」
詐貸たちにファイルが渡された。映っていたのは浅黒い肌を持った北京原人の女性であった。すべてが写し出されている。詐貸は途中で見るのをやめた。
水良が話を続けた。
「夢久十の知り合いの研究者に、京都の大学の不妊治療で有名な医者がいました。さらに東京の大学に発生の専門家がいました。夢久十は彼らに北京原人を見せたのです。ただ、初期縄文人の遺体だと言ったそうです。
遺伝子に関しては解明が進んでいなかった頃です、その医者と発生学者は獣医師と供に人工授精を研究していたことから、北京原人、いや縄文人と思っていたわけですが、卵巣から成熟した卵を取り出し、復活させ精子と合一させたのです」
「戦後と言うと1945年よりちょっと後ということですか」
「そうです、人工授精は家畜などで行なわれはじめていたのですが、人では全く行なわれていませんし、倫理問題がありましたので、公にはできないことでした」
「その医師たちは縄文人の卵を使って人工授精を試みたわけですか」
「はい、最初その受精卵を一人の女性の子宮に戻したのです、妊娠は順調に行き、現代人と北京原人の二世第一号が誕生したのです、生まれたのは女性でした」
「精子は誰が提供したのですか」
「夢久哉有です、哉有も夢久十に協力していました、戦争も終わり新たな北京骨商が軌道に乗っていたころです」
「とすると、その北京原人二世は夢久哉有の娘ということになりますね」
「そうです、それが背は低かったのですが聡明で、不思議な力を持っていました。とても勘がいいのです、おそらく北京原人の持つ能力だったのでしょう、夢久十の家で育てられ、大きくなってから私の妻になりました」
その話も驚きだった。
「私も始めて聞く話だわ」
愛子も驚きを隠せないでいた。
「愛子さんのご主人だった人は、北京原人の血を引いた人だったのですね」
「そういうことになります」
愛子は夢久哉有の娘、すなわち従姉妹の子供と結婚したことになる。
「それだから叔父さんの奥さんは三十五より前に亡くなったのね」
愛子が納得の顔で頷いている。この話は愛子が一番驚いていることだろう。
水良社長は頷いた。
「それで佐里雄も三十四で死んでしまった」
まだ信じられない話である。
「私、佐里雄さんに寿命を打ち明けられたの、北京原人のことは知らなかったけど、遺伝的にそういう運命だって、子供のころから優しくしてもらっていたし、佐里雄さん自身も私と結婚することを強く望んでいたから、詐貸君と一緒になったらきっと彼は自分で命を落としていたでしょう」
愛子もそれを聞いて複雑な気持ちだったろう。悩んだのは詐貸にはよく分かった。愛子はとてもまじめな女性だった。彼女は佐里雄と結婚しても長くは続かないことを知って結婚したのだ。
「それじゃ、佐里雄さんは海で亡くなったんじゃないわけ」
詐貸が聞くと、水良も愛子も首を横に振った。
「海で死んだのは本当、遺体も見つかっていない、ただ佐里雄は自分で分かっていたのだと思うわ、船の上で立ちくらみか何かを起こして、これが寿命だと思って海に入ったのじゃないかと私は思っているの、優しい人だったわ」
詐貸はすぐには声が出なかった。佐里雄は自殺かもしれないのだ。ちょっとの空白の時間があったが、彼は気を取り直して聞いた。
「それで、あの部屋にいる三人の北京原人の子供というのはどのように関係してくるのです」
「その当時、卵をいくつか採取して発育させ、北京骨商に勤める女性や夢久十の知り合いの女性達から希望者を募って、十人ほどの子供をつくりました。それはすべて違う男性の精子を用いて行ないました。大きくなった北京原人混血一世は私どもの会社で色々な形で働いていました。研究をしている者、漁を行なっているもの、製薬に関わっているもの、能力は現代人と変わりありません、ただ北京原人は寿命が短い」
「私にも北京原人の血が入っています」
副所長の綿貫が言った。驚くことばかりである。
「そのうち二世たち同士が結婚して子供ができた。そこに問題があったのです」
「先祖帰りだ」
吉都が叫んだ。
「その通りです、先祖帰りが起きてしまった。遺伝的に純粋に近い北京原人が生まれてしまったのです。それがあの三人の子供です」
「なんです、先祖帰りって」
「進化をしていく過程で、昔の形質が現れてしまうこと、要するに古い生き物になってしまうことです、遺伝子の混ざり具合で元にもどってしまうのです」
「大変なことですね」
「そうです、それで北京原人の血が入っている者同士の結婚は避けるように今ではその者たちにお願いしています」
「その人たちは自分に北京原人の血がはいっていることを知っているのですね」
「はい、知っています、何も恥ずべきことは無いことも彼らは知っています、現代人以上の能力を発揮してくれているのですから、彼らも自信があります、ただ寿命のことを言うのはつらいことでした。そういうことで、今この研究所では、私が指揮をして北京原人の遺伝子の研究をしています。全く外部には知られていません、いずれそれにより寿命に関わる遺伝子を明らかにしたいと思っています。遺伝子治療で寿命を延ばしたいのです、その時は実験動物を使って正式に研究をした結果を世の中に出したいと思います」
「縄文人と思って人工授精した卵を子宮に移植した先生方は黙っていたのですね」
「先ほども言ったように倫理的に問題があります、だからその人たちは外部に言いませんでした。お一人はご存命で来年百歳を越えます。ただその技術は伝えられ、今の不妊治療の基礎となっています。それはその先生方の誇りだったと思います」
「今その話が漏れたら大変でしょうね」
「ええ、だけど信じる人はほとんどいないでしょう、この研究所の研究は魚を用いていますから、調べられても分からないと思いますよ」
「僕たちだけが知っているということになりますね」
「そうです、私の意志で決めたのです、詐貸さんにはすべて打ち明けました」
「どうしてでしょう」
「あとでお話したいと思います、まだ愛子にも言っていないことです」
水良の言葉に嘘はなさそうに感じた。しかし北京原人の子供となると、あまりにも不思議な話である。詐貸は頭の中が整理できない状態だった。他の二人もいつもより寡黙だ。
「今日は、私の社宅にお止まりください。風呂にでも入ってゆっくりしてください。部屋にはビールなども用意してあります、ご自由に召し上がりください。七時に夕食ということでどうでしょう、そのとき夢久家のコレクションのこともお話しましょう、きっともっとお聞きになりたいこともでてくるでしょうし」
詐貸たちは水良の社宅に送ってもらった。三階に客間がいくつもあり独りづつあてがわれた。ホテルの上等な部屋といった感じである。大きな風呂がついている。後で聞いたところでは外国からの客を泊めることも多く、富山のホテルに管理を任せているということである。
夜の食事も豪華だった。ボイルした伊勢海老や岩牡蠣が大皿に盛ってある。蛍烏賊の煮物、魚介類カルパッチョも器に入って置いてある。もちろん刺身もある。
「ステーキやノドグロはお食べになりたいときにおっしゃってください、それから焼きます、どうぞ好きなものをおとりになって召し上がりください、海のものはお手の物ですので」
コース料理ではなく、料理人がその日水揚げされたものを使って得意なものを作ってだすという一品形式である。好きなものを好きなだけとって食べる。ちょっと気楽で詐貸にはとてもありがたいことであった。
「詐貸さんは飲めるほうですか」
「先生は強いですよ」
野霧が口をはさんだ。
「好きなものを言ってください」
「ありがとうございます、ビールお願いします」
野霧と吉都は白ワインをもらっている。愛子と水良は赤ワインだ。詐貸には氷見の地ビールだった。
「今日は豪華ね、どうしたの」
愛子が水良に尋ねている。
「だって、大事な探偵さんをお迎えするんだから」
よくわからない返事をしている。
「私たちがきてもこんなに豪華じゃないわよね」
愛子がちょっと笑っている。詐貸は肝心なことを切り出した。
「夢久哉有氏のコレクションについてお伺いしたいのですが」
「はい、夢久家の人々に収集癖があるのはよく知っていました、ただ当時私は研究のことしか頭に無かったので、哉有さんの集めているものに関心を払っていませんでした、子供の頃は哉有さんがもっていた化石骨や十おじいさんの集めた貝は見たことがありますが、学生になってからは夢久家から離れましたからね」
「富山の街中にお住まいがありますね」
「ええ、今は私の家ということになっていますが社のものです、哉有氏の集めていたと思われるものはそこにはありません、むかしは動物の骨の類や北京からもってきたと思われるマンモスの牙などもありました」
「なぜ哉有氏は集めている物を周りの人に言わなかったのでしょう、愛子さんも知らないと言ってますが」
「愛子は東京で生まれていますし、富山のことはあまり知らないと思いますよ、お父さんの多助は知っていたのかもしれません」
「いやなぜ水良さんや愛子さんに言わなかったのかという点なのですが、世間に知られたらまずいものじゃなかったのですか」
水良はちょっと困った顔をした。頷いたようでもある。
「それと、夢久十氏が貝のコレクションを全部売ってしまったわけは、別のものを集め始めたからと思うのですが、どうでしょう」
「十おじいさんから売った理由は聞かなかったですね、哉有さんが飽きたんだろうと言っていたのは覚えています」
「愛子さんのお母さんのことあまり聞いたことがないけど、お母さんは知っているということはないですか」
「母は東京の人なので全く知らないでしょう、知っていたら私にも言ってるわ」
始めて愛子の母親のことを聞いた。
「私の住んでいる九品仏の家は母の家です、父が仕事を東京に移し、母と結婚したときにそこに住んだのよ」
なるほど少し分かってきた。
「それじゃ、お母さんは富山に余りおいでにならないのですね」
「私と同じくらい、私が子供の頃、一緒に富山で夏を過ごすのに来たりしているから水良の叔父様にはずい分世話になりました」
「まだお会いしていないけど、忙しいのですね」
「ええ、お華とお茶の先生をしているのでほとんど家にいないわね、もともと東京のそういう家の長女よ」
「愛子さんのお父さんのコレクションは根付でしたね、しかもいろいろな人の頭骨を彫ったものでした。本物を見たようによくできている」
愛子ではなく水良今それにが答えた。
「愛子の父親は根付が好きだったですね、彼は相当沢山持っていたのですけどね、世界にはもっとすごいコレクターがいます、それを知っていたので、頭骸骨の根付だけを集めるようになり、さらに自分だけの根付を作らせていました。頭骸骨根付に関しては世界で一番でしょうね、よく自慢していました」
「哉有さんも骨を集めていたのではないですか」
水良はちょっと考えた。
「いずれ科学博物館に寄贈するような、動物、特に哺乳類や化石哺乳類の骨格標本は持っていましたよ、しかしそれは仕事がらみのものでした。」
「哉有氏の集めた骨格標本は今でも富山の邸宅にあるのですか」
「いえ、八尾町の山奥にある別荘に置いてあります。亡くなってからくまなく別荘を調べたのですが、骨格標本以外にはなにもありませんでした」
そんな別荘を持っているとは知らなかった。
「実は夢久家の土地などを調べさせてもらったのですけれど、その別荘のことは引っかかってきませんでした、どうしてでしょう」
「土地も家も借りているからでしょう、名義は夢久のものではありません」
なるほど、それでわからなかったのか。
「愛子さんはその別荘のことは知っていたのですか」
「八尾町の別荘のことは知らなかったわ、私が富山に遊びに来ていた頃は動物、特に魚の骨格標本が家や工場においてあったわよ。子供の頃は気味が悪いと思っていたし、研究のためだよと父も言っていました」
「骨から薬を作っていましたから、夢久十と哉有氏の二人が集めたもので、別荘を借りてそこに移したのは哉有が亡くなる一年前でしたね、だから最近です、富山の街中の家や工場に入りきらなくなったのですよ、別荘は倉庫のつもりで借りたのです、あのころ、佐里雄のこともあり愛子に別荘のことが伝わらなかったのですね、この社宅が哉有氏のもっている本来の別荘でした、愛子も子供ころはよく遊びにきたものです」
「ええ、この家は海水浴場も近いのよ、工場もこんなに沢山建っていなくて、ちょっと離れていたわね、今は工場の敷地の端っこという感じだけど」
「明日にでも、八尾の別荘というのを見ることができませんか」
「いいですよご案内します、お時間があるのなら、いつまで泊まっていてもかまいませんよ」
とても寛大な申し出である。
次の日、みんなでその別荘倉庫に行くことにした。
富山市の八尾は古くからの町で、きれいな町並みがある由緒あるところであるが、別荘は町からかなり山にのぼったところにあった。小さな湖があり、裏には御高山がある。道にそった林を切り開いた奥まったところにある、木造二階建ての大きな屋敷であった。周りには他の家が全くない。道からは木々に隠れて建物があるのさえ分からない。
「この建物はこの辺りの資産家が建てたものですが、その方がなくなって、家族の方が使わないということなので、哉有氏が借りたのです、誰も住んでいません、セキュリティ会社に管理を頼んであります」
水良氏が玄関の鍵を開けて扉を開いた。ちょっと澱んだ空気の匂いが鼻についた。締め切ってあるためだろう。骨の匂いも混じっているのかもしれない。
「一階には五つ部屋があります、そこには魚の骨格標本があります」
すべての部屋に魚の骨の標本が整理されて、所狭しと置いてあった。学名の書かれているラベルが台に貼ってある。。
「見事なものでしょう、魚は今の北京骨商の大事な薬の元ですので、夢久十と哉有も集めましが、どちらかというと私が研究のために世界中から取り寄せて、次第に集まってしまった感じのものです。これはいずれ社宅の隣に魚の骨のミュージアムを建てて収納しようと思っています」
「私が小さいころ工場の隅にお魚の骨が置いてあった、こんなに沢山になっていたのね」
二階に上がると化石哺乳類の骨格標本が並んでいた。さすがにマンモスのような大型のものは置いてないが、頭骨だけはあった。やっぱり霊長類の骨格標本が中心のようである。進化の図が示されていて、それに沿って頭骨が置いてある。科学博物館なら大喜びだろう。
「夢久十と哉有はこの化石類は好きでしたね、力を入れていました」
化石の骨を見て回っていた詐貸はあることに気がついた。原人や新生人の頭骨が置いてあるが、北京原人の骨がない。それは失われているので当たり前だと一端は思ったのだが、そうではない。夢久十は北京原人そのものを水から引揚げて入る。
「水に入っていたという北京原人はまだ冷凍にされているということでしたね」
「ええ、細胞を調べるために、からだの臓器ごとに分けて冷凍してあります。すべての部位の遺伝子の詳細を調べているところです」
それを聞いて疑問はさらに深まった。骨に興味のある夢久十や哉有氏が北京原人の完璧な骨を放っておくはずはない。水良氏の話では臓器ははずしてあるという。骨はどうしたのだろう。しかし詐貸はそれを口にださなかった。
「すごい化石動物の標本ですね、いずれこれらも我々の目にも触れるようになるわけですね」
これだけでも一流のコレクションである。その上に哉有のコレクションがあるとすると、やはり人の頭骨を考えざるを得ない。
「はい、科学博物館に寄贈するかどうか分かりませんが、いずれ一般の人も見ることができるようにしたいと思います」
「この建物には地下室や屋根裏部屋はないのでしょうか」
「建築物の図面上にもそれはありませんでしたが、我々もそう思って細かく調べました、しかしものを隠せるような場所はみつかりませんでした」
詐貸たちは庭も散策した。隣接する林の中も歩いた。いい散歩になったが何かを隠せるような場所はなかった。他人の所有する土地である。細工をしても将来はどうなるか分からない。そのようなところを隠し場所にしないだろう。
詐貸はその夜の食事の時にも水良にいくつか尋ねた。
「水良さんは紫式部の墓を守る会に寄付していらっしゃいますね、何か関係があるのですか」
それを聞いて、水良はちょっと苦笑いをした。
「ははは、よく調べられましたね、ええ、あのお墓は島津機器の本社敷地にあるでしょう、うちの研究所では島津さんの器械をずい分使っていましてね、担当の人からそういう会があって、余裕がないという話を聞いて、寄付をしてあげました、私は歴史も好きですし、古典も好きです」
「小野小町の墓の管理にもお金を出していらっしゃる」
「ええ、小野小町は小野篁の孫でしょう、紫式部の会の人でこの篁にぞっこんの人がいて、孫の小野小町にも入れ込んでいて、その人から寄付を依頼されたものですからね、そういえば紫式部の墓が紫色のペンキで塗られたのは、やっぱり紫式部のファンでした、その篁の信奉者が電話で教えてくれました」
跡出も同じことを言っていた。跡出と水良は何か似ている。
「それに、お岩さんの墓の修復にもお金を出されている」
「ああ、それもご存知でしたか、あれはあのお寺から脇でマンホール工事をしていた振動が良くなかったんじゃないかと工事会社の方にクレームがいきましてね、その会社では多助さんの会社、私が顧問をしていますけど、その小型掘削機を使っていましてね、あまり振動しない優れている機械で、そのデーターを見せれば墓を倒すことなど起こることはないのが明らかですが、私のほうで寄付するからということで、穏便に済ませたのです。その工事会社はこれからという会社で、そこが発展すれば多助さんの会社も利益が上がると思ってそうしました」
納得できる話ではあるが、偶然としてかたずけていいものか詐貸にはまだ分からなかった。
水良氏は最後にこんなことを言った。
「この会社の研究所では、魚もですが北京原人の組織を使って寿命に関わるとても重要な遺伝子の研究をおこなっていることはお話ししましたね。それは人の健康に大きく役立つものです。解明には私の代では終わりません。あの北京原人の子供のことが知られてしまうとすべて壊れてしまいます。違法のことをやっているわけではないのですが、メディアに漏れればどんな形で批判が集まるか分からない。今のメディアは聡明、賢明とはいえない部分がある。もちろんもれないように万全をきしています。
そういったことがちょっと何かの形でもれたとき会社をどのように守るか、北京骨商の弱点は法律に関わるガードです。いま顧問弁護士が複数いますが、その連中は経営のことを任せています。彼らは研究のことを知りません。そういう点で第三者の立場で意見を言ってくださる法律家の方が欲しいと思っています。どうでしょう詐貸さんお引き受けいただけないでしょうか」
これにはびっくりした。そんなことが自分にできるわけはないと即座には思った。科学音痴である。
「僕に向いているかどうか考えてみないと」
詐貸は断るでも引き受けるわけでもない返事をした。
愛子はただ頷いていた。
次の日、東京に帰ることにした。
詐貸たちは水良今に北京原人の三人の子供については他言しない約束をした。今やっている仕事が片付いたら提案の件は返事をすると言った。
余計なことには首を突っ込みたくないという詐貸の性格でもあった。ともかく依頼された北京原人の頭骨を追うことと、その依頼人を知ることである。北京原人の頭骨を見つければ依頼人跡出馬盛に会うことも出来るが、難しいことだろう。
電車の中で愛子が「なぜ跡出馬盛の事を聞かなかったの」と不思議そうな顔をした。
「俺の勘かな、言わない方がいいんじゃないかと思ったんだ」
「水良の叔父も詐貸君が富山に出向いたのは、北京原人探しのためだけじゃないことはわかっていると思うんだけど、叔父もあまりその点は聞いてこなかったわね、むしろなぜ詐貸君にあの研究所を見せてしまったのかな」
「嘘は言っていないということを示してくれたのかな、それにあの依頼は本気かもしれないな」
「私を佐里雄さんと結婚させてしまって、詐貸さんに悪いことをしたと思っているのかも知れないわ」
愛子は笑った。そのようなこともあるかもしれないが結婚相手を選んだのは愛子で、水良今のせいではない。ただ佐里雄のいない今、愛子に自由にやりなさいといっているのだろうか。
「詐貸君なぜ結婚してないの」
詐貸は愛子を見た。愛子の考えていることがちょっと分からない。
「自由と一人がいいのかな」
詐貸は当たり障りの無い返事をした。
二人の依頼人
事務所に入ると別世界のような感覚におちいった。巣鴨はやっぱり落ち着く。
富山から帰って、詐貸は跡出に電話を入れた。
電話に出た女性が「跡出さまはちょっとの間旅に行かれています、お急ぎでしたら私のほうから探偵事務所に電話するように伝えます」ということだったので、「特に急がないから帰ってきたら電話が欲しい」と伝言をたのんだ。
「水良は俺に北京原人探しを頼んだ人間を知っているな」
「どうしてですか」
野霧が尋ねた。
「水良も跡出も紫式部のペンキを塗った犯人のことを知っていた。ということは、あの式部の会にどちらも関わっている」
「紫式部顕彰会ですね」
「そう、それと跡出馬盛は演技をしている、頼まれてやっている、きっと水良を知っているか、夢久家を知っている人物だろう」
「北京原人の血を引いた人と跡出さんと関係があるのでは」
野霧が鋭い指摘をした。それは詐貸が哉有の八尾の別荘で不審に思ったことを思い出させてくれた。水に浸かって腐らなかった北京原人の女性の骨はどうして標本にしていないのだろうかという疑問だ。
そのことを野霧と可也に話した。
「先生、確かにそうですね、水良さんは何か隠していますね」
「盗まれたのじゃないかな」
「そうですね、盗まれたのなら探すでしょう、きっと誰かに依頼するはずです」
「だけどあの骨は公には探せないよ、北京骨商の従業員の多くは北京原人の血が入っていることが世間に判ったら大変だ」
「だから、間接的な方法で先生を引っ張り出したかったんじゃないかな」
吉都もなかなかいい推測をする。
「失われた北京原人の頭骨を探していることが知られると、夢久十が見つけた遺体の骨をもっている人間が現われる可能性がないわけじゃない、跡出馬盛は水良が依頼した人間かもしれないね」
「その可能性もありますけど、それならどうして先生を最初から富山に呼んで、研究室を見せて、依頼しなかったのでしょうね」
「俺のことが信用できるかどうか分からんだろう、愛子に聞くことはできなかったと思うよ、愛子に俺のことを聞く理由を問い詰められたら困るからな」
「夢久十の見つけた遺体の骨はだれが盗んだのでしょう」
詐貸は「それだ」言った。
「北京原人の遺体の骨を知っていたのは、夢久十、夢久哉有、水良今、それらの人に関わる人間ということになる、水良を除くと十か哉有だが、十は先に亡くなっているから、哉有ということになりはしないか」
「そうですね、哉有がもって行ったけど、ありかが分からない」
「そうだよ、哉有が自分のコレクションに加えたんだ、水良は遺体の骨は誰がもっているか知っていた、しかしどこにあるか知らない」
「先生その通りですね、哉有のコレクションのありかが分かれば水良の探している北京原人の骨は見つかるということですね」
詐貸は頷いた。水良もそれが知りたいのだろう。
ともかく、詐貸探偵事務所は二つの北京原人の行方を探すはめになった。
「ずい分混戦してきた,おそらく一つ紐が解けると、一気に絡んでいる紐がすべて解けるような感じがする」
「探す方法を思い切って変えるほうがいいのではないですか」
逢手が言ったことで、吉都がこんなことを思いついた。
「先生、秘密裏に北京原人の骨を捜す必要があるのですか」
「いや、跡出はそれを秘密にしろとは言っていない、探し方は任せられている。いままでの活動だって公にやってきたわけだよ、北京原人の骨を捜していることはもう知られているよ。本当の目的は分からないだろうけどね、我々もわからないんだから」
「とすれば、新聞に周口店の北京原人頭骨について情報求むとでも出してみたらどうでしょう、研究のためにとして」
「面白いわね」
野霧が相槌をうっている。確かにそうだが。
「反響が大き過ぎないかな」
「SNSほどじゃないと思うからいいんじゃないかしら」
野霧が言った。
「行き詰った時、すべてを壊すと、そのほころびから新たなものが飛び出すことがある、よし、それをやってみよう」
詐貸は二人に言った。
「野霧君、文面を考えてくれるかな、主要紙に載せる手続きお願いするね、大事な情報には謝礼を出すと書いてくれ」
野霧のまん丸な顔がひしゃげた。嬉しいのだ。早速作業にかかった。
「可也君は寄せられた情報を整理するリストをPCに作っておいてくれないか、忙しくなるぞ、大事なデータだけを拾い出さなければ」
「はい、すぐにやります」
重要な情報がくれば調査に飛び回らなければならない。資金はたっぷりあるが三人でやり切れるだろうか。
こうして日曜日の新聞第一面の広告欄に載せた。
(北京原人の頭骨、情報をお持ちの方は連絡ください、重要情報には謝礼―詐貸探偵事務所)
最初の反応は跡出馬盛からの電話だった。
「詐貸さん、とうとう新聞に載せたのですね、うまくいくといいですが、果たしてどんな情報が来るか、がせねたが多いと思いますので大変になりますよ」
跡出も良く分かっているとみえる。
「ええ、すみません、こちらも打つ手がなくなってきてこうなりました。許可のお電話をしたのですが、ご旅行だったそうで勝手にやってしまいました」
「ええ、一昨日帰りました、新聞広告かまいませんよ、費用がかさんだでしょう、追加が必要なら言ってください」
それで電話が切れた。
新聞に載せた日からメイルでかなりの数の情報が寄せられた。もうすでに物の本に書かれているような内容のものが多い。謝礼ほしさだろう。まじめに詳しく書いてあるようなものには御礼だけの返事をした。
二日目の吉都が作ったリストの中に調べた方がいい情報が一つあった。東北の古い病院の院長からのものである。昔からある頭骨の標本の中に古くて現代人のものとは違いそうなものがある、北京原人のものかどうか分からないが、役に立つことがあるだろうかということだった。
吉都が北京原人頭骨の写真を持っていさんで出かけていった。北京原人の頭骨が日本にあると考えている外国の研究者から依頼されているということでつじつまを合わせるように可也には話しておいた。違うものであっても十万ほどの御礼を包ませた。本物ならまた別の形で交渉をする必要が出てくる。
帰ってきた可也は、
「若い医者で、父親が亡くなったので病院を継いだばかりだということでした、色々整理をしようと思っていたところに新聞広告が出たので連絡したと言っていました。見ると確かに古代人の骨のようですが、原人ではないと思います、縄文の初期の辺りの骨だと思いました、古代人の専門家に見せたほうがいいと助言しておきました。その方にはお礼を渡してきました」
そう言って写真を見せてくれた。確かに似た感じではある。
いくつかの面白そうな情報はあった。庭の隅から出てきた骨がそうじゃないかというものは昔墓場だった土地に家を立てた持ち主からだった。竹薮に転がっていた骨だとか、高校の生物の準備室にあった骨だとかあったがみな違った。
一つ興味を引いたのは、かなり名の知れた画家からの連絡だった。スケッチ用にいくつか頭骨を購入したのだが、他の骨と違うものが一つあるということだった。画家なので目は確かだろう。
それで詐貸も吉都と一緒に訪ねて行った。信州の画家の家にいくと、大きなアトリエに沢山の頭骨が置いてあった。
「これはみな骨格標本屋から昔買ったものです、その当時インドは骨を輸出していたということでした、みな本物の骨ですよ、その中の一つ、ほらそれ北京原人の骨に似ているでしょう、前からそう思っていたのですよ」
彼が頭骨を一つとって詐貸たちに差し出した。確かに北京原人によく似ていた。ちょっとつぎはぎになっているのは掘り出した骨を組み立てたようにも見える。詐貸には本物の北京原人の頭骨に見えた。
ところがそれを見た吉都は「北京原人の骨ではなさそうですね」と言った。
「どうして」
詐貸が聞くと吉都は頭蓋骨の表面の筋を指差した。
「ほら、表面も縫合線もきれいですね、長い間曝された骨だと縫合線に塵がしみこんで黒ずんで汚れていたりするのですけど、まだ新しいような気がします、それに眼窩の上の出っ張りが弱いと思います」
「なるほど確かにそうだな、骨の表面は他の骨とあまり変わりがないね、いい目をしてるね、君は」
吉都は有名な画家に褒められてまんざらでもなさそうである。
「先生、お時間とらせてすみませんでした、ありがとうございました」
「いや、面白かったよ、北京原人の骨は私も興味があったので、そうならいいと思っていたのですよ、誰が頭骨を捜しているんですかね」
「外国の研究者から間接的に依頼されました。日本にあると考えている人です」
「だけどなぜ探偵社に依頼したのかね」
「すでに医学部を中心に探されたそうです、なにも見つからず、違う手法で探そうと考えたようです」
「そうなんですね」
お礼の十万を渡すと、
「いや、いいですよ」と固辞された。それでもと渡すと、画伯の書いた茸のスケッチを一枚いただいてしまった。そのほうがずーっと高いものである。
新聞に載せて一週間経つとほとんど連絡が来なくなった。新聞記事の寿命といったところだろう。SNSなら拡散して、もっと長い間連絡が来るに違いない。そのころ週間誌が取材にきたが、研究のために依頼をされたことを話すと、記事にならないと思ったのか早々に引揚げた。
「日本国民は北京原人の骨にはもう興味がないようだね、ご苦労さんでした、蕎麦をごちそうするよ」
昼に二人を誘って西巣鴨のいつもの蕎麦屋に行った。
「おそろいで久しぶりだね、新聞見ましたよ、面白いものを探してるね、俺は骨なんかやだな」
主人は笑いながら蕎麦の用意をはじめた。
「今日は松本の蕎麦だよ」
みんな天麩羅蕎麦を頼んだ。ここは温かい蕎麦はない。天麩羅は何種類かの野菜から四つ選んで揚げてくれる。それを食べ終えるころ蕎麦をゆでてくれる。しし唐に衣をつけながら店主が言った。
「そうだ、前に話した詐貸さんのことを聞いた人がまた来てね、どんな人か尋ねたよ、だから助手が二人いるやり手の探偵さんで、何でも見つけちまうと言っておいた」
主人が笑っている。
「そしたらどうでした」
「俺も頼もうかななんて言ってたよ」
「どんな格好でした」
「四角い顔の髭を生やした爺さんだ、ちょっと洒落た背広を着ていたな」
「知らない人だな」
「詐貸さんの探偵事務所とうちはかなり離れてるのにまた聞きにきたということは、詐貸さんがここにくることを知っているんだね」
それを聞いて、揚がった天麩羅を塩をつけて食べ始めた野霧がはっと顔を上げた。
「その人は先生のことを知らないのね、もしかすると依頼人」
「いや依頼人はすでに僕のことをよく知っていると思うよ、代理人も来ているしね」
「そうだわね、それじゃ、あの依頼人に関係ないけど、北京原人の頭骨に興味のある人だわ」
「新聞記事を見て、探している物を知って改めてここに来て、俺のことを聞いたのだろうかね」
「もしかすると、その人先生の探偵事務所を調査していますよ、事務所の辺りで聞き込みをやっているのじゃないでしょうかね、あとで周りの店に聞いてみますよ」
吉都が思いついたように言った。なかなかいいところをついた。
「探偵事務所というのはなかなか複雑なんだね」
聞いていた主人が笑った。
吉都が探偵事務所の近くの店や寺の人に聞いたようだ。電気屋の奥さんが探偵事務所の場所を訪ねられ、そのときどんな探偵さんと聞かれたという。若い方で挨拶はよくしますよと答えたそうだ。寺の墓守も探偵事務所のことを尋ねられ、そこで働いている人とよく話をすることや、まじめそうな探偵事務所だと答えたという。吉都のことを知っているじいさんだ。お岩通りに昔ながらの小さな和菓子屋があるが、そこのばあさんも聞かれたけど、どのような探偵さんか知らないと答えたらしい、ただそこの秘書さんのような人がお菓子をよく買いに来ると言ったという。野霧のことだ。そこはアイスクリームも置いてある。どんな人に聞かれたのか尋ねると一様に、背の低い髭を生やしたおじいさんだったと言った。蕎麦屋で尋ねた人と一致する。丁寧な言葉遣いだったと一様に言った。
それからに三日してからである。電話が鳴った。詐貸が受話器をとると、相手は
「あのう、新聞にあった北京原人の頭の骨は見つかりましたかと」と切り出した。
新聞には頭骨を捜しているとは書いていない。この人は頭骨に興味のある人に違いない。
「どなたでしょう」
「私も趣味で北京原人のことを調べているのですが、もし見つかったなら見て見たいと思いまして電話しました」
「いや、まだ見つかっていません」
「見つかりそうでしょうか」
「分かりませんが、見つけたいものです、何かご存知のことありますか」
「いえ」
「一般には、周口店で見つかった骨は船でアメリカに運ぶ途中に船ごと海に沈んだことになってますが、日本にあると思ってらっしゃるのですか」
「あ、そうですね、中国の遺骨などに混じっていないかと思って」
この人は何か知っている。詐貸はそう直感した。跡出と同じことを考えている。
「そんなこともあるのでしょうか」
「いや、ちょっとそんなことを思っただけなのです」
「もし、他に何かご存知のことがあったら、こちらの方で教えていただきたいものです。もし発見できたらご連絡差し上げます。依頼人に確認を取って、お見せできると思います」
「見つかったら連絡くださるというのですな」
「はい、連絡先とお名前を教えてくださいませんか」
相手は電話番号を言った。名前はと聞くと「跡出馬盛、遺跡の跡と出るで、あとでといいます」と答えた。
詐貸は受話器を取り落としそうになった。こんなことがあるのだろうか。跡出馬盛が二人になった。電話の主の電話番号が依頼人の跡出馬盛のものとは違うし、声も違う。これは慎重に事を運ばなければならない。
「よろしくお願いします」
第二の跡出は電話を切った。
詐貸は電話を置くと、あわてて野霧と可也の机のところに椅子をひっぱっていった。
二人は驚いて詐貸を見た。
「大変なことがおきた、跡出馬盛が二人になっちまった」
「どういうことです」野霧が食べようとしていた鴬餅を紙の上に置いた。
「今、跡出馬盛から電話があった」
「それがどうしたのです」吉都がPCから目を上げた。
「依頼人ではない跡出馬盛だ、声も電話番号も違った」
「それでなんと言う電話だったんです」
「北京原人の頭骨が見つかったら、見たいという電話だ、おかしなことに、北京原人が遺骨の中にまぎれているのではないかと思っていると言っていた、これは依頼人の跡出馬盛が言ったことだ、それで清掃会社の調査をしたわけだよな」
二人とも頷いた。
「偶然同じ考えを持つことも考えられますけど、そうでないとすると、先の跡出と電話の跡出はどこかで同じ話を聞いているわけですね」
「電話の跡出さんは清掃会社に出資している人じゃないでしょうか」
吉都が気がついた。
「そうだ、これで最初の依頼人の跡出と清掃会社の跡出は完全に違う人物ということが分かったね、どちらも北京原人をおいかけている」
一つ進歩だ。
野霧は食べようとしていた鴬餅を口に入れた。
それをあわてて飲み込んで言った。
「先生、依頼人の跡出さんに電話して、北京原人の骨が中国の遺骨に混じっていると思っている人から連絡があったと言ってください、どのような反応をするか」
確かにそうである。さらに何かが開けそうな予感がした。
詐貸は自分の机に戻った。
依頼人の電話番号を固定電話でかけた。いつものように秘書という女性が受話器をとった。
「もしもし、詐貸ですが跡出さんお願いします」
「はい、ちょっとお待ちください」
今日はいるようだ。
「詐貸さん、なんでしょう、新聞に載せて何か反応がありましたか」
「ええ、北京原人に興味を持っている人から電話があって、見つかったら見たいそうです。それに、その人は中国の遺骨に混じっているのではないかと、跡出さんと同じようなことを言いました」
「ほう、それはずい分研究をしている人ですね、名前はなんという人です」
「いや、電話番号しか聞きませんでした」
あえて名前は言わないでおいた。どっちかが贋物の跡出馬盛である。
「私のほうで調べてみましょう、電話番号教えてくれませんか」
詐貸はちょっとだけ躊躇したが、大金をもらっている依頼人である、机の上の紙に書いておいた電話番号を読み上げた。
「いい情報になればいいですね、ありがとうございました、これからもよろしく頼みます」
と電話が切れた。
「どうでした」
二人が詐貸を見た。
「あの反応はどういったらいいのかな、驚いてもいなかったし、喜んでもいなかった、なんとも読めないな」
「あえて、驚いていることを隠していたんではないでしょうか」
そうかもしれない
捜索の終了
ところがそれは一気に解決に向かうものだったのである。
一週間経った月曜日の朝、一本の電話が詐貸にかかってきた。
「おはようございます。水良です。すべて解決しました。お会いしたいのですがいかがでしょうか」
何が解決したというのだろう。
「私はかまいませんが、いつそちらに伺ったらよろしいのでしょうか」
「いえ、私は今東京にいます。愛子も呼びます。お迎えの車をやります。明日二時ごろいかがでしょうか」
ずい分急だ。
「ええ、私一人でしょうか」
「いえ、どうぞ助手のお二人も一緒においでください」
「わかりました、お待ちしてます」
詐貸はそのことを二人に伝えた。
「何が解決したというのでしょうね、あの北京原人の子供のことでしょうか」
野霧が不思議そうな顔をした。
「それなら、我々を呼ぶことはないでしょう、哉有のコレクションがみつかったのかな」
吉都は首をひねった。そういえば迂闊にもどこに行くのか聞き忘れた。改めて電話してもいいが、明日になれば判ることだ。
「北京原人の骨のことに違いないが、富山で水良は関係ないと言っていたよな」
「やっぱり関係あったのですね」
次の日、黒塗りのハイヤーが時間通りに探偵事務所の脇に止まった。三人はそれに乗り込んだ。
ハイヤーは白山通りから千石一丁目で右折した。不忍通りを進み目白台二丁目で右折した。目白通りである。日本女子大や東京カテドラル聖マリア大聖堂のある方向だ。詐貸の出た大学も近い。目白台三丁目に来ると、細い道をそのまま直進し、住宅街の中に曲がっていった。
車は一般の住宅の立ち並ぶ中のちょっと広めの庭を持っている住宅の前で止まった。その家はおそらく昭和はじめに建てられその後増築したものであろう。いい建材を使っているようだが外観は普通の瓦屋根の二階屋である。玄関はよくあるガラスの格子戸でまん丸な白い玄関灯がつけてある。
運転手が「つきました」と車から降りて後ろのドアを開けてくれた。
家の玄関が開くと水良が出てきた。その後から愛子が出て来た。誰の家なのだろう。
三人が庭に入ると水良がやってきた。
「詐貸さん、いろいろありがとうございました、ここが夢久十と哉有のコレクションの家です。二人で集めたものがここにあります」
やっぱり哉有のコレクションだ。だがなぜここのことを知ったのだろうか。
「詐貸君、入って」
愛子が玄関に向かっていく。詐貸たちもあとについた。玄関は何の変哲もないありふれた造りである。ただ昭和の家なので靴を脱ぐための石が置いてある。玄関に腰掛けて靴を脱いで上がると案内されたのは十畳ほどの畳みの間で真ん中の欅のテーブルの周りに座布団がおいてある。一角に品のいい白髪の和服の女性が座っていた。詐貸たちが入っていくと立ち上がった。詐貸がどこかで見たことのある女性だと思っていると愛子が紹介してくれた。
「私の母です」
「愛子の母です」
その声を聞いたとき詐貸は思い出した。最初に跡出の使いと言って一千万円の現金を持ってきて契約書を交わした女性である。その時は髪が黒く洋装だったのでだいぶ感じが違う。ということはやはり愛子はこの件を知っていたのだ。
愛子は詐貸の考えたことを感じ取ったようだ。
「詐貸君、母は跡出の使いとして探偵事務所に行ったようだけど、私は全く知らなかったの、あとで水良叔父が説明します」
「申し訳ありません、愛子の全く知らないことです」
白髪の女性は頭を下げた。
「いえわかりました」
詐貸は複雑な気持ちで、他の二人と並んで床の間を背にして座った。水良は愛子の母の隣に座った。
そこに老人がお茶を運んできた。四角い顔に髭を生やした背の低い男だ。
水良が言った。
「この家の主人、跡出馬盛さんです」
この人が蕎麦屋で詐貸のことを尋ねた人だろう。二番目の跡出馬盛だ。依頼人の跡出馬盛は誰だろう。跡出は水良の隣に座った。
そこに「遅くなりました」と紳士が入ってきた。
北京骨商の研究所長、壱岐長石だ。
「壱岐です、詐貸さんすみません、私が跡出馬盛と名乗って、北京原人の頭骨探しの依頼をしました、水良社長に頼まれたことです」
その声は確かに依頼人の声だった。富山で会ったときマスクをしていた意味がわかった。その時もどこかで聞いた声だと頭の隅で思った。
北京原人の頭骨探しは水良が仕掛けたことがこれではっきりした。大筋は詐貸たちの推理が正しかった。
「すべてをお話します。騙すような形になったことをお詫びします、しかしこうやってすべてうまく行ったのは詐貸さんのお陰です、ありがとうございました」
「愛子さんも知っていたのですか」
「愛子は何も知りません、話したら反対したでしょう、詐貸さんを騙すことなど愛子にはできないことです」
詐貸はちょとほっとしていた。
「本当は失われた北京原人の頭骨ではなく、別の北京原人の骨格を探したかったのです」
「夢久十さんが周口店で見つけた水に浸かっていた北京原人の骨ですね」
「おわかりになっていましたか」
「水良さんが、臓器を取り出して冷凍保存をしたとおっしゃった時に気付きました、骨はどうしたのかと疑問に思いました」
「あ、そうですね、さすが探偵さんですね、私はそこまで考えずに話してしまいました」
「その骨はどうしたのですか」
「きれいな骨格標本にしました。完璧です、それを見たら世界も驚くでしょう、ただ外には出さないつもりでした。ところが夢久哉有が自分がもらうと、もって行ってしまったのです。社長ですからしょうがないのですが、それでうすうす彼のコレクションが骨であることには気がついていました」
「十さんも関係していたのですね」
「いいえ、哉有が北京原人の骨もっていったのは十おじいさんが亡くなってからです、それまでは別荘、今の私の社宅の一室に大事に保管していました」
「そのコレクションの場所を探したのだけどわからず、跡出馬盛氏の名前で私に北京原人の頭骨探しの依頼をなさったわけですね」
「はい、その通りです、どういう人に依頼していいのか途方にくれていたのですが、何でも見つけてしまうと評判のいい探偵事務所があると東京の知人が教えてくれて、それで詐貸さんを知ったのです、最初は愛子の同級生の詐貸さんとは思っていなかったのですが、愛子の母親が契約金を持っていった時に、どこかで見たことがあると気付き、愛子のもっていたサークルの写真を思い出して私に連絡してきたのです。
まさか愛子のことから夢久家が分かってしまうとは思いませんでした、さすがです」
「この逢手が思いついて、吉都が調べ上げたのです、私のほうも驚きました」
「しかし、私どももだんだん気持ちが変りまして、私の作った北京原人の骨格標本が見つからなくても、詐貸さんには会社のことをいつかお話して、手助けをお願いするつもりでした」
「跡出馬盛さんが二人になった時には驚きました」
「跡出馬盛さんは富山でお話した人工授精で誕生した北京原人と現代人の遺伝子の入った一人です。大きくなってからいつの間にかいなくなりました、私は直接跡出さんには会ったことがありませんでした。大学院で研究している時、十さんから北京原人の死体を中国からもってきて凍らしてあることを言われ、その子供がいることまで聞かされた時にはびっくりしました。私が博士課程に進んだとき、十さんや哉有さんから知り合いだという若い女性を紹介され、結婚を勧められました。大学院の費用や生活費は十さんがだしてくれるということで、一緒になり子供が生まれそれが佐里雄です。その時、哉有さんが、北京原人の寿命のことを教えてくれて、妻が北京原人一世であって、哉有の娘だと知ったのです、それで北京原人の遺伝子が入った人がどれ程いるのか調べました、北京原人一世の人は北京骨商で働いている人や、大学に行っている人色々いたのですが、跡出馬盛さんだけ消息不明になっていました、それで跡出さんの名前はおぼえていました。
跡出さん特に若くして死んだと哉有は言っていました。何らかの原因でなくなったのだろうと思い彼の言うことを信じていました。詐貸さんに依頼するとき跡出の名前を思い出しその名前を使いました、あの完璧な北京原人の骨格は跡出馬盛さんの母親のものです、それで母親の骨を捜す人の名前として相応しいとも思ったのです」
確かにそうなるわけである。
「跡出さんという従業員の精子をつかったわけですね」
「その通りです、その方はもう亡くなっています」
「産みの母親は分かっているのですか」
「愛子のおばあさんです、愛子のお母さんのお母さんは中国に住んでいて、北京骨商の人たちが戻る船でたまたま一緒になり、東京に戻る前に富山に滞在されました、東京に戻ってからも夢久家と交流があり、夢久十の人工授精の話を聞いて協力してくれることになった女性の一人です。そこから生まれたのが跡出馬盛さんです」
愛子のお母さんと跡出馬盛は同じ女性から産まれたことになる。
「跡出さんを生んだ愛子さんのおばあさんは結婚されていなかったのですか」
「はい、お相手は軍人で中国でお亡くなりになっていました、愛子のおばあさんは馬盛さんが生まれてしばらくしてから、夢久十の計らいで東京の茶道の家柄の人と見合いをして結婚し子供を産みました。それが夢久多助と結婚したの愛子の母親です。それもあって多助は東京で事業をおこしたわけです。
今度のことは私が愛子さんのお母さんに頼んだことです、その時点で目的を話しました。うちの北京原人の骨を捜すということです」
詐貸はおかしなことに気づいた。後の依頼人、本当の跡出馬盛が北京原人混血の一世だとすると、年は夢久多助や水良今と同じほどか上だろう。なぜ生きていることができたのだろうか。
水良がそれを説明した。
「他の一世の人と違ってからだが年をとるのが遅く、若々しかった跡出馬盛さんを不思議に思った十と哉有は、見守るつもりもあって、東京のこの借家に住まわせて自分のコレクションを管理することをさせたのです、哉有は仕事のことで東京に良く出て来ました。そんなこともあってこの家を見つけたのでしょう、今この家は跡出さんのものになっています」
「この家のどこかにコレクションがあるのですね」
「はい、二階はすべてそれで埋まっています、あとでご案内します」
「だけど哉有さんが亡くなって、跡出さんはなぜ水良さんに連絡しなかったのです」
「絶対に富山に行っちゃいかん、連絡をしてもならん、この家をしっかり護れ、と殿様に言われておりました、殿様は東京にこられるたびにこの家に寄り集めた頭骨を磨いていらっしゃいました。ただ決して泊まろうとしませんでした」
はじめて本物の跡出馬盛が口を開いた。跡出馬盛を殿様と呼んでいるところを見ると、相当服従心の強い人なのだろう。
「哉有氏が亡くなったことをどうして知ったのですか」
「亡くなってすぐに、名前は出せませんがある人から連絡が来ました。殿様は俺が死んだときは、全部お前にやる、完成させろとおっしゃっていました。わしが一生食べていけるお金はもらっております」
「それは哉有氏のコレクションのことですか」
「そうです、殿様は頭の骨を集めていらして、行方が分からない周口店の北京原人の頭の骨がほしいといつもおっしゃっていました。手に入れば完璧ではないがコレクションが満足できる物になると思っておられたのです、遺骨に混じって日本に来ているかもしれんと殿は考えておられて、実際にご自分で遺骨の安置所に行って探されたのですが、見つかりませんでした」
遺骨安置所の係官が昔探しにきた方がいたというのは夢久哉有だったのだ。
「それで殿が亡くなったあと、わしも清掃会社にまで金を払って探させました、確かに泰皇島とあった古い箱があったので持ち帰えらせたのですが、中には何もなかったので戻しました、誰かが盗んだのだと思いましたな」
遺骨の安置部屋の出来事と一致する。
「だけど、哉有さんはすでに北京原人の骨格を手に入れていたわけですよね、それでも周口店の北京原人の頭骨が欲しかったのですか」
「殿は、大殿が見つけた北京原人の骨を自慢にしてはいましたが、頭骨を飾りたかったのです、しかしこの北京原人は跡出の母親だ、頭の骨だけ外して飾ることは出来ない、とおっしゃっていました、それと有名な北京原人の頭骨が欲しかったんだと思います」
夢久家の優しさなのか、収集癖のある完ぺき主義者なのか。
詐貸は水良に向かって言った。
「それで水良さんは私に失われた北京原人の骨探しを依頼して、それが世間に伝わるとご自分で作った北京原人の骨を持っている人から連絡が入るだろうと考えたわけですね」
「その通りです、哉有は自分のコレクションを誰かに管理してもらっていることはわかっていました。誰だかは全く想像がつきませんでしたけど、亡くなってから管理している人が、私が標本にした北京原人の骨を売ってしまったりしたら困ると思いました。まさか跡出さんが管理人だとは思いもしていませんでした。
あの富山の別荘に原人などの化石骨がいくつかあったのはごらんになったでしょう、哉有は戦時中に失われた北京原人の骨が欲しいとよく言っていました。彼は周口店の北京原人に関する本や資料をずい分集めていました、跡出さんが言ったように自説として北京原人の頭骨は中国での戦死者の遺骨と混じって日本に戻っているかもしれないとよく話していました、それでこのような芝居をしてしまったのです」
「わしも詐貸さんのところに北京原人の骨探しを依頼したのが夢久家の水良さんと知って驚きました、それに母の骨を形にしてくださった方だということもお会いしてから知りました」
「私から本物の跡出さんの電話番号を知った水良さんが跡出さんとコンタクトをしたということですね」
「そうです、その前に、詐貸さんが清掃会社に跡出さんが出資していると電話でおっしゃったのでびっくりしました。別の跡出さんがいるとその時思いました。しかし北京原人一世の跡出さんだとは考えもしませんでした。それから東京の知人に清掃会社に聞きに行ってもらいました。清掃会社の社主は跡出さんではなく違う人で、跡出と言う人は知らないということでした」
「ああ、すまんことです、若い人が社長のところにいろいろ聞きに来たと主任が言っていたので調べさせました。あの清掃会社の社員の何人かはわしから直接金を渡している人間で、裏のことをよく知っています。聞きに来た若い人が詐貸探偵事務所の人だということを突き止めて報告してきました、それで探偵さんが巣鴨の蕎麦屋によくいくということだったので、わしが直接行ったのです。
最近新聞で北京原人の情報を欲しいという詐貸探偵事務所の広告をみて、清掃会社を調べたのはやっぱり北京原人の骨のためだと分かり、今度は私自身で探偵事務所の周りをまわったり、もう一度蕎麦屋に行ったりして様子をうかがったのです、探偵仲間の評判も聞きましたが、探したものは百パーセント見つける探偵事務所ということで、もしかするとあの箱から頭骨を盗み出した犯人を見つけているかもしれないと思って電話を入れました、そのお陰で水良さんと会えることが出来ました」
そこまで野霧も吉都も何ともいえないような顔をして聞いていた。詐貸自身もこのような展開になるとは思ってもみなかった。振り返ってみると野霧と吉都の閃きが要所要所にあったからである。自分で何もやっていないと詐貸は卑屈になっていた。
水良氏が再び話し始めた。
「私がこの家で跡出さんと直接会いました。跡出さんとはじっくりと話をし、私のお願いを理解してくださって、このような会見になりました。
実は哉有の頭骨のコレクションは世に出せないものです。跡出氏も自分が死んだ後はどうなるのだろうかと心配していたようです、それで私の申し出を受けてくださったのです」
水良と跡出が立ち上がった。
「これから、お見せしたいと思います、愛子も一緒にいらっしゃい」
詐貸たちはぎしぎしいう階段を上った。二階は木でできた洋間で黒光りしている。壁はガラスの引き戸がついた棚になっていた。一番目のつくところに一体の全身の骨がつるしてある。
「これが、母の骨です」
跡出馬盛がその骨を指差した。小柄な北京原人の女性の骨であった。
見ていくと、棚には「歴史上の人物」「俳優」「作家」「画家」「政治家」「スポーツ選手」などのラベルが張ってある。そこに頭の骨が並べられていた。みなきれいに磨かれ、そろってこちらを向いている。何も言わないはずなのに声が聞こえるような気がする。
「これは本物ですか」
「そうです」
「墓から盗んだのですか」
「そういうことになります。殿は欲しくなると何が何でも手に入れようとなさりました」
「跡出さんが盗んだのですか」
「私も大きくなってから少しは手伝いましたが、もっと前から夢久十の大殿と一緒に集めていらっしゃいました」
「どうやって集めたのです」
「裏の手配師に大枚を出してやらせていました。戦後のどさくさのときに知り合った者達のようです、もう人も訪れないような墓が多かったので、難しいことは無かったのです」
「だけど、それじゃすぐ噂は広まるでしょう」
「墓を掘った中心になる者にその骨を持たせて写真を撮っています」
跡出は一つの引き出しから古びたノートを取り出した。
「これは、すべての記録です。そこにある日本人の頭の骨のすべてです、ほら、写真が貼ってあるでしょう、もし墓を暴いた連中が警察にでも言ったら自分も捕まるのです。それよりも、かなりの金を渡しましたので、そんなことをしようとも思わないでしょう、戦中戦後殿たちが助けた連中です」
「これじゃ、やはり秘密のコレクションですね」
詐貸が言うと水良もうなずいた。
頭骨を見ていた吉都が「マリリンモンローがありますよ」と声をあげた。
棚の上に白く曝された日本人とはちょっと違った感じの細身の頭骨があった。
「殿はアメリカやヨーロッパの富豪と知り合いでした。それも進駐軍との関わりからそういう道筋をつけたようです、その人たちが腕のいい盗人を見つけてくれていたようです」
「モンローの墓はロサンゼルスのウエストラード、メモリアルパークにあります。独立した墓ではなく、石室が積み重なっているようなものです、そんなとこから盗めるのかな」
モンローのことを良く調べていた可也が呟いている。
「盗もうと思えばやれるものです、しかし相当苦労したという話を殿がしていましたな、マリリンモンローは大変でしたが、大統領や野球の大選手、映画俳優のものは意外と簡単だったようですよ、アインシュタインの頭骨もあります」
アインシュタインと書かれた頭骨は上部に切断された跡があった。
「だけど、アインシュタインの骨は粉にされて散骨されたんじゃないの」
野霧が不思議そうに聞いた。
「いや、このノートにも書いててありますが、解剖医の研究室の端に隠してあったそうですな」
可也の推測が当たっていた。やはり持ち出されていたのだ。
「それにしても、これが知られたら大変なことになる」
水良は不安そうに言った。
「外に漏れたら国がかかわってくる事柄ですね」
「そうです、じゃが今私は骨を返しているのです、元の墓に戻しているんです、この骸骨たちは夢久十の大殿と、哉有の殿様が集めなさったものです、見つかったら殿たちに傷がつきます。罪人になりますから、わしが欲しいのは周口店の北京原人の頭骨だけでした、わしの手で殿のコレクションを完璧にしたかった」
詐貸は跡出の言葉に驚いた。
「それじゃ、お岩、外骨、紫式部、小野小町の墓荒らしは跡出さんが頭骨を戻した跡ですか」
「はい、墓の下というより脇に超小型の掘削機で円筒形に土を掘って、頭骨を入れて土をかぶせているのです」
だから、掘った跡が小さかったのだ。お岩さんの墓が崩れたのは別の要因だろう。
「棚を見てください、骨が無いところがあるでしょう」
吉都が見て回った。
「外骨、紫式部、小野小町の名前はあるけど頭骨はありません」
「一昨年から、頭骨を元に戻すことをはじめました。私も苦労して裏の組織をみつけました。これは外部に漏れたら大変ですが、墓守に顔が利く組織があって、それが墓守に頼んで骨を戻す作業を黙認してもらうのです、もちろん大金を渡します、墓守も骨を盗むのではなく、戻すということで功徳になると思ってやってくれるものです、あの清掃会社にいる者たちが中心になって動いてくれています」
「これを跡出さんから聞いて驚きました。紫式部とお岩さんの墓の修復は私もお金を出しまし、小野小町にもかかわりました、すべて偶然でした、でもよかったかもしれません」
水良はこれらの骨戻しに偶然にも力をかしてしまっていたのだ。
詐貸たちもよく知っている人間の頭骨もたくさんあった。これからすべてを戻すとなると大変な作業だ。
「だけど水良さん、なぜ宮武外骨のことを私に教えたのですか」
詐貸たちは外骨の墓にも調べに行っている。
「ああ、宮武外骨は私も尊敬はしています、その話を哉有にしたら、私以上に外骨に惚れこんでしまいました。名前もガイコツだったせいもあるでしょう、あの人のように生きたいと哉有は言っていました、それで北京原人の頭骨を探すヒントにでもなればと思って詐貸さんに伝えただけのことだったのです」
跡出が口をはさんだ。
「殿は頭骨を集める時、最初に宮武外骨の頭骨を手に入れています。それはとある解剖学教室にあったものです、全身骨格をもらってきましたが、頭骨だけとると、あとは染井霊園の墓に埋めました。ずい分昔のことです、最近、私が頭の骨ももどしましたので、ここにはもう外骨の頭骨はありません」
全く驚くことである。
詐貸たちの目に止まった頭骨があった。真ん中ほどの段に置いてある二つの骨だった。夢久十、夢久哉有とある。
「あ、お祖父さんと、叔父さんの骨」
愛子が声をあげた。
跡出が二つの骨の前で頭を下げた。
「大殿様は、いつもいくら集めても完璧にはならない、何せ自分の頭の骨を見ることは出来ないんだからな、とおっしゃっていました。大殿が亡くなったとき、殿が大殿の頭骨をきれいになさいました。哉有の殿様はある葬儀関係の人に自分が死んだら、頭をわしに送るようにたのんでいたのです。その人が殿が亡くなったことを知らせてくれました、その後すぐに殿の頭が私に送られてきて私が作りました、そうせよとおっしゃっていたものですから」
跡出が目を伏せた。それを聞いて水良も声が出ない様子である。哉有の葬式は首の無いものだったのだ。
「すごいコレクター魂なんだな」
詐貸は人間の脳は一体どうなっているんだろうと思った。
二人の頭骨の隣に頭一つ分空いたスペースがあった。
「ここに失われた北京原人の頭骨を探して置くことが私の使命でした」
服従するのも脳の仕業である。
詐貸たちは下にもどった。愛子の母や研究所長はそこで待っていた。
詐貸が跡出に尋ねた。
「このコレクションは夢久十氏がはじめたものですか」
彼は頷いた。
「どうして頭の骨を集めるようになったのか聞いていらっしゃいますか」
それには跡出は首を横に振った。代わりに水良が答えた。
「骨に関わる薬の商売をやっていて、どこかで頭骨に興味を持ったのではないでしょうか、それで集めるようになった」
いつものように野霧が口をはさんだ。
「多助さんは頭骨の根付のコレクションをしていましたね、それで夢久十のお爺さまも頭骨に興味を持って、本物を集めようとなさったということはありませんか」
「だけど、時代的にあうだろうか」
詐貸の疑問に吉都が答えた。
「大丈夫ですよ、夢久十氏は1890年生まれ、多助氏は1922年生まれ、多助氏が25の時には十氏はまだ75です。十分重複します」
「多助さんが根付を集め始めたのはいつごろですか」
「あれは二十歳半ばのころでしたね、夢久家の人は収集癖が強くて、多助君が何かの拍子に根付を集め始め、十さんは喜んで金銭的なサポートをなさっていましたね」
「貝のコレクションを手放したのはいつでしょう」
「あれは我々がまだ二十代半の頃でした、いきなり十のおじいさんが貝を売ったといって、私にも学費や生活費にとかなりの金額をくれて感謝しました、大学院で研究をしようとしていたところで大変ありがたかったですね、結婚を勧められるちょっと前だったですね」
「とすると、野霧君の推測もあながち間違いじゃないね、息子が集めている頭骨の根付を見て、それじゃ俺は本物をと思ったかもしれないな」
これはあくまでも推測である。しかし、コレクター気質を持っているとこんなことも多々あるのではないだろうか。
水良が頭を下げた。
「もう一度詐貸さんにはお詫びをします、身内のごたごたを申し訳ありません」
「いや、報酬は十分にいただきましたから、むしろ北京原人の頭骨を見つけることができませんでした、すみません」
初めて依頼されたものを見つけることができなかった。詐貸には失敗の結果である。
「いや、あの骨は日本にある確立はゼロに近いものですし、あったとしても海の底かもしれないし、そんなに簡単に見つかるものではありません」
詐貸は騙されたのはしょうがない、商売だからと割り切った。
「跡出さんと会って、我々はノーベル賞に近づいたのです、と言って、ノーベル賞が欲しいわけではありません、跡出さんは今七十一、私と同じでしょう、北京原人の遺伝子を持っていてなぜ長生きをしているのか、北京原人、現代人、跡出さんの遺伝子の違いから、より正確に寿命の遺伝子が特定できる可能性が出てきたのです。これは跡出さんも喜んで協力してくれることになりました。私にとってはもうここにある哉有が墓から盗んだ骨を全部砕いて分からなくしてしまいたい程の気持ちです、そうすると短い余生ですが研究に専念できる。しかしそうもいかないでしょう、苦手なことですが跡出さんと一緒に裏の社会に頼んでまた元の墓に戻せるのは戻したいと思います」
遺伝子の話は分からないが、これが水良氏や夢久家のまじめさでもあるのだろう。
「探偵事務所にはこれからも、定期的に入金させてください、正式ではなくてもいいのですが、弁護士として夢久家そして愛子を守っていただけませんでしょうか」
水良が言った。
詐貸はなんと中途半端な話しだと思った。
「愛子をよろしくお願いします、これからも」
愛子の母親が頭を下げた。
それはどういう意味だろう。まあ、深く考えない方がいいと、ただ頭を縦に振った。盗んだ頭の骨を元に戻そうとどうしようと自分とは関係ない。と詐貸はちょっと強がってみた。
愛子が「この話は私の遺伝子にも関係しているわね、小説にしてもいいかしら」と言った。
それにも黙って頷いた。
「そのうちお礼の夕食会をどこかでしましょう」という水良の声を後に、ハイヤーで探偵事務所に送ってもらった。
新たな出発 エピローグ
「先生、疲れましたね」
帰ってくるなり飛び出して甘いものを買ってきた野霧が、桜餅を詐貸のデスクの上に置いた。もう秋である。何で桜餅なのだろうか。節操の無い和菓子屋だ。
一口食べるとなんだかほんわかした。野霧の味だ。
「ごくろうさん、とうとう何もみつけられなかった」
「そんなことありませんよ、先生の推理は要所要所で当たってましたよ、やっぱり先生の頭はすごいですよ、とってもスマート」
「いや二人のおかげだよ」
「スマートは洒落てるっていう意味もありますよ」
吉都がきなこ餅を食べながらPCで英語の辞書を開いている。餌にかじりついている蟷螂のようだ。
「それがどうしたの」
「スマートなヘッドで洒落頭、しゃれこうべ、先生シャレコウベだ」
それを聞いて野霧が柏餅をほう張りながら笑った。
飲み込むとぼそっと言った。
「だけど北京原人はもう探さないのでしょう、先生、私たちもうおしまいですか」
それを聞いて鴬餅を食べながら吉都が小声で言った。
「おかしな終り方ですね、変な探偵小説になったな」
野霧は草餅に手を伸ばした。
「でも本当にあった話なんだわね、信じられない」
二人は詐貸が残りの桜餅をくちゃくちゃ噛んでいるのを見た。
やけ食いみたい。
詐貸が顔を上げた。
「なあ、君たち、これからも付き合ってくれよ、弁護士の件引き受けることにするよ」
野霧も吉都も笑顔になって何も言わずに大きく頷いた。
完
すべてフィクションです。(原案 2019年1月23日)
あとがき
探偵小説とはなにか。広辞苑では推理小説と同じに扱っている。日本国語大辞典では推理小説は探偵小説の形をとることが多いと違いを認めていて、探偵小説は主人公が探偵とある。どちらも犯罪事件、犯罪方法、犯罪動機にまつわる謎を論理的に推理、解明する小説とある。広辞苑には犯罪でも特に殺人事件とある。広辞苑は血生臭いのが推理小説と考えているようだ。
どちらにしろ、いつも自分が書いている小説ではない。犯人が異次元に行けばSFになるし、犯人が花に変化すれば幻想小説になってしまう。そういった話しが好きなのだが、ひょんなことからここに初めて探偵小説を書いてしまった。
この話しでは殺人事件は起こらない、死体はあるが殺人死体ではない。探偵が主人公であり北京原人の骨を探す話であるから、探偵小説であることは確かである。
なぜ論理を整然とさせないと成立しない探偵小説を書きたくないのか、理由は明らかである。四十数年、推理小説作家と同じ畑の仕事をしてきたからである。刑事さんかと勘違いされては困る。科学の世界にいた。科学は宇宙の物理の法則をもとに理路整然とした文で結果を示さなければならない。もう疲れた。妄想をそのまま文にしたらどんなに幸せかと、退職後は幻想をそのまま話しにして楽しんでいるわけである。
そんなある日、宮武外骨が自分の死後骨格標本にしてくれと言っていたというエピソードがヒントになって、骨集めの幻想小説を思いついた。最初は「面白半分―外骨の骸骨」と言うタイトルだった。外骨、モンローやアインシュタインの骨を集めた収集家の家を探す短編にする予定だった。
それが書いているうちに、北京原人の頭骨の紛失や、探偵の大学時代などが絡んできて、探偵事務所を巣鴨の庚申塚の近くにしたことから、そばにお岩さんの墓もあり、染井霊園があり、違う方向の話しになっていき、とうとう探偵小説になってしまったわけである。
いつもの書き方で、思いつくままに書いていって、出来上がったとき印刷して読んでみた。これが大変である。昭和の初期から平成半ばまでの、三代にわたるある収集癖のある家の物語であることから、年に関してつじつまの合わないところが多々出て来た。登場人物の年譜を書き出す必要性に迫られた。その結果、年の調整などを行なわざるをえなくなり、何度か書き直してやっと落ち着いた。探偵小説など書くものではない。人生お化けが出ようが、いきなり違う世界に入ろうが、いいではないか、と茸の幻想小説を書き続けている。
人の収集癖が動物の餌を溜め込む習性の名残だという説を読んだことがある。決して否定はしないが、万人がもつ性質ではなく、一部の人間で強く見られるもので、人の性質や性格がどのような形で脳の中に形成されるのかわからないことには、その本質は分かるものではない。
誰でも脳が満足しなければ幸福感に浸れない。収集を成就すれば達成感と幸福感が生じる。収集癖は人で極端に発達した大脳新皮質のなせる業で、人特有の脳の満足を得る性癖である。と同時に成し遂げられないときはストレスの要素になるし犯罪の根源にもなりうる。それに小説のネタにもなるわけである。
筆者も収集癖は強い。ただ完璧主義は捨てている。それが満足感を得られる一番の近道である。もう一つ満足を得る方法がある。
ある作家の本を長年集めていた。完璧に集めることは無理である。好きな本を完璧な収集にするにはどうしたらいいのか。それは自分の本を集めることである。もう十七冊もの本を書いて自装して自費出版した。それは完璧に自分の本棚にある。
収集癖をもつ人間は何とかして自分の収集を増やして完璧な物にしようとするものである。
2019年5月1(今日より平成が令和になった)
著者
洒落頭(しゃれこうべ)


