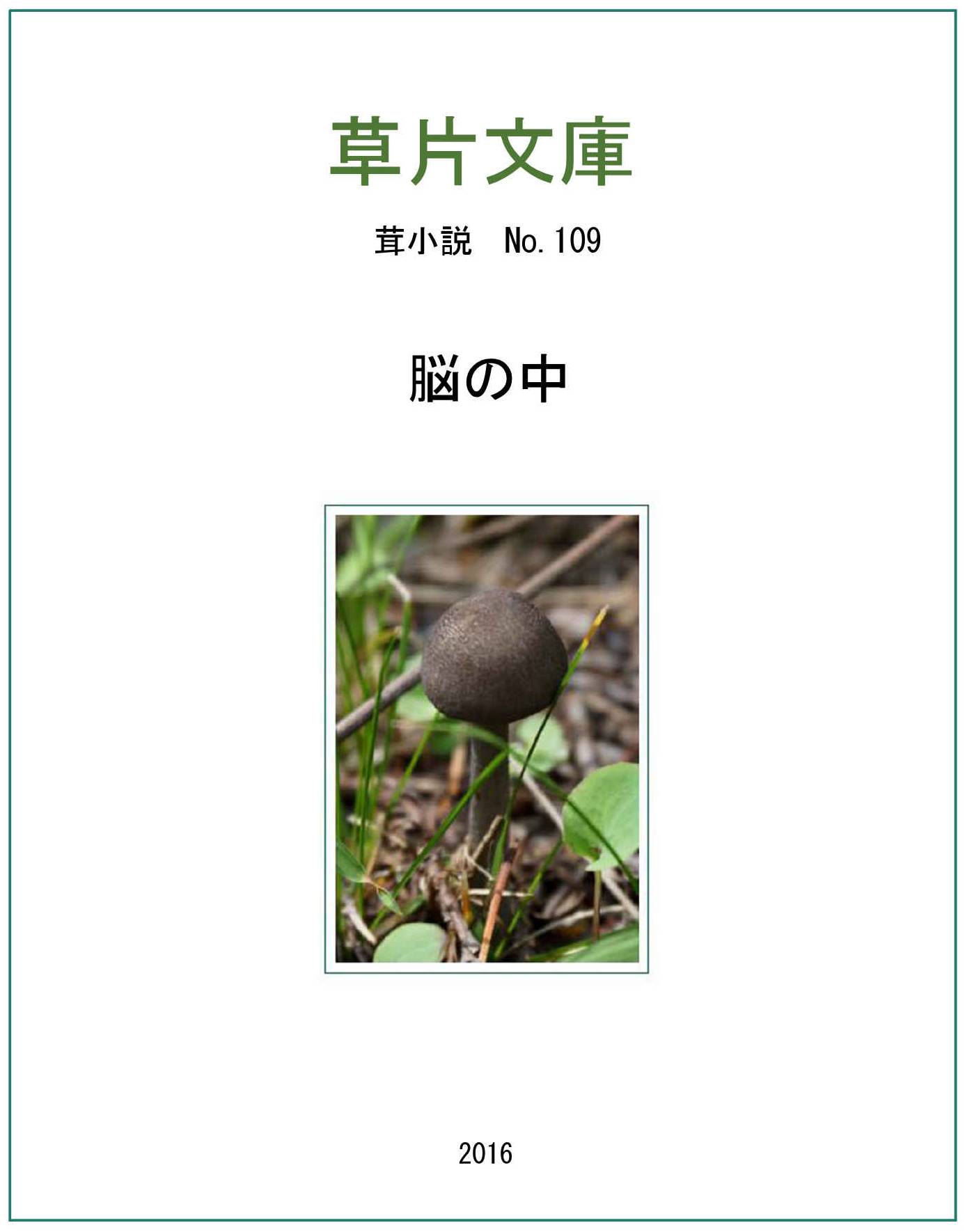
脳の中
昨日から脳の中がむずむずする。と言って、気分が悪いわけではなく。ただむずむずするのである。体の中が何となく痒く、だけど掻くことができず、もどかしく身の置き所がないような、そんな感じなのである。
それが一日中続くのではなく、朝起きて朝食をとる前、昼食前、夕食前に生じる。と考えると、お腹が空くと脳がむずむずするようになるのかもしれないわけだ。確かに食事が終わると治まっている。
そのような状態が一月続いたが、いっこうに治る気配がなく、職場の隣の席の叶圭子に打ち明けた。別に解決しようなどとは思っていなかったのだが、彼女が大学時代に心理学を勉強したことを思いだしたからだ。
「でもねえ、脳の中は痛みも、かゆみも何も感じないのよ、ということは、気持ちの問題か、それとも、脳の膜のあたりに何か動くものがあるのかもしれないわね」
「どういうこと」
僕にはよくわからない返事である。
「大学の脳のことを教えてくれた先生が、そう言ってたのよ、頭が痛いというのは、脳が痛いと感じているけれども、脳膜の血管が広がったりして、それが痛みとして感じるんだって、脳の中そのものが痛いのじゃないのよ」
「ということは、脳の中にではなくて、脳の膜のあたりがむずむずしているということかな」
「もうしかしたら、脳膜の血管の血液の流れがおかしいのかもしれないわね、渦巻いているとか、ふふ」
どうも真面目に話してくれていない。でもよく知っていると感心する。
「どうしたらいいのかな」
「虫下しでも飲んだら」
何という返事だろう、脳膜に回虫が住み着いたとでも言うのだろうか。僕がまじめな顔をして悩んだものだから、彼女は笑いだした。
「正ちゃん、まじめに聞いちゃったの、冗談よ、虫がいる分けないじゃない、何かの機会に保健室のお医者さんに聞いてみたら」
僕は久米正という。
何せ生物学などからっきしわからないのでしかたがない。
「うん、そうする」
彼女は三つほど上の先輩で、仕事のこともいろいろ教えてくれる、頼りになる女性である。
それから一月ほど経った。モゾモゾしていたものが、なんだか大きくなって、ごろごろしてきた。痛いわけでも痒いわけでもないが、額の裏側あたりで動くようなものがいるのは気持ちがよいわけない。
とうとう会社の保健室に行く気になった。産業医に様子を話した。週一回、うちの会社に来てくれている近くの大学病院の医者である。内科が専門だが、産業医の資格をもっているので、ストレスに関することもよく知っている。小太りのかわいらしい感じの女医さんである。佐々木先生という。
「久米さんですね、どうしました、顔色や艶いいわね、からだの動きは問題なさそう、風邪も引いていませんね」
「頭の中がむずむずするのです」
「ちょっと血圧測りましょう」
彼女は僕の目をのぞき込んで血圧計の腕帯を巻いた。聴診器を腕にあてながら、
「熱はなさそうだし、ストレスもなさそうですね」
そういって腕帯を膨らませ止めると、聴診器を耳から離し、
「上が120、下が71、至極正常だわね、それで脳の中がむずむずするのはいつ感じるのかな」
「朝食の前で、食べると治るのですが、最近はお昼前や、夕飯前にも起こることがあります」
「ふーん、血糖値が下がると起こるのね、ところで仕事はなんです」
「帳簿の整理です」
「デスクワークですか、運動してますか」
僕は首を横に振った。
「ここのところ、仕事で問題はありましたか」
やはり首を横に振った。
「住まいはお一人ですか」
「はい」
「何か不便なことは」
「いや、特に感じませんね」
「話をきいていると、メンタルには全く問題なさそうだし、習慣病も特になさそうだし。脳の中の血管の一部になにかあるのかな」
叶女史の言うことが少し当たっている。
「むずむず、ごろごろ以外に何か感じますか」
「今はそれだけです」
「脳のMRIでも撮るしかないですね、撮れば安心するでしょ、病院に紹介状書きましょう、暇なときに受けてください」
ということで紹介状が手元にある。
しばらくして、会社の創立記念日で仕事の休みの日、朝起きるといつもより頭の中がむずむずしたこともあり、病院にいってみようという気になった。
大学病院など大それたところに行くのははじめてである。気後れしながらも、紹介状をもって受付に行った。提出書類を書き提出すると、脳神経内科に行くように言われた。担当は佐々木先生の先輩で、恰幅のいい男性の医者だった。室田先生といった。
「頭の中がむずむずするということですね」
「ええ、もう一月になります」
「佐々木先生の紹介状には、体の調子はすこぶるよいとありますね、やっぱり、脳内血管の局所的異常で、血液の流れがそこだけおかしくて、そんな感じを持つのかもしれませんね、MRIの前に、一応一通りの検査をさせてください。血圧測定、心電図です。血液検査は定期検査のもので大丈夫ですのでやめましょう」
ということで、室田先生に血圧を測ってもらい、看護師室で身長や体重の測定、それに心電図をとってもらってから、MRI室にいった。
脳のMRIを撮るのも始めてである。担当の技師がMRAですねと言ったが、意味がわからない。いえ、MRIですと答え、不思議な顔をしていると、彼は、「失礼しました、MRIなのですが、血管を詳しくみるMRIでMRAといいます」と説明してくれた。
頭を蒲鉾型の機械の中に突っこまれ、動かないように二十分我慢してくださいと言われた。とっとっとっと、がんがんがんがん、なんだか大きな音で頭が突っつかれ、どうなるかと思ってがまんしていると、やっと二十分が経った。
脳神経内科の待合室にもどっていると、名前が呼ばれ、診察室に入った。
室田先生がデスクの前の脳の大きなネガフィルムのようなものを見ていた。自分の脳の写真のようだ。早いものである。
「脳の中の血管は全く問題ありませんね、脳膜の血管も問題はないが、それよりも脳膜の中に何かあります。MRIのほうがよかったかもしれませんね、前頭骨の内側のクモ膜下腔が膨らんでいる。血管に何かあると思ったのでMRAにしたのですが」
「MRIのほうがよく映るのですか」
「そういう訳じゃないのですが、血管に特化した方法だと、脳の組織そのものはちょっとはっきりしない。普通のMRIだと組織がはっきり映ります。両方とも鮮明にとはいかないところがありますが」
「腫瘍みたいなものですか」
「いや、この大きさの腫瘍なら症状が何か現れるでしょうけど、頭痛もなければ、機能障害もない、きっと悪いものではないのでしょう。炎症があると、酷いときにはかなり症状がでるものです」
「どうしたらいいでしょう」
彼は電話をかけて私の方を向いた。
「ごめんどうでなければ、これからMRIが空いているのでどうでしょう」
また、同じように蒲鉾のなかに首を突っ込むのは気が進まないが、いっぺんにすませてしまった方がいいかもしれない。
私はうなずいて、もう一度MRI室に行った。さっきの技師さんが、「ご苦労様です、今度のはMRIです」と言ってさっきと同じ注意を繰り返した。
また、かっつかっつかっつっか、どっつどっつっどと音に攻められ、神経内科の診察室に戻った。
部屋では机に向かって、室田医師が首を傾げている。
私が戻ったことに気がついて
「ご苦労様でした、不思議なものが映っていますね」と私の方を振り向いた。
彼は写真を指さして「おでこの内側にほらこんなものが」と言った。
そこには、大きさからすると、5センチほどの茸のような形をしたものが白く映し出されていた。
「なんですか」
「わからないのですよ、水分の多い何かだが、脳の組織とも違うし、腫瘍のような感じでもない、写真が少しぶれているのは、これが動いているからでしょう」
「どうしたらいいでしょう」
「ちょっと検討させてください。医局の会議で皆の意見を聞きます、悪いものではないでしょうから、心配いりませんよ、一週間後に来れますか」
仕事のことも気になるが、頭がむずむずしたり、ごろごろするのももっと気になる。
お礼を言って、次回の予約をしてから家に戻った。
次の日、会社に行って、隣の席の叶圭子に報告した。
「何でしょうね、お医者さんが大丈夫といているんだから、大丈夫よ」
一日休んでしまったので仕事がたまっており、それをこなすのに、集中した成果、その日は、脳の中のむずむずはあまり感じなかった。
こうして何とか一週間が経った。病院に行くと、室田医師が言った。
「血液検査をします。もしかすると、黴菌が巣食っているかもしれないので、細菌検査で確かめます、ただからだに症状が無いので、影響の無い菌かもしれません」
またもや血を採られてしまった。また一週間後に行かなければならない。
再び病院を訪れると、室田医師によって、細菌学の教授室に連れていかれた。
室田先生は、細菌学の教授という羽田先生に私を紹介した。
「この人が連絡した久米さんです、血液の中に、不思議な菌が混ざっていましてね、水虫の元の白癬菌がはいることはありますが、血液の中には入るはずのない菌があったのです」
「よろしくお願いします」
何がなんだか分からないが、ともかくえらそうな先生なので恐縮してしまった。この先生は室田先生と違ってほっそりとして背が高い。
「羽田です、ご足労をかけます、すでに血液の中のものを培養してあります、頭の中の物をはっきりさせるのに、ご本人にはいろいろ協力をいただくことになると思い、ご理解をいただくためにきていただきました、実験室のほうにご案内します」
医学部の実験室と言うところにはじめてはいる。
「この実験室は危険なものは扱っていませんが、一応、これを着てください」
羽田先生が白衣をわたしてくれた。白衣など着たことが無い。なんだかちょっとえらくなったような気がした。面白いものである。
戸を開けると、白衣を着た何人もの研究者が顕微鏡をのぞいていたり、シャーレになにやらこすり付けていたりしている。なにもかも始めて見る光景だ。少しばかり緊張する。だが新鮮なものである。恐ろしさも感じた。
僕が入っていくと、みなさんが一斉に僕を見た。
羽田先生は、培養室と書いてある部屋に入っていった。
「これを見てください」
培養室のガラスの容器には、たくさんの真っ赤な茸が生えていた。
「あなたの、血液の菌を培養したら、あっというまに茸になりました」
「どういうことでしょう」
「あなたの脳の中のものは茸かもしれない」
室田医師がいった。茸と聞くと食べる茸しか思い浮かばない。森に生えるものが何で俺の脳に生えたのだ。自分としてなにをすればいいのか見当もつかない。羽田先生が不思議そうな顔をしている僕に説明をしてくれた。
「我々の研究室では病気の原因になる細菌の研究をしています、厳密に言うと、細菌と菌類、すなわち茸は分類上、全く細菌とは異なります。細菌やウイルスは細胞膜を持ちませんが、動物、植物、菌類の細胞はもっています。まずそういう違いがあるのですが、細菌、ウイルス、それに酵母菌などの菌類も微生物と言う範疇に入ります。だから、我々の研究室はどちらかと言うと、微生物学と言ったほうがいいのだと思います。菌類にもある程度知識があります」
詳しくは理解できるわけはない、だけどここが微生物を研究する研究室で、茸なんかも扱えると言うことらしい。しかし、茸は微生物なのだろうか。
「茸は菌類の花ですから大きくなりますが、本体は土や木の中に存在する菌糸で、それは微生物です」
茸は花なんだ、とすると、頭の中で菌の花が咲いたのか。
室田先生が言った。
「久米さん、そういうことで菌を殺す薬を飲んでみましょう」
「細菌を殺す薬ですか」
「あ、いや、真菌と言って、カビを殺す薬です。そう、水虫菌を殺すような薬です」
水虫も菌類なんだ。
羽田先生は、「しばらく観察させてください。脳の中で菌が繁殖し、茸を作るなどと言うことは、あり得ないことです、今、この茸について、科学博物館に問い合わせをしています」
ということで、僕はこの病院に入院することになってしまった。会社の方は、何とか周りがカバーしてくれるというし、だいたい勤めてからこのかた五年近く有給休暇をほとんど消化していない。そういうことで急だが三日後に入院することにした。一週間ほど様子を見ると言うことなのでいい休養になるだろう。
病室は四人部屋の予定だったが、病院に行くと個室が用意され、なぜか丁重なもてなしである。看護婦さんに、こんな高そうな部屋、僕には無理だと思うと言ったところ、羽田先生と室田先生からの指示で、病院の方で用意したという。差額はいらないと言うことでもあった。
「珍しい症状で、少し調べさせてください」
室田先生がそういうと、羽田先生も、「検査にご協力いただければそちらの料金はいただかないことにします」と言った。そこで僕の頭の中の出来物はよほど珍しいらしくて、研究の対象になると言うことだと理解ができた。
病室はテレビもあり、看護婦さんが親切で、自分の家にいるより快適な生活が送れる。独り者は食事の用意も何もかも自分でしなければならない。ここでは何でもやってもらえる。一日のうち、何時間か定期的に何らかの検査を受けたりしたが、ほとんど自分の時間だった。
退院二日ほど前に、羽田先生が病室に来て言った。
「科学博物館から、新種の茸で、馬糞茸の仲間ということだそうですよ、アンモニアが好きな茸です」
「僕の頭にできているのもアンモニアが好きな茸ですか」
なんだか汚いところが好きな茸のようだ。俺の頭の中はくさいんか。
「おそらくそうでしょう」
「頭の中にアンモニアがあるのですか」
「いや、血液に少しは排出するものとして含まれていますが、アンモニアをだす細菌もいますので、その細菌とこの茸の両方の作用かもしれません」
と言う話だった。
糞の茸が脳に生えたとなると、脳が糞と言うことなのか、あまり気持ちのいいものではない。
「頭の中の茸はどうするのですか」
「やはり開頭して、取り出して、その部位を消毒します」
開頭ということは、脳を露出させるわけだ。おっかない気がする。
「頭を開くのだと、かなり入院するのでしょうか」
「開けた状態でどうなるかわかりませんが、ただ茸を取り出すだけであれば、さほど時間はかかりません、二週間から一月と言うところでしょう」
それでもそんなにかかるのだ。
「会社が首になるかもしれない」
「大丈夫ですよ、休職扱いになるでしょう、こういうことで首には出来ない」
ちょっと安心したが、「頭の毛が元に戻るまでちょっとかかります」と言われたのにはがっかりした。頭蓋骨を開けるには毛を剃らなければならないのだ。
退院して、上司に休んだお詫びと、医者に言われたことを話した。首になるかもしれないと少しびびっていたのだが、上司も体が大事だよ、十分休養してまた活躍してくれたまえ、と言ってくれた。手術は一月後に行なわれる予定になった。
手術一週間前に一日だけ入院し、再度検査をすると、茸が大きくなっているといわれた。ごろごろしなくなっていたので、もしかしたら直っていると期待したのだが、そうはいかなかった。おでこのところが熱ぼったくなっているのは、茸によって押されているのではないかということだった。
「そんなに長い手術じゃありません三時間もあれば十分です」
医者は簡単に言うが、頭をいじくられるというのはなんだかいやだ。
とうとう手術入院の日がきた。
手術の前日、頭の毛を刈られ、消毒された。初めて坊主にする。鏡を見ると、別人のようだ。
当日の朝九時、手術着に着かえさせられ、手術室に運び込まれた。
手術を見学する室田医師、羽田医師も新しい白衣を着て手術室に入った。ずい分見学の先生が多いようだが、みな何が出てくるのか楽しみなのだ。僕としては、うるさいなという感じだが、しかたないか。
室田医師が近寄って来た。
「取ってしまえばすっきりしますよ、手術はあっという間です」
腕っ節の強そうな老人が近寄って来た。
「私が執刀します、ご安心ください」
脳神経外科の天野教授である。どうやら教授自ら行なうようである。日本ではかなり有名な先生で、脳の中の難しい小さな腫瘍でも奇麗に取り除くことができる一人者だ。簡単な手術と言っていたのに、なぜその人がやるのだろうと不信に思っていたが、後で彼の興味のためであることがわかった。その時はちょっとぞーっとしていたのである。
注射を打たれ、さらにマスクでなにやら気体を吸わされ、あっと言う間に眠ってしまった。後はICUのベッドで目を覚ましただけだ。頭には包帯が巻かれ、おでこのあたりがしくしく痛い。
気がつくと看護師さんが「今日は、食事はできません、点滴だけで我慢してください、おしっこは言ってください、シビンを持ってきます」
にこにこと笑顔で言ってくれたのだが、生まれてこの方、病気らしい病気はしたこともなく、入院など初めてで、果たしてベッドの上でおしっこがでるかどうか不安になった。
そこへ、室田医師と羽田医師を伴って教授が入ってきた。天野教授だ。手には大きな瓶を持っている。中には、真っ赤な茸が浮いていた。
「これが、頭の中にできた茸ですよ、きれいに取れましたから、問題ありません」
「もう生えることはありませんか」
教授はちょっと考えた。
「おそらく大丈夫でしょう、カビ、茸類を阻止する薬を飲んでもらいます」
「その茸はどうするのですか」
そう聞くと羽田医師が答えた。
「科学博物館で調べてもらうことにしました。おそらく血液を培養したときにでできたものと同じでしょう」
馬糞茸か。
「胞子がついていたので、胞子が血液に入って、脳の中に回ってしまった可能性がありますが、薬で何とか大丈夫でしょう」
「その、アンモニアを作る細菌もいましたか」
「いや、いなかったのですよ、ただ、あなたの脳脊髄液に微量のアンモニアが入っていました。きっと、脳の組織が作り出してしまったのかもしれません」
「私の脳にはおしっこがはいっているということですか」
「おしっこじゃありませんけどね、珍しいですね」
先生方は笑いながら病室を出ていった。
こうして次の日は個室に戻された。トイレは車いすで連れていってくれたが、自分ですることができたのにはほっとした。歩きたいと言ったら、頭の手術をしたところがしっかり固まるまでだめと言われた。
一週間もすると、歩いてもよくなった。逆に退屈になってきた。
「若いから元気だね、退院を早めてもいいけど、家に帰っても全部自分でしなければならないのなら、予定通り一月いますか」
室田医師は回診のときそういったのだが、まかせることにした。
会社の人が見舞いに来た。上司と叶圭子だ。
「元気そうだね、よかったわ」
圭子は見舞いのメロンを机の上に置いた。
「病名がつけられないそうだね、産業医の佐々木先生が言っていたよ」
「そういえば、僕もまだ病名は聞いていません、脳に茸が生えました」
「なあに、それ、真面目に言ってるの」
「そうなんです、初めてのケースで、これから研究対象になります、そのかわり、治療代はただだそうです、それに差額ベッドもただです」
「よかったというべきかどうかわからないが、まあよかった」
その後会社の様子を話してくれて、二人ともにこやかに帰っていった。
数日後、予定通り退院ができ、脳の中もきれいになって仕事も普通にできるようになった。
科学博物館で茸をさらに詳しく鑑定したところ、やはり馬糞茸の仲間であり、新種と言うことらしい。科学博物館の茸の専門家が専門誌に紹介するということである。日本で見つけたので、学名にニッポニカとつくそうである。それにクメという僕の名前も入るかもしれないということである。
それから数ヶ月たったある日のこと。朝、駅をでて、会社に行く道を歩いていると、いきなり耳にしゃらしゃらしゃらという音が聞こえてきた。耳鳴りかと思い、また、医務室に行かなければならないと考えていると、しゃらしゃらが治まって、水がほしいと言う女性のつぶやきが聞こえてきた。
どこから聞こえてくるのかと、立ち止まり、周りを見たのだが、男性が数人歩いているだけで、女性はいない。道に面した商店の中かと見ても、どの店もまだ開いておらず、人がいる様子はない。
会社に向かって歩き始めても、水がほしいと言うつぶやきは消えることはなく、強くなっていく。花屋の前を通ると、鉢がいくつかおいてあり、その一つからつぶやきが強く聞こえてきた。
その鉢にはなにも植えられいない。土が乾いている。少し生えている草も先が黄色くなっている。
通り過ぎる寸前、水ちょうだいと、言い方を変えて僕の耳に声がとどいた。立ち止まって鉢を見ると、茶色の細い茸がしおれて頭を鉢からたらしている。
まさかと思いながら、茸の傘に指を触れると、痛いと女の声がして、水ちょうだいとまた言った。
持ち歩いているペットボトルのお茶を茸の生えているところに少し掛けてやった。すると、「どうも」、と言う声がして、茶色の茸がちょっと頭をもたげた。
今日の暖かさじゃ、これだけの水では十分じゃないなと思ったところ、頭の中に「私はもうすぐしなびるから心配しないで」と女性の声がした。「一夜茸なのよ、ありがとう」とも言った。それで僕はなんだか安心してその場から離れた。
その日の帰り、夕飯の材料を買おうと駅のマーケットによった。今日はパックのにぎり寿司でも買おうと、魚売場に向かう途中でお経が聞こえてきた。なむあみだぶつ、なむあみだぶつ、なんまいだ、なんまいだ、ほうれんげーきょう、たくさんの男と女が小さな声でお経を唱えている。しかも宗派もヘったくれもなく、ごちゃまぜである。
野菜売場の前だ。どこかの主婦がエリンギのパックを籠に放り込むと、一時お経が途切れた。主婦が立ち去ると、またお経が始まった。椎茸、エリンギ、マッシュルーム、エノキ、マイタケたちからきこえてくる。食われちまうからなのかよくわからないが、売場の茸たちはお経を唱えているのだ。干した椎茸に耳を傾けてみたが、声はしなかった。僕の耳は生の茸の声が聞こえるようになってしまったようだ。脳に茸が生えたからか、頭を手術したからか
また悩みができてしまったが、茸のお経を人に理解してもらうのは生易しいことではない。必ずカウンセリングを受けろとか、精神科にいけとか、周りからやいやい言われることになるのは目に見えている。
ともかく茸のつぶやきをうまく聞き流さなければならない。どりょくをしていたところ、なんと茸のつぶやきが役に立つことがあったのである。
お盆になり、信州の実家に帰った。山裾にある古くからの家で、昔は農業を営んでいたこともあり、かなり広い敷地がある。僕の姉たちはみな結婚をして、日本中にちらばっている。一番近くでも名古屋である。父親と母親しか住んでいない。父親は市役所に勤めており、母親は農協でアルバイトをしている。
あまり天気が良くなく、空に雲がかなりかかっている。久しぶりに庭を歩いたら、そこここに茸が生えており、耳に声が聞こえてきた。茸がぶつぶつとつぶやいていた。どの茸も雨が強くなると言っている。天気予報でもそう言っていたことなので驚くことはなかったが、家の裏に回ると、裏山の林の中の茸たちが、「だめだ、おわりだ、だめだ、おわりだ」とつぶやきっぱなしだった。どんな意味があるのだろう。耳を澄ましていると、ある茸が「地すべり、地すべり」と繰り返している。裏山は酷い傾斜ではないが、地滑りが起きれば我が家は押し潰されるだろう。
注意したほうがいいのではと思ったが、そのまま親に言っても信じてもらえるわけはない。もし本当になったら危ない。何とかしなければと思って、こんなことを考えた。親父とお袋に、
「たまには温泉でもはいりたいね、近くにあるじゃない、今日どうだろう、旅館の料理でも食おうよ、おれがだすからさ」
いきなり息子がそんなことを言うものだから、両親ともぽかーんとしていたが、「たまには親孝行と思ってな」とごまかした。ともかくそれじゃ行こうということになって、おやじの知り合いの宿をとり、おやじの車で向かった。家から三十分ほどのところにある宿である。
その夜、天気が急変し、台風まがいの低気圧が来て、豪雨に見舞われた。
夜遅くになり、実家のあたりも含め避難命令が出された。予報どおり、山際では山崩れが起き、川の水もあふれ、そのあたりの家は家の中まで水につかった。非難しなかった数人が山崩れで亡くなったのである。
僕の家も半分つぶれた。両親は命拾いをしたと、僕に感謝感謝であった。補助金も出るし、いい機会なので、家は建て直すことにした。今年の暮れには新しい家も建ち、両親はいい新春を迎えることになるだろう。
まさに茸のつぶやきさまさまといったことである。
困ることもある。仕事仲間の家で、鍋物をごちそうになったときである。用意された椎茸やエノキの唱えるお経が耳に聞こえてくるばかりではない、茸が鍋の中に放り投げられるごとに、「あっちあっち」とつぶやきが聞こえる。どうも食べる気がおきずに、そいつのかみさんに「久米さんは茸がお嫌いなようね」と言われてしまった。
すると、そいつは「そりゃ、そうだよ、頭の中に茸が生えちまって、手術までしたんだ」と言いおった。
奥さんは興味津々に僕を見た。
「そういえば、そうでしたね、その茸はどうなさったの」
「今、科学博物館で調べています」
「食べられるの」
「いや、馬糞に生える茸の種類で」
と言ったとたん、みなが笑いだした。
「久米さんの頭の中は馬糞か」
その話は大笑いで終わってしまった。
ということで、茸のつぶやきは生きている茸が生えていれば聞こえてくる。茸の声は人間の声とはどこか違う。人間一人一人違うように、どの茸も違うのだが、人間の声とどこが違うと問われると、一口で言うことはむずかしい。雀の鳴き声と鼠の鳴き声が違うように、茸と人の声が違う。茸のほうが低音とか高音とかいえない。低音の茸もあるし、高音の茸もいる。ただ茸の声は、みゃみゅみょ、のような感じである。
茸に口があるわけではないので、僕が聞いている茸の声は、僕の体のどこかが、茸の発する音を感受して、脳が茸の声と判断しているのだろう。僕のからだにそう言う仕組みができあがってしまったのだ。
心理学を学んだ叶圭子に「脳の中に何でも人間の言葉にしてしまう場所があるの」
と聞いた
「どうしたの、正ちゃん、脳に茸ができて、脳に興味を持つようになったの」
「うん、そんなところかな、MRIの画像なんかをみせられてしまったからね」
「そう、脳の表面に言葉を操るところがあってね、見たもの感じたものは、みな言葉が付随して記憶にしまわれるし、記憶も言葉を伴って思い出されるわね」
「猿にもそんな場所あるのかな」
「人間だけよ、言語野っていうの、二カ所あるのよ、運動性言語野は、言葉にすることを指令する場所、感覚性言語野は入ってきた感覚を言語で理解するところ」
ということは、僕には茸からの情報を人間の言葉に置き換えることのできる、感覚性茸言語野ができたのだろうか。
「叶さんは脳のことよく知っているな、僕も勉強しよう」
「面白いわよ、脳って、でもなぜ茸が生えたのでしょうね」
そんな話をする機会が増え、自分も脳に興味をもつばかりではなくかなり知識が増えてきた。NHKなどのメディアによく顔を出す有名な脳科学者とやらの本を買ってもみたが、本当のところはなんにもわからなかった。叶圭子の方が説明はうまい。
ともかく、茸のつぶやきが聞こえるようになったのはどうしてか知りたいが、相談できるまでの親密な科学者がいない。
そうこうしているうちに、茸をとってもらって半年目の検診になった。
「どうです、顔色もいいし、脳のどこも異常がありませんね、血液もきれいだ」
「菌のほうはどうでしょう」
「羽田先生が培養をして調べていますが、人間に悪さをするようなことはないそうです、どうして、あなたの脳に寄生したかわからないそうです」
「もう、脳の中に茸が生えることはないのでしょうか」
「そのところは断定できません、それで、もう少し検査をしたいのですが、ご協力ねがえますか」
「ええ、時間が許す限り」
「遺伝子検査というのをご存じですか」
「いえ、そちらの方は全く知識がなくて」
「人間の遺伝子についてはその基本的構成はすべて解析されています、細かい部分は個人個人によって違うのですけれども、それをみることによって、特定の病気になりやすさなどがわかります。あるアメリカの大女優が、遺伝子検査で将来乳ガンになりやすいということがわかって、リスクを避けるためきれいな乳房を削除してしまったということが報道されています、これは極端な例ですが、体質を知ることにより、自分の持つリスクを下げることができます、一方で、自分のことがわかりすぎてしまう怖さもあります。その情報が外に漏れると、結婚、就職に悪影響を与えないとも限りません、そういうことを知った上で、検査を受けるお気持ちがおありなら、こちらですべて取りはからいます」
「自分の遺伝子を知ることができるのですね」
「そういうことになります、ただ、人の遺伝子がわかったというのは化学構造上のことで、その意味については必ずしもすべてがわかっているわけではありません、われわれが今わかっているのは、いくつかの病気のリスクを予知することはできるということです」
「大学としても遺伝子情報は極秘情報として、外に漏れないようにきびしいセキュリティーをしいています。また、その遺伝子の個人名は何十にも暗号化がされており、わからないような仕組みになっています」
「そうですか、受けてみます」
「受けていただくと、なぜ久米さんの脳に茸が生えたかわかるかもしれませんし、将来また脳に茸ができるかどうかもある程度予知することができるかもしれません」
覚悟を決めて遺伝子検査をうけた。ただ血液を提供することでよかったのだが、その結果を聞くまではかなり時間がかかった。
叶さんに「遺伝子検査って知ってる」ときいてみたのだが、返事は「知ってるけど、あんなもの怖くて受けられない」だった。
「どうして怖いの」
「未来を知ることができるって、いいことと悪いことがあるでしょ、こんなことが起こる可能性がこのくらいあるって言われたら、それがすぐに死んじゃうくらいのことだったらどうする、知らなきゃよかったと思うでしょ」
「でもいいこともあるわけ」
「そうね、ある病気になりやすいことを知ったら、それを避けるように工夫ができるものね」
医者と同じことを言った。
「遺伝子っていくつもあるんだろう」
「二万いくつかって書いてあった気がする」
「そんなにあるの」
「生き物によって違うからね、多ければいいわけじゃなくて、その遺伝子がうまくコントロールされていれば、複雑な進化した生き物となるわけよ」
「遺伝子が多くなくてもいいんだ」
「そう、遺伝子は、数だけでいえば人は必ずしも多くないらしい」
叶さんはいろいろなことよく知っている。
「脳に茸ができてから、いろいろ興味を持つようになったわね、久米君、それはいいことよ」
と言われてしまった。確かにそれまではからだのことなど全く興味がなかった。
遺伝子検査の結果を聞く日が来た。
病院で名前を呼ばれ診察室に入ると、室田先生はなにやら細かな記号や数字が書かれている紙を見ている。僕が入っていくと、
「元気そうですね、どこかおかしいところありますか」と笑顔になった。茸のおしゃべりが聞こえることを言おうかどうしようか迷っている。
なにもないと答えると、遺伝子検査の結果を教えてくれた。
「私は遺伝子の専門家ではないのですが、遺伝子解析の専門家の付箋が付いていていますので、それから説明します」
内容はこういうことだった。
「わかっている病気の遺伝子に関しては、大きな問題のあるところはありませんでした、ガンにしても、血圧にしても、本当に珍しいくらいきれいな遺伝子です」
わ、嬉しい。
「ところが、わからないと言うか、おかしな部分が見つかりました、動物にはない遺伝子が混じっているのです。それは働いてはいないようなので、体に影響を及ぼすことはないでしょう」
なんのことかわからなかった。
「動物にはない遺伝子だとすると、植物の遺伝子ですか」
室田先生は首を横に振った。
「いえ、菌類の遺伝子です」
「茸の遺伝子ですか」
「まあ、そうです」
「それがあるとどうなるのでしょう」
「わかりません、菌糸をのばす遺伝子のようです、それが久米さんの遺伝子の中にあったので脳に茸ができた可能性は否定できません」
ずいぶん持って回った言い方だが、やっぱりそれしかないのだろう。ということは、また茸ができる可能性があるということだ。
「どうして、茸の遺伝子が僕の遺伝子にまざったのでしょう」
「まったくわかりません」
茸のたくさん生える信州でうまれたからか。
「また脳に茸ができるのでしょうか」
「いや、脳に馬糞茸はもうできないでしょう、馬糞茸の遺伝子ではありませんでした。久米さんの遺伝子の菌類というのは、どうも冬虫夏草のたぐいのものらしいとあります」
「冬虫夏草ってなんですか」
「蝉の幼虫などにその菌がつくと、蝉になる前に体に菌糸が回って、その幼虫を殺してしまい、そこから茸がでてくるのです」
僕がびくっとしたのを見て、室田先生はあわてた。
「あ、いや、冬虫夏草が久米さんに生えると言うことではありませんから、安心してください。ほ乳類に生える冬虫夏草はありません」
「それで、僕はどうなりますか」
「いや、どうもならんでしょう、珍しいケースとして学会誌にのるくらいです」
「でも、いつか茸が僕から生える可能性はあるのですね」
彼は首をひねっていた。なんと答えたらいいか考えているのだ。正直な先生だ。
「実はこの遺伝子は面白いところにあるのです、Y染色体というのはご存じですか」
「男の遺伝子と聞いたことがあります」
「そうなんです、男と女の方向を決める遺伝子のあるのは性染色体です。それにはXとYの二種類があります、Y染色体に精巣を作る遺伝子があります。要するに男の遺伝子です。Y染色体はとても小さい染色体で、しかも遺伝子がのっていない不思議な場所がありるのです、何をしているのか分かりません、そこに冬虫夏草の遺伝子があったのです」
「僕の精子にはその遺伝子が入っているわけですか」
「いや、精子の性染色体はYかXだから、精子の半分にははいっていません」
「もし、僕に男の子どもができれば、受け継がれるということですか」
「そうですね、おわかりになっているじゃありませんか」
ともかく、そのようなことで、遺伝子検査の結果はわかっている病気に関してはリスクがすくないことがわかりほっとしたが、茸の遺伝子を持っている人間第一号として、有名な科学雑誌に載ることになった。茸の遺伝子を持つ人間第1号である。その雑誌の表紙には冬虫夏草の写真が載っていた。室田先生が祈念に一冊くれた。
僕は茸の声が今でも聞こえてくる。僕が茸に話しかけても、茸は反応してくれない。それができるようになると、僕は人間で茸の仲間でもあることになる。しかし茸の声で両親を救うことができたのは茸に感謝しているが、今では茸の声は耳鳴り程度にしかとらえていない。頭の中に馬糞茸もはえることはない。そういうことで、僕は至極元気に会社勤めをし、生活をしている。
今、やたらと室田先生からからだの様子を聞く電話がかかる。遺伝子検査では病気にはかかりにくいことがわかったのだから、そんなに電話をよこさなくてもいいのにと思うのだが、冬虫夏草が僕から生えるのを待っているのだろうか。
そう考えると、なんだか股間がむずむずする。股間に茸が生えたらどうなるのだ。複雑な気持ちである。
最近、結婚をどうしようか思案している。この遺伝子は僕だけで終わらせたほうがいいのではないかと考えたからだ。一方で、大事な人間の進化を中断してしまうことになりはしないのか、とも考えてしまう。
茸に好かれ、茸の遺伝子を持つ人間第1号の心の葛藤が脳の中に芽生えたのである。
脳の中
私家版 第十三茸小説集「珍事件、2022、一粒書房」所収
茸写真:著者: 長野県北安曇野郡白馬村 2016-9-12


