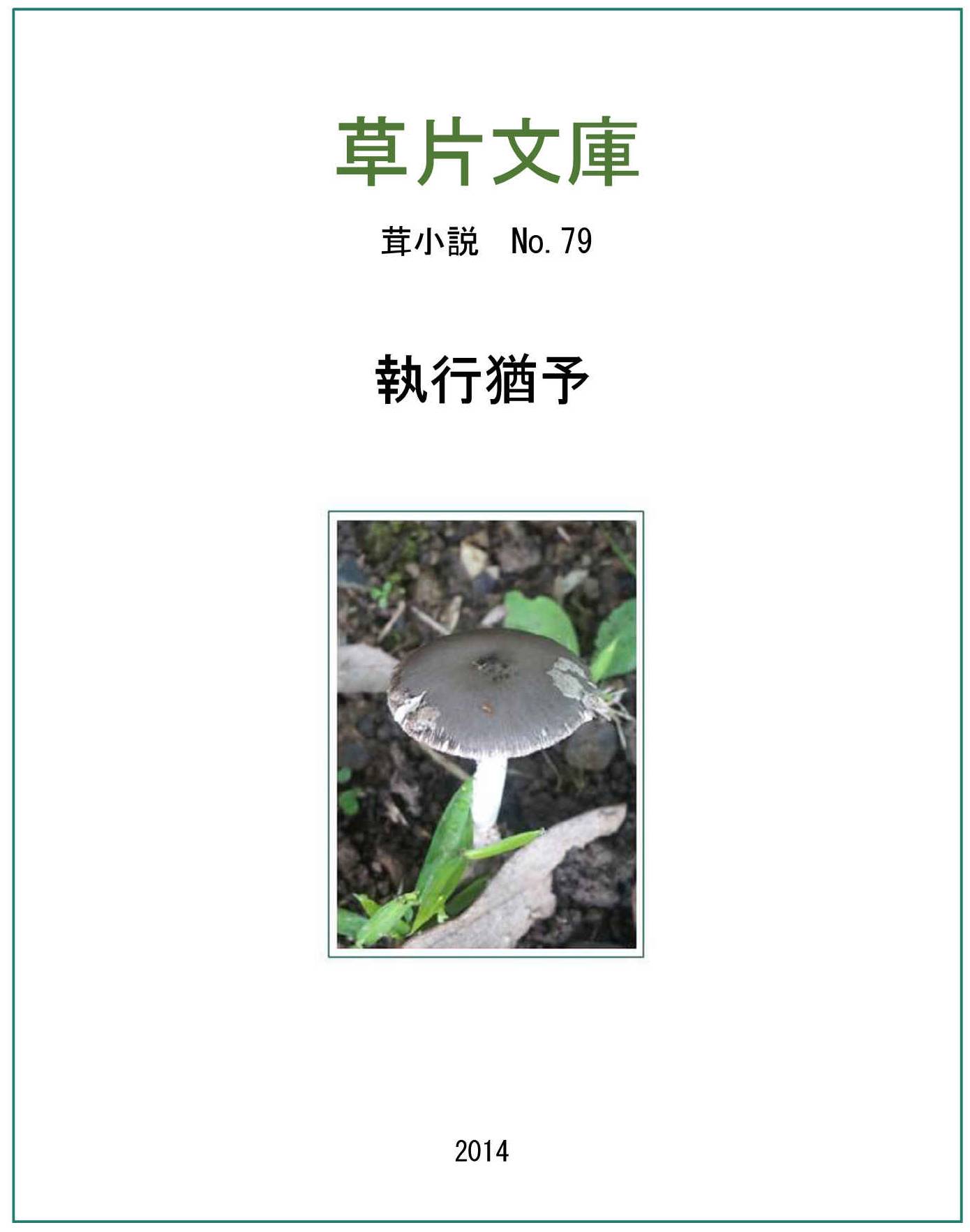
執行猶予
秋晴れの続いた先週の日曜日、会社の同僚たちと高尾山にハイキングに行った。噂には聞いていたが、あまりの人の多さにうんざりして、途中から林の中の横道にそれた。人気の少ないところで、やっと自然に囲まれた気がしてきた。
「どこかで、お弁当にしよう」
秘書課の鞠目(まりめ)が大きな目で僕を見た。
「うん、腰を掛けるところがあったらそうしよう、みんなもいいかな」
洋和も美知もうなずいた。
林の中の一本道をいくと、きれいな水たまりのある場所にでた。大きな木が何本か切られていて、切り株が腰掛けに丁度いい。
我々は腰掛けて、めいめい持ってきたお弁当を広げた。
僕はコンビニで買ってきたおむすびを取り出し、洋和は奥さんの作った弁当を広げた。鞠目と美知は東京駅で買ってきたお弁当だ。結婚しているのは洋和だけである。奥さんも誘ったのだが、子供の幼稚園の遠足で来られないとのことだった。洋和の弁当は遠足のおあまりということになる。
紀ノ国屋の弁当をつつきながら、鞠目が下草の中を指差した。
「あそこにポツポツと赤いものが見えるけどなにかしら」
確かに赤いものがある。
「茸だろう」
「赤いのは毒ね」
美知が赤いウインナーソウセイジをほうばりながら、もごもごと独り言のように言ったのに対し、めずらしく洋和が口を開いた。
「赤いのでも食べられるのもあるんだよ」
洋和は人付き合いが得意ではない。女の子と話すことなど、仕事以外にはないだろう。よくハイキングに来たものである。
「茸に詳しいんですね」
「詳しい訳じゃないけど、日本ではほとんど食べない真っ赤な卵茸はおいしい茸なんだよ、高尾山にもよく生えてたな」
だから来たんだな。
「どんな風においしいの」
「バター炒めにすると、いい味がでるよ」
「食べたことがあるの」
「うん、かみさんも茸に詳しくてね、家の近くの公園にたくさん生えたことがあって、採ってきて食べさせてくれた」
「へえ、奥さん料理の先生でもしているの」
「うん、その通り、料理を教えている」
それは知らなかった。
「うらやましいね」と、本音がでた。
「早真(そうま)さんも、早く結婚したらいいのに」
僕は早真光也と勇ましい名前をもっている。
食べ終わった鞠目が立ち上がって、草むらに入っていった。
赤い茸をとってくると、「これが卵茸」と洋和に尋ねている。
「ちがうよ、卵茸なら白い壷がある、これは、紅天狗茸っていう猛毒茸だよ」
「やだあ」
鞠目は茸を放り出すと足で踏みつぶした。そのうえ、草むらに入っていくと、足ぶみをしている。
「八本も生えていたのよ、誰かが触ると危ないから、踏みつぶしたの」
「毒と言っても、たいしたことない、むしろ精神異常になる」
洋和が笑っている。
お昼を食べてもう少し先まで歩いた。遠くまで見渡せる絶景のところに出た。
遠く新宿の高層ビルまでよく見える。
「そろそろ帰ろうか」
鞠目と未知はもう満足のようだ。早々に高尾山を降りた。都合よく京王線の発車時刻だ。帰るのにはまだはやいとみえ、すいていてみんな座れた。洋和は千葉、あと都内のマンション住まいだ。電車が動き出すと鞠目がぽそっと一言。
「どこかで飲んでいきたいな」
「私もいくよ」
美知も同調する。洋和までうなずいた。
「それじゃ、大国魂神社にでもよるか」
ということで京王線府中駅で電車を降りた。府中は久しぶりである。以前大国魂神社に初詣に来たことがある。
駅からつながっている伊勢丹の中を降り、大国魂神社に突き当たる大きな通りにでたのだが、入りたくなるようなお店はなく、府中本町駅近くまで来てしまった。
わき道をのぞくと、暖簾がかかっているのが見えた。行ってみると、間口は狭いが、入口が昔ながらの引き戸になっている焼鳥屋だった。茶色の暖簾に焼鳥としか書いていていない。しかしいい匂いがする。よさそうだ。
「ここにしよう」
美知が促した。私が引き戸をあけると、裸電球の下で鉢巻姿の老人が焼き鳥を焼いている。その前のカウンターには誰もいない。
「へい、らっしゃい」
老人がこちらを向いた。誰かに似ている。そうだ昔の喜劇俳優だ、名前を思い出さない。
「あちゃこに似てる」
鞠目がくすっと笑った。
「お任せでいこうか」
僕が聞くとみんなうなずいたので、
「お任せします、適当にお願いします」とたのんだ。
「うーん、困った、うちは安くないよ」
みんなは顔を見合わせた。確かに料金表がない。
「それじゃ、最初にふつうの焼き鳥をめいめいに一本」
洋和がこれも珍しく注文をした。
「あいよ、飲み物は」
「生ビールありますか」
「冷えたのがあるよ」
「お願いします」
「最初に出すかね」
「はい」美知が返事をした。
「焼鳥は時間かかるよ」
「はい」今度は鞠目が返事をした。焼鳥屋のおやじが鞠目をぎろっと見た。
おやじは、冷蔵庫から冷えたグラスをとりだすと、ビールの注ぎ口に置いた。スイッチを入れるとゆっくりとビールが注がれていく。別の冷蔵庫を開けると茶色いものを四つ取り出して自分の前に置いた。
我々は何だろうと目をやったが、美知が「えっ」という顔をして私を見た。
ビールが一杯になると、
「どうぞ、どなた」とおやじがいうので、私が女性の方を指さした。おやじは美知の前におき、また注ぎ口の下にグラスを置いた。
「飲みなよ」私は美知にうながした。
一口のんだ美知は「あー、おいしいビール」と驚いた顔をした。
「地ビールだ」
おやじが言った。その手を見ておどろいた。死んだ雀が握られている。おやじは毛をむしると手元で雀を解体しはじめた。
みんなもそれに気づいた。
おやじが、洋和の前にビールを置いた。
雰囲気を察したかのように、おやじがつぶやいた。
「本物の雀焼きだぞ、食うところは少ないが、空気銃でとっつかまえるのも、時間がかかる」
聞いていなかったのか鞠目がにこにこして、「おじさんなにしてるの」と聞いた。
「焼き鳥を作ってるのさ、一人前は一羽、自然ものだわさ」
我々はお互いに顔を見合わせた。鞠目はやっとわかったようだ。びっくりしているどころではない。おそるおそる僕が聞いた。
「早くできるものはなんでしょう」
「そうさな、エリンギや舞茸ははやいよ」
「それもください」
おやじが、私の前にビールを置いた。
「椎茸なんかもいいな」
僕が言うと、おやじはじろりと僕を見た。
「ないよ」
訳が分からないことを言って、串に刺した薄っぺらい肉の破片を火にくべた。
「今、雀を乗っけたからね」
エリンギと舞茸も冷蔵庫から取り出した。
「これだって、地元産だからな」
おやじは雀焼きをひっくり返した。
やっと鞠目の前にビールが置かれた。鞠目はグーッと半分以上飲み干した。
焼き始めれば早い。雀焼きは我々の目の前に置かれた。
「食っていいよ」」
おやじの声で、雀の貧弱な肉をかじりとった。たしかにうまいものである。だが、ビールがもうなくなってしまった。
「ビールもういっぱい」
美知が声を張り上げた。
「同じものかい」
「ええ」
「ふーん、金持ちなんだな」
「このビールそんなに高いの」
「ベルギーの工場に特別注文してつくらせている」
「え、日本の普通のビールでいい」
「はじめからそういえばいいじゃないか」
おやじの胸のポケットから携帯の振動音が響いた。
「お、連絡きた」
おやじはそう言うと、携帯を耳に当てた。
「ええ、来ています。いま、雀焼き食ってます、目の大きいの、はいかしこまりました」
「これから裁判官が来るから、待ってなさい」
おやじはエリンギと舞茸を冷蔵庫のもとのところにしまってしまった。
しばらくすると戸が開いた。紺のスーツを着た髭を生やした男性が入ってきた。
「お待ちしておりました、どうぞ、ほれ、あんた、脇にどいて」
おやじは僕を指さして、席を空けるように指図した。
僕は立ち上がった。どこに行っていいのかわからなかったが、おやじが洋和の隣を指さしたので、そこにビールと皿を持って移った。その紳士は鞠目の隣に座ることになった。
「あんたさんか、高尾山で茸を踏んだのは」
紳士が鞠目に声をかけた。
びっくりした鞠目は私たちの方を見た。
「あんたさんだね、紅天狗茸を踏んだのは」
また紳士が言った。鞠目は気味悪そうにうなずいた。
そこへ、また、客が入ってきた。
赤いスーツを着た、色の白い外人のようなほりの深い顔をした女性だった。
「裁判長、いらっしゃいませ」
「しばらくぶりね、お元気でした、お目にかかるのは引退してから初めてかしら」
「そうですねえ」
「やだ、大先輩にそんな丁寧な口をきかれちゃあ、やりにくくなる」
「今じゃ人間に焼鳥食わしているんで」
「おかげで、人間の情報が入る、感謝しているんです。そのうち感謝状がでると思います」
「そんな、感謝状なんて、人間がやるようなことを考えるこたあないよ」
「でも、所長が人間の世界にはいると言われた時には驚きました」
「そうかね、人間って言うのも案外面白いよ、単純でね」
そこに、また、年をとった背広姿の男性と、ジーパン姿の若い男の子が入ってきた。
「あ、ごくろうさま、それじゃ、そちらに座ってください」
カウンターはいっぱいになった。
我々は呆気にとられて、食べるのも忘れていた。
「さて、始めてください」
いったいなにをしようと言うのだろう。
赤いスーツの女性が言った。
「それでは、裁判を始めます。検察官陳述をしてください」
最後に入ってきた老人が、鞄から書類を取り出すと、読み上げた。
「高尾山頂近くで、紅天狗茸八体の殺茸の罪で、あの女性を訴えます。今日、十一時五十八分、なにも罪のない茸を一つ抜き取り、踏みつぶし、さらに、その仲間七体を踏みつぶすという暴挙を行いました、その罪は重く、終身刑を言い渡します」
「ふむ、その証拠はありますか」
赤いスーツの女性が聞いた。
「はい、この青年が一部始終を見ておりました、切り株の脇に住んでいる万年茸でございます」
「万年茸、検察官の言ったことにそういないか」
青年は「はい」と答えた。
裁判長は鞠目にむかった。
「紅天狗茸を踏み潰したのに相違ありませんか」
といった。
鞠目はびっくりして、こっくりとうなずいた。我々もこれはなんだと声がでない。
「ハッキリ言ってください、どうですか」
「はい」
鞠目は小さな声で答えた。鞠目が僕を見た。僕はそれでいいんだとうなずいた。洋和は口を開けたままだ。美知にいたっては鞠目の腕をつかんで震えている。
「それでは、弁護人、どうですか」
「はい、これから、被告に尋ねたいと思います、被告人、なぜ赤い茸を踏んだのですか」
「怖かったからです」
「生き物を無意味に殺すのは罪になりますが、そのことは知っていましたか」
「はい、でも、子供の頃から花をつんで遊んでいたので、植物はかまわないと思いました」
ずいぶんしっかりとした答えである。
「茸は植物ではありません」
裁判長が言った。弁護士が手を挙げた。
「裁判長、このように、この人間は、無知からしたことですので、無期懲役ではなく、懲役20年ほどだと思いますが」
検事は立ち上がると首を横に振った。
「いや、被告は、紅天狗茸を一つとって潰したあと、わざわざ戻って、すべて潰すという一級殺茸をおこなっていますので、無期懲役が妥当だと思います」
これはまずいと思ったので、私が立ち上がって言おうとした時、裁判長に制された。
「傍聴人は発言できません」
僕は弁護士に、証人として発言させてくれるように言った。
弁護士が、「あの、男を証人台にお願いします、その場にいた人間です」
「検事はいいですね」
検事がうなずいた。
「鞠目さんは、自分の為に紅天狗茸を踏んだのではありません、子供がきて毒に当たると危ないと思ってしたことです、その場でそう言いました」
「それは確かですか、万年茸も聞きましたか」
万年茸は正直に、
「はい」と、うなずいた。
裁判長が宣言した。
「それでは、言い渡します。懲役五年、執行猶予十五年とします、さらに、周りの人たちはそれを止めなかったことから、執行猶予一年にします」
裁判長がそういい終わると、焼鳥屋のおやじが、
「はい、一人五千円」
と言って、私たちを見た。
周りには誰もいない、我々だけであった。
結局茸は食べず雀焼き一本しか食べなかった。高すぎるとは思わず、お金を払い、我々はぼーっとなって電車に乗った。いつの間にか家に帰り着いていたのである。
会社での仕事生活にはかわりがなかった。ところが、我々自身はたいへんなことになっていた。次の年の春、やたらとくしゃみが出るようになった。美知と洋和も同じようにくしゃみの連発だった。ちり紙が離せない。当然のこと病院にいった。重症のスギ花粉症だといわれた。
鞠目は元気だった。夏休みになるころに我々の頃花粉症はおさまり、どうやらいつもの生活に戻っていた。ところが、秋の兆しが見えてきた頃、元気だった鞠目は仕事をよく休むようになった。体がだるくて、熱が無いのにあつっぽく、仕事に集中できないという。
僕が彼女の分も、仕事をかたずけた。
あんなに元気だった鞠目は、目に見えて顔が引きつれていた。
ときどき、食事に誘ったりしたのだが、なかなかよくならない。それどころか、奇妙なことに、茸が食べられなくなっていた。茸を食べると吐き気がするそうである。
病院に長く通い、やっと原因がわかった。
茸のアレルギーであった。彼女はくしゃみも出はじめ、マスクが離せなくなった。マーケットの茸売り場の近くにはいけなかった。特に椎茸アレルギーである。
彼女が僕に打ち明けた。
「わたし、仕事できないわ、やめようかと思うの」
「茸アレルギーでかい、秋がすぎればなおるんじゃないの」
「お医者さんが、今はコンビニまでも茸が売られていたりするので、冬になっても、春がきても、一年中茸アレルギーはついてまわるんだって」
「仕事やめて、どうするの」
「おくさんにして、家事はできると思うの」
という具合で、彼女は仕事をやめ、僕の奥さんになることになってしまった。僕には嬉しいことだったのだが。
「高尾山の帰りの焼鳥屋のことみんなあまり覚えていないようだけど、私だけはしっかり覚えているのよ、私茸にしかられたのよ」
あの焼鳥屋のことは美知も洋和も僕も、本物の雀を食べたことしか覚えていなかった。
それから十五年、会社では洋和が別の部署の部長になって、僕が今までいた部署の部長になっている。美知はあのあと、海外の会社に移り、今はニューヨークにいる。
結婚してからも、鞠目は秋になるとアレルギー反応を起こし、くしゃみがとまらないことが時々起きる。それでも元気な二人の子どもができた。
今二人の子供はもう中学生である。
ある秋晴れの日曜日、朝、ベッドから起き上がり、歯を磨いたあとに、ダイニングに顔を出すと、鞠目が嬉しそうに言った。
「あなた、不思議なの、今日目をさますと、鼻がすーっと通って、肌がすべすべになっているの、若い頃のようよ」
確かに、顔に艶がでている。
「更年期の始まりじゃないの」
「まさか、それじゃ反対よ、それに更年期はまだまだよ」
「散歩にでも行ってみるか」
「うん」
今までは、秋になると、鞠目のアレルギーはひどくなり、散歩どころではなくなる。町のコンビニで茸が置いてあるとくしゃみがでた。だから、買い物は私がやっていた。
秋に二人して外にでるのは久しぶりである。
「秋晴れね、きれいだわ」
「くしゃみでないね」
「だいじょうぶみたい」
駅のコンビニの方に歩いていくと、朽ちた木から黄色い茸が生えていた。
「あ」と黄色い茸を見て鞠目が声を上げた。アレルギー反応はおきていない。昔なら大変だ、くしゃみで鼻がくしゃくしゃになっていただろう。
「ねえ、昨日、何日だった」
「十月七日だよ、なぜだい」
「昔、高尾山にいったの、十月八日じゃなかった」
「そう言われて、思い出した、昨日で十五年だ」
「そうよ、わたし、執行猶予十五年、無事はたしたのよ」
「なんだっけ」
僕は全く覚えていない。
「焼鳥屋で私の裁判が行われたの、あなたたちは杉花粉症で執行猶予一年ね、私は茸の胞子のアレルギーで終身刑になるところだった、あなたが弁護してくれて、執行猶予十五年になったの」
コンビニに入ると、新しい椎茸が山盛りになっていた。
「おいしそう、食べたらいけないかしら」
「きっと大丈夫だよ」
椎茸を一袋買った。
夕飯に天ぷらにした。
「おいしい、おいしく食べるのはいいのね」
執行猶予が終わった鞠目は幸せそうだった。
鞠目をみて、ふっと頭がはっきりした。思い出した。とても奇妙な焼鳥屋だった。あそこにきた裁判官たち、だれだったのだろう。それにあの雀焼、本物だったのだろうか。
執行猶予
私家版 第十三茸小説集「珍事件、2022、一粒書房」所収
茸写真:著者: 東京都日野市南平 2015-7-12


