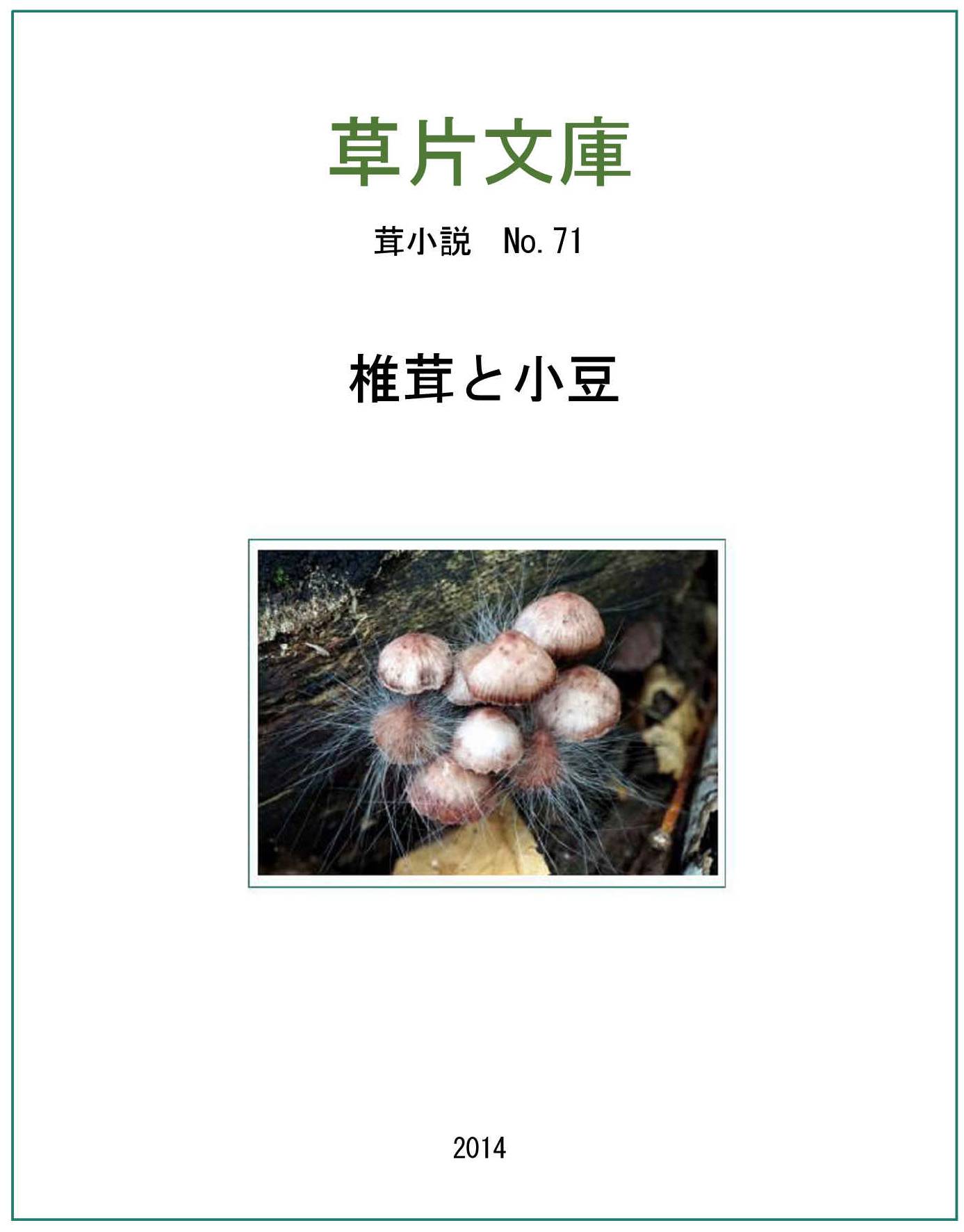
椎茸と小豆
窓の外を見ると、少し先の電線に数羽の雀が止まっていた。顔をこちらに向けている。かわいらしいものだな、と思っていると、真ん中ほどにいた一羽を周りの雀が押し始めた。押しくら饅頭だ。押されている一羽はもこもこしている。いや、なんだかほかの雀より太っている。
いじめるんじゃないよ、などと思いながら、机の上のPCに眼を戻した。頼まれた原稿の締切りが迫っている。
十枚ほどの短いものだが、テーマが小豆と茸という、なんだか結びつきの悪いものである。頼んできたのは、男の料理の雑誌で、今はやっている退職後の趣味として、料理の楽しさを説いている本である。雑誌を支えているのは、材料を提供する会社で、いかに自分の材料を使ってもらおうかという魂胆がすいてみえる。
このテーマも、編集長が茸の栽培の会社と、小豆の会社のご機嫌を考えた苦肉の策である。迷惑な話ではある。
椎茸の頭を焼いて餡子を詰めると、鯛焼きのようになるかもしれない。一度やってみるか。などと、考えているのだが、ワードの画面はまだ白紙のままだ。
窓の外から、じゅじゅくと雀の声がした。
まだ電線の上で押しくら饅頭をやっている。先ほどと変らず、真ん中の一羽を両脇から押している。
眼を凝らすと、真ん中の一匹はどうも雀としてはおかしい。どのようにおかしいか。なんだか寸胴なのである。薄い茶色に見えたやつだが、そいつの頭が赤っぽく見える。
近眼の私にはよくわからない。机の引き出しから双眼鏡を取り出した。遠くに山並みがあり、天気のいい時にはのぞいてみたりする。
だが、年をとってからはピント合わせが大変だ。赤い頭がふらふらしている。
双眼鏡の視野にやっととらえることが出来た。くっきり見えた。だが雀の間にいるのはありゃなんだ。
茸に見える。
そんなはずはない。そう思っていると、雀たちが電線から飛び上がった。カラスが電信柱の上に止まったので逃げたのだ。
頭が赤い茸に見えるものも飛び上がった。
ということは茸ではないのだろう。
双眼鏡で追いかけると、ピント合わせが大変だが、雀と一緒に飛んでいる。茸と小豆のことを考えているものだから、そのように見えたのに違いがない。
雀たちはこうして視野から消えていった。
さて、原稿用紙ならぬワードの画面に眼を向けた。さっき頭に浮かんだ小豆を餡にして椎茸に詰めるお菓子はいいかもしれない、そのレシピをつくろう。
小豆を茹でて砂糖を加え潰す。生椎茸は頭だけを切り落として、ボイルした湯に入れしばらくおいてからとりだす。レモンを絞っておくとちょっといいかもしれない。水をきって餡を詰め、二つを合わせる。とりあえずそれで、焼けば鯛焼きのような状態だ。というより形は太閤焼きか。次にオーブンにて焼く。熱々の椎茸焼きができあがる。
このままでもいいが、衣をつけて、天ぷらにするのもいいだろう。
今回はこのレシピを考えた過程を述べて、次回には作って食べた感想を書くのがよい。レシピを知り合いの料理家に送り、実際に作ってもらって、食べてみるか。
このような一案ができたのでほっと一息、窓の外を見た。
なんだ、また雀が電線に止まって押しくら饅頭をしていやがる。さっきと同じで、真ん中に雀とは違う鳥が止まっている。今回は頭が黒い。茸に見えたやつだ。
見ていると、茸のような鳥を隣の雀が突っついた。突つかれた鳥の黒い頭が削られて下に落ちた。
あわてて双眼鏡をつかむと雀たちに向けた。焦点を合わせるためダイヤルを回した。焦点が合ったと思ったとたん、みんなして飛び上がった。茸のような奴も飛び上がった。双眼鏡の視野の中は茸のような物を二羽の雀の足がつかんでいるのが見える。
鳥じゃないな、やはり茸なのだろうか。そんなことはないだろう。電線に茸が止まるわけがない。
双眼鏡を机の上に戻すとPCに眼を戻した。
さて、もう一つ小豆と茸の料理を考えなければ。
もう一つ甘いものといくか、汁粉に椎茸もいいかもしれない。これなら簡単だ。よしと、だが、男の料理の本だから酒のつまみを考えなければ。
小豆と椎茸の塩茹でで立派なつまみだが、それじゃつまらんだろう、それじゃゆでてオリーブオイルに入れ、ハーブで香りと味をつけ、それに椎茸の細切りをトリュフのようにしてくわえて味を調える。これは、ちょっとしたつまみにはなりそうである。
それをワードに書きしたためた。
もう一つ、茹で小豆を押しつぶし、醤油を足し、レモンを搾り、味噌のようにするのもいいだろう。これなら焼き椎茸の頭につめると結構旨いかもしれない。ビールにいけそうだ。と、とんとん拍子に二つばかりまとまった。
窓の外をみると、また雀が押しくら饅頭をしている。いやまてよ、おかしいな、真ん中にいるのは雀だが、まわりは茸のようだ。さっきと逆だ。茸が電線にとまって押しあってやがる、真ん中の雀をギュウギュウ押している。
目が疲れているのだろうか。雀がみんな茸に見えてしまう。だけどよく考えたら、この季節、寒くもないのになぜ押しくら饅頭をやっているのだろう。九月はじめ、まだ秋の序の口である。
茸に見える雀の頭が白かったり黒かったり赤かったりする。光のあたり具合でそう見えるのだろうか。羽は茶色かというとそうではない、というより羽がない。だから寸胴だ。ということは茸なのである。
目をこすってみた。ちょっとぼやける。疲れているようではある。
午後の二時を回っている。少し休もう。
ベッドに入って、読みかけの本を読み始めたがすぐに眠気がおそってきた。後期高齢者になってからは昼寝が欠かせない。
夢を見た。
ひなびた温泉峡にきている。雪に埋もれているところを見ると、私の田舎の秋田のようだ。下駄を履き、旅館の母屋から庭に出ると、石段を登って離れの温泉小屋に行った。戸を開けて中にはいると、薄暗い裸電球が脱衣場を照らしている。羽織っていたどてらを脱いだ。
湯殿にはいると紫色の湯がたっぷりと沸き出ている。湯気の中、湯に入ると、どろどろの紫の湯が肌にまとわりついた。
周りを見ると、粒粒が浮いていて体にぶつかってくる。湯加減はちょうどよいのだが、ねっとりとした湯がまとわりついているのはさっぱりしない。
ぽちょんと湯がはねて口に入った。
甘い。
何だと見渡すと、どうも汁粉の中にいるようだ。天井がいきなりなくなった。家内の顔がのぞいている。
「汁粉に椎茸が入っているわ、またあなたのばかばかしいレシピなの」
横を向いて言っている。
私は自分をみた。手足がない。椎茸みたいだ。家内は私を見て椎茸と言ったのだ。
私の頭に箸が落ちてきた。それに挟まれると持ち上げられ、家内の口の中に吸い込まれた。
歯がせまってきて気絶をした。
「あなた、何うなされているの」
ベッドの上から家内の圭子がのぞいている。猫の玉が胸の上に乗っている。
「いや、変な夢を見たんだ」
「玉が乗っていたからでしょう」と玉をベッドの脇におろしてくれた。
「はい、葉書と手紙」
圭子が郵便物を届けに二階の私の部屋にきたのだ。
「仕事はかどっているの」
「まあまあな、お前が作れるものがあるから、レシピを渡すよ頼むな」
簡単に家庭でできるものは圭子に作ってもらうことがある。
「なにを」
「椎茸の鯛焼き」
「何それ、鯛焼きの中に椎茸を入れるの」
「それに近いが、ちょっと違う、いや大分違う」
「またなの、いつも美味しくないものを作って、それを美味しいって書いて、いいの、そんな嘘ばっかで」
勝手なことを言っている。作るのが下手だからまずいのだ。
「へへへ」
私はベッドから降りると、玉の頭をなぜ、また机に向かった。
窓の外を見ると、雀がたくさん飛んできた。雀たちは電線に止まった。今度は子供の雀のようで、かなりちいちゃい。雀そのものも小さくてかわいいものであるが、さらにかわいらしい。子雀たちも押しくら饅頭を始めた。真ん中にいるのはと見ると、真っ赤な雀である。いや、茸に見える。
圭子を呼んだ。
「なあに、お茶でもほしいの」
下の部屋から声がした。
「いや、ちょっと上がってきて見てくれよ」
「今、玉に餌やってるのよ、終わったらいく」
圭子はすぐに二階に上がってきた。
「あの電線を見てくれよ」
圭子が電線を見ると、ふぁーっと、子雀が舞い上がるところだった。
「あら、子雀ね、かわいらしい」
「電線で押しくら饅頭やってるんだ」
「へー、寒くもないのにそんなことして遊んでいるのね」
「それが、必ず、雀とは違うものが真ん中にいてね、それが押されてるんだ」
「それ、なーに」
「茸のように見えるんだ」
「まさか、あなた疲れているのね」
「そうらしい、それでちょっと昼寝した」
「まあ、のんびりやってよ」
圭子は下に降りていった。
PCに向かって、また椎茸と小豆のレシピを考え始めた。
ジュースにするのはどうだろうか。椎茸のドリンクというのを飲んだことがあるが、やはり匂いがすっきりこない。といって小豆のドリンクだと、汁粉になってしまう。あまりいい取り合わせではない、それでは、それに何か加えるのはどうだろうか、しかしほかの果物を入れても、椎茸の匂いを食欲がそそられるように変えることは難しそうだ。飲料にするのは無理だろう。あきらめよう。
また、電線にたくさんの雀が集まっている。押しくら饅頭を始めた。真ん中に茶色い傘の茸のようなものがいる。雀がその茸に向かってからだを押している。
見ていると、一斉に飛び立った。茸も飛び立った。二羽の雀が寄り添っているところを見ると、支えているのだろうか。
雀たちが窓の方に飛んできた。見ているうちに開けてある窓の縁に止まって、押しくら饅頭を始めた。真ん中にいるのはなんと椎茸だった。
呆気にとられていると、雀がその椎茸をけっとばした。椎茸はぴょんと空中にとばされて私の机の上に転がった。
雀は、ジャラジャラジャラジャラと飛んで行ってしまった。
机の上に椎茸が転がっている。ただ何となくさわるのは気味が悪い。なぜ雀が椎茸を机の上に放りなげていったのか。いやこれは本当の椎茸なのだろうか。椎茸型爆弾か。雀が爆弾を持っているはずはない。とすれば偶然か。それにしてもできすぎている。椎茸のレシピを考えているところに、何で椎茸なんだ。
手を伸ばし、人差し指で椎茸の傘に触れてみた。
するといきなり、椎茸が起きあがって、机の上ですっくと立った。
なんだ、椎茸型のロボットか。
「違う、椎茸だ」
いきなり椎茸の傘が上下して、声がした。
「茸がしゃべるわけがない」
「バカにするな、しゃべるのは人だけじゃない」
「それで、なにの用で椎茸がここにいる」
「全く、人間てえのはほかの生き物に尊敬の念を持たない、困ったものだ」
「いや、そんなつもりはないが、驚いたからだよ、驚かない人間がいるだろうか、椎茸がしゃべって」
「確かに、いきなり現れてしゃべったら驚くよな、それはわかる」
「それで、もう一度聞きたいが、なぜいるのかな」
「雀に運ばれてきた、あんたの手伝いをするのが椎茸のためになると言われてな」
「それは、どうしてだろう」
「椎茸の旨い食べ方を教えて、椎茸の地位を向上させろと、雀が言うのよ」
「へー、それはありがたい、それで、どうやっていただこう」
「お吸い物も、焼いても、切り刻んでもそりゃ何でもうまい」
「そう思うよ、だけど、小豆と一緒に旨くなってほしいのだよ」
「小豆の奴も俺と同じで個性が強い、それを一緒にするのは難しい、しかし、できないことはない、すでにあんたも考えたろう」
「確かに、だがもっといい方法はないのだろうか」
「どちらも乾燥させ潰すのさ、混ぜようによっちゃ、面白くなる」
「椎茸小豆粉だな」
「そうよ、それでな、椎茸のあの独特の匂いと、小豆の匂いを強調するのよ、どうなるかな」
「なんだ、知っているのかと思ったら知らないのか」
「俺は椎茸だ、小豆と一緒になったことはない、ただ想像しただけだ」
「やってみなければわからんということだな」
「そうよ、不老長寿の粉になるかもしれん、フェロモンになるかもしれん」
「そうか、そうだな、もしだめでも砂糖を入れたり、練乳をいれたりして、菓子にすればいいしな」
「そうだよ、餅に絡ましてみな、きなこ餅のように結構売れるかもしれんぞ、自然志向だからな今は」
「まず粉にしよう」
「あなた、なに言ってるの、粉がどうしたの」
圭子の声が聞こえた。僕の肩をたたいている。
「なんだおまえ」
「なんだもないでしょ、大きないびきが聞こえるから上がってきたら、机にうつ伏せで大いびき、大丈夫」
「ああ、今、雀が椎茸持ってきて、その椎茸が面白いレシピを教えてくれた」
「なにが雀なの、夢でしょう」
「うん、あ、そうか、でもな、椎茸と小豆を干して粉にして椎茸小豆粉を作る、それで椎豆粉として、餅につけて食う」
「面白いわね、作ってあげたわよ」
「え」
「そろそろ、夕ご飯よ」
私はダイニングキッチンに降りていった。
テーブルにはすでに、皿が並んでいた。
椎豆粉が用意され、餅や、焼き鳥、があった。それをつけて食えと言うことだろう。椎茸の傘に小豆を練ったものが入っている皿があった。それをあげたものもある。お汁粉に椎茸が入っているもの、鯛焼きのように椎茸に小豆餡をいれ衣をつけて焼いたもの、すべてそろっている。
「おい、これ、さっき俺が考えたばかりのものだけど、どうしたんだ」
「あら、先月号に、あなたがのせたレシピに沿って作ったのよ、食べてもいないのに、さも食べたように書いていたじゃない。本当にそうかどうか、食べてみなければいけないなって、言ってたから作ったのよ」
「え、もう、本に載ってるのか」
「なにいってるの、今度のテーマは雀焼きだって、昔は本当に雀を食っていたんだよな、って言っていたじゃない」
そうか、今日は全く原稿が進まなかったんだ。
「あなた、近頃変よ、疲れているんじゃない、今日は一日、机に向かって、ぶつぶつぶつぶつ言っていただけでしょう」
「何で疲れるんだろう」
「あなた、いくつになっていると思っているの、もうすぐ九十よ、もっとのんびりしたら」
「そうか、もう九十か」
そう思って、机の上を見ると、机の上の椎茸料理が皆起き出して、椎茸と小豆が踊りだした。
「椎茸と小豆が踊っているよ」
そう言うと、三十下の圭子が、
「明日お医者さんに行きましょう」と優しく言ってくれた。
椎茸と小豆
私家版 第十三茸小説集「珍事件、2022、一粒書房」所収
茸写真:著者: 秋田県湯沢市小安 2017-9-17


