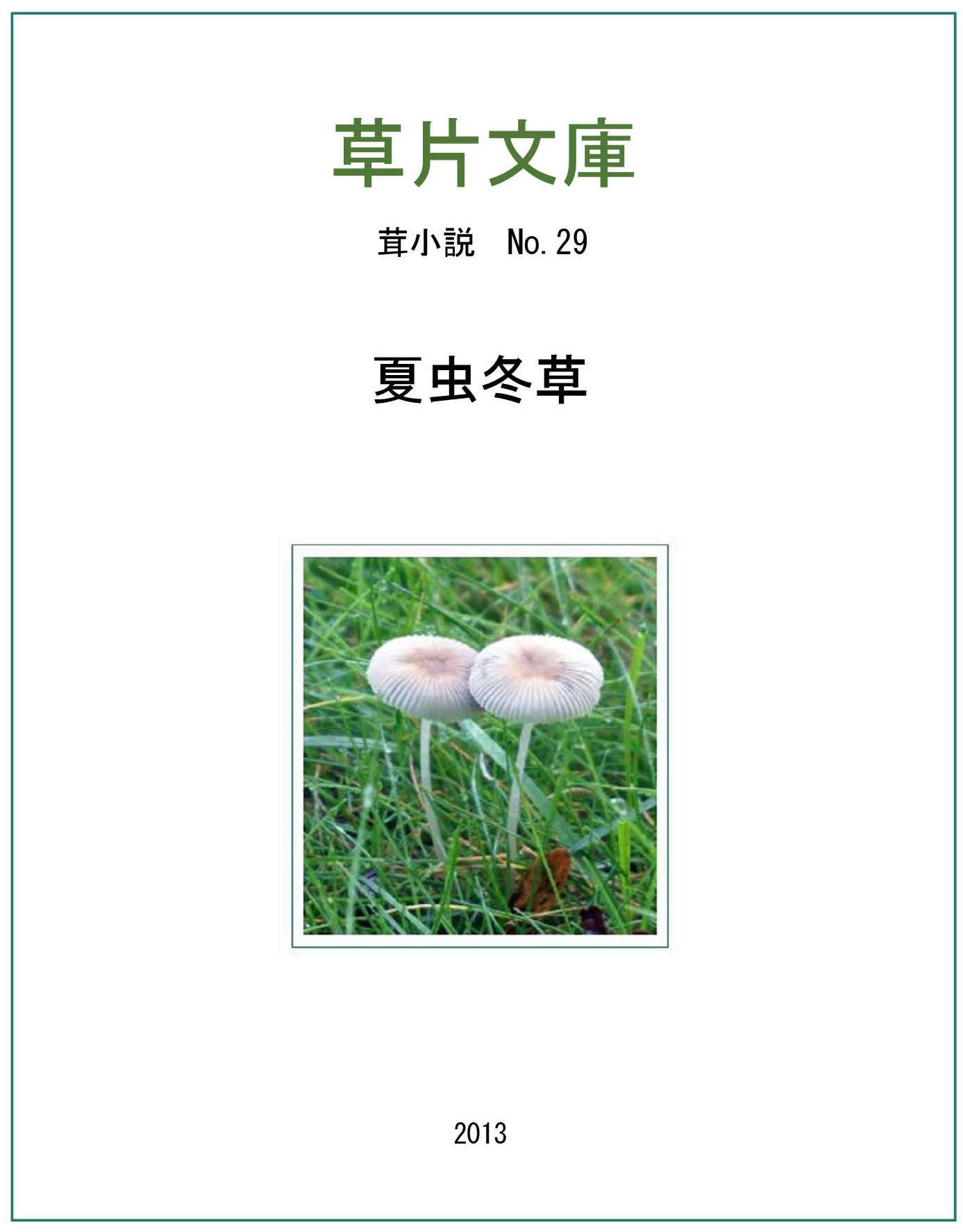
夏虫冬草
昨夜はあまり吹雪かなかった。と言っても、東京のほうから来た人からみればえらい降り方をしたと感じるであろう。それが寒い国、秋田の町である。
借りている家の周りには、雪が一メートルも積もっているだろうか。こちらではいつもの風景といえばそうなるのだが、東京から縁あってここにきて三年、慣れるにはなれたが、そんなに単純に同化はできない。
今日の朝はいい天気で、からりと晴れ上がっている。積もった雪が眩しいほどである。ふった後のこのような日は気持ちがいい。東京で味あうことはできない。
玄関の前の雪掻きを終え、着替えをすると、勤め先の図書館に行くために家を出た。
いつもの道を歩いて行くと、畑にも一メートルほど雪が積もっていて、真っ白だ。
ふと見ると、畑の真ん中あたりの雪の表面に、葱坊主(ねぎぼうず)ほどの真っ赤なものがニョッキリと飛び出している。やけに目立ってきれいだ。
立ち止まってよく見た。どこかで見たような感じだが思い出さない。出勤時間がせまっており、思い出さないまま歩き始めた。植物である事は確かだ。
図書館の入口につくと、いつものようにシャベルで雪をソリの上に積んでいる守衛の正直(まさなお)おじさんが私を見て頭を下げた。
「館長さん、おはようごぜえます、昨日の雪はてえしたことがなくてよかったす」
「そうですね、しばらく天気が続くということですね」
「そのようなんで、助かりますが」
おじさんは、ソリに積んだ雪を駐車場の脇に捨てにいった。彼の本名は高橋正直という。
図書館の玄関にはいると、受付の花ちゃんはもうデスクの準備をしている。花ちゃんは高橋花代というのが本名だ。いつも来るのが早い。
「おはよう」
「あ、おはようござえます、館長」
ニコニコと挨拶を返してきた。
図書館に勤める人たちは、私が館長になってから、気を使って標準語を話すようにしているようだが、どこかアクセントが違う。無理しなくてもよいと思うのだが、この町の人たちの親切心である。
自分のデスクの前に行くと書き置きがあった。
図書館員の高橋光平君の字だ。誰も彼もが髙橋である。秋田には髙橋姓が多いが、この図書館では私以外ほとんど髙橋だ。だから名前で呼ぶことが多い。
光平君は朝早くきて、どこかに出かけたようである。彼は東京の理学部出身だが、司書の資格をとり、この図書館に勤めた。図鑑やら理学書の整理をしている。もともとはこの町の出身者だから地元にもどったわけだ。
本人は植物や昆虫の写真を撮ったり観察をしたりするのが好きなので、この町に戻ったようだ。時として、カメラを持って、今のように外に飛び出していくことがある。このあいだは雪虫が現れたと騒いで、写真を撮りにいってしまい、半日図書館の仕事をしなかった。図書館も今は暇であり、そのようなことも勉強になるだろうと許している。それにこの町では、図書館が子どもたちにとって科学博物館である。子どもたちがこの虫なに、と彼に聞きに来ることもよくある。
書き置きにはおかしな茸がでたので調べてきますとあった。
それで思い出したのだが、図書館に来る途中で見た、雪の上に顔を出していた赤いものは茸ではないだろうか。彼の言う茸が私の見た茸のことであれば、彼と出会っているはずである。ということは違うところにもでているのかもしれない。それにしても、雪の今頃茸がでるというのは奇異である。
今日は特にしなければならない用事もないことから、私も彼の後を追うことにした。
「花ちゃん、光平君はどっちにいったの」
「市役所の隣の畑です。私も見たけんど、一メートルもある雪の上に黄色い細長いものがでていました」
「へー、僕は真っ赤なのを見たよ」
「えー、館長さんも見たですか」
「うん、家からくる途中だから、火之平さんの畑だ」
「あら、高橋家の本家さんの畑ですか」
「うん、それじゃ、ちょっと行ってくる」
そう言って、今脱いだばかりのジャンパーを羽織ると、僕はまず市役所の隣の畑に行った。
見ると、畑の中で雪に埋もれながら、光平君がスコップを持って雪を掘っていた。雪の上には黄色の細長いきりたんぽのようなものが突きでている。
光平君が僕に気がついた。
「館長、こんな寒いときに、こんな大きな茸が生えるなんて奇妙です」
「これ茸なの」
「多分そうです。冬虫夏草にそっくりです、でもこんなに大きくて、冬にでるのなんて知りませんけど」
「あ、そうか、冬虫夏草だ、どこかで見たと思ったんだ、夏に光平君がキノコの図鑑で見せてくれたんだよな、本物もとってきたよね」
「そうです、昨年の夏に山でずいぶん採りました。図書館にもってきて、種類を調べました」
「うん、覚えている、でも手の平にのるほどのものだったよね」
「ええ、これはとてつもなく大きくて、信じられません、誰かの作り物かと思ったのですが、触ってみると、まさに茸です。ほら」
黄色の頭に傷がついて、白っぽい繊維状の物がのぞいている。
「この茸は虫から生えるのではなかったかね」
「そうです、この下に何があるか楽しみで」
「そうだね、火之平さんの畑には赤いのがでてたよ」
「え、後で行ってみます」
光平君が雪をかき分けていくと、黄色い先っぽにつながる白い柄が現れてきた。くねくねと地面の方に延びている。一メートル以上ある。
光平君はスコップをさくっと地面につきたてた。くっと力を入れると、凍った土がもこっと盛り上がり、茸が横に倒れた。
茸の根本の土の塊がでてきた。
光平君は手で土を丁寧にはがしていった。
「でた」
彼の手元をみると、鼠ほどの動物があらわれた。
彼は叫んだ。
「土竜だ、土竜の冬虫夏草、いや夏虫冬草だ」
「土竜は虫じゃないよ」
私はちょっと得意げに言ったのだが、
「昔は、モグラもミミズもみんな虫といっていました、土の中にいるのはみんな虫です」
光平君は理系なのに、日本文化にもいやに詳しい。
「それを採っていってどうするかね」
「大学の友人が科学博物館で茸の研究をしています、連絡して来てもらいます」
「秋田のこんな田舎までくるのかね」
「もちろんきます。あいつは茸というとどこにでもとんで行く男です。大喜びできますよ、モグラからでる冬虫夏草なんて世界で初めてでしょうから」
世の中にそういう人間はたくさんいる。好きなものはどこまでも追いかけていく。
光平君は、もってきた大きなゴミ袋に、夏虫冬草をそうっといれた。頭は飛び出している。彼が抱えてみると、意外に丈夫で、静かに持っていけば、折れる心配はなさそうである。
「これを図書館において、火之平さんの畑に行きます。今日は仕事休んでいいですか、それとこれ図書館のどこかにおけますか」
彼はそれを詳しく調べるつもりなのだろう。図書館には余裕のある部屋がないが、倉庫の片隅でも使ってもらおう。
「いいよ、休みにしなくても、外での活動にしとくから、十分に調査していいよ、もし、何かに発表する事があったら、ここの図書館を宣伝しておいてよ」
「はい、科学博物館の友人がきたら、子供教室を開いてもらって、茸の話でもしてもらいましょう、もちろん無料で」
「そりゃあいい考えだ。今時子供たちも退屈している、冬に茸の話というのもいいね、図書館の企画としてとても面白いよ、茸は倉庫においておきなよ」
冬休み中で子どもたちは家でゲームなどをして遊ぶだけだ。もっと雪で遊べばいいのにと常々思っている。昔の子達はいつも外で雪遊びをしていたのに違いない。
「はい、彼にいろいろ相談します」
私は光平君と一緒に図書館にもどった。
図書館に戻ると、花ちゃんが目を丸くした。
「アー、オッもしろい茸、おっきい」
光平君はニコニコしながら、でも黙って、倉庫に冬虫夏草をもっていった。
「手伝おうか」
花ちゃんが光平君の後を追った。
光平君はすぐに戻ってくると、
「もう一度いってきます」
図書館を後にした。
「私も行ってみたいなあ」
花ちゃんが呟いた。
「いいよ、受付は僕がやっとくから、誰も来ないかもしれないしね、光平君は今頃、火之平さんの畑にいってるよ」
「すぐもどりますから」
花ちゃんはコートを羽織ると図書館を急いででていった。
実のところ、花ちゃんは光平君に気がありそうなのだ。
それはともかく、あの茸が珍しいことは文系あがりの私でもよくわかる。
その日はいつものように暇であった。図書館を利用に来たのは、暖かい図書館の閲覧室に暇つぶしに来た近所のおばあちゃん一人であった。
二日後、図書館にはお客さんが相次いだ。
光平君が彼の掘り出した黄色と赤の夏虫冬草の写真をメイルで友人に送った。そのために科学博物館では大騒ぎになったそうである。おかげで、光平君の友達はもちろん、東大や早大にいる茸の専門家もあいついで秋田の小さな町の図書館に押し寄せてきた。
私が教育委員会に連絡をしたので、教育委員会の人や高校、中学の先生方が光平君の採った茸を見に訪れた。もちろん地方新聞の記者さんもやってきた。
図書館の準備室を急いで片付けると、展示場に当てた。
その日は花ちゃんも大忙しであった。
訪れた人たちは、大挙して町に繰り出し、方々を歩き回った。その結果、さらに、黄色と赤の茸が見つかり、茸の研究者は大喜びをした。
新しい植物などが見つかったとき、発見者の名前が付くことがある。光平君は、科学博物館の友人に、町の名前を入れてほしいと申し込んだ。町の表彰ものである。
土竜の冬虫夏草のことは、新聞の全国版にそれなりに大きく扱われた。世界で始めての大発見との見出しも見られた。
市長さんからも連絡があり、市役所の一部屋を使ってもよいとの申し出もあった。
それから一週間たたないうちに、この茸のニュースは世界に広まり、雪も深いこの辺ぴな町に世界中の茸の学者が集まることとなった。
しかし茸はもう生えておらず、光平君が見つけた、黄色と赤の二種類の茸の標本を虱潰しに詳しく調べた。
茸はモグラのものは黄色の頭をもち、ヒミズのものは赤色の頭をもっていた。
光平君の茸は哺乳類から生える冬虫夏草の第一号と、二号に登録された。しかも、冬虫夏草ではなく、新たに、夏虫冬草と言う名前で呼ばれることになった。
黄色い方がモグラ冬草、赤いほうがヒミズ冬草と和名がつけられた。
学名はコルディセプス、モンジャモグラとコルディセプス、モンジャヒミズというそうである。
この町の名は秋田県裏門市門者町という。
さて、このモグラ冬草とヒミズ冬草について科学博物館から発表があり、新聞に詳しくのった。モグラやヒミズが夏の間にその菌をもっているミミズを食べると、その菌に感染し、冬になり、土の中でおとなしくしている土竜とヒミズの脳の中で菌糸がのび、いつの間にか、頭のてっぺんの骨を突き破って、雪の中から茸が顔を出すそうである。珍しいことに零度に近いと生えてくる茸であることも分かった。
そのようなことがあり、図書館では子どもの茸教室は行われるは、市民ホールでモグラ冬草とヒミズ冬草の写真展が行われるわ、門者町は有名になった。
秋田の裏門市も、市に湧き出る温泉の宣伝に努め、モグラのゆるキャラまで作り、冬草羊羹まででてきて、観光地としても少し芽が出てきた。
漢方薬の会社が特に目をつけた。中国の冬虫夏草の乾燥したものは何にでも効く長寿の薬として高価である。
モグラやヒミズの成分を吸って大きくなった夏虫冬草は哺乳類に絶対的な薬効があるに違いがないとふんだのである。いくつもの漢方生薬の会社が門者町にやってきた。
市ではさらに市民にお触れを出した。モグラをやたらといじめないよう、モグラ条例をつくり、市長はモグラ公方と呼ばれる羽目になった。五代将軍綱吉をもじって、一代商運綱吉と呼ばれている。市長の名前は高橋綱吉である。
そんなことで、町の人たちはモグラのために畑を耕し、モグラを養うことになったのである。ミミズももちろん大事にしなければならない。この市と町はよくテレビにでるようになった。
こうして、いろいろな方面から哺乳類にとりつく茸の研究が始まった。
次の年、野鼠につく茸が発見された。門者町の北の山の中であった。やはり、冬の寒い雪の深いときである。茸の色は橙であった。そして驚いたことに、茶色の茸が見つかり、雪の下からは兎が掘り出された。それぞれ野鼠冬草と兎冬草と名付けられた。不思議なことに門者町の隣の町からは一つも見つかっていない。
その次の年は茸の当たり年で、世界から調査のために訪れた人は数知れなかった。町の温泉宿の泊まれる数はたかが知れており、電車で一時間も離れた少し大きな町のホテルが満員であった。
それに目をつけたある会社が駅からさほど離れていないところにホテルを建てる計画をたてた。全国展開をしている温泉つきホテルを経営している会社である。
町の中には外国人がうろうろと茸を探してさまよっていた。地元の飲食店は大いににぎわい、活気付いていた。それだけではなく、夏虫冬草茸も豊作であった。
オーストラリアから来た学者は桃色の茸を見つけ掘ってみると猫が出てきた。アメリカの学者が掘り出したのは犬だった。黄土色の頭をもっていた。
フランスから来た茸の学者が町の外れの農家の家の脇から緑色の大きな冬草が顔を出しているのを見つけた。フランス人はそこを覗いて驚いた。馬から茸がはえていたのである。イギリス人の研究者は豚小屋から黒い冬草が出ているのを見つけた。
そしてその時はいきなりきた。
夏虫冬草茸が見つかって三年目である。
まだ雪の深い一月四日のことであった。
私は家の前の雪掻きをして、その年始めて図書館に出勤した。
いつものように、守衛の正直おじさんは玄関を掃いていた。
「館長さん、おはようごぜえます、今日は、花ちゃんも、光平さんもまだですだ」
「ほー、めずらしいね、正月はどうでした」
「あー、孫が来ていて、忙しいったらねえでした、婿夫婦は子供ほっぱらかして、スキーさ行っちまうし、ちっこいのを二人、かみさんといっしょにお守でさあ」
「それも楽しいじゃないですか」
「とんでもねえ、ほれ、孫に引っかかれた」
正直おじさんの頬に猫に引っかかれたような傷があった。
「猫よりたちが悪い」
「ははは、それにしても花ちゃんが遅いのは珍しいね」
「館長さんしんねえのけえ」
「花ちゃんは光平さんともう一緒に住んでるということだで、今の若い人は平気だね、親も許しちょるようだよ」
「結婚するんだろうね」
「だろうよ」
私は図書館の事務所にはいり、初仕事の準備をした。開館時間までまだ少しあるが、もし二人が遅れるなら、受付の準備をしておかなければならない。あわただしく受付のデスクの上に書類をだした。
彼らはなかなか来ない。遅れるときには必ず連絡をくれる律儀な二人である。何かあったのかもしれない。
光平君の携帯に電話を入れた。
呼び出し音が聞こえる。しかし、出る様子がない。
今度は、花ちゃんの携帯にかけた。
やっぱりでない。
どこかに旅行に行って、帰ってくることができないのかもしれない。しかし、それならば、携帯はつながるはずである。
昼になってもこなかった。
これから、市役所に行かなければならない、通り道でもあるし、公平君の家に寄ってみることにした。
彼の家は三軒続きの市営住宅であった。軒まで雪が積もって玄関が雪で埋まってしまっている。声をかけてみた。返事は返ってこない。人がいるようには見えない。やはり留守なのだろうか。両隣も誰もいないようである。
僕は庭の方に回ってみた。すると二階の窓から、紫色の大きな茸が二つ、外に頭を出していた。
私はぎょっとした。いやな予感がはしった。
まず警察に電話をした。すぐに、パトカーが来た。パトカーから降りた顔見知りの警官たちは玄関の前の雪をかいて戸をこじ開けた。
「一緒に中に入りますか」
刑事の髙橋差次郎さんが声をかけてきた。
「ただの留守かもしれないのですが」
しかし玄関には彼らの靴が揃えておいてあった。いるのだ。
私は靴を脱いで警官たちのあとをついていった。
一階の居間を通り越して、階段を上がると、寝室らしき部屋の戸を警官があけて、 あっという声を上げた。
警官がカメラを構えて写真を撮った。
ベッドにいる二人の頭から、茸が生えていた。
二人とも幸せそうに手をつないでいる。
「触っちゃだめだ」
警官が二人を触ろうとしたので私は声を上げた。
恐ろしいことに気がついたからだ。
その後、私の町は封鎖され、町民数百人は、十数年の間、新しく開発される薬を待って暮らすことになってしまった。
この新しい夏虫冬草は、蝉の冬虫夏草がミミズの体内で突然変異を起こし哺乳類に付く茸になったようである。モグラとヒミズに広まり、鼠から兎、猫、犬、家畜、そして、人間にまで広まってきたのである。感染力は強くないが、大事をとって、日本政府はこの町を封鎖した。
図書館には、暇をもてあました町民が本をよく借りにくるようになった。臨時の司書である美美ちゃんと、春樹君は秋田弁丸出しでがんばっている。苗字は二人ともやはり髙橋である。
夏虫冬草
私家版 第十三茸小説集「珍茸件、2022、一粒書房」所収
茸写真:著者: 北海道女満別 2015-9-14


