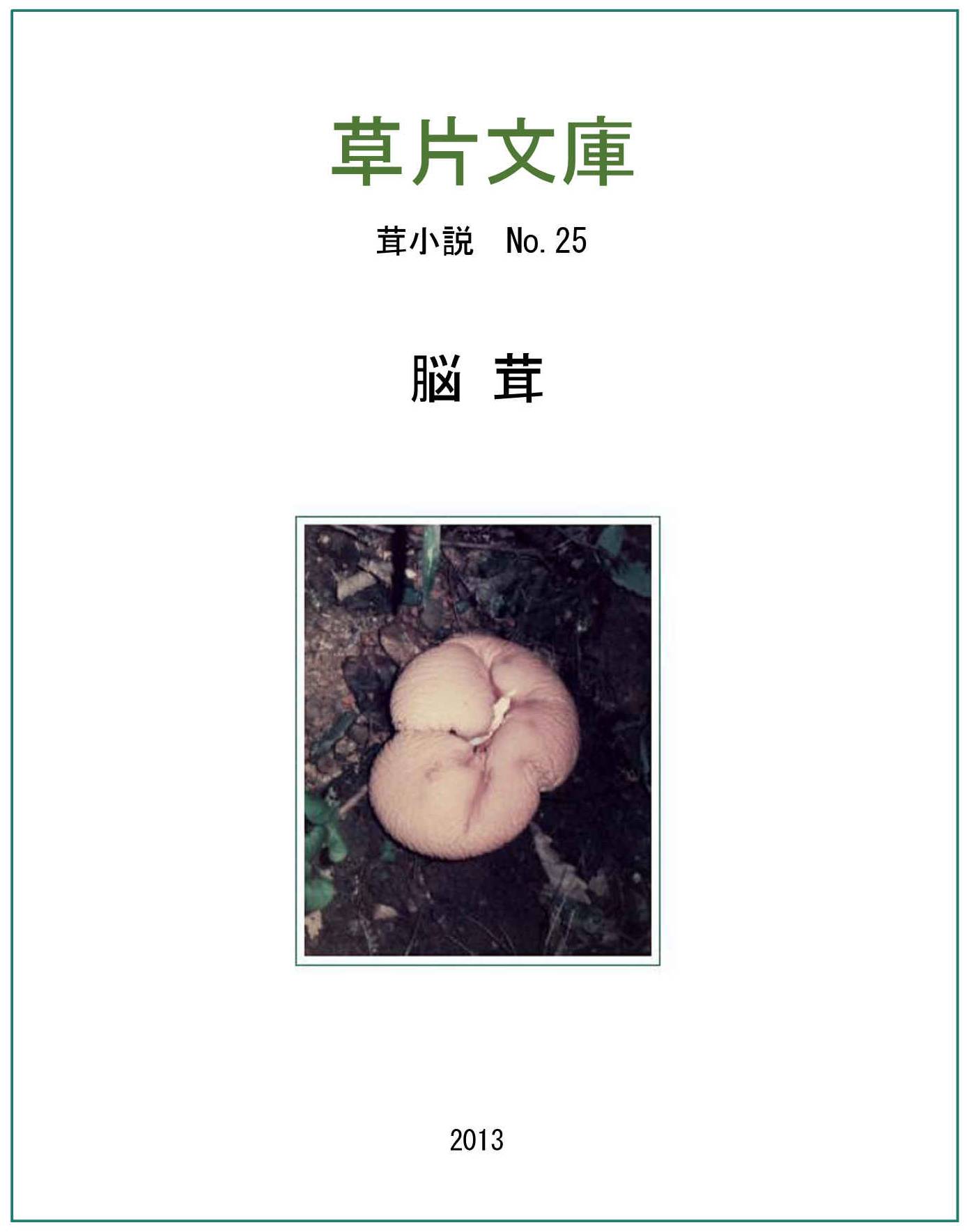
脳茸
彼は仕事がらみのストレスにさいなまれていた。おかげで頭痛がしょっちゅう起きる。会社を辞めればいいのだが、そのあと雇ってくれる会社がそう簡単にはみつからない。
自分は頭が弱いんだ。彼は本気でそう思っていた。頭がすぐに疲れてしまう。友人に相談したら、脳に行く血管の細い人がそうなるということであった。本当かどうかはわからない。そこで病院にいって調べてもらったことがある。しかし、結果ははずれで、特に細いことは無く、おかしなところもなかった。脳の中に頭痛の原因となるようなものも存在しなかった。心の問題でしょ、とつれない医者の一言で終わってしまった。それに血管の太さと頭の弱さなど関係ありませんよと、笑われてしまった。
彼は製薬会社の販売担当である。いうなればMRという職種で、医師に薬の効能を教えることが本来の役目である。しかし結局は売らなければ首が飛ぶ。そういった仕事柄、薬を積んで町の医院を回ることが多い。
東京の外れの市が担当で、そこのいくつかの医院を回っている時であった。多摩丘陵の高台にある医院に、頼まれた薬品を納め外にでると、病院へのアプローチの脇に、茶色っぽいこぶしほどの固まりが目にはいった。皺が寄っており脳そっくりである。
たまたま、そこに、医院の奥さんが買い物から帰ってきた。
「あら、脳茸が出ていたのね」
奥さんはそう言うと、彼に「いつもごくろうさまです」と声をかけて病院脇の自宅に入っていった。
脳茸か、確かに脳に似ている。こいつに頭痛はあるのかね、思わず彼はそんなことを考えた。
彼は茸を採るとポケットに入れた。
その日もかなりの病院に寄り、会社に戻らずに直接アパートに帰った。もう九時過ぎである。キッチンのテーブルに買ってきた弁当を置き、ポケットのものをとり出した。ティッシュペーパーと一緒に脳茸がコロンと出てきた。脳茸を採ったのを忘れていた。見れば見るほど脳によく似ている。人の脳の大きさは千三百グラムと言う話だ。とすればこれはずいぶん小さな脳だ。犬の脳はこれくらいかな。
彼はつまんで持ち上げた。そのとき茶色っぽい煙がふわっと目の前に広がった。一瞬なんだかわからなかったが、そうかこれが胞子かと思った、そのとたん目の前が曇った。
「うへえーーー」片方の手で目の前の煙を払った。それでも胞子は口の中や鼻の中に入った。耳の中にまで入った。幸い目に入ることなく、視界は問題なかったが、くしゃみは出るは、耳はごそごそした。
茸を流しの塵捨てに放り込んで、あわてて洗面所でうがいをし、顔を洗うとタオルで耳や鼻を拭いた。
テーブルの上にも茶色っぽい胞子の粉が散っている。テーブルの上を拭くと、おろしたての布巾が茶色に染まった。
腹が減っているのに改めて気がつく。彼は缶ビールを一本冷蔵庫から持ってきた。買ってきた唐揚げ弁当の蓋を取り、少し焦げすぎではないかと思うほど色の着いた唐揚げをつつきながら、ビールを空けた。テレビには今日のニュースが流れている。いつもの雑多な事件が報じられているが、さしたる重大なものはない。
野球もやっていないし、見るものもない。まだ十時過ぎだが寝ることにした。
あくる朝、どうも体の調子が悪い。体温計で計ってみると七度二分である。中途半端な体温だ。軽い疲れか、風邪がはいったか、微熱のわりにはかなり頭が重い。頭痛もちだからだろう。しかしいつもの頭痛は起きていない。咽がからからである。彼はベッドから降りると、キッチンに行って冷蔵庫を開けた。パック入り牛乳が目に付いた。彼は取り出すと一気に飲んだ。
牛乳を美味く感じたのは始めてである。普段は美味いともまずいとも感じる事はない。ただ、朝は牛乳という子どものころからの習慣が抜けず毎朝飲む。
牛乳はうまかったが、会社に行く気力がない。まだ微熱があるからだろ。もう少し横になって様子をみよう。
彼はまたベッドに横たわった。
寝室の小型テレビをつけると、天気予報をやっていた。今日は午後雨となっている。閉めてあるカーテンを開ける気力もなく、ボーっとしていたが、カーテンの隙間から日の光は差し込んでこない。すでに雨が降っているのかもしれない。
ニュースになった。日本の領海を中国の船が出入りしていることをやっていた。子どもじみたことだ。
横になってテレビを見ていると、なんだか頭が軽くなってきたような気持になった。調子が悪いとどんどん頭痛がひどくなり、頭が重くなるのだが、今はふわっと頭が浮いた感じになっている。これも微熱のためかもしれない。風邪を引くと歯が浮いたり、体が浮いたり感じる。自分の場合、頭が浮いた感じがするのだろうと勝手に納得した。
やっぱり今日は仕事に行くのは止めておこう。幸い特別急いで配達する必要のあるものは無い。会社に電話をしようと枕もとにおいた携帯をとった。
でたのは秘書課の女性だ。
「そーお、届け物はないのね、それなら問題ないわ、お大事に」
彼女は、いつもの長話をすることもなく切った。
携帯をもどしたところで、いきなり睡魔が襲ってきた。
彼はガクッと頭を落すといびきをかき始めた。目がきょろきょろと動いている。
二十分も経っただろうか。彼は、うーんと伸びをすると、少しばかり目を開けた。寄り目になっている。天井を見ているようだが、きっと見えていない。今見た夢のことを思い出しているようである。
変な夢を見たものだ。勤め先の製薬会社の支社に出社したところ、秘書の彼女も、課長代理も他の同僚もみんな、茸になってしまっていた。彼が部屋に入り自分の机に座ると、茸たちが一斉に彼を見た。
ただそれだけの夢であったが、茸の傘は色とりどりで、綺麗なものだった。
彼はくしゃみをした。鼻から茶色の煙が立った。何だと一瞬思ったが、昨夜脳茸の胞子を吸い込んだのを思い出した。そいつが吐き出されたのか。
目がやっと周りの状態を見ることができる状態になったようだ。ナイトテーブルの上を見るとしなびた脳茸がころがっている。流しに捨てたのではなかっただろうか。
奇妙に思ったとそのあと、脳茸は食べられるのだろうかという疑問がいきなり湧き出した。だが彼はもう寝息をたてはじめた。
彼は満員の通勤電車の中で茸に囲まれて潰されそうになっていた。ぎゅーっという音がして、彼が潰れてお腹から何かが飛び出した。そのとたん目が開いた。口で息をしている。どうも鼻が詰まっているようだ。鼻の穴の中になにかあり、そいつが蓋をしている。小指で鼻の穴を突っついた。茶色の粉が付いてきた。いつ吸ったのだろう。昨日吸い込んだ胞子は洗い流したはずだが。
それにしても鼻の穴の中にずいぶん深く、硬く入り込んでいる。咽の奥も何かもそもそする。
ふんふんとやってみたが、鼻は詰まったままである。ベッド脇のティッシュをとって鼻をかもうとしたとたん、ふたたびすーっと意識がなくなり寝てしまった。
目が開いて壁にかけてある時計を見ると昼ちょっと前である。お腹は空かないが、咽が渇いた。そういえば鼻が詰っていない。気持ちよく空気が出入りしている。起き上がってキッチンに行った。冷蔵庫を開けるとジュースを取り出し、半分ほど飲んだ。
だるさが感じられる。あとで体温を測らなければ、ベッドの上にもどった。体温計が見つからない。右の耳の中でががさがさ音がしている。そっちが気になりだした。 右耳を下にして頭をたたいた。茶色の粉が少しばかりこぼれた。なんだ胞子が耳に残っている。耳から喉のほうに何かが降りてくるような気配を感じた。その時、時計が十二時をしらせた。最後の音がしたと思ったら、また眠りに入っていた。
今度の夢は茸に追いかけられていた。大きい茸や小さな茸が追いかけてくる。理由は分からないが逃げていた。一生懸命走って逃げるのだが、すぐ後ろに来ている。会社からアパートに向かって走っている。茸はどんどんせまってくる。やっとのことでアパートに走りつくと、鍵をガチャガチャ回し、なんとかドアを開けて入ると茸たちもどやどや入ってきた。あっという間に家の中は茸でいっぱいになり、彼は押しつぶされ、内臓が飛び出した。そこでまた目が覚めた。
ふー、彼はため息をついた。三時である。体中汗をかいていた。手を伸ばしてティッシュをとり顔の汗をふき取ると茶色の胞子がついてきた。手の甲や手のひらから胞子が湧き出している。顔に手をやると茶色の胞子がついてきた。足の先を持ち上げてみた。茶色の胞子で覆われている。パジャマの中を覗いてみた。大事なものもすべて茶色の胞子で覆われていた。
大変である。医者に行かなければと思い、立とうとするが立つことができない。それどころかあせって足をばたつかせるのだが、からだを起こすことが出来ない。目の前が茶色く見えるようになってきた。目がとろんとする。胞子が目に湧いてきたようだ。頭の中もかさかさする。頭痛から開放されたら今度は胞子が脳の中に入って、何か考えると動いて音がでる。
意識がまたもや朦朧としてきた。彼は会社に行かねばと、やっとのことでベッドの上で上半身を起した。あぐらをかいて気持を張りつめようとしたとたん、意識がなくなった。
数日後、無断欠勤していた彼のアパートに秘書の女性が訪ねてきた。呼び鈴を押しても返事はない。大家さんと一緒に彼の部屋に戻った彼女は部屋に入った。彼の名前を呼んだのだが返事が無い。彼女は大矢さんと共に部屋の中に入った。
彼はベッドの上であぐらをかいていて後ろを向いていた。
「大丈夫なの」
彼女が彼に声をかけた。彼が振り向いた。茶色の目で彼女を見ると、口を動かし、あうあうといいながら、自分の頭を指差した。
そのとき、彼の頭がぱくっと開くと、中から脳茸がむくむくむくとせせりだし、茶色の胞子が沸き出すと部屋一杯に広がった。
「窓を開けましょう」
秘書の声で大家さんが窓を開け放った。胞子はすーっと窓の外に吸い込まれ、周りに散っていった。
彼は自分の手を頭に持っていくと脳茸を中に押し込んだ。
「わざわざすみません」
彼は秘書の人に謝った。
「救急車よびましょう」
彼女が大家さんに言うと、彼は首を横に振った。
彼はベッドの上に横たわった。
彼の頭が割れた。とうとう脳茸が外に飛び出した。
驚いている秘書と大家を尻目に、脳茸は部屋の中に飛び出し、開いている窓からでると、すーっと空に上っていった。
脳のなくなった彼は幸せそうに目を閉じた。脳がなくなり、ストレスも何もなくなった彼は永遠のからだの幸せを手に入れた。
ストレスは脳がつくりだすものなのである。
脳茸
私家版 第十三茸小説集「珍茸件、2022、一粒書房」所収
茸写真:著者: 秋田県湯沢市 1973-10-15


