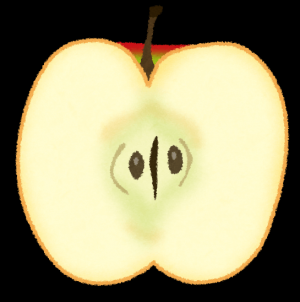いのちの白さ
わたしの双子の姉。母親の産道を広げて、わたしの生まれる道を作ってその人生を終えた姉。
世界の光を見ることがなかった姉。世界の音を聞くことはできたのだろうか。生みの苦しみに耐える母の叫びとわたしの声を、その耳はとらえたのだろうか。ひとは今際の際まで聴覚が残るという。一番知りたいそのことを、姉はすでに知っている。
母は事あるごとに姉の話をした。わたしはここにいるのに、まるでわたしのことが見えていないみたいだった。わたしは姉の代わりだった。姉につけるはずだった名前でわたしは呼ばれた。
ひとの命は死の上に成り立っている。わたしは誰もいない教室の片隅で自らの机の上に花を飾った。悼むための花。わたしは生きながら死んでいる。わたしの身体を生きているのは姉なのだとその時は思っていた。それはある一面では正しく、ある一面では間違っていた。
この出来事を暗闇のなかでそっと語ったとき、わたしは泣いていた。母も泣いていた。「お姉ちゃんのために泣いてくれてありがとう」触れた母の手の暖かさに涙は止まった。近くにいてもどうしようもなく遠いところに母はいた。
わたしと同じくらいの背丈になった姉の姿を夢で見る。その背を追いかける。あなたの人生の役割はわたしをこの世に送り出すことだけではなかったはずだと声を上げる。その声は風にかき消される。声は届かない。
すべての声はわたしの中で反響する。わたしは姉のために、わたしを生きる。わたしが命を終えて、この声を姉に届けるまで。
いのちの白さ