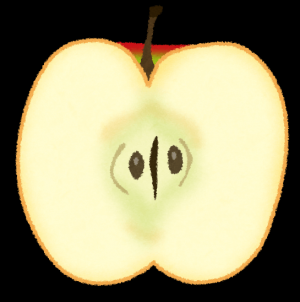惚れた弱み
手首に光る腕時計の針は22時を回る。この時間でも開いている喫茶店で助かった。あいつが来るまで待つことができる。
サイフォンで淹れられたコーヒーを少しずつ飲み、サービスされた多めのミルクを足しながら待っていたらこの時間になっていた。コーヒーの色はすっかりミルク色に染まっている。
この喫茶店はいつもあいつとよく来ているが、この時間に利用したことはなかった。何度目になるか分からないが客席を見渡してみると、睦言を交わすカップルや仕事をしているであろうサラリーマン、飲み会から流れてきたらしき若者たちなど、意外と賑やかだった。
客たちは入れ代わり立ち代わり、この場所でひととき寛いでは過ぎ去っていく。彼ら彼女らがどこから来てどこへ行くのか、本当のところはわからないが、人生が交差している瞬間だと感じる。
煙草をすうっと吸い、ふ、と吐き出す。紫煙が情緒もなく換気扇の方へ吸い込まれていったが、穏やかな気持ちだった。待たされているのにも関わらず。
甘いものは得意ではないので、すっかりミルク色に染まってしまったコーヒーを眺めて、飲みにくくなってしまったなと物思いにふける。あいつだったら砂糖も加えて本格的に甘くして飲むだろう。
いつかこの喫茶店でコーヒーを飲んだ日に、あいつの唇からした甘い香りを思い出す。味覚が正反対で、煙草も吸わない奴だが、それでも不思議と気が合うのがいいところだ。
ラストオーダーの時間になった。もう一杯コーヒーを注文し、苦味と酸味の消えた手元のコーヒーを一気に飲み干した。しばらくしたのち、新しいコーヒーと引き換えに店員が空いたカップを下げていった。店が閉まるまであと30分。
店内の客はまばらになっていた。椅子の背へもたれかかり思い切り体を伸ばす。腰のあたりに凝りが溜まっているのが分かった。静かになった店内で腕時計の音がその存在感を高めている。
店員たちが密やかに言葉を交わしながら店を閉める準備をしている。今度はコーヒーにミルクを入れずに、普段通りに飲み始めた。苦くてうまい。
煙草は1箱吸いきっていた。もはやヘビースモーカーだろうか。ライターを手のなかで転がし、蓋を開けては閉じた。
閉店の時間。そして日付の変わる時間でもあった。手首を眺める。
「おまたせ」
そこにはあいつが立っていた。顔を上げると、悪びれた表情もせずに笑みを浮かべている。
店を出ると時計はちょうど0時を指していた。今日のデートは何にしようかと尋ねてみた。
「今日は夜食というものが食べてみたい」
そのために待たせたのだろうか?怒りがこみ上げてくるというより、同じようにどこかで時間を待っていたあいつの姿を思い浮かべるとむしろおかしかった。
待った時間の分だけ、あいつと食べた夜食は美味しかった。
惚れた弱み