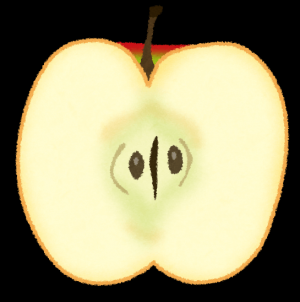雪の中のキリン
私と由希は1年遅れの卒業旅行として旭川の動物園へ来ていた。私と由希は大学の同期で、同じ研究室に配属され、他のゼミ生が全員男性だったのもあって、特に付き合いが深かった。大学を卒業して1年、彼女は社内研修が終わり配属先が決まったと、チャットアプリで聞いていた。それに比べて私はというと、就職活動に失敗しうつ病を患い、引きこもってしまっていた。この旅行も、親に無理を言ってお金を借りてきて実現したものだった。
「付き合ってくれてありがとう、こんなに大量の雪を見るの、一人じゃもったいなかった」
彼女は明るく言った。さくさくと足元の雪が音を立てる。踏み固められた部分に足を取られないよう、頭をたれて歩いた。由希はまっすぐ前を向いて歩いているようだった。私たちの頭の上に雪が降る。
そうしているうちに人の流れと人だかりの気配を感じて顔を上げると、キリンが見えて、思わず声を上げた。
「あ、キリン」
「こんな寒いところにもキリンっているんだね」
「ねー」
キリンは白い雪の中で器用に歩いている。キリンのいる場所は客のいる高さより数段低くなっており、客がキリンを見下ろす形になっている。私たちは手すりまで近寄ってキリンを眺めた。
「雪の中のキリン、ってどうかな」と彼女。
「何、それ」
「ことわざ。生まれたところとは全然違うところに連れてこられて寒い!っていう意味」
「それことわざじゃなくない?」
自然と笑みがこぼれそうになるが、固まってしまった表情筋の抵抗を感じた。笑いたいのに、上手く笑えない。
彼女の視線から目をそらすと、キリンが木箱の上の雪を口にしているのが見えた。客がもたれかかることのできる手すりの、すぐそばに備え付けられたエサ箱の上に雪が積もっているのだろう。エサにたどり着くために冷たい雪を食べなきゃいけないのか、と私には哀れに思えた。
「そういえば私、実花に言ってなかったことがあるの」
由希の方を向いた。何だろう。不思議と胸がドキドキした。
「私ね、仕事辞めることにしたんだ」
由希が仕事を辞める。
その言葉を聞いて私は反射的に嬉しくなってしまった。この旅行は、私に憐れみをかけるためでも、経済的負担を負わせて友情を強いるためのものでもなかったのかもしれない。ようやく由希と自分の立場がイーブンになれる。たとえ自分が病を患っていて働けないのだとしても、無職の状態には世間体の悪さとやましさを感じていて、それを一時期だけでも分かち合える無職仲間、が欲しかったのかもしれない。
そこまで一瞬で考えてしまった私に彼女から冷水を浴びせかけるような一言を聞いた。
「また大学に通うことにしたんだ」
「そう、なんだ……」
少しでも喜んでしまった自分が恨めしかった。定職に就けずふらふらとしている自分と由希が対等になるなんてことはなかった。
「大学に通うって、何大学?」
「やだな、私たちが通ってた大学に戻って、博士課程に行くってこと」
私はまたしても恥じ入ってしまった。ほぼお情けで修士論文を受理してもらった私との差にまた胸が痛んだ。
「博士課程に進んだら、もう研究一筋にならなきゃいけないし、その前に実花とだけでも思い出を作りたかったんだ」
由希の言葉が私の上を虚しく通り過ぎていく。私のコンプレックスに彼女が気づくことは、ないのだろう。
「おめでとう、頑張ってね」
私は大学生の頃に戻りたかった。そんな私を尻目に彼女は前に進んでいる。修士課程の頃から教授に目をかけられて学会発表もこなしていた彼女だ。就職先だって、誰もが知っているような会社で、私の知る限りでは仕事ぶりも安泰のようだった。
私が手に入れることのできなかった何もかもを彼女は手に入れて、それでも自分の道を選ぶだけの自由があった。羨ましくて苦しかった。大学生の頃の彼女はもういなくなってしまったのかもしれない。このような状況で、旅行に誘われた時点で気づくべきだった。
もし雪の中のキリンということわざがあるとしたら、それは、高いところの草が欲しくて首が伸びるように進化したキリンでも、雪が積もってしまえばエサにたどり着けないという意味を私は読み取る。私はこのコンプレックスと共に生きていくのだ。たとえ私が相対的に恵まれているとしても、絶対的には惨めなのだ。私は私を憐れむことでしか、絶望するやり方でしか自分を愛せない。
由希が満足そうに口を開く。
「雪の中のキリンってさ、実花みたいだよね。カワイイ」
雪の中のキリン