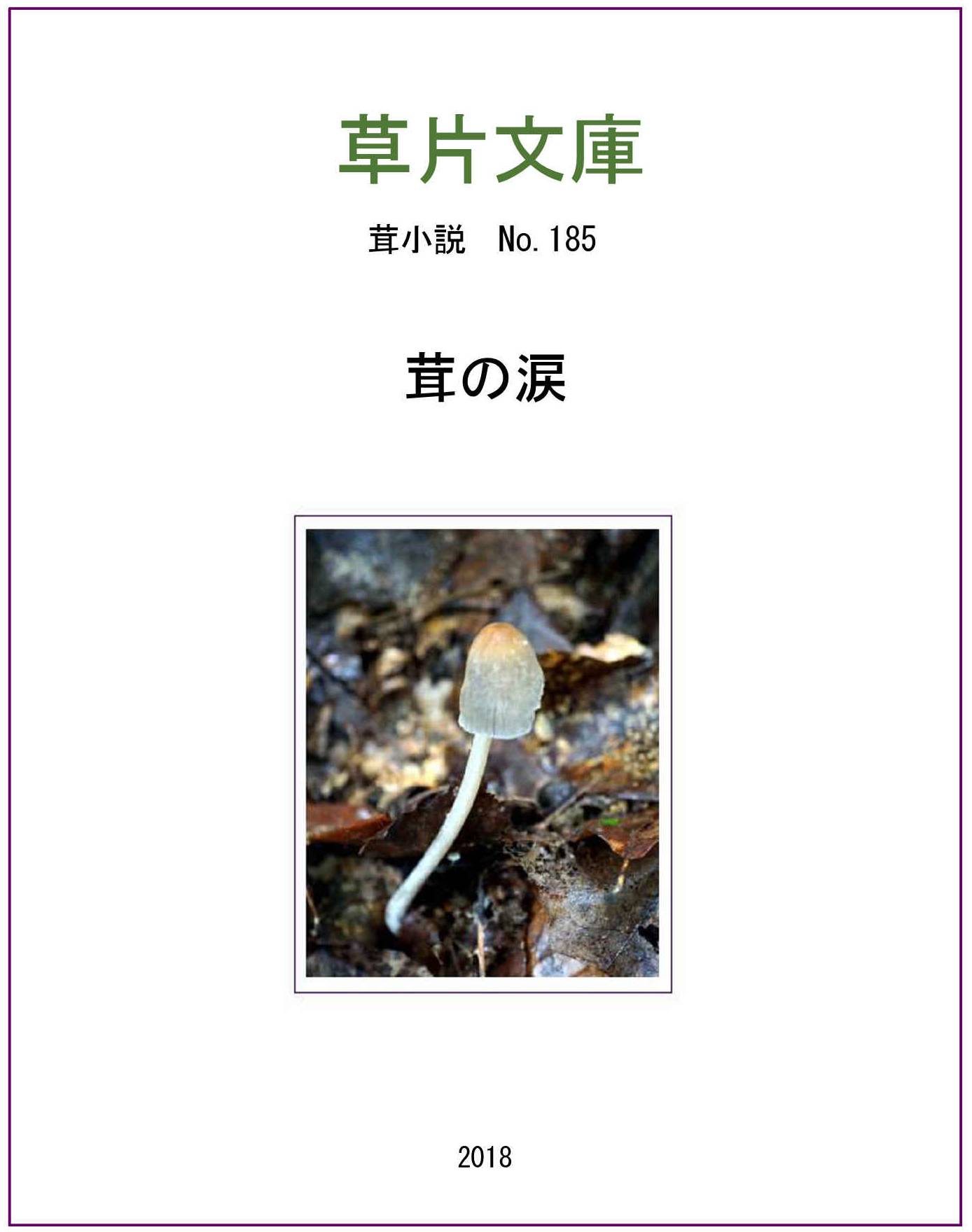
茸の涙
今、病院のベッドで酸素吸入を受けながら思い出している。
退職をしたのが六十五の時であるから、もう三十年近く前のことである
信州の実家に帰っていたときのことだ。
私の実家は古くからの農家だったが、父は市役所勤めとなり、兼業農家にならなかったことから、もっていた田畑をみな手放した。残っているのは売れない裏山とそれに続くいくつかの山だけである。
私は東京の大学をでてから信州に帰ることなく、東京の商社勤めをしていた。二十年ほど東欧の支所を点々とし、定年退職を迎えた。ハンガリーのブダペスト、スロバキアのブラチスラバ、それにチェコ、ブルガリア、ルーマニアの都市、どこも古くからの石造りのいい建物が残っている町で、そのときはとても楽しい思いだった。それが東京に戻ってくると、三十五階のマンションから見える景色は、近代的なガラスの建物が箱庭のように並んでいるだけで、味気なさを感じた。
人に管理を頼んでいた信州の実家を整備し、別荘代わりにしようと思い、様子を見に帰ったとき、日本を感じ、求めていたのはこれだと確信した。家は最小限の改装を行っただけで古い農家の家の形をそのまま残した。一度住んでみたら、気に入ってしまい一年のうち春から秋遅くまで実家で過ごすことになってしまった。ということは東京の家には正月を挟んで少ししかいないことになる。女房は東京でおしゃべり仲間と楽しんでいることもあり、たまに信州にくるだけで逆の生活になった。
実家暮らしが三年目になった時のことである。
短い夏が終わるころ、裏山から泣き声が聞こえてきた。それまではつくつく法師が鳴き、秋の訪れが間近であることを知らせてくれていたが、それが終わったとたん、夜の八時ころになるとその声が聞こえてきた。言葉に表わすのは容易ではないが、しくしくという表現がもっとも近いだろう。泣いているように聞こえるが、人間にそう聞こえるだけで、本当は何かが鳴いているのだろう。
山にはいろいろな動物がたくさんいる。大きいのなら熊や鹿だろうが、我家の裏山に棲んではいない。山の林の中に永住しているのはもっと小さい奴らである。栗鼠、鼠、兎、土竜。しかしそいつらがしくしく泣くわけがない。むしろ私の知らない小さな虫に、そんな鳴き方をするのがいるのかもしれない。
ともかく何かが鳴いている。言葉らしきものは聞こえない。
ある時変なことに気がついた。虫や鳥がなくのは「鳴く」と書く。ところが人間は「泣く」である。鳥が鳴き声をだすのはコミュニケーションの 為だから、鳥に口と書くのだろう。人間でいう話すことである。人間の泣くのは感情の現れで、ひとつのコミュニケーションにはなっているのだろうが、音を口から出すだけではなく、からだに変化が起きる。目から涙がでる。感情で勝手にからだの反応がおきるのである。それで三水に立なのか。立はどのような意味だろう。字通(白川静著)を開いてみた。りゅうとあり、つくる、はじめる、あらたにつくるなどの説明がのっている。とすると、水を作る、始めるということなのだろう。
猫や犬が苦しかったり、痛かったりした時に声をあげても鳴の漢字を使う。そういったとき犬猫が涙を流したのを見たことはない。哺乳類の眼は涙で守られている。犬猫だって涙をいつも流して目を保護している。しかし尾っぽを大きく振って大喜びしている犬が涙を流すことはないようだ。そこが人の泣くとの違いなのだろう。
裏山の林の中はいろいろな山菜が採れる。昨年の今頃はアケビが大きく実った。茸も盛りである。今年もそうだろう。茸の下で虫の鳴いている様子を想像した。
泣き声が聞こえているのは、ほんの十五分ほどである。しくしくと表現したが、小学生低学年の女の子が泣いているイメージとはまたちょっと違う。もっと静に小さな湿った声である。しゅくしゅくなくと言う表現があればそれである。
空高く晴れ渡ったその日の夜、ヘッドライトをつけ裏山に入った。東京だったら蚊がよってくるだろうが、ここではこの時期もうでてこない。それは楽である。
林の中は夜になるととても爽やかである。寒ささえ感じる。山の上に続く小さな道があり、林の中の下草もまばらで、様々な茸が顔を出している。裏山の道はなれたもので夜でも怖さは感じない。ゆっくり登っていくと、いきなりしくしくと泣き声が聞こえてきた。人間だとするとちょっと薄気味悪いが、それとはちょっと違う。
そこまでくると泣き声がどちらの方から聞こえてくるか明らかになった。泣き声に向かって登っていくと、ヘッドライトの光の中に赤い小さな茸が浮き出た。その隣に大きな赤い茸が萎びて倒れている。
泣き声なのだか鳴き声だか分からないが、辺りを見回した。何もいない。そのとき、小さな声であるが、しゃくりあげるような泣き声になった。年をとって耳の聞こえが悪くなっているが幻聴ではない。耳をそばだててそうっと声のほうに近づいて行ってみる。地面に近いところから聞こえてくる。
泣き声が止んだ。こうなると探しようがない。目の前には赤い小さな茸がある。かがんでその周りを見渡したが何も動くものは見当たらない。倒れている萎びた赤い茸の下にでもいるのかもしれないと思い、茸の頭をもって起こしてみたが、その下にはなにもいない。
手を離すと、古い茸はぐずぐずと崩れてしまった。するとまた泣き声が始まった。えーん、えーん、と本当に子供が泣くような声である。
土の中かもしれないと思い耳を草の根元に近付けてみる、意外とはっきり聞こえるので土の中ではなさそうである。耳元には赤い小さな茸が立っている。耳のせいだろうか赤い小さな茸から聞こえているような気もする。
赤い小さな茸をじっくりと見ていると、どうも赤い傘が小刻みに震えているようである。老眼鏡をかけた。ヘッドライトに照らし出された赤い小さな茸が確かに震えている。
あ、っと声を出しそうになった。
茸の傘の縁から水が染み出し、小さな玉となって、ぽとりと落ちたのだ。泣き声が高くなった。するとぽたぽたと水玉がおちた。
茸が泣いている。
「どうした」
ついつい声をかけてしまった。思いもかけず感情移入をしている。
すると、頭の中に声が聞こえたのである。
「姉ちゃんが、死んじゃった」
小さな声だった。まさか茸が言ったわけではあるまい。周りの状況から、自分で想像したことが聞こえてしまった、すなわち幻聴なのであろう。
だが、ついつい、「それはかわいそうだねえ」と声を出していた。
すると、「うん、でも明日にはあたいも立派な茸になる」
「そうしなさい」
そんな風に声をかけていた。他の人が見ていたら呆けたと疑われそうである。大きな茸が萎れていたので、小さい茸が悲しんでいるんだろうという、自分の意識には上らなかったが、そう思ったから、それで思わず話しかけたのだろうと自分でつじつまを合わせた。
小さな赤い茸から出ていた水滴が止まった。
時計をみると、家をでて一時間がたっている。ここまでくるのに十分もかからないということは、四十分もこの茸のところにいたことになる。ずいぶん夢中になって泣き声の主を探したものだ。
家に戻って居間の畳の上にころがった。なんだかボーっとしている。
四十分の空白が心配になってきた。頭の老化だろうか。認知症じゃないだろうか。
と、いきなり、目の前に涙を流している赤い小さな茸が現れた。そうだ赤い茸と長い間話をしていたのだ。
姉ちゃんが死んじゃった、と赤い茸が言ったのだ。そう、その後に、私が、
「どうして死んじゃったの」
と聞いた。
赤い小さな茸は、涙を落としながら、
「赤鼠が姉ちゃんのきれいな足をかじったの、そうしたら、姉ちゃん倒れちゃった」
「そう、痛かったろうね」
「うん、痛いって言ってた、そうしたら、今度は茸虫がきてかじったの」
たしかに倒れていた茸は虫にずいぶん食われていた。
「そうしたら、姉ちゃん死んじゃった」
「かわいそうにね、いくつ年が離れていたの」
「一日」
「一日前に生えたんだね」
「そう、それで、とってもきれいな赤い茸だったの、私もお姉ちゃんのようになりたいっていったら、私よりきれいな茸になるわよ、って言ってくれた」
「そうだね、きっときれいな茸になるよ、でも泣きすぎると水がでてしまうからね」
そういったら、赤い小さな茸はこっくりと傘をたおしてうなずいた。それから涙が止まったようだ。
そんなことを思い出した。いや本当にあったことなのか定かではない。
それでも次の朝、あの小さな赤い茸は悲しみを乗り越えて、きっと立派な娘茸に成長していることだろう、まったく感情移入も甚だしいが、そんな思いに駆られ、もう一度裏山に登った。赤い茸の生えているところまでほんの十分である。
私はそれを見てちょっと涙ぐんでしまった。
赤い茸は確かに大きなすらっとした茸に成長していた。だけど頭がちぎれてなかった。赤い傘はきっと鼠か何かにかじられて食べられてしまったのだろう。
しかし、幹はぴしっと立派に立っていた。さぞきれいな茸だったのに違いない。
その日の夜、また山の方から泣き声がきこえてきた。あの赤い茸の泣き声とはずいぶん違って、金切り声に近いような泣き方である。それが絶え間なく続く。縁側にでてみると声が大きく聞こえる。きれいな月が山陰の上で煌々と輝いている。
金切り声に近いような泣き声はやっぱり裏山の方からである。
あまり気持ちのよいものではない。まさかまた茸ではあるまい。獲物を捕る仕掛けなどこの山の中にはないはずだから、何かで怪我した動物が仲間を呼んでいるのだろうか。
庭に面した居間でテレビを見ながら酒を飲んだ。泣き叫ぶ声は部屋の中からだと、途切れ途切れであまり気にならない。テレビの映画にのめり込んで終わりまで見ると、風呂にも入らずに寝てしまった。
明くる朝、目を覚ますと、まだあの鳴き声が聞こえた。一晩中泣いていたのだろうか。何も食べずにもがいていたのだろうか。想像すると痛々しい。
朝食の用意をした。味噌汁にのりと、干物、漬け物、それに生の胡瓜とトマト、白いご飯、まさに田舎の食事だ。東京ではトーストと紅茶、ヨーグルトと果物だったことを考えると、百八十度の変化というところだろう。
食後いつものように朝のテレビを見てから散歩の時間である。あの泣き声は止んでいる。ともかく裏山にいつものように登っていった。
あの赤い小さな茸のところにくると、すでに跡形もない。すべて虫に食われちまったのだろう。茸の一生は短い。
そこを過ぎてさらに登っていくと、斜面の一角が平地にされ、崩れそうな小屋が建っている。その昔、山の道具を入れておいた小屋である。木の手入れや間伐、下草狩り、そういったための道具置き場である。今は道具類が錆びたまま放置されている。小屋の周りは少しばかりだが庭のように広くなっており、椅子代わりの丸太と、もう壊れていて使えないが手作りのテーブルがおいてある。働いた男たちが、そこで食事をしたり、道具の手入れをしたりしたところである。園芸用の草花がはびこっているのは、その当時奥さん方が手入れをしたのだろう。
その小屋の周りにはお茶の木が植えてある。しかし場所が悪い、発育不足で何の木だかわからないほど矮躯化している。その間を埋めているのが茨である。トゲトゲで痛そうだ。
小屋のガラスは割れていて、中を覗くと埃がたまり土が入り込んでいる。
その時、後ろの方から泣き声が聞こえた。苦しそうないやな泣き方だ。
振り返ってみると、どこだかわからないが声の出所は近くだ。小屋の庭の中を歩いてみた。探していくと、お茶の木の間の茨の中である。
あ、あった。また茸だ。白色の頭の大きな茸が茨の中に生えている。その茸が苦しそうに泣いている。やっぱり傘の間から水が落ちている。
よく見ると茨のとげが白い傘や、幹に突き刺さっている。茨の中に生えてしまい、大きくなってしまったのだ。なんだか戦争をしている国に産まれた子供のようにかわいそうな運の悪い出来事だ。
痛々しい、我慢をしていたのだろうが大きくなるにつれ、棘が身体に深く刺さり、苦しくなったのだ。
「とってやるよ」ついつい口から言葉がでてしまった。
小屋に入ると錆びてはいたが鎌があった。それを持って茨をはらった。白い茸の頭や幹に切り傷がたくさんある。茸が痛みを感じるとはつゆとも思わなかった。泣くのだから当然痛みを感じているのだろう。
涙を流していた白い茸は傘を震わせて言った。と思った。
「ありがとうございます、恩にきます、これで楽に崩れていけます」
茸は数日で枯れてしまう。
白色の茸はよほど我慢していたのであろう。楽になったとたん、傘の襞から黄色の煙が立ち上った。胞子を放出したのである。茸は身震いして快楽をむさぼっている。
私はそれを吸い込んだ。そのとたん、すーっと体が軽くなってすっきりとした。だんだん幸せになって、なんだか宙に浮いているような気持ちになった。
目の前をもやもやとした煙がうずまいた。
空を飛んでいる。
白い茸がお礼を言っている。
楽しんでトリップしてねと言っている。
いつの間にか自分の家に戻っていた。白い茸の棘を抜いたことは覚えている。その後どのようにして帰りついたのか全く覚えていない。
ところが居間でぼっとしていると、庭から駐在さんがやってきて、「もどったけ」と声をかけてきた。ともかく、「ええ」と答えたのだが、何かしでかしたのではないかと心配になる。
「お世話になったようですみません」と答えた。
「いえね、なんてことはなかったんだが道端の端に座りこんで、なにしてるかと見たときはびっくらしましたよ」
「僕はなにをしていましたか」
「道端の茶色の小さな茸になにやらぶつぶつ言ってましたな、こりゃ朝から酒飲んでいい気分なんだと思いましたよ、顔も赤かったし、それでお宅にお連れしたんで」
「全く覚えていなくて、すみません」
「いんえ、ここいらの人は結構ありますから、みなよく呑むからね」
「駐在さん、これ東京のお菓子、お嬢ちゃんにどうぞ、昨日かみさんが送ってくれたんで」
若い駐在さんにはかわいい娘が二人いる。
「ありゃ、旦那さんのだろうに、いやすいませんな」
駐在さんは喜んで帰っていった。あの茸がトリップと言った意味がよく分かった気がした。あの胞子を吸うと頭が宙を舞うのだ。
それで泣き声が収まったと思ったのだが、二日後の夜中にまた聞こえてきた。やっぱり茸が泣いているのだろうか。ただ不思議な泣き声だ、表現に困るが、うーっと言った泣き声、要するに気持ちをこらえていたが、どうしても溢れ出てしまって、泣き声が漏れてしまったというような感じである。三回目になると茸がどのような状態だかなんとなくわかる。
それで朝早く裏山に入った。押し殺したような泣き声は前のところと違う方角から聞こえてくる。
そちらには道らしきものがないので、下草を踏み分けてすすんでいった。五分も歩かないうちに、泣き声が近くなってきた。黄色い茸が羊歯の葉の上に頭を出すくらい大きく延びてすっくと立っている。それが、泣き声というかうめき声というか、すごみのきいた声をもらしていた。
黄色い茸の前にホトトギスが紫色のきれいな花を付けて首を垂れていた。よく見ると花が折られている。なにかが折ったようだ。
「どうした」と黄色い茸に声をかけた。
黄色い茸はうなり泣くのを止めて、
「ちょくしょう」
いきなり大きな声をあげた。私の頭の中に聞こえたのだ。
「なんだ」と聞くと、誰かに聞いてもらいたかったのだろう、涙を流しながら思いの丈をぶちあげた。
「おいらはな、あのホトトギスの花が膨らみ始めたときに、ここに顔を出したんだ。ホトトギスには八つの蕾がついていて、蕾たちは「かわいい坊やが顔を出したよ、って、おいらを見たんだ」、それからホトトギスの八つの花はだんだん開いてきて、「早く大きくおなり、茸の王様におなりよ」って、おいらをかわいがってくれた。おいらは一生懸命大きくなろうとして、ほら今じゃクジャク羊歯より大きくなった、そうしたら、ホトトギスの姉さんもきれいな花になって、おいらは周りの茸に自慢したよ、あんな美人の姉さんと一緒なんだってな、ところが山の上から猿がおりてきやがったあいつらアケビの実を食べたり、山葡萄の実を食べるために降りてきたんだ、ところが、このあたりにはアケビも山葡萄もなかったものだから、ホトトギスにやつあたりしやがって、折っちまいやがった。きれいな姉さんが、あんなになっちまった、おいらはくやしくてな、なんとか仇を打ちたいと歯ぎしりをしていたんだ」
茸に歯があるとは思わなかった。
「歯だって、脳だって、神経だってあるんだ、人間だけにあると思ったら、大間違いだ、人間は、歯は体の中でいちばん堅い組織だと思いこんじまっているから、茸の歯が見えないんだ、歯の役割は食いもんを粉砕することだろう、茸だって菌糸が吸った養分を化学的にすりつぶす」
考えたことがわかっちまったようだ。それにしてもやけに科学的な茸だ。
「それで、あだを討つってどうやるんだ」
「それができないから悔し泣きだ」
なるほど、それはよくわかる。
「それじゃ、私が仕返しをしてやろう」と余計なことを言ってしまった。
「どうやってだ」
とっさに思いついたことがあった、それを言ってみた。
「ここに落とし穴を掘って、落っことしてやる」
「たったそれだけか」
「禿を作る」
と言ったのだがどうやったらいいか困った。ところが黄色い茸は言った。
「それはまかしとけ」
ということで家に戻ると、スコップを持って山に入り黄色い茸の近くに穴を掘った。私の手がやっと縁にとどくほどであるから、深さは2メーターもあるだろう、猿はジャンプ力があるから、すぐ出ることができてしまうかもしれないが、ともかく落とし穴に落とすことが第一だ。その後はどうやったらいいのか名案が浮かばないでいると、
茸は「大丈夫だ、落ちてさえくれれば、やっつけることができる」と言っている。
穴の上には細い竹を格子状に何本か渡し、シダの葉っぱをその上に敷いた。バナナをもってきて穴の蓋の上にそうっとおいた。うまく行けば猿はひっかかるだろう。
黄色い茸はうなずいて言った。
「猿のやつ意地汚いから必ず引っかかる、毛をむしりとるのは俺たちがやる」
どうやってやるのか興味があったが、それは聞かないで家にもどった。
そうすぐにはひっかからないと思い、三日後に行ってみた。茸の前の落とし穴のふたがおちている。黄色い茸がなんとなく笑っている。
「うまくいったのか」
声をかけると傘を前に倒した。頷いているようだ。
もう出てしまったのだろうと穴をのぞき込んだ。あにはからんや、大きな猿が穴の中でうずくまって頭を抱えている。私が覗いたことに気がつくと、のっそりと立ち上がった。やけに動作が鈍い。頭のてっぺんがまあるく禿ている。茸のやつが禿を作ったのだろうか。
猿はそのまま大儀そうに飛び上がると穴の縁に手をかけて、やっこら外に出てきた。動きが緩慢だ。みると背中も毛が抜けみすぼらしくなっている。
黄色い茸が今度は大きな声で笑っている。
「おかげで猿公に復讐できた、感謝しますぞ」
どうやってあのあばれんぼうの猿が二日も三日も穴の中でおとなしくしていたのだろう。なぜ毛が抜けてきたのだろう。
茸は私の言いたいことがわかるとみえてそれに答えた。
「猿が穴に落ちたので、胞子を撒いたんだ、眠くなるんだよ、それで猿の奴、ぐずぐずと穴の中で寝ちまった」
黄色い茸は毒茸というより、マジックマッシュルームの仲間のようだ。幻覚作用や動きを緩慢にする毒をもった胞子をばら撒くことができるのだ。
「だけど禿はどうしてだろう」
「仲間に頼んだんだ」
「誰に」
「白癬菌だ、水虫菌だよ、あいつら猿の皮膚にとりついたんだ、すごい威力で毛が抜けた、それだけじゃない猿のやつ山奥に帰ると体中かゆくなって、全部毛が抜けちまうはずだよ。あか裸さ、くくくくく」
怒って泣いていた茸が今は笑っている。茸は笑うことも出来るのだ。
お礼の言葉に送られて私はなんとなく良かったと思いながら家に戻った。
それから数日は静かだった。ところが、真夜中今度は笑い声が聞こえる。茸が笑っているのだろうか。ひゃひゃひゃひゃと大笑いの様子だ。やっぱり裏山の方だ。
朝になり裏山の道を登っていくと、羊歯に囲まれて三センチほどの小さな茶色い茸が大きな声で笑っている。傘の下から滴がしたたり落ちている。おかしくて涙を流しているのだ。それにしてもこんなに小さな茸が大きな声で笑うものだ。
「なにがおかしいんだ」
茸は私を見て傘を動かした。
「あんたさんか、この山で噂になってる、茸と話せる人間だろう」
私は裏山の茸の間では有名人のようだ。
「なにが涙を流すほどおかしいのかね」
「見てみなよ」
羊歯に囲まれたところに、団子虫が平らに延びている。なんだか間抜けだ。それで笑っていたようだ。
「どうしたのかな」
「腰の筋肉痛で、丸まれなくなったんだ」
「かわいそうじゃないか」
「それで、今医者を呼んだんだ」
「だけど、何で笑っていたんだ」
「団子虫のやつ上向けになって丸まろうと一生懸命でな、その様子がおかしくてな」
「人の不幸を笑ってたのか」
「いやすまん、だけどおかしいんだ、医者を呼んでやったよ」
医者って誰だろう。そう思っていると赤い座頭虫が急ぎ足でやってきた。
「遅くなってすまんな、今日は団子虫の筋肉痛が多くてな、これで八匹めだよ」
座頭虫は長い足を団子虫の十四もある節におくと、きゅっと押した。すべての節のところを押すと、団子虫が上向きにひっくり返って、短い足をばやばやさせて、くるりと玉になった。たしかにおかしい。
それを見て、茸は大笑いをしながら、治った治った、と涙を流した。
笑い上戸の茸のようだ。
「ところで、どうして今日は団子虫の筋肉痛が多いんだろう」
茶色の茸はこう答えた。
「この山はとっても生き物にとって生活しやすくてな、鳥は増える蛇は増える、アリもたくさんいる。トカゲなんて、ほら、あそこからこしょこしょ出てきた。
きれいな色のトカゲがちょろっと走り過ぎていった。
「それはいいことじゃないのか」
「ところがな、そいつら団子虫を食っちまうんだ、丸まろうがどうしようが、関係なく食っちまう。それで団子虫はあの細い短い足で一生懸命逃げるわけだ、坂にくれば丸まって転がる。団子虫は命がけさ」
「なるほど、それで腰の筋肉が動かなくなったのか。そりゃかわいそうだ、笑っちゃいけないのじゃないかな」
「そうだな、笑っちゃいけないけどな、だけど正直、あの団子虫の格好は滑稽だよ」
まあそうだがなと、複雑に思いにかられたが、しょうがないことだろう。
「それで、座頭虫を呼んでやったんだ、あいつら、腰をもむのは上手なものだ、我々ももんでもらうんだ、傘が重くなって、首のところが疲れるからな」
座頭虫がよってきて、茶色の茸の傘に二本の足をのせた、プルプルとふるわせると、茶色の茸が「はー」とため息をついた。
その様子がおかしくて、ついつい声を出して笑っちまった。
「なにがおかしいんだ」
「あんたが、団子虫を見て笑っていたのと同じだよ」
私はそう言って、家に戻った。茸はおかし涙もながすんだ。それがわかった。
それはもう三十年も前のことである。信州の実家でそうやって茸たちと暮らしてきた。虫たちとも仲良くなった。楽しい生活だった。
今、病室から年をとった子供と大きくなった孫たちが出ていった。最後の別れに来たようだ。家内はもう三年前に亡くなっている。
その夜だった、物音で目を覚ますと、機械の小さな音に混じってコショコショと何かが歩く音がする。呼吸維持機械の小さな赤や緑の点滅が見える。
「楽しかったよ」
枕元で声が聞こえた。
ベッドの脇の小さなテーブルの上に、色とりどりの茸が傘を揺らしている。みんな傘から水の滴をポタポタと垂らしている。
声を出さずに泣いている。
わざわざ信州からこの病院まで最後の挨拶に来たようだ。
茸の本当の涙である。
「ありがとよ」
茸たちに声をかけて私は目をつむった。
茸の涙
私家版第十七茸小説集「茸伝説、2024、234p、一粒書房」所収
茸写真:著者 秋田県湯沢市小安 2018-9-30


