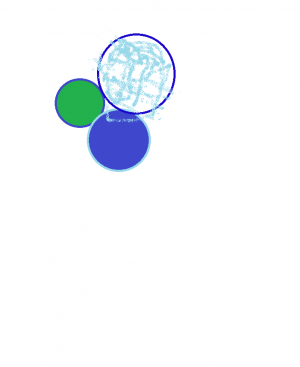SHIHOへの道
悠かなひとへ
「これ、まだ中にフィルム入ってるよ。それに、結構最近まで使ってたみたい。」
と沙乃が言って、
「あんまりいじって壊すんじゃねえぞ、間違っても思い出の品だぞ。」
と啓祐が言った。
「でも中にぎっしりフィルム入ってるよ。おじさん一体何に使っていたんだろうね。気にならないの?」
と言う。
4人兄弟だった父の一番上の伯父が、一人身のまま亡くなったという連絡を聞いて、俺たち沙乃、啓祐のいとこ三人は親族代表として身辺整理にやってきていた。
伯父の住んでいた(そして遺体が発見された)アパートはすでに業者によって整理されていて、俺たちはその業者の事務所に行って金目、もとい遺産分けになりそうなものがあったら選んで引き取ってください、と言われている訳なのである。
「これはもらって帰ろうよ。中に何が入ってるのか気になるじゃない。貴志、あんたこういうのいじるの得意じゃなかったっけ?」
と沙乃のに言われた。それで、俺はフィルムのマウントが入ったままのスライドプロジェクターを見てみた。
単純な構造の物だ。この手の製品が流行り始めたころごく初期に生産されたもののように思える。そして、沙乃の言うように、物が古めかしい割には手入れはしっかりされていて、電源を入れればすぐにでも動きそうな状態だった。
「ああ。動くよこれ。映してみようと思ったらそんなに難しくねえと思うけど。」
「じゃあこれだけ持って帰ります。」
大体人の話を聞かない沙乃は勝手に業者に話を付けている。馬鹿野郎、他の物もちゃんと見てからそういうことを決めるんだよ、と几帳面な啓祐が怒っている。
「模造紙でも張ればいいんじゃないの?」
と啓祐の家で沙乃が言った。結局俺たちはそのプロジェクターの他にカメラ道具一式その他諸々を受け取って、とりあえず一番近い場所にあった啓祐の家に行ったのだった。
俺の父親も沙乃の父親もすでに死んでいる。啓祐の父親は認知症が進んでいて、おばさんが在宅で必死に介護している。
「啓祐、そこのカレンダー外せ。おまえんち壁が白いから、これだけ広さがあれば十分だ。」
「お前結構適当なこと言うんだな。」
「模造紙張った方が却って見にくいよ。いいからそこのカレンダー外せよ。」
おじさんは海外で遺跡を発掘するチームの一員だったと聞いている。と言っても土を掘り返したりするのではなくて、発掘の過程や掘り出された遺物を写真に記録することを担当していたらしい。
業者から引き取ってきたものには手帳や日記もいくつかあって、その中には何年の何月にアフリカのどんな地域で発掘を行っていたのか、などと言うことが書かれている。
歴代最新、つまりピラミッド時代の終焉を飾るものではないか、という遺跡を発掘している、などと記録が残されていた。
「たかしー、さっさとセッティングしてー。」
「うるせえなお前は、こんなもん電源繋いでスイッチ入れるだけなんだからちょっと待ってろ。」
昔から、人のタイミングというものを一切無視する性質の沙乃に俺はちょっといらいらしながら、啓祐の持ってきたライティングテーブルにプロジェクターをセットして電源を繋いだ。
「よし、これで映るぞ。啓祐、カーテン閉めて明かり消せ。」
「おう。」
「なんかわくわくする。ポップコーンとか買ってくれば良かった。」
「お前な。なんか勘違いしてんじゃねえか。どうする。殺人現場のスナッフ画像かも知れないぞ。」
「下手な脅しね。」
とお互いを罵っている二人を面倒に感じながら、俺はプロジェクターのスイッチを入れる。
半端に暗い壁の中に、
【SHIHOへ】
という文字がまず浮かんで、俺たちは一瞬で黙った。
SHIHOへ。
俺は二枚目のフィルムを再生した。荒れ地の中に小さな赤い花が大きく咲いている。いや、花が大きいんじゃない。
花に寄り添ってシャッターを切っているから大きく映って見えるのだ。
次のフィルムには同じような荒涼とした土地に咲いている、紫のグロテスクな花が入っていた。
グロテスクなんだけど、背景が乾ききった石ころだらけの場所なので、そこだけに光が集まっているように映っている。
次のフィルムも同じだった。乾いた砂の大地に、オレンジ色の長い花びらを持った花が散らばって咲いている。その様子を、大きく俯瞰して映しているものだった。
俺たちは黙ってその様子を見ていた。
おじさんが発掘記録を行っていた場所は大体アフリカで、土地が荒れているところがほとんどだった。写真の背景も、だからそういう場所ばかりだった。
おじさんが仕事の傍ら、現場に咲いていた花をカメラに収めたのだろう。
【SHIHO】という人のことを思い描きながら。
誰なんだろう。
どんな人なのだろう。白い壁の中には次から次へと色とりどりの花が浮かび上がってくる。その人は、この花々を見ることは無かったのだ。
きっと無かったのだ。
おじさんはその人にこれらの写真を見せたことは無かった。確信は無いのだが俺たちの誰もがそう思っていた。
それでも、その人に見せるために、その人を思って、花々の写真を撮り続けていたんだろう。
プロジェクターの中に納まっているフィルムは不思議といつまでたっても尽きることが無かった。俺たち三人は、啓祐の壁に咲き続ける花を、時を覚えず見守った。
SHIHOへの道