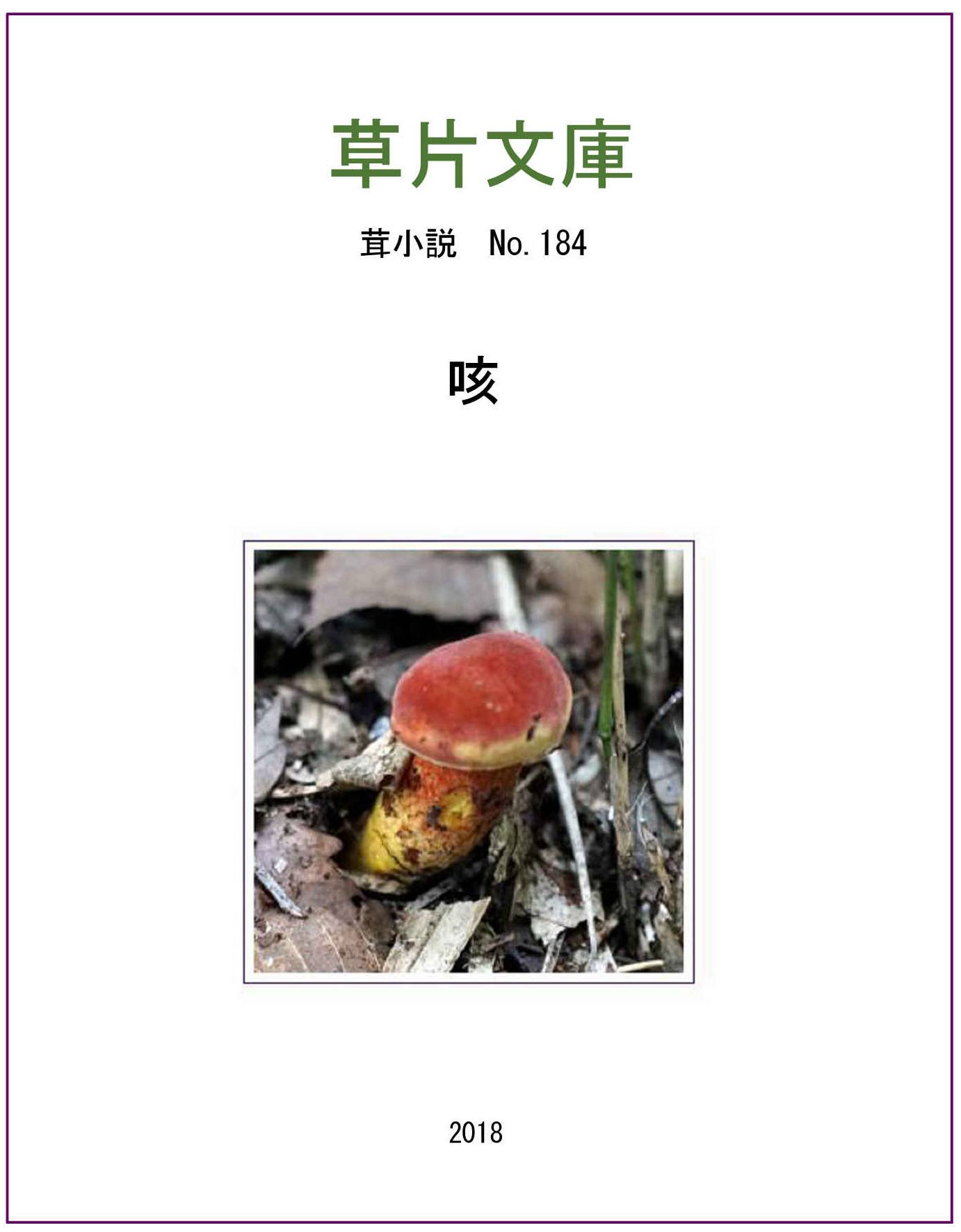
咳
咳が止まらない。やっかいなことである。
一月ほど前に風邪を引いた。熱は三十八度でさほど高くなかったのだが、医者に扁桃腺も腫れているし、その周りも広く赤くなっているので、薬を飲んで身体を休めるように言われた。幸いちょうど五月の連休で、会社を休むことなく治すことができた。それでも会社にでたときにはしゃがれ声で、顔がなんだか痩せたみたいと同僚の女子に言われた。
咳は一月ほど続いたがその後は順調に回復し、梅雨が明ける頃にはすっかり出なくなった。今年は梅雨明けが早く、連日三十五度が続くほどの暑い夏となったが、食欲も落ちず、いつもより元気に過ごすことができた。
秋風が吹き始めた頃、仕事場の隣の席の彼が茸狩に行かないかと誘ってきた。彼は山梨の出身で、すこぶる茸好きである。反対隣の席にいる茸料理大好きの彼女がそれを聞くと、まだ茸狩りって行ったことがない、と大変乗り気である。私ももちろん行くよと返事をした。この二人とはたまに飲みに行く仲のよい間柄である。
彼らが音頭を取ると必ず茸料理が出るところに連れて行かれる。彼女が店を選ぶことが多いが、行くところは中華やイタリアンの茸料理店で、いろいろな茸の味が楽しめる。私茸大好き、と食べながら茸料理の話になる。それに彼の茸の薀蓄を聞く羽目になる。私は彼らほど茸マニアではない。それでも茸の料理は嫌いじゃない。
彼の提案した茸狩は彼の出身地である甲府の茸サークルが企画したものであった。その茸の会に彼は高校のときから入っており、同級生が今も活動をしているという。
旅行会社が企画するものは茸栽培農家とタイアップしていて、自然味がないので面白くないよと彼は言う。茸の会が主催するものは、茸に詳しい説明者がいるし、自然が楽しめるという。どのような茸が採れるかわからないところも面白いらしい。私と彼女は天然茸については分からないので彼にお任せである。
今回は甲府駅に八時半集合である。茸狩としてはかなり遅い時間であるが、遠くから参加する人もいるということでその時間になっている。新宿始発の特急あずさは七時しかなく、甲府につくのが八時過ぎである。それで集合時間を遅くしてくれたのだそうだ。茸サークルのOBが参加するときは集合時間を融通させるということだ。
私は土曜日まだ暗いうちにマンションをでた。新宿駅につくとホームの上では、帽子をかぶってジャンパーをはおり、ザックをしょった彼がすでにスマホをのぞいていた。電車はまだ入っていない。
「はやいね」
「楽しみで寝られなかった、今日山梨の方は晴天だってよ」
彼はスマホで当地の天気予報を見ていたようだ。
電車が入ってきた。彼女はまだ来ていなかったが、指定券をもっているので我々は席に着いた。しばらくすると彼女も来た、発車五分前である。
「二人とも早いのね、指定席でしょ」
体格のいい彼女はジーパンをパンパンにはらせてどしんと椅子に座った。
新宿から甲府まで一時間半弱である。動き出した列車の中では、そこでどのような茸が採れるか、彼は自分の経験を詳しく話してくれたおかげで、水も飲まずに甲府駅についてしまった。あきれるほどの茸好きだ。
駅前には籠などを肩に掛けた人が十人ほど集まっていた。みな駅から出てきた我々を見つめている。彼は一人の背の高い老人に近寄ると挨拶をした。その人が茸の会の会長で、その地域の茸は一目でわかるそうである。我々も紹介された。
「初めての経験です」と言うと、会長さんは「気楽に楽しんでください」と笑顔で応じてくれた。がちがちの茸研究の人ではなさそうで、これなら楽しめるとちょっと安心である。後で知ったのだが、ある大学の名誉教授で、茸の研究では日本で十本の指に入るということだ。人望の厚い人はコミュニケーションがうまい。
今回集まっていたのは地元の愛好家で、使い古した竹か弦でできた籠をもっている。我々だけザックにビニール袋をつるしていた。
駅からバスで四十分ほど山の中腹の道を走り目的地についた。会長を先頭にぞろぞろと林の中に踏み込んだ。木々がほどほどの間隔で生えていて、日の光が程良く下草を照らしている。すっと頭が軽くなる。気持ちがいい。足下に黄色の茸が生えている。自然の茸などあまり縁のない私が立ち止まって見ていると、老人に、
「そりゃあ、卵茸もどきっていいましてね、かわいいんだけど毒ですぞ、これから立派な茸が生えているところに案内しますよ」と笑われてしまった。
山に入ってから三十分もぶらぶらと歩いた。いろいろな茸が生えていて面白いので、彼女とともに時々足を止めたが、彼も含め会員の人たちは目的地にむかって、話もせず黙々と足を動かしている。
老人の足が止まったところは、薄日の差し込む、ちょっと暗い大きな木がまばらに生えているところである。
彼がこれは楢やブナだと言った。
「きっと、舞茸探しだ」
とも言った。
舞茸はコンビニでも売っている茸だから、なぜ彼が驚いたように言ったのかわからなかった。これも後、自然の舞茸はセミプロでないと探せないとし、もし買ったら何千円どころか、大きさによっては万になるということを知った。
老人がみんなの前で茸の採り方を教えてくれた。根っこごと引っこ抜いてはいけないようだ。根元を残せと言っている。
「さて、はじめてくだされ」
会長の話しが終わると一斉に散っていった。私と彼女も彼について茸を探し始めた。ともかく食べられそうと思ったものを袋に入れた。結局引っこ抜くことになってしまっている。
彼が朽ちて倒れた木の後ろにいくと「おい、見ろよ」と小さな声で私と彼女を呼んだ。行ってみると幹に薄茶色の茸が鈴なりになっている。食べられそうだ。
「すごいのにあたったな、これなんだかわかるか」
彼に聞かれたが八百屋では見たことがない。首を横に振った。
「だろう、まず採ろう」と彼に促されて、我々は袋にその茸を詰め込んだ。
「滑子だよ」
滑子がこんなに大きくなるとは。
「天然滑子なのね、すごい」、彼女は一つ一つ丁寧に採って袋に入れている。
「これを見つけただけだって来た甲斐があるよ」
「甲斐だものな」
洒落たつもりだったが、彼には通じなかったようだ。滑子に目を奪われてしまっている。確かに立派なものだと感心しながら採ったが、彼ほどの感動は感じていない。それよりも羊歯の下などに隠れている赤や白い小さな茸の方に目が行く。食べられるかどうかよりも、面白いかどうかだ。時々スマホで写真を撮った。
滑子を採り終わって場所をかえると、他より日の光が強く当たっているところで、ずんぐりした頭の胴体の太い茸が目に入った。なんだかいい格好だ。私がそれを採ろうとしたとき、茸の会長さんが近づいてきた。
「いい茸をみつけましたな、それはヤマドリタケモドキと言いましてな、めっぽううまい茸です」
褒められた。この年でも褒められれば嬉しいものだ。喜んで採った。
「似ているのに毒ヤマドリタケがあるので気をつけてくださいよ、ただ毒ヤマドリタケは針葉樹林だから、ここには生えとらんと思いますがな」
老人はそう言うと、他の人のところ行った。
彼と彼女がよってきた。
「何採ったの」と彼女がきいたので、それを見せると、彼が、
「山鳥か、ポルチーニだよ、いいじゃん」と言うと、
彼女は私の手から茸を奪った。
「あら、これがポルチーニなの、生は始めてみるわ、干したのばっかり」
僕もポルチーニの名前は知っていた。レストランのメニューにある。
彼女が言った。欲しそうだ。
「いいなー、これがあのイタリアの茸なのね」
「そうなんだね、日本にもでるんだね」
「ポルチーニって言うのはその仲間の呼び名だよ、イタリアのとはちょっとちがうんだ、イタリアのはヤマドリタケ、日本に多いのはヤマドリタケモドキ」
彼が説明を加えてくれた。
それからしばらくそれぞれ勝手にあたりを探していたのだが、まだ若い細い木の根元に赤っぽいこれもずんぐりした茸が生えているのをみつけた。
どうみても毒茸である。しかし一応採った。
一時間ほどそのあたりで茸採りをすると集合の合図があった。
会員たちが老人の周りに集まると、沢の方に行きましょうと山を下り始めた。
しばらく歩くと大きな岩がごろごろしている小さな谷川にでた。
それぞれ大きな手頃の石の上に採った茸をひろげた。我々も三人のものを一緒にして大きな石の上にのせた。
老人がそれぞれのグループのところに行って、茸の判別をしている。
老人は我々のところにくると、
「お、これはすごいね、滑子がよく採れましたな」と一つ手にとった。
「よく発育している、立派だ、うまいですよ」
会長は、「みんな食えるね、さすがだね」と、彼に言って、他の人のところに行った。赤っぽい茸は赤ヤマドリタケと言って、やっぱりポルチーニの仲間で食べられるとのことだった。ずんぐりしていてちょっと可愛い茸である。
「ずいぶん採れた、よかったね、それじゃ分けよう」
彼が三等分にしようとしたので、僕はそんなに料理をしないし、家族のいる彼と、まだ独身だが料理好きで大食漢の彼女にたくさん持たせた。ただ赤ヤマドリタケはきれいだったので自分でもらうことにした。
こうして一握りの滑子と赤ヤマドリタケをもってマンションに帰った。
その日の夜、さっそく滑子と赤ヤマドリタケを食べることにした。
滑子は湯がいて食べればいいと彼が言っていた。大根おろしを用意し、沸かした湯に滑子をくぐらせた。
赤ヤマドリタケが問題である。ポルチーニと違うようだが、ネットで見るとやっぱり炒めたりするらしい。
採取したものには虫が入っていることが多いらしいので塩水につけた。しばらくおいておいたが、虫らしきものはでてこなかった。面度なことはしたくない。松茸のように焼いちまおう。ビールのつまみだと、焼く用意をした。
赤ヤマドリタケを網の上に載せ卓上ガスコンロに火をつけた。しばらくすると赤ヤマドリタケが松茸のような色に変わってきた。松茸のような香ばしい香りはない。どこまで焼けばいいんだろう。じゅうじゅうとしてきたところで皿の上にあげた。
熱いほうがうまいだろう。ちょっと裂いて醤油をつけて口に入れてみた。松茸を想像していたせいか、それほど感激しなかったが、決してまずくない。
ともかく一気に食ってしまってビールを飲んだ。旨かったといった方が正しい。
滑子は絶品だった。ビールが二缶空になってしまった。
次の朝、喉がむせったくなって目が覚めた。枕元の時計を見ると4時である。いつも7時に起きるので、まだ3時間ある。
咳がでた。山の林の中を歩くという慣れないことをしたので風邪でも引いたのだろうか。以前のしつこい喉風邪にならなければいいが。だがあのときのようなだるさはない。熱もなさそうだ。起き上がってキッチンで水を飲むと、咳がおさまったので、またベッドに入った。
しばらく寝たようだ。いつものように7時に目が覚めた。咳はとまっているが、喉はむずむずしている。起きていつものように食事の支度をしていると、また咳がでた。ひどい咳ではない。
8時半、会社に出かける時間である。マスクをかけた方がよいだろうかと思案しながら家を出て、駅の売店でマスクを買った。おかげで電車の中では咳き込むこともなく会社に着いた。すでに彼も彼女もオフィスにいた。
「茸狩りはお蔭様で面白かったよ」
「茸おいしかったわ、ポルチーニはシチューに入れたのよ、あんなのが採れるなら、また行きたいわね」
「うん、赤ヤマドリタケ、焼いて食ってみたよ、旨いことはうまかったが、やっぱり炒めた方がよかったようだな」
「面倒だったんだろう」
まさにそうなのでうなずいた。その拍子に咳がでた。
「風邪かい」
「いや、熱もないし喉がやられているんだろう、帰りにうがい薬買って帰るよ」
また何度も咳き込んだ。マスクのまま席に着いた。
仕事は無事に終わったが咳がよくでた。そのたびに喉がひりひりしてしゃべるとまるで、どどどどど、と言った低音になった。
「人の声じゃないみたい、お医者さんによって帰ったら」
彼女が言った。
「気をつけてな」
彼も気遣ってくれた。
会社のはいっているビルの夜でもやっている医院に寄った。いつもは患者が何人かいるのだが、だれもおらず、ちょうどいい具合にすぐに診てもらえた。
「こりゃ、喉が真っ赤だ、何かのアレルギー反応のようだな、いかんな、熱はないようだからいいが、もっと腫れると息が苦しくなるかもしれませんね」
医者が言うとおり、ちょっと息苦しい。
「消炎剤と抗ヒスタミン剤、それに咳止めをだしておきますから、一日か二日は仕事を休んだ方がいいかもしれませんね、診断書、書きますか」
私はうなずいた。有給がかなり残っているので、会社を休むのは問題ないだろう。仕事は彼と彼女がカバーしてくれる。
「もし、咳がひどくなったり、息苦しくなったら大きな病院にいってくださいね」
先生にそう言われて薬をもらうと家に帰った。
マスクをかけていたのだが電車の中でも咳こんだ。
家に帰ってからも咳はとまらなかった。ただ不思議なことに、喉の痛みはなかった。だがまだ腫れぼったくて息が何となくしにくい。熱はないようだし食欲もあった。
明くる朝、目覚めた時の感じでは体もだるくないし、特にひどくはなっていないようだが、喉の熱ぼったさと咳はかわっていない。仕事には支障がなさそうだが、診断書はもらったし、咳がひどくて周りも迷惑だろうから会社は休もう。
会社には電話で連絡をし、家でごろごろすることにした。電話先の受付の女の子が、
「まるでオートバイのような声ね、お大事に」と言ってくれた。
気分は悪くないのだが、咳だけは薬を飲んでも止まらない。咳が続くと胸が痛い。
ソファによりかかってテレビを見ていると喉がむずむずしてきて、立て続けに咳がでた。
ごふぉごふぉと喉の奥から何かがわき出るような音がしてきた。
いきなり胸が苦しくなった。息ができない。喉をかきむしるように手で押さえつけた。こんな経験は初めてだ。
ソファから転がり落ち、意識がなくなりそうだと倒れたとたん、ごごごごごという声がでてきて、がーっと言う音とともに口から赤いものが飛び出した。
涙が出てきて目の前がにじんで見える。
そんな目の前で、ぼんやりと赤いものが床の上でゆらゆら揺れている。胸はいきなり楽になった。
だんだん目の曇りがとれてきて焦点がはっきりしてきた。
床の上で赤っぽい茸がゆらゆらと揺れている。えっと思った。さらに眼がはっきりしてくるとそれが赤ヤマドリタケであることがはっきりした。しかもまだ傘が丸っこくて子供の赤ヤマドリタケのようだ。
また息苦しくなってきた。ゴホゴホと咳がでてきた。胸がきゅーんと痛む。がーっという音がして喉の奥から赤い固まりが飛び出した。涙が晴れると目の前にいたのはやっぱり赤ヤマドリタケの子供だった。
二つの赤ヤマドリタケの子が床の上で立っている。
からだを立て直してソファに座りなおした。
また咳こんだ。胸が痛い。またでそうだ。喉の奥で蠢いている。今度ははっきりと自覚できた。ごにょごにょと喉を上ってくる。
苦しい息ができない、ゴホゴホと咳をしたとたん、やはり、がーっという音とともに赤ヤマドリタケの子が床の上に飛び出して立った。
三つの赤ヤマドリタケの子供は床の上でゆらゆら揺れている。
咳はおさまった。ちょっとほっとしたが、ソファから立ち上がることができない。エネルギーがすべて赤ヤマドリタケに吸いとられてしまったようだ。
ぼーっと床の上を見ると、三つの赤ヤマドリタケの子供が集まって私の前に並んだ。
私の方を見ている。
「かあちゃん」
赤ヤマドリタケの子が私を見るとつぶやいた。ゆらゆら揺れている様はかわいくは見えるが、ポルチーニの仲間だと考えると美味そうにも見える。
「かあちゃん、子食いはやだよ」
見透かされたようだ。
「母ちゃん、おっぱい」
自分からでてきたのだから、赤ヤマドリタケにとって俺が母ちゃんだろうが、何で、茸がおっぱいを飲むんだ。
「おれは、父ちゃんだ」
「なーにそれ、茸は母ちゃんしかいない」
確かにそうかもしれない。みんな胞子をつくる。
「だけど、俺は男なんだ、おっぱいはあってもミルクはでない」
赤ヤマドリタケにTシャツをまくって胸をみせてやった。
すると三つの赤ヤマドリタケの子が膝の上に飛び乗って胸に跳ね上がってきた。
もそもそとTシャツの中に頭をもぐりこませてきた。
なんだとエリを広げて胸を見ると、自分のおっぱいが膨らんで女のものになっている。その乳首に二つの茸が吸いついている。
なんだかこそばゆい。
茸がおっぱいを吸っている。残りの一つが膝の上で順番を待って、二つの茸がTシャツの中で動いているのを見つめている。
一つの茸が乳首からちょっと離れてTシャツから床に落っこちた。するとすかさず膝にいた茸が飛び上がって吸いついた。乳首が吸われるとなんだか身体が熱くなる。
先に吸いついていた赤ヤマドリタケの子供は床の上でゆらゆら揺れていたが、見ている間にくくっと背が延びた。大人の赤ヤマドリタケの形になった。
お乳に吸いついていた二つの赤ヤマドリタケが乳首から離れて床の上に飛び降りた。急に胸のところが涼しくなって、なんだか空虚感におそわれた。それと同時に自分の胸に女のお乳があるのが恥ずかしくなってあわててTシャツを引き下げた。Tシャツの上から膨らんだ自分の胸を手で触ってみた。確かに自分のものである。
急に腹が減ってきた。あわててキッチンに行くと冷蔵庫から牛乳パックを取り出して飲んだ。牛乳がやけに美味しかった。授乳中の母親はきっとこうなのだろう。
居間に戻ると、三つの茸は大きくなって揺れている。なんだかかわいい。しかしこれからどうしたらいいのだろう。
茸たちが並んで歩きだした。キッチンを通り玄関に行った。
玄関を開けろと言っている。
「母ちゃん、バイバイ」
戸を開けるとぞろぞろと外に出ていった。我家はマンションの一階。
ふと胸に手をやるとまっ平らだった。
何がおきたのか頭の中が混乱したままやけに眠くなり寝室のベッドに倒れ込んで寝てしまった。
はっと目をさました時には4時になっていた。昼食も食べずに寝てしまったのだ。
喉がむずがゆくなってきた。お昼に飲まなければならなかった咳の薬を飲んでいない。遅くなったがともかく飲んだ。しかしまた咳が出始めた。
夕飯の用意をしておかなければ。今日は生姜焼きにでもしようと冷凍してあった豚肉を外に出した。
咳でむせる。キッチンで米を炊飯器に入れてスイッチを押した時やたらと咳こんだ。
テーブルの前に腰掛けると朝と同じことがおきた。息苦しくなってコーンと大きな咳がでると赤い茸が飛び出してテーブルの上にのっかった。今度は次から次へと、何と八つの茸がテーブルの上で揺れている。
赤ヤマドリタケの子供たちだ。
咳がとまったらなんだか胸が張り出してきた。
さわってみると膨らんでいる。
テーブルの上の茸が二列に並んだ。何を待っているのかわかっている。Tシャツを持ち上げてやった。
大きな乳がぽこっと飛び出した。自分の胸に女の乳があることは気味が悪いが、吸われる感触は悪くない。
二列に並んだ茸の前の二つが胸に飛びついてきた。そいつ等は私の乳首を吸はじめた。今度は落ち着いて観察することができた。傘の縁の一部が乳首をくわえている。
とくとくと乳を飲む音が聞こえる。
だがなぜ茸が乳を飲むのだろう。
吸い終わった茸の子供がテーブルに戻ると二列目の茸が吸いついてきた。
「うまいか」
ついつい聞いてしまった。
赤ヤマドリタケの子供はうなずいている。
次の子供が吸いついた。乳をのんでいるのは三分ほどだろう。だから十何分か乳を吸われていたことになる。喉がだいぶ渇いてきた。また冷蔵庫から牛乳を取り出して飲んだ。
「母ちゃん、うまかった、外に出してくれ」
茸はテーブルの上で揺れながらそう言った。玄関を開けてやるとぞろぞろと外に出た。今度は自分もサンダルをはいて外に出た。朝の連中はどこに行ったのだろう。
八つの茸は律儀にも二列になって動いていく。玄関をでると階段をおり、エントランスから出ると、マンションの庭のほうに曲がっていった。
小さな庭だが何本か木を植えてある。侘助椿の木の下に、成長した赤ヤマドリタケが三つ生えている。朝の連中だ。今回の八つの茸も、その三つの茸の近くに陣取ると成長をはじめた。
あっという間に、大きな大人の茸に成長した。
「どうして咳がでると赤ヤマドリタケの子供が産まれるんだろう」
無駄だと思ったのだが、朝の三つの茸に向かって言ってみた。すると答えが返ってきた。
「不思議な進化の現象が起きちまったようだ、あんたの食った山梨の赤ヤマドリタケの胞子が咳でむせた拍子に肺に入った。そこで胞子が成長し肺に菌糸がはびこったようだ。これからもおいらたちが生まれるぜ」
「だが、何でお乳を飲むんだ」
「それが進化の不思議なところで、あんたはほ乳類、おれたちゃ茸類なのだが、ほ乳類の特徴であるお乳を飲むような進化がおきたようだ」
「だが、俺のお乳が女のお乳になったのはなぜだ」
「ともかくわからんことがおきたのだが、菌糸から胎盤ホルモンがでたんだろう」
「なんだいそれは」
「ほ乳類なら知ってるだろう」
どうも生物学は苦手だった。
「胎盤から卵巣ホルモンや乳汁分泌ホルモンがでているんだ、それで妊娠している母親の乳腺が発達して、赤子が生まれるとすぐにお乳がでるような仕組みになっているんだ」
なるほど生物学というものも大事なものだ。
「男なのにお乳が膨らんだのは解せないな」
「あんた知らないのかい、ホルモンさえ打てば男だってお乳が大きくなるんだよ、そうやってお乳を大きくしている男がたくさんいるじゃないか」
たしかにカミングアウトした男性はホルモンを打って乳房を膨らめている。
「それで、これからあんたたちはどうなるんだい」
木の下の茸はそれを聞くと、
「それが困ったことに成長するとやっぱり土の上に立っていたくなってね、枯れるまでここにいるよ」
またむせったくなった。咳が出始める。
「ここで、我々の兄弟を産むなよ、庭でお乳をさらけだすのはまずいだろう」
茸も成長したものである。言っていることが正しい。部屋に駆け込んで、キッチンで咳をすると一つだけ茸が生まれた。
Tシャツをまくるとその一つの茸は飛びついて乳を吸いはじめた。
そいつはなんと十分も吸っていた。それから離れるとテーブルの上でどんどん大きくなり人間の頭ほどの大きさになった。
「大きくなったな」
「母ちゃんのおかげだ」
自分の胸を見ると元の平らな男の胸に戻っていた。
「おまえも庭に出たいか」
玄関の方に行くと後ろから、
「おいらは、ここにいたいよ」
前の連中とは違った答えが返ってきた。さらに進化した奴なのだろうか。
「テーブルの上にずーっといるのかい」
「ああ」
「土は恋しくないのかね」
「土はいらないが水は飲みたくなる。できれば器に水を入れておいてくれないか」
そう言うのでいらないどんぶりに水を入れて床の隅に置いておいた。そいつはテーブルから飛び降りると、ぴちゃりとどんぶりに浸ってすぐに飛び出した。
「おい等は勝手にするから、あんたもご自由に」
茸は動き回り始めた。どうやって動いているのだろう。
赤ヤマドリタケは家の中をくまなく回っている。戻ってくると言った。
「一人で住んでいるんか」
「ああ、この年でも一人もんでな」
「なんだ、かみさんももてないのか」
しゃくにさわったが頷いた。両親は遠く北海道で暮らしている。
「兄弟はいるのか」
「ああ、八人兄弟の四番目だ」
「すると、親の面倒はみなくてもいいのだな」
「そんなとこだ」
茸はそんなことを聞くと、居間に行って窓から庭を眺めている。
ずーっと茸の相手をしていることはできない。
キッチンで夕食の用意をし始めると、大きくなった赤ヤマドリタケがテーブルの上に飛び乗った。ずい分ジャンプ力がある。
「今日は何を食うのだ」
「生姜焼きだ」
「なんだそれは、醤油をかけた豚肉を生姜でいためたものだ」
「豚肉とはなんだ」
「豚は哺乳類だ」
「仲間じゃないか、それを食っちまうのか」
「そのために育てたものだ」
赤ヤマドリタケはびっくりしている。
「豚は人間の食べ物なんだな、それしか食わんのか」
「いや、主食は米だ、他にも野菜を炒めたりする、茸だって食うよ、赤ヤマドリタケは美味いよ」
「ほ、俺たちはうまいんか」
「お前さんがた、何を食うんだ」
「うーん分からん、哺乳類と菌類のミックスの我々は、何が食いたくなるかまだわからん、庭に行ったやつらは菌糸を伸ばして土から何か恵んでもらっている、きっと土の中の成分を吸っているんだろう」
「お前は違うのか」
「庭にいたいと思わないから、違うのだろう」
フライパンに油を敷き生姜醤油につけておいた豚肉をさっといためた。
「獣の匂いがするな、生姜はいい香りだ、俺も肉食になっているようだ」
生姜焼きに何か付け合わせがほしくなった。ちらっと赤ヤマドリタケを見て思った。
『赤ヤマドリタケを食べちまおうか』
それがいけなかった。
そう思ったとき、私の後ろに大きなものが現れた。
最後に生まれた赤ヤマドリタケが私と同じほどの大きさに膨らんだ。
振り向くと赤ヤマドリタケの傘に大きな亀裂ができた。
あ!っと思ったとたん、その亀裂が上下に割れると私の頭をくわえちまった。それで私の頭を飲み込んだ。
「すまんな、肉食になったようだ」
そんな赤ヤマドリタケの声が聞こえたような気がした。赤ヤマドリタケの口の中のべたべたが顔にかかったらぺろりと顔の皮膚が剥けてしまった。もう何も見えない。気が遠くなっていく。痛みがないのが幸いなのか。
咳
私家版第十七茸小説集「茸伝説、2024、234p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2017-7-4


