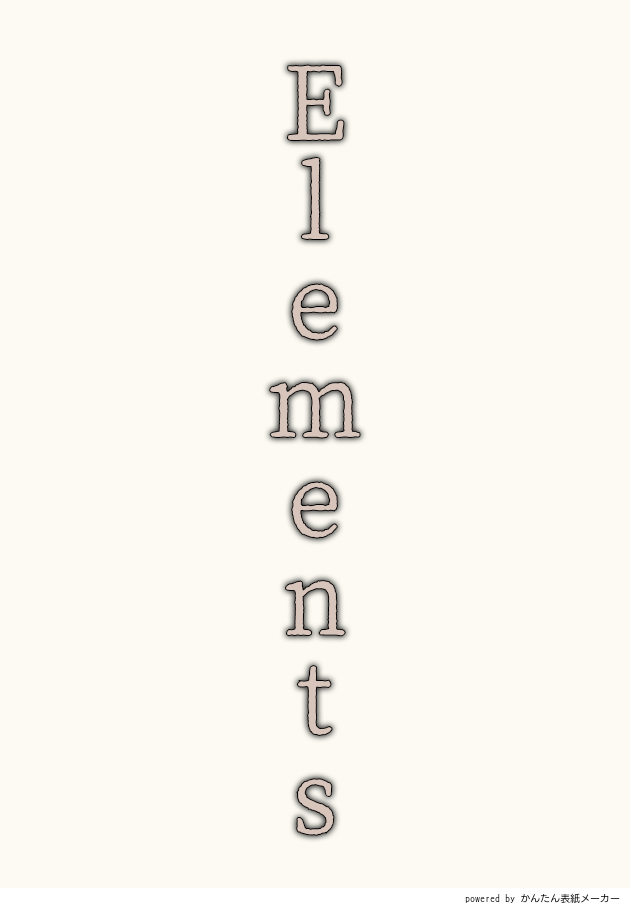
Elements
港町ビアンカ
ここは、エルスメノス王国。数多ある世界の中の、さらにその中の国のひとつ。
かつては多くの植民地を持つ強国であったが、今はすっかり大人しくなり、技術開発に力を入れた結果、科学の最先端とされている。
そして、その科学を影で引っ張っていたのが、王立の研究所、森羅万象研究所…またの名を、エレメント・ラボリティ。
名前を口にすることもはばかられる。
彼らは、技術の発達のためならば、手段を厭わなかったのだ。
そう、例え、少女の身体を毟り取ってでも…。
が。
そのようなことはどうでもいいのだあ!!!
さて、エルスメノスの北西に、ビアンカという港町がある。
商業の中心地で、毎日多くの貿易船も行き来する。市場も常に賑わっており、また、町に張り巡らされた水路では、水遊びをする人も見られる。
元々ここには川が流れていたのだが、町を作る際に整備したためこのようになった。
「あら、おはようスィエルちゃん。お仕事かしら?」
「おはようございまーす、お仕事です!」
「ご苦労さまねえ、頑張ってらっしゃい!」
賑わう市場を駆け抜ける少女。
水色の髪、水色の瞳、水色のワンピース。
彼女は水素。わかりやすく言えば、化身のようなものである。
彼女達の存在は、世界中で認識されている。
もちろん、特にビアンカでは知らない人はいない。
何故か。
ビアンカの近くに、名前のない小さな山がある。その山の頂上には、ある施設がある。
ギルド、Elements。
今では殆どが潰されてしまったギルドだが、Elementsは事情が事情なので、今も残っている。
というのも、Elementsには、彼女のような元素が集まっている。元素たちの安全が、ビアンカによって公式に確保されているのだ。
とはいっても、元素にまだ人権は無い。
ビアンカの人々は元素を快く受け入れたが、すべての村や町がそう考えるとも限らない。元素たちはその事について大して興味は示していないようだが…。
そして、元素たちは無意味に集まっている訳では無い。
元素でないと解決出来ないような問題も世界にはある。そういった大きな事件から小さな人助けまで、様々な依頼を集めているのだ。
そして、スィエルも現在、その依頼を受けている。
市場を抜けると、前方には、森や山に遮られた村や町を行き来するエルスメノス鉄道の、ビアンカの駅が見える。周りの建物と同じように、カラフルな粘土で作られた駅へと走っていく。
その方向には、二人の少女が立っている。
「ちゃんと間に合ったわね。五分後の列車に乗るわ」
茶髪に青眼、赤ふち丸眼鏡のオウカ。酸素。
「隣町までだから、すぐ着くしー」
銀髪に黒目、オフィショルとジーパンというラフな格好のシータス。炭素。
今日は、古くからの知り合いであるこの三人でお仕事だ。
向かう先は、海沿いを南に行った方にある、煉瓦の町フィスプ。
人権はなくとも、ちゃんとお金を払って乗車する。
元素たちはその事について余り興味は示していないようだが。
賑やかなギルド
石造りの大きな建物。ここはElements。
その近くにある、柵に囲まれた牧場。
エルスメノスの暦においては、今は皐之月。五月に相当する。
若々しかった草も、随分とたくましくなってきた。
「ちみどろちゃん、今日はちゃんとご飯を食べてくれたんですね。」
橙色の三角巾とスカート、黄色いセーター、金銀のオッドアイのふわふわ栗毛少女、キャシィ。カルシウム。
物騒な名前の牛を愛おしそうに撫でながら、微笑む。
「乳の方はそれほど異常はなかったし…ただの食欲不振かな。」
家畜として飼われる運命が決まっているなら、せめてその一生をじっくり堪能してほしい。
身勝手な願いだと理解はしているが、キャシィは心からそう思っている。
Elementsは、ビアンカの市場を奥に進んだ方にある小さな山のてっぺんにある。一応、ビアンカの許可をとって運営しているのだが、町長は見返りとして、牧場や畑を営み、収穫物の一部を町に納めるように求めた。町長の素敵な計らいである。
「ふう…一旦戻って休憩しましょう。」
それにしてもキャシィ、独り言が多いのである。
建物の裏にあるドアを開けるや否や、賑やかな声たちが飛んでくる。
いつも通りの、明るいElementsである。
「キャシィ、お疲れ様マグ!」
とてとてと駆けて来たのは、金色ツインテールの小さなメイドさん、マグナ。マグネシウム。
「カフェオレでも飲むマグ?」
「あっ、飲みたいです!」
そう言うと、マグナはグッと親指を立てると、カウンター裏へと走り去る。
キャシィは、カウンターの椅子に腰掛ける。
彼女たちには、食事、睡眠は必要ない。
とはいえ、美味しいものを食べるのは幸せなことであるし、疲れれば眠りたくもなる。
したければすればよい。したくなければしなければよいだけだ。
「お疲れ様でございます、キャシィ様。」
カウンターには、もう一人メイドさんがいる。
銀色のツーサイドアップで正統メイド衣装、優しい笑顔のフェルニー様。鉄。
「は、はい!」
「あなたがいてくれて良かったのでございます。動物達もよく懐いていますし。」
「い、いえ!そんな!!」
とても嬉しそうに謙遜の言葉を述べる。
「キャシィ、どうぞマグ。」
キャシィの前にグラスを置く。カウンター裏にはマグナが乗るための台が用意されている。
(…マグナちゃんは、小さいのに凄いなぁ。)
せっせと働くマグナを見ながら、そんなことを考える。
(それに比べて私は…そもそも金属としての需要に差があるし、理科の学習でも人気ですよねマグネシウムって、私だって炎色反応があるのにそもそも金属だっていう認識も余りされてないようですしあとそれに)
ピンポーン、と、キャシィの思考をチャイムの音が遮る。
入口近くにあるチャイムを押すと、カウンターにある機械も音を鳴らすのだ。
「来客のようですね…エルシー。」
「わかりました。」
フェルニーは、カウンターに座っていた、エルシー…、金色の短いウェーブヘア、刺々しい黄色の瞳、塩のように白いワンピースとヒールを身に付けた少女に声をかける。塩素である。
マグナほどではないが、幼く見える方だ。
エルシーは、玄関に向かう。
訪ねてきたのは青年のようだった。
少し話し込んだ後、紙を受け取り、青年を見送ると、カウンターへと戻ってきた。
「依頼でございますか?」
「はい。わざわざアンダンサから来てくださったようです。」
アンダンサとは、臨海集落と呼ばれる小さな村だ。エルスメノスの南海岸の中央辺りに位置しており、漁業が発達していることで有名である。
「では…はい、登録しておきますね。」
Elementsの依頼管理方法は、依頼ごとに番号を設定し、解決して番号が開くと、そのあと届いた依頼は、空いている番号にに、小さい数字から詰めて登録されていくというものだ。
「ところでエルシー、あの子はどちらに?」
「…知らないですけど。」
フェルニーに笑顔で尋ねられ、エルシーは少し営業スマイルを崩す。
「あの子?」
「ふふ、可憐で儚い愛らしい子でございますよ。」
「似合いませんよ、そんなの。」
キャシィは、首を傾げるばかりであった。
優美なる彼女
絹のように滑らかな、ウェーブがかった白い髪。
磨かれた陶器のように白い肌。
力を込めれば折れそうな、桃の枝のように華奢な身体。
洞窟の奥に秘められた泉のように、無垢な瞳。
魅せられぬ者はほとんどいないであろう、見目麗しゅうお嬢様。
そんなわけなので。
「お茶だけでも、ね?」
「そ、その…けっ、け…結構、です…。」
銀のように澄み渡った声で答える。
絶賛ナンパされ中である。
「そんなこと言わずにさ~。」
引き下がらない、しつこい男。嫌われるよ。
しかし、美しい金属には毒があるのが鉄則であり…。
「ちぇいやー!」
涙目になっていた少女の後ろから、何かが飛んでくる。
毒ではなさそうだ。
「うちのスイジーに何してんのよ、某ハロゲンに殺されるぞ!」
銀髪ポニーテールの小柄な少女。青銀の瞳で、吹っ飛ばされて倒れた男を見下ろす。
彼女はエイン、銀である。
そして、スイジーもまた元素であり、水銀だ。
「………あの、エイン。気絶…しちゃったみたい。」
「え、嘘ぉー!ドロップキックは強すぎたかー。」
てへぺろっ★と、明らかに故意であることを全面に押し出す。
「それは置いといて、スイジー!」
「ひゃいっ…!」
スイジーよりも少し背丈の低いエインは、ずいっと詰め寄って見上げる。
「あんたももう少しはっきり言うこと!ダメそうなら殴る!」
「…はい。」
「で?こんな一通りの少ない住宅街で何やってたの?」
「…ひ、人の少ない道からElementsに行こうと。」
「ふーん…。」
エインは、しょんぼりするスイジーの手を取る。
「仕方ない、心の広いこのあたしが一緒に行ってあげるわ!」
得意げに言いながら、ウィンク。手を引いて、カラフルな家の間を歩いていく。
窒素固定と書くのがめんどくさいのでチエ固と書いたことがある
それは、何年も前、ある日の理科の授業のことだった。
プリントにはたくさんの元素の名前が並んでいた。
しかし。
その中で。
窒素だけが擬人化されていなかった。
そしてさらに。
テストで漢字間違えた。おまけでマルしてもらったけど。
まあそんなことが積もっていて、とりあえず言えることは。
窒素は不幸…薄幸不運…。
「私になんの責任もないだろ!!」
チエちゃんこと、窒素に怒られた。
「…だってさ。凄いしつこかった。」
「へえ、エインちゃんが?」
薄灰色の髪と瞳の常識元素チエは、廊下を歩いていたらエインに出会ったらしい。
すると、今日スイジーを助けた話を延々と聞かされたそうだ。
いやあツイてない!!
「…。」
「ち、チエちゃん、次元の壁は越えちゃダメよ?」
「…善処する。それにしても、エヌーゼ。何を混ぜているんだ?」
薄い銀色の髪に黄色の瞳、真っ黒なドレスを着た少女は、白い手でビーカーの中の何かをかき混ぜながら、ウィンク。ナトリウムさん。
「ひ・み・つ♥」
「ああそうか知ってた。」
無表情で返す。
「もう、あなたが聞いたのに冷たいわねえ。」
仕方ない、言動がいつもアブソリュート・ゼロだから。
「誰が絶対零度だって?」
「チエちゃ~ん、次元の壁が~。」
越えたい~。
「にしても、小さなボディーガードさんは一緒じゃなかったのかしら?」
「ん?…ああ、さっきの話か。…あいつのことなら、さっき広間に居たのを見たが。」
「あの子、不思議とスイジーを気にかけているものねえ。化学的な関わりはあるにしろ薄いのに。化合物を作るとか、医療関係の役割を交代したとか。」
「…いいんじゃないか、性格の問題だろ。心を持っている以上、そういった枠に囚われない関係性が生まれてもおかしくない。」
年中真冬のチエにも、感情はしっかり備わっているのです。
「ふふ、それもそうね〜。」
かき混ぜていたビーカーの中身を容器に移すと、蓋を閉めて密閉する。
近くに似たような容器がいくつかあり、箱に詰められている。
怪しいもの⋯ではなく、エヌーゼは、薬品調合などの依頼を任されているのだ。たまにチエも手伝っている。
本来はエヌーゼの得意分野ではなかったが、やっていくうちに技能が身についていった。
これは、人の器を得たことの利点だろう。
そう考えながら様子を見ていると、突然ノックの音がした。
「どうぞ~。」
エヌーゼが言うと、ドアを少しだけ開けて、少女が顔を覗かせる。
「あら、エルシー。珍しいわね、何の御用かしら?」
「…いえ、人を探してただけです。居ないみたいですね。」
失礼しました、と素っ気なく残して去っていく。
二人はしばらくドアを見つめ、顔を見合わせる。
そして、春に咲く花のように小さく微笑んだ。
おふたりさん
スイジーは、廊下の端を俯きながら歩いていた。
「…」
窓から外を見ると、緑の木々が風に揺れている。少し離れたところには、ビアンカの港、そして輝く海も見える。
綺麗な景色を見るのは好きだ。けれど、見る度苦しくなる。あの綺麗な景色を、自分自身の手により壊したと思うと。
見たいけれど、見たくない。これが、コンフリクトというものか。
「こんなところで何をしているんですか、ど腐れお嬢様。」
「ひゃ!」
驚いて声のした方を向くと、そこには、スイジーより少し背丈の低い少女がムスッとしながら立っていた。
普段の彼女がほとんど見せることのない態度である。
「…会っていきなり罵倒されるような覚えはないのだけれど。」
その姿を確かめると、ツンとしながら返す。
顔がぱあっと明るくなっていたことに本人は気がついていない。
「全く、嫌でも人通りの多い道を選べと何度も言っているじゃないですか。それか一人で歩かないこと。歳のせいで難聴なんですか?」
「うぐっ…。」
それに関しては言い返せない。
「探してもいないし、全く…。」
「………エルシー。」
「何ですか?」
名前を呼ぶと、視線だけ向けて応えた。
「私を探していたって、どうかしたの?」
「……。」
エルシーは硬直する。滑らかに目を逸らすと、
「別に。注意と監視に来ただけです。」
素っ気なく呟いた。
そして舞台は移り、Elementsがある山の途中に置かれた丸太椅子。
金髪ツインテールの妖精のような少女と猫耳カチューシャメイド服の黒髪少女が、並んで座っていた。
「クロルちゃーん!ニケの愛しのクロルちゃーん!」
「ちょ、こ、こんなところで…もう!」
「えー?クロルちゃんは、ニケに抱きつかれるの、イヤ?」
抱きついたまま、黒い瞳で見上げるように見つめる。確信犯(誤用)である。
「っう、い、嫌じゃないけど…。」
「それじゃいいでしょ?」
「うう…。」
どういう原理か猫耳をピコピコさせ、尻尾をピンと伸ばして震えるクロル。
これが、こんふりくとというものか。
「で、でも、ニケ…私…。」
「なあに?」
「私…ニケとの時間は二人だけがいいの…。」
「…。」
「あ、その、やっぱり気にしな」
「ああああああ萌え死する可愛い愛してるっ!」
「え?」
「殺す気?殺す気なの?ニケを萌え死させるつもりなのね!無事昇天しましたありがとうございます!とっても可愛いですありがとうございますこの世にクロムという元素を生み出してくれてありがとうございます!でも残念、この可愛いクロルちゃんはニケのなんだな!誰にも渡しませーん!ニッケルといえばクロム!クロムといえばニッケル!合金のニクロムは有名!ところで二クロム酸カリウムって紛らわしいよね!ニケたちは世界から認められているんだなーあ!大金つまれても世界が滅んでも譲らないんだなぁー!ニケたちの愛を邪魔するものは刹那に塵に還します!いや、塵も残さず消滅させます!ニクロムに誓います!」
「え、あ、の、え?」
暴走するニケと困惑するクロル。
横でバット片手に立つフェルニー様に気が付くのは、もう少し後の事。
輝く彼女は今何処
鉱物のように光沢のある栗色の髪を、小指でさらりと掻き分ける。
緑色の瞳は光を吸い込み、同時に光を跳ね返しているようである。
白いチャイナドレスに身を包んだ少女、ユキエは、賑やかなElementsの広間の隅にポツリと座っていた。
高貴で美しい元素、金。
ユキエが座っている椅子と机の近くには、本棚がある。そこには、過去の事件、依頼の資料などが置いてある。
「ユキエ、何を読んでいるんだ?」
赤茶色のおさげ、赤い瞳の少女、キュオルは歩いてくると、隣に座る。
丈の短いノースリーブの着物を着ている…正しくは、肘の上あたりから袖先だけはある。
彼女は銅である。
「アラ、キュオル。マグナから頼まれてネ。過去に、局地的に木が枯れる現象があったかどうか調べテと言われたノヨ。」
普通の日本語…ごほん、エルスメノスの公用語だが、どこか特徴のある話し方だ。
「ふむ。何かあったのか?」
「そうらしいワネ。私もよく知らないケレド。」
よく知らないのに調べているのか、と心の中で突っ込む。
「それよりあなた、お暇なら頼まれごとをしてくれないカシラ?」
「…えー。」
「失礼する。」
図書室の扉を開け、キュオルは中を覗く。
「あら、キュオルちゃん。どうかしたんですか?」
「怖い魔物とかはいないのよー。安心してでておいでなのよー。」
恐る恐る覗いたつもりは無いが。
中にいたのは、ベルとイヨ。
茶色いセミロングヘアに茶色い瞳の臭素、ベル。
薄紫のドリルツインテに紫の瞳、そして掃除箒がトレードマークのヨウ素、イヨ。
「いや、それが、エインを探していてな…。」
「エインちゃん?」
「ああ。あいつは、見つけようと思ったら見つからないんだ。全く何処をほっつき歩いているのやら。」
「神出鬼没なのよー。」
気がつけば掃除を始めているイヨ。伊達箒ではないのだ。
「エインちゃんですか…うーん、Elementsにはいると思うんですが。」
ベルはエインと仲が良い。ベルは写真を撮るのが趣味で、エインはそれを見るのが大好きらしいのだ。。
「ありがとう。別のところを探すよ。」
「はいはーい、またねなのよー。」
ドアを閉じ、次はどこへ行こうかと考える。
ふむ。そうだ、あそこにしよう。
行き先を決定し、赤い絨毯の敷かれた廊下を歩き出す。
銀色大捜索
「え、エインさんですか?」
「見てないのって…。」
個室その1。黒髪おさげの制服少女ホウコ、ホウ素と、透明感のある水色の短髪と瞳が綺麗な少女ルル、テルルは首を横に振る。
「でも、さっき廊下ですれ違ったのって。」
右目を覆う前髪を揺らし、耳のあたりに着いている羽をピコピコさせながらルルは言う。
⋯原理は不明だ。
「そうなんですか?あ、ごめんなさい私はずっとここにいたので…ごめんなさい私地味なだけで何のお役にも立てな」
「お日様が沈む方に向かっていったのって。」
ルルの瞳に悪意はなかった。
「な、なるほど…。ありがとう、探してみる。」
そして今度は別の個室。
誰もいなかった。
次の個室。
誰もいなかった。
またさらに別の個室。
キャシィが暖炉の炎を橙赤色にして遊んでいた。
見なかったことにした。
またまたさらに別の個室。
スイジーが本を持ったままお昼寝していた。
静かにドアを閉めた。
なんとさらにまた別の個室。
マグナがパソコンを三台同時に操作してなにかブツブツ言っていた。
そっとドアを閉めた。
物置。
ストロンチウムのストールが時計を3つ並べて眺めていた。
ドアはもともと開いていたのでそのままにした。
またやってきた個室タイム。
エヌーゼが蝋燭の炎を黄色にして遊んでいた。
お前もか、ドアを閉めた
個室。
あれ、ユキエお前さっきまで広間に…。
ドアを閉めた。
結局、見つからなかった。諦めて広間に戻ろう。
そう思い、戻ってきたのだが。
居た。
カウンターに座って、フェルニーと話していた。
「…。」
無性に腹が立ったので、青緑の炎を纏ってヘッドスマッシュした。
「あだぁっ!?」
煉瓦の町フィスプ
ビアンカの南側の近い位置。小さな森を挟んだ向こう側に、フィスプという町がある。
別名、煉瓦の町。
その名の通り、道や建物などには煉瓦が多く使われている。
エルスメノス王国中を走る列車に乗って、二人の少女がフィスプへとやって来た。
「ふいー、着いたわね。」
「え、えと、町長のカーマンさんが駅の近くにいるはず…。」
エインとスイジー。二人は、フェルニーのご指名によるお仕事中だ。
「局地的に木が枯れる、ねえ…ふーむ。」
今回の依頼の内容は、フィスプ付近の森の木が特定の場所だけ枯れてしまうので、原因を調べてほしいというものである。
詳しい話は、町長が直々に教えてくれるようだ。
駅舎を出ると、噴水の近くに立っていた老人がこちらに手を振った。
見た目の特徴は伝えていたようだし、フィスプの人の髪色は、ほとんどが濃いので、すぐにわかったのだろう。
「あの人よね。」
「多分…。」
駆け寄ると、老人は深々と礼をする。
「よくぞ来てくださいました。わたくしが町長のウェルズィ・カーマンです。ささ、是非わたくしの家へお越しくださいませ。」
「ご自宅ですか?」
「ええ。今回の依頼は実は、私と近しいもので話し合った上での独断でもありまして…」
人差し指を立て、小声で言う。
組織の中の個人名義の依頼は、よくある事だった。
組織となれば人が集まる。その人々の中には、元素の存在を快く思わない者もいることがあるのは当然だから。
町長の家は、駅前広場からそれほど離れていなかった。
周りよりかは少し大きく見える屋敷であった。門を開けると、石畳の道がある。その両側には、植物が不規則に育っている。
形は整っているので、植物自体の手入れはされているようだ。
そして、二人は屋敷の応接間に招かれた。
壁にはフィスプの写真であろうものが飾られている。古いものから最近のものまで、年代はバラバラだ。
クラッシックなソファに座るように促され、そのフカフカした身に腰を下ろした。
部屋には白い飾り枠のついた煉瓦の暖炉があるが、もう使う季節は過ぎ去ったため、しばらく使われた気配はない。
「すみませんね、わざわざ。」
ウェルズィも、反対側にある同じソファに腰掛ける。
「いいえ、お仕事ですので!」
誇らしげに胸を叩くエイン。スイジーは控えめに頷く。
「それでは、早速詳細をお聞かせいただいても?」
「はい…。まず、フィスプの南側にある名もなき森。そこの木が、一部のみ枯れてしまったことはご存知ですな。」
「はい。その後、そこには何の植物も育たなくなったと。」
「その通りです。土を調べて見ても異常はなく、特に異変はないようでした。しかし…。」
「…明らかにおかしい。人智を超えている、と。」
「そうなのです…。どうすれば良いのかわからず、噂に聞いたElementsへとご依頼した限りです。」
ウェルズィの表情は、疲れているようだった。
Elementsが、最後に残った頼みの綱なのだろう。
「…了解しました!あたしたちが必ず解決してみせます!ね、スイジー?」
スイジーは慌てながらコクコクと頷く。
「それはそれは…どうぞよろしくお願いします。」
ウェルズィは、ほっとしたように微笑んだ。
道祖神の気まぐれ?
森。葉を揺らす木々の隙間には、人の手により作られたような道がある。
この先は、さえずりの森と呼ばれる場所に繋がっている。小さな草原を挟んでおり、そこが境界とされている。しかし、この名もなき森をさえずりの森に含める場合もある。
エルスメノス鉄道は、さえずりの森の先にある黒翼の谷という場所を避けて走っているので、さえずりの森にも通っていない。
異変が起こっていると言えど、森の中は自然の音で満ちていた。
「と、得意げに言ったは良いけれど…、宛はあるの…?」
「あああああたぼうよ!」
「ラボ送りにしましょうか…?」
「サーカス送りみたいに言わないでごめんて。」
意気揚々と調査を始めたはいいが、地図が読めなかった。
二人に地図を読む能力自体ががない訳では無い。
ここがどこだかわからないだけだ。
「まあ、いざとなれば飛べば。」
「私たち…気体じゃない…。」
常温で気体の元素は空中浮遊が可能であるが、二人は固体と液体だ。
「ナンテコッタイ。」
エインはまさに意気消沈。
「…あーあ。旅の神様とかが助けてくれないかしらー。」
何気なく呟いた。
「…!」
エインの言葉に続くようにそよ風が吹いた。それ自体は何らおかしいことは無いのだが、スイジーは僅かな異変を感じ取った。
「ね、ねえ、エイン…その、今なにか…。」
「んぇ、どしたの?」
「…いえ、何でも…。」
エインは特に何も感じていない様子だった。今のは自分の過剰反応だったのだろう。
だって、エインが気付かないで私だけが気が付くだなんて有り得ないもの…。そう心の中で自分に言い聞かせる。
「あー、じっとしてても意味無いわ。あっちの道に行ってみましょ。」
「え?あ、待っ…待って…!」
駆け出すエインを追い掛けるスイジー。
その方向は、今…。
川が運ぶは彼の地の知らせ
「あ、あっちに開けた場所がありそうよ。」
木々の隙間にできた細い道を歩き続けていると、エインが突然言った。
「…川。」
耳を澄ますと、水が流れるような音がする。
深呼吸をしてから、スイジーはそちらへと向かう。
足元に気をつけながら、少し下り坂になっている道を進む。やがて地面には小石が散らばり、さらに進むと小石だけとなった。
水は穏やかで、そこまで深くはなさそうだ。
しかし念の為警戒して、あまり近づかないでおく。
「上流の方まで見えるわねー。」
そんなスイジーを気にすること無く、エインは川辺に寄る。
「あ。」
いきなり声を上げたかと思うと、ガバッとこちらに振り返って、
「橋みたいのが見えるわ!」
「橋?」
「そ。あんた、水には入れないでしょ?」
「…そ、それ、は。」
確かにその通りだ。しかし、そのようなことをエインに告げたことは一度ももないはずだ。どうして知っているのかと少し困惑する。
(入れたらぶちのめすってあいつに言われてるからね…。)
エインが誰かに、脅される勢いで言われているなど想像もせず。
「まああたしも濡れたくないし、川辺に沿っていきましょ。」
「…ええ。」
川の中には、小さな魚が泳いでいる。
この川が生きている何よりの証拠である。
このまま異変を放っておけば、この命たちは滅んでしまうかもしれない。
元素は、死なない。自然が全て滅ぼうと、生命が全て絶えようと、死ぬ事は出来ない。そう、生きてなどいないから。
だからこそ、今ある美しき生を無闇に脅かしてはならないと強く思う。
「階段だわ、あそこから上がれそう。」
橋の横には、恐らくこの川辺へ降りるためであろう石の階段がある。
綺麗に整えられた階段を登り、橋の向こうに目を向ける。
するとそこには⋯。
「…あっ。」
目的地へと着いたことを示す光景が広がっていた。
最後の天然元素
地面に生える草すら無い。土があらわになり、石ころがいつくか転がっている
辛うじて立っている木にしがみつく葉の色は黄色。茶色。一片、また一片と散っていく。
近づくだけで命を吸い取られそうな荒廃した土地。
それが、木を中心とした円のように広がっている。
「こ、これが…カーマンさんの言っていた…。」
「多分そうよね、あそこだけおかしい。周りは変わった様子はないわ。」
警戒しながら、近付いていく。
荒れた円に入ろうとした、その時。
「止めときな。」
背後からだった。
振り返ると、そこには女性が立っていた。
「そこに踏み入れば最後、生命を吸い尽くされるよ。」
どこかの何千年も前の古い王朝にありそうな服を着た女性の声は、大人びている。
「お前さん達が…例えば元素だとか、人間じゃない限りは構わないがね。」
琥珀色の長い髪に、萌黄色の瞳。
「あなたは…一体…?」
袖先を口にあて、ニヤリと笑う。
「私はフララ…ただの通りすがりさ。」
纏うオーラはただ者ではないことを十分に示していた。
「あ。あの、ちょっとこっちきてくれますか?」
「え…?」
エインがけろりとした表情で言う。
「いいよー。」
「いいの…?」
スイジーは焦りながらその状況を見守る。
そして、フララと名乗る謎の女性がエインの横まで来た時。
「うおりゃあっ!」
蹴った。
「蹴った…!?」
「へぶぼっ。」
フララ、サークルの中へ吹っ飛ぶ。
生命を吸い尽くされている様子はなさそうだ。
「………。」
「さて、あんたの話が本当なら、あんたは人間じゃない」
「や、やり方が豪快すぎる…初対面の方に何ということを…。」
控えめに突っ込むスイジー。もっと主張していいんだよ。
「くっ…お前さんなかなかの策士だね…。」
たぶん違うとオモイマス。そんな声を心の中に反響させる。
「さあ、お前は何者だ!吐きやがれ!」
「わーっ、酷い、川にとびこんでやるー!未だ誰も行ったことのないビッグで豪快な爆発実験してやるー!」
「さてはお前、アルカリ金属だな!?」
「ひーっ、よくぞ見破ったー!!」
(…たすけてえるしー。)
場の空気についていけず、一言も発せなくなる。
「とまあ、さて、茶番はこれくらいにして。」
「そうね。」
「お願いだから…そうして…。」
「お前さんたちが、アレか。この森の異変を調査しに来たっていう?」
「そうね。」
「そうか、やっぱり私の直感に狂いはないな。」
「そうね。」
「…。」
「しかしまあ、これ以上被害が拡大することは無いだろう。」
「そうね。」
「エイン…そこは流してはいけないところ。」
「おおっと危ない、詳しく聞かせてもらいましょうか」
いくら元素同士とはいえやけに対応が雑な気がするが何故だろう。
「まあ、そのつもりで来たし。…昨日の夜、私は、この事件の犯人を追っていたんだ。」
服に着いた汚れを払いながら、フララは立ち上がる。
「奴の目的はわからんが、ここで何かをしていたよ。だから取っ捕まえて尋ねようと思ったんだがねぇ、何分逃げ足が早くて。流れ星みたいに消えちゃったよ。だから恐らく、もうここら辺にゃあいない。」
「…術式は全て解除されてしまっているけれど、まだ魔力が少し残っている。生命力を吸うということは、自身の魔力だけでは足りなかったから…。残った魔力の量から見て、そこまで力がない訳でもない。…ということは、大掛かりな魔術を行使しようとした…みたい…。」
「はえー、あんたそんなことまで分かるの?あたしはあんまり感じないわ。」
「おや驚いた。彼女は魔術師なのかい?」
「そうよ、一応あたしもね。でもま、あたしは力が弱いから、あんまり魔力とか感じられないわけ。」
「…。」
スイジーは、エインの言葉にどこか納得のいかなそうな顔をするが、本人は気が付いていない様子だ。
「…それで、その犯人は……警戒して、どこかへ行ってしまったと…?」
「………ハイ、恐らく。」
「逃がしたの?」
「………ハイ、恐らく。」
「ええー…。まあいいわ、収穫っちゃ収穫だし…」
「ま、魔力が完全に消えれば、土地も元通りになるはず…。」
「なーんかしっくりこないけど、犯人がいないなら帰るしかないわね。」
やれやれと溜め息をつく。
「…で?あんたは結局、どれ なわけ?」
「私かい?私は…フランシウムさ。」
にひひ、と妖しげな笑みを浮かべながら言った。
星のカケラ
「そうでしたか、ありがとうございます。フララさんも。」
「いーえいーえ。私も出歩いてて悪いねぇ。」
どうやら、フララはフィスプでは有名らしく、森に住むお人好しとして頼りにされているという。
今回もまずはフララを頼ろうとしたが、住み着いている小屋を何日も空けていたため、諦めたそうだ。
「報酬については、遠慮しておきます。十割フララのお陰ですし。」
「全部じゃんか照れるー。」
「そうですか⋯。…では、代わりに、また何かあった時には頼りにさせていただきましょうか。」
「もっちろん、任せてくださいなー!」
そんな三人の会話を聞きながら、スイジーは一人考えていた。
犯人の目的は一体何なのか。相当な力を持っているにも関わらず、周りの生命力を奪ってまでしなければ発動出来ない魔術。
もしそれが実際に発動されたとしたら?
悪いこととは限らないが、周りには何かしら大きな影響が出るだろう。
決して油断していけない。木の枯れた場所は他にもあるので、またどこか別の場所で行われる可能性は十分にある。
(…生命を、奪う。)
植物だけではなく、動物の命さえも。
誰も触れることはしなかった、あの小さな骨たちが脳裏に浮かぶ。
犯人はその被害を厭わない。
「…そうだ、スイジーとやら。」
「…え?」
「あのリスの…遺骨。というか、小動物の遺骨。他のところでは全く見かけなかったよ。」
そう言うフララの意図は、一つぐらいしか浮かばなかった。
「はあっ…はあっ…!」
月に照らされぬ木の影を裂くように、白いローブを着た人物が走っていた。
どうしてバレた?何度やっても、あの女は自分の前に現れた。
森を抜け、星空の見える場所まで辿り着いた。
ゆっくりと立ち止まり、呼吸を整え、方位磁針を腰にあるポーチから取り出す。
南へ来たらしい。
となると…向こうに見える仄かな明かりは、ああ、あの村だろう。ある程度地図は暗記していた。
一面の星。
手を天高く伸ばす。星めがけて。
「私は。」
ぎゅっと握りしめ、あの時の決意を思い出す。
「あの時聞いた声を忘れない。どこかの星から届いたあの声を。絶対、夢なんかじゃない。」
なぜ自分の元に届いたかはわからない。それでも。
「私は星を目指す。」
星へ繋がる道を作り出す。望遠鏡で覗くだけじゃ全然届かない。もっともっと綺麗な星々を私は知りたい。見たい。
争いごとにしか興味のない野蛮な奴らに見せつけてやる。星空の神秘を。恐怖を。広大さを。素晴らしさを思い知らせてやる。邪魔なんてさせない。絶対にやり遂げる。やり遂げるんだ。待ってて、星たち。
噛み締めるように呟くと、再び、濁りのない瞳で前を見据えて走り出す。
「絶対…諦めるもんか!!」
邪魔なフードを乱雑に取り払う。
紺色の空に、尻尾をつけた星が見えた。
「⋯約束、だから。」
流れ星が落ちるように儚く、少女の口から零れ落ちた。
湯けむり少女
枯れ木の一件から一週間後。
「まーぐー…。」
机に突っ伏して唸るマグナ。狭く感じる部屋に置かれた机には画面やキーボードなどがごちゃごちゃ置いてある。
その沢山あるものを、器用に使い分けている。身体の小ささからは想像もできない技能だ。
「あまり根詰めすぎないで、休憩も肝心ですよ。」
紅茶をもって、フェルニーが入ってくる。
「マグ。…でも、元素は順調に集まってはいるものの放射性元素がいないというのは心配マグ。」
座ったまま、地面に全く届いていない足をばたばたさせる。
Elementsにいる元素は、人に敵意を持っていない。しかし、全ての元素がそうとは言い切れない。
もし、望んで人に害を与えたならば、こちらとしても黙っていられないのである。
「ほら、お茶でもお飲みなさいな。」
フェルニーが紅茶を差し出すと、目を輝かせてそれを受けとった。
「今のところ放射性元素うんぬんの被害は出ていないようですが…ちょっとした情報を仕入れました。」
「マグ?」
「ふふ、旅人ベレーのお話は覚えていらして?」
「もちろんマグ!」
数日前、エメラルド色の瞳の旅人についての話を聞いた。
各地を転々としており、魔法を活用した絵を描いては現地の人にプレゼントするというのだ。
素性が謎に包まれた少女である。
「謎がある人はとにかく確認。ということですので、これから誰かをアルシャフネリーへ向かわせましょう。」
アルシャフネリー…花の町と呼ばれる場所だ。
スイジーとエインが行ったフィスプとは反対側の方向にあり、ビアンカからはそこそこの距離がある。とはいっても遠い訳ではない。
「…つまり、アルシャフネリーにいるということマグね。」
「ええ。まだいるはずです。」
そしたら、誰を向かわせようか。
暇そうなのは…。
「エインを向かわせるマグ。」
「承知。」
即決だった。
数分後にはもう、エインは列車に揺られていた…。
あらすじ!よくわからないけどベレーとかいう人に会いに行くことになったよ。
「なんか解せない…。」
確かに暇だったし嫌でもないしなんの問題もないのだが…。
どこか解せないところがある。
「きゃほう!」
「…。」
…常に暇な人というイメージを持たれるのは、ちょっといただけないお話であり…、…。
「…あの、大丈夫ですか?」
さすがに隣で盛大にすっ転んだ人に手を差し伸べないわけにはいかなかった。
「あ、ご、ごめんなさいねぇ…どうもどうも…。」
手を握った時、事件は起きた。そう、事件は列車で起きてるんだ!
紺色の着物を着た穏やかそうな少女の手に触れた瞬間、エインの体に異変が起こった。
銀白色の髪はあっという間に黒く染まり、瞳は黄色く変化した。
「…。」
黒く染まった自らの髪を見て驚くエイン。
「…。」
互いに硬直する。
「あの、…あれ?」
目をぱちくりさせる着物の少女。
「…と、とりあえず立ちましょう?」
なんとか場を繕おうとして口に出たのはそんな言葉だった。
地面に膝をついた状態のままにさせるのも申し訳ないだろう。
「え、えっとぉ、ごめんなさい?」
未だに状況が理解できていない着物少女。
「大丈夫ですよ。あの、お名前をお伺いしても?」
エインは何となく予想がついており、どうすれば然り気無くそれを確かめられるかを悩んでいた。
「ああ、わたくしはエスオと申します。お初お目にかかります」
のんびりゆったりと喋る着物少女からは悪意は感じられなかった。
「…あ、名乗り遅れました、あたしはエインです。えっと、あなたは今どこへ向かっていたのですか?」
しまった。今の聞き方は少し怪しいだろうか⋯。
「えっ?…ええと、えっと」
…怪しいのは向こうだった。
「…硫化。」
「あ、そういうこと…ではなくなんのことでしょう!」
(…まともに悪役できない人だわ、絶対。)
「硫黄くらいよ、あたしを真っ黒にできんの。ち、ちょっと油断してたって言うのもあるけど!」
元々硫黄だとわかっていれば硫化を最小限に食い止めることはできた。そう、できたの!!(エイン談)
まさかこんなところで硫黄と出会うとは、夢にも思ってもいなかった。
連れ帰ればそれは充分な成果だ。
「………。」
件の彼女は、動揺しすぎて目が波に逆らい大海を泳いでいる。
『間もなく、アルシャフネリーに到着します。お忘れものをなさいませんよう、ご注意ください。』
アナウンスがかかり、エスオはハッとして席を立ち上がる。
「つつつ次の駅で降りますのでぇ!」
「…奇遇ね、あたしもよ。」
「…。」
エスオは完全に諦めた表情をしていた。
列車が止まり、二人はアルシャフネリーに降り立つ。
高台にある駅からは、花畑が見える。噂で聞いたことがあるのだが、アルシャフネリーにしか咲かない花があるようで、それらは季節ごとに変わった花を咲かせるらしい。
無言のまま二人で駅を出ると、ようやくエインが口を開く。
「…じっくりお話を。」
「そ、それはぁ…ちょっとぉ!!」
びゅばんっ!と高速で逃げ出すエスオ。着物なのによく走れるなーと思ったが、よく見たら飛んでい…あれ、わずかに腐乱臭が…。
なるほどなるほど、気体になれば空も飛べるはず⋯。
「じゃねーわ待ちなさいっ!あとこれ戻せ!」
エインも後を追いかける。
すれ違うアルシャフネリーの人々は、不思議そうにその光景を眺めていた。
風が届ける彼女の便り
どれくらい追いかけっこをしたことか、街から少し離れた平地にたどり着いた。
「はあ…はあ…もうそろそろ大人しく捕まりなさいよ…。」
「うう…いざとなれば力業よお!」
エスオがそう叫び、両手を横に広げると、青い火の玉がぼんやり現れる。もし夜のお墓にいるとすれば、相当不気味だろう。
「そっちがその気ならやってやるわ!」
手の中に黒い塊を数個生み出し、弾のごとく撃ち出す。
青い火の玉はくねくねと動き、避けにくい。
「あたしには当たらないけどね!」
ひょいひょいとかわし、攻撃も緩めない。
「ううーっ、戦闘なんてしないのよおー。」
なんてことは言っているが、すいーすいーと避け、簡単には負けてくれなさそうだ。おや、何やら腐乱臭が…どこにそんな量の水素を持ち歩いているのだろうか。
「本当、思うように戦えないだなんて不便だわ…。」
「煽ってるの!?煽ってるのぉ!?」
次第にエスオは防御に徹していく。一方的な攻撃となっていき、勝負はついたようなものであった。が、エスオは粘り強い。
「だいたいあんた…何が目的であの電車に乗り込んでたのよ?」
「そ、それはぁ…そのぉ、別にぃ…どこかにお出かけして爆発とかしようとしてたわけじゃ…。」
「おーけー、地獄送りだ。覚悟しろ」
「ええっ、あなた普通に強いじゃないのぉっ!!」
急に黒い塊が増え、動きも素早くなった。エスオは対応しきれず、塊の攻撃を受けて、芝生の上に倒れる。
「ろ、老体は労っておくれぇ…。」
へにょんと力なく身体を起こし、大人しくなる。
エインはどこかへ電話を掛けていた。
「あーもしもし?なんか硫黄さんを見付けたから連れてって欲しいんだけど…。あー、アルシャフネリーの…なんだここ。まあ、うん。駅につれてく。うん。よろしくー。」
電話を切り、ポケットにしまうと、エスオの前に立つ。
「とりあえずこれ、なおしてくれる?」
「これ…?ああ、わかったよぉ…。」
エスオが手を伸ばすと、エインの姿が元に戻っていく。
「あー、これよ。しっくりくる感じ!」
くるんと一回転したあと、再びエスオに向き直る。
少し身を屈め、手を差し出す。
「んじゃほら。連行よ、連行。」
「うっ…致し方ないかぁ…。」
今度は硫化することなく、手を引っ張りあげる。
「あんた、悪いことしなさそうなんだけどね。典型的ないい人っていうか…。」
「そう?私もちょっと…魔が差しちゃったのかも、ねぇ」
エスオの瞳の光が一瞬陰ったのをエインは見逃さなかった。
「…そ。まあ、実害がないから何とかなるわよ」
しかし敢えて触れることはせず、軽く流した。聞く必要などないし、わざわざ話させる必要もない。
そういう理由を、誰が聞くわけでもないのに、心のなかでつけた。
(硫黄だからと鼻をつままれ続け早数十年…挙句の果てには石を投げられ、ぐすん)
そんなことを考えていたのだが、エインは知る由もない。
花畑が見下ろせる丘の上に、二人の少女の姿があった。
「んー、やっぱりこの手で絵を…世界を生み出していると考えると、感慨深いものがあるね…。」
キャンバスの中の花に色をつけ、綺麗に咲かせるのは、ベレー帽に、トレーナーとズボンというシンプルな服装の少女。
「かんがいぶかい?」
横で見ていた幼いもこもこ少女が、首をかしげながら繰り返した。
もこもことしたワンピースは、まるで羊のようだった。
「そうね…。土に水が染み込むように、心に深く、しみじみーっと、何か、素敵なものを感じるんだよ。⋯多分。」
「にゅー…。」
あまり理解できていなさそうな様子を見て、正直私もよくわからないのよねー、と筆を動かしながら笑う。
モデルというモデルはない。ただ、風景を見て、思ったままに、自分なりに表現するだけだった。
そこに根付く生命の活力や意志。感じた通りにそれを描いた。
特に目的はない。描きたいと思うから描くだけである。
好きなように行動する。やりたいことをやる。旅空の住人として生きることを決意した所以である。
「…まあ、いつまで続くかわからないけどね。」
キャンバスを眺めながら、ぽつりと零れた言葉だった。
エメラルド色の旅情
エスオは、かけつけたユキエに連行されていった。敬礼…じゃなくて。
ようやく本来の仕事を始められる。
彼女がまだアルシャフネリーにいることを願うばかりだ。
「…とはいえ。」
名前しかわからない。どう探せというのか。
今思ってみれば中々に鬼畜な仕事じゃないか?
いや、しかし旅人ということは聞き込みをすれば絞れるかもしれない。また、絵を描いているという情報も役に立つだろう。ベレー帽というのも…もしかしたら。
やることは決まった。まずは誰かを見つけなければ。
「…あ、あのー、そこの方!」
歩いている女性に声をかける。買い物帰りなのか、手にはビニール袋を下げていた。ネギがひょっこりはみ出している。
「あらぁ、どうしたの?」
「え、えっと、最近ここに旅人が来ませんでした?絵を描いている…。あと、ベレー帽をかぶっているかも。」
そうねえ…と記憶を探っている様子のお姉さん。
やがて思い付いたように目を開き、
「ああ、いたわ。小さな女の子を連れてたわねえ…。綺麗なエメラルド色の目をしていたから、よく覚えてるわ。」
「本当ですか!あの、もしよろしければ…どこにいるかお教えいただいても?」
「んー…、どこかで絵を描いていると思うんだけど…どこかしらねえ?」
「うーん…では、この辺りで街が見通せたり…風景が美しい場所を教えてください。」
「それなら…西の方にある高台と、山の方にある展望台ね。どちらから見下ろす花畑も、とっても素敵なのよ。」
「なるほど…ありがとうございます。」
「良いのよ、せっかくだし、人探しのついでに楽しんでいってね。」
優しそうに微笑み、去っていく。
時計と太陽を見て西を見つけ、そちらを見てみると、確かに高台らしきものがあった。
展望台は…恐らく、山肌に見える白い建物だろう。
さて、どちらに向かうか。
「…高台の方が絵を描くにはいいわね。」
恐らく展望台で画材を広げるということはあまりないだろう。
そこそこ広ければ話は別かもしれないが。
正確な道はわからないが、とりあえず方向さえあってればつくはずだ。
洋服についているレースのような装飾がされたレンガの建物に挟まれた道を歩いていく。
そして、目の前にはコンクリートの階段。恐らくここが高台だろう。
少し緊張しながら、上がっていく。街並みが下へ下へと下がっていくように、景色が変わっていく。
そして頂上には、人がいた。
一人の、幼い少女だった。
「…ただの人間…という感じはしないわね。」
幼い少女は、遠くをぼんやり眺めていた。
今の季節には不釣り合いな真冬に着るようなもこもこ生地のワンピースを着ているが、ノースリーブである。季節なんて気にしないということか。
「…そこの子、ちょっと良いかな。」
勇気を出して話しかける。敵意があるかどうかはまだわからない。
「…にゅ?」
水色の髪を揺らして振り返り、少女の目がこちらを見つめる。朱色だった。
つまり、目的としているベレーではないということだ。
…しかし、先程の女性は小さな女の子を連れていると言っていた。それがこの子である可能性は十分にある。
「あなた…ベレーって知ってる?」
「にゅ…ベレーがどうかしたにゅ?」
「えっとー、探してるんだけどね…。」
幼い少女は黙りこむ。
エインが目線を合わせるためにしゃがもうとしたときだった。
「お姉ちゃん。」
少女は俯きながら、
「どこの機関の人?」
なにかを察知したエインは素早く身を後ろにひく。
ほぼ同時に、少女の周りに赤い火花が散る。
バチバチと音をたてて散るそれは、恐らく…
「電撃ね…やっぱり普通の女の子じゃない。」
少女は赤い電気をまとい、飛び掛かってくる。
間一髪でかわすと、星形の銀の塊を生み出し、ひょいひょいと投げる。
少女はそれをかわしたが、それらが地面にぶつかると、拡散し、小さな粒となって少女を追いかける。
「うにゅ!」
火花を散らして払いのける。見た目に反して、一筋縄ではいかなそうだ。
「あなた…人間じゃないわよね。」
どこの機関の人。たしかに彼女はそう訊ねた。だとするとやはり…。
「……。」
少女は答えない。代わりに、火花が飛んでくる。
「っ、これ…熱い!」
火花は高い熱を持っていた。もちろん、通常よりも高い温度だ。
(赤い火花…赤い火花…一体『誰』?)
頭のなかに浮かべたのは…周期表。
しかし。
(候補ぉ…ありすぎんよぉ…。)
そういえばまだあんまり集まっていないのだった。
そのように考えていたのが原因で、火花の線が一本、直撃した。
「っ…!」
普通の電気ならばなんともない。しかし、確かにダメージがある。
「もう…大人げないとか気にしなくてもいいわよね?」
エインはにやりと笑うと、先程までは比較的穏やかだった攻撃が激しくなっていく。
「にゅ…っ!」
銀の粒を避けきれなくなっているが、攻撃は最大の防御と言わんばかりに雷撃も激しくなる。
「熱くて赤い電流、もしかして…っと!」
不規則な軌道が予測をさせず、エインにも確実にダメージを与えていく。
もうそろそろ日が沈もうとし始める時間だった。
静かな高台に、電撃の音と銀塊が拡散するときの、明らかに自然界に存在しない音が響いていた。
「あーもう、やるしかない!」
エインが叫び、大きく後ろへ飛ぶ。
その時、
「リチェ!下がりなさい!」
その声は、階段の方から聞こえてきた。ベレー帽を被った少女が、こちらに歩いてくる。
「私が代わりにお相手しましょう。」
幼い少女の前に立ち塞がった彼女の手には、筆が握られていた。その瞳の色は、美しいエメラルド。
「あんたがベレーね。」
「いかにも。私を探すなんて物好きだね。もっと面白い元素があるんじゃない?」
「あんたも…。」
「ほら、やっぱり探すなら他の元素でしょ?旅のなかでも話はよく聞くよ。やっぱり水素とかそこらへんよ。金とか銀もよく聞くね。案外銀の方が需要あるかもーとかね。」
「マジで?」
「まあ、とりあえず相手はしよう。」
「…ベレー。」
「大丈夫、離れてなさい。」
リチェは渋々その場を離れる。
エインもその背を追ってまで倒すほど大人げなくはない。
明らかに普通のものではない筆を構え、じっとエインを見据える。
「じゃあ始めようか。」
そう言うと少女は空中をなぞるように筆を動かす。
するとそこにはしっかりと絵が描かれ、実体化してエインに襲いかかる。
「うおっと!」
避けると、絵は地面に吸い込まれるように消えていく。再び襲いかかってくることは無さそうだが、すぐに新たな絵が描かれる。
「面白い力ね。」
「汎用性には富んでいるんじゃないかな。」
銀塊をかわしながら返す姿には、余裕がある。
「でも、あたしだってちゃーんと戦えるのよ?」
得意気に言うと、マイクを生み出し手に握る。
「それじゃあお客さん約二名!あたしの歌を聴きやがれ!」
元気よく叫ぶと、一体どういう原理なのか曲が流れ出した。
「………。」
唖然とするベレー。
しかしすぐに気を取り直すと、警戒する。
『眩しく光り輝くあなたの
瞳はいつでも優しくて』
魔法により奏でられる音に合わせ、カラフルな星がベレーめがけて飛び出していく。
「これは…っ!?」
『桜舞い散る この季節に
心奪われた』
ベレーが放った絵さえも、触れた瞬間に弾け散るように打ち消される。明らかに銀ではなかった。
『何気ない日々 雑踏のなかで
私は見つけた
大切なもの 守りたいもの
あなたの笑顔が好き』
「いやいや、こんなのってアリな訳?」
ベレーは焦ったように呟く。リチェはそれを心配そうに見つめている。
「ベレー…!」
小さな声は震えていた。
『何一つ変わらない世界で
巡り会えた奇跡 信じたい
教えてくれた煌めきを
私も輝き始めた』
『近くて遠いよ もどかしい距離
触れあう指の先から
桜舞い散る この季節に
勇気振り絞った』
「こりゃあ…勝てませんな…。」
攻撃は全て弾かれ、星を避けるのにも限界を感じる。
魔法だけで描いた絵では太刀打ちできない。せめて実体があるものならば…といったところか。
「なるほどね。私の弱点ってことだね。」
気づきもしなかった。というより、魔法を封じられたことがなかったのだ。
『銀色に光る 輝く想い
伝えたい静かな想い
桜舞い散る この季節に
心揺らしてる…』
そんなベレーの様子を見て、エインは歌をやめる。
「どう?二番まで聴いてく?」
「いやいや、降参。それにこんな力、人間業じゃない。」
「まあ、人間じゃないもの。」
なぜかどや顔で言う。
リチェがぱたぱたと駆け寄ってくと、不安そうにベレーの後ろに隠れる。
「…私もね、最初は、探してた。他の元素を。でも、旅を続けたかったんだ。」
「Elementsに来たら旅ができなくなりそう。そう思った?」
「そう。危ないからって止められてね。」
苦笑いをしながら、天を仰ぐ。
「楽しかったなー、旅は。でももうおしまいか。」
「そんなわけないでしょ、考えすぎよ。」
エインはふふんと笑う。なぜ彼女が得意気なのかはわからない。
「確かにうちのギルドの…ラスボスはおっそろしいけど。そんな鬼じゃないわよ。案外自由にやってるわよ、私たち。」
たまに脅されるけど。思い付いたように付け足す。
「…じゃあ、旅…しても良いにゅ?」
「もっちろん!…と思う。ほぼ確実にね。」
リチェの目がキラキラと輝く。敵意は完全になくなったようだ。
「とりあえず、あたしはエイン。きらんきらんの銀よ!」
「あ、銀…ああ。えっと、私はベリリウム。こっちがリチウムのリチェさ。」
「なるほどやっぱりそうか。…じゃあ、とりあえずギルドに来てもらうけど良いかしら?」
「まあ、そうするしかなさそうだしね…。」
「…ベレーはいっつも諦めが早いにゅ。」
「あはは、それ何十回目だってば。」
(何…十?)
こうしてエインは任務を見事に遂行した。
今回であった元素たちが友好的だったのが幸いしたのだろう…。
鉄道に乗って
「か、海底の洞窟?」
「そうでございます。小規模ながら久しぶりの遠征でございますわ。」
ギルドの会議部屋に集められた元素たちは、フェルニーの説明を受けていた。
「なんかオカルティックね!」
目を輝かせて言うのはスィエル。
「全く、遊びじゃないのよ?」
なだめるように言うのはオウカ。
「でもロマンを感じるしー!」
笑いながら言うのはシータス。
「ほ、本当に私がここにいてよいのでしょうか。」
言葉とは裏腹にやる気に満ちた顔をしているのはホウコ。
「…子守り?」
光を失った目をフェルニーに向けているのはチエ。いや、元々無かっげほんごほん。
「さて、詳細を説明させていただきます。」
そう言うとフェルニーは壁掛けパネルにエルスメノス西部の地図を浮かべる。中心はビアンカで、フィスプやアルシャフネリーなども見えている。
「皆様に向かっていただくのはエルスメノス王国南部に位置する珊瑚海でございます。珊瑚礁がとても美しい海ですね。」
パネルを操作すると、地図がそれにしたがって写す範囲を変える。
「近くの村、アンダンサの方々も協力してくれるようです。なにしろ王国直々のお願いでございますからね。」
指で場所を示しながら言う。
今回の目的というのは、ビアンカからみればずっと南西に位置する、珊瑚海にて発見された海底洞窟の調査だ。場所の問題もあり、人間が調査するのはあまりにも大変であるため、ここへ依頼が来たのだ。
「はあー、ドキドキする。」
スィエルは不思議なことが大好きなのだ。自分自身も不思議の塊ではあるのだが。
「突然奇行に走り出すのは止めてね、ただのホラーだから。」
「さ、さすがにそんなことはしないよ!?」
無自覚というのは、時に底知れぬ恐怖を生み出す。
まあ、自覚しているのもそれはそれで怖いこともあるだろうが。
「良識的な行動を心掛けてくださいね。」
「こいつらにはそんなもの無い。」
真顔でチエは断言する。経験者は語る。
「大体、このメンバーなのは何故だ?」
フェルニーは笑顔を崩さず、
「気分で非金属から。正直錆びなきゃ誰でもいいのでございます。」
ああ、惜しい。もう少しで常識元素になれただろうに。いったい何が彼女を3度ぐらい曲げてしまったのだろうか。
「おいひいでひゅ。」
「わかったまず飲み込め。」
ホウコがフェルニーからもらったパンを頬張る。
前にも言ったように必要ではないのだが、美味しいものを食べても嬉しくならないのは通常の精神状態ではあり得ない。って偉い人が言ってた。
「さすがに反対側の海となると遠いわね…。」
この列車の団体席は四人掛けで、五人で座っているのだが、もともとゆとりをもって作られているのか綺麗におさまった。
「植民地は返したっていうのに、充分広いよね。でもなんでそんなにたくさん奪う必要があったのやら。」
「多ければ多いほど力を誇示できたんだろう。攻める気をなくさせるほどの力を。」
「でも実際、管理行き届かなさそうだしー。」
「しっかり管理する必要はない。そこが領土であることが重要なんだ、恐らくな。どんな暮らしを送れるかなんて気にしない、人をそこに住まわせて、守らせる。昔は繁殖の殖の字で、殖民地としていたらしいじゃないか。」
「…人を繁殖させる土地でもあったのかあ。なんか、家畜みたい。」
「ま、当時の人々の思考なんてわからないけどね。その場にいたわけでもないのだから。」
そんな何でもないような話をしながら、時間を潰す。
やがて、ずっと森や山に埋め尽くされていた景色に変化が訪れる。
遠くに、四角柱や円柱のものが見えた。
「あれがミデレーリア?」
それらは高層ビル。見えているのは大都会ミデレーリア。最先端の科学や技術が取り入れられ、近未来的に発展した大きな町だ。
「随分と違うのね、ビアンカやフィスプ、アルシャフネリーとは。」
「北部の方は…なんか、街並みの美しさに重きをおいているというか…昔ながらのものを慈しむ懐古主義の傾向が強い?」
「文化の違いってやつだしー?同じ国なのに随分と変わるしー」
「エルスメノス王国というくくりなんてあってないようなものよ。法とかが同じだけで。」
「もともと、南のルージャ。北のダーキル。西のアクシア。東のゴーデ。中央のフォレントの五か国からなる連合国家…というかダーキルが従属させたみたいな感じだし…。」
「じゃあエルスメノスの王家はダーキル出身ってことね。」
「そうそう。よく四桁も続いているよな。」
「すごいよねー、なんか誇れる。」
ミデレーリアも通りすぎ、ようやく南部エリアに差し掛かったことだろう。
「なんで急に見付かったんだろうね。」
唐突にスィエルが切り出す。初めて目的についての会話がされた瞬間である。
「何が?」
「海底洞窟だよ。結構深いところにあるのかなー…。」
「今まで見付からなかったのだから…技術の進歩によりやっと存在が明らかになったのかしら。」
「なるほど。それは確かに人間じゃ調査できなさそうだな。」
「でも王国直々にお願いなんて、しますかね?」
「そりゃあ…なにかわからないとなると危険度がわからないからじゃないか?その存在が平穏を脅かす存在になりえるかどうかを知っておけば対策も可能になるから。」
「考えすぎじゃない?ただ単に新しい発見があるかもしれないからーとかじゃないかな?資源とかも含めて。」
「どっちもかもしれないしー?」
(あの)スィエルに盲点をつかれてちょっぴりショックを受けていたチエを、シータスがそれとなくフォローする。
「どうにせよ仕事は仕事。全うするのが私たちの役目よ。」
「そうですね、受け入れましょう…。これは…Elementsに訪れる前から決心していたことです。例え恐ろしい陰謀にこの身を滅ぼすとしても…今さら後戻りなんて出来ません。」
「やめてそんな大袈裟に言わないでただの仕事だそんな悪意渦巻いていないぞ。」
暗いトンネルのなかに入り、目的地はどんどん近づいていく。
臨海集落アンダンサ
「や、やっと着いたね…。」
「日が暮れそうなんだけど。」
五人がアンダンサに着く頃には、空は薄い橙色と淡い水色が混ざっていた。
そしてそこから更に、少し歩いて宿に着くと、ぼんやりとした境界線はもうすっかり低くなっていた。
「なるほどなるほど。なんでお昼に送り出されたのかと思えば、周辺調査をしたくなるような時間になっています。」
「そ…そうなんだ。」
「やっぱり伝承とか聞きたいよね?意外とヒントになるかもよ?」
スィエルはやっぱり欲望に忠実で、オウカが呆れたように息を吐くと、チエに目配せする。
(…任せた。)
言葉が要らないほど慣れたやり取り。
「あ、私はちょっと気になることがあるから単独行動を求めるしー。」
「…まあ、シータスなら大丈夫だろう。」
「じゃあ私はチエさんと…ですか?」
「ああ、そうしよう。」
そうして三組に分かれ、集合時間を決めて解散した。
チエは、とりあえずホウコに任せることにし、ふらふらと歩き回っていた。
「…ホウコ、なにか宛があるようには思えないが…。」
「これは気になる…。」
「は?」
「誰か住人の方にお話をうかがいたいですね。」
「…何かわかったのか?」
「はい。経験則みたいなアレです…。」
目を伏せて、明らかに何か事情がありそうに振る舞うホウコ。
「その、まあ、勘なんですけど。」
全く誤魔化せてない。しかしまあ、触れないでおこう。
こちらも経験則から、実はそこまで重い事情はないと見た。
「どこかの本来の能力より能力じみた直感使いさんのように確実性はないのですが…。」
「はっくしょん。」
「テンプレートのくしゃみマグね。」
「誰かに噂されてる。直感。」
件の直感使いフララは、ギルドにてマグナの手伝いをしていた。
近くで資料やらを一緒に眺めて、元素探求計画を練るというものだ。
「それにしても海底洞窟ねえ…。こりゃあもしかすると…とんでもない子が潜んでるかもね。」
「君のは嘘だと思えないから怖いマグ。」
「あれだよ、知識に基づいた勘さ。」
「信憑性増したマグ。」
「増しすぎて?」
「寧ろ疑わしいマグ?」
「実際、正反対のことを言ったこともある。」
「ええー…マグ。」
直感さんは気まぐれなのである。
「すいませーん!そこの方!」
ホウコは近くにいた住人のもとに駆け寄る。
「お、君らが調査に来ている人かい?こりゃあまあ可愛らしいお嬢さん方だ。」
気さくな住人は、ホウコたちの詳しい素性を知らないようだった。
「ふふ、お言葉が上手ですね。ところでお聞きしたいことがあるのですが…。」
「おうよ、答えられる範囲でならいくらでも質問してくれ。」
「はい。ええと、最近地震はありましたか?」
住人は一瞬きょとんとした顔をしたが、すぐに答えてくれた。
「あったっちゃあったな、何回か。だけどどれも小さいやつだぞ?…でも、震源がこっちに向かってきてるらしいから不安だな。」
「そうですか…ありがとうございました。」
「これくらいなんてことないさ。それじゃあ、頑張ってくれよなー。」
がははと笑いながら、住人は歩き去っていった。
何故、地震があったと思ったのか。そのような情報はいっさいなかった。ホウコだけ知らされていたということはないだろう。
まさか、地震の痕跡がわかるのだろうか?
「チエさん、用事終わりました!戻りますか?」
「はいは…それだけ!?まだ7時には早いぞ!?何か探そう?なにをって訳じゃないけどお散歩でもいいしさ?」
「お散歩…!お散歩しましょう!」
「そうしましょう?もう少し調査しよう?」
自由奔放なホウコに引っ張られていくチエ。
今日も気苦労が絶えませんでしたとさ。
一方、スィエルとその保護者オウカは、宿の主人のもとを訪ねていた。
「はえ、ここに伝わる昔話?」
主人はのっそりと顔をこちらに向ける。
「はい、是非とも教えていただきたいですまふ!!」
「ほら、人と話すときは深呼吸。ひっひっふー。」
「多分それ違うひっひっふー。」
「…んあ、あるにはあるんじゃが、ちっとばかし長くなるでのぉ…本当にちーっと長いだけじゃが…。」
「構いません!」
「ふむ、それじゃあそこの椅子にお座りなさい、立ちながらじゃあ足が棒になってしまう…というのは言いすぎじゃな。茶でも淹れてやろう。」
「わーい!ありがとうございます!」
立派な白い髭を撫でながら、主人はほっほっほ、と孫を見るように笑った。
調査⋯?
それは六百年ほど前のこと。紙と筆はすでにあった時代の話じゃ、信用性は十分じゃろう。
この世界特有の神様はいない。皆、別の世界から来たものだとされておる。…というのは知っておるな。神様はこの世界で羽を休めるのだという。
そして、このアンダンサに降臨なさった小さな女神様がおったそうじゃ。
浜辺に降り立たれた女神様は、悲しみに暮れていた。話を聞けば、たくさんいた子供を全員殺されてしまわれたらしい。
放っておくことなどできず、村人は女神様を丁重にもてなした。
料理や舞踊、そして談笑。アンダンサに神様が降臨したのはその時が初めてだったんじゃと。きっと手探りであたふたしながらだったんじゃろうなぁ…。
して女神様じゃが、親切で親しみやすかったのじゃろう。人間に対し非常に友好的だったそうじゃ。
美しい自然を見て、女神様はだんだん落ち着きを取り戻してきなさった。そして、恩義を感じなさり、報いたいと考えられたという。
女神様は村に恩恵を与えてくださった。
周辺の賊などの侵攻のみならず、災害を遠ざけてくださったそうじゃ。なんとも有り難いことじゃ。
今日までこの村が在り続いているのも、女神様のお陰じゃな。
そしてある日、もう一人、女神様が降臨なさった。
大変強力な女神様であったそうで、村人は警戒した。
しかし、その女神様は娘を探しに来たのだとおっしゃる。
その娘こそ、小さな女神様よ。二人はしばらくアンダンサに滞在なさった。
これは正しいかどうかわからないが、母親の女神様はアンダンサに繁栄の加護を授けなさったそうじゃ。その時から村が賑わい続けているという。
そしてある日、二人は海に出たまま帰りなさらなかった。
恐らく静かに元の世界へお帰りになったとされておる。
しかし今も村が繁栄しているということは、まだきっとわしらを見守っておられるのじゃな。
ここら辺では、教訓話として取り上げられているぞ。
あれじゃ、情けは人の為ならずのスケール大きい版じゃ。
しかし人の手により書かれた記憶じゃて、どこまでが真実かはわからない。
話を終えると、宿主はこほんと咳払いをし、
「…ということじゃ、有名な部分だけじゃが。図書館なんかにはもっと詳しい資料があるじゃろう、気になるなら見てみなされ。」
「いっやー素晴らしいです、たぎります。」
「…今回の件と関係あるとは思えないけどね。」
「うぐ。」
「ふぉふぉ、知識は多いに越したことはありませんぞ。」
「⋯それもそうですね。」
宿主にお礼を言い、二人は図書館へ行くことにした。
今回のことについても何かわかるかもしれないし、知識はいっぱいあっても損ではないだろう。
人が寄り付かないような木々の隙間をすり抜け、シータスは走っていた。
(多分、こっちの方に…。)
感覚だけを便りに、目的の場所を目指す。
「…あった。」
草も映えていない場所があった。
(なんでこんなところに…。)
炭素を操ってスコップにし、土を掘り返してみると、そこにあったのは宝石。
しかも、大量にある。
天然…ではないだろう、形が整えられている。
「…まさか、誰かのへそくりじゃないだろうしー。」
しかし、誰のものかわからない。
こんなにたくさんの…ダイヤモンドを奪ってしまうという結果になるのは避けたい。
まあ、特に問題がなければ放置でもいいだろう。
(…いやでも、こんな不自然にダイヤモンドがあること自体問題かもしれないしー。)
やっぱり、誰かをつれてくればよかった。
三人よれば文殊の知恵。まさしくその通りである。
スィエルがいたりすれば、魔術的なこともわかる。オウカは知識が豊富である。チエは洞察力が鋭い。ホウコは様々な視点から物事を見れる。三人で文殊の知恵ならば、五人ではもっと良い。船頭多くして云々は知らない。
(とはいっても、なにか起こってるわけでもないしー、今回の件とも関係があるかどうかは…うーん。)
そして、悩んだ末に出した結論は、
「…困ったときの保留だしー。」
ダイヤモンドが無くならない限り、この場所はわかる。ならばまた今度来ればよいだろう。
シータスは、月の方角だけを頼りに、戻っていった。
「…。」
ローブの少女は、木の裏でその様子を眺めながら、ほっと一息ついた。
誰の誘導?
アンダンサは、エルスメノス王国の南沿いに位置し、珊瑚海に面する小さな村である。
しかし、村は大変活気に溢れている。
隠れた旅行スポットとして、一部では非常に高い人気を得ている。
この繁栄は、女神の加護によるものとされている。六百年ほど前に女神二柱が降臨したという。
珊瑚海独特の魚介類もあり、近くの街でも有名である。
最近になって海底洞窟が発見されたが、私はオカルティックな何かを感じてならない。
だって、海の底にいきなり現れたとしか思えない!
魔術師の端くれの端くれの端くれとして、放っておけないわ!
「ねえスィエル素が出てる。」
「はっ…つい興奮して…。」
「というか何のためのレポートよ。」
「気分です。」
図書館から帰ると、既に七時前になっていた。
ちょうど良い時間である。
「まあでも、めぼしい情報は見つけられなかったわね。」
「……案外そうでもなかったりしてね?」
「………いや確かに神様の主張激しいし何らかの関係性がある気がするけど確証がないでしょ?ミスリードだったらどうするのよ。」
一体誰にリードされているというのか…。
二人が言い合っていると、
「ただいま。」
「ただいま帰りましたー。」
チエとホウコが戻ってきた。
「おかえり。…一応聞くけど収穫は?」
「小さなことならな…。」
チエはそう言うと、ホウコの方を見る。
ホウコは、私!?と驚いている様子だったが、やがて、モジモジしながら口を開いた。
「最近、地震があったらしいんです。小さなものですが、段々震源がこちらに近づいているとのことで、住民の方が心配なさってました。」
「地震…なるほど、シータスが戻ったら詳しく教えてくれるかしら?」
ほんの少し遅れて、シータスは帰ってきた。
オウカがテーブルを囲んで座るように指示をし、五人は着席する。
「まあ、今日はとりあえず平和でしたと。それぞれ、収穫らしきものでも何でも話しましょう。…ホウコ、地震について、お願い。」
「はいっ!ええと、住民の方によると、最初の地震は二週間前。そこそこ大きかったそうですが、津波などの被害は出ていません。」
「神の御加護かな?」
「ああ、お散歩してる時に出会った若い女性にも聞いたが、そんなことを言ってる人がいたような…。」
「な、なんだってー!」
スィエルの目が輝きを放つ。これは真実味が増してきた、とでも思っているのだろう。
冗談で言ったのか、本気で言ったのかはわからないというのに。
「えっと、それで、その後も五、六回地震があったようですが、不思議なことに、大きさは小さくなっていて、しかし調査によると震源は村へ近づいているとのことで。」
「震源が近づいているのに小さく…?まあ、大きくなるよりはいいけども…。」
「んー…まあ、そりゃそうだけど、もっと悪いことの予兆かもよ?」
「一つの可能性としては有り得るな。」
この先悪いことが起こると用心するのも大事だが、いつ来るかわからないものにただただ怯えても仕方ない。
「…やっぱり洞窟がクサイですな。」
心底楽しそうにスィエルが言う。イマイチ緊張感が感じられないが、オウカは、そういえば今までスィエルに緊張感があった試しがないようなという気がしていた。
「で、シータスはどう?」
「んー、関係あるかは分からないけど、地面に埋められたダイヤモンドを見つけたしー。」
「埋められた…?」
「地表近くに、固まって埋められてたんだしー。」
見つけた経緯を詳しく話す。
「なるほど。それは気になるな…。」
「人為的に埋められたたくさんのダイヤモンド…何だろう?」
「洞窟に関係があるかはわからないけど、覚えておきましょう。」
「そうですね。…ええとそれで、お二人は?」
「ああ…。」
二人は村長から聞いた話を要約して話した。
「なんか怪しすぎて逆に騙しに来てるんじゃないかって思うんだけど…。」
おっとチエちゃん、一体誰に騙されるというのだろう。
そんなことしたら海王様に怒られるんじゃ⋯
山の隙間から、太陽が顔を覗かせる頃。
船着場には五つの影があった。
「調査するぞー!」
「朝早くから元気ね…。」
元素五人組は、まさに今海底洞窟の調査に出かけようとしている。
「お嬢ちゃんたち、準備はOKだぜ!」
小型船に乗った男が手を振る。
五人は船に乗る。途中までは船で行き、潜る時には…ある方法を使う予定だ。
「それじゃあ出発すんぜ!」
エンジンが動き出し、飛沫をあげながら船は進んでいく…。
「最近ここら辺は人が多いなー。」
海のど真ん中に、ぶかぷか浮かんでいる少女がいた。
彼女が身につけているものと言えば、小さなクラウンとビキニ、そして浮き輪だけである。
浮き輪の上に仰向けになって身を預け、空を仰いでいる。
青緑のツーサイドアップの髪はふんわりと広がり、濡れた白い肌は朝日に照らされ輝いているように見える。
「何か事件でもあったのかー…?」
大して興味もなさそうに呟く。
実際、どうでもいいのだ。自分が被害を被らなければ。
「…。」
しかし、今回ばかりは事情が違いそうだ。
少女の視線は、海原を駆ける一隻の船へと釘付けになっていた。
「…あの船。」
指を鳴らすと、浮き輪は貝のボートに姿を変えた。
少女はその上にまたがり、目標を目指す。
「今日はよく晴れてますねえ…。」
ホウコは空を見上げながら、のんびりと言う。
「こういう時こそ、何かしら起こるかもしれないしー。」
「縁起でもないこと言うんじゃありません!めっ!」
スィエルの切れのいいチョップがシータスに命中する。
「ほらほら、あんまりはっちゃけ過ぎないの。落ちちゃっても知らないわよ。」
良かった、オウカはまだまともだった。チエはほっと一息つく。
「もし落ちて、サメに会ったら殴る。シャチに会ったら殴る。とりあえず殴るのよ。」
…まだまともだ。きっと他と比べると。
「で、結局どこまで行くわけ?」
「んー、船長さん、あとどれ位かわかります?」
「そうだな…もう少しだ。」
船で途中までは行く…というのも、しっかりとした理由が存在する。
単純に、海底洞窟が見つかったあたりは、何故か、風が強く波も荒いからだ。その理由も調査中らしい。何故かっていう魔法の言葉。
チエは、ずっと手に持っていたあるものを耳に取り付ける。
ケイ素のケイが作ってくれた、通信機である。
スイッチを入れると、ある場所に繋がる。
「誘導は頼むぞ。」
『了解致しました。』
小型通信機から聞こえるのは、フェルニーの声。
「そろそろだな…ここら辺で船を止めるぜ。」
船があげる飛沫はどんどん小さくなる。
やがて船は完全に停止する。波は穏やかだ。
「フェルニー、よろしく。」
『そこから…南西、ちょうど七時の方向でございます。距離は1,4kmほど。』
「OK、任せて!」
スィエルは元気よく立ち上がる。目が輝いており、とても活き活きしている。
「…本当にやるのか。」
チエは引き気味にたずねる。
「え?そうだよ?」
けろりとした顔で振り向くスィエル。
「じゃあ、行きまーす。ぱっかーん!!」
その擬音通りに、海が割れた。
割れたのだ。
モーセ(物理?)である。
怒ってないね楽しそうだね
これまでのおはなし!もーせ!
「…………。」
「おう、派手にやるねえお嬢ちゃん!」
「派手とか言ってる場合かなこれ?」
「大漁ね。」
「あの跳ねてる魚持ち帰るつもりなの?」
「のーでん」
「言わせないぞ?」
繰り返すようだが、今日は快晴だ。チエのツッコミも空も澄み渡っている。
「うまくないから。澄み渡ったツッコミってなんだよ。」
青い海にできた道は、目的地までまっすぐ続いているだろう。
「で、俺ぁ本当に帰っちまっていいのか?」
「ええ。帰りはアンダンサまで飛びます。」
「私たち固体は化合して気体になればいいしー。」
「ふふふ…フッ素は持ってきてあるんですよ…。」
元素ちゃんたちは、基本的に気体の状態であれば飛行が可能だ。
まあ、基本的にと言うのだから…つまりそういう事だが。
シータスはオウカの力で二酸化炭素となり、ホウコは持ってきたフッ素を使うのだ。
…何故フッ素を持っているかって?気にするな…というのは冗談で、フェルニーさんが一晩で用意してくれました。
「まあ、俺にはよく分からんからな…じゃあ、頑張れよ!」
爽やかな笑顔で手を振る船長に礼を言い、早速固体二人は気体へと変化する。
エインの硫化とは違い、外見は変わらない。
船から飛び立つと、海の道を進んでいく。
…と、その途中でのことだった。
「ド派手にやってくれたなー君たち!豪快で面白いじゃないかー!」
貝殻ボートに乗った、一人の少女が道を塞いだ。
浮いてる、ボートが浮いてるよ。
「わあ、人間技じゃないしー。」
「妖精さん?魔物さん?元素さん?」
五人は立ちはばかる少女を前にブレーキをかける。
「…と、こういう時はこっちが名乗るんだっけー。」
クラウンビキニの少女はそう呟くと、持っていた矛を突き出し、堂々とした声で、
「私はネプ!海王の名を持つ者!」
と名乗った。
矛を持っているところを見ると…戦意があるのだろう。
「…私たちが何とかする。」
「え、私?」
チエがスィエルの首根っこを捕まえて言い、先に行くよう促す。
「んー、まあ、二人いてくれればいいかなー」
警戒しながら通り抜けた三人に対し、呑気そうな少女は興味を示さなかった。
「一体、何の用だ。」
「君たちに…何かを感じたんだよねー。」
「…はぁ?」
「こうさ、いつも通り海で浮いてたら、ピリピリリとなー。」
いまいち要領を得ない回答だ。
「とりあえずさ、君たちの力を見せてもらえないかなー?」
勝手に話を進めるネプと名乗る少女。
矛を天に掲げると、その先端から陣が展開される。
「魔術!!」
スィエルがいち早く反応する。
「ほー、魔術に精通している者とは。これは珍しいなー。」
「そうなの?」
スィエルが首をかしげてチエに尋ねる。
「え、いや知らない。」
魔術に詳しくない私に聞くか…?と疑問に思うところがあったが、よく考えれば相手はスィエルだった。
深い意味は無い。
「それはおいといてー。ちょっとだけ付き合ってもらうぞー。」
ネプは矛を振り下ろす。すると、周りに水の蛇が召喚された。
それらは二人に向かってくる。
かわしても、執拗に追ってくる。
「あーもう…。」
チエが襲いかかる蛇に手を翳すと、それはピキピキと音を立てて凍りつき、轟音を立てながら砕け散った。
「…所詮水。」
「所詮とか言わないでお水はすっごいのよ!」
スィエルが過剰反応する。
…まあ、今のは確かに悪意があったのだが。
「おーう、これを凍らせるだなんて、相当な温度だな。」
そりゃそうです。窒素だもの。
なんてことを言うはずもなく、こちらも反撃に出る。
「チエ、お願い。」
「はあ、目的語をだなぁ…。」
とはいいつつも、冷たい空気をまとって合図する。
スィエルの操る水を、チエの冷気で凍らせる。そしてそれを投げつける。
あくまで状態変化なので、スィエルの制御はまだ及ぶ。
「ほうほう、水じゃ私を傷つけられないことがよくわかったなー。」
ネプが乗っていた貝殻ボートは、馬に変化し、空中をひょいひょいと駆け回って氷の粒手を避ける。
「海王の魔術だもの、どうせ全部弾かれるわ。」
「ふむ、聡明でよろしい。」
(スィエル…スィエルが、聡明…?)
「なんかすごい貶された気がするんだけど。」
それは気のせいだ。
「とにかく、どうしたらどいてくれるの?」
「んー、もっと確信がないとなぁー…。」
またもや全く要領を得ない返事であった。
「まあさ、とりあえず戦おうよー。ずっと待ってたんだ、戦える人をねー。なんでか、みんなすぐ逃げちゃうんだもんー…。」
その傾げられた首が疑問からなのか、それとも落胆からなのかはわからなかった。
「だから、もうちょっとだけ、ねー?」
「そんなこと言われてもだな…っと。」
ネプは矛を振り回し、周りの水から刃を生み出して投げつけてくる。
「効果的な攻撃はなんだろう…。」
「何かさ、こう…魔術的なやつはない?」
「海王ってすっごいのよ大陸支えてるとも言われてるし。」
「うわ。」
「だから………どうしましょうかっ!」
「そうだな…。…とりあえず、避けるか。」
空から矛の雨が降り注ぐ。
「…逃げないんだね。」
「逃げるって言っても…。」
「あれ…?」
突然、チエは右耳に違和感を感じた。何か、耳元でがさがさと音がした気が…。
『もっ、もしもし…。』
「…あっ。」
連絡機を付けていたのを、すっかり忘れていた。
「どうしたの?」
「さあ?…えーっと、チエだけど…。」
矛やら蛇やらをかわしつつ、返事をする。
『………ぅ。』
すると、絞り出したような声になりきれない声が聞こえた。
「………。」
『ちょっとあなたいい加減通信機器で連絡するくらい出来るようにならないんですか。』
エルシーの声が聞こえた。ああ…特定した…。
「えっと、スイジーか?」
『そ、そう…そう…、そう?』
「落ち着け。どうかしたのか?」
『ええと…フェルニーが、チエに連絡してって言って…、その、オウカから連絡があったらしくて。』
「オウカから…?」
『ちょっととりあえずけたたましい水音に突っ込んでくださいよ。』
『あっ、水音…えと?』
「チエ!ちょっと貸して!」
「え?ああ…。スイジー、スィエルに替わる。」
攻撃を器用にかわしつつなんとか無線機を渡す。
「…いっつもこうやって威嚇するだけで逃げちゃうのに。」
その様子を見ながら、ネプは不思議そうに、しかし目を輝かせて呟いた。
かいおーねぷねぷ
「スイジー、えっと、海王と遭遇した時の対応方法って知ってる?」
空だけでなく、ネプの方からも矛が飛んでくる。
『へ?』
(そりゃあいきなりそんなこと言われてもな。)
『海王…ネプチューン?』
「そうよ。」
(冷静だな…!?)
このときチエは、自分も初めに会った時それなりに冷静だったことに気づいていない。
『世界たちは認識により混ざり合う…。ネプチューンがこの世界にいるのなら、か、彼女だと思う…。…それは惑星の名を貰った者、あるいは同じ名を冠するもの…。』
「惑星の名を貰った…?」
『…一人、いる。海王の惑星の名を貰った…元素。』
「…ネプツニウム!!」
「ネプツニウム!?」
「ネプツニウム。」
「ネプツニウム?」
「ウム。」
「人の名前で遊ばないでよー!」
矛が二割増で飛んでくる。
「危ない危ない危ないってええええ。」
「これも凍らないか…。」
くるりと回ったり下がったりと、器用に避ける。
こちらを正確に狙ったものでもなかったので、かわすのはまだ可能であった。
「もうー…。まあでもご名答ー。」
「んー…でもスイジー、どうしてすぐに分かったの?」
「ほう。そちらのお助け電話の相手は優秀だねえ。この元素たちが暮らす世界で海王といえば、私だけ。すぐに辿り着くとは博識だなー。」
「へえ…。」
「じゃあ…。」
「「捕獲っ!!」」
「え?」
急に目を光らせて襲いかかってくる二人に驚いて呆然とするネプ。
しかし、海王様とだけあって、易々と捕まってはくれない。
『あ、えっと…その、彼女の弱点を教えましょうか?』
「弱点があるの?」
「すごーい、知ってるんだね。」
「えええええなんで知ってるの相手誰だしいいいい!」
海の上は水塊やら氷塊やら煽りやらが飛び交う戦場となった。
「…二人とも、大丈夫かしら。」
洞窟の入口で、三人はスィエルとチエを待っていた。
より正確に言えば、魔術に精通した者がいないため、先に調査を進めておくといったことができないのだ。恐らくそういう類であろう仕掛けが施してあった。
「心配しなくても、平気だと思うしー。」
「そうですね、なんたって…あの二人ですからね。今は信じましょう、彼女たちなら絶対大丈夫!笑顔で帰ってきますから!」
「なんでそう意味深風な発言をしたがるかな…。」
「…!…この冷静なツッコミは!!」
「やめて。なんかやめろ。」
歩いてきたのは、チエ、スィエル。
それと、首根っこを掴まれているさっき会った女の子。
ろうまんあんどぐりーす
「…え、えと!仲良くなったんですね!」
「…解せないぞー。」
チエに首根っこを掴まれて、ネプが連行されてきた。
どう考えても痛そうだが、表情一つ変えていないところがさすが海王といったところか。
「むふふー、海王星なんて所詮私の力で照らされている惑星なのよ。」
「恒星は強いんだぞー。」
「さっきの悪口、私たちが考えたんじゃないからな…。」
スイジーは、ただひたすらにネプを煽れと言った。そして、そのネタをたくさん教えてくれた。アーテナイのうんぬんかんぬんや、デメテルのうんぬんかんぬんとか。
すると面白いほどにボロが出た。そしてこれは行けると引っ捕まえたのだ。
「電話のお相手、色々な意味で会ってみたいぞー…。」
「とりあえず。先に進もうか」
「…連れてくの?」
「だって、あんな海原に放置できないし…。」
「放置されたくないし…。」
物語的に困るし…。
「…今さりげなく天の声が聞こえた気がする。」
「あら、チエ。あなたそれ、地獄からの呻き声と間違えてないかしら。」
きっと気のせいだろう。
さて、一行は洞窟の奥へと向かっていく。
「そうそうスィエル。そこら辺に変な紐があっても引っ張らな」
「えいやー。」
遅かった。
どこからか重々しい音が響いてくる。それは水の流れる音だとすぐわかった。
「この遺跡は王道をわかっているわね。」
「でも私たち王道とかシラナイデスネ。」
「ホウコ、お前疲れてる?」
「憑かれました。」
「ふーん、なんか違う気がしたけどこれは会話だからよくわからないしー。」
そうだね。会話だからね。
「うおおおお水だ!さあ、私の半身よかもーん!」
元素ちゃん特有の、自分と同じ元素なら引っ剥がせる能力を駆使する。
便利だね。魔法の力だもんね。魔法なら出来るよ。
「今回は水だったからよかったけど…用心しなさいね。」
「はあい。」
あまり理解していない返事だった。先が思いやられる。
それにしても、岩で囲まれた洞窟というと陰鬱な雰囲気であると思われるが、ここは不思議とそうは見えない。
じめじめとした空気や薄暗い道をものともしないこの元素ちゃんたちの軽い性格のお陰なのだろうか。
「先程から道が一つですね。」
「しかも整備されているわ。昔に使われていたのかしら。」
「そうかもな。この木…樫の木とかかもな?」
「え?確かにどれも湿ってるけど、あっ…霊木…確かにね!」
「え?うん。」
チエは何となくでそう思っているが、スィエルはその方が神話っぽいという理由で、むしろ願っている。
全く、この子は変わらない。
「ん、何か扉が見えてきたぞ。」
「おっ、これは謎解き不可避ですね!?ね!?」
ホウコもホウコで変わらず願望を込めて言う。
確かに扉にはなにか石版のようなものが付いている。
「えーと?なになに…我を示すものこそ鍵だって。なんか文字が浮かんでるけど…、2LiNbO3…?」
「……。」
「………。」
「分解しよう。」
「そうだな。」
「あ、ちょっとそこの二酸化炭素。」
「任せろしー。」
「ソヨソヨー。」
なんだろうこれ。
シータスとオウカが二酸化炭素を作り、石版にぶつけると、文字が変化する。
「2LiNbO3+CO2になった!使うのが二酸化炭素なら、人間でも開けられるわね。」
「ここに来るまでが大変だけどね。酸素の量的に。ちょっと貰ったけど、どこからも補充されていないわ。」
二人がそんな会話をしている間、何かを考えていた様子のチエは文字に触れようとしていた。
そして、タッチパネルのごとくなぞって見る。
すると…
「おおー、動きましたな。」
「最近の遺跡はハイテクだぞー。」
「いやこういうのって魔術の類なん…あれ、お前魔術師じ」
「わあー、Li2CO3+NbO2になったー。」
Liと書かれた石版が二つ、Cと書かれた石版が一つ、Oと書かれた石版が三つ、どこからともなく出てきて、床に落ちる。
浮かんでいる文字は、NbO2だけになった。
「おー、これはNbを残せばいいのかー?よくわかったなー。」
そう言いながら、ネプは興味深そうに覗き込む。マイペースなやつだと思いながら、チエは操作を続ける。
「まあ、CとOはここにいるし、Liは最近見つかったからな。消去法。」
後は速い。O2を動かすと、またOと書かれた石版が二つ床に転がった。
「これでいいはず…恐らく。」
「そもそもこの先にいるのが元素とも限らない気がしますが…。」
「あっ。」
普段から元素が近い場所に、というか自分が元素であるので、勝手に脳が化学モードに切り替わってしまったのだろう。
もしかしたら記号を並べ替えて名前を作れ的なやつだったかもしれない。
「でも、扉開いたぞー?」
いつの間にか扉を開けて中に入っている四人。
いつの間にかネプがとても馴染んでいる。
「…元素じゃないとも限りませんが。」
「これで間違ってなにか起こったら一週間ぐらい立ち直れなかったかも。」
結果オーライということにして、二人も続く。
嫌な⋯伏線だったね
その先の部屋は、とても大きな空洞だった。
松明の明かりで、薄暗く照らされている。
床や壁などは白く美しい大理石で装飾されているようだ。
そして、中心には、これもまた美しい女性の像があった。神々しいその像の真上を見上げてみると、ステンドグラスのようなものがあり、どこから来たのか、まさか海上からの光では無いだろうが、明かりが差し込んでいた。どうりで壁から離れた場所も薄暗くはなっているわけだ。
「なんか、すごく綺麗だね。」
「でも、これ…泣いてるしー?」
よく見るとそれは、涙を流して立ち尽くしている様子が表されていた。
「なんだろう…。」
そう言ってスィエルがまじまじと見つめていると、急にそれにヒビが入り出した。
「スィエル、今何か…。」
「な、何にもしてないよ!!」
「おやおやー…これは降りてくるよー。」
ネプが含みを持たせて言うと、像のヒビは全体に広がり、やがて煙をあげて崩れた。
何が起きたのかと思いながら見れば、土煙の中から出来てきたのは一人の少女だった。
金色の髪はなびき、白い衣は揺れる。
まるで、白昼夢を見ているかのようだった。いや、最初はそう疑った。
ぼんやりとした幻想的な光をまとったその少女は、ゆっくりと目を開いた。
光は空気に溶けるように消え、あたりは先ほどと同じ景色に戻る。
突然、少女は腕を振り上げた。
眩い光が上に現れ、拡散して飛び散る。
「あたると痛いよー!」
ネプが叫んだのを聞き、五人はそれを避ける。
そのまま呆然としている中、ネプは一歩歩みでる。
「やあ、お寝ぼけ女神。私だぞ。」
空色の目がネプを見据える。
「………私だぞ?」
反復するように、女神と呼ばれた少女は言った。
「おはよう、随分長いお昼寝だったなー。」
「む…お昼寝じゃない、冬眠。」
「そうかそうかー。それで何だって急に起きようとしたんだー?」
「起きようとしてない…誰かが…何かした…?」
「曖昧すぎるぞー…。」
普通に会話をしている。その様子を見て、チエがようやく口を開く。
「ネプ、そいつは…。」
「おー、こいつか?こいつはニオべだぞー。」
「ニオべ…だよ…。」
「ギリシア神話の神ニオべ。タンタロスとディオーネの娘だー。前に会ったことがあるぞー。」
「うん…その通り…。」
「神話…?別の世界から来た神様?」
「そうとも言えるなー。でも、ニオべはこの世界に適応している。つまり、この世界の住人である条件を満たしているんだー。」
何を言っているのか、理解することは出来なかった。しかし、とりあえずこの世界の住人であるらしいことはわかった。
この世界の住人という言葉もあまり耳慣れなかったが。
「そこの薄幸そうな元素なら、勘も良いだろうしわかりそうだなー。」
「あ゙?」
「ごめんなさい。」
「…ニオべと言えば、そいつが由来の奴がいたな。」
「そ、そういう事だなー。」
ギリシア神話のニオべ。その女神の名に由来する者とは…
「彼女は元素番号四十一番、ニオブ。さっきあった扉の『我』というのは、彼女のことを指していたんだろう。結局分解していって残ったのはニオブだったからな。そこから予想はしてた。」
「んー…そうだったかもしれない…?」
「本人が疑問系でどうするんだ一体。」
「こいつはそんな奴なんだー。」
口を閉じれば神々しく、口を開けば威厳は消える。
仕方ないさ、(見た目)幼女だもの。
「はあ…それで、これからどうしろって言うんだ?」
「そうね…帰って報告書でもまとめる?」
「ママ…。」
ニオべはキョロキョロと周りを見回し、呟いた。
「え?」
「ムッターがいない。」
「むったー?」
「マンマ…。」
「………お母さん?」
「ふむ。確か親も元素に…、タンタルのことか?」
「そうかも…?」
相変わらず疑問符付きの回答である。
「もうツッコまないぞ。」
「マムも近くにいると…思う…。」
「自信持っていいよ自信。」
「まーとりあえず、まだ先があるみたいだぞー?」
ネプが指さす方向には、確かに木の扉がある。あの先にいるのだろうか。
「進みま…すよね。」
「そだねー。」
「この子はどうする?」
「むー……、待ってる…。」
スィエルに頬をムニムニされながらそう答えるので、六人で行くことにした。
「やっぱこれは樫の木だろうなー。」
「神様だもんねー。」
扉を開けると、ひんやりした石の通路に出た。
その先へ、ゆるーくゆるーく進んでいく。
エクストラ道中
「ひぇえええええええう!!!!」
「はしれえええぇぇぇえ!!!!!」
絶叫が通路を埋め尽くす。
というのも、少し進むと、なんと後ろから矢やら光線やらがこちらを追いかけてきたのだ。
まあなんたってその数が尋常じゃない。消える命の灯火がないとて痛いものは痛いのだ。
「素数を数えよう!いちにいさんご!」
「1は素数じゃないしー!」
「やりがちなミスね!」
「だいたい何故この状況で数える!?」
「こいつはそんな奴さー!」
「なるほど、追っかけがキツいというのは大変なのですね!!さすがアイドル!!!偶像!!」
「間違ってないけどていうか大正解だけど偶像とか叫ぶなアイドルが泣く!!あと追っかけとは割と違う気がする!!」
「こいつはそんな奴さあー!!!」
「最近の口癖なのそれ!?」
高速ダッシュ、早口でのんびり会話を繰り広げる。
元素って…器用。
「たいちょー!上から岩が落ちてくるでありますしー!」
「避けろぉぉぉぉ!!!!」
軽い身のこなしで、ぴょこぴょこと、どこから来たかもわからない岩を避ける。
「これ…帰れるの!?」
「海に穴を開けよう!!!!!」
「海の神様が怒るぞ!!」
「なるほどー!!それは名案だぞー!!!」
「はい海王様の許可いただきましたー!」
「ええ…いいのかよ。」
「たいちょー!今度は前から蛇がー!」
広いところに出ると、一旦矢などのトラップは停止した。しかし、先への道は大蛇によって塞がれている。
噛み付こうと寄ってくる大蛇に、チエは無表情で冷気を吹き付ける。
すると、なんとも呆気なく倒れてしまう。
「アブソリュートゼロってやつだなー。」
「変温動物だからな、仕方ないな。」
「チエあなた憑かれてるのよ。」
「何か違う気がするけど文字だか……デジャヴだしー!」
「ふう…ちょっと休憩しまし」
「たいちょー!早く行かないと、今度は壁が崩れてくよー!」
「さっきから気になってるけど隊長って誰なの。」
「知りません!行きましょう!潰される!!!」
「うおおおおおおお!!!!」
再び全力疾走。休みなど与えてくれないようだ。
次の通路は、下り坂だった。
「あっ…ああ…走らなきゃ行けない気がします…。」
「んえ?」
ホウコの予感は的中する。後ろからガコンという音がした。
丸い岩だ。
「にげろおおおおおおおお!!!!!!」
「うわあああああああああぁ!?」
おそらく螺旋状になっている坂道を、ぐるぐる下っていく。
壁がところどころでこぼこしていて、岩が減速するのが救いだった。
「な、なんだってこんな仕掛けがあるしー!!!」
「き、鬼畜すぎぃぃいい!!!!」
「休息をくれないだなんて、本当にブラックな遺跡よね!!」
「最後の良心、岩肌!!!」
「岩肌…お前、良い奴だったよ…。」
「おめぇのことは忘れねぇだよ!」
「ホウコ、口調どうした!?」
焦ってるからね。仕方ないんだね。
ゲームをやる我々と同じなんだよ。
「あっ、でっかい水溜まり!うぃず開けた場所!!!」
「勝利だ!脇に逸れろ!!」
「…ん?」
「やったしー…誰一人として欠かさず…。」
「あのさ、これって岩だよね。」
「うっ、感極まってしまいます。」
「そしたらさ…。」
「泣くな!まだ泣くな!戦いは終わっていないよ!」
「あの、感動してるとこ悪いけど。」
「そうだぞー、皆で帰るんだぞー。」
「……壊せばよくない?」
全員がその場に立ち尽くす。時空が静止する。
…あ、べつに作者も今まで壊すという発想がなかったなんてことは断じてありません。今思いついたとかそのような事は一切ありません。
「…壊そうか、シータス。」
「了解たいちょーだしー!」
シータスが向かってくる岩にドロップキックを喰らわす。
炭素の力で強化された足に痛みはない。
岩だけが、木っ端微塵に砕け散る。
「隊長ってチエだったのね。」
「たいちょー!たいちょー!ターゲットクリアだしー!」
「…まあ、うん。じゃあ進もうか。」
「さーいぇっさー!」
しかし、先へ進む道は、見たところ見つからない。
「あるえー…?」
「まさか、でっかい水溜まりを割れっていうの…?」
「湖でいいだろ。あとこれ以上割るな。」
そんなやり取りをしていると、どこからか地響きがする。
警戒していると、地響きはさらに大きくなり、そして、湖の底から四角い石が姿を現した。
「…えっと。」
「どうやら橋のようだが…。」
「先が見えにくいしー。」
「まあでも、ここしか道はないのだから進みましょう。最悪洞窟に穴を開けるわ。」
「おいおい怒られるぞ王国に。」
「元素は人権ないから裁かれないもーん!」
「…涙拭けよ。」
「うぇぶ、ひっくひっく。」
橋の上に乗っかってみる。沈んだり矢が飛んできたりということはなさそうだ。
しかし、しっかりと、かつゆるーく進んでいく。
神格の性格
「そういえばさ。」
歩きながらスィエルが口を開く。
今は罠もなく、静かな通路にいる。
「なんでネプは海にいたの?」
「ん?そりゃあ、海王だからだぞー。珊瑚海は綺麗だし魚達も住みやすいから、私もそこでゆらゆらしてたんだー。」
なんとも自由らしさ溢れる答えだろう。
「他のアクチノイドの居場所とか知ってたり…する?」
そう聞くと、ネプは少し唸った後、
「いや、わからないなー。でも、最近ここら辺で怪し気なやつの気配を感じたなー。」
「怪しげなやつ?」
「宇宙に向かって何かの儀式でもしようとしてたのか…。あれはあいつの加護ではじかれて失敗したなー多分。あと、使い魔に様子を見に行かせたら、害はない程度の痕跡が残ってたなー。ホープダイヤモンドが埋まってたくらいか。」
「ホープダイヤモンド?」
「魔力のこもったダイヤモンドよ。ダイヤモンドってすっごいから魔術に使ったりするのよ。魔力が上がるのよ。すっごいでしょ?」
「そうそう、凄いんだぞー。」
こいつらの語彙力が無いため補足するが、つまりダイヤモンドは魔術を行う際の補助道具としての価値があるのだ。
認識が現実となりうるこの世界では、宝石の神秘性を利用して魔力を高められる。
しかし、大掛かりな魔術になると、どうしても物理的な硬度がないと負荷に耐えきれなくなってしまう。
なので、ダイヤモンドを使うのだ。
「見たことあるかもしれないしー。」
「そういえば言っていたな。それのことか。」
「まあ、で、そのダイヤモンドがたくさんあったってことは確実に大掛かりな儀式が行われたってことだなー。」
「それこそ海底遺跡が見つかった原因とか。」
「有り得なくはないぞー。時期的にも近いし。そいつを防ぐためには、眠ったままでは足らなかったとかー。」
「可能性の一つとして覚えておきましょう。」
話しながら進んでいると、ようやく扉にたどり着く。
豪華な装飾が施された、石の扉だ。
「ここにあいつの母がいるとすれば…。」
「何かあるかもしれないわ、用心しましょう。」
スィエルがその重たそうな扉を押すと、扉は低く唸りながら、ゆっくりと開いていく。
そこはまた先程と似た広い空間で、真ん中には木で作られた祭壇が置いてあった。
暗闇の中に生まれた。たった一人。
何を思うわけでもなく辺りを見回すと、自分の中でなにか熱いものが生まれた気がした。
なので、それを外に出してやった。それは小さなオレンジ色の球体だった。
まだいくつも同じものがある気がしたので、全て解き放った。
恒星達は一気に果てしない宇宙へと飛び立っていった。
そこからの記憶はない。きっと、眠っていただろうから。
気が付いたら原っぱの上で寝転んでいた。
「どうしたの、こんなところで。」
目を開けると、茶色い髪の女の子がこちらを覗き込んでいた。
体を起こして目をぱちくりさせていると、足音がしてもう一人、白い髪の女の子がやってきた。
「こんなところで寝ていたら風邪ひいちゃうしー!」
首を傾げた。どこで知ったかはわからないが、二人の言葉を理解出来た。
ここがどこか。そして、私が誰なのかも。
『でもそれは本当なのか?』
そんなこと言われても、わからない。
『お前は本当に自分の思っているような存在であるのか?何を根拠にそう思う。』
だって、本当の自分が何なのかなんて、誰も教えてくれない。だったら私の思う自分を自分にすればいい。
『お前の存在は不確かだ。』
それはそうだけど…。
『お前が存在している証明はできない。』
出来なくても、こうやってワイワイ過ごせてるからどうでもいい、そんなもの。
『不安にはならないのか?』
なるはずない。だって、楽しいから。不安なんて感じる暇ない。
だから…
『お前は誰だ。』
「ねえ、あなたはだぁれ?」
自信たっぷりに言った。
「私はね、スィエルだよ!」
「あなたの名前を教えて?」
胸を張って言った。
「シータスだしー!」
「じゃあ、君の名前も教えるしー!」
迷うこと無く言った。
「オウカよ。よろしくね。」
「あなたの名前を教えてくれるかしら?」
疑いもせず言った。
「………チエ。」
「どうか、お名前を…教えてください。」
無意識的に言った。
「ホウコです…、お気をつけて。」
「そなた、名は何という。」
え、私もかー?…じゃなくて。
誇らしげに言った。
「海王、ネプだぞー!」
―『正解だ。』―
目の前は暗闇となり、声だけが響いた。
夢を見ていた気がする。景色は海底遺跡の広間。
変わらず、中心に木の祭壇がある。
「…あるえ。」
しかし、その祭壇には誰かがいた。
「よくぞたどり着いた、どうやらお前達は元素のようだな。」
「いかにも、だしー。」
黒い布に身を包んだその女性は、まるで古代の壁画から飛び出てきたように神々しかった。
木の杖をカタンと鳴らしながら、地に降り立つ。
「我が名はディオーネ。アトラースの娘ともされ、ティーターン神族の一人、天空の神ともされるギリシア神話の女神だ。」
「神話の曖昧さを利用して二つの神格を得たんだなー。うん、私もそれやったことあるぞー。」
「おや、賢いと思えば、お前はネプテューヌスか?」
「いかにも、だぞー。」
(自分含め誰かの言葉を反復する癖でもあるのかな…、)
チエはそう思ったが、空気を壊さないために心の中に留めておく。
「そうか。どうりで我が子が大人しくなった訳だ。」
「ニオベちゃん?」
「そうだ。可愛いだろう?それこそ神格級の可愛さだろう?」
「え、あっはい。」
(あれー…?)
「あいつはな、いつもママムッターマンマと駆け寄ってきてな、それはそれは愛らしいんだ。」
まさにほへーという表情で話す女神様。
(何だ、ただのただならぬ親バカか…。)
「そうだなー、可愛いなー。ここは一体何なんだー?何で二人は眠っていたんだー?」
(棒読みで流したがその判断はきっと正しい。)
「ああ、それはな。」
(切り替え早いな。)
「何だかよく分からないが、邪悪な魔力に襲われてな。実は…天空の女神の神格が封じられてしまったんだ。とてつもない感情が込められた魔術だった。ニオベも大怪我を負って…。全く、許せんな。そしてこのように眠って傷を癒していたんところ、誰かに起こされて今に至るわけだ。神格はバッチリ二つあるぞ。」
(寝過ぎたのか。)
「誰かに起こされたというのは?」
「近くで、害のある力を使おうとした者がいる。加護により守ったが、その影響で何だか目が覚めてしまってな。」
「やっぱりあの、森のホープダイヤモンドですね…。」
「ほう、そんなものが。…まあ、とりあえずそんな時にお前達が入ってきたわけだ。だからまだ降臨せずに神殿の様子だけを見ていたわけだ。お前達はここまで無事来れたが、そうでなければ留まるつもりでいた。」
「あ、はいはいあのあの、地震について何か知ってるかなあ?」
「地震…地震はなかったぞ。強いていうなら、神殿が機能し始めたことによる地響きはあった。ちょうどアンダンサ近海の地下にあるからな。」
「へえ、じゃあ悪いことが起きる前触れとかじゃないんですね。」
「ふむ、そうかもしれんな。」
「ところで女神。ここの構造は知っているんだなー?」
「ああ。確かお前らは調査に来たんだったな。ならば、ここには我々がいる以外には特に何もない。部屋もここで終わりだ」
つまり…残りの仕事は、帰って報告書をまとめるだけだ。
「…ここへたどり着くまでどれくらいかかった?」
「数時間は。そろそろお昼の時間だぞ。」
「割と…経ったんだね。」
さらにここから帰るとすると…。
「帰りの時間はいつになるんだろう…。」
「ん、それなら案ずることはない。すぐに帰れるぞ。」
そう言うと、ディオーネは天井を指す。正確には、ステンドグラスを。
「もともとこの神殿は我が力により造られた。眠るためにな。用済みとなったことだし、あそこを割ればすぐアンダンサだ。」
「割る…?」
「ああ。そもそも、その為にああいった構造にしたからな。」
なるほど…だからニオベの部屋も同じようになっていたわけだ。
「することがないなら、今からでも出るが」
「待って待って大事な質問!」
スィエルが声を張り上げる。
「えっと、その、二人はこれからどうするのかなって!!」
そしてかえる
「…これからか?」
ディオーネは深く考え込む。
「少なくとも…元居た世界へ帰るつもりは無い。」
「元居た世界…?」
「ああ。あそこは…あまりに危険な場所になってしまった。」
この世界に降臨する前は、恐らく他のギリシャ神も住まう場所にいたのだろう。しかし、詳しい事情まではわからなかったが、危ないという。
「しかしそうだな、アンダンサは私の加護がある限り安泰であろうし、無理に留まることもないな。」
この女神…空気が読める!?
…さすが、天空の女神。
「じゃあ、引っ張っていってもいいのね?」
「おい言い方。」
「はは、構わんよ。我々はここでは元素でもある。何も理解していない訳では無い。」
「⋯そうか。」
「よし、話は決まりだ。ネプテューヌス、力を貸してくれ。脱出するぞ!」
「任せろー!」
パリンという音がすると同時に、空へと向かって飛び立つ。
「わあ…。」
水や魚が、まるで自分たちを避けるかのように道を開ける。
「むふふ、海王の威厳だぞー。」
こんな子でも海王の名は伊達じゃないらしい。
上へ出ると、本当に近くだったようで、そこからでもアンダンサが見えた。
「ところでディオーネ、ニオベちゃんはどうしたの?」
スィエルが聞くと、笑いながら答える。
「あの子なら、とっくにアンダンサにいると思うぞ、」
人が変わり時代が変わっても、小さな女神がアンダンサへの深い感謝を忘れることはない。
「そうなんですね。」
二人が伝承に残された女神だとはつゆ知らず。
…いや、チエ以外が忘れているだけで。
7人は海の上を飛び、アンダンサへ向かう。
✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼
目的、珊瑚海に現れた海底洞窟の調査。
海底洞窟には二人の女神が眠っていただけである。害は何もないし、宝も何もない。…トラップはあるが。
アンダンサ付近で魔術の跡が確認されており、その儀式が原因で二人の女神を呼び起こしたと思われる。なお、儀式についての詳細は不明。
現在洞窟内は海水が入り込んでいると推測される。もはや用もなく行くような場所ではないだろう。
文之月 九日
✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼
「ふう…最低限のことは書いてあるからこれでいいでしょうかね…。」
一人、報告書と向き合っているのはホウコ。
他の七人は挨拶に行っている。
書き終えて筆記具を置いた時、連絡機が震え出した。
何だろうと思いながら、応答ボタンを押して耳に当てる。
「ホウコです、どうかしました…?」
『女王陛下がお亡くなりになりました。』
聞こえてきたのは、フェルニーの声だった。
「ああ…とうとう…、そうなんですね…。」
前から陛下は病気をしており、周りの懸命な看病によりなんとか生き長らえていた、という状況だったのだ。
『ええ。非常に残念ですが⋯。』
「陛下は…私たちにも優しくしてくださって…それで、大変…、よくしてくださって…。」
『ええ。』
王族のなかでも、元素たちの扱いは議論となっている。
その中でも特に、陛下…シェーリの態度はとても寛容だった。
排他的な大臣たちを説き伏せ、今回のように依頼をしてくれることすらあった。
『ですから、しっかりと…報告をしましょう。陛下の最後のご依頼でございましたから。』
通信は切れた。
ホウコは、もう一度ペンを握りしめる。
「大人しく帰れば見逃してあげてもいいよ。」
どこかの森。空は灰色に曇り、今にも雷雨が降り出しそうだ。
そんな森の道で、一人の少女がある男を見下ろしていた。
「わ、わかった…わかった。わかったから、どうかこのことは…。」
腰を抜かしたその男は、体格がよく、軽鎧を纏っている。
対する少女は、華奢な体の上に、Tシャツ短パンパーカーといった軽装である。
「べっつに言う相手いないし。早く帰りなよ。」
少女の眼は男を捉えてなどいない。
「…。」
見据えていたのは、その先に立つ少女の姿だった。
みゅーじっくふぇすた!
前女王が亡くなってから数週間が経った。
人々の悲しみもいくらか和らぎ、今度は新女王の誕生に沸いている。
そしてその即位式は、王城のある聖都セレネメンティアにて華々しく行われる。
その余興として、音楽祭も同時に開催される。
それに興味があり、今、空色の短い髪の少女―ルルは、セレネメンティアを訪れている。
街には活気があり、市場や民家まで装飾が施されている。
広場まで行くと、大きな緑の針葉樹が植えられている。その木も、派手な装飾がされていた。
それをじっと見ていると、通りすがりの人が声をかけてくる。
「あの木が気になるかい?」
見た目の年齢は大学生といった感じの少女であった。
本当の金色のウェーブがかった髪で、騎士のような、しかし騎士にしては美しすぎる薄い鎧をまとっている。
「うん…クリスマスみたいなのって」
細々と答えると、少女は笑う。
「そうだね、本来それがこの木に込められた意味なんだけど…。それにしても、君は…保護者とかはいるのかな?」
「一人なのって。ビアンカから来たのって、」
そう言うと、少女は驚いた顔をする。
まあ、ルルの容姿というのは小学生らしいので当然だが。
「遠くからお疲れ様だね。即位式を見に来たのかな?」
「ううん、音楽祭を見に来たのって。」
「へえ、音楽祭か。いいね、私はいつも弾いてばかりいるけど、聴くのも大好きだよ。」
「って。そうなのって。」
「君も楽器を弾くのかい?」
「弾くのって…!」
「はは、そうかい。弾くのは、いいよね。何ていうか…あの曲が、あの音が、自分の手によって奏でられていると考えると、とても興奮してしまうよ」
「て…お姉ちゃんの言う通りなのって!」
そう言うと、何だか照れくさそうにしながら少女は言う。
「お姉ちゃん、だなんて。スピカでいいさ。それが私の名前だ。」
「スピカ…、お星様なのって…。って、ルルは…ルルなのって?」
「ルルか。可愛らしい名前だな、」
こうして、二人は出会った。
その後、音楽祭まで二人でお祭りムードの街を回った。
そうしていると、突然スピカが立ち止まる。
「…あの紋章。」
ルルも、スピカの視線の先を見る。
見えたのは、二人組の男。黒く重そうな服を着ていて、その左肩には紋章が入っていた。
それには見覚えがあった。
「森羅万象研究所って…?」
かつて大規模な元素捕獲作戦が行われた。いくつかの研究所が合同で行った、その名のとおり元素たちを捕まえるという作戦だ。
それを主導したのが、森羅万象研究所。
表立って知られてはいないものの、研究者の中ではとても有名である。しかし、その存在を公言するようなことは誰もしない。暗黙の了解で、誰もが口を閉ざす。そのような研究所なのだ。
「何故その名を、君は一体…。」
「…?ルルはルルなのって。」
すると、視界の隅に、こちらを振り向く男の姿が映った。
「まずい。君もおいで、その名を知っている以上、なんの関わりもないことはないだろう。」
「て…あの人たちには近づいちゃダメって言われてるのって。」
「…事情はわからないが、君はもしかして…。いや、それよりも今は人混みに紛れて…。」
小声でつぶやくと、スピカはルルの手を引いて歩き出す。
「…ねえ君。君は何故奴らを知っているんだい?」
「教えて貰ったのって。みんな言ってるのって。あの紋章を見たら安全な場所まで逃げてって。」
「どうして…だい?」
「あの紋章の人はルルたちを狙ってるのって。捕まったら危ないから近寄らないでって。」
「………もしかして君は、人間じゃないのかい?」
「………わからないのって。」
ルルは正直に答えた。元素だとか人間だとか、そんな区別がよくわからないというわけだ。
するとスピカはその意図を察してか、くすりと笑って頷いた。
「私も自分が人間じゃないのかなんてわからないや。」
「難しいのって…ルルにはよくわからないのって。」
「…私は。」
少し躊躇いがちに言い出した。
「私はね…、アンチモンらしいんだ。よくわかんないけどね。」
「て……ルルはね、テルルみたいなのって…!」
二人は人混みに紛れてやり過ごし、音楽祭を見ていた。
聴衆も、踊り、歌い、随分と華やかなものだった。
「…ルル、演奏するのは好き?」
「大好きなのって!」
「ふふ、私もだ…。」
そう言うとスピカは、魔法でバイオリンを生み出す。
ルルも、笑って、ベルリラを生み出す。
星降る夜に、たくさんの音が響いていた。
「さっきの金髪の女の子、超可愛くなかった!?」
「それはわかるが…、観光先でナンパはマズいだろ。」
「えー…。」
実はあの男性二人組は、こんな会話をしていたのだが…。
リンリンスズスズ
「…あの。」
「ああ…あのトロリとした黄色いふわふわ卵…トゥルンと咥えたスプーンから滑り落ちれば広がるやわらかなお味…。」
「ちょ、あの…聞いてください。」
「そしてほのかな酸味のあるお米に絡んで…じゅるるるる。」
「ぴぃ…!」
スズは、ある依頼を受けた後にフィスプに寄っていた。
すると、明らかに異質な者がいたのだ。
緑っぽい青色のお団子ふわふわロングだけならまだしも、なんと矛と盾まで持っている。
ここら辺では珍しい武器である。
しかし、一度絡んでしまったならば放っておくわけにはいかない。(社会地位的に)
「オムライスが食べたいんですか?」
「それ!それネ!オムライスネ!」
オムライスに反応して、がばぁっと勢いよく顔を起こした。目はキラキラ。
「…どうでしょう、ビアンカでならご馳走できますよ。」
「ホント!?嬉しいヨ~!」
(身元を詳しく調べましょう…。)
「ワタシはリン、ネ。よろしくなのネ。」
(名前紛らわしい…。)
なんとなんと、元素名と被っている。
「スズと申すのです。こちらこそよろしくです。」
そういえばこの名前も他の元素と
「被ってるのネ…。」
そうそう、被ってる。被って…、
「さあ早くビアンカへ善は急げです、」
「ン?わからないけどわかったネ!」
「ということでれんこ…連れてきました。」
「おーおー、ここがElementsなのネー、」
急がずとも、元々リンはここへ来るつもりだったらしい。北東の国から、北を回って来ようとしたところ迷子になっていたらしい。あそこで話しかけたのは運命というものか。
北東の国では、名前は「鈴」という表記だったという。リンともスズとも読める。うむ、紛らわしい。
「承知致しました。オムライスでしたらすぐご用意できるのでございます。」
事の顛末をフェルニーに話すと、そう言って台所へと入っていく。
「良かったノネ…。」
「…そんなにオムライスが食べたかったんですか。」
こくりと深く頷く。
凄まじい熱意だ。一体何が彼女をそこまで突き動かすのか…。
「今日もにぎやかですねー…。」
ワイワイとはしゃぐ元素たちの間をすたすた歩き、椅子に案内する。
「今は数人が小規模な遠征に行っていますが、それなのに十分騒がしいです。」
「この騒がしさなら良いことネ。ワタシの住んでた国は、音が大きなだけで命の騒がしさを感じないネ。」
苛立ちや悲しみはなく、ただただどうでも良さそうに言う。
国はどのようなところか聞いたところ、昔は活力に溢れる国だったという。いつの間にか人と人との関わりは薄れ、利己的な感情は個人で完全完結してしまっていたのだとか。
礼儀作法やマナーも知らない者が増え、その時代の遷移についていこうとは思えなかったそうだ。
「頭の堅い懐古主義と言われるかもしれないネ。」
「なるほど…しかし、確かに私達は時代の移り変わりを見ることができますから、昔のこれがよかったと比較してしまうのはあってもおかしくありませんよ。思い出補正もあるでしょうし。」
「フフ、思い出補正ネ…。」
「たっだいま帰りました~!!」
戸を思い切り開け、元気良く声を響かせたのは…。
「マグ!遠征お疲れ様マグ!」
遠征組たちだ。…どうやら、3人ほど増えてるが。
「あらあら、たくさん連れておいでですね。」
お皿を持ったフェルニーが笑顔で歩いてくる。
目を輝かすリンの前に、とろとろしていそうな輝く卵が覆いかぶさったオムライスが置かれる。
「ありがとネー!それじゃあ冷めないうちにいただくヨ!」
パクパクと、幸せそうな顔をしてオムライスを口に運ぶリンはそっとしておいて、フェルニーは遠征組たちの元へと向かう。
「わたくしはフェルニーと申します…、Elementsの事務その他諸々を担当しております。以後お見知り置きを。」
礼儀正しく頭を下げる。
新しく仲間が加わった。それも一気に4人。なんとも喜ばしいことだ。
「さて、とりあえず報告書をいただくマグ。」
「あ、はーい!」
マグナは紙の束を受け取り、奥へ入っていく。
「そういえば、聞いた?新しい女王様のこと。」
スィエルがパタパタと鳥のように手を振りながら話し出す。
「ああ、確かクリス様でございましたよね。わたくしはてっきり妹様がご即位なさるものかと…。」
「そう!その妹さん!その、聞いた話によると…行方不明なんだって」
「行方不明…?しかし、それならば…妹様を探しませんか…?」
「やっぱりアレですよ…陰謀渦巻く悪事に巻き込まれて…。」
ズモモモモと後ろに文字が浮かび上がりそうな顔をしてホウコが言う。
「それお前が好きなだけだろ。」
チエちゃんお守りお疲れ様…。
「まあ、お土産話はお座りになってからに致しましょう。立ち話もなんですし。」
はーいと元気よく返事をして、テーブルを囲む。
「ごちそうさまネー!あ、どうも、私はスズのリン、ヨ!」
「そしてこちらリンのスズですが何か。」
「うわ紛らわしいの来た!!」
リンもさっそく雰囲気に馴染みそうな様子だ。
「マンマ…、楽しそう?」
「そうだな…お前もきっとすぐ馴染めよう。」
「ここは賑やかなんだなー。」
「でも、これからはもっと賑やかになりそうだしー。」
「ふふ、そうでございますわね。」
「これ以上騒がしくなれるなんて信じられないマグ。」
まさかこの後、ルルがもう一人連れてくるだなんて、夢にも思わなかっただろう。
枯れない花と枯れた木
もう歩き疲れた。草履はとうに壊れて使い物になりやしない。
数週間飲まず食わずで歩き続けた。それはただ、自分の人ならざる身を強調するだけであり、それを辛く感じた。
雨傘を傾けて、空を見やる。
鼠色の雲には終わりが見えない。
雨も降り止みそうにない。
この雨傘だけはいつでもそばにあった。不思議な事に、壊れもしないし無くなりもしない。
きっとどこかの神様がそうしてくれているんだと思うと、嬉しく感じた。自分を見てくれているのだと。この努力は無駄ではないと認めてくれているような気がしたのだ。
それが目的ということではなかったが、今まで随分と頑張ってきた。雑用はなんでもこなしたし、とうとう最高位までのぼりつめた。
あのセンイーン街で名を知らない者はいないほどだった。
相手を選べるような位であり、裕福そうな客には特にたくさん貢がせた。
しかし、もう精神は持たない。この老いない身体が憎い。もう何十年も働いた。解放してくれたっていいではないか。
ふと後ろを振り返る。
木々の隙間から、明かりがぽつぽつ見えた。
追っ手だ。そうに違いない。
駆け出した。
寒い。体がちぎれそうだ。しかし止まる訳にはいかない。
国境はもうすぐだ。エルスメノス王国は目の前だ。
いつか聞いた、あの仲間たちの元へと。
ぼろぼろの美しい太夫は、裸足のまま逃げ続けた。
「どうして私が連れてこられたの?」
「そこに居たからマグ。諦めて調査に取り掛かるマグ。」
白銀の街スノーゼル。その北部にある、エルスメノスと北方の国ヴィザーパンとの国境近くの森で、急に木が枯れだしたという。
「あなたが調査だなんて、随分珍しいですこと。」
「…そんなにエルシーと来たかったマグ?」
「そんなわけないでしょ。」
調査に来たのは、フィスプ付近の森での一件に関わりのあったスイジーと、普段はデスクワークに徹しているマグナ。
「けっ、大体君を連れてきたのはエルシーだったし、一体何百年一緒にいるっていうマグ。」
元素は桁数が違う。軽々しく百とかいう。
「…あなただって、フェルニーとは何百年一緒にいるの?」
「元素狩りの数十年前マグ。」
「……そう。」
「ま、とにかく調査調査マグ。」
「はいはい。なんだか肌寒いし早く終わらせましょう。」
もうすぐ葉之月に入るというのに、非常に冷涼である。さすが高緯度なだけはある。ビアンカ辺りもそこそこ高緯度ではあるが、風や海などによりぽかぽかしている。
「気候は不思議マグ。」
「そうね…。」
二人は森の中へと入っていく。
「で、何となく察しがつくと思うけれど。」
「ふむ。この前聞いた話と合わせれば、仮説は立つマグ。」
二人の目の前には、枯れた木々、そしてたくさんのホープダイヤモンドがある。
この前のアンダンサ遠征組も、同じものを見たと言っていた。
「十分移動できる時間はあったマグ。同一犯と見て間違いないマグ。」
「まだ魔力を感じる…最近のものみたいね。それにしても、まさか偶然ではないでしょうね。」
「木が枯れる現象…でも、前は見つからなかったマグ?」
「確かに…、そうだったかも。」
しかし、あくまで可能性の一つとして、有り得ない話ではなかった。
ホープダイヤモンドを中心に木が枯れているように見えないわけでもない。半径はおよそ三メートル。大分狭くなっている。ホープダイヤモンドに魔力を貯め、それらを併せて使うことで、術式を小さくしたのだろう。
「…とはいっても、それ以外何もわからないマグね。」
「…手掛かりはこれだけか。」
一時間以上は探しただろう。しかし、ようやく見つけたものも関連性があるか疑わしいものだ。
「寒いマグー、薄着で来るんじゃなかったマグ。」
「…帰る?」
「帰りたいマグ。」
との事なので、そうすることにした。
そして森を抜けようとしたまさにその時だった。
「…?」
微弱な何かを感じ取り、スイジーが振り向く。
「どうかしたマグ?」
「いえ、別に…。」
本当のところはすぐにでも戻って調べたかったが、マグナがぶるぶる震えているので諦めた。
華の楽園へ⋯
「…これからか?」
ディオーネは深く考え込む。
「少なくとも…元居た世界へ帰るつもりは無い。」
「元居た世界…?」
「ああ。あそこは…あまりに危険な場所になってしまった。」
この世界に降臨する前は、恐らく他のギリシャ神も住まう場所にいたのだろう。しかし、詳しい事情まではわからなかったが、危ないという。
「しかしそうだな、アンダンサは私の加護がある限り安泰であろうし、無理に留まることもないな。」
この女神…空気が読める!?
…さすが、天空の女神。
「じゃあ、引っ張っていってもいいのね?」
「おい言い方。」
「はは、構わんよ。我々はここでは元素でもある。何も理解していない訳では無い。」
「⋯そうか。」
「よし、話は決まりだ。ネプテューヌス、力を貸してくれ。脱出するぞ!」
「任せろー!」
パリンという音がすると同時に、空へと向かって飛び立つ。
「わあ…。」
水や魚が、まるで自分たちを避けるかのように道を開ける。
「むふふ、海王の威厳だぞー。」
こんな子でも海王の名は伊達じゃないらしい。
上へ出ると、本当に近くだったようで、そこからでもアンダンサが見えた。
「ところでディオーネ、ニオベちゃんはどうしたの?」
スィエルが聞くと、笑いながら答える。
「あの子なら、とっくにアンダンサにいると思うぞ、」
人が変わり時代が変わっても、小さな女神がアンダンサへの深い感謝を忘れることはない。
「そうなんですね。」
二人が伝承に残された女神だとはつゆ知らず。
…いや、チエ以外が忘れているだけで。
7人は海の上を飛び、アンダンサへ向かう。
✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼
目的、珊瑚海に現れた海底洞窟の調査。
海底洞窟には二人の女神が眠っていただけである。害は何もないし、宝も何もない。…トラップはあるが。
アンダンサ付近で魔術の跡が確認されており、その儀式が原因で二人の女神を呼び起こしたと思われる。なお、儀式についての詳細は不明。
現在洞窟内は海水が入り込んでいると推測される。もはや用もなく行くような場所ではないだろう。
文之月 九日
✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼
「ふう…最低限のことは書いてあるからこれでいいでしょうかね…。」
一人、報告書と向き合っているのはホウコ。
他の七人は挨拶に行っている。
書き終えて筆記具を置いた時、連絡機が震え出した。
何だろうと思いながら、応答ボタンを押して耳に当てる。
「ホウコです、どうかしました…?」
『女王陛下がお亡くなりになりました。』
聞こえてきたのは、フェルニーの声だった。
「ああ…とうとう…、そうなんですね…。」
前から陛下は病気をしており、周りの懸命な看病によりなんとか生き長らえていた、という状況だったのだ。
『ええ。非常に残念ですが⋯。』
「陛下は…私たちにも優しくしてくださって…それで、大変…、よくしてくださって…。」
『ええ。』
王族のなかでも、元素たちの扱いは議論となっている。
その中でも特に、陛下…シェーリの態度はとても寛容だった。
排他的な大臣たちを説き伏せ、今回のように依頼をしてくれることすらあった。
『ですから、しっかりと…報告をしましょう。陛下の最後のご依頼でございましたから。』
通信は切れた。
ホウコは、もう一度ペンを握りしめる。
「大人しく帰れば見逃してあげてもいいよ。」
どこかの森。空は灰色に曇り、今にも雷雨が降り出しそうだ。
そんな森の道で、一人の少女がある男を見下ろしていた。
「わ、わかった…わかった。わかったから、どうかこのことは…。」
腰を抜かしたその男は、体格がよく、軽鎧を纏っている。
対する少女は、華奢な体の上に、Tシャツ短パンパーカーといった軽装である。
「べっつに言う相手いないし。早く帰りなよ。」
少女の眼は男を捉えてなどいない。
「…。」
見据えていたのは、その先に立つ少女の姿だった。
巣立ち
拘束は解かれた。
手足は自由になったが、スイジーは動かないままだ。
「無駄に手を煩わせないでください。」
その変わらない悪態を聞き、肩の力が抜ける。
「…。」
しかし何だか気まずくて、やはり黙っていた。
「………大きな迷惑より小さな迷惑の方がまだマシだってことですよ。」
手を引かれ立たされる。
「殺してませんから、気にする必要ありません。」
そして、少女、エルシーはミホに視線を移す。
「どうかしましたか?」
こちらを見つめていた彼女に声をかけると、びくりと肩を震わせた。
「主らは…その、まさか…果実の森で……。」
今度は二人が硬直する。
「…果実の森がどうかしましたか。」
「…あちきは、まだ意識を手に入れてすぐのとき、大分甘やかされなんした。して、一度だけエルスメノス王国へ来たことがありんす。その時…フルチェリカに訪れなんした。」
果実の里フルチェリカ。果実の森に隣接している。
「森に出かけ、見かけなんした…。走り去る主を。」
「…確かに私である可能性はあります。が」
「後ほど知りんした。あの時期から考え、恐らく化学者から逃げていんした…。」
「ええ、そうかもしれないですね。」
「やはり…。」
ミホは少し間を置いた後、立ち上がって言った。
「もし…もし、主らが…良いならば。あちきを、ビアンカまで連れていってくれなんし。」
ビアンカは良い町だ。分け隔てなく接してくれる人がとても多い。
だから、元素はいずれビアンカに集まる。
かつて誰かがそう言ったように、また一人、新しくやって来たようだ。
「あちきはミホ。…ホルミウム!」
華やかな籠から、鳥は空へと飛び立った。
スノーゼルからは、その名の通り花が多い森丘のブロッサムフォレスト、アルシャフネリーを経由してビアンカまで列車で行くことがでる。
その列車に、三人は乗っていた。
「それならもしかすると、希土類かもしれなんし。」
枯れ木の件を話すと、ミホはそう言った。
意外な情報源であった。
彼女によれば、希土類元素同士では、何となく気配を察知できるらしい。ほとんど似通った性質であることに由来するのだろう。
最近ここらを隠れながら逃げていたらしく、その際に気配を感じることがあったらしい。
昨日になって突然消えたらしいが。
しかし、スイジーも今日はあまり強い力を感じなかったのだから十分関連が疑える。
「誰なのかまでは分からさんすが…そのような気配はしんした。」
「なるほど。有益な情報を得たかもしれませんね。」
ビアンカに着くまで、やはりスイジーはあまり喋らなかった。
あの子って本当運が悪いのかしら。どうしてことごとく彼女と遭遇するんでしょ。
溜息をつきながらそんなことを思う。
彼女の瞳は、もたれかかっている木の葉と同じ深緑。
森を讃え木を祀り
「マグー、まったく、マグナが脅されたマグ。」
「別に伝えてもよかったのではありませんか?」
「マグ。」
「とりあえずそれは置いておくとしまして、あちらの件は暇な方を摘んで向かわせておきますね。」
「マグ。」
「その感動詞で全ての感情が伝えられると思ったら大間違いでございます。」
「マグ。」
「全くいつも貴女の意図は次元が別かと思うくらい図りかねるのでございます。」
そう言って、フェルニーは立ち去る。
馬鹿にしている訳では無い。むしろ褒めているし、その上信用を表している。
「あたし何でこんな暇っ子キャラになってんのよ…。」
「あらあら、出番が多くていいじゃないですか?」
早速セリフがメタいのは、臭素のベル。
「わ、私、ベル自身からは匂いは発せられてませんよ!…確かにその、臭素は臭素ですから発することは出来ますけど、蒸気とか出そうと思えば出せますけど、子供用パジャマとかに私含まれてますからねー!」
「…どうしたのよ急に。」
「いえ、何でも。」
ベルにとっては重要な問題なのだ。ベルにとっては。
暇っ子元素エインは「いやあ、あたしも人気よね〜困っちゃう。」
「暇ですからねえ…。」
「フォローするのか貶すのかどっちかにしなさいよ。」
今日も暇、元素のアイドルエインちゃん。
「だから!暇人キャラ付けんなっての!」
喚く彼女の声は作者の心に届かなかったのでした。
さて、今回二人は神樹の森へと向かっている。
ビアンカから西の岸へ行ったところあたりに、レスティという里がある。森の民の里と呼ばれている。
そして、その中心にあるのが神樹の森だ。
その名の通り、神樹がある森である。
地域の移動なので、やはり列車を使う。
「北西側は街にも緑が多いわねー。」
「何も無い田舎だの言われますけれど、私は温かくていいと思いますよ。」
「ほー…う。」
北側の高地を通っているので当然寒い。世間からすれば不思議な感想なのかもしれない。
まあ、そのような子がいても何もおかしいことはない。なにせ118人118色にしたいから…色なのだ。
「頑張れよ知識発想力妄想力フル活用しろよ。」
「それより、もらった資料の確認しましょ、」
「うぇ?あーうん。」
ベルお姉ちゃんに言われて、カバンから資料を取り出す。
まず、依頼者はレスティの住民たち。
目的は神樹の森の凶暴化した動物達の調査。
その兆候は二週間前からぽつぽつ現れていたのだが、一昨日あたりになって無視出来ないほどになったようだ。死者はまだ出ていないが、怪我人は大勢居るという。
神樹の森の薬草や果実を薬などにも使用しているため、森に入れないと困ってしまうとのことだ。
いつ人里に現れ襲ってくるかも分からないので、何人もが協力して、大掛かりな術式を組んで結界を張っているようだ。しかし長くは持たなそうなのだという。
「ふうん、何だか大変なのね。」
「まあ私たちに依頼してるんですからね。」
「そりゃそーだ。とにかくあたしらはその異常事態について調べりゃいいのね!」
意気揚々と言う。簡単に言ってのけるが、それほど容易いことではない。エインがそれを分かっていない訳ではないが、そんなことは気にしないのが彼女である。
神樹の里レスティ
レスティの駅からも森は見える。
石造りの階段を降りれば、そこはもう森の入り口だ。
「んー、自然いっぱいだわー。」
「ツリーハウスツリーハウス…。」
幻想的だと本にも載る場所ということで、二人とも目を輝かせている。
整備された道の脇には木の柵がある。それほど頑丈ではなさそうで、もともと森の生物たちは穏やかだったのだろうと考えられる。
「観光で来れたらよかったけど。」
「じゃあ終わったら観光しましょうか。写真もいっぱい撮りたいですし。」
「そうね、一刻も早く依頼を達成しないとね。」
まず向かうのは、里の長のもと。
道に従ってまっすぐ歩いていく。
「ようこそおいでくださいました…わざわざ遠くからありがとうございます。」
出迎えてくれたのは、巫女姿の女性だった。
「わたくしがこの里の長、レアです。わたくしどもではどうにも出来ませんゆえ、今回ご依頼しました次第です。」
「けが人が出るかもしれない方を選ぶよりかはあたしたちがやった方がいいでしょう。体は頑丈ですから。」
「大変心強いです。」
得意げに胸を叩くエイン。彼女はこのときすでに目星が付いていたのである。
レスティに近づくたびに強くなっていく何かの力。一つは結界だが、もう一つは…?
エインは一応魔術師の端くれではあるので、力自体は感じることが出来るのだ。
しかしそうだとしても、エインが感じ取れるのなら、その力は隠されていないのだろう。さすがに二つの異なる魔力の識別はできる。
森のどこかに、その術式はあるだろう。
「ふーん、お参りに来るだけあって、神樹の森も一応道という道が無い訳じゃないのね。」
「そうですね…。」
しかし、駅からレスティまでとは違い、この神樹の森の道には柵がない。
「策で仕切る必要が無いほど親しかったのね…。」
動物を殺せば簡単に問題を解決できるかもしれない。その問題とは動物達の凶暴化に限定されるが…。それをしないというのは、里の民は自然を敬い、共存を望んでいるということだろう。
それが実現していたことが、奇跡というものなのか。レスティの民からしてみれば当たり前だったのだろうが。
「うーん、凶暴化したって、具体的にどんななのか聞いておけば良かったわね。」
エインがやる気に満ち溢れすぎていて、飛び出してきたような感じになってしまった。
人に対して襲いかかってくるのか、それとも動物同士の殺し合いがあるのか。何にも構わず暴れ回るのか。
「無駄に傷つけたくはないわね。」
「そうですね。」
とにもかくにも、その実態を見て見ないことにはどうにもならない。
ちょうどその時、草の揺れる音がした。
「あら、何かしら。」
軽い台詞とは裏腹に、神経を研ぎ澄まして警戒する。
音は段々こちらへ近づいてきている。
「…前だわ。」
ゆっくりと、音を鳴らしていたものは現れた。
猫のような、狐のような生き物だった。
しかし様子がおかしい。
足はふるえ、耳はへなりと下がり、すぐその場に座り込んでしまった。
「怪我をしているわ…。」
「随分と弱っています。」
そっと近づくが、襲ってくる様子はない。というより、そのような体力ももう無いのだろう。
「どうしましょう、なにか手当できれば…。」
「ちょっと失礼、君たち。」
「ひい。」
「ほい。」
いつの間にか、背後には少女が立っていた。
桑染色の長い髪、枯れた葉っぱのような髪飾りとドレス。そして左手には緑の杖。
「ふむ、またか。私に任せてくれたまえ。」
そう言うと、少女は杖を動物にかざす。先端が光り輝いたと思うと、みるみるうちに動物の傷が癒えていく。
「…。」
「…。」
「うむ。これでよし」
「えっと、あの…あなたはレスティの方ですか…?」
「そうとも言えるしそうでないとも言える。」
返ってきたのは、極めて曖昧な回答だった。
「私は神樹の森で暮らしている者だ。もしかして君たちが依頼でやって来たという…?」
「そ、そうです。」
「ほう、なるほど…君たちではなかったのか。」
「あの…。」
「おっと失礼したな。私の名はカリハ。神樹の森に住んでいた妖精のはずだったんだが気が付いたらこうなっていたのだ。」
こう、と言われても、特にわかることはない。
「…妖精って、本当に存在したんですね。」
「もうほとんど滅びたがね。住処も無くなってきたし。」
妖精は伝承に登場する存在で、自然の力というものをエネルギーにして暮らしていたらしい。今はそのようなもの、ただの作り話だというのが常識になっている。
目の前の少女が言っていることが絶対に正しいとは言い切れないが。
「それで、その、こう、とは。どうなのでしょう。」
「私も君たちの仲間ということだ。」
「…仲間?」
神様仏様ハロゲン様
元素ちゃんたちはどのように誕生したのか。
エインもベルも、気が付いたらこの姿でいたことしかわからない。ただ、自分は元素なんだなという意識だけがあった。
「考えてみると、確かにわからないわね。」
「だろう?だから、私自身も本当に妖精なのか、そして今の私も本当にカリウムなのかはわからないのだ。」
カリハはそう言いながら、アイスコーヒーを運んできた。
「ありがとうございます。」
「ありがとう。」
カリハは、神樹の森にぽつぽつとある中の大きな木のうちの、ある一本にあるあまり目立たないツリーハウスに隠れ住んでいるようだ。そこの周辺は、妖精の集落だった場所で、一つの小屋に何人もの妖精が暮らしていたという。確かに、そう言われても頷ける広さだ。
空いたスペースで動物を保護できるくらいなのだから。
「そうだ。神樹の森の植生は凄いんだぞ。例えばこのコーヒー豆。こんな所に実るはずが無いのに実る。当然種類は全く違うが。」
「ふうん。凄いわね。」
どうやら、本来この辺りのように冷涼な気候では育たないようなものが、この気候にあった状態で育っているらしい。
「と、自慢は抑えて、本題だな。先程見たように、全ての動物が凶暴化している訳では無いのだ。」
「そうよ。一体何が起きているの?」
「私の推測だがな。」
椅子に腰掛けて、カリハは話し出す。
「何らかの力で、動物たちが凶暴になっている。その力に耐えたとしてもあの様だ。とは言っても、その力が何なのかは分からない。」
「もしかしたら、魔術かもしれないわ…。結界の他にもう一つ、別の大きな力が働いている。」
決めるのは早いが、大いに有り得る。
「ふむ、なるほど。魔術か…。」
「あの、魔法と魔術って何か違うんですか…?」
ベルは前々から気になっていた疑問をぶつけてみた。
「似ているんだがね。イメージだけ言うと、魔法は使うもの、魔術は組み立てるものだ。あと、魔法は自然に深く結びつくが、魔術は魔力に強く関係する。簡単に言えばね。」
魔法に準備は要らない。本人に魔法が使えるのなら、使えるのだ。元素や妖精などは自然との結び付きが強いので、扱える。
対して魔術は、魔力さえあれば誰でも使える。種族は問わず、正しい手順を踏めば行える。
魔力を身に付けられる方法は一応ある。しかし、ほとんど才能が左右する。一度魔力を手に入れれば、そこからは修行を積めば許容量も増えるという仕組みだと考えられている。
「君たちは凶暴化した動物達を見たかい?…ああ、こういう時に人間を外すのは暗黙の了解だよな。」
人間以外の動物だなんて言うと、長ったらしくて面倒だ。そういう意味でも、そのように括ってしまった方が楽なのかもしれない。
「そういえばまだ見かけてないわね。あの子が初めてだったわ。」
「あまり時間もたっていませんでしたし…。」
「そうね。」
「そうかい。」
カリハは考え込んでから、
「やはり、実際に見るが早い。付いてきてくれたまえ。」
出会ったのは、耳が羽となっている兎だった。
「あいつはミミット、聴力を犠牲に飛行能力を得た兎というところだな。」
「…傷だらけ。」
なんとも痛々しい。体中に傷があり、血塗れだった。
しかし先程のとは違って、弱っている様子はない。
「動きさえ封じられれば、治せるのだが。」
「ふうん、そういうことね。」
「あ、じゃあ皮膚」
「を腐食させるのはやめろ。」
「…じ、冗談です。」
ハロゲンはみんなこうなのだ。すぐそういう発想になるんだからー。
「んー、じゃあ眠らせるのってどうよ。あたしが子守唄を歌ってあげるわ。魔術のね。」
「ほう、そんなことが出来るのか。興味深いな。」
「あたしも原理は知らないけど、頭の中に旋律とかが湧いてくるのよね。」
「その方法で行きましょうか。早くしないと健気に待機してくれてるミミットちゃんが不憫ですよ。」
そういうのって言っちゃダメなんだけどハロゲンには関係ないのだ。
深緑の瞳
「効果テキメンね。さっすがあたしの歌だわ~。」
「さて、早く治してやらないと…。」
先程と同じように杖の先をかざす。傷の癒えた動物は、その場で眠ったままだ。
「うーん、でも、原因を突き止めないとどうにもなりませんよね。」
「そうだな。例え全員治したとしても…。」
ミミットを抱き上げながらカリハは首を傾けて唸る。
「…ん?これ…これだわ!」
突然、エインが声を上げる。
「この魔力だわ!私が感じていたのは…!」
そう叫ぶと、走り出した。
「エインちゃん!」
「ま、待て!置いてくなー!」
二人も慌ててそのあとを追う。
「え、エインちゃ~ん!待って~…」
エインは急に立ち止まった。
理由は明確だった。
「あんたは誰なの。」
「…。」
「まさかとは思うけど…。」
どこで聞いたか、エルフという生物がいたという。尖った耳をもつ人型の小神族なのだが、そのイメージと酷似していた。
「…ちぇっ、何だぁ。別の奴が来やがったの。」
金色の短い髪を揺らし、こちらを振り返る。
緑色の瞳が三人を見つめる。
「でも…まだ銀の名があるだけ幸運ね。」
「あんた」
「おっと、何を言おうとしているかはわからないけど、禁忌には禁忌とされるだけの理由があるのよ?」
「…わかってるわよ。」
ベルとカリハには何の話をしているのか理解出来なかったが、わかることと言えば、この二人は知り合いらしいということだ。そして、あまり良好な関係ではないということも。
「で?あんたはこんな所で何をしているわけ?」
少女はくすりと笑った。
「さあ?私にもわからないわ。けれど…もういいわ、言われなくても手は引くわよ。」
あまりにもあっさりとそう告げた。とても信じられることではなかったが、エインの変わらず落ち着いた様子を見ると、本当なのかもしれない。
「…何のためにこんなことを?」
「…さあね?そんなの誰にもわかりゃしないさ。」
そう言って彼女がくるりと一回転したと思うと、いつの間にかその姿は消えていた。
「待ちなさいっ!」
「エインちゃん……。」
オロオロとしながらベルは、悔しそうに息を吐くエインに駆け寄る。
「あいつ…確かね。…あー、なんて言ったっけ。まあいいか。でもあいつの気配は消えたし…何より、あいつの『手を引く』だけは信用していい。」
「…お知り合いなのですか?」
「知り合いっていうか…んー、なんだぁ…?まあ知り合い?よくわかんないけど。あいつの目的も、全然わかんない。」
複雑な事情があるのか、それともただの遠い知り合いなのかはわからないが、エインの言葉はあまりに曖昧だ。
「では、早く動物達を助けにいきましょうか。」
無理に聞く必要も無いと判断し、二人にそう提案する。
「しかし…時間がかかりそうだな、あのやり方だと。」
「うー、この森の中心ってどこ?」
「神樹だ。…恐らく魔力が集まってるはずだが、森の端まで届くだろうか?」
「あたし…歌以外には火とか雷とかぐらいしか完璧に使いこなせないけど、一応不得意な魔術ってのはないのよ。でもあんまり力が強くないの。だけど、魔力を借りれば大きな魔術が出来ない訳でも無い。」
腕を組みながら言うが、それは一つの要求を表していた。
「…ああ、皆を助けるためだ。神も許されよう 。」
キラキラお星様 まんまるお月様
ゆらゆら揺り篭 妖精が揺らすよ
森も眠る 木々が眠る
さあ眠りなさい
夜はこれから 朝はもう少し…
静かに受け継がれる心
「さあ選びなさい。」
提示した選択肢は二つ。Elementsに来るか、ここに留まるか。
「…良いのか?確かお前達は元素たちを探しては引っ捕らえているようではないか。」
「だいぶ曲がって伝わっているのね…。」
Elementsの目的とは、全元素の所在を明らかにするということがまず一つである。
そこから、周りに危害を及ぼすような者がいれば監視をするということになっている。
割と強引に連れ帰ってくる者が居ないわけでも…ないのだが。というかエインにも前科がある。
カリハは友好的で、何の事件も起こしていない。だから、ここに留まりたい理由があるのならば、許可も降りよう。
「ふーむ…。」
それを説明すると、カリハは腕を組んで考え出す。
「ならば…私は遥か昔からこの地に住み着き、生活して来た。ここから出たこともない。そのわけも、この森を守っているからだ。神樹のお世話をしているのも私だ。簡単に離れられる場所でもない。」
「そう…それじゃあ。」
「だから時間をくれ。私はレアに伝えなければならないことがある。教えなければならないことがある。神樹を守るための術を、レスティを守るための術を。それさえ教えられれば…私も安心してこの場を離れられる。」
レア…レスティの長にして、神樹の巫女。
廃れつつある神樹信仰を復活させるため、巫女の代わりに様々な儀式を行ってきたカリハが、それを伝え直す。
そのための時間だけが欲しいという。
「…ふーんなるほど。多分オッケーは出ると思うわ。そういう風に伝えておく。」
「私達は戻りますので、またいつかということになりますね。」
「ああ、すまないな…動物達を助けてくれてありがとう。」
「いいのいいの、お仕事ですから!」
「お仕事ですので!」
二人は、カリハに手を振って歩き出した。
レスティの人々に見送られて、汽車はビアンカに向け走り出した。
「お邪魔になるから観光はまた今度ねー。」
窓の外を見ながら、エインは名残惜しそうに呟いた。
「ええ、そうですね。」
エインは窓側の席に座っていたので、ベルにその表情は伺えなかった。
蝋燭の炎
日は落ち、月明かりと街灯に照らされているビアンカの住宅街。周りと比べて明らかに豪華な家の、ある一室。
コトン…と静かに音を立て、ティーカップが机に置かれた。
「ありがとう…。」
ぎこちなく紅茶を口に含み、飲み込む。
「それで。」
お盆を持ったメイドは顔を上げる。
「今はマグナが番をしているので構わないのでございますが…、ここまで来てお話することとは一体何でございましょう。」
「フェルニー…その、実はね。」
高級そうなソファーに腰掛け、緊張したように肩を狭めているのは、エイン。
「今日、会ったの…あいつと…。」
「…あいつ、とは?」
「覚えているかしら…いえ覚えているでしょうけど。金髪緑眼のエルフ…。」
漠然とした情報だが、フェルニーにはそれで十分にわかった。それは、表情が険しくなったことから伺えた。
「…ああ、彼女と。では先程の報告にあった謎の女というのは。」
「ええ。そいつよ。」
「彼女がついに目立って動き始めた…と。」
「また始まるのかしら。」
「いいえ。そんなことは私どもがさせません。そうでございましょう?」
「…ええ、ええ。そうね。だってこんなに暖かいの…こんなの初めてだから。絶対に守らなきゃ!」
立ち上がって拳を握りしめる。
「ふふ、ご報告ありがとうございます。こちらでも何かしらの対策を練りますので…、あら。」
ガチャリとドアが開く音が聞こえてきた。誰かが帰ってきたのだろう。
「ちょうどお嬢様がお帰りですね…。夜道は暗いので、くれぐれもお気を付けくださいまし。」
「…ええ。ごめんなさいね急に。でも少し気が楽になったわ。」
帰り道、ふと気がついた。
フェルニーはお嬢様が帰ってきたと言った。しかし、自分は誰ともすれ違わなかった。居たのは一階の入口近くで、すぐ部屋を出たのだから足音ぐらいしてもいいはずだ。⋯いや、それは本当に偶然で、考えすぎなだけかもしれない。
しかし、フェルニーが誰かに仕えているという話は聞いたことがない。あの家ならお金持ちが住んでいてもおかしくはないが、一体どのような人物なのか。
知らなくても特に問題は無いのだが、何だか気になる。
「…こんなこと考えたってわからないわね。」
どうでもよい疑問は放り投げて、真っ直ぐギルドの寮に帰った。
蝋燭の炎がゆらりと揺らめく部屋。
「先程のお話ですが…。」
「ええ、彼女は聞いていませんよ。私に聞こえなかったのですし恐らく。」
「…あなたにはお伝えしておきます。くれぐれも…。」
「彼女も含め口外厳禁ですね、わかっています。」
「ええ。よろしくお願い致しますわ、」
極秘任務
✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼
突然のお手紙、失礼致します。
私は、ミデレーリアに暮らすもので
す。この度、あなたがたにお頼み申
し上げたいことがあり、このような
形でご依頼させていただくこととな
りました。
というのも、私は事情があり、ミデ
レーリアから出られないのです。
事情について詳しくお話すると長く
なりますので、申し訳ありませんが
省かせていただきます。
さて、それでは本題に入らせていた
だきます。
実は今、極秘に調査していることが
あるのです。ある方からの頼みで、
口外は厳禁だと言われています。
その方は、あなた方に直接ご依頼す
ることが難しく、こうしてわたくし
が代わりにお頼み申し上げているの
でございます。
このような状況なのですが、もしあ
なた方がこのお手紙を読み、お話を
聞いてくださるというのであれば、
どうかミデレーリアにお越しいただ
けはしないでしょうか。
明日午後八時、以下に示す場所で─
✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼
その場所を確認して、手紙を畳む。
もとの古びた封筒に戻して、目の前の女性に渡す。
「へえ、それで、その任を私たちにということかい?」
「そうマグ。君たちが適任…らしいマグ。」
「…私がか。別にいいけど。」
フララとチエ。突然呼び出されて都会風の服を着せられたと思ったら、今の手紙を読み上げて聞かされた。
「マグナに文句言うんじゃないマグ。二人を推薦したのはスイジーマグ。」
誰を向かわせるかフェルニーと話していたところ、スイジーが提案してきたのだ。
「ほう。」
「フララを挙げた理由は知らないけど、チエはもしものための常人枠って。」
「知ってた。」
チエちゃん強く生きて。
「とにかく、頼むマグ。」
小さな司令官は人差し指をビシッと突き出しながら言う。
時計の針は、もうすぐおやつの時間を指そうとしている。行くとしたらそろそろ出なければならないだろう。
「りょーかい。」
「はいはい、承知した。」
二人分の列車のチケットを渡され、ビルのひしめく大都会へと出発する。
大都会ミデレーリア
ミデレーリアへは、列車に乗って数時間かかる。
草原を抜け、山を抜け、そして木々が少なくなれば大都会へと到着する。
その頃には、もう午後七時。夏なのでまだ少し明るかった。
駅から出ると、看板を重たそうに持った高層ビルや、気だるげに走る車、機械仕掛けのように歩く人々が目に入る。
「…私はこんなところでは暮らせそうにない。」
チエが溜め息混じりに言うと、フララも苦笑いをして返す。
「同感だね。」
地図を確認し、目的地へと向かう。
「にしても、スイジーが、か。」
人々の隙間を縫いながら、チエがぽつりと呟く。
「珍しいことなのかい?」
「ああ。珍しいというか、こういうことは一度も無かった。」
「そう。…彼女は博識聡明と聞いたが。」
「それは間違っていないだろうな。」
もしかすると、今までもマグナに助言することがあったのかもしれない。
「彼女は…大事にされているね。特にあの少女に。」
「…ああ。あいつは優しすぎるんだ。あんなことがあっても尚、性善を信じて疑わない。頭は良いが、馬鹿ってことだな。」
全く仕方の無い馬鹿だ、と、楽しそうに笑う。
「そうなのかい。」
フララもその様子を見て、柔らかく笑みを浮かべる。
チエはもう一度地図を確認すると、前方にある建物と建物の隙間を指さす。
「…そこの路地裏に入ってすぐだと。」
隙間へ入っていくと、手紙の通り、ネオンの看板が置いてあるお店が見えた。
Dreamy Bar…メルヘンチックな名前だ。
「店名も間違いなし。じゃあ入るか。」
ドアに付けられた鐘を鳴らしながら、引いて開ける。
「あら、いらっしゃ〜い。」
木の板の床、橙色の照明。木製のカウンターに立つのは、ポニーテールの若い女性。
「初めてみる顔ね〜。…あ、もしかしてメアちゃんの言ってた待ち合わせ相手?」
「お、恐らく…?」
依頼主の名前はメアというらしい…人違いでなければ。
「大丈夫、彼女からしか予定は聞いてないから。じゃあここの椅子にどうぞ〜。」
そう言って、五つしかないカウンター席の端っこを指す。
「ビアンカからよね。ご苦労さま、」
「いえ、そんな…。」
「私の名前はネオラ・モンティーギュ。出身はセレネメンティアだけど、あまりにも退屈な環境だから、こうしてバーのママさんをしているの。」
退屈というのは、人間関係のことだろう。セレネメンティアで暮らすといえば、貴族がほとんどだ。そんな世界でのカチカチした人付き合いより、こうしてフレンドリーに接する方がいい、ということか。
彼女のにこやかで柔らかい態度から、そう予想した。
「あら、もうすぐ四十五分…そろそろ来ると思うわ」
待ち合わせの十五分前。自分たちが言うのもなんだが、早めに来るタイプの人間のようだ。
そして、ネオラの言った通り、ドアが開いて、少女が入ってきた。
「こんにちは、メアちゃん。この二人みたいよ、」
ジト目が特徴的な、黒い髪に、焦げ茶の触り心地の良さそうなケープとワンピースを着た少女。
見た目だけ見れば、十八歳ぐらい。
チエもそうだが、路地裏に入る時に誰も不審がらないのだろうか。いや、誰も見ていないか。
「…。」
メアと呼ばれた少女は、黒い瞳で二人をじっと見つめる。
「えっと、こんばんは…?」
「…こんばんは。」
ネオラに手招きされ、二人の隣に座る。
「このような遠い街まで、わざわざ来て頂いてありがとうございます。」
恭しくお辞儀をする。
「いいえ、どうってことありませんよ、」
「それで、その…。」
「ああ、待ってね。」
メアがネオラに目配せすると、ネオラは思い出したように店の外へ一瞬出た後、戻ってきてドアの鍵を閉める。
「これでOK、看板の明かりも消したし、誰も来ないでしょう。」
「ごめんなさいね、」
そういえば、聞かれてはまずいような話と書いてあったような。
「ええと…こほん。改めて、私がお手紙を差し上げました、メアです。こちらへお越しいただいたのは、他でもない、極秘調査をご依頼するためです。」
続けられたのは、衝撃的な言葉だった。
「前女王シェーリ様のご息女…三姉妹の末の、ミリス様より言伝を預かりました。」
ミステリアスレディ
「現女王陛下は、長女クリス…様。そしてミリス様との間の、次女ティリス様。彼女についてのことです。例の噂はご存じですか?」
そういえばスィエルが何か言っていたような。確か…、
「行方不明だとか。」
フララが言った。そう、それだ。
「…その通り。残念なことに、それは事実です。」
「なっ…!」
唖然とするチエ。フララは、驚いた様子はなく、冷静だ。
「私の第六感には嘘じゃないみたいだね。」
「第六感…。ふふ、なるほど。」
僅かに微笑むメア。
先程から思っていたが、このメアという少女は不思議なオーラを纏っている感じがする。身の上についても話すと長いと言うし、一体何者なのだろうか。ミステリアスの擬人化か。いや、無いな。と、心の中でも突っ込みを欠かさないプロフェッショナル、チエ。
「それで…調査をしてほしいのは、もう想像が着くと思います。」
もちろん、ここまでの情報だけでも容易だった。
「ティリス様を探す、ということだね。」
「ええ。ミリス様は…無事であることが確認できればそれで良い、と仰っております。」
連れて帰るわけではなさそうだ。
もし無事だったとしても、行方をくらますぐらいの事情があったことに違いない。そこを無理矢理連れ帰るのもよろしくないだろうということか。
「うん、わかった。確かに承ったよ。」
「…くれぐれもお気を付けて。継承時の事件なんて、ロクなことじゃないでしょうから。」
「…エルスメノス王国憲法第一章第二条。それに触れるようなことがないことを切に願うばかりだねぇ。」
「??」
「…王位は、継承法典に基づき受け継がれる。この厳粛な継承が汚された場合、国の定める法により厳しく罰せられる。」
「ああ…なるほど。」
よく覚えているものだ。それにしても、自分たちは暮らしている土地のルールを知らないのによく生活出来ているな、と思う。世間で言う真っ当な人間として生きてゆけば、触れることは無いのだろうが。
とは言っても。
「憲法…軍隊を持たないなんてのもあったっけ。でも、元素が集まれば軍隊みたいなものだな。」
「だからこそ、非武装を宣言できたようなものだがね。敗戦国だけが軍を奪われることに異を唱えた唯一の大国。まさか自分も軍を捨てちゃうとはね。」
「その代わり、国境警備とかが強化されたけど。」
海は海上警備隊がパトロールし、孤島には積極的に人を住まわせ、陸の国境は陸上警備隊が目を光らせている。
そしてそこに、元素が集まっていることでの圧力のようなものが加わる。
「国境警備隊は立派な軍隊だから無くせーと言う奴もいるが、要は国土を危険に晒せと言っているようなものだな。軍隊と捉えること自体には反対しない。しかし、現実を、周りにある国を考えてみろという話だ。それに国境警備隊にかけられているお金なんて、他国の軍隊と比べて圧倒的に少ないのに。」
周りにある国で特に危ないのは、戦の国とも呼ばれるセイントセント。未だに核兵器を保有している。確かに、貿易での結び付きが強いが、攻撃されない保証はない。
北の国ヴィザーパンも、あまり友好的な関係を築けているわけではない。
「憲法で定められているからね、自衛のための戦力の保有のみを許すって。まあ、そこに穴があるんだけど。⋯と、無駄話が過ぎたね、失礼。」
「構いません。」
メアはくすりと笑う。
「…ビアンカは、良い所でしょう?」
「そうだな…。」
「元素が集まる地としては、最高さ。あそこを見捨てて他の国に行くことなんて、私にはできないね。」
それを聞くと、メアはとても嬉しそうな顔をした。
姫君の行方
「…良かったじゃない。」
「あら、私が選んだのだから当然でしょう?」
「ふふふ、そうね…。」
暖かな照明の下、少女たちはくすくすと笑った。
「さて、とりあえずどうする?」
バーを後にし、来た道を戻る。
「国境警備は厳しいから、身分を明かさずに通ることは不可能に近い。ほとんど魔術師で構成されているから、普通の軍隊の包囲網より強固だろうね。ま、話のわかるやつがいれば別だけど。国内の…人間の生活地帯から離れている、森とか谷とかが怪しいね。」
依頼主メア、正確にはミリスからは、何ヶ月かかっても良いと言われている。
とはいえ、出来るだけ早い方が良い。他の元素の協力も得て、探すべきだろう。
「…連絡するか。」
小型の連絡機を起動し、耳に当てる。
「……もしもし、チエだ。…ああ、フェルニー。実は…。」
窓から外を眺めていた。特に何を見ようとしたわけでもなく、ただそこに窓があったから。
答えは単純でいい。
「雨は嫌い?」
後ろのソファでくつろいでいるであろう少女に投げかけてみる。
「嫌いじゃないよ、好きでもないけど。」
あまりにも彼女らしい答え方だった。
「…そう。」
善と悪、美と醜、愛と憎、生と死、そして白と黒。
融通のきかない奴は、ある特定の決まった形でしか物事を判断出来ない。
人間だとかそれ以外だとか、見た目が一緒ならどうせ分からないのに。言わないとわからないくせに。
きっと、猫や鳥の形をしていれば、受け入れられたのかもしれない。
人間と似たように生活して、人間と似たように考えて、だけどそれは、人間の形をしているだけで全く別の存在。
でも、だからといって何なのか。
何の問題があるのか。
何故、嫌悪の対象となるのか。
別に理由などどうでもいいのだが、こちらには実害があるので迷惑千万なのである。
危険?いつ、こちらが手出ししたのだろう。お前達が勝手にこちらを襲撃するから、追い払っているだけなのに。
つくづく、都合が良い生物だ。
理論武装をして、意地でもこちらを害とする。
その努力は、もっと他に使い道があるだろうに。全く、妙なところに頭を使うものだ。
「君は?」
「え?」
「君はどうなの?」
私、私は…。
「好きだったわ。…来客が少ないから。」
これもまた、私らしい言い方というものなのだろうか。
ふわふわ
「ローレ、見てー、お花畑だよー。」
「…ああそうだな。」
やわらかい。
「あ、ローレローレ、ちょうちょ!」
「そうだな。」
やわらかい。やわわわ。
ここはアルシャフネリーの北西に位置する、ブロッサムフォレスト。名前の通り、いたるところにお花が咲く森である。
「ところで貴様。何をしに来たかわかっているのか?」
薄い金色のポニーテールを指で払い、少女は問い掛ける。
彼女はローレライ。ゲルマニウムだ。
「ふぇ?」
そしてもう一人。月白の三つ編みおさげを揺らし、振り返る。
彼女はケイ。ケイ素。
「もっちろん、わかってるよー。お姫様を探すんだよね!」
ふにーと笑う。やわらかい。やわやわ。
「…分かっているならよし。」
厳しいようで甘い。それがローレライである。
「まさか気体じゃあるまいし、誰かが通れるような道だよね。でも、ここまで歩いてきたけど、誰も知らないって。」
誰も、というのは、すれ違った動物達。魔法という訳では無いのだが、柔らかい性格からか喋れるらしい。
「ふむ。…ブロッサムフォレストは、身を潜めるにはあまりお勧めできないような場所ではあるな。」
きっと、見つからないようにしているはずだ。ならばあまり人が来ないような場所が望ましいだろう。且つ、人間の力でも行き来出来る場所でもある。
「そうだねー、人は多いわ、人が少ないところといっても険しいわで大変だ。」
「…でも仕事は仕事だ。しっかり探すぞ。」
決められたことはきちんとこなす。それがローレライである。
そしてこちらはフィスプ南方のさえずりの森。キュオルとユキエが捜索中である。
「ここを探す必要があるのか?」
「念には念を、と言うでショウ?」
それに、徒然なりたる元素ちゃんはたくさんいるのだ。そんな元素ちゃんの中には、むしろ進んで引き受ける者もいた。やつら、真面目にやりつつ手を抜くという器用な方法を心得ていたりするのである。
とはいえ。さえずりの森は人通りも多いし、木の密度も低い。隠れられるような場所はほとんどないだろう。
「…あんまりかからなそうだな、時間。」
もっと広く、隠れる場所がありそうな所を探している元素はさぞ大変だろうなあ、と完全他人事に考える。
例えば、ミデレーリア南西の妖魔の森、ミデレーリア南東の精霊の森。そして、中心山岳部の南東側に広がる…果実の森。
果実の森
果実の森。エルスメノス王国の中心山岳部の南東側に広がる、色鮮やかな木の実で有名な森である。
そこへ捜索に来たのは、
「あなたが赴くだなんて、珍しいわね。ギルドの事務は?」
澄み渡った空色の瞳の少女。
「マグナが残っているので大丈夫でございます。」
笑みを崩さないメイド服の少女。
「私と一緒で疲れない?」
「ふふ、あなた自身がいなくとも錆びる危険はございますので」
オウカとフェルニー。酸素と鉄である。
「それに、彼女の提案したことですから。」
「彼女のねえ。随分甘いじゃない、彼女に。」
「彼女の前では金すらデレデレ、でございますから。」
「あらそう。」
「あなたも、あの娘に甘いではありませんか。」
「だってあの娘は私とくっつきたがるから。」
「そんなことおっしゃって…。」
少し沈黙が流れる。そして、打ち合わせをしたかのように同じタイミングで目を合わせる。
「「可愛いからに決まってるじゃない(ですか)〜!」」
あははうふふと、幸せそうな顔を浮かべて森の中の道を歩く。
二人は元素ちゃんの中でも特に真面目な方なので、仕事はきっちりこなす。
だから、たった今見つけた無人らしき屋敷にも突撃する。
「ドアノブが風化してしまっていますね。」
「強く引っ張れば開きそう…えい。」
開いた。
老朽化が激しいのは、見ただけで十分にわかるほど。そんなボロボロな屋敷の中に入ると、広い玄関に迎えられる。青いカーペットには、埃が積もっているのが目視で確認出来る。所々に小さな足跡があるが、森の動物が隙間から入り込んだのだろうか。
「カビとかは生えてなさそうだけれど、人のいるような気配は無いわね。」
雨に降られただろうし、どこかしらに出来ていそうなものだが。見た目の老朽具合からみても、びっくりだ。
「二階へ上がってみましょうか。もし一階を経由せずに行ける方法があるとすれば、可能性はあるはずです。」
「そうね…獣道の先にあるんだもの、人なんて寄り付かないし…。」
二階へ続く階段が二つあるが、それぞれの先に廊下が繋がっているため、分かれた方が良さそうだ。
「わたくしは左へ。」
「じゃあ私は右。」
階段を上がり、反対側の探索を始めようとする相手を確認すると、そっとスカートのポケットに手を伸ばした。
地下洞窟へ
扉を開けた。
綺麗に整った家具と、やはりそれに積もる埃。
壁際のシェルフに、目的のものは置いてあった。
(…これは!)
それは、写真。誇りを払ってよく観察する。
写真には、二人の少女と老夫婦が、笑顔で写っている。
一体なぜ、このような場所に?
疑問が浮かぶのは当然のことだった。何しろ写っていたのは…。
「あら、フェルニー。早いわね。」
「何もございませんでしたので。」
「…そうね、こっちも。」
本当にただの放置された屋敷だった…。
「あとは地下ね。」
と決めるのはまだ早いようだ。
「地下があるのですか?」
「恐らくね。正確には空洞っぽい何かが。普通の地面とは思えないくらいの原子の存在を感じたわ。」
元素ちゃんは、自分を表すそのもの…要は同じ種類の原子の存在を、察知しようと思えば、それが可能である。
オウカは、先程自分が探していた方の階段下まで歩いていく。
そして、そこに敷かれているカーペットを退ける。…凄い埃だ。
するとなんということだろう、…目視では何も見えない。
フェルニーも近づいていく。
「綺麗に隠してあるようだけれど…。」
オウカは、床板に手を付き、くるりと捻った。すると今度こそはっきりとした変化が起きた。
床板の一部が回転したのだ。
「しかし、持ち手がないと開けにくいですね。」
「そうね…。」
「うーん、仕方が無いですね。」
フェルニーは、スカートの中を漁り出したと思うと、金槌を取り出した。そして、それを振り上げる。
「壊しましょう。」
床板は無残に散った。
「なるほど、ドアと同じでね。」
消えた床板の先には、ぽっかりと穴が空いていた。
…これはフェルニーのせいではなく、元からあったのだろう。
「降りましょうか。」
遠くにに小さな光が見える。
「ええ。」
オウカが飛び降り、少し間を空けてフェルニーも飛び込む。フェルニーは魔法では飛ぶことが出来ないが、魔術なら話は別だ。
「着いたっと。」
「えいこらさっと。」
器用に着地する。
そこは、四角い部屋だった。
洞窟に手入れが施されている。
「…明るい。」
「松明がありますね。」
ということは、今も誰かがここにいるのだろうか?
落ちてきた穴の反対側には、道がある。
しかし、そこに明かりはなさそうだ。
「…仕方ないわ、私が松明代わりになる。」
「わたくしにはあまり近づけないでくださいまし。」
オウカは手を広げる。そして、そこに小さな炎を生み出す。
フェルニーがオウカの後ろを歩き、通路を進んでいく。
嘘も方便
赤髪の少女はソファに座っていた。気だるげな目の先にはテレビが置いてある。
一体どのようにして電気を通しているのやら⋯。
「ふむ、雨ですか。道理でじめじめするわけです。」
「お姉、ここら辺はそんな変わんないと思うよ。」
ソファの後ろから、黄緑の瞳の少女が顔を出す。同じく真っ赤な髪である。
「うーん、それもそーですね。でも外に出たくはないですし。」
「もー、お姉ったらぐうたらー。内職しかしてないしー。」
「三人の可愛い妹が頑張ってくれているからです。私は幸せ者です。」
「そうやって褒めたって何にも出ないけどお仕事行ってくるからね!」
「行ってらっしゃいですー…」
いつも頑張ってくれている末っ子に手を振りながら、ソファの横に置いてあるダンボールに手を伸ばす。
中には、ビーズなど、アクセサリーの材料が入っている。
「さて…、始めま」
「おーねーえーちゃーんーっ!」
小さな少女が、レーザービームのごとく飛んできた。
「大変、大変なのっ!奥から人が!奥から人が!」
「落ち着けです、ゆっくり話すです。」
「うん、あのね、お姉ちゃん…。」
時は少しだけ遡る。
「この先には明かりがあるわね。水の音がするから、水の通り道がありそう。」
「そうでございますね。少し登ってきたような気がしましたが。」
オウカとフェルニーは、既に10分ほど歩いていた。そして、ようやく広間へと出れるようだ。
広間の入口には、柵がある。
扉などは着いておらず、跳び越えるしかなさそうだ。2人はひょいと、いとも容易く越えた。
「まあ、こんな洞窟に大きな川。」
「本当でございます、水汲み場のような…。」
木の桶が置いてある。近寄ってみれば、最近使われたのだろう、湿っているのがわかる。
「今も誰かがこの辺りで暮らしているようでございますね。」
「こんな地下にねえ…日の光を浴びたくないヴァンパイアとか、逃亡中の犯罪者とかかしら?」
「ふふ、冗談とも言いきれないのでございます。」
恐ろしいことを言いながらも、笑顔は崩さない。
「さあ、先へ進みましょう。」
次の通路は、随分と様子が違った。綺麗に人の手が施されている。つまり、先程までのスペースはほとんど利用されていない、ということだ。
「…だとすると、あの炎は魔術とか魔法の類いってことになるわね。」
「あら、やはりそうでございましたか。」
落ちてきた部屋にあった松明。魔術や魔法でも、炎のようなものは生み出せる。現の炎か虚の炎かは見分けがつかないが、元素的に二人にはわかったのである。
「…ところで、この先が行き止まりだったり見知らぬ場所に出たりしたらどうす」
「風を感じてください。」
「善処します。」
そんなこんな話しているうちに、次の部屋も見えてくる。この通路よりも低くなっているので、はしごでもあるのだろう。
と、その時。
「そこにいるのは誰ですか。」
少女の声が響いた。道の先からだ。
その正体を確かめるため、二人はそこから飛び降りる。
空洞の中にいたのは、赤毛の少女。
「全く、どこから鼠が入り込んだのやら…。」
「入口…裏口?からです。」
「落ちてきました。」
正直なお二人だこと。
「テルー、報告を。」
少女は呼びかけると、どこかで足音がしたと思うと、遠ざかっていく。
「そのまま受け取るとすると、三人以上はいるようですね。」
「このようなところまでやってくるだなんて、一体何が目的なのです?」
「人探し?」
「そうでございます。」
何とも正直なお二人だこと。
「人を探してここへ、と?」
「いやまあ。」
「偶然と申しますか。」
恐ろしく正直なお二人だこと。
「………。」
おかしいね、正直に話しているのに冷たい視線を向けられているよ。嘘も時には役に立つと言うけれど、本当らしいね。
「…さては組織の人間ですか。」
果たしてなんの組織なのかは分からないが、恐らく人違いだろう。
「組織には所属しているけれど。」
「ええ、確かにしているのでございます。」
そうそう、Elementsという組織に…果てしなく正直なお二人だこと。
「ならば覚悟は出来ていますね…?」
おっとすれ違いが生じてしまったような雰囲気だ。正直さ故に。
少女がペンライトぐらいの棒を取り出したと思うと、次の瞬間、カッ!と、まるで剣を成すように赤い光が放たれる。
「どこかの映画で見たことがあるような。」
「それ以上は駄目です検閲により私たちが作者もろとも削除されてしまいます。」
ひえっ…やめとこ…。
「その口から漏れる言葉を、組織の情報にしてやりますっ!」
小さな身体が、レーザービームのように飛んでくる。
歯車グルグル
二人の居た場所を切り裂いた赤い閃光。
「あら、なんとお速いこと。」
ひらりと優雅にかわすと、
「オウカ様…ここはわたくしにお任せを。」
「この先に一人で…?やめておいたほうがいいと思いますよ、私は楽になりますが。」
「ええ、楽にして差し上げます。」
不思議でいっぱいのスカートの中から、取り出されたのは錆一つない鉄パイプ。絶対に収まる長さではない。まあこの世界には魔法があるからね。おかしくないね。
「じゃ、私はとっとと先へ行くわ。」
危機感なく言うと、ふわりと浮き上がり風のように去る。
少女に特に焦った様子はない。先には何かがあるのだろう。しかし、オウカがそう簡単にやられはしないと信じられた。
「さて、それでは失礼致します。」
鉄パイプを握ったまま微笑んでお辞儀をすると、次の瞬間その姿は消えていた。
「…!」
少女は本能的にその場から離れると、右側から風を感じた。
鈍い音と共に、床に打ち付けられたパイプがひしゃりと曲がる。
「あらぁ、外してしまいました。」
鉄を曲げるほどの威力で殴ろうとしたのか。可哀想に、少女は怯えている。
フェルニーが曲がった鉄パイプをすっと指でなぞると、まるで柔らかくなったかのように元の真っ直ぐな形へと戻っていく。もちろん腕力などではなく、鉄原子自体を動かしているのである。
「さ。さてはあなた…森羅万象研究所の生物兵器…。」
「断じてそのようなことはございません。」
全く、元素に向かって兵器だなんて失礼な奴だ。それに、あの忌まわしい研究所の。ぷんぷん。
「あなたこそ。その名を知っているとは、まさか研究所から(研究が嫌になって)逃げたクチでございますか?」
「…ええそうですよ(狙われていたので)逃げて来ましたよ。」
すれ違いを感じる。
「何と…それでここに隠れ住んでいるのでございますか。」
「そうです。せっかく追っ手をまいたというのに、捕えられてたまるものですか。」
「わたくし共に手出しをしないのなら何も致しませんが。」
「手を出したのはあなた達です。私たちは研究の試料になどなりたくないのです。」
「研究の資料にされてしまうのですか…!?人間でさえ、わたくし共と同じように身をちぎられ…。」
「…。」
「…。」
ようやく、何か噛み合っていないことに気がつく。
「あなた、その金属棒をどのように元の形に戻しました?」
「あなたも、その赤い光は魔法ではありませんか?」
「魔法です。」
「わたくしも魔法です。」
歯車の歯がカチリと揃った。
少女は、赤い光を静かに無くすと、恭しくスカートの裾を持ち上げて、一礼。
「私の名前はエリー。ランタノイドの仲間、エルビウムです。」
「まあまあご丁寧に。わたくしはフェルニー。Elementsより参りました、鉄でございます♪」
フェルニーも深々と頭を下げる。
「Elements…コヨビから耳にした事ならばあります。」
「あら、詳しいお話はあまり届いておりませんか。」
「…恐らく、ずっと前から地下で暮らしていたからかと。」
「なるほど…。」
「しかし、先程の彼女を追わなければなりませんね。」
「オウカ様…酸素でございますね。」
「この先には私の姉がいます。余計な争いごとは起こしたくありません…それが私達の仲間となれば尚更です。」
となると、今から二人が行うことは限られる。
オウカを追って、走り出した。
それが平和かはわからない
「侵入者ですか…?」
「うん、今エリーが足止めしてるの。」
赤髪のポニーテール少女は、その緑色の瞳の上に不安げにまぶたをかぶせる。
「わかったです。すぐに向かうです。」
立ち上がり、ポンと少女の頭に手を乗せる。
「テルーは入口の確認をするです。」
「わかった!」
テルーと呼ばれた少女は、再び走り去る。
(エリー、今すぐ…。)
まさに駆け出そうとしたその時だった。
『待ってください。』
頭の中で声が響いた。
「…これは、さっきの子の声?」
階段を上っていたオウカにもそれは同じように聞こえ、速度を緩めながら耳を傾ける。
「…エリー?」
そして、勢いよく走っていた幼い少女にも。
「もし争いがあるならば、それは無駄なものです。もしまだないのならば、決して生み出してはいけません。…つまり。」
回りくどく言いながら、フェルニーに声が届いているであろうことをグッドサインで示す。
エリーは、ある程度の範囲にテレパシーで一方的に話しかけられる魔法が使えるらしい。
「私はエリー。エルビウム。私も含めここにいる者は、あなたたちの敵になろうと思わないはずです…。」
「…ま、私達も迷い込んだだけだからね。」
よく良く考えればただの侵入者であった。
「なるほど。」
その声は、階段の上から聞こえた。独り言を言っていたら近くに誰かいた時ってすごく恥ずかしいよね。
「さてはあなた、穴から落ちてきたりしたですか?」
「いかにも。」
「やはり、どこかに通じていたんですね。あの空間は何か嫌な感じがしたので柵をして行かないようにしていたんですが。」
「壊してはないわよ。越えただけ。」
「です。」
「でも、別にデストロイしに来た訳では無いの。」
どこかのお鉄様がデストロイモードに入りかけてはいたが。
「…私は酸素。名前はオウカ。人探しをしていたら迷い込んでしまったのよ。」
「人探しですか…。」
ようやく、真っ直ぐ伸びた赤髪の少女がその姿を現す。長袖短パンジャージ姿は、その気だるげな表情とマッチしていた。
「私はユイ。イットリウムです。十数年程前から、この人のいない空洞に住み着いていましたです。」
「十数年前…?」
「はい、この空洞は元々あったものです。ですから、最深部の穴のことは私も知らないです。何のために作られ、そしてどこと通じているのか。」
「…森の洋館よ。恐らくただの隠し通路ね。」
どのように使う気でいたのかまではわからないが。
「…それで、探し人とのことですが。」
「ああ…。」
「ここには私達四姉妹以外は居ないです。」
「四姉妹?」
「長女の私に、双子の次女エリーとテルー、そして末っ子のコヨビ…。今、コヨビはお出かけ中ですが。」
「そう…。何だか押しかけて悪かったわね。」
「いえ、こちらも事故とは知らず妹が失礼したです。」
深々と頭を下げられるが、エリーとかいう少女は何も悪くないような気がする。
「お姉様。」
後方から声がする。振り向くと、そこにはエリーとフェルニーの姿が。
「どうやらここには、彼女はいないようでございますね。」
「ええそうね…ちょうど聞いたところ。」
「果実の森は見当ハズレだったかもしれません。」
「他のみんなに期待ね…。」
ユイは二人の様子を見て、
「さて…。さっきお湯を沸かしたです。コーヒーぐらいしかないですが。」
「あら。」
「飲んでくですか?」
「それじゃあ…お言葉に甘えて。」
元素であることがわかっただけで、争いが一つ消えた。彼女たちには、必死になって守れるような命がないからだろうか。ある種の無気力であるために、無駄な争いを避ける。
それにしても、守りたいような命とは一体どのようなものだろう。
ユイは、ふと考えた。
妖魔の森
「睡眠が要らないからって、すぐに探索に向かわされるなんてねえ。」
「いいだろ、どうせ近いんだから。」
ミデレーリアから少し離れた場所に、ダークブラウンの樹木で埋め尽くされ、空は葉により遮られる陰鬱な森がある。
妖魔の森。
いかにも、妖の類いが現れそうな雰囲気ではある。
そして、フララとチエは、直接そこへ向かわされていた。
しかし、ここも探そうと提案したのはフララである。言い出しっぺが責任を負わされたのだ。
「…確かにこんな場所、人は寄り付かないだろうな。わざわざここを通らなくとも、鉄道があるし。」
地面には、苔らしきものも見える。ジメジメしているし、彼らにとってはちょうど良い環境だろう。
「魔女の住処と言われてもいるからね…。」
「魔女…?」
「ああ。この森は、エルファーリン、アンジェル、ミステカに囲まれているだろう?だから、魔女が住んでいるという言い伝えだけが残っているのさ。」
妖精の村エルファーリン。
神託の郷アンジェル。
そして、魔女信仰の総本山ともいうべき、魔女の村ミステカ。
三つの地域の伝承の中には、同一存在であろう魔女が登場し、妖魔の森で暮らしているという。
魔女は最初、恐れられていた。しかし、魔女は人々に恩恵をもたらした。金属の鋳造法や、薬の作り方などの知識を。
また、妖魔の森に迷い込んだ者たちは、魔女と出会い、無事に帰ることが出来たと言う。
それらの記録が、やけに生々しく語り継がれていた。
昔の人々にとって、魔女は尊敬の対象だった。しかし、今はどうだろう。科学技術の発展は目覚ましく、魔女の恩恵が当時どれほど有難かったものかなどと考える人はいない。となるとやはり、魔女というのは、人を捕って喰う恐ろしいイメージを抱かれ得る。
「なるほどな…そんな話があるのか。」
フララの説明を興味深そうに聞く。
長く語り継がれれば、周りの環境も変化する。その本質の変化など、よくある事だ。
「…とにかく、不気味な場所ってことだね。」
「そんな不気味な森に何の用?」
前方からの声だった。
道の橋の草むらから、一人の少女が飛び出てくる。
薄黄色の髪と赤い目。見た目の歳は十代前半あたりか。
「妖魔の類いかね?」
「間違っちゃいない。」
少女は、右の手のひらを上に向け、横にまっすぐ伸ばした。すると、背後にナイフが浮かび上がる。
「だから、帰りな。ここは人間の来るところじゃない。」
「悪いね、生憎こちらも妖魔の類いで。」
フララは、いつもの服ほど広くはない袖口を自分の口に添えながら言った。
「居なくなったお姫様の安否を調べに来ただけさ。それさえ済めばすぐに帰るよ。」
その言い方は、まるで。
「居なくなったお姫様ねえ…。何かの比喩?」
「いいや、比喩じゃない。その依頼が正式に来たんだよ、Elementsまでね。」
「Elements。なるほどね…。」
まるで…。
「そんなの見つかるわけないじゃん。どっかで平和に暮らしてるみたいでしたーって報告しときゃいいのに。どうせわかんないよ。」
「ああ、そうだね。確かにそれでもいいかもね。」
とても遠回しな会話。
なるほど、確かに言い出しっぺはフララだった。
最初から、知っていたのか。ティリスがどこにいるのかを。
フララなら有り得ない話ではないのがまた恐ろしい。
しかし、あの少女は一体誰なのだろう。妖魔の類だというが⋯。
「もういいでしょ、探したって見つからないよ。とっとと帰りな。」
「そうだねぇ…見つからないなら、探しても無駄なだけ。早く帰って早く報告しちゃおうか。」
「…そうだな。」
いつも軽く言っているが、預言とは何なのだろう。
神が授ける言葉というのはわかるが、一体どの神だろう。この世界には神が多すぎる。固有の神は存在しないとしたら、わざわざこの世界の住民に預言をするのは何故か。ただの気まぐれで済んでしまうかもしれない事だが。
そんなチエの思考も、とある場所にまでは至らなかった。そう、自分たちがここへ来ることとなった原因は…。
銀のような需要が高い元素に休みなんてねぇ!
「失礼します。」
開いた扉の先には、少女の姿。
「ご指示の通りに、全て致しました。」
ごめんなさいね、と少女は言う。
「いいえ、構いません。私も驚きはしましたが…。」
少女は座ったまま振り返り、言った。
本当は自分が行くべきだったのだけれど、それでは怪しまれてしまう。誰かにバレてしまっていたかもしれない。
「…お気になさらずとも良いのですよ、あなたのために、この身を捧げる覚悟をしたのですから。」
ごめんなさい、ともう一度謝ったあと、間を置き、はにかんで、ありがとうと付け足した。
そして、翌日。バー店主のネオラを通じて、依頼主と再び落ち合った。
「さすが、お早いお仕事ですね。」
「いいえ。多人数の強みってやつです。」
この前とは変わって、今回ミデレーリアへやってきたのは、エイン。
「…穏やかに暮らしているのですね。」
「はい、みたいです。」
「それなら良かった。」
そう言いながら、メアはコップに注がれた透明な紫色の液体を一口、飲み込む。ブドウジュースだろうか。
「…彼女にとってはとても煩わしい世から逃げ出せる、あまりにも突然舞い降りてきたチャンスだったのでしょう。」
女王だからと身内とさえ騙し合い、欲望まみれの大臣に囲まれて。顔色を伺って生きなければ待つのは陰謀の刃。…こう考えると、一般の人々の生活にも似たようなものがあるのでしょうか。彼女にとっては、今の方が幸せなのかもしれない…いいえ、そうに違いない。
そう語るメアだが、果たして彼女は王家となんの繋がりがあるのだろう。ミリスの遣いなのか…もちろん、公のものでなく。もしかすると非常に高貴なお方だったり…?
「…お礼はギルドに送らせてもらいます。本当に有難うございました。」
「あ、いえいえ!ご依頼には最善を尽くすってのがウチのギルドなので!」
昨日は神樹の森で迷子になってカリハに助けられていた奴がよく言うものである。
「それじゃあまた、何かあったら遠慮なくどうぞ!」
「はい、有難うございます。」
「お疲れ様~、バーにはまた来てもいいのよ?」
「そうですね、いつかお邪魔させてもらうかもしれません。」
ぺこりと軽く礼をして、店を後にする。
「…ふう。まだ朝の八時か。」
店を出ると、明るい空が細いビルの隙間から覗けた。
他には用事はないことだし、真っ直ぐギルドに帰ろう。
そう思い、大通りへ出た。
「あ…。」
壁際に、一人の少女が立っていた。
「あら、スイジーじゃない。付いてきてたの?」
「あっ…、その、依頼主が気になっただけ…。」
あわあわしながら、絞り出すように言った。
…さては誰にも言わずに来たのか?
「依頼主なら、まだ中にいると思うけど…会う?」
「…いえ、…やっぱりいい。」
「そ、そう?」
ここまで来たのに結局会わずに帰るのは無駄足であると思うのだが…。本人がそう言うのならそれでも良いだろう。
「そ、それと…本題、というか。」
「ん?」
「あ、あなたが出発してすぐ、依頼があって…。その件で、お呼び出しがかかっているの…。」
「あたしに?」
「そう、あなたも…。」
「あたしも!?」
…きっとフェルニーの指名に違いない。なんと銀使いの荒い鉄だろう。
緊急招集
「あー、疲れた。」
「疲れたしー。」
列車に揺られる、スィエルとシータス。
たった今、仕事を終わらせてきたばかりである。
「馬車の護衛って寒いんだね。」
「自分の来ている服を見てみろしー。」
「ずっと同じ体勢でいないとだから大変。」
「お前割りと自由に動いてたしー。」
「帰りは自力だし。」
「それはいつもだしー。」
「すやぁ。」
「もうすぐ着くし寝るなしー。」
気の抜けた声が、空席が目立つ列車内に響いている。
そのまま二人がだらんとしていると、次の駅が近付いているとアナウンスが知らせる。
「すやぁ。」
「置いてくしー。」
「やだ!!起きる!!」
列車はビアンカの駅で止まり、二人は降りていく。
駅を出ると、商店街だ。
ふと、人混みの中に見知った顔を見つけた。
あの銀の髪と輝きたいオーラは忘れたくても忘れられない。
あちらも気付いたようで、手を振って駆け寄ってくる。
「二人とも!やっと来たわね!」
「どうしたの、エイン?」
ミデレーリア帰りのエインである。ちなみに一緒に帰ってきたスイジーはエルシーに回収されていった。
エインはビシッと人差し指を伸ばして二人の前に突きつける。
「緊急招集よ!あんたたちも連れてくるように言われたの!」
「おお来たか、待っていたぞ。」
会議室の扉をノックすると、キュオルが出迎えてくれた。
「おかえりなさいませ、スィエルさん、シータスさん。依頼主から報告は受けているのでございます。」
部屋の中を見回すと、どうやら他にも呼ばれている元素は大勢いるようだ。
「急に何があったしー。」
「…さて、皆様揃いましたのでご説明いたします。」
険しい顔つきで、フェルニーは話し始める。
「緊急の依頼とのこと。場所はハーミ近くの森の中。ハーミの方々より、近くで怪しい動きをしている奴がいるという情報が入っております。これは前にもあった事で、その時は何者かもわからない集団によりハーミは壊滅状態になったそうで、今回も同一集団ではないかと考えていますそうです。」
ハーミ。ビアンカを海沿いに南へ行った辺りにある、辺境の里。
「キュオル、エイン、スィエル、シータス、オウカ、チエ、エヌーゼ、あと…エルシー達。」
「どうして私達は一括りなんですか?」
エルシーは素早く抗議する。
「…。」
フェルニーは沈黙する。そしてやっと口を開いたかと思うと、
「それでは皆様、準備が出来しだい出発なさってください。」
「間を空けておいて無視しないでください!」
「い い か ら ど う ぞ ご 準 備 を ?」
「はい。」
物凄い圧に負け、その場にいた全員はほとんど逃げるように部屋をあとにした。
「…ふふ、この私をそう簡単に欺けると思いまして?」
パタンとファイルを閉じる。それは、昔の書類。
目を光らせながら、少女はにやりと笑った。
黒い布から透ける正体
「…ねえ、私たちどうしてこんなことになってるの?」
スィエルが首を傾げながら訊ねる。
「さてな、知らん。」
キュオルが感情のない声で答える。
「あたしの追っかけと見た。」
エインがボジティブに捉えて言う。
「違うと私が保証してやる。」
チエがその希望をを無残に崩す。
「何だか可笑しな人たちに絡まれたわね♪」
エヌーゼが楽しそうに言う。
「この世に生まれ落ちたことがかしら。」
オウカが淡々と言う。
「…オウカ、ハロゲン並みの刺々しさだしー。」
シータスが小さな声で言う。
「あはは何かおっしゃりました?」
本物のハロゲン様がのたまう。
「…刺々しい。」
スイジーがボソリと呟く。
列車を降りた瞬間この有様だ。
黒装束集団がわらわらと湧き出てくるではないか。
「巣から這い出る蟻のようだな。」
「こいつらがアレ?ハーミに危害を加えるっていう集団?」
「我々はその手下だ。」
突然、黒装束の一人が口を開いた。なんと素直な悪者だこと。悪役依頼された人でももう少しうまく演出できるのではないか。
「し、シャベッター!」
「スィエル落ち着け!普通のことだ!」
「我らの野望を打ち砕こうとはなんと愚かよ。」
「我らは崇高なる理想のために」
「我らの主の仰せのままに」
「我らの気高き意志は」
「だあーっうるさい!敵だってんなら殴る!」
「エインよいつからそんな野蛮になった!」
元からだと思う。
「私…皆より戦闘苦手なんですけど⋯♪」
「エヌーゼ。こいつら基準にしちゃダメだから。」
「その暑苦しい黒装束を燃やしてあげましょうかしらねえ。」
「オウカ。ここは森だ、やめろ。」
チエが安定のお守り役らしい。
「…だが。知っている事は全て吐かせるから手加減しろよ。」
お守り役の許可が降りました。突撃!
…というわけなのだが。
「お話になりません。」
「口程にもないな。」
「きゃ♪私勝っちゃったわぁ♪」
「鬼め…」
結果は言うまでもない。こいつらは軍隊ともやり合えるであろうし。
「ぐ…。」
黒装束が一人逃げ出そうとした。
しかし、その足は直後に停止する。
「逃げるな。お前らには聞きたいことがたっぷりあるからな。」
足には白い煙がまとわりついていた。
「あ、熱い…熱いっ!」
「おっと温度を下げすぎたか。」
「チエちゃんあなたさっき私に鬼って言ったわよね…!?」
チエによって生み出されたそれは、0度など軽く下回る。凍傷なんてお手の物なのである。
息を乱してもがく黒装束に与える慈悲など持ち合わせていなかったらしい。心の温度0ケルビンだからね。
「…と、こういうのは私には向いてないな。…エルシー頼む。」
「ちょっとどういう意味かわかりかねますがわかりました。」
「ちっ、下の下の下の下ですか。ろくな情報持ってやしませんね。」
気絶した黒装束を放り投げ、悪態をつく。
何か話したとしても、人によって言っていることが違ったりした。下っ端だから何か変な教団の思想を理解しきれていないのか、それともバラバラなだけなのか。
どちらにせよ、まともな情報はない。
「社会から迫害されて辿り着きでもしたんですかね。」
「エルシー本音出てる実はさっきから割と出てるけど本音出てる。」
「はっ、私とした事が…。」
転がる黒装束たちを置き去りにして、一行は里へ向かう。慈悲などない。
道以外に人の手が加わっている様子はない。ひらひら落ちた紅い葉までそのままだ。
「…もう、長之月も終わりますね」
長之月が終われば神之月がやってくる。すなわち十月である。
「あー、新しい元素と出会えないかなー。」
「でも、最近はやけに新しく見つけまくってるしー。」
「チート能力もった奴が来たからな。」
いったい何ランシウムなのか…。
「来たぞ!」
唐突に響いたその声に驚き、ビクッと全員揃って立ち止まる。
「いらっしゃいましたか皆さん!」
「ああ助かった!」
進行方向から聞こえてくる。先に見える人影はハーミの人々だろうか…。こちらに手を振っている。
「ささ、皆さまこちらへ!」
随分と距離が離れた歓迎となった。
辺境の村ハーミ
「………。」
「どうしたんです、何だか落ち着きがないですね。」
今、スィエル、シータス、オウカの三人が詳しい話を聞きに行っている。後ほど、話し合ったことも含めて伝えられるらしい。
そしてここは宿屋の一室。ハーミの人々が無料で貸してくれている。
エルシーが部屋に戻ると、何やらスイジーが挙動不審だったということで先程のセリフに至る。
「な…なんだか落ち着かなくて。」
「…。」
「…。」
じーっと見つめるエルシーとたじろぐスイジー。
「話してください。」
「…。」
「話しなさい。」
「はい…。」
気迫に負けて、渋々スイジーは口を開いた。
どうやら、誰かに見られているような気がするのだという。ただ見られているのではなく、身体にまとわりつくような視線を感じるらしい。
「…はあ、そうですか。」
「でも、もしかしたら気のせいかもしれないから」
「とりあえず。」
スイジーの言葉を鋭く遮る。
「何があっても絶対に私の側を離れないでください。ったく、探しに行く身になってみろって話です。」
「うっ…。」
迫力に負けて頷く。
スイジーの孤立癖は筋金入りだ。水銀だけど。
「大して面白くないです。」
「ひねりが感じられない。」
うっ…。こほん、その理由も、他人を巻き込みたくないという理由ではなく、そもそも誰かに相談するという発想に至らないことが多いのだ。その点、非常に厄介だろう。
しかし、自分に対しては、何かを話そうとして躊躇っている様子をよく見せる。頼りにされていると思っても自信過剰ではないだろう。エルシーは表情ひとつ変えずに、心の中で呟いた。
「…座ったらどうです?」
「…ええ。」
二人は柔らかそうなソファーに腰掛ける。
いつからだったのだろうか。相当怯えているようだ。
尋ねてみると、スイジーは、
「列車に乗ってから。」
と答えた。
「えーまず、敵の素性は不明。目的も不明だが、前例もあり、良くない事であると予想できる。近くの森に廃墟があるらしく、そこが怪しいとのこと。さっきの件もあるから、早めに突撃したいところだけど…一晩様子を見るわ。見張りを置く。交代でね。」
オウカはスラスラと話し、次に見張りの担当について続けた。
「静かねえ…♪」
もうすぐ12時。エヌーゼとチエは見張り台の上から村中を見ていた。
誰かが見張っていると言うだけで、相手も大胆な行動はしないだろう。バレたくないとすれば。
…例の黒装束はとてもオープンで、相手から素性を明かしてくれたが。
「不気味なくらい静かだな。ハーミに来てから人間以外の動物を見ない。」
「何か事情でもあるのかしら♪」
前にも襲撃を受けたと聞いた。その時から、環境が変わってしまったのかもしれない。そういえば、家畜も一匹もいないそうだ。もはや生存すら難しいということか。
そう考えると、ハーミの人々は苦労しているだろう。何せ、辺境の里と言われているほどなのに肉類は全て他の地域から送られてくるものに頼り切りなのだから。
近くにある…と言っても遠いのだが、工業都市マーキャンデリは畜産を全く行っていない。
「今どき、食肉は全て他地域から貰ってるなんて場所は珍しくないがな。」
「あらでも、それは大抵それなりの都市よ?」
「お二方。」
12時。日付が変わる。交代の時間だ。
「ああ、よろしく頼んだ。」
エヌーゼとチエははしごを降りていった。
「…さて。」
交代したエルシーとスイジーは、見張り台の椅子に腰掛ける。
「…行きましたね。」
それを確認すると、エルシーは通信機を取り出す。
「……。」
少しすると、声が聞こえてくる。
『はい、…こちらも近くまで来ております。確実に圏内には入っていますが、もう少し時間がかかりそうです。』
「そうですか…、気をつけてください。」
「さっき、謎の集団に襲われたの。恐らく奴らでしょうね。」
『 あら、そうなんですの?ええ、十分注意いたします…それでは。』
プツンと通信が切れると、再び通信機をしまう。
「ふう…、どうですか?」
スイジーは目を閉じ、神経を集中させる。
「…北北西に人影一つ。その他に活動している気配なし。」
つまり、今の話し相手以外は起きて活動をしていないということだ。
それなのに。
「あなたは?」
「まだ感じる。」
生物ではないのだろう。だとするとまさか…。
一つの推測が頭をよぎる。しかし、それはあまりに…自意識過剰といったようなものなので、やはり言わないでいた。
「で。」
「で?」
「はい。」
「ここがあの教団のハウスね!」
目の前にはぽつんと建つ四角い建物。人の気配はない。
本来ここは警戒するものなのだが、
「ん?このドア立付け悪いよ。」
「そりゃあ廃研究所だしねえ。」
こいつらに緊張感なんてなかった。
いきなりドアを開けて中を探る。RPGの勇者か。
「でもこんな狭い廃墟を粗探ししたところで…何ですか?」
エルシーが突然言葉を止めたと思うと、スイジーが何か耳打ちをする。
「地下…ですか?」
「地下か?」
「地下だしー。」
「地価ね♪」
「エヌーゼだけ何か違う気がする。」
でも文字だからわからないね。
チエちゃん今日もお疲れ様っす。
「えっと、廊下の突き当たり…、霊魂に反応して開く術式がある。」
「霊魂…えっと、つまりどういうことだしー?」
「その…霊魂というのは、各々の存在を表すもの。私たちにもある。決して同じものは無いし、…基本的に失われることも無い。あの術式はつまり、顔認証システムのようなもの。」
言うなれば、霊魂認証システムか。
しかし、そうだとすると問題が発生する。
「どうやって開けばよいのだろうか…。」
キュオルのその言葉は、質問というよりかは零れたというようだった。一つとして同じものはないのなら、そのロックを外すことは不可能ではないか。
しかし、スイジーに困った様子はない。
「…こじ開ける。」
弱く言い放つと、廊下を進んでいく。そして、何も無い壁にすっと手をかざす。
「………。」
何かを囁いたような気がしたが、聞き取れたものは誰一人いなかった。
するとなんということだろう、青色の光が浮かび上がってきて、扉が現れた。
「すごーい!」
「はえー。」
スィエルとエインは興味津々に眺めていた。
「まあ、よく分からないが道は開けたんだな。ありがとう。」
「…いいえ、構わない。」
いつも冷たいチエがお礼を言った。
「何だか今失礼なことを言われた気がする。」
それこそどうでもいい話だ。
「…。」
扉を開くと、先は地下へ続いているであろう階段になっていた。
壁は青混じりの灰色で、青い線のような照明は近未来という感じがした。
一本の通路を歩いていくと、分岐路に辿り着いた。
「じゃあスィエルとシータスと私はこっち。」
あいあいさー!と元気の良い二人。息ピッタリである。
「あたしとキュオルはこっちでいいわね。」
ふんす、とやる気に満ちている二人。
「じゃあ、チエとエヌーゼはあっち。」
オウカが通路のひとつを指す。エヌーゼはひらひらと手を振り歩き出し、チエも頷いて追いかける。
「スイジー、エルシーはそっちをよろしく頼むわ。」
「わかりました。」
通路は長く、それぞれ先の様子はわからなかった。
研究所
「どう?開きそう?」
「ええ、ただちょっと面倒ねえ…、私はこういうの専門じゃないから時間がかかりそう。」
エヌーゼとチエは、いかにも厳重ロックされていそうなゴテゴテした扉の前にいた。
恐らく何かしらのキーがあるのだろうが、もちろんそんなもの持っているわけがないので解体まがいに開かなければならない。
「うーん、ケイでもいてくれたらねぇ。」
「ああ、あいつはこういうのに強そうだからな。」
「ふええっくしょおん!」
「大丈夫か?」
「あい…かじぇしいだがもでふ。」
「すごく鼻が詰まっているぞ。」
Elements。何とも特徴的なくしゃみをしたケイを気遣う、ローレライ。
…あれ、何か微妙にデジャヴ?
「あ。」
「…何か間違えたという意味ではないよな。」
「開いたわ♪」
ほっとため息をつくチエ。
しかし、こんなに厳重にロックして、一体何がこの中にあるというのか。
そっと扉を開けてみる。
そこにあったのは…、
「なんだ…紙や本が山積みに…?」
「ふーむ、これは…研究室かしら♪」
資料には、グラフや表がちらほら見える。
中には、原子力発電所の安全運転についての資料や、どこかから盗んできたような核兵器の構造に関するものまであった。
「原子力発電所の資料はどうでもいいけど…この図面が気になるわね♥︎︎」
よく見てみると、ある部分に印がしてある。爆弾部分のようだ。
「何だこれは?解体方法が書いてあるが…。」
「それはね、私らが放射性物質を拝借するための計画図みたいなものさ。」
「ふーん…。」
あれ?
後ろに誰かいる。なんと解説してくれた。
ゆっくり振り返ると、白衣の少女がいた。
二つお団子が目立つ、眼鏡の少女。
「あの厳重引き篭もりロックを解除するとは、恐れ入ったよ。」
気だるそうな顔で言いながら、少女は眼鏡をクイッと押し上げる。
「む…?そもそもここへの入口は認証式で現れたはず…。」
首を傾げてぶつぶつと何かを呟いている様子だが、やがて何かを思い出したように両手をパンと合わせる。
「それより、こういう時は…。」
チエは身構える。
「逃げよう。」
少女はダッシュで部屋から出ていった。
「今の絶対戦闘開始のノリだっただろ!」
そのツッコミが彼女の元へ届いたか…それは定かではない。
「じゃあこの部屋漁ってから追いかけましょ?」
「…好きにして。」
「さっきの子、放射性物質を拝借するって言ってたけど…どう拝借するのかしら。」
資料に目を通しながらエヌーゼが呟く。
「兵器ごと持ち出す…だなんてことは流石にないだろうけど。」
そんなことが出来ては国家転覆どころじゃない大危機である。
「ま、この図面から見て、本当に放射性物質だけを…っていうかほぼウランとプルトニウムだけど。それらだけを抜き取っているのかもしれないわねえ。」
さっきの少女の言うことが本当なら、わざわざ放射性物質と限定したのは、そういうことなのだろう。
一体何故国際問題に発展しかねない盗みを働くのか。ウランやプルトニウムを集めてどうするつもりなのか。そもそも、どのように遠くから運んでくるのか。不思議なことが山積みだ。
しかし、あまりよろしい話ではなさそうなのは明白だ。
ウラン、プルトニウム…まだ会ったことは無いが、同胞たちが虐殺にでも使われたりしたら、それは二人にとっても黙っていられないことである。
「とにかく。もう読み終わったろう。後を追って問い詰めればいい。」
少々乱暴だが、効率的ではある。相手がすぐに話してくれれば、だが。
少女はすぐに見つかった。
「な、なんだ…わわわわ私悪いことしてないぞ。」
「他国に盗みを働いているヤツの言うことじゃない。」
敵にもツッコミを忘れない、さすがプロである。
資料に記されていたのは、隣国セイントセントの核開発研究所の情報。
「放射性物質を集めて、何をするつもりかしら?兵器でも作るの?」
「そんな!…そ、そんなことはするわけないだろ。」
一瞬声を荒らげたが、すぐに淡々と喋り出す。
「あらあら、でも放射性物質を集めて出来ることなんて限られてるわよねぇ♪」
「…はあ、なるほどな。」
チエはエヌーゼの意図を察したようだ。本当にいい性格をしているな、と心の中で毒づく。
「放射能というのは、人間の害となる能力だ。放射能に限った話ではないな。兵器を作らなくても、そこにあるだけで周りを毒し命を破壊する」
「チエちゃん待ってあなたさり気なくえげつないわよあとそれエルシーの前で言ってみなさいズタズタにされるわよ。」
「まさか本気で思ってるわけないしそんな被虐に悦びを感じたりしないし問題はない。」
かっくんかっくんと揺さぶられながら、心の温度0ケルビン疑惑が浮かびつつあるチエさんが申しております。
煽って煽って情報を引き出そうとしたが、なんか駄目だった。ほんわり失敗した。
「…ふむ。」
放っておかれている少女は、何かに気づく。二人からはそこまで敵意が感じられない。むしろ友好的に接することが出来るのではないか。
潜ませておいた攻撃用の機械の電源は切らずに、こちらから歩み寄ってみる。
「こちらとしては戦闘は嫌でね、疲れるし苦手だし痛いし。とりあえず君たちの目的を聞かせてもらえるかい。場合によっては、こちらのことも話そう。」
癖なのか、眼鏡をクイッとして、そう言った。
Argentum
「薄暗いわねー、ここ。」
「照明が青くて神秘的だな。」
「…神秘的っていうかSF?」
雑談をしながら廊下を歩くエインとキュオル。やっぱり緊張感がない。
とは言っても、決して警戒していない訳では無い。何しろ、通路を闊歩する警護ロボでもいそうな雰囲気であるのだから。
「うーん、開きそうな部屋はないわね。」
先程からいくつもドアを通り過ぎているが、どれも機械的なロックがかかっていて、外せそうにない。
「やはり、あのいかにもバトルフィールドな空間に行ってみるしかないんじゃないか?」
「そうねえ…。」
通路の先に、空間があると思われるような光がある。
「…そうよねえ。」
ちょっぴり苦笑いしながら、先へ進んでいく。
予想は的中した。
先にあったのは、メルヘンな部屋。壁は明るい桃色で、パステルグリーンのフカフカ絨毯が敷かれている。
ぬいぐるみやクッション、そしてロボットがたくさん置かれている。
「…だぁれ?」
そして一人の少女がいた。
「どろぼうさん?」
「…かなぁ?」
「泥棒ではないんじゃないか?」
「?」
疑問符を浮かべられている。
「うーん。」
「誰だろうか。」
「???」
疑問符が増殖している。
「はてさて。」
「わからんな。」
「?????」
疑問符パラダイス。
「でも、しんにゅーしゃはゆるさないよ。」
考えることを放棄したのかそう言うと、少女の手の中に槍が現れる。
「幼女に物騒なものをもたせおって。」
「ブーメラン投げてるっていうのは黙っておいた方がいいのかしら…。」
残念ながらキュオルの武器はブーメランではないが。
「パルチだって、たたかえるもん!」
少女の叫び声に呼応するように、ロボットたちが動き始める。
「ええー多い!機械に歌は効果ないからキュオル何とかしてー!」
「何だって。」
「うー、これなら硫化してた方が戦える。」
「…はあ、全く。ならばその少女は任せたぞ!」
「お安い御用!」
キュオルの手に、巨大な棒付きキャンディーのような武器が現れる。金瓜錘だ。
まったく、幼女に危ないもの持たせおって…、って持たせてるの作者か。
「ただの金属と甘く見るなよ、魔法の銅なのだからな!」
重たい鈍器を軽々と振り回し、ロボットたちを薙ぎ払う。
ロボットも反撃をする。遠距離から、光弾を撃つ。
キュオルは武器から片手を離すと、掌を突き出し、青緑色の炎を放つ。
それらは光弾にぶつかると、光弾もろとも消滅する。
攻撃するには小さいが、防御としては十分だ。
「さあて少女よ。このエイン様に年齢なんて関係ないから!」
大人気ない。なんと大人気ない。
といっても、槍を振り回すくらいなら、普通の少女ではないのだろうが。
「パルチ…まけない!」
少女は槍を構える。対するエインは、小さく呪文を唱え、右手に炎、左手に雷をまとわせる。
「電気伝導に熱伝導、トップレベルの魔術を見なさい!」
槍をかわし、炎撃と雷撃で応戦する。
(…その炎と雷で機械と戦えばいいんじゃないかな。)
心の中でキュオルが呟いたのを察してか、
「…私魔術師としてはど底辺だからそんなに相手したら魔力持たないの。」
とても生気のない顔をしてぼそりと呟いた。
「そうか…範囲攻撃は得意だし構わんだろう。」
金瓜錘で、早速ロボットの半数が片付きそうだ。
「にしても器用なもんねー。その槍、身長より大きいんじゃない?」
「そうだよ。でも、おねーちゃんとれんしゅーしたからへーきなの。」
エインの質問に律儀に答えてくれる少女。良い教育を受けているようだね。
「へえ、お姉ちゃん?」
「いつもいそがしいのに、パルチのためにじかんをつくってくれるの。」
「あらそう、いいお姉ちゃんね」
「パルチのおねーちゃんだもん。いいおねーちゃんにきまってるもん。」
「姉想いなのねえ、ご両親もいい子に育てたもんだわ。」
(あいつら何で普通に話しているんだ。)
映像はとても激しいが。
「…パルチにパパとママはいないよ。」
「え?…っと!」
一瞬動きが鈍ったが、すんでのところで避ける。
「パルチ、めがさめたらきのしただった。」
攻撃が弱まる。
「そしたら、おねーちゃんがとなりにいた。」
動きもゆっくりになっていく。
「おねーちゃん、パルチにいった…。」
その少女を容赦なく打ちのめしたりはしない程度の大人気はある。
「『 私は君から産まれたようだ』。」
少女は完全に攻撃をやめた。同時にロボットも停止する。
「パルチ、わからない。どういうことなのか…。パルチはどうやって、どこでうまれたのかしりたいけど、おねーちゃんにそんなこときけない…。だっておねーちゃんはいそがしいから。」
声を震わせしょんぼりと俯く。
「でも、こわいよ…。」
心細そうに零す彼女に、エインはいつかの少女を重ねていた。
「…わかんないよ!全然わかんない!」
泣きじゃくる少女。
「私は誰なの?どうして私は皆と同じように生まれてこなかったの!?…嫌よ、自分のことがなんにもわからないなんて!!」
そんな少女は、その後なんと言われただろうか。
(確か…。)
「私も自分がどうやって生まれてきたかわからない。」
「エイン…?」
「でもそんなの気にしなくたっていい。これから自分を創っていけばいいのだから。」
二人しか…いや、もしかすると自分一人しか覚えていない言葉。そして、そこに自分の言葉を付け足す。
「あなたはこれから何者にでもなれる。自分を、自分の好きなように彩れる。生まれた場所になんて縛られることない。だけど怖いわよね、自由は。だけど心配しないで、あなたには頼れる素敵なお姉ちゃんがいるんでしょ?」
「…わたしを、これからつくる。」
「そ。だから怖がらないでいいのよ。」
近づいても逃げないのを確認すると、前まで歩いていき、屈んで頭を撫でる。
(…リチェやルルがエインに懐いているのはこういうことか。)
幼女に優しいエインお姉ちゃん。という言い方をしただけで何だか変な響きになる。言葉の力は凄いのですね。
エインが放つのは、金ほど眩しくはないが、暖かい輝きである。
(おや?でも私にはそこまで優しくないような…。)
Elements


