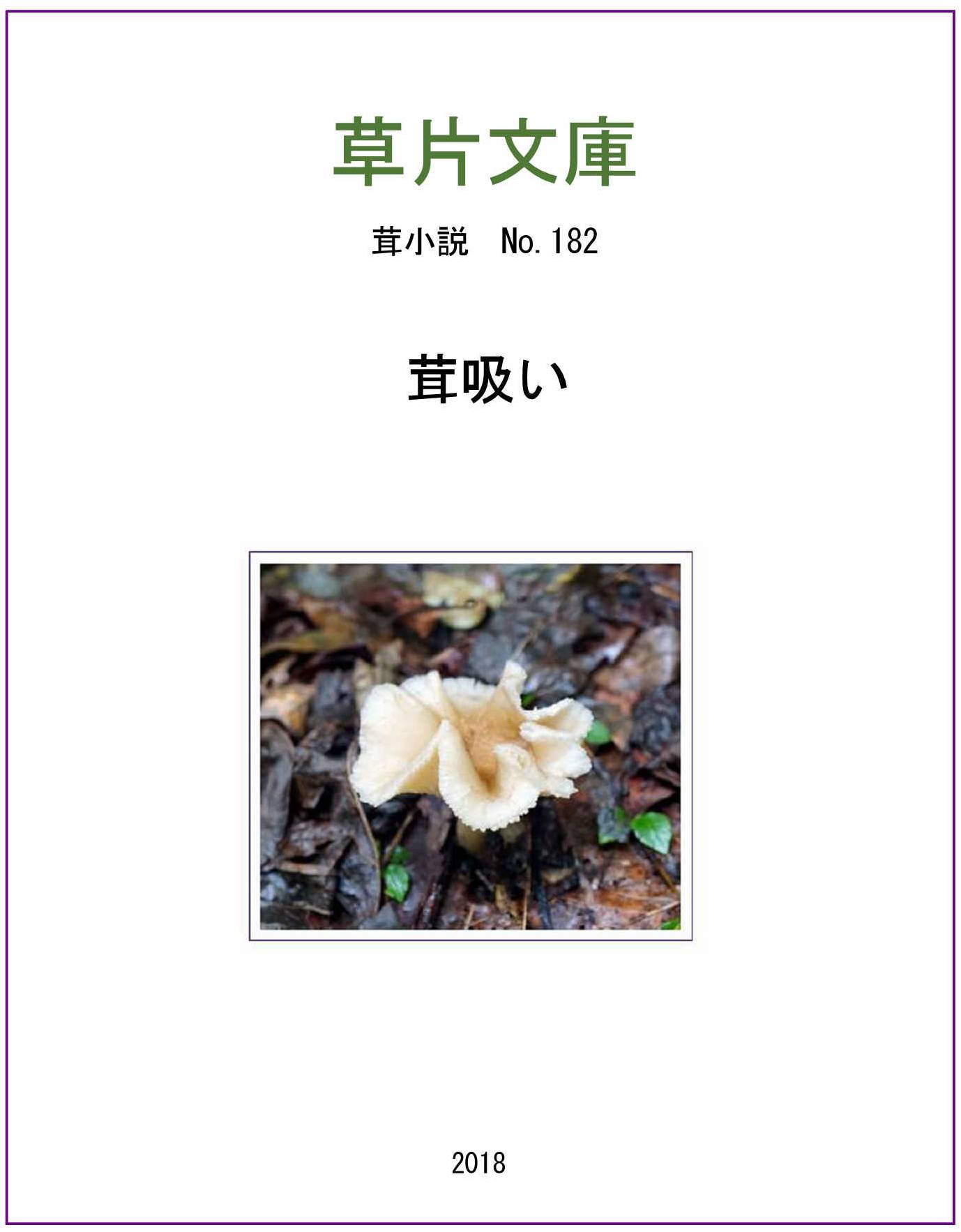
茸吸い
昨日、ちょっと奥山さ行って、いつもの赤松の林にはいると、落ち葉の間から立派な松茸が頭をだしていてな、葉っぱをかき分けると、ずいぶん大きな奴だった。そいつを採って、周りを見ると、やっぱり輪っこになっててな、立派なやつが六本も採れたんだ。羊歯の葉っぱにくるんで籠に入れてな、大喜びだわさ、くろんぼも何本か採れて、それで帰りがけに、脇の林で滑子まで見つけちまってね、飛んで家に帰ってきたんだ。山をひとつ越え、谷川に降りてな、近道して家に帰ったんだわ。
家でかかあが首長くして待ってたんでな、まず滑子とくろんぼをだして、さて、羊歯に包んだ大きな松茸を見せてやろうと思ったんだ。
それで床の上で羊歯をひらいたら、そりゃ見事な松茸が全部で六本ならんだんだ。かかあは大喜びじゃ。一本は二人で分けて食べて、残りは明日朝市にだすべということになった。
ところが驚いたね、かかあが松茸を一本もちあげると、「なんじゃ」とおかしな顔をした。
「どした」と聞くと、かかあは松茸を下から覗いたんだ。
「やられとる、このあたりでも出るようになったんじゃ」
と青くなった。
なんだと、おらも松茸を手にとって驚いた。紙のように軽いんじゃ、下から見ると松茸の中はがらんどうで、薄い紙で出来ているようじゃった。
「なんじゃ、これは」
おらは他の松茸を手に取って見た。みな同じだった。風船のようにふわっとして、中身がなかった。
かかあが言ったんだ。
「これは茸吸いのしわざだね」
かかあの田舎は山を三つ越した隣の村だが、その村には昔から茸の中身を吸い取るという妖怪がいたそうだ。
かかあが話してくれた。
かかあの村はここより奥山で、田圃にできる土地はそれこそ猫の額ほどしかなく、祭りやお祝い事があるときに使うくらいの米しか穫れなかった。だからみんなしてその田んぼで米を作り、分け合って使っていたんだ。畑はそれなりにあったが大した収穫はなかった。それで村人たちは山で穫れる菜や実、それに茸、鳥や獣、魚を獲って暮らしていた。それでも何とか食べていけたし、気持はなかなかゆったりした良い村じゃった。
昔々の話じゃが、村にやっかい者が一人おって、その男は年のころ十六ぐらいだったろう、人を傷つけるような悪さはしないのだが、家の脇にしょんべんをひっかけたり、長い舌でなめようとしたりするので、気味悪がられていたんだ。全く言葉はしゃべらんかった。だがその男の子がそうなったのにはわけがあった。
その男は平太といって、そのあたりでは、みなが頼りにしていた古くからの家の子供だった。その主人も家族もいい人たちで、周りから好かれていた。村の大事な人たちだったのだ。ところが平太が五つのころだっただろうか。野武士がこんな山奥まで襲ってきおってな、平太の家のものはみな殺しにされちまった。
平太はただ気絶していただけで、命は助かったんだ。村人たちが介抱してなんとか息を吹き返したのだが、口をきかぬようになっちまった。
平太が九つになるまではなにくれとなく村人たちが世話をしていた。村人が食事を運んだり、家を片づけたりして助けていたのだが、村人たちもそれぞれに仕事や事情があり、次第に平太にかまう時間が少なくなった。
そんなこともあって平太は十になったころから自分で畑を作ったり、山で食料を探して一人で生きていくようになった。よく働いて平太は立派に一人で暮らしていけておった。だけど同じくらいの年の友達というものがいなかった。
しばらくしてだ。村のガキ大将の一人が、平太をいびるようになった。ガキ大将の仲間は平太が畑で野菜を育てているところに行ってからかったり、平太が川に行って鯰を捕まえようとしているのを邪魔したり意地悪をした。しかし平太はそのようなことには無頓着にせっせと自分のやることをしていた。平太は時間が余ると他所の家の手伝いをしたりして塩や味噌などをもらったりしていた。
秋になると平太がもっとも得意とする茸採りが始まった。平太は小さいにも関わらず、毒茸と食べられる茸をわけることができた。だから秋になると平太は食べ物に困らなかった。山にはアケビや山柿、山栗など実がたくさんなった。
大人たちは平太が悪さもしないし、一人でよくやっていると感心をしていたものだった。ところがガキ大将たちは親に少しは平太を見習えと言われ、ムシャクシャしておったんだ。
ある日ガキ大将の仲間の一人が、
「平太のあとをついていって茸をぶんどるべ」
と提案した。平太は旨い茸がたくさん生えているところを知っていたからである。それを横取りして親に褒められようという魂胆である。
平太は朝薄暗いうちに山にはいる。そのためには早起きをしなければならない。
その日、ガキ大将たちも珍しく早起きをして集まった。
ガキ大将たちは籠を背負って平太のあとをついて山に入った。
平太はなれているのですたすたと歩いていくが、ガキたちは蜘蛛の巣や木の根に足をとられながら、やっとこついていった。四半時も登っていくと、茸がたくさん生えている林の斜面にでた。
平太が茸を採るところをガキたちは木の陰に隠れて見ていた。茸を選ぶことができなかったので自分たちから採ろうとはしなかった。平太の籠がいっぱいになると、陰から飛び出した。驚いている平太を荒縄でぐるぐる巻きにして、木の下に転がすと、平太の籠から茸を自分の籠にうつした。そうして家に戻ったのである。
ガキたちは親に褒められた。
そのころ平太は動くことができず、舌をのばして羊歯の葉についた水滴をなめていた。だんだん腹が減ってくる。平太は草の中を転がって食べられる茸のそばにくると、舌をのばした。ちょっとなめてみる。何度も繰り返しているうちに、舌で茸を巻きとって口に入れることができた。
いくつかの茸を舌で口に運んだとき、たくさんの蟻が平太のからだにのぼってきた。平太はあわてて羊歯の中をころがった。蟻は何とか退治できたが、からだが痣だらけになった。ともかく虫たちがのぼってくるのには閉口した。
毎日毎日、林の中を転がりながら、茸を舌で絡めとって食べていた。平太は茸を食べながら少しずつ林の中を転がり落ちていくと沢にでた。そのころ縄が朽ちてきて、それに平太がやせたことで、縄から這いでることができた。
平太は沢の水で喉を潤し身体を洗い、茸をたらふく食うと、安全な場所を見つけて久しぶりにぐっすり眠った。
平太が半月ほど家に戻っていないと村人たちは心配していた。茸採りに山奥に行って遭難したに違いないと思っていた。それはガキ大将たちが、平太が大きな籠を背負って、奥の山目指して登っていったと言いふらしたためでもある。
ところがガリガリにやせた平太が村に戻ってきたのである。
平太は自分の家の前で、通る人を見ていた。
驚いた村人たちは野菜や食い物を平太にもっていった。しゃべらない平太でも昔はお礼の一つぐらいは言ったものだが、山から戻ってきてからは全く口を利かず、野菜を受け取ってもただぼーっと村人を眺めているだけであった。村人たちはよほど怖い目にあったのだろうと同情した。
平太が戻ったことを聞いたガキ大将の仲間たちが平太の家を覗いた。ガキ大将たちの顔を見た平太は大慌てで家の中の隅で足を抱えて小さくなった。怖かったのだ。それからは村人が平太に近づくと平太は家に隠れるようになった。そんなことから平太はまた放っておかれるようになった。
しかし平太は自分で生きていた。食べ物がなくなると山に入り、茸や木の実をとって食った。以前のように自分の家で暮らしはじめた。
年が変わったある日、ガキ大将が平太の家の前を通ると、家の中から平太が飛び出してきた。驚いたガキ大将が立ち止まっていると、平太はしょんべんをまき散らし、ガキ大将はほうほうの体で逃げ出した。
こうして平太には誰も近づかなくなった。それから五年、平太はぼろぼろの着物を身につけて、夜になるとぶらぶらと出歩くようになった。
よその家の脇でしょんべんをして、人を見かけると近づいてきて、長い舌でなめようとした。
村人たちは気味の悪い平太を何とかしなければと思うようになった。
「平太は山の中でも生きていけるべ」
一人の村人がそう言った。周りの村人も相づちを打った。
「家がなけりゃ、山に行くにちげえねえ」
村人たちは平太が山に茸採りに行っている間に、平太の家を打ち壊してしまった。
茸の入った籠をしょってもどってきた平太は家がなくなっているのを見て、しばらくうろうろと、周りをうろついていたが、やがていなくなった。
村人の思惑通り平太は山に入っていったのである。
やがて平太のことは村人たちの頭の中から消えていった。
年月もたちガキ大将だった者たちもいっぱしの大人になって、家庭を持つようになった。ある秋の気持ちのよい朝、ガキ大将の仲間の一人が子供とかみさんを連れて、林の中に茸狩りにでかけた。
林の中には食べられる茸も毒茸も色とりどりに生えていた。村人たちは大人になれば山にある草や茸は食べられるか食べられないかわかるようになっている。稲作ができない村では山の中のものが命の糧になる大事なものだからだ。
「ようけ出ているな」
「今日はうまい茸の料理だ」
みんなで食べられる茸を選んで籠に入れた。
「おまえさん、この茸たちを見てごらんよ」
かみさんが旦那を呼んだ。まだ年端が行かない子供もよってくる。
見ると、切り株の上に色のきれいな茸が八つほど立っていた。
「なんだ、こりゃ、いつもはこんなところによう生える茸とは違うんだがどうしたんだろう」
子供は、きれいきれいと喜んでいる。
「食べられる茸かね」
「ああ食える茸だ」
男は切り株の上の茸を手にとった。手に持った茸を見て不思議そうな顔をした。
「ずいぶん軽い」
そう言うと茸の底を見た。
「空になっとる」
茸の中身が抜き取られていたのだ。
「どれ」
かみさんもほかの茸をとった。どれも空で軽いものであった。
「どうしてこうなったんかね」
「なんかの虫が食っちまったんじゃないかね」
「だが、きれいなもんだ」
空になった茸を切り株の上に戻すと、また茸採りにせいをだした。
「一服すべえ」
家族はもってきたふかした芋を食いながら水を飲んだ。
こうしてその家族は採った茸の入った籠をしょって家に戻っていった。
さて茸の下拵えと、かみさんが籠の中から大きめの茸を取り出すと、おかしいなという顔をした。
かみさんが茸を見ると、中ががらんどうであった。もう一つ茸をとった。それも空になっていた。木の上に並んでいた茸と同じだ。
籠の中の茸を取り出した。すると籠の上の方に乗っていた茸はすべて空であった。
「あんた、ちょっときてよ」
旦那が土間に降りてくると、それを見て仰天した。
「採ったときは確かに重みがあって、うまそうな茸だと思ったのにな」
「どうしたんだろうね、気味が悪いよ」
「下の方の茸は食えるんだろう」
「ああ、大丈夫そうだ」
それでもその日は、いろいろな茸のごちそうが夕食に並んだ。
そのような目にあったのは、その一家だけではなかった。村人が茸採りに行くと、必ず空の茸が並んでいるのに出くわした。時に籠の中の採った茸がそうなってしまっていた。
何のしわざだろうか。村人たちは犯人探しを始めた。茸の生えているところに行って見張っていたのである。ところが、見張っている村人の後ろに空になった茸がきれいに並べられたりしていた。いつの間にか何かが空にした茸を並べたのである。
とうとう誰もその犯人を見つけることはできなかった。
その村では、茸の中身を吸ってしまう虫か鳥のせいだということになった。
ある日、小さな子供たちが集まって近くの林に行った。木の実を拾ったり、茸を採ったり、いい遊び場である。
中で一番小さな男の子が赤い茸をとったとき、箕をまとった人がそばに寄ってきた。男のようである。その男は手の平を子供の前に差し出した。
男の子は茸がほしいのかと思って、手のひらに赤い茸をのせた。
すると男はにっと笑った。「ありがと」と言って、口から細い舌を出した。舌は管のように丸まっていた。茸の底に突き立て中身を吸い出した。
空になった赤い茸を男の子に返すと、「うまい」
と言って山の奥に消えていった。
ほかの子供が、その男の子のところによってきた。
「今、誰かいたんか」
「うん、男の人」
「なにした」
「これ作った」
男の子は手のひらの空になった赤い茸を見せた。
「山に行くと時々ある奴じゃ、おっとうは茸吸いという鳥が作るのだと言っていた」
「ちがうよ、男の人だった」
家にもどって小さな子供はそう言ったのだが誰も相手にしなかった。
こうして、その村では、時々空になった茸が林の中できれいに並んでいるのが見られたり、採った茸が空になっていたりすることが起きた。それは茸吸いのしわざだということになった。本当は小さな男の子が見た、箕を着た男のしたことである。それが平太であるということはもう誰も想像できなかった。
かかあの話したのは、こういう伝説である。しかし百年も前のことで平太が生きているわけもない。それなのに茸の中身が吸われてしまった。
だけど、かかあはこう言うんだ。
「平太は妖怪になったんじゃ、妖怪は年をとらん」
そんなことはあるはずがない。
ともかく折角採ってきた松茸は売りものにならなかった。それからくろんぼだけど、なんとこいつもがらんどうになっておったんだ。滑子だけはなぜかなんともなくて美味かった。
あの山の赤松の林は初めて行ったところだが、なかなかいいところだ。また様子を見にいってみべえ。
それから三日後、かかあも行くというから連れてったんだ。おっかあも山で育った人間だから茸採りは得意なんだ。
赤松の林に入ると、すぐにかかあが松茸を見つけた。
「ほら、この林はいいじゃろう」
「ああ、ええ赤松の木じゃ、日の当たり具合もええな、松茸にはいいところじゃ、お前さんいいところ見つけたものだ」
そういいながら、立派な松茸をいくつも見つけた。もちろんくろんぼも採った。
かかあが、「ほら、向こうにも赤松の木が見えるでねえか」
というので、反対の山の斜面を見ると、確かに松の木が何本も生えている。
「こことは日の照り方が反対向きだが、もしかすると、生えているかもしんねえよ、行ってみよう」
かかあがそう言うので、斜面を降りて沢に出ると、反対の山に登った。確かにその松林も松茸が出そうだった。
「ほら、あるでねえか」
そこの松の木の根元にも松茸が顔をだしていた。反対側のものより少し小ぶりだがいい匂いがしてくる。
「かかあは、おらより茸探しはうめえな」
かかあは「小さい時から採ってたからな」と笑った。
そこでも松茸を何本も採った。
「こりゃあ、大漁だ、朝市にだすべ」
「そうしべえ」
かかあとおらは勇んで家に帰った。何しろ二人の籠は松茸でいっぱいだ。
土間に籠を降ろすと、羊歯を並べて松茸を置いた。
「後の松林の松茸はちょっと小さいが匂いもいいし、こりゃ高く売れるべ」
その松茸を並べ終えて、籠の下のほうの最初採った大きな松茸を取り出した。
手に持って、かかあもおらも驚いた。大きな松茸はみんな空になっていたのだ。
「茸吸いにやられとる」
「んだ、だけど反対側の斜面の松林の茸はだいじょうぶじゃ」
「あの松林には妖怪、茸吸いがすんでいるんだ」
かかあはさらに言った。
「爺さまが言っておった、茸吸いがでたら、茸を供えなければ、すべての山の中に茸吸いがあらわれて、茸をみんな吸われてしまうんだと」
おらは庄屋さんに相談することにした。
庄屋さんはもう八十にもなる人だが、いろいろなことをよく知っている。かかあの言ったことを話すと、茸吸いのことは聞いたことがあると言った。
どうするかしばらく考えてみようということになったのだが、それからしばらくして、採った茸ががらんどうになって、食うこともできないと、庄屋に訴える村人がでてきた。
それで庄屋さんは、息子をその松林に案内してくれと、おらに言ってきた。それで連れてったんだ。
赤松の林にはまた立派な松茸が生えていた。おらが採ろうとすると、息子どんは「やめてけ」と止めた。
赤松の中を歩き回っていた庄屋の息子は、斜面の一箇所に穴があるのを見つけた。羊歯が覆っていてよく分からなかったのだ。人が頭を下げれば入れるほどの穴だった。庄屋の息子が中にはいると、おらを呼んだ。おらが行ってみると、奥まったところに骨が横たわっていた。
「こりゃ、人の骨だ、男だの」
それで庄屋の息子は「爺さまに相談する」と家にもどった。
庄屋の爺さまはこう言った。
「隣村の平太の骨でねえか」
平太が山を彷徨って、茸の良くはえるあの赤松の森に住むようになり、死んで妖怪になったのではないかというのである。かかあの言っていた話とつながるんだ。
おらもそうかと思った。あの赤松の林は、ちょうどかかあの生まれた村とおらの村の境にある。
「その穴を丁寧に埋めて、そこに小さい社を建てや、わしが金を出そう」
庄屋の爺さんはそう言った。
「そこに茸を供えて、平太の魂を鎮め、茸の豊作を願うようにするべ」
隣村にはかかあの兄弟もいる。かかあは実家に帰ってこのことを話した。すると向こうの庄屋から一緒に社を建てさせてくれという使いが、おらの村の庄屋のところにきた。
それで二つの村でその場所に社を建て、町にある大きな神社にたのみ、平太の魂を鎮める祭を行なった。
平太のいた穴のある赤松の林は平太林と呼ばれるようになり、社は豊茸(ほうたけ)神社と名付けられた。
社の前で年に一度、秋の節句、九月九日に二つの村の合同の茸慰霊祭が行なわれた。
それからは、茸吸いはあらわれることはなかった。
このあたりでは、九月九日は菊の節句とは言わずに、茸の節句と呼んでいる。今でもその森からは立派な松茸が採れる。平太の松茸と呼んで、一番大きいものを天皇に献上するしきたりが残っている。
茸吸い
私家版第十七茸小説集「茸伝説、2024、234p、一粒書房」所収
茸写真:著者 秋田県湯沢市秋の宮 2018-9-28


