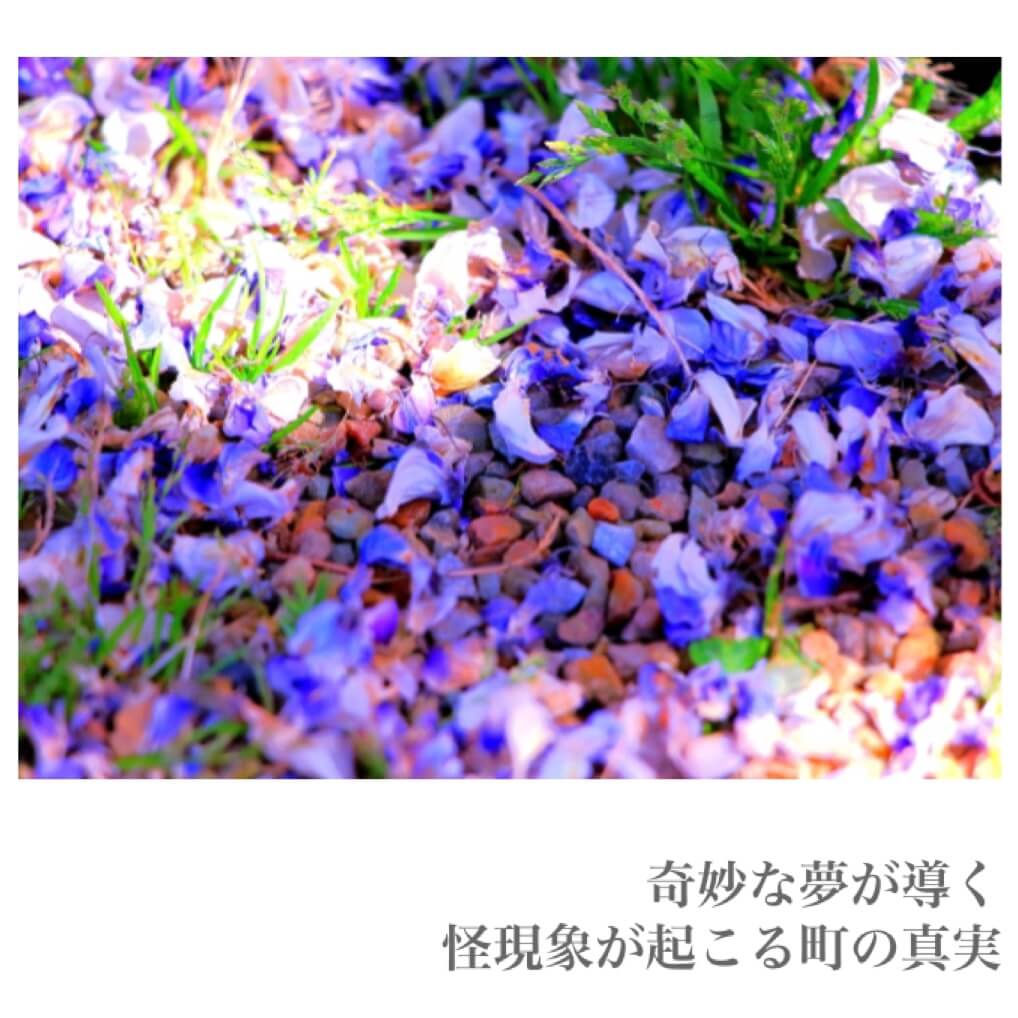
かぎろひの君
夏の終わり Ⅰ
もう……最期だ、と言わんばかりに蝉が鳴く。
そんなまだ蒸し暑さの残る頃。彼らがこれ程までに煩く鳴いているのは、限られた時間の中で新たな生命をのこすという使命を全うする為らしい。
少し前に見たテレビ番組で得た知識は一応あるが、この声を聞いているとどうしても実はもっと人間的な感情が込められているんじゃないかと思えてくる。
例えば終わり往く夏を惜しんでいるとか、残り少ない自らの命を嘆いているとか。
「まぁ、そんなわけないか」
穏やかでのんびりとした田園風景に向かってつぶやくと、彼らの叫び声が一層大きくなった気がした。
取り留めもないことを考えていると、部屋のドアがノックされた。
「浅倉〜ちょっといいか?」
「あ、はい。どうぞ」
返事をしながらドアを開けると、この小さな寮を営む高田家の次男で現寮長の良佑先輩が立っていた。
「お、もうほとんど片付いたみたいだな」
良佑先輩は部屋の様子を見て感心したようだった。
「あと少しで終わりです。もともと荷物少なかったんで」
「ホントさぁ、昨日届いた時ビックリしたよ。皆で、コレだけ? って」
「大きい物とか両親の荷物は……おじさんの家に置かせて貰ってます」
「そっかぁ〜。ま、あんまここでは気ぃ遣わなくて良いからな。みんな兄弟みたいなノリだし」
バシッと励ますように背中を叩かれる。
「ッありがとうございます。あ、それより何か用事があったんじゃ?」
そうだった、と良佑先輩が焦る。
「今日浅倉の歓迎会も兼ねて夏の恒例行事やるからな!」
「夏の、恒例行事?」
「内容は来てからのお楽しみってことで、17時に食堂集合な。じゃあまた後で」
颯爽と去って行くその背中を眺めながら、嫌な予感が頭を過ぎった。
この町に引っ越して来たのは、母の死から丁度3ヶ月が経った昨日のこと。
物心がつく前にはすでに父も他界していて、そのうえ親戚の話なんて一切聞かされていなかった。頼る身寄りはない、これからは1人で生きていくしかないのだと覚悟した矢先、俺の存在を知った父の弟夫婦が引き取ると申し出てくれた。
ならば何故こうして荷解きをしているのかと言うと、突然の事で困惑気味な俺に気付いたおじさんが高田寮を紹介してくれたからだ。知らない大人達との同居より、歳の近い子たちと生活する方が気楽だろうと。
ただ一つ、週に1度は必ずおじさん夫婦の家に顔を出してほしいと言われた。今後、一緒に暮らす暮らさないは関係なくして少しでもお互いの距離を縮められたら、という夫婦の希望が込められた約束事。
そうして俺は、巡り巡って両親の故郷へと辿り着いた。
「そろそろ時間か」
時計を見ると17時になろうとしている。タイミングよく片付けも終わったところで部屋を出た。
◆❖◇◇❖◆
食堂へ着くと夕飯当番(手伝い)の良佑先輩と高田家四男で同級生の秀祐、それから高田兄弟の祖母で寮母のトキさんがテーブルにたくさんの料理を並べていた。
「あら、然くん時間通りだねぇ」
真っ先に気が付いたトキさんが声を掛けてくれる。
「はい。丁度片付けが終わったので。皆は、まだみたいだね」
「全員時間にルーズだからな。部活生多いのに」
やれやれと秀祐がため息をつく。
入寮したのが昨夜遅くだったので、トキさんとそこに居合わせた高田兄弟3人とは少し話をしたが、朝食も昼食も寮の皆は部活だったり用事があったりで1人で済ませたので、他のメンバーと会うのはこれからだ。
「俺も手伝います」
「お! 助かる。ありがとな」
良佑先輩と秀祐に物の在り処を教えてもらいながら手伝っている内に、次々と寮生が現れ準備が終わる頃には皆が集合した。
「全員揃ったな? んじゃ冷めないうちに、いただきまーす」
良佑先輩の声に続いて皆も手を合わせて食卓の挨拶を口にする。メインのおかずに手を伸ばしながら、慣れた様子で良佑先輩が司会進行を始めた。
「ほとんどの奴が浅倉と初対面だし、食べながら自己紹介でもしてこうか。改めまして俺から。基本ツッコミ担当の高田良佑です。この間まで野球部でした〜。好きな食べ物はとんかつです」
好きな食べ物って、と続く先輩が呟く。
「3年の嶋宗一郎だ。宜しく」
「短ぇな。ぃよ! 生徒会長!」
すかさず良佑先輩が端的な自己紹介を茶化すが、宗一郎先輩は至って冷静だ。
「オヤジかお前は。……まぁ勉強は出来る方だから、わからない所があったらいつでも聞いてくれ」
本気で頭良いから、と秀祐が教えてくれた。
「次は僕かな? 同じく3年の木村快斗です。陸上のスポーツ推薦がほぼ確定しちゃってて、練習で高校に行ったりするから寮にいない日もあるけど忘れないでね。好きな食べ物はチーズケーキです」
好きな食べ物のくだりいらんだろ、と言う宗一郎先輩の横から良佑先輩が補足する。
「カイキャプテンファンクラブがある程、女子に大人気です」
「元キャプテンね♪部活引退したのにずっと応援してくれて、ホントに有難いよ」
「出ました! 好感度高めぇなセリフ〜。キラキラしてんな〜ムカつくわ〜」
「僕って好感度しかないから♪良の魅力はその暑苦しさだよね?」
サラッと笑顔で毒を吐くあたり、快斗先輩の恐ろしさを垣間見た。
「そうだな。良佑の暑苦しさにはよく救われる」
その毒に大きく相槌をうつ宗一郎先輩。
「何それ、2人して褒めてんの? 貶してんの? まぁいいわ。快斗と宗一郎は来年からこっちを離れて首都圏の高校に行く予定で、寮か一人暮らしになるから慣れる為に4月からここで生活してんのよ。次、2年's大輔〜」
気だるそうな感じで自己紹介をする高田家三男の大輔先輩は、これが通常テンションらしい。
「うーっす。野球部エースの高田大輔」
「自分でエース言うな」
「あ、門限破った時のごまかし方法とかそういう類いのことは俺に任せろ」
「後輩に変なこと吹き込むな」
こいつウチの兄弟一やんちゃだから気を付けて、と良佑先輩が小声で付け足す。が、その言葉を無視して3年生2人が名乗りを上げた。
「大ちゃん、今度教えて」
「俺にも頼む」
「えっ!? 何、お前らが便乗すんの?」
同級生のまさかの裏切りに良佑先輩は驚愕する。
「OK。じゃあ手始めに今夜ですね……」
「兄の話を少しは聞けッ。今夜何する気だよ!?」
そんな4人の会話をぶった斬る強者も登場した。
「和菓子好きの平良紘です。一応帰国子女なんで、英語くらいは教えれるよ」
「ありがとうヒロ、察してくれて」
「あ、大丈夫でした? 僕いっつも空気読めないって言われるんで」
「今のはいつになく完璧だった」
良佑先輩がGoodサインを送る。
「ヒロの家系は皆海外で仕事しててね。家族も親戚もほとんど日本にいなくて、一人暮らしさせるのは不安って事で寮住まい。1年'sは拓馬からね」
「俺っスか? んーっと、あ! 憧れのカイ先輩を隣町からわざわざ追いかけてきた、陸上部の西沢拓馬っス。好きな食べ物はから揚げっス」
から揚げを掲げながら満足そうな拓馬。
「そう言えばここにもいたな、カイキャプテンLover……」
大輔先輩が呆れ顔だ。
「だから元キャプテンね♪でもこう見えて拓馬は、期待の新人だからね」
「そんな! カイ先輩から期待されたら、頑張るしかないっス!」
目を輝かせながら拓馬が快斗先輩に応える。
「快斗が絡むと良佑以上に暑苦しいな、拓馬は」
宗一郎先輩の一言に真っ先に反応したのはやはり良佑先輩だった。
「はい、今のは完全にけなしましたー傷つきましたー。拓馬も傷つきましたー」
「へ? 俺、傷ついたんスか?」
ご飯をがっついていた拓馬はきょとんとする。
「はぁー拓馬は今日もアホだなー。和むわー」
「ねー。本当に何だろうね、このマイナスイオンは」
またしても褒めてるのかけなしてるのか怪しいセリフを紘先輩が放ち、快斗先輩がそれに同意する。
カオスと化してきた自己紹介に、痺れを切らした秀祐が声を上げる。
「あぁもうアンタ等長過ぎ! この通り変な奴ばっかだけど、いざとなったら皆意外と頼りになるから困った時は何でも言えよ。これからよろしくな」
「わ。あの小さかった秀祐が一番まともな発言して、何かちょっと感動」
「俺もう中1だっつの。ホントにオヤジか良兄は」
最近オヤジ化がスゲーのよ涙もろいし、と言いながら良佑先輩が俺に振ってきた。
「最後は……もう名前で良いな、然!」
「えっと、浅倉然です。久しぶりにこんな大勢で夕飯を食べて純粋に楽しいです。これからよろしくお願いします」
皆からもよろしく! と歓迎され、少しホッとした。そんな和気あいあいとしたムードの中、良佑先輩が締めくくる。
「ま、こんな感じでいっつも賑やかにやってるから、ホント遠慮とか無しでやってこうな」
「ちょっと! 俺をスルーすんなよ〜。高田家長男の優介で〜す。ピッチピチの20歳で大学生やってま〜す」
おふざけにずっと参加したそうだった優介さんがようやく乱入を果たした。そんな唯一の兄に良佑先輩が冷やかな目を向ける。
「あえて今まで触れなかったけど、何で兄貴がここにいんの?」
「いや〜実家にいたらさぁ、チビッ子たちが俺を取り合って喧嘩になるから。俺って罪作り〜♡」
「おもちゃにされてるの間違いだろ」
大輔先輩が痛い所を突く。
「優さんが参戦したんだし、トキさんもどう?」
皆の様子を微笑ましげに見ながら、ゆっくりと食事をしていたトキさんに快斗先輩が自己紹介を勧める。
「私かい? じゃあそうだねぇ。ここで20年くらい寮母をしてる高田トキです。高田寮に入った時点で、み〜んな孫みたいなもんだからね。良ちゃんと秀ちゃんが言った通り、遠慮なく頼ってきて良いんだよ? 然くん、こちらこそ宜しくね」
トキさんの言葉に自然と拍手が湧き起こって、自己紹介は無事終了した。
各々食べながら談笑していると、良佑先輩から不意に尋ねられた。
「然、何か質問とかある?」
「質問ですか……あ、そう言えば良佑先輩達の実家ってすぐ近くなんですよね。どうして3人とも寮暮らしなんですか?」
「あ〜それはねぇ、実家の部屋数の都合上、高田家男子は中学生になると自動的に寮へ追いやられるのです」
良佑先輩の説明に、ウチ大家族だからねーと優介さんが笑う。
ごちそうさまでした、が聞こえ始めてきたところで良佑先輩が切り出した。
「さてと、食べ終わったところで……行きますか! あ、兄貴は俺らの代わりにばあちゃんの手伝いね」
「えー俺も行きたいー」
優介さんが駄々をこねるが良佑先輩は安定のスルー。
「じゃあ優兄の代わりに俺が手伝う!」
そんな兄たちのやり取りを見て秀祐が名乗りを挙げるが。
「「お前はダメ」」
良佑先輩と大輔先輩がそれを容易く却下した。
夏の終わり Ⅱ
玄関を出てすぐにメインイベントの内容を知らされる。
「肝試し……ですか?」
あの予感は的中した。
「露骨に嫌そうな顔してるねぇ然くん。シンプルに良い反応♪」
快斗先輩からお褒めの言葉を頂戴した。
「やっぱ俺ヤダっ! 帰る!」
そんな俺たちの横では、絶叫する秀祐の腕をがっしりと掴んだ兄達が運んで行く。
「秀祐は何であんな嫌がってるんですか?」
「あー……まぁ秀は、怖がりだから」
あまり歯切れの良くない回答が紘先輩から返ってきた。
寮から少し歩くと、アスファルトから舗装されてない山道へと続く境目の地点に着いた。どうやらここがスタートラインのようだ。
「それではルールを説明しよう! この先を真っ直ぐ進むと、てか真っ直ぐしか進めないけど。途中で山の上に向かう石の階段があるから、それを登りきった先の藤棚に生る藤の実を採って来るのだぁ!」
戦隊モノとかのナレーションでよく聞くあの解説を、絶妙に似てなく真似た良佑先輩の暑苦しい演説を聞き終えると同時に、拓馬が律儀に手を挙げて質問した。
「藤の実ってどんなのっスか?」
素朴な疑問に宗一郎先輩が応える。が、実物を知らない俺にとってこの例えは最早丁寧なんだか雑なんだか、判断に困るものだった。
「どデカいさやえんどうみたいなヤツだ。まぁ、行って見れば分かるだろ」
そうこうしていると、不敵な笑みを浮かべた大輔先輩の発言を皮切りに肝試しが始まってしまう。
「トップバッターはやっぱ1年ッしょ」
◆❖◇◇❖◆
指示された通り山道を真っ直ぐ進む内に、だんだんと先輩達の姿が小さくなっていき、ついには見えなっなった。
「2人は怖くないのか?」
気持ちを切り替えたらしい秀祐から問われる。どうやら色々と諦めたようだ。
「んー俺は昔から恐怖心が薄いみたいだから。拓馬は?」
確か薄そう、という秀祐の相槌を掻き消して拓馬が食い気味に話し始める。
「めっちゃ怖いッスよ! でもカイ先輩が楽しそうだからやるしかねぇ! って感じ」
「お前の脳内は快斗先輩のことしかねぇのか」
「もちろん!」
秀祐の呆れ顔などものともしない二つ返事だった。
恐るべし、カイキャプテンLover……。
これ以上拓馬が快斗先輩への愛を語り出す前にと、秀祐が話題を変えた。
「つか然、こんな山道歩いたことないだろ?」
「そうだな。ずっと結構な街中に住んでたし、小学校で行った林間合宿もある程度人の手が加えられてる感じの山だったから、記憶にある限りでは無いのかも」
そう答えながら辺りを見渡した。向かって右側は鬱蒼とした山が斜面を這うように生い茂り、反対の左側はまばらな草木の合間から清流が覗いている。
「だよなぁ……いかにも都会っ子な雰囲気だもんな、然は」
「俺も一応都会生まれッスけど、こんな雰囲気ない?」
拓馬は自身と俺を交互に指差しながら秀祐に尋ねた。
「全くねぇよ! 拓馬の場合はもう他のイメージが刷り込まれ過ぎて、手に負えないから……あ、着いちまった……」
落胆した秀祐の言葉で足を止めると、深く茂る木々を切り裂くようにして上へと伸びた長い石段に出会す。
「然、先行ってくれ」
今まで先陣を切っていた秀祐が前を明け渡した。
「うん? まぁ良いけど。逆に後ろの方が怖くね? わぁ〜! って背後から来られたら」
「大丈夫だ、最後は拓馬だから。俺は真ん中」
謎理論で返されたが、拓馬も黙っちゃいなかった。
「えー。それひどいッスよー。でも真ん中だって、着いて来てるはずの俺がいつしか違う誰かに変わってる……っていう恐怖も有りうる」
「やめろッ、ここへ来て変な事言うな! もう良い。3人横に並んで行こう」
反逆の拓馬による脅しが効いたようだ。けれど両脇を俺達で固めて、ちゃっかり秀祐は真ん中にいる。
こうして布陣も定まり、意を決して1段目に足を踏み出した。
「あーもうマジ寒気してきた……」
「やっぱ秀祐も? 俺なんてだいぶ前から寒くてどうしようかと思ってたっスよ」
数段上がると2人が自身の体を摩り出す。
「そう? 何も変わらないんだけど俺」
「おい然、それマジでおかしいって。冷気半端ないだろ」
「もしかして、此処って結構ヤバいとこ?」
何気ない俺の問い掛けのせいで、秀祐の顔にギクリという文字が滲んだ。
「う。その話は……今、したくない」
「えー! めっちゃ気になるんスけど! てか、言わない時点で相当ヤバいとこでしょ!!!」
珍しく的確な指摘だったが、敢えてそこは触れないでおく。
「あれ、拓馬も知らないんだ?」
返事はキッパリしたものだった。
「うん。カイ先輩のこと以外、興味無いんで」
「拓馬。お前、それストーカーの域まで行ってんぞ」
呑気な会話もここまでで、徐々に2人の口数が減っていく。やっぱり何ともない俺は、気晴らしになればと話を振るが彼等からは短い返答しかない。
異変が起きたのは石段の中腹に差し掛かる所だった。
「今、何か音したっスよね?」
拓馬の一言で足が止まる。
「妙なこと言うなよ!」
また秀祐の発狂スイッチが入ってしまいそうだ。
「俺も聞こえた。たぶん鈴の──」
そう言い終えるか終えないかくらいのタイミングで、石段脇の草むらがガサッと大きく動く。
「「うわぁー!!!」」
悲鳴と同時に2人は猛スピードで石段を下って行った。
「おい! 置いてくなよっ……て、もういないし」
サッカー部と陸上部の俊足にスポーツ未経験者の俺が着いて行けるはずもなく、あっさりと置いてけぼりをくらった。歩いて戻ろうとした瞬間、さっきの草むらから何かが飛び出す。
──チリン
現れたのは、美しくも不思議な猫だった。
木々の隙間から差し込む夕陽に照らされた毛並みは銀色に輝き、滑らかにしなる尻尾は二股に分かれている。
その猫は数秒の間、吸い込まれてしまいそうな青い瞳で俺をじっと見つめたかと思うと踵を返してトットッと石段を登り始める。この軽快な動きにつられて、戻ろうとしていたはずの身体は勝手に猫の後を追っていた。
すると、不思議なことに気付く。前を歩く猫が動く度、銀色の毛並みが弾んでキラキラと煌く光の粒が零れるのだ。それは、触れようとすると実体を潜めてフッと消えてしまう。
儚い道標のようだと思った。
そんな道標に導かれるまま足を進めていると、石段の終わりを告げるかのように建つ鳥居が見えてきた。
猫に続いて登切り鳥居をくぐると直ぐに、藤棚と思われるものが現れる。
太い木材を垂直に組み合わせて作られた棚状の骨組には蔓性の植物が絡まり、10から20cm程の細長い実が生っているので、間違いないだろう。
正に大きなさやえんどうといった形をしている藤の実を目にして、宗一郎先輩は丁寧だったと判定した。
ただの肝試しという遊びに過ぎないが、一応ルールに従い実を取って帰ろうと藤棚に近付く。だが途端に、この場所の異様さが浮き彫りとなった。絡み付く蔓の隙間から見える木材が炭のようになっていて、所々補強してある。地面には、ほとんど風化してしまってはいるが瓦礫も落ちていた。
藤と言う植物が絡まっている骨組は、何かしらの建物の焼け跡だ。
屋根や壁、床は完全に焼け落ち、太い柱と梁、桁だけが黒焦げになりながらも残されている。かつてここで、酷い火事が起きたのであろう事は容易に想像出来た。
不気味な雰囲気に圧倒されるあまり気付くのが遅れたが、焼け焦げた藤棚の更に奥には幾重にも絡まり合い捻れた太い幹を持つ大木が鎮座していた。そこから伸びた蔓が、黒焦げになった桁を伝って全体に巻き付いている。
まるで、悲惨な焼け跡を覆い隠そうとするかのように。
なんとなくこの場からは早く立ち去った方が良い気がして、身近にある藤の実を取ろうと手を伸ばしたその時だった。
「これ、でいいか……」
「駄目よ」
背後からの思いもよらぬ強い口調に一瞬肩がビクつく。
「その藤に触れては駄目」
もう一度ゆっくりと窘めるように言われ、固まった手を下ろした。
恐る恐る振り返ると綺麗な漆黒の髪を腰の辺りまで伸ばした女の子の姿。歳は俺よりいくつか上だろうか。夏休みだというのに制服を着ているので、部活終わりの高校生かもしれない。案内人の猫は知らない内にその子の足元で、お行儀良く前足を揃えてお座りをしている。
絶え間なく叫び続ける蝉達の声が渦巻く中で、俺と彼女の視線が重なった瞬間、時が止まったような気がした。
「あなた……よくここまで来れたわね」
RPGのラスボスを彷彿とさせる予想外な彼女の言葉が時の流れを元に戻す。
「え? あ、まぁ確かに石段は長かったけど、登ってこれないってほどでは──」
勇者気質ではない俺は格好良いフレーズの一つも言えない。その上、胸元を指し示された事によって村人Cくらいの発言すら遮れた。
「きっと、それのおかげね」
シャツの下に隠れているペンダントの存在を見抜かれ、疑義の念が口から溢れる。
「……どうして」
「とても、強い力がある物のようね。大切に持っていた方が良いわ」
取り出されたペンダントを一目見てその正体まで勘づいた彼女は、そういったモノが分かる人なのだと勝手に解釈した。
第六感ってヤツかな?
「母から貰ったお守りなんだ。肌身離さず持っているようにって、母もしつこく言ってたよ。何が起きても必ず護ってくれるからって」
「……それなら、尚更にね」
「おーい! 然!」
「然くーん!」
会話が途切れるのを見計らったように届いた、自分を呼ぶ声にハッとした。すると、同じように聞こえたらしい彼女が口を開く。
「もう、皆の所へ戻った方が良いわ」
「あ、うん。そうだね。……君はまだ、帰らないの?」
「えぇ」
彼女の当たり前だと言いたげな反応に、少し気圧される。
「あの、さ。名前を、聞いても良いかな?」
深く息を吐いて目を伏せた彼女は、迷っているかのような長い沈黙の後に、答えてくれた。
「……宮森、千咲よ」
何故だか脳裏に漢字が浮かんだ。
「もしかして、千に咲くって書いて?」
「そう」
「やっぱりそうか。綺麗な名前だ」
それまで表情一つ変えなかった彼女が、分かりやすく複雑な表情を見せる。
「然〜! 上にいるなら降りてきてくれ〜!」
また皆が呼ぶ声が聴こえてくる。
「ほら、呼んでいるわ。早く行きなさい」
諭す様に言われ、その場を後にした。
「うん。じゃあ、また……」
「さようなら」
一拍置いて聞こえて来た彼女の別れの台詞は、酷く冷たく感じた。何人も寄せ付けないような。
先程置いてけぼりを食らった石段の中腹辺りまで降りてくると、快斗先輩と大輔先輩、いつの間にやら合流したらしい優介さんが迎えに来てくれていた。
「うわ〜然〜。良かったぁ、降りて来てくれて」
「はい、まぁ声が聞こえたんで。てか、どうしたんですか? 皆、顔色悪いですよ」
「はぁ!? お前、何ともないのかよ?」
驚愕する大輔先輩。
「何がですか? 普通ですけど」
秀祐が言っていた通りだ、と愕然とする3人。
「凄い形相で秀祐と拓馬が戻って来て、でもあの子ら然くんを置き去りにしてるの気付いてなかったみたいでさ。慌てて全員で迎えに来てたんだけど、このメンバー以外はどんどん脱落してっちゃって。俺らも石段登り始めてすぐから寒気が半端なくて、上まで行けそうにないから呼んでたんだ」
経緯を説明してくれる快斗先輩だが、やはり気になるワードが出て来た。
「あぁ、それ秀祐と拓馬も言ってましたけど、冷気がどうとかって。何なんです?」
「秀から聞いてねぇのか。あんの馬鹿ッ……あ、そっかだから上まで行けたんだな。実を言うとここは──」
大輔先輩が何か言い出そうとしたものの、今度は優介さんから話を濁される。
「あ〜はいはいはい。今ここでは止めようねその話。皆が途中で待ってるだろうし、完全に日が暮れてしまう前に帰ろ。な? そんで、良の部屋でゲームでもしよう。徹夜でしよう、そうしよう!」
「お〜! ついでに良佑の部屋を荒らそう〜!!!」
もれなく快斗先輩がこの企画に便乗した。
◆❖◇◇❖◆
寮に辿り着くなり交代でお風呂を済ます事となった。
理由は言わずもがな、蒸し暑さが残る夏の終わりにも関わらず皆が寒がるからだ。
結局あの場所の真相を聞く暇もないまま、優介さんと快斗先輩の宣言通り、全員が良佑先輩の部屋に集まりゲーム兼部屋荒らし大会となった。
0時を回る頃、各自解散となり俺は自室へと戻った。
これだけ騒ぎ散らかしたのは久しぶりで、明日からもこんな日々が続くんだと感慨深くなりながら眠りに着く。
その朝方、奇妙な夢を見た。
脳裏を流れていく景色は、絶えず嘆き続ける彼らがまだ地中で過ごしている季節を想像させた。
白い背景に、枝先から紅みがかった濃い紫の美しい花を房状に長く垂れて咲かせている大木と、人影が在る。
あれは……藤、の花? じゃあ、あの子は……
降りそそぐように花達を散りばめた大木は、夢の中であるはずなのに甘く瑞々しい薫りで俺を包み込んだ。
同時に、風に揺れる花と人影が一瞬にして炎の渦に飲み込まれる。
でもその景色は、何を意味するモノなのかを考える余地も与えず、目の前をただ通り過ぎて行く。考えようとすればする程、夢は捕まることを拒んで俺から逃げて行くようだった。
けれど、一つだけ掴めたモノがあった。
夢見心地でも絶えず聞こえてくる蝉達の嘆きを一瞬だけ打ち消して鼓膜を震わせた、祈るような声。
「もっと、早くこうするべきだった。……でも、これで終わり。全ての縁を断ち切るの……」
夢から覚める間際、遠くで鈴の音がした。
夏の終わり Ⅲ
始業式から、数日が経った。
2学期という中途半端な時期にこの参月中学へ転校してきた俺は学校にとって、少し異質な存在だった。なにしろ小学校、早ければ保育園くらいからほぼ同じメンツで過ごしてきた生徒達が殆どなので、それも仕方ない。だが、寮の皆は何かと気に掛けてくれるしクラスメイト達も親切なので、この距離感が縮まるのは時間の問題だろう。
「おーい! 然ー」
教室移動をしていると、後ろから秀祐に呼び止められる。振り返ると、手に持った何かを振りながら走ってきた。
「然、お前机の上に筆箱忘れて行ってたぞ。どうやってノート取る気だよ」
秀祐が筆箱を差し出す。
「あぁごめん。ありがとう、助かった」
「おーよ。つか、ずっと思ってたんだけど、然って何かお上品だよな」
至って真面目な顔で言う秀祐の言葉を聞いていたのか、目的の教室前の廊下で雑談をしていた2人組の生徒の片方が彼に声を掛けた。
「ちょっと秀祐~。繊細そうな浅倉君をガサツなあんたの世界に引きずり込むのだけはやめてよね!」
「んだと? 瑞穂! 俺以上にガサツな女に言われたくねぇよ」
「はぁ? 何ですって! もう1回言ってみなさいよ! 蹴り飛ばすわよ?」
「何度でも言ってやるよガサツ瑞穂!」
威勢の良い瑞穂と一緒にいた生徒が、シッシッと犬でもあしらうように右手を振る。
「はいはい、夫婦喧嘩は余所でやってよね。浅倉君が困ってるじゃない」
「「誰と誰が夫婦じゃ、よう子!」」
噛みつくような勢いで見事にハモった彼等に、あんた達以外に誰がいるのよとしっかりツッコミを入れたよう子は、いつでも冷静沈着といった感じだ。そんなよう子が2人を放置して俺の方へと向き直る。
「そういえば浅倉君、藤の社に行ったって本当?」
「えーっと? 何の事?」
困惑する俺に秀祐が補足してくれる。
「あ〜ほら、アレだよ。……肝試しん時行った」
「ん? あ、あの何か建物の焼け跡があるとこ?」
聞き返すとよう子が説明してくれた。
「数十年前に起きた火事であんな状態になってしまったけど、あの場所には元々この地域を護る神様を祀ったお社が建っていたの」
「へぇ、そんな場所だったのか」
1人納得する俺の隣から秀祐がよう子に尋ねる。
「てかよう子、然があそこに行ったって誰から聞いたんだ?」
「誰って、西沢君よ」
「拓馬か……あんのお喋りめ」
それまで静かに傍観していた瑞穂が秀祐に詰め寄るように捲し立てた。
「ていうか何であんな所に浅倉君を連れて行ったりしたわけ!?」
負けじと秀祐も言い返す。
「兄ちゃん達がどうせ登り切る以前に近付くのすら全員無理だろうからって決めちまったんだっつの! 俺だってやめた方が良いって散々言ったわ!」
ふと、あの日聞き忘れたままだった事を思い出した。
「言い合ってる所申し訳ないんだけど、あの場所ってそんなにヤバいとこなの?」
俺の問い掛けで、途端に3人が押し黙る。
そして、この沈黙を破ったのは何事も物怖じしなさそうなタイプの瑞穂だった。
「あのね、浅倉君はこっちに来たばかりだから知らなくて当然なんだけど、あの場所にはあまり良くない言い伝えがあるんだ。近くを通りかかっただけで事故に巻き込まれて、それも大怪我だったり最悪の場合は死人が出たり……」
瑞穂の話の後に、声を潜めたよう子が続ける。
「もっとずっと昔に遡ると、籐の社へ足を踏み入れた者は必ず神隠しに遭う、そう言われてたそうよ」
「……神隠し」
俺は聞いたままを復唱した。
「ただの言い伝えだって言う人もいるけど、実際最近も事故が起きたりしてるから、この辺りの人間は怖がって今はほとんど近寄らないようにしてるわ。だから浅倉君もこれからは行かない方が良いと思うよ」
「それにお社での火事の時──」
よう子が言い終えるのを見計らって瑞穂が何かを付け加えようとした時、教室内の男子生徒から呼び掛けられた。
「秀祐〜浅倉〜、瑞穂達も。そろそろ席着かないと先生来るぞー」
片手を挙げて秀祐がそれに答える。
「おう、分かったー」
「この話はまた後にしよっか」
そう言った瑞穂とよう子は先に席へと向かった。
「然? とりあえず教室入ろうぜ」
たぶんぼんやりしていたのだろう。秀祐から腕を引かれた。
「あ、うん……ごめん」
こちらの様子を窺いながら秀祐が言う。
「何で謝ってんだよ。俺、あんまりああいう話って信じない、と言うか信じたくないしぶっちゃけ怖いの苦手だから嫌いだけど、さっきよう子が言った通り、あの近くで事故が起きてるのは事実だから、頂上まで行った然は気をつけた方が良いかもな。次から行こうとした時は俺も止めるしさ」
「そうだな、気を付けるよ」
返事はしたものの、俺はやっぱり上の空だった。
何故だかずっと、千咲と名乗ったあの子の事が頭を過って仕方がなかったから。
◆❖◇◇❖◆
結局、授業の後も藤の社の話をする事がなかったらから、余計にこんな行動を取ってしまったのかもしれない。
学校が終えると通学カバンを置きに一先ず寮に戻る。それから俺の足は、誘われるかの如くあの場所へと向かっていた。
あんな話を聞いて近付くべきじゃないのも分かっているけど、どうしても彼女に会わなければならない気がしたからだ。会ってどうなる訳でもないし、会ったのだってたったの1度きり。なのに何故か、千咲の顔が見たくて、声が聞きたくて、その衝動を抑える事が出来なかった。
あの日と同じように山道を歩く。けれど、あの日と違って心細い。それは夏の終わりが近いせいか、1人で居るせいか、どちらなのかは判断し難いが。
殆ど早足だったから、直ぐにあの階段まで行き着いた。こうして見ると、山の中にあるのが不自然な程やけにきっちりとした石畳だ。所々苔に覆われ古びたその石畳の階段を登って行く。
結構長いはずなのに、2度目の今日は前より早く登り終えた気がした。
鳥居をくぐり一旦立ち止まると、焼け跡が待ち構えていた。その奥には藤の蔓を広げた大木がひっそりとそびえ立つ。夕方の静けさがこの場所の雰囲気を引き立たせ、焼け焦げた社の存在を強調させる。
この存在感が、何に対してか説明しようのない焦りを感じささた。
そんな焦燥感に駆られながら玉砂利の敷かれた地面を数歩進めば、藤棚と化した社の焼け跡の真下へ辿り着く。
あの日はよく見えていなかったが、蔓の持ち主である大木は非常に大きなものだった。大木と言うより巨木と呼ぶ方が相応しいように思う。
巨木の波打つ幹に腰掛け、膝の上に乗せた銀色の猫の背を撫でている千咲の姿を見つけ、そちらへと踏み出す。すると彼女達はほぼ同時にこちらの気配に気付いて振り向いた。
千咲は、少し驚いた表情を見せる。
「……また、来たのね」
声を掛けてくれる千咲に、言い様のない感情が湧いてきた。
「あぁ、うん。……学校が始まって、ココの話題になったら急に君の事を思い出したんだ」
何処か懐かしむように彼女は呟く。
「そう言えば、もうそんな季節ね」
千咲の呟きは耳に届いていたが、こんな風にグルグルと勝手に心慮が巡り始める脳内を止められなかった。
姿も見える。声も聞こえる。彼女はちゃんとそこにいる。
でも何故か頭から消えない、〝神隠し〟の言葉。
「何を考えているの?」
そう問い掛けてくる千咲と視線が重なった瞬間、思考を読まれている気がしてふと我に返る。
「あ、いや……君は、この場所が恐ろしくはないのかな、と思って」
「……」
俺の言葉に、彼女は応えなかった。
だから余計によく考えもせず咄嗟に発言してしまったことを強く後悔した。けれど放たれた言葉はもう戻ってこない。
「いや、クラスメイトからココの言い伝えを聞いて、それで」
そう言うと千咲は白銀を撫でていた手を止め、何処か遠くを見つめた。その横顔は、息を飲む程に美しかった。
「……この場所の周辺でよく起こる事故や神隠しを恐れて、この町の人間はほとんどココへは近付かないって。でも君は、ココにいる。だから皆みたいに怖くないのかなと、思ったんだ」
千咲は黙っまま、ピクリとも動かない。
「本当は、近付かない方が良いって言われた。でも、それでも何故か君に会いに行かなくちゃと思ったんだ」
「貴方も」
沈黙を貫いていた千咲がやっと口を開いた。
「貴方も人ではないモノの存在に気が付くでしょう」
「?」
疑問符を浮かべる俺の顔を見た後、千咲は縋るような声を出した。
「もし、そのモノの心を感じ取ってしまったら……どうするのが一番良いと思う?」
けれど俺には彼女の問いの真意が解らず、聞き返すしか出来ない。
「それはどういう意味?」
しかし、千咲はすぐ様前言を撤回した。
「いいえ、何でもない。今の話は忘れて。それから、皆の言う通りここへは、来るべきでは無いわ。だからもう、帰って。……そしてもう2度と来ては駄目よ」
そう言う彼女の瞳に強い意志を感じて、これ以上はどうしようもないと悟った。
再び押し黙った千咲は目の前に居るはずなのに視界から消え去ったようで、掛ける言葉も見つけられず為す術もない俺はその場から離れた。
夏の終わり IV
寮へ真っ直ぐ帰る気になれなくて、遠回りになるが寄り道する事にした。
舗装されていない砂利道からアスファルトへと変わった道を歩いて行き数件の民家を通り過ぎた後、魚が泳ぐ姿が確認出来る程透き通った川に架かった小さめの橋に辿り着く。そこを渡り、緩やかな坂を登りきるとようやく片側一車線の道路に出る。
向かって右手へと数歩踏み出した丁度その時、通りかかった車から名前を呼ばれふと我に返る。
「然くん!」
顔を上げて声の主を目にするや否や、しまったと思った。
「あ、千悟さん」
今日が約束の日である事を忘れていたからだ。
「その顔は忘れてたって顔だね?」
「すみません」
「良いよ良いよ、大丈夫。とりあえず乗って。ドライブに行こう」
そう言ってくれる彼は怒るどころか、とても楽しそうにしている。
この人、向坂千悟は父さんの弟。つまりは俺の叔父さんで、この町へと俺を誘った張本人だ。まだ叔父さんと呼ぶには気が引けて、名前で呼ばせて貰っている。
俺を助手席に乗せる為、置いていた荷物を後部座席へと移動させている。視線に気付いたのか説明してくれた。
「コレね、嫁さんにお砂糖ついでに買ってきてーって頼まれちゃってさ。要するに使いっパシリ」
そんな風に言っているが、スーパーの袋を持ち上げて笑う千悟さんはとても楽しそうに見える。
「今の話を詩織さんが聞いたら怒るんじゃないですか?」
詩織さんとは千悟さんの奥さんで俺の叔母さん。
「そうそう。だから俺と然くんの二人だけの秘密ということで」
いたずらを隠す子どものように真剣な顔で言われて、俺もつられて真面目に頷く。でもお互いすぐにその真剣さが可笑しくなって、どちらからともなく笑い出していた。
「あーやっといつもの然くんだ」
「え? 俺、何か変でした?」
「変というか、ぼーっとしてる感じだったから、何か悩み事かな? と思ってね」
俺で良かったら聞くよ、と車を発進させる。
とは言え、車内では本題には入らなかった。雑談を交わしながら少し走ると通り沿いに公園を見つけた千悟さんからちょっとあそこ寄ろうか、と誘われ隣接する駐輪場に車を停める。
「はい、どうぞ」
「あ、ありがとうございます」
入り口にある自販機でジュースを買った千悟さんは、一本を俺に渡しながら公園の中へと入って行く。
ブランコと鉄棒、あと砂場くらいしかないこじんまりとした公園。遊んでいた子ども達は丁度、母親や兄弟に連れられて帰り始めた時間帯で、少しだけ物悲しい雰囲気を纏っている。
「お、ブランコだ! 俺子ども頃ブランコ大好きで、休み時間中ずっと乗ってたよ」
また子どものように無邪気になった先生は、一目散にブランコへと駆け寄った。
「ブランコを高く高く漕いでいったらさ、空に浮かぶ雲の上が見えるんじゃないか届くんじゃないか、もしかしたら乗れるんじゃないかって、そればっかり考えて必死になって漕いでたなぁ」
「千悟さんの子ども時代って、すぐ想像出来ますね」
「あ! 然くんちょっとバカにしてるだろ? いつまでも少年の心を持ち続けるのは大切な事なんだぞ」
楽しそうにブランコを漕ぐ姿は、言葉の通り少年の心を大事にしていると教えてくれる。
「バカになんかしてないですよ。そんな千悟さんだからこそ、俺もこの町へ引っ越す決心が出来たんです」
名乗り出てくれたのが千悟さんではなかったら、多分俺は1人で生きて行く道を選択していただろう。
「嬉しいこと言ってくれるねー。じゃあその調子で悩み事言っちゃえ言っちゃえ!」
言われて、やっぱり千悟さんは凄いなと思った。俺のペースに合わせて、少しずつゆっくりと話をしやすい方向へ持って行ってくれていたのだ。
「まだ2回しか会った事無いんですけど、すごく気になる人がいて」
俺の発言に、茶化すような口調で言う。
「もしかして、好きな子だったりして?」
「いや、そうではないと思います。けど、自分でもこの感情が何なのかよく分からなくて……そういう意味でも困ってますね」
「あ〜なるほどねぇ」
深くは語らず、千悟さんは1人納得した。
「それとこの感情より困ってるのが、その人にとって恐らく一番言われたくない事を言ってしまったんです」
「それで怒らせちゃった?」
「いいえ。それが、怒るでも哀しむでもなく、ただただ拒絶されてしまって……」
思い出すと疑問が頭に浮かんで、言葉が詰まってしまう。
「だからあんな悲しい顔してたんだね」
「そんな顔、してました?」
指摘されて初めて、あぁ、悲しかったんだ、と思った。
「うん、してた。でも話を聞いて、ちょっと嬉しくなった」
「え、ひどッ」
俺の反応に千悟さんは慌てて謝った。
「いや、ごめん! 然くんが悩んでるのを見て愉しんでるわけじゃないんだよ! 大人でも子どもでも、生きていれば悩みが増えていく。特に人間関係なんて全世代共通のものだ。その悩みを然くんが抱えてるってことは、然くんにとって大切にしたい人が出来たんだろうなって思って」
「大切に、したい人……」
千悟さんは本当に自分のことのように嬉しそうに笑った。
「悩み事って確かに辛い思いをしたり悲しい気持ちになったりするけど、でも人はね、悩んだ分だけ成長するんだ。そう考えると素敵だと思わない?」
「はい、素敵です」
辛い、悲しい、と思っていたはずなのに、考えや物の見方を少し変えるだけで、素敵だと口に出来るほど前向きな気持ちになれた。
「千悟さんはやっぱり凄いですね。俺にとって千悟さんも大切な人の1人です」
「本当? 嬉しいなぁ。ちょっとでも然くんの力になれたみたいで良かった」
俺は単純だ。背中を押してくれる人がいて前向きになってしまえば、こんなにも簡単に動き出せる。
「俺さっきまで、また会いに行って拒絶されたらどうしようって、そればっかり考えてました。でも怖がってばかりではダメですね。色々確かめたい事もあるし、明日……もう一度会いに行ってみます」
悩んだり傷付いたりすることは構わない。でも、後悔だけは絶対したくないから。
約束の日は向坂家に泊まる事になってるのだけど、この日はそのまま寮に送って貰った。
◆❖◇◇❖◆
翌日の放課後、俺は宣言した通り藤の社へと向かった。その次の日も、次の次の日も、彼の場所へと足を運ぶ。今日こそは、という思いを胸に。
けれど、何度行っても、千咲の姿はなかった。あの不思議な猫も見掛けない。
そんな日々を繰り返して、一週間が経とうとしていた。
「然どうした? 最近元気ないじゃん」
夕食後、寮生数人と食堂で宿題をやっていると、良佑先輩から不意にそう声を掛けられる。
「え? あ、いや……そうですか? 普通ですよ」
普段通り過ごしていたつもりが、どうやら負のオーラを醸し出してしまっていたらしい。
「いんや! 元気ないね。俺、結構そういうの見抜く力すんごいんだから」
「暑苦しいけどな。でも、確かに元気ないとは思ってた。学校にまだ馴染めないんじゃないか?」
力強い発言をする良佑先輩に続いて総一郎先輩からも心配され、慌てて否定した。
「全然! 学校は、秀祐もいるし皆仲良くしてくれて楽しいです。ただ、何でしょうね……遅く来た夏バテですかね」
「何だよ〜夏バテかよ〜。俺はてっきり恋煩いかと」
「お前は本当に思考がおっさんだな」
「おっさん言うな! その前も暑苦しとか言いやがって! ちゃんと聞いてんだからな! 総一郎! ま、それは兎も角。トキさ〜ん! 然が夏バテらしいから、しばらくは喉通りやすく且つスタミナつく料理お願いしまぁす」
切り替えの早い良佑先輩は、明日の朝食の下ごしらえをしているトキさんに注文する。
「だいぶ難しいオーダーだな」
「あとおはぎも食べたいで〜す」
総一郎先輩のツッコミをバッサリと切り倒し、良佑先輩に便乗してリクエストしたのは紘さんだ。
「まぁた渋いメニュー出してきたよ、ヒロが」
「本当にな」
「YEAH、食べたいんで」
何故かノリノリで答える紘さんへ、総一郎先輩がすかさず指摘する。
「ラッパーか、お前は」
いつもの如く混沌を極めてきた会話をトキさんがニッコリと笑って綺麗さっぱり一纏めにした。
「はいはい。喉を通りやすいスタミナ料理とおはぎね。お任せ下さいよ」
就寝時間となり解散して自室へと戻る。
1人になるとまた、千咲の事が頭をよぎり始めた。もう会うことは無いのだろうかと、ベッドの上で考えていると部屋の窓がコツンと音を発てる。
窓の外は一階の玄関付近の屋根と繋がっていて、その屋根の上に人影がある。もうすぐ日にちを跨ごうという時間帯に、10歳くらいの少年が窓から部屋を覗き込んでいた。
少年は歴史の教科書で目にするような現代では見慣れない衣服を纏っている。部屋の灯りに照らされて煌くその少年の髪の毛は、見覚えのある銀色だった。
「君は、もしかして……あの、猫?」
窓を開けながら俺は少年に尋ねる。彼は、その幼い見た目には似つかわしくない含み笑いを零した。
「お前といい、千咲といい、勘が良いというか何というか。ちゃんと人を見てんだよなぁ……。そ、俺はあの猫、白銀だ」
白銀はそう言いながら、俺が手を差し伸べるより遙かに素早い身のこなしで、いとも簡単に窓枠をヒョイと越えて部屋に入って来た。
「だってその銀色の髪の毛、見間違うはずがない」
確かにこんな頭じゃそうか! と、笑い声を上げながら白銀は頭をガシガシ掻いた。
「というか何者? 人間だったの? もしかして……魔女から猫の姿に変えられてたとか?」
「そんな訳ねぇだろ。ファンタジーじゃあるまいし」
「人型になる猫なんてファンタジーでしか見ないよ」
本やアニメ、お伽噺の中の出来事だと思っていたことが、今現在目の前にある。
「俺だって元々は、つってももうずぅ〜っと昔のことだが、一応飼い猫だったんだぜ」
「ずぅ〜っと昔って……今何歳なの?」
「歳? う~ん、500歳は越えてると思うが、途中から数えるの面倒になって忘れた!」
確かに、100年も生きられない人間ですら年齢を忘れることがあるというのに、500年も生きていれば分らなくなっても当然だ。
「まぁ、それもそうか。でも500歳を越えてるって、10歳くらいにしか見えないんだけど?」
「あー、この姿は今のお役目を務めるのに色々と便利なんだよ」
「お役目? って、何するの?」
ずっと質問してばかりだな、と思いつつもやっぱり質問してしまう。
「最近じゃもっぱら神様の花嫁の遊び相手と化してるが、一応はつかわしめってやつだ」
それでも白銀は嫌な顔一つせず、一個一個答えてくれる。
「つかわしめ?」
聞きなれない単語も、きちんと噛み砕いて説明してくれた。
「まぁ何だ? 神の使いって言ったら分かり易いか。神様の言葉をお告げとして人間に伝えるモノ! なんだと」
ニカっと笑う白銀。
「何か他人事な言い方だよな」
「いや、だってさっきも言ったが最近じゃあんまりその役目ないし、俺が仕えてる神様ってのはな……まぁ、アレだ」
白銀はそこまで口にして言い淀んだ。
「アレって、全く分かんないんだけど。ていうか神様とか言い出してる時点で、やっぱ十分ファンタジー」
「あーまぁ、そう言われればそうだな!」
綺麗な見た目には不釣り合いな豪快な笑い声。でもその笑い声で落ち込んでいた気持ちが励まされて明るい気持ちに変えてくれる。
「何だろう、猫の時と随分雰囲気が違う気がする。もっと冷静とか静穏とか澄ましてるイメージだった」
「気のせいだ、気のせい! ん? つーか失礼な奴だな」
「誉めてるんだよ?」
生意気な俺の言葉に、白銀は嘘吐け! とまた底抜けに明るい笑い声を上げた。
そしてその笑いが治まった後、猫の姿の時を思い出させる凛とした顔つきになった。その表情や態度は、長く生きてきた事を窺わせる。
「ま、俺の話なんてどうでも良くって、本題は全く別。神様でも仏様でも何でもなく、俺自身が思ってることを然に伝えに来た」
今から話す事、理解は出来なくても良い。でも、何も言わずに聞いてくれと、そう前置きをして、白銀はゆっくりと語り始めた。
「もう誰かから聞いたかもしれないが、あの藤はな、この辺りの守り神でありながら……人間から、命を奪うんだ。近くに居過ぎれば少しずつお前の寿命を吸い取っていくだろう。触れれば最悪、即座に死んでしまう場合もある」
この説明を聞いて、理解した。だからあの時千咲は藤の実に触れようとした俺を止めたんだと。
「千咲が然を遠ざける態度を取ったのは、それが理由だ。そして然が千咲にとって大切な存在で、千咲が守った命にとっても大切な人間だからだ。それは俺も同じ気持ちで俺もお前を守りたい。だから然、もうあそこへは来るな。お前に与えられた時間を無駄にしないでくれ」
俺の返事は聞かず、白銀はまた顔見に来るからと言い残して、来た時と同じように素早く部屋を出て行った。
秋の訪れ Ⅰ
早朝から寮の台所と食堂では、トキさんによる料理教室が開かれていた。
「然くん! 焦げる焦げる!」
どこか上の空だった俺は快斗先輩の声でふと我に返る。
「え? あ、うわっ」
指で示された手元に目をやれば、フライパンの中で良い音を奏でる黄色い卵焼き。危うく焦げる寸前のそれを、慌ててパタンパタンと折り畳んで巻いていく。
「コレくらいならセーフでしょ」
焼き具合を確認して快斗先輩が判断してくれた。
「ですよね? よかった、焦げなくて。有難うございました」
こうして料理をしているのは、今日が月に1度の自分でお弁当を作って学校に持って行く〝お弁当の日〟だから。何を作るか決めるのも、買い出しも、調理してお弁当箱に詰めるのも、後片付けも、全て自分自身で行うのがルールだ。
「どういたしまして。もしかして朝早くてまだ眠い?」
「はい……。快斗先輩は眠くなさそうですね。他の皆も」
朝から爽やかな風が吹く快斗先輩に眩しさを感じながら、皆を羨むと案外簡単な答えが返ってきた。
「ヒロと然くん以外は部活生だから、朝練とかで早起き慣れてるもんね」
「あ、そう言われてみれば紘先輩も確かに眠そう」
快斗先輩とは反対側の隣にいる紘先輩が眠そうな声を出す。
「眠いよー。あと10分で良いから寝たいよー」
「急いで作れば少し眠れるんじゃないっスか?」
時計を見て逆算した拓馬が、紘先輩に悪意の無い知恵を授ける。
「だよな? よっしゃ、さっさと作るぜ☆」
「そのテンションならもう寝なくて良くねぇ?」
テーブルを挟んだ真向いで紘先輩を見ていた大輔先輩が、ハイテンションを指摘した。
「いや、寝る! 俺は絶対寝る! 寝る、絶対」
「どっかのキャッチコピーみたいに言うな」
紘先輩の寝る宣言に大輔先輩のツッコミが飛ぶ。そんな皆のやり取りを聴きながら卵焼きを作り終えると、快斗先輩がしみじみ言った。
「てか然くん、めっちゃ手際良いよね」
「それに美味そう」
良佑先輩が快斗先輩の横から顔を出し、俺のお弁当を覗き込む。
「母さんから結構料理を教わってたので。そうだ、卵焼き余りそうなので、良かったらお弁当に入れるか食べるかして下さい」
「ヤッターラッキー♪……うまッ」
「あー! 良兄ズルいぞ!」
すかさず口へ頬張った良佑先輩に秀祐の文句が。
「よく食う奴だな。さっきは拓馬からしょうが焼きのお裾分け貰ってただろ」
「育ち盛りだからな、俺」
「全員そうだろーがッ」
総一郎先輩への返事をもごもごしなからする兄に秀祐が正論を放つ。
「じゃあ僕はお弁当に入れさせて貰おっかな」
そんな中でも冷静な快斗先輩は丁寧にお弁当の中に卵焼きを詰めた。
「さぁ皆、出来上がったら朝ご飯だよ」
トキさんの言葉に皆それぞれ返事をして、自分の作業を進める。
そうやって出来上がったお弁当を携え、朝食を済ませた後皆で学校へと向かった。
◆❖◇◇❖◆
月日が流れるのは早いもので、藤棚へ行かなくなって3週間が過ぎようとしていた。
相変わらず俺は千咲の事ばかりが頭を巡っている。 家にいても授業中でも、誰かと一緒にいても一人でいても。今朝だって寮の皆と賑やかに過ごしている中でも、卵焼きを焦がしそうになる程ぼーっと考え込んでしまう。
千咲と白銀から言われたことの真意を思案しては、全てを理解出来ない自分が歯痒かった。
こんな風に、考えても仕方のない事を考え続けるくらいならいっそ会いに行けば良いのだが、どうしてもそんな気にはなれなかった。と言うよりも、行ったところで千咲は居ないだろう。そんな確信があった。
「授業終わったぞ。おーい、然」
「ん? 何?」
「ん? じゃねえよ。授業終わったぜ!」
終着点のない考え事をしている内に、午前中の授業が終わっていた。 秀祐の声で現実に引き戻された俺は周りを見渡すと、クラスの皆はもう各々の行動に移っていた。机を寄せ集めてすでに昼食を始めていたり、お弁当を持って別の教室に移動したりしている。何と言っても、月に1度の自らが調理した弁当を持って来るお弁当の日という事もあり、いつもの給食時より賑やかだ。
「うわ、本当だ。ごめん、秀祐……」
俺も慌てて机の上を片付けた。
「然、最近心ここに在らずって感じ多いよな。朝も卵焼き焦がしかけてたし、何かあったのか?」
どんな時でも元気で明るい秀祐に、心配そうな顔をさせてしまい胸が軋んだ。
「いや、何でもないよ。って言いたい所だけど、本当は凄い悩んでる」
「そっか。俺が聞いても大丈夫な話?」
少し探るように尋ねられる。
「大丈夫だと思う。ただ、俺の頭の中できちんとその事を整理しきれてなくて……。だから、話せるようになったら話す。それでも良いかな?」
「いいとも〜! じゃなくって、無理して話そうとしなくて良いからな!」
「あぁ、有難う。どうにもこうにも行かなくなったら、文字通り体当たりで相談するかも。秀祐頑丈そうだから」
「そうそう、俺は頑丈だけが取り柄……っておい! 俺だって繊細なお年頃だぞ」
ノリツッコミで明るさを取り戻した秀祐を見て少し安心した。
「ははは、秀祐って意外といじり甲斐あるよね」
「然は時々サディスティックだよな。まぁでも本当に、こう見えてどんな事でも受け止められるから、かかってこんかぁ〜い」
「流石にそのセリフは繊細なお年頃の人は使わないと思うわ」
「そうです! 俺は逞しい人間です!」
秀祐のいさぎの良い宣言に二人して笑っていると、廊下から元気な声が飛んできた。
「朝倉くーん! ついでに秀祐も。今日外の方が気持ち良いしさ、一緒に中庭でお弁当食べようよ!」
秀祐と同じくいつも明るい瑞穂が、元気に手を振っている。
「ついでとは何だ! 瑞穂!」
「ついではついでよ!」
「ああ? お前が俺と一緒に弁当食いたいだけだろ!」
「はあ? 自惚れんのも大概にしてよね! 誰がアンタなんかとお弁当食べたいもんですか」
いつものことだけれど、未だに慣れない二人の喧嘩腰の会話の前で割って入るべきか迷っていると、よう子がフォローしてくれた。
「あー、この2人は昔からこうなのよ。もう放っておいて先に行きましょう、朝倉君」
だが、その対応が二人は不満なようで。
「「こら! ツッコメよう子!」」
3人の漫才に凄く元気をもらった。
◆❖◇◇❖◆
お弁当を抱えて外に出ると、瑞穂が言った通り風が心地よかった。
「あ〜やっぱり季節は秋が1番好き!」
中庭のベンチに4人並んで腰かけ、お弁当を広げると同時に瑞穂が言った。
「食欲の秋って言うからなぁ。食い意地の張った瑞穂にはお似合いだぜ。俺は断然夏。海! 川! 大好き!」
秀祐はまた瑞穂が怒り出しそうなことを口にする。
「うっさいわね! 秀祐なんて夏になるとさらに暑苦しくてウザったいじゃない」
「な!? 良兄と比べれば俺はまだ涼し気な方だ!」
秀祐は身近な人物を引き合いに出す。
「……そうね。良兄は秀祐以上、と言うか情熱的って単語も加わるから猛暑並なのよね」
それに対して瑞穂は深く納得した。
「だろ? だから俺は───」
「それでもやっぱりウザったい」
「んだとぉ!?」
「まーた始まったわ。私はいつ二人の相手しても寒さで冷静になれる冬が好き」
「よう子……今日は一段と毒舌でいらっしゃる」
「つか、どんどん氷のように言葉が冷たくなってるよな」
秀祐と瑞穂の会話を無視して、よう子が俺に聞く。
「朝倉君はどの季節が好き?」
「俺? 俺は、春かな。冬から春に変わる頃に吹く暖かい風に包まれると、何となく寂しい気分になるんだけど、でもそれが好きかな」
俺の答えを聞いた三人は口々に感想を述べた。
「朝倉君てやっば繊細だよね」
「うん、何か清純って感じ。どっかの誰かさんとは大違い」
「確かに。どっかの誰かさんと違……って俺のことかいッ!」
俺だって繊細だ! と言い張る大輔を、3人ではいはいと受け流す。
久しぶりとなる外でのお弁当は、寮の皆と一緒に作り秀祐達と食べたという事もあってとても美味しく感じた。
食べ終わって一息ついていると、何処からともなく声を掛けられる。
「おーい、そこのお若いのやー」
声の主は良佑先輩だった。
「だからお前はオヤジかって。いや、オヤジ通り越してじいさんか」
「皆でバレーボールやらね?」
総一郎先輩のツッコミを華麗にスルーして手にしたバレーボールを構える。
「良いですねぇ! こてんぱんにしてやんよ、良兄」
良佑先輩の提案に誰よりも早く賛同したのは瑞穂だ。彼女は高田兄弟全員と幼い頃から親しくしている。
「言うじゃねぇか瑞穂。喰らえ、今中のスローカーブ!」
「それ、野球だから。てかマジでお前何歳だよ」
「俺、球技苦手……」
この発言から良佑先輩の予想外な事実を知る。
「大丈夫大丈夫。良兄も野球以外の球技苦手だから」
「なのにどうして他の選択をするのかしらね。おバカさんなのかしら」
「苦手だからこそ熱くなれるらしい。訳が分からん」
「元々暑苦しいのに、困った兄だ」
「良兄だもん、仕方ないじゃない」
移動しながら皆で愛ある陰口を叩いていると良佑先輩が叫ぶ。
「お前らー全部聞こえてるからなー!」
かぎろひの君


