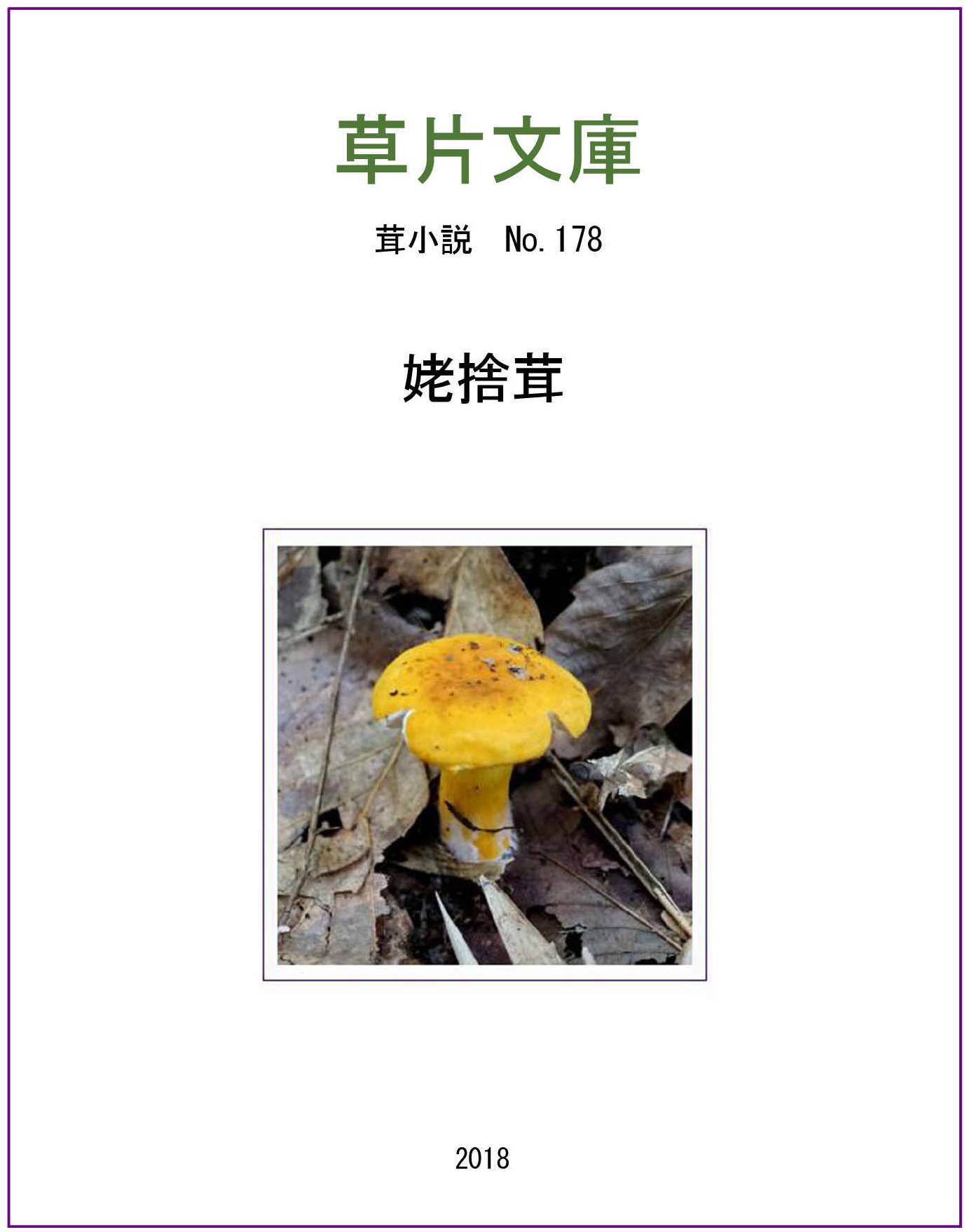
姥捨茸
「ばあちゃん明日だなあ、暖っけえうちにいきゃあ、からだもなれるべえ、わりいなあ」
息子はおっかあの、菊のことをばあちゃんと呼ぶ。子供たちがばあちゃん、ばあちゃんとしたっているから、そうなっちまった。
「にゃにをいっとる、おまえら夫婦は子供八人もよう世話しちょる、いい嫁さんでよかったの、安心してあちらにいけるで」
継ぎはぎの短い着物から、日に焼けた太い足を床にのばして、壁に寄りかかっている嫁は、節くれた太い指で膨らんだ腹をなでている。もうすぐ九人目の子供が産まれる。嫁は目に涙を浮かべて声にならない。
最後の夜なのに、芋すら姑に食べさすことができない。野菜の端くれを茹でて、ほんの少しあった味噌で味を付けた。子供たちには器に八分、夫婦は半分、明日山に入るばあさまにも八分、それが精一杯。
菊ばあさんは若いときから野良仕事に精を出し、やっぱり八人の子供を育てた。畑をする傍ら、山菜や茸採りが得意で、大いに家を助けてきた。ともかく茸に詳しい、菊ばあさんに聞くと毒か食えるかすぐわかる。
「ほんとに、熊山でいいんかね」
このあたりの年寄りはみな笹山にいく。笹山には野天湯もあり、気持ちよく死ねるという話だった。ところが菊ばあさんは熊山がいいという。熊山は今こそ原生林に覆われているが、その昔は大きな噴火をした火山だったそうである。もちろん大昔のことで、今は自然豊かで動物たちがたくさんいる。熊も多い。しかし怖くて猟師しかはいらん山である。
「熊に食われるぞ」
「なに言っとる、どうせ死ぬんじゃ、熊の餌になりゃ本望じゃ、役に立つだろう」
「だが、熊を捕まえても食えんようになる、ばあさまを喰った熊かもしれんからの」
このあたりじゃ熊なんぞが穫れたらごちそうで大喜びである。
「大丈夫じゃ、わしが熊を食うんじゃ、石をぶつけてやっつけてな、ついでに熊の胃をとって長生きするぞ」
元気なばあさんである。
姨捨の風習はいろいろな話になって残っている。長野の篠ノ井線に姥捨てという駅がある。駅から見下ろす善光寺平の棚田風景は見事である。川中島の合戦の場でもあった。しかし、菊ばあさんの住んでいるこの地はそう言った豊なところとは縁もゆかりもない山奥の寒村である。まだ野武士が闊歩している時代のことである。
朝になった。太陽が山から少し顔を出した。まだ薄暗い空に浮かんでいる雲の下が橙色に染まっている。今日も五月晴になるだろう。
息子に付き添われ、菊ばあさんは熊山に向かった。自分で編んだマタタビの蔓でできた籠、火打ち石、古い布、塩、それに自分の茶碗が入っている。
熊山までいくつかの山を越して、二里も歩かなければならない。熊山は高く険しい山だが、そこに行き着くまでが大変である。熊山には滝があったり、いくつもの洞窟があったりする。そういうところでは熊に出会うことが多い。だが熊の住んでいないうまい洞窟に行き当たれば、冬でも雪にあわないですむ。
菊ばあさんは六十とは思えない足取りで、息子と同じ速さで登っていく。
やがて道が途絶えた。そこで菊ばあさんとお別れだ。
「ばあちゃん、ごめんな、ここまでじゃ」
「おめえが謝るこたないだろう、どのうちでも年寄りは山に入るんだ」
「だけんどな」
息子が包みを渡した。
「なんじゃ」
「飯じゃ、握り飯」
「どしたんだ米なんて、こんなもん食えん、嫁にやれ、もうすぐ生まれるんだろう」
「庄屋さんが菊さんにと都合してくれたんだ、嫁が炊いた」
「いい嫁だ、ほれ早く戻れ、この握り飯はわしの弔いだと思って、嫁さんと二人で食え、おらは道を探していくで、狐や鹿なんぞの弱いものの通り道を探せば、熊なんぞにはあわん、元気で子どもをこしらえろや」
菊ばあさんはそう言うと、背を向けて歩いて行ってしまった。
息子はしばらく立っていたが、くるっと後ろを向いて山を降りていった。
熊山までいくつか山を越さなければならない。菊ばあさんは山の中をさくさくと草をかきわけ登っていった。山の稜線にでると、尾根づたいに次の山にはいった。
あと一つの山を越すと子熊山になる。子熊山を越せばやっと熊山だ。
子熊山にも道らしき道はない。最近動物が通ったと思われるところの、たおれている草を踏んでいく。
しばらく行くと尾根の一つにでた。少しばかり見通しがよくなった。お日様の位置から方角がわかる。山菜や茸採りのときに自分の場所をそうやって知った。ばあさんの背に日が当たっている。正しく西に向かっている。尾根を少し歩くと、子熊山の頂上よりもっと高くそびえたつ山が見えた。山腹の所々に大きな岩が飛びでている。それが熊山である。
子熊山の林の中に足を踏み入れると、伸びた下草の中を降りていく。子熊山をぐるっと回って熊山の前に出るのだ。
小柄なばあさんが歩く後姿は、狸が二本足で笹をかき分け進んでいくようにも見える。もう山に溶け込んでいる。
お天道様が上の方に見えるようになってきた。だいぶ子熊山を下ってきた。木々の間から谷川が見えた。熊山と子熊山の間には川がある。かなり大きな川である。谷川の見えるところまで降り、川に沿って上流に向かっていけば、滝があるはずである。熊撃ちが得意だった死んだじい様に聞いたことがある。菊の旦那はよく働く男で、畑でも何でもやって、その上熊猟もやっていた。
菊ばあさんは山の中をせっせと降りて行った。かなり河原が近くなる。水の音が聞こえてくる。見通しのよいところにでると菊ばあさんは倒木に腰掛けた。下のほうに河原が見える。反対側の熊山の裾の林の中は暗くて見通せない。しかし子熊山と同じように深い林だ。
ふと、腰掛けていた倒木の脇に手をやると、ぷるんぷるんとしたものが指に触れた。木耳だ。顔を向けてみると、やっぱりそうだ。茶色い木耳がばあさんの座った木の幹にたくさん生えている。このあたりは茸が採れそうだ。
木耳はうまい茸である。ばあさんはむしり採るとかごに放り込んだ。塩をほんのちょっとつけて生で食った。ばあさんの口元がほころんだ。
口をもぐもぐ動かしながら、川向かいを眺めていると、林の中に黒いものが動いている。熊のようだ。怖いことは怖いが、図体の大きな熊が生活しているということは、生き物が住むのによい環境であることを示すものでもある。
木耳をもう一つ口にいれ、眺めていると、案の定小さな子供を二頭連れた親熊が、林から出てきた。河原におりてきて川縁を眺めている。魚を捕るつもりだろう。ヤマメなど川魚がたくさん泳いでいるに違いない。親熊が水しぶきを上げた。口には魚を咥えている。子熊が川縁にやってきた。母熊が上がってくるのをまっている。母熊は魚を河原の石の上にのせた。飛び跳ねて石の間に落ちた。二匹の子熊が探している。母熊はまた水の中に入った。もう一匹捕まえるとまた子熊に与えた。やがて子熊たちが食べ終わったのだろう、母熊は再び林の中に入っていった。子熊もついて行く。
ばあさんも河原に降りてみた。川幅はそれほど広くない。水の量もさほど多くない。しかし渡るのはちょっとむずかしそうである。ばあさんは河原を上流に向かった。その先に滝が見える。そこから上に登り、滝の上から熊山に入ろうと思ったのだ。
谷川はだんだん狭まってきた。大きな石が目立つようにった。歩きにくい。ばあさんはもう一度子熊山の林の中に入った。下草を掻き分け、木の陰から谷川を見下ろしながら歩いていくと、ざあざあと水の落ちる音がする。滝の音だ。意外と近い。
下を覗くと滝壺が見える。さほど大きな滝壷ではない。
木々がさえぎって滝がはっきり見えない。下に降りようとしたのだが、林の下は断崖のようになっている。降りる道がない。ばあさんはきたところを少し戻って降りる道を探した。河原に降りることのできそうな斜面になった。ばあさんは気をつけながらゆっくりと河原に下りた。大きな石がごろごろしていて、歩くのに大変だったが何とか歩いていくと滝が見えてきた。熊山と子熊山をつないでいる断崖の途中にある洞窟から水が流れ落ちている。きれいな滝である。
滝壺の縁からあふれ出た水が谷川の流れをつくっている。ばあさんは滝つぼの縁に登った。中を覗くと泳ぐ魚が見える。
「いいとこじゃな」
菊ばあさんは石に腰掛けた。
今日はとりあえずこのあたりで野宿かと考えていたときである。
稲光のような青白い閃光が走り、目の前の風景が白い光に溶け込んで、見えなくなってしまった。
ああお迎えが来てくれたのか、ありがたい。菊ばあさんは目をつむった。その拍子に、どどーんという音がして、あたりがぐらぐら揺れ、ばあさんは石からおちそうになった。あわてて目を開けると、もうもうとした砂煙とともに、空の上に白い雲もくもくと湧きあがっている。雲じゃない、煙だ。
熊山が爆発した。
菊ばあさんは慌てて河原をもどって子熊山の林の中に駆け込んだ。
またどどーんと音がした。熊山からあがる白い煙は、川の下流の方向にたなびいている。爆発したわりには火は見えないし、黒い煙は上がっていない。
すると大きな揺れがきた。ばあさんは手頃な木にしがみついた。
川の反対側に砂埃が舞い上がり、がらがらという音ととも熊山の斜面が崩れ落ちた。生えていた木が倒れ、河原は倒木と石で埋もれてしまった。
滝がどうなったかばあさんからは見えない。
しばらくすると揺れは落ち着いた。空には白い煙が上にのぼっている。
ばあさんは河原に降りた。滝が流れ出ている断崖は何も変っていなかった。水はかわらず流れ落ちている。滝壺まで歩き、水面に目をやると木々の枝が散乱して浮いているが水はさほど濁っていない。
ばあさんは下流に向かって歩いた。熊山側では所々山崩れが起きて、生えていた木が土砂とともに滑り落ち、川の中に転がっている。流れている水は茶色に濁り、死んだ魚がたくさん浮かんでいる。食ったらうまい魚だ。
子熊山の中を最初に降りた所までもどった。熊の親が魚とりをしていたところだ。
その時、また大きな揺れがきた。あわてて林の中に入り木につかまって、しゃがみこんだ。
反対側の斜面の一部がふたたび崩れ落ち、木や石が河原に押し寄せてきた。水のしぶきが舞い上がった。
土ぼこりがおさまり、様子がわかるまでかなりかかった。
対岸のほうはまだほこりのたつじょうたいだったが、ばあさんは河原に戻り様子を見た。熊山からおちてきた石や木がこちら側まで転がってきている。
おや、と見ると、河原に大きな黒いものがひっくり返っている。
ばあさんは川っぷちに行った。熊山から崩れてきた石の間に熊が横たわって口角から舌をだらんとのばしている。落石に当たって土砂におされて反対側にきてしまったようだ。
熊山の斜面を見ると、崩れなかった林の中から二頭の子熊が河原に降りてくる。対岸の河原をしきりと歩き回っている。母熊を探しているようだ。
菊ばあさんはしばらくその場で様子を見ていた。
その後何度か小さな地震があった。そのつど子熊山に逃げた。ばあさんのいた子熊山の側には被害はほとんどないようだ。熊山の斜面の崩れ方はひどい。
空を見上げると、もう噴煙は細くなっている。あまり大きな噴火ではなかったようだ。それにしても村の連中は騒いでいるに違いがない。きっと息子たちはわしがおだぶつになったと悲しんでいるだろう。それでいい。
ばあさんは浮いた魚を何匹か拾うと、枯れ枝を集めて火をつけた。石を熱くして、その上に魚を乗せると、上手に焼いた。腹ごしらえだ。
いい匂いがしてくる。
「なんだべ、家にいたときよりうめえものが食える」
ばあさんは焼けた魚をほうばった。
「うめえ」
反対側の二匹の子熊がこちらを見ている。魚の匂いにつられたのかもしれない。
転がってきた石が川の中に点々とあり、向こう側に行くのはたやすくなっている。
ばあさんは魚を二匹拾うと石の上をわたって反対側に行った。子熊は犬ほどの大きさだ。乳離れをしたばかりなのだろう不安そうである。
相当腹が減っているようだ。ばあさんは子熊に魚を見せた。
子熊がよってきた。
ばあさんが魚をやると不器用にかじりついた。
「よっしゃ、育ててやるべ」
子熊が魚を食べ終わる頃にまた魚をもっていった。
子熊たちは腹がいっぱいになると、菊ばあさんにこすりついてきた。ばあさんは鼻の上をなでたり、体に触れたりかわいがった。子熊たちは眠くなってきたようだ。
ばあさんは子熊をせき立て残っている林に入った。林の中で野宿するつもりだった。
子熊は早足になった。行くところが決まっているようだ。ばあさんも後をついた。子熊が羊歯の茂みの後ろに消えた。ばあさんが行ってみるとそこには大きな穴があった。熊のねぐらだ。子熊は自分の巣穴に戻ってきたのだ。
ばあさんもついて入った。暗くてよく見えないがかなり広い。子熊はいつもの寝床なのであろう、隅で二匹寄り添いながら寝てしまった。
なかなかいい穴だ。いいところがあったものだ。
菊ばあさんは穴からでると、細長い石の欠片を拾い、それをもって反対岸の死んだ母熊のところに行った。まだ暖かい。
ばあさんは石を使って熊の腹を裂いた。石はいい包丁になった。皮膚がいっきにうまく裂けた。内臓をひっぱりだすと、まず胆嚢をとりだした。
「熊の肝はいい薬じゃ」
若い頃、男どもが熊を射止めて村に持ち帰り解体をしたことがあった。それをばあさんは見ていた。
記憶を遡って、爺さまたちがどのように熊を処理していたか思い出した。
食べられそうなところは、すべて切り出したのである。切り出したものは石の上にならべた。ずい分時間がかかった。胃や腸や子宮は後で火にあぶっておこう。心臓だってうまい。脂肪は脂を取ったり出来る。脂は明かりにもなる。肉を剥ぎ取った骨は曝しておけば、いろいろなことに使える。頭蓋骨は器にもなる。肉片を取り除くと石の上に載せて日にさらした。
最も大きな収穫は皮である。ばあさんは皮から脂を擦り取り、たたくと大きな石の上に広げた。しばらく経てば使えるようになるだろう。
作業を終えたばあさんは腰をのばした。疲れた。
「えらえ、てえへんだったわい、だけどここへきて、こんなごちそうがまってるとは思わなかったのう」
空を見上げると、噴煙は細くなったが、まだ空の上にたちのぼっている。
「子どもまでできちまった」
菊ばあさんは笑いながら水際に行った。茶色かった水が少し澄んできた。死んだ母熊のいらない部分を川に放り投げた。
浮いている魚を拾えるだけ拾った。内臓をとると、石の上で開きにして曝した。いくつかは干物になってくれるだろう。子熊の餌にもなる。
「ずいぶん働いた」
そう言いながら、熊の穴にもどった。暗くて奥の方は見えないが、入ってすぐの所で寝ている熊の子供たちは見える。ばあさんは子熊の頭をさすった。その脇にもってきたぼろ布を引くと横になった。
「明日は林の中を歩いてみようのう」
そう言いながらあっと言う間にいびきをかきはじめた。寝ている間に弱い地震が何度かあったが目を覚ますことはなかった。
菊ばあさんは冷たいものが顔に押しつけられるのを感じて目を覚ました。子熊の鼻が頬の前にある。身を起こすと二頭の子熊がばあさんの周りをうろうろしている。穴の外は少し明るい。もう朝である。家をでて丸一日だ。
いろいろなことがあったな、などとばあさんは考えることをしない。ともかく今である。動くことだけを考えている。竹筒から水を飲むと穴をでた。河原に降りてみると、水の濁りがほとんどとれている。
反対岸にはばあさんが解体した熊の皮や臓物が石の上にならんでいる。旨く干されれば食料になる。
ばあさんは滝壺に向かった。子熊たちがついてくる。
滝壺はなにも変わることが無く、きれいな水が静かにたゆっていた。
水を口に含んでみた。うまい水だ。顔を洗った。
滝壺の周りを歩くと、編傘茸が生えている。春の茸だ。この茸は食べることをしないところが多いが、ばあさんの村ではうまい茸としてよく食われていた。これはごちそうである。生で食べると腹をこわすが火を通せば大丈夫だ。子熊は平気でそのまま食べている。いったん籠をとりに戻ると、編傘茸をいっぱいにして、河原に干した。
枯れ枝を拾ってきて火打ち石を打った。火が大きくなると、石の上に広げておいた魚を焼いて食った。
そのうち魚捕りもしてみよう。そのための笊と籠を編まねばならない。蔓はたくさんある。アケビがあれば一番いい。あれは薬にもなるが若い芽は食える。ばあさんは村の川で川エビやナマズをよく捕まえたものである。ナマズがいるとは思えないが、蛙だって食える。
子熊を連れて林に入った。山菜は豊富だ。ゼンマイがこのあたりではまだ生えていた。こういうものも干しておくと、いつまでも使える。今食うもんは探せばいくらでもあるから、冬のためにも準備しておく必要がある。
ばあさんは辺りを見て回った。ハゼの木を見つけた。木の下にはたくさんの実が落ちていた。まだ使えるだろう。子熊は落ちた実を食べている。秋遅くに生るハゼの実は種を包んでいる周りの部分を熱せば蝋がとれる。蝋燭の材料である。そのままでも火をつければ燃える。後で集めに来よう。
マタタビが木に絡んでいる。奥に入れったらアケビはいくらでもあった。どちらも籠や笊が編める。そうすれば魚をすくえる。穴の中の敷物もつくろう。ただ石の欠片しかもっていないばあさんは、切り取るのに苦労をした。しかしこれから時間は十分ある。夏になればもっと動きやすい。ともかく熊の皮が手に入ったのは助かった。寒さをしのぐには最適である。土砂崩れで死んだ動物がいればその皮ももらおう。
こうして保存食を作ることと、蝋を作ることに精を出し、蔓も編んだ。住まいの穴の周りに石を積んで囲いや竈を作って火を絶やさないようにした。
ハゼの実から蝋がとれてからは、枯れたアケビの蔓を叩いて芯にしてろうそくを作った。お陰で熊の洞窟の中を詳しく調べることができた。かなり奥まで広がっている。石をところどころに置いて蝋燭を立てた。子熊たちも蝋燭の火になれた。
穴の奥には保存食をしまういい横穴もある。横穴の底に石を敷き、食料を庫にした。
毎日毎日家づくりに励むことで、熊穴は一段と住みやすくなった。熊山はそれっきり爆発をすることもなく平穏な日が続くこととなった。
子熊たちとなかよく歩き回る毎日である。辺の様子もよく分かってきた。
熊たちは一月もすると犬の倍以上になった。菊ばあさんを母親と思っているのであろう、いつもあとをついて歩いた。
ある日、ばあさんは熊にまたがってみた。まだ子供の熊であるがばあさんが小さいこともあり、いやがる様子もなく、むしろ喜んで林の中を歩き回った。ばあさんは二頭の熊に代わる代わるまたがった。ずい分らくちんだ。移動手段まで手に入れてしまったのだ。
自分で作った籠を背負って、熊にまたがり山歩き。金太郎もどきだ。
菊ばあさんが熊山でそのよう生活をしていようとは、村の息子達には想像もつかなかったに違いない。
夏になると、二頭の熊が滝壺に入って水浴びをするようになった。深い滝つぼだったが一ヶ所浅いところがあった。熊とばあさんは暑い日は水に浸かった。ばあさんも真っ裸で滝に打たれた。
そのころになると熊たちは自分で食べ物をみつけることができた。木苺など木の実をよく食べた。むしろばあさんは熊たちの食べ残しをもらってそれで十分なくらいだった。村にいるときより顔色がいい。熊が蜂の巣を見つけ咥えてもってきた。蜂蜜がたっぷり入っている。村にいたらこんなに甘くて旨いものは食えなかっただろう。孫達にも舐めさせてやりたいものだ。
住まいの穴もずいぶん便利になった。蝋燭の作り方も上手くなり、穴の中はいつも明るい。上手に石を積んで竈を作り、その上の石を温めて料理をした。
秋になると大変だった。至る所に食えるキノコがボコボコ生えた。舞茸、鳶茸、うまい茸がわんさかとれた。これも孫たちに食わしてやりたいものだ。ばあさんは村の生活を懐かしいとは思わなかったが、家族がまともなものを食っているかどうか心配だった。たくさんの茸を干して蓄えとした。アケビや山柿、いろいろな秋の木の実が食卓を賑わした。熊たちも果物は大好物だった。なんといっても熊たちはドングリが好きだ。熊達は地面一面に敷き詰められている落ちたドングリの中で両足を投げ出し、お尻で座ると、ドングリをつまんだ。器用なものである。
それまでに、いくつかの動物の毛皮が手に入った。死んだ鹿の毛皮をとった。角は石で砕くと、とがった所が残り、それが包丁のかわりになった。小さな獣の毛皮で靴のようなものをつくった。雪が降るようになったら使おうと思ったのだ。
蔓をたたいて編み、着るものを作ったりもした。
秋も終わるころ胡桃や栗をリスのように集め穴の中にしまった。
熊たちはずいぶん大きくなった。胸の白い輪の模様がくっきりとしてきた。まだ大人の大きさではないが、ばあさんに寄りかかるとばあさんは押し返すのに大変だ。
寒くなってきた。熊たちの動きはにぶくなり、穴の中にいることが多くなった。
秋も深まると、二匹の熊は穴の中で寝たきりになった。ばあさんは熊たちの腹に寄りかかって寝た。何しろ温かい。
雪が降り始めたが穴の中は暖かかった。
やがて外では雪が降り積もり、穴の入り口はふさがれてしまった。ばあさんは入口に積もった雪に穴を開け、自由に出入りできるようにした。
そういったことで雪の状況でもばあさんはなに不自由なく暮らしている。乾燥したものはたくさん穴の中に保存してある。穴の入り口近くの雪の中には茸や秋の木の実、山菜が埋めてある。干したものとちがって、溶かせば新鮮な状態で食べることができる。ばあさんは特に山柿が好きで毎日一つ食べるようにしていた。
冬眠した熊たちは時々眼をさます。そのとき熊はばあさんに擦りつき、ばあさんは頭をなで、熊はふたたび眠りにつく。
春になり再び林の中はにぎやかになる。熊たちは魚を捕り、木の芽を食べる。ばあさんもおこぼれにあずかる。熊たちはとうとう死んだ母熊と同じほどの大きさになった。二匹とも雄のようだ。
瞬く間に三年が過ぎた。菊ばあさんはますます元気になった。木や蔓をたたいて繊維にしたもので作った布や動物の毛皮を着て、毎日を充実して暮らしていた。すきま風が自由に通り抜ける今まで住んでいた家より暖かい穴があった。しかも大きくなった熊はばあさんを乗せてどこにでも行った。熊はばあさんの言うことをよくきいた。
熊たちはもう親離れの時期のはずだったが二匹ともばあさんから離れようとしなかった。
「育て方を間違えたかもしれんにゃ」
ばあさんはそう言いながらも笑いながら熊たちをかわいがった。
その年、熊たちは何日も穴に帰ってこないことがあったが結局二匹とも戻ってきた。
今年は空気がちょっと暖かいようだ。雨が少ないので滝の水が少ない。しかし、きれいな水が滝壺を満たし、たくさんの魚が泳ぐのが見えた。
菊ばあさんが熊山に入って五年、村に飢饉がおそっていた。干ばつである。雨が降らず、米がいつもの十分の一しかとれなかった。野菜類も萎びたものだけである。息子の家族はあれから二人増えていた。
「ばあちゃんはどうしてるべ」
息子の嫁は菊ばあちゃんが好きだったようだ。
「んーん、ばあちゃんが入ったとたん熊山が爆発しよったからな、助かってればいいが、助かってもこの日照りじゃ食いもんがありゃせん」
「もし生きとったら、あっちのほうが涼しいからええんじゃないかね」
嫁はまた身ごもっている。
「そうかもしれんが、だけんどばあちゃんが今おったら、ここじゃ食えんようになっとった、助かったな」
「ほんに、申し訳ないけどな」
「庄屋さんが言っとった、ずーっと遠くだが野武士があばれとると、日照りで食いもんが少ないから、いつかこっちにもくるだろうとよ、もしそいつらがくると、みんなもってちまうだけじゃなく、女をかっさらうそうだ、おめえも娘たちも気をつけなきゃ」
戦で食いっぱぐれた野武士は野盗となって、弱い小さな村を襲って生きていた。
今九人の子供のうち娘が三人いる。
「こわいの」
「用心棒でも頼めりゃいいのだろうが、この村には金がない、庄屋さんていったって、大きな村の庄屋から比べりゃ、たいしたものをもっちょらん」
その次の年も日照りが続いた。川には水がチョロチョロしか流れていない。稲は全く実らないだろう。遠くの地に旅たつ家族もあったが、菊ばあさんの家では近くの野山で食べることのできそうな草や実を集め、畑ネズミを食い、なんとか生き延びようとしていた。どこの家もそうだった。
そのようなある日の朝、息子の嫁は、いつものように早く起きると、近くの山で食えるものを探してこようと籠を背負って家をでた。朝日が山の間に顔を出している。今日も暑くなりそうだ。
ふと軒下を見ると、大きなシダの葉が何枚も敷かれ、その上に見慣れない茸が山になっている。黄色い傘に太い柄がついている茸である。この辺りでは見たことがない。それだけではない、干した茸が積み上げられている。
「なんだべ」
黄色い茸を手に取ってみると、採ったばかりなのであろう、しゃきとしていて、ずっしりと重い。
「とうちゃん、こんな茸が家の前にたんと積んである」
家の中に戻ると、起きようとしていた夫のところにもっていった。
「見たことがねえ茸だな」
身を起こした息子も首を傾げた。
親の声で眼を覚ました子供たちも母親の持つ茸を見ると、
「うまそう」
と声を上げた。腹が減っているのだ。
「毒じゃなさそうだが、本当はどうかわかんねえから、まだ食うな」
息子は子供たちに言った。
三番目の男の子が外に走り出た。きっとしょんべんだろう、息子はそう思って、自分も起き上がって外にでた。
するとどうだろう、子供がその茸を食っていた。
「おい、食っちまったのか」
よほど腹が減っていたのだ。見つかってしまったという顔をして、あわてて飲み込んだ。
「おめえ、でえじょうぶか」
父親が聞くと子供はこっくりとうなずいた。
「うめえ、茸だ」
「腹は大丈夫そうか」
「うん、腹減った、食いたい」
他の子供たちも顔を出した。茸を見て食いたそうな顔をしている。
菊ばあさんの息子は一本手にとると、ちょっとかじってみた。いい味だ。苦みや塩辛さは全くない。うまみだけがある。経験からすると食べられそうだ。
子供たちの顔を見ているとかわいそうになった。
「よしゃ、生じゃだめじゃ、うでて食おう」
子供たちは大喜びで茸を竈に運んだ。父親は竈に火をおこし、鍋に水と塩を入れた。
「ちょっと待て」
そう言って茸を鍋に入れた。
ぶくぶくと水が沸き立つと茸を器に入れた。
湯がくくらいで大丈夫だろう。「食っていいぞ」と言うと、子供たちはよってたかって食った。嫁も食った。うまい茸だ。
「なんの茸なんだろうね」
「うん、それより、誰だろうこんな茸を置いていったのは」
「庄屋さんかもしれねえな、後で聞いてみよう」
「誰でもいいわ、今食べなきゃ子供たちが死んじまう、お腹の子供だって死んじゃうかもしれん」
そう言いながら、嫁も嬉しそうに食べた。
茸は一日で食べ尽くしたが、次の日も積んであった。
「庄屋さんに聞いてみたが、庄屋さんの家にも茸がおいてあったそうだ、それにな、隣もその隣にも茸が置いてあったんだと」
腹持ちのいい茸で、しかもうまい。傘の黄色に白い筋が入っているは菊の花に似ている。どうしても菊ばあさんを思いだしてしまう。菊ばあさんがあの世から送ってくれたんだろう。息子はそう思って、菊茸と呼んだ。
茸に混じって、干した魚まで置いてあることがあった。こうなるともう神の仕業しかない。村の人はみな天からの授かりものと手を合わせた。
そのころ、菊ばあさんは新しく見つけた洞穴でくらしていた。前の穴より滝に近いところで、もっと便利である。ここに来たときに起きた地震で穴の入り口が開いたようだ。熊にまたがって林の斜面を歩いているときに偶然に見つけた。
そこは鍾乳洞で、中に入ってみると、前の穴とは比較できないほど大きなものだ。奥も深く、横穴もたくさんあり、一人で暮らすのには広すぎる。しかし、熊も大きくなったから、一緒に住むにはいいところである。水まで流れている。
一つの横穴には、広くなった場所があって、天井から鍾乳石がツララのように垂れ下がっていた。そこの床や壁に、今まで見たことのない茸が生えていた。傘が黄色で白い筋が入っている。柄は白く太い。これは食える、と思ったばあさんは食ってみた。うまい茸だった。
熊たちも入ってきた。何匹もの子熊もついてきた。
今年になり、熊たちはどこからか子供を連れて戻ってきていたのである。母熊も連れてきていた。さすがに母熊は菊ばあさんに近寄ろうとはしなかったが、危険を及ぼすようなことはなかった。母熊と子熊は、ばあさんとは別の穴にすんでいたのだ。ただ、子熊は時折、菊ばあさんのところにやってきて父親と一緒に遊んでいる。菊ばあさんは熊の鼻の鳴らし方や、動作を身につけていた。だから子熊も菊ばあさんによくなれ、言うことをきいた。
この天気では、村は長い間飢饉が続いていることだろう。子沢山の息子の家は食い物に苦労しているにちがいない。そう思った菊ばあさんは洞窟に生えている茸を山ほど採ると、熊にのって久々に村に帰った。真夜中である。夜中でも熊にまたがっていけばなんてことはなかった。熊は夜活動できる。
村は長い日照りのせいか、夜も暑く感じられた。通りには、うるさいほどいた野良犬も歩いておらず、活気が感じられない。
息子の家はますます古ぼけて崩れそうになっている。菊ばあさんは息子の家の前ばかりではなく隣近所にも茸をおいた。茸ばかりではなく山の木の実、山菜、干し魚いろいろ運んだ。
飢饉が始まって三年目、夏の夜中に村にやって来た菊ばあさんは、村人たちが庄屋の家に集まっているのに出くわした。ばあさんはそうっと家の陰から中をのぞいた。息子もいる。
「庄屋さん、用心棒は雇えないかね」
「わしの全財産を投げ出しても、せいぜい下級の侍を一人雇うぐらいだ」
「それじゃ、十人もいる野盗たちにゃかなわねえ」
「どっちみち取られちまうんで、命だけを助けてもらわねばな、わしの蓄えをまずさしだすが、すぐ次の要求がくる」
「その間に逃げるしかねえのか」
「だが庄屋さんそれだけですむかね、女さしだせって必ず言うだろう、おらの所にゃ娘がたくさんいる、そんなんはいやだ、もう逃げるしかねえ」
「だがどこに逃げたらいいんじゃ、隣の村はもう野盗たちの手になっている、あとは山に行くだけだ」
「笹山か」
「そうだな、とりあえず女子供は笹山に隠すしかねえべ」
「んだな」
「隣村の女子たちはどうなってるべ」
「あそこの庄屋はみんなで抵抗したようだ、男は殺されたようだし、女子は山に隠れてたが、連れ戻されて働かされている」
「それもいずれは殺されちまうべ」
「そいならうちの連中を山に隠しても無駄だろう」
「いや、無駄じゃねえ、おまえ等も一緒に山に行って、どこかに逃げるんだ」
「すぐ追いかけてくるべ」
「わしがいる、それでとりあえずすべて渡し、その日は帰ってもらう」
「そんなに聞き分けがいいわきゃねえべ」
菊の息子が言った。
「どっちみちだめなら、もてなしてやろう、どうじゃ、庄屋どんの家で、毒茸食わすじゃ、腹こわさせて、当分乱暴できないようにしてやるんじゃ、その間に、女や子供を逃がすんじゃ」
「そううまくはいかんじゃろ」
「うちに茸がたんとある、あれはうまい茸だ、誰がくれたかわからんがな」
「ありゃ助かっておる、この飢饉に俺たちが元気でいられるのはあの茸のお陰じゃ」
「それで、あの茸を食わせ、それに毒茸をまぜておくのよ」
「だがな、そうはうまくいかねえよ、すぐにばれる」
村人たちは考え込んでしまっていた。
「それでいつくるのかね」
「明日にでもくるようだ、隣村にももう食うものがなくなってるだろう」
「戦うべ、それしかねえ、女子供を笹山にのがして、俺たちでやるしかねえ」
「だが、隣の村と同じになるぞ」
「もっとうまくやるべ」
「どうする」
「あの茸のごちそうをして、油断したときに、鍬で叩く」
「食ってくれるだろうか」
「かみさんたちに働いてもらう」
「こわがるべ」
「みんなでなくていい、何人かやってもいいという女はいないかの」
「よしわかった、みんな頼んで見べえ、うまい茸の料理を作り、やってもいいという女に、酌をたのむべ」
「庄屋さん、酒を都合できるかね」
「祝い用にちょっとはある」
「それでいい」
男たちは庄屋の家からでていった。
菊ばあさんは気づかれないように、息子の後をついていった。
家に入った息子は嫁にその話をした。
「おめえは、腹の中に子供がいる、菊茸の料理をしてくれや」
「大丈夫だ、腹のでかい女なんて野盗は気がゆるむべ、わしが酌をしてやる」
気丈な女子である。
「いいか、子供たちは、盗賊が来たら家から出たらなんねえからな」
「おら、父ちゃんを助ける」
男の子が言った。
「いや、いいか、妹や姉ちゃんを守るんだ、それまでは静かにしていれ」
男子たちはうなずいている。
みんないい子に育っちょる。
隙間からのぞいた菊ばあさんは、そう呟きながら家から離れ、藪に隠れていた熊にまたがって、自分の棲家へと帰っていった。
「明日は忙しくなるでよ」菊ばあさんは熊にそう言った。
明くる日、野盗どもは馬に乗り、昼近くになって村にやって来た。怖いものなしの様子で刀を見せびらかすように振りあげ、ゆっくりと集落のほうに近づいてくる。山裾の庄屋の家に来るようだ。
村の男たちは庄屋の家の庭に集まってそれぞれのところに隠れていた。気丈なかみさんたちと、庄屋が門から出て野盗たちが来るのを待った。
野盗たちは馬にまたがり、一列になって山裾の道を庄屋の家めがけてやってくる。
「やっぱり、おらたちも外に出べえ」
男の一人が言うと、庭にいた村の男たちも庄屋の後ろに集まった。手ぶらなら野盗もすぐには襲わないだろうと思ったからだ。
野盗の親分が乗った馬が庄屋の近くまでやってきた。髭面の男は刀を振り上げてにたにた笑っている。
庄屋さんの足が震えている。それでも「私が庄屋でございます、何なりと差し上げます、うまい茸が手に入りました、一献差し上げた上でお話したいと存じます」
庄屋さんがこんな話し方ができるとは誰も思っていなかった。たいしたものだ。
「それじゃ、おめえの命をもらう」
馬の上から男が刀を振り上げ、馬を先に進めようとしたとき、すべての馬が嘶いて、後足で立ち上がった。のっていた男達は何が起きたのかと思う間もなく、馬から放り出された。
真っ黒い動物が山裾から飛び出してきた。馬は驚いて一目散に逃げていく。
馬から落ちた野盗たちがなにごとかと立ち上がった。そこに黒い動物が覆いかぶさり、首をかじり、手足をかじり、血しぶきが飛んだ。野盗たちは血まみれになって転がった。
見ていた村の男たちはたくさんの熊が野盗に襲いかかるのを見た。
熊は野盗を踏みつぶしかみ殺した。
野盗に襲い掛かる先頭の熊の背には、木の皮で編んだ布を体に巻き付けた女がまたがって腰まで垂らした真っ白い髪の毛を振りみだしていた。
熊の上の女が手を振りあげ咆哮を上げた。まさに熊の吠える鳴き声だった。手には大きな茸が一つ握られていた。
熊たちは一斉に野盗に噛みつくのをやめた。
野盗たちは一人残らず息絶えて転がっていた。
熊に跨った女が振り返えった。
「山姥だ、山姥が助けてくれた」
男たちは、山姥に向かって手を合わせた。
ただ一人、息子は菊ばあちゃんだと息を飲んだ。
山姥が手に持っていた大きな茸を息子の前に放った。
熊たちはからだを揺らしながら楽しそうに熊山の方に戻っていった。
息子は菊ばあさんの放り投げた茸を拾った。それは黄色い傘をもった熟した大きな茸だった。菊茸だ。
「ばあちゃん」息子は呟いた。
息子が拾った茸は鍾乳洞の中に生えていた茸だ。菊ばあさんが改良して大きくより栄養のある茸に育てたものだった。
やがて茸は村でも作られるようになり、山姥のくれた菊茸として知られるようになった。滋養に富み味も良いことから、よその国から買いにくるようになった。
熊山に行く道の入口には山姥を祀った社が建てられた。ご神体は茸である。熊は神聖な動物として敬われるようになり、石で彫られた二匹の熊が、社の入り口で狛犬のように向かい合って置かれた。
秋になると、黄色い菊を持ってお参りに行き、村人たちがそこで秋祭りをするようになった。茸豊作のお礼の祭りである。
山陰から山姥が祭りを見ていたという噂もささやかれた。山姥は百八歳で茸になって地の中で茸菩薩になったともいわれている。そんな言い伝えがこの村にはあった。
姥捨茸
私家版第十七茸小説集「茸伝説、2024、234p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2018-9-17


