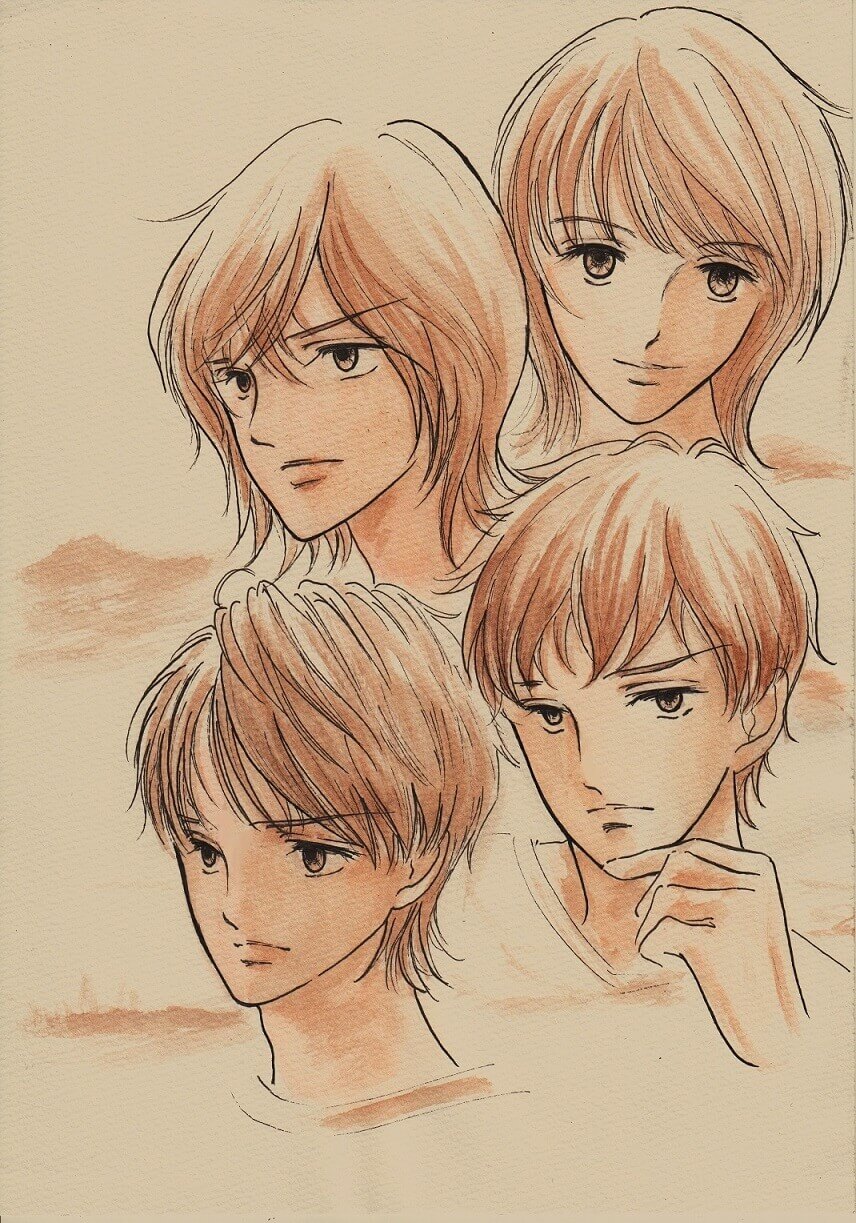
君の声は僕の声 第二章
寮の少年
「おい、おっさん」
おっさん呼ばわりされて怒る気にもなれず、タツヒコは少年に向き直った。
「何だい? 櫂」
少年の名は櫂、日焼けして引き締まった肌に琥珀色の瞳が光る。
KMCの工場から三キロほど北西へ行くとカンパニー所有の炭鉱のひとつがあり、そこから南に森を行けば、レンガ造りの建物がある。『特別クラス』へ通う少年たちの寮である。タツヒコはアリサワと共に寮の管理人との話を終え、工場の事務室へと戻ろうとしていた。
「へえ、今日は怒らないんだね。大人になりましたね。タツヒコ君」
櫂が短髪の後ろで手を組み、タツヒコを見上げながら、片方の口角を上げた。悪戯っ子のように笑うが目は笑っていない。
櫂は寮の少年たちの中でも背が高く体格が良い。もしも大人に成長していたなら、男も羨むような体になっていただろう。と長身だが痩せているタツヒコは思っていた。
「何か聞きたいことがあったんじゃないのかい? そうじゃないなら、僕は行くよ」
タツヒコは目を細めて櫂を見下ろすと、額に青筋を立てながら踵を返そうとした。
「まあまあ、俺たちからすれば三十過ぎなんてみんなおっさんなんだからさ」
「僕はまだ二十八だよ」
自分がからかわれていると気づきながらも律儀にそう答えるタツヒコに、櫂は肩をすぼめた。
「たいして変わりゃしないよ」
「櫂、君は何年ここにいる? 僕がここへ来た時には、すでにみんなのボスだったな」
「ふん、そうさ。おっさんよりずっと長くここにいる。おかげで社員の裏の顔も知ってるさ。あいつら、俺たちを子供だと思って油断しちゃうんだよねえ。今度ゆっくり教えてやるよ」
「それはどうもありがとう。で、何だい?」
「何が?」
「何がじゃないだろう、人を呼んでおいて」
「ああ、そうそう。ベッドを一つ用意しておけって言われたけど、いつまでに用意すればいい?」
タツヒコは隣のアリサワに目をやった。アリサワが小さく首を横に振り、タツヒコが少し考え込むのを、櫂はじっと見つめていた。
「そうだな、もう……。いや、今月中でいいよ」
「──わかった、久しぶりの新入りだからね、歓迎会の準備もしないとな」
「おいおい、虐めるなよ」
タツヒコの言葉に櫂の表情が硬くなる。タツヒコを見つめる目は冷めていた。
「虐めなんてするもんか、あんたはここに夢を抱いて来たようだけど、俺たちは違う。俺たちがここへ来るときはみんな……」
そこまで言って櫂は口を閉じた。
「おっさんに話しても仕方ねえや。ベッド、今週中には用意するよ」
そう言い残して右手を軽く上げ、櫂は寮へ戻って行った。余計な事を言ってしまったと、櫂の背中を見つめたまま突っ立っているタツヒコに、
「大丈夫さ、櫂は物わかりのいい奴だよ。それに、君にあんな口をきくのは、君を気に入っている証拠さ」
と、アリサワが事務所に戻るぞ、と目で合図をする。
「アリサワさんでも間違いはあるんですね。彼は僕をバカにしてます」
大股で歩きながらタツヒコが不満そうに言う。
「櫂は会社の上の連中や白衣の連中には敬語で喋る。決して目上だと思ってるわけじゃない。面倒なんだよ。関わりたくない人間には敬語で喋ってる。逆なんだよ。櫂の表現は。つっかかってくるってことは、君に気を許してるんだよ」
タツヒコの頬に赤みが差す。アリサワの言葉にタツヒコは照れながら頭を掻いた。
「そ、そうですか」
タツヒコの声は弾んでいる。アリサワは横目でチラリとタツヒコを見ると「君は正直だからね」とため息混じりに小さく頭を振った。
「ところで、さっきの話ですけど、あの少年、まだ見つからないんでしょうか?」
タツヒコが真顔になって聞く。
「ああ、上の連中も探しているようだが、家にも学校にも、友達のところにも現われないらしい」
タツヒコは泣き崩れていた母親を思い出した。あの両親の気持ちを考えると、自分がしていることは正しいのか疑問に思う。タツヒコは聡の両親に会う前に、アリサワからこの国に伝わるある話を聞いていた。
この国を治める王朝はもともと、この国の北から北東に伸びるカルシャン山脈を越えた先にあったという。天から巨人が降りてきて国を造り、地から這い出てきた小人が国を滅ぼし、生き残った者たちが山を越え、この大地に新しい国を造ったという。
どこにでもあるような伝説ではあるが、この国では時々『成長が止まってしまう子供』が現れるという。
タツヒコは先天性の病だろうと思うのだが、迷信深いこの国の人々にとっては『国を滅ぼす悪魔』なのである。
はっきりとしたことは誰にもわからない。都市伝説のようなものと思われているが、実際はひっそりと闇に葬られ、奇妙な連帯感で大人たちが口にしないのだ。
KMCの役員たちが、この話を聞いて思いついたのが『特別クラス』である。
『特別クラス』はふたクラスある。表向きはふたクラスとも『成績や特技が優れた子供たち』としているが、ひとクラスは『成長が止まってしまう子供たち』である。世間から隠さなくてはならなくなった子供たちを全寮制の学校へ編入し、授業の一環である実習として、大人たちには入れない狭い炭鉱の穴に入ってもらう、というのである。もちろん手当は支払われる。それも本人と家族の両方に、である。
子供をどうしたらよいか途方に暮れる親にとっても、KMCにとっても、都合の良い『クラス』なのだ。
櫂は寮の部屋で、清潔なシーツに取り換えられたばかりのベッドに寝ころがり、天井を見つめていた。
仕事や学校に不満があるわけじゃない。仕事は九時から十二時まで、日曜日は休み。時間を過ぎて働かされることはない。特別クラスができたばかりの頃は、危険な仕事もあり、命を落とす少年もいたが、今は細心の注意が払われ事故は起きていない。
仕事が終われば、学校へ行きたいものは学園の特別クラスで勉強できる。学校へ行くのは本人の自由で、寮の中に完備されている談話室で寛ぐのも、図書室へ行くのも、外で遊ぶのも、街へ買い物に出かけるのも、部屋で寝るのも本人の自由である。
食事も一日に三度、カンパニーの社員食堂と同じ、手作りの食事が提供される。手当は一年目から会社の初任給と同じ額が支給される。休みの日に家へ帰るのも自由だ。だが、実際に家に帰るものはいない。会社もそれを承知で『自由』としているのだ。
手当の二十パーセントは家族へ送られている。家族にとっては、王立学校やKMCの普通クラスへ通うより余程ありがたい。
普通クラスはその名の通り、普通のクラスである。各学年六クラスずつ。KMCの社員の子供や、自分の子供を将来このKMCで働かせたい熱心な親が、高額な学費を払って通わせている。もちろん卒業したからといって、全員がKMCの社員になれるわけはない。
普通クラスも、もうひとつの特別クラスも、この『特別クラス』のためにあるだけだ、と、櫂は思っている。
『特別クラス』が『特別』であることを隠すためのカモフラージュであると。それから、その高額な給料と寮費は、普通クラスの学費や寄付金で賄われているとも。
櫂たちの手当も高額だが、寮費だって相当の経費がかかっているはずだ。
寮は三階建て。一階には食堂、浴室、二人部屋があり、三階は個室になっている。二階は図書室と大小二つの談話室がある。広い談話室には暖炉を囲むように、一般の家庭ではみかけないような高級なソファが置かれ、その周りにもテーブルを囲んでソファが並んでいる。チェスやカードなどのゲーム、ピアノやギターなどの楽器や蓄音器が置かれ、ガラスの棚には、本格的な釣り道具が並んでいた。
もうひとつの特別クラスの寮は、遠く離れた別の敷地に建てられていて、お互い行き来はできないから、どんな寮なのか櫂にはわからないが、似たようなものだろう。
部屋も床もぴかぴかに磨き上げられ、常にベッドはパリパリのシーツに替えられている。櫂はクタクタになったシーツのほうが寝心地が良いので、あまり替えないようお願いしてあるのだが、今日は替えられてしまった。
故に、余計に気分が悪い。
少年たちだけでなく、家族にまで不満の出ないように配慮された待遇が、櫂をイラつかせていた。
「櫂いる?」
部屋のドアがノックされた。
「ああ」
櫂は天井を見つめたまま答えた。
「今、談話室でさ、歓迎会の話をしてるんだ、櫂もおいでよ」
一年前にここへ来た流芳(りゅうほう)が顔をのぞかせた。童顔で小柄なこともあり、みんなの弟分の彼は、自分よりも年下の少年が一年ぶりに来ることがよほど嬉しいらしい。歓迎会の準備の雑用を自ら進んでやっている。
「もう少ししたら行くから、先に行っていてくれ」
ベッドから身を起こし、櫂は言った。
危険な少年
「櫂、こっちこっち」
櫂が談話室に入ると、流芳がソファから立ち上がり手を振った。暖炉の前で流芳の他に、ふたりの少年がテーブルを囲んでチェスをしていた。
「これだけ? ほかの奴らは?」
「櫂が遅いからみんな部屋へ帰っちゃったよ」
流芳が不満げに口を尖らせる。と、そのとき一人の少年が談話室へ入ってきた。
「あっ、杏樹」
流芳が少年を呼び止める。
名前を呼ばれた杏樹がこちらを見た。少女のような名前の通り、色白で華奢な杏樹は本を手にし、神経質そうに眉をひそめて立ち止まった。
そんな杏樹の様子を瞬時に感じ取った麻柊は「やめとけ」と、チェスの駒を持つ手を止め、首を横に振っていた。流芳はそれに気づかずに杏樹に駆け寄っていく。
「さっきの話し、みんなにも聞かせて……!」
流芳が言い終わらぬうちに、「何の話だ」と不愉快そうに杏樹は眉間のしわを深くした。
「仕事の帰りに話してただろう? 歓迎会でさ……」
流芳が愛想よく笑うと、「そんな話、した覚えはないよ」と睨むように言って、杏樹は部屋から出て行ってしまった。
「だからやめとけって言ったのに。今のあいつは機嫌が悪いぞ」
顔をしかめて麻柊が言った。
「気にするな、いつものことだよ」
いきなり睨まれて気持ちの収まらない流芳に、もうひとりの少年、透馬がボードを見つめながらそう言うと、長い指に挟んだチェスの駒を置いた。その指の動きに麻柊と流芳の目が吸い寄せられる。透馬の動きは指の先まで品がある。
「寮に戻りながら一緒に話してたんだ。杏樹のアイデア面白そうだったから後で談話室でねって言ったのに……」
「ああ、そういえば寮に帰ってくるときは冗談言って笑ってたな」
麻柊が、チェスの駒と透馬(とうま)のポーカーフェイスを交互に見ながら言った。それから駒を置くと、透馬を挑発するように満足そうに笑った。
「あいつ仕事のときは黙々と働くし、休憩のときは、自分から話しかけて人を笑わせたりしてるのにな、寮に帰ってくるとああなるかも」
透馬が平然とチェスの駒を置きながら言うと、麻柊の得意気な顔が曇った。
「ふつう、逆でしょ」
気を取り直して麻柊が駒をすすめながら、櫂に同意を求めた。返事はない。
「ここにも寮に帰ってから機嫌が悪いやつがいるよ」
櫂にしかとされ、軽く首を振って麻柊が言う。
櫂は先ほどからソファに深くもたれ、腕を組み、足をテーブルの上に投げ出したまま黙り込んでいた。
「おーい、櫂。どうしたんだよ」
麻柊が櫂の顔の前で手を振る。
「歓迎会な……必要なくなるかも」
櫂が表情を変えずにぼそりと言った。
「ええぇ! そんなぁ」
流芳が肩を落として「何で」と、櫂に詰め寄る。チェスをしていた二人も手を止めて櫂に顔を向けた。
「さっきアリサワとタツヒコに会った。どうも、変だね」
「ベッドを用意しておくように言われてたんだろう? 必要なくなったって?」
チェスの駒を早く置けと催促する麻柊を無視して透馬が訊ねる。
「いや、それはない」
「悩んでるんじゃない? 死亡届にするか……どうするか」
チェスの駒を挟んだ指を口に当て、チェスボードの自分の駒と相手の駒を交互に見ながら麻柊が言った。
「愛されているんだね、家族に」
流芳ががっかりしてそのままソファに倒れ込んだ。
「学校へ行かなくていい。仕事もしなくていい。親が食べさせてくれる。いいなぁ」
麻柊がため息をついて言うと、それを聞いた櫂の表情が険しくなった。
「俺はいやだね。学校も仕事も好きで行ってるわけじゃないが、家に籠っていつまでも親に面倒見てもらうなんてな。親は歳をとるんだぞ。何年、何十年も家ン中に籠ってみろ。本当に幽霊になっちまう」
吐き捨てるように言って櫂はソファから立ち上がり「歓迎会の準備はもう少し様子をみてからにしよう」と談話室から出て行った。残った三人は座ったまま黙り込んだ。
麻柊が本気で言ったわけではないこと、櫂がそうと知りながらも言わずにはいられなかったことも、みんなわかっていた。誰もが抱えている苛立ちが時々ふとしたことで噴き出す。どんな言葉も慰めにはならないから、ただ聞き流す。そのうち日常のなかに消えてしまうのだ。
「僕は家にいるよりここの方がずっといい。学校もね」
流芳がぽつりと言った。
童顔で小柄な流芳は、他の少年よりもコンプレックスが強い。もとの学校では同級生からもからかわれ、両親からも体が小さいことや勉強ができないことに『家族の恥』とまで言われていたのだ。流芳の両親は喜んで彼を『特別クラス』へ編入した。
「僕だってそうさ。だけどおまえはまだここへ来て一年だけど、櫂はな……」
透馬が駒を手に取ってボードを見つめたまま言った。
「櫂は……長いの?」
流芳が二人に向かって遠慮がちに訊ねた。麻柊が俺は知らないと言いたげに透馬に目をやる。
「僕がここへ来たときには、すでに櫂はここにいた。寮の中でも長くいる方だろうな」
寮には五十三人の少年たちが暮らしている。見た目にはみなほぼ同級生だが、寮に古くからいる者と新参者では、本人の性格にもよるが、接する態度や見る目が違う。お互いに何年いるかなどと話す者はいないが、寮に入って半年もすると、周りの人間関係と、そこでの自分のポジションがそれとなく出来上がってくる。櫂はアリサワにも一目置かれ、寮の少年たちを仕切っていた。
「流芳いる?」
三人が押し黙っているところへ杏樹が顔をのぞかせた。先刻とはうって変わった明るい笑顔に誰もが閉口する。
「おまえ、さっき流芳を睨み付けて出て行ったばかりだろう」
麻柊がソファから立ち上がり杏樹に噛みついた。すかさず透馬が麻柊を制するようにソファに座らる。
「悪い。さっきから腹の調子が悪くてさ……」
杏樹の言い訳にムッとした麻柊がまた立ち上がりそうになったので、流芳は「気にするなよ」と、杏樹と麻柊のあいだに入った。流芳は杏樹に笑いかけ、話をしながら談話室を出て行く。
「なんだよ、あいつ謝りもしないで。しかもあんなみえみえの言い訳しやがってさ。よく笑顔で話しかけられるよな。どーゆー神経してんだ? あーもうこんなゲーム止めだ」
そう言ってチェスの駒をボードへ転がし、ソファに体を投げた。透馬が軽くため息をつき駒を片付け始めた。
頭の後ろに手を組み、ソファにもたれて透馬が駒を片づけるのをしばらく見ていた麻柊は、体を起こし、一緒に片づけ始めると、流芳が戻ってきた。
「あれ、チェス終わったの? 透馬の勝ち?」
「違うよ」
麻柊がぶすっとして答えた。
「おまえさ、少しは怒ったほうがいいんじゃないの? おまえがそんなだからあいつはコロコロ、コロコロと態度が変わるんだよ」
「うん。──でも、機嫌の悪いときの杏樹は近寄りがたいけど、ほんとはいい奴なんだ。人の話を自分のことのように聞いてくれるし、いつもは人懐こくて面白い奴だよ」
流芳が言うと麻柊も、思い当たる。というふうに黙ってしまった。
「そうだね、でも」透馬が声を落として静かに言った。「杏樹には気を付けた方がいい。ここにいる奴らはみんな不安定で、キレるのはよくあることだ。だが、杏樹のキレ方は尋常じゃないときがある。僕たちよりずっと傷が深いのかもしれない。杏樹は、流芳がここへ来る前に、殺傷事件を起こしてるんだ」
「殺傷……事件?」
「ああ、それは俺も知ってる」
麻柊が声を低くして言った。
「僕の部屋に行こう」
談話室を見渡して透馬が言った。
事件と毒林檎
流芳と麻柊は二人部屋の同じ部屋で生活している。透馬は個室だ。寮の部屋はどこも南に大きな窓がある。窓に向かって机が置いてあり、壁際にベッドとクローゼット、それから個室にだけは、二人掛けのソファが置かれていた。
透馬の部屋は綺麗に整理整頓されていた。余計な物が置いてない。
寮の少年たちは支給される手当から寮費や生活費を払っているわけではないので、人によってはインテリアや趣味にお金をかける者も多いが、透馬の部屋に高価なものといえるのは、ここへ来てから始めたヴァイオリンとレコードくらいである。机の上もすっきりとしていて、洞窟で見つけた綺麗な石や化石が、机の棚に並んでいるだけであった。
透馬がベッドに座り、流芳と麻柊はソファに座った。
「杏樹が夜中に一人で寮を出て行くのは知っているか?」
透馬が流芳を真っすぐに見る。流芳は知っている。と首を縦に振った。
「絶対について行くな。知らないふりしろって、寮に来た日に麻柊に言われたんだよね」
麻柊と顔を見合わせると、ふたりは一緒にうなずいた。
「事件前は寮から出て行くことはなかったんだ。ただ、毎日深夜に一人で部屋を出て行ってたらしい。そのとき同室だった奴がそれに気づいて、ある日こっそり後をつけたんだ。杏樹は浴室に入っていった。中から鍵をかけてね。興味を持ったそいつが次の日、浴室の鍵を壊しておいて、またこっそり杏樹の後をつけた。杏樹は仕方なくそのまま浴室に入ったんだろう……。そして事件は起きた」
流芳と麻柊がごくりと唾を呑みこんだ。透馬がさらに声を落とす。
「悲鳴が寮に響きわたり、悲鳴を聞いた者たちが浴室へ駆けつけると、脱衣所から浴室への扉付近で脇腹から血を流して倒れているそいつがいた」
流芳が体をひいて顔をしかめた。
「近くには血がついた陶器の欠片が落ちていた。洗面台の陶器が粉々に割られていたんだ。杏樹は、濡れた髪に着替えを済ませた格好で脱衣所にいたらしい。杏樹は知らないと言い、刺された本人は怯えていて、杏樹ではないと言い張った。でも誰に刺されたかは決して言わなかったんだ」
流芳と麻柊は顔を見合わせた。
「でも、それって……」
流芳がつぶやいた。透馬はうなずきながら続けた。
「刺された奴はその後、家族が迎えに来て寮を出て行った。杏樹はそれから相部屋にひとり、そして真夜中にひとり、寒い冬の夜でも寮を出て行くんだよ」
「…………」
三人は神妙な顔でどこを見るでもなく視線を落とした。
「杏樹がやったの?」
流芳の問いに麻柊が口を挟む。
「あの細っこい杏樹に陶器でできた洗面器が割れると思うか?」
三人は考えこんだ。
「じゃあ、誰がやったの?」
「それは……、誰にもわからない。最初に駆けつけた奴らも、杏樹は本当に知らないようだったって。浴室にはふたりしかいなかったと言うし」
「浴室の窓から逃げたんじゃないの?」
「窓には鍵がかけられていた」
透馬の応えに麻柊が首をかしげた。
「浴室は廊下のつきあたりだし──みんなが駆けつける前に廊下を通って逃げたのかな」
「でも、それなら杏樹が見てるんじゃないか?」
「…………」
透馬の応えにふたりは言葉を詰まらせた。
「そもそも杏樹が何も知らないということがおかしいだろう? だが、刺された奴も、杏樹の後をつけたことまでは話しても、それ以上は話さなかったらしい」
「刺したのは杏樹だ」
麻柊が言った。
「なぜ杏樹だと言えるの? 陶器は杏樹に割れないって、麻柊が言ったんだよ」
「刺したのが外部の人間なら、そう言うはずだ。そいつは杏樹を庇ってる。いや、杏樹を恐れているのか……。杏樹はなぜひとりで浴室へ行くんだ? あいつ、仕事が終わった後、俺たちとシャワーを浴びたこともないよな?」
「杏樹には人に見られたくない秘密でもあるんだろう」
「秘密を知られて刺したの? ──秘密を知られたからって、そこまでするかな?」
流芳がいぶかしんだ。
「だから杏樹のキレ方は尋常じゃないと言ってるんだ。──まあ命に別状はなかったし、別に謎解きをしようとは思わないけど、杏樹には少しおかしなところがある。さっきだって流芳を睨みつけたことなどすっかり忘れているようだったし」
「確かに……。言い訳はいい加減だったけど、本当に知らないみたいだったなあ」
「だから杏樹と話をするくらいはいいけど、あまり深入りしない方がいいぞ」
透馬の助言に納得のいかない様子で流芳はうなずいた。
「あいつ女みたいに綺麗な顔しているだけに、怒ると迫力あるんだよな」
麻柊がつぶやいた。
※ ※ ※
聡が家を出てからひと月ほどが過ぎていた。両親のことは気になっていたが、家へ戻ることは考えなかった。秀蓮も両親のことや学校のことは聞いてこなかった。
そしてその日、朝食を終えた秀蓮は白衣に身を包んだ。
「急ぎで薬を作らなくてはならないからひとりにして欲しいんだ。時間のあるときに教えるから、そのときは一緒に作ろう」
そう言って研究室へ籠るようになった。それから数日、聡は扉から漏れてくる異臭に耐えなければならなかった。いったい何の薬で、何の為に作っているのか?
酷い匂い何てものではない。不快で吐きそうになる。窓を開け放しておく季節ではないが、聡は家中の窓を開け、玄関のドアも開け放し、窓際に椅子を持っていき、毛布を被っていた。
夕食の時間になっても秀蓮は部屋から出てこなかった。朝食べたきりでずっと籠ったままだ。
「秀蓮、食事だよ。昼も食べてないだろ。いい加減出て来いよ」
聡は鼻をつまみながらドアをほんの少し開けた。部屋は蒸気が立ち込めている。部屋の奥の奇妙な機械からだ。硝子瓶には赤黒い液体。その液体から気泡がぽこぽこと音を立てている。天井から垂れる枯草の下、その液体をすくった試験管を持つ秀蓮の後ろ姿は、まるで魔女だ。
聡はドアを閉め、そっとその場を離れた。
「ここへ運んでくれるかい?」
白衣に染みをつけた秀蓮が顔を出した。強烈な匂いが鼻を突く。聡は鼻をつまんだまま寝室へと逃げた。
「君も次からは一緒に作るんだからな!」
秀蓮がドアを指さして怒鳴る。
「嫌だ。魔女!」
ドアの向こうから聡が怒鳴り返した。
それから数日、ようやく異臭がおさまり、聡はやっと落ち着いて居間で過ごすことができた。朝食の片付けを終え、居間に戻ると、テーブルの上には林檎がひとつ。
「…………」
聡は首をかしげて林檎をのぞき込んだ。つまみ上げて下から見る。おそるおそる鼻に近づけて臭いを確かめた。
──今度、毒林檎を作ってあげるよ
秀蓮はそう言っていた。彼を魔女呼ばわりしたのは自分だ。魔女といっても悪い意味で言ったわけではない。むしろ畏敬の念から咄嗟に出た言葉だったのだが……。まあ同じような意味か? 本音は魔女と呼ばれたことに腹を立てたのか……それともジョークか?
それにしても本当に作るとは。
「秀蓮、驚いた。君、本当に毒林檎作ったんだ」
聡の後ろで忙しく動いていた秀蓮が聡の林檎を持った手を軽く叩いた。
「痛っ」
「食べられるよ。今朝摘み取ってきたばかりの林檎だ」
そう言って秀蓮は林檎を手にすると、鼻を近づけて香りを嗅いだ。
「明日、人が訪ねてくるんだ。僕の事情を知っている信頼できる人だから、聡は隠れる必要はないし、いつも通りにしていてくれていいからね。──そうそう、この林檎をあと五、六個ほど摘み取ってきてくれるかい?」
聡は唖然としたままうなずいた。
訪問者
翌日、ひとりの男が、大きな荷物を背負って訪ねてきた。汚れた靴と、質素な旅支度に身を包んではいたが、秀蓮に丁寧にお辞儀をする身のこなしは洗練されていて優雅であった。年の頃は三十後半くらいであろうか。背が高く、少年の姿の秀蓮を見下ろすようになるが、秀蓮への振る舞いは謙虚で高踏なところはなかった。
秀蓮は男を家の中へ招き入れた。台所にいた聡が顔を出し、「彼は聡。僕の友人です」と紹介した。男は聡を見て少し驚いた表情を見せたが、すぐに優しげな笑みを浮かべ、手を差し伸べた。
「私は瑛仁といいます。ここへは度々薬を買いにくるのですよ。そうですか、秀蓮のお友達ですか」
柔らかで張りがあり、心地よく響く声。その笑顔には、初対面であるのに、ずっと以前からの知り合いのような安心感があった。
聡がすでに用意をしておいたお茶を、秀蓮が運んできた。
「しばらくここへ泊まってゆっくりしていってください。そう言われているでしょう? ここまで来るのだって大変なのに」
「いいえ、ここへ来るのは私の休息なのです。この森は静かで美しい。都は慌ただしくて、毎日が分刻みで動いていますから。ここへの使いは、外に出ようとしない私への休暇なのですよ」
瑛仁は香りを楽しみながらゆっくりとお茶を口に含んだ。疲れた体がほぐれていく。
「秀蓮の入れたお茶には本当に癒されます。都にもこんなお茶を入れるお店はありません。あの方にも飲ませて差し上げたいですね」
「…………」
秀蓮は目を伏せた。
お茶を飲み終えると、瑛仁は背負ってきた荷物から、綺麗に折りたたまれた紙を取り出した。それをテーブルの上に広げると、秀蓮と瑛仁は紙を指さしながら何やら相談を始めた。
「聡、君に話しておきたいことがある」
茶器を洗っていた聡は、秀蓮に呼ばれてその手を止めた。
ここへ来てから、毎日を過ごすのに精一杯だった。秀蓮から教わることは初めて知ることばかりで、学校でいえば、机に座って先生の話を訊いている授業ではなく、毎日が実験や実習ばかりで、興味深く楽しいものだった。でも、本当は秀蓮とゆっくり話がしたかった。聞きたいことは山ほどあった。聞きたいけれど聞くのが怖かった。現実を受け入れるのが怖くて、考える時間を作らないようにしていただけもしれない。
聡はぎこちない返事をしてテーブルについた。
「聡はひと月前にここへ来たばかりで、まだ何も知らないんだ。でも一緒に話を……。いいかな」
「わかりました」
「聡、これを見て欲しい」
秀蓮がテーブルの上の青い紙を指さす。
「これは?」
「KMCの設計図の写しだよ」
「どうして設計図なんか……」
「成長が止まってしまうのが僕たちだけじゃないことは前に言ったね」
聡がうなずく。
「君はなぜ森へ逃げてきたんだい? 両親から話しを聞いて? それともカンパニーの人間から聞いたのか? どこまで知ってる?」
「どこまでって……」
聡はあの日あったことの覚えている限りをふたりに話した。
「そうか……。彼らがどこに連れて行こうとしたのか、死亡届にどんな意味があるのかは知らないわけだ」
秀蓮は聡にどう説明するか考えてから、ひとつひとつ確認するように話し始めた。特別クラスのこと。特別クラスは全寮制で、そこに自分たちと同じ少年が暮らしていること。それから死亡届とは、カンパニーとこの国とが結託して死亡届を受理し、世間的には子供は死んだとされること。その後は家族の自由。ただし、死亡しているのだからその日から学校へはもちろん、一歩も外には出られない。働くこともできない。近所の人に見られれば『悪魔』と忌み嫌われ、そこに住み続けることは難しい。家族の庇護のもと一生隠れて生きていくのだということ。
瑛仁は黙って聞いている。
「じゃあ、父さんと母さんは僕を……」
「──傍にいて欲しかったんだろうね」
秀蓮の言葉は聡の胸に優しく響いた。
「聡、家に帰るかい? 家に帰ってご両親と相談して、特別クラスへの編入は今からでも遅くはないし、死亡届を書いてもらうこともできるよ。──特別クラスだって悪いものじゃない。僕たちが隠されるのは、何もきまりや法律があるわけじゃない。世間の偏見なんだ。特別クラスがまだなかったころ、子供を隠さずに堂々と生活していた家族もいたんだよ。でも町中から非難されて差別を受けてね、悲惨な事件が起こったこともあった。特別クラスはそんな家族を保護する意味もあるんだよ」
聡の脳裏に、必死に自分の名前を呼ぶ父の姿が浮かんだ。兄にも知らせているだろう。みんながどれほど心配しているかを思うと胸が痛んだ。
──だが、
「秀蓮、僕はここにいたい」
聡は真っ直ぐに秀蓮を見つめた。聡の決意を読み取って秀蓮はうなずく。
「聡、大丈夫か?」秀蓮が心配そうに聞く。「続きは後で話そうか?」
「いや、大丈夫だよ。僕も真実が知りたい」
「わかった」
秀蓮が頷いて続ける。
「巨人が国を造り、小人に国を滅ぼされた王朝が山を越えて、ここに新しい王朝を築いた話は知ってる?」
「えっと、学校の歴史で教わった神話なら」
「それでいい。国造りの神話だけでなく、この国に言い伝わる話には必ずと言っていいほど小人が悪者として登場する。迷信深いこの国の人々にとって、小人は『国を滅ぼす悪魔』なんだ。──学校の教科書や絵本には手のひらに乗るような小人が描かれている。そうだね?」
聡がうなずく。
「ではなぜ、僕たちが『国を滅ぼす悪魔』として隠されるのか──」
秀蓮が聡の反応を見ながら言った。
聡は秀蓮の言っていることを理解するのに精一杯だ。自分と小人を重ねて考える余裕はない。
「神話の小人は実在した。現に僕たちが存在するようにね」
咄嗟に理解できずに、聡は首をかしげた。
「二千年前に何があったかはわからない。だけど、小人と呼ばれる者が、僕たちのような子供だったとは考えられないか?」
聡は、のぞき込むように見つめる秀蓮を、瞬きを忘れたかのように見つめ返した。伝説の小人が僕たち? 聡には秀蓮が何を言いたいのかわからなかった。
「神話や伝説以外に、小人の存在を示すもの何もない。僕たちのような確かな存在として現れたのは……、この国にKMCが来てからなんだ」
秀蓮は話し疲れたのか、ため息をついて席を立った。秀蓮がお茶を入れているあいだ、瑛仁が聡に語った。
「採掘が始まったのは八十年ほど前です。その頃は人の手によって掘られ、規模も小さな、ただの採掘場でしたが、それから三十年後に、現在のカグラ会長によって最初の工場が建てられました。当時工場が建つのを反対する人たちが多かったのですが、従業員の多くはこの国の人々で、当時この辺りは貧しい農村ばかりでしたから助かりました。工場の建つ町や国には毎年、KMCから多額の寄付金が支払われています。生活を豊かにする電気が使えるようになり、国民の多くが恩恵を受けていると言えるでしょう」
「──それじゃあ、KMCは悪い企業ではないの?」
「良いか悪いかで判断するのは難しいですね」
神話と迷信
瑛仁は設計図の写しを折りたたみながらため息をつくと、秀蓮がお茶を運んできた。いい匂いがする。
「少し休もうか」
そう言ってなにやら指でつまめるほどの黒い塊を乗せた皿を、秀蓮がテーブルに置いた。
「何これ?」
聡が眉をひそめてひと粒摘まみあげる。
「うわっ、君が作っていた薬と同じ色。まさかそれを固めたの?」
そっと鼻を近づけて臭いを確かめる聡に、「そんな失礼なことするならあげない」と、秀蓮は皿を引っ込めてひと粒口にした。
「うん、美味しい」
言い方がわざとらしい。
秀蓮の口もとから甘い匂いが漂った。聡も恐る恐る、塊を口に入れた。ほろ苦く甘い香りが口の中に広がってとろけていく。
「美味しい!」
「だろ?」
「これ、瑛仁さんが持ってきてくれたの?」
もうひと粒口に入れて聡が訊ねる。
「瑛仁でいいですよ」
「いつも手土産に珍しいお菓子を持ってきてくれる。瑛仁、こんな失礼なやつはほっといて二人で食べよう」
「あ、酷い」
「酷いのはそっちだろう。だいたい人が寝る間も惜しんで仕事をしているっていうのに、お茶のひとつも運んできてくれない。それどころか人を生ゴミのような目で見て──」
「見てないよ」
「鼻つまんで見てただろう」
秀蓮はそう言いながら聡の鼻をつまんだ。
「痛っ。やめてよ」
笑いながら嫌がる聡を見て、秀蓮は悪戯っぽく笑った。こんなときの秀蓮は見たままの少年だ。くったくのない笑みを浮かべた秀蓮は子供のように楽しそうだった。じゃれ合うふたりを、瑛仁は目を細めて見つめていた。
瑛仁の視線に気づいて秀蓮が頬を赤らめた。
「あなたでもそんな風にはしゃぐことがあるんですね」
こんな見たことも聞いたこともないお菓子を持って訪ねてくる男と、その男に薬を売る目の前に座って無邪気にお菓子を食べている少年はいったい何者なのか……。なぜ、どこからこんな情報を持ってくるのか。聡はふたりを交互に見ながら思った。
「そろそろ話に戻ろうか」
取り繕うように秀蓮が咳払いをする。お皿を下げて戻ってきた秀蓮から無邪気さは消えていた。
「KMCがどんな方法でエネルギーを作り出しているかは企業秘密だけど、安全性──人体への影響や環境破壊──はKMCには情報を公開してもらい、国でも専門家による調査団を派遣している。実際、今まで環境の汚染もなければ、健康の被害を訴える人もいないんだ」
「それならどうしてKMCを疑うの?」
「調査団の結果は白。国民からの訴えもないのですから、国ではそれ以上は何もしません。ですから、私たちで独自に調べました」
瑛仁が別の地図を広げた。
「特別クラスへ編入した子供たちと、死亡届が出された子供たちの情報を国では管理しています。それらの子供たちが生まれ育ったのは、いずれもこの辺り」
瑛仁は、KMCの北から西に森に沿って都へと流れていく西恒川(さいこうがわ)の周辺を指さした。いくつかの家に印がついている。
「源流は一緒でもKMCから離れた東恒川(とうこうがわ)の下流には一軒もありません」
「川は汚染されていないし、これといった健康被害は出ていない。ただし、同じくこの五十年ほどの間に、やはりこの周辺で、生後一年未満に原因不明で亡くなった子供たちがいる。それから生まれる前に流産してしまった例もある。何か関連していると思わないかい?」
聡ははっとして顔を上げた。
「僕にはもうひとり兄がいたんだ。生まれてすぐに原因不明で亡くなった……」
「何だって!」
秀蓮と瑛仁が驚いて顔を見合わせた。
「やはり、関係がありそうですね」
「そういえば聡にはお兄さんがいたね。彼……は?」
「うん。今、大学生で健康に成長してる」
「そうか」
秀蓮は返事をするとしばらく考え込んだ。そしてまた聡に問いかける。
「生後一年を生き抜いた者が僕たちだとは仮定できないか?」
秀蓮の質問に聡は思考がついていかない。
「どういうこと?」
「亡くなった胎児や生後一年未満の子供たちと僕たちは、同じ病気……というか、同じ突然変異でも起こしたとして、僕たちは、理由は分からないが、一年目は乗り越えた。そして僕たちの成長が止まってしまうのが十三、四歳前後──思春期ってやつだ……そして、それらの子供たちは男の子ばかり。女の子はいない」
秀蓮が反応をうかがうように聡と瑛仁へと目をやる。
「──テストステロン」
聡がつぶやいた。「生後半年と思春期は、テストステロンの分泌が増加する頃だ」
「よく知ってるな」
「兄が王立大学の医学生なんだ。秀蓮からもらった石の力を試したくて、あれからずっと兄の医学書を読みあさってた」
「驚いたな、君はそんな子供のころから医学書を読んでいたのかい」
秀蓮は目を丸くして聡を見つめた。そして満足そうに、にやりと笑う。
「石を渡したかいがあったな」
「王立大学の医学生ということは、都の寮に?」
瑛仁の問いに聡がうなずいた。
「優秀なお兄さんですね」
瑛仁が秀蓮と顔を見合わせ視線を絡めた。
「話しを戻そう。僕は、それらの子供たちは胎児のときに何らかの影響を受け、ホルモン異常を起こしたのではないかと思う。だがまずは原因だ。原因が汚染されていない川の水にあるのは間違いない」
秀蓮が厳しい顔で言うと、瑛仁も同意するように頷いた。
「KMCが川の水をどのように利用し、処理しているのか。探ってみる必要があると思わないか」
それから秀蓮が身を乗り出して聡の瞳をのぞき込むように言った。
「聡、君は大人になりたくないのか?」
狭い寝台の中で聡は何度も寝返りをうった。
夕食の準備をしている間にも、秀蓮と瑛仁は設計図を見ながら相談をしていた。夕食のあと、秀蓮がよく眠れるようにと香草茶を入れてくれたが、今日話したことで脳が興奮しているのか、なかなか寝付くことができなかった。秀蓮に問いかけられた言葉が頭から離れなかった。
──君は大人になりたくないのか、と。
自分だけが取り残されていく疎外感。思い出しただけでも悔しくて胸が痛む。友達に追いつきたい気持ちはある。が、大人になりたいか、というと正直よく分からない。家に帰って家族と普通の生活に戻りたい気持ちはあるが、毎日ここで秀蓮とこうして過ごすことが今は日常になっている。特に望むものはない。
この家には寝台が二つしかないので、秀蓮の寝台には瑛仁が休んでいる。寝返りをうった聡の目の前には秀蓮の白い首と背中。それを見て、意外に小さいんだな、と聡は思った。
「友達だよ」と言われても、秀蓮は自分よりずっと年上のはずであり、教わることが多いから兄というよりも、父のように感じることすらある。それなのに目の前の背中は鍛えられた筋肉に引き締まってはいるが、自分の肩よりも華奢に思える。
ふと、父と兄の背中を思い出した。小さな聡を軽々とおんぶしてくれた背中は、逞しくて大きかったっけ。
本当なら秀蓮の背中も大きいはずなんだな。
彼はいったいどれくらいの時間、少年の姿でいるのだろう。一緒に机を並べていた友人たちは少しずつ大きくなり、やがては父親となって、大きな背中で自分の子供をおんぶするのだろう。だけど、僕たちにそんな日は永遠にやってこないのだ。
男の正体
翌朝、瑛仁は寄りたい所があるからと、朝食もとらずに帰り支度を始めた。荷物のほとんどを秀蓮に預け、代わりに薬が入れられた。そして薬代にと瑛仁が麻の袋を手渡した。
「では、半年後にまた来ます。──あの方にお伝えする事はありますか」
帽子を被り、目を伏せるようにして瑛仁が口にする。秀蓮はいったん瑛仁から視線を外し、少し考える風にしてから瑛仁の瞳を見つめ、微笑した。
「いつも、ありがとうございますと。それから、約束は必ずと、そう伝えて下さい」
「わかりました。お伝えします。では、くれぐれもお気をつけて」
瑛仁は秀蓮に丁寧にお辞儀をした。瑛仁が玄関を出ようとしても聡の姿がない。秀蓮が台所にいる聡に声をかけると、
「ちょっと待って」
慌てた声が返ってきた。がさごそと音をたて、秀蓮の足元に、鍋が大きな音をたてて転がった。
「おいおい、大丈夫か」
見かねた秀蓮が、鍋を拾い様子を見に来ると、「これ」と、聡はパンと干し肉と搾りたてのジュースを入れた籠を見せた。
「途中まで送ります」
聡は瑛仁に笑いかけ、籠を片手に玄関を出た。
さきほどから聡は落ち着きなくチラチラと後ろを振り返っていた。それを横目で見ていた瑛仁は、見送っている秀蓮の姿が見えなくなると、聡に声をかけた。
「それで? 私に何を聞きたいのです?」
「いっ……!」
唐突な瑛仁の質問に思わず声が出た。見透かされて赤くなった顔を隠すように、聡は片手で前髪をなで、「えっ……食事を一緒に、僕はただ……食べようと、あれです」と口ごもった。
しどろもどろである。聡はがっくりと肩を落とし、ため息をついた。
「わかりました。そこの木陰で一緒に食べましょう」
瑛仁は帽子を脱ぎ、クスクス笑いながら聡の肩に手を置いて木陰に誘った。
瑛仁は腰をおろすと、まだ赤くなっている聡から籠を受け取り、パンを半分に割って聡に「どうぞ」と手渡した。聡が早起きして焼いたパンはまだ温かい。
聡がパンをちぎりながら、何をどう訊ねようか迷っていると、瑛仁はそれを察して口を開いた。
「私は冷泉家に仕える者です」
森の木々を飛び回る小鳥を目で追いながら、瑛仁がおはようと挨拶するように言った。あまりに平然として言ったので聡は瞬時にわからず、変に間があいてからパンを落っことし、口を開けたまま固まった。
冷泉家といえばこの国の皇族である。都から遠く離れた小さな町に住む聡にとっては雲の上も上、一生関わることのない世界である。兄が都へ行くというだけで、親戚中が大騒ぎするのだ。帝は世界の中心。地上の世界を治める天命を受けた天子である。その天子に仕えている──。
そんな世界の人がなぜここに?
自分はこの人に失礼がなかっただろうか……聡は思考をめぐらせ昨日のことを思い出す。聡の顔が蒼くなる。この人が持ってきてくれたお菓子を、そうとは知らずに何て言ったっけ……。
背中に冷たい汗を感じて「あ、あ、あの、ぼ、僕」喋ろうとしても口が強張ってうまく話せなかった。
「そんなに固くならないで──私は仕えているだけで、皇族ではありませんよ」
瑛仁は笑いながら持っていたパンを聡に渡し、落ちたパンを拾って土をはらい、それをちぎって口に入れた。
「私の家は代々城に仕える医師です。秀蓮からは何も聞いていませんか?」
聡はまだ喋れずにただ頷いた。
「冷泉家の主治医だった秀蓮の父親の後を継いだのが、私の父なのです」
聡がまたパンを落としそうになり、慌てて瑛仁が受け止めた。
「それじゃあ、秀蓮は……」
「大人になっていたら、間違いなく父親の後を継いでいたでしょうね。幼いころから利発で、時の帝にも可愛がられていたようですから」
瑛仁はそう言って目を伏せた。強張った顔をゆっくりと瑛仁へと向け、震える唇で聡は訊ねた。
「秀蓮が……冷泉家の。秀蓮は。──秀蓮は……いったい何歳なの?」
瑛仁の伏せた目が聡に向けられる。
聡は一番気になっていたことを口にした。
「それは──秀蓮からお聞きなさい」
「でも、僕が聞いて欲しくないことを秀蓮は聞いたりしない。だから僕も聞けないんだ」
聡は瑛仁から目を逸らし、困惑した様子で俯いた。そんな聡の肩に手を回して瑛仁は微笑む。
「それは、あなたがまだ自分の気持ちの整理がつかないから触れないでいるのでしょう。秀蓮はとっくに気持ちの整理はついています。むしろあなたが聞いてくるのを待っていると思いますよ」
瑛仁は諭すように言った。
秀蓮が待っている? 聡は不思議そうに瑛仁を見つめた。
「ご両親を亡くしてから、彼はひとりこの森で過ごしました。きっと誰かに聞いて欲しいはずです。私では彼の力にはなれません。彼と同じ気持ちを共有することはできませんから……。あなたも辛いでしょうが、私は秀蓮にあなたのような友達ができて嬉しいのですよ。昨日のようにはしゃいだ彼を見たのは初めてです。本当に楽しそうだった」
瑛仁が目を細めた。それからおもむろに立ち上がったので、聡は慌ててもうひとつ質問した。
「秀蓮は早く大人になりたいのかな?」
リュックサックに伸ばした瑛仁の手が止まる。
「それは……私は秀蓮ではないから、彼の気持ちはわかりません。ただ、私があなたの歳の頃には、早く大人になりたいと思っていましたね。でも大人になった今は、大人なんて良い事ばかりじゃないって思いますよ。子供の頃は嫌な奴など相手にしなければいい。だけと大人はそうはいきません。城の中にはいろいろな人たちがいます。でも喧嘩なんてしたら自分の首が飛んでしまいますからね。子供の頃に欲しかった自由の代わりに責任を負うことになります。子供の頃は良かった、なんて思うことはいくらでもありますよ……。でもそれは、大人になった今だから言えることなのでしょうね」
瑛仁は梢を見上げた。それから聡に笑いかけ、
「でもね、子供を持つ友人の話しを聞いていると羨ましいですよ、守れる家族がいるっていうのは。──だから、守りたい人がいるときに、守れる力がない……というのは男としては辛かったでしょうね」
瑛仁はそう言って目をふせた。
辛かった……とは? 秀蓮のことなのだろうか。瑛仁は帽子を目深に被ってしまったので表情は見えなかった。それからリュックサックを肩に背負うと、「これは頂いていきます」と、残りの食べ物の入った籠を手にした。
「秀蓮と話をしなさい。今はお互いに話せないことでも、いずれ話せる時が来るでしょう」
「でも、友達といっても僕は秀蓮と違って子供で……」
「それがいいのですよ。秀蓮を子供に戻してあげてください」
子供に戻す?
瑛仁の言っている意味が聡には分からなかった。
瑛仁は聡の正面に立ち、少年の、その眉目秀麗な顔を見据えた。宮廷医である瑛仁は、皇族だけでなく、高官たちを数多く見てきた。その顔を見ればその人物なりが分かる。若くして亡くなった先帝たちは、政の重圧や病に勝てる相を持ち合わせてはいなかった。心の弱さは顔に現れる。
答えを求めるように自分を見つめる強い瞳を、瑛仁はじっと見つめ返した。
「聡……。名前の通り、あなたは聡明です。あなたのその真っ直ぐな気性と知性は彼の助けになるでしょう。また来ます。それまで秀蓮をよろしく頼みますよ」
そう言って軽く帽子を上げると、振り返らずに瑛仁は行ってしまった。
親犬に突き放された子犬のように聡はその場に立ち尽くしていた。
餓鬼
「お帰り」
いつもと変わらない態度で秀蓮が迎えてくれた。
本当なら、今頃は城で帝の主治医をしていたと思うと、秀蓮の顔をまともに見ることができず、聡は思わず顔を逸らしてしまった。
瑛仁に見透かされていたのだから、秀蓮が気づかないはずはない。それでも秀蓮は何事もないように振る舞ってくれた。聡はといえば、平静を装おうとすればするほど、ぎこちなくなるのが自分でも分かるほどで、「畑に行ってくる」と言って外へ逃げた。
見た目が秀蓮と変わらないだけに、聡は自分が餓鬼に思えて情けなくなる。「秀蓮をよろしく」なんて言われたけど、世話をかけているのは自分の方だ。
秀蓮が、帝の主治医になるはずだったという事実が聡の気持ちをいっそう乱した。未来のあった少年が、なぜこんな森の中で隠れて暮らさなければならないのか……。自分だってそうだ。秀蓮から貰った石の力を信じて、秀蓮の言葉を信じて、父のように、兄のようになりたくて努力してきた。
誰にもぶつけられない怒りが込み上げてきた。
怒りに全身が震える。
こんな風に自分の気持ちをコントロールできないのも、大人になれないせいなのか──。どうにもできない苛立ちを押さえることができなかった。がむしゃらに畑の雑草を引きちぎり地面に投げ捨てた。跳ね返った土が目に入り目が痛んだ。その場に崩れ、握りしめた拳を何度も何度も地面に叩きつけた。
「聡」
不意に名前を呼ばれ、聡の手が止まった。いつの間にか後ろに立っていた秀蓮に声を掛けられても、聡は振り向くことが出来ずにいた。
「君の気持ちを考えずに一度に話しすぎたね。ごめん。僕が悪かった」
秀蓮が聡の背中を包み込むように屈み、きつく握りしめて血が滲んだ聡の拳に優しく手を添えた。気づくと聡の手には雑草だけでなく、ふたりが育てた野菜までが握られていた。
畑がめちゃめちゃになっていた。
「違う、違うんだ。僕は自分が情けなくて……それで……畑までこんなにして、僕は餓鬼だ……」
聡の悔し涙が秀蓮の手を濡らした。
「僕だってずいぶん荒れたよ。テーブルと寝室の床に大きな傷があるだろう? あれは僕がつけたんだ。暴れてね。父親におもいきり殴られた。父とはよく喧嘩したよ。その度に母親に泣かれてね。酷い状態だった。だから今の聡の気持ちは良く分かるよ。我慢なんかしなくていいさ。餓鬼でいいじゃないか。僕たちは子供なんだからさ」
秀蓮の手に涙がぽとぽとと落ちる。
聡は声を上げて泣いた。
聡は、右手の傷を秀蓮に包帯で巻いてもらいながら、左手で異臭を放つガラス瓶の蓋を閉めた。ガラス瓶に歪んで映るテーブルの端を見つめると、なるほどそこには、二の腕ほどの大きさの傷が、別の板で補修された後があった。同じ色で気付かなかったが、よく見ると年輪の筋が、そこだけ平行ではなかった。こんな頑丈そうなテーブルの板にこれだけの傷をつけるには、相当な力が加わったと考えられる。
包帯を巻く秀蓮をチラリと横目に見る。
涼しい顔。
聡の頭に、テーブルを壊す暴れた秀蓮が浮かんだ。
「ふっ」
聡の口もとから笑いが漏れた。
「何?」
「何でもない」
笑い止め、真顔で答える。聡の目は涙で赤く腫れていた。
「ふっ、ふふっ」
堪えようとすればするほど、笑いが込み上げてくる。口を押さえても肩が震えてくる。ついには大声で口を開けて笑い出した。
「何だよ」
「だって、テーブルの傷って、こんなでかい傷、普通つける? どんな暴れ方したの?」
聡は腹を抱えて笑いだした。泣いた後で気分が高揚しているせいか、笑いが止まらなかった。
「まったく君って奴は、泣いたり笑ったり。付き合いきれないね」
秀蓮の強い口調に、聡は笑いを止めた。「まずい」と、口元を引き締める。が、すぐに緩んでしまう。
「ふふっ」いちど吹き出すと止まらない。再び笑い出した。涙を流して笑っている。
「何だよ。テーブルはすぐに修理できるけど、野菜はまた一から作り直さなきゃならないんだぞ、分かってんのか」
口調は怒っているが、秀蓮の顔には安堵の笑みが浮かんでいた。それからも聡はテーブルの傷を見るたびに笑い出すので、テーブルは秀蓮に布を掛けられ、傷は隠されてしまった。
ようやく笑いが出なくなったその夜。秀蓮は聡を呼んでテーブルにKMCの設計図を開いて話を始めた。
「準備が整ったら、僕はKMCに忍び込むつもりだ」
「忍び込むって、企業秘密を探るの?」
「ちょっとだけ拝借してくる」
「拝借って、それは盗んでくるってことだよね」
「聡、これは僕ひとりでやる。ずっと前から計画していたことだからね」
「そんなことしなくても、国が調査してるんだろう? 夕べ瑛仁と話したことを調査団に調べてもらえば──」
「無理なんだ」秀蓮が遮った。「今この国ではKMCの力が強くてね。役人や調査団の中には、KMCから賄賂を受け取っている者がいる始末だ」
聡は次の言葉が出てこない。国や政治のことなんて考えたことはなかった。だけど、父親たちがこっそり批判めいたことを言っていたのは知っている。帝がまだ幼いのをいいことに、先帝の后である皇太后が未だに実権を握っているから、KMCの言いなりだと。早く帝に成人してもらって安定した世の中にして欲しいと言っていたっけ。
「この国はそんなに弱ってるの?」
「先帝が──二代続けて若くして亡くなっていて、今の帝もまだ成人されていない。皇太后の古い体制とそれに反対する改革派とで朝廷は二つに分かれている。そこを莫大な金でKMCが付け込んでくるんだ」
秀蓮はテーブルに肘をついた姿勢で指を組み、ため息をついた。それから聡に目をやると、テーブルから肘を離し、聡の目を見つめたまま言った。
「聡、僕は自分の目で事実を知りたいんだ。まずはKMCに原因がないのか。彼らのエネルギー開発はこの国にとって救世主なのか、それとも悪魔なのか。それを確かめる」
「ちょっと待ってよ、秀蓮。僕も行く」
「駄目だ。足手まといだ」
珍しく秀蓮がきつい言葉を投げた。
「なっ」
はっきり言われて聡は言葉を失った。だがここは引けない。
「いや、行く。ふたりでやった方が絶対にいい。君が探ってる間の見張りだっていた方がいいだろう? それに……僕の方が逃げ足は速い。君には負けない。絶対に!」
負けずに言った。足の速さや体力なら負けない自信がある。秀蓮が少し考えてからきつく結んでいた口をゆっくりと開いた。
「なら、条件がある。もしも見つかったり、捕まりそうになったら、聡が書類を持って逃げる。何があってもだ。いいか。それでいいなら連れて行く」
「OK! わかった」
聡が満面の笑みで握りこぶしを上げて喜んでいる。
「喜んでないで、さっさと設計図と地図を頭に叩き込めよ。それから君が捕まったら、僕は君を置いて書類を持って逃げるからな。覚悟しておけよ!」
「大丈夫。僕にはこれがある」そう言って首から下げた石を秀蓮の目の前に差し出し「もし頭に入らなかったら、それは君が嘘をついたってことだ」と、聡はふふん、と得意気に笑った。
秀蓮がいまいましそうに睨む。
「まったく君には呆れるね。そもそも君が親の言いつけを破って森へ入るような子供だったということを、僕は忘れていたよ」
秀蓮が聡を指さす。
それから毎日、聡は暇さえあればKMCの設計図と周辺の地図を広げた。
これ見よがしに石を握りしめながら。
企
「しっかし広いんだねえ。KMCの工場って」
地図を見ながら聡が感嘆の声を上げた。
「山を切り崩したんだ。周辺の森も潰してね。広さといい、高い塀といい、まるでこの国のもうひとつのお城だな。まあ広いのは工場で、僕たちが忍び込むのは管理棟事務室だからここね」
秀蓮がそう言って指を差したのは、東西の壁に沿った細長いレンガ造りの倉庫と、北側に巨大な煙突が立つ工場ではなく、南側正面に建てられた小さな三つの建物のうちのひとつだった。
小さいと言っても、部屋数が十もある木造二階建ての建物だ。
「管理棟? ──役員の部屋はこっちの建物でしょ。こっちじゃないの?」
聡はそう言って管理棟の北に建ち並んだ建物を指さした。
「ああ。役員の部屋には大きな金庫があってね、現金や株、会社の重要書類が入ってるんだ。そっちは関係ない。僕たちにとって重要な書類は、この管理棟の小さな金庫に入ってるんだ」
「──ふうん」
聡が、つまらなそうな、納得できないような顔をして「どこから入るの?」と、図面に視線を落とす。
管理棟は、正面の門から入るのが近いが、正面入り口には警備室があり、当然正面から忍び込むことはできない。工場を取り囲む塀は大人でも登れそうにない。
「正面から」
秀蓮がこともなげに言った。
「でも警備員は夜でもいるんだろう?」
「警備員は二人、二時間交代で一人は工場の敷地の見回りに行く。その間に警備室に残ったひとりは薬を使って眠ってもらう」
「薬……?」
嫌な予感。
「まさか……」
「そうだよ。薬を作るんだ。僕と、君とで」
秀蓮は『君と』を強調して言った。聡はあの異臭を思い出し胸が悪くなった。
「嫌ならいいよ。そのかわり工場には僕ひとりで行く」
「いいよ。やる。やるよ!」
聡がムキになって言うと、秀蓮は目が無くなるほどに、にっこりと笑った。
「魔女」
聡が声を低くしてつぶやいた。聡のつぶやきを聞き流して地図を見ながら秀蓮は話を進める。
「時間は二時間だ。警備員を眠らせたら鍵を拝借して、管理棟事務室へ向かう」
秀蓮が地図から顔を上げて聡を見つめた。聡の表情が引き締まる。
「僕が鍵を開けて中に入ったら、君は管理棟の鍵を閉めて、外で警備員の様子を見張ってくれ。警備員が管理棟の見回りを終えたら僕に知らせてほしい。そして警備員が戻ってくる前に鍵を戻す。いいね」
二人は顔を見合わせてうなずいた。
まずは工場の下見に向かった。夜の工場の警備の様子を確認するために。
秀蓮の家から工場までは急いで歩いて片道二時間。聡は夜の森を歩くのにも慣れた。けれど、前を歩く秀蓮にはかなわない。むき出した木の根や崩れそうな岩でも軽やかによけて行く。秀蓮の後ろ姿に一年前に出会った狼が重なった。
「狼?」
「うん、一年前にむしゃくしゃしていた時があって、真夜中に森に来たんだ。秀蓮が石をくれた時のことを思い出して、君は何か知ってるんじゃないかと思ったから」
「…………」
「そしたら狼に遭ったんだ。僕をじっと見て、しばらくしてそのまま行っちゃった」
「この森に狼はいないよ。もっと山奥にいけばいると思うけどね」
腑に落ちない様子の聡を見て、秀蓮は耳慣れない言葉を口にした。
「聡が見たのは『イシカ』かもしれない」
「イシカ?」
「何て言うか……イシカはこの辺りに伝わる神、精霊、神秘といったもの……例えば木には木のイシカ。水には水のイシカ。山には山のイシカがいる。イシカは時々、鳥や獣に姿を変えて人間の前に現れると言われてるんだ」
「イシカ」
聡は美しい狼の姿を思い返した。
「それで、狼に遭ってどうしたの?」
「何か、とても悔しくなって、僕も狼みたいになりたいって思ったんだ。気高くというか……負けたくない、って」
「ふうん。──きっとイシカだよ」
秀蓮が微笑した。
こんな話を学校の友達としたなら「何言ってるの」と笑われそうだ。それなのに、秀蓮の口から語られると、不思議な事でも当たり前の事のように納得してしまう。町の生活から離れて自然の中にいるせいか、神や精霊といったものが何となく解るような気がする。童話の中に登場するようなものではなく、偶像崇拝の対象でもなく、科学では解明されていないだけの、自然の力、神秘。自分が受け止めなければ感じることはできないもの。聡はそんなものを肌で感じるようになっていた。
「川の流れる音が近くなってきた。川を渡ると工場の煙突が見えてくるよ」
秀蓮の言った川は森に沿って流れている。以前、聡が薬草を探しに森へ入るときに渡った川と同じ西恒川(さいこうがわ)だ。山をいくつか超えた上流に行くと、川は二手に分かれ、工場の東側を流れる。その東恒川(とうこうがわ)はKMCの社宅やいくつかの町を抜け海へと流れていく。そちらの川の水を利用している人たちの中に『特別クラス』の少年はいない。
川には新しくできたばかりの橋が架けられていた。KMCが架け直したものだ。最近、川のこちら側にもKMCの研究施設が建てられた。かつての工場跡地だ。五十年近く前に初めてKMCの工場が建てられたのがここで、二つの山を切り崩して建てられた。十年前に今の場所へ工場が移され、ここには新しい研究施設が建ち並んでいる。まだ使用されてはいないらしい。秀蓮が暗闇にぼんやりと浮かび上がる施設を見つめていた。
橋を渡ると、行く手に巨大な煙突が見えてきた。KMCの工場だ。まだ二、三キロは先だろうか。右手には森が広がっている。そこで秀蓮は足を止めた。
「聡、この森の奥に『特別クラス』の寮がある」
聡は森の奥に目を凝らした。それらしい建物は見えないが、静まりかえった闇の中に小さな灯りがいくつか確認できた。あの灯りの中に自分と同じ少年たちが暮らしているのか。
「聡、もしも見つかった場合、僕のことはかまわずに書類を持って君だけは逃げてくれ。そして、この寮に『櫂』という少年がいるから、彼にその書類を僕からだと言って渡して欲しいんだ」
「そんなこと……できないよ。僕だけ逃げるなんてできるわけないじゃないか」
「約束だっただろう。嫌なら僕だけで行く。君は連れて行かない。いいかい、ふたりで捕まったら、せっかく盗んだ書類を奪われてしまう。それに僕なら大丈夫」
「大丈夫って」
「……僕には捕まっても切り札があるんだ。だから大丈夫。必ず帰れるから。それまで寮で待っていてくれ。いいね」
秀蓮が聡の肩に手を置き、真っ直ぐに聡を見つめる。
聡は納得できずに口をつぐんだ。
「見つかったらの話だ。上手くやればいいことさ」
秀蓮が聡の肩を叩いた。
聡は釈然としないまま黙って歩いた。しばらくすると、暗闇の中からKMCの姿が浮かび上がってきた。
星空に突き刺すようにそそり立つ、巨大な煙突。
図面から大きさを把握していたつもりだったが、間近で見る高い塀と巨大な煙突に圧倒された。工場の彼方には煙突よりもはるかに高い山脈が連なっている。山は美しいだけではない。時に人間に対して恐ろしい力を見せつける。だが、山には感じたことのない何かを聡は感じた。それが畏怖なのか何なのか、聡には解らなかった。
「ここに……忍び込むんだね」
聡がこわばった喉から絞り出すように言った。
「ここで待っているかい?」
「行くに決まってる」
聡は星空を黒く切り取る巨大な煙突を睨みつけた。
侵入
KMCの正面には、塀に沿って工場を囲む道路と、正面から南へ真っ直ぐに伸びている、広いアスファルトの道路が整備されていた。社宅や診療所、銀行、郵便局、雑貨店、食堂、学校などが建ち並び、ひとつの町をつくっている。
ふたりは正面の警備室から道路を挟んで、はす向かいの診療所の植え込みに身を隠した。
正面から見るKMCには、先ほどの威圧感はなかった。高い塀と煙突は変わらず不気味にそそり立っているが、入り口の門には花をつけた木々が植えられ、警備室の脇に立つ街灯の灯りが、満開の小さな花を白く浮かび上がらせていた。
警備室も管理棟も真っ白なベランダ付きの木造二階建てで、青磁色の屋根で統一されている。二人が隠れている診療所も同じ造りだった。まわりのお店や銀行なども似たような木造か、レンガ造りの建物で、通りには街灯が灯っていた。目に映る華やかな街並みに、聡はまだ見たことはない、話に聞いた外国の町を想い、憧れに似た気持ちを抱いた。
秀蓮に小突かれ我に返る。警備員が交代するところだった。秀蓮がポケットから懐中時計を取り出す。
「今、ちょうど二時だ」
警備員は交代すると、灯りを手に塀の外を歩き出した。まずは工場の外まわりを見まわるらしい。警備室に戻ったもうひとりは、受付カウンターの窓を開け、暇そうに煙草をふかし始めた。いち時間ほどで塀の外を一周して警備員が戻ってきた。そして警備室を通り過ぎ、そのまま正門から中へ入っていった。
敷地の中をどのように巡回しているのかは、ふたりの場所からは見ることはできない。
四時になると警備員が戻ってきた。はたして毎日敷地の外から巡回しているのかもわからない。が、とにかくひと巡りするのに二時間かかるのに間違いはない。その日の下見はそれで終わりにすることにした。
「管理棟のどこに、書類の入った金庫があるかわかってるの?」
帰り道、歩きながら聡は秀蓮に訊ねる。
「二階の一番奥の部屋だ」
「開けられるの?」
「ああ」
「なぜ?」
「いくら弱っているとはいえ、そのくらいの情報は掴んでいるさ」
「でも、なぜ秀蓮がそれを知ってるの? 国のどんな機関がどんな手を使っているのか知らないけど、それをなぜ君が知ってるの? 瑛仁と秀蓮が親しい関係なのはわかるけど、KMCの図面だって、そんな大事なものをなぜ瑛仁が持っていて、親しいだけで渡すの? なぜ君がやるの?」
聡の問いかけに秀蓮は立ち止まった。口を堅く結び、深く考え込んでいる。
「話したくないのなら無理に聞かないよ」
「いや、そうじゃないんだ。聡にはきちんと話そうと思ってた。ただ、僕以外の人たちのことは、今はまだ話せないんだ。はっきりしたら聡に相談しようと思ってる。今は僕だけの話でいいかな」
聡は無言でうなずいた。
「僕の父は宮廷の侍医だったんだ」
秀蓮がそう言って聡の表情をうかがうと、聡は瞳を動かさずにじっと秀蓮を見つめていた。その様子から、この話は瑛仁から聞かされていたのだと思い、歩きながら話を続けた。
「だから自然と僕も侍医になるものと思っていたよ。小さな頃から父に連れられて父の仕事を見てきたからね。時の帝や皇后も僕を可愛がってくれて、皇太子とは歳も近かったから、一緒に勉強したり遊んだりした。城の中には珍しいものがいっぱいあったから退屈なんてしなかった。──だけど僕の成長が止まったとき、父は僕を森へ隠した。そして父も侍医を辞めたんだ」
「お父さんまで……どうして?」
「この国では『小人は国を滅ぼす悪魔』だからね。そんな子供をもつ者が城に入るわけにはいかないだろう」
聡の足が止まった。秀蓮は振り返り、悔しそうにしている聡に笑いかけた。
「それでも悪い事ばかりじゃないよ。父はもともと医者になるより薬の研究がしたかったんだ。だから、薬草がたくさん自生しているこの森の中で暮らすことは、父にとっては好都合だったんだ。ふたりで薬を作ってね、楽しかったよ。匂いが我慢できなかった母をのぞいてはね」
秀蓮はいたずらっぽい目でちらりと聡を見た。
「お母さんは気の毒だったね」
聡は心の底から同情するように首を横に振った。それからふたりは、顔を見合わせてちょっと笑った。
「父の信頼できる友人が何人か訪ねてきては、研究をしたり講義をしてね。その中のひとりが瑛仁の父親だったんだ。そのうちに瑛仁も来るようになって、今も交流が続いているってわけ。そして、彼を通して、皇族のあるひとに相談されたんだ。個人的にね。『成長が止まってしまう原因を探して欲しい。決して表沙汰にはしないように』とね」
聡は眉をひそめた。
「そのひとが僕に情報をくれるんだ。今、僕が話せるのはここまでだよ」
秀蓮は立ちどまり申し訳なさそうな顔をする。
「じゅうぶんだよ。話してくれてありがとう」
聡は礼を言うと考えた。皇族のある人とは誰なのだろう。なぜ秀蓮に頼んだのか。
いや、もう考えるのはやめよう。秀蓮はきっといつか話してくれる。聡は秀蓮と並んで歩き始めた。
※ ※ ※
月のない暖かい風の吹く夜。
「行くぞ」
秀蓮が目で合図をした。警備員のひとりが、塀の外の見回りに出かけていく。警備員の姿が暗闇に紛れたところで、ふたりは隠れていた診療所から向かいの銀行へと走った。そこから通りを横断し、塀にぴたりと身体をつけ、警備室をそっとのぞいた。
風に乗って花の甘い香りが漂っている。正門の前だけではなく、敷地内の通路に沿って、樹木や花が植えられていた。
秀蓮が背負っていたリュックサックから薬の瓶を取り出した。布に薬を湿らせ、警備員が後ろを向いた隙に警備員の口を塞いだ。秀蓮は残りの薬を、気を失っている警備員の胸元にかけると、壁に並んだ鍵の中から、『管理棟』と書かれた鍵を取り、布を拾って、ふたりは管理棟事務室へ走った。
入口の扉は建物の北側。秀蓮が建物の中へ入ると、聡は鍵をかけて扉の前の植え込みに隠れた。どうか警備員が気付かずに通り過ぎてくれますように。そればかり考えながら、時計を気にしていた。そろそろ一時間が過ぎる頃だ。警備員が塀の外の見回りを終えて、敷地の中に入ってくる。
──遅い
秀蓮は何をしているのだろう。金庫を開けるのに手こずっているのか……。できれば最初にここを通り過ぎて欲しい。そう思っていると、警備員がこちらに向かって歩いてきた。
心臓から勢いよく送り出される血液が、耳の奥を叩く。聡は息が荒くなるのを必死に抑え、自分の気配を消そうと心を落ち着けた。
警備員は扉が閉まっているのを確認すると、手に持った小さな棒のようなもので扉のガラス窓から中を照らしてのぞき込んだ。中を照らしていたのはほんの数秒だったが、聡には長く感じられた。そして警備員は踵を返し、隣りの棟へと歩き出した。
聡の口から細く長い息が漏れた。直後、息が止まる。五・六歩歩いたところで警備員が立ち止まった。聡は声を出しそうになり慌てて口を押えた。風に煽られた木々のざわめきが聡の気配を消してくれたが、闇を伝って、警備員にまで聞こえてしまうのではないかと思うほど、聡の心臓が波打ち始めた。
警備員は首を傾げている。そして手にした鍵を探しながら扉へと戻った。聡の顔から血の気が引いた。警備員が鍵を扉の鍵穴に差し込んだ。聡は驚きに震える手で、今にも心臓が飛び出しそうな口をふさぎ、成り行きを見守りながら頭の中で考えた。建物の構造と、警備員が建物の中に入ったらどう行動するかを。
今は出て行けない。警備員が建物の中へ入ると、聡は急いで建物の西側へと回り込んだ。南側全面に取り付けられたベランダへの外階段を駆け上がり、秀蓮が忍び込んだ二階の東の奥の部屋の窓の下に静かに身を隠した。窓は鍵がかかっている。そっと部屋をのぞくと中に人影はなかった。警備員はまだ来ていない。聡は静かに窓を叩いた。
なんの反応もない。
秀蓮はどこだ? もうこの部屋にはいないのか……もう一度窓を叩いた。
人影が近づいてくる。聡は身を縮めた。窓が開き、秀蓮が顔を出した。
「警備員が来る! 早くここから逃げよう」
そう言って聡が手を差しのべたとき、廊下にちらついた灯りが部屋の前で止まった。
「早く!」
聡が小さく叫ぶと、警備員が手にした灯りが秀蓮の足もとを照らした。聡は慌てて身を隠した。秀蓮は窓ガラスを閉じた。窓の外の聡を隠すようにして秀蓮は入り口に向き直った。警備員はじっと秀蓮を見つめていた。灯りは徐々に足もとから体へと上がって行き、秀蓮の顔を浮き上がらせた。
銃声
「何をしている」
太い声。警備員の声は落ち着いている。
「見回りご苦労様です」
秀蓮が静かに答えた。警備員は秀蓮の顔に灯りを当てたまま「子供か?」と目を細めた。相手が子供だと警戒を緩めた警備員は、秀蓮の顔に当てていた灯りを胸元へと移動させた。
「はい。父を待っているんです」
この男がそんな言葉を信用するとは思っていないが、秀蓮は落ち着き払って、にっこり笑ってそう答えた。
聡は息を殺して壁にぴたりと体をつけ、中の会話に耳をそばだてた。
このままやり過ごせるだろうか。
体格の良い男だが、ふたりでかかれば何とかなると聡は思った。いつでも窓から入れるように身構えた。
警備員は表情を硬くしたままゆっくりと秀蓮に近づく。秀蓮がリュックサックから薬の瓶を取ろうとすると、
「動くな!」
言うと同時に警備員が腰に当てた手を秀蓮の額に向けて構えた。
──銃!
背筋が凍り付く。
秀蓮は一瞬目を光らせたが、すぐに無邪気な笑顔で「いやだなあ。僕は銃なんて持っていませんよ」と両手を上げた。
リュックサックが床に落ちる。
中に書類の入った封筒が入っていたのを警備員は見逃さなかった。
「その封筒は何だ?」
銃は秀蓮に向いたままだ。
「父に頼まれた書類です」
「ほう。君のお父さんは誰もいない暗闇の中で仕事をしているのかい?」
馬鹿にしたような口ぶりで、警備員が封筒の入ったリュックサックに手を伸ばしたそのとき、秀蓮は激しくぶつかり合う衝撃音を聞いた。振り返った秀蓮の瞳が、窓から飛び込む聡の姿をとらえた。聡は素早く窓を飛び越えると、その勢いで警備員の右足を蹴り放った。警備員がバランスを崩して床に手をついた。その隙にリュックサックを奪い取る。すかさず警備員の手にした銃へと手を伸ばした──
が、警備員はすぐに態勢を戻して立ち上がった。
聡は四つん這いのまま、自分へと向けられた銃を睨み上げた。
「聡……」
秀蓮は思わずつぶやいた。聡が来てくれたことへの安堵と共に、警備員の動きから目を離さず、この危機を回避する方法を巡らせた。聡は荒い息で警備員を上目づかいに睨みつけている。
聡が銃口を見つめ、ごくりと唾を呑みこむ。
「ふたりもいたのか……立て。手をあげて、その封筒を寄こすんだ」
聡が唇を固く結び、べっとりと汗で滲んだ手で滑り落ちそうになるリュックサックを胸にきつく握りしめると、警備員は銃口を聡の額に近づけた。聡は悔しそうに唇を噛みしめると、警備員ではなく、自分の足元近くに放り投げ、両手を上げた。
リュックサックから封筒がはみ出した。
なぜ警備員が銃なんか持っているのか……。秀蓮は聡だけは逃がそうと、警備員が隙を見せるのを待った。
警備員が封筒に左手を伸ばす。
視線を落とした瞬間、秀蓮は警備員に飛びかかった。警備員が瞬時に避けたので、銃を持つ右手は無理と判断した秀蓮は、咄嗟に左腕を背中に回してひねり上げた。
「銃を降ろせ。さもないとあんたの腕をへし折るぞ」
聡は秀蓮の恫喝的(どうかつ)な声を初めて耳にした。秀蓮が普段は見せたことのない怒りを露わにする。
「ふん、そんな子供の細い腕で何ができる」
屈強な体つきの警備員があざ笑うように言った。秀蓮の顔が怒りにひきつる。
「聡! 行け!!」
警備員を睨みつけたまま怒鳴りつけ、同時に秀蓮は警備員の腕をさらに押し上げた。
銃声が響き、銃が床に転がり落ちた。警備員の悲鳴と同時に骨の砕ける鈍い音が聡の耳に不快に響く。ひるむ聡に、なおも秀蓮が必死の形相で叫んだ。
「早く行け!! 早く!!」
聡は床の上の書類を掴むと、秀蓮を振り返った。その顔は迷っている。
「行け!!」
聡の迷いを払うように秀蓮が怒鳴る。
聡は素早く窓から飛び降り、転がるように走った。奥歯が砕けるくらい歯をくいしばっていた。
警備員が折れた左腕を抱えこんでうずくまり、力のない目で秀蓮を睨んでいる。警備員を見つめ返しながら、秀蓮は階段を駆け下りる音に耳を澄ました。
「体の構造を知っていれば、子供の力でもあんたの腕を折るなんて簡単なことだよ」
秀蓮が肩で息をしながら、顔にかかる前髪で隠れた口もとをゆがませて言った。警備員のくちびるが、何か言いたげに微かに動いた。
秀蓮が、床に転がった銃に手を伸ばすと
「動くな! 手を上げろ!」
背後から声がした。
「くっ……」
秀蓮は唇を噛みながら、ゆっくり手を上げて振り向いた。
銃声を聞きつけたもうひとりの警備員が、銃を構えて部屋の入り口に立っていた。
「なんだ、子供じゃないか」
秀蓮の姿を見て、子供と安心した警備員が、銃をおろして近づいてきた。その隙に秀蓮は床に落ちた銃に再び手を伸ばした。倒れていた警備員が苦しそうに「だめだ。そいつは……」と呻く。
慌てておろした銃を構える。秀蓮が銃を拾いあげ、近づく警備員に銃口を向けた。
静まりかえった夜の工場に銃声が響く。
警備員が引き金を引くのがわずかに早かった。秀蓮が手にした銃がごとりと床に落ちる。秀蓮の体が弾かれ、磨き上げられた真っ白な床に赤い血が飛び散った。
警備員が銃を向けたまま秀蓮に近づいた。秀蓮は左肩を押さえて警備員を睨み上げた。肩から流れる血が秀蓮の腕を赤く染める。
銃口が秀蓮の額にぴたりと止まった。
「何ごとだ!」
今度は警備員の背後から男の声がした。警備員の影になり声の主は秀蓮からは見えない。
「何をしている! 勝手な真似はするな」
秀蓮に銃口を向けたまま、警備員が男を振り返る。
「勝手な真似ではない。ネズミを捕まえているんですよ」
「そんな物騒なものをこの工場内で振りまわさないで頂きたいね」
秀蓮は男の声に耳を傾けた。こんな時間に駆けつけるとは、敷地内に住むKMCの役員か……。聡が逃げ出した窓はすぐそこに開いたままだ。今のうちに逃げ出したいが、体を動かすこともできなかった。
「そんなことを言って、このネズミはあなたたちの大切な金庫の中を荒らしたんですよ」
そう言って警備員は鍵の掛かっていない金庫の扉を開けてみせた。男が警備員の肩越しに秀蓮をのぞく。男は銃声を聞きつけて慌ててやってきたのか、寝衣にカーディガンを羽織っていた。
男の顔が何かに気づく。さらに秀蓮をじっと見つめる。顔を上げた秀蓮と目があった。
「君は……」
男は警備員の銃を手で押さえ、「この少年に何かあったら、ただではすまないぞ」そう言って、羽織っていたカーディガンを引き裂き、秀蓮の肩をきつく縛った。秀蓮の顔が激痛にゆがんだ。
──この男は誰だ? 僕を知っている?
秀蓮の目の前が暗くなる。
──ここで気を失うわけにはいかない……気を、しっかり持つんだ……。
「おい、大丈夫か? しっかりしろ──」
男の声が遠くなる。
秀蓮の意識は、そこで途切れた。
銃声に足が止まる。
聡は後ろを振り返った。
──どうする? 戻るか? いや、ここで戻ったら秀蓮が身を挺して僕を逃がした意味がない。秀蓮を信じよう。とにかく僕にできるのは、この書類を寮にいる櫂という少年に渡すことだ。渡した後、秀蓮を助けにこよう
聡は必死に走った。警備室には誰もいない。さっきの銃声を聞いて秀蓮のところへ行ったのか。さらに不安が押し寄せた。聡は立ち止まり、管理棟を見上げた。闇に浮かぶ白い花が揺れている。
聡は不安を振りきり、寮へと走った。
工場周辺の灯りが見えなくなったところで聡は足を止めた。呼吸を整えながら振り返る。誰も追ってはこなかった。耳を澄ませると川の流れる音が聞こえた。研究施設への橋がかかる場所まではもうすぐだ。
左手には森が広がっている。秀蓮が言っていた寮はこの森の中にある。聡は目を凝らしたが森の中は真っ暗だった。寮の灯りは見えない。聡はゆっくりと森へ足を踏み入れた。
月明かりのない初めて踏み入る森を、聡は迷うことなく突き進んでいった。足もとを注意する集中力は残っていない。転びそうになりながら歩いていくと、暗闇に目が慣れ、寮と思われる建物が見えてきた。灯りはなく静まりかえっている。みんなまだ寝ているのだろう。
聡はどこか入れるところがないか建物の周辺を歩き出した。洒落たレンガ造りの建物に、本当にここが秀蓮の言った寮なのか……聡はいぶかしんだ。
正面の入り口には重厚な木製の両開きの扉がはめ込まれ、その横には『神楽第一中等部寮』と銅のプレートが打ち付けられている。間違いはない。扉にはめ込まれた厚いガラスから中の様子をうかがった。正面にはホールが広がっており、奥に階段がある。左右に廊下が続いているようだった。廊下は真っ暗で誰も通りそうにない。聡は仕方なく扉の前に座り込んで朝になるのを待った。
空が白んでくると、裏口の窓に明かりがついた。陶器のぶつかる音がする。朝食の準備が始まったようだった。朝日が昇りすっかり明るくなると、寮の南側の窓からカーテンをあける音が聞こえてきた。
聡は入り口の扉の前に立って中をのぞいた。誰も通らない。聡はしだいにいらいらしてきた。我慢できずに扉を軽く叩いた。廊下は静まり返っている。誰も起きてこないのか。もう一度扉を叩いた。ひとりの少年がホールに現われ、音に気づいてこちらを見た。聡は少年が通り過ぎないように、夢中で扉を叩いた。
「うるさいなあ、誰だよ、朝帰りするなら鍵くらい持ってけよ」
少年が面倒臭そうに扉を開け、聡の顔を見て顔色が変わった。
「あんた達の寮はここじゃないだろ」
不機嫌な口調でそう言い放つと、少年は扉を閉めようとした。慌てて聡が身体を滑り込ませて止める。聡の必死な様子に少年は少し驚いた表情を見せた。
「人を、訪ねてきたんだ。櫂という人に渡したいものがある」
聡は真剣な目で訴えると、手に持っていたリュックサックを上げて、少年の瞳から目をそらさずに愛想良く笑ってみせた。
「櫂に?」
少年は不審そうに聡を見た。だが、聡のただならぬ様子に「ちょっと待ってて」と言ってドアを閉め階段を上がっていった。
待っているあいだ、何人もの少年たちがガラス越しに通り過ぎて行った。彼らが『特別クラス』の少年たちなのか……。
さっきの少年が体格の良い少年を連れて階段を降りてきた。
「俺に何の用だ?」
少年は寝ぐせで乱れた短めの髪をなでながら、あくびを押え、迷惑そうに言った。
「これを……君に渡すように秀蓮から頼まれた」
「秀蓮……」
櫂の瞳に光が走る。そして、聡を見つめていた目を細め、見定めるように下から上まで聡を見ると「ついてこい」とあごをしゃくった。
不愛想な少年
通された部屋には大きな暖炉があり、一組のテーブルとソファが置かれていた。
櫂に勧められてソファに腰を下ろした聡は「うわっ」と声をあげ、思わず腰をあげそうになった。柔らかいのに体が沈まず、包み込まれているような心地良さだ。
「いいソファだろう? KMCの応接室と同じソファなんだよ。他の物もな」
ソファに深くもたれ、足を組んだ櫂の言葉には、自慢ではない意地の悪い響きがあった。たしかに、暖炉も、高い天井から吊るされたレースと厚手のカーテンもテーブルも、手織りの絨毯も、聡には見たこともない外国製の品物ばかりだ。
レンガ造りのモダンな建物といい、この部屋といい、正直『特別クラス』の少年たちがこんな贅沢な環境で生活しているとは思ってもみなかった。
「あんた、聡か?」
いきなり名前を言われて聡は驚いた。なぜ自分の名前を知っているのだろう。
「ここに来るはずだった奴の名前、確か『聡』っていった。いつまでたっても来なくて、おかしいと思っていたら……秀蓮のところにいたのか」
少年の口から秀蓮の名前が出て、櫂に助けを求めるように、聡は身を乗り出した。
「秀蓮を知っているんだね? 秀蓮はまだKMCにいるんだ。これを君に渡すようにって、僕を逃がして、自分だけ……」
櫂は眉間にしわを寄せ、首を傾けた。
「どういうことだ? あんた、カンパニーから逃げてきたのか?」
「あ……」
聡は思わず夢中で話してしまったが、この少年は秀蓮を知ってはいても、秀蓮がKMCに忍び込んだ経緯は何も知らないのだとわかり、肩を落とした。
「ふたりで、KMCの工場に忍び込んだんだ……だけど、見つかって、秀蓮だけ……」
「忍び込んだ?……」
怪訝そうにじっと見つめる櫂に、聡はこくりと頷いた。
櫂は考え込むように腕を組むと下を向いた。が、すぐに顔を上げ「まあ、秀蓮なら大丈夫さ。捕まったとしても今頃は丁重に扱われているよ」と、表情を変えずにケロリとして言った。
先ほどから櫂は聡に対してニコリともしない。櫂の言葉に聡は拍子抜けした。
「俺に言えば、秀蓮を助けに行くとでも思ったのか?」
聡の顔が赤くなる。図星だ。
「あいつなら心配ない。俺たちが行ったところで足手まといになるだけだ。事を荒立てては、秀蓮が動きにくくなる。奴らは秀蓮を手荒に扱うことはできない。そのうち帰ってくるさ」
ソファに深くもたれたまま話す櫂の言葉を、聡は冷静に受け止めることはできなかった。聡はソファから立ち上がるとドアに向かった。自分ひとりでも秀蓮を助けに行く。ドアノブに手をかけたと同時に、櫂に反対の腕を引っ張られた。その拍子に聡はよろめき、倒れそうになって、櫂に抱きかかえられた。
聡は唖然として自分の足を見つめた。そんな聡に櫂が同情しながらも呆れたように言う。
「そんな足で何ができる? 秀蓮は自分の身は自分で守れる。だがおまえまでは無理だ。だからおまえを逃がしたんだ」
櫂の正論に、聡は力なく項垂れた。
「ほら、座れ」櫂は聡をソファに座らせ「秀蓮なら大丈夫だ。安心しろ」と聡の肩に手を置いた。
「で、その封筒はなんだ。何をして捕まったんだ?」
ソファに浅く腰掛け、さきほどより柔らかな口調で櫂が訊ねる。
聡はまだ迷っていた。気持ちは今すぐにでも秀蓮を助けに行きたかった。秀蓮の無事をこの目で確認したかった。少し考え込んでいたが、諦めて封筒の中身を取り出し、ふたりでカンパニーに忍び込んだ経緯を大まかに話した。
「それを、秀蓮とおまえでやったのか?」
聡が頷きながら「それで、秀蓮が来るまで、ここで待たせてもらいたいんだ」と、まだ秀蓮を気にしているのか、一本調子で力なく言うと、櫂はソファから腰を上げ、聡に右手を差し出した。
「わかった。聡。おまえ、たいした奴だな」
そう言って初めて笑顔をみせた。
聡はほっとして差し出された手を握り返した。
櫂はそのままここで待つように聡に告げると、部屋を出て行った。櫂に封筒を渡して安心したせいか、急激に眠気が襲ってきた。秀蓮のことが心配だったが、櫂は気休めを言うような人ではないと思った。櫂の言葉を信じよう……そう思うと同時に意識を失った。
櫂がさっきの少年──流芳(りゅうほう)を連れてきたとき、聡はソファでぐっすり眠っていた。櫂は流芳に毛布を持ってくるように言った。毛布を聡に掛けてやり、流芳には口止めをして部屋へ戻るよう言うと、封筒の中の書類を出し、書類に目を通し始めた。
※ ※ ※
「様子はどう?」
「熱が上がってきたわね。傷口は思ったより浅かったみたい。弾が少し掠っただけ。撃つつもりはなかったのかしら……。それにしても、こんな子供に銃を向けるなんて」
「ああ、彼らを何とかしないとな。医者は?」
「彼なら信頼できるわ。大丈夫よ」
「ありがとう。それから、暫くこの少年をお願いできるかな」
「いいわよ」
※ ※ ※
「目が覚めたか?」
自分が寮へ来たことを思い出して、聡は慌てて起き上がった。
「まだ寝てていいぞ」
テーブルを挟んだソファに座っていた少年が言った。
──ああ、そうだ、彼は櫂だ。彼に書類を渡して眠ってしまったんだ。
「いま何時?」
聡が訊ねると、櫂は暖炉の上の置時計を見た。これまた優美な装飾の施された時計だ。気づかなかったが、暖炉は大理石だ。時計は十時四十分をさしていた。
「ちょっと俺、部屋に戻るな。ああ、君のことは、俺の親戚が面会にきたって話してあるから。寮の中、好きにしてていいよ。管理人も寮のおばちゃんも、俺たちには干渉してこないから。それと。トイレはドアを出て廊下を左奥な」
言うだけ言って、櫂は部屋を出て行ってしまった。聡はドアからそっと廊下をのぞいた。誰もいない。聡は封筒をリュックサックにしまい、ソファの下に隠した。そっと部屋を出ると、足音を立てないように左奥へ進み、ドアを開けた。細かな彫刻が刻まれた額縁の大きな鏡に、大理石の洗面台。見たこともないような内装に聡はまたも驚いた。顔を洗って鏡をのぞくと秀蓮の顔が浮かんできた。
──本当に無事なんだろうか。秀蓮が言っていた『切り札』って何だろう。櫂も『手荒に扱うことは出来ない』って言っていた。秀蓮の言う切り札のことなのだろうか。櫂は知っているのか。
聡は部屋に戻ると封筒の中から書類を取り出した。秀蓮が戻って来るまでに目を通しておこうと思った。が、専門用語ばかりで、とてもこのままでは読めない。もう一度封筒にしまい、リュックサックに入れて肩に掛けると部屋を出た。
隣りの部屋をのぞいてまた驚く、今いた部屋が五つは入るだろうか。ソファがいくつも並び、蓄音器やピアノまで置いてある。暖炉の横に雑誌やボードゲームが重ねられ、棚には珍しい釣り道具が並んでいた。
トイレの前にもうひとつ部屋があったはず、廊下を歩きながら窓の外を眺めた。寮の裏は森が続き。川が流れ、小さな湖が見えた。湖には桟橋があり、小さな小屋とボートがいくつも浮かんでいる。寮の少年たちの為に用意された物なのだろうか。
聡はあの日、KMCの男が「悪い条件ではありません。子供たちが暮らしている様子をご覧になれば安心されると思いますよ」と言っていたのを思い出した。確かに、もしも母親がこの寮を見ていたら、自分はここに来ていたかもしれない。
もうひとつの部屋は図書室だった。それも高い天井まで、壁じゅうに本がびっしり敷き詰められていた。
「凄いや……」
聡は見上げながら呟いていた。それから手頃な辞書を三冊ほど棚から引き抜くと、窓辺に座って書類を読み始めた。昼を過ぎると仕事から帰った少年たちで階下が騒がしくなった。少年たちはシャワーを浴び、そのまま食堂へと入っていく。聡が廊下をのぞいていると、櫂が姿を見せた。
「ここにいたのか。昼めし、一緒に食おう」
聡が遠慮していると「大丈夫、おばちゃん達には話してあるから、腹減ってるだろう?」と、返事を聞かずに聡を引っ張っていった。
「こんな俺たちを相手にしているおばちゃん達はみんな訳ありさ。お互い何も聞かない」
櫂が皮肉まじりに笑みを浮かべてそう言った。
食堂には六人掛けのテーブルが並べられ、ここもまた綺麗に内装されている。南に面した大きな窓ガラスには森の緑が揺れ、まるでレストランのようだった。
食事は、並べられた大皿に盛られた料理を好きなだけ取る。みんな仕事の後だけに、皿から零れそうなほど盛っていく。
「座れよ」
櫂がテーブルの端に座り、聡に真ん中の席を勧めた。隣りに座っていた櫂を呼んでくれた少年が椅子を引いてくれ、聡は落ち着かない気持ちでテーブルに着いた。
聡の前には二人の少年が座っている。櫂が三人を紹介した。
「彼とは会ったね、名前は流芳だ。君の前に座っているのが麻柊。隣が透馬だ。聡、君のことはさっき簡単に話しておいたよ」
「聡です。よろしく」
そう言って麻柊から透馬に目をやり聡は「あっ」と小さな声を漏らした。透馬が首を傾げる。麻柊は差し出した手を引くに引けずひらひらさせていた。
「透兄? 透兄だよね? 慎兄の、友達の……」
聡の言葉に透馬の目が少しずつ見開かれていく。
「慎の弟か!? 驚いたな。──こんなところで会うとはな」
透馬は顔をゆがめて笑った。
「慎は元気か? 今どうしてる」
「都へ……王立大学で医学を勉強してる」
「そうか、あいつ夢を叶えたんだな。頑張ってたからな」
透馬は懐かしそうに目を細めた。
慎は子供の頃から一緒に王立大学へ行こうと励まし合ってきた親友だった。その親友が夢を叶えたのだ。嬉しいはず……だった。それなのに、胸に何かつかえているような重苦しさを感じる。透馬はそんな気持ちを吹っ切るように明るく言った。
「ここでは僕たちはみんな同級生だ。透兄はやめてくれ」
透馬が手を差し出た。聡が手を握り返す。麻柊の手は引っ込められていた。
「なんだ? 知り合いか」
櫂が訊ね、透馬と聡がうなずいた。
「まあ、続きは後にして。──聡がとんでもないものを持ってきた」
困惑した顔を向けた聡を横に、櫂は不敵な笑みを浮かべていた。
君の声は僕の声 第二章

