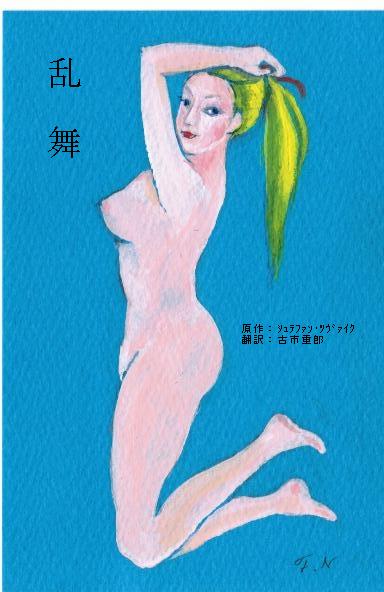
イレーネ夫人
まえがき
シュテファン・ツバイクは王妃マリーアントワネットを描いた。王妃は豪奢な宮廷生活の果てに断頭台に向かった。なんと凄惨な壮絶なシーンであろうか。ツヴァイクがなぜそれまでして王妃の生涯を語りたかったのか、私は知りたかった。
イレーネ夫人
乱舞
シュテファン・ツヴァイク 作
フルイチ ジュウロウ 訳
絵 古市宣子
イレーネ夫人は恋人のマンションを出て階段を降りてきた。そのとき、不意にまた言い知れぬ不安におそわれた。にわかに黒い星がまぶたにうなりをあげて廻りだした。膝が硬直しガクガクした。不用意に前にのめらないように、あわてて欄干にしがみついた。夫人が危険きわまる逢引をおかすのは初めてではない。こうした不意にくる戦慄(せんりつ)も決して珍しくはない。帰り際にかならず、内心どんなにあがいても、意味のないばかげた不安から不測の発作におそわれるのである。とはいえ、逢引の道はためらいなく痛快である。訪ねる時、街かどに車を止めるやいなや、夫人は脇目もふらず急いで門口まで駆け込んだ。そこからあわてて階段を昇った。すみやかに開くドアの陰に恋人がじっと待ってくれると夫人は意識した。やるせない焦りに燃えて、新たな不安は相見る熱い抱擁の中に消えた。だが、いざ帰るとなると、また別の不気味な不安が悪寒とともに込みあげてきた。罪の恐怖とともに、自分がどこから出てきたかは往来の人たちの目にとまったかもしれない。そして、狼狽する様子にそっけない微笑で応じるだろうといった余分な妄想に夫人の心は乱れた。彼の胸のなかで、そんな予感の不安が昂じて、つかの間の惜別(せきべつ)の思いはそがれた。彼から離れようとすると、いらだつ焦りから諸手が小刻みに震えた。彼の言葉をうわの空にきき流しながらも、とりとめなく男の情欲の虜(とりこ)になるまいとあがいた。帰らなくては、ただちに帰らなくては、恋人の部屋から、恋人の家から、情事から逃れて、自分の静かなブルジョア世界に戻りたいとひたすら願った。明らかに背信の恐怖から、夫人はどうしても鏡の中をのぞけない。たしかに彼女は愛の時間をすごした。だが愛の戯れによって衣服に一点の染みがないことを見ておく必要があった。そのとき、興奮のあまり聞きとりがたい言葉がささやかれた。別れぎわの空しい慰めの言葉だった。階段を昇り降りする者がいないかと、しばしドアの陰に身をひそめて聞き耳を立てた。やはり、外に不安が立ちはだかった。それは一気に夫人を捕まえようとしていた。恐怖のあまり、心臓の鼓動があらあらしく打った。息を殺して階段を降りるうちに、張りつめた集中力がふっ切れるのを夫人は感じた。
イレーネ夫人はしばしまぶたを閉じてたたずみ、薄暗い踊り場の冷気をむさぼるように吸った。すると、上階のどこかのドアがバタンと閉まった。彼女はびくっとした。思わず厚いヴェールをしっかりつかんで階段をかけ降りた。今またあの別れぎわの恐ろしいつかの間におびえた。他人の家の玄関から往来に出て、ひょっとして通りすがりの知人から「あなた、どこから出てきたの?」と、とっさの問いかけに彼女は困惑し虚(きょ)の危険にさらされるであろう。彼女はレースに挑むスプリンターのように頭を低くしずめ、一瞬のすきに半開きの門口に急いだ。
そのとき、いきなりひとりの女が入ってきて、イレーネ夫人にドンと突きあたった。「失礼」と、女は顔をしかめて言った。夫人はせわしく相手の脇をすりぬけようとした。しかし、女は門口いっぱいに立ちはだかり憤然と、しかも妖しい嘲笑で夫人をにらみつけた。「いつか、あんたをつかまえてやろうと思っていたわ」と、女はぶしつけに荒げた声で叫んだ。「なるほど、お上品な奥様でいられるわ、噂どおりに! ご亭主もいて、金もたんまりあって、それでも満足できず、そのうえ貧しい女から恋人を盗っちまうなんて‥‥」
「まあ、なんてひどいことを‥‥人ちがいですわ‥‥」と、夫人はしどろもどろだ。気まずそうにその場を逃れようとした。すると、女はデンとからだを張って出口をふさぎ、甲高い声でまくしたてた。「いや、人ちがいなんかじゃない‥‥あたしはあんたの跡をつけてきたのよ‥‥あんた、エドワードのところから出てきたじゃない。彼はあたしの男よ‥‥いまやっとあんたをつかまえて、納得できた。あの男、最近なぜかあたしに会ってくれないのよ‥‥あんただったのね‥‥ずるい女だ!」
「お願いですから」と、夫人はかぼそい声で遮った。「そんな大きな声を出さないでください」と、思わず後ずさりして、また戸口に戻った。女はあざけるように夫人をじっと見た。恐れおののき不安に夫人は困惑の顔を隠せない。その様子に女はなんとなく気をよくした。というのも、女はふてぶてしくあざけり、満足げな薄笑いで恋敵をしっかり見ることができたからだ。女の声はいやしい快感のあまりすっかり上機嫌にきこえた。
「結婚されたご婦人が、お上品な奥様が、他人の亭主を盗むときはそんな恰好をされるんだ、ヴェールを羽織って。なるほど、ヴェールを羽織(はお)ってね。それで、お上品な奥様は訪問する先々で男たちとたんまりおたのみっていうわけね‥‥」
「なんて‥‥ひどいことを、あなたは一体なにをおっしゃいたいの?‥‥私、あなたなんて存知ません‥‥私、急ぎますから‥‥」
「お急ぎで‥‥分かってるよ‥‥旦那さんのところへ‥‥温かいお部屋で、お上品な貴婦人が下男にお洋服を脱がせてもらって‥‥ところが、あたしなんかどんな生活をしようが、飢え死にしようが、上流のご婦人には全く関係ないからね‥‥そうまでして他人様から大事なものを奪おうってことね‥‥おしとやかな奥様が‥‥」
イレーネ夫人はくるりと背を向けると、暗黙の了解で、本能的に懐中の財布に手をやった。さっき銀行からおろしてきた札束をつかんだ。「じゃあ、‥‥これで、これをお持ちになって‥‥さあ、私を放してちょうだい‥‥ここへはもう二度ときませんから‥‥誓いますわ」
女サギ師は陰険な目付きで金を受け取った。「この売女(ばいた)!」と、女は言いすてた。その言葉に夫人はぞっとした。しかし、女が門を開放する気配をみせるやいなや、自殺者が塔から身を投げるように夫人は憤然と息もつかず転げでた。人波を押しのけて先へ先へと走った。暗く沈んだ眼差しで、街角に待つタクシーによろよろとたどりついた。かたわらを通り過ぎる人たちがしかめっ面で見やる顔を夫人は意識した。わが身をまるで物のように、シートにドーンと投げた。全身がすっかり硬くなって動かない。不審な乗客に「行き先はどこですか?」と、運転手はいぶかしげにたずねた。夫人はただ悄然と見つめていた。しばらくして、空白の頭がようやく運転手の言葉を理解した。南駅までと、あわてて夫人は叫んだ。にわかに女サギ師に追われている想念にとりつかれ、「急いで、急いで、速く走(や)って!」と言った。
車の中で、あの遭遇がなんとショックであったか夫人はため息をつた。夫人は手を合わせようとするが、腕は硬直し、無感覚になった物体のように冷たくからだにぶらさがっていた。全身が急に激しく震えた。咽(のど)もとになにか苦(にが)いものが込みあげてきた。吐き気をもよおし、同時に腹の底が痙攣のようにうずいた。得体の知れぬ重苦しい憤りをおぼえた。悲鳴をあげて取っくみ合えばよかったのか。そうすれば恐怖の記憶も払拭できたであろう。だが、まるでくさびが額に打たれたように、記憶は脳裏に残った。そこには、嘲笑する卑しい顔、プロレタリア女の臭い吐息、憎たらしい卑劣な言葉で罵倒するあの醜い口、威嚇(いかく)して振りかざす赤らんだ拳(こぶし)があった。ますます嫌悪感がつのった。なにやら吐き気が喉もとに込みあげてきた。車はスピードを上げて左右に大きく揺れた。運転手にゆっくり走るよう促すところだった。そのとき、夫人は紙幣をすべて女サギ師に与えてしまったのに気づいた。精算する金が足らないかもしれないと思った。夫人はあわてて運転手に車を停めるよう指示した。夫人が急に車から降りることに運転手はけげんな顔をした。手持ちの金でなんとか間に合った。しかし、気づいてみると、夫人は見知らぬ街で、賑やかな人々の雑踏の中を徘徊していた。人々の言葉も目つきもなじみがない。同時に、不安のあまり膝はくたくたに疲れ重い足を運んだ。とにかく、自宅に帰らなければならない。全神経を集中し、夫人はまるで沼地や膝ほど深い雪の中を歩くようだ。路地から路地を超人的な意志で突き進んだ。やっと自宅に着いた。いらだたしくあわてて玄関に倒れこんだが、すぐ態勢をととのえた。動揺する心が気づかれないように、彼女はりんとした態度でそっと階段を昇った。
イレーネ夫人はメイドの手をかりてコートを脱いだ。足もとで長男が妹と賑やかに戯れていた。安心した目で持ち物を手にとり、所有物と身の安全を確かめた。とりあえず冷静を取り戻したようだ。一方で、激しい興奮の波が張りつめた胸にいたくあたった。彼女はヴェールを脱いだ。しっかりした意識で何気ない様子をつくろい、顔をなでつけながら食堂に入った。夫が夕食の支度のできたテーブルについて新聞を読んでいた。
「イレーネ、遅いな、遅いじゃないか」と、夫はやんわりと皮肉っぽい声で話しかけた。彼は立ちあがると妻の頬にキスをした。思わぬキスに彼女は恥ずかしく心が痛んだ。夫婦はテーブルについた。彼は新聞を離さずに、さりげなく「こんなに長い時間、どこに出かけていたんだ?」と訊いた。
「私‥‥あの‥‥アメリエのところに‥‥あの人なにか買物をしたいと言うもので‥‥私がついていったのよ」と、彼女はつけくわえた。恐ろしく下手な嘘をつく自分の軽率さが腹立たしかった。いつもなら、かならず前もって入念に工夫され、周到にあらゆる事態に対処できる嘘の言葉を用意しておいた。だが、今回は不安のあまりそんなこともすっかり忘れ、下手な言いわけになった。つい先頃、恋人と二人で劇場に芝居を見にいった。そのとき、もし夫から電話でもかかって問い合わせられたらどうしようかといった雑念が脳裏をかすめた。
「いったいどうしたんだ?‥‥おまえ、いやにいらいらした様子で‥‥どうして帽子を脱がない?」と、夫は訊いた。あらためて困惑する自分に気づき、身震いした。彼女はあわてて立ちあがった。自室に入って帽子をとった。しばらく鏡に映る動揺の目をじっと見つめているうちに、やっと視線がしっかり落ちついた。夫人はキッチンに戻った。
メイドが夕食を運んできた。ふだんと変らない夕食の光景である。だが、みんないつもより口数は少なくなじみがない。素っ気ない怠惰な家族の会話はギクシャクした。彼女は絶えずもときた道をさまよい、女サギ師と対峙した身の毛のよだつ瞬間に想いが及び、身震いした。夫人は目をあげて安全を確かめた。身の回りに温かく息づくものをひとつひとつそっと触れた。どれにも想い出と意味が込められて部屋に置かれていた。夫人の心にあわい安堵がよみがえった。壁時計は沈黙の中に非情なテンポでときを刻んだ。いつの間にか彼女の心臓もふたたび正常に安定した鼓動をうった。
あくる朝、夫は裁判所へ、子供たちは散歩へ出かけた。やっとひとり残された夫人は、午前の明るい陽光のもとで、あの恐ろしい遭遇をひとつひとつ反芻(はんすう)した。そのうちに、恐怖心はおおかた消えた。ヴェールが非常に深かったので、女サギ師は私の顔の特徴に気づかず、認識できないだろうと夫人は判断した。冷静に周到な箕隠しを詮索した。恋人のマンションには二度と訪ねない。そうすれば、女サギ師の奇襲作戦をうまくかわすことができる。しかし、女サギ師と偶然に出くわす危険は残るが、それは有りえないだろう。なぜなら、あの時私は車に逃げ込んで、相手は追ってきたわけではない。女サギ師は私の名前も住所も知らない。だから、漠然とした顔形からふだんの確かな顔を識別できない。しかし、最悪な場合にそなえ、夫人は万全の策を講ずればいい。それによって、もう恐怖の鉄の万力に噛まれることはあるまい。地のままに応ずればいいと、夫人は覚悟した。冷静な態度を保ち、一切を否定し、相手の錯誤を冷たく主張すればいい。さらに、現場に居合わせたものはいないのだから、訪問の立証はたたず、かえって女に詐欺罪が適用される。夫人が市内でも名の知れた判事夫人であることは有利である。夫と同僚の法律家の談話などから、恐喝(きょうかつ)などはきわめて冷静な態度を持してかかればただちに撃退できることを夫人は認識していた。ともかく、追及される側が逡巡し、不安な様子を見せると相手は優越感を増長するものである。
第一の対抗策として、イレーネ夫人は「明日はお約束の時間にうかがえません、翌々日も無理です」と、恋人に宛てて簡潔な手紙をしたためた。ざっと目を通した。初めて筆跡を偽って書く手紙はなんとなく釈然としない。さらに、昨日の遭遇の想いが邪魔して、無意識に行間に冷たさが残った。心の底から激しい憎悪がありありと表出した。だが、無愛想な言葉を親しい言葉にかえることもできた。しかし、自分が恋人の愛をあんな卑しい下品な先客の後に享しんだという、はなはだ不愉快な事実を知ったとき、夫人の自尊心は著しく傷つけられた。憎悪の感情で言葉を詮索しながら、むしろ復讐しようとする冷たい手法に転じられたのも、あの女の奇襲をほどほどに寛容な気持ちで受けとめたからでもある。
イレーネ夫人は、はからずも限られた社交の夜会で、たまたま新鋭の青年ピアニストを知った。まもなく、これといった理由もなく知らず知らずに彼の愛人になった。もともと、女のからだが男の血を求めたのではない。肉欲的精神的な絆で男のからだと結びついたのでもない。ひたすら彼を必要としたのでもない。激しく恋い焦がれたのでもない。男の意志に抵抗するのが億劫なのとある意味で浮気から男に肌を赦したのである。
なにはともあれ、彼女は夫婦の幸せを十分味わった。人妻によくある精神的な興味を失ったわけでもない。そのなかで、愛人を求めたわけではない。彼女は自分より裕福で精神的にもすぐれた亭主と二人の子供と一緒にいるだけで十分に幸せである。悠々自適の静かな生活に、彼女はなに不足なく満足して時間をすごした。しかし、そこには驟雨(しゅうう)や嵐のように狂おしく官能をさそう空気がただよっていた。幸福にひたっていると、かえって不幸のとき以上に刺激を求めるものである。満足感をえた女たちだって、失望感のあまりたえず不満をいだく人と同じ宿命をたどる。満腹感は空腹感にまして刺激的である。したがって、生活が安泰で安穏であるがゆえに、アバンチュールの好奇心が誘発されるのである。彼女の生活に不自由はない。家政のすべてが任されていた。生活になんの心配はない。愛情もあり、なごやかな愛と家庭的な配慮など万全なケアがほどこされている。家庭の規律は第三者の事情に乱されることもない。家族から無視され敵対行動など受けたこともない。しかし、なんとなく実生活の快適さに翻弄(ほんろう)されていると彼女は思った。
新婚生活は仲むつまじく安らぎ、若い母性をくすぐる興奮に燃えた。大きな愛と感情のエクスタシーに幻想をいだいた乙女はその夢をついにかなえた。やがて、三十近くになった今、夢がふたたびよみがえった。ちまたの女たちと同様に、彼女のからだの中に激しい愛欲の本能が目覚めた。確かに、アバンチュールを経験したい気持ちはあっても、なかなかその危険というほんとうの代償を払う気になれない。
自分ひとりだけでは昂揚(こうよう)しない穏やかな時の間隙に、あの青年が強引に露骨な欲望で夫人に迫ってきたのだ。芸術のロマン性にことよせて、彼女のブルジョア世界に立ちいってきた。ほかの男たちは執拗に母性を求めたりせず、他愛ない冗談やちょっとした色眼で、もっぱら「きれいな奥様」とうやうやしく褒めそやすのである。夫人は少女時代以来はじめて心の底から興奮を覚えた。彼の人間性に触れ、哀愁の影に彼女はひたすら魅せられていった。彼の清楚(せいそ)な顔に哀愁が漂い、彼女は自然と強烈な印象をうけた。彼が長い間研究してきた即興曲を高める美の技法や、メランコリックに沈むうつうつとした情念をしっかり習得したとはその相貌から測れなかった。充分に満たされたブルジョア的な人たちに取り囲まれていると夫人は感じた。哀愁の中に、書物が華やかに描写し、脚本家がロマンチックに演出する高度な世界がうかがえた。夫人は、思わずふだんの感情の際に身をかがめ、自分をじっとみつめた。たちまち心が奪われて、彼女は彼の演奏に熱い賛辞の言葉を贈った。賛辞をきいて彼はピアノから彼女を仰ぎ見た。彼の一瞥が彼女をとらえた。彼女は愕然とした。同時に、あらゆる不安のもつ快楽を感じた。そのとき、すべてが深層の焔に照らしだされ、燃えるような対話が交錯した。対話は彼女の活発な好奇心をいっそう激しく駆り立てたのである。新しい遭遇を求めて彼女は公開コンサートに必ず出かけた。
二人は頻繁に逢った。どうやらそれはもう偶然ではない。彼女には自分の真の芸術家の理解者であり、また助言者として大義名分があると、彼は熱っぽく口説いた。彼女の功名心をたてて、数週間後、彼は「あなたの前で、あなたの家であなたのためにぼくの最新の作品を演奏したい」と申し出た。彼女はそれを軽率に信じてしまった。約束は、おそらく彼の本心からなかば正直なものだろう。だが、それは接吻となりついには不意をうたれて彼女は肌を赦すことになった。初めての気持ちが意外にも肉欲に変心したことに自分でも驚くほどであった。男と女にまつわる異様な恐怖心はたちまち払拭された。不本意な姦通に対する罪悪感は、ある面で皮肉にも虚栄心によって、また、気ままに生きてきたブルジョア世界を否定する独善的な判断によって癒やされたのである。当初恐れていた不倫に対する恐怖心は虚栄心になり、昇華されて自尊心に転じた。
しかし、こうした妖しい興奮にすっかり緊張したのも最初の時だけであった。じつは、彼女は本能的にこうした人間に対し心の底で抵抗感があった。彼のファッションや、女性の好奇心を惹く奇才にもたしかに抵抗があった。常に浪費と貧困の間をさまよいながらも、彼の派手な服装や、生来の放浪癖や収入の不安定は夫人のブルジョア感情を逆なでした。とはいえ、多くの女性と同様、彼女は遠くからひときわロマンチックな芸術家を求めた。しかも、彼女はプライベートな付き合いの中で非常に礼儀正しくふるまいながら、モラルの鉄柵の奥でほえる猛獣でありたかった。彼女は彼の演奏に酔った。情交のときも、彼女は彼の情熱に不安をいだいていた。もとより、彼女はそんな唐突で一方的な抱擁は好きではない。ひとりよがりで無遠慮な激しい抱擁と、何年たってもなおシャイで尊敬できる夫の情熱とを彼女は比較した。ところが、彼女はいったん不貞を働いた今となって、幸せになるとも不幸になるとも考えなかった。なんとなく義務感や慣れ合いの惰性から頻繁に恋人を訪ねていた。彼女は自ら浮気な女たちに交わり、はからずも、高級売春婦の仲間になっていた。内心ブルジョア感覚が非常に強いので、不倫にもきまりをつけたかった。すなわち、みずからの不貞に一定の家庭規律を敷いた。忍耐の仮面をつけて、特別な感情を日常生活に張り巡らそうとした。数週間後、彼女はこの若い恋人をなんとかしっかりと自分の生活の枠にはめこみ、姑がわりに週一日をデートの日に定めた。しかし、この新しい関係は夫人の過去の生活をいささかも損ねず、単に自分の生活に一つのイベントが加わったにすぎない。しばらくたっても、恋人は彼女の生活の快適なメカニズムを損なうことはない。新しく生まれた第三子か、あるいは新車を買ったように程よい幸福の付加物となった。そして、アバンチュールはやがて赦された快楽になりごく月並みに思えてきた。
今あらためて、夫人はこのアバンチュールに危険という現実的な代償を払わなければならないと思った。彼女は詳細に代償の計算を始めた。幸せに恵まれ、家族に愛され、富裕な資産をつくり、このうえ望むものはない。だが、こうした新たな煩わしさに出会って、夫人の愚痴が多く
なった。精神的ゆとりができたからといって、ただちに気を赦したわけではない。知らず知らず恋人のために自分の快適な生活を犠牲にしていた。
午後になって、メイドが恋人からの手紙を持ってきた。神経を逆なでるようないらだたしい手紙である。思い乱れて切々と訴える文面に、このたびのアバンチュールを終わりにしようとする彼女の決心がふたたび揺らいだ。なぜなら、彼の情欲が彼女の虚栄心をくすぐり、彼が絶望の淵に立たされて情欲に燃えるからである。「もしぼくが知らないうちにあなたの気持ちを傷つけたなら、せめてぼくの罪を赦してほしい」と、彼は切々とした言葉でひとときの逢引を懇願してきた。そこで、相手をあせらせ、理由なく拒絶することで、自分をさらに高尚な存在であると相手に知らしめてやろうと、新たな悪戯に彼女は胸を躍らせた。彼女は内心有頂天になった。冷静な人がとるように、恋にときめくのも自分ひとりでは燃えないといった態度をみせた。さっそく、彼女は喫茶店に彼を呼んだ。たまたまイレーネ夫人はその喫茶店をおぼえていた。娘の頃に若い俳優とデートに使った場所だ。いまになってみると、子供じみたデートだった。相手は慇懃な態度を見せるが、隅におけない男だった。不思議にも、そんなロマンスも八年の結婚生活の間にすっかり失せてしまった。だが、わが人生がいま再び咲きかけると思うと夫人はほくそえんだ。昨日の女サギ師とのそっけない遭遇も内心快感があった。久しぶりに夫人は強力な刺激的な実感をうけて、すっかりたるんでいた神経が心の底から震えた。
今度、女サギ師に遭遇することがあったときに、女の記憶を紛らわせると思った。イレーネ夫人は黒っぽい目立たない地味な洋服を着て、変わった帽子をかぶった。相手に気づかれないように、ヴェールを用意したが、急にそれを嫌って帽子にしたのだ。彼女は尊敬され有名な判事の夫人である。だからといって、まったく見ず知らずの人たちに気兼ねして、なぜ公然と街を歩けないのだろうか? さらに、危険に対する恐怖心と異様に刺激的な興奮と挑発的でズキズキうずく悦びが混ぜんとした。それは、指に剣の冷たい刃を感じ、ピストルの黒いグリップに死が詰めこまれ、その銃口が向けられたときの戦慄だった。アバンチュールの戦慄も、彼女の心に秘めた異常な生命力である。それは夫人のそばでいつもいたずらっぽく誘惑した。こうした興奮に神経は著しく緊張し、電流を感ずるようにからだがビリビリ感じた。
夫人は往来に出るやいなや、不安が心中をよぎった。湖水にからだを沈める前に足先を水に浸すときのように、そぞろ流れる冷たさに身の毛がよだった。しかし、その冷たさはいったん彼女のからだにしみこむと、貴重な生の悦びに胸が躍った。それは身に覚えのない悦びだった。緊張しながらも揚々とした足取りで、非常に軽快に力強く闊歩した。気づいてみると、彼女は喫茶店の近くにきていた。漠然とした意識がリズミカルに躍動した。妖しくひきつけるアバンチュールの誘惑に彼女はうきうきと入っていった。待合せの約束の時間が迫っていた。恋人が先に待っていてくれるという快い安心感が夫人の血を熱くした。店の中に入ると、彼は奥の片隅に座っていた。感激のあまり、いきなり彼は抱きついてきた。そうした行為は胸を打つが、つらかった。大きな音を立てないようにと彼女は彼をなだめた。というのも、彼の興奮のどよめきとともに、熱い疑念や非難を浴びかねないからだ。彼女は逢引きをやめた本当の理由を言わず、意味ありげな言葉でごまかした。そんな曖昧さが彼の気持ちをいっそう苛立たせた。彼の懇願に対しむしろ彼女はよそよそしい態度で、逢引の約束をはばかった。なぜなら、思いがけない急な心ばなれと拒絶が、どんなに著しく彼の気持ちを傷つけるかを彼女は察したからである。三十分ほどの熱い話し合いの末、彼に対しいささかの愛情も保証せず、約束もせずに二人は席を立った。そのとき、彼女は少女時代に知った異様な好奇心に気持ちが燃えた。ほのかにゆらめく焔が深層で赤く燃えた。焔は彼女の頭上でパチパチと音を立て、火をあおりたてる風を待っているようだ。
道すがら、裏町の人たちが浴びせる視線を夫人は敏感に意識した。思いのほか、多くの男たちの誘惑の視線を浴びた。自分がどんな顔をしているのだろうかという好奇心を強くいだいた。そこで、彼女はフラワーショップのショーウインドの前に立ちどまった。赤いバラと露の光るすみれの花籠に映るわが美貌を眺めた。ガラス窓にあまく若い眼差しがまばたいた。半眼半口の官能的な顔が向こうから満足げにほほえみかけてきた。二三歩あるいて、彼女は意識的に自分の肢体をちいさく動かした。肉体的に解放されたい、踊りたい、酔いたいといった欲求から、足取りがふだんの軽快なリズムを取り戻した。夫人は足速にミッチェル教会の前を通りすぎた。そのとき、教会の時を打つ鐘の音をきいた。鐘の声は彼女を家路に急がし、窮屈な秩序ある世界へと招いた。こんなさわやかな自分を意識するのは少女時代以来のことである。肢体にこれほど強い生気を感じたことはない。結婚当初にも恋人の抱擁にも今ほどからだが焔に熱く燃えたことはない。この不思議な軽快感も甘い血潮の情熱もすべて規則正しい時のなかに消えてしまうのを、彼女は惜しんだ。彼女はとぼとぼと街なかを歩き続けた。自宅の前でしばし立ちどまった。燃えるような大気を、ひとときの錯乱をもう一度胸を広げてすった。斜陽のアバンチュールの波を胸の深くまで享受したいと彼女は思った。
そのとき、誰かがイレーネの肩に触れた。夫人は振り返った。「なに‥‥なんの御用ですか、あなたは、また?」と、突然夫人がその忌わしい顔を見たとたん、愕然とし死にそうな思いだった。そして、うらみがましい言葉をきいて再び愕然とした。もしどこかでこの女と遇っても、知らん顔で一切を拒否し、女サギ師に真っ向から対抗するつもりだったが‥‥すべてが手遅れだった。
「あたし、もう三十分もここで待ってたのよ、ワグナーさん」
自分の名前をよばれて夫人はぞっとした。女は夫人の名前も住所も知っていた。今となって、すべてがおしまいだ。救いようもなく女の術中にはまった。夫人は不安なまま用意しておいた計算ずくめの言葉を舌の間に詰まらせた。だが、舌がからまって声がでない。
「もう三十分もあんたを待ってたのよ、ワグナーさん」と、威嚇的にもったいぶった口調で女はまくしたてた。
「なんの用があるのです?‥‥私に一体なんの用があって‥‥」
「わかってるじゃない、ワグナーさん」と、自分の名前をきいて、夫人はふたたびぞっとした。
「あたしがなぜお訪ねするかなんて、よくわかってるはずよ」
「私はあの人ともう会ってませんから‥‥私を放して下さい‥‥もうあの人と会うこともないのですから‥‥決して‥‥」
夫人の興奮がやむのを、女はゆっくりと待った。そのとき、女は召使に対するように荒々しく言いはなった。
「嘘を言うんじゃない! あたし、あんたの跡をつけて喫茶店までいったよ」と、たじろぐ夫人を見て、さらに女は嘲けるように畳みかけて言った。「あたし、いま働くところがないのよ。お店も首になったし。仕事はもうないって言われてさ、景気が悪いとか。まあ、それを口実に使い捨てっていうわけさ。だから、あたしたちみたいな女も、たまに浮気すんのさ‥‥上流家庭の奥様たちと同じよ」
イレーネ夫人の心臓を突き刺すように冷たい陰険さで女は言った。下品で露骨な残酷な女から身を守るすべがないと夫人は感じた。そして、女は大声をあげはしまいか、あるいは夫が通りがかりはしまいかと、夫人は戦々恐々とした。なにもかもおしまいだ。夫人はすばやく懐中に手を入れると、銀色の財布をとり出し、有り金を手にとった。略奪品を待ちうけるように、女の手が厚かましくヌーッと伸びてきた。憮然として、夫人は札束を女の手につきだした。
ところが、女が札束を感じるやいなや、慎ましく手を引っ込めるどころか、手は鷹の爪のように宙にひらいた。
「シルバーのお財布もいただくわ、お金をなくすといけないから!」と、嘲笑的にひんまがった口は濁声でゲラゲラ笑った。
イレーネ夫人は女を一瞥したが、ほんの一瞬だった。女の不敵で卑しい嘲笑が耐えられない。うずく苦痛のように、憤懣やるかたなく全身が震えた。ただひたすら逃れたい一心だった。こんな顔は二度と見たくない!と、夫人は目をそむけた。さっさと高価な財布を渡すと、恐怖につかれて階段を昇った。
夫はまだ帰ってなかったので、彼女はソファに身を沈めた。ハンマーで打ちのめされたように、身動きもせずソファに横になった。指がはげしく痙攣し、腕から肩まで震えた。からだ中に恐怖がうずまき、突き上げる憤りの感情を彼女は抑さえることができない。外から夫の声がきこえた。夫人は渾身の力でやっと立ちあがった。反射的な動作とうつろな意識で自分の部屋に身を引きずっていった。
いまや恐怖は家の中の夫人の身にまといつき、部屋から外に出られない。長い空しい時間に、寄せてはかえす波のように、いまなおあの恐ろしい遭遇の情景が彼女の脳裏を行き来した。彼女の失意の状態があきらかになった。女サギ師は、どこで知ったのかわからないが、夫人の名前も住所も知っていた。さらに、最初の恐喝が見事に成功した。だから、先々その手口を使って恐喝を続ければ下手な工作はいらないのは明らかだ。長年の間、女サギ師は悪霊のように現れ、夫人の人生を苦しめるであろう。必死にもがいてもその呵責を拭い去ることはできないだろう。夫人は、財産がありまた裕福な亭主の妻である。しかし、女サギ師から逃れるには相当な金がいる。それを調達するにはどうしても夫に相談しなければならない。とりわけ、夫らから洩れてくる談話や訴訟事件からこの種のケースを彼女は知っていた。だから、こんな狡猾で恥知らずの女の契約や約束は全く意味がないのだ。一、二か月くらい事件は長引くだろうと夫人は推測した。そのうち、家庭の幸せという不自然な建物も崩壊するに違いない。自分が破滅して、女サギ師もろとも崩壊させるという手段に望みをかけた。そもそも、夫人自身が失った生活と、自分が唯一被害者であることで脅かされた呵責を照らし合わせると、本件に関し悪辣で十分に罰せられるべき確定犯に対し六ヶ月の懲役が妥当である。今日まで、恵まれた生活をしてきた。運命を自分で切り開く必要はまったくない。だから、新しい生活を始めることは彼女にとって不名誉であり屈辱でありまた納得できない。そもそも、家には子供もいる、夫もいる、郷里もある。しかし、一切を失って初めて、家庭生活の面も実態もいかに大事かを夫人は痛感した。かつてスキンシップで子供たちに触れた生活がたまらなく懐かしく思われてきた。一方で、見知らぬ放蕩女が巷をのうのうと闊歩した。女は権力的な一喝で暖かい家庭を破壊させるようとした。だが、そんな風潮が夫人には許しがたいのだ。
災難は免れがたく、回避は不可能であることを夫人はまざまざと知らされた。しかし、なにが‥‥なにが起ころうとしているのか? 朝から晩まで彼女はそんな想いにおびえた。いずれ、内容を証明する通告が夫のもとに届くかもしれない。夫が血相を変えて入ってくる。彼女の腕をつかみ詰問する姿を彼女は想像した。しかし、いまさら‥‥いったいなにが起こるのか? 夫はどうしようとするのか? すると、様々な映像がにわかに乱れ、無情な不安の闇に消えた。彼女にはその先が分からない。彼女のイメージはすみやかに奈落へ消えた。しかし、悶々と想いめぐらすうちに、夫について彼女はなんと無知であったか、あらかじめ夫の本性をはかれなかったか、といった雑念が意識にのぼった。彼女は両親の薦めになんの抵抗もなく結婚した。今日までなんの苦労もなく好意により、快適なゆりかごに揺られて幸せな八年が過ごした。夫の子供をもうけ、夫婦の交歓の時間も多くあった。だが、これから彼がどんな態度に出てくるかをあらためて問うてみた。彼女にとって彼がなんと遠く未知の存在であるかを痛感した。過ぎ去った歳月をサーチライトが妖しく探索するように、彼女は熱い想念をめぐらした。夫の正体がつかめない。頑固なのか、優柔なのか、厳しいのか、優しいのか、彼女はいまなお分からないのだ。折悪しく、深刻な生活不安に鼓舞された罪悪を彼女は認めざるをえない。ただ、夫の人格の表面の社交面を知りながら、他方であの悲劇的な法廷で判決を下す夫の精神面を見ぬけなかった。彼女は無意識のうちに繊細な顔色や表情をうかがった。同様の疑念に夫がどんな対話で判断するかを推察した。非常に驚いたことに、夫は個人的な意見を一切話さないことを知った。もちろん、彼女の方も心中の想いを夫に訴えることもない。あらためて、彼女は夫の性格を明示できる個々の特性に分析し、夫の本性を推測してみた。彼女は恐る恐るハンマーで小さな記憶をトントンたたき、彼の心の秘密の部屋の入口をさぐった。
イレーネ夫人はかすかな音にも耳をそばだて、夫の帰宅をしきりに待った。夫は妻の顔を見るのもそこそこに手にキスをし、髪をなでるのが彼の挨拶である。そんな行為に彼女が恥ずかしく女々しく拒んでも、夫は心から深い愛撫を示し、彼女への衷心な愛情を見せた。彼女に話しかけるとき、けっして苛立ちもせず興奮もせず、落ちついていた。彼の態度には鷹揚で好意的である。彼女の気持ちがどんなに動揺しても、変わらない好意を示した。それはいつも活発で、時には明るく、時には悲しい態度を見せる子供たちに対する好意と変わらない。今日もまた彼は相変わらず家庭状況をたずねてきた。彼の関心事はさておき、彼女には関心事を人前で述べる機会が与えられた。よくよく考えてみると、夫が彼女を非常に大事にした。謙虚な態度で日常の談話に適応していた。あたり障りのない雑談もすぐに理解し容易に適応した。夫の言葉になんの含みもないものの、彼女の安堵したい心は満たされないままである。
言葉が夫の胸の内を明かすわけではない。夫はひじ掛け椅子に座り、電灯の明かりのもとにいかめしい顔で本を読みふけっている。彼の顔に彼女は問いつめた。そこに、まるで他人の相貌を彼女は発見した。日ごろ見慣れているものの、にわかに他人になった顔つきから、八年間の夫婦生活で知り得なかった彼の性格を読み取ろうとした。額はつややかで品があり、芯が強く精神的な努力によって磨かれた顔に、口もとはきりっとして譲歩がない。どこから見ても精かんな顔つきは引きしまって、非常にエネルギッシュで力強い。驚いたことに、彼女はそこに美しさを発見していた。たしかに、彼の謙虚で真面目な、毅然とした態度と厳格な人間性に彼女は敬服した。そんなことは、彼女の単純な考え方からすればなにも楽しくなかった。だから団欒(だんらん)がなごむわけがない。ところで、両眼はほんとうの秘密を隠したまま、本に注がれていて、妻の顔色など見る余裕はない。一方で、彼女はもの問いたげにその横顔をじっと見つめた。冷ややかな顔の厳しさに彼女はビクッと肩をすくめた。その厳しさの中に秀でた美しさがあらためて認識された。神託が告げる唯一の言葉を、すなわち無罪か有罪かを夫が宣告するのだ。気づいてみると、夫を微笑ましく誇らしく見つめていた。こうした意識に目覚めても、なんとなく苦しく重い感情が胸にひっかかった。自分の至らなさには申し訳ないと思うが、彼女は夫の肉体から性的興奮を一度も感じたことはない。そのとき、夫は本から目をあげた。彼女はあわてて暗い闇に身を引いた。彼女が熱い視線で問いかけたりすれば、夫の疑念に火をつけかねない。
まる三日間ずっとイレーネ夫人は家にこもっていた。珍しく家におとなしく引きこもるものだから、それがほかの者たちの目にとまり、彼女はつらかった。そもそも、彼女が長い時間、あるいは数日間も家にこもるなんてなかったから、不審に思われるのも当然である。彼女は決して家庭的とはいえないが、経済的な心配はほとんどなく、家計的に自立し暮らしはゆたかである。住いは仮の宿でしかない。街や劇場はいろいろな人たちと出会う社交の場である。絶えず世間の変化の流れにのった、最も愛すべき休息の場である。なぜなら、たのしみに心の緊張はいらないし、眠気がさしても、五感が刺激に著しく反応するからである。彼女は自分の考えでウィーンの優雅なブルジョア層の社交界に所属していた。機密協約の趣旨は、会の完全な規則にのっとり、仲間の全会員がたがいに日ごろ同じ時間に同じ趣味で出会い、常に平等を遵守し、女性の存在の意識向上に努めるものとした。だれもみないざ自律し孤独になると、自然な共同体になれた生活はその支え失う。たくわえの食糧がなくては、ささいとはいえ重大なセンセーションを巻き起こす意図を失うものだ。孤独はたちまちいじけた自己嫌悪におちいる。たえず彼女は時の呵責を痛感した。日常の規則がなければ時間もその意図を失う。地下牢の壁の間に立たされたように、彼女は自室の中をいたずらに悶々と徘徊した。彼女の実生活と共存する街も世界も遮断された。そこには焔に燃える剣をもった閻魔(えんま)王が立ち、かたや女サギ師がいかめしい顔で立っていた。
母親の変わり様に最初に気づいたのは子供たちだった。なかでも長男は、母親が始終家にいるので、素朴に不審な気持ちをいだいた。痛ましいほど同情の念を見せた。一方で、使用人たちはささやきあい、家庭教師の女とうわさ話に興じた。空しい努力とはいえ、ある面で成功だったが、夫人はいろいろ念入りな御託を並べて不審な引きこもりをかこつけた。しかし、どんなにうまく説明しても、長い間疎んじてきた生活空間に自分がなんと不要な存在になっているかを痛感した。母が家事にかかろうとすると、唐突な行動が適切な生活習慣を侵害し拒否され、家族の感情を損ねた。母は四面楚歌(しめんそか)に立たされた。慣習を破ったことから、母は自分の家という組織体の門外漢になった。それゆえ、母は身の処し方もタイミングも分からない。とりわけ、子供たちが急に騒ぐような問題に母親が新たに規律を敷こうとすると、かえって子供たちに疑われ、しつけに母は大変てこずった。子供の行動にいちいち口をはさむと、お母さんはどうして外出しなくなったのかと、七歳の長男が生意気にたずねてきた。そのとき、自分でも恥ずかしく赤面した。母が手をかそうとする先々で、秩序を乱し、同情をよせれば、疑いの目で見られた。とにかく、本を読むにしても家事をするにしても、自分の現実の立場に目を閉じて、おとなしく部屋に引きこもっていられる器量はない。強情な性格がもとで神経症を併発した。たえず彼女は心の不安を部屋部屋へ追いちらした。電話が鳴り玄関のベルが鳴るたびに、彼女はビクッと身をすくめた。ときおり彼女はカーテンの陰から往来の様子を眺めた。ああ、人がこいしい、せめて人の光景でもいい、自由がほしい。だが、恐怖はしのびよってきた。路ゆく人々の顔々の中から突如一つの顔だけがヌウッと浮かびあがったのだ。それは夢の中まで追ってきた顔だ。夫人の静かな生活はまたたく間に崩壊し破滅するのを意識した。すると、完全に崩壊したはずの生命が無力から息をふきかえしたのだ。彼女にとって牢獄のような部屋で暮らしたこの三日間は、夫婦生活の八年間よりも長く感じた。
おりしも、その三日目の晩に舞踏会があった。イレーネ夫人は数週間前から夫に同伴するよう招待を受けていた。いまさら正当な理由もなく急に招待を断るわけにはいかない。そのうえ、彼女の生活を取り囲む目に見えない恐怖の檻(おり)は、自分で壊さなくても、いずれ破壊されるにちがいない。彼女には味方が必要だった。自殺の恐怖の寂しさから、ついつい自分ひとりだけのひと時に安らぎを求めていた。それならば、友人の家にいるのが最も安全である。しのびよる影の追跡に対して友人以上に安心なところはない。彼女が恐怖を感じたのは家から出た瞬間だった。あの遭遇以来はじめて、どこかにあの女が待ち伏せているかもしれないと思いながら、往来に出たときだった。思わず夫人は夫の腕にすがりついた。目を閉じたまま、舗道(ほどう)に停まっているタクシーまでおろおろと歩いた。夫のわきに支えられていた。車が閑散とした夕方の街路を疾走した。しだいに心の鬱積がからだからスウーッとぬけた。身の安全を意識しながら夫人はホールの階段を昇った。今のわずかな数時間が過去の歳月と同じように長く感じられた。牢壁から出て日の目を見る者のようにすがすがしく軽快な歓喜の昻揚を感じた。ホールはあらゆる追跡から防壁で守られている。怨念はここまで入れないだろう。ホールには夫人を愛し尊敬する人たちがいる。身を着飾り、とくに目的もない人たちがなまめかしい焔に赤々と照らし出された。享楽の輪舞は再び限りなく夫人を巻きこんでいった。夫人は輪舞の中へ入るやいなや、いっせいに他の人たちの視線を浴びた。彼女は美しい。それを意識すると、気分が増長した。想念の鋭利な鋤(すき)が頭を無情に穿(うが)たれた。からだ中がうずき痛んだ。だが、沈黙の日々の後はこのうえなく気持ちがいい。言葉はまるで感電したように肌の奥までひびき、血潮をあおりたてたのである。そんななまめかしい言葉を聞けるのもこのうえなく幸せだ。夫人はその場に立ちすくんだ。なんとなく不安な感情が胸につまり、それを吐き出そうとした。突如、閉ざされた笑いが一気に爆発した。シャンペンがボトルからパーンパーンという音とともに噴出した。その音ははなやかな装飾音の旋律をかなでた。夫人は腹の底から笑った。ほろ酔い機嫌に恥じらいながら、思わず彼女はカラカラと笑った。神経がゆるんで、からだがビリビリっとした。五感はしっかりして快く興奮した。彼女は久しぶりに食欲を取り戻し、旺盛に飲み食いした。
枯渇した心はむしょうに人を恋しがった。彼女はなによりも生と享楽をむさぼった。音楽は彼女の心を誘って、燃える肌の奥深くにしみこんでいった。円舞が始まった。知らぬまに、彼女は渦の中に巻きこまれていった。彼女は生まれてこの方かつてないほど踊り舞った。回転し旋回しながら、鬱積(うっせき)を思い切り吹きとばした。リズムは全身に増幅して、燃えるような動きに生気が肉体によみがえった。音楽がやんだ。彼女にとって静寂がつらい。蛇の火焔は彼女のおびえる肢体にめらめらと燃えあがった。からだを冷やし沈める水を浴びるように、彼女は再び渦巻く中に身を投じた。ふだん彼女はとてもおとなしいダンサーだった。今日は非常に用心深く控えめで、ステップはぎこちなく慎重だ。しかし、奔放な歓喜に酔って、五体は抑えがきかない。彼女の野性的な情熱を一つの鋳型(いがた)につなぎとめていた恥辱と自制の鉄のタガが、いま真っ二つに切断された。自分が節操もなく、とめどもなく、うつつに溶けていくのを彼女は感じた。身のまわりに手や腕を感じた。それは触れてはまた消えた。言葉の息吹やくすぐるような声がささやかれた。音楽に血潮が燃えた。全身は緊張し、緊張のあまりドレスが地肌に燃えつくと、無意識に彼女は身を覆うすべてをかなぐり捨てた。酔いは裸体の奥深くへしみこんでいった。
「イレーネ、どうされました?」と、パートナーは訊いた。彼女はよろめきに笑みを浮かべ、パートナーの抱擁に熱い視線を向けた。そのとき、いぶかしげに凝視する夫の視線が冷酷に彼女の胸に突き刺さった。彼女はぎくっとした。私、気でも狂ったのかしら? 乱舞をみて、なにかあばかれたのかしら?
「なにをおっしゃるの、フリッツ?」と、彼女は口ごもった。夫の視線のとっさの一撃にたじろいだ。それはからだ中に奥深く食いこむようだ。胸は完全にとどめを刺された。うがつような厳しい目に夫人はいまにも悲鳴をあげるところだった。
「こんなはずではなかった」と、やっと夫はつぶやいた。内心あきれていた。夫がなにを言おうとしているのか、彼女はたずねる気がしない。彼はおもむろに顔をそむけた。そのとき、鋼(はがね)のようにたくましいうなじから広く頑強で大きな肩に流れる稜線を彼女は見た。全身に戦慄が走った。まるで殺人者と共存しているような感じがして、彼女はおそろしく混乱しおびえていた。だが、すかさずそれを一蹴した。いまさらながら、自分の夫なのに、初対面のように頑固でこわいという恐怖感をいだいた。
ふたたび音楽がはじまった。一人の紳士が彼女に歩みよってきた。彼女はすぐさま男の腕をとった。だが、にわかになにもかもが怠惰に思えてきた。明るいメロディにも彼女の肢体が硬直して動かない。鬱々とした重圧が頭の先から足の先までひろがって、一歩一歩が苦痛だった。そして、彼女はやむなくパートナーに遠慮したいと訴えた。身を引きながら、ふと夫が身近にいないかどうかと周囲を見まわした。そのとき、彼女は震えあがった。待ちぶせていたかのように、背後に夫が立っていたのだ。彼の視線がきらりと光り、彼女の視線に突きあたった。「この人はなにを考えているのかしら? すでになにか秘密を知っているのかしら?」と思いながら、夫の前であらわになった胸を隠そうと、思わず彼女は襟をかきよせた。夫の沈黙は眼光と同様かたくなだった。
「出ましょうか?」と、彼女は不安げに訊いた。
「ああ」と、夫の声はかたく無愛想にひびいた。彼が先に立った。ふたたび彼女はあの幅広い威圧的なうなじを見た。彼の手をかりて毛皮のコートを着たが、からだが震えた。黙ったまま二人は肩を並べて外にでると車を走らせた。彼女は話そうとしない。彼女は暗に新たな危険を感じていた。とうとう彼女は四方から包囲されていた。
その晩、イレーネ夫人は夢にうなされた。なんとなく異様な音楽が騒然と流れていた。ホールは明るく天井は高い。夫人はホールへ入った。多勢の人たちとカラフルな色彩は夫人の動きをはやしたてた。そこに、一人の青年が夫人に歩みよった。青年に見覚えがあるようだが、はっきりと思い出せない。パートナーは彼女の腕を取り、ペアは踊りはじめた。彼女は気持ちよくうちとけていった。おしよせる音楽の波に、足が地につかずからだが浮遊した。こうして夫人はいくつものホールを踊りわたった。ホールの天井には金の燭台が星のように燦々(さんさん)ときらめき、小さな焔を灯(‚Æ‚à)していた。壁面ごとに連なった鏡が自分の微笑を投げかけてきた。さらに彼女はめぐりめぐる鏡の中へ引き込まれていった。舞踏は次第に熱気をおび、音楽は次第に燃えあがった。青年はからだをぴたりと密着してきた。手を彼女の肌身の腕の中へ入れるのを彼女は感じた。胸にせまる悦びのあまり、呻き声をあげそうだった。そして、夫人の視線が彼の目に沈んだとき、彼を知己の人に思えた。青年は自分がかつて少女時代にすっかり夢中になって思いをよせた俳優のように映った。エクシタシーに酔う夫人はすんでのところで俳優の名を口に出そうとした。だが、青年はその静かな叫びを燃えるような接吻で封じた。たがいに唇が溶け合い、肉体はもつれあって燃えた。二人は恍惚の風に乗るようにホールを次から次へ舞った。壁がめくるように流れた。名状しがたいほど軽快に、肢体を締める鎖が切れた。ドレスがひるがえるのも時のたつのも忘れて夫人は舞った。
そのとき、そっと、誰かが夫人の肩に触れた。はたと夫人は足を止めた。同時に音楽もやみ照明も消えた。暗闇に四方の壁が迫ってきた。すると、パートナーの姿も消えていた。「あんた、泥棒じゃない、あたしの男を盗(と)るなんて!」と、気味の悪い女が叫んだ。かん高い声が壁面に響きわたる。すると、氷のように冷たい指が夫人の手首をぎゅっとつかんだ。夫人は立ちすくみ、驚愕のあまり、おのずと錯乱した金きり声をあげていた。たちまち、二人は取っ組み合いになったが、女の力が勝った。夫人の真珠のネックレスは引きちぎられ、ドレスはずたずたに引き裂かれた。千切れた服から胸も腕もあらわになった。たちまち人だかりができた。あちこちのホールから野次馬の悪口雑言が飛びかった。彼らは半裸の夫人を嘲けるように凝視した。女は「あいつ、あたしの男を盗んだのよ、盗人(ぬすっと)よ!」と金きり声で叫んだ。夫人は身の置き所も、目のやり場もない。人々は後から後から裸身に迫ってきた。物見高い野次馬どもは鼻をならし、夫人の裸体に手をのばしてきた。すると、夫人のうろたえた視線は助けを求めて逃げまどった。そのとき、突然暗いドアのかまちで、右手を背後に隠して夫が不動に立っているではないか。夫人は絶叫し夫から逃れていった。ホールを次々に走りぬけた。背後に野次馬が群がった。ドレスはおさえきれず、だんだんずれ落ちていった。そのとき、夫人の前に扉がスウッと開いた。救われたい一心に、夫人は夢中で階段を転がり降りた。だが、階下にはすでにウールのコートを着たあの卑しい女が鷹の爪の諸手を差し出し待ち伏せていた。夫人は脇にとびのくと、狂ったように外へ駆けだした。すると、相手の女は背後から突進してきた。こうして、二人は闇をついて長い静寂の大通りを疾走した。ランタンは歯をむき出し、二人を嘲けるようにその頭をたれていた。背後にたえずあの女の木靴がカタコトと音を立てて跡を追ってきた。街角に立つたびに、あの女がまた飛び出し、次の街角からまたも飛び出てきた。行く先々の建物の陰に、右にも左にも女は待ち伏せた。逃れる先々に女が現れた。恐ろしいほど人が増えて、追い越すことができない。たえず女は飛び出してきた。夫人はへとへとになってもう膝がきかない。夫人はつかまりそうになった。やっと、夫人は家にたどりつくと、床にドーッと倒れた。だが、ドアを開けたとたん、そこに夫がナイフを手にもって立ちはだかった。夫は射ぬくような眼差しで夫人をにらんだ。「どこに行ったんだ?」と、彼はじんわり訊いた。「どこへも」と、夫人が応じたのと同時に、わきからゲラゲラ笑う声がきこえた。「あたし、見てたわよ、あたし、みんな知ってるわ」と、いきなりわきに女がヌーット浮かびでたのだ。女は気ちがいのように笑いながら歯をむき出して叫んだ。そのとき、夫がナイフを振りかざした。「助けて!」と夫人は絶叫した。「助けて!」・・・・。
イレーネ夫人は見あげた。彼女の怯えた視線が夫の視線につきあたった。どうして‥‥どうしたこと! 私が自分の部屋にいるなんて。ランプが蒼白く燃えていた。気づいてみると、夫人は自宅のベッドにいた。しかし、どうして夫が私のベッドの縁に腰掛けて、私を病人のように見守っているのだろうか? 誰がランプをつけたのだろうか? なぜ夫はそんな深刻にじっとそばに居るのだろうか? 恐ろしくなって全身がガクガク震えた。思わず夫人は夫の手に視線をやった。あっ、手にナイフがない!目覚め後の朦朧状態と夢の中の心象が遠い稲妻のようにひらめくと、ゆっくりひいていった。彼女は夢を見ていたにちがいない。うなされて叫び夫を起こしたにちがいない。しかし、なぜ彼はそんな深刻にそんな冷たい目で私を見つめるのだろうか?
イレーネ夫人は苦笑した。「どうして‥‥いったいどうして? あなたはどうしてそんな目で私を見るの? 私、きっと悪い夢でも見たのね」
「たしかに。大きな悲鳴をあげていた。向こうの部屋まできこえたのだ」
私はどんなことを言ったのかしら。どんな秘密を洩らしたのかしら? なにか彼に知られたのかしら?‥‥そう思うと、からだが震えた。彼が見つめている間、彼女はどうしても立ちあがれない。だが、夫は妙に落ちついて彼女をじっと見おろした。
「どうした? イレーネ。おまえの中でなにが起こっている? ここ数日で、おまえはずいぶん変わった。熱におかされて、いらだち気持が乱れたのだろう。夢の中で助けを求めて悲鳴をあげたんだね?」
ふたたび、イレーネ夫人は苦笑した。「いいや」と夫ははばんだ。「ぼくにはどんなこともかくさないでくれ。なにか心配な事があるのか、なにか悩み事でもあるのか? 家のものたちはみんなおまえの変り様に心配している。ねえ、ぼくを信頼するんだ、イレーネ」
夫はそっと彼女ににじりよった。夫の指がはだけた腕を撫でまわすのを彼女は感じた。夫の目が異様に光った。彼女は葛藤していた。一層のこと、夫のたくましい肉体にわが身を投げだし、しがみついてすべてを告白し、彼のなすがままになればいい。彼は苦しむ妻を見て、ただちに赦してくれると彼女は思った。しかし、いまさらといった思いだった。
しかし、灯火の焔が彼女の蒼い顔をくっきり映しだした。彼女は恥ずかしかった。自分の
言葉がこわかった。
「心配なさらないで、フリッツ」と、彼女は苦笑したが、からだは足のつま先まで震えていた。「私、ちょっとノイローゼ気味なの。すぐなおるでしょう」
夫はそれまで肩においてい手をすばやくひいた。額に透明な光が蒼白く映えて、暗い想念に苦脳の影がただよっていた。それを見て、彼女は愕然とした。おもむろに彼は身をおこした。
「よく分からないが、このごろ、おまえはぼくに話したいことがあるようだが。なにか、おまえとぼくの間に関わることでも? ここにはぼくたち二人だけしかいない、イレーネ」
イレーネは横になったまま動かない。夫の真剣な渋い視線に催眠術がかけられたようだ。いまならすべてのことがうまく運ぶかもしれないと夫人は思った。短いひとこと「お赦しください」と言えばいい。そうすれば、夫は謝罪の理由など問うまい。だが、なぜ灯火は燃えるのだ?焔(ほのお)がえんえんと大胆にしかもきき耳を立てて燃えた。 闇の中でなら、謝罪を告げることができるであろうと、彼女は思う。だが、灯火は彼女の気勢を打ち砕いた。
「じゃあ、ほんとになにもないんだね、ぼくに話すことはまったくないんだね?」
言葉の誘惑がなんと恐ろしいことか、夫の声はなんとやさしいことか! 夫がそんな風に話すのを彼女はきいたことがない。だが、あの焔は‥‥灯火は‥‥あの黄色い貪欲な焔は!
彼女はくるりと背を向けた。「なにか気にかかることでも」と、彼女は笑いながら、自分の声の変わりぶりに驚いた。「私が眠れないからといって、秘密があるとでもおっしゃるの? つまり、不倫ということを?」
その言葉が不実に侮辱的にひびいて、彼女は身震いした。それは骨身にしみた。彼女は思わず目をそらした。
「じゃあ、おやすみ」さらりと夫は言ったが、突き刺すようにきこえた。すっかり変わった声は、まるで脅迫するようにも意地悪くこわい嘲笑にもきこえた。
すると、夫は灯火を消した。夫の白い後姿が音もなく、灰色に、まるで夜半の幽霊のように、戸口に消えていく姿を彼女は追った。ドアがパタンといったとき、棺が閉まるような気がした。世界がすっかり死の廃墟(はいきょ)に映った。硬直したからだの中で、心臓がトントンと荒々しく胸を打った。鼓動をうつたびに心が痛んだ。
あくる日、夫人は家族と一緒に昼食をとっていたとき、さっそく子供たちの喧嘩が始まった。喧嘩をしずめるのに骨がおれた。そのとき、メイドが一通の手紙を持ってきた。「奥様、いま返事を待っています」と言った。驚いて夫人は見慣れぬ筆跡を眺めた。あわてて封を切った。最初の一行を読んだとたん真っ青になった。彼女は愕(がく)然とし飛びあがった。ほかの者たちから一斉に不審な視線を浴びた。うかつにも秘密を洩らしそうになった。そんな軽率な考えに自分でもあきれていた。
手紙は短かった。「どうか、この手紙を届けた者にキャッシュの百クローネをお渡し下さい」と三行で書かれていた。サインも日付もない。明らかに偽った筆致で、不気味で脅迫的な命令調だ!イレーネ夫人は金を取りに自分の部屋に駆け込んだ。だが、金庫の鍵のおき置き場所を忘れたので、引き出しをかたっぱしから開けてはかき回し、やっと鍵を見つけた。震える手で紙幣を折って封筒の中に入れた。彼女みずから戸口へ走り、待っている遣いの女に渡した。夫人は催眠術にかけられたように、なにも考えずすべてを始末した。躊躇する余裕もない。彼女は席を立ってから二分もたたないうちにキッチンに戻った。
みんなシーンとなった。彼女は気まずそうにおろおろとテーブルについた。あわててその場しのぎの口実を詮索した。手が激しく震えるので、いったん取り上げたグラスをあわててテーブルにおいた。恐ろしいことに、興奮の衝撃のあまり目がくらみ、彼女は手紙を開封して自分の皿の横においたまま席をたった。ちょっと手をのばせば、夫は手紙を自分の手元に引き寄せることもできたであろう。一目見ただけでも大きな字にたどたどしく書かれた数行を十分読むこともできたであろう。彼女に言葉はもう用を足さない。人目を盗んでその紙片を握りつぶし懐にしまい込もうとした。ふと、彼女は顔をあげた。そのとき、いままで見たこともない夫の厳しい視線にぶつかった。射ぬくような鋭く厳しい視線だった。ちかごろ、夫はしげく疑いの視線を彼女になげかけた。衝撃のあまり彼女は心の底まで震えるのを感じた。もう身をかわすすべがない。舞踏会のときも、厳しい視線で夫は彼女のしっぽをつかもうとした。その鋭い眼光は、昨晩、寝ている彼女に突きつけられたナイフのように閃めいた。
夫をキリキリ、カリカリ、イライラさせ、苦しめるものは知識なのか、それとも知識欲なのか? なお、彼女は言葉を模索するうちに、すっかり忘れた記憶が脳裏に浮かんだ。それは以前、夫が弁護士としてある予審判事と対決した時の話だ。判事には奥の手があった。判事は審問中にいわゆる近視眼で書類を詳細に調べてみせた。やがて実際に決定的な尋問を行う段になった。判事の稲妻のような眼光に被告人がたじたじとなった。その隙を見て、判事は匕首(あいくち)のように鋭い眼光を突きさしてきた。注意力を集中させた判事の険しい眼光につきあたって、被告人は落ちつきを失い、慎重に抑えてきたアリバイが無惨にも崩されるというのである。今回も、夫はみずから非常に危険な策略をねった。彼女はその犠牲になっているのではあるまいか? 彼の厳しい心理的追求の情熱は、弁護士としても司法の要請の範疇をはるかに超えていた。それを知っているだけに彼女はいっそう恐ろしかった。別の賭博(とばく)や色沙汰についても、犯意を観察し、嗅ぎつけ、恫喝(どうかつ)する手法を彼はうまく利用した。そうした心理的な捜査や追跡の日々に、彼は心底から情熱を燃やした。夜中でも燃えるようないらだちに、彼はしばしば起きあがり、仕舞ってある判決文を探しだして、被告に対し不屈な洞察力を働かすのである。夫はつとめて飲食を節制し、つねに葉巻を口にし、出廷前の時間まで言葉をひかえた。かつて夫が法廷で弁護するところを彼女は見たことがある。あれ以来二度と見ていない。それだけに夫の弁明の不思議な情熱や敵意をあらわにした激昻や、さらに夫の顔に現れた陰鬱で辛らつな表情を見て彼女は驚愕した。思いがけなく、威圧的に眉根をよせて凝視する形相を彼女は再発見した。
失われた記憶のすべてが一気に頭の中に混乱し、思いは喉もとまで出かかって言葉にならない。彼女は黙った。だが、沈黙がいかに恐ろしいかを感じた。そして納得のいく弁明能力がなんと著しく欠けているかを意識すればするほど、彼女は混乱した。彼女はあえて目をあげない。ふだん、夫の手は非常に静かに落ちついた動きをするが、今日は野生の小動物の手のようにテーブル上をせわしく動いた。動くたびに、彼女は目を伏せがちにおどおどした。何事もなくようやく昼食は終わった。子供たちは席を立つやいなや、元気に賑やかな声で隣の部屋へ駆け込んでいった。女家庭教師がはしゃぐ子供たちをしずめようとするが無駄だった。夫も席を立ち、顔をしかめ足早に自室へ行った。
ようやくひとりになった夫人はあの不吉な手紙をふたたび取り出し、あらためて数行に目を通した。「どうか、この手紙の遣いの女に現金百クローネを渡して下さい」。すると、憤怒のあまりそれをビリビリに引きさいた。残片を丸めて、紙くず箱へ捨てようとした。だが、ためらいがちに身を暖炉にかがめて、焔々と燃える暖炉の中へ紙くずを投げ入れた。あわい焔が脅迫状を貪るようにメラメラ燃えた。彼女の心は落ち着いた。
すると、彼女はドアのところに夫の戻ってくる足音をきいた。彼女は焔のほてりと不意の奇襲に顔を赤らめ、すばやく立ちあがった。暖炉の口はなお裏切るように開いたままだ。彼女はぎこちなくからだでその口をふさごうとした。夫はテーブルに着いて、葉巻を喫おうとマッチをつけた。その焔が彼の顔に近づいたとき、彼の小鼻のあたりがヒクヒク震えた。彼の場合きまってそれは怒りの表情であった。静かに彼は振り返った。「ちょっと言いたいことがある。 おまえにきた手紙だから、ぼくに見せる義務はない。ぼくに対して秘密を隠したいなら、それは一向かまわない」。彼女は黙ったまま、相手を見ようともしない。少し間をおいてから、彼は胸の奥底からしぼりだすように強い吐息で葉巻の煙を吐き出すと、重い足どりで部屋を出た。
イレーネ夫人はもう何も考えたくない。ひたすら生きたいのだ。耳をふさぎ、空しい無意味な雑事に気を紛らわした。家にこもるなんて、もう堪えられない。恐怖のあまり気が狂わないために家を出て街を歩いた。人波に紛れ込むのがいいと彼女は思った。百クローネを払って、せめてあの女サギ師からわずか数日間だけでも自由を買い取りたいと願った。あれこれ配慮した。とりわけ、家にいれば不審で異様な挙動を隠すことになるだけに、あえて外出した。まるで飛び板から身を投ずるように、彼女は玄関から一目散に街の人波へまぎれこんだ。足下の舗装はかたいが、人波の中はあたたかい。彼女はいらいらとせわしくあるいた。ごく平凡な女をよそおって、人目につかないように黙々と先を急いだ。眼をじっと路面にすえながらも、あの恐ろしい眼にふたたび逢うかもしれないという、測り知れない恐怖に憑かれた。待ち伏せをくらうなんて、まったく考えられない。余分なことはなにも考えまいと彼女は思った。そのとき、ふと誰かが彼女のからだに触れた。彼女はびくっとした。どんな音にも、追ってくるどんな足音にも、通り過ぎるどんな人影にも神経がピリピリした。タクシーの中や他人の家にいるときだけ、彼女は心からほっと息をついた。
紳士がイレーネに会釈した。彼女は顔をあげた。むかしから家族ぐるみで付き合っている隣人だった。愛想のよい話し好きな白髪の老人である。ちょっとした痛みや、恐らく想像上の、身体的苦痛を長々と訴えた。相手の迷惑など一向に考えない。それゆえ、いつも彼女は敬遠してきた。相手の会釈に快く応じたものの、同行しなかったことに彼女は恐縮する思いだった。とはいえ、知人が側にいれば、あの女サギ師から不用意に話しかけられたときにガードになった。彼女はためらいがちに後ずさりした。そのとき、誰かが後から足速にかけよってきた。戸惑うことなく彼女は本能的に走りだした。しかし、不安から神経がピリピリしていた。背後から追いかけられるような予感がした。彼女はその追跡から到底逃れられないと知りながら、ますます速足になった。足音がますます接近するのを感じた。次の瞬間、女の手が肩に触れたように感じた。彼女は恐怖に震えた。そして、足を速めれば速めるほど、膝は重く動かない。背後にぴたりとつきまとう追跡者を彼女は意識した。すると、「イレーネ!」とあらい太い声が、背後から呼びとめた。彼女はふと思いとどまった。その声は少なくとも彼女を脅迫する不吉な恐ろしい女サギ師ではない。ほっと一息ついて、彼女は振りかえった。彼女が急に止まったので、あやうくぶつかりそうになったのは元の恋人だった。彼の顔は蒼ざめ、興奮の姿は心の混乱だった。彼女の怒りの眼差しに突きあたると彼は恐縮した様子を見せた。恐る恐る彼は挨拶の握手を求めた。だが、彼女がそれに応じなかったので、彼は手をひいた。しばし、彼女はじっと彼を見つめた。こんな処で彼と会うなんて思いもよらないことだ。このところ不安な日々が続いたせいか、彼女は恋人のことなどすっかり忘れていた。だが、彼の蒼白い顔はもの問いたげに、いつもの頼りない感情がひとみにただよい、途方にくれた虚ろな表情をしていた。そのとき、突然、憤りが熱い血潮となって体中を走った。彼女の唇(くちびる)が一つの言葉を模索して震えた。彼女の興奮の形相があまりにもあらわだったので、彼は驚いて、しどろもどろに彼女の機嫌をうかがった。「イレーネ、お元気ですか?」と。すると彼女のあわてた挙動を見て、じっと控えめに言いそえた。「ぼくがいったいなにをしたんですか?」
彼女は抑えきれない憤りをあらわに凝視した。「あなたが私にしたことって」と彼女はカラカラと笑った。「なんでもないわ! 全然なんでもありませんわ! 幸せだったわ! 楽しかったわ!」
彼の眼がうつろで、驚きのあまり、口はポカンと半開きのままだ。その様相に彼の愚直さと滑稽さが顕著に現れていた。「でもね、イレーネ、イレーネ!」
「みっともないわ」と、彼女は静かに彼を制した。「そんなお芝居もうやめて。きっとまた女サギ師が近くで見張っているわ。あなたの素敵な女が。そのうち、また私をおそってくるわ‥‥」
「誰が?‥‥いったい誰のことですか?」
男の甘ったれた泣き面をひっぱたいてやりたかった。彼女の手は傘をつかみかけていた。これまで彼女は人を軽蔑し憎んだことはなかった。
「でもね、イレーネ」と、彼はうろたえて口ごもった。「ぼくがいったいあなたになにをしたというんですか?‥‥あなたが急に来なくなって‥‥ぼくは昼も夜もあなだを待っていた‥‥今朝だってずっとあなたの家の前に立っていた。少しでも話ができないかと思って」
「待っていらしたのね‥‥そう‥‥あなたも」と、怒るのがばかばかしく思えてきた。男の顔をひっぱたいたらなんと気持ちがいいだろう! だが、彼女は自制した。もう一度あつい怒りに燃えて彼をにらみつけた。それでも、屈辱(くつじょく)とともにうっせきした怒りを彼の顔にたたきつけてやりたかった。すると、彼女はツンと背をむけると、振り返りもせず人波にのまれていった。彼は懇願するように手を差しのべ、その場に悄然(しょうぜん)と立ちすくんだ。たちまち彼も街の雑踏にのみこまれていった。すると、奔流に沈んでゆく木の葉のように、彼はくるくると旋回しながら、無抵抗のまま押し流されていった。
あんな男がもと恋人だったなんて、いまさらながら空しくばかばかしく思えてきた。恋人の眼の色も相貌も思いださない。まして男の愛撫なんてもううんざりだ。悩ましく女々しい鼻声で、「でもね、イレーネ!」と、しどろもどろに彼は言う。その絶望的な声が彼女の耳についた。彼がすべての禍(わざわい)の根源であるだけに、忙しい日常に彼のことなど考えたくない。もう夢にも見ない。彼女の人生にとって彼はなんの意味もなかった。魅力も感じないし想い出もない。あのとき、自分の唇が彼の唇を感じたなんていま考えられない。あんな男のいうことはいっさいきかないと彼女は心に誓った。なぜあんな男の胸に抱かれたのか?魔がさしてアバンチュールに走ったのだろうか? いま自分でも信じられない。なんと愚かな女か? そこから得たものは何もない。それどころか、事件はすっかり紛糾し、彼女はその渦中に立たされていた。
ところで、イレーネ夫人にとってこの六日間ほど事態が目まぐるしく展開したことはない。すさまじい一週間だった。硝酸(しょうさん)のように、胸を痛めた不安に彼女の生活を破壊され、ばらばらになった。事態が一挙に急変した。すべての価値が逆転し、係わり合いが錯綜した。彼女は重い気持ちでそっとまぶたを閉じた。今までの生き方をたどってみた。にわかに、恐ろしいほど美しい光明が心中にともった。彼女がこれまでに感動したことのない事態が眼の前にかがやかしく展開した。自分の真実の人生が黙示されるものと、ふと彼女は予感した。すると、つぎに重要に見えた事態がふたたび煙のように消えていった。今日まで、彼女は活動的な仲間や富裕層のおおらかな話し好き仲間とたのしんできた。もとより、それは彼女の姿なのだ。しかし、この一週間、彼女は家という牢獄にこもったが、仲間がいなくても不満は感じなかった。むしろ、ひま人の空しい生活にはうんざりした。はからずも、彼女の強い意思でこれまでの愛情不足を認識し、同時にふだんの愛情で数々の怠慢を反省していた。
過去が地獄に映った。八年間の結婚生活が過ぎた。非常につつましやかな幸せに恵まれながらも、彼女はどうしても夫になじめなかった。子供たちならまだしも、彼の真の人間性がつかめない。自分と家族の間を取りもつ人たちがいた。家庭教師と使用人たちは彼女をわずらわす心配事を軽減してくれた。彼らは子供たちの生活にやさしく世話をやいた。男たちの熱い視線より子供たちがいとおしく、抱擁以上に幸せを彼女は感じていた。次第に、彼女の生活は新しい意識で改善され、家族はみんなの絆でかたく結ばれていた。たちまち彼女に真剣で緊張した顔がよみがえった。彼女が危険を知り、危険をともなう真意を認識してから、にわかに様々な事態と未知なことが明らかにされた。あれこれ彼女は想いめぐらした。かつて、ガラスばりの透明な世界がにわかに彼女自身の影の暗い面を映しだした。彼女の目のとどく先々と耳にきこえる先々がたちまちリアルに映った。
イレーネ夫人は子供たちの間に座った。娘がみんなの前で王女にかんするメルヘンを読んでいた。『王女は宮殿内の全室を監視する役目を負わされていた。ただし、一部屋だけ銀の鍵が掛けられていた。ところが、王女はその部屋を開けてしまった。それが王女の命取りになった』というあらすじである。禁じられた事に誘われ、奈落に落ちるのも人間の運命でしかないのであろうか? ひとむかし前だったら、こんなメルヘンは短絡的な事件として一笑にふされたであろうが、メルヘンは少女に深い知恵を与えた。新聞には高官のゴシップ記事が載せられていた。高官が窃盗容疑から背任罪をおかしたというトピックスである。彼女は震えながら記事を読んだ。金をつくって二、三日の休暇を買い、幸せの切符を手に入れるなんて考えられない。自殺の記事も、犯罪も、悲劇もたちまち彼女自身の事件に及んだ。すべての記事が夫人のことのようだ。生活に疲れた者、自殺者、誘拐されたメイドや捨て子などすべてが夫人の命運にかかわっていた。たしかに、夫人は豊かな生活を享受した。同時に、自分の運命が一瞬にしてどん底に落ちることも意識した。すべてが終焉に向かう今となって、夫人は新たな始まりを感じていた。終焉と始まりが限りなく見事に絡み合って、世界は展開した。だからといって、あの堕落した女に横暴な腕力で破壊する権力がゆるされていいのだろうか? そうした犯罪がゆえに、貴重な尊厳や美徳がすべて失われていいのだろうか?
たしかに夫人は神意を心から信じていた。だが、なぜ彼女はむやみに神意に逆らうのか! なにゆえに、彼女はささいな過失に大罪を負うのだろう! 金のために情夫に抱かれ、腕の中で男を快楽に落とす無恥な女、破廉恥(はれんち)な女、遊び女、さらに、高慢ちきに嘘に生きる女、見事に美しく変装し、さらに男を執拗に追い、恐怖のアバンチュールに巻き込まれた女たちを、夫人は何人も知っていた。女たちは恐ろしい犯罪に手をそめてやむなく身を滅ぼしていった。
しかし、はたして夫人に罪はあるのか? あんな男に、あんな恋人と私は関係ない。あのとき、自分の日常生活はそこなわれた覚えはないと、夫人は心底から思った。他方、男から得たものはなにもないし貢ぎもしなかった。過去も忘却もすべて夫人の犯行ではなく、相手の女の犯行なのだ。いま夫人は二度と思いだしたくない。とはいえ、時とともにつぐなわれた過去を一体誰が罰することができよう?
イレーネ夫人はぎくっとした。贖罪(しょくざい)はもはや自分ひとりの考えではないと彼女は思った。誰が贖罪を告げるのだろうか? 数日前に、はじめて彼女の身近にいた若者かもしれない。思いめぐらした。だが、驚いたことに、彼女にその考えを示唆したのは夫であった。夫がやや興奮し血相を変えて裁判所から帰ってきた。ふだん口数の少ない夫は彼女と居合わせた同僚たちに「今日は無罪を言い渡した」と唐突に言った。イレーネやその他の人たちから質問をあびると、夫は非常に興奮して語った。事件は三年前にさかのぼり、横領の罪で泥棒は処罰された。だが、三年前の犯罪は全く被告人の犯行ではなく、その逮捕が不当と判決されたのである。別の犯人が処罰され、真犯人には重罪が課せられた。なぜなら、被告人は三年間にわたり恐怖の独房にいて、永久的な冤罪(えんざい)の恐怖にさらされていたからである。
思えば、かつて、夫人は怖いもの知らずによく夫に反駁した。世事に疎い自分だが、犯罪者はいつの世も市民生活の害虫と思う。なんとしても撲滅しなければならない。ところで、自分の論拠がなんと脆弱(ぜいじゃく)なことか、他方、夫の論拠はなんとたしかで、かつ妥当であるかを彼女は実感した。彼女の場合、人を愛するのでなくアバンチュールを享しんでいると、彼は判断するだろうか? 彼女の生活に広がる数々の善行にも怠惰なくつろぎにも、夫は連帯の責任を負うというのだろうか? 彼女の事例について、夫は判事として妥当な判決を下すことができるのだろうか?
ところが、イレーネ夫人は余計な世話をやかないように配慮した。そんな矢先の時に、早々に一通の手紙がきた。それはうちひしがれていた感情をあおる痛い仕打ちだった。今度は二百クローネを要求してきた。要求額の急な高騰に夫人は愕然とした。すんなりと夫人は金を渡した。しかし、金銭的にもうついていけないと夫人は判断した。自分が資産家の家柄とはいえ、人目を盗んで多額の金を調達できるわけではない。これから先、相手はどんな手をうってくるだろうか? 明日は四百クローネになり、やがて千クローネになるだろう。それどころか、与えれば与えるほど金額はどんどん高騰し、あげくの果てに、彼女の資力は尽きて、当局の通告が彼女の自己破産を宣言するであろう。彼女が手に入るものはわずかな時間だった。息のつける時間は二日三日あるいはひょっとして一週間程度だろう。しかし、休息の日も苦悩と緊張がはりつめ、恐ろしく無駄な時間をすごした。この数週間、不眠どころか恐ろしい悪夢に彼女は苦闘した。息が苦しくて自由に動けず、休むことも働くこともできない。彼女の心は悪霊にとり憑かれ、読書どころか仕事も手につかない。病気ではないかと思った。彼女は非常に激しい動悸におそわれ、急激な発作に腰がガクンと落ちた。不安なうつ病にさいなみ苦しめられ、疲労の汗に全身がびっしょり濡れた。眠るどころではない。
夫人の存在自体が不安にむしばまわれ、恐怖に破壊され、肉体は毒されていった。からだが見るからに痛く、自覚症状がはっきり現われてくれればいい。そうとなれば、同情し哀れんでくれ人もいるだろう。だがそういう病ではない。冥界の苦悩の時間にいる病人を彼女は羨ましく思った。サナトリウムの白壁の間にある白いベッドで哀悼の花々に囲まれて眠るのがなんと幸せなことであろうか。人々が病人の快復を願って見舞ってくれるであろう。苦悩の雲のはるか彼岸に、巨大なやさしい太陽のように、完治の安楽が存在するだろう。苦しいとき、せめて大きな声で泣くのがいい。しかし、絶えず一日中、彼女は新たな恐怖の場に立たされた。しかし、明るく健康的な悲喜戯を演じなければならない。いらいらしても、笑顔を見せ明るく振舞わなければならなかった。だが、明るく振舞う裏に並々ならぬ努力があった。彼女は日ごろ無駄な自己管理に並々ならぬ精力を費やしていた。
一人の男が夫人を観察していた。彼は、彼女の心中をよぎる不安を少なからず察知した。彼女はこっそり追跡されていたのだ。彼女はそう判断すると、彼女はかたくなにさらに警戒するようになった。男はたえず彼女に気づかい、同時に彼女も相手を気づかった。二人は昼も夜も足を忍ばせて歩きまわった。まるでワルツを踊るようだ。お互いがそれぞれの秘密をかぎつけては、自分の秘密をこっそり隠すのである。近頃、夫もすっかり変わった。当初、法廷に出ていた頃の威圧的な厳しさがなく、彼なりの善意と気遣いを見せた。ふと彼女は新婚時代を想いだした。夫は彼女を病人のように丁寧に世話をやいた。そうした配慮に加え、著しい偏愛を彼女は恥かしく思った。他方、恐怖感もあった。なぜなら、彼は、一瞬の隙にゆるめた手からふと秘密をあばこうと、罠をかけようとするからだ。夫が彼女の寝言をきいたあの夜から、彼女の手に手紙を見たあの日から、夫の不信は同情に変わった。彼女の信頼を得ようと、夫は執拗にからだを求めた。度重なる愛撫に、彼女は安堵しすべてを赦した。たちまち猜疑心は消えていった。それも一つの策略ではないだろうか? 予審判事が被告を誘導尋問し自白を取って、すかさず判事の思い通りに被告を無防備にさせて信頼をえるという罠であるのか? あるいは、判事の心中に、傍聴人や傍聴の増える状況に耐えられないという感情をいだくのだろうか? だから、判事の同情のおもいが非常に強いので、彼女の日ごろの目にあまる苦脳に彼も一緒に耐えているのだろうか? どのように夫があつい救いの言葉を差しのべ、どのように自白に誘導するのか、と思うと彼女は急に恐ろしくなった。一方で、夫の意図を理解するとその善意がありがたく嬉しかった。しかし、そうした愛着の気持ちが昂じると、夫に対する恥辱感もつのった。彼女は以前に不信におちたとき以上にかたくなで拒否的な言葉をはいた。
最近、夫は正面からとてもはっきり彼女に意見をいうようになった。彼女が帰宅すると、リビングからなにやら大きな声がきこえてきた。鋭く力強い夫の声と家庭教師の騒がしい多弁な声と娘の泣きじゃくる声だった。まず驚愕の思いが走った。家の中で大声や激昻する声をきくたびに、彼女は身の縮む思いをした。彼女のもとで異常な事が起きるたびに不安感が反応した。手紙がまたきてないか、秘密がばれはしないかと戦々恐々とした。彼女が玄関に入るやいなや、まず、彼女の問いたげな視線は家族の顔色をうかがった。留守中になにごともなかったか、どこか地方で暴動でも勃発しなかったかとたずねた。ついに子供の喧嘩について簡易な即興尋問がはじまった。数日前、伯母が長男に色鮮やかな子馬の玩具を与えた。一方、妹は味気のないフォークをもらい、兄を羨んだのである。分相応の権利の正当性を主張したが、無駄だった。しかも、妹はあまりにも強情なので、兄は妹に子馬を絶対触らせなかった。それが原因で子供たちが大きな怒声をあげて騒動になった。頻繁に暗く卑屈で頑固な沈黙が続いた。すると翌朝になって、突如子馬の姿が消えていた。兄がいくら探しても無駄だった。結局、消えた子馬はばらばらにされ、木製の部分が破壊されていた。カラフルな毛皮はずたずたに引き裂かれていた。胴体は空洞になって、ストーブの中から発見された。嫌疑は言うまでもなく妹にかかった。兄は泣きながら父親のもとに駆けこみ、弁解の余地はない悪行を訴えた。さっそく尋問がはじまるとすいうのである。
イレーネ夫人は激しい嫉妬を覚えた。子供たちはいつも父親にあれこれと気遣い近寄っていくが、どうして母親のところにこないのかしら? むかしから、子供たちは喧嘩も不服もすべて父親に訴えてきた。これまで、彼女は面倒なことから解放されてきたのはうれしい。だが、激しい嫉妬の思いに駆られるのは、子供たちの愛と信頼を意識していたからである。
小法廷ははやばやと結審した。冒頭に娘が犯行を否認したが、なんとなく後ろめたく眼を伏せがちだった。秘密を洩らすまいと声は震えていた。家庭教師は反論した。娘は口惜しいあまりに子馬を窓から投げ捨ててやると、おどかす発言をきいたと家庭教師が証言した。娘は必死に否定したが無駄だった。娘のすすり泣く声と失意に小さなざわめきが起こった。母はきりっとした眼で夫を見つめた。父は子供を裁判するどころか、どうやら母親自身の運命が裁かれているように思えた。というのも、明日には自分も同様にからだを震わせ、うわずった声で夫と対峙するかもしれないと危惧するからである。娘が嘘を主張する間、父は厳しい視線でじっと見つめた。どんなに拒絶しても決して腹をたてずジレンマをおさえ、噛んで含むように説得した。ところが、拒絶の言葉もしどろもどろになったとき、父はやさしく娘に話した。そして、娘の行為のほんとうのいきさつを適確に説明した。娘は愚かにも腹をたて、ねたみの初動行為に及んだ。意外にも、それは現実に兄を深く悲しませた。それでも父は娘を弁護した。さらに、父は非常にやさしく詳細に娘を追求した。娘は次第に自信を失っていった。父は子供に自分自身の犯行に道筋をたて判断するように説明した。すると、娘はわっと泣き出し激しく嗚咽した。しばらくして涙もかれて、とうとう被告はぼそぼそと供述をはじめた。
イレーネ夫人は駆けよって泣きじゃくる娘を抱きよせたが、娘は憤然と母をつき飛ばした。夫は母親の先走った同情を厳しく誹謗した。そもそも、夫はこの犯行を罰しないままにしておくつもりはない。そこで、数週間も前から娘が楽しみにしてきた明日のイベントへ連れていくことを中止した。ささいな事件とはいえ、子供にとっては重い罰である。娘は泣きわめきながら父の判決をきいた。兄は大声で凱歌(がいか)をあげた。だが、冷笑する憎い嘲弄(ちょうろう)に、兄にもただちに同罪が課せられることになった。すなわち、相手の不幸を喜んだという理由で罰としてイベントへ行けなくなった。子供たちは罪の連帯に悄然とし、同罪の傷をなめあう結果となった。イレーネと夫だけが残った。
ところで、子供たちの罪や自白に関する話し合いのきっかけは、自分を曖昧にするのでなく、わが罪を告白するチャンスであると、イレーネはふと思った。なんとなくほっとした気持ちになった。せめて厳粛に懺悔し情状の酌量(しゃくりょう)を願った。だが、彼女が子供の弁護にまわって、夫がそれを素直に承諾するかどうかは疑問だ。そこで自分を弁護する言い訳はなり立つだろうかと、彼女は自問した。
「ねえ、フリッツ」と、彼女は切り出した。「明日、本当に子供たちをイベントに連れていかないおつもり? 子どもたちは非常に悲しむわ、ことに娘の方が。あの子のしたことって、そんなに悪気があったわけじゃないでしょ。どうして厳しい罰を与えようとなさるの? まだ子供じゃないの、可哀想と思いませんか?」
夫は彼女を見つめた。そして、おもむろに彼は腰を下ろした。問題を正面から議論しようとする態度を見せた。彼女は愉快とも不愉快ともつかぬ気持ちをいだいた。なぜなら、彼は一つ一つ言葉を選択したからである。彼が意図的に慎重に慎重を重ね、引きのばす言葉の間のびに彼女はいらいらした。
「子供たちが可哀想と思わないかっておたずねだね? では、答えるが、いま同情はしない。罰せられたのだから、いまは辛いだろう。だが、しばらくたって、気持ちは楽になるさ。昨日は不運だった。息子は家の中の隅々まで小馬を探し回った。ほかの人に拾われてしまうかもしれないと心配していた矢先のことだった。哀れな小馬はばらばらに壊されて、ストーブの中に発見された。不安は処罰よりこわい。なぜなら、処罰は多かれ少なかれ確定される。しかし、未確定ほど恐ろしい処罰はない。不安はこのうえない恐怖だ。緊張の戦慄は永久にやまない。娘は自分の罰を認めれば、気が楽になる。泣き声に惑わされてはならない。今になって涙が出てきたが、これまで涙は内にこもっていた。内にこもる方が外に出るよりも始末が悪い。思うに、娘はもう子供じゃない。ひょっとして自分の結末をすっかり見抜いているのかもしれない。そもそも、自分の罰を受けて泣くほうが楽なのだ。一夜あければずっと楽になると、ぼくは思う。そのとき、娘は安心して遊べるし、そのうち、疑ったりする者もいなくなるだろう」
イレーネ夫人は顔をあげた。夫の一つ一つの言葉が胸に突きささるようだ。だが、彼はそれをまったく気にとめない。むしろ、相手を気にせず淡々と話し続けた。
「ほんとうに、ぼくを信用するんだ。法廷や予審の状況をぼくは知っている。被告らは大方が隠蔽、発覚の恐怖、恐ろしい脅迫に耐え、数々のこまかい目にみえない攻撃から嘘言を主張しなければならない。裁判官は犯罪と立件と判決などすべてを掌握してから、根ほり葉ほり自白を引き出そうとする。だが、被告が胸の内を明かさず吐き出さなければ、自白は成立しない。判事はそんなケースを見るのがつらい。被告が悶絶する姿は悲惨だ。抵抗する肉体から被告の「はい」という自白の一言を吐かすのはまるで刃(やいば)でえぐり取るようなものだ。からだ中から抑えきれない力がしきりに込みあげてきて、「はい」の言葉が咽もとをついて出てくる。被告は咽が苦しくたまらない。ようやく言葉が咽もとに出かかる。そのとき、被告に邪心がはたらき、言いしれぬ虚栄心や恐怖心におそわれるのだ。すると、被告らは咽もとにつまる言葉をのみこんでしまう。再び新たな苦闘が始まる。こんなとき、裁判官もまた被告以上に苦しむ。すると、被告らは決まって、実際に自分の味方である裁判官を適視する。ぼくは被告の弁護士として、また代弁者として、とにかく被告に嘘言を強固にして自白するよう促がすべきなのだが、ぼくの本心はそうさせたくない。そもそも、被告らは自白して罰をうけるよりも、自白しないほうが苦しむからだ。危険を知って犯行をおかした者が、後になって自白する気がないということが、そもそもぼくには理解できない。自白の言葉の不安はささいなことだが、これはどんな犯行より嘆かわしい」
「いつも‥‥いつも心を邪魔するものは‥‥もっぱら恐怖だとおっしゃるのね? 恥じは‥‥恥じとはいえないかしら? 大勢の前で自分の心を打ち明けのも恥‥‥人前で裸になるのも恥じゃないかしら?」
彼は驚いて顔をあげた。これまで彼女から反ぱくをうけたことはない。だが、彼にはその言葉がうれしかった。
「恥じ‥‥と言ったね‥‥確かに‥‥それもきっと恐怖ともとれる‥‥だが、もっとレベルの高い‥‥罰に対する恐れでなく‥‥そうだ、自分では分かっているんだが‥‥」
彼はひどく興奮して立ちあがり、右往左往した。彼女の反ぱくが胸を突いたようだ。急に震えて激昂した。はたと彼は立ちどまった。
「ひとつ付け加えておくが‥‥それは人々に対する恥、他人に対する恥‥‥まるで新聞紙からバターパンをむさぼるようなホームレスの恥だね‥‥とはいえ、少なくとも身近な人にはそれを告白するはずだ‥‥むかしぼくが弁護にあたった放火犯のことを知っているだろう‥‥ぼくに特別な好意をもっていた男だ‥‥犯人はぼくにすべてをうち明けてくれた。少年時代からの日常茶飯事まで‥‥プライベートなことまで‥‥やっと彼は犯行をほのめかした。有罪判決が下されていても‥‥しかし、ぼくには犯行を認めなかった‥‥それこそまさしく恐怖だが‥‥ぼくは彼を疑えるだろうか‥‥恥ではない。なぜなら、彼はすっかりぼくを信用しきっていた‥‥思うに、ぼくは彼の人生から友情のようなものを意識した。かけがえない人間だ。‥‥これもやはり他人に対する恥じではない‥‥では、一体なんだったのか、何を彼は信用したらよかったのか?」
「たぶん」―彼女は背を向けた。なぜなら、彼にじっとにらまれて、自分の声が震えているのに気づいたからである。「たぶん‥‥それもおおむね恥です‥‥いざ面と向かうと‥‥さっそく意識するものよ」
気勢をそがれたように、彼ははたと立ちどまった。
「なるほど、そう思うんだね‥‥おまえの考えは‥‥」すると、彼の声は急に変わった。声が著しく弱く暗くなった‥‥「おまえが思うに‥‥ヘレーネは‥‥だれか他の者に対して‥‥きっと家庭教師なら‥‥自分の罪をもっと自供しやすかったと‥‥あの子が‥‥」
「たしかにそう思う‥‥あなたの判決があの子にとってあまりにも厳しすぎるから‥‥だって‥‥だって、あの子は‥‥あなたを最も愛してますから‥‥だから‥‥だからこそあなたにあれほど盾突くのよ‥‥」
また彼は立ちどまった。
「たぶん‥‥たぶんおまえの言う通りだ‥‥いや、きっとそうだ‥‥だが、それにしてもおかしい‥‥そこまでぼくは考えてなかった‥‥話は実に簡単なこと‥‥ぼくはちょっと厳しすぎると、おまえは認識しているが‥‥ぼくはそうは思わない。しかし、さっそく尋問に入るが‥‥娘は当然うったえをしりぞけることができる‥‥実は、ぼくはあの子の高慢さと反抗心を懲罰するつもりだった。実は‥‥あの子はぼくを信用していない‥‥しかし、おまえの言うとおりだ。ぼくが人を赦せない人間と思うだろうが、それはちがう。それはぼくの本意ではない、いやしくもおまえからそんな風に思われたくない、イレーネ」
彼は彼女をじっと見つめた。その視線を浴びて彼女の顔が赤くなった。そんな風に言われるのはなにか下心あっての事なのか、それとも偶然か? 意地悪なあやしい偶然なのか? 相変わらず彼女は不気味な不安におそわれた。
「判決を破棄する」―-と、彼になんとなく明るい兆しが見えたようだ。「へレーネは無罪だ。本件についてぼくが知らせてくる。この判決に満足してくれるね? それとも、なにか特別な要求があるのだろうか?‥‥おまえにも‥‥分かるように‥‥分かるだろう。やっと今ぼくは寛大な気持ちになれた‥‥たぶん、快く早々と間違いを認めたことでほっとした。いつもそうすれば気が楽になるのだが、イレーネ、いつも‥‥」
夫の主張がなにを意図するかを彼女は理解したようだ。思わず彼女は夫に身をよせた。
夫が言葉に窮するのを彼女は感じた。彼女が抑制しているものを、すばやく受けとめるように、夫も身をよせた。そのとき、彼女の視線は彼のぎらぎらした視線にぶつかった。夫は彼女に自白を急き立て、人間性からなにかを嗅ぎ出そうとしているようだ。同時に、彼女も燃えるような焦りを意識した。にわかに彼女の中ですべてがガラガラっと音をたてて崩れおちた。彼女は怠惰に手をだらりと落とし、顔をそむけた。心中をけっして明かしてはならない、心中にともり、安堵を求める解放の言葉を吐いてはならないと彼女は思った。だが、それは無駄かもしれない。まじかに雷鳴のような警鐘(けいしょう)がとどろいた。自分はもう逃れられないと観念した。一縷の望みをかけて、彼女はこれまで恐れてきたものを渇望した。救いの光明とは暴露だった。
思ったより早く、イレーネの願いはかなうかもしれない。二週間にわたって葛藤は続いた。彼女は我慢の限界を感じた。女サギ師の連絡がこなくなって四日がたった。とはいえ、不安は彼女の血肉にしみこんでいた。玄関のベルが鳴るたびに、夫人がみずからドアの鍵を開けにいった。そうするのも、直接女サギ師の遣いに会って、自分で一件を無難に始末したいからである。こうした行動にも焦りや葛藤があった。いわば、夜の安息のために夫人は金を払い、また二、三時間子供たちと散歩に出かけるというわけである。昼であれ夜であれ、夫人は街に出かけ友人たちに会ってほっとひと時をすごした。もちろん、家にいるのもいい。夫の知識はたしかだ。だからわずかな安堵のために緊迫した危険をおかすような人ではない。だが、夜中に彼女の血はむしばむ悪夢に苛なやまされた。
ベルの鳴る音とともに、彼女はあわてて出ていきドアを開けた。意識が過敏になっているだけに、遣い女が現れるという不安は猜疑心をあおり、容易に敵意をひきおこした。しかし、いつも慎重に考えすぎて、抵抗心はヘタヘタッと崩れた。電話の鳴る音におろおろし、ドアのベルの音に全身が鞭に打たれたように飛びあがった。丁度そのときベルが鳴って、彼女は部屋を飛びでてドアへ走った。ドアを開けるやいなや、夫人は見知らぬ女をいぶかしげに見た。次の瞬間、新しい装いに派手な帽子をかぶった女サギ師の憎々しい顔を認めた。夫人は愕然として後ずさりした。
「まあ、今日はいられたのね。ワグナーさん。まあ、なんて好都合な。ご相談したい事があってね」と女は言った。夫人は驚愕し、震える手でドアのノブにからだをあずけた。女は返事を待たず、中に入るや傘を置いた。あでやかな赤い日傘だ。明らかに、ゆすりで騙しとった金で買ったものである。まるで我が家のように、この上なく落ち着いたもの腰である。満足気に、いわば一種の安堵感で豪華な家具調度品を見回した。案内もされないままに応接間へ通ずる半開きのドアの中へ入った。「あげていただくわね?」と、女は冷笑を抑えぎみに言った。驚きのあまり、夫人は話す言葉を失った。だが、女はなだめるように言った。
「いけないとおっしゃるなら、お話は早く済ませるわ」
返す言葉もなく、夫人は女の言葉に従った。夫人は女サギ師を自分の部屋にいれたことを悔いた。同時に、女の法外な大胆不敵な態度に夫人は呆然(あぜん)とした。なにもかもが夢を見ているように思えた。
「素敵なおうちじゃない、なかなか素敵」と、快適さをわざとらしくほめそやして、女は腰をおろした。「あら、なんて座り心地がいいこと。それにたくさんの絵。ここに来て初めて分かった。あたしってなんと惨めな女かって。すばらしいじゃない、ほんとうにすばらしい、ワグナーさん」
不法者が夫人の部屋に心地よくどっかり居すわる様子を見て、苦しめられてきた憤りが爆発した。
「一体なにが欲しいのです? どろぼう! 他人の家に入ってくるなんて。しかし、私は死ぬまであなたに苦しめられませんから。私は‥‥!」
「そんな大きな声を出さないでよ」と、女は侮辱的な慣れなれしさで遮った。「ドアは開いているから、使用人に聞こえちまうよ。そんなこと、あたしにはどうでもいいけどさ。ほんとうだよ。あたしは豚箱に入ってもいいんだから。今以上貧しい生活はないだろう。でも、ねえ、ワグナーさん、もっと用心したほうがいいよ。そんなに癪にさわるなら、あたしがドアを閉めてくるわ。でも、ひとつ言っておくけど、あたしは怒鳴られたって、なんとも感じないからね」。
イレーネ夫人は、しばし怒りに燃えて気勢をはろうとしたが、それも女サギ師の動じない態度にふたたびヘタヘタっと崩れた。どんな呵責が課せられるのか、こわがる子供のように、夫人は意気消沈し不安にたちすくんだ。
「だから、ワグナーさん、あたし、ややこしいことをくどくど言いたくないの。分かるでしょ。生活がやっていけないのよ。ほら、前にも話したでしょ。すぐに家賃代が要るのよ。もう長い間納めてないの。ほかにも要るの。とにかく少しでも始末したいの。それで、あんたのところに来たの。実は、あんたに支援していただこうと思って。まあ、とにかく四百クローネほど出していただかないと」
「とんでもない」と、多額の金に驚いて夫人は口ごもった。そもそも、夫人はもうそんな多額の現金で持ちあわせていない。
「私、ほんとうに持ちあわせてない。今月はすでに三百クローネをあげました。一体、私がそんな大金をどこに持っていると思うの?」
「ふん、じゃあもういいよ。でも、よく考えな。あんたは裕福な奥様じゃない。お望みの金はたんまりあるはずよ。まあ、きっとあんたにその気がないのね。でも、よく考えてみて、ワグナーさん、なんとか作っていただかないと」
「だって、本当に持ってないのよ。あれば、さっさと出すわ。ほんとうに、そんな大金は持ってません。少しだけなら、まあ、なんとか‥‥せいぜい百クローネなら‥‥」
「四百クローネって言ってんのよ、必要なのよ」と、不満足な応答に侮辱されたように、女サギ師は頑としてこの言葉をつき返した。
「だって、ほんとうにお金がないのよ」と、夫人はヒステリックに叫んだ。いま、夫が帰ってきたらと夫人はしばしば想像した。いつなんどき夫が帰ってくるかわからない、「ほんとうです、私、持ちあわせがないのです‥‥」
「それなら、お金を用意しようと一肌脱ぐ気にならないの‥‥」
「できません」
女は夫人の頭の先から足の先までなめるように見た。
「ほら‥‥例えば、指輪だってあるじゃない‥‥それを金に換えれば、けっこうなお金になる。もっとも、装飾品なんてあたしは詳しくないけど‥‥一度も身につけたこともないし‥‥しかし、しっかり四百クローネにはなると思うよ‥‥」
「指輪ですって!」と、夫人は悲鳴をあげた。それはエンゲイジリングである。一度も手から外したことのない唯一の指輪で、貴重な美しい宝石は高価である。
「まあ、どうして指輪はだめなんだい? 質札はあんたに送るわ。だから、お望みのときに取り返せるじゃない。すぐ戻ってくるよ。あたしが指輪を着けるわけじゃない。あたしみたいな貧しい女が、そんな素敵な指輪をもってどうするっていうわけ?」
「どうして私をそんなに責めるの? なぜあなたは私を苦しめるのですか? 無理です‥‥無理です。そんなこと分かるでしょう‥‥ご覧の通り、私はできるかぎりのことをしてあげたわ。そんなこと分かるはずよ。人になさけっていうものがあるでしょ!」
「あたしはなさけをかけられたことなんてなかった。餓えに瀕して、野たれ死に同然だった。このあたしがさ、なんで裕福な奥様に同情しなくちゃあなんないの?」
イレーネ夫人は激しく言い返そうとした。そのとき、夫人は外からドアが開く音をきいた。にわかに夫人の血の気がひいた。夫が裁判所から帰ってきたにちがいない。戸惑う間もなく、夫人は指から指輪を引き抜き、待ち受ける女にそれを差し出した。女はすばやく仕舞った。
「あんた、心配しないで。あたし、すぐ帰るから」と、女はうなずいた。そのとき、女は夫人の顔に名状しがたい不安を認めた。踊り場に人の気配を感じた。たしかに夫の足音がはっきりときこえていた。女はドアを開けると、入ってきた夫に会釈した。彼はちらっと女に目をやっただけで、とくに気にかからないようだ。女は出ていった。
「あの人、私に用事があってきたのよ」と、女の背後でドアが閉まるやいなや、最後の気力を振り絞って夫人は弁解した。最悪の事態を免れた。夫は黙ったまま、昼食の揃っているキッチンへゆっくり入った。指の皮膚に指輪の冠状の跡が冷たく残った。空気が燃えるようにふれた。やけどのように露出した箇所に周囲の者たちは気づいたようだ。食事の間じゅう、彼女は手を隠した。そんな仕草をみせながら、彼女は過剰に反応しないようにつとめた。夫の視線が執拗に彼女の手のあたりをさまよい、同時に手の動く先々を追った。夫の注意をそらそうと、彼女は矢つぎ早に質問をして、会話の流れを止めないように配慮した。夫に子供たちにそして家庭教師にしきりに話しかけた。単調な話しで繰り返し話題に花をさかせた。しかし、そのたびに彼女は息詰まる思いをした。それでも彼女はあえて上機嫌の様子を見せた。そして、つとめて他の人たちを陽気にさせた。子供たちをからかい、けしかけたりするが、逆らいもせず笑いもしない。母の快活さには、なんとなくなじまない違和感があった。彼女もそれを察した。どんなに努力しても、彼女の挑戦はうまくいかない。しまいに彼女は疲れて沈黙した。
他の人たちも黙った。皿の音がカタカタとひびいた。心中には恐怖に悩む声がきこえた。そのとき、ふと夫が口を切った。「あれ、いったい指輪はどうしたんだ?」
イレーネ夫人はぎくっとした。心中でだれかが「ああ、万事休す!」と大声で叫んだ。だが、さっそく女の防衛本能が働いた。いまこそ全神経を集中しなければならないと彼女は思った。今ひとつのセリフが、ただひと言がほしい。そして、ひとことの嘘言に、最後の嘘に気づいた。
「あれ磨きに出しましたの」
そして、この嘘言をはずみに、いま一度きっぱりと彼女は付け加えた。「明後日、取りにいきますの」と、明後日を強調した。彼女はもう逃げられない。うまくいかなければ、嘘はばれるだろう。あらためて彼女は指輪の期限を定めた。すると、混乱した不安感が新たな感情にあいまって満足感をおぼえた。彼女は決心するにいたった。「明後日」という指定期日を彼女は腹にすえた。指定したことで、妙な安心感が不安感に取って代わった。彼女の心中に新しい力、生きる力、そして死への力がよみがえった。
イレーネ夫人は差し迫った判決を前に自分の意識を確認した。思いがけなく彼女の心に透明感が広がった。不思議にもいらだちがひいて、彼女の気持ちが落ちついてきた。不安感は貴重なクリスタルのような安堵感に変わった。おかげで、彼女の色々な生活模様がみごとに明らかにされ、自分の価値感で判断した。彼女はわが人生を予測してみた。そして、生きることの重大さを痛感した。あらたに高まろうとする意志で、人生を大事にし、向上させなければならない。悶々とする日々に彼女はそれを痛感した。今から、けがれなく純粋でしっかり人生をやりなおそうと、彼女は覚悟した。しかし、彼女は生きることに疲れはてた。だから、離婚した妻として、不貞な女として情事に汚れて生きつづけることはできない。安心の期限を金で買ったが、それも恐ろしい危険な賭けだ。といって、今さら逆らうわけにもいかない。終焉は近い。夫に、子供に、身辺の人たちすべてに自分の罪がばれる危険は迫っていた。彼女の四方八方は敵にふさがれ、逃げられない。自白も確かな救いも失われたと、夫人は悟った。ひとつの道だけがまだ残されていたが、その道には帰路がないのだ。
一方、生命は胎動する。閉ざされた冬の母体を、しげく荒々しく突き破って春が明けた。春の日和は穏やかに限りない紺碧の空である。暗闇につつまれた冬の時間に息づくように、深遠で広大な空を人は実感しているようだ。
子供たちは今年はじめて春の晴着を着せてもらって大はしゃぎである。悦ぶ姿に、母はもっぱら涙をこらえて対応した。子供たちの笑顔が母の胸に苦しい余韻を残すのだ。その間に、母は決意をあらたにした。かならず指輪を取り返すと。というのも、自分の命が何度賭されても、彼女の過去に一抹の疑惑も残してはならない。だれも罪の証拠をはっきりつかんだわけではない。子供たちは、彼女にまつわる恐ろしい秘密を知るよしもない。秘密なんて白をきって、だれにも弁解する必要はない。
さっそく夫人は質屋を訪ねた。自分でもこれまでほとんど身に着けたことのない家宝の装飾品を質に入れた。背信の指輪をいつでも女サギ師から買い戻せるだけの金を調達した。財布に相当額の現金を入れた。すると、昨日まで最も恐れてきた女サギ師との遭遇をむしろ懇願した。夫人は意気揚々と街を闊歩した。空気はなごやかに、陽は家並みに映えた。激しい風の動きとともに、白い雲が速やかに空をかけめぐった。夫人は人波のリズムの中に吸い込まれていった。荒涼とした冬のたそがれ時に、人々の足はことのほか軽やかにせわしくみえた。ふと彼女は脳裏にひらめくものを感じた。死の想念は、まるで船内に閉じ込められたように、小刻みに震える手から抜けでようとしない。それはみるみる妖怪になって、彼女の意識から消えた。悪らつな女の一言ですべてが破壊されていいのだろうか。輝く門構えの家々も、疾走する車も、らいらくな人たちも、そして血気のさかんな感情もすべてが破壊されていいのだろうか?万象が活気に燃える永遠の焔をたった一言が消していいのだろうか?
イレーネはひたすら歩いた。沈痛な眼差しはもうない。肩で風を切って歩いた。獲物をつかえようとする意欲をあらわにした。どうやら獲物が狩人を獲るというのだ。窮したネズミのように、逃れられない。絶体絶命と思うやいなや、突如、追跡者に戦いを挑んだ。女サギ師をこらしめようと夫人は敢然と立ち向かった。生きる衝動が絶望する者に賦与されたのだ。夫人は最後の力をふり絞って立ちむかった。女サギ師がよく待ち伏せた家の近くに夫人は立ちどまり、ときには街中を忙しく探索した。というのも、売春婦の男買いと間違えられないためである。指輪を奪い返す戦いはもはやそれだけの問題ではない。いま指輪には猶予がない。運命の予告にしたがい、自分の決断にそむいても、生死をかけて夫人は女サギ師との遭遇を願った。指輪の奪還が見えてきたようだ。しかし、どこにも女サギ師らしい姿は見あたらない。袋小路のねずみのように夫人は大都会の限りない雑踏の中に消えた。そこで、昼にいったん帰ることにしたが、諦めたわけではない。昼食後に徒労の捜索を再開することにした。好奇心にかられて街を散策したが、それらしき人にも会わない。心中に別の恐怖がよみがえった。夫人を不安にするものは女サギ師でもなく、また指輪でもない。それは理性では到底判断できない、いわば遭遇すべてにともなう戦慄の極致である。女サギ師は念力で夫人の氏名も住所も知った。夫人の家族関係など一部始終をつかんでいた。女はいつもぞっとする恐怖の束の間に現れ、タイミングよくすばやく消えた。女は気ままに、近くのどこか大きなビルに潜んでいるのかもしれない。だが、どんなに推測しても見当がつかめない。脅迫してくる兆候も見えない。女の住まいも見つからない。夫人はへとへとに疲れ、つのる不気味な恐怖を力なく訴えた。神が夫人の破滅を呪詛(じゅそ)しているのかもしれない。弱みにつけこまれて、夫人は悪運の渦中に巻き込まれた。いらだたしく憤然とした足取りで、夫人は相変わらず同じ道を昇っては下った。自分が娼婦のように思えてきた。しかし、女サギ師は一向に現れない。おびやかすように宵闇は迫っていた。早春のゆうべに明るい空の色彩が消えて灰色の濁色になると、夜があわただしく訪れた。街路にはランタンが灯り、人の波は家路に流れ、日中の営みはすっかり闇に消えていった。いくたびも夫人は道を行ったり来たりした。それでも最後の望みをかけて街中を偵察した。むなしく夫人は帰路についた。身が凍えた。
憔悴しきってイレーネ夫人は二階へ昇った。メイドが子供たちを寝かしつける様子を、彼女は聞いた。しかし、自分から子供たちに「おやすみ」の声をかけず、ひとりひとりに別れを告げず、さらに神への祈りもためらった。自分は今なにを見つめているのか? なに不自由ない幸せに子供たちの上機嫌なキスをうけ、明るい顔で愛を示すためなのか? とうに失せた悦びなのに、いまさらなんを悩むのか? 彼女は切歯扼腕(せっしやくわん)の思いだった。いや、様々な過去に想いをはせた。私は善行や愚行はおろか、この世になにも望むものはない。明日に私はこうした因縁をすべて一気に断ち切らなければならない。だが、実際に、災難や憎悪や雑念や悲劇や女サギ師やスキャンダルなど夫人をとりまくすべてに真正面から考えようとした。
夫が帰宅した。同時に怠惰なひとり思考が断たれた。にぎやかな団らんに加わりながら、夫は彼女に親しくあれこれたずねてきた。そうした彼の大様で敏捷な配慮に、彼女は過敏な神経を使う必要はない。だが、昨日の事件のことを思うとどんな話題にも抵抗感があった。心中に漠然とした不安が広がった。といって、彼女は愛の拘束をうけ、同情をかうつもりはない。夫は彼女の抵抗を察したようで、なんとなくけげんな顔をした。さらに、彼女は夫の気づかいを危惧し、それ以上の深入りを避けた。夜も早々に就寝するよう促した。「おやすみ」と彼は応じた。そして彼女も出ていった。
「おやすみ」とは近くにあって限りなく遠くにあった! 彼女にとって眠れない夜が恐ろしく、深遠な暗闇だった。街の騒音はだんだん遠くなった。灯りが部屋に反射した。やがて外の灯りは消えた。別の部屋の寝息が身近に感じた。そこに子供たちや夫の命があると彼女は実感した。近くにありながら、はるか遠くにすっかり消えていく世界に、名状しがたい沈黙があった。沈黙は、自然でもなく、周囲からでもなく、深層の神秘にさざめく源泉からくるものであった。彼女は棺に納められたわが身を意識した。果てしない静寂と闇の中に、よみの国の闇黒を身にひしひしと感じていた。闇の中に時計はひときわ大きな音を打った。すると、夜は闇となり静まりかえった。だが、あらためて彼女は限りなく空しい闇の意味を確認したかった。いまさら彼女は別れや死についてなんとも思わない。だが、自分がどうしたら夫から逃れ、子供たちに知られないうちに、スキャンダルの恥を払拭できないものかと思案した。
あれこれ思いめぐらすうちに、自分が死に向かって歩いていることを意識した。自殺のあらゆる手段を模索した。ふと思いあたることがあった。かつて不眠におよぶ苦しい病にあった時に医師がモルヒネを処方してくれたのである。彼女は小瓶から甘辛い毒物をほんのわずかほどなめた。話によれば、その毒物は少量で安らかに息をひきとることができるという。ああ、もう追われることもない、安らかに眠ることができる。永久に眠ることができる。心は恐怖の打撃を受けることもない! この甘い陶酔の思考に不眠者は限りなく興奮した。彼女は唇に苦味を感じ、かすかに意識が混濁(こんだく)した。彼女はあわてて立ちあがると灯りをつけた。探し出した小瓶は半分量にもたらず、十分な致死量でないのを彼女が危惧した。執拗にあちこちの引き出しを探したところ、やっと処方箋が見つかった。処方箋には最大量の服用で死に至ると書かれていた。高価な紙幣のように、彼女は笑顔をつくりながらそれをしまった。やっと彼女は死を手中にした。悪寒におびえながらも落ちついてベッドに戻ろうとした。だが、自分が映し出される姿見の前を通り過ぎるとき、ふとその暗い枠に亡霊のように蒼白く眼がくぼみ、帷子(かたびら)のような白衣をまとい対峙するわが姿を見た。からだに戦慄が走った。灯火を消して、凍りつくベッドにもぐりこんだ。夜が明けるまで目は醒えていた。
午前、イレーネ夫人は自分にきた手紙などを焼き捨て、いろいろこまごました書類を処分した。だが、なるべく子供たちに会わず、愛着のあるものはいっさい見ないようにした。享楽と欲望に執着し、無駄なためらいによって冷静な決断をくだせない人生をおくるつもりはない。もういちど最後の命運をかけて女サギ師に会うために、気分をあらたに街へでた。彼女はなお根気よく街を探索したが、かつて昂揚した緊張感はもうない。からだがなんとなくだるく、再挑戦する気力も失くしていた。二時間ほど、彼女はまるで義務感を負ったように歩き続けた。女サギ師に似た姿はどこにも見あたらない。自分が惨めとは思わなくなった。女に会えるような望みがなくて彼女は落胆した。往来の人たちの顔をのぞき込んだが、誰もがよそよそしく、誰もが生気を失い、なんとなく死んだようだ。なにもかもが遠く消えた。自分とまったく無縁になった。
イレーネ夫人は一瞬ぎくっと身をひいた。往来の向こう側を見やると、雑踏の中にふと夫の視線を察したのだ。それは最近彼女があらたに知った異様に厳しく射るような視線だった。恐る恐る彼女は向こう側をじっと見た。だが、その姿は眼の前をよぎる車の陰にかき消された。いまの時間にいつも彼は裁判所で執務中であるはずだと思って、彼女は落ち着きをもどした。張りつめる興奮に、彼女の時間感覚が不確かになった。昼食時には遅れて帰宅した。しかし、いつものように夫はまだ食事の席におらず、二分ほど後にやっと帰ってきた。彼にいらだちの色が見えた。
イレーネ夫人はあらためて夜までの時間を数えた。もう道連れにする者はいないことを確認した。それにしても、なんと多くの時間が残されているのだろう。万象はなんと不思議なのか、別れを告げる時間はなんと短いことであろう、一切がなんと無価値にみえるのだろうと、彼女は驚嘆した。そのうち睡魔が彼女をおそった。なにも考えず恐れもせずそして当てもなく、機械的に彼女はふたたび街に出た。とある交差点で、ふとした瞬間に御者が馬を引き返した。彼女の目の前を、御者の車体が突き進んできて胸すれすれに過ぎた。御者に罵倒された。彼女はからだの向きを変えることもできない。救われたのか、あるいは延命だったのか。偶然が彼女の最後の死の決断をはばんだのかもしれない。彼女はとぼとぼと歩き続けた。まったくなにも考えずに、暗い終焉の感情にただ乱れて、静かに降りそそぎ、すべてを包む霧を彼女快く感じていた。
街の名を知ろうとふと目をあげたとき、彼女はあ然とした。さ迷い歩くうちに、彼女は偶然にもかつての恋人の家の門前に立っていた。これはなにかの予兆であろうか? きっと彼が私を救うことができるであろう。彼は女サギ師の住居を知っているにちがいない。彼女は大きな期待に小躍りした。しごく簡単なことなのに、こんなことがどうして気づかなかったのだろう? にわかに肢体がいきいきした。暗い思いに混乱して気狂いしそうだったが、希望の光がさした。さっそく彼をつれて女のところへいき、きっぱりと決着をつけなければならない。女サギ師に脅迫を止めるように一喝してもらいたいのだ。女を街から追い出すには、恐らく金で済むであろう。哀れな男をひどく粗末に扱ったことが急に悔やまれた。とにかく、彼は救ってくれると確信した。救いがまさに終焉のときに訪れたなんて、なんと不思議な因果であろう。
イレーネ夫人はあわただしく石段を駆けのぼった。ベルを押したが、ドアが開く様子がない。彼女はじっと耳を澄ます。ドアの向こうに秘めた足音がきこえたような気がした。もう一度ベルを押した。なお応答がない。するとやっと中からかすかな音がきこえてきた。彼女はたまらない気持ちだ。たて続けにベルを鳴らした。現実に彼女の生死にかかわることなのだ。
やっとドアの後ろでなにかが動いた。するとカチャカチャする解錠の音とともに、細い隙間が開いた。「私よ!」と彼女はせきこんで言った。
びっくりして彼はすぐドアを開けた。「君か‥‥いや、あなたですか‥‥奥様」と、彼は当惑した顔で口ごもった。「ぼくは‥‥すいません‥‥ぼくは‥‥まだ仕度もしてないので‥‥あなたが見えるなんて‥‥こんな格好でごめんなさい」と、彼は自分の肌着の袖を指さした。肌着は半分開いて乱れていた。
「私、あなたに緊急な相談があって‥‥私を助けてほしいの」と、いらだたしげに言った。なぜなら、彼女はホームレスのようにしばらく廊下に立たされていたからだ。「私を入れないおつもり、ちょっとだけ話をきいて」と、彼女は憮然と言いそえた。
「どうか」と、彼は狼狽して空を仰いだ。「ぼくはこの通り‥‥乱しておりますので」
「あなたは私の話をきく義務があるわ。実はあなたの責任なのよ。あなたは私を救う責任があるわ‥‥私の指輪を取り返さなければならないの。あなたの責任よ。そうでなければ、せめて女サギ師の居処を教えて下さい‥‥あの女は私をどこまでも追ってくるの‥‥、いまは姿をくらましているわ‥‥あなたの責任よ。私の言うことをきいてちょうだい、あなたの責任よ」
彼は彼女をじっと見た。そのとき、彼女はつじつまの合わない言葉をつらねて喘ぐ自分に気づいた。
「まあ、なんて‥‥知らないなんて‥‥じゃあ言うわ、あなたの恋人よ、もと恋人よ。以前、私があなたのところから出たときに出くわした女よ。それ以来、私を追ってくるの‥‥死ぬほどつらい‥‥こんどは私の指輪を奪ったの。それを私は取り返さなければならないわ。今晩までに取り返さなければならないの。今夜までに取り返すと、主人に約束したのよ‥‥だから、どうか私を救ってほしいの」
「急に言われても‥‥奥様‥‥」
「助けてくれるの? それとも嫌なの?」
「だから、ぼくはそんな女性を知りません。あなたは誰のことを言っているのですか、ぼくは知りません。ぼくは女サギ師などとまったく関係ないのですから」と、彼はひどくあわてて言った。
「そう、あなたはご存知ないのね。あの女が口からでまかせを言ったのね。だってあの女はあなたの名前も住所も知っていたわ。あの女が脅迫するような女じゃないって言うつもり? きっと、私が夢でも見ていると言うのね」
イレーネ夫人はカラカラと笑った。彼は不快な顔をした。彼女は気が狂っているのではないかという疑いがふと彼の脳裏をかすめた。彼女の眼はひどくぎらぎらしていた。挙動が乱れ、言うことがちぐはぐだ。おどおど彼はあたりを見まわした。
「どうか落ちついて下さい‥‥奥様‥‥ぼくは確信します。あなたは思い違いをされています。とんでもないことです。決して‥‥いや、まったく身に覚えがないことです。ぼくはそうした類の女性を知りません。ご存知のとおり、二人の付き合いは、ぼくがここに越してきてからのことで、そんな長かったわけではなく‥‥名前だって聞いたことがありません‥‥それにしても、本当におかしいです‥‥思い違いと断言します‥‥」
「それでは、あなたは私を助ける気がないのね?」
「いや、必ずお助けします‥‥ぼくにできることなら」
「それなら、いらっしゃって。一緒にあの女のところへ行きましょ」
「誰のところへ‥‥一体誰のところへ?」と、彼は言った。夫人は彼の腕をつかまえた。そのとき、夫人の頭がおかしいのではないかと思って彼はぞっとした。
「女のところよ‥‥行きましょう、それともお嫌なの?」
「いいえ、かならず行きます‥‥きっと」と、相手の強引に迫る気勢に彼の疑念がますます深まった。「行きます‥‥行きますから」
「じゃあ、いらっしゃい‥‥私にとって生きるか死ぬかの問題なのですから!」
彼は笑うまいと息をこらえて、急にかしこまった。
「ごめんなさい、奥様‥‥いますぐというわけにはいきません‥‥ぼくはピアノのレッスンがあります‥‥いまから休むわけにはいきません‥‥」
「そう‥‥そうですか‥‥」と、彼女は真正面からククっと笑った。「ピアノのレッスンですって‥‥シャツ一枚で‥‥嘘つきね」と、妙な妄想に駆られて、夫人はつかみかかってきた。彼は相手を引き離そうとした。
「それじゃあ、ここにあの女が居るのね、女サギ師があなたのところに? 結局、あなた方二人でお芝居をみせたわけね。きっとあなた方は私から奪った物をみんな山分けしているのね。とにかく、私はあの女をつかまえてやるわ。いま、私になにも怖いものはないの」と、夫人は大声で叫んだ。彼は夫人をしっかり抑えたが、もみ合いとなった。夫人は身を振り放し寝室のドアに走りこんだ。
人影がスウット動いた。明らかに誰かがドアの陰で盗み聞きしていた。イレーネは呆然として、乱れた服装をした見知らぬ女をまじまじと見た。女はツンと顔をそむけた。女は夫人が正気でないと見て、争いをとめようと夫人に羽交い締めをかけようとした。しかし、一瞬の隙に夫人はその場から逃がれた。「失礼しました」と、夫人はつぶやいた。頭がすっかり混乱していた。もうなにもかも分からない。夫人は底知れぬ嫌悪感と虚脱感におそわれた。
心配そうに見送る彼を見て、「失礼しました」と、夫人はもう一度言った。「明日‥‥明日すべてが分かるわ‥‥いま、私は‥‥私自身もなにもかも分からないの」と、夫人は他人行儀に言った。自分がかつてこの男の恋人であったという思いはもうない。未練もない。いまになって様々な事が以前よりいっそう混然となった。ただ、なんとなく偽善がましい自分が存在しているという意識が働いた。しかし、夫人はあまりにも疲れすぎて思考力がない。あまりにも疲れすぎて集中力を失っていた。まぶたを閉じて夫人は段階を降りた。判決を受けた罪人が絞首台にいくときのような思いだった。
外へ出ると、街は暗かった。きっと、あの女はいまどこかで私を待ちぶせているだろう、きっと、最後の瞬間に救いがおとずれるだろう、という考えが夫人の脳裏を去来する。手を合わせて、これまで忘れてきた神に祈りを捧げる思いだった。おお、あと二、三ヶ月だけ猶予を下さい。夏までの二、三ヶ月だけでいい。そうすれば、女サギ師の手の届かない所で、平穏に暮らせるだろう。この夏だけでも牧場や田園にかこまれて暮せるだろう。夫人はすっかり暗くなった街並を血眼になって女サギ師を探し歩いた。向こうの家の門に人影かひそかにうかがっているように思えた。だが、近づいていくと人影は玄関の奥へ消えていった。その瞬間に、夫人は夫と似た姿を発見した。ふたたび、あの不安が夫人をおそった。突然、街中で夫の視線を察知したときの恐怖である。夫人は確かめようとしたがためらった。だが、その姿は再びもの陰に消えた。落ちつかず夫人はその姿を追った。背中に燃えるような視線を浴び、珍しく緊張感がうなじに走った。もういちど夫人は振り向いた。だが、もうその姿はない。
薬局は遠くない。ひそかな戦慄を覚えながら、夫人は店に入った。薬剤師は処方箋を受け取ると調剤に取りかかった。わずかな時間に、夫人は新品の計量器具、かわいい分胴、小さなレッテル、上棚にずらりと並べられ、なじみのないラテン語の薬剤名を記したエキスなどすべてに目をやった。夫人は無意識のうちに、薬の綴りの一字一句を眼で追った。時計の音がカチカチと鳴った。独特の香りと薬剤のほんのりした甘い臭気は鼻をついた。ふと子供のころを思い出した。当時、薬局に遣いにいかせてほしいとよく母親にせがんだ。薬の匂いや、たくさんのピカピカ光る薬瓶の並ぶ珍しい光景が好きだった。そのとき、夫人は自分の母親との別れを忘れていたのを思い悄然とした。かわいそうな母を思うと夫人は痛く悲しかった。母はどんなに嘆くだろうと、夫人はうろたえた。丁度、薬剤師は透明な薬剤を大きな容器から青い小瓶に一滴ずつ入れて計量器にかけた。「死」がこの容器の中から小さいビンの中へ移されていく様子を夫人はじっと見つめた。薬はあの小瓶から次第に彼女の血管へ注入されるはずだ。すると、冷たい感覚が彼女の全身に流れる。正気を失い、一種の催眠状態に陥る。いっぱいになったビンに栓が封じられた。その恐ろしい丸い瓶の上にレッテルを貼りつける薬剤師の指先を、彼女はじっと見つめた。恐怖の思いに金銭感覚をすっかり麻痺(まひ)していた。
「二クローネいただきます」と薬剤師は言った。麻痺から醒めて彼女はいぶかしげにあたりを見まわした。すると、彼女は機械的に手を懐に入れて金を取り出した。頭の中はなにもかもまだ朦朧としていた。金を見ながら、すぐにそれとは気づかない。金の勘定が意外に手間どった。
ほんの一瞬に、彼女の腕が荒っぽく払いのけられた。同時に、硬貨がガラスの平鉢の上にカチャカチャンと音を立てた。彼女のわきに誰かの手が伸び、小瓶をつかんだのである。
思わず彼女は振りかえった。彼女の眼差しが硬直した。そこに立っているのは夫だった。唇を固くむすび、顔は蒼ざめていた。額にぬれた汗が光っていた。
イレーネ夫人は失神しそうになって、テーブルにしがみついた。街で見かけた男も、さっき門の陰でうかがっていた男も夫だったと、あらためて彼女は分かった。彼女の脳裏はすでにあのとき、なんとなく夫だということを察知していた。たちまち精神が混乱した。
「来なさい」と、絞りだすように鈍い声で夫は言った。彼女はまじまじと夫を見つめた。心の底で、おぼろげな深い意識の世界で、不思議にも彼女は夫に従順になっていた。意識せずに、彼女の足は彼についていた。
二人は並んで街中を歩いた。双方とも相手を見ようとしない。夫は小瓶をしっかり手に握っていた。はたと彼は立ち止まって、汗に濡れた顔をぬぐった。思わず彼女も足をとめた。しかし、彼女は目をあげる勇気がない。双方ともなにも話そうとしない。二人の間に往来の喧騒(けんそう)がどよめいた。
階段の前にでると、彼は彼女を先に歩かせた。だが、夫が自分のそばから離れるやいなや、急に彼女の足もとがぐらついた。彼女は立ち止まり休んだ。彼はとっさに彼女の腕を取った。腕に触れたとき、彼女は全身が震え、最後の階段を一気に駆けあがった。
イレーネ夫人は部屋に入った。その後を彼は追った。闇の中に壁面が鈍くぎらぎらして、ほとんど物の見分けがつかない。相変わらず二人はなにも話そうとしない。彼は包装を破ると小瓶の蓋を開け中味の液をぶちまけると、小瓶を片隅に激しく投げつけた。ガシャンというけたたましい音に夫人はおびえあがった。
夫婦は黙ったままだ。見やることもない。じっとこらえる夫の姿を夫人は意識した。やっと彼が彼女に歩みより、脇にぴたりと身をよせてきた。彼の苦しい息づかいを彼女は感じた。厳しい悩み深い顔つきに、目の輝きだけが部屋の闇の中に映るのを彼女は見た。いまにも怒りが爆発しそうな夫を彼女は意識した。夫の強い腕力につかまれるわが姿を想像すると彼女は震えた。だが、彼女の気持ちは落ちついていた。ただ神経だけが張りつめた弦のように震えた。体罰はもう免れまい。むしろ彼の仕打を望んでいた。しかし、彼は相変わらず口を閉じたままだ。彼の近よる歩みがもの静かな足取りであるのに、夫人は不気味な恐怖を覚えた。「イレーネ」と、彼は口を切った。その声は異様なほど優しくひびいた。「これから先、どれくらいぼくたちは苦しまなければならない?」
そのとき、急に全身が痙攣した。奇妙な意味のない動物的な叫びが、抑えきれない衝動で夫人の胸をつき破って出た。この数週間ずっと、我慢し抑さえてきた鬱積が嗚咽とともにほとばしり出たのだ。怒りの手が彼女の肝をつかみ、荒々しく揺すったのかもしれない。彼女は酩酊したようにフラフラッとその場に倒れこむところを、すばやく夫がしっかり抱きかかえた。
「イレーネ」と、彼はなだめた。「イレーネ、イレーネ」と、声がしだいに弱まり、そして優しく名前を呼びかけた。痙攣した神経は絶望的な発作をおこした。彼は愛情をこめた言葉をかけつうづけて、発作をやわらげようと思った。だが、応答する声はもっぱら嗚咽だけだ。それは全身をゆさぶる荒々しい衝動と苦痛の波であった。彼女のわな泣くからだを抱いてソファに寝かせた。だが、嗚咽はやまない。まるで感電したように四肢が嗚咽に震えた。戦慄と悪寒の波が責めさいなむ肉体を洗い流すように思えた。この数週間、彼女は耐えがたい緊張の連続だった。神経はずたずたにされ、苦悩は容赦なく無感覚な肉体の中を荒れ狂った。
興奮も極限に達していた。妻の脅えおののくからだを夫はしっかり抱いた。冷たい両手をとって、なだめようとキスをした。不安と苦悩にあばれる彼女の服をつかみ、うなじにキスをした。すると、戦慄が切り傷のように苦しむ全身に走った。とうとうせききった嗚咽の波が胸中からこみあげてきた。涙に濡れて冷たくなった妻の顔に彼はそっとさわった。すると、額に血流が脈々とうっていた。彼は言い知れぬ不安におそわれた。彼はひざまずき彼女の顔にぴったり顔を寄せて呼びかけた。
「イレーネ」と、彼はなんども彼女の手をにぎった。「どうした‥‥いま‥‥いまなにもかもが終わった‥‥どうしてそんなに苦しむのだ‥‥もう怖がることはない‥‥今後、あの女はもう二度と現れないから、決して‥‥」
イレーネのからだがピクピクピクッと動いた。彼は両手に彼女のからだをしっかり抱きかかえた。夫は、あたかも自分が彼女を殺害したかのような恐怖感とともに、拷問にかけられた肉体を引きさくような絶望感をいだいた。彼はなんども彼女にキスをし、取りとめのない謝罪の言葉をささやいた。
「いや、もう決して‥‥誓って言う‥‥おまえがこんなひどく惨めになるとは考えなかった‥‥ひたすらおまえを家に呼び戻そうと思ったのだ‥‥責任を自覚してほしくて‥‥永久に‥‥あの男と別れるように‥‥ぼくたちの家族に戻ってほしくて‥‥たまたま事実をきいたとき、こうする以外にほかの選択がなかった‥‥といっても、ぼくからおまえに言えなかった‥‥そこで考えた‥‥おまえがかならず帰る手段を考えた‥‥だから、おまえを追いたてるようにぼくはあの女をつかった。あわれな女でね‥‥実にあわれなやつで。男に捨てられて、女優だが‥‥実は、こんな役を断ってきた‥‥だが、ぼくが頼んだ‥‥それが好ましくない結果になった‥‥とにかく、おまえに帰ってきてほしかった‥‥ぼくは常々言ってきた‥‥ぼくはおまえをいつでも迎える用意があると‥‥いつもおまえを赦すつもりでいた‥‥けれども、ぼくの気持ちを分かってくれなかった‥‥だから、おまえを追い出すなんてありえない‥‥あんな姿を見るのは耐えられない‥‥ぼくは昼も夜もおまえを見守ってきた‥‥分かるだろう、ただ子供たちのため、子供たちを思えばこそぼくはおまえを脅迫した‥‥しかし、いますべてが終わった‥‥これからすべてがよくなるだろう‥‥」
その言葉はイレーネ夫人の耳元にひびいた。それは果てしない彼方からおぼろげにきこえてきた。だが、理解できない。すべてがかき消され、雑音が頭中にどよめいた。意識が混沌とし、感情はことごとく消えていった。夫は彼女の肌に密着し、接吻と愛撫を彼女は感じた。さらに、涙はすっかり冷たくなった。だが、体中に血潮が高なり、鈍くどよめく音が鳴り響いた。それは勢いよく高まり、狂った半鐘の音のようにひびいた。そのとき、彼女は完全に正気を失った。失神からうつろに醒めたとき、衣服がすっかり脱がせられていた。彼女はいく重もの雲にかすんだ夫の顔をおだやかに心配そうに見つめた。すると、彼女はまた深い闇黒へ、長い欠落した暗黒の夢なき眠りへ落ちた。
翌朝、イレーネ夫人が目をさましたとき、部屋はすっかりあかるかった。彼女は明鏡止水の境地にいた。心に一点の雲りもない。血液がしゅう雨によって浄められたかのようだ。夫人はわが身に起きたことを想い起こそうとするが、なにもかもがなお夢のように思われた。非現実的で自由奔放に、夢の空間を浮遊していたようだ。頭はハンマーでたたかれたようにしびれていた。正気に戻っているのかどうかを確かめようと、夫人はしげしげとわが手をさすった。
突然、イレーネは震えあがった。自分の指に指輪が輝いているのだ。目がすっかりさえていた。半ば失神状態で、言葉は混乱し聞こえたり聞こえなかったりした。 不安な重い気分は想念にも猜疑心にもならない。その二つの関係がいまやっと明瞭にされた。夫人は、夫の問いかけやアバンチュールの顛末などすべてを理解した。網の目がすっかり解かれて、自分が絡まっていた恐ろしい網を夫人は知った。憤りと恥辱が夫人をおそい、ふたたび神経は痙攣(けいれん)しかかった。ふと、夢のない不安のない眠りから目覚めたことがかえって悔やまれさえした。
そのとき、隣室から笑い声がきこえてきた。子供たちが目をさました。早朝にさえずる野鳥のように悦びの声をあげていた。イレーネ夫人は長男の声をはっきりと意識した。驚いたことに、その声が父親の声にそっくりなのだ。静かな微笑が夫人の口もとに漂っていた。夫人はまぶたを閉じて横になった。彼女の命となり幸せとなるものすべてを存分に享受した。心中になお痛みがうずくが、それは怪我のように熱く燃え、ゆるやかに癒やされていく快い痛みだった。
イレーネ夫人
あとがき
シュテファン・ツヴァイクを知ったのは20代のころだった。ドイツ語を理解できなかったため、ツヴァイクの心の情熱を読み取ることができなかった。この物語はイレーネ夫人の脅迫症をあつかったものです。信じるべき夫が信じられない。自分さえ信じられない。ツヴァイクは人の命のはかなさをうたった。そこに作家の死生観があった。
本書はFischer版(2005年12月発行)Stefan Zweigシリーズ中のAngstを全訳した。

