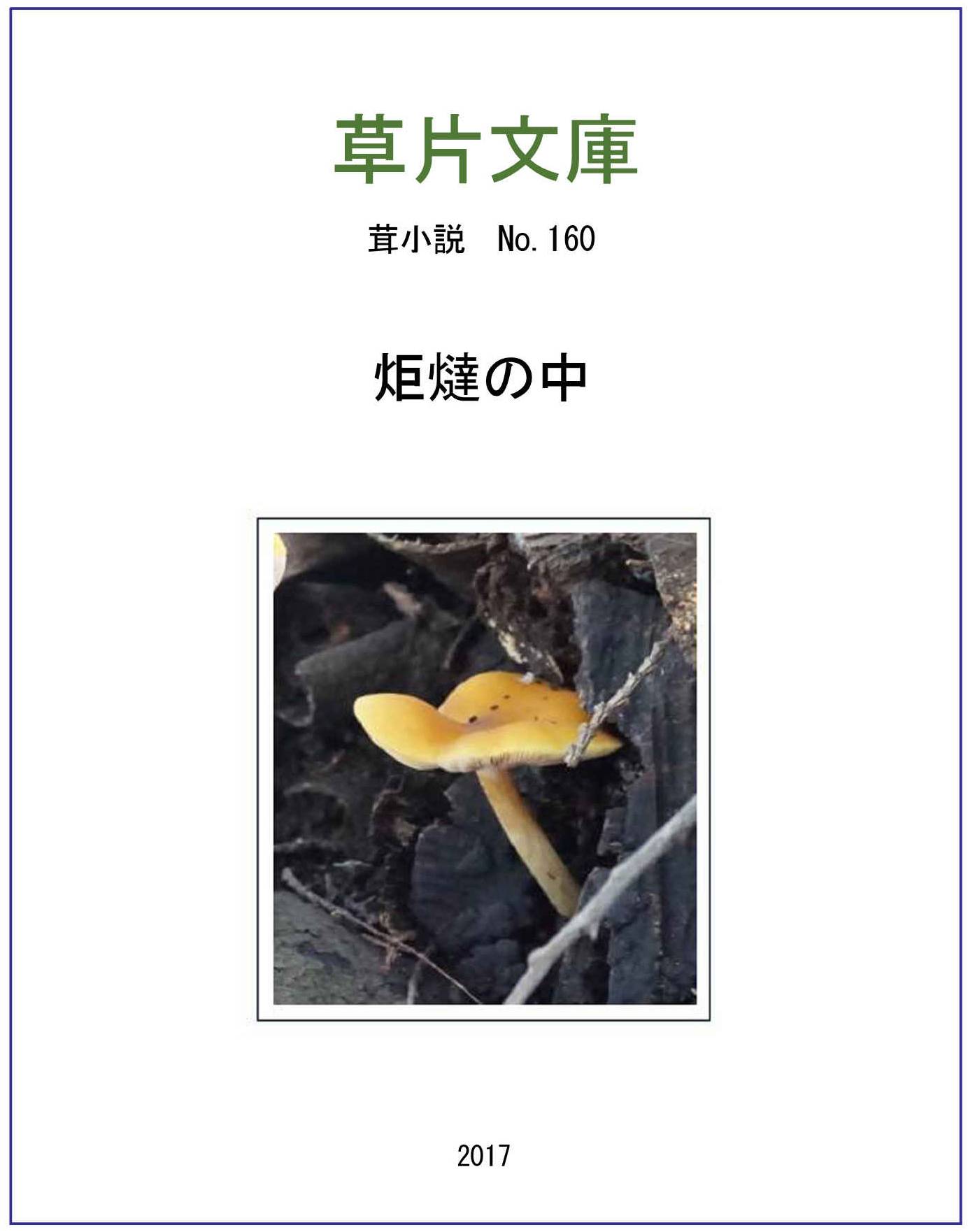
炬燵の中
東京に妻と高校受験の娘を残し、単身赴任で信州の茅野に住むことになった。茅野の蓼科湖の近くの、会社の研究所の管理部門に転勤を命じられたからである。この研究所は茸から薬を抽出する研究をおこなっている。所長は生化学者で茸の成分の分析では世界から評価されており、大学教授だったのだが、会社が引き抜いた人である。
私は法学部出身で、薬の特許だとか、海外との契約やらを担当している。管理部門の部門長として赴任した。特許出願の窓口である。研究所の副所長待遇で、この若さでと羨ましがられて本社を出てきた。
蓼科湖の近くには別荘や貸し別荘がたくさんある。部屋を借りるのに貸し別荘を当たってみたが、どれも瀟洒な作りで家賃がかなり高い。とても無理なので、地元の不動産屋をまわり、空いていた農家を借りることにした。家そのものも大きいが、庭も広すぎるくらいあって、柿の木やら、枇杷やリンゴの木までが植えてある。手入れをすればいい実がなるにちがいない。妻と娘も見に来て、夏はここで過ごすと喜んだ。
庭に面して三つの部屋がある、娘は一つの部屋を自分の部屋として独占するつもりだ。ただ冬は寒いと思われる。自分はキッチンに近い八畳を自分の居間とすることにした。どこも畳の間で東京のマンションとは足の感触が百八十度違う。
六月に赴任してもう半年近くたつ。来た当初は山歩きで山菜捜しを楽しみ、夏は涼さと快適な生活をした。もちろん娘達も夏休みを十分楽しんだ。
秋になり、家の周りにも研究所の周りにもいろいろな茸が生えた。茸の研究所を作るだけのことはある。茸に適したところである。林の中に生えている茸は食毒関係なくとても綺麗だ。茸のことをさほど知らない私も、東京ではほとんど使うことのなかった写真機を持ち出して茸の写真を撮り、それをブログにアップして楽しんだ。
研究所の研究員達は茸のエキスパートである。それだけではなく、生活の中で当たり前のように、茸の料理を楽しんでいた。私もそのご相伴に預かり、レシピを教わって自分でも簡単な料理をするようになった。といってもオムレツに茸を入れる程度である。それでも土日に泊まりに来た娘と妻にも振る舞って、ちょっぴりだが尊敬される存在になった。
九月はじめになると、空気はひんやりとして寒く感じるようになってきた。部屋ごとにエアコンがついているが、あまり大きな物ではない。夏は風通しがよかったのでほとんど使わなかった。だがエアコンだけで部屋を暖めようとすると、寒いだろう。長年この地で研究をしている研究所の人たちにきくと、石油ストーブかガスストーブが必要だという。確かに家の脇に大きな石油タンクが備えられている。だがストーブは古くなったのだろう、取り外されていてない。
家には大きな納戸がある。借りるとき、中の物はなにを使ってかまわないということだった。中を探ってみると使えそうな石油ストーブがあった。七輪や火鉢も入っている。やっぱり暖房に必要な物はそろっている。さらに小型の炬燵が立てかけてあった。電気炬燵である。炬燵用の掛け布団もビニール袋にいれられてある。とりあえずはこの電気炬燵を出しておくことにした。
東京では炬燵を使う家が少なくなった。一つには畳の間がなくなったこともあるが、やはり家の気密性が高くなり、同時にエアコンの性能の向上があげられるだろう。年輩者は子供のころに炬燵に足を入れた記憶はあるであろうし、火鉢に当たったことも少なからずあるだろう。両親の子どもの時代は掘り炬燵で、練炭の七輪が使われていたという。炬燵の中で熱くなった猫がぐったりしていて、引き上げたというようなことを親たちは言っていた。炬燵の中から引き上げられた猫は酸素不足、ぐにゃっと脇で伸びて、目があいてからもしばらくぼんやりしていたそうだ。だから部屋の換気には気を使ったものだということである。私が育ったマンションはすべて電気であった。その点、電気の暖房器具は換気の必要がなく健康にはよい。したがって私は炬燵も火鉢も知らない。結婚してから住んでいる東京のマンションに炬燵はない。
その日曜日は急に冷えた。家の中でも靴下をはいていないと足が冷たい。そこで、炬燵をつけることにした。
居間は私が住むにあたって不動産屋さんが新しく替えてくれた畳表で、いい匂いである。炬燵をテレビの前に置いてスイッチを入れた。炬燵布団をあげて中を覗くと、かなり古いタイプと見えて、赤い光が畳を照らした。赤外線炬燵である。
靴下を脱いで足を入れる。ほっこりと暖かい。
寄りかかり椅子が必要である。
納戸に行くとあった、昔風の二つに折り畳むタイプのものである。ビニール袋から出してみると、買ったばかりの物のようで、そのまま使える。
椅子によりかかり、炬燵にはいっていると、なんだかゆったりするものだ。
炬燵の上で新聞を開いた。新聞のニュースは昨日テレビでやっていたことと同じで、新しい情報はほとんどない。それどころか、トピックスまで同じことがある。読む気になるところは、気に入った人物が書いている連続エッセイくらいだろう。ここのところ落語家の小三治が昔のことを書いていて面白い。それを読むともう読むところがない。
テレビを見ると、朝のテレビドラマのあとのバラエティー風番組をやっている。
そのとき、玄関が開く音がして「神崎さん」という声が聞こえる。日曜日の朝早くから誰だろう。
行ってみると、研究所の庭を管理している寺山さんが顔をのぞかせている。
「おはようさんで」
寺山さんは地元の人で、結構な地主さんなのだが、好きで研究所の庭の管理をしてくれている。研究所の土地ももとは寺山さんのものだったということだ。もう七十近い老人だが、もともとは市役所に勤めていて、助役までやった人である。この家を紹介してくれた不動産屋も寺山さんの親戚筋の人である。
「あ、なんでしょう」
「朝、はやくすまんことです、今、山に行ったら霜降りを見つけましてな、持ってきました」
「あー、それはすみません」と返事はしたが、霜降りとやらはなんだか分からない。
「この茸、霜降り占地といってうまい茸ですよ、秋の遅い時期にでる占地です、だけどもうでてました。天ぷらだって、ゆでてそのまま酢醤油と大根下ろしなんてのもいいですよ」
彼は玄関に新聞紙にくるまれた黒っぽい茸を置いた。霜降りとは茸のことだった。
「すみません」
「初めての長野じゃ寒いでしょう、必要な物があったらいってください」
彼の家は私が借りている家からかなり離れているはずだが、と思って玄関の外を見ると、軽トラックが止まっている。山に茸採りに行った帰りのようだ。
「炬燵を出しました、お茶でもどうです」と誘ったのだが、「うちのが茸を待っているんで、すぐ帰ります、またゆっくりこさせてください」
と出ていった。ここの人たちはだれもが親切である。
霜降り占地という茸は初めて聞くが、ネットでレシピを調べようと思いながら、台所にそれを持っていき、居間に戻ってまた炬燵に足を突っ込んだ。
テレビではオムレツの作り方をやっている。
そのとき何か生暖かいぷるんとしたものが足先に当たった。
中を覗くと、足の先で赤外線に当たって赤く照っている茸が畳から突っ立っている。どうして茸がそんなところにあるのだろう、と手を伸ばして取った。手元でじっくり見ると、ずんぐりとした黒っぽい茸である。寺山さんが持ってきた茸とよく似ている。だがなぜ炬燵の中につったっていたのだろう。
ともかく、それを持ってキッチンに行き、寺山さんがくれた新聞紙の中をのぞくと、同じ茸だ。霜降り占地というやつだ。
奇妙だがともかく出所がわかった。無意識に炬燵にもっていってしまったのだろう。
PCをもって炬燵に戻った。霜降り占地をネットで調べると、占地の中でも特においしい茸とある。松茸より美味いと書いてあるものもある。
占地はどんな料理にも使うのだから食べ方は何でもいいのだろう。ただ焼くだけでも美味いとある。焼いただけで美味いということは、茸そのものに相当味があるということだ。うどんに入れてもいいとあるので夜の食材として楽しみである。
そのとき、足にふにょっと生暖かい物が触れた。またか。
布団をあげてみると、また茸が生えている。霜降り占地だ。どうもおかしい。キッチンにもっていって一緒にした。
そのまま台所から庭にでてみると、勝手に実をつけているリンゴが色づき始めている。手入れをしていないので、虫が食ったり、いびつだったりしているが、十分食べられる。妻と子供が来ると、喜んで持って帰るだろう。柿はしっかり色づいているが、渋柿なので干すか酒をちょっと浸すかしないと甘くならない。これも自分じゃやらないが、妻が持って帰って甘くするだろう。
さて今日は何をするか。
日曜日は研究所の誰かを誘ってドライブにいったりする。信州には新潟、富山とまたがって、いろいろ見るところがある。白馬、黒部、それに、糸魚川など日本海側にでるのも難しくない。天気さえ良ければちょっと行ってみることができる。もちろん近くには白樺湖もあるし、八ヶ岳など有名な山々もある。秋になって感じるのは周りの山の紅葉の美しさである。まるで絵葉書のようだ。
しかし今日はだれも時間がないようで、一緒に遊ぶ人がいない。研究員の人たちはこちらに住みつくつもりで家を買い、家族と住んでいるのだから休みはいろいろあることだろう。それで茅野の駅にでてお昼を食べ、レンタル屋でDVDを借りにくることにした。
一人でドライブにいくこともあるが、今日はあまりその気にならない。炬燵を持ち出したためかもしれない。
庭にたまった落ち葉をはくのもちょっと楽しいことである。掃いた落ち葉に火をつけて燃やすということはやったことがないので、なんとなく怖い気がして、集めた葉っぱを裏山に捨てに行く。そのあと車を出して茅野の駅に出た。予定通り、うまいそばを食べ、DVDを借りてきた。夜の飯は霜降り占地を料理してみよう。
今日は、炬燵に入って映画鑑賞ということである。借りてきたのは大昔のSF映画、未知との遭遇とスターウオーズである。どちらも私が子供のころ同じ年に封切られたものである。DVDをかけて炬燵に足をつっこんだ。おや、また足にグニョグニョしたものが当たる。気持ちが悪い。
炬燵の板をどかし、布団をはいだ。畳の上から茸が何本も生えている。
何てことだろう。畳が炬燵で温まって茸が生えてきたのだろうか。
茸をみんな引っこ抜いた。八本もあって、すべて霜降り占地だった。もらったものと一緒にした。一日じゃ食べきれないほどの量になってしまった。それにしても気味の悪い炬燵である。炬燵を脇に動かして、畳の上を見たが、茸が生えていたところは他のところと違った様子はない。
再び炬燵をもとにもどしてDVDプレーヤーのリモコンスイッチを入れた。その後は茸が生えることはなく、とうとう昼間に二つの映画を見てしまった。
台所に立つと、霜降り占地をゆでて大根下ろしと和えた。豪華な夕食だ。ビールにとてもあう。残った茸は茸そばにして食べたがこれがまたおいしかった。
次の日、研究所で寺山さんに礼を言った。
「天麩羅もうまいよ」
「天麩羅は作ったことがないんで」
「奥さんに教わっときなよ、信州はいろんな茸が生えるから、天麩羅ができるといいよ」
確かにその通りである、天麩羅を作ることができると、茸ばかりでなく、山菜、たけのこ、いろいろ楽しめる。一人暮らしをしたことがなかったので料理はからっきしだめだが、ここに来て、少しずつではあるが料理になれてきた。当然天麩羅にもチャレンジしなければもったいない。
その日、仕事が終わると、ちょっと遅くなったので、外で食事をして家に帰った。エアコンをつけたが足下が寒い。電気炬燵が便利だ。部屋の真ん中に持ってきてスイッチを押した。テレビではどのチャンネルもアメリカの大統領が日本に来ていることを報道している。都内の交通は大変だろうと思いながら見ていると、アメリカ大統領の顔が大写しになった。猿の仲間だ。そう思ったとたん、ぐにょっとした感触に足を引っ込めた。また霜降り占地が生えたのか。布団をめくってみると、霜降り占地ではない。もっと背が高く黄色っぽい茸だ。
今度は採らないで、炬燵をそのまま持ち上げ移動させた。
黄色い背の高い茸が五本、畳の上からニョッキリ立っている。立派な茸だ。
デジカメを持ってきて写真を撮った。
茸を引っこ抜いた。採った跡は少しばかりも残ることはなかった。畳の表面はまったく変化がなくきれいなものである。越してきたとき替えてくれた新しい青畳だ。
ネットの図鑑で調べると、黄金茸のようである。食べられるらしい。熱を通せば美味しい茸とある。黄金茸か、いい名前だ。茸はキッチンのかごに入れた。明日研究所にもっていって本当に黄金茸かどうか確かめよう。
脇によけていた炬燵に布団を掛け、そのまま足をいれた。するとまた足に茸らしい物があたった。のぞくと生えている。炬燵をそのまま持ち上げて床の間の前に置いた。
見ると炬燵のあったところに三本の茸が生えている。
この茸は私でも良く知っている。網笠茸だ。凸凹していてヨーロッパではとてもおいしい茸として好まれる。だがな、この茸は春に生える茸のはずだ。
電気をつけっぱなしにしてあった炬燵をもちあげた。ありゃ、もう生えている。今度は滑子である。たくさんの滑子がかたまって畳の上に生えている。
プラグをコンセントからはずして炬燵を部屋の隅に持っていった。
畳の上には編傘茸と滑子が生えている。写真を撮った。畳の上が茸の培養地になってしまったようだ。
隅に置いた炬燵の中を覗いた。茸は生えていなかった。プラグをコンセントに差し込むと赤い光が畳を照らした。布団をめくったままにして見ていた。でてきた、やっぱり畳から茸がにょきっと生えてくるのが見えた。今度は白い茸で名前はわからない。
コードをそのままにして炬燵を廊下に出した。茸は生えなかった。畳の上にしか茸は生えない。スイッチを切った。
廊下から居間を見ると、茸がにょきにょき生えている。
また写真を撮って、すべて収穫してしまった。
茸を採ってしまうと、畳は全くのもと通りである。
不思議どころではない話だ。その日は夢の中にいるような気持ちで寝床に行った。
次の朝、炬燵の茸を持って研究所にいった。研究している現場にはほとんど行くことがないが、茸のことを相談できる誰かいないか管理室に顔を出した。
「神崎さん、めずらしいですね」
研究室の管理をしている佐原さんがデスクから立ち上がった。
「研究員の人たち忙しいでしょうね」
「今、培養の様子を見に行ってますから、三〇分もすると一度戻ってきますよ」
「手の空いている人がいたら、ちょっと私のところに来てくれないか言ってください、見てもらいたいものがあるんです」
「なんですか」
「いや、昨日採った茸を持ってきているんだけど、名前を教えてもらいたくて」
「ああ、種類の同定ですね、宝田先生が得意だから伝えときます」
佐原さんは私が採ってきた茸が食べられるかどうか知りたいと思ったのだろう。
宝田さんは三十半ばの茸の研究者で、幅広い知識を持っているだけではなく、茸そのもの大好き人間で、しょっちゅう山に行って面白い茸がないか探している。
「それじゃ、お願いします」
部屋にもどって書類に目を通していると、一時間ほどしたときに、宝田さんが部屋に入ってきた。
「神崎さん、茸採ってきたそうですね」
「あ、宝田先生、すみません来て頂いて、これなんです」
彼は机の上に載せて置いた茸を見て目を丸くした。
「これ、どこで採ってきたのです、奇妙ですね、黄金茸や滑子はともかく、編傘茸は春の茸ですよ、この白いのは白鹿舌(しろかのした)ですね、みんな食べられる」
彼は一気にそういうと編傘茸を手に取った。目の近くに持っていって、いろいろな角度から見ていたが、首を傾げながら、
「天然物ですね、土は付いていないけど、春の茸だから培養したものかと思ったのですけど、違いますね」
他の物も手に取ると、
「天然物ですね」と言った。
「奇妙なことが起きたのですよ」
「編傘茸ばかりじゃなく、他の茸だってこんなに寒くなったら、そんなに生えませんよ、どこか暖かい空気でも流れているところを見つけたのですか」
「そうなんですよ、信じられないかもしれないことを言いますけど、炬燵の中に生えたのです」
「炬燵って家の中のですか」
「そう、畳の上の電気炬燵の中」
「神崎さん、冗談言ってますね、培養の床に畳を使って暖かくしたってことですか」
「うーん、そういうことになるかもしれないけど、言った通りなんだ、畳の上の炬燵の中」
彼は目を丸くして私を見た。おかしくなったのじゃないかという顔をしている。
「いや宝田さんをおちょくっているわけではないのですけどね」
「茸は採りたて本物だから、どこかに生えたってことは事実ですね、その場所を神崎さんは知っているってことですね、それは信じます」
彼は真剣な顔をしていた。
「生えているところを教えましょうか」
「お願いします」
「それじゃ、五時になったら案内しましょう」
「今じゃだめですか」
ずいぶんせっかちだ。
「就業時間中はまずいでしょう」
「ああ、私たちは研究のためなら、外出も自由です。一応、研究所長には言いますけど」
我々管理の職員とは勤務時間の認識が違うようだ。
「私はそうはいかないと思いますよ」
「所長に神崎さんも一緒に行くと言っておきますから大丈夫ですよ、培養に関するデータ収集ということで、どうでしょう、あ、神崎さんがやらなければいけない仕事があるなら仕方ないですね、すみません」
「いや、大丈夫ですけど、それじゃいきましょうか」
ということで、所長に許可をもらって、宝田さんを連れて車で家に帰った。
「神崎さんの家ですか」
「そう、借りています、単身赴任ですから」
「大きな農家ですね、きっと茸の栽培をやっていたのではないですか」
「そういえば、なにを作っていたのか聞いたことはありませんね、寺山さんの関係の不動産屋さんに借りたのですよ」
「寺山さんの関係だと茸栽培だったのに違いないですよ」
「どうしてです」
「寺山さんは、このあたりの大地主で、茸の栽培をしていた農家の総元締めだったのですから、この農家もそうだったのに違いがありませんよ」
そのような謂れは初めて聞いたが、納得できることである。
彼を私の居間に通した。畳が新しく眩しいくらいだ。
「ここに生えたわけではないでしょう」
彼が奇妙な顔をした。
私は電気炬燵を部屋の真ん中において電気をいれた。炬燵布団をめくったままにしておいた。
彼は不思議そうに見ていたが、炬燵の中で起こり始めた様子を見て仰天した。
「な、なんだこれは、茸が生えてきている」
「そうなんです、畳の上に炬燵を置いて電気をつけると茸が生えてくるのです」
炬燵の中では茸が数本大きくなってきた。
「編傘茸と黄金茸が生えている」
「廊下では生えませんでした」
「どういうことでしょう、畳に胞子があったにしても菌糸が伸びなければ茸はでない、畳の上を見ても菌糸がはびこっている様子は見えない」
「科学的に解明できますか」
「そりゃあできますよ、まさか茸の妖異現象なんてお話の中だけですから、まず、この畳を調べなければならないでしょうね、ちょっと削って持って帰っていいですか」
私は頷いた。
「その前に研究室から赤外線発生装置をもってきます。畳にかけてみましょう」
彼を研究所に連れて帰り、改めて彼は自分の車で赤外線発生装置や研究道具を私の家に運びこんだ。私も再び家に戻った。
「畳の上の物を廊下に出していいですか」
私はうなずいて、一緒に炬燵を片づけ、テレビと茶ダンスもどかして、畳の上からすべてものをなくした。
彼は廊下のコンセントに赤外線発生装置のプラグを差し込み肩にかけた。火炎放射器のような形をしているが火がでるわけではない。
「赤外線は熱くなるので、炬燵と同じ程度に調節しないと畳が焦げでしまう」そんなことを言いながら、宝田はスイッチを入れた。
八畳間全体にまんべんなく当たるように装置の放射口を動かしている。赤外線は目に見えないが、赤い光もでるようになっているので、当たっている状態は目で見ることができる。赤外線炬燵と同じである。
なにも起きない。
彼は畳の上を触ってみた。私も触ってみたが、あまり暖まっていない。もっとあげなければ炬燵と同じにならない。私はエアコンのスイッチを入れ、暖房の設定を三十度にした。炬燵は布団をかぶせてあるのでかなり温度は上がる。
彼は赤外線発生器のダイアルの数値を上げ再び放射を始めた。
とうとう出はじめた。茸たちがニョキニョキ生え始めた。それもいろいろな種類の茸が顔を出した。
「すげえ」宝田君が驚きの声を上げた。
昨日採った霜降り占地、黄金茸、網傘茸、白鹿舌は炬燵を置いたところと同じところに生えた。それ以外にも数種類が生えてきた。
私は昨日起きたことを話した。
「きっと目には見えないけど、菌糸がそこに張り巡らされているのですね」
「だけど、表面からはわからないし、新しい畳表だよ」
「畳床が古い藁床で、そこで菌糸が発達していたんじゃないですか」
「それにしても、見る見るうちに大きくなるのはどうしてだろう」
「畳床に茸をすぐ大きくする成長因子があるんですよ、それが分かると、会社も大もうけだ、赤外線で刺激されるんですな」
なるほど、たしかにそうだ。
茸は十分な大きさになった。彼は照射を止め、写真を撮り始めた。全体を撮り終えると、それぞれの茸の生えている畳の上を拭いた綿を試料瓶に入れ、茸の種類など状況を記入した。
そのとき玄関の開く音が聞こえた。
「神崎さん」
寺山さんの声だ。
玄関に行くと、寺山さんが笑顔で、
「これ、霜降り占地の天ぷら、家内がもっていけって」
器を差し出した。
「それはすみません」
「客ですかね、車があるけど」
「研究所の宝田さんが来てますよ」
「ほう、晃が来てるんかね」
宝田君は晃という。
「知ってますか」
「茸採りに行く仲間ですよ」
「いま、試料を取っているところです、ちょっと上がって見ていただけますか」
「試料ってなんですかね」
そう言って、寺山さんがあがってきた。
居間に通すと、畳一面に生えている茸を見て立ち止まってしまった。目が点になっている。
「なんかね、これは」
驚いてまともな声にならない。
「晃が生やしたんかね」
「寺山さん、驚いたでしょう、僕も驚いているんです、畳に熱をかけたら生えてきた、神崎さんが発見したんです、大変なことになりそうだ」
宝田君は生えている茸を採取し始めた。それぞれを試料袋に入れて状況を書いていく。手元の紙にはすでに畳のどこにどの茸が生えていたか地図が描かれている。
「霜降り占地まで生えているじゃないの、これみんな食える茸だ、なぜ生えたんだい、奇妙なことですな」
寺山さんはあまりの不思議なできごとに我を忘れている。
私は二人に言った。
「あちらにお茶をよういします、いらしてください」
キッチンでお茶を用意し、家内が送ってきた東京の羊羹をテーブルにだした。
二人が入ってきた。。
「おかしなことが起きて、宝田さんに相談したんです」
「不思議ですけど、かならず科学的に解明できます」
宝田君はいきごんでいた。寺山さんは考え込んでいる。
「どうしたんです」
「いや、以前この家にすんでいた人のことを思い出しましてね、水野さんていう夫婦ですけどね」
「茸の栽培をやっていた人でしょう」
宝田君が言うと寺山さんはうなずいた。
「いい茸を作っていたんだけどね、意地悪をされましてね、それで旦那は首をくくって死んじまった」
「ここで、首をくくったんですか」
ちょっと気味が悪くなった。
「いや、自分の山の中ですよ、それも二十年前になりますね、そこで椎茸のホダギ栽培をしてたんですよ、椎茸には適した風通しと、光の当たり具合のよい、いい山だった。彼の椎茸は毎年品評会で入賞をして、一度は大賞をもらったことがあるほどでしたな、ところが、隣の山の持ち主ともめていましてね。隣の山でも茸の栽培をやっていたんです。境界のことでもめていたようだけど、それは大したことはなかった。ところがね、彼の奥さんが隣の山の男とできちまった。自慢のきれいな奥さんだったね。隣の山の男は遊び人でね、きまじめな彼とは全く違うから、奥さん魔が差したんだね、言葉巧みに遊ばれちまった。奥さんの方は堅く口を閉ざしていたのだが、男が周りに自慢げにちょっとそのようなことを言ったんだ。それは広がっちまった。
彼は耐え切れなくなったんだな、とうとう首をつっちまったんだ。
奥さんが一人でこの家に住んでいたよ、茸の栽培は隣の山の男がやっていた。この家に出入りしていたようだから、一人になっちまった奥さんがその男を頼ったんだろう。奥さんは農協で働いていたな。
彼が首をくくってから十五年、奥さん一人で住んでいたけどね、ある日、毒茸に当たって死んじまった。そういうことでね、子供もいないし、今この家は新潟に住んでいる彼の弟のものでしてね、不動産屋が管理しているってわけです。
あの八畳の部屋は奥さんが使っていた部屋ですよ」
寺山さんはそんな話をしてくれた。しかし話してくれたことと、畳から茸が生えることは結びつかない。宝田も黙って聞いていた。
「ともかく、茸があそこの畳から生えるのはとても不思議なことで、畳に少なくとも菌糸がなければ茸も生えてきませんから調べます、赤外線がどのような効果なのか、とても面白いことです、原因が見つかると日本中が驚くようなことかもしれません」
宝田君の言う通りである。
炬燵から茸のでた話は研究所の者たちに詳しく話をしていない。宝田君と私、それに寺山さんの三人の頭の中にしまっておくことにした。
宝田君は彼の本業の茸からの薬物質抽出に精をだす傍ら、畳を買ってそれに胞子をつけて茸が出るかどうか調べている。
私の部屋に宝田君がきた。
「買った畳でしらべました。畳表に、茸の胞子をつけて赤外線を当てても、畳床に胞子をつけて赤外線をあてても茸ははえません」
「ということは、僕の家のあの部屋の畳じゃないとだめと言うことだな」
「そうです」
「それじゃ畳を一つもっていきなよ、新しいのいれるから」
「いいですか、それじゃ、これからもらいに行きたいのですけど」
宝田君は研究となると一途である。
彼は我が家の八畳の畳を上げ、結局そのまま研究所にもっていった。私は不動産屋に同じ畳をたのんでもらった。
その数日後である。
宝田君が報告に来た。にこにこしている。
「やっぱり神崎さんの家の畳床に胞子をまいて、赤外線を照射すると、茸がでてきましたよ、しかも調べてみると、胞子から直接茸がでてるんです、世界がびっくりしますよ、菌糸を作らずいきなり茸が出来たんです」
「でも、新しい畳だとだめなのはどうしてだろう」
「神崎さんの家の畳床には何かがしみこんでいるんです、ずいぶん古いものですから、畳床からどんな物質が抽出できるかやってみます、僕の領域ですから得意です。、その成分が胞子に何か変化かを与え、赤外線に反応して、茸を生やすようにしているのだとすると、その物質で、いろいろな茸をつくることができる」
彼の話は科学的であるが、本当にそうなったらノーベル賞ものだ。
古い畳床から物質の抽出は、なかなか進展しない、何百種類もある物質を一つ一つしらべていかなければならない。ただ胞子が茸に変化する遺伝子レベルの研究はある程度進んでいるようだ。証拠として、胞子から直接茸が生じる映像を撮影したものを見せてくれた。菌床を作らなくても、茸を直接胞子から発育させることができる証拠である。新発見であり、茸栽培の大革命になる。
その年の暮れ、妻と娘が雪の中の正月を経験してみたいと来ることになった。
初めての本格的な雪国の冬である。研究所の人や寺山さんにいろいろ教わった。野菜の貯蔵方法、寝るときの注意、その中でも暖のとりかたは気をつけなければならない。東京とはずいぶん違う。
部屋の中は石油ストーブが一番暖まる。エアコンとの併用である。ガスはプロパンなので、暖房に使うとすぐなくなるから、風呂ぐらいにしておいた方がいいと言われた。このあたりでも新しく建てられた家には最新の電気暖房設備があるのでエアコンでも十分なのだそうだ。この家は昔ながらの農家だからしょうがない。
家族が来た日は天気が良く、雪もあまり積もっていなかった。娘は夏に来た時に使った十畳の部屋がお気に入りだ。
一番奥の広い十四畳の部屋が家族が集まり我々夫婦の寝室にもなる。立派な床の間もついている客間である。テレビもそちらに移動した。大きな炬燵を買って用意しておいた。
寺山さんがつきたての餅を持ってきてくれたり、信州のおいしい酒を差し入れてくれたり、家族たちは大喜びである。東京では味わえない食べ物が口に入る。
大晦日も元旦も東京のマンションにいるときとはずいぶん違う雰囲気であった。
幸い晴の日が続き、寒さをこらえて夜に庭にでて空を見上げると、こんなに星があったのかと思うほど空一杯に星がまたたいている。星が降ってきそうだ。娘に寒いから中に入ろうと言っても、なかなか入ろうとしなかった。
昔ながらの風呂にはいり、ビールを飲みながらテレビを見る。そばを食べながら年をこした。どこからか除夜の鐘が聞こえてくる。始めての経験だ。
元旦の朝もいい天気であった。寺山さんの奥さんの手作りのおせちを食べ、何とも違った時代に生きているような気分ですごすことができた。
四日には家族が帰り、五日から私も仕事が始まる。
家族を駅まで車で送って家に戻った。
やはり一人では、八畳が居心地がいい。テレビなど日常のものを八畳にもどし、エアコンをつけて、この家にあった炬燵のスイッチをいれた。そこで思い出した。茸がでるかもしれない。しばらくすると、やっぱり足先にぐにょっとしたものが触れた。
中を覗くと、茸がたくさん生えている。茶色の茸でいかにも美味しそうである。今まで生えた茸は食べられる物ばかりであった。これもきっとおいしい茸なのだろう。夕飯に食べよう。全部採ってキッチンのザルに入れた。
もっと生えてくるかと炬燵に入っていたのだが、もう生えてこない。それで、ちょっと炬燵を移動させた。するとまた茸が生えてきた。また同じ茶色の茸である。
それもキッチンに持っていった。今日はこの茸の天麩羅でも作ってみよう。家内に天麩羅の作り方を教わった。試してみたい気分である。もう一回炬燵を移動して茸を採った。キッチンのザルの中は茶色の茸で山盛りである。
夕方、寺山さんがおせちの器を取りに来た。
「あ、おめでとうございます、美味しくいただきました、返しに行こうと思ってたんですが、すみません、家族がとても喜んでいました。ありがとうございました」
器を返し家内が持ってきたみやげを渡した。
「お子さんは楽しまれましたかの」
「ええ、夜空もきれいだし、静かだし、初めての経験です。いい暮れと正月でした、奥さんにもよろしくお伝えください」
「晃は暮れも研究所にきていたよ、彼は独り者だからね、それでやっぱりおせちを差し入れしたんだ」
「そうでしたか」
「上手くいってるようで、嬉しそうでしたよ」
「新しいことが見つかるかもしれないのですよ」
「そうだろうね、畳から茸なんて不思議だもんね」
「あ、そういえば、今日も炬燵から茸がとれました、これも美味しそうですよ」
私はキッチンからもってきて、山盛りの茶色の茸を見せた。
それを見た寺山さんの顔が緊張して、青くなったように見えた。
「か、神崎さん、それは猛毒の茸だで、捨てや、俺が捨ててやるで、」
怒鳴るような声をだして、わたしからザルをひったくった。
「これは、食える茸とよく間違えるんだ、食ってもすぐにゃ死なないが、焼け付くように手や足が痛くなって、寝ることもできない。それだけじゃねえ、酷い痛みが一月も続く、やっけえな茸だ。このあたりじゃ余り出ない茸でね、知っている者があまりいねえ、毒笹子っていうんだ」
さらにこんなことを言った。
「この家の奥さんが毒茸を食って死んだことは話したでしょう、食べた茸とはこいつのことなんだ、もう寒くなってからだったな、どこでみつけたのかわかんねえけどね、毒笹子をたくさん食っちまった、それでねあまり苦しいんで、亭主が首つった山の中に入って、走り回って死んじまった。自殺のようなものだ、それにな、その茸を、相手の男も食って、自宅で一月も痛みに苦しんで、魂が抜けてしまって、白痴になっちまった、外をふらふら彷徨って、親戚筋は困っておったな」
それから、はっと訴えるように私を見た。
「あの炬燵の中に生えた茸を食ったのかもしれねえ、神崎さんあの部屋使わんほうがいいかもしれんよ、畳全部変えるように不動産屋に言っとく」
「宝田君がたべるといけない」
私が言うと、「そりゃ大丈夫だ、あいつは茸のことはよく知っているから、もし生えても食わんですよ、だけど、これから研究所にまわってみます」
私は大きなビニール袋を持ってきて、寺山さんがもっていたザルから毒の茸を全部移した。
「そいつは、うちでもしちまうで」
「すみません、何もかもありがとうございました」
寺山さんは、毒笹子の入ったビニール袋と空いたおせちの器を持って車にもどった。
私は八畳にもどると、炬燵のプラグをぬいた。炬燵布団を片づけると、炬燵の足をはずし、納戸にはこんだ。元のようにビニール袋に入れるとしまった。
八畳に戻ると宝田から電話があった。
「おめでとうございます、さっき寺山さんがきました、毒笹子が出たんだそうですね、僕のほうではでていませんので大丈夫です。胞子から直接茸が出ることはうまくいきそうです、今年もがんばります」
「おめでとう、それはよかった、こちらこそよろしく」
彼のほうは問題なさそうで、よかった。だが、炬燵のことは頭がもやもやする。
この部屋で、この炬燵の中で、この家の主人だった男の妻の足が、憎んでも有り余る男の足と触れ合う。そんな場面が目の前に浮かぶ。それをもし主人が見たらどう思う。主人の使っていた炬燵だって何か感じたのじゃないだろうか。まさかとは思う。炬燵の中に食べられる茸を生やし、次に知られていない毒茸を生やす。これも食べられると思いこんだ人がそれを食べて苦しむ。
そんなことがあるはずはないとは思うのだが、頭の隅っこでは、なにかうじうじと科学では説明できない気味の悪いものが渦巻いている。
新しく買った大きな炬燵を八畳に運び込んだ。
炬燵の中
私家版第十四茸小説集「茸耳袋、2023、269p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平2015-10-19


