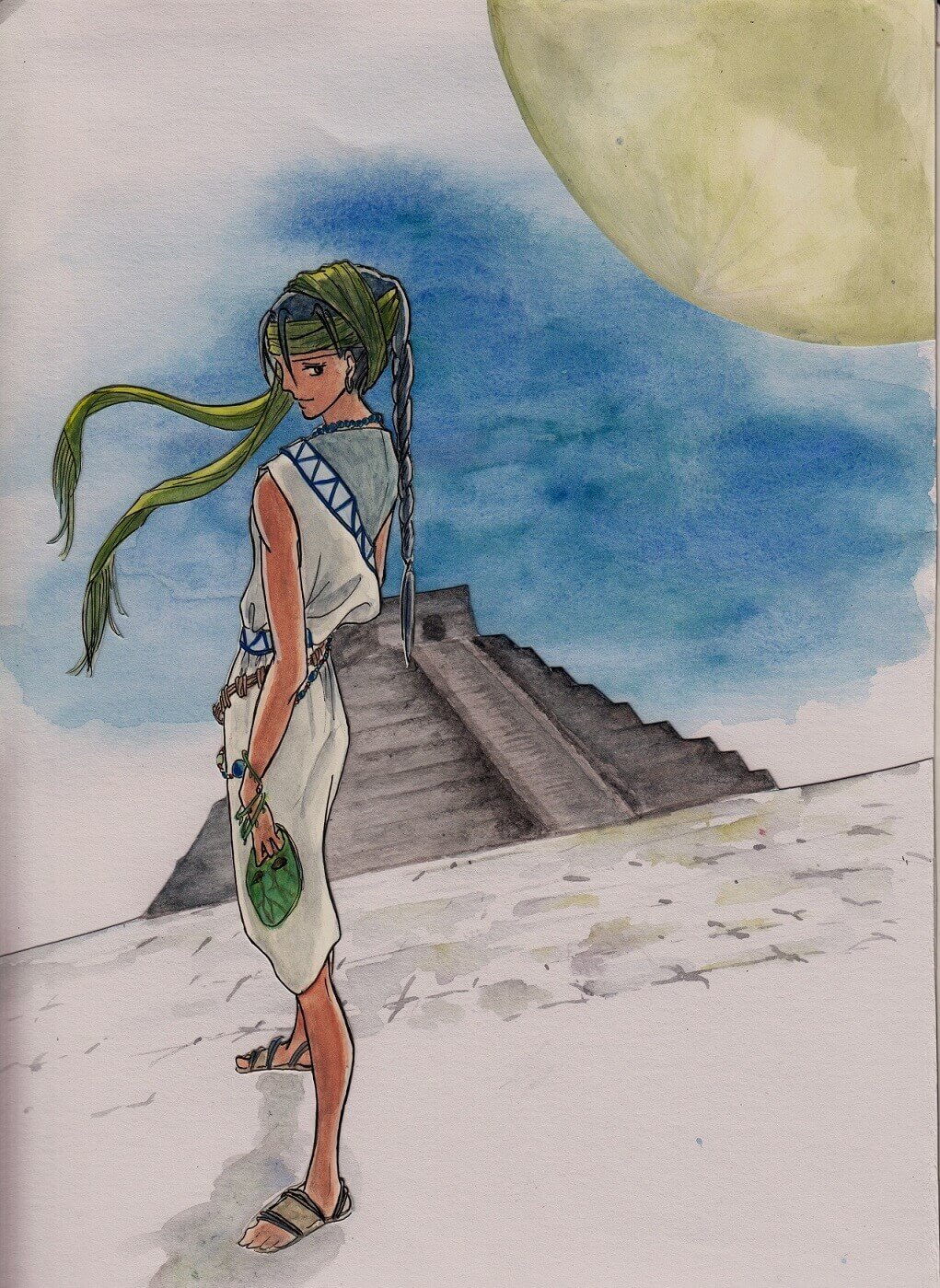
君の声は僕の声 第六章 8 ─玄室─
玄室
聡と櫂に気づいた瑛仁が、立ち止まってふたりの足もとを照らしてくれた。足もとが良く見えるようになったのはいいが、同時に転がったしゃれこうべと目が合う。どれも口を大きく開けていて、その顔は恐怖に叫んでいるようにも見える。
思わず身震いした。
聡が、顔を青くしながらぎこちない笑顔を瑛仁へ向けると、瑛仁はふたりの後ろへと回った。瑛仁の照らす灯りは、数メートル先まで転がる白骨を浮かび上がらせた。聡は思わず櫂の腕にしがみついた。櫂が身体を震わせたが、笑う余裕もなく、ふたりは骨を避けながら、足早に前を行く秀蓮に追いつこうとした。
「なあ、こいつら、おかしくないか?」
「えっ?」
櫂の問いかけに聡は思わず足もとに目をやった。櫂がこいつらと言ったのは転がっている骨の事だ。ふたりが立ち止まると、瑛仁もふたりの足元に光を止めた。瑛仁はしゃがみこんで人骨を調べた。
「これは……燃えた跡だな」
瑛仁が骨に残された繊維をつまみながら言った。
「それから、これ」
櫂がつまんだのは、人骨に残された布。色褪せてはいるが、みな同じように赤い布だ。瑛仁が周辺を照らす。同じように焼け焦げ、色褪せた赤い布が、骨の隙間に散乱していた。
先を行く秀蓮の照らす灯りは、呼鷹のかがんだ背中と通路両脇の壁を照らしていた。しばらく歩くと壁が途切れた。呼鷹の伸ばした背中だけが見える。足もとに骨はなくなっていた。
天井が高くなり、呼鷹は広い空間に出たようだった。秀蓮もその後に続いて空間に足を踏み入れた。
「ここは……」
最後に入ってきた瑛仁の声がやたらと響く。
懐中電灯を手にした三人は声も無く壁や天井を照らした。その灯りを目で追う聡と櫂は声にならない声を上げて天井を見上げた。
部屋はドーム型で天井は高く、すべてに繊細な模様が描かれ、何色もの鮮やかな塗料がいくらか残っていた。塗料がすべて残っていたら、素晴らしく美しい部屋であったと誰もが想像できた。
天井から正面へと灯りを移す。人ひとりが横たわれるくらいの、綺麗に削られた石の箱が置かれているのが浮かび上がった。灯りを持つ三人はゆっくりと石箱の輪郭に沿って灯りを当てた。三人の手が止まる。見ていた聡と櫂の目も止まった。
誰かの喉がごくりと鳴る。
石の箱を囲むように、ここにも人骨が並んでいた。並んでいる、というより、手を取り合うように背もたれている。
呼鷹が骨に灯りを当てながら近づいた。しゃがみ込んで灯りを当てて骨を調べている。
「子供の骨だな」
瑛仁は手を合わせて目を閉じた。
「生贄?」
聡が歩み寄る。
「いや、生贄ならこんな何もない床の上に並べたりしないだろう。もっと丁寧に埋葬されるはずだ」
呼鷹が骨を撫でるようにして応えた。
「僕たちと同じくらいの少年だ」
秀蓮がそう言うと、瑛仁も呼鷹もそれには返事をしなかった。
沈黙のなか、遠くから声が届く。
「透馬だ」
櫂が来た道を振り返った。
「四人を呼んで来よう」
呼鷹が立ち上がる。「おそらくこの部屋に、遺跡へと続く地下通路への入り口があるはずだ」
そう言って呼鷹は瑛仁を連れて四人を呼びに部屋を出て行った。
残った三人は薄暗い部屋の中、秀蓮の持っている懐中電灯ひとつの明かりで、壁伝いに手探りで入り口を探した。だが、何も見当たらない。天井から床まできっちりとすき間なく石が埋め尽くされてる。そうするうちに青い顔をしてフラフラと歩いている麻柊たちを連れて瑛仁と呼鷹が戻ってきた。
「何かあったか?」
そう言って入ってきた四人は、照らし出された石箱を前にして立ちすくんだ。今通ってきた通路に転がっていた骨よりも小さくて細い。
「これは、棺だね」
秀蓮は骨を避けながら近寄り、棺の蓋をなぞるように触れた。
棺の蓋には、入り口の扉に掘られてあったものと同じ、絡み合った二匹の蛇が掘られている。みんなも吸い寄せられように棺に近づいた。
ここは初代帝の陵墓だ。そして棺。この中にあるものはただひとつ。
みんなは棺に手を当てた。棺の蓋は思いのほか重い。蓋を持ち上げることはせずに、少しだけ浮かすようにしながらずらしていく。
「あっ……」
少年たちの口から思わず声が漏れ、手も止まった。
「空だ……」
誰かがつぶやく。
灯りを持つ三人が棺の奥を照らした。浮かび上がったのは綺麗に削られた棺の底。何かが入っていた形跡もない。呼鷹はさらに頭を突っ込んで棺の中を探ると、声を上げて何かをつまみ上げた。少年たちは呼鷹の指を見つめたが、何も見えない。
「ほら、よく見て」
呼鷹がつまんだものを手のひらに乗せて見せた。
「髪の毛?」
少年たちがのぞき込む。
「おそらくね。──繊維かもしれないが……」
呼鷹がもう一度じっくり見つめて言った。そしてポケットから布を取り出し、丁寧に包んだ。
「盗掘されたのかな?」
流芳が誰にともなく訊ねた。
「そこらへんに骨が転がってるのに、なんで肝心の棺が空なんだ? それにこの部屋──」
櫂が振り返る。
壁の装飾の豪華さに比べて、部屋の中には何もない。この棺と思われる石の箱がぽつんと置かれているだけだった。副葬品も何もない部屋。
「この石の箱は棺なのかな?」
そんな声が上がる。言われてみれば棺にしては少し小さい気がする。
「大昔の人間は、俺たち現代人より小さいんだろ」
麻柊がぶっきらぼうに言った。
「これは何だろう……」
聡が棺に顔を近づけ、指で棺をなぞる。そこには筆でなぐり書きしたような、薄い黒い染みが重なっていた。それは蓋や棺の角に多く見られ、大小不規則にあちこちに染みになり、棺に描かれた模様とは言い難かった。
「…………」
誰も応えられない。
「本当にこの部屋から地下通路に出るの?」
聡がいぶかしげにあたりを見回す。
「地下通路?」
顔を上げた透馬に呼鷹が答えた。
「ああ、この部屋から遺跡へ行けるはずだ……どこかに入り口があるはずだよ」
「どこか。って、なんだよそれ。壁には入口なんてないぞ。なんで肝心の事が書かれてないんだよ」
櫂がいらついて言った。
「それなんだよな……」
呼鷹がぽつりと言う。それは呼鷹も思っていた事だった。大伯父の遺した書物には、遺跡は初代帝の墓から地下通路を抜けた先、としか記されてはいない。通路への入り口も遺跡の正確な場所も記されてはいなかった。 考えながら呼鷹は壁に灯りを当てた。三つの懐中電灯だけでは部屋中が照らし出されるほどの明かりにはならない。暗い部屋の中で、みんなが壁を探り始めるなか、聡が目をキョロキョロさせながら、手をかざしていた。
「どうした?」
聡の奇妙な行動に秀蓮が声をかけると、聡はかざした手をゆっくりと動かしながら「空気が動いてる」と、つぶやいた。
「風……とまではいかないけど、空気が動いているように感じたんだ」
瑛仁が聡の手もとを照らした。
聡はかざした手を足もとへと移す。
「ほら、感じる」
聡が床に伸ばした手をピタリと止めて秀蓮を見上げた。
秀蓮も同じように床に手を伸ばした。
「!」
秀蓮が何かを感じて聡に目を向けた。
聡が勢いよくうなずく。
「この棺の下だ!」
聡の自信に満ちた声が玄室に響いた。
「この棺の下に、秘密の抜け道があるんだよ」
かがめていた上半身を起こして聡はきっぱりと言った。自分の言った言葉に確信を持ってうなずく。
「ほら、見て。床の傷。きっと棺を動かした時に出来たものだよ。調査をした時にも一度動かしているはずだ」
秀蓮はゆっくり立ち上がると棺にそっと手を添えた。棺に目を落とし、おもむろに口を開いた。
「もしかして、この骨は……。地下通路を棺で塞ぐために、ここに残った少年たちの骨なのかもしれない」
その言葉に少年たちは秀蓮から棺へ、そして棺の周りの少年たちの骨へと視線を移した。聡が棺をなぞりながら、秀蓮に応えた。
「僕たちが通ってきた通路に転がっていた、あの骨の奴らから守るために、この棺に眠っていた初代帝の遺体を、地下通路を通って遺跡へ運んだ……そして、地下通路への侵入を防ぐために、この少年たちがここへ残り、地下通路への入り口を棺で隠した──」
聡が「そういうことだね」と訴えるように秀蓮を見つめた。
秀蓮がゆっくりうなずく。
「手を取り合うように寄り添っているのは、もしかしたら呼鷹の大伯父さん達が、調査を終えて棺を元に戻した時に、この少年たちに敬意を表したのかもしれないな」
秀蓮の言葉に呼鷹が続けた。
「そうか……。だから通路への入り口を、あえて書き残さなかったのか──」
みんなは神妙な顔で、棺の周りの骨を見つめた。少年たちは棺を守りながら、お互いに寄り添うようにして息耐えたのかもしれない。
少年の骨は七体。
「たった七人でこの石でできた重い棺を動かしたっていうのか?」
透馬が、信じられない、というよりは七人でやるしかなかった少年たちを想うように言った。
「ここに骨が残っているということは、棺を動かして力尽きたのか、それとも死ぬまでここを守り通したのか……」
櫂はそう言って黒い染みを手でなぞりながら口を固く結んだ。黒い染みの正体は少年たちの『血』だ。
血を流しながら、この重い棺を動かしたのだ。誰も口にはしなかったが、みんなそうとわかって目を伏せた。瑛仁と透馬は祈りを捧げるように目を閉じていた。
「そんな顔してないで、さっさと棺を動かしたらどうだ?」
みんなが少年たちに想いを馳せていた静かな空気を破るように、杏樹が高慢に言い放った。
君の声は僕の声 第六章 8 ─玄室─

