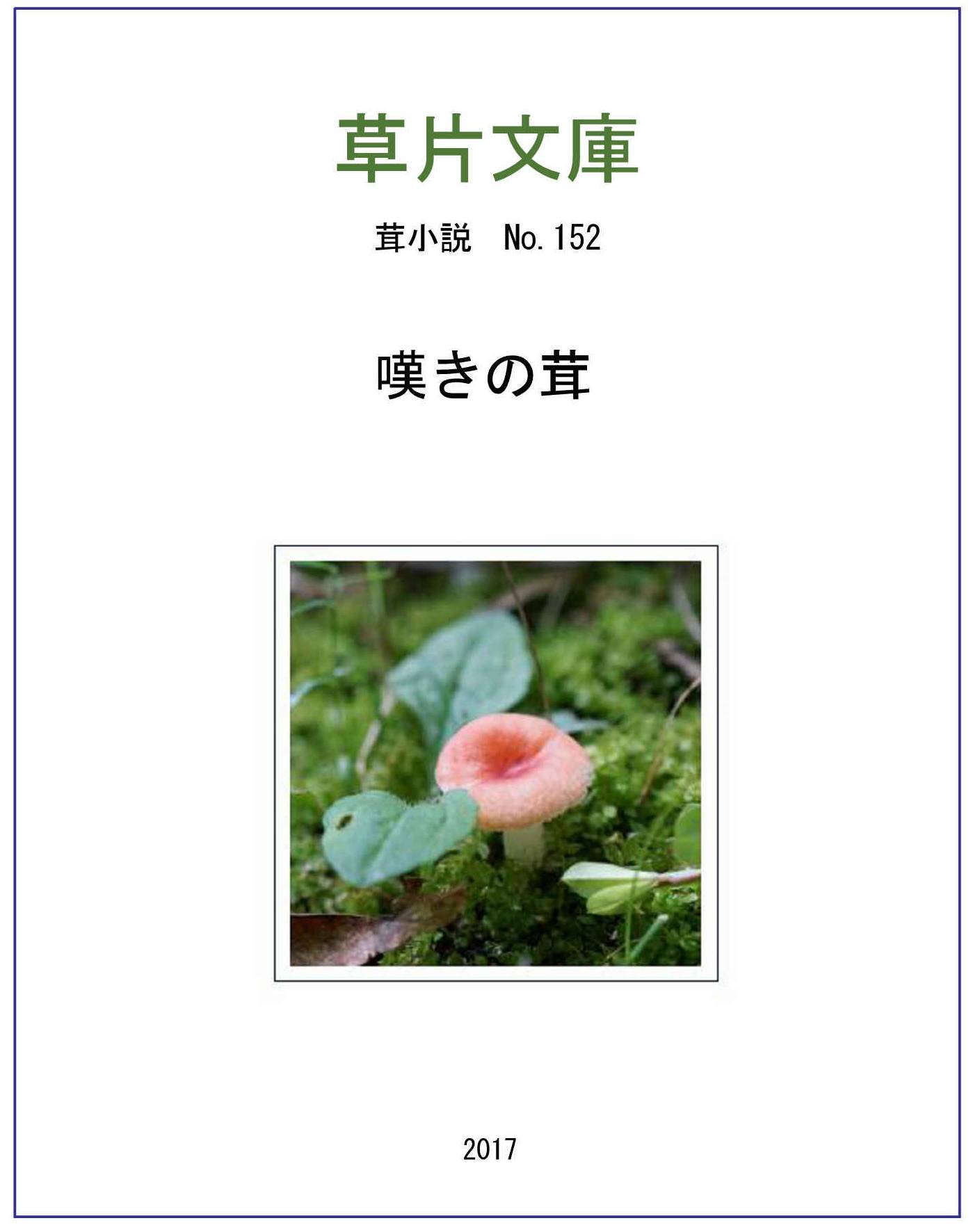
嘆きの茸
羊歯の葉の下にぽちっと白い糸くずのような物が見えた。百足がその上を通り過ぎ、白い糸くずをいくつかの足で踏み潰した。
「茸殺すにゃ刃物はいらん、お日様二日も照ればいい、てけてん」
などと歌いながら、いっちまった。ここのところ雨が降らずに、なかなか茸が生えてくることができない。白い糸くずは菌糸である。
それでも次の日から二日ほど雨が降った。
夜中、白い糸くずから、赤い頭がでてきて、土を持ち上げた。茸の子供が頭をだしたのだ。
「ほい、ここには赤い茸の赤ん坊だよ」
二匹の座頭虫が茸を跨ぎながら通っていく。
茸の成長は早い、明け方、見目美しい、若い女子の赤い茸が、羊歯の葉の先から落ちる露の滴を浴びている。
「気持ちがいいわ」
そこに、女郎蜘蛛が羊歯から降りてきた。
「おんや、なかなかいいスタイルだね」
赤い茸は女郎蜘蛛をちろりと見ると、
「黒と黄色は目立つわね、赤も混じっているじゃないですか、なかなかね、でもあたいにはかなわない」
「生意気な娘っこ茸だね、お前さん今だけだよ、そんなことを言っていられるのは」
女郎蜘蛛は、そう言ってまた羊歯の上に戻っていった。蜘蛛の巣を張るにはあまりよいところではなかったようだ。
朝日が林の中に筋をなして射してきた。
「あら、いやだ、日焼けするじゃない」
赤い茸は身をよじったが、動くことはできない。だが、この程度の日差しはそんなに悪い気持ちにはならない。
そうこうしていると、赤い茸はもっと伸びて、羊歯の葉より背が高くなった。赤い茸はあたりを見渡した。
マムシ草が赤い実をつけてつっ立っている。
「あんたの赤は朱色だね」
赤い茸は声をかけた。
マムシ草はうなずいたが、返事をしなかった。赤い茸がなにを言いたいのかわからなかったからだ。
「あたしは真っ赤よ」
マムシ草は、そりゃわかっていると、これにも返事はしなかった。
「私のほうが本当の赤よ」
赤い茸が自慢げにいうものだから、うるさくなったマムシ草は、
「あたしの花の色は紫よ、高貴な色よ、これは花の後にできた実」
赤い茸は実という物を知らなかった。マムシ草と赤い茸の様子を見ていた野菊がマムシ草に向かっていった。
「茸と植物は違うのよ、茸に実といってもわからないよ」
マムシ草は「ああ、そうだったのね」と、納得し、
「赤い茸の娘さん、明日になれば、胞子を作るでしょう、実の中に種があり、それは胞子のようなものよ」と説明した。
若い赤い茸はそういわれたが、胞子というものすらまだわかっていない。
そこにばさばさと、カラスが降りてきて、マムシ草の赤い実を折りとってもっていってしまった。
赤い茸は驚いて「どろぼー」と叫んだのだが、野菊が笑った。
「あのね、赤い茸の娘さん、あれでいいのよ」
「どうして、もっていっちゃったじゃないの、食べられちゃうでしょ」
「カラスはマムシ草の実は食べないのよ」
「どうして、とったの」
「黒いカラスは赤い色が好きなのよ、どこかで捨てるでしょう」
「私も赤いのに、もって行かれなかった」
「あんたさんは、きっと、毒キノコよ」
「マムシ草の実だって捨てられたら困るでしょ」
「そこで、実の中の種からまたマムシ草が生えてくるのよ」
それを聞いていたマムシ草は、
「赤い茸のお嬢さん、あんたさんは意外とやさしいね、ありがとよ」
と笑った。
林の中がだんだんにぎやかになってきた。いろいろな虫や鳥が動き出したのだ。
赤い茸はなんだか眠くなってきた。あたりがぼやけてきて、とうとう寝入ってしまった。
お昼過ぎになると、大人になった赤い茸が目を開けた。体がなんだかこそばゆい。気持ちが悪いと自分を見た。
柄のところに茸虫が食らいついていた。茸虫は赤い茸をうまそうにくちゃくちゃかんだ。
赤い茸は身震いした。
「やだ、やめなさい」
赤い茸が大声を出しても、無視をして虫は食い続けた。
そこに、蛇の子供がやってきて、茸虫に食らいついた。
蛇の子供は茸虫をごくりと飲み込むと、舌をちょろちょろ出して口の周りをきれいにすると、ニョロニョロ林の奥にうねっていった。
赤い茸はほっとしたのだが、ぼやいた。
「みてごらん、この足下を、この真っ白な足に、こんな傷をこさえちまって、あたしゃ、あいつが憎いったらありゃしない」
話し言葉が、ちょっと姉さん風になっている。少し大きくなったのだ。
いつの間にか隣に黄色い茸が育っていた。
黄色い茸はなぜか世の中をよく知っている。
「どっちみち、明日になりゃあ、頭にはしわが寄り、その白い足だって、茶色の筋が入ってくるじゃないか」
「今日一日が大事じゃないの、あの虫の奴、なんとかしちまいたい」
「そういったところで何にもできない、あきらめるのが肝心、そういやあ、蛇がもってったじゃないか、もう飲み込まれて糞になってら」
そこに、金蠅が飛んでくる。
「ちょいと、金蠅のお兄さん、あたしの足を齧った馬鹿虫を知ってるかい」
金蠅は茸の前に生えている羊歯に止まると、
「知らないねえ」と手で頭を洗った。
「ほら、みてごらんよ、あたしの白い足に穴を開けちまった」
「おや、かわいそうにねえ」
「お兄さん強そうだねえ、その、きんきらした膨らんだ腹、なかなか立派じゃないか、強いんだろう、あの虫の仲間を見つけたら懲らしめてくれないかい」
「そりゃいいけどね」
金蠅は羊歯の葉から地面の上に降りると、赤い茸の足下に近寄った。
「穴があいちまってるね」
「全く、あの茸虫ったら、こういう悪さをするんだからいやよね」
金蠅は見上げると、「いい穴をあけちまったね」
なぜか赤い茸の柄にのぼり始め、柄の穴のところに尻をつっこんだ。
「こそばゆいじゃないか」
赤い茸は身をよじった。といっても、動く訳じゃない。
黄色い茸が金蠅に「およしよ、そんないたずらは、赤い茸がくすぐったいって言ってるよ」、そう言ったのだが、金蠅は、赤い茸の穴の中に尻から白い小さな玉をころころとひりだした。
「なにしてるのさ」
それを見ていた黄色い茸が「卵を生んでるよ、この金蠅は、雄じゃないんだ」
そう言ったら金蠅は、
「あたしゃ、雌だよ、それに確かに金色だがね、金蠅じゃないのさ、茸蠅」
と、飛んで行ってしまった。
「あああ、もうだめ、卵がかえったら、あたしの体は茸蠅の子供らに舐められ、吸われ、齧られ、めためたになるのよ」
「その前に、早く傘を開いて、胞子をまきなさいよ」
黄色い茸が言うのだが、そうおいそれといくものではない、明日か明後日にならないと、饅頭型の赤い傘は開いてくれない。
赤い茸ががっかりしていると、百足が歩いてきて、赤い茸を見上げた。
「きゃ、百足がきた」
赤い茸にとって、踏んだり蹴ったりだ。百足の奴はじょろじょろ周りを歩いている。なにをするでもなく、歩き回るのは気色が悪い。
「気持ち悪いいいい」
赤い茸が悲鳴をあげると、百足は白い柄のところにとっついて、上に上ってきた。
赤い茸は身震いをしているのだが、動かないので振るい落とすことなどできない。
頭の上に上ってくると、なぜか八回も頭の周りをまわって辺りを見回す。
「なにしてるのさ」
赤い茸はだいぶ我慢をして百足に聞いたのだ。
「いやなに、なかなかいい景色だから、このあたりで、糞でもしようと思ってな」
「なに言ってるのさ、あたしの頭の上に糞などしないでおくれ」
「この赤い色が腹の辺りにチクチク感じられて、たまっていた物がでそうだ」
「なんだいそりゃ」
「昨日でかいゴキブリを食ったんだ、うまくてね、みんな食べちまった。だけど、便秘になったんだ、うんちがでない」
「だけど、あたしの頭の上はやだよ」
「あ、でそうだ」
大きな百足は赤い茸の傘の上で立ち上がった。うーんと気張ると、ちっこい丸っこい黒いうんこが、ころっとでた。
「お、でた」
百足は、傘の周りを歩き始めた。
「でるでる、ほら、でるでる」
そういいながら、百足は黒いころころうんちをひりながら、八回回った。
「オー、気持ちがよかった」
そういって、ぴょーんと、羊歯の上にとび移った。とび百足のようだ。
「やっと行ってくれたね」
赤い茸はほっとしたのだが、赤い傘の上には黒いぽちぽちの模様がくっついてしまった。そこに藪蚊が飛んできて、「黒いぽちぽちの、赤い茸さん」と、声をかけてきた。
また嫌な奴が来た。
「あたしの傘に黒いぽちぽちなどないよ、きれいな赤だよ」
「いやいや、黒い点々模様があるじゃないの」
「そんなはずはないけどねえ」
そこで百足がうんちをしたのを思い出した。
「百足のうんちがついているのかもしれない」
「これが、百足のうんちかい、あんたの、生まれつきの模様かとおもったよ」
赤い茸は傘にうんちまでついて、がっかりした。
「ところで、あんたはなにしにきたの」
「血の匂いがするので飛んできたんだよ」
「血が出る奴なんていないよ」
ところが、茸が足下を見ると、赤鼠が柄に齧りついていた。
「やめとくれ、たおれちまうじゃないか」
藪蚊は、ほら血がいるじゃないかと、赤鼠の耳に吸いついた。かゆくなってきた赤鼠は、茸を齧るのをやめると、後ろ足で耳をかいた。蚊は飛び上がると、今度は鼻の頭に吸いついた。あわてた赤鼠は羊歯の間を走って逃げた。
「助かったね」
赤い茸は少しばかり藪蚊に感謝をした。
それでも柄の一部が齧り取られてしまった。
そんな様子を見ていた黄色い茸は、もっと未来がわかっていた。
「おれたちゃ、茸だろ、他の生き物にやられる前に、お仲間にやられちゃうさ」
「なにさ、それ、茸が茸に悪さするっていうのかい」
赤い茸には理解できなかった。
「茸は菌類だ、菌類はこの星に空から、山から、土から、地下から、海から、みんな入り込んでるんだ、ご主人様だ、我々茸も、自分の仲間に滅ぼされるんだ」
そう言っていると、赤い茸の柄の窪みで、茸蠅の卵がかえった。
孵ったウジ虫は穴の中から、しゅろしゅうろと茸の柄を食べて中に入っていった。
「なにするのさ、こら、外に出なさい」
赤い茸がいくら叫んでも、蠅の子供たちが言うことを聞くわけがない。何せ茸はうまいのだ。
赤い茸の体に入ったウジ虫は、しゅろしゅろと、茸の中を食べながら動き回った。しばらくすると、ウジ虫はおとなになり、茸蠅になって飛んでいった。
赤い茸の柄は穴だらけだ。そこに黒っぽい物がとりついた。目に見えない、その黒い物は赤黒く変化すると、トロトロと赤い茸を溶かしはじめた。
「やだー、なんとかして」
黄色い茸はそれを聞いて首を横に振った。
「さっき言ったろう、菌がついたのだよ」
「気持ち悪い、痛くもかゆくもないのよ」
「それならいいじゃないか」
「いや、だから気持ち悪いのよ、私の体どうなるの」
赤い茸に、赤黒い筋が体中に入り込んだ。
茸の好きな鼠が友達をつれてきた。
「おい、遅かったな」
一匹がそう言っている。
「たしかにな、こんなにとろけちゃうまくない」
二匹の鼠はそういって通り過ぎて行ってしまった。
赤い茸は、赤黒くなりぬるっとしてきた。
ナメクジがきた。
「あ、やだ、ナメクジくるな」
茶色の大きなナメクジは「うまそうになったな」と言いながら、赤い茸のとろけ始めた付け根のところをジョロリと舐めた。
「嫌だ、気持ち悪い」
赤い茸が叫んだが、ナメクジは知らん顔だ。
「ふむ、いい腐り具合だ」
ナメクジは柄をなめながら登りはじめ、赤い傘の上にはいずりあがった。
にゃろにゃろと傘を舐めると、赤い傘に茶色の跡がついた。
「なめくじ、やめろ、そこに百足の糞が付いているぞ」
ナメクジは赤い茸がしゃべったので怒った。
「飯は静かにしてろ」
「おまえこそ五月蠅いわ」
どうも年取ってきた赤い茸はヒステリー気味だ。言葉も乱暴になった。
「もっと食ってやる」
ナメクジは赤い茸の傘を半分食ってしまった。
「まだ、胞子を出してないんだ」
「そんなこと知るか、どっちみち胞子はできないさ、なにせ、もうたくさんの菌がついているからな」
赤い茸はちょっと前までしゃきっと、それはきれいに立っていた自分を思いだしていた。とうとう胞子はつくれないのだろうか。
ナメクジはゲップをして茸を降りていった。
「全部食べられちゃうかと思った」
赤い茸は隣の黄色い茸に声をかけた。返事がない。
ふと気がつくと、隣の茸がいない。下を見ると、なんと、付け根だけ残っている。
そばに大きな茶色の物がころがっている。やっぱりナメクジだ、倍の大きさになっている。
ナメクジの舌なめずりってしっているかい。猫の舌なめずりは絵になるが、全くみっともない。ナメクジの奴、口の周りをべろべろなめてやがる。
「黄色い茸は旨かったよ」
ナメクジが赤い茸がながめているのに気がついた。
「黄色い茸に気がついたので、お前さんは半分しか食べなかったんだ、黄色い茸の美味いこと、よかったよ」
ナメクジが黄色い茸を全部食っちまったんだ。
そこに蝦蟇蛙がやってくると、太ったナメクジをぺろりと飲み込んじまった。
「ざまあみろ」
赤い茸は黒っぽく溶けながら毒づいた。半分になってしまった傘が、全部とろけるのは時間の問題だ。
夕焼け空だ、明日も晴れるのだろうか。
冷え冷えとしてきた。こうなると、溶けるのはちょっと遅くなるのだろうが、それにしても、朝にはなくなっちまう。さみしいなあ、と赤い茸が沈んでいると、ほとんど溶けている傘の下の襞の一つに、ぽつりと赤い点ができた。
赤い茸は頭がちょっと熱くなった。
何だと思っていると、その赤い点が、風に吹かれて、赤い茸から離れた。
その一瞬、赤い茸は気持ちが良かった。
赤い茸は、とろけながら、空中に浮かんだ赤い点をみた。
「胞子だ」
思わず赤い茸は、声を出した。そして、そのまま、黒くトロトロと溶けてしまった。
しかし、そのせつな、赤い茸は幸せだったに違いがない。たった一つだが、胞子を作ることができたのだ。
赤い胞子は、風に揺られて、しばらく、林の中を漂っていたが、いつの間にか消えていってしまった。
これが、赤い茸の一生である。
嘆きの茸
私家版第十四茸小説集「茸耳袋、2023、269p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2018-9-5


