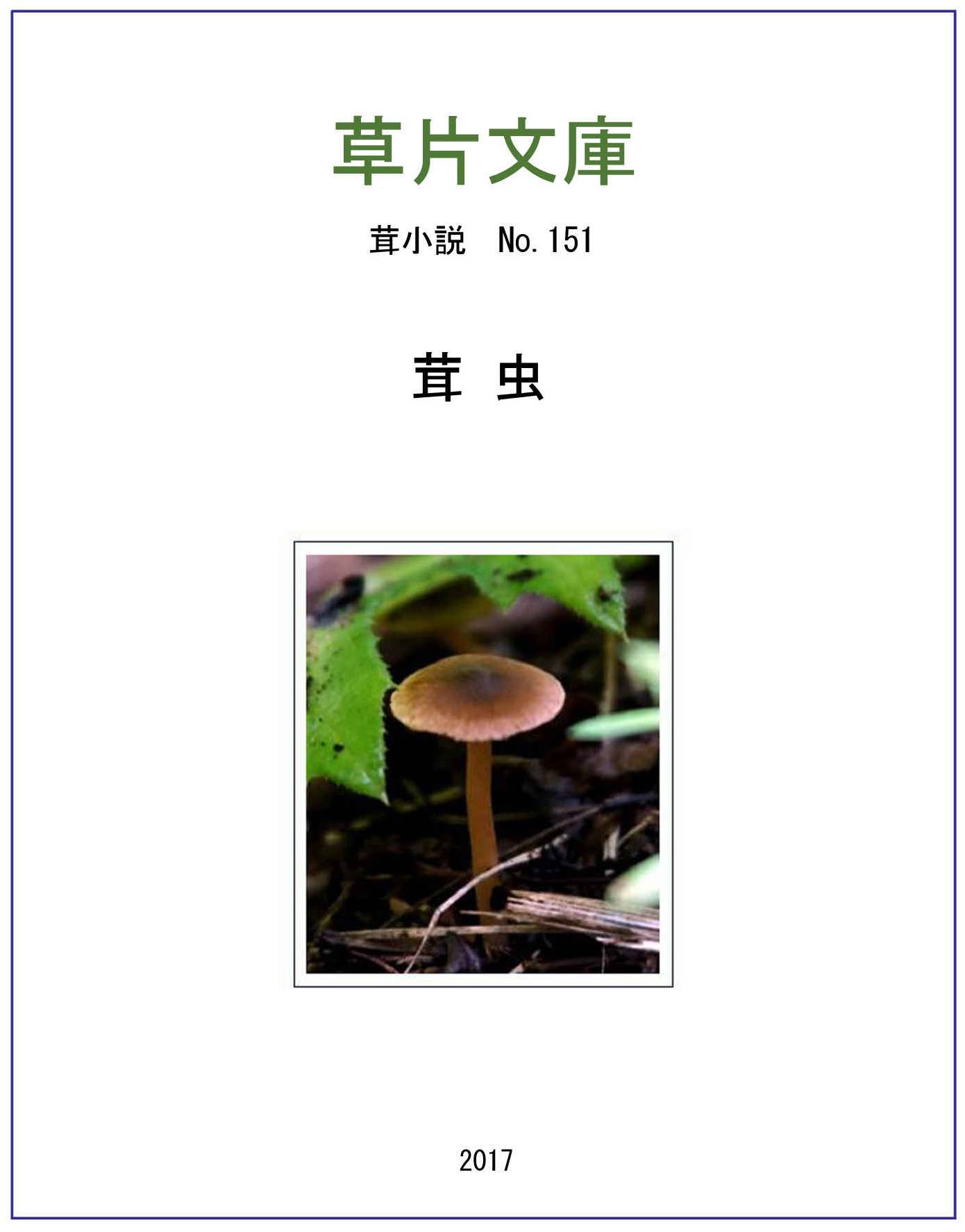
茸虫
大学四年になり卒業ゼミにはいると、仲間にちょっと変わったやつがいた。
ゼミ生は七人、男四人に女三人である。何のゼミかというと、食物を民族学や心理学から研究する講座で、みなそれぞれにテーマを考えて卒業研究をおこなっていた。私のテーマは茸を食べる文化についてである。地方によって同じ茸でも呼び名が違うのはよく知られているし、茸の方言に関する本はいくつかでている。私は食生活の中でその茸がどのような位置づけで考えられているのか知りたくて、地方による茸の扱い方の違いなどを調べていた。
他の連中はラーメン、そば、雑煮、汁粉、沢庵、梅干し、どれも、日本に特有のものをテーマに選び、その中で関心のあることに的をしぼって調べている。
その同級生は梅干しをテーマにしていた。和歌山県のみなべ町出身だからかもしれない。みなべ町は梅干、南高梅の発祥の地として有名でもある。
彼はアルマイトでできた、昔ながらの大きな弁当箱を大学に持ってくる。ふたを開けると、白いご飯の上に梅干しが一つ載っている。日の丸弁当で、それこそもののない戦中、戦後の弁当の代表だった。しかし彼の弁当はちょっと違った。毎日違う地域で採れた、または作られた梅干しが一つのっていた。それを白いご飯とともに食べ、味やご飯との相性など、主観的なことを記載収集している。卒業研究の原データを昼の弁当から集めているのである。
彼の脇にあるノートには、そこの土地の梅干し作りの特徴を調べたもの、気候や地理的特徴が書かれている。もちろん使われている塩の種類や塩の塩梅も重要だ。
さらに、彼は出かけていって、土地の人の舌のありよう、すなわちその場所の人が生まれ育つ間に梅干とどのようにつき合わされているか調べ、その人たちの梅干に対する味の感想を聞く。違うところの梅干を食べてもらってどのように感じるかなどを調査している。もちろん、男女差、年代差なども調査対象だ。
昼休み、彼は一人で学生ラウンジの椅子に腰かけ、日の丸弁当を食べる。写真も撮っているようで、いつもデジカメが脇にある。およそ三十分かけ、アルマイトの弁当箱のご飯を食べ、梅干の種をなめるのである。
その時間になると、遠巻きに女の子たちが集まる。
なにをしているのかというと、彼は種だけになった梅干しを口の中に入れ、神妙な顔をして口を動かす。時に、口をすぼめ、舌でころころと種を口の中で動かしたりして、酸っぱさ加減によって様々な表情をする。
女の子たちはそれを見に来るのである。
「あれ、きっとしょっぱすぎたんだ」
「今日のは甘さが強かったんだ」
などと女の子は彼の表情から、想像をして楽しみ、あとで、
「今日の梅干しどうだった」と彼に聞くのだ。
すると彼は、
「うん、うまかった」と言う。
いつも同じ答えなのだが、それがやはり表情が違う。女の子たちは心理学専攻の子たちで、
「ほら、やっぱり、酸っぱかったんだ」
などと言って、当たったと威張ったりしている。必ずしも正しくないのだが、それで満足だ。だから心理学はだめなんだ。などと当時思っていた。
私が彼に、「いつも同じ返事だけど本当はどうなの」
と聞いたことがある。すると、彼は、
「簡単には言えないよ、塩味だって、いろいろあってね、甘みもそうだ。きっと、それを作った人の感性ということだろうね、つきつめれば、その人の育った環境がその人の味覚を作りだし、その結果というわけさ、どうだったと聞かれてもね、うまかったというのが端的に正しい答えだろう」
そういって笑った。きっと心理学を笑っていたのだと僕は思う。
彼はデパートやお店を回り、いろいろなところの梅干しを買って、冷蔵庫に入れておいて必ず弁当をつくる。
梅粒はそのようにして食べて、記録を取り、残りは食べきれないので、友人や周りの人に分けている。私もお裾分けにあずかったことがある。
それでは梅干しばかりを食べているのかというと、そうではない、と本人はいう。夜は外食が多いが、肉っ気の物を食べると言っていた。朝はパン食だそうだ。そのほうが、弁当の梅干の味がはっきりわかるという。
さて彼の容姿の話にもどろう。彼は甲虫に似ている。背が高くひょろんとしている割には寸胴で、手足は取り立てて長くはない。むしろ短い。頭は小さく、顔は丸く目が大きい、だから甲虫だ。
誰かがお尻が光れば蛍みたいだと言っていた。蛍に似ていると言われて、きれいだというイメージで喜ぶべきものなのか、それとも蛍の形だとすると、嘆くべきものなのか、本人はどう思っていたのかわからない。ゼミの仲間ばかりではなく、下級生までも彼のことを蛍が日の丸弁当を食ってるというのだ。そんな周りの目に彼自身も気がついているのだと思うが、いつもにこにこしている。甲虫の笑い顔だ。気にしている様子はない。
前置きが長くなったが、彼は甲子(きのえね)梅太郎という。卒業研究に梅を選んだのは、出身地ばかりではなく、自分の名前にちなんだのかもしれない。
ところが、ある時、なぜ梅干しを研究材料に選んだか聞いたことがあった。それが意外な答えだった。
「梅の味は嫌いじゃないのだけど、匂いは大嫌いなんだよ、嫌いな物のほうが客観的に見ることができると思ってね」
「嫌いなのによく食べられるね」
「さっき言ったように、味は嫌いじゃないのだよ、味というのは本来匂いと一緒に感じるものなのだろうけど、僕にとって梅に限っては、味と匂いと分けることができるんだ、だから大丈夫だよ、逆に舌の感覚だけでの純粋な判断ができるんだ」
不思議な答えが返ってきた。
こんなことも言った。
「実は、君のテーマの茸が大好物なんだ、よく食べるよ」
「どんな茸が好きなんだい」
「どんなと言うより、茸ならみんな好きだよ、椎茸だって松茸だって、マッシュルームも編傘茸も」
「じゃあ、昼は茸なしで、しかも梅の匂いを我慢して日の丸弁当を食べてるんだな」
彼はうなずいて、
「君は茸の匂いがするね」
と笑った。
茸の匂いとはどういうことかよくわからなかったが、僕が茸の研究を始めたからそう言ったのだろう。
彼とは特に親しいというわけではないが、よく話をした友人の一人といったところだ。大学時代は彼も含め仲間たちとよく飲みに行ったり、旅行をしたりした。彼とはゼミに入る前から、ドイツ語でも一緒のクラスになったし、般教でもよく顔を合わせた。学生時代の記憶によく残っているクラスメートである。
彼はどこか他の連中とは違っていた。他の学生と同じように振舞っていたにもかかわらず目立っていた。今にして思うには、誰とでも話をして、特定の仲のいい友達とつるんでいたりしないから、逆に浮いて見えたのかもしれない。
卒業のとき、甲子の卒業研究が大学内の研究アワードをとった。大学院に行くように先生にも勧められたようだが、結局、大手製菓会社の研究部門に勤務することになった。いろいろなチョコレートやキャラメルをだしているところで、彼の役割は、自社の菓子が日本の地方でどのように受け止められているか調査することである。彼にはうってつけではあったが、最初は九州の支社に赴任したと聞いている。
私は茸を栽培する信州の会社に入り、マーケティングをやっている。これも卒業研究の続きといえば続きである。
卒業した年の暮れにクラス会を開いた。北海道の会社にはいった男と、シンガポールの会社に入った二名が来れなかったが、彼を含め五名が集まった。
「仕事はどうだい」
だれもが張り切って自分の役割に慣れるように努力している新入社員だ。彼も九州の現場でがんばっている。
「おもしろいね、若者のチョコレートだけどね、同じものでも東京で売れているのに、九州じゃあまり売れ行きがよくないのがある、それで調べたら、味じゃないのさ、パッケージだね、その土地で流行っていることとマッチすると売れるね、それで東京で売れているチョコレートの箱に、東京ファーストと英語で端っこに入れたらね、九州でも売れるようになったよ」
「どうしてだい」
「東京で売れているものを買おうという、その辺りの若者の心理だね」
私のほうは信州で新しい茸の栽培を試みている会社なので、食べ方をいかに浸透させるかということに苦労していることを話した。
「どんな茸を栽培しているんだい」
彼が興味を持って聞いてきた。
「松茸を試みているんだけど、珍しいところとしては、杏子茸、編傘茸などだね、西洋や中国では好まれる茸だよ」
「ほら、きのこの山っていう、チョコレートとビスケットでできたのがあるだろう」
みんなよく知っている。
「あれがでたときには、子供用の菓子なんだと深く考えずにいたのだけど、今では季節バージョン、地方バージョン、様々で、若い人ばかりじゃなくて、あれがでた当時、子供に買い与えていた親がはまっている。一つ個性的な物を作ると、その会社はそれを育てれば、どんどん発展するよ」
「そうだな、うちでも、どれか面白い茸が大当たりしないか考えている、その茸が椎茸のように用いられるようになると、大変なものだからな」
「たしかにな」
そのようなことで、まだ半年なのに、みな立派に会社の戦士として育っていた。
それから、五年が経ち、まとまったクラス会をやっていなかったので、そろそろやろうということになった。
女の子たちの多くは結婚をしていて、子供がいる者もいるが、男で結婚したのはその甲子だけであった。学生時代には男の中では一番その様子がなかったので、通知をもらった時には驚いたものである。
しかし集まった面々はまだ学生臭さが残っていて、さほど変わっていなかった。
彼だけがなぜかここでも目立った。頭一つ飛び出した感じである。
女の子の一人が「蛍君、大人に見えるわよ」と言っていたが、確かに、ちょっとおじさん的だ。
「相手はどこでみつけたんだ」
「いや、小学校の同級生だ」
「それじゃ、和歌山のみなべ町か」
「うん」
「長いつきあいだったんだね」
「いや、九州から、和歌山の支社に転勤になったら、そこにいたんだよ、彼女は高校を出てから、ずっとそこに勤めていたんだ、はじめはわからなかったんだけどね、話しているうちに、あれ、ということになってね」
「へえ、奇遇だね」
「まあ、母親同士が知り合いだったしね」
というようなことだった。私のほうはそのような兆候はみじんもなく、独り身で会社に奉仕している。
それから、さらに二年ほど経った頃だったろうか。甲子から電話がかかってきた。信州の私の勤める会社の近くに出張で来ているので会えないかというものだった。
もちろん、喜んで夕飯に付き合うよと電話を切った。
私の会社は諏訪にある。諏訪湖の周辺ではなく、もっと山の奥にはいったところである。会社から車かバスで繁華街まではそんなにかからない。旨い店やしゃれた店はたくさんある。
彼は諏訪湖の畔のなかなかいいホテルに泊まっていて、その中のレストランに有名なところがあったので、そこで食べることにした。
「こういった、山と湖のある場所もいいね、和歌山の会社は海に近いところにあるのでね」
「でも、海もいいじゃないか、和歌山にはいい海岸がたくさんある、やっぱり海の幸だ」
「そうね、ここは山の幸、あっちは海の幸か」
「奥さんはまだ勤めているの」と聞くと、彼はうなずいた。
「うん、まだ同じ会社にいるよ、もちろん部門は違うけどね、あっちは作るほう、俺は売るほう」
「お子さんは」
「まだなんだ」
「俺は忙しすぎて、かみさんをもらうどころじゃないよ、嬉しい忙しさなんだけどね、前話した杏子茸と編傘茸の栽培がうまくいって、その技術で特許とってね、それをヨーロッパで展開することになって、今うちの会社の評価が鰻登り」
「すごいじゃないか、それじゃヨーロッパのほうに行くのかな」
「いや、俺は開発の部長にさせられて、新たな茸のマーケティングを担当することになっていてね、俺の部下がヨーロッパのほうの責任者になっているよ、俺は語学がだめだから」
「いや、すごいもんだ、それで、今はなにの茸かな」
「卵茸だけどね、これは以外と簡単そうなんだ」
「卵茸なら俺も知っているよ、シーザーが好んだ茸だろう、昔日本人は食べなかったが、今は有名になったよな」
「そう、あの茸、真っ赤でとてもきれいだろう、でも料理するときに、赤い色が水に溶けちゃって、茶色っぽいつまらない色になるんだ、それで改良を加えて、その赤が落ちないようにする工夫をしているんだ」
「水に溶けないようにするわけか」
「そう、今うまく行きかけている、はじめは普通の卵茸を薬品につけて色落ちしないようにしてみたのだが、使う薬品が食物には使えないことがわかり、結局遺伝子改変をやってみている。生物系の技術者が何人かいるので、そいつらが赤い色素をある物質でコートしてしまう遺伝子を卵茸に発現させたんだ。そうすると、コートされた赤い色素は水に溶けなくて、その上、そのコートをする物が痴呆、いや認知症の予防にいいんだな、一石二鳥と言ったところだよ」
「そんなことを他人にしゃべっていいのかい」
「もう、そこまでは特許をとってあるからね、培養はもうすぐ完成、かなり安く大量につくれるよ、それを瓶に入れて売るつもりだ。とてもきれいで飾っておくだけでもいいんだよ、この茸もヨーロッパやアメリカでもてはやされるだろうね」
食事をしながらそんな話をした。
すると彼はこんなことをいいだしたのだ。
「相談というのはね、家内とのことなのだけどね」
そこまで聞いて、そういえば相談があると電話をもらったことを思い出した。
「今、うちの会社できのこの坊やという、お菓子を作っていてね、家内がそれに携わっているんだ、家内も茸が好きでね」
「それこそ企業秘密じゃないのかい」
「いや、もうすぐ発売になる」
「だけど他の会社にきのこの山や竹の子の里があるじゃないか」
「うん、あれはビスケットとチョコレートだけど、うちのは、ゼリーのような物で違うものだよ」
「そうなのか」
「それをつくるまでに、家内や担当の者が山に行って茸の散策をして、専門家の指導を受けて、茸の子供の写真を撮ったり、採取したりして、ずいぶん苦労を重ねて作り出してね、そっくりの形のものを作ったんだ」
「大変だったんだ」
「そう、それでね、家内は休みの日も山を歩いて、きのこの坊やにはどのような茸がいいか考えていたね、それでね、俺も休みの日にはね、一緒に山に行ったんだよ、ところがいつもは茸が生えている山に行っても、一本も見つからないんだ」
「日のあたり具合、雨降りの具合で、全く生えないことがあるからね」
「いや、そうじゃないんだよ、家内が一人でいったときにはずいぶんいろいろな茸が採れたのが、俺がいくと必ずといっていいほど茸が顔を出していないんだ」
「そういうときにぶつかったんだろう」
ところが彼は驚いたことを言った。
「よく考えてみると、生まれてこのかた、生えている茸を見たことがないということに気がついたんだ」
「そんなことがあるはずないじゃないか、どういうことだい」
「ほら、子供の頃にはキャンプに行ったり、ハイキングに行くだろう、その頃から、全く生えている茸を見ていないのだ」
「だけど、茸のことは知っているじゃないか」
「そう八百屋に並んでいるのを見たりしているからね、それに、図鑑などもよく見るし。茸は好きなので茸料理も食べるしね、だけど、生まれてこの方、自然の茸を見ていないことに気がついたのだよ」
「気がつかなかっただけじゃないの」
「今、庭付きの家を借りているけど、庭で一つも茸を見たことがない」
「きっと、日当たりがいいんだよ」
「そうでもないんだけどね」
「気にすることはないよ、明日、うちの会社でたっぷり見せてあげようじゃないか、いろんな茸が生えているから」
「それは嬉しいな、見せてくれるなら行くよ、明日、昼間はこっちの支社に用事があって、終わったら夕方になるけどいいかな」
「いいよ」
そう言って携帯の電話を教えた。
明くる日の夕方、四時頃だったろう、仕事が終わったので会社を訪ねていいか電話があった。もちろん、すぐ来てかまわないと返事をしたら、三十分後に来るということだった。
デスクで書類の整理をしていると、受付から電話があった。彼がきているという。エントランスに迎えにでると、彼はにこにこと笑顔で「茸の匂いはいいなあ」と言った。私にはそんなに茸の匂いがしないが、彼は鼻がとてもいいようだ。それとも自分が麻痺してしまっているのだろうか。
「実はね、昔、君は茸の匂いがすると言ったのを覚えているかな」
もちろん覚えていた。
「家内もね、会社で会ったときに、小学校の時の同級生だと言うことはわからなかったが、茸の匂いがしたんだ、それで話すようになって、付き合うようになったんだ」
「そうだったんだ、茸の匂いに敏感だね」
私は彼を茸の培養室に連れていった。まだ開発中のものである。
「ここでは将来の茸を栽培している、入るには体を消毒しなければならないから、窓から見てくれよ」
本当は外部に漏れてはいけない珍しい茸もあるからである。
小さな無菌室が連なっている。それぞれの部屋で有望な茸の培養を行っている。部屋の中はガラス張の窓からみることができる。彼は食い入るように中を眺めた。ところが、茸の生えている瓶が見えない。
「いつもは、何本かの瓶から茸が生えているんだけどね、ちょうどお休みのようだ」
「これは君が管理してるのかい」
「まさか、僕は文系だよ、菌学を研究している連中がやっている、僕はどのような茸を栽培するか選んだりする役割だ、世界の茸情勢から判断する」
「そりゃ大変だ」
「食文化だから、僕の好きな領域だよ」
「生えている茸が見たいなあ」
彼がぼそっと言ったので、生産ラインをみせることにした。
「今度は、生産しているところを見せてあげよう」
研究棟からでて、生産棟につれていった。生産棟は二階建てで、八棟ならんでいる。今のところ十種類の茸をフル生産してる。
外部の人にはなかなか見せないのだが、一番当たり前のマッシュルーム棟につれていった。これはどの会社も同じように栽培しているので問題はない。
小部屋に分かれていて一つの部屋で毎日一万本の生産を誇っている。
彼にエプロン、帽子とマスクをしてもらい中に入った。
あれ、白い丸いぽこぽこが当然のこと目にはいるかと思ったら、棚の上にはきれいに並べられている箱だけで、中には一本も茸が生えていない。
「おかしいな、この部屋は生産を中止しているのかな、隣に行こう」
私は次の部屋に案内し、まず私が中をのぞいた。そこにはきれいな白いマッシュルームが伸び伸びと育っている。ここなら大丈夫だ、彼に入るように促した。
ところが、彼が部屋に入ったとき、棚の上を見たら、茸は全く消えていた。
「やっぱり、ここも茸が生えていないね」
彼はあまり驚かずにそう言った。むしろ驚いたのは私である。
「おかしいな、今のぞいたら生えていたんだが」
私は前の部屋にもどり中をのぞいた。つい今しがたなにも生えていなかった箱の中に白いマッシュルームが大きく育っている。
私は狐に摘まれたような気持ちになって、三つ目の部屋に彼を案内した。彼は黙って付いて来た。
私が先に中に入った。立派なマッシュルームが数え切れないほど生えている。
彼が入ってきた。
私はその瞬間を見た。
白い茸が身をよじるようにして、菌床の中にもぐりこんでいってしまった。あっと言う間のできごとである。
このようなことがあるはずがない、
ゴム手袋をはめ、床の菌床をほじくってみたが白い茸の頭がない。
「なにがおきたんだ」
彼は一人で外にでた。見ていると菌床からもくもくと白い茸が顔を出した。
なんだこれは。
廊下に出た彼が笑っていった。
「ほら、俺がいると、茸がいなくなるだろう」
私はうなずくことができず、なにかに化かされているような気になってきた。
「おかしいな、こんなことが起こるはずがない」
「起こるんだよ、俺は茸に嫌われているんだ」
「近くの林の中にいってみよう、茸でてるよ」
私の会社は山の中腹にあり、まわりの林の中ではそれはたくさんの茸を見ることができる。昼食後に歩いたりするが、きれいな茸に出会える。
「きっと茸はいないよ」
彼はそう言いながらついてきた。
林の中はひんやりしていて、羊歯や名も知らない草が元気に生えている。転がっている岩は苔生し、いかにも茸の好きそうな環境である。林の中には小さな道が続いていて、その脇には赤や白や黄色の茸が顔を出し、目を楽しませてくれる。ところがしばらく歩いても全く茸にであわない。こんなことがあるはずがない。
「やっぱりないねえ」
彼はそういいながら林の中を熱心に見回して歩いている。
「やっぱりそうなんだ」
「なにが」
「うちのほうにある昔話だよ」
「なんだい」
「今日も一泊するから、また夕飯つきあってくれるかい、そのとき話すよ」
「いいよ」
私はふと思い立って、
「ちょっと前に行くから、ゆっくり歩いてきてくれないか」と、早足で先に進んだ。
羊歯に隠れて紅天狗茸が生えている。私はそこで彼を待った。
彼は周りを見ながら、近づいてくる、すると紅天狗茸がもじもじと動き始め、土の中にめり込むように、小さくなりながら入っていく。そばに生えていた針金落葉茸も土の中に吸い込まれていく。
甲子がすぐそばまでくると、茸たちはみんな土の中に入ってしまった。
「やっぱりないね」
「ないんじゃないんだよ」
言おうとしていることは自分でも信じられない。だが目の前で起こった。
「どういうこと」
「ここに紅天狗茸が出ていたんだ、君が近づいたらみんな土にもぐっちまった、こんなことがあるなんて」
「俺はね、さっきも言ったように、茸に嫌われてるんだよ、僕は好きなんだけどね」
「もどって一緒に町にでよう、一杯やりながら話を聞くよ」
彼は頷いた。
車で町に出た。たまに行く飲み屋で彼は話し始めた。
「和歌山のうちのあたりには茸の伝承話があってね」
「茸はどこでも採れるから、いろいろな話があると思うけど、和歌山はあまり知らないな」
「そうだろうね、普通の茸じゃなくてね、万年茸の話なんだよ」
「万年茸か、あれは薬にもなるが、お飾りとしても縁起物で人気があるからな」
「そうだね、床の間に飾ったりね」
「どんな話だい」
「大昔ね、和歌山にもたくさんの茸が棲んでいたんだそうだ」
「棲んでいたんだ、生えていたのじゃないんだね」
彼はうなずいて、話しはじめた。
和歌山の茸たちが林の中で噂話をしていた。
「近くまで、茸虫というのが来ているということだ」
「何だ、その茸虫というのは」
「なんでも、我々、茸をあっという間に食ってしまう恐ろしい奴らしい」
「わしらをそんなに早く食うことができるんかい」
和歌山の茸は茸虫をまだ知らなかった。
「茸虫は茸を端から食ってしまい、日本の茸の種類を減らしているということだ」
「日本は世界で茸が一番多い国だと思うがな」
「昔はそうだ、しかし茸虫が現れたことで、どんどん茸一族が減っているということだ」
「ともかく、茸虫の奴らが隣の村まで来ているということだ」
「茸虫とはどういう虫だ」
「我々を食うだけではないんだ、茸の中に卵を産んで、子供がかえると、そいつらも茸を食らうんだ」
「どんな格好をしている」
「寸胴で、顔は丸くて目は大きい、硬いからだをもっている」
「なんだ、かみきり虫みたいか」
「あんなに大きくない、蛍ぐらいだ」
「それで、どこから現れた」
「なんでもやつらは、茸にすんでいて露を吸って生きていたのだが、あるとき、茸の傘から顔を出した茸虫が、上から垂れてきた朝露を飲んだところ、いい香りがするものだと感激したそうだ」
「そりゃあ、茸はいい香りだ、花のように変に甘ったるくなく、大人の匂いだ」
「それで、その茸虫は、茸にかみついたそうだ、すると、旨いじゃないか、いままで、草の露で生きていたのだが、それから茸虫一族は茸を喰らうようになった、しかも、食欲旺盛な虫だ」
「そうか、それなら逃げたほうがよいのだろうな」
「そりゃあそうだろう」
茸の長老が打ち合わせをしている。みんな逃げる支度をしていた。松茸は京都に逃げるといって赤松から離れると、一族で移動を始めた。椎茸は群馬に逃げることにして、滑子は長野に、舞茸は秋田に逃げる。他の茸たちもそれぞれ逃げる場所を決めていた。こうして、茸たちはみんな逃げ出したのだ。
ところが万年茸は、「あいつら、俺たちの堅い身を齧ることなどできるわけがない」
自信たっぷりにそう思い、逃げることをしなかった。
それから朝が来て夜が来て、また朝がくると、茸虫たちが万年茸のいるところにやってきた。
「やあ、茸のみなさんとは仲良くしたいな」
ひどいもので茸虫は林の中に入ってくると、そう言っていながら、万年茸に齧りついた。茸虫は万年茸の堅いからなど物ともせずに食いついて、卵を産みつけた。
これはたまらんと万年茸は林から逃げ出した。山を下っていくと、梅の木の林があった。あのあたりでは、梅の木がよく育っていたのだ。
万年茸は梅の林に逃げ込み隠れたのだが、茸虫は茸の匂いに敏感だ。好きな茸の匂いはすぐわかる。それで、万年茸は梅の木に登っていった。
茸虫も後を追いかける。
万年茸は梅の木の上に追い詰められ万事休す。
しかし、万年茸の長老が、
「梅の実をぶつけろ」
と激をとばすと、万年茸は一斉に梅の実を茸虫にぶつけた。梅の実が茸虫にぶつかると、茸虫は木から落ちてひっくり返った。
万年茸はひっくり返った茸虫に更に梅の実をぶつけたものだから、茸虫は足がもがれたり、触覚がとれてしまった。動けるものも梅の匂いにむせて梅の林からすたこら逃げ出した。
梅の林から逃げだした茸虫は、そこの茸はあきらめて、よその国に、茸を求めて、逃げてしまったということだ。どうやら茸虫はこの村からいなくなった。
その出来事から万年茸は梅の木に生えるようになったという話だ。
この国の茸たちは茸虫の匂いがすると、あわてて土の中に隠れるようになった。
甲子はそんな話をした。
「そんな話聞いたことがないね」
「うちのあたりだけに伝わるものだからね、それに続きがあるんだよ、長い長い年が経って、万年茸が人に代わり、茸虫も人に変わったそうだよ」
「なんだいそりゃ」
「俺の祖先は、茸虫なんだそうだ」
「誰がいったんだい」
「実は、じいさんがそう言っていた、かみさんの祖先は万年茸だそうだ」
「それで」
「だから、俺が茸のそばに行くと、茸が隠れてしまうんだ、茸虫の匂いがするんだ、梅があまり好きじゃないのもその証拠だよ」
「でもな、奥さんは隠れたりしないだろう」
「うんそれなんだ、そのうち隠れてしまいそうで心配しているんだ」
冗談のような話だが、彼の顔は本気で心配していた。
「おかしな相談だな、もし甲子が茸虫だとしたら、奥さんが結婚しなかったろうに」
「うん、いや、だんだんと昔のことがわかってきてな、別れ話がいつ出るのか心配なんだ」
「奥さんにそんな兆候があるのかい」
「何とも言えないけど、最近、家に帰るとドアを開けて待っているんだ」
「仲のいいことじゃないか」
「うん、俺が門の所までくると、あなたの匂いがするの、って言うんだよ」
「変なことに気を病んでいるんだな、仕事のしすぎじゃないか」
「そうかもしれない、だけど君も見ただろう、俺がいると茸が隠れちまう」
確かにその点は奇妙だった、茸が潜り込んだところを見たのであるが、彼の雰囲気にのみこまれ、そう見えちまったのかもしれない。
「あんまり気にしないで、仕事をがんばろうじゃないか」
その後話を変えた。今の仕事がとてもおもしろいし、うまくいっているという。それは楽しそうにしていた。私も茸の培養のことを話して、機会があったらまた会うことを約束して彼と別れた。
それから一年ほどたち、彼から電話があった。
「やっぱり、かみさん消えちまったよ」
彼は悲痛な叫び声をあげた。
「探したのかい」
「もちろん、警察にも届けた」
「いついなくなったんだい」
「子供が生まれてすぐだよ、病院からいなくなった」
「赤ちゃんができたんだね、おめでたいじゃないか、それなのにどうして」
彼の返事にはちょっと間があった。
「赤ん坊が、俺そっくりだったんだ、今、脇のベビーベッドで寝ているよ」
私が目にした茸の奇妙な現象は、ようやく私の頭も信じることができた。だけど、彼になにかしてやれるのだろうか。そうか、思いついてこう言った。
「茸虫が好きになる匂いを開発に頼んでやるよ」
「それはうれしいな、それをかければ、かみさんも戻るよな」
彼は喜んだ。
僕は反対のことを考えていたのだ。茸虫が好きな匂いをつくって、茸虫をさそいだし、一網打尽に退治できる。茸の敵をやっつけられる。そんな薬は茸の栽培農家に売れるだろう。だがそのことは彼に言わなかった。
茸虫
私家版第十四茸小説集「茸耳袋、2023、269p、一粒書房」所収
茸写真:著者 長野県富士見町 2016-8-2


